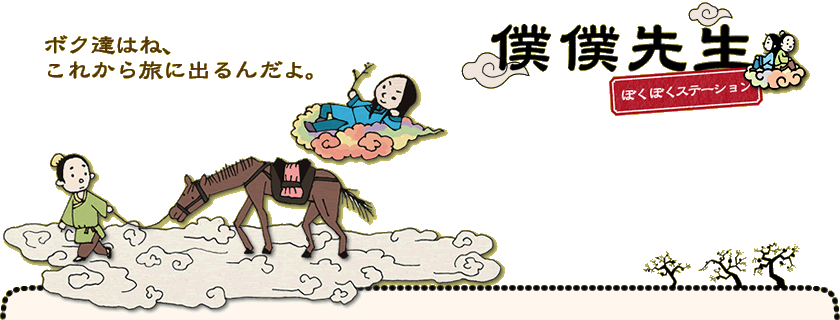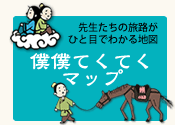前回雑記を書いたのが八月。気づけばもう年が明けているではありませんか。ご無沙汰して申し訳ありません。ひで山です。
昨年十月、おかげさまで『朱温』(朝日新聞出版)という歴史小説と、『千里伝 五嶽真形図』(講談社)というファンタジー小説を世に送り出すことが出来ました。全てが済んでほっとした私がカレンダーを見上げると、時が過ぎ去っていたという次第です。他社で出した作品のことを書いてもいいなんて、さすが新潮社さんは太っ腹やで!
さて、前回はチベットの小説を書くにあたって、彼の地に大変お詳しい渡辺一枝さんを訪ねたところまで書きました。一枝さんのお宅にはもちろん、ご主人の椎名誠さんがいらっしゃるわけです。まあ当たり前といえば当たり前なのですが、わかっていてもスウェット姿ですたすたと階段を下りて来られて「よ、仁木くん」とあのにかにか笑いをされると、ファンである私はもうそれだけでテンションが上がるのです。
ご挨拶が済んだ後、一枝さんに誘われて一室に足を踏み入れた私は、目を瞠りました。そこには一枝さんが集められたチベットに関する書物がぎっしりと並び、タンカ(仏画)などの品々が収められていたのです。それも、ただ収められていたのではありません。私が彼の地で見た寺院のように、バターの灯明の明かりと香の薫りの中で“生きて”いました。
人によって作られた“もの”というのは何でも、人の手が触れていないと死んでいきます。人の住まない家、子供の姿が消えた校舎、作家が使わなくなった灰皿……、どれも生気を失って寂しい風景の一部となっていきます。美術品や仏具といったものもやはり同じで、人の手や視線に日々触れているものと、倉庫にしまわれているものとでは、なんというか色彩が違う。一枝さんの家にあるチベットの品々は、故郷にある時のように輝いていたのです。
本棚に並ぶ本に目を奪われていくうち、私は数冊のアルバムに気付きました。中には一枝さんが現地で撮られた写真がぎっしりと並んでいます。そのアルバムに収められている写真はみな、観光地を写しているのではありませんでした。ごく普通の人々の暮らしと、そこで使われる道具の数々が写されている。写真については詳しくない私ですが、不思議な温かみとその道具自身が持つ息遣いすら感じられて、目を奪われたものです。
居間に戻り、一枝さんがチベットで見てこられたこと、日本でチベットの人々を支援している活動について話して下さいました。その詳細はここで私が書くよりも、一枝さんが各地で行っていらっしゃる講演会、そして各出版社から刊行されている書籍を読んでいただくのが一番だと思います。
はばかりながら言葉を生業にする私が、自分では上手くお伝えできないと思うのには理由があります。チベットという地域とそこに住む人々は、政治的にも社会的にも、非常に微妙で難しい状況に立たされています。私はチベットが大好きで、実際に訪れたこともありますが、現状をしっかりと考察してきたとは言い難い。チベットに入れ込んでいるつもりで軽々しく語ることが、チベットの人たちのためになるとは限らない。だからこそ、彼の地を深く知る人の言葉に直接触れていただきたいのです。一枝さんの著作である『わたしのチベット紀行』(集英社文庫)と『チベットを馬で行く』(文春文庫)を強くお勧めしておきます。
一枝さんは言いました。ある人々を助けたいと思った時に一番必要なことは、その人たちの抱える問題を、自分の問題として考えることだ。だから自分はチベットに行くのだ。人々を連れてチベットに行きたいのだ、と。一枝さんの言葉に私は衝撃を受けました。そして納得したのです。一枝さんの写真から感じられた温度や匂いといったものがどこから来たか。この人の視線は、チベットの人々を兄弟のように家族のように見つめるところまで昇華されているんだ、と。
私は「他人のためにボランティアをしている」というのを信じ切ることが出来ません。さまざまな使命感があったとしても、どこかに自身がなにがしかの満足を得るためにするものだ、と考えています。ですが、だからこそ助けられる人の問題を己の中でしっかり咀嚼する作業を忘れてはならない。小説を書く際に取材をすることも多い私ですが、そこにも通じることだな、と一枝さんの姿勢に強く胸を打たれた一日でありました。