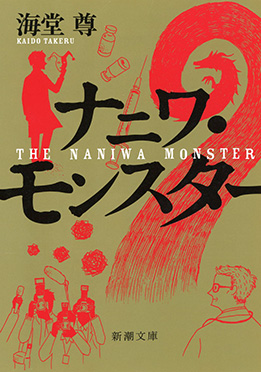ナニワ・モンスター
1,760円(税込)
発売日:2011/04/22
- 書籍
この国の病巣にメスを入れよ! 近未来を透視する壮大なメディカル・サスペンス。
関西最大の都市・浪速で新型インフルエンザ・キャメルが発生した。経済封鎖されて壊滅的打撃を受けるナニワ。だが、その裏では霞が関の思惑が絡む巨大な陰謀が蠢いていた――。日本の大変革を目論む風雲児・村雨府知事は、未曾有の危機を打開できるのか。この国を救う“究極の処方箋”とは? 海堂ワールドの新たなステージ、開幕!
目次
序章 砂漠 二〇〇五年三月
第一部 キャメル
#01 浪速診療所 二〇〇九年二月四日
#02 浪速市医師会 二〇〇九年二月四日
#03 水際防疫 二〇〇九年四月二十二日
#04 キャメル・パニック 二〇〇九年四月二十七日
#05 検疫官・喜国忠義 二〇〇九年四月二十八日
#06 レッセフェール・スタイル 二〇〇九年五月十日
#02 浪速市医師会 二〇〇九年二月四日
#03 水際防疫 二〇〇九年四月二十二日
#04 キャメル・パニック 二〇〇九年四月二十七日
#05 検疫官・喜国忠義 二〇〇九年四月二十八日
#06 レッセフェール・スタイル 二〇〇九年五月十日
第二部 カマイタチ
#07 特捜部エース、西へ 二〇〇八年六月十八日
#08 電光石火 二〇〇八年十月十七日
#09 不祥事ルーレット 二〇〇八年十月二十一日
#10 不可視陰謀 二〇〇八年十月三十日
#11 検察の正義 二〇〇八年十月三十一日
#08 電光石火 二〇〇八年十月十七日
#09 不祥事ルーレット 二〇〇八年十月二十一日
#10 不可視陰謀 二〇〇八年十月三十日
#11 検察の正義 二〇〇八年十月三十一日
第三部 ドラゴン
#12 舎人町の心臓 二〇〇九年五月十三日
#13 東北の巨人 二〇〇九年五月十三日
#14 日本三分の計 二〇〇九年五月十四日
#15 桜宮岬 二〇〇九年五月十五日
#16 ナニワ・ドラゴン 二〇〇九年五月十五日
#13 東北の巨人 二〇〇九年五月十三日
#14 日本三分の計 二〇〇九年五月十四日
#15 桜宮岬 二〇〇九年五月十五日
#16 ナニワ・ドラゴン 二〇〇九年五月十五日
終章 両雄並び立たず 二〇〇九年六月
書誌情報
| 読み仮名 | ナニワモンスター |
|---|---|
| 雑誌から生まれた本 | 週刊新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 384ページ |
| ISBN | 978-4-10-306573-9 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | ミステリー・サスペンス・ハードボイルド |
| 定価 | 1,760円 |
インタビュー/対談/エッセイ
波 2011年5月号より 【海堂 尊『ナニワ・モンスター』刊行記念対談】 「思考停止社会」からの脱却
異例の展開?/「検察崩壊」の中で/チームの力/危機感を持たない幹部 |
異例の展開?
海堂 郷原さんと対談するのはこれで三度目ですよね。実は今回書いた小説『ナニワ・モンスター』には、以前の対談の際にうかがった検察に関する話が、ストーリーの骨格に反映されているんです。
郷原 この小説は、浪速市という架空の都市に新型インフルエンザが発生して危機的事態に陥り、その背後に霞が関の陰謀が存在するというのが根幹のストーリーですが、その中で検察という存在をどう捉えるかという問題が、基本的なコンセプトになっていますよね。その部分は、検察の現場で仕事をしていた人間として興味深く読みました。
海堂 小説の中に「浪速地検」という架空の地検の検事が登場しますが、そもそも検察の問題を書き込もうと思ったきっかけは、厚生労働省の村木局長逮捕でした。あの時に一番感じたのは、「なぜ大阪地検特捜部の人間が、霞が関の役人を逮捕するのか」ということ。これは何なんだろうと思った時に、ストーリーが頭に浮かんだんです。
郷原 あの事件の場合、「障害者団体向け低料第三種郵便制度不正利用事件」の捜査がベースとしてあり、そこに現職の局長が関わっていたという疑いが出てきたことで、村木さんの問題にまで拡大していった。最初から現職局長の逮捕を狙っていたわけではありませんね。
海堂 それは流れとしてはよくわかります。でも、今までだったらあれほど拡大させないで、うやむやになったんじゃないでしょうか。あそこまで徹底的にやるということが凄く不自然に思えて、違和感を覚えたんです。
郷原 特捜部の感覚としては、更にその先を考えていたと考えるのが普通ですね。
海堂 政治家ですか。
郷原 そうです。大阪地検であれ、東京地検であれ、特捜部は政治家を捕まえるという目標を常に持っています。政治家が狙いであれば、おっしゃるような「大阪地検がなぜ」という違和感はありません。ただ、後から検証すると、本気で政治家までたどり着くと思って捜査していたとも思えないんです。ですから、ターゲットを厚労省の局長に置いたという点では、確かに大阪地検特捜部の捜査としては異例の展開だったかもしれません。
海堂 郷原さんのように理路整然と説明はできませんが、その異例の展開というのが、われわれ一般人にも何となく伝わってくるんです。「あれ、何かいつもと違う」という感じ(笑)。今回はその感覚が物語の原点になり、そこから話を組み立てていきました。
「検察崩壊」の中で
郷原 海堂さんは小説として描いたわけですから、検察の現場にいた人間のリアリティとは異なる部分もあります。でも、最後まで読んで「この小説では検察の捜査というものを一つの暴力装置として描こうとしていて、それが重要なツールになっているんだな」という全体像がわかると、それなりに納得できます。
海堂 もちろん、ディティールはかなり取材したつもりですが、完全にリアルに描くことは難しいですね。
郷原 取り調べの場面などは、ある意味ではリアリティがありました。ただ、小説の中で鎌形という東京地検のエースが、浪速地検に異動を命じられますよね。そして、赴任するとすぐに地検内部の粛正をして、さらに府庁の裏金問題に手をつけようとします。このあたりは、少し違和感がありました。
海堂 「いきなり裏金にまで手をつけるやつはいない」っていうことですか(笑)。
郷原 そうです(笑)。
海堂 自分が力を発揮するために権力抗争を仕掛けるという設定ですが、やろうと思えばやれることですよね。そう考えると、リアルなんじゃないかと……。
郷原 まあ、実際の検察の世界にいると、なかなか思いつかない話ではありますね。
海堂 でも、村木局長に関する大阪地検の証拠改竄が明るみに出てからは、どんなに素っ頓狂なことを書いても、まったく荒唐無稽であるとは言い切れなくなってしまったような気がします。
郷原 あの事件では、検察のクライシス・マネジメントが最悪でした。それによって世の中から、検察というのはとんでもない組織だと思われても仕方ない状況に陥ってしまいましたからね。
海堂 まさに検察崩壊と言ってもおかしくないような状況になってしまいましたね。証拠改竄というのは、医者で言えば患者を救うことを放棄するようなもので、基本的にあってはいけないことです。それが行われたのはなぜなのか。それによって、検察は何を守ろうとしたのでしょうか。
郷原 それは結局、特捜部の「看板」ということに尽きるわけです。この小説でも、最初は錆びついていた浪速地検の看板が途中から光り始めて、政治と結びついていきますよね。「看板」というのは、実際にそのような使い方ができるものなんです。実は過去の特捜部の取り調べにおいても、言ってもいないことを調書にとるという証拠捏造に近いことが行われたとして、問題にされたことは山ほどありました。ですから、取り調べの可視化ということが現在、議論の対象になっているわけです。
海堂 そうなると、特捜部の捜査で何が行われているか、結局われわれにはわからないんですよね。だから、郷原さんが違和感を覚えながら読んだ部分も、もしかしたら他の検察官は違和感なく読むかもしれません(笑)。
郷原 そういう人もいるかもしれませんね(笑)。
チームの力
郷原 海堂さんの小説の中で、『チーム・バチスタの栄光』に登場する異色の官僚・白鳥圭輔のような存在、自分の所属する組織や世界にあえて挑戦していくタイプの人間は、官公庁の組織にはあまりいません。その点では、今回の浪速地検の鎌形副部長という検事も、検察という組織の中では規格外の人物ですね。検事の人物像などは、どのように作っていかれたのですか。
海堂 なんとなく、ですね(笑)。ただ、鎌形は部下の千代田、比嘉という二人の検事を指揮して動いていくわけですが、そのチーム作りに関しては、郷原さんの長崎地検時代の話を参考にさせていただきました。公共工事受注をめぐる違法政治献金の実態を暴き、自民党の県連幹事長、事務局長の起訴にまでこぎつけた、二〇〇二年のいわゆる「長崎の奇跡」。この時に次席検事として地検のチームを率いた郷原さんの組織論が、頭の中に残っていました。
郷原 読みながら、私の話を参考にしてもらっているんじゃないかという気がしていました(笑)。
海堂 輪郭を使わせていただきました。僕は人から話を聞いたら、よく理解をして、細部は忘れることにしています。細部にまで囚われると、物語が動かなくなってしまいますから。
郷原 でも、組織に力を発揮させるために重要なのは、間違いなくチームの作り方であり、チームの中での人の動き方ですね。逆に私も『チーム・バチスタの栄光』に書かれているチームを長崎で自分が率いたチームと対比して考えたりしましたが、それぞれの個性がうまくお互いを補完し合ってまとまると、乗数的に大きなパワーの高まりが生まれることを、長崎地検の捜査で経験しました。
ところが、従来の特捜の組織は全く違っていました。すべて指揮官の能力の範囲内で制限されてしまい、極端に言えば下の人間は単に言われた通りに調書を取ってくるだけ。まったくチームとして機能していませんでした。
海堂 鎌形は、優れたチームを作れる人間なので、東京地検からはじかれてしまったんですよ。
郷原 そうですね。ただ、普通の官庁では規格外の人物は踏み絵を踏まされて従順になるか、はじき出されるかのどちらかなのですが、検察官には個人の権限の独立性もあります。ですから、やり方によってはその個人の権限を使って、組織と対決することもできるんです。でも、東京地検特捜部には鉄壁の体制がありますから、個人の力で下から変えていくことは一〇〇%不可能です。その意味では、鎌形が東京地検から地方に移って、自分の創意工夫で組織を動かせるようにしたという話には、リアリティがありますね。
海堂 東京地検は鉄壁で難しいんですか。全く考えていませんでしたが(笑)、そう言われるとすごく納得しますね。お墨付きをもらえてよかったです(笑)。
危機感を持たない幹部
海堂 僕がこの小説で書きたかったことの一つは、思考停止してしまった組織が存在することによって、大災害が生じる可能性がある、ということです。それでは、どうすればいいのか。まあ、壊すしかないですよね。
郷原 確かに、日本全体が思考停止社会になろうとしていますよね。これだけ物事が多様化し、複雑化して変化が激しくなってくると、一つ一つの問題を個別に考えていかなければ解決できないのですが、従来の方向性から脱却できず、常に同じような対応しかできないんですね。想定をはるかに超えた今回の大地震、大津波は変化の最たるものですが、日本の官公庁の組織は、その変化に適応できているとは言えません。
海堂 思考停止した社会をなぜ壊さなければならないかと言うと、結局は子供たちのためなんですよ。硬直したシステムによって殺されてしまうのは若い人たちですから。
郷原 『ナニワ・モンスター』にも海堂さんが訴え続けているAi(死亡時画像診断)の話が出てきますが、あの問題も従来の医療の世界からは少しはみ出しているために、海堂さんが苦労されているんですね。
海堂 そうです。僕がいくらこれからの日本の社会にはAiが必要だと主張しても、法医学者たちは相変わらず「解剖するべきだ」と言う。でも、法医学者の数は減り続けているのに解剖が増えていったら、いずれクラッシュするに決まっています。そんなことも考えず、ただ現在のシステムを維持しようとするのは、明らかに間違っています。
郷原 検察の中にも、危機感を持って自己改革しなければと考えている人間はいます。ただそれは若い世代、中堅以下の世代で、幹部になると組織としての危機感を持てなくなってしまうんです。
海堂 このままでいてほしいと願う人間は、往々にして権力者です。だから、余計に難儀なんですよ。
郷原 今回の震災で東日本が壊滅的な状況になり、この国全域の形も大きく変わらなければいけない状況になっています。その中で思考停止と責任回避では、絶対にやっていけません。『ナニワ・モンスター』でも海堂さんがそのことを投げかけているような気がしました。
海堂 僕は面白いと思って書いているだけなんですが(笑)。でも、言葉で物事を壊すことは難しいですよ。読んでくれた人の心の中に言葉が入って、その人たちが壊してくれればいいと思っています。
(ごうはら・のぶお 弁護士・元検事/かいどう・たける 作家)
書評
波 2011年5月号より
浮上する時が来た
杉江松恋
潜航艇がついに浮上しようとしている。
海堂尊『ナニワ・モンスター』を読み、そんな感想を抱いた。いや、海堂が今まで不遇だったとか、そういうことを言いたいのではないです。なぜか彼の出身母体であるミステリー界は、海堂の台頭に気づいていないふりを続けているように見えるのだけど。二〇一〇年に海堂が発表した『アリアドネの弾丸』(宝島社)は、その年のベストと言ってもいい斬新なトリックと論理性を備えたミステリーだったが、いかなる賞にもノミネートされなかった。不思議だ。
だが、そんなことは些事である。二〇〇五年にデビューを果たして以来、現在に至るまでの六年間で海堂は、端倪すべからざる力を示して旺盛に作品を発表してきた。それらの作品はすべて、読者を楽しませることに徹した娯楽小説だったが、作中には将来の浮上へと向けて周到に準備された伏線が織り込まれていたのである。たとえば、デビュー作から続く〈桜宮サーガ〉で常に論争の焦点とされてきたAi(死亡時画像診断)システムのセンター設立問題、『極北クレイマー』(朝日文庫)で描かれた地方都市の財政破綻、このたび映画化された『ジーン・ワルツ』(新潮文庫)では産婦人科医が直面している医療崩壊が物語の重要な背景となったが、それも含めていいだろう。
医療という切り口で日本の姿を見直したとき、必ず見えてくることがある。少数の誠実な医師の努力によって、水際で崩壊が食い止められているという厳しい現実だ。海堂はそうした事実の砕片を掻き集め、自作に埋め込んできた。光を照射される機会があれば、それらの砕片は一気に自己主張を始めることだろう。『ナニワ・モンスター』は、そのトリガーの役割を果たす作品なのだ。漠然としていた遠景が、近づくにつれて輪郭の力強さを獲得し、やがてくっきりとした図となって観察者の前に姿を現す。そうしたズーミングの技法はフレデリック・フォーサイスやアーサー・ヘイリーといった巨匠作家たちが得意としたものだが、海堂はおそらく彼らに学んだのだろう。作品を群として考え、総体で一つの主題を浮かび上がらせようとしたのだ。だから今、〈潜航艇・海堂尊号〉は浮上しようとしている。ついにその時が来たのである。
二〇〇九年二月、浪速の町の一隅から物語は始まる。その地で長く個人診療所を開業してきた、菊間徳衛という老医師がいた。彼はある日、浪速大学医学部が奇妙なキャンペーンを仕掛けていることに気づく。尖兵となっているのは、同大の公衆衛生学教室で講師を務める、本田苗子だ。彼女は盛んにテレビ出演を行い、海外で流行しているインフルエンザ・キャメル・ウィルスの危険性について啓蒙するような発言を行っていた。ウィルス感染者がひとたび国内に入れば、パンデミックを引き起こし、多くの犠牲者が出るであろう――本田は、そうした論調で大衆の不安を煽っていた。
ある日菊間は、診察を受けに来た子供がキャメル・ウィルスの感染者であることを知る。厚生労働省の水際作戦により、国内への侵入を許していないはずのウィルスが、すでに浪速の下町に入りこんでいたのだ。このことから一気に火がつき、浪速という都市全体を巻き込んだ事態へと発展していく。
第二部で作者は、時計の針を一旦巻き戻し、キャメル・ウィルス騒動の一年前へと読者を連れて行く。騒動はなぜ引き起こされたか。国民の命を守るという大義名分の陰で、医療行政はいったい何をしているのか。関係のないように見えるバラバラの事象が結び合わされ、一つながりの総体が露わになっていくのは第三部でのことだ。過去の海堂作品でもしばしば名前が取り沙汰されてきた人物が、本作の影の主役である。その人物が真意を語ることにより、断片として示されていた事柄の結びつきが、ついに明らかにされるのだ。以前からの海堂ファンほど、驚かされることになるのではないか。えーっ、海堂尊って、こんなことを書こうと思っていたんだ。
医学・医療という主題には人命を扱うという崇高な理念が伴うが、政治的な思惑によって基盤が左右されやすいという危うい側面もある。だからこそ医療小説という分野から、多くの傑作が生み出されてきたのだ。本書はそうした系譜に連なり、さらに新しい扉をこじ開けるべき、画期的な作品だ。柄の大きな物語を好む人は諸手を上げて歓迎することだろう。三度繰り返す。海堂尊、ついに浮上す。
(すぎえ・まつこい 書評家)
著者プロフィール
海堂尊
カイドウ・タケル
1961(昭和36)年、千葉県生れ。医学博士。外科医、病理医を経て、現在は重粒子医科学センター・Ai情報研究推進室室長。2005(平成17)年、『チーム・バチスタの栄光』で「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、翌年、作家デビュー。確かな医学知識に裏打ちされたダイナミックなエンターテインメント作品で、読書界に旋風を巻き起こす。2008年、『死因不明社会』で、科学ジャーナリスト賞受賞。他の著書に『ジェネラル・ルージュの凱旋』『イノセント・ゲリラの祝祭』『ケルベロスの肖像』『極北ラプソディ』『スリジエセンター1991』『輝天炎上』『ジーン・ワルツ』『マドンナ・ヴェルデ』『ガンコロリン』『ほんとうの診断学』などがある。
判型違い(文庫)
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る