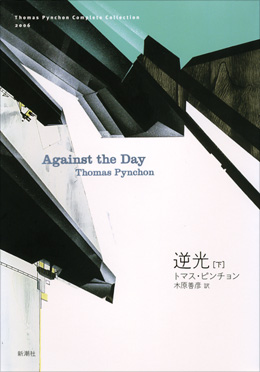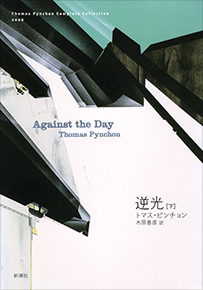
逆光(下)
4,840円(税込)
発売日:2010/09/30
- 書籍
これがあのピンチョン!? 時空を超えた感動に誘う世界沸騰の巨篇がついに刊行。
フロンティア消滅直後の19世紀末アメリカ。謎の飛行船〈不都号〉を駆る「偶然の仲間」が探し求めるは……砂漠都市シャンバラ! 地球空洞説に未確認生物、探偵に奇術師が跋扈する冒険と博覧会の時代が戦争の世紀を切り拓くとき――超弩級作家が紡ぐある一族の運命、出会いと別れ。原書2006年刊、『重力の虹』を嗣ぐ傑作。
第四部 逆光
第五部 旅立ちの道
書誌情報
| 読み仮名 | ギャッコウ2 |
|---|---|
| シリーズ名 | 全集・著作集 |
| 全集双書名 | トマス・ピンチョン全小説 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 848ページ |
| ISBN | 978-4-10-537205-7 |
| C-CODE | 0097 |
| ジャンル | 文芸作品、ミステリー・サスペンス・ハードボイルド、評論・文学研究 |
| 定価 | 4,840円 |
書評
波 2010年10月号より (詐欺のような)美しい結末へ
物語は一八九三年のシカゴ万博から始まる。最初に登場するのは、〈不都号〉(Inconvenience)なる飛行船に乗り組む〈偶然の仲間〉五人組。彼らの冒険は、少年向けのヒーロー小説シリーズとなり、世界中で人気を集めているらしい。
ふむふむと思いつつページをめくると、もう一匹の乗組員、しゃべる犬のパグナックスが登場。読書好きなんだそうで、いきなりヘンリー・ジェイムズ読んでます(しゃべる球電やしゃべる巨大砂蚤も本書には登場するので、このくらいで驚いてはいけません)。その後、〈不都号〉は、ニコラ・テスラの無線送電実験の影響を調べるため、南極点から地球内部に入り、空洞を抜けて北極に出現。ロシアのライバル飛行船とベニス上空で交戦したかと思えば、タイムトラベラーの誘惑を逃れるためハーモニカ楽団に偽装(なぜに?)。内陸アジアでは潜砂フリゲート艦〈サクソール号〉に乗り込み、伝説の砂漠都市、シャンバラを探求する……。
ヴェルヌかドイルもかくやというこの冒険物語と並行するもう一本の軸が、トラヴァース一家の物語。銀鉱山で働く父ウェブの裏の顔は、線路や鉄橋を爆破する無政府主義テロリスト〈珪藻土キッド〉。だが彼は、テスラの研究にも出資している大富豪スカーズデールが雇った殺し屋によって殺されてしまう。以降は、残された四人の子供たちの人生と復讐の物語が複雑怪奇にからみあいながら進んでゆく。中心になるのは、父の仇とも知らずスカーズデールから学費の援助を受けてイェール大学に通い、数学を勉強してベクトル主義者となった末っ子のキットで――とか説明しているとキリがない。
“脱線に次ぐ脱線、錯綜する人間関係、時間と空間を超え展開する物語。(中略)あらゆる知識、あらゆる断片、あらゆるアイディアとガラクタをかきあつめ、あらゆる境界線を破壊するパラノイア的想像力が生みだした文学史上最高最大、究極のスーパーフィクション”という、国書刊行会版『重力の虹I』カバー裏の惹句は、そのまま本書にもあてはまる。しかもこちらは、誰が主役かもわからない群像劇。冒険小説、西部劇、伝奇、SF、歴史、スパイ、ロマンス、オカルト、戦争活劇、コメディ、官能……とあらゆるジャンルを横断しつつ、ピンチョンは“9・11以後”を映した奇怪な迷宮を建設する。同時代の日本の小説で言えば、奥泉光『神器』と舞城王太郎『ディスコ探偵水曜日』と古川日出男『聖家族』を混ぜて三倍に煮詰めた感じ? 『重力の虹』よりはずっと読みやすいものの、話の道すじを見失いがちなこと(物語の行き当たりばったりぶり)にかけてはひけをとらない。登場人物を五分の一に、分量を三分の一にするくらいでちょうどいいかも。とはいえ、ピンチョンの場合、無駄な細部の饒舌にこそ読書の快楽があるから始末に負えない。たとえば、“急角度に削られた斜面に挟まれた谷を埋めるように、失敗したタイムマシン――〈クロノクリプス〉〈アシモフ型世紀横断機〉〈時間変性機Q98〉――が、使える部品をすべて外された状態で、捨てられていた”とか、“森の模様がプリントされた風呂敷をカウガールのバンダナのように三角折りにして巻き、ビール割りのウィスキーを驚異的なペースでぐいぐい飲”む美貌の天才数学者、釣鐘ウメキ嬢とか。
対策としては、お気に入りの人物を見つけて道しるべにすること。わたしのお薦めは、オカルト的秘密結社TWITの庇護下にあるヤシュミーン。セックスのあいだもゼータ関数が頭から離れない数学おたくのレズビアン美女です。
ちなみに、それでも最後には(詐欺のような)美しい結末が待っているのでご安心を。健闘を祈る。
関連コンテンツ
訳者あとがき
本書はトマス・ピンチョンの長篇小説Against the Day (New York: Penguin Press, 2006)の全訳である。固有名詞の発音などについては、ディック・ヒルが全篇を朗読した力作CD(全四十二枚、総計約五十四時間)も参考にした。こっけいな部分は徹底的にこっけいに、叙情的な部分は感傷的なほど叙情的にと非常にメリハリのあるヒルの朗読には、他の点でも教えられるところが多かった。
読者がこの巻末に求めているのはひょっとすると「作品解題」よりも、注釈的な要素かもしれない。実際、かつて『競売ナンバー49の叫び』や『ヴァインランド』が初めて邦訳されたときには、小説としては異例の、膨大な訳注が巻末に付されていた。本書では、最低限必要と思われる情報のみを脚注として付した。その際、主に参照したのは、インターネット上のいろいろなホームページを除けば、オクスフォード社の各種英語辞典、『リーダーズ英和辞典』『リーダーズ・プラス』(共に研究社)、『ジーニアス英和大辞典』(大修館書店)、『ランダムハウス英和大辞典 第二版』(小学館)、『大辞泉』(小学館)、『ブリタニカ国際大百科事典』(ブリタニカ・ジャパン)、『百科事典 マイペディア 電子辞書版』(平凡社)、『広辞苑 第六版』(岩波書店)であるが、これら以外にもいろいろな専門事典にも当たるよう努めた。
さらなる注釈的情報を求める読者のために、本書を読む際に参考になる文献で比較的入手しやすい和書をいくつか挙げておきたい。
デビッド・マイケル・ジェイコブス『全米UFO論争史』(ヒロ・M・ヒラノ訳、ブイツーソリューション、二〇〇六)
また翻訳に当たっては無数のホームページを参照したが、中でも飛び抜けて有用だったもの(いずれも英文)を挙げておく。
http://against-the-day.pynchonwiki.com/wiki/ついでに、本書で印象的に登場するアイテムのうち、「マヨネーズ」などあまりにも日常的なものを除き、比較的容易に安価で(数千円以内で)入手できる品も、注釈を補うものとして挙げておこう。どれも本書を読む際に手元にあると楽しいが、参考になる度合いはそれぞれに異なる。小説執筆中のピンチョンも作品に登場する品々を机の周りに置いているという噂があるので、読者も多少それに近い気分を味わうことができるかもしれない。
- ライダー版のタロットカード。ライダー=ウェイト版と呼ばれることもある。
- 透明な方解石(氷州石)の標本。
- 一八九三年米国発行のコロンブス記念博覧会半ドル硬貨。
- コロラドの鉱山で採れた銀鉱石の標本。
- 計算尺。現在では円形のものなら手に入りやすいが、棒形のものは入手困難。
- 少し古いチベットの硬貨。米国版の原書で目次の後に印刷されている印章に図案がよく似ていて、獅子とヒマラヤの山々と二つの太陽が描かれている。
- ガズニー朝時代のアフガニスタンのディルハム銀貨。ヤシュミーンがペンダントにしているものと同じく縁の削れたものが多い。
- ハーモニカおよびウクレレ(ただし楽器として使えるウクレレは数千円では買えないようだ)。
- メキシコ産の隕石標本。最も有名なものは、一九六九年にチワワ州に落下したアエンデ隕石で、太陽系で最も古いと考えられる約四十六億年前の物質が含まれている(ただし小説中でフランクが拾うものは、時代的にこの隕石ではあり得ない)。
仮にこの「あとがき」に「作品解題」的なものを求める読者がいるとしても、この巨大小説についての解説を――極力簡単にとどめるとしても――ここで行うのは不可能と言ってよいだろう。したがって、『逆光』論のような文章は別の形でまとめることとして、ここではあくまでも作品の輪郭をごく簡単になぞるにとどめたい。
まずは本作品の印象的なタイトルについて述べよう。「アゲンスト・ザ・デイ」(Against the Day)という語句の意味は、作品を読んでも直ちに明確にはならず、むしろその多義性が浮かび上がる。小説の中では一度だけ、昼と夜、光と闇という対照を強調するように、「次の日に備えるため」という意味でこの句が用いられている(下396頁)。
「アゲンスト・ザ・デイ」という語句の背後には、しかし、他にいくつもの含意とほのめかしがある。第一に、聖書の句としては、「裁きの日まで」「裁きの日に備えて」「怒りの日のために」「戦いの日のために」の意でペトロの手紙二の三の七、ローマの信徒への手紙の二の五、箴言二一の三一、ヨブ記三八の二三などに現れるし、ミルトンの『失楽園』など多くの文学作品にも同様の意味で用いられている。『逆光』の最後のページをめくったとき、この語義を強く感じる読者も少なくないだろう。
第二に、この小説の最重要テーマの一つ、光や写真術と関連した文脈では、フランス語で “contre-jour” (英語に直訳すれば “against the day [daylight]”)という語がある。これは日本語で「逆光」を意味する。すなわち、被写体の背後から差す光、あるいはその位置関係のことだ。
第三に、「アゲンスト・ザ・デイ」という語句は、「時流に逆らって」と解釈することも可能だ。無政府主義的な爆弾テロリストの一家を中心に据えたこの小説は、「テロとの戦争」の先頭に立つ二〇〇〇年代のアメリカ合衆国の時流に逆らっていることは間違いない。
「これらを含む複数の解釈のうち、どれに基づいて日本語タイトルを決めればよいか」と著者に単刀直入に尋ねたところ、二つ目の「逆光」の意味が出るようなタイトルがよいとの回答があったため、これを邦題として採用することにした。日本語タイトルを「逆光」とした結果、作品内の光と闇という対照が浮かび上がり、「光に逆らう、光に向き合う」という骨太なテーマが前面に出ることになった。しかしもちろん、「アゲンスト・ザ・デイ」というフレーズを耳にした英語話者の頭にはまず「裁きの日に備えて」という聖書的な意味が思い浮かぶことと、「ぎゃっこう」という邦題の音の背後には「(時代に)逆行(する)」という別の意味が隠されていることも、ぜひ読者には知っておいていただきたい。
もう一つ、出しゃばりな訳者として少しだけ説明しておきたいのは、この小説の舞台設定についてだ。『逆光』の背景となっているのは一八九三年から第一次世界大戦直後に至るまでの時代で、地理的にはアメリカ合衆国各地、ロンドンやベニス、オステンドやゲッティンゲンを主とするヨーロッパの各都市、中央アジアなどにまたがっている。この時代にどのような空気が漂っていたのかを、比較的有名な映画と小説、そして歴史的事実を参照しながら、かつ、小説内で明示的・暗示的に言及されている出来事に関連するものに絞って、ざっと眺めてみよう。
映画創成期にリュミエール兄弟が撮影したフィルムを集めたDVDボックス『レ・フィルム・リュミエール』には一八九五年から一九〇五年の間に撮影された貴重な映像がいくつも収録されている。中には、小説中でヤシュミーンらが観る「船から撮影された大運河のパノラマ」をはじめ、「バクーの油井」「海岸と公衆浴場」「バッファロー・ビル:レッド・スキン」「サントス・デュモン氏の飛行船実験」「飛行船とその推進装」など、『逆光』と直接結びつくものも含まれている。
映画に絡めて話を続けるならば、西部劇でしばしば取り上げられる「OK牧場の決闘」は一八八一年の出来事だし、『駅馬車』など有名な西部劇のほとんどは一八八〇年代以前の西部を舞台にしている。一八九〇年代のアメリカ西部を描いた映画としては、ブッチ・キャシディーとサンダンス・キッドを主人公とする『明日に向かって撃て!』(一九六九)を思い浮かべる人が多いかもしれない。あの映画が描いていたように、一八九〇年代はまさに、「西部」という名の何ものかが失われていった時代だった。
アメリカの都市部でも、それに呼応するような動きがあった。日本ではあまり知られていないアメリカのポストモダン小説家E・L・ドクトロウの『ラグタイム』(一九七五)は、影絵師から映画王に成り上がるユダヤ系移民、テロリストになる黒人ピアニスト、奇術師のハリー・フーディニ、無政府主義者のエマ・ゴールドマンなど、虚構と実在の人物を織り交ぜながら、『逆光』と重なる時代のアメリカの都会を描いている。あの独特な語り口で人気となったドキュメンタリー番組の『プロジェクトX』みたいに淡々とした、箇条書きのような文体が印象的な『ラグタイム』は、世紀転換期のアメリカの風景をこう書いている。
何百万というひとが失職していた。運良く仕事に就いた者も組合の結成に向かわざるをえなかった。裁判所は彼らの運動を禁止し、警官は彼らの頭を殴った。指導者は刑務所に入れられ、代わりの人間がその職をもらった。組合は神に対する冒涜と見なされた。ある富裕階級の男が言った、労働者は煽動家によって保護されたり世話をされたりするのではなく、神がその無限の英知においてこの国の資産管理を任せているキリスト教徒によって庇護されるべきだ、と。他の手段で弾圧できないときは、軍隊がかり出された。
ドクトロウ『ラグタイム』(邦高忠二訳、ハヤカワ文庫、一九九八 53-54頁)
ちなみにアメリカでは、南北戦争後の好況に沸いたおよそ一八六五年から一九〇〇年ごろにかけての時期は“金ぴか時代”と呼ばれている。それは成金趣味と汚職、軽薄と強欲の時代だった。
“金ぴか時代”の終わったアメリカで一九〇五年に雑誌に連載され、一九〇六年に単行本として出版されると共に話題を呼び、ベストセラーともなったのは、アプトン・シンクレアの小説『ジャングル』だった。これは、シカゴの食肉加工場を舞台とした作品で、当時の工場の衛生状態の悪さや、そこでの労働条件のひどさを描いたものだった。『逆光』でも、それによく似た光景が描かれている。
また、大量食肉加工の前提となる交通網に関して言えば、アメリカで最初の大陸横断鉄道が完成したのが一八六九年、ヨーロッパでオリエント急行が営業を始めたのが一八八三年だから、この時代には広範な地域で大量の物資や人が移動し始めていたと言えるだろう。
そして、この時代を代表するアメリカ人小説家マーク・トウェインが一八八九年に発表した『アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー』において、初めてアメリカ文学に「過去へのタイムトラベル」という仕掛けが登場した。ところ変わって一八九五年のイギリスでは、H・G・ウェルズの『タイムマシン』が発表され、サイエンスフィクションの礎を築いた。ウェルズよりも先にSF的な小説をいくつも書いていたフランスの作家ジュール・ヴェルヌは、一八六三年に『気球に乗って五週間』、翌一八六四年に『地底旅行』を出版している。ヴェルヌに影響を与えたアメリカの作家エドガー・アラン・ポーが『ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語』で南極探検を描いたのは一八三七年のことだが、極地探検が現実に本格的に試みられたのは一九〇〇年代初頭のことだった。
探検といえば、スウェーデン人の探検家スヴェン・ヘディンが第一次中央アジア探検を行なったのは一八九三年から九七年にかけてのことだ。彼は四度にわたる遠征の中で、秘境チベットを訪れたり、不毛の砂漠のただ中にさまよえる湖「ロプ・ノール」を発見したりした。
『逆光』の時代に関して私たちが既におおよそ知っているであろう背景知識を簡単に整理するなら以上のようになる。それはつまり、大工場、鉄道、探検、SF、映画、気球、奇術、西部の喪失、劣悪な労働条件、労働組合に対する弾圧、強欲、無政府主義、テロの時代だ。
そして、これだけ壮大で多様な要素を一つの小説の中に織り込んだのが『逆光』という大作だ。情報サイト「アバウトドットコム」の書評が本書に関して「活動昂進状態にある聡明な子供が自分の持っているすべてのおもちゃについて、一つ一つの歴史と構造の蘊蓄を延々と語っているみたいだ――一度もそれらで遊ぶことなしに」(http://contemporarylit.about.com/od/fiction/fr/againstTheDay.htm)と述べているのは面白いたとえだ。ただし、私には作家が蘊蓄を交えながら飛び切りの持ちネタで遊んでいるように思われるし、一緒に遊ぶように読者を誘っているとも感じられる。別の書評は本書を「カール・マルクスがマルクス兄弟に加わったようだ」と評しているが、これもまた絶妙の形容だと思う。
アメリカ出身の大作家ヘンリー・ジェイムズはかつて、一つの形態の中で主題を過不足なく利用し尽くしたものを最善の小説と考え、それとは逆の、散漫で構成の緻密さを欠いた長篇小説、主題を浪費している小説を「ぶよぶよでぶかぶかの化け物(loose baggy monster)」と呼んで批判した。しかし、もしも同じ語句がプラスの意味(「束縛するものがなく懐も深い怪物」)に解釈できるとするなら、本小説こそまさにその形容にふさわしい。『逆光』はジェイムズ的な審美眼とは違う美学に基づいて書かれている。作品を最後まで読んでも「あれ、あの話はその後どうなったの?」とか「この話はこれだけで終わり?」という疑問が残る部分も多々ある一方で、意外な細部にちゃんとした落ちがついていたりする部分もやはりこの作家の独特なスタイルの一つだ。
原作の文体は他のピンチョンの小説に比べると平易な方だと思うが、日本語に訳しづらい点では他の作品に劣らないだろう。例えば冒頭近くに、“in a spirit of constructive censure” というフレーズがある(原書13頁、本訳書・上巻26頁)。これは簡潔に訳すなら「擬制的
異なる種類の例としては、(これは実際には作品中にない文だが)「彼は後に吐くことになるその液体を飲んだ」と訳せる文があった場合、しばしばそれは「彼はその液体を飲み、その後、それを吐くことになった」とも訳せる。ピンチョンの持つ絶妙のユーモア感覚が表れるこうした局面では、基本的には英語の語順に近い形で読者に情報が伝わるような訳を心がけた。英文解釈的に折り返して訳すと「落ち」が「ネタ振り」の前に来て、結果的に興醒めなギャグになるので、それを防ぐ必要があるからだ。しかしそれはあくまで原則だ。最終的には個別的にそれぞれの文の面白さが最もよく伝わる訳し方を選んだつもりだが、あくまでもそれは私個人の判断によっているので、読者の中にはそこにかなりの恣意性を見る方もあるかもしれない。ご寛恕を願いたい。
本書は構成などの点でも、ピンチョンの他の大部な作品と比較して、読みやすい書き方がなされているように思う。記述は、途中に少しずつフラッシュバックとフラッシュフォワードが挟まるけれども、ほぼ時系列に従って進むし、各節ごとのまとまりもあるので、多少人間関係を見失うことはあっても、それぞれの挿話を楽しみながら――あるいは悲しみながら――読み進めることができる。訳文のぎこちなさが読者の楽しみの障害とならないことを祈るばかりだ。
やや余談になるが、本書には声と口の動きが微妙にズレる人物が登場する。その描写は人気腹話術師のいっこく堂氏を彷彿とさせるし、実際作者が本書執筆中に、二〇〇三年の「いっこく堂ニューヨーク公演」(あるいはテレビ映像など)を見た可能性さえ感じさせるが、確証はない。また別の場面でハミングされる「タタタタ、トン、トン/トントン、トン……」という中国風のメロディーも、「ほら、あの中華食品のテレビコマーシャルで流れるあの曲」と注を付けたいところだったが、曲名も分からず、音符を添えるわけにもいかないので自重した。もちろんそこまで主観的・妄想的・お遊び的かつ曖昧な注を付けるわけにはいかないが、作品の随所にちりばめられた「これって○○!」にもしも一つでも気づいていただければこの上なくうれしい。
京都大学の若島正先生が新潮社出版部の北本壮さんに私のメールアドレスを伝えてくださったことがきっかけとなり、私が本作の翻訳をすることになった。この翻訳を担当できたのは望外の幸せでした。若島先生、ありがとうございました。そして「トマス・ピンチョン全小説」の刊行はまだ先が続きますが、北本さん、ご苦労様でした。そしてありがとうございました。訳稿の作成に当たっては、一人一人のお名前はここでは挙げないが、さまざまな方々のお世話になった。ありがとうございました。いつものようにFさん、Iさん、S君は、ゲラの厚さにして約十センチという長大な翻訳作業に私が没頭した約二年の間、常に訳者に励ましと元気を与えてくれた。ありがとう。
最後に一言。何だかんだ言っても、ピンチョンの小説を読む人々に訳者がかけられる言葉はやはり一つしかない。「さあ、みんなで――」
二〇一〇年八月
訳者
著者プロフィール
トマス・ピンチョン
Pynchon,Thomas
1963年『V.』でデビュー、26歳でフォークナー賞に輝く。第2作『競売ナンバー49の叫び』(1966)は、カルト的な人気を博すとともに、ポストモダン小説の代表作としての評価を確立、長大な第3作『重力の虹』(1973)は、メルヴィルの『白鯨』やジョイスの『ユリシーズ』に比肩する、英語圏文学の高峰として語られる。1990年、17年に及ぶ沈黙を破って『ヴァインランド』を発表してからも、奇抜な設定と濃密な構成によって文明に挑戦し人間を問い直すような大作・快作を次々と生み出してきた。『メイスン&ディクスン』(1997)、『逆光』(2006)、『LAヴァイス』(2009)、そして『ブリーディング・エッジ』(2013)と、刊行のたび世界的注目を浴びている。
木原善彦
キハラ・ヨシヒコ
1967年生まれ。大阪大学教授。訳書にトマス・ピンチョン『逆光』、リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』、アリ・スミス『両方になる』『夏』、オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』、ジョン・ケネディ・トゥール『愚か者同盟』、ジャネット・ウィンターソン『フランキスシュタイン』など。ウィリアム・ギャディス『JR』の翻訳で日本翻訳大賞を受賞。著書に『実験する小説たち――物語るとは別の仕方で』『アイロニーはなぜ伝わるのか?』など。