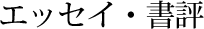腑に落ちてくる不思議さ
奇譚とは不思議な話のことをいう。ここには五編の奇譚が収められている。
数々の偶然に導かれるゲイの調律師。サーファーの息子を亡くした母親が見たもの。行方不明者の捜索が行なわれるマンションの階段。人生において本当に意味を持つ女のひとりと出会った男。じぶんの名前だけ忘れてしまう女。
それぞれの物語に登場する人物はみな東京に住み、普段はいわゆるごく普通の日常生活を送っている。そんな彼らがあるとき、とても現実のものとは思えない、奇想天外な出来事に遭遇する。
小説とはいえ、「そんなばかな」と突っ込みを入れたくなりそうな話ばかりである。最後の一編である「品川猿」では、あまりの突拍子のなさに「猿......」とつぶやいてしまった。けれど読んでいる最中は話の流れから意識が離れることなく、ごく素直に、ときには深くうなずきながらページを繰っていた。
登場人物たちに突然のように訪れる事件が、彼らにとって本当に非現実的な、降って湧いたような出来事としては書かれていない、というせいでもある。
生き物というのは、生きているかぎり何かを欲し、欲するものを手に入れるため、無意識のうちにもみずからのテリトリーに伏線を敷きつめるらしいことが、五編の短篇から感じ取れる。しかも、その舞台として選ばれたのは、珍妙さをあたかも滋養のように呼吸しつづける都市、というか時空、東京だった。
それに、ここで描かれるさまざまな不思議さを、じつは自分もどこかで知っている、とも思う。おなじ体験を味わった覚えはないが、自身のどこかでは、はからずも、自然に納得している。もしかしたらその部位にとって、それらの不思議さのあり方は、しごく理に適っているのかもしれない。
不思議の理を小説にするとは、これこそが理を超えた、不可思議な行為である。これまでの作品においても、目に見えないもののありかを、ここだと指差し、どんなものだか描写してみせてきた著者だから可能なのだろう。
猫にまたたびのごとく、人間は謎のとりこである。もしや人の一生は謎解きに明け暮れて終わるのではなかろうか。謎はいずれ解かれることを期待されている。解けた、と思われたときの快感は相当なもので、だからなぞなぞ遊びはまず答えありきである。
この小説にはそういった類の謎はない。あるのはやはり、不思議さだけだ。
不思議さというのはどこまでいっても不思議なままで、なぜなのか理由が明かされることは永遠にない。けれど人間である以上、謎解きの魔力から逃れることもできない。
魔力にとりつかれ、不思議さの源をたどろうとすればそこに現れるのは、運命、時間、記憶、言葉といった、自分のものであるようなないような、それでいて私たち自身になじみ深いものたちである。
作中でそれらは、どこぞから立ちのぼってくる芳香のように扱われている。鼻をくんくんいわせているうちに、匂いは鼻腔を抜けてこちらの細胞にまで染みこんでくる。どうやら抽象的概念と呼ばれるそれらは、私たちの生々しい肉体の所作であると同時に、源の所作でもあるような気がする。登場人物たちがいつのまにか、けれどもある意味みずからの意志でとらわれ、とらえようとしているものに、読んでいるこちらも肉薄してゆく。著者、あるいは著者を通して伝わってきた不思議さそのもの、による導きのままに、両者の感覚は重ならざるをえなくなる。感情移入ならぬ感覚移入が、起こるべくして起こる。そういえば彼らも私たちも、同じ不思議さを生きる者どうしだったと、体のどこかが思い出す。
それにしても「品川猿」を読んだあとは、もしも私の住んでいる世田谷区に猿が現われたらみんなどうするだろう、としばらく考えてしまった。私たちには、人間様にとんでもないことをしでかす、奇妙キテレツな猿をどうにかできるほどの知恵と経験が、はたしてあるんだろうかと思う。
たった今も、私たちの生活は、うろんなものや猿の出現に密かにおびやかされながら、かろうじて続けられているのかもしれない。
(くりた・ゆき 作家)
波 2005年10月号より
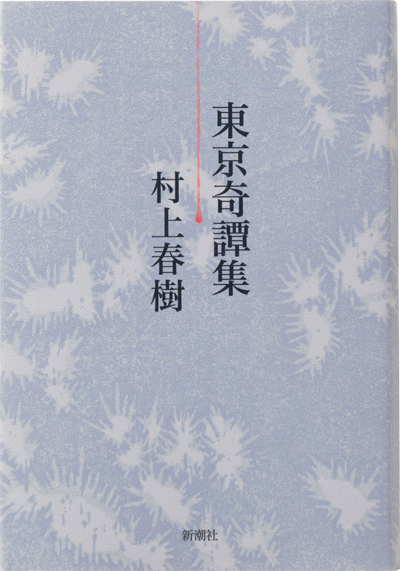
単行本
東京奇譚集
村上春樹/著
発売日 2005年9月16日
1,760円(定価)