第15回 受賞作品
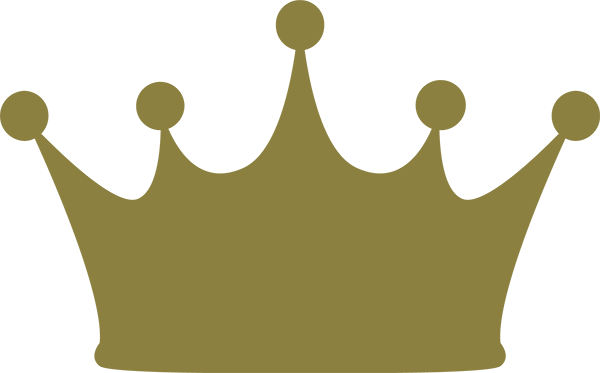 読者賞受賞
読者賞受賞

――このたびは受賞おめでとうございます。四年連続で最終選考に残っていた一木さんの読者賞受賞は、私たちも嬉しいです。受賞第一報はどのような状況でお聞きになりましたか。
受賞の連絡は、バンコクの自宅の、いつも書いている部屋で受けました。日本との時差はマイナス2時間なので、現地では16時くらいだったと思います。エンリケ・イグレシアスを聴いているときでした。
――受賞の連絡を受けた瞬間、どのように感じましたか。
やったー! とか、よかったー! という感想よりも、ああ、今年だったんだな、という感じでした。ほっとしたのとも違うのですが、静かな感動、というのがぴったりかもしれません。
――今までの作品と比べて、手応えのようなものはありましたか?
ありました。いつもあると言えばあったんですけど(笑)。これまでも、最終候補に残った作品は、友だちや家族も読んでくれていたのですが、「西国疾走少女」が一番評判が良かったんです。「物語に入って行きやすかった」「主人公がかわいい」という感想をもらえて、そういう風に読んでもらえたんだな、とうれしかったです。でも読者がどんな風に読んでくれたのかは謎です。すごく知りたい。
――この賞に応募したきっかけはなんだったのでしょう。
インターネットで偶然見かけて応募しました。自分の書いたものがどんな評価を受けるのか興味があったので、二次選考の段階で編集者のコメントをいただけるのがよかったです。2013年に最終候補に残ってからは、R−18文学賞に的を絞って応募してきました。そのほうが、読んでくださる方に届く気がしたので。ここ数年は、3月どきどき、4月がっかり、というのが年中行事のようになっていたので、来年はもうそれがないのだと思うと、なんだか変な感じです。
――いつから小説を書こうと思われたのですか。
作家になろうと思っていた訳ではなかったんです。ただ、初めて書きたいと思った瞬間のことは、はっきり覚えています。大学生のときに出会った女の子がいて、彼女と一緒に過ごしたのはたった1日、数時間だけだったのですが、彼女のうつくしさと言動に不思議な吸引力があって、強く印象に残ったんです。いつか、彼女のような「人間」を小説に書きたいと思いました。それが、創作意欲が芽生えた瞬間だったと思います。時を同じくして、たまたま大学のゼミの先生から「けいさんは面白いことが書けると思う」と言われたのも、後押しになりました。でも、しばらくはうまく書けませんでした。書きたいとは思っていたけれど、書いても書いてもこれじゃぜんぜんだめだと笑って破りすてるような作品ばかりでした。
「書ける」と言ってくれたのは経済学部の教授だったのですが、その先生とは本の趣味も合って。卒業してからもゼミの仲間といっしょに飲んだり、みんなで先生の別荘に泊まりに行ったりしていました。それがある日、先生の奥様から「亡くなりました」と電話で連絡を受けたんです。先生の死のあと、家族や友人が相次いで亡くなり、生死について考える時期が続きました。書かないとおかしくなってしまうようなときがあって、そこからパソコンに向かう時間が増えたのだと思います。
そうなると、書きたくて仕方なくて、なんとかして時間を作って書いていました。フルタイムではなかったのですが仕事もしていたし、子育てもしていたんですけど、どうやって書く時間を作るか、ということばかり考えていました。
――過去の最終候補作を読み比べてみても、一木さんはとてもたくさんの引き出しを持っていらっしゃるというイメージがあります。どうやって作品のテーマを探しているのでしょうか?
受賞作の「西国疾走少女」は2015年に寝屋川市で起こった事件がきっかけで書きました。中学生の男の子と女の子が、夜に家の外で会う、その危うさや閉塞感がずっと頭から離れなくて。とても怖くつらい事件でしたが、自分にも中学生のころ、夜に外へ出たいという好奇心や暗さがあったなと思ったんです。でも、今回のように外からの情報で何かを書きたいと思うことは珍しくて、いつもはひたすら自分の中に潜っていく感じです。
――今後はどのような作品を書いていきたいですか?
気になっているテーマだと「罪悪感」「支配」「アルコール依存症」あとは「ちょっと頼りないけどにくめない政治家」などですかね(笑)。
タイでの生活はとても快適です。日本語でどんな破廉恥なものを読んだり書いたりしていてもばれません(笑)。「日本で書くのとタイで書くのと違いはあるか」と授賞式の際に何度か訊かれたのですが、やはり違うと思います。自分の中の、日本語で抱いている感覚を、タイの人に伝えるときにタイ語でどういう風に表現しようかなと考えたり、テロやデモがあって落ち着かない中でどうやって暮らしていくかとか、日本で生活していたときにはなかった感覚がうまれていると実感しています。言語感覚が敏感になって、日常が不安定だったりするからこそ、書きたいものはどんどん書いていかなくてはならないと思っています。言い換えればその気持は、いつ訪れるかわからない死への焦りかもしれません。でもそれこそが、作品を生み出す原動力にもなっている気がします。

