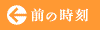
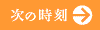
24:05 末広町駅-神田 |
|
これでいい。 うなずくと同時に、ドアが閉まった。 電車が動き始めると、朝子は手帳に目を戻した。 これで、会議室中の視線を窓に向かせておくことができる。 ここまでは、これでいい。 だとすると、次の問題は、後始末だ。 松波幸三郎を落下させた装置を、誰も気がつかないうちに片づけなくてはならない。いくら大勢の人間に落下する松波を見せたところで、装置が発見されてしまってはなにもならない。 もちろん、装置が仕掛けられているのは7階の社長室ではない。 あたりまえだ。 ほとんどの者の関心は路上の死体に向けられているだろうし、ビルを飛び出していく人間も何人かはいるに違いない。救急車と警察が呼ばれ、松波の死体が路上から運び去られるまで、人々の視線や意識は、ずっと路上に惹きつけられている。 しかし、飛び降りたのが松波だとわかった時点で、社長室を覗きに行く人間がいる可能性も充分にある。もちろん、警察は必ず社長室を調べるだろう。 だから、装置は社長室にはない。社長室で彼らが発見するのは、大きく開かれた窓だけだ。 装置は、7階の社長室ではなく、その真上――8階に置かれている。 実際に松波の死体が落下するのは、8階の窓からなのだ。 松波幸三郎は、その部屋で殺され、その窓から放り出される。 片づけなくてはならないのは、8階に置かれた装置だ。 簡単な装置――。 朝子は、手帳のページを前に繰った。 そこに、装置の簡単な設計図が書いてある。 設計図というより、装置の構造図だ。 使用されるのはアルミ製の大きな脚立が1台。人の身体が乗るぐらいの合板が1枚。丈夫な巨大風船が1つ。圧縮空気のボンベ1個。そして、圧力感知機能を備えたバルブ。50センチほどの針金が6本。 それで全部だ。 窓を大きく開放し、脚立を載せた机を窓に寄せて置く。脚立の天板を窓の下枠に圧着し、その脚の上に板を載せる。合板の中央の何ヶ所かには穴が開けられており、針金を通して板と脚立をしっかり固定する。脚立の脚の間にしぼんだ風船をセットし、その風船の口をバルブにつなぐ。板の上に松波幸三郎の死体を載せ、ボンベのコックを開いて空気を風船に送り込む。 仕掛けはそれだけだ。 時間が経つごとに風船が膨らみ、脚立の脚を開かせる。服を着た人間の身体は摩擦のために多少の傾きでは動かないが、実験の結果35度を超え40度あたりになると転がり落ちる。その時間が最短18分50秒、最長では22分30秒なのだ。バルブの感圧装置は、風船が設定した数値以上の内圧になると空気の送出をストップさせる。そのバルブがないと、風船は松波を転がり落とした後も膨らみ続け、ついには大きな音を立てて破裂してしまう。 破裂音など、もちろんもってのほかだ。そこに装置があることを知らせているようなものだから。 今日のテストで教えてもらったのは、風船も、何度も膨らませたりしぼませたりすると疲労してくるということだった。つまり、何度も繰り返しているとゴムが弱くなり、破裂しやすくなる。まあ、話によれば、そういった疲労が現われるのは数十回も繰り返した場合のことで、まず影響はないと考えていい。 とにかく、問題は、8階に置かれているその装置を片づけることだった。 膨らんだ風船をしぼませ、バルブを外してボンベを片づける。 脚立に固定されている板を外し、板と脚立と針金を、バラバラにして部屋のあちこちに分散させる。 むろん、開け放たれている窓は、真っ先に閉めなければならない。 実は、この後始末のうちで一番厄介なのが膨らんだ風船をしぼませる作業だ。バルブを風船につけたまま、まずボンベを切り離し、バルブの調整によって空気を抜かなくてはならない。早く作業を終わらせたいからといって、風船の口からバルブを外したり、風船に穴を開けたりするわけにはいかないからだ。穴を開ければ破裂させるのと同じことで大きな音が出るし、バルブを外しても今度は勢いよく噴出する空気が、ベーッ、というとてつもない音を立てる。空気は、徐々に抜かなくてはならないのだ。 計測した結果、音をあまり立てずに空気を抜くには7、8分が必要だった。 テキパキとこなして、15分ぐらいかな。 朝子は、手帳のページを眺めながら思った。 つまり問題は、松波幸三郎が路上に落下してから、どの時点で、その15分を手に入れるかということだ。 できれば、警察が到着する以前に、すべての片づけを終えていたいのだが、それはどうも不可能であるような気がする。日本の警察は、迅速な初動捜査を得意としている。 ううむ……。 朝子は、手帳を見つめながら顔をしかめた。 |