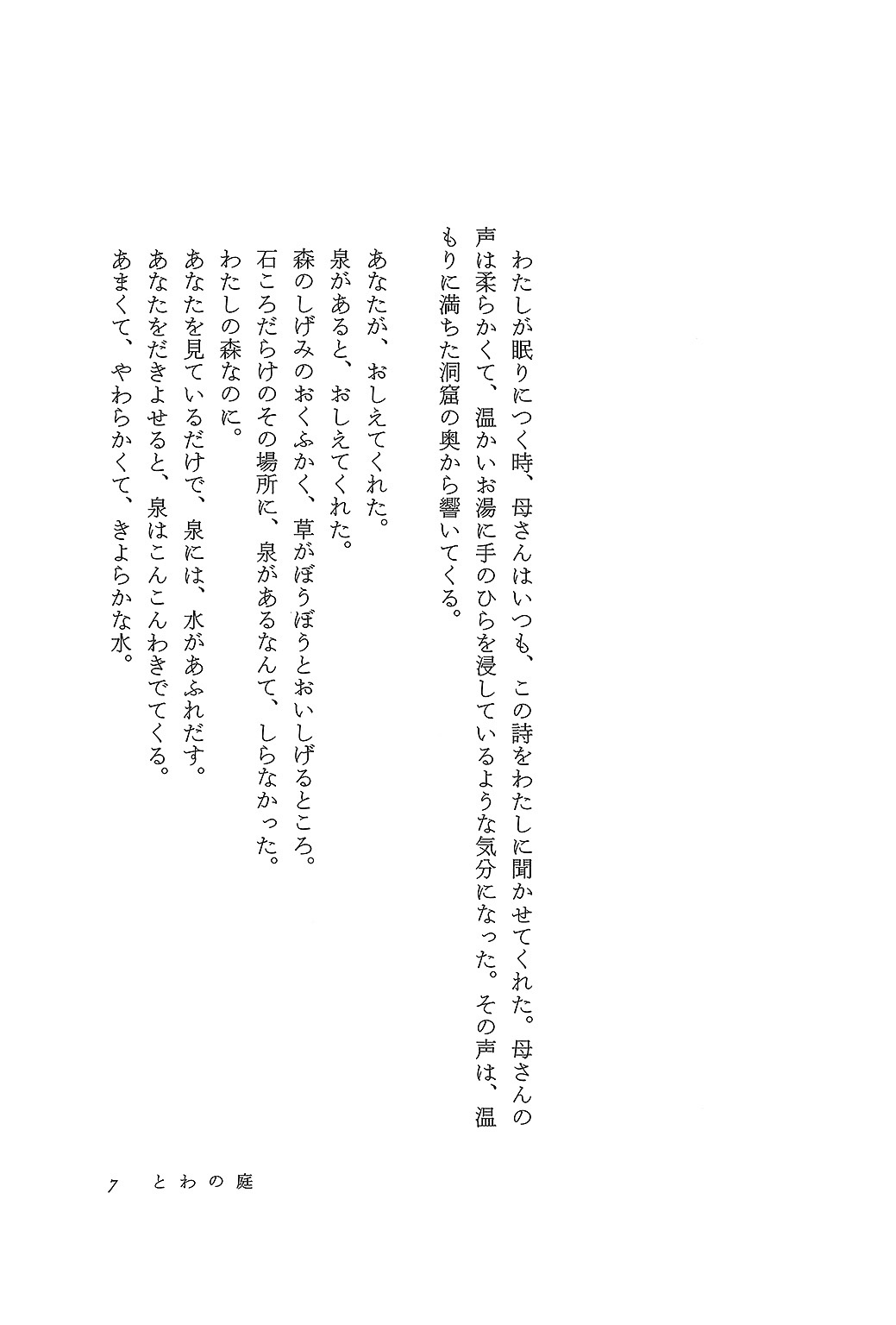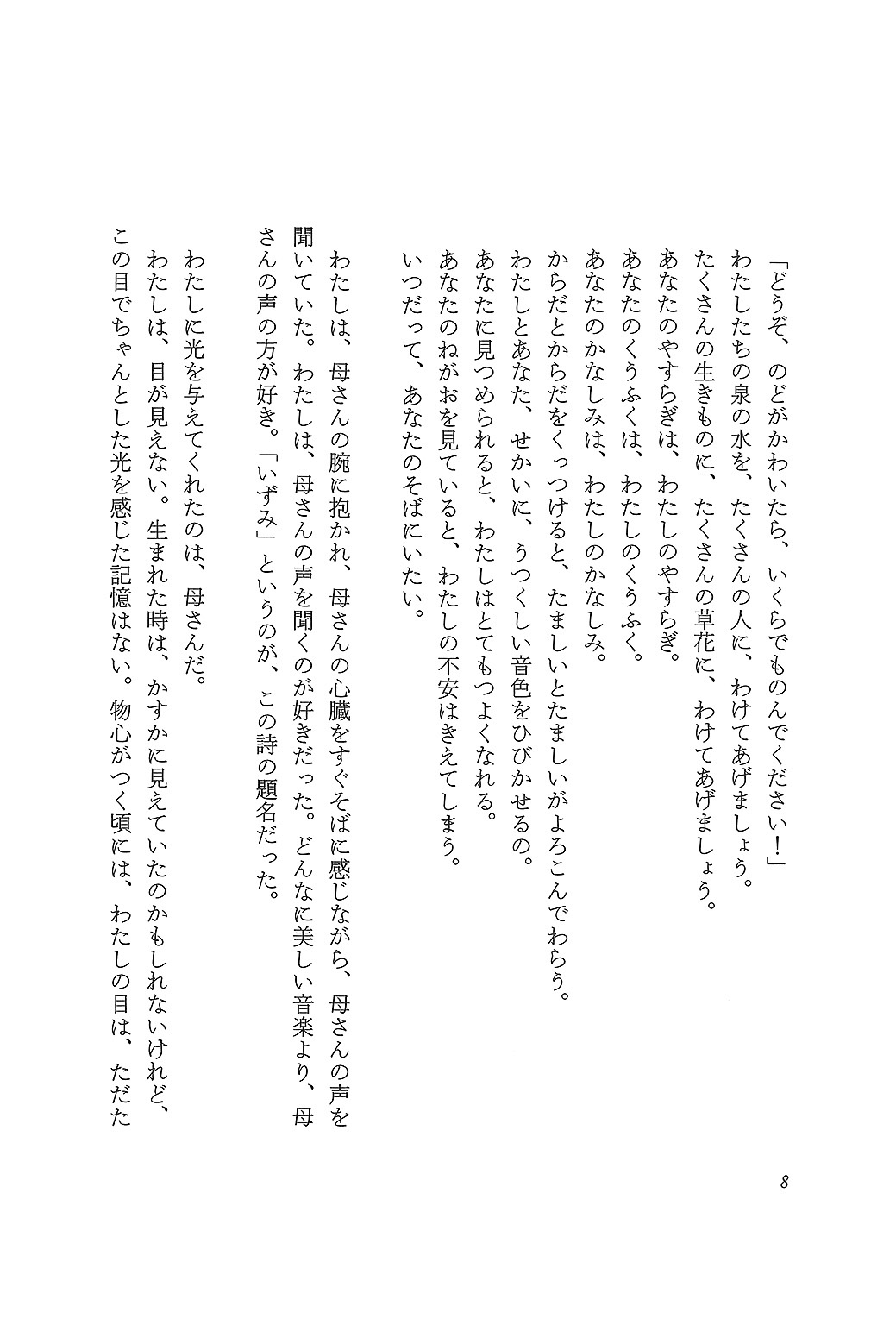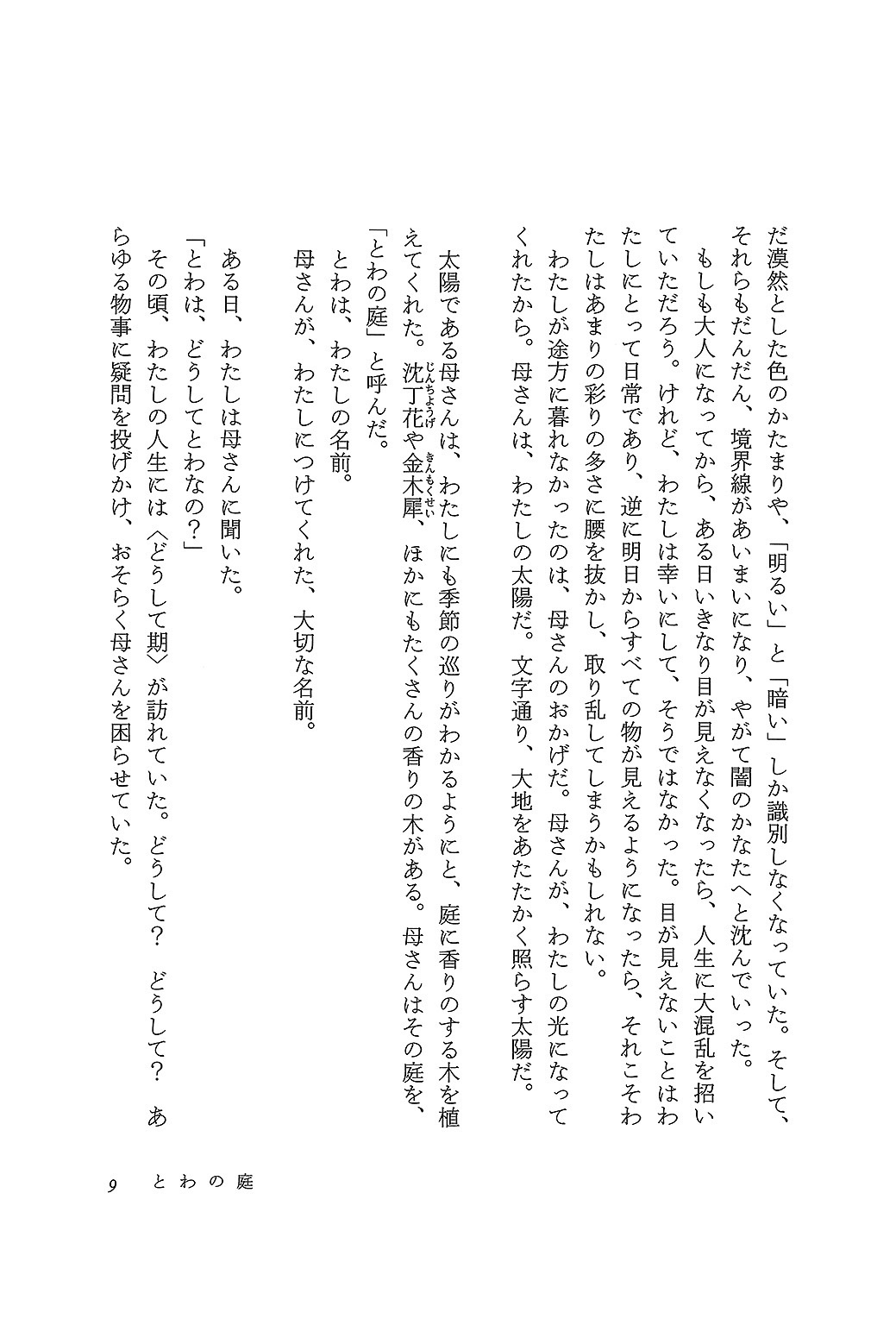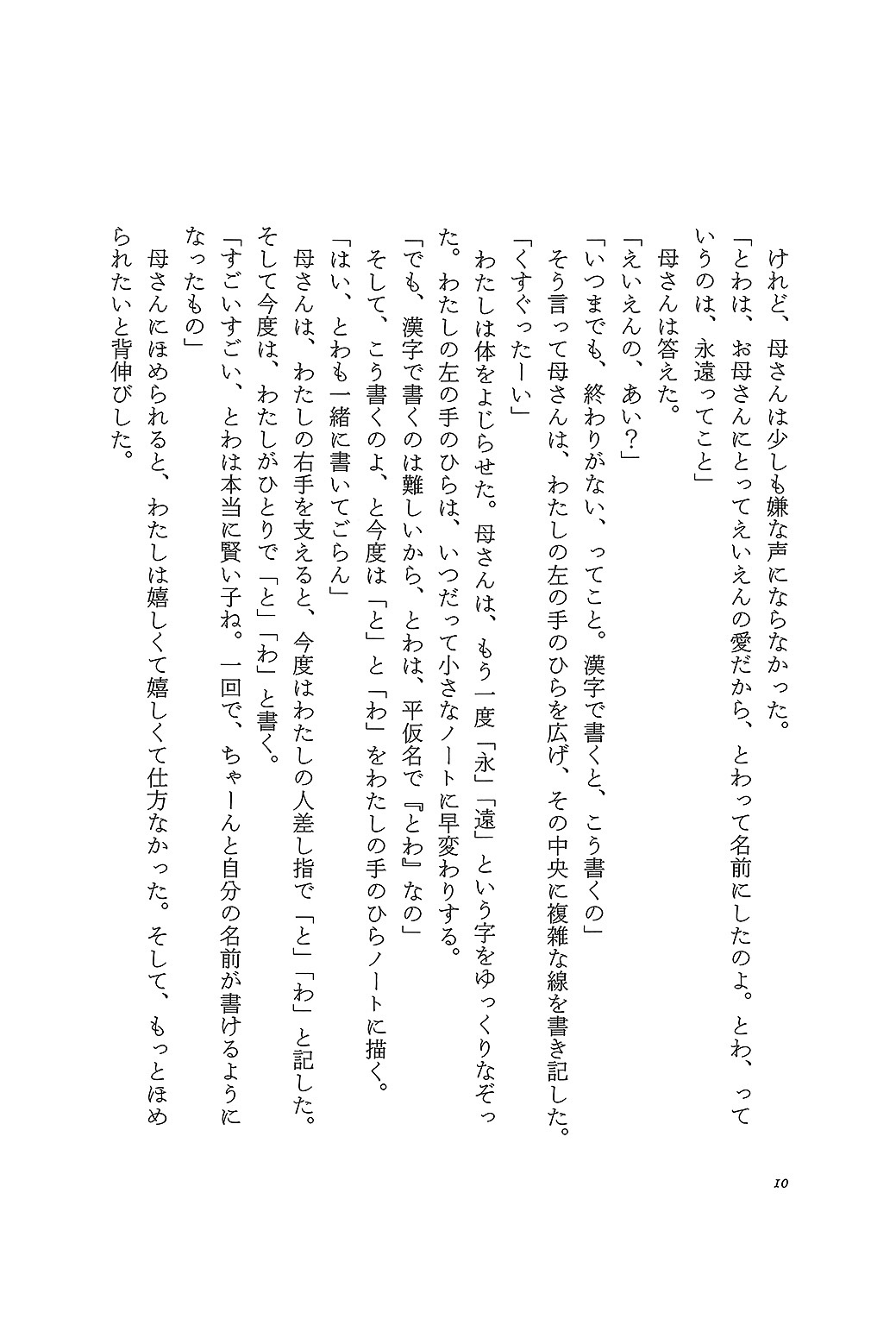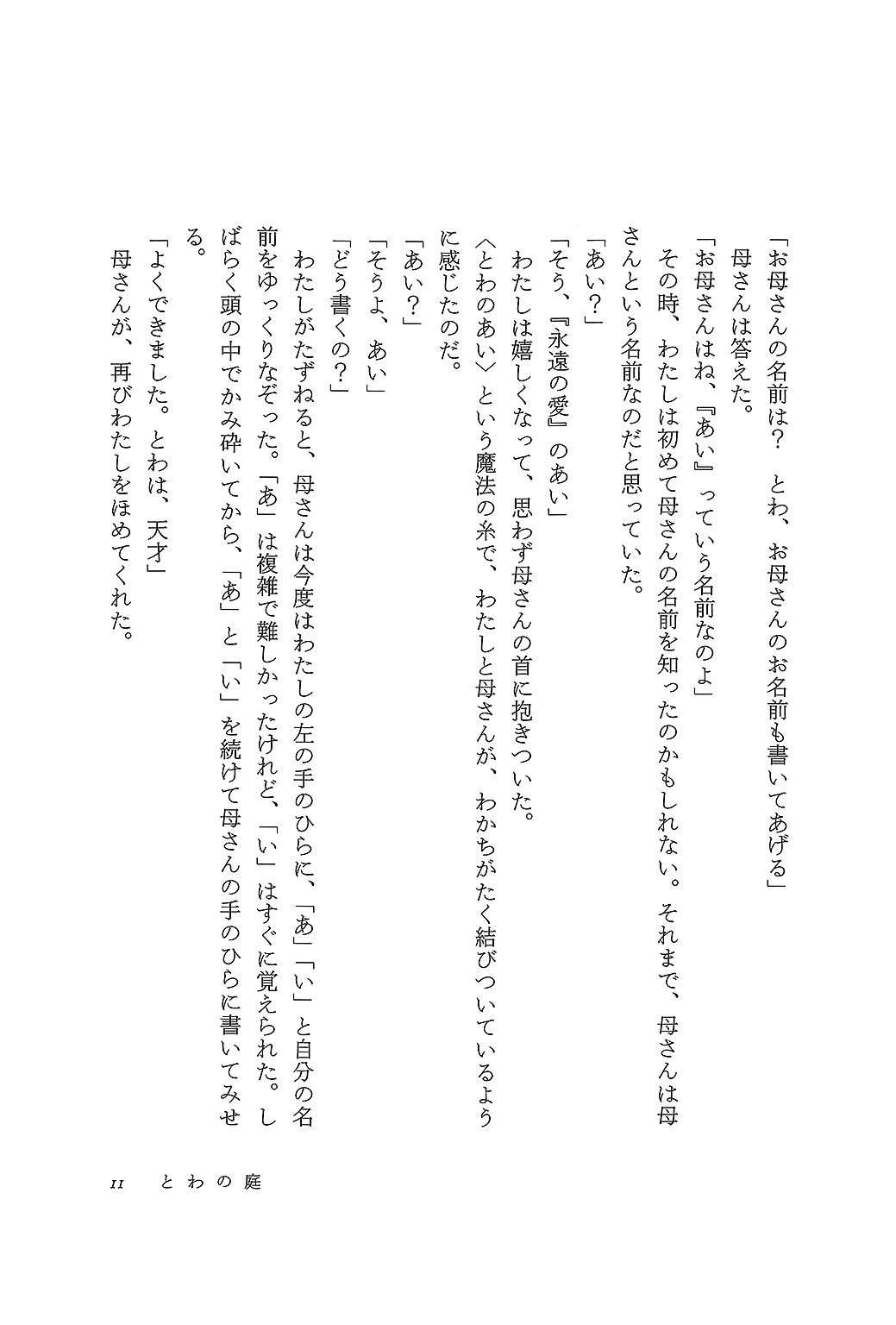わたしが眠りにつく時、母さんはいつも、この詩をわたしに聞かせてくれた。母さんの声は柔らかくて、温かいお湯に手のひらを浸しているような気分になった。その声は、温もりに満ちた洞窟の奥から響いてくる。
あなたが、おしえてくれた。
泉があると、おしえてくれた。
森のしげみのおくふかく、草がぼうぼうとおいしげるところ。
石ころだらけのその場所に、泉があるなんて、しらなかった。
わたしの森なのに。
あなたを見ているだけで、泉には、水があふれだす。
あなたをだきよせると、泉はこんこんわきでてくる。
あまくて、やわらかくて、きよらかな水。
「どうぞ、のどがかわいたら、いくらでものんでください!」
わたしたちの泉の水を、たくさんの人に、わけてあげましょう。
たくさんの生きものに、たくさんの草花に、わけてあげましょう。
あなたのやすらぎは、わたしのやすらぎ。
あなたのくうふくは、わたしのくうふく。
あなたのかなしみは、わたしのかなしみ。
からだとからだをくっつけると、たましいとたましいがよろこんでわらう。
わたしとあなた、せかいに、うつくしい音色をひびかせるの。
あなたに見つめられると、わたしはとてもつよくなれる。
あなたのねがおを見ていると、わたしの不安はきえてしまう。
いつだって、あなたのそばにいたい。
わたしは、母さんの腕に抱かれ、母さんの心臓をすぐそばに感じながら、母さんの声を聞いていた。わたしは、母さんの声を聞くのが好きだった。どんなに美しい音楽より、母さんの声の方が好き。「いずみ」というのが、この詩の題名だった。
わたしに光を与えてくれたのは、母さんだ。
わたしは、目が見えない。生まれた時は、かすかに見えていたのかもしれないけれど、この目でちゃんとした光を感じた記憶はない。物心がつく頃には、わたしの目は、ただただ漠然とした色のかたまりや、「明るい」と「暗い」しか識別しなくなっていた。そして、それらもだんだん、境界線があいまいになり、やがて闇のかなたへと沈んでいった。
もしも大人になってから、ある日いきなり目が見えなくなったら、人生に大混乱を招いていただろう。けれど、わたしは幸いにして、そうではなかった。目が見えないことはわたしにとって日常であり、逆に明日からすべての物が見えるようになったら、それこそわたしはあまりの彩りの多さに腰を抜かし、取り乱してしまうかもしれない。
わたしが途方に暮れなかったのは、母さんのおかげだ。母さんが、わたしの光になってくれたから。母さんは、わたしの太陽だ。文字通り、大地をあたたかく照らす太陽だ。
太陽である母さんは、わたしにも季節の巡りがわかるようにと、庭に香りのする木を植えてくれた。
とわは、わたしの名前。
母さんが、わたしにつけてくれた、大切な名前。
ある日、わたしは母さんに聞いた。
「とわは、どうしてとわなの?」
その頃、わたしの人生には〈どうして期〉が訪れていた。どうして? どうして? あらゆる物事に疑問を投げかけ、おそらく母さんを困らせていた。
けれど、母さんは少しも嫌な声にならなかった。
「とわは、お母さんにとってえいえんの愛だから、とわって名前にしたのよ。とわ、っていうのは、永遠ってこと」
母さんは答えた。
「えいえんの、あい?」
「いつまでも、終わりがない、ってこと。漢字で書くと、こう書くの」
そう言って母さんは、わたしの左の手のひらを広げ、その中央に複雑な線を書き記した。
「くすぐったーい」
わたしは体をよじらせた。母さんは、もう一度「永」「遠」という字をゆっくりなぞった。わたしの左の手のひらは、いつだって小さなノートに早変わりする。
「でも、漢字で書くのは難しいから、とわは、平仮名で『とわ』なの」
そして、こう書くのよ、と今度は「と」と「わ」をわたしの手のひらノートに描く。
「はい、とわも一緒に書いてごらん」
母さんは、わたしの右手を支えると、今度はわたしの人差し指で「と」「わ」と記した。そして今度は、わたしがひとりで「と」「わ」と書く。
「すごいすごい、とわは本当に賢い子ね。一回で、ちゃーんと自分の名前が書けるようになったもの」
母さんにほめられると、わたしは嬉しくて嬉しくて仕方なかった。そして、もっとほめられたいと背伸びした。
「お母さんの名前は? とわ、お母さんのお名前も書いてあげる」
母さんは答えた。
「お母さんはね、『あい』っていう名前なのよ」
その時、わたしは初めて母さんの名前を知ったのかもしれない。それまで、母さんは母さんという名前なのだと思っていた。
「あい?」
「そう、『永遠の愛』のあい」
わたしは嬉しくなって、思わず母さんの首に抱きついた。
〈とわのあい〉という魔法の糸で、わたしと母さんが、わかちがたく結びついているように感じたのだ。
「あい?」
「そうよ、あい」
「どう書くの?」
わたしがたずねると、母さんは今度はわたしの左の手のひらに、「あ」「い」と自分の名前をゆっくりなぞった。「あ」は複雑で難しかったけれど、「い」はすぐに覚えられた。しばらく頭の中でかみ砕いてから、「あ」と「い」を続けて母さんの手のひらに書いてみせる。
「よくできました。とわは、天才」
母さんが、再びわたしをほめてくれた。
ひとつのどうして? が解決すると、すぐに次のどうして? が発生するのが、その頃のわたしの頭の中で起きていた現象だった。わたしは母さんにたずねた。
「あいって、なーに?」
すると、母さんはしばらく考え込んでから、ぽつりと言った。
「愛っていうのは、人やものに対して、報いられなくてもつくしたいと思ったり、自分の手もとにおきたいと思ったりする、温かい感情。慈しむ心。大切に思う心。
国語辞典には、そう書いてあるわ」
けれど、わたしはうまく理解できない。
「いいこと?」
わたしからの問いかけに、けれど母さんは答えなかった。その代わり、わたしをしっかりと胸に抱きよせ、
「とわとお母さんに、永遠の愛があれば、何も怖いことはないわよ」
そう、わたしの耳元でささやいた。
「大好き」
わたしも母さんの背中に両手でひしっとしがみつきながら、言った。
「とわ、お母さん、とわに大好き」
覚えたばかりの、「永遠」という言葉を使ってみたかった。
「お母さんも、とわを、えいえんに愛しているわ」
わたしと母さんが愛をささやき合うのは、決して珍しいことではなかった。わたしたちは、日常的に、お互いへの気持ちを言葉にして確かめ合った。それは、決して恥ずかしい行いではなかった。
それまで、わたしは母さんとべったり、片時も離れず一緒に過ごしていた。わたしたちが住んでいたのは、二階建ての小さな家で、二階にある寝室の上には更に小さな屋根裏部屋があり、一階の台所の下にはささやかな地下室が隠されていた。家の前にあるのが、とわの庭だった。
わたしの暮らしには、母さんの愛があふれている。わたしの食べ物は母さんが毎食作ってくれたし、服は、母さんの古着を仕立て直して、母さんが縫ってくれた。スカートのポケットにはいつだってアイロンのかけられた清潔なハンカチが入っていたし、トイレの場所がすぐにわかるよう、トイレへと続くみちすじに天井から毛糸を吊るしてくれたのも母さんだった。
目が見えなくても、母さんがどこにいるかは、すぐにわかった。母さんには、母さんだけの匂いがあったから。その匂いが、とわの庭に生えている植物の香りに似ていると気づいたのは、ずいぶん後になってからだけど。わたしは、母さんの匂いならすぐにかぎ分けることができる。
オットさんにも、ほんのわずかだけれど匂いがあった。母さんが、オットさんが届けてくれた箱のふたを開けると、いつも、今までそこになかった匂いがする。
それは、葉っぱのような奥深い香りで、うんと鼻に集中しないとわからない。大人になって、ホワイトセージという葉っぱをいぶした匂いをかいだ瞬間、脳裏にオットさんのことが思い出された。けれど、子どものわたしはホワイトセージなんて植物を知る由もなかった。
いや、知る由はあったのかもしれない。母さんが、わたしにたくさんの本を読み聞かせて、世界を広げてくれたから。けれど、ホワイトセージを意識したことはなかった。だから、オットさんの匂いを正確に言葉で表現するのは難しかった。
それは、決してほの暗いイメージの匂いではなく、どちらかというとひなたに近いような匂いだった。わたしにとっては、匂いにもそれ特有の色のような光のようなものがあり、わたしは匂いと色を結びつけてイメージすることが多い。
オットさんは、週に一度、わたしと母さんが暮らす家に生活必需品を届けてくれた。
確かめたことなど一度もないけれど、オットさんは、おそらく男の人だった。母さんは、オットさんに買い物のリストを空き缶に入れておき、それを見たオットさんは次の週の水曜日に届けてくれる。
〈水曜日のオットさん〉
わたしは彼を、心の中でそう呼んでいた。
オットさんが誰なのか、母さんは教えてくれない。オットさんと母さんが言葉を交わすことはなかったし、オットさんが家に上がることもない。もしかすると、わたしの目が見えないように、オットさんも体のどこかに機能しない部分があったのかもしれない。
オットさんは、水曜日のだいたい夕方頃にやって来て、家の勝手口に荷物を置くと、勝手口のドアを、コン、コン、コン、と三回鳴らす。それが、オットさんが来た合図で、その音を聞いてしばらくしてから、母さんは外に置かれていた荷物を家の中に取り込んだ。食材もトイレットペーパーも絆創膏も風邪薬も、石けんも歯ブラシも、すべてオットさんが届けてくれた。
母さんが家の中に荷物を取り込むと、たいてい電話が鳴った。呼び出し音が続くと、やがて自動で留守番電話のメッセージに切り替わり、そこに奇妙な音が吹き込まれる。わたしには、うまく聞き取れない。それはまるで、冬の始まりの頃に吹く、冷たい北風のような音だった。
ただ、母さんにはその言葉が聞き取れるらしく、その音がすると、オットさんね、と毎回つぶやいた。
電話は、オットさんからかかってくる以外は鳴らなかった。わたしはずっと、電話というのは本来そういうもので、ある特定の人物と一対一でしかつながらないものだと思っていた。
わたしには、時間の流れという感覚があまりよく理解できないのだが、強いていえば、オットさんは時計の短い針だった。オットさんが来ることで、わたしはその日が水曜日であると理解し、一週間という時間の流れを感じることができた。
オットさんが短い方の針なら、長い方の針はクロウタドリだった。
そう、黒歌鳥合唱団!
黒歌鳥合唱団のコーラスが、わたしに、朝を知らせてくれるのだ。
目の見えないわたしにとって、光の加減で朝が来たり夜になったりすることを知るのは難しい。けれどクロウタドリが、わたしの目の代わりに朝の気配を感じて歌ってくれる。
クロウタドリが、わたしの時計。わたしは、クロウタドリの歌を聞くことで、朝の到来を知ることができる。
とわの庭は、黒歌鳥合唱団にとって絶好のステージだった。クロウタドリたちは競い合うように、とわの庭で美しい歌声を披露した。機嫌がいいと、クロウタドリは夕暮れ時にもやってきて歌をうたうので、わたしは朝だけでなく、夜の訪れも知ることができる。
問題は曇りや雨の日で、そういう日は黒歌鳥合唱団の活動もお休みになるらしく、その美しい歌声を聞くことができない。クロウタドリは、わたしに朝夕の訪れだけでなく、その日の空の様子も教えてくれる、頼りがいのある存在だった。
クロウタドリが歌わない朝は、母さんがレコードをかけて、わたしに朝を知らせてくれた。レコードから流れてくるのはたいてい穏やかなピアノの曲で、母さんはピアノの音が好きだった。
朝からピアノが流れる日、母さんはいつも以上に機嫌がよかった。
わたしに言葉を教えてくれたのは、母さんだ。
母さんはある日、わたしに筆箱を買ってくれた。中を開けると、そこには消しゴムと、先の尖った鉛筆が数本入っていた。
「今日から、お勉強をしましょう」
母さんは張り切って言ったが、わたしはそれをどこか上の空で聞いていた。消しゴムから、オレンジみたいなレモンみたいな、おいしそうな香りがしたからだ。わたしは消しゴムを鼻に近づけて、匂いをかいでばかりいた。
とりわけ、わたしを夢中にしたのは言葉のお勉強だった。
ある日、母さんはわたしの手のひらの真ん中に、綿のかたまりをのせて言った。
「とわ、これをゆっくりと、優しく握ってみて」
わたしは言われた通りに、少しずつ指先に力を入れて、そのかたまりを手のひらで包みこんだ。
「ふわふわ。ね? とわ、わかる? これが、ふわふわ」
母さんは、言った。
「ふわ、ふわ」
わたしは確かめるようにゆっくりと、母さんの言葉を繰り返した。
「そう、ふわふわ。だって、ふわふわ、しているでしょう」
そう言われると、確かに手のひらの中にあるものは、ふわふわしている。それ以外の言葉は似合わない気がした。
見渡すと、「ふわふわ」は身の回りのいろんなところにあった。たとえば、母さんのふくらはぎ。たとえば、トーストする前の食パン。たとえば、わたしの唇。
「わくわく」も、すぐに理解できた。わくわくは、常にわたしの内側にある期待の気持ちだった。母さんがそばに来るとわくわくしたし、夜、眠りにつく前、本を読んでもらうのもわくわくした。大好きなオムライスを食べる時も、わくわくした。
「ぬめぬめ」も、簡単だった。母さんが、わたしの手にナメコという名前のキノコをのせて、触らせてくれたから。母さんは「ぬめぬめ」や「ぬるぬる」があまり得意ではないらしく、字面までぬめぬめしていると忌々しげに言っていたけれど、わたしは、「ぬめぬめ」も「ぬるぬる」も結構好きだった。
「すべすべ」もすぐにわかった。母さんが、自分の太ももの内側にわたしの手を導いて、そこを撫でさせてくれたからだ。
「すべすべ」
わたしが言うと、母さんも同じように繰り返した。
わたしは、自分の頬っぺたを母さんの太ももに当てて、すべすべ同士を隣り合わせた。
「すべすべ」は、とても気持ちのよい言葉だった。
逆に難しかったのは、「きらきら」や「ぴかぴか」、「もくもく」で、すぐには理解できなかった。
わたしはいまだに、「てくてく」がよくわからないし、自分の思っている「てくてく」が、果たしてその他大勢の人たちが使っている「てくてく」と同じ姿形をしているか、よくわからない。だからわたしは、「てくてく」を使う時、おなかに穴があいたような覚束ない気持ちになる。
それから、色についての表現を理解するのも難しかった。
赤と言われても、赤とオレンジがどう違うのかわからない。青も、黄色も、紫も、わたしにははじめ、宇宙人の言葉を聞くみたいで途方に暮れた。けれど、母さんがていねいに教えてくれたから、なんとなくわかるようになった。
わたしは、理由はよくわからないけれど、「にびいろ」という言葉が好きだ。鈍色だけは、最初からわかるような気がした。にびいろという言葉を最初に教えてくれたのも、母さんだった。母さんは、昔の人の喪服の色だと教えてくれたのだ。喪服って? とわたしが更に質問すると、母さんはしばらく間を置いてから、愛する人や親しい人が遠くへ行って、もう二度と会えない悲しみに包まれた時に着る服よ、と言ったっけ。
それなら、わたしはまだ知らないはずだった。だって、愛する母さんはいつもわたしのそばにいるもの。けれどわたしは、「にびいろ」という言葉に出会う前から、鈍色を知っていたような気がする。鈍色とわたしは、もしかすると前世で親友だったのかもしれない。
読書家の母さんが、わたしにもよく本を読んできかせてくれたから、わたしは家にいながらにしてたくさんの旅をすることができた。クロウタドリという名の、体の左右に翼の生えた空を飛ぶ生き物がいることを教えてくれたのも、外国で書かれた物語だった。
旅に出るのはたいてい寝る前の時間だったけど、たまに、陽だまりの中で旅をすることもあった。日本が舞台のおはなしも、外国が舞台のおはなしも、架空の国が舞台のおはなしも、いろいろあった。今のおはなしも、大昔のおはなしも、未来の宇宙人が出てくるおはなしもあった。
本もまた、オットさんの手によって、毎週水曜日に届けられた。