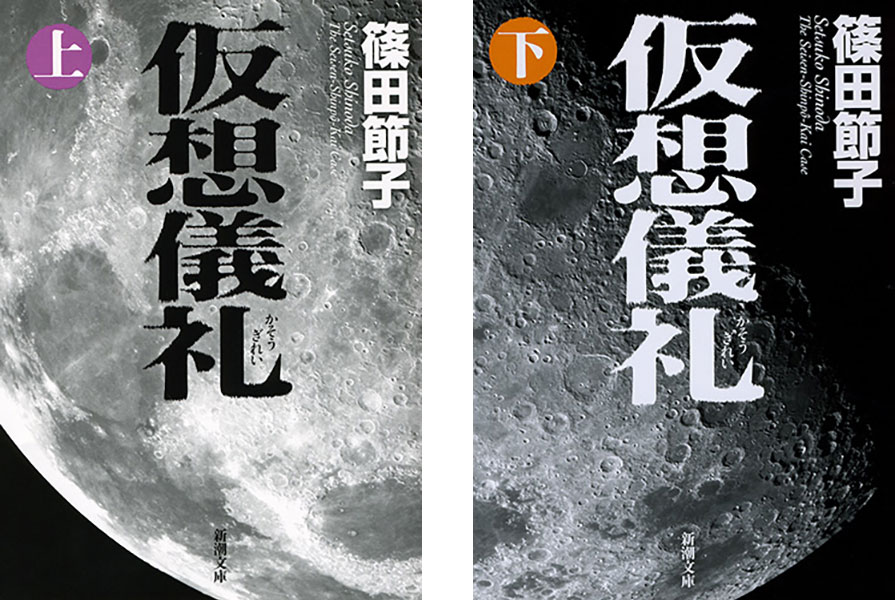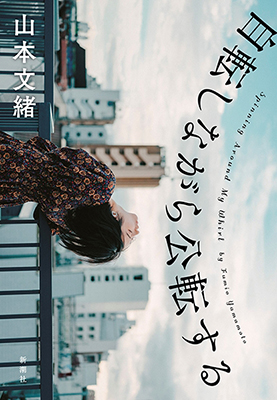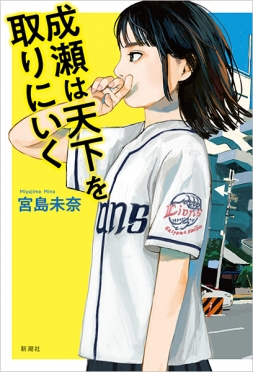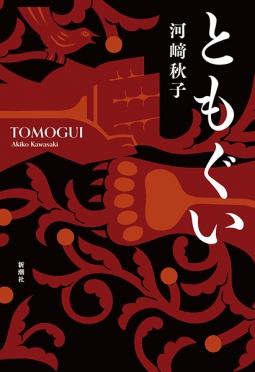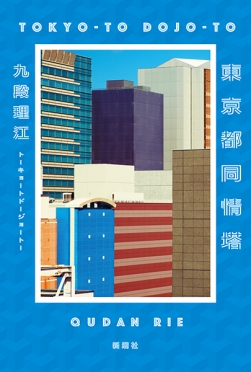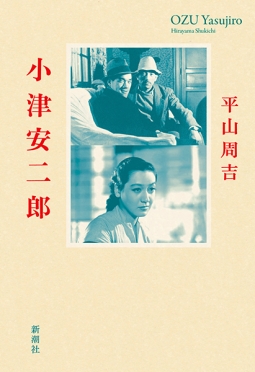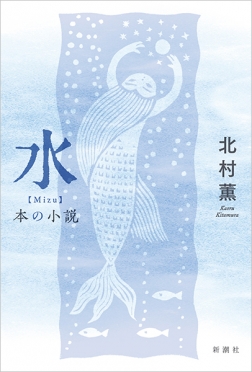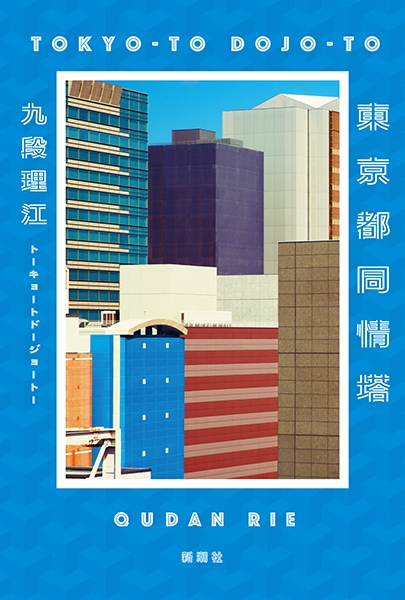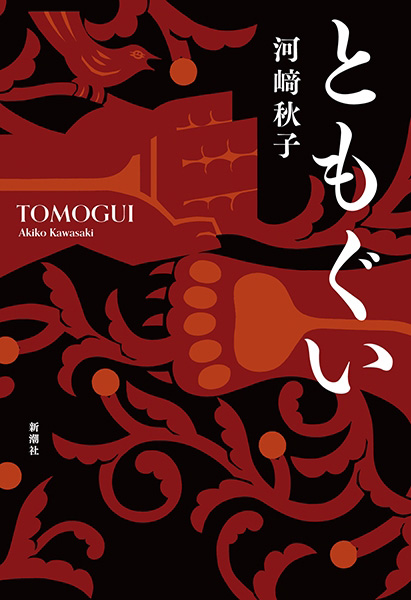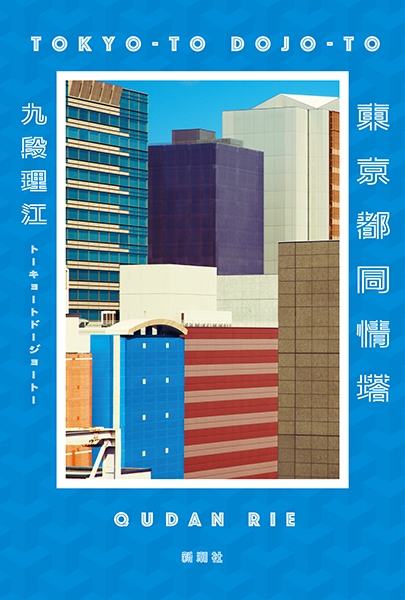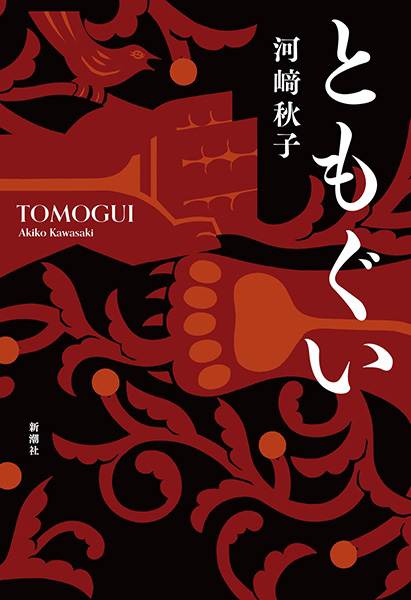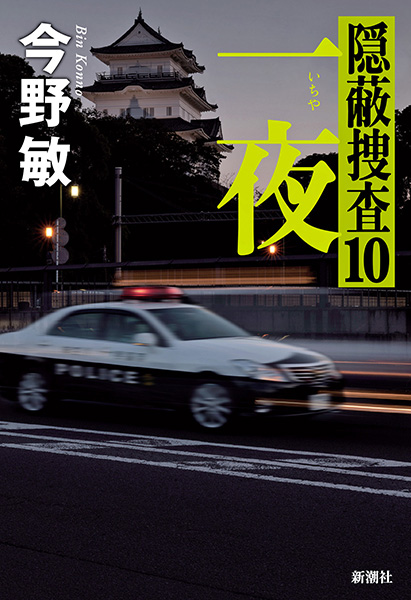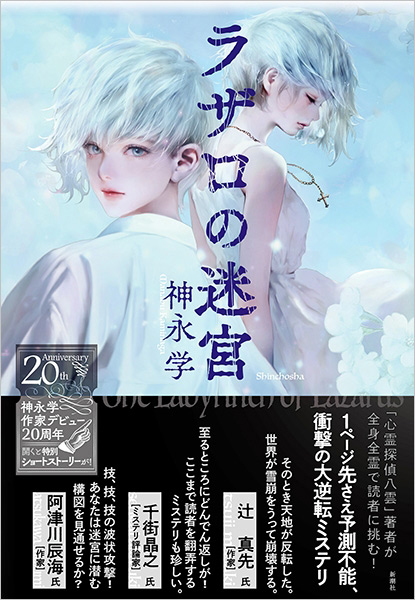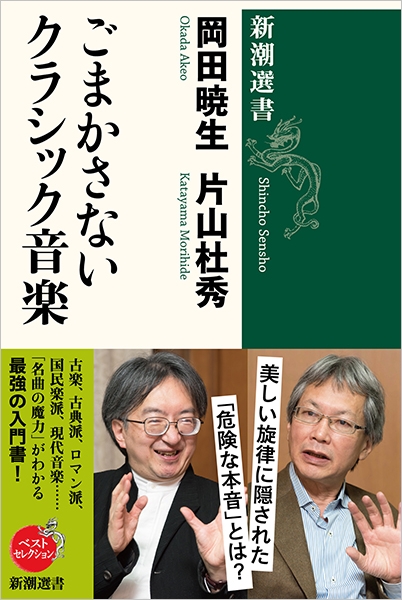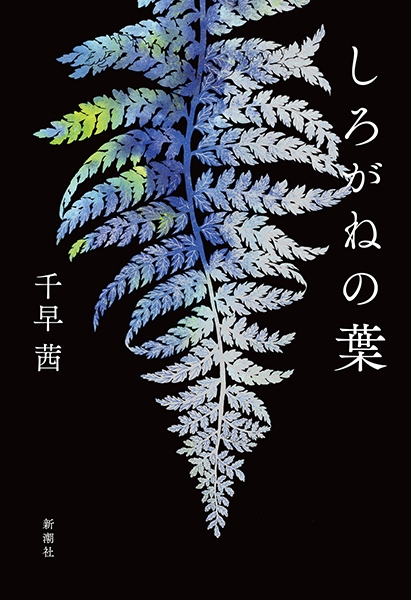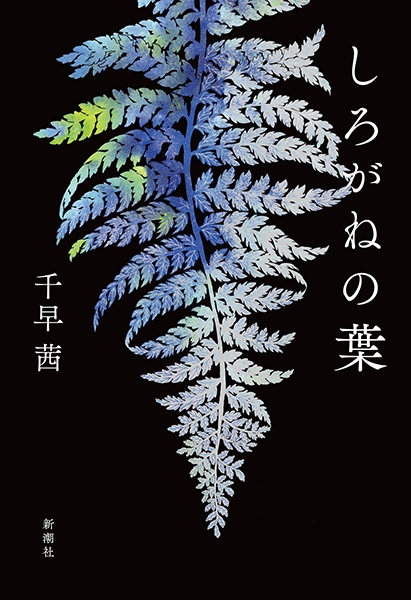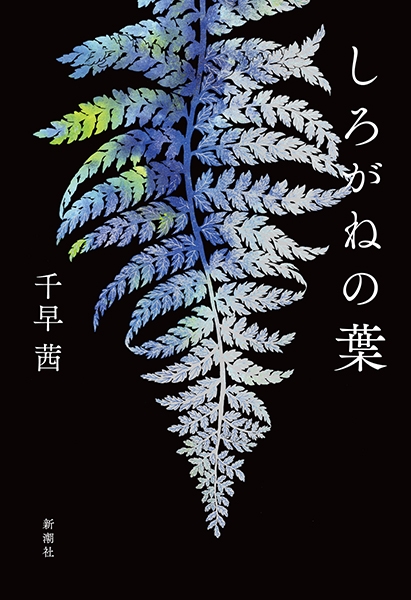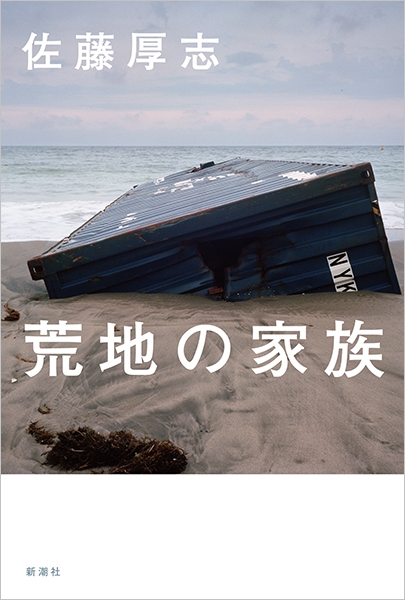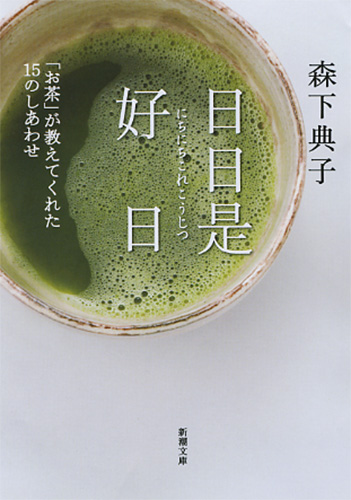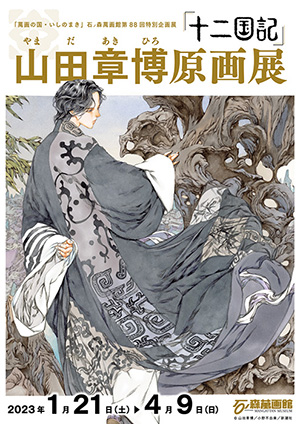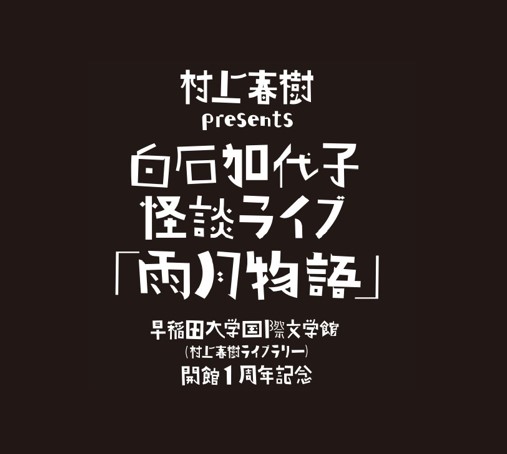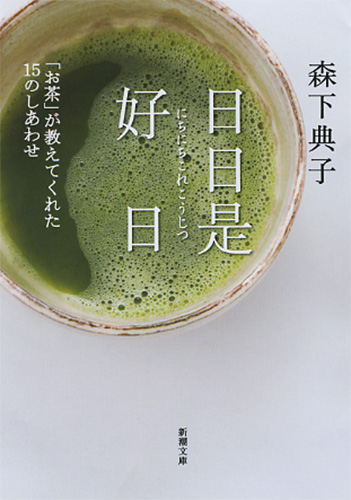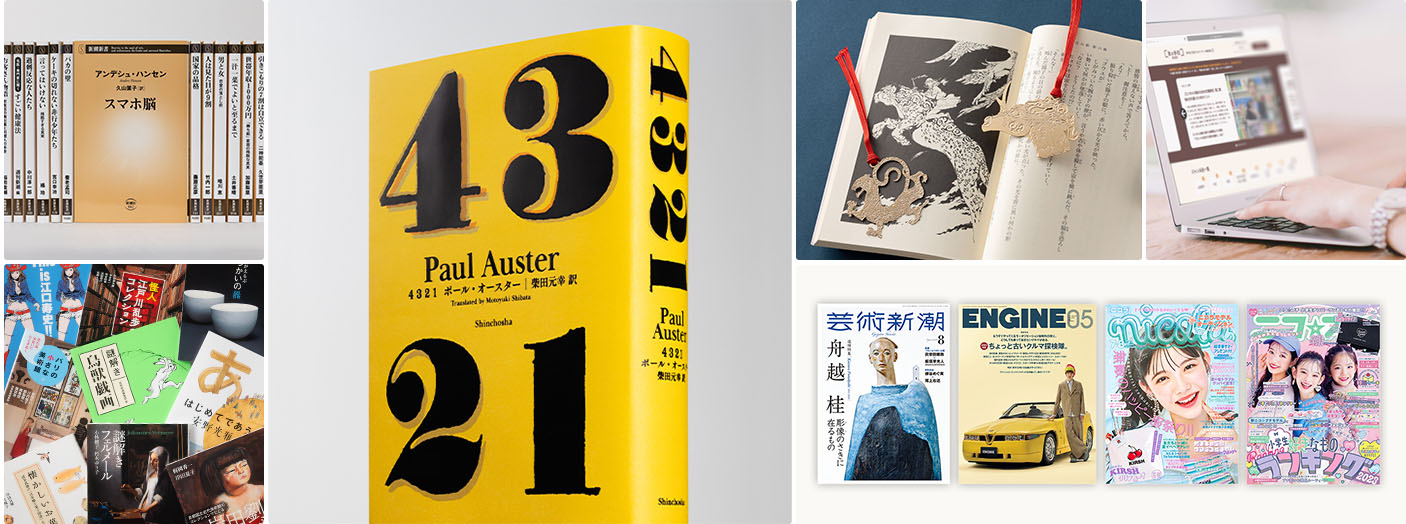
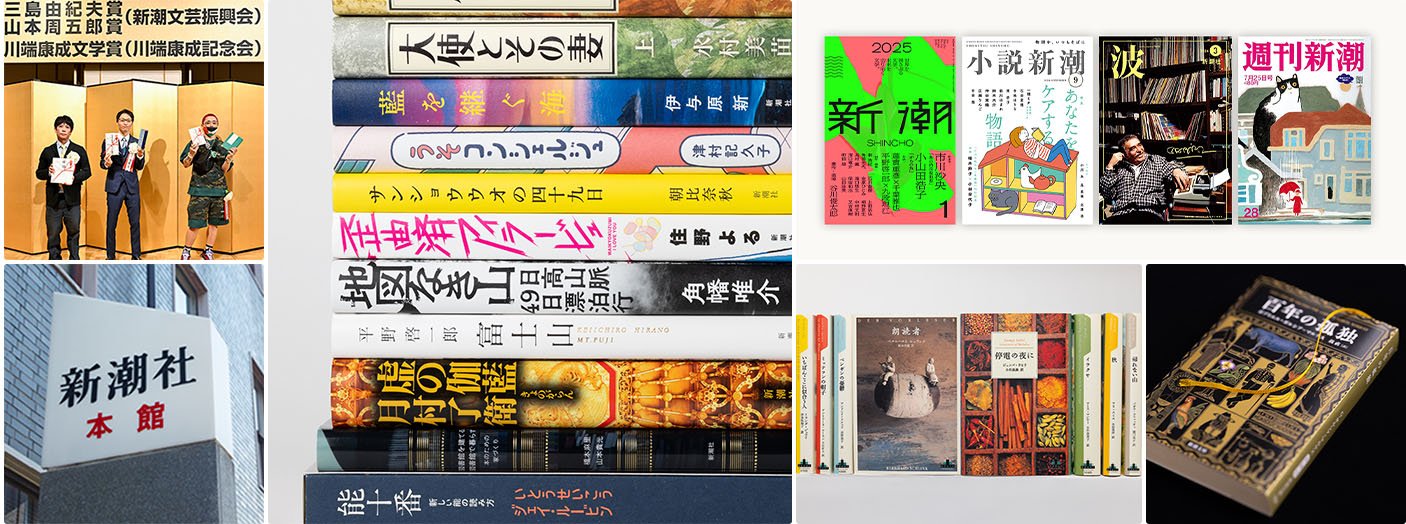
プレスリリース

新潮社の事業
新潮社の新刊
映画・テレビ・舞台化作品
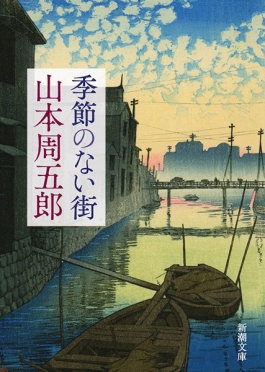
| 放送局 | テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 |
|---|---|
| 放映中 | 毎週金曜24:42~25:13 ※最終回(6月7日)は5分拡大(24:42~25:18) |
| 企画・監督・脚本 | 宮藤官九郎 |
| 出演 | 池松壮亮、仲野太賀、渡辺⼤知、三浦透⼦、濱⽥岳、増⼦直純、荒川良々、MEGUMI、⾼橋メアリージュン、皆川猿時、⼜吉直樹、前⽥敦⼦、塚地武雅、YOUNG DAIS、⼤沢⼀菜、奥野瑛太、佐津川愛美、小田茜、坂井真紀、⽚桐はいり、広岡由⾥⼦、LiLiCo、藤井隆、鶴⾒⾠吾、ベンガル、岩松了 ほか |
| 関連サイト | https://www.tv-tokyo.co.jp/kisetsu/ |
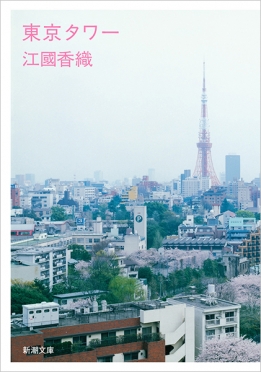
| 放送局 | テレビ朝日 |
|---|---|
| 放映中 | 毎週土曜23:00~ |
| 脚本 | 大北はるか |
| 監督 | 久万真路 ほか |
| 出演 | 永瀬廉、板谷由夏、松田元太、MEGUMI ほか |
| 関連サイト | https://www.tv-asahi.co.jp/tokyotower/ |
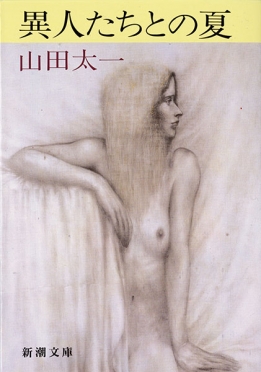
| 配給 | ディズニー |
|---|---|
| 監督 | アンドリュー・ヘイ |
| 出演 | アンドリュー・スコット、ポール・メスカル、ジェイミー・ベル、クレア・フォイ ほか |
| 関連サイト | https://www.searchlightpictures.jp/movies/allofusstrangers |

| 配給 | 東京テアトル、ヨアケ |
|---|---|
| 公開 | 2024年5月17日(金) |
| 監督・脚本 | 大森立嗣 |
| 出演 | 福士蒼汰、松本まりか、福地桃子、近藤芳正、平田満、根岸季衣、菅原大吉、土屋希乃、北香那、大後寿々花、川面千晶、呉城久美、穗志もえか、奥野瑛太、吉岡睦雄、信太昌之、鈴木晋介、長尾卓磨、伊藤佳範、岡本智札、泉拓磨、荒卷全紀、財前直見、三田佳子、浅野忠信 ほか |
| 関連サイト | https://thewomeninthelakes.jp/ |




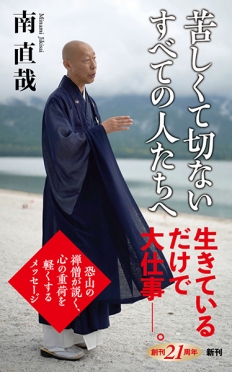
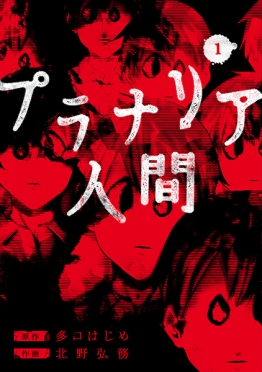



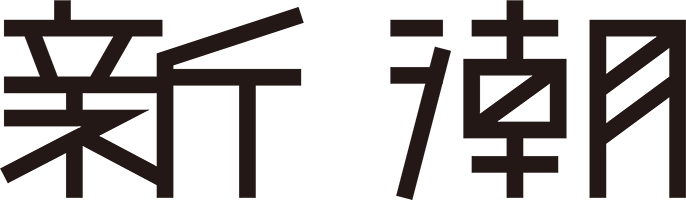















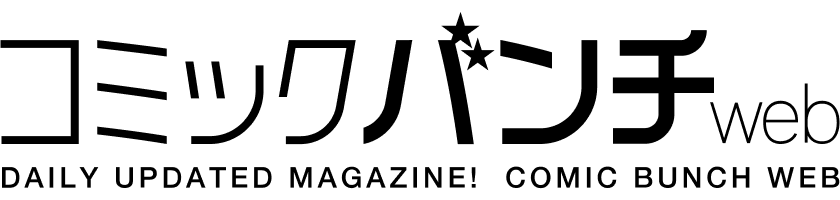
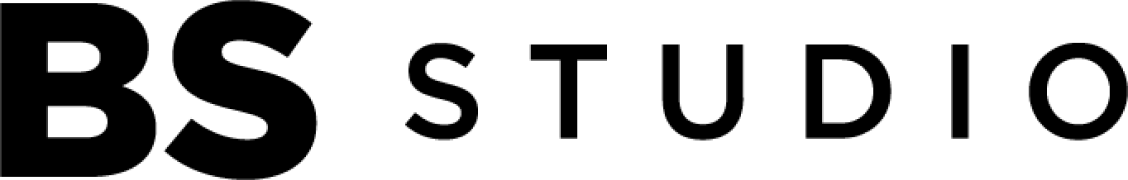






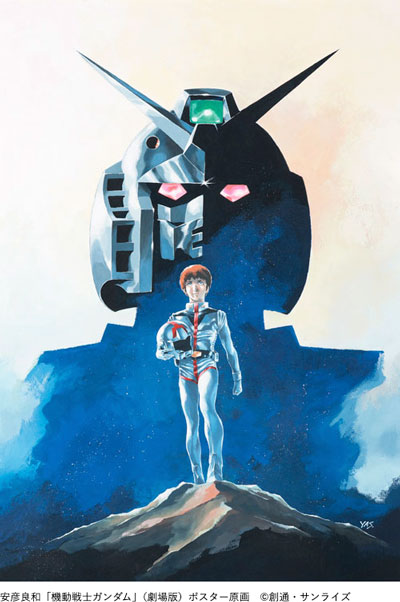




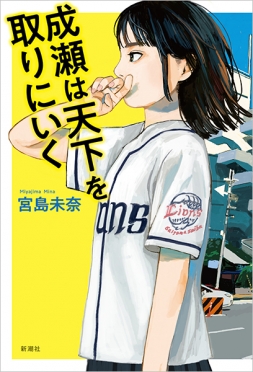
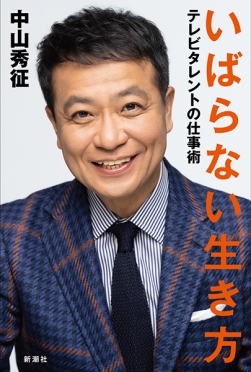
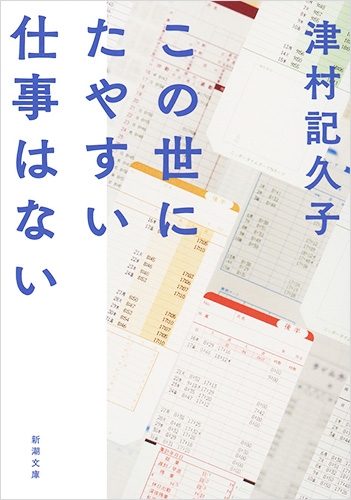
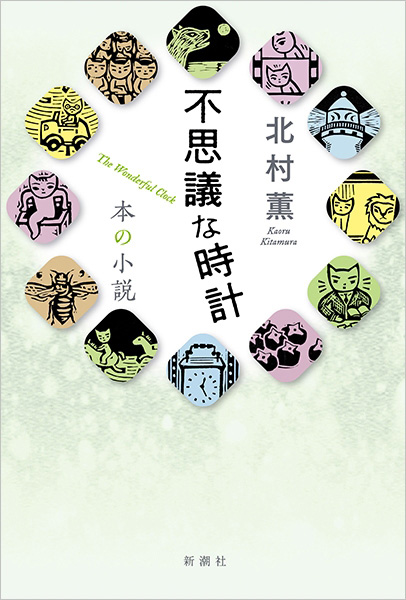
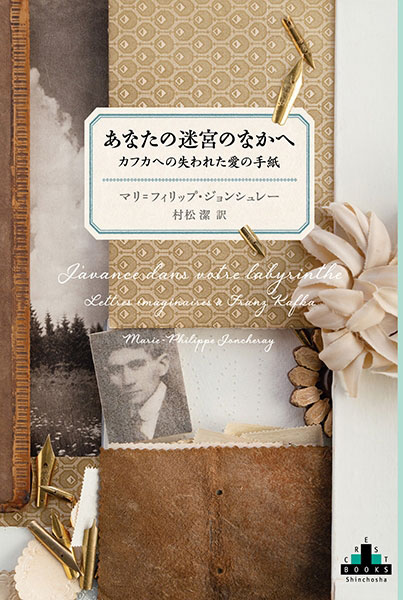

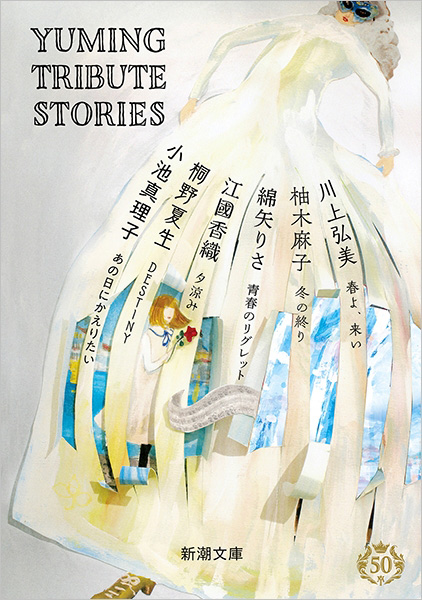
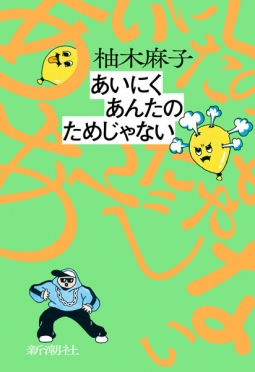
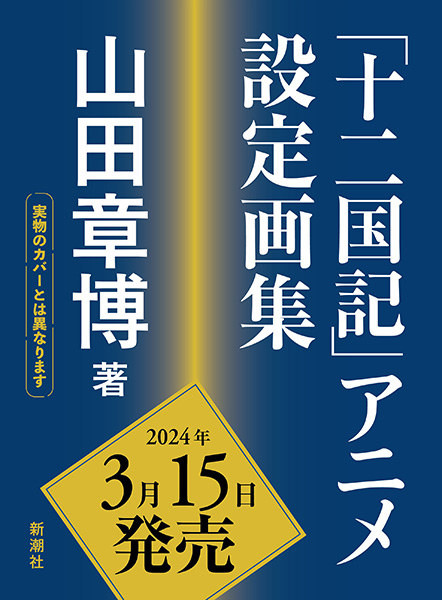
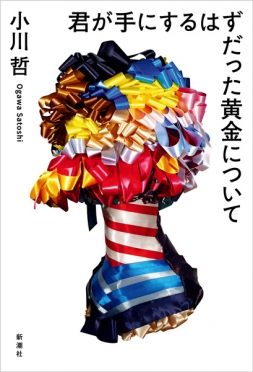
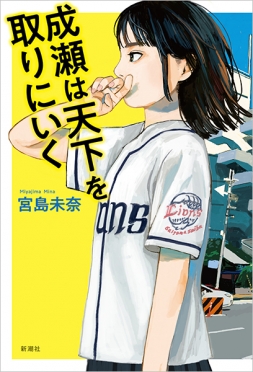
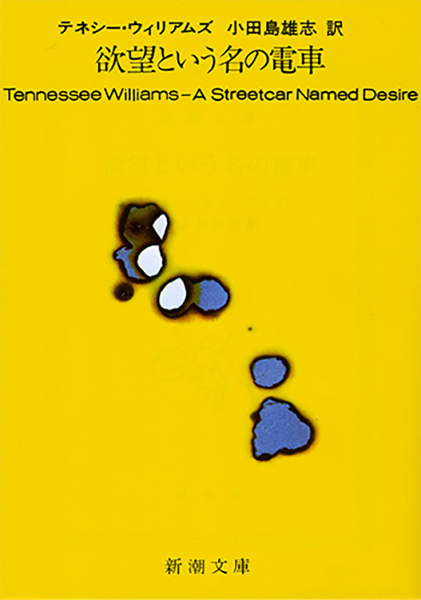
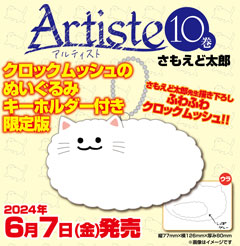
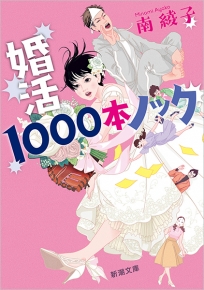
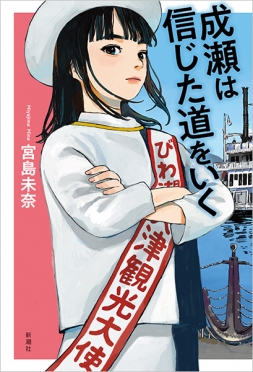
![[新潮文庫]<br />
第11回 中高生のための<br />
ワタシの一行大賞](/images_v2/news/3108.png)