 編集長から 「新潮」8月号
編集長から 「新潮」8月号
 驚異の新人の投稿を巻頭一挙掲載
驚異の新人の投稿を巻頭一挙掲載

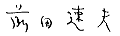
 京大法学部在学中の学生の投稿作品を巻頭一挙掲載し
京大法学部在学中の学生の投稿作品を巻頭一挙掲載し
 ました。平野啓一郎君の「日触」二五〇枚。もちろん、
ました。平野啓一郎君の「日触」二五〇枚。もちろん、
 異例中の異例ですが、ルネッサンス前夜のフランスの寒
異例中の異例ですが、ルネッサンス前夜のフランスの寒
 村を舞台に、異端と聖性の問題を追求した本作は、その
村を舞台に、異端と聖性の問題を追求した本作は、その
 高度な内容と荘重な文体で、三島由紀夫の再来かと、小
高度な内容と荘重な文体で、三島由紀夫の再来かと、小
 生を驚喜させました。弱冠23歳、ポスト・モダン総崩れ
生を驚喜させました。弱冠23歳、ポスト・モダン総崩れ
 の中で、出るべくして出た才能に、ご声援を。
の中で、出るべくして出た才能に、ご声援を。
 これと併せての特集が、「21世紀への新人たち」。柳
これと併せての特集が、「21世紀への新人たち」。柳
 美里、町田康、阿部和重、角田光代、目取真俊、見沢知
美里、町田康、阿部和重、角田光代、目取真俊、見沢知
 廉、辻仁成と、最近登場して、めきめき力をつけてきた
廉、辻仁成と、最近登場して、めきめき力をつけてきた
 注目の作家七氏を、同世代の若手評論家が、長所と課題
注目の作家七氏を、同世代の若手評論家が、長所と課題
 の両面から論じます。批評家・文芸記者26人によるアン
の両面から論じます。批評家・文芸記者26人によるアン
 ートは「いま最も期待する新鋭作家」。七氏以外で複数
ートは「いま最も期待する新鋭作家」。七氏以外で複数
 票を得たのは、藤沢周、車谷長吉、笙野頼子、三浦俊彦、
票を得たのは、藤沢周、車谷長吉、笙野頼子、三浦俊彦、
 松浦寿輝、藤野千夜、多和田葉子の諸氏でした。
松浦寿輝、藤野千夜、多和田葉子の諸氏でした。
 その他、小説は小川国夫氏「プロヴァンスの坑夫」、
その他、小説は小川国夫氏「プロヴァンスの坑夫」、
 山田詠美氏「瞳の致死量」の二短篇が、ヴェテランの冴
山田詠美氏「瞳の致死量」の二短篇が、ヴェテランの冴
 えを見せ、高樹のぶ子氏「燃える塔」一〇〇枚は、「眠
えを見せ、高樹のぶ子氏「燃える塔」一〇〇枚は、「眠
 れる月」「海からの客」「鳥たちの島」と続いた連作
れる月」「海からの客」「鳥たちの島」と続いた連作
 「FURUSATO」を、鮮やかに締め括ります。
「FURUSATO」を、鮮やかに締め括ります。
 小田実氏の長編評論は、大震災から三年半、復興の掛
小田実氏の長編評論は、大震災から三年半、復興の掛
 け声とは裏腹に荒廃が深刻化する西宮の市街を眼下に、
け声とは裏腹に荒廃が深刻化する西宮の市街を眼下に、
 ギリシアの哲人ロンギノスに思いを馳せ、「動かす人間」
ギリシアの哲人ロンギノスに思いを馳せ、「動かす人間」
 にも「動かされる人間」にもならずに、「文」で「全体」
にも「動かされる人間」にもならずに、「文」で「全体」
 に対峙した「戦後文学」の作家たちへの共感を語ります。
に対峙した「戦後文学」の作家たちへの共感を語ります。
 なお、吉村昭氏会心の歴史小説「生麦事件」は、今号
なお、吉村昭氏会心の歴史小説「生麦事件」は、今号
 で連載が完結しました。単行本は九月刊行の予定です。
で連載が完結しました。単行本は九月刊行の予定です。

|