 編集長から 「新潮」9月号
編集長から 「新潮」9月号
 夏の炎
夏の炎

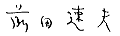
 夏といえば怪談がつきものだが……と始まるのは、増
夏といえば怪談がつきものだが……と始まるのは、増
 田みず子氏「火夜」四八〇枚。盛夏の読書にふさわしい、
田みず子氏「火夜」四八〇枚。盛夏の読書にふさわしい、
 怖くて胸さわぐ、小説の醍醐味に溢れた逸品です。葛飾
怖くて胸さわぐ、小説の醍醐味に溢れた逸品です。葛飾
 の宿場町の顔役だった一族の六代にわたる血の秘密──
の宿場町の顔役だった一族の六代にわたる血の秘密──
 ─幕末の皆殺し伝説から、近親者に夥しい変死・劇死ま
─幕末の皆殺し伝説から、近親者に夥しい変死・劇死ま
 で、炎に焼かれる「孤細胞」たちの「百年の孤独」を、
で、炎に焼かれる「孤細胞」たちの「百年の孤独」を、
 その末裔である作者が透徹した眼で捉えた本篇は、従来
その末裔である作者が透徹した眼で捉えた本篇は、従来
 のどちらかと言えば繊細で内向的な増田作品から、一転
のどちらかと言えば繊細で内向的な増田作品から、一転
 して、スケールの大きな劇的な文学へと、見事に脱皮し
して、スケールの大きな劇的な文学へと、見事に脱皮し
 ました。
ました。
 辻征夫氏「黒い塀」は、川端賞の最終候補作に残って
辻征夫氏「黒い塀」は、川端賞の最終候補作に残って
 評価の高かった「遠ざかる島」に続く小説第二作。回顧
評価の高かった「遠ざかる島」に続く小説第二作。回顧
 を現在進行形で表現する工夫が光ります。筒井康隆氏
を現在進行形で表現する工夫が光ります。筒井康隆氏
 「作中の死」、司修氏「絵具」も、作者の個性鮮やかな
「作中の死」、司修氏「絵具」も、作者の個性鮮やかな
 佳篇。
佳篇。
 河合隼雄氏と松岡和子氏の対談「夏の夜の夢」は、ご
河合隼雄氏と松岡和子氏の対談「夏の夜の夢」は、ご
 存じシェイクスピアの劇作(ミッド・サマーは真夏では
存じシェイクスピアの劇作(ミッド・サマーは真夏では
 なく、夏至を指すとのことです)を入口に、夢と無意識
なく、夏至を指すとのことです)を入口に、夢と無意識
 の奥深さを語ります。
の奥深さを語ります。
 評論は中沢新一氏「GODZILLA対ゴジラ」と建畠皙氏
評論は中沢新一氏「GODZILLA対ゴジラ」と建畠皙氏
 「耳なし芳一異聞」。前者は現在上陸 (上映) 中のアメ
「耳なし芳一異聞」。前者は現在上陸 (上映) 中のアメ
 リカ映画に見るそれと元祖ゴジラを比較対照して、西欧
リカ映画に見るそれと元祖ゴジラを比較対照して、西欧
 の原理と日本の神話的思考に説きおよび、後者は般若心
の原理と日本の神話的思考に説きおよび、後者は般若心
 経の書かれなかった両耳に対して、文字が復讐するのは
経の書かれなかった両耳に対して、文字が復讐するのは
 なぜか蘊蓄を傾けます。文芸時評は、今号より山口昌男
なぜか蘊蓄を傾けます。文芸時評は、今号より山口昌男
 氏が登場。竹西寛子氏の連作随想「山河との日々」は最
氏が登場。竹西寛子氏の連作随想「山河との日々」は最
 終回で、故郷広島の穏やかに暮れてゆく空に、半世紀以
終回で、故郷広島の穏やかに暮れてゆく空に、半世紀以
 上前の「夜半になってもいっこうに暮れない空」を重ね
上前の「夜半になってもいっこうに暮れない空」を重ね
 て、静かに幕が下りました。
て、静かに幕が下りました。

|