 編集長から 「新潮」10月号
編集長から 「新潮」10月号
 愛の渇き
愛の渇き

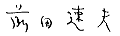
 性が氾濫する今日、愛はどのようなかたちで生き延び
性が氾濫する今日、愛はどのようなかたちで生き延び
 ているのでしょうか。今月号の小説四篇は、はからずも
ているのでしょうか。今月号の小説四篇は、はからずも
 現代人に特有の、韜悔し、屈折した愛を、浮き彫りにし
現代人に特有の、韜悔し、屈折した愛を、浮き彫りにし
 ています。
ています。
 一周忌を前に完成稿が発見された中村真一郎「城北綺
一周忌を前に完成稿が発見された中村真一郎「城北綺
 譚」一四六枚は、題名からお分かりのように、永井荷風
譚」一四六枚は、題名からお分かりのように、永井荷風
 「ぼく(「さんずい」に「墨」)東綺譚」の向こうをは
「ぼく(「さんずい」に「墨」)東綺譚」の向こうをは
 った問題作。ここでは謹厳な実業家が生涯隠し通した、
った問題作。ここでは謹厳な実業家が生涯隠し通した、
 人妻との禁じられた愛が赤裸に語られ、林京子氏「思う
人妻との禁じられた愛が赤裸に語られ、林京子氏「思う
 ゆえに」では、壮年期に離婚した夫婦が老年になって再
ゆえに」では、壮年期に離婚した夫婦が老年になって再
 開した奇妙な同棲生活に、岡田睦氏「”愛”の交換ノオ
開した奇妙な同棲生活に、岡田睦氏「”愛”の交換ノオ
 ト」では、妻に逃げられ極貧の一人暮らしを余儀無くさ
ト」では、妻に逃げられ極貧の一人暮らしを余儀無くさ
 れた男とホームヘルパーの女性との淡く危うい交情に、
れた男とホームヘルパーの女性との淡く危うい交情に、
 また村田喜代子氏「虚空」では、愛人への真情を表すた
また村田喜代子氏「虚空」では、愛人への真情を表すた
 めに中小企業の経営者がとった最後の行動に、愛の渇き
めに中小企業の経営者がとった最後の行動に、愛の渇き
 が逆説的に表現されました。
が逆説的に表現されました。
 長堂英吉氏「黄色軍艦(ちいるぐんかん)」二〇〇枚
長堂英吉氏「黄色軍艦(ちいるぐんかん)」二〇〇枚
 は、日清戦争中の沖縄秘話。清国艦隊の来攻を待って、
は、日清戦争中の沖縄秘話。清国艦隊の来攻を待って、
 日本の支配から脱しようとした人々がいたことを小説化
日本の支配から脱しようとした人々がいたことを小説化
 して、琉球処分の虚偽を衝きます。ドナルド・キーン氏
して、琉球処分の虚偽を衝きます。ドナルド・キーン氏
 と小田実氏の対談は「崇高にしておぞましき戦争」。日
と小田実氏の対談は「崇高にしておぞましき戦争」。日
 本軍と敵対したキーン氏の「玉砕」評が印象的です。
本軍と敵対したキーン氏の「玉砕」評が印象的です。
 萩原朔美氏「『天井桟敷』の人々」は、三十年前同じ
萩原朔美氏「『天井桟敷』の人々」は、三十年前同じ
 寺山修司主宰の劇団にいた仲間の奇人変人達の意外な後
寺山修司主宰の劇団にいた仲間の奇人変人達の意外な後
 半生を追跡した好読物。待望の河合隼雄氏の新連載は
半生を追跡した好読物。待望の河合隼雄氏の新連載は
 「猫だましい」(「だましい」は、「たましい」と「だ
「猫だましい」(「だましい」は、「たましい」と「だ
 まし」の掛け詞)。毎回、猫を主人公とする古今の名作
まし」の掛け詞)。毎回、猫を主人公とする古今の名作
 を取り上げながら、猫を通して人間のたましいの働きを
を取り上げながら、猫を通して人間のたましいの働きを
 考える筆者の独壇場。第一回は「なぜ猫なのか」。ご期
考える筆者の独壇場。第一回は「なぜ猫なのか」。ご期
 待ください。
待ください。

|