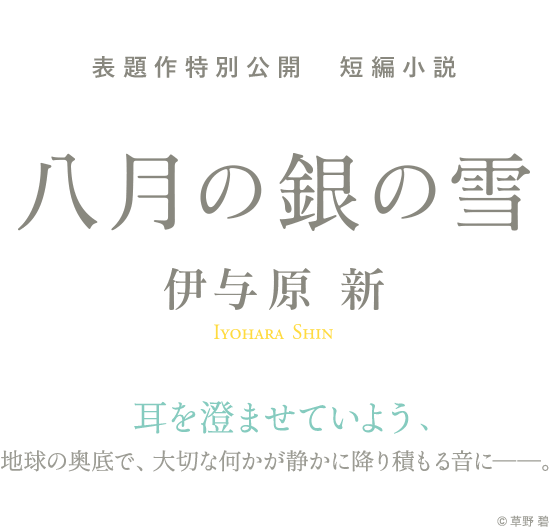本作品の全部または一部を、無断で複製(コピー)、転載、改ざん、公衆送信(ホームページなどに掲載することを含む)することを禁じます。
〔 page 1/4 〕
抜け出せる気がしなかった。
何もかもが不快なこの季節から、永久に。
日付もそろそろ変わるというのに、外の蒸し暑さは和らぐ気配すらない。
面接でぼろぼろにされたあとなのに、帰る途中研究室の先輩に呼び出された。今までかかってやっていたのは、実験の手伝いだ。
八月に入ってからというもの、ずっとこんな日々が続いている。僕が絶望の淵で喘いでいることなど、誰も気に留めない。そこへとどめをさすように、ひたすら鬱陶しい東京の夏が首を締め上げてくる。
環七通りに出入りする車が、この時間もひっきりなしに通る。トラックのクラクションに驚いたのか、街灯からアブラゼミが飛び立った。大学の正門を出て三分も歩いていないが、もうワイシャツが背中にはりついている。
上のボタンをはずそうとして、研究室でもネクタイを締めたままだったことに気がついた。舌打ちして乱暴にほどき、ねじれたまま合皮のかばんに突っ込む。だめだ。疲れで頭が回っていない。
西武新宿線の踏切をわたると、商店と住宅が並ぶ細い通りが続く。店舗のシャッターはどこも当然下りているが、駅からやってきた帰宅途中の人々がまだまばらに歩いていた。
クリーニング店の角で十字路を左に入ると、すぐにコンビニがある。ほとんど無意識のまま、そのガラス扉を押し開けていた。買いたいものがあったわけではない。アパートへ帰る前に立ち寄るのが習慣になっているだけだ。
都内にしてはゆったりした店舗で、入ってすぐ左側に五席ほどのイートインスペースがある。今座っているのは一人だけ。窓際に置かれた長いテーブルの一番奥に、若い男がこちらに背中を向けてスマホをいじっている。
商品棚のほうにも客の姿はほとんど見えない。ぼんやり店の奥へと進み、飲料コーナーに近づいていく。
その横の奥まった空間に、ふと目が留まった。トイレのドアの脇に、折りたたんだ段ボールの空き箱が数枚重ねて立てかけられている。いつもの癖で、その紙質を目だけで確かめるが、やはりろくなものはない。コンビニで丈夫な段ボールが手に入ることは、稀なのだ。
そのまま冷蔵ケースの前まで行き、扉に手をかけようとしたとき、レジのほうで誰かのいらついた声が響いた。
「違う違う、その横。ロングのほうだって。日本語わかんねーの?」
見れば、小太りの中年男がレジ奥に並ぶタバコを指差し、口を尖らせている。細い腕を伸ばしてその銘柄をさがしているのは、あの外国人アルバイトの女だ。
またあいつか。冷たい視線を向ける。相変わらず、使えないやつ。
アジア系で、年齢はたぶん二十代。黒い髪をうしろで束ね、化粧っ気はない。小柄で痩せているせいか、ストライプの制服がやけにだぶついて見える。
タバコのバーコードを読み取る彼女を横目に、冷蔵ケースの扉を開く。何気なくエナジードリンクを手に取ったとき、思い出した。店内の冷房のおかげで、脳が働き出したらしい。
明日、粗大ごみの収集を申し込んであったのだ。この区では、事前にごみ処理券のシールを購入し、廃棄する物品に貼って住居の前に出しておくことになっている。捨てるのは壊れたカラーボックスで、料金は四百円だ。
ドリンクの缶を棚に戻し、レジへと向かった。あいにく他に店員の姿はない。仕方なく彼女の前に立ち、ぶっきらぼうに告げる。
「粗大ごみのごみ処理券。二百円のを二枚」
「粗大ごみの……」細い眉を寄せて訊き返してくる。「何ですか?」
やっぱりだ。マジで面倒くさい。こんなやつに一人で店を任せるな。
僕は短く息をつき、さっきと同じ台詞を繰り返した。彼女は神妙な顔で小さく「ごみ処理券」と復唱すると、小走りでバックヤードに消える。
そこで誰かに教わったのか、戻ってくるなりカウンターの下の引き出しを開けた。中をあさって券をさがし始めるが、なかなか見つからない。いらいらしながら、その胸の名札にあらためて目をやる。片仮名で〈グエン〉とある。そう、そんな名前だった。
彼女がいつからここで働いているのか、はっきりしたことはもちろん知らない。僕がその存在を認識したのは、先月の中頃。そのとき僕は、この店で公共料金の支払いをしてから駅に向かい、ある企業の説明会に出ようとしていた。ところが、レジの彼女がひどく手間取ったせいで電車に乗り遅れ、説明会に五分遅刻してしまったのだ。
コンビニで働く外国人は、大半が日本語学校に通う留学生だとどこかで聞いた。たぶん彼女もそうだ。ここのイートインスペースで日本語の教科書を開いているのを見たことがある。だが、客の言うことにろくに返事もしないところをみると、まだ初学者同然なのだろう。
彼女はやっとごみ処理券の束を見つけ出した。そこから二枚ちぎってレジに通し、領収印を押す。お待たせしました、のひと言もない。最後にレシートを差し出しながら、抑揚のない声で「またお越しくださいませ」とだけ唱えた。あんたのレジにはもう並ばねーよ。心の中で毒づきながら、出入り口に向かう。
ガラス扉に手をかけたとき、イートインスペースから「あれ?」という声が聞こえた。奥の席でスマホをいじっていた若い男が、こっちを見ている。知った顔だ。
「堀川じゃん。だよね?」彼は細く整えた眉を器用に持ち上げた。
「ああ……」喉まで出かかった名前が、出てこない。
「覚えてない?」自分の顔を指差して言う。「清田。ほら、教養のゼミで」
「――覚えてるよ。班長」
そうだ、清田だ。確か、経営学部。二年生のとき、「課題探究ゼミ」という教養科目で一緒になった。同じ班で十五週にわたってグループワークをしたので言葉は多少交わしたが、他のメンバー同様、親しくなったわけではない。
彼にはちょっとした恩がある。最初の授業で班分けをしたとき、講義室の隅で一人あぶれていた僕に声をかけてくれたのだ。いかにもイマドキな風貌なのに、清田は真っ先に班長に手を挙げた。互いに初対面のメンバーたちにまんべんなく話を振り、教授のくだらない冗談にも上手くツッコミを入れる。要するに、僕とは正反対の人間だ。
それだけに、僕の顔と名前を覚えていたというのは、驚きだった。どこにいても、いないのと同じような僕のことを。
会話が始まってしまったので、仕方なく数歩近づいた。柑橘系の香水の匂いが鼻をくすぐる。
「久しぶりじゃん」清田は笑みを浮かべ、僕の全身に目を走らせた。「仕事帰り?」
「――いや」うまくごまかせそうにない。「就活だよ」
「就活? なんで今? あ、そういや理工学部だったよな。大学院行ってんのか」
「いや、まだ四年なんだ。一年間休学してたから」
「ああ、そうなんだ」清田の目つきが変わった気がした。だが口調は軽やかだ。「そっか。この時期まで就活続けてるなんて、大変だな。でも、理系だし、キープしてるところも何社かあるんだろ?」
「――まあ」目を伏せて言った。「……なくはないけど」
「お、いいじゃん。何個持ってんの? 内定」
「一応……二個」
大嘘だ。三月から四十社以上にエントリーしてきたが、内定どころか、二次面接を突破したことすらない。
「おー、いいじゃんいいじゃん」口もとこそほころばせているが、清田は見透かすような目でこっちの顔をのぞき込んでくる。僕はたまらず質問に回った。
「そっちは社会人一年目だよね。何系の会社?」正直そんなこと、知りたくもない。
「うん、俺はね」清田は、細身のパンツに包んだ長い脚を組み直した。知らないブランドの高そうなスニーカーを履いている。「会社員じゃないんだ。今は、投資とITの中間みたいな仕事してる。いずれはもっと大きなビジネスにつなげていくつもりだけどね」
「へえ。なんかすごそうだね」
もう話を切り上げたくてそれ以上訊かなかったのに、清田は前のめりになった。
「でも、いろいろ悩みもあってさ。ちょっと聞いてくんない?」
「え?」なんで僕に。ゼミで一緒だったときだって、個人的な話はしたことがない。
「まあ、ちょっと座れよ」清田が笑顔で隣りの椅子の背を叩く。「もう、うちに帰るだけなんでしょ?」
「まあ……」それはそうだが、さっさと帰って少しでも作業をしたい。それに没頭して頭をリセットしてからでないと、今夜は眠れそうになかった。
「久しぶりに会ったんだし。五分ぐらい、いいじゃん」
五分と言われると断りにくい。渋々椅子を引こうとしたとき、突然後ろで、がちゃん、と大きな音がした。
驚いて振り向くと、出入り口のそばに置かれたゴミ箱の前に、さっきのグエンがポリ袋を持ってしゃがんでいる。まわりの床にはドリンク剤の空きビン。ゴミを片付けようとして、ポリ袋に入っていた中身をぶちまけたらしい。
もう、どうしようもない。呆れることさえやめて、椅子に浅く腰掛けた。
「俺さ」清田がどこか自慢げに言う。「仮想通貨のアフィリエーターやってんだよね」
「ああ――」出た。いきなり怪しげな話。
アフィリエートというのは、個人がブログやSNSで商品やサービスの宣伝をし、生じた利益に応じて企業から報酬が支払われる仕組みのことだ。副業としてやる人が増え、最近は大した収入が得られないと聞いている。
「仮想通貨ウォレットってあんじゃん?」
「いや、よく知らない」僕は理工学部でも、材料力学の研究室にいる。ITの知識はそれなりにあっても、金融の方面には疎いし、興味もない。
「まんま、仮想通貨の財布ってことなんだけど。要は、買った仮想通貨を安全に保管しといてくれるサービス。配当型ウォレットってのもあってさ。みんなから仮想通貨を預かって、運用して利益を出して、それを配当に回してくれるわけ」
清田はボールペンを取り出し、テーブルの上の薄汚れた紙を手もとに引き寄せた。そこに文字や矢印を書き込みながら、慣れた調子で説明を続ける。中指にはごつごつしたシルバーのリング。そんなものも香水も、二年生のときはつけていなかったはずだ。
「俺がやってるのは、アメリカのベンチャーが立ち上げた配当型ウォレットでさ。独自に開発したAIを駆使して資金を運用してるから、配当がめっちゃいいんだわ。で、ここからが大事なポイント。ある程度まとまった額の仮想通貨を買って、そのウォレットに預けると、アフィリエーターの資格が得られる」
「そのウォレットの宣伝をしたら、報酬がもらえるってこと?」
「宣伝というか、紹介かな。SNSでも知り合いのつてでも、使えるものは何でも使って、新たな顧客を紹介する。で、仮想通貨を買ってもらって、ウォレットに預けてもらう。そしたら、その額の一〇パーセントがアフィリエーターに入ってくる」
「ああ……」これはやっぱり――。
「まだあんだよ。自分が紹介した顧客がまた別の客をつかまえたら、そいつが買った仮想通貨からもマージンが入ってくる。おいしいだろ? 誰も損しない。頑張ったら頑張った分だけ、収入が増える」
清田がさらさらと描く顧客たちの関係図が、一人のアフィリエーターを頂点にピラミッド形に広がっていく。
「でも、それって……」もう間違いない。マルチ商法とかネットワークビジネスとか、その類いだ。
AIを駆使した資金運用なんて、でたらめに決まっている。とにかく利用者を増やし続けて、集めた資金の一部を配当に回しているだけだ。大儲けするのは上層部だけ。遅かれ早かれ破綻して、ほとんどの顧客は泣きを見ることになる。
「もしかして、胡散臭いと思ってる?」清田は目を細める。「確かにこういうのって、日本だとあまりイメージよくないかもしんない。けど、アメリカじゃごく普通のビジネススキームなんだよ」
「うん。それで、悩みって何」どうでもいいから、早く解放されたかった。
「俺、上からも期待されててさ。もっと成績上げて、さっさとマネージャーになれって言われてるんだわ。あ、マネージャーってのは、アフィリエーターを何人か統括する立場ね。でも最近スランプでさ。顧客の獲得数、伸び悩んでるんだよね」
知るかよ、そんなこと。
「言っとくけど、僕は無理だよ」脱力して言った。「そんな金ないし」
「金がないからやるんじゃん。みんな、学生ローンとか組んでやってるよ」
「ごめん、そういうの興味なくて。わかるでしょ」
「――わかる」意外な反応だった。清田は体ごとこちらに向け、真顔になって続ける。「堀川がこういう話にすぐ乗ってこないだろうってことは、わかるよ。ゼミでも一番の慎重派だったもんな。だからさ、投資するんじゃなくて、ちょっと手伝ってくんない? 今、何かバイトしてる?」
「いや、就活中だし」
「就活するにも金は要るでしょ。いいじゃん。うってつけだよ」
「無理だって。そういうの、向いてない」
「大丈夫。堀川は基本、座ってるだけでいいし。週に二、三回、二時間だけ俺に付き合ってくれたら――」清田は人差し指を立てた。「その都度一万出すよ」

*
夕立が上がっても、湿気が増えただけで涼しさは微塵も感じない。
寝汗で湿ったTシャツのままアパートを這い出てきたが、体は鉛のように重い。通りの木々で一斉にセミが鳴き始め、耳をふさぎたくなる。
今日の昼前、研究室でノートパソコンを開いていると、こないだ面接を受けた会社から“お祈りメール”が届いた。不採用通知のことだ。文面が〈今後のご活躍をお祈り申し上げます〉と締めくくられていることが多いので、就活生の間でそう呼ばれている。
さすがにダメージを受けて研究室にいるのが辛くなり、アパートに帰ってベッドに倒れ込んだ。昼食もとらずにさっきまで寝てしまっていたのだが、今も食欲はない。
とうとうこれで、持ち駒はゼロ。また一からやり直すのかと思うと、この場に崩れ落ちそうになる。
もうこれ以上、君は要らないと言われたくない。傷つきたくない。耐えられない。何より、もう二度と面接を受けたくない。
僕は、人前でうまく話せない。コミュニケーションが下手というレベルではない。誰かから、とくに複数の人間から注目を浴びていると、言葉が出てこなくなるのだ。子どもの頃からそうだった。
そういう場面はできる限り避けて生きてきたが、就活でそれを回避する術はない。とくに、二社目の面接での出来事は、トラウマになってしまった。僕が一番入りたかった大手工作機械メーカーの一次面接。一社目以上に緊張していたし、気負いもあった。
もちろん、定番の質問への答えはちゃんと暗記していた。志望動機を教えてください。あなたの長所と短所は何ですか。序盤はつまりながらも予定通りに対応することができた。
学生時代、力を入れていたことは何ですか。一番しっかり答えたい質問だ。間違えずにうまく話さなければ。そう思った瞬間、頭が真っ白になった。「えっと……」とつぶやいたまま、たぶん十秒以上固まっていた。面接官たちの顔がみるみる曇る。それを見て、さらにパニックになった。口をつく単語をしどろもどろにつなげたが、何を言ったかは覚えていない。
そして最悪なことに、僕にとって最も難しい質問が次に来た。大学を一年間休学していた理由は何ですか。僕の頭は完全にフリーズしてしまった。全身に噴き出す汗以外、何も出てこない。結局それにはひと言も答えないまま、面接は終わった。
それからの活動は、まさに地獄だ。グループディスカッションでも面接でも、人の視線を意識すると、途端にうまく話せなくなる。何だこいつと思われているだろうと思うと、唇まで動かなくなる。悪循環。負のフィードバック。こんな挙動不審な学生が、面接を突破していけるわけがない――。
無性に喉が渇いていた。〈値下げ!〉というシールが貼られた自販機でペットボトルの水を買い、一気に半分ほど流し込む。
ラベルに描かれた雪山のイラストを見て、新潟に帰るという選択肢がまた頭をよぎる。田舎の小さな会社なら、面接もどうにか乗り切れるだろうか。両親は去年からずっと、地元で公務員試験でも受けろと言っていた。東京の会社など、お前に勤まるはずがない、と。
新潟でも職探しをするとしたら、今後東京との間を何往復かすることになる。交通費が要るが、就活が長引いているせいで生活費さえ底をつきかけている。
清田がもちかけてきた話をあの場できっぱり断ることができなかったのも、それが理由だ。彼から三年ぶりのラインが届いたのは、昨夜のこと。〈明日18時半、来れる?〉というメッセージに、迷った挙句〈行けることは行けるけど〉と返信してしまった。メンタルが今日こんなことになるとわかっていたら、無視していただろう。
待ち合わせ場所のあのコンビニに、約束の時間に三分遅れて着いた。
通りからガラス越しにイートインスペースを見ると、清田が立っていた。制服姿の店員と何やら言い合っている。またあの外国人――グエンだ。
扉を押し開くと、清田の声が響いてきた。
「だから、知らねーって! しつけーよ!」
グエンはひるむ様子もなく、まだ何か言いたげに清田を見上げている。僕に気づくと、清田は構わずテーブルのトートバッグをつかみ、「行こうぜ」と言ってさっさと店を出た。あとに続く僕の背中にも、彼女の視線を感じた。
「何があったの」歩き始めて僕は訊いた。
「わけわかんねーよ、あの店員」清田はまだ怒っている。「こないだ堀川と会った夜、俺あのイートインの一番奥に座ってたじゃん? そこに忘れ物がなかったかって言うんだよ。何もなかったって何回も言ってんのに、しつこくからんできてさ」
「忘れ物って、客の?」
「知らね。ちゃんと聞かなかったし」
呆れを通り越し、哀れに思えてきた。あの店には他にも何人か外国人アルバイトがいる。皆こちらの求めを難なく理解し、てきぱきと仕事をこなす。なのにあのグエンだけが、いろんな客とトラブルを起こし、罵られているのだ。
多くの外国人バイトと同じように、彼女も日本語をマスターして進学や就職につなげたいと考えているのだろうが、あの仕事ぶりでは何をやってもダメだろう。
線路沿いの道を駅のほうへと歩く。後ろで踏切が鳴り始め、新宿行きの電車が轟音とともに僕たちを追い越していく。
道すがら、これから会う学生について簡単に聞いた。文学部の四年生で、清田が入っていたサークルの後輩の彼氏の友人。清田の言葉を借りれば、最近は大学時代の人脈を掘っているらしい。面談するのは今日で二回目だそうだ。もちろん僕とは面識もつながりもない。
僕の仕事は、その文学部と一緒に清田の話を聞くこと。アフィリエーター側ではなく、仮想通貨の投資に興味がある大学生としてだ。そして最後に、「決めました。僕、契約します」と宣言する。そう、インチキ商法ではお馴染みの、サクラだ。
わかっている。クソみたいな仕事だ。でも、楽して稼ごうとこんな話に乗ってくるやつだって、同じぐらいクソだろう。罪の意識は大して感じない。
面談場所は、駅の北口にあるチェーンのカフェだった。コーヒー一杯に三百五十円も払えるような暮らしはしていないので、入ったことはほとんどない。
一足先に着いていた文学部の学生は、やたらとへらへら笑う男だった。清田が支払いをした飲み物を持って、隅のテーブル席に着く。奥に清田、向かいに並んで僕と文学部だ。文学部はスーツ姿だったので、もしかして就活中かと思ったら、違った。
「どうだった? 内定者懇談会」清田が軽い調子で訊いた。
「いやあ、何だかなあって感じです。選択ミスったかも」文学部はにやけて首をかしげる。
「会社なんて、どこ入ったってがっかりするもんだよ」清田が訳知り顔で言う。「俺なんてさ、内定六個とって、その中で断トツにいいと思ったとこに入ったけど、結局二カ月で辞めたからね。ああ、こいつら全員無能だな、意識高いやついねーなって、すぐわかったから」
清田もいったんは就職はしたのか。知らなかった。文学部は間の抜けた顔で、「内定六個ですか、すげー」と感心している。
「その点、俺のアフィリエーター仲間とかマネージャーさんとかは、マジで全然違うよ。ちゃんと高い目標持って、夢持ってやってる。人脈もヤバい。若手の実業家とか投資家とか、その辺とみんなつながってるんだわ。そういう人たちとの交流会もあってさ。俺が紹介すりゃ君も来れるよ。参加費が三万かかるけど、二回目からは友だち一人連れてきたら無料になるから」
僕も別の意味で感心していた。いくらマニュアルや台本があるにせよ、よくこうもすらすらと与太を並べられるものだ。
「そういや、堀川君も――」清田が振ってきた。「こないだ交流会デビューしたんだよね。刺激受けたでしょ?」
「ああ……そうですね」
適当に話を合わせろと言われているが、気の利いた言葉はとても出てこない。
「学生じゃ普通会えないような人に会えるからね。人生観変わるよ。ただ就活してても絶対入ってこないような情報がバンバン入ってくるし。ぶっちゃけ、そういう世界に足踏み入れていかない限り、チャンスなんか一生つかめない。俺も初めて交流会出たとき、めっちゃ焦ったもん。俺は今まで何やってたんだ、安月給のサラリーマンなんかやってる場合じゃねーって」
「マジすか」文学部は目を輝かせている。
「今の時代、どんな大企業に入っても安心なんかできないぜ。会社がつぶれたらどうする? コンビニでバイトでもする? この先AIが発達したら、そんな仕事さえなくなるよ。だからさ、他人に雇ってもらおうって考えから、まず抜け出す。自分の力で稼いで、夢を叶える」
清田はそこでコーヒーをひと口含み、「そんなわけでさ」と続けた。
「書いてきてくれた? やりたいこと、なりたい自分、五十個のリスト。あ、堀川君はいいよ。こないだもらったから」
「一応、書きましたけど」文学部はクリアファイルからレポート用紙を一枚取り出し、へらへらと清田に差し出した。「一〇〇パー無理なことばっかになっちゃって」
「いいじゃん。全然いいよ」
何のことだかよくわからないが、これも手口の一つなのだろう。汚い字の箇条書きを、清田が読み上げていく。
「〈ベンツのジープを買う。タワーマンションの最上階に住む。当たり前に銀座で寿司〉」
「ちょっと、声に出すのはマズいす」文学部は照れてさらにへらへら笑う。
「いいって。〈三十歳までに起業する。投資家になる。休暇は海外の高級リゾートで。プライベートジェットを手に入れる。宇宙旅行(月)〉。おお、いいじゃんいいじゃん」
僕はたまらず文学部の横顔に目をやった。心底驚いていたからだ。リストが夢物語で埋めつくされていたからだけではない。ここまでステレオタイプなことばかりを平然と挙げる神経が、とても理解できなかった。この男にはきっと、本当にやりたいことなどないのだ。
けれど清田は、それと正反対のことを言った。
「でもさ、書き出してみたらよくわかったんじゃない? 本当にやりたいこと。なりたい自分」
「まあ、そうすね」文学部はあっさり誘導される。
「このリスト、実現するには何が必要だと思う?」
「金、ですかね」
「だよね。普通に会社員をやってるだけじゃあ、絶対無理。でも、君のリストの中に一つだけ、金がなくてもできることがある」清田はボールペンでその項目に囲みを入れた。「〈投資家になる〉ってやつ。ここ勘違いしてるやつは、一生浮き上がれないよ。投資はね、今すぐ始められる。もっというと、始めるべき。金がないなら、借りればいい。学生でも、学生ローンとか組めるし。堀川君、その辺調べてみたんだよね?」
「ああ……はい」僕は清田の顔色をうかがいながら答えた。
「全然大丈夫っぽかったでしょ?」
「そうですね。思ったよりは」
「要はさ」清田は視線を文学部に戻す。「何に投資するかさえ間違えなければ、何も心配いらないわけ。最初は少額の投資でも、いったんうまく回り始めたら、もうこっちのもん。金が金を生んで、他の夢もどんどん実現できていっちゃう。実際、俺の知り合いなんかは――」
それから二時間、僕はただ、一秒でも早く時が過ぎ去ってくれることだけを願っていた。

クリーニング店の十字路まで来ると、アパートのある左へは行かず、右に曲がった。ひしめく家々の間を五十メートルほど歩き、小さな児童公園に入る。消耗しているのに熱を持ってしまった頭を、暗い静かなところで少し冷やしたかった。
清田が先に文学部を帰したのが、九時過ぎ。僕は一万円を受け取り、清田の自慢話に少し付き合ったあと、カフェを出てきた。清田は二、三本電話をかけるからと言って、店に残った。今日の報告か、また別の面談でもしているのだろう。
この時間、公園に人の姿はない。象の形のすべり台が、敷地に一本だけある外灯に照らされている。ブランコの前を通って、いつもの隅のベンチに座った。
眠れないときや気分が沈む日は、真夜中にここへ来て、しばらくぼうっと過ごす。自分の孤独がまわりの暗闇に溶け込んでいくような感覚があって、妙に心が落ち着くのだ。
だが今夜は、同じことがぐるぐる頭の中を回って、なかなか消えてくれない。
さっきの文学部。あんなやつでも就職できる。内定者懇談会に出て、贅沢に愚痴までもらしている。
僕は、あいつ以下なのか。へらへら笑ってマルチに手を出そうとしている男より価値がないのか。たまらなく惨めだった。
結局、冷めない頭のまま、二十分ほどで公園を出た。十字路を過ぎ、光に吸い寄せられるようにコンビニの出入り口に近づく。
ふと、ガラスに貼られた〈アルバイト募集〉の掲示が目に入った。さっきの清田の言葉がよみがえる。会社がつぶれたらどうする? コンビニでバイトでもする――?
このまま就職が決まらなければ、来年は僕もどこかでアルバイトの身だ。ここの制服を着た自分の姿が頭に浮かび、中に入る気が失せる。
そのまま通り過ぎようとしたとき、「すみません!」と背後から呼び止められた。振り返ると、ガラス扉の前にグエンが立っている。店から飛び出てきたらしい。
「え――僕?」自分の顔を指した。
うなずいたグエンは、素早く振り返って店内の様子を確かめ、足早に僕の目の前まで来る。
「今日、夕方です」真剣な表情で言った。「お店であなたの友だちと話しました。四日前の忘れ物のこと」
こんなまとまった言葉を彼女の口から聞くのは初めてのことだった。思っていたよりずっとまともな日本語だ。
「ああ、なんか、ちょっと聞きましたけど」
「あなた、四日前も彼と一緒にいました。何か見ませんでしたか」グエンはガラス越しに見えるイートインスペースのほうを指差す。「一番奥の席です。テーブルの上か、椅子の上。もしかしたら、床の上」
「気づかなかったけど――どんな物ですか」
「論文です」
「論文?」意外な言葉だったので、思わず確かめる。「論文って、何か研究の?」
「そうです。古い論文のコピー」
「お客さんの忘れ物ですか」
「違います」グエンはかぶりを振った。「わたしの物です。一番大事な論文」