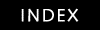


|
「5番線に参ります電車、59分発の浅草行最終電車です」 アナウンスを聞いて、千佳子はふっと笑いを顔に出した。 「間に合いましたね」 三宅が言い、千佳子はうなずいた。 「ほんとに、わざわざ送ってくださらなくてもいいのに」 言うと、三宅は、いやいやと首を振った。 「こんな時間に一人で帰せませんよ。すっかりお世話になっちゃったんで すから」 「お世話だなんて……だって、ちゃんとアルバイト料もいただいたんです よ」 言ってしまってから、千佳子は、まずかったかなと後悔した。 アルバイトなんて、強調することないじゃないの。 「それとこれは別ですよ。少なくとも、今日一日は、僕たち恋人だったん ですから、ちゃんと送り届けるぐらいのことはしなきゃ」 「最終ですよ。送っていただいても、帰りはどうなさるんですか?」 「そんなのは、どうにでもなります。車を拾えばいいし」 「世田谷でしょう? タクシーなんて、すごく高いわ。ここからなら、半 蔵門線で一本なんじゃありません?」 どうして、あたし、こんなこと言ってるんだろう、と千佳子は思った。 まだ一緒にいたいくせに、なんで帰れなんて言うの? せっかく二人になれたんじゃないの。ほんの少し前までは、ずっと三宅 のお母さんと一緒だった。お母さんをホテルまで送って、それでようやく 二人になれたんじゃないの。 「お送りするの……」と、三宅が千佳子を見返した。「ご迷惑ですか?」 ほら、みなさい。ばかなことを言うから。 「迷惑だなんて……そんなことないですけど、申し訳ないような気がして」 「じゃあ、送らせてください。帰りの心配はご無用ですから」 「すみません」 千佳子は、ぺこりと頭を下げた。 どこかほっとした。 「ほんとうに、今日は楽しかったですよ。千佳子さんに……あ、ごめんな さい。癖になっちゃった。駒形さんに来ていただいて、とっても助かりま した」 「千佳子でいいですよ。そんな急にあらたまらなくても」 笑いながら千佳子は言った。三宅も照れたような笑いをみせた。 アルバイトの一日恋人か……。 千佳子は、そっと三宅の顔を盗み見た。 ほんの少しだけ、彼の頬が赤らんでいるように思えた。 |
| 三宅 聡 |