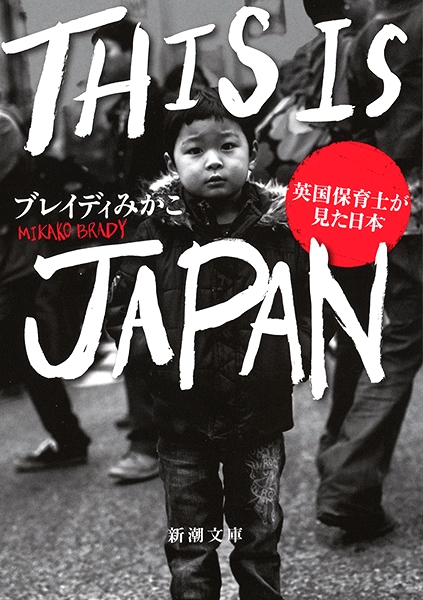THIS IS JAPAN―英国保育士が見た日本―
page 3〔 page 4/4 〕

労働する者のプライド
わたしがキャバクラユニオンのメンバーたちと一緒に仲町通りに立っていたとき、しきりに思い出していたのは英国から成田へ向かう飛行機のなかで見た映画のことだった。それはサラ・ガヴロン監督の『SUFFRAGETTE(サフラジェット)』という作品で(日本では2017年1月に『未来を花束にして』の邦題で公開)1910年代を舞台に女性参政権を求めて闘った英国の女性たちを描いた映画だった。キャリー・マリガン演じる主人公が、著名な女性活動家ではなく、工場で働く末端の女性労働者だったので、地べたの女の目線で見た女性参政権運動映画と英国では大きな話題になった。
この映画のなかで、主人公が同じ工場に勤めている女性参政権論者の影響を受けて運動に参加するようになったとき、職場で周囲の同僚たちから迫害を受けるシーンがある。男性の同僚だけでなく、女性の同僚も「Shame on you!(恥を知りなさい)」と彼女を罵倒し、村八分にする。工場の女性労働者たちは男性よりもずっと低い賃金で働かされ、工場長に性的に凌辱され、劣悪な職場環境のなかで労働者ピラミッドの底辺にいる奴隷として扱われてきた。主人公と同じようにそのことに不満や怒りを感じているはずの女性労働者たちが、「もうこんなことには耐えられない」と立ち上がった主人公になぜか憎悪の視線を向け、いじめる。
あの上野の仲町通りで目の当たりにした光景も、それに似ていた。
キャバクラ嬢たちの労働条件の凄まじさを聞いたとき、いったいいつの時代の話なんだと思ったのもあの映画を思い出した理由の一つかもしれない。あの時代の英国の工場でもまた、労働者たちが、運動に参加する労働者を目の敵にしていた。みんな不幸、みんな大変、みんな辛いのだから、この共有の受難の輪を乱すやつは許さないとばかりに一丸となって、状況を改善しようとする者を攻撃する。そもそもの「みんなの不幸」をつくりだし、それを運営している上部には怒りのベクトルが向かわなかったのだ。それは労働者たちが、彼らを取り巻くシステムが変わりうるとは想像もできなかったからだろう。淫らなまでに格差が広がっていたヴィクトリア朝からエドワード朝にかけての時代を生きた庶民には、平等とか公正とかいうコンセプトは、自分たちとは関係のないどこか上のほうで展開されていることだったのだ。
『サフラジェット』という映画自体は、わたしはあまり好きではなかった。憔悴し、一途に思いつめた女性活動家が自らの命を捨てて(競馬レース場で全速力で走る国王の馬の前に身を投げ出して)訴えたことがきっかけとなり、女性参政権は実現した、という描き方はあまりに暗いし、陰惨すぎる気がしたからである。誰かの死と運動の勝利をリンクさせる結末は、個人的には好みではないし、「社会運動はちょっと精神的にヤバい人がするもの」みたいな、当時の労働者たちが持っていた偏見とあの映画のラストシーンの撮り方は図らずもシンクロしてしまっていた。
だが、ジェンダーの問題にしても労働や人種の問題にしても、英国社会で「ヒューマン・ライツ(人権)」が勝ち取られて来たのは、ディベートやツイッターでの論破などということではなく、現実に街頭で血が流されてきた結果なのだ。『サフラジェット』にしても、レディーファーストの国であるはずの英国で、参政権を求めて闘った女性たちは警官の男たちに殴られ、蹴りを入れられ、血まみれになって倒れていた。忘れられがちな女性運動のヴァイオレントさを思い出させた意味では貴重な作品である。
一方、同じ英国映画でも、1910年代から70年が過ぎた1984年を舞台にした『パレードへようこそ』では、そうした運動の血なまぐささや陰惨な部分は希薄になり、人民の「ユナイト」がテーマになる。この時代まで来れば、同じような境遇で働く労働者が結束して上に向かって拳を上げるのは当たり前のことになり、今度は労働者とLGBTコミュニティという、まったく違う立場だがやはり自分たちの権利を求めて闘っている、異なるセグメントの人々の連帯はありえるのか、という一歩進化した「ユナイト」がテーマになる。
1979年に首相の座に就いたサッチャーはゴリゴリに公共投資を抑えた緊縮財政政策を推し進め、1947年にクレメント・アトリー率いる労働党政権が国営化した石炭業界への補助金を削減して、次々と炭鉱を閉鎖に追い込んでいく。こうした露骨な「小さな政府」志向と、強引に製造業からサービス業への産業構造の転換を図る姿勢は、サッチャーの「非産業革命」とも呼ばれたが、彼女の経済政策は大勢の失業者と貧困を生み出した。1984年から1985年まで続いた英国の炭鉱ストライキは「失業保険よりも炭鉱で働かせろ」と炭鉱閉鎖に抗って立ち上がった労働者とその家族たちの闘いであり、この映画はその時代のウェールズの炭鉱を舞台にしている。
同性愛者を大っぴらに差別していたマッチョ思考の炭鉱労働者たちが、自分たちのストライキを助けてくれる同性愛者たちと出会い、誤解や衝突を繰り返しながらも最後には共に手を携えて国会前をデモ行進する姿は、日本でも多くの人々を泣かせたそうだが、あの映画の原題は『PRIDE(プライド)』だ。「プライド」はもちろん、毎年世界中でおこなわれているLGBTのコミュニティとカルチャーを讃えるフェスティバルの名称だ。しかし、このプライドは当然ながらダブルミーニングである。
実在の人物たちを実名で描き、現実にあった話をそのまま映画化した同作には、パディ・コンシダインが演じたダイ・ドノヴァンという人物が登場する。ウェールズの小さな炭鉱の組合代表者だった彼は、現在でも『ガーディアン』紙のインタビューで「労働組合員」という肩書きを誇らしげに使っている。映画にも出て来る「ピッツ&パーヴァート(炭鉱と変態。当時、同性愛者は「変態」と呼ばれて差別されていたので、逆に同性愛者たちのほうから「変態」と自ら名乗ってやった誇り高きブラックユーモアだ)」という炭鉱ストライキ支援の慈善コンサートで、その多くが同性愛者だった聴衆を前に、組合を代表して登壇したダイ・ドノヴァンが実際におこなったスピーチはこうだった。
「君たちは、『COAL NOT DOLE(失業保険ではなく石炭を)』というバッジをつけてくれた。君たちはハラスメントが何なのか知っている。僕たちもそうだ。今度は僕たちが君たちのバッジを胸につけ、君たちをサポートする。それは一朝一夕には変わらないだろう。だが、14万人の炭鉱労働者たちはこの社会には別の問題や闘うべきイシューがあることを知った。僕たちはいま、黒人やゲイや核兵器の問題があることを知っている。僕たちはもう以前の僕たちとは違う」
プライドとは、即ちここで語られている「バッジ」のことだろう。このバッジとは、各人が誇らしく胸につけて歩く矜持のことである。
『サフラジェット』と『パレードへようこそ』は、両者の間にある70年間に英国の運動とピープルの連帯がどう進化したのかを見せてくれる。
① 労働者が闘う労働者を侮蔑して妨害した時代から、
② 労働者同士が団結して闘う時代に移行し、
③ 別の問題で闘っている団体とも協力する時代が訪れ、
④ 労働者たちが社会には様々な問題があることを知覚できるようになり、ユナイトしてすべての人々の権利のために闘うようになる。
これが英国の労働運動史の漸進の歴史だとしたら、わたしが上野の仲町通りで見たものはどこにあたるのだろう。
日本の労働運動は、ひょっとするといま、①の状態なのではないか。という疑念にわたしは駆られた。いっぺんは成長したけどそこにまた戻ってしまったのか、あるいは最初からまともに育っていなかったのかはわからないが、とにかくなぜかそこにいるのではないか。労働運動が健やかに広がることも、逞しく進化することもなかった社会では、労働する者のプライドは育たないだろう。