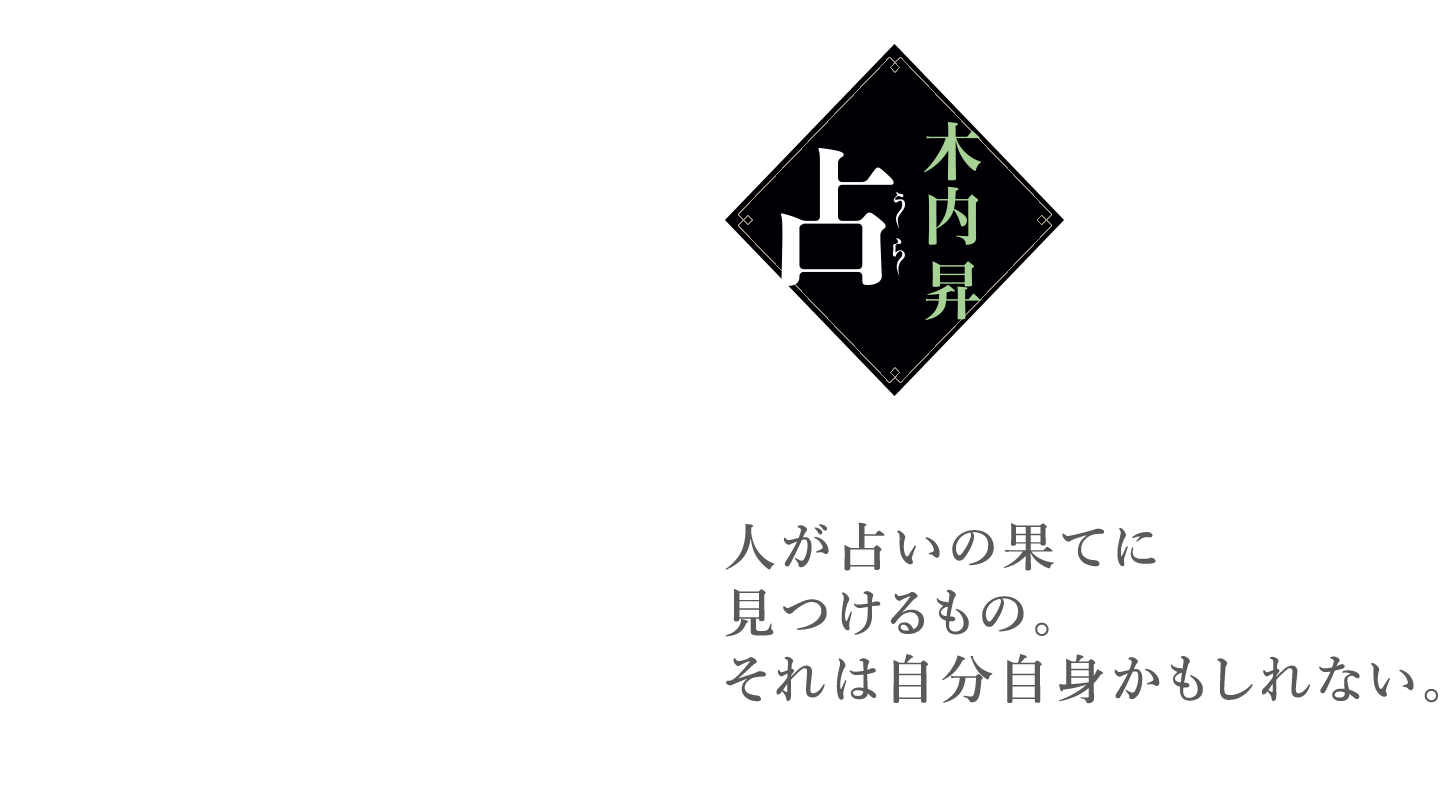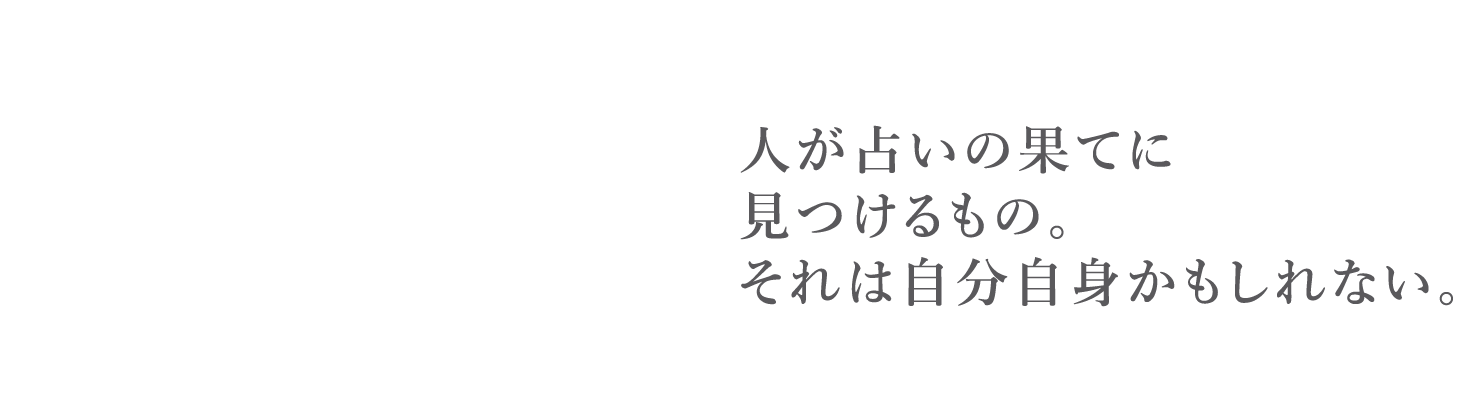本作品の全部または一部を、無断で複製(コピー)、転載、改ざん、公衆送信(ホームページなどに掲載することを含む)することを禁じます。
なお、この試し読みは校了前のデータで作成しています。ご了承ください。
〔 page 1/3 〕
単行本刊行時掲載
第一話
時追町の卜い家
一
もうここには来ないで、と桐子は言った。
玄関戸に手を掛けた男の、こちらに向けられた柔らかな笑みが一瞬で凍てつき、薄墨に浸したように沈んでいった。
今日でおしまい。あなたといた時間は本当に愉しかったし、感謝もしてる。だけどこの先一緒にいても仕様がないと思うの――そう追い打ちを掛けた桐子に、彼はひと言も返さなかった。追いすがることも、わかったと頷くことすらせずに、ふらりと敷居をまたいで、それきりになった。
これで気鬱から解き放たれる、自分の暮らしに戻れると、その日は心底清々したのだ。それなのに翌朝目が覚めると、桐子は手酷い後悔で雁字搦めになっていた。翻訳の仕事もろくろく手につかず、日がな一日、窓からぼんやり表を眺めている。夏の陽を受けて木々の一葉一葉が命を謳歌するように輝いている様がまた、桐子をいたずらに責め立てた。
かわいそうなことをした。苦しんでいる男を見捨てるような真似をしてしまった。助けてやることも、話を聞いてやることさえせずに、突き放したのだ。
夜は眠れず、食欲も失われていった。部屋に残る、男の使った箸や寝間着が目に入るたび、桐子の胸は歪な音で軋んだ。
ひょんなきっかけで縁を結んだ男だった。
四年前に父が逝ってから、桐子はこの咲山町の一軒家に独りで住まっている。三十女が独り住まいだなんて、と周りは哀れんだり訝ったりしたが、生まれ育った家は慣れ親しんだ親友のように居心地が良かったし、女学生の時分に夢中で学んだ英語を活かして翻訳の仕事も得ていたから暮らしに詰まることもなく、気ままな日々を楽しんでいたのだ。
男は、瓦の修繕を頼んだ大工に付いていた弟子だった。軒先が少し崩れただけだったから作業は半日も掛からずに終わり、ふたりの職人があっさり引き上げていったその晩、玄関戸を叩く者があって出てみると、弟子の若者が佇んでいたのだった。
「今、仕事が終わったんで」
不可解な一声を彼は放ち、やにわに工具を広げた。意味がわからず動じる桐子に構うことなく下駄箱の戸を外すや、その一辺を鉋で削りはじめたのだ。
「ぴったり閉まらないでしょ、この戸。昼間、奥さんに出していただいたお茶をこちらでご馳走になったとき、目に付いたんですよ。親方がいるんで口出しできなかったけど、どうにも気になっちまって」
こちらは見ずにひと息に言い、手際よく鉋をかけ終えると、引き戸の溝に蝋を塗ってから戸をはめた。滑らせた戸が隙間なく閉まる。すると彼は振り返り、満面の笑みをたたえたのだ。子供みたいに笑う人だ、と桐子は胸を押さえる。平素、眉間に深い皺を刻んで小難しいことばかり並べ立てる仕事仲間としか接していない彼女にとってそれは、感銘を覚えるほど鮮やかな笑みだった。
ありがとうございます、そしたら御代を、と言った桐子に、道具を片付けながら「とんでもない」と彼はかぶりを振った。
「わっちが勝手に気になって伺わせていただいただけですから」
下駄箱脇に立てかけてあった箒を目敏く見付けて、鉋屑を掃き集め、彼はそれを自分の頭陀袋に放り込んだ。こちらで捨てますから、と慌てる桐子に、笑顔のまま首を横に振った。
「夜分にお邪魔しました。時分時に奥さんを付き合わせちまって、かえって申し訳なかったです」
男が頭を下げた拍子に、私は奥さんじゃあないんです、とつい口走ってしまったのはどういうわけだったのだろうと、未だに桐子は不思議に思う。一軒家に住む薹の立った女に対して、出入りの業者が「奥さん」と呼びかけるのはよくあることで、桐子はそれにすっかり慣れて逐一改めずにきたのである。
男は束の間目を丸くし、それから視線をほうぼうにさまよわせた。さも大きな失態をしでかしたといった挙措に、彼女のほうがいたたまれなくなった。もしよければ今度遊びにいらしてください、今日のお礼に甘いものでも差し上げますから。ばつの悪さを拭おうと、ふと言ってしまってから、子供に駄賃でもやるような物言いだと慌てた。が、男は気にする素振りもなく、「そいつぁありがてぇな。是非伺います」と素直に応じた。その返事を受け取ってから、ひどく大胆な誘いをしてしまった、と桐子は密かにうろたえたのだ。
男はけれど、なかなか訪ねてはこなかった。ひと月が過ぎた頃には、彼は誘いを社交辞令ととったのだろうし、自分も勢いで言ってしまっただけだから、と桐子は気持ちを片付けた。それでも時折、大正も末だというのに江戸っ子みたような気っ風が滲んだ男の様子を想った。どういうものか、それだけで決まって胸の奥底が和らいだ。

男がひょっこりやって来たのは、修繕からふた月が経った、春先の夕間暮れだった。大工道具を抱えた作業着姿で、「今、仕事が終わったんで」と以前と同じ台詞を口にして、彼は顔を赤らめた。お菓子、今日は支度がなくて。桐子は、それだけ返すのが精一杯だった。嬉しいような、愛おしいような、懐かしいような、これまで味わったことのない感情が湧き出して、型どおりの受け答えを阻んだのだ。
男は伊助と名乗った。所作や言葉遣いだけでなく名前まで江戸風だと、桐子は可笑しかった。座敷にあげると、彼は書斎にしている奥の六畳間を埋め尽くした本の山に目を留め、「すげぇなぁ。異人さんの言葉がわかるんですか」と、大仰に驚いてみせた。桐子の出した茶を「熱ぃ」と言いながら啜り、「この家はなんだか居心地がいいな」とつぶやいたと思ったら、その場にごろりと寝そべったのだ。ろくに言葉も交わさぬうちに、あたかも自分の家よろしくくつろぐ男に肝を潰しはしたが、桐子は少しも嫌な気がしなかった。それどころか、この家に彼がいる景色が至極自然であるように感じられたのだった。
男と深間になるまで、時間はかからなかった。伊助は三日に一度は桐子の家に顔を出し、桐子の支度した夕飯を頬張る。
「うめぇな。うちは竈も壊れてっから、ろくな支度ができないんだよ」
幸甚町の長屋に、彼はひとりで住まっている。親方の家が近ぇし、家賃も安いから決めたんだが、台所も便所も朽ちかけてるあばら屋で、雨漏りまでするんだぜ、と彼は幾度となく笑い話にした。それで桐子は、馴染んでふた月が経った頃、そっと告げてみたのだ。
もしよければ、ここで一緒に住まないか、と。
告げたのは半ば勢いだったが、けっして思いつきではない。伊助とはいずれそうなるだろうという予感が、初手からしていたのである。
いいのかい、と彼はいつもの照れ笑いで応えるはずだった。家賃はいただくよ、と桐子は冗談口で返すつもりであった。
ところが伊助は声を呑んで、目をそばめたのだ。それきり押し黙ってしまったからさすがに気まずくなって、冗談よ、そんな仲でもないものね、と桐子が繕うと、伊助はようようこちらに向いた。これまで見たことがないほど物憂げな面持ちだった。
「ちょいとご不浄を借りるよ」
不意に断って彼は腰を上げ、ずいぶん経ってから戻ってきた。桐子の向かいに正座して、大きく息を吸った。それから苦しげに口を開いた。
「わっちには、離ればなれになった妹がいます」
途切れ途切れの声だった。目にはうっすら涙が溜まっている。ただならぬ様子に、桐子も居住まいを正した。
「その妹を、なんとか探し出したいと思ってる。それまでは自分が落ち着くわけにはいかねぇんだ。わっちにとっては妹が、この世で一番大事だから」
妹といっても、血の繋がりはないのだ、と彼は言った。
伊助は三つで父を亡くし、しばらくは母親に女手ひとつで育てられたが、八つのとき、母が後妻に入った。その相手にも連れ子があった。伊助より五つ下の梅という娘である。目がくりくりした器量よしで人懐こくもあったから、母は実の子のように梅をかわいがったし、伊助もまた兄としてこまめに世話を焼いた。あいにく伊助は義父との折り合いが悪く、十五になると逃げるようにして家を出て、今の棟梁の下に弟子入りしたが、それでも梅に会うためだけに、休みのたび三里も離れた実家へ足を運ぶことは欠かさなかった。
「梅のために土産を買って、次はどこへ連れて行ってやろうかと考えるのが愉しくてね。そら、恋仲になると、相手をどこへ連れてってやろうかと男はあれこれ思い巡らすだろう? あれと似たような感じかもしれねぇな」
伊助が目を細めて語るのを聞きながら、そういえば自分はこれまで一度たりともどこかに連れて行ってもらったことがなかったな、と桐子は気付く。彼は仕事帰りにふらりとここを訪れて、休んでいくだけなのだ。泊まったところで、買い物ひとつ、一緒に出掛けたことはないのだった。
梅が実家から消えたのは、二年前のことだという。十五になったから奉公に出したと義父は言ったが、実は遊里に売られたのだと母が泣きながら打ち明けた。義父の商売はだいぶ前から左前で、見かねた梅が自ら願い出て決めてしまったらしい。目の前が暗くなると同時に、実の娘が身を売るのを止めなかった父親に殺意さえも覚えた、と伊助は唇を噛んだ。
「それきり実家には帰ってねぇんだ。わっちは梅を探し出そうと、暇を見つけちゃほうぼう訊いて回ってるんだが、なかなか手がかりが掴めねぇ」
伊助を慰めなければ、と頭ではわかっていた。それなのに、泥だらけの下駄で胸を踏みしだかれているようで、息をすることさえ難儀だった。ようやくの思いで、そうなのね、話してくれてありがとう、と絞り出したとき、ついさっきまで自分の手元にあると信じていた伊助の心が、桐子にはまったく見えなくなってしまったのだ。
この日以来、伊助は憚ることなく梅の話題を口に上らせるようになった。
「虱潰しに片っ端から貸座敷に当たってるんだが、なかなか行方が知れねぇんだ。一昔前なら張見世があって直に妓の顔を拝めたが、昨今じゃ写真見世だろう。写真じゃどうも判じがつかなくてさ」
詮方なく見世の門口を守る見番に訊いてはみるものの、男たちは一様に口が堅い。さぁ、どうですか、と言い抜けて、まともに取り合ってくれないのだという。休みのたびに遊里を尋ね歩き、消沈して桐子の家へやって来ては、「わっちは情けない兄貴だ、妹ひとり守れなかったんだから」と、溜息と一緒に吐き出す。それから決まって、妹との思い出話をひとくさり語る。小さい頃に川で遊んだこと、花火や祭りに連れて行ったこと。桐子の支度した飯を頬張りながら上機嫌で話に興じていたかと思うと、「今、梅がなにをしているのか考えるだけでおかしくなりそうだ」と、頭を抱えるのだった。
自らの懊悩をまき散らすばかりで、伊助は桐子の仕事や生い立ちについては一切興味を示さない。仕事の打ち合わせで訪ねてきた編輯者から、翻訳の心得や、技術の習得法、好きな本や趣味、はては好物まで多岐にわたって質問をされるたび、伊助からは月並みな関心すら持たれていないのだ、と桐子は虚しかった。
伊助といるとどんどん自分が透明になっていくようだった。そのくせ、ふたりの間に挟まった梅の存在は日増しに膨らんでいくのだ。恋敵でもなんでもない、ただの妹ではないか、と自らを慰めるたび、伊助と梅の間には血の繋がりがないという事実に行き着いて、薄暗い嫉妬に駆られるのである。
梅雨にさしかかる頃には、江戸の気っ風を感じさせた出会った頃の彼の様子を思い出すことすら、桐子には難しくなっていた。
「本当は、わっちはもう独り立ちできる腕があるんだ。それでも親方のところに身を置き続けているのは梅のためなんだ。今の奉公先を梅は知ってるからさ。同じ長屋に住み続けているのも、梅がいつでも訪ねてこられるようにそうしてるんだ。わっちは梅のためならなんでもする。なんだって我慢できるんだ」
梅への思いを語られるたび、ならば私はなんなのだ、と桐子は苛立つ。悩みを四六時中聞かされるだけの付き合いにどんな意味があるのかと、うんざりもする。それでも桐子はどういうものか、伊助を嫌うことができなかった。伊助に腹の中の不満を真っ直ぐにぶつけられたらどれほど楽になるだろうと想像しながらも、波立つ内心を抑え込んでひたすら彼の話を聞き続けたのだ。