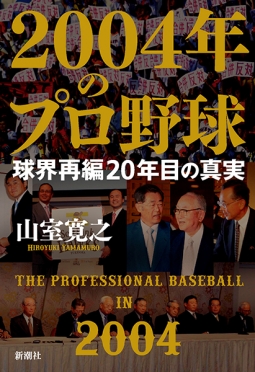一
この五粒の種を、きっとあさってのツルばあちゃんの誕生日に棚田に植えるようにと皐月に伝えることを忘れないでくれ。ほかになにを忘れてもいい。この種を、もう二度と米を作らないあの棚田に植えるようにと皐月に念を押すことだけは忘れないでくれ。
母はひどく慌てている表情で言いました。
そんなに大事な植物の種を初めてのひとり旅に出る小学五年生の息子に託して大丈夫なのだろうか。いったいなんの種なのだろう。皐月ちゃんがどうしてもと欲しがったのだろうか。皐月ちゃんはどんなに欲しいものがあっても、それを求めて駄々をこねるということはいっさいない子なのに。
わたしがそう訊こうとする暇も与えないで、五粒の種が入った上等の縮緬で作った小さな巾着袋を十歳のわたしの半ズボンのポケットにしまいながら、母は東海道本線の列車に早く乗るようにと背を押しました。そして、わたしが急行列車に乗り、窓際の席に坐ったのを見届けて、大阪駅のホームの階段を降りていきました。六十四年前の七月三十日。夏休みが始まったばかりで、昼前なのにもう入道雲が肩をいからせるように青い空に光っていたことを覚えています。
いまが令和五年、二〇二三年の春ですから、わたしは七十四歳になりました。皐月ちゃんはもうじき七十七歳。いまでも夏はあの別荘で夕ご飯用のおかずを釣り上げることを楽しみに家の前で釣竿を振っています。
木の枝のように細くて、体も目鼻立ちも一本の線のようにまっすぐだった皐月ちゃんも、さすがに二、三年前あたりからあちこちが斜めになり、膨らみのある頬にも幾つかの皺が刻まれてはいますが、皐月ちゃんという女性を作り上げている芯を為す箇所は歪んでいないのです。
皐月ちゃんとわたしは姉と弟ですが、父親が異なります。皐月ちゃんが生まれて三か月のときに父親は京都市内で軍用のトラックに轢かれて事故死しました。終戦の一年後だったそうです。
その二年後の昭和二十三年に皐月ちゃんのお母さんはわたしの父と再婚したのです。そしてその翌年にわたしが生まれました。皐月ちゃんは昭和二十一年生まれ。わたしは昭和二十四年生まれ。
母も皐月ちゃんも舞鶴で生まれ育ったからというわけでもないのでしょうが、わたしの父は結婚を機に舞鶴に居を定めました。父はそのとき二十八で、召集先の大連の北方でソ連軍の大砲の破片を踵に受けて、日本軍の野戦病院に収容され、この足では役に立たないと判断されて、早々に日本に傷病兵として送り返されたのです。
父は大学では電気工学を専攻していましたが、そのころには戦況は只ならぬ様相を呈していて、電気技師でもなんでも銃を持たせろという状況だったそうです。しかし、父はお陰で命拾いして日本に帰ることができたのです。
踵の傷は帰国してから骨が腐り始めて、父は京都の病院の医師の勧めで山中温泉の湯治宿で養生に努めました。その粗末な湯治宿で釘を踏んで破傷風になりかかった舞鶴の旋盤工さんと親しくなり、その人の娘さんがどこからか調達してくる米や野菜や鶏卵や鶏肉などを分けてもらっていたのですが、そのうち、まだ赤ん坊の皐月ちゃんをおぶってくる娘さんと「まあ、仲ようなっていってるうちにお前ができたんや」そうです。
旋盤工さんは田鷲公作、わたしの母は菜々江、わたしとは父親の異なる姉は皐月という名です。田鷲という立派な名は片仮名にした途端になさけない字面になるのが面白くて、まだ五十代のころから親しみを込めて「タワシ爺ちゃん」と呼ばれるようになりました。旋盤工と言いましたが、タワシ爺ちゃんは旋盤だけでなく、大工、溶接など、幾つかの職人の手練れな技術を持っていました。タワシ爺ちゃんの従兄でもあり義弟でもあるマジナイ爺ちゃんは、手先はさほど器用ではありませんでしたが、小金稼ぎの名人でした。大金には縁がないのですが、「今月はちょっと五千円ほど足りんなあ」というときには、どこからか五千円を用立ててくるのです。すべてはマジナイで空中からつかみ出したそうです。
「ああ、またマジナイをやったんかいな」
とさして驚きもしないで微笑むのはタワシ爺ちゃんの奥さんのツルばあちゃんで、「おんなじマジナイ使うんなら五万円とか五十万円とかをチチンプイプイとひねりだしゃあええのに」と本気で言うのはマジナイ爺ちゃんの奥さんであり、ツルばあちゃんの妹でもあるカメばあちゃんです。このふたりの姉妹の漫才コンビのような名は本名なのです。
わたしとわたしの両親も含めた八人は昭和三十四年の夏から西舞鶴の迷路のような二階屋で一緒に暮らすようになりました。五粒の植物の種を預かって、わたしが生まれて初めてのひとり旅で舞鶴へ行った夏休みからです。わたしは無事に舞鶴に着いて、皐月ちゃんと吉原の漁師町へと走って、タワシ爺ちゃんをみつけたあと、白杉漁港の少し先の別荘の二階の木の床に長々と仰向けになったときも、自分がこのまま舞鶴に住みつづけるはめになるとは想像もしていませんでした。これからは舞鶴のタワシ爺ちゃんの家で、総勢八人が暮らすことになるのだろうかと考えたのは、翌日、わたしが皐月ちゃんと月明かりの小さな船着場でおぼろな島影を見ていたときだったのです。
だから、母はあんなに慌ててしまって、心ここにあらずという状態になり、急がなければならない引っ越しの算段で頭のなかはいっぱいになっていたのでしょう。
(続きは本誌でお楽しみください。)