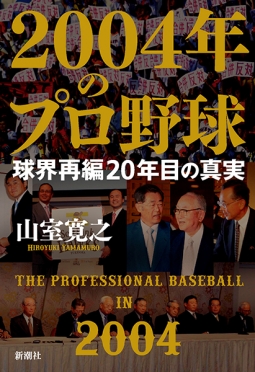0 悲しい仮定法
仮定法は後悔を噛み締めるために作られた文法というわけでないが、「もしもあの時に」と唇を噛み締め、舌打ちをする者が後を絶たないので、少なくとも希望よりは絶望と相性がいいことだけは間違いない。逆に仮定法が存在しなければ、ヒトは後悔と無縁でいられるだろうか? 愚かな選択をしたことを謗られることもなく、どんな結末も笑顔で受け容れられるものだろうか?
幸か不幸か、どの言語にも仮定法がある。仮定法の使用を一切拒否したところで、明日から爽やかに生きていける保証もない。最終的には「もしもあの時に」などと考えること自体、無意味なのだから、つべこべいわず今の結果を受け容れよ、という結論に誘導される。要するに「諦めが肝心」というわけだが、往生際の悪い人はいつまでもブツブツいい続ける。「あの時本気を出していれば」、「もう少し勇気があったら」という後悔、「ほかに選択肢はなかった」、「誰も反対しなかったのだ」という正当化などパターンは限られる。
こうなっていたかもしれない可能性は当然、運にも左右される。奇跡や恩寵というべき幸運に恵まれることもあれば、悪運が重なり、最悪の事態になったケースも少なくない。地団駄を踏むか、神に感謝するかは確かに運任せであるが、その運も確率の問題に過ぎないともいえる。統計学者に歴史を語らせたら、それぞれのケースで細かい数字を出してくるだろう。
たとえば、第二次世界大戦でナチスドイツと大日本帝国が勝利を収めていた可能性は、どんな条件下での試算かによって大きく変わる。どれだけ日本に有利な計算をしても、日本勝利の可能性は低いが、ナチスドイツの勝利の可能性はドイツがアメリカより先に原爆を開発し、イギリスの暗号解読チームにチューリングが参加せず、エニグマが解読できなかった場合など複数の決定的条件が揃えば、かなり高まる。ドイツ、イタリア、日本は同盟関係にありながら、それぞれ個別の戦争を遂行していたが、同盟を強化し、共同の軍事戦略を展開していたら、戦局は連合国側に不利になっていただろう。さらにドイツが独ソ不可侵条約を守り、ソビエトへの侵攻を行わず、ソビエトを同盟に加えて、アメリカと対峙していたら、ファシズム同盟が勝利する可能性は五〇パーセントを超えていたかもしれない。日本は単独ではアメリカに勝利する可能性が絶望的に低かったが、ドイツの快進撃に便乗していたら、フィリップ・K・ディックが『高い城の男』で描いたように、アメリカはドイツと日本に分割統治されていたかもしれない。作中では、東半分は大ナチス帝国、西海岸、西部一帯は日本太平洋合衆国と呼ばれている。アメリカ人は易経を生活の規範としつつも、支配者の顔色を窺う卑屈な態度を取っているが、反抗的な者は中西部の中立地帯を拠点にレジスタンスを展開している。奇しくも『高い城の男』と同じ一九六二年に発表された小津安二郎の遺作『秋刀魚の味』では、トリス・バーで酔客が軍艦マーチを聴きながら、自分が乗っていた駆逐艦の元艦長に向かってこんな戯言を呟くシーンがあった。
――けど、艦長、これでもし日本が勝ってたら、あたしたちどうなってたでしょうね。
――さあね。
――勝ったら、艦長、今頃、あなたも私もニューヨークだよ、ニューヨーク。パチンコ屋じゃありませんよ。本当のニューヨーク、アメリカの。
――そうかね。
――そうですよ。負けたからこそね、今の若え奴ら、向こうの真似しやがって、レコードかけてケツ振って踊ってますけどね、これが勝っててご覧なさい、勝ってて。目玉の青い奴が丸髷かなんか結っちゃってチューインガム噛み噛み、三味線弾いてますよ。ザマーミロってんだ。
あの酔客は場末のバーで、もしかしたらあり得たかもしれない歴史の可能性について語っていたわけだが、その想像力の貧しさが笑える。艦長はそれを受け、あっさりと「けど負けてよかったじゃないか」と現状肯定するのである。酔客も安酒に酔った勢いで適当なことを口走っただけなので、あっさりと「そうですかね。うん、そうかもしれねえな。バカな野郎が威張らなくなっただけでもね。艦長、あんたのことじゃありませんよ。あんたは別だ」という。戦後長らくは、「負けてよかった」と思う人が多数派だった。それは占領軍によるマインドコントロールの成功を意味するのだが、もし私があの酒場のカウンターにいて、風呂上がりのママさんと向き合っていたら「負けるにせよ、一九四二年六月のミッドウェー海戦で手を引いておけば、占領されることもなく、全く違う戦後を迎えることになった」と一言いい添えたかった。
「歴史にIfはない」は歴史家の口癖である。歴史は出来事の結果に過ぎず、仮定の話をしても結果が変わるわけでもないから、諦めろというわけだ。その原則に大人しく従うと、常に勝者が正義で、敗者は悪という評価に甘んじることになる。実際、敗戦国がいくら巧みな弁舌を弄して、おのが正当性を主張したところで、何ら説得力を持たない虚しい遠吠えにしかならない。しかし、同じ負け惜しみでも、どっちに転んでいたかわからない場合は、極めて現実味が高い「正論」になるかもしれず、敗者のいい分にも耳を傾ける価値は充分ある。歴史に仮定法を持ち込むなというのは、そうした事態を避けたいからに違いない。実際、敗者の主張は人道的で理が通っていなければ、通用しないが、勝者の主張はしばしば独善的で、理不尽で、暴力的であるが、国際社会に罷り通ってしまう。力が正義だと渋々認めるしかないが、それでも奇妙な逆転現象は生じ得る。戦争終結から三十年も経過すると、敗戦国が経済大国に成り上がり、戦勝国が経済危機に陥ったりして、どっちが勝者かわからない事態になったこともある。またファシストは撲滅されたかに見えたが、時間の経過とともにその亡霊は各地で復活し、一定勢力を保ち、政権に食い込んでいるところもある。歴史にはそうした皮肉がつきものである。
(続きは本誌でお楽しみください。)