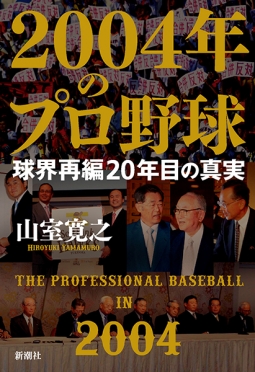「工場」の息継ぎ
――創刊一二〇周年を記念して、新潮新人賞を受賞して以来、日本文学の第一線で活躍し続けている三人にデビュー作、それからご自身にとって転機となった作品、また、今の時代に小説を書くことについて語り合っていただきたいと思います。新潮新人賞の受賞は小山田さんが最も早くて二〇一〇年、次いで滝口さんが翌年の二〇一一年、上田さんが二〇一三年ですから、極めて近い時期に小説家としてキャリアを歩み始めたことになります。お互いがそれぞれの作品を、どう読み、何を感じるのか、率直にお話しいただけますでしょうか。まずは、小山田さんのデビュー作「工場」(初出「新潮二〇一〇年一一月号)からお願いします。
滝口 僕は「工場」を、まだデビュー前の何者でもない時期に、でも小説を書くことへの意識は強くあって翌年に作品を応募するような者として読んだわけですが、この作品に出会ったときに受けた異様な感じをよく覚えています。例えば、作中で使われているいくつかの単語の語感。「私」が入社した職場では荷物を配送する運輸部隊が、彼らの着ているジャンパーのロゴから「UNYU」って呼ばれていたり、あと懇親会的な飲み会が「コマーシャル」と呼ばれたりもしてます。そういう独特な語彙、組織内だけで通じている符丁みたいな言葉が地の文に現れる。そのローカルな感じの独特さについ笑っちゃうんだけど、でもそれは当人たちにとっての笑いじゃなくて、他者から見たときの奇妙さというか、ひとと言葉の関係性の上に生じるおかしさが観察されているということなんだと思う。他にも、改行がないまま段落が続く文章のビジュアル的な重さも、今でこそ小山田さんの代名詞みたいになっていますが、当初はやっぱり異様な感じを受けたし、いろんな意味で、なんだこれは、というのが初読時の印象でした。あと、書き手が作品を答えのようなところに向かわせまいとする必死さというかかたくなさも感じられて、その姿勢には異様さというよりは、僭越ながらも支持するような気持ちというか、その姿勢は自分と通じるものがあると思った気がします。それらの印象は今読み直してもほとんど変わりません。
上田 滝口さんは異様さって言いましたが、僕がこの作品を読んで一番強く感じたのは不穏さですね。小山田さんは小説のなかで語り手たちの日常の細部を、執念深くと言いたくなるほどこだわり抜いて書こうとしています。この場合の日常というのは労働なんですが、それを書けば書くほど、不思議と不穏さが現れてくるんです。その結果、微視的なものが作品全体を通して見ると巨視的なものへと転じていて、そこが面白いと思いました。これは勝手な想像なんですが、おそらくこの作品は元々大きなプロットが用意されていたわけじゃないのではないでしょうか。ここからこの人物には絶対にこう見えているはず、みたいな視点を保持しながら、小山田さんは書き進めたんじゃないかと思うんです。だから、別に不穏さを狙って表現しているわけじゃなくて、書いているとどうしても不穏になってしまうってことなのかな、と。そのどうしようもなさが小山田さんの作家性の魅力の一つなんだということがよく伝わってくる小説だと思いました。
小山田 ありがとうございます。滝口さんから改行の話がありましたが、この作品、最初はもっと改行が少なかったんですよ。入稿するときに見開きごとに一箇所くらい改行を入れて、今のかたちになりました。あの頃、私自身、大きい工場に派遣されて、何もわからない状況で目の前の小さな仕事だけをひたすらしなくちゃならない時期だったんですね。それがとにかくしんどくて。ここから逃げ出さなきゃおかしくなる、といったことを毎日感じてました。そんな状態で小説を書くと俯瞰することなんてできないんです。水のなかであっぷあっぷしている感じと言いますか。水に潜りながら、たまに浮上して息をして、また潜って、また息をして、また潜る。息が続く限り書かなきゃ死んでしまうので、改行なんてしてられませんでした。だから当然、巨視的なプロットに行き着くわけもありません。上田さんがおっしゃったように、一つひとつ、目の前のことを書くしかなくて。とりあえず今、与えられたこの現実を自分なりに解釈していかないとどこにも行けないぞと思いながら、必死に書けるところだけを書いていました。
上田 改行するとそれ以上先が書けなくなる、みたいな感じですか。
小山田 そうですね。吐き出せるところまで吐き出して、少しでも前に進まないとって必死でした。一回浮上して息を吸うとまた違う潜り方になってしまうという感覚があったんです。それは今も同じなんですけど。
滝口 小山田さんにとって改行は息継ぎなんですね。入稿前に改行が増えたのは編集者からもっと増やすように言われたからですか?
小山田 はい、見開きに一個は改行を入れてほしいって言われたので。私の作品で二〇〇枚を超えたのってこれくらいしかないんですよ。いつも息を止めながら書いたものを並べて、これはどうやったら小説になるんだろうと思いながら切ったり貼ったりして一つの作品に仕上げていて、パズルみたいなものですよね。
それと「UNYU」や「コマーシャル」みたいな単語の話がありましたけど、その世界でしか通じない言葉っておそらくどんな組織にもあるものだと思います。そこに入った瞬間は「え?」って思うけど、そのなかで生きているうちに自分も使うようになり、いつの間にかそれが普通になっていく。学校や職場でよく経験することですよね。この作品では組織の一部になっているのに馴染みきらない感覚を書くために登場人物たちが抱える違和感をそのまま表現しようと思ったんです。私が抱えてた苦しさをなんとか楽しさに変えたかったという気持ちもありました。滝口さんが言ったように、「UNYU」って言葉は外の人はそもそも知らないけど中に入りきってそれが普通になっていたら笑えない、その距離感が語り手にも当時の自分にも必要だったなと思います。あのときは、生きるために、おかしくならないために、必死で書いていたんだなって今、話しながら思い出しました。まぁ、それも結局、今とそんなには変わらないんですが。
(続きは本誌でお楽しみください。)