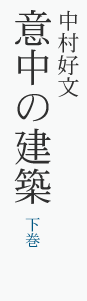 |
生物学者との二人三脚
ソーク生物学研究所 設計=ルイス・カーン
1965年 アメリカ カリフォルニア州ラ・ホヤ

ソーク生物学研究所はメキシコにほど近いラ・ホヤの、太平洋を望む断崖にあります。一九六五年に建てられたこの研究所の創設者はジョナス・ソーク博士(一九一四~九五)で、難病と言われた小児麻痺のワクチン開発に成功した天才的な生物学者です。しかし実を言うと、私たち建築家の間では博士より建物の方がずっと有名です。
建物を設計したのはルイス・カーン(一九〇一~七四)。建築界では超有名で、亡くなってから三十年あまりを経た今でも人気の高い建築家です。現代建築の三巨匠と言われたフランク・ロイド・ライト、ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエには、称賛者と同じだけ(あるいはそれ以上に)批判的な意見を持つ人がいますが、ルイス・カーンには人柄も作品も人の心を捉えて離さない特別な磁力があって、誰もが一目置かずにはいられないのです。一度でも実際にルイス・カーンの建築の前に立ったことのある人なら、または、その建築空間に身を置いたことのある人なら、時流や風潮に流されないカーン建築の独特の「靭(つよ)さ」に感服するに違いありません。「有無を言わせぬ」という表現にはどこか力ずくの印象がありますが、カーンの建築には何人も、ごく自然にこうべを垂れずにはいられないという意味での「有無を言わせぬ」説得力があると言ったら良いでしょうか。
今にして思うと、生物学の権威であるジョナス・ソーク博士と、カリスマ建築家ルイス・カーンが出会った瞬間に、このプロジェクトの成功と、「アメリカで最も美しい建築」と言われるようになることが約束されたのかもしれません。依頼者(クライアント)と建築家が固い信頼関係を持ち、計画から完成までの六年間という長い年月を、二人三脚のように協働したことも、ソーク生物学研究所を語る上で忘れてはいけないと思います。出会った直後から二人は友人同士のように、お互いの専門分野の話をし、人類の未来や芸術についてとことん語り合ったと言われています。後にソーク博士は「私たちはまず遊ぶことから始めた」と述懐したそうですが、そのときの二人の自在に展開する会話を記録しておいたら(なにしろその道の達人同士なのですから)、そうとう読みでのあるものになっただろうと想像されます。
会話の中で研究所の設計に直接的な影響をあたえたのは、ソーク博士がカーンに、「新しい研究所の施設はアッシジのサン・フランチェスコ教会の修道院を規範に……」と示唆したことだと言われています。カーンも以前にサン・フランチェスコ教会を見学して大いに心惹かれ、数多くスケッチしたりしていたので、この点でも二人はピッタリと息の合ったコンビになったのでした。くだけた言い方をすれば、二人はどこか「似たもの同士」だったのです。
二〇〇四年の冬、ソーク生物学研究所を見学に行って来ました。私がこの建物を訪れるのは二度目、最初の訪問はちょうどその十年前の秋のことでした。再訪してみると、そのとき工事の真っ最中だった敷地東側の付属棟(残念ながらカーンの設計ではありません)が完成していて、そのあたりはだいぶ様変わりしていましたが、カーンの設計した実験棟と中央広場にはまったく変化が感じられませんでした。カリフォルニアの真っ青な空と、海から吹いてくる爽やかな微風も十年前とそっくり同じです。季節は幾度となく巡ったはずですが、時間は静止したままのように見受けられました。十年前、ふたつの実験棟に挟まれた中央広場の片隅にたたずみ、建物で切り取られた空と太平洋を眺めていたとき、「美しい神殿」という言葉が頭に浮かびましたが、その印象も変わりませんでした。建物は高貴で神秘的な面影を宿していますし、広場は冒しがたい神聖な気配に支配されています。
神殿のように思える理由のひとつは、厳密なシンメトリーの配置計画によるものです。大きさも構成もまったく同じ南棟と北棟の建物が広場を挟んでお供え物のようにキチンと配置されていて、鏡に映したような対称形になっています。そして、その広場の中心に、鋭い刃物で一直線に切り裂いたような幅の狭い水路が設けられています。広場のデザインはたったこれだけ。水路のほかにあるものといったら、建物の前にきちんと並べられた二列六本の石のベンチぐらいです。それも人がそこに座るためのものというより、広場という祭壇にしつらえられた祭器の一部のようです。
しかし、この広場がこれほどまでに象徴的な姿になるには、おびただしいスケッチと長い長い煩悶の時間が必要でした。水路そのものは計画の初期から考えられていましたが、カーンはその水路の両側に並木のように樹を植えるつもりでいましたし、設計の軌跡を示すスケッチを辿っていくと、その樹種もイタリアにある糸杉にしようと思ったり、ポプラにしようと考えたり、悩みに悩んだ跡が窺えます。並木だけでなく広場のほかの場所にもたっぷり植栽して、研究者たちが憩える緑豊かな庭にしたいという意向を持っていたカーンは、その植物選びについても悩みつづけ、ついには自分でもどうしていいか分からなくなってしまいました。結局、メキシコの建築家で作庭の名手でもあるルイス・バラガン(一九〇二~八八)を呼び寄せて助言を求めることになるのですが、やって来たバラガンがその場に立ち、即座に「この場所には一本の樹木も、一枚の草の葉もいらない。ここは庭になるべきではなく、広場(プラザ)になるべきだ!」と言ったというエピソードは有名です。そしてカーンは、バラガンの忠告に素直に従い、広場は現在の姿になったのです。時間が止まっているように感じるのは、植物のように成長したり変化したりする要素を、広場から完全に排除したせいであることに気づきました。広場の側廊にあたるアーケードの床面には壁柱の影がくっきりと連続模様を描いていて、陽光の中の凍りついたようなその光景は、まるでキリコの絵でした。そこから、私はかすかに「廃墟」の匂いも嗅ぎ取っていました。
|
|
|
|
|