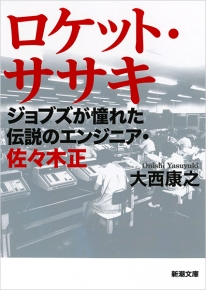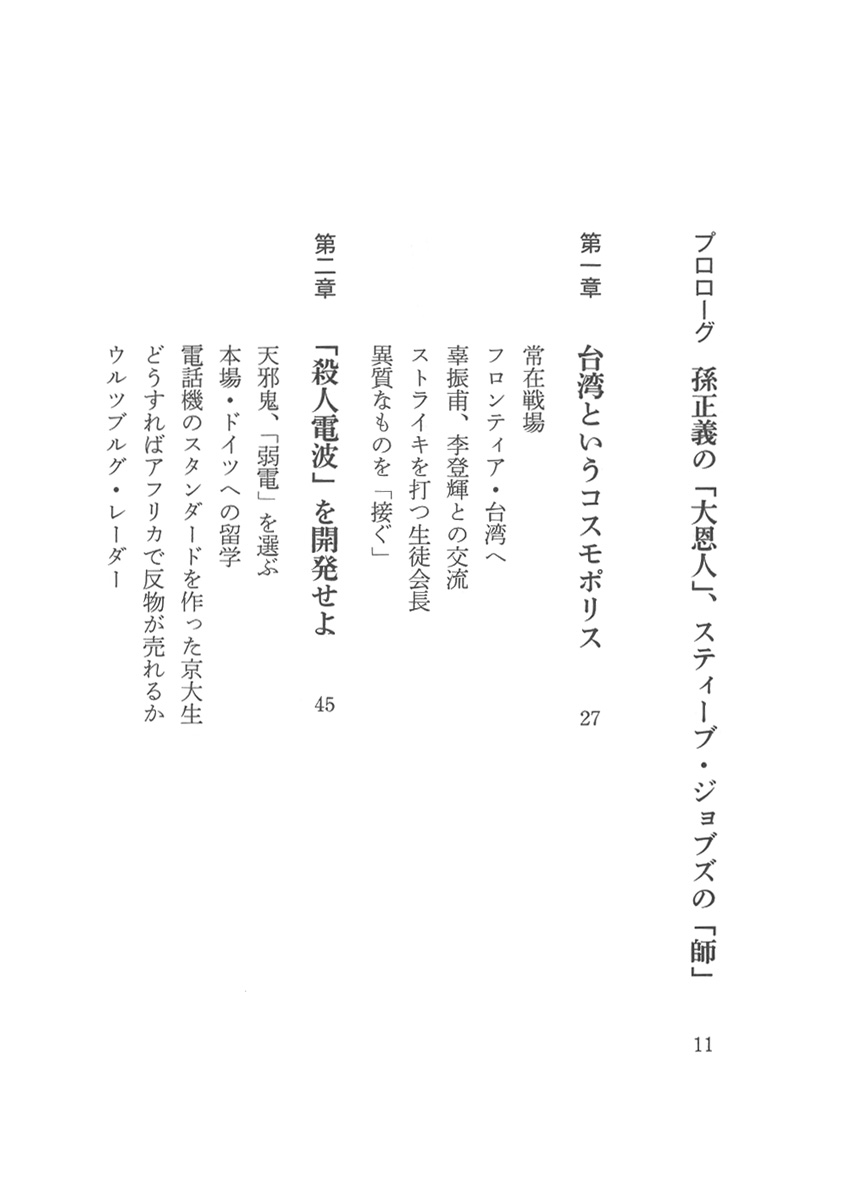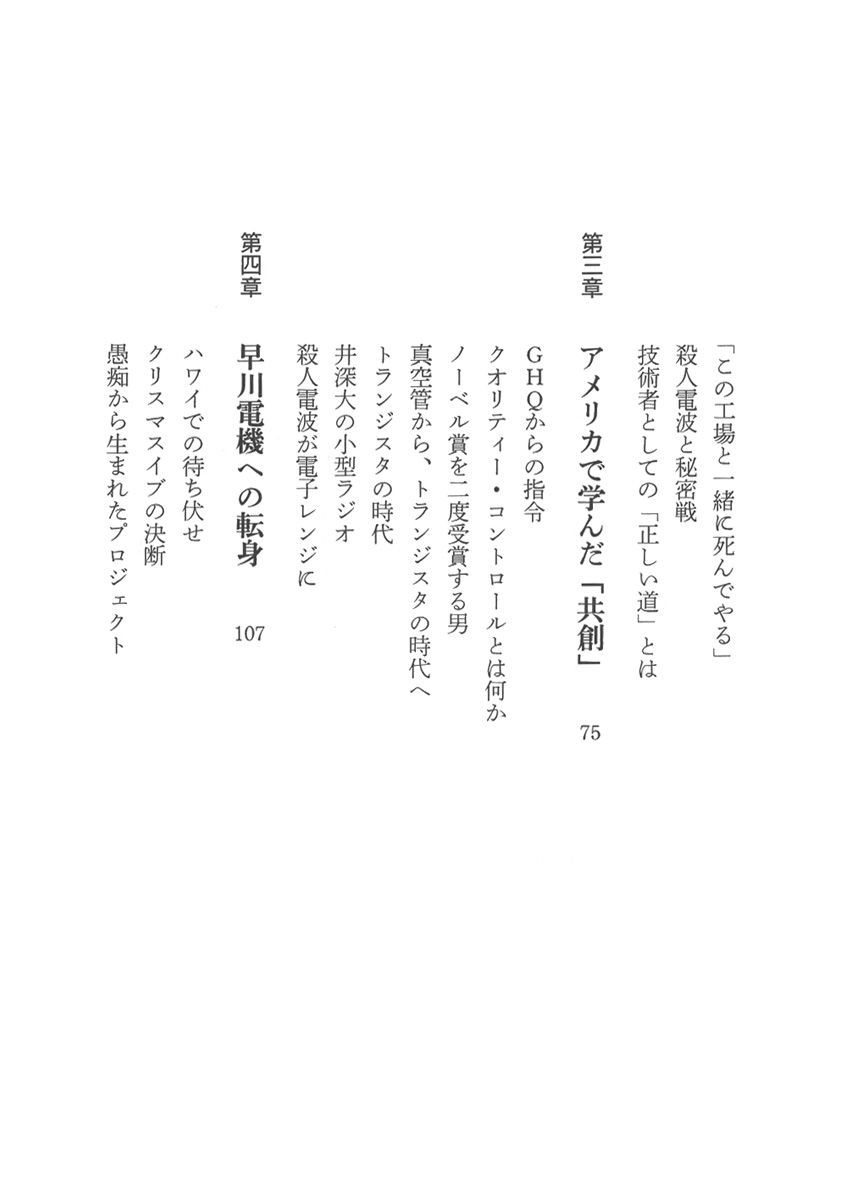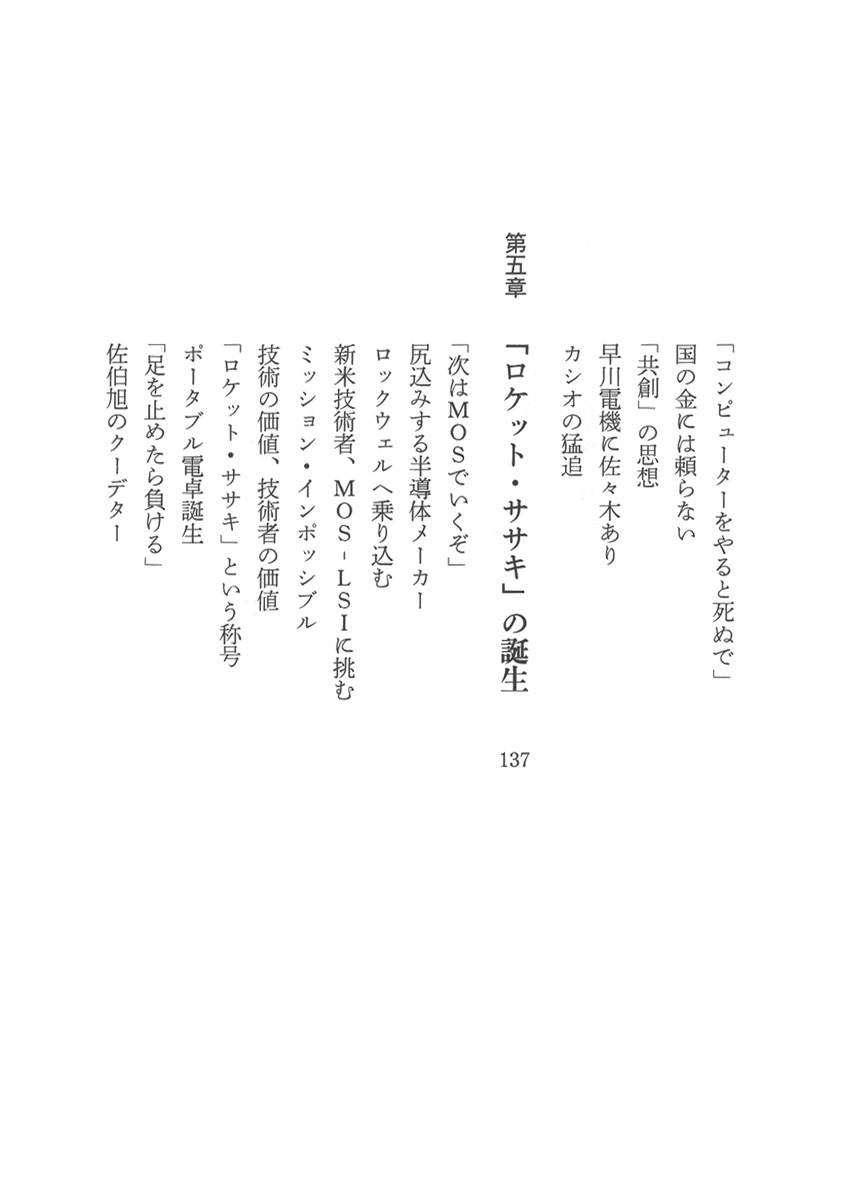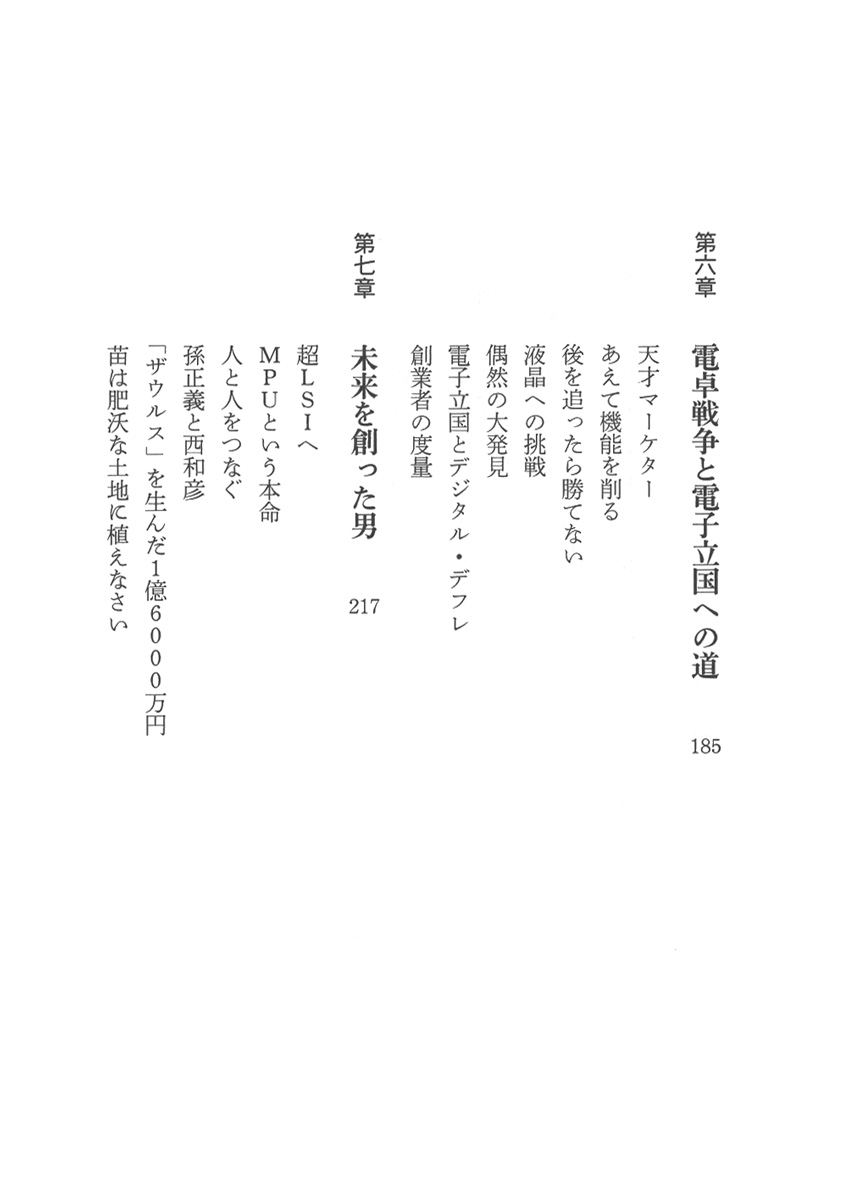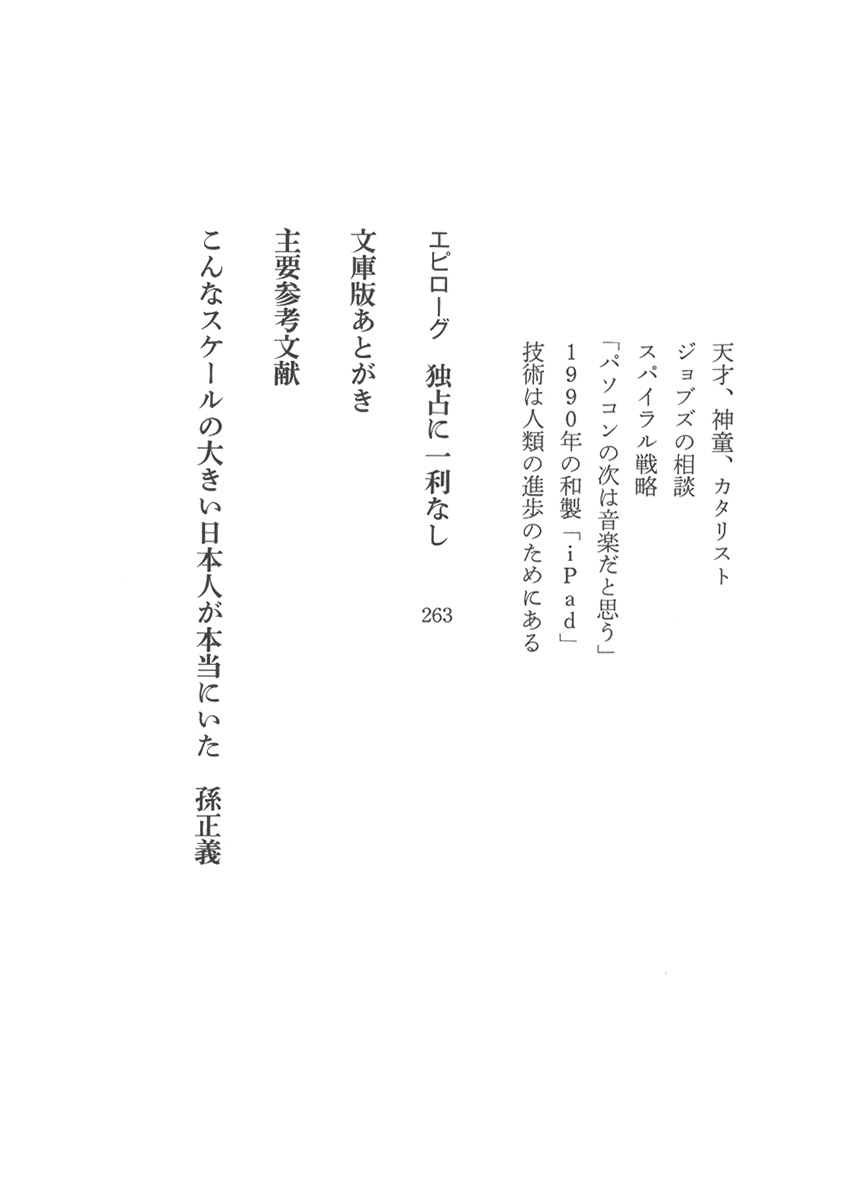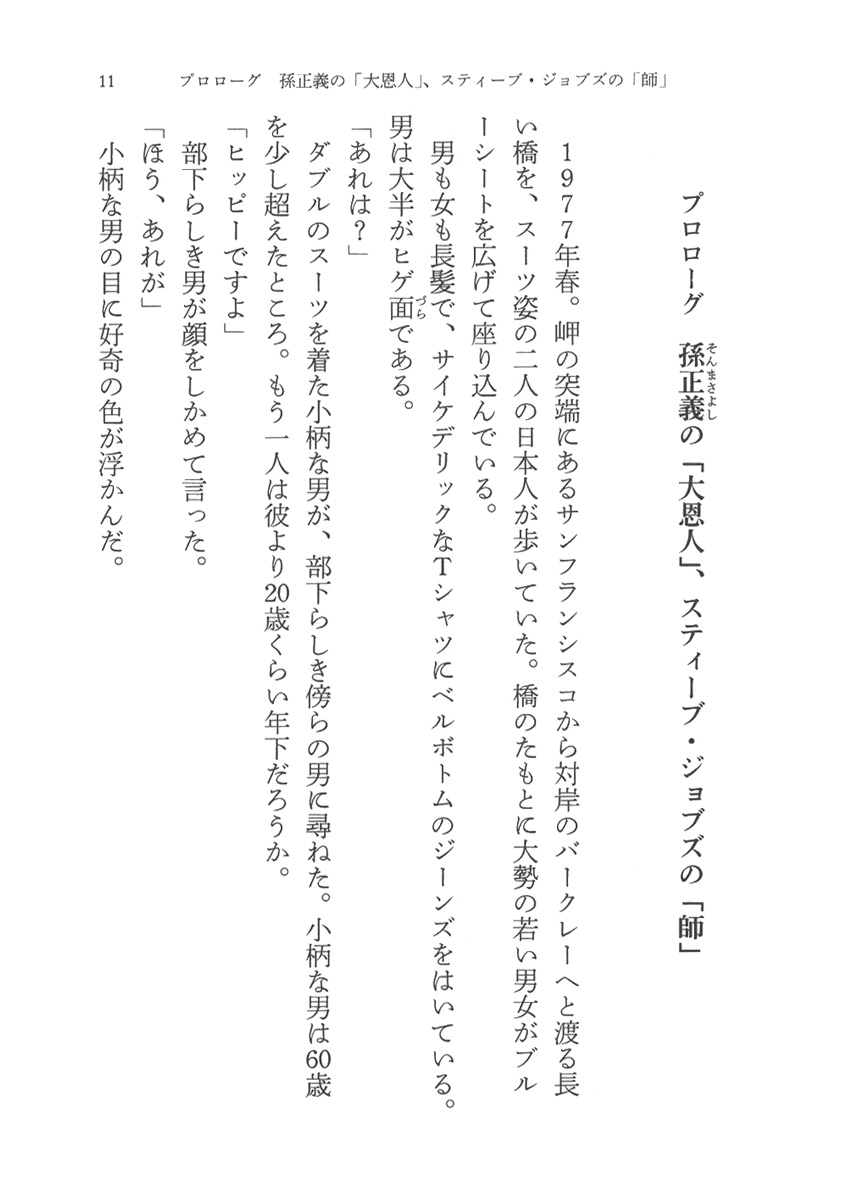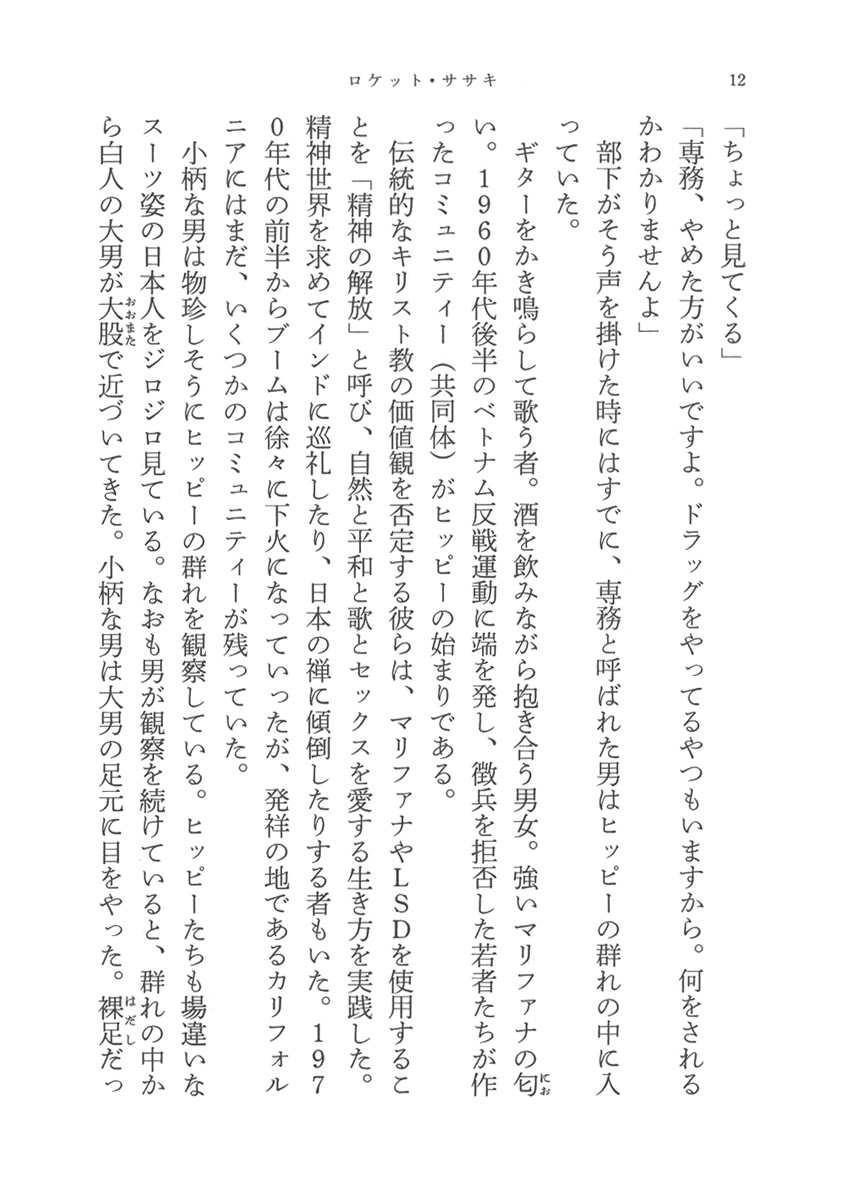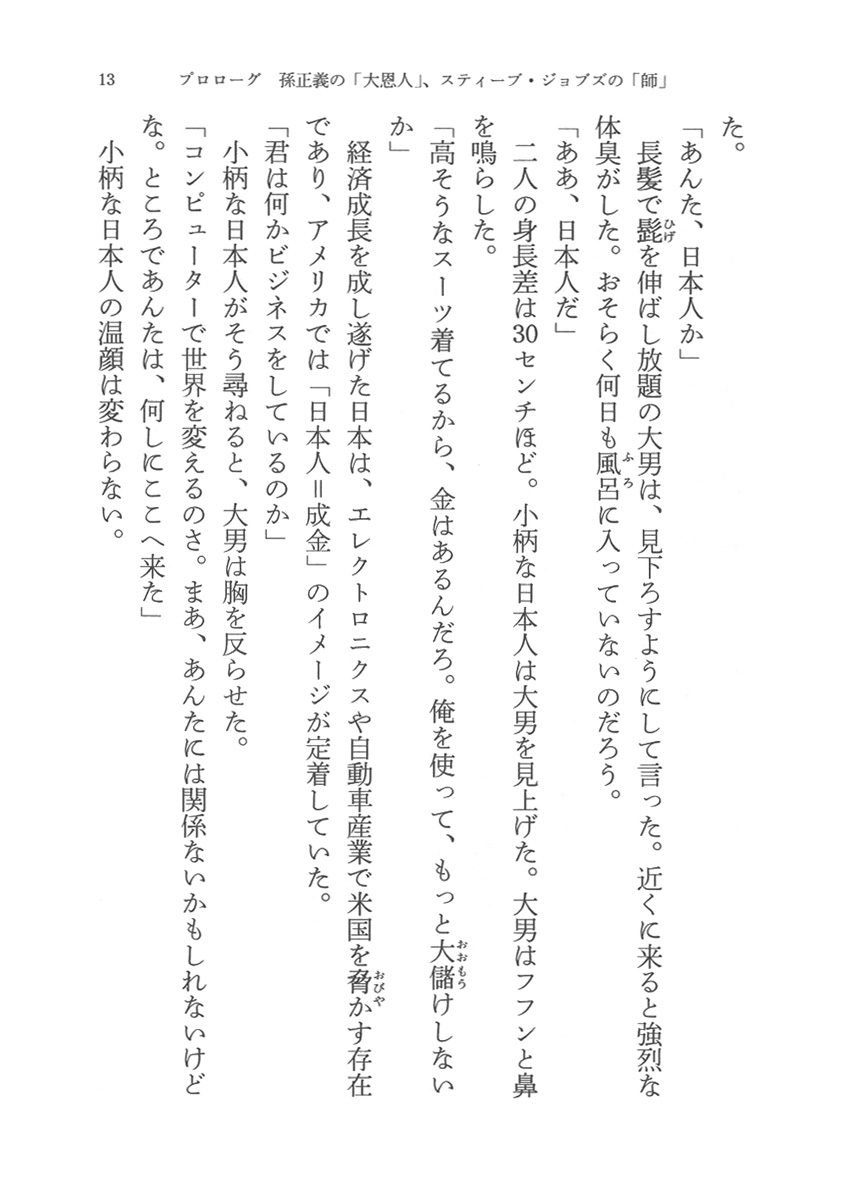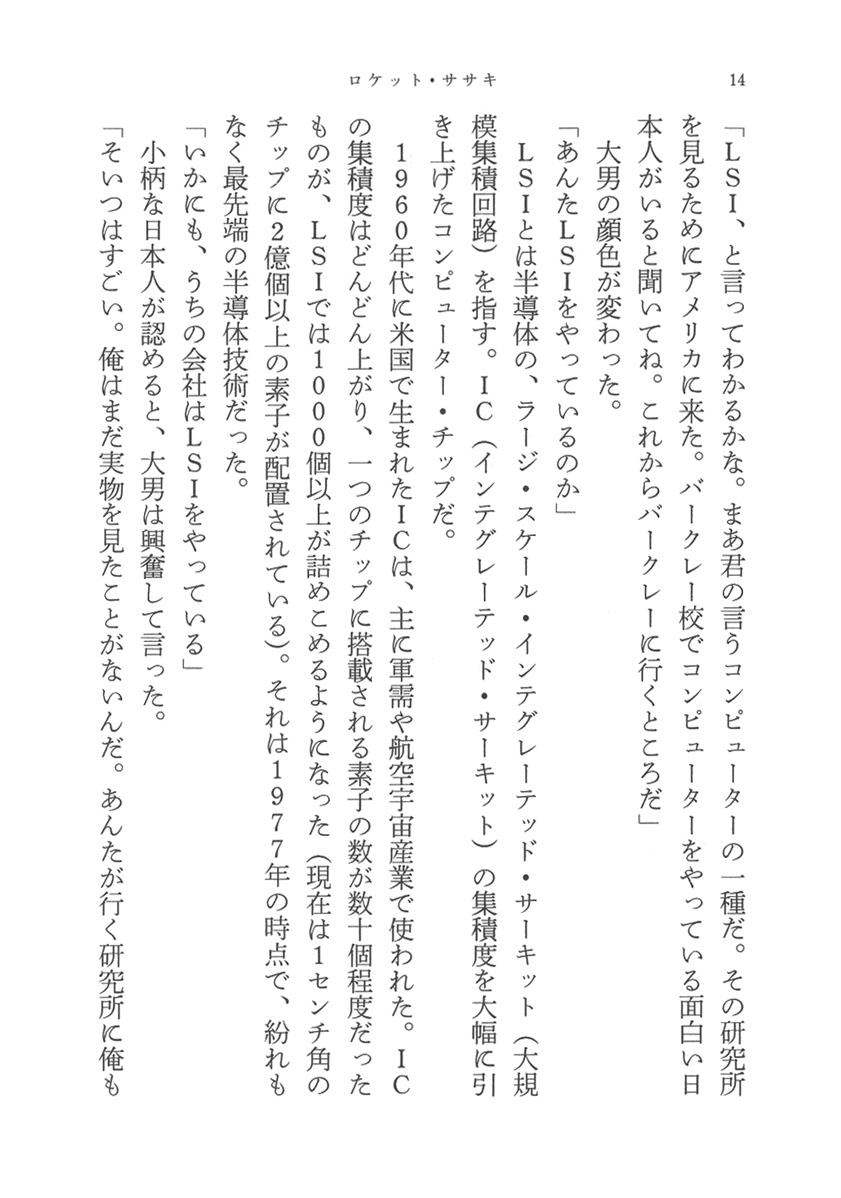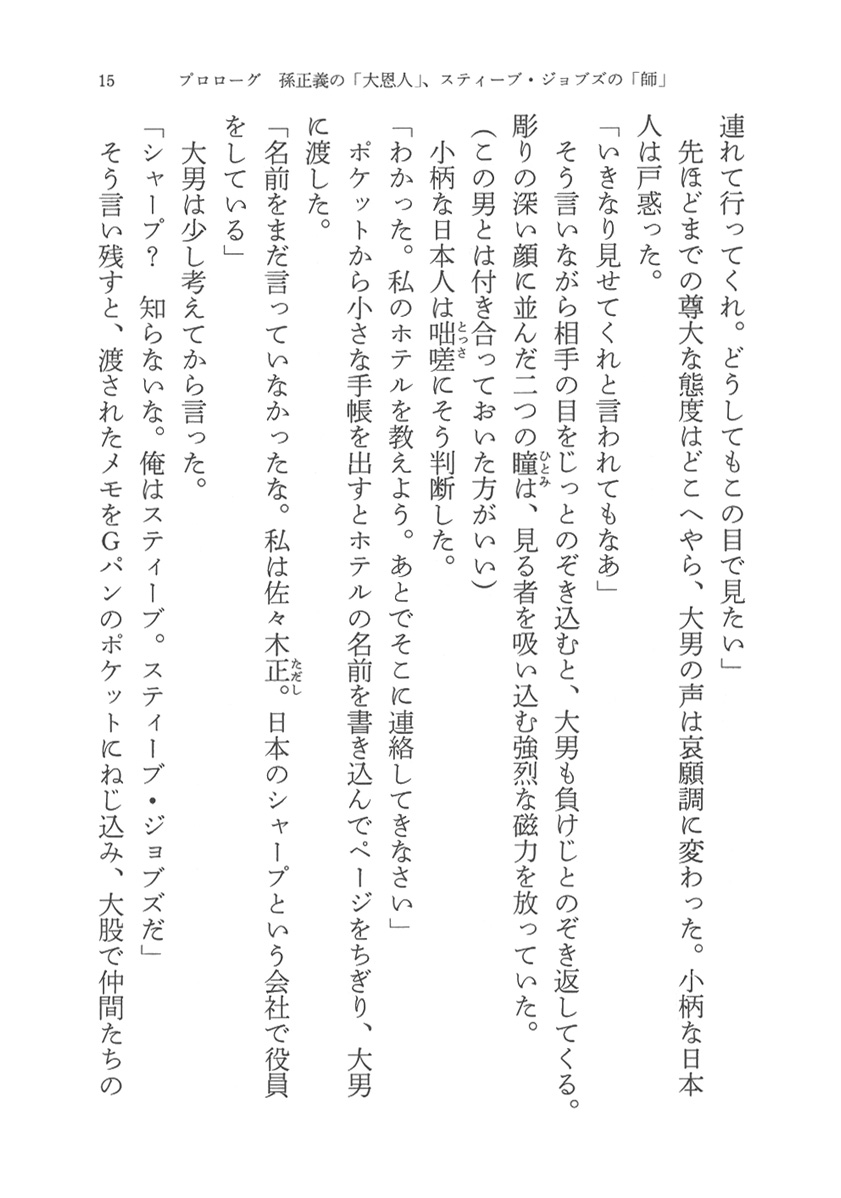プロローグ 孫正義の「大恩人」、スティーブ・ジョブズの「師」
1977年春。岬の突端にあるサンフランシスコから対岸のバークレーへと渡る長い橋を、スーツ姿の二人の日本人が歩いていた。橋のたもとに大勢の若い男女がブルーシートを広げて座り込んでいる。
男も女も長髪で、サイケデリックなTシャツにベルボトムのジーンズをはいている。男は大半がヒゲ面である。
「あれは?」
ダブルのスーツを着た小柄な男が、部下らしき傍らの男に尋ねた。小柄な男は60歳を少し超えたところ。もう一人は彼より20歳くらい年下だろうか。
「ヒッピーですよ」
部下らしき男が顔をしかめて言った。
「ほう、あれが」
小柄な男の目に好奇の色が浮かんだ。
「ちょっと見てくる」
「専務、やめた方がいいですよ。ドラッグをやってるやつもいますから。何をされるかわかりませんよ」
部下がそう声を掛けた時にはすでに、専務と呼ばれた男はヒッピーの群れの中に入っていた。
ギターをかき鳴らして歌う者。酒を飲みながら抱き合う男女。強いマリファナの匂い。1960年代後半のベトナム反戦運動に端を発し、徴兵を拒否した若者たちが作ったコミュニティー(共同体)がヒッピーの始まりである。
伝統的なキリスト教の価値観を否定する彼らは、マリファナやLSDを使用することを「精神の解放」と呼び、自然と平和と歌とセックスを愛する生き方を実践した。精神世界を求めてインドに巡礼したり、日本の禅に傾倒したりする者もいた。1970年代の前半からブームは徐々に下火になっていったが、発祥の地であるカリフォルニアにはまだ、いくつかのコミュニティーが残っていた。
小柄な男は物珍しそうにヒッピーの群れを観察している。ヒッピーたちも場違いなスーツ姿の日本人をジロジロ見ている。なおも男が観察を続けていると、群れの中から白人の大男が大股で近づいてきた。小柄な男は大男の足元に目をやった。裸足だった。
「あんた、日本人か」
長髪で髭を伸ばし放題の大男は、見下ろすようにして言った。近くに来ると強烈な体臭がした。おそらく何日も風呂に入っていないのだろう。
「ああ、日本人だ」
二人の身長差は30センチほど。小柄な日本人は大男を見上げた。大男はフフンと鼻を鳴らした。
「高そうなスーツ着てるから、金はあるんだろ。俺を使って、もっと大儲けしないか」
経済成長を成し遂げた日本は、エレクトロニクスや自動車産業で米国を脅かす存在であり、アメリカでは「日本人=成金」のイメージが定着していた。
「君は何かビジネスをしているのか」
小柄な日本人がそう尋ねると、大男は胸を反らせた。
「コンピューターで世界を変えるのさ。まあ、あんたには関係ないかもしれないけどな。ところであんたは、何しにここへ来た」
小柄な日本人の温顔は変わらない。
「LSI、と言ってわかるかな。まあ君の言うコンピューターの一種だ。その研究所を見るためにアメリカに来た。バークレー校でコンピューターをやっている面白い日本人がいると聞いてね。これからバークレーに行くところだ」
大男の顔色が変わった。
「あんたLSIをやっているのか」
LSIとは半導体の、ラージ・スケール・インテグレーテッド・サーキット(大規模集積回路)を指す。IC(インテグレーテッド・サーキット)の集積度を大幅に引き上げたコンピューター・チップだ。
1960年代に米国で生まれたICは、主に軍需や航空宇宙産業で使われた。ICの集積度はどんどん上がり、一つのチップに搭載される素子の数が数十個程度だったものが、LSIでは1000個以上が詰めこめるようになった(現在は1センチ角のチップに2億個以上の素子が配置されている)。それは1977年の時点で、紛れもなく最先端の半導体技術だった。
「いかにも、うちの会社はLSIをやっている」
小柄な日本人が認めると、大男は興奮して言った。
「そいつはすごい。俺はまだ実物を見たことがないんだ。あんたが行く研究所に俺も連れて行ってくれ。どうしてもこの目で見たい」
先ほどまでの尊大な態度はどこへやら、大男の声は哀願調に変わった。小柄な日本人は戸惑った。
「いきなり見せてくれと言われてもなあ」
そう言いながら相手の目をじっとのぞき込むと、大男も負けじとのぞき返してくる。彫りの深い顔に並んだ二つの瞳は、見る者を吸い込む強烈な磁力を放っていた。
(この男とは付き合っておいた方がいい)
小柄な日本人は咄嗟にそう判断した。
「わかった。私のホテルを教えよう。あとでそこに連絡してきなさい」
ポケットから小さな手帳を出すとホテルの名前を書き込んでページをちぎり、大男に渡した。
「名前をまだ言っていなかったな。私は佐々木正。日本のシャープという会社で役員をしている」
大男は少し考えてから言った。
「シャープ? 知らないな。俺はスティーブ。スティーブ・ジョブズだ」
そう言い残すと、渡されたメモをGパンのポケットにねじ込み、大股で仲間たちのもとへと帰って行った。
佐々木正はシャープの技術担当専務である。カシオ計算機との激しい「電卓戦争」でシャープの陣頭指揮を執り、後に「電子工学の父」とも呼ばれた。電卓は当時、電子工学のあらゆる先端技術が詰め込まれた最先端のハイテク商品だった。
1964年に早川電機が発売した世界初のオールトランジスタ電卓は、重さ25キログラムで価格は53万5000円。机の上を占拠する大きさで、自動車が1台買える値段だった。
だが激しい開発競争の中で、電卓は劇的に小さく、安くなっていく。それを可能にしたのがLSIだ。軍需産業でしか使われていなかったLSIを「電卓に使う」と決めたのが佐々木である。
シャープは1969年に世界初のLSI電卓(9万9800円)を発売した。製品の重さはわずか1・4キログラム。わずか5年で重さは18分の1、価格は5分の1になった。その後も電卓は進化を続け、1985年にはついに、胸ポケットに入る重さ11グラムのカード電卓(7800円)が発売された。凄まじい技術革新である。
20年間に及ぶ「電卓戦争」は日本メーカーの独壇場だった。半導体を発明した米国も、電卓を発明した英国も、日本メーカーが仕掛ける激烈な小型・低価格化競争についていけず、続々と脱落した。電卓は日本が外貨を獲得する輸出産業としても、重要な役割を担った。
まだパソコンも携帯電話もゲーム機もなかった時代。電卓は民生分野における半導体の最大市場であった。将来有望な電卓市場には、最盛期に国内だけで約60社が参入した。その中にはキヤノン、ソニーといった大手メーカーの姿もあったが、「軽薄短小」を極限まで追求する激烈な開発競争に耐えられずに落伍していき、最後はシャープとカシオ計算機のマッチレースになった。
電卓の激しい価格戦争の間に、頭脳であるLSIは爆発的な進化を遂げた。これが後のパソコン、携帯電話、スマートフォンへとつながっていく。
電卓が生んだイノベーションはLSIだけではない。
電卓を薄く軽くするために、蛍光管より消費電力の少ない液晶表示装置が生み出された。これがやがて液晶テレビやスマートフォンに進化していく。薄く、軽くを追求するため民生品で初めて太陽電池を使ったのも電卓である。いまや風力発電と並び「再生エネルギーの柱」とされる太陽電池だが、電卓がなければ量産されることはなかった。
半導体産業を育てた電卓はハイテク技術の孵化器であり、電卓戦争は様々なデバイスを産み落とすことで、現在のインターネット社会の礎を築いた。電卓戦争でシャープの開発部門の責任者を務めた佐々木は、まさに時代の先頭を走っていた。
その電卓戦争も、佐々木がバークレー校を訪れた1977年には、ほぼ終熄していた。佐々木はLSIを使った次の事業を模索するために、米国のLSI工場を回っていたのである。
その頃、アメリカでは半導体を使った新しい産業の姿が、おぼろげに浮かびつつあった。佐々木と出会う2ヶ月前の1977年1月、スティーブ・ジョブズは、親友で天才エンジニアのスティーブ・ウォズニアック、投資家のマイク・マークラと資金を出し合ってアップル・コンピューターを設立した。
1975年、「アルテア8800」というコンピューターの組み立てキットが売り出された。ウォズニアックはその廉価版を開発し、コンピューターの愛好家が集まるシリコンバレーの「ホームブリュー・コンピューター・クラブ」で発表。絶賛された。
ジョブズはウォズニアックが作った「それ」が「ビジネスになる」ことに気づき、個人向けコンピューター「アップルⅠ」として666・66ドルで発売した。キーボードもモニターも付いていない、今思えば不完全な製品だったが、それでも一部のマニアには受け入れられ、ジョブズたちはかなりの額の利益を手にした。
その資金を元手に、より本格的なパーソナル・コンピューター「アップルⅡ」を開発・生産するため、ジョブズはウォズニアックとマークラを引き込んでアップルという会社を立ち上げた。
会社と言っても本社はジョブズの実家であり、開発拠点はガレージだった。電話の対応は母が手伝い、部品を基板に乗せる仕事は妹にやらせた。
ヒッピーに代表されるカウンターカルチャー(主流の、体制的な文化に対抗する価値観や様式をもった文化)にどっぷり浸かったジョブズは、「精神の自由」を求めてドラッグでトリップし、インドを放浪した。
果実食主義(動物と植物を殺す行為に基づく食べものを摂取せず、果実、種のみを食べる)を信奉し、「満月の夜に処女が摘んだ葉っぱしか食べない」と言って母親を困らせた。「果実食主義者には体臭がない」と言い張り、シャワーも週に一度しか浴びなかった。
インド放浪から戻ると、鈴木大拙と並ぶ欧米への禅の伝道者である鈴木俊隆が開いたサンフランシスコ禅センターに通い始めた。禅への傾倒はのちにアップルの経営者として追求した「ミニマリズム」(製品から余分な機能をそぎ落とし必要最小限にすること)につながっていく。
佐々木は日本人の中でも小柄な方で、髪を七三に分け、度の強いメガネをかけていた。アメリカの風刺漫画で描かれる日本人にそっくりである。サンフランシスコの橋のたもとでジョブズが佐々木に声をかけたのは、創業したばかりのアップルがコンピューターを作る工場をもつための、まとまった金が必要だったからだ。高度成長でにわかに金持ちになった日本企業を利用してやろうという魂胆である。
佐々木正がジョブズの話に耳を傾けたのは「電卓の次」を探していたからである。シャープは電卓戦争を勝ち抜くため、奈良県の天理市に社運をかけて巨大なLSI工場を建てた。これが当たって熾烈な競争を勝ち抜いたのだが、電卓需要がピークを過ぎると大きすぎる生産能力が重荷になった。早く次の市場を生み出さないと、せっかくの工場が金食い虫になってしまう。
そんな佐々木が目をつけたのが、このころ米国各地で産声をあげたばかりのコンピューター同好会である。バークレー校にはその総本山と言える「ホームブリュー・コンピューター・クラブ」があり、後で知ったことだが、ジョブズとウォズニアックもそのメンバーだった。
ホームブリューとは「自家醸造」、つまり手作りのことである。当時、コンピューターは国の研究機関や大企業が使うもので、個人が所有できるものではなかった。「アップルⅠ」を開発した時、ウォズニアックは自分の勤め先であるヒューレット・パッカード(HP)に試作機を持ち込んだが、まるで相手にされなかった。しかし電卓戦争のお陰で頭脳となるLSIが小さく、安くなり、新しい物好きの若者たちが、自分のためのコンピューターを自分の手で作り始めた。その中心がホームブリュー・コンピューター・クラブであった。
最初は車1台分の値段で企業にしか手が届かなかった電卓を「八百屋のおカミさんが使える製品」にした経験を持つ佐々木には「コンピューターもいずれ個人の持ち物になる」という予感があった。
自分と同じことを考える若者がアメリカにはたくさんいるらしい。同好の士を求めて佐々木はホームブリュー・コンピューター・クラブを訪れた。
佐々木がバークレー校を訪れたのには、もう一つの理由があった。そこに「面白い日本人がいる」と知り合いに聞いたからだ。
それを佐々木に教えたのは、のちにアスキーを創業し「パソコンの天才」と呼ばれた西和彦である。当時、早稲田大学理工学部の学生だった西もまたコンピューターに魅入られ、自分が在学している早稲田ではなく、いつでもコンピューターに触れる東京電機大学の教授の部屋に入り浸っていた。
神戸にある須磨学園の理事長をしていた西の父親は佐々木の知り合いだった。その縁で、西は物心がついた頃から「お父ちゃんの友達で、どっかの会社の偉い人」という感じで「佐々木のおじさん」を知っていた。
コンピューター三昧の学生生活を送っていた西は、米国のコンピューター雑誌を愛読しており、米国のパソコン同好会にも知り合いが大勢いた。そして彼らからこんな話を聞いたのだ。
「カリフォルニア大学のバークレー校に最近、変な日本人が編入してきたんですわ。パソコン同好会にも首を突っ込んで、大きな顔をしているらしい」
よくしゃべる西は、「佐々木のおじさん」にその男の話をした。
「確か孫とか、いう名前ですわ。日本人じゃないかもしれませんね。とにかく顔の広い奴だそうです」
何気ない会話だったが、孫という名前が佐々木の心に引っかかった。
「ついでだから、会ってみるか」
米国のLSI研究所の視察に来た佐々木は、西に教えられた住所を頼りに、バークレーにある孫のアパートまで足を伸ばした。
孫のアパートはバークレー校の門の真ん前にあるタバコ屋の2階だった。コンピューター関連の雑誌や書籍が雑然と積まれた狭い部屋だった。佐々木は挨拶もそこそこに、ここへ来る途中に出会った大男の話をした。
「妙なルンペンが寄ってきてな、大儲けさせてやると言うんだよ」
佐々木と同じくらい小柄で、髪を肩まで伸ばした孫は、面白そうに佐々木の話を聞いた。
「ここは、そんなやつばかりですけどね」
「で、孫くんと言ったかな。君はここで何をしている」
「コンピューターですよ。LSIって知ってますか。この前、雑誌でその拡大写真を見たんだけど、僕は涙が出た。こんなものを作る人類はすごいなって。このLSIのおかげで、これからはコンピューターがどんどん安く、小さくなって、それを個人が持つようになる。そしたら革命が起きるんですよ」
「そうか。革命か」
「ええ革命です。情報革命です」
佐々木は自分がLSIビジネスのど真ん中にいることをあえて話さなかった。クリクリとした目を見開いて、唾を飛ばしながら、まるでそれが明日にでも実現しそうな勢いで、途方もない未来の話をする。この若者の話を黙って聞いていたいと思ったからだ。
二人が話を始めてしばらくすると、もう一人の若者がドアを蹴飛ばすようにして飛び込んできた。
「おいマサ、TI(米半導体大手のテキサス・インスツルメンツ)が電子翻訳機を出すって聞いたぞ」
「本当か、ルー。じゃあ、俺たちも急がないとな」
ルーと呼ばれた中国系の青年は、佐々木の存在など気にも留めず、興奮しきった様子で孫と話し込み始めた。
「私はこのへんで失礼するよ」
佐々木の声は二人の耳に全く届いていない。佐々木は、やれやれというように首を振り、アパートの階段を降りながら、腹の底から湧き上がる愉快な気分を抑えきれずにいた。
(今日は面白い男に会う日だ)
のちにソフトバンクを立ち上げ日本を代表する起業家となる孫正義は、佐々木を「大恩人」と呼ぶようになる。iPhoneやiPadを世に送り出し、我々の生活を一変させたスティーブ・ジョブズもまた、佐々木を「師」と仰いだ。
子供の頃から佐々木を知っていた西和彦はアスキーを興した後にマイクロソフトの副社長にもなり、ジョブズの宿命のライバル、ビル・ゲイツとともにパソコン革命を巻き起こす。
だが、この時点ではまだ誰も、自分の運命を知らない。
20代のジョブズ、孫、ゲイツ、西は、人間よりはるかに速く計算をこなす8ミリ角のチップに魅入られてコンピューターの世界に足を踏み入れた。
起業家たちの名は歴史に刻まれたが、彼らが革命を起こすのに必要なチップを作った男の名は知られていない。
そのチップを世に送り出したのが佐々木正である。佐々木が蒔いた種は、ジョブズ、孫、ゲイツ、西に受け継がれ、やがてインターネット革命という、とてつもなく大きなうねりとなって世界を飲み込んでゆく。