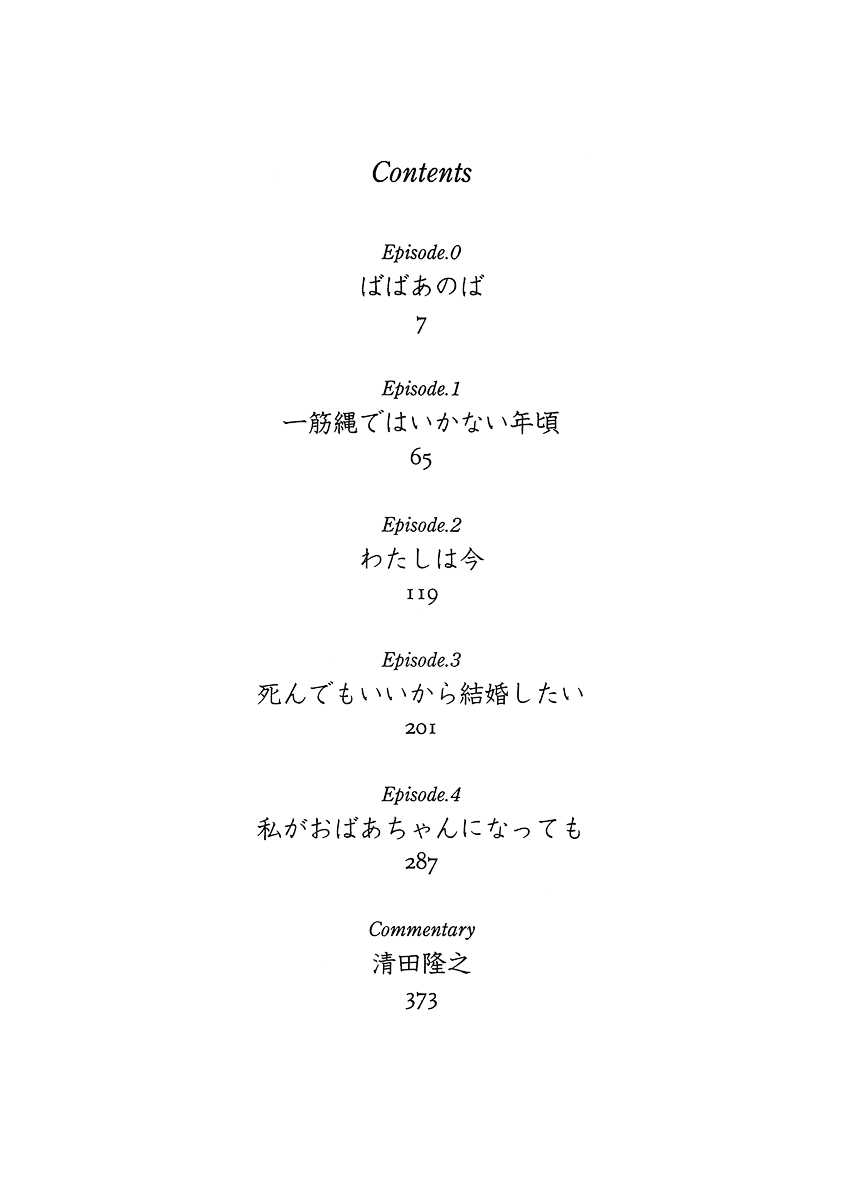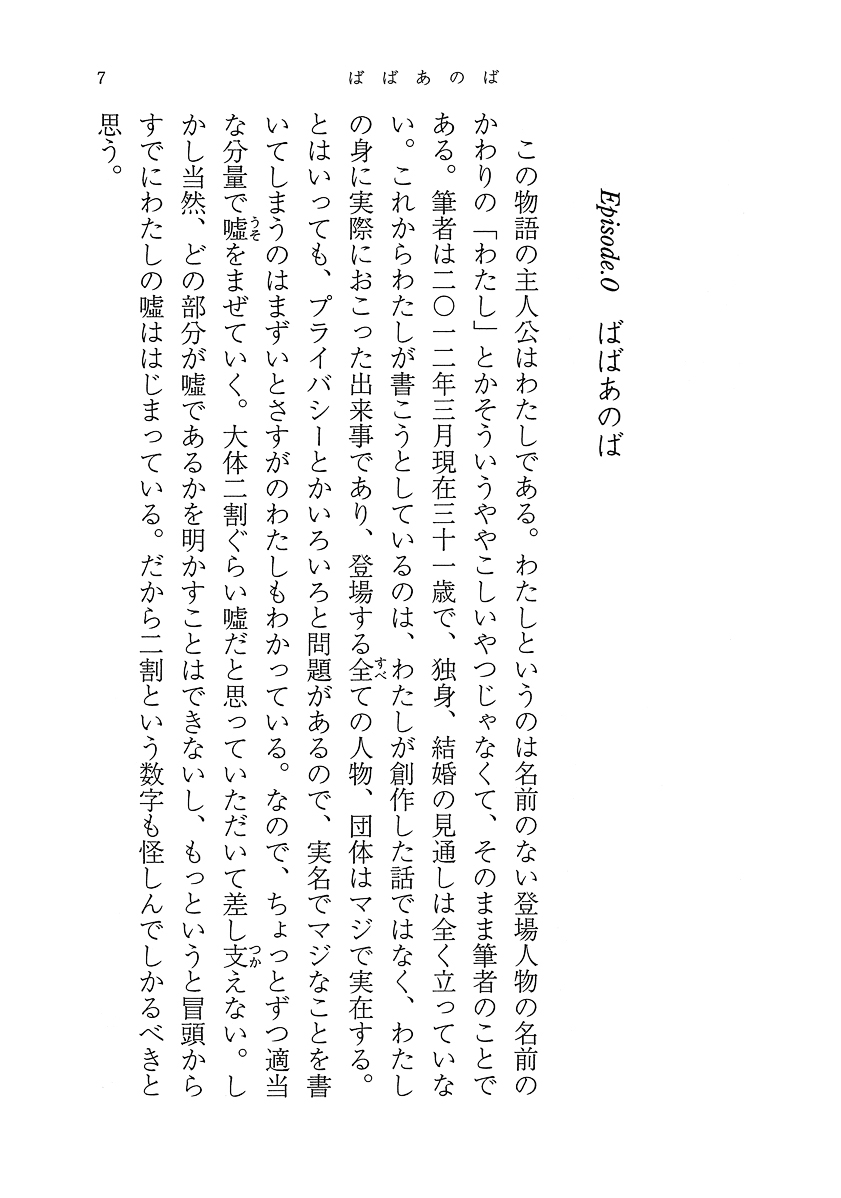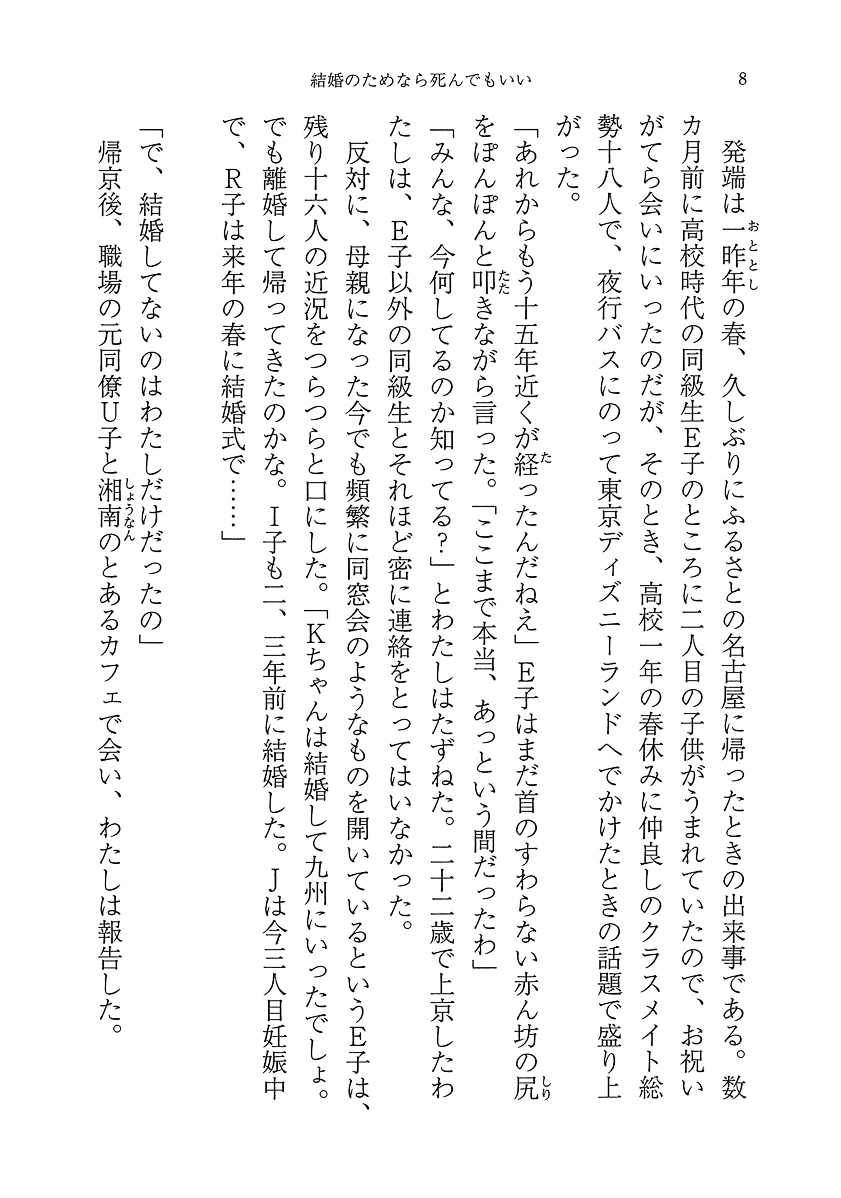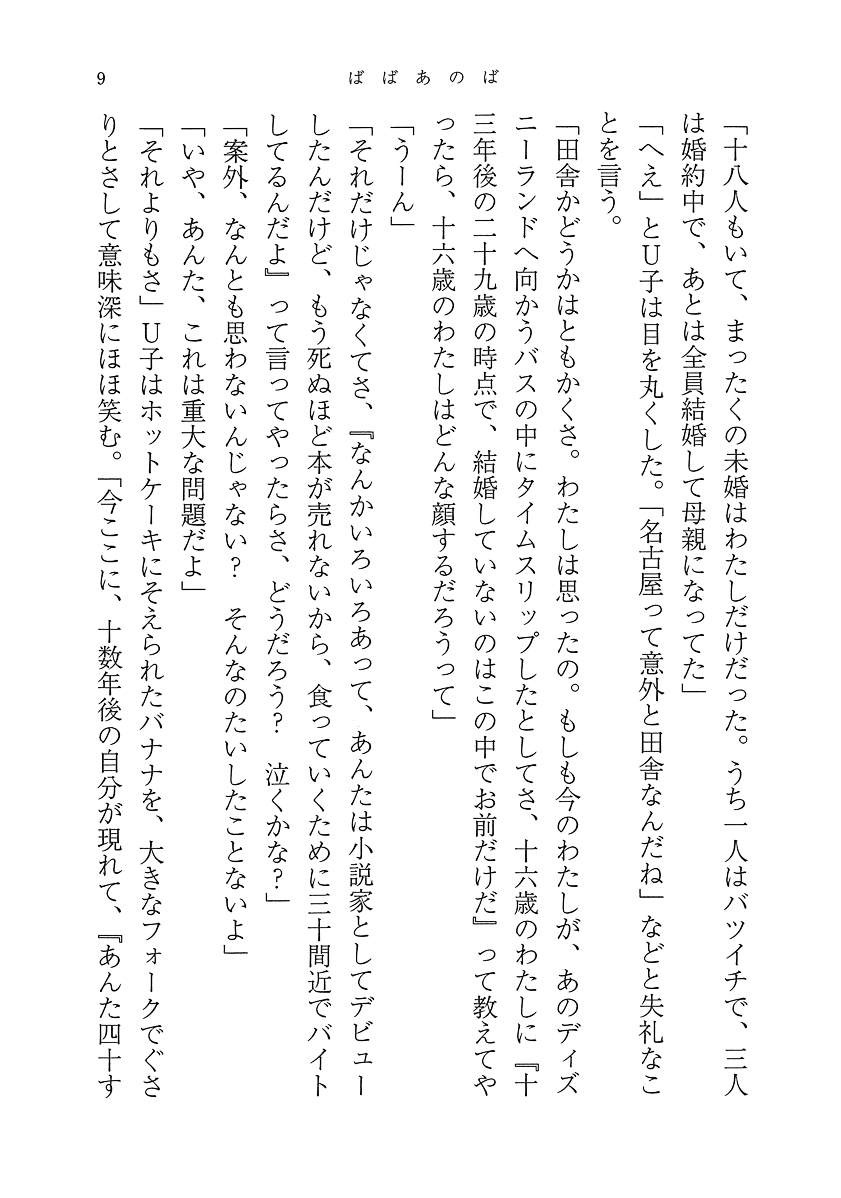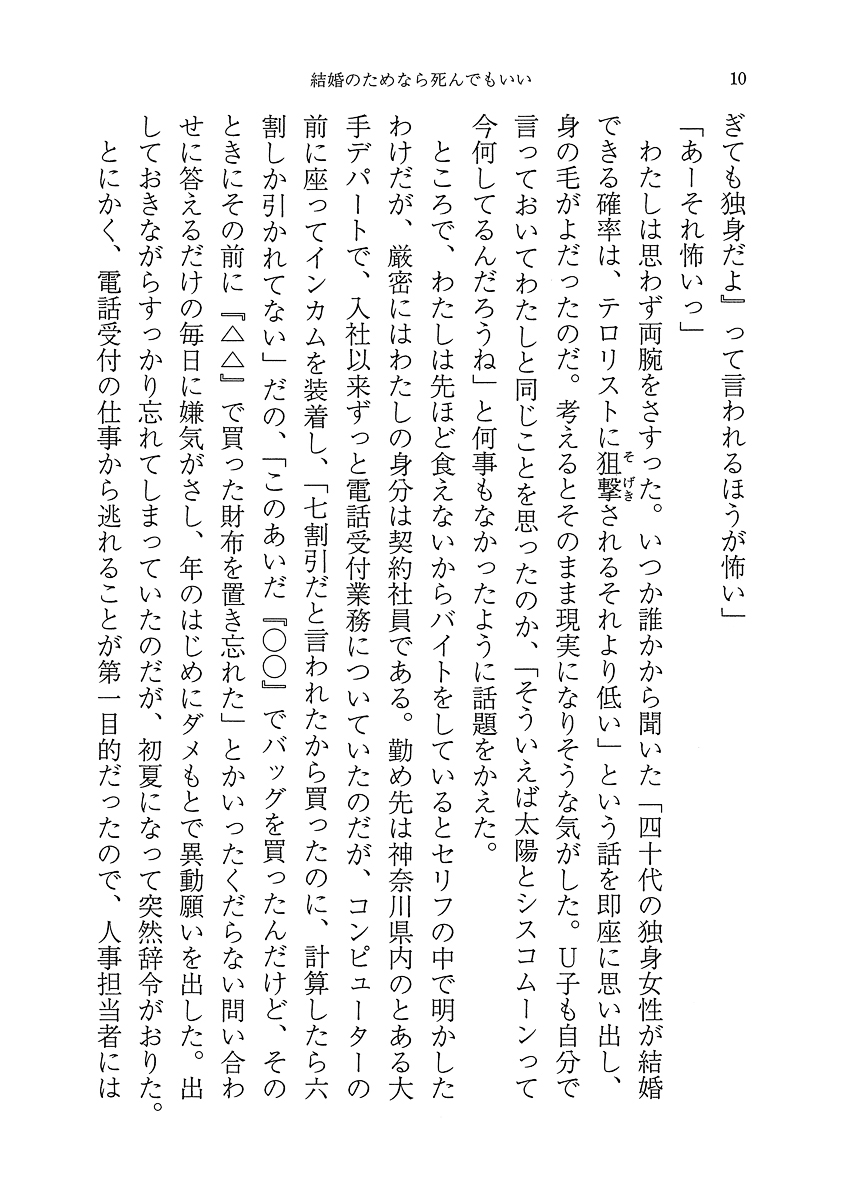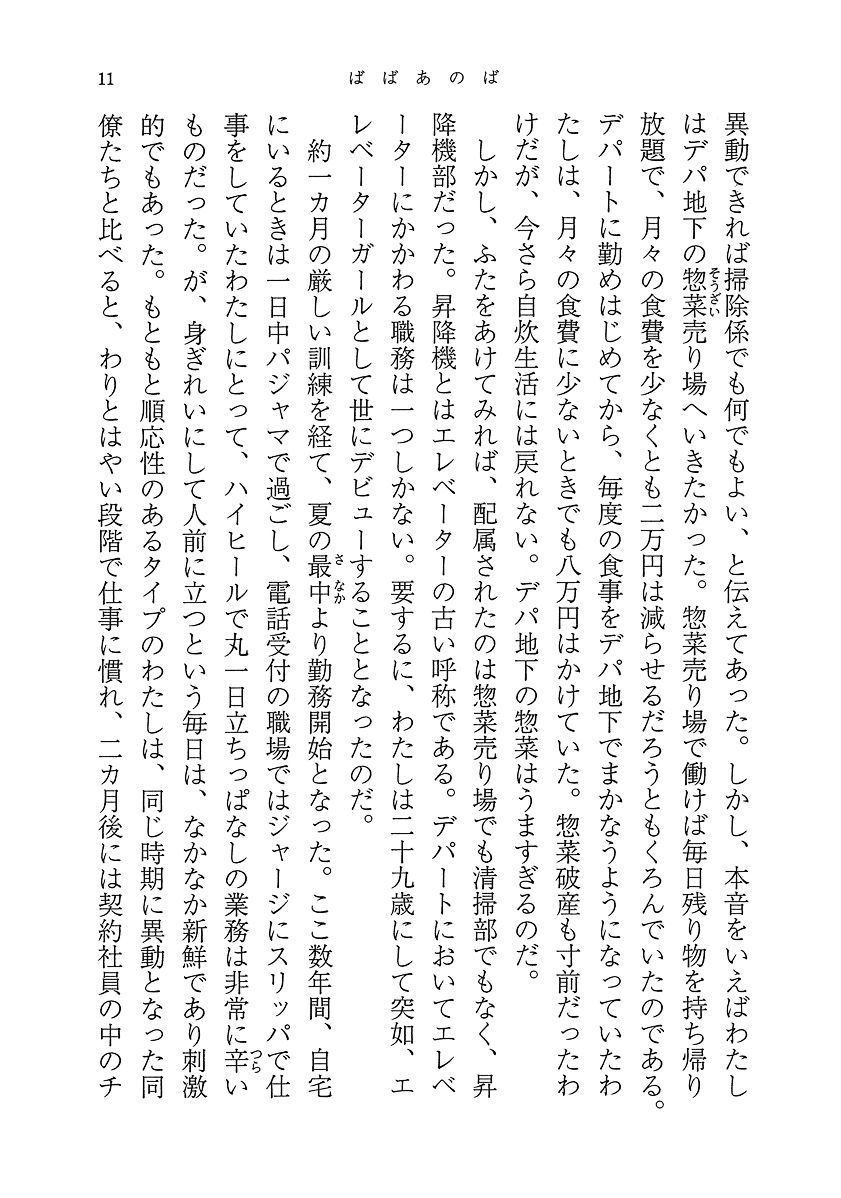Episode.0 ばばあのば
この物語の主人公はわたしである。わたしというのは名前のない登場人物の名前のかわりの「わたし」とかそういうややこしいやつじゃなくて、そのまま筆者のことである。筆者は二〇一二年三月現在三十一歳で、独身、結婚の見通しは全く立っていない。これからわたしが書こうとしているのは、わたしが創作した話ではなく、わたしの身に実際におこった出来事であり、登場する
発端は
「あれからもう十五年近くが
「みんな、今何してるのか知ってる?」とわたしはたずねた。二十二歳で上京したわたしは、E子以外の同級生とそれほど密に連絡をとってはいなかった。
反対に、母親になった今でも頻繁に同窓会のようなものを開いているというE子は、残り十六人の近況をつらつらと口にした。「Kちゃんは結婚して九州にいったでしょ。でも離婚して帰ってきたのかな。I子も二、三年前に結婚した。Jは今三人目妊娠中で、R子は来年の春に結婚式で……」
「で、結婚してないのはわたしだけだったの」
帰京後、職場の元同僚U子と
「十八人もいて、まったくの未婚はわたしだけだった。うち一人はバツイチで、三人は婚約中で、あとは全員結婚して母親になってた」
「へえ」とU子は目を丸くした。「名古屋って意外と田舎なんだね」などと失礼なことを言う。
「田舎かどうかはともかくさ。わたしは思ったの。もしも今のわたしが、あのディズニーランドへ向かうバスの中にタイムスリップしたとしてさ、十六歳のわたしに『十三年後の二十九歳の時点で、結婚していないのはこの中でお前だけだ』って教えてやったら、十六歳のわたしはどんな顔するだろうって」
「うーん」
「それだけじゃなくてさ、『なんかいろいろあって、あんたは小説家としてデビューしたんだけど、もう死ぬほど本が売れないから、食っていくために三十間近でバイトしてるんだよ』って言ってやったらさ、どうだろう? 泣くかな?」
「案外、なんとも思わないんじゃない? そんなのたいしたことないよ」
「いや、あんた、これは重大な問題だよ」
「それよりもさ」U子はホットケーキにそえられたバナナを、大きなフォークでぐさりとさして意味深にほほ笑む。「今ここに、十数年後の自分が現れて、『あんた四十すぎても独身だよ』って言われるほうが怖い」
「あーそれ怖いっ」
わたしは思わず両腕をさすった。いつか誰かから聞いた「四十代の独身女性が結婚できる確率は、テロリストに
ところで、わたしは先ほど食えないからバイトをしているとセリフの中で明かしたわけだが、厳密にはわたしの身分は契約社員である。勤め先は神奈川県内のとある大手デパートで、入社以来ずっと電話受付業務についていたのだが、コンピューターの前に座ってインカムを装着し、「七割引だと言われたから買ったのに、計算したら六割しか引かれてない」だの、「このあいだ『○○』でバッグを買ったんだけど、そのときにその前に『△△』で買った財布を置き忘れた」とかいったくだらない問い合わせに答えるだけの毎日に嫌気がさし、年のはじめにダメもとで異動願いを出した。出しておきながらすっかり忘れてしまっていたのだが、初夏になって突然辞令がおりた。
とにかく、電話受付の仕事から逃れることが第一目的だったので、人事担当者には異動できれば掃除係でも何でもよい、と伝えてあった。しかし、本音をいえばわたしはデパ地下の
しかし、ふたをあけてみれば、配属されたのは惣菜売り場でも清掃部でもなく、昇降機部だった。昇降機とはエレベーターの古い呼称である。デパートにおいてエレベーターにかかわる職務は一つしかない。要するに、わたしは二十九歳にして突如、エレベーターガールとして世にデビューすることとなったのだ。
約一カ月の厳しい訓練を経て、夏の
そんなある日のこと。いつも通りわたしはエレベーターに乗り込んで、上にいったり下にいったりしていた。その頃になると、たとえばエレベーターがとまってドアが開いたとき、そこに誰もいなくても、一応決まりで「下へまいります」などとフロアに向かって(しかも例のあのひっくりかえったような変な声で)言わなければならない妙な恥ずかしさも克服できていたし、エレベーター内が無人になったときには、ちょっとしたものまねの練習をしてみたりする余裕も生まれたりと、われながらなかなかにエレガぶりが板についてきた。
午後二時、休憩を終えたわたしは同僚と交代するため、最上階のエレベーターホールで待機していた。しばらくしてチーンと音が鳴り、ドアが開いて中にいる客の全員が出てきた。同僚と目礼だけして入れ違いに乗り込みながら、フロアに向かって「お乗りになる方はいらっしゃいませんか」と声をかける。
誰もいないと思ったのに、ちょうどわたしと対角線上の角に小柄な女性がぽつんと立っていた。年齢不詳。まず最初にその言葉が浮かんだ。季節外れの赤いタートルネックのセーターを着ており、おそらくノーブラ。腹周りの肉づきはたっぷりとしているが、脚や腕の先は細いというアンバランスな体型をしている。肩まで伸びた髪は総白髪。その割に、白く化粧気のない肌のつやは悪くなく、そういったちぐはぐさが女の印象をより怪しげなものにしていた。
女は猫背、というより前のめりといったほうが正しいような体勢で、じっとこちらを見つめていた。本当なら「ご希望の階数をおっしゃってください」と言わなければならないのに、なぜか口がかたまったようになってしまって何も言えなかった。しばらくして、女の顔にどことなく見覚えがあるような気がしはじめた。しかも、最近知ったばかりの顔ではないような感じがする。もっと昔、もっと幼い頃に慣れ親しんだ人のような……自分と深くつながりのある、とても大事な人に似ているような……じっと見つめているとなんとなく
「わたしはね」
唐突に女が口を開き、一歩前に踏み出した。そのときになって急に恐ろしくなったわたしは、あわてて振り返って「開」ボタンを押した。しかし開かない。連打しても開かない。
「わたしはね」
また一歩近づく。
「わたしはね、今、五十五歳なんだよ」
だから何だ、と即座に思ったがわたしはかろうじてほほ笑み返した。少し落ち着いてきたようだ。
「お客様、ご希望の階数を……」
「もうあんた、わかっとるんだろう」
「お客様……」
「もう気づいとるんだろう」
「あの、何のことだか」
「わたしはね、五十五歳になったあんた自身なんだよ」
このくそばばあ。わたしは腹の中で舌打ちした。変な
「あんた、この間、もし四十代になった自分が未来から現れたらどうするって話を、友達としとったね」
なぜ知っている。どこで聞いていた。そのとき、さっき感じた懐かしさの理由に突然思い至った。母の実家の仏壇の部屋に飾られていたいくつかの遺影。その中の右から三番目の写真の人に女はそっくりなのだった。自分にとって何にあたる人なのかは随分昔に聞かされたきりなので覚えていないが、子供の頃から、よく似ているだの、年をとったらお前はあんな感じになるだろうなどとよく言われていた。
まさか、本当にこのばばあは……。
「あんたら二人の話を聞いてね、バカ言っとるんでないよとわたしは思ったね。悪いけど、あんたは五十五歳になっても独身だよ」
ガーンと頭の中で音が鳴り響く。五十五歳って。五十五歳っていったら今の母よりも年上じゃないか。
「あんた今、男おらんのだろう? でもそのうち適当に暮らしとれば出会いがあって、彼氏ができて、遅くとも三十五歳ぐらいまでには結婚できると思っとるんだろう?」ちっちっちっちと女は指を左右に振る。「このままいったら、あんたはね、もう二度とまともな恋人はできん。もちろん子供も産めんわ。孫の顔を見せれんまま親を死なせるんだよ。親不孝もんだね」
そこまで言うと、女は五十五歳とは思えない俊敏さでずずずいっと距離をつめてきた。「わたしはね、忠告にきたんだよ。あんたは今年、大きな間違いを犯す。その間違いさえ回避すれば、未来は変わるかもしれん。わたしのことを信じて、
わたしは即座にうなずいた。首がちぎれてふっとびそうなほど何度もうなずいた。
「よし。よおく聞くんだよ。ここのシステム管理部に、Hという男がおるね。あんたはその男と近々不倫関係に陥ることになる。あげく、妻ともうじき別れる、なんてありふれた嘘にだまされて、十年以上の年月をそいつのためにドブに捨てることになるんだよ」
「でも、Hさんがわたしと付き合うなんて、そんなのありえないよ」
「黙って聞きなさいっ」女はぴしゃりと言ってわたしの両頬をつねってひっぱった。ものすごく痛かった。「いい? とにかく、やっとのことでHとの関係を解消しても、気がつけばあんたは四十過ぎ。四十過ぎの女の結婚がどれほど困難なのか、わかっとるね?」
テロリストに狙撃されるよりも。わたしはひっと息を吸った。
「あんた、実はもうすでにHに片思い中なんでないの」
どきりとした。わたしの顔を見て、女はうすら笑いを浮かべる。
「しかも不倫関係になると聞いて、実は内心ちょっとよろこんだだろう。全く、あんたは本当にタワケだね。われながら大タワケだね。いいよ、思う存分どっぷりと不倫地獄の湯につかって、いずれ孤独な独居ばばあになるがいいよ」そう言って、女は人差し指をこちらにつきだした。「このわたしのようにね! ドーン!」
ハッと気がつくとわたしは私服に着替え、従業員用出入り口の前に立っていた。
すでに日は暮れて、正面にある駅ビルの真上に少し欠けた月がぽっかり浮かんでいる。他の従業員がぼうっと突っ立ったままのわたしの横を邪魔くさそうに通りすぎていく。強い向かい風が吹いていた。寒い。
記憶がなかった。エレベーターの中で変なおばさんと二人きりになって、それから今までの記憶がすっぽり抜けている。その間、何度か休憩をとったはずだがそれも覚えていないし、どうやって着替えてどうやってここまで出てきたのかもわからない。一体どうなっているのか。夢でも見ていたのか。あのおばさんは何者なのか。まさかタイムスリップなんて
気になるのは、最後におばさんがやっていた「ドーン!」っていう
後ろから誰かに押され、そのままわたしは歩き出す。バッグの中で携帯が鳴っていることに気がついた。知らない番号からのテレビ電話だった。通話ボタンを押すと、画面いっぱいにあのおばさんの顔が映し出され、わたしは「ひゃっ」と道端で悲鳴をあげた。
「あんた今、あれは夢だったとか、盗み聞きだったとか、くだらないこと考えとっただろう」
おばさんの顔は携帯の画面越しに見ると余計に
「タワケだね。われながら本当にタワケだね。ったく、わたしがあんた自身だとはとても信じたくはないよ」
それはこっちのセリフだと思ったが、言えなかった。
「とにかく、あんたのことだから、あれだけ言ってもどうせ不倫するんだろう。もし一線を越えそうになったら、この番号に電話しなさい。説教してやるから」
「あ、あの……」
「いいかい? あんたはわたしで、わたしはあんた。あんたの行動次第で、わたしの姿はいかようにもかわるんだよ」
Hさんはシステム管理部の部長さんだか課長さんだかをしている人で、電話受付の部署にいた頃、システムトラブルが発生したときによく姿を見かけた。それ以外で彼との接点は全くなく、昇降機部に異動になってからは一度も顔を見ていない。当然、従業員は従業員専用のエレベーターを使用する。
彼を意識するようになったのは、ある出来事がきっかけだった。それまでは、コンピューター関連で問題が発生したときに駆けつけてくれる小柄なおじさん、程度の認識だった。
二十七歳になったばかりの冬のことだ。セール中でとても忙しかった。わたしは数人のオペレーターとともに残業していた。午後十時過ぎ、突然、社内システムに不具合が生じ、情報が入力できなくなった。
その場に正社員がいなかったので、一番先輩格だったわたしが代表してシステム管理部に連絡した。きてくれたのはS君という若手社員だったが、調べてみるとどうも事態は予想外に複雑だったらしく、上司を呼ぶと言って引き返していった。数分後、HさんをともなってS君は戻ってきた。
そのときのHさんの姿があまりに強烈で、忘れられない。ノーネクタイの黒いシャツはしわしわでスラックスから半分はみ出し、スーパーで980円ぐらいで売っていそうなサンダルを、しかも裸足で履いていた。七三分けの髪はいつもボサボサしている印象だったが、その日はボサボサというよりワシャワシャしていて、後頭部のあたりはススキのようにけばだっていた。とても社内で仕事中だった人間には見えず、わたしだけでなくオペレーター全員がその姿態に面食らっていた。するとS君がこっそり「あの人、社内で晩ご飯食べると、いつも居眠りしちゃうんだよね」と教えてくれた。
一生懸命に状況を説明するS君の横で、Hさんは
ところが、五分ほどの沈黙の時を過ごした後であろうか。Hさんはやおら背筋を伸ばすと、ものすごい勢いで目の前のキーボードを叩きはじめた。ときおりふっと手をとめては、髪の毛をいじったり、
専門用語ばかりだったので、彼が何を言っているのかわたしには全くわからなかった。が、彼がものすごく頭のいい人だということは、その話しぶりで理解できた。S君が把握したかどうかも確かめず、あらかた自分の言いたいことを言い切ってしまうと、Hさんはわたしたちオペレーターには見向きもせずにサンダルをぺたしぺたしと鳴らしながら去っていった。
その背中は小さかった。しかし思いのほか尻の位置が高く、手足が長いのだった。後頭部のアホ毛が空調の風にふかれて生きているみたいに揺れていた。それを見つめながら、なんでだろうとわたしは思った。
額は後退気味で、顔には大きなシミがいくつかあった。三白眼かつ左右の目の大きさが違い、人を下から見上げる表情はトカゲなどの
彼の細く長い指が、キーボードを超高速で叩く様子が頭の中でリピートし続けていた。左の薬指にはめられたゴールドの指輪の輝きが目に焼き付いていた。
「あの人さあ、ものすごく優秀は優秀なんだよ」取り残されたS君が後片付けをしながらつぶやく。「もう、なんでデパートのシステム管理なんてつまんない仕事しているのかわからないぐらい優秀。だけどさ……」
「だけど?」
「いや、見ただろ? あんな感じでルールを守るのが苦手っていうかさ。ネクタイはしないし、眠たくなっちゃうと昼でも会議中でも寝ちゃうし。
そのS君の話で、わたしの恋心は決定的なものとなった。仕事ができるのに社会不適合者、という男にわたしはどうも弱く、
しかし、当時のわたしはすでに二十七歳。いくら優秀とはいえ、社会不適合者と付き合っている場合ではないことは充分に自覚していた。しかもHさんはあれでも既婚者だ。結婚適齢期を過ぎた女が不倫なんてはじめてしまったら、そこで人生投げ出したも同然。二十代半ば以下の読者は「なんと大げさな」と思うかもしれないが、同年代以降の方にはこの心情を理解してもらえると思う。
今ならまだ間に合う。そう思った。まだ何もはじまっていないのだから、何にも起こらなかったことにしてしまえる。わたしはHさんのことを極力考えないようにつとめた。社内で彼とすれちがっても
はたして、それから二年以上、とくにめぼしい展開もないまま日々は過ぎた。わたしは自分の自制心が誇らしかった。もっとも、その自制心ゆえなのか、独身のまともな男性とのまともな関係を築くことも全くないまま
それはともかく、だからどう考えても、今さらHさんと不倫関係なんかに陥るはずがない。未来のわたし(とまだ全面的に認めたわけではないが)との
しかし、事件はその日のうちに起こった。
閉店
わたしは犬に追い立てられた羊のごとく
しかもそれは客ではなかった。というかHさんだった。
わたしたちはしばし見つめあった。その数秒の間に、さまざまなことが洗濯機の中の衣類のように脳内をぐるぐるとかけめぐった。
なぜ従業員の彼がこのエレベーターに乗り込んでいるのか。なぜまたしてもこの人は裸足にサンダルなのか。昨日の今日でこういう出来事が起こったということは、あのおばさんの言っていたことは正しく、要するにわたしたちはこれをきっかけに不倫関係に陥るのか。ということはやっぱりあのおばさんは未来のわたしであり、ということは二十数年後にはタイムトラベルが実現し、ということはわたしは五十五歳の時点で一度も結婚経験がなく子供も産めず……。
「あの、ボタン押し続けてたほうがいいんじゃない?」
Hさんが言った。そのときわたしは、ああそうだと思った。この人はこういう、なんというか、低くて少しかすれて、ざらついた、
「あの、ボタン、押し続けないと」
わたしはあわてて階数ボタンのほうに向きなおる。驚きのあまり指を離してしまっていた。
再び非常用ボタンを押し続けると、しばらくしてスピーカーから応答があった。原因不明の停電で緊急停止してしまったのだそうだ。復旧にははやくて十分、長くて三十分近くかかるかもしれない、ということだった。
「……だそうです」
振り返るとHさんはその場にぺたんと座りこんでいた。が、わたしと目が合うとすばやく立ち上がった。
「君って、南さんだよね? 確か前はコルセンにいなかった?」
「あ、そうです」
「異動したのって夏ぐらいだよね?」
そう言って、Hさんは
「いや俺、実はさ、前から結構、客用のエレベーターにこっそり乗ることがあってさ。ほら、従業員用のやつって遅いし、遠いじゃん? で、君のことも何度か見かけてたんだけど……君ってさ、面白いよねえ」
「何がですか?」
「いや、たまにさ、日曜とかですごく混雑してるとき、どさくさにまぎれて『こちらは婦人服と婦人用ブラジャー&パンティー売り場でございます』とか『おもちゃ売り場でございます。大人用はございません』とかめちゃくちゃなことを言ってるでしょ」
言葉が出なかった。誰も聞いていないと思っていたから言っていたのに、よもや身内に聞かれているとは。しかもよりによってそれがHさんとは。
「この間なんて、『お降りになるときは足もとのツタウルシにご注意ください』とか小声でつぶやいていたよね。全く、ここは里山かよ、と思ったよ」
Hさんは声をあげて笑いだした。わたしは恥ずかしさのあまり、米粒ぐらいに小さくなってどこかの
「南さんって、小説書いてるんだって? いや、そういう人は人間もユニークなんだなと思ったよ」
「いや、わたしなんて、そんな、普通ですよ」
「いや、普通の人が『十一階、カードカウンターでございます。ご利用は計画的に』とかどさくさにまぎれていわないから」
「ていうか、一体何回客用エレベーター使ってるんですか」
「え、毎日」
当たり前のように言うので、ついわたしは吹き出してしまった。
「でもさ、どういうわけか、俺、南ちゃんが乗ってるエレベーターに乗り合わせることが多い気がする。なんでだろう」
「なんででしょう、不思議ですね」と平静を
それからわたしたちは、微妙な距離を保ったまま当たり
十分たってもエレベーターは動かなかった。その少し前から、徐々に二人の距離がつまってきていることにわたしは気がついていた。どうやらさりげなくHさんは前進しているようだった。
「コルセンって、怖そうな女の人が多いよねえ」
そうつぶやきつつ、Hさんはまた数センチこちらに近づく。
「南ちゃんのことも、コルセンで見かけたときは、愛想のない女の人だなーっと思ったんだけどさ」
Hさんは上目使いで笑う。以前はその三白眼の目立つ顔がトカゲみたいだと思ったのに、今は妙にセクシーに見えた。って何がセクシーだよ? バカじゃなかろうか、わたしは。どこからどうみたってただの禿げた小柄なおっさんだ。多分もっと近づけば加齢臭がするはずだし、夏場になれば額はてかてかと
ていうか、バカなのだろう。
「うちの部署でも、南さんって怖いよねって言ってるヤツいたんだよ」
ここへきて、Hさんは大胆に歩幅を広げた。古雑誌の
奥さんがやっているのかな。
「まあ確かに愛想はよくないけど、でも俺は、なんか気になるっていうか」
気になるっていうか。
「前から少し、ちょっと……」
少し、ちょっと、何だよ。
「ちょっと……一度ちゃんと、話をしてみたいなとずっと思っていたんだ」
気がつくと、その距離三十センチ。Hさんはスラックスの尻ポケットをごそごそいじっている。携帯電話を出そうとしているのは明らかだった。しかし見つからないのか、体中のポケットをぱしぱしと叩きはじめた。
それでも見つからず、彼は胸のポケットから手のひら大のポストイットを取り出すと、そこに自分の連絡先を書きつけてこちらに差し出した。
受け取りながら、唐突に、あのおばさんの顔が脳裏に浮かぶ。喪黒福造のものまねをしながらこちらに指を突き出した、あの、
「よかったら、一度飲みにいかない?」
「わたし、お酒飲めないんですよ」
「じゃあ、まあ飯でもいいからさ」
「あの、じゃあ、大勢でなら」
「えー、メンバー集めるのがめんどうくさいよ。二人でいいじゃない」
そのとき、再びガタンと音がして停電した。すぐに明かりは点灯し、同時にエレベーターが上昇しはじめた。
一つ上の九階でとまった。ドアが開くと、数人の従業員が心配そうな顔をしてこちらをのぞきこんでいた。みんなは同時にほっとした様子になり、しかしすぐにこの場にいてはいけないはずのHさんの存在に気がついて不穏にざわつきはじめた。わたしはその隙に箱の中から逃げ出し、振り返りもせず事務室へ引きあげた。
電話が鳴った瞬間、あのおばさんからに違いないと直感した。しかし、かけてきたのは大手出版社Q社の編集者Rさんだった。
「南さんっ。やっと話がまとまりました」
午前零時過ぎにもかかわらず、Rさんはやたらと高揚した声で言った。すでに
「合コンですよっ。うちの総務部の男子に交渉してみるって言ったじゃないですか」
「あー、そういえばそんな話、ありましたね」
「そういえば、じゃなくて。ぜひやりましょうよ」
Rさんとはその夏から「お見合い」をテーマにした連作をやろうという話がもちあがり(ちなみに二〇一二年三月現在、絶賛停滞中である。いや、悪いのはさぼってるわたし)、取材と実益をかねて、わたしはあちこちのお見合いパーティやイベント合コンに足を運んでいた。しかし一向に成果のあがらないことを打ち明けたところ、ちょうど社内に手ごろな独身男性がいるので紹介したい、という話になった。それでも、編集者という生き物はわりとノリで「××しますよ!」と言ったまま忘れてしまうことが多いと、わたしはすでに数年の売れない作家生活を経て気がついていたので(いや、悪いのは売れていないわたし)、全く期待していなかったのだが、Rさんは思いのほか真剣に考えていたようである。
そしてとんとん拍子でことが運び、九月下旬、Rさん幹事の合コンが、渋谷のお
しかし、やたらとうれしそうに合コン合コンとRさんが言っていたのでわたしも仕方なく合コンという言葉を使用しているが、実のところ開かれたのはそれとはまったく程遠いものだった。何せ参加者五人のうち、四人はQ社社員なのだった。残る一人はわたしである。単なる同僚同士の飲み会に部外者が無理やり紛れ込んでしまったようなものだった。
女性の参加者はRさんの他に、文庫編集者のKさん(既婚、確か三十一、二歳だった。はず)で、男性は広報部のWさん(独身、三十四歳だと言っていたと記憶しているが定かではない。当日になって急きょ参加が決定したらしかった。ちなみに名前もど忘れしてしまってWというイニシャルは適当)、そして総務部のGさん(独身、七十八年の早生まれだったと記憶)。
わたし以外は当たり前だが気心の知れた者同士であり、合コン特有のあの丸虫に体をはいまわられているかのようなむずがゆいほどにぎごちない自己紹介タイムなどもなく、開始当初からみんなリラックスしたとてもいい状態だった。その点では、人見知りであるわたしは非常に助かった。Gさんはわたしの正面に座り、その向かって左手にWさんが座った。さて、まず肝心のGさんの印象であるが。
フッツー。
とにかく全てがフッツー。
見た目もフッツー。しゃべりだしてもフッツー。いや、普通が悪いことではないし、外見の印象だけでいえば、彼はいわゆるイケメン的な部類にはいるのは間違いない。もしかするとモテモテな人かもしれない。だからわたしの感性がおかしいんだと思う。
しかしフッツーだ。
反対にWさんはぱっと見ただけでオリジナリティにあふれる人だということがわかった。髪型はほとんど
しかし、数分もしないうちにWさんはやや、いや結構、むしろかなり、めんどうくさそうな性格であるらしいことがわかってきた。意味もなく発したこちらの発言や質問を、そのまま意味もないものとして受け流してくれないのだ。外国に留学していた時期があったというので、「すごいですね」となんとなく口にしたら、「ただの留学の、何が一体どうしてすごいのか」と説明を求められ、もうそれだけでもともと極度のめんどうくさがりのわたしはイヤになった。もちろんわたしは三十間近の大人なのでそれを態度にあらわしたりはしない。が、わたしより三歳若いRさんは酒がすすむとそんなWさんにくってかかるようになり、二人はたびたび
しかし、そうなってくると不思議なもので、相対的になんだかGさんがいい感じに思えてくる。Gさんは二人がいくら醜くののしり合っても、穏やかに笑っていた。Wさんに突然、何の脈絡もなく「Gくんって童貞?」「うちの母親と合うんじゃない? リュウマチだけど」と侮辱に近いことを、まして合コンと銘打っている会の最中にもかかわらず言われたときも、むっともせずにニコニコしていた。またKさんの「Gさんは怒らない教の教祖なんです(何をしても怒らないという意味らしい)」という発言もわたしの心に響いた。わたしは相変わらずどうでもいいことでののしり合っているWさんとRさんを完全無視し、さりげなくGさんを観察しつつ、脳内で内なるわたしと会議を開いた。
ここはもう彼に決めてしまうべきではないか。正直なところ、男性的な魅力は感じない。しかし人間的な魅力はとても感じる。わたしは想像してみた。彼との婚約が決まり、自分の実家に挨拶にいく場面を。母の安心した顔が即座に浮かんだ。それでは、もしHさんが奥さんと別れてくれたとして、彼を婚約者として会わせたらどうなるか。うちはわりと放任主義的なところがあるので反対はしないだろうが、がっかりするのは間違いない。いくらわたしにとって彼がセクシーでいい男でも、多くの人にとってはただのハゲた四十過ぎのオッサンだ。母の失望した顔を想像して、わたしはもう男の色気がどうのとか言っている場合ではないことを改めて自覚した。
きっとGさんは、自ら積極的にアプローチはしてこないだろう。もしそれができるのなら、彼みたいな人にはとっくに恋人か妻がいるはずである。が、その分押しに弱いかもしれない。何度かデートして、よきタイミングでこちらの好意を打ち明ける。彼はたとえ断りたいと思っていてもはっきり断れないのではないか。優しいから。その優しさに、ぜひともつけこむべきである。
勤め先もしっかりしているし、真面目そうだし、オクテそうだから浮気もきっとしない。ああ、人ってこんなふうにして結婚を決めるのだな、初対面でピンときたとか、運命的なものを感じたとか、そういう夢みたいなことは凡人には起こらないのだな、と後から考えれば早とちり以外の何ものでもないことをわたしは感慨深く思ったりした。
合コンは一次会だけで終了した。わたしはその晩のうちに、Gさんにメールした。お礼の気持ちと、次は二人で会いたい
翌日、Gさんからさっそく返事があった。「楽しかったです。また飲みましょう」的なあたりさわりのないことが、これ以上ないというほどあたりさわりのない文面で書かれていた。しかしこのときのわたしは、さしてそのことに意味を読み取らなかった。とにかく彼は極度のオクテで、女性との関係をスムーズに発展させていくのが苦手なだけだろうと決めつけた。そして返事をくれたんだから、少なくともわたしに対して悪い印象は持っていないだろうと思い込んだ。全文転載して読者の方々の意見を募りたいところであるが、さすがにそれはやめておく。メールに彼の個人の連絡先は記載されていなかった。それを引き出すのに、その後、三往復ほどやりとりしなければならなかった。最初のデートの約束をとりつけるのには、さらに複数回のメールのやりとりを要した。
思えば。
思えばもうこの時点で、結論は出ていた気がする。気がするんじゃなくて、事実そうなんだろう。しかしわたしはそこから、もげるほど首をぶん回す勢いで目をそらしていたのだった。
フッツー。
初回のデートが終わったとき、わたしの正直な感想は、それだった。
渋谷のアジアンレストランはわたしが予約した。ムーディー過ぎず、ほどよくにぎやかで、食事もおいしく、我ながらベストなチョイスだったと思う。会話が途切れることはほとんどなく、それなりに笑いはあったし、互いにいろいろなことを知ることもできた。Gさんは気前よくごちそうしてくれ、また会いましょうとも言ってくれた。
しかし。
この心の躍らなさ具合は何だろう。彼と別れ、下りの私鉄電車に揺られながらぼんやりと考える。男性と二人きりで食事をするのは随分と久しぶりだった。出かける前は多少ドキドキしていたはずだった。しかし、店に入って彼の顔を見た瞬間、なんか違うと思った。前回の店は薄暗かった。今夜の店は結構明るかった。こんな髪型していたっけと思った。あんなに
われながらいい年こいて何言ってんだと思う。顔なんてどうでもいいじゃないか。人間いずれみな年をとって若さを失うのだ。それに彼は、別に不細工なわけじゃない。むしろかっこいいほうだ。Hさんのほうがよほど変な顔をしている。ただ思いのほか、なんか、違ったのだ。そしてなんだかピンとこなかったのだ。
そうだピンとこないのだ。さっきからやたらと頬が痛いのは、ピンとこない人を相手に愛想笑いをし続けたせいだ。一度も腹から笑えなかった。彼の何を聞いても、興味深いと思えなかった。
電車が駅のホームに滑り込む。空気の抜けるような音を立ててドアが開き、乗客が入れ替わる。混雑する車内でわたしは人の波に押されて回転した。そのとき、古雑誌のような匂いが鼻先に漂い、はっとした。Hさんの加齢臭と同じ匂いだ。わたしはミーアキャットのように背筋を伸ばして周囲を探った。ホームに吐き出されていく人々の中に、ススキのように揺れるおっさんの後ろ髪を見つけた。あんなにアホ毛をほったらかしにしているサラリーマンはそうそういない。Hさんだ。流れにのってそのままホームに降り、しかしすぐにアホ毛を見失ってしまった。ダッシュして改札まで先回りしようかと考える。そのためにはとりあえず準備運動をしなければと足首をぐるぐるねじっていると、バッグの中で携帯がけたたましい音をたてて鳴った。マナーモードにしていたはずなのに、と思いながら取り出す。
テレビ電話だった。
「人違いだよ」
女はエレベーターで遭遇したときと同じ赤いタートルネックのセーターを着ていた。顔面をかなり携帯に近づけて話しているようで、背景が全く見えなかった。
「こんなところにHがおるわけないが、あんたは全くタワケだね」
わたしは反射的に「くそばばあ」と悪態をついた。すると女は即座に「わたしがくそばばあなら、あんたもくそばばあだが」と言い返してきた。
「まあええわ。あんたね、ピンとこんとか、髭跡が濃いとか、そんなくだらんことでみすみすチャンスを逃がす気かね。言っとくけど、Gさんより条件のいい男は、今後一切あんたの前に現れんよ」
「一人も?」思わずそう聞いていた。女は神妙な顔になってうなずいた。
「一人も。あんたは数年後、死ぬほど後悔することになる。くだらんことにこだわらんと、Gさんにしとけばよかったって」
「後悔……」
「参考にね、わたしが今、どんな暮らしをしとるか教えてあげようか。当然、小説の依頼なんてとっくの昔に途絶えとるわね。毎日ね、朝から夜まで、ラブホテルの清掃をしとるんだわ。くたくたになったシーツとか、床に捨てられた避妊具とかを毎日毎日飽きもせずに片付けとる。食っていくためにね。しかも実はHさんの奥さんに不倫がばれて、慰謝料を払うために借金した。まだ残っとる。昼飯は清掃仲間と仕出し弁当食べて、夜は一人でコンビニの……」
電話を切った。そのまま電源も落とした。同時に次の電車がホームに滑り込んできた。風が舞う。スカートがめくれ上がるにまかせた。どうせわたしのパンツなんて誰も見たがらないし。なぜか視界が淡くにじんでいた。
Gさんも同じくピンときていないのではないか、とわたしは恐れていたのだが、二度目のデートは意外にも彼のほうから誘ってくれた。二週間後、今度は代々木の鉄板焼き屋でわたしたちは会うことになった。
その夜、わたしはある決意を胸に秘めていた。とにかく、彼のいいところをがむしゃらなまでに探すこと。この人と結婚したい、と思う要素をできる限りほじくり返すこと。
デート前、最低限たずねておくべき項目を胸のうちにリストアップしておいた。それらは以下の四点である。このまま定年まで会社をやめずにいるつもりはあるか(独立願望のある男は何かと面倒なため。そういった夫や恋人を持つ友人は大抵苦労している)、万が一、会社が倒産したり、あるいはリストラされた場合の対処法は考えてあるのか(ご存知のとおり出版界は不況にどっぷりとつかっている。そうでなくても何があるのかわからない世の中だ)、後々に影響の出そうな病歴はないか(だって介護とかイヤだし)、親は元気か(これも介護とか以下略)。
Gさんは優しいのでどんな質問にも丁寧に答えてくれた。おおむねこちらの望む以上の回答が得られた。その結果、Gさんは想像したとおりの、とにかく真面目でまっとうで、そしてかなり好条件な人物だということが改めてわかった。こういう人を
その夜もGさんはごちそうしてくれようとしたが、わたしが強引にワリカンに持ち込んだ。店を出て駅までの道を彼と並んで歩きながら、わたしは五十歳を過ぎた独身女性がラブホテルの清掃で生計を立てるとはどういうことかと真剣に考えた。
秋の夜風が肌に冷たかった。Gさんは腕組みをして歩道の端を歩いていた。距離を詰めようと近寄ったら、彼は道路側に飛び出してクラクションを鳴らされていた。
やがて、わたしたちは駅前に着いた。わたしは少し前からちょっぴりドキドキしていた。今日は金曜日。明日は彼も休みだ。終電まであとわずか。「よかったら、うちの近所で飲みなおしませんか」と言ってくれないだろうか。もうお互い大人だし、何ごともある程度スピーディに進めないとなかなか発展しないだろうし、ぶっちゃけ言葉であれこれ約束するより、既成事実作っちゃったほうが手っ取り早いし、でも自分から誘ってアバズレみたいに思われるのは困るし、だけど彼はオクテだからそういうの苦手かもしれないし……。
「俺、ここから新宿まで歩きます」
彼はこちらを振り返ると、右手の高層ビル街のほうをまっすぐさして言った。
「まあ、楽しかったです。どうもありがとうございました」
打ち合わせのあとに編集者が作家にするみたいに、Gさんはぺこりと丁寧にお辞儀した。遠ざかっていく細い背中を見つめながら、結局、別れ際まで彼はわたしにずっと敬語をつかっていたのだなあと
「それってさ、あんたに好意があること前提で話してるけど、正しいの?」
そうU子に問われ、はっとした。わたしたちは春に訪れたのと同じ湘南のカフェにいた。
わたしはU子に、オクテの男性とてっとりばやく恋人になるにはどうすればいいのかを相談していたのだった。いい年ぶっこいて情けないが、わたしはこれまでの人生であまり男性を積極的に誘ったことがなく、またオクテの男性との接点もほとんどなく、Gさんに対してどう行動すればいいのかよくわからなくなっていたのだ。
「好意っていうか……でもまあ二度も会ってくれるってことは、嫌な印象は持ってないと思うけど」
「同僚の人の手前、無下にはできないってだけではなくて?」
「……」
潮風が冷たかった。キラキラと光る海でサーファーたちが揺れる海草のように
「だって、その二回目から連絡ないんでしょ?」
そうなのだった。すでにあれから一カ月半が
「大の男が二週間も風邪を引き続けるかね」
「わたしにうつしちゃいけないって気をつかってるんだよ」
「自分に対して積極的に手を出してこない男をオクテと決め付けるのって、ただ単に真実から目をそむけてるだけだと思う」
「真実って何さ」
「オクテな男って、そもそもこの世に存在するのだろうか」U子は腕を組んで前方右手にある江の島を見る。「そんなものは、もてない女がもてない言い訳のかわりに生み出した、幻想なのではないか」
そのとき、横のテーブルからキャッと女の叫び声が聞こえた。スカートにジュースがこぼれたらしく、それを隣の男に
「Gさんって人、自分の好みの相手を前にしたら、普通にケモノになるのかもよ」
何か言い返そうとして、しかし言葉が見つからなかった。隣のカップルは猫みたいにじゃれあいながら席を立ち、店を出ていった。
オクテという概念はもてない女が生み出した幻、もしくは言い訳。
その後も定期的に様子見のメールを送り続けたが、彼からの返事はつれなかった。しかし、十二月に入ったある日、突然Gさんからメールがきた。
「長らくお待たせしてすみません。やっと風邪も治り、仕事も落ち着きました。来週の金曜あたりどうですか」
思いのほかよろこんでいる自分にわたしはちょっと驚いた。彼のことをあれこれと考えているうちに、自然と恋心が芽生えてしまったのかもしれない。店はわたしが予約すると申し出た。雰囲気がよくて狭いカウンターのある店を探した。強制的に物理的な距離を埋めることにより、彼のわたしに対するよそよそしさを取り除く作戦だった。
しかし、その日が近づくにつれて次第にわたしの気分は
恋って一体なんだろう。
ていうか、三十近くにもなってそんなことを悩んでいるわたしは、あのおばさんが言うようにタワケなのだろうか。
その日、デパートの仕事が休みだったので、美容院へいった。気分を盛り上げるためだった。そして家に帰る電車の中で、目を閉じてGさんと結婚式をあげるところを空想した。より一層のイメトレ強化の必要性を感じていた。場所は南国の島がいい。家族だけを連れて、抜けるような青空の下、きらきらと光る海を背景に永遠の愛を誓うのだ。ああ、なんて幸せな景色……。
古雑誌の匂いがした。
わたしは閉じていた
そのほほ笑みが思いのほか、思いのほかな感じで、わたしは自分から彼を捕まえておいて何も言えずに固まってしまった。Hさんはそんなわたしを見て、困ったような笑顔になって広い額をぽりぽりとかいた。その顔もまた思いのほかな感じでわたしはもはや胸が痛かった。これはもしかして心筋
駅は広大で、いくつもの線路が走っていた。右手を見ると駅ビルの向こうに暮れかけた薄いオレンジの空が見える。なんでだろうとわたしは考える。こんなにおっさんで、こんなに脱毛症が進行していて、こんなに加齢臭がするのになんでだろう。
「今日、仕事休み?」
やっとHさんが口を開いた。鼻声だった。「あれ? 雰囲気かわった?」
「ええ。E駅の美容室で髪を切ってきました。Hさんもお休みですか?」
「うん。風邪ひいちゃってね。でも熱下がったから、家を抜けだして本を買いにいってた」そう言って、右手に持った袋を顔の前に掲げる。「家、この辺なの?」
「あ、違います。J駅の近くです」
「え? じゃあなんでここで降りたの」
「あ……」と言葉に詰まったわたしを見て、Hさんは何かを見透かしたような顔になってくすりと笑った。わたしはぽろりととれてしまいそうなほど耳が熱くなっていくのを感じた。本当は何にも気づかれてないのかもしれないが、Hさんと話していると心の奥底まで
「もしよかったらどこかでお茶でもする? でも、忙しかったら……」
「忙しくないですっ」
あわてて答えたら
「じゃあ、いこうか」
Hさんについて駅を出た。Hさんはわたしの一歩半先にたってずんずんと進んでいく。黒いシャツの上にグレーのピーコート、下は細身の綿パンと、わりと若々しい格好をしているのに、なぜか普段よりふけて見えた。
しばらくして、Hさんは小さなカフェの前で立ち止まった。
「中、見てくる」と言い残し、さっさと一人で店に入ってしまった。数秒後、そそくさと出てくると「満席だ」と言った。
その三軒隣のカフェもまた満席らしかった。その隣のコーヒーショップは改装中で、道の向かい側のファミレスもなぜか閉まっている。
「なんか、タイミング悪いね、俺達」Hさんは笑った。「仕方ないから、散歩でもする?」
むしろそのほうがいいとわたしは思った。向かいあって話すのは緊張してしまう。
この近くにあるという広い公園を目指すことになった。横並びで歩きながら、とりとめもないことを彼は話した。去年から飼いはじめたというウサギの徳永(顔が徳永
ふと、会話が途切れた。と同時にHさんはわずかに歩調をはやめた。まわりに人気はなく、予報通り空はくもりはじめている。Hさんはどこか遠くを見ながら「歩きすぎて、疲れたね」と言った。
確かに疲れた。わたしは五センチヒールのパンプスを履いていた。それにいい加減、何か飲み物がほしい。
「どこかで休憩する?」
「そうですね。さっきファミレスの前を……」
そこで、わたしは言葉を飲み込んだ。Hさんの視線の先にあるものに気がついたからだ。
フリータイム五千九百円から。宿泊八千九百円から。「九月 全面リニューアルオープン‼」と書かれたのぼり旗が風にあおられてはためいている。入り口のビラビラカーテンから黒い車が出てきた。運転手と目があった。こめかみの部分だけ白くなった五十代半ば頃のおっさんだった。車は猛スピードで西へ向かって走っていった。
「なんか寒いし、ああいうところのほうが落ち着いて話せるんじゃない?」
Hさんは顔をそむけたまま言う。コートのポケットに両手を突っ込んで、足をもじもじさせている。彼なりに、多少の居心地の悪さは感じているらしかった。
ああ、とわたしは思う。
ああ、なんでこんなに急展開なんだろう。彼は結婚していて、今後まともな関係なんて築けるはずもなく、母親どころか友人にさえ紹介できない人だというのに。誰の前に出しても恥ずかしくないGさんとはため口をききあうことさえままならなくて、Hさんとはこの異常なほどのスピード感。なんでだろう。なんでこんなにうまくいって、うまくいかないのだろう。
「あ、ごめん、冗談冗談。そんないきなりホテルとか、ありえないよねー。怖い顔しな……」
「い、いいですよっ」
わたしは彼の言葉を遮って言った。また
路上でわたしたちは見つめあう。Hさんの顔は相変わらずトカゲみたいだと思った。三白眼で、左右の目の大きさが違って、薄い唇を長い舌でぺろぺろなめている。どこがいいのか自分でもわからない。バカバカバカとわたしは内心で自分をなじる。バカバカバカ。
彼の視線から逃れたくて、時間を確かめるふりをして携帯を見た。いつの間にか午後五時を過ぎていた。休憩を一時間で切り上げたとしても、Gさんとの約束の七時半にはきっと間に合わない。そもそも一度中に入ってしまったら、一時間で切り上げるつもりもない。
「じゃあ、いく?」という彼の言葉にわたしは深くうなずいた。彼はわたしの左手をとると、同じようにうなずいた。二人はまるで危険なつり橋を目の前にした冒険家みたいだと思った。走って道路を渡ると、迷いをふりきるようにそのままの速度で自動ドアを抜けて中に入った。
入り口正面に大きなクマの彫像がそびえたっていた。そのとき、このホテルの名前がパシフィック・ベアというのだとはじめて知った。太平洋のクマとは一体どういう意味なのかじっくり考えてみたかったが、すぐにそんな場合ではないと気がついた。クマの横に、部屋を選択できるパネルがたっている。現在空いているのは二部屋だけだった。そのことにHさんは大層びっくりしていた。その二つのうち、金額の高いほうを彼は選び、取り出し口に落ちてきた
そのとき、「ちょっと」とこちらを呼ぶ声が聞こえた。
背後に受付カウンターがある。無人だと思っていたが、すりガラス越しに人が動いているのが見えた。わたしはおずおずとそこに近づくと、すりガラスの仕切りの下部に空いている三十センチ四方の穴から中を覗き込んで「なんですか」と問いかけた。
その瞬間、体中の毛が逆立った。
あのおばさんがいた。
未来の、五十五歳のわたしだ。
清掃員の格好をした五十五歳のわたしがモップを右手に、汚水のはいったバケツを左手に提げて仁王立ちしていた。
「もうあんたに何も忠告する気はないよ、わたしは」
五十五歳のわたしはそう言って、絶望的なほどに長いため息をついた。あまりに長いので永遠に続くかと思った。
「わたし、もう死のうと思う」
おばさんは言った。そしていきなり汚水の入ったバケツを床の上でひっくり返した。決壊したダムのごとく黒い水が床にあふれ、わたしは思わず「わーっ」と叫んだ。おばさんはびしょぬれの床などお構いなしにバケツの上に立つと、あらかじめ天井に仕掛けてあったらしい縄で作った輪に首をひっかけようとした。
「もうわたしは死ぬ! お前は好きにしろ!」
「ちょ、ちょっと待ってよっ」
「お前のせいでわたしの人生ぼろぼろだよっ」
「わたしのせいとか意味わかんないしっ」
「見ておくがいいよ、自分の死に
わたしは振り返ってHさんを見た。間違いだ、と思った。この人とこんなところにいるのは間違いなのだ。
時間を確かめる。家に帰って支度するのを省けば、充分Gさんとの待ち合わせには間に合うはずだ。
もう一度Hさんを見た。Hさんは
外は小雨が降っていた。
待ち合わせには間に合った。むしろ少しはやめに駅についたので、デパートの化粧品売り場の試供品でメイク直しをした。
わたしが予約したのは渋谷のおしゃれな焼き鳥屋さんだった。カウンターはペアシートになっていて、想像していたのよりもずっと狭苦しい感じでわたしは心の中でガッツポーズをした。照明もほどよい明るさで、実はメイク直しをするとき大幅にアイラインをはみ出してしまったのだが、それもこの暗さならバレずに済みそうだと思った。
Gさんは少し遅れてきた。振り返ったわたしを見て、「どうも」と少し照れくさそうにつぶやく彼を目にして、わたしははじめて自然にドキドキした。ついさっき自殺しようとする人間(しかもその正体は自分自身)を目撃した不安感からくるドキドキだとわかっていたが、この際そんなことはどうでもいい。
Gさんが座席を見下ろして、少し戸惑うような顔になったのをわたしは見逃さなかった。しかしまさかテーブル席に移ろうなどとは言い出さぬだろうと思っていると、Gさんはそろりそろりと、わたしの隣にこしかけた。
まるでいつでも遊びに出かけられる体勢をキープしてお昼ご飯を食べる夏の小学生男児のようだった。わたしがとって食うとでも思っているのだろうか。わたしは魔女か何かか。しかし、しばらくして話も盛り上がって打ち解けた雰囲気になれば、いずれ彼のほうから近づいてくれるだろうと、心のうちで自分を慰めた。
わたしは前回の自分の態度を反省していた。鉄板焼き屋でのわたしは、彼に対してあまりにぶしつけで失礼だった。社内でのポジションや彼の過去、そして家族について、
だから汚名返上とばかりに、今夜はとにかく彼を
しかし、二時間半たっても彼の尻の位置はそのままだった。
それだけでなく、一時間が経過したあたりから彼はしきりに腕組みをするようになった。何か食っちゃあ腕組み、食っちゃあ腕組み。いつか読んだ心理学の本に、腕組みはもっともわかりやすい拒否のサインだと書いてあった。足もとを見ると、お行儀のいい子供みたいにぴたっと
そのとき、彼と最初に会った合コンでのことを思い出した。わたしが飲んでいたオリーブソーダに彼は興味を示し、「同じものを飲んでみようかな」と言って、実際にその後オリーブソーダを注文したのだった。相手と同じ行動をとるのは、好意を抱いている証拠だといつか誰かに聞いたことがある。
会話が途切れたとき(というかほとんどわたしがしゃべっていたのでわたしの話が一段落したとき)を見計らって、「何を飲んでいるんですか」とたずねてみた。彼は手元のグラスをぐっと
「おいしいですか?」
「いや、普通の味」
「飲んでみようかな」わたしは店員を呼んだ。「彼と同じやつ、ください」
「あ、じゃあこっちはオレンジジュース」
Gさんは女の若い店員に声をかけるときだけ腕組みをはずした。正面に向き直るとまた腕を組んだ。
その後もとにかく思いつく限りのことをわたしはしゃべりまくって、閉店ぎりぎりまで居座った。「楽しい時間はあっという間ですね」と語尾に音符をつけるイメージで言ってみたが、Gさんは聞こえなかったか聞こえないふりをしているだけなのか、ノーリアクションのまま「ちょっとトイレ」と席をたった。
追い出されるようにしてわたしたちは店を出た。小雨が降っていてとても寒かった。道玄坂を駅にむかって下って行く人々はみな身を寄せ合うようにして歩いている。わたしたちの間には大型犬二匹分ほどのスペースがあった。
わたしたちに足りないのは言葉だ、とわたしはその大型犬二匹分の空間をぼんやり見つめながら思う。それも決定的なもの。何度こうして二人で食事をする機会を重ねても、二、三時間ほど世間話をして別れるだけでは一年たっても何の進展もしないかもしれない。どちらかが決断しなければいけないのだ。今日、Hさんが思い切ってわたしをパシフィック・ベアに誘ったように。けれど男の人ってこの手のことに時間的な
坂下の交差点に着いたら言おうと思う。わたしの家で飲み直しませんか、と。
しかしそのとき、ふいにGさんが立ち止まった。少し先を歩いていたわたしは数秒遅れて振り返った。
彼は無表情で腕を組んでいた。
「俺、こっちからも帰れるんで」
そう言って、背後を指さす。井の頭線の出入り口があった。
「あ、あの」
「じゃ、ここで。どうも」
彼はダンサーみたいに華麗にターンした。それから、ステップを踏むように軽やかに去っていった。
途端に雨が強くなった。人々が「キャー」とか叫びながら走りだす。わたしはゆっくりとバッグから折り畳み傘を出して広げ、そのまま坂の途中で立ちつくしていた。
やっぱり鉄板焼き屋でのわたしの態度にむかついていたのか。あるいは同僚の編集者の手前ことわれなかっただけで、はじめからわたしになんか興味なかったのか。もしくはもっと若い子がいいのか。二十九歳はもうおばさんか。今になって急に、心臓をわしづかみにされたようなせつなさがこみ上げる。あれ。とても悲しい。なぜだ。そんなのおかしい。だって、彼はピンとこない人のはずなのに。話していても全然楽しくなかったはずなのに。今、わたしの胸は痛いほど苦しい。ふと思いついてバッグから携帯を出した。あのおばさんに電話しようと思った。別に何を話したいわけじゃなかったけれど、とにかく電話をしなければと思った。
そういえばこちらからかけるのははじめてだった。つながるかどうか不安だったが、すぐに呼び出し音が聞こえた。
「はい」と聞き覚えのない女の声で応答があった。
家族だろうか。家族だとするとわたしの家族になるわけだが一体誰だろう。子供はいないはずだ。
「もしもし?」と女は不審げな声で言う。「どちら様ですか」
「あ、えーと」
「Hの携帯ですけど、会社の方?」
びっくりしてわたしはそのまま携帯を落とした。あわてて拾いあげるととりあえず洋服で水気をとった。すでに電話は切れていたが念のため通話ボタンを連打した。それからわたしはあることを思い出してはっとした。
あのおばさんの電話番号の登録名を「ばばあのわたし」にしていたのだった。ハの付く名前の知人はHさん以外にいなかった。ばばあにかけようとして間違えてHさんにかけてしまったのだ。
わたしはメモリーを呼びだして、もう一度ばばあにかけようとした。
しかし、確かに登録したはずなのに、消えていた。
自分で消した記憶はない。わたしは急に恐ろしいような気持ちになってあたりをきょろきょろと見まわした。すると、ななめ左後方の電柱の陰に、見覚えのあるものが放置されているのを発見した。
恐る恐る近づいた。ばばあが昼間、手にしていたバケツとモップ、そして縄だった。
雨水を吸って、モップはぶよぶよに膨らんでいる。縄はなぜかちぎれていた。そんな汚いものを見下ろしているわたしを、若いカップルが毒虫でも見るような目で通りすぎていく。
はたして、五十五歳のわたしは一体どうなったのだろう。折り畳み傘をばしばしと
タイムパラドックスって言葉を聞いたことがある。あれって一体何のことだっけ。ああ、今は何も考えたくない。はやく家に帰って温かいお
何分そこに立ちすくんでいたのかわからなかった。やがてわたしは
さて。
一応、物語は以上をもって終わる。しかしこれは実話であるので、わたしが生きている以上、完全な「了」となることはなく、現在進行形であれこれ続いているわけである。これもまた、いろいろとプライバシーやらのややこしい問題があるので詳細に語ることは控えさせていただくが、とりあえず二〇一二年三月現在、わたしは相変わらず食っていくためにダブルワークを続けており、結婚のめどは全く立っておらず、雨の道玄坂で間違い電話をかけたことがきっかけでこちらの番号をHさんに知られてしまい(翌日、さっそく「あれ、南ちゃんだった?」と聞かれた)、ときどき電話がかかってくるようになって一年以上が経つものの、あの日以来一度も二人きりにはなっていない。全てはわたしの自制心にかかっている。しかしもういろんな意味でギリギリである。そして、Gさんからはそれきり一切、いいいいいっっっっっさあああああい、連絡がなかったことはここにご報告しておく。