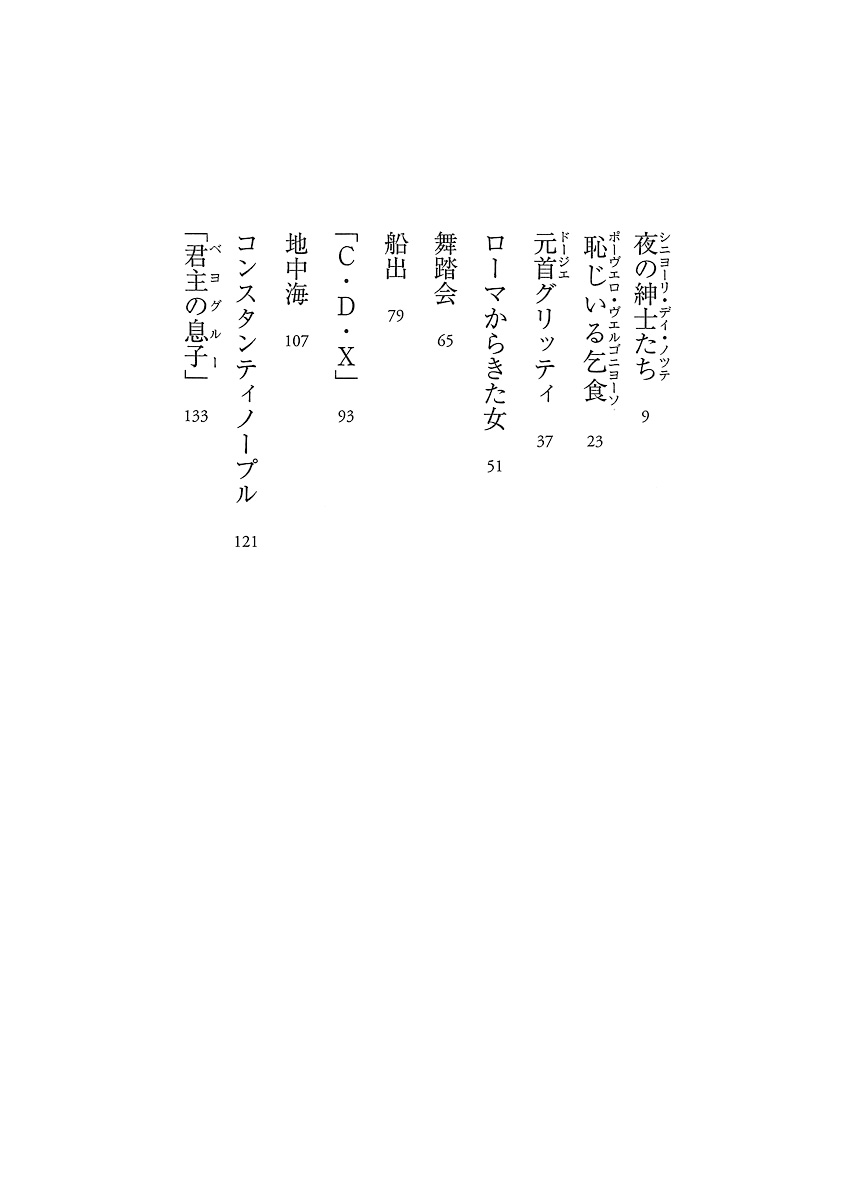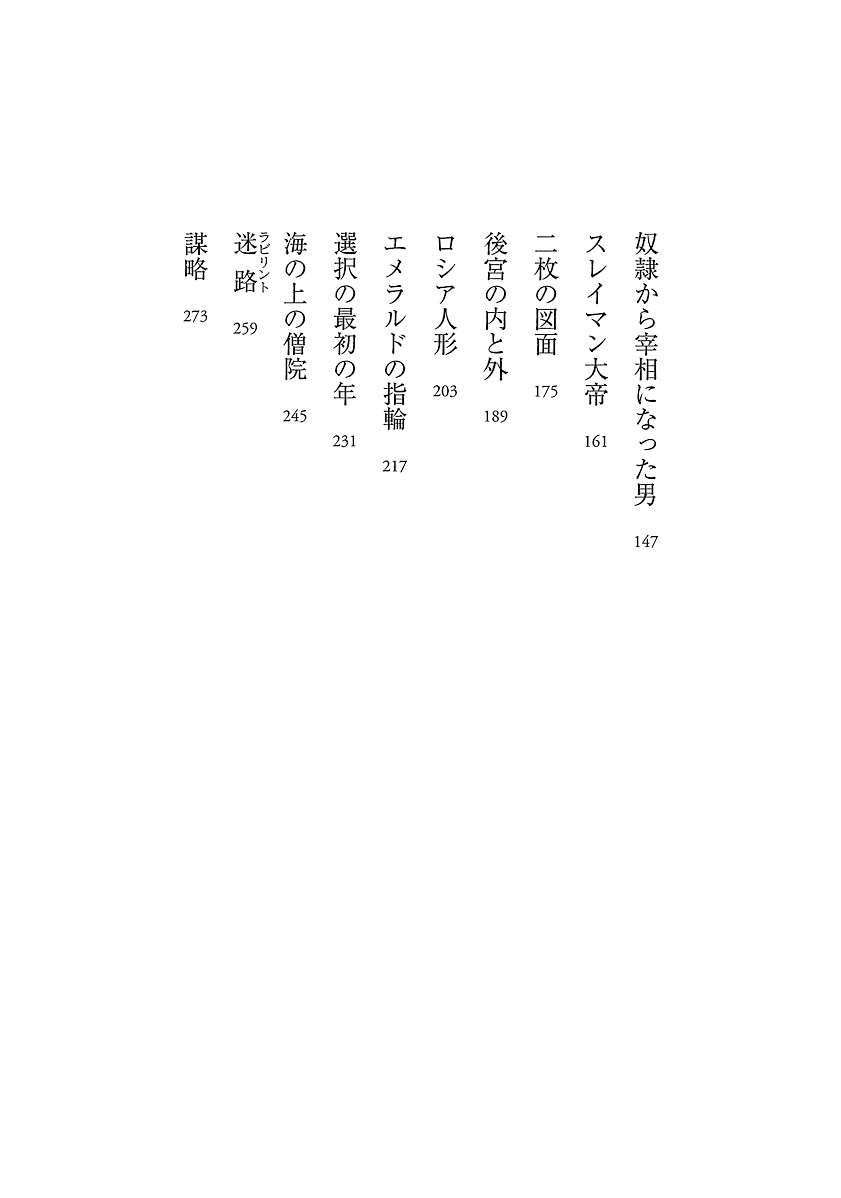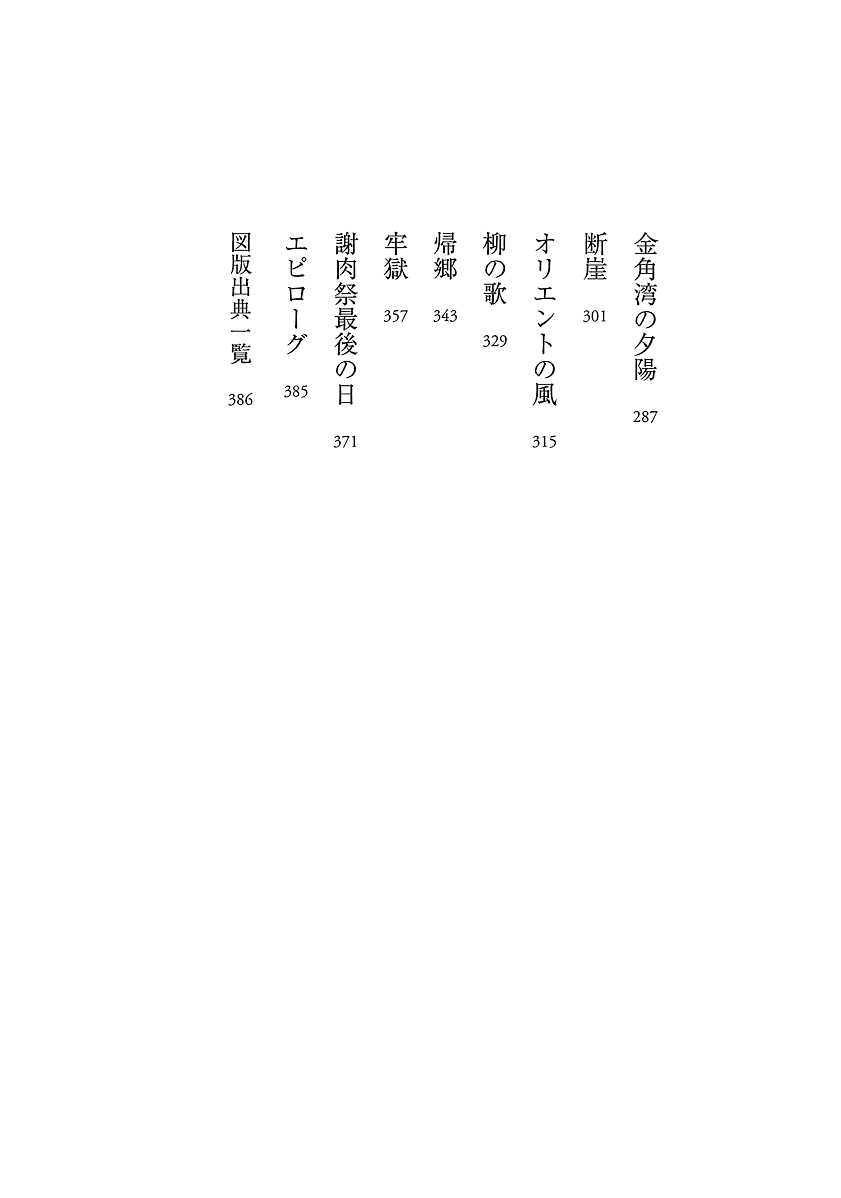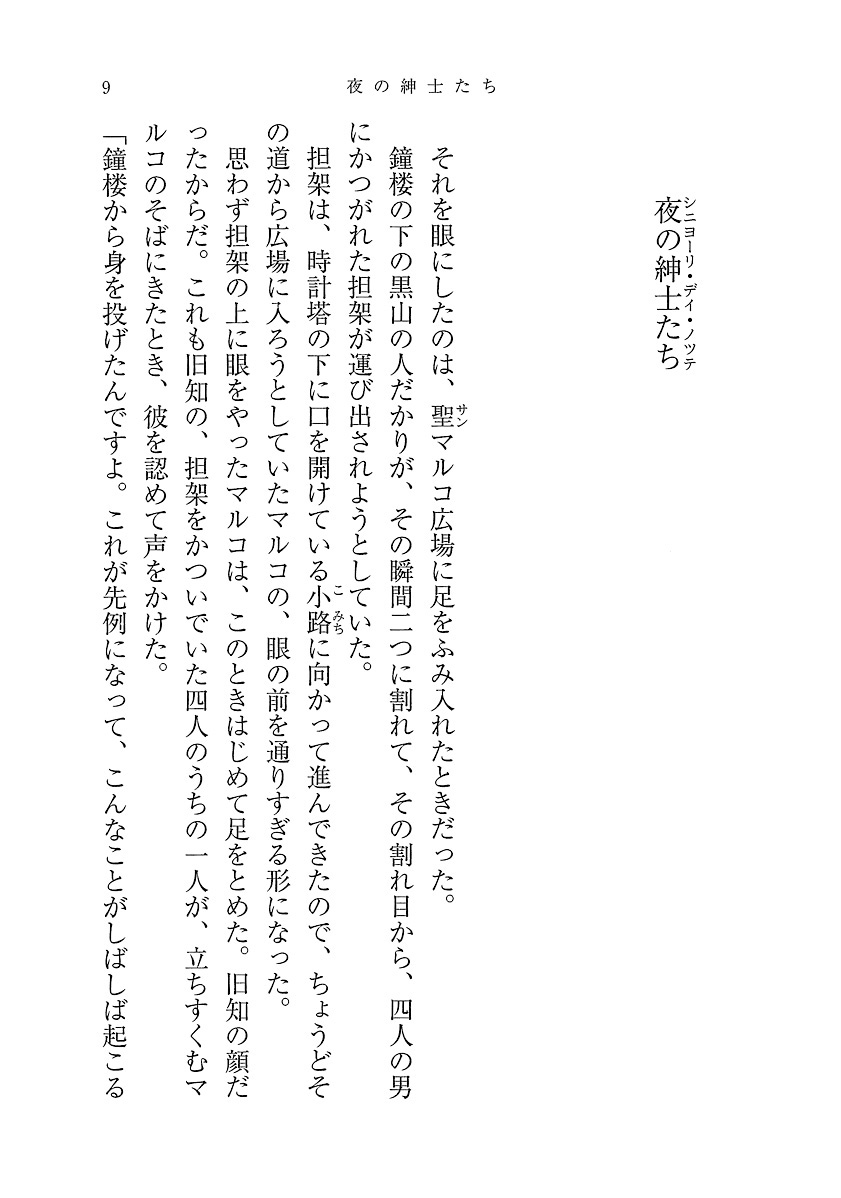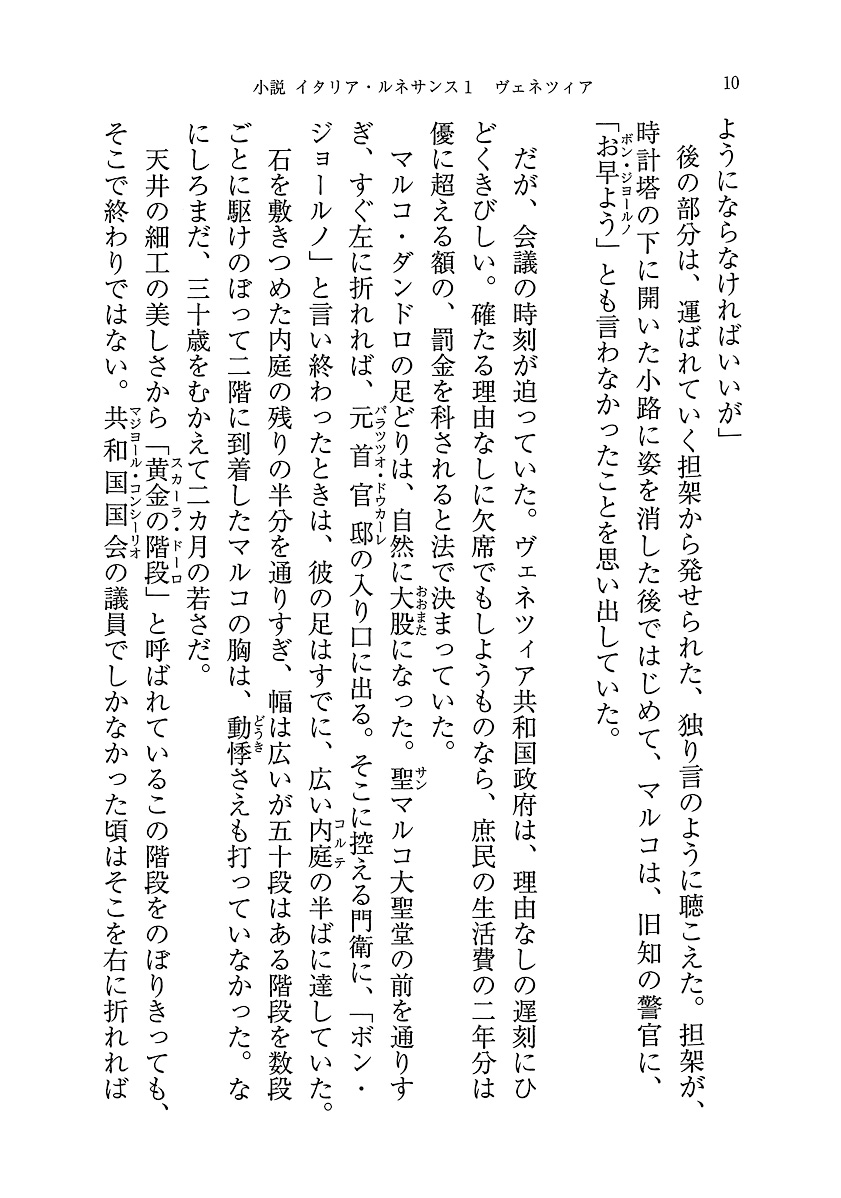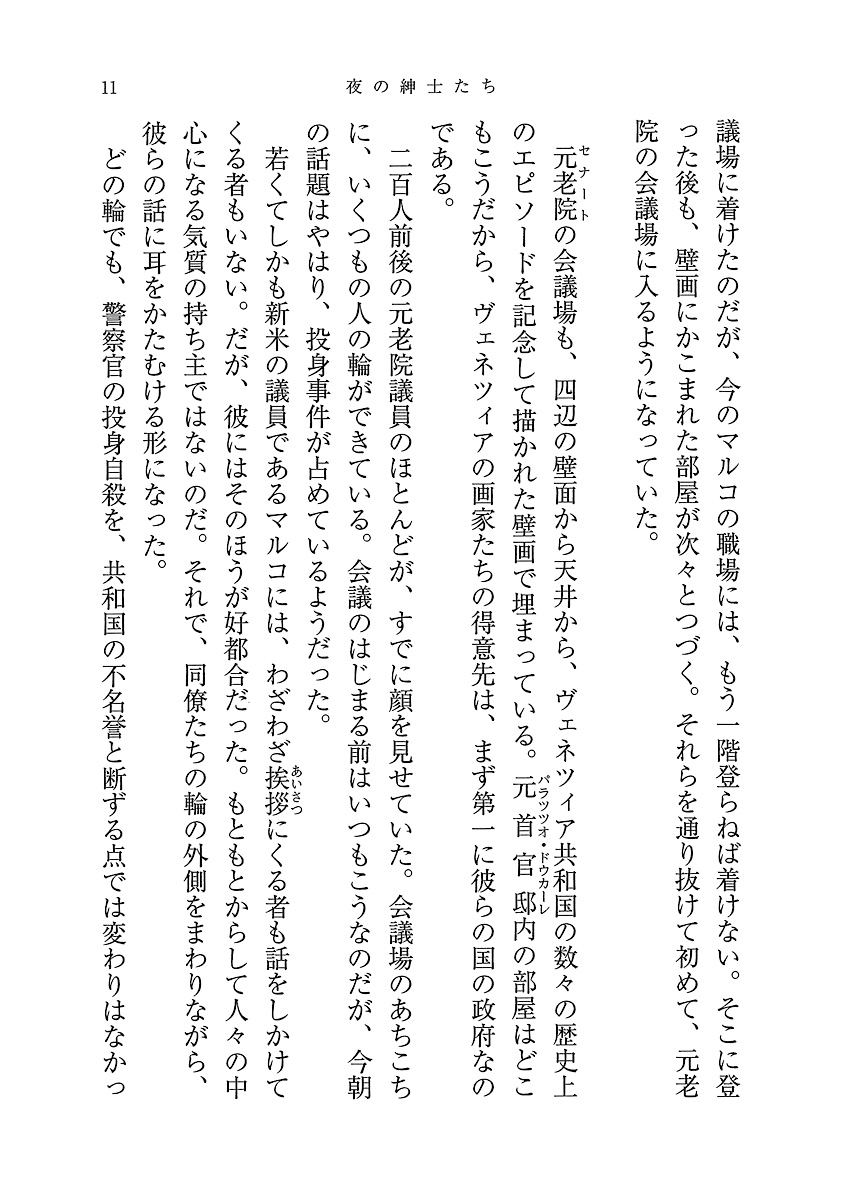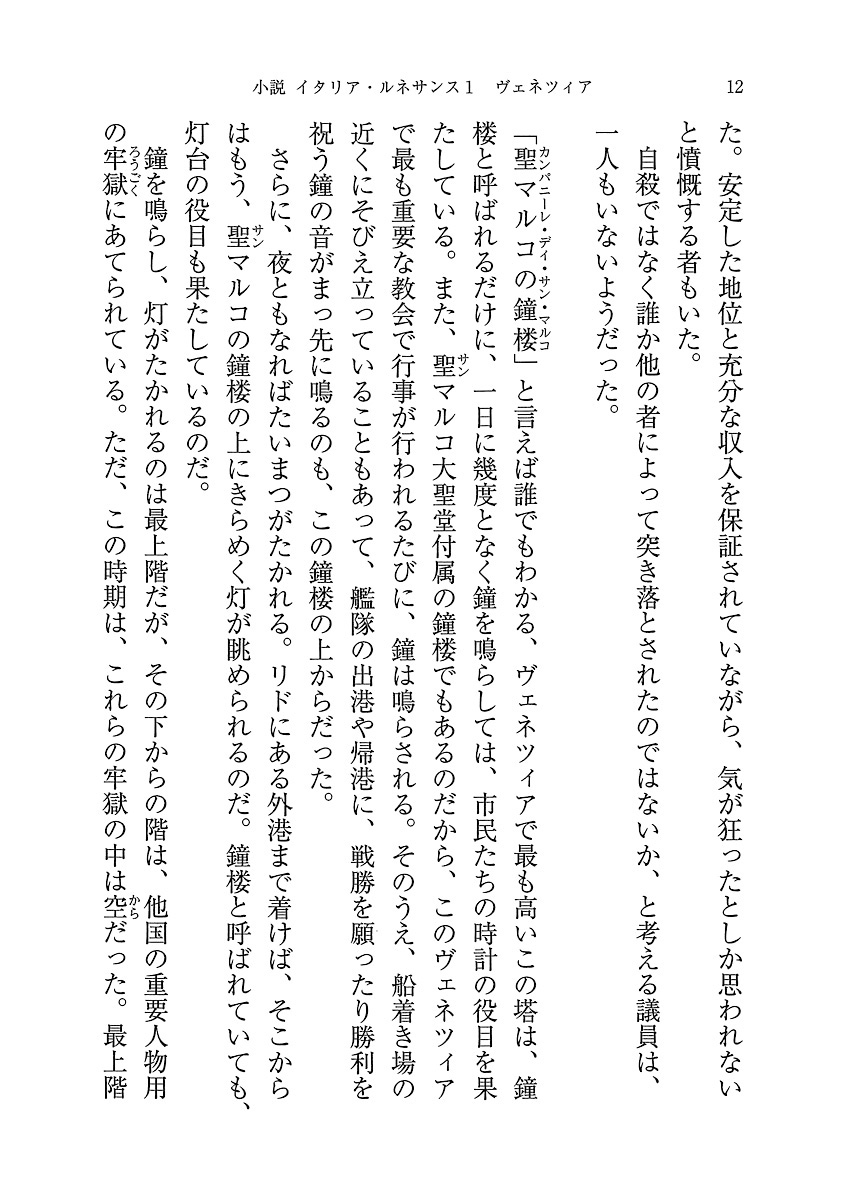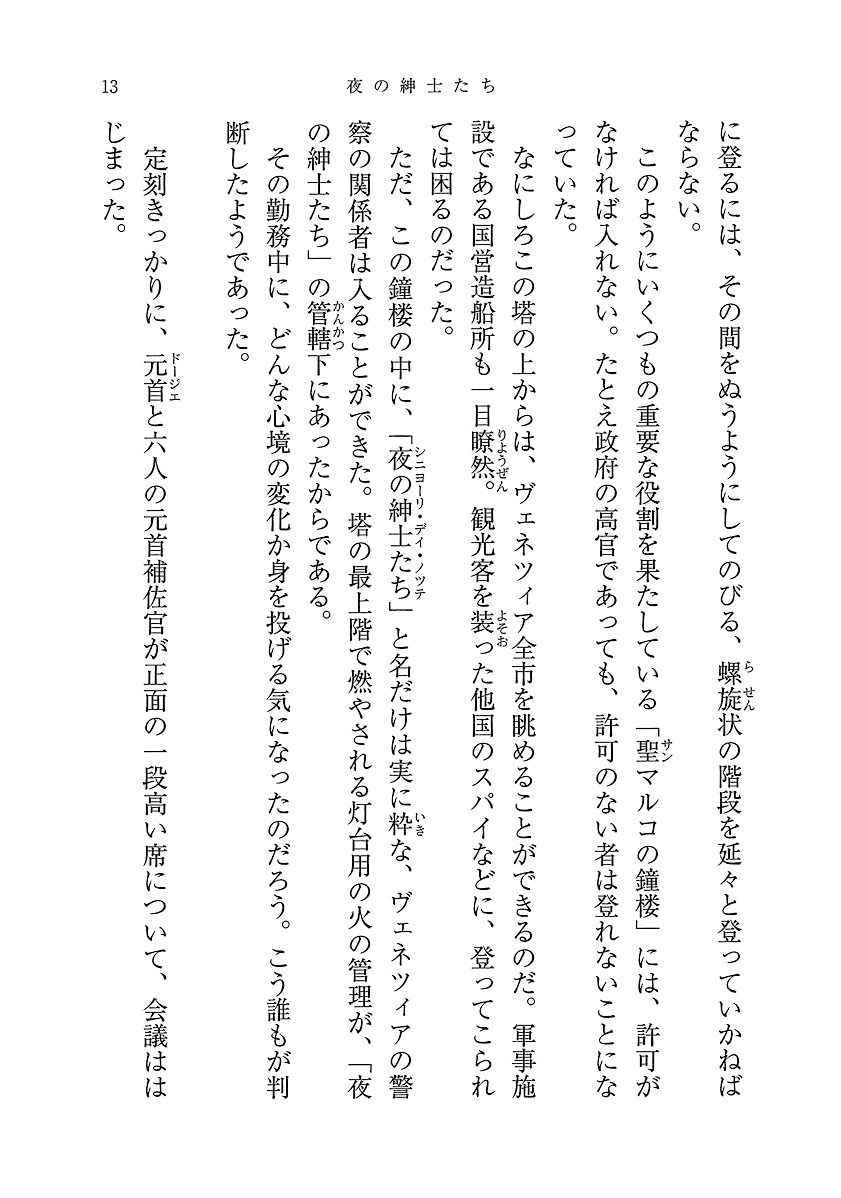1 夜の紳士たち
それを眼にしたのは、
鐘楼の下の黒山の人だかりが、その瞬間二つに割れて、その割れ目から、四人の男にかつがれた担架が運び出されようとしていた。
担架は、時計塔の下に口を開けている
思わず担架の上に眼をやったマルコは、このときはじめて足をとめた。旧知の顔だったからだ。これも旧知の、担架をかついでいた四人のうちの一人が、立ちすくむマルコのそばにきたとき、彼を認めて声をかけた。
「鐘楼から身を投げたんですよ。これが先例になって、こんなことがしばしば起こるようにならなければいいが」
後の部分は、運ばれていく担架から発せられた、独り言のように聴こえた。担架が、時計塔の下に開いた小路に姿を消した後ではじめて、マルコは、旧知の警官に、「
だが、会議の時刻が迫っていた。ヴェネツィア共和国政府は、理由なしの遅刻にひどくきびしい。確たる理由なしに欠席でもしようものなら、庶民の生活費の二年分は優に超える額の、罰金を科されると法で決まっていた。
マルコ・ダンドロの足どりは、自然に
石を敷きつめた内庭の残りの半分を通りすぎ、幅は広いが五十段はある階段を数段ごとに駆けのぼって二階に到着したマルコの胸は、
天井の細工の美しさから「
二百人前後の元老院議員のほとんどが、すでに顔を見せていた。会議場のあちこちに、いくつもの人の輪ができている。会議のはじまる前はいつもこうなのだが、今朝の話題はやはり、投身事件が占めているようだった。
若くてしかも新米の議員であるマルコには、わざわざ
どの輪でも、警察官の投身自殺を、共和国の不名誉と断ずる点では変わりはなかった。安定した地位と充分な収入を保証されていながら、気が狂ったとしか思われないと憤慨する者もいた。
自殺ではなく誰か他の者によって突き落とされたのではないか、と考える議員は、一人もいないようだった。
「
さらに、夜ともなればたいまつがたかれる。リドにある外港まで着けば、そこからはもう、
鐘を鳴らし、灯がたかれるのは最上階だが、その下からの階は、他国の重要人物用の
このようにいくつもの重要な役割を果たしている「
なにしろこの塔の上からは、ヴェネツィア全市を眺めることができるのだ。軍事施設である国営造船所も一目
ただ、この鐘楼の中に、「
その勤務中に、どんな心境の変化か身を投げる気になったのだろう。こう誰もが判断したようであった。
定刻きっかりに、
今日の議題は、本土に広がる土地の干拓だ。ヴェネツィアの小麦の輸入先は、黒海周辺も領土に加えているトルコ帝国なのだが、東地中海域では利害が相反するトルコに、最も重要な食糧を依存している現状は、いつかは改善されねばならなかった。南イタリアに輸入先を換える手もあったが、あの地方もスペイン王の支配下に入ってしまっている。スペイン王カルロスのイタリア全土領有への野望があからさまな現状では、南イタリアに全面的に輸入先を切り換えるのも利口なやり方ではない。干拓地を広げて、国内生産高を増やすことに、誰も異存はなかった。
それを専門に担当する委員会の設置も賛成多数で可決。委員五人の選出もとどこおりなく終わり、その日の元老院会議は、二時間もたたないうちに散会した。
早いほうだった。これが、元老院が主として担当する外交や軍事となると、昼食抜きで夕暮にまでおよぶこともしばしばなのである。
広場は、いつもの日の広場にもどっている。人間の
ヴェネツィアを代表するこの広場も、市内の他の広場と同じようにいくつもの小路が口を開けているので、この街で生活する人々にとっては、通り抜けるためにまず存在する。
また、この
オリエントからの人とわかる色とりどりのターバンも、ここヴェネツィアでは振りかえる者もいない。ギリシア語で話す船乗りの一団のすぐわきを、ドイツ語を話す商人たちが通りすぎる。広場の片すみでは、歯を抜くだけの歯科医が晴天開業をきめこみ、そのすぐとなりでは、床屋が
人々のかもしだすこの騒々しい活気の中では、広場を漫然と歩む元老院議員に、注意を払う者はいない。元老院議員といっても、それとわかる服装をしているわけではない。役職にでもつかなければ、一年中黒の長衣で、といっても季節によって薄地になったり毛皮の裏打ちになったりぐらいの変化はあるのだが、この服装は、医者や交易商人や教師のような頭脳労働者ならば、ヴェネツィアでは誰でも着ているものだった。
マルコは、ときおり塔の頂上に眼をやりながら、足は動いていても考えこんでいた。
あの男は、ほんとうに自ら命を断ったのだろうか。
しかも、
百メートルの高所から落下したにしては、顔には
彼は、あの男を知っていた。それも、よく知っていたといってもよいくらいに、知っていたのである。
六カ月前までのマルコ・ダンドロの職場が「
ヴェネツィア共和国では、貴族の
だが、国家の方向を決めるような重要事でなくても、国政には種々の仕事がある。その一つが治安だった。「
任期は一年。選出は、共和国国会でなされる。選ばれるのが六人なのは、ヴェネツィアの市街地全体が六つの行政区に分かれているからで、一区ごとに一人ずつ、その区域内に住まう者が選ばれることになっていた。
マルコは、この警察署長に、二度選ばれていた。この時期の業績と、海軍省の役人をつとめた期間の仕事ぶりが認められて、三十歳にして早くも元老院に議席をもつという、幸運を彼にもたらしたわけだ。ヴェネツィア政府の重要な役職はほとんど元老院議員の中から選ばれるので、元老院に議席を得てはじめて、政治家としてのキャリアのスタートラインに
六人の若い貴族が署長をつとめる「
六人の署長たちは、先にのべたような事情で、一年任期で選ばれた者たちだ。しかも、ヴェネツィア共和国のほとんどの役職と同じで、任期の期間と同じだけの休職期間をおかなければ、再選は認められないことになっている。
これは、長期に居すわることによっての癒着を防ぐための配慮だったが、職務の熟練度ということになるとマイナスになりかねない。それで、刑事や警官たちは、ヴェネツィアの市民権をもつ者の終身雇用と認められていた。署長は代わっても、部下たちは代わらないのである。
鐘楼から落ちて死んだ男は、刑事の一人であり、担架をかついでいてマルコに声をかけた男は、警官の一人なのだ。通算にしても、二年もの間「
死んだのがもしもあの男でなく、別の刑事であったならば、マルコとてこうも考えこむことはなかったろう。死んだ男がどのような人間であったかをよく知っていたからこそ、投身自殺ということが、なんとしても
自殺ということ自体、宗教で禁じられているキリスト教徒には簡単にはやれないことだ。カトリック教会は、自殺者には教会内での葬式も許さず、教会が管轄する墓所への埋葬も許さなかった。
それに、あの男は、とかくの
他の同僚たちは皆、
そんなことを考えているうちに、時間はだいぶたっていたようだった。時計塔の上では、機械仕掛けの人形が動き出して、正午を知らせる鐘を打ちはじめていた。
マルコは、朝方とはちがう、
小路に足をふみ入れると、広場でのにぎわいが
それにかかる橋を渡ろうとしたときだった。マルコは、首すじに、人の視線を感じた。
だが、ここで振りかえるのもためらわれた。彼の足は、半円を描いてかかる橋の上に達しようとしていた。橋の上では、全身をさらすことになる。
マルコは、気づかないふうを装いながら、橋を渡りきり、それにつづいてのびている、小路に入って行った。首すじに感じた視線は、小路を行く間は消えていた。だが、それを抜け、
ちょうどよいぐあいに、独身のマルコの世話をしている老夫婦の
広場には、物売りの店とそれに集う女たちと、
ところが、その小路を半ばまできたとき、またも背後に視線を感じたのだ。恐怖よりも不快な
小路を抜けると、小ぶりの広場に出る。その正面に、ダンドロ家の屋敷の、陸側の入り口がある。大運河に面した表口よりも、この裏口を使うほうが多かった。
その扉の前に着いたとき、マルコは、今度はあからさまに背後を振りかえった。そのマルコの眼に、今まさに小路を抜け出ようとしていた、黒衣の乞食の姿がとびこんできた。
あたりには人はいない。乞食は扉の前に立ちふさがったマルコの眼を、避けようともしなかった。といって、彼に物乞いする様子もない。それどころか、みじめそうにこごめていた身体を突然のばしたのだ。そして、堂々とした歩調でマルコに向かって近づいてきた。
2 恥じいる乞食
直訳ならば「恥じいる哀れな人」としてもよい黒衣の物乞いは、ルネサンス時代のヴェネツィアでは、政府も他の乞食とは区別したし、乞われて小銭を与える庶民のほうも、同じとは思っていなかった。
この人々の前身が、貴族であったり、貴族には生まれなくても、裕福なのは貴族と同様であった人々だからである。それが、なにかを機に、物乞いするまでに落ちぶれた人々なのであった。
ヴェネツィア共和国は、海外との交易で生きる国である。全財産を投資して送り出した船が
このように運や才能に恵まれなかったりした人々でなく、その両方はもちあわせていながら、まったく不運にも投資先が戦争にまきこまれてなにもかも失ったという、非難しようもない哀れな人々もいただろう。
ヴェネツィアやフィレンツェに代表される、ルネサンス文明も
ただ、ルネサンス人は、成功者には
しかし、足を使って行けるヨーロッパを主な市場にしていたフィレンツェと比べて、海の上を行くしかない地中海世界を主な市場にしているヴェネツィアのほうが、浮き沈みの度ははげしかった。ヴェネツィア共和国では、この種の乞食を、完全に制度化していた。寄附用の受け口を街のあちこちにもうけるぐらいでは、必要を満たせなかったからだ。
他の物乞いならばボロを着ようと勝手だったが、「
黒地の布でできた、足もとまでとどく長さの
この服をつけているかぎり、何者であるかということは誰にも知られずにすむ。乞食のほうからは見えても、乞食が誰かはわからない。そのうえ、「
これほどの思い
自由経済は、活気があればあるほど繁栄するものである。また、十六世紀に入ってもヴェネツィアには、敗者復活の機会はいくらでもあった。昨日までの物乞いが、明日になれば再び、交易商人として活躍しはじめるかもしれないのだ。そのときに、乞食をしていたという前歴が重くのしかかることがないようにという、思い遣りもあったのである。
「
黒衣の乞食が、乞食らしくもない歩調で近づいてきたのには、さすがにマルコも緊張した。思わず、二、三歩後ずさりしていた。乞食は、それを追うように足を早めながら、あたりをはばかるような押さえた声で言った。
「中に入れろよ。ここだと誰が見ているかわからない」
その声を耳にしたとたんに、マルコは突然、十年昔に引きもどされたなつかしさでいっぱいになった。そして、屋敷の扉の
乞食は、ここに入ってきてはじめて、黒い頭巾を脱いだ。だが、マルコは、それを脱ぎ終わらないうちに声をかけていた。
「アルヴィーゼ、いつからヴェネツィアにもどっていたのだ」
黒い頭巾の下からあらわれた顔は、笑っていた。忘れもしない幼友だちの、アルヴィーゼ・グリッティの顔だった。
友がそれに答えるのを待たずに、マルコは再び、あきれたという口調で声を出していた。
「それに、なんだいそのかっこうは。
アルヴィーゼは、これにほがらかな笑い声で答えた後で言った。
「ひざを曲げ、背をこごめて哀れそうに振る舞うのも
後の言葉は、黒衣まで脱ぎ捨て、シャツとタイツの姿になった後、両手を上にあげて伸びをしたときに言った。そして、まだ立ったままでいるマルコに、いたずらっぽい
「
老僕夫婦の妻のほうが料理し、夫が給仕する昼食を、二人は、これだけは十年昔と少しも変わらない食欲でたいらげた。
その後で二人は、上の階にあるマルコの私室に席を移す。アルヴィーゼは、この部屋におかれているトルコ式の低い
マルコ・ダンドロとアルヴィーゼ・グリッティは、八歳の年からの友だちの仲であった。
その年、文法や簿記やラテン語を学ぶためにマルコが通っていた私塾に、途中から入ってきたのがアルヴィーゼだった。トルコ帝国の首都のコンスタンティノープルで生まれ、幼少期もそこですごしたのだが、ヴェネツィア市民である父親の考えで、教育はヴェネツィアで受けることになったからだ。
一言でいえば、変わった少年だった。ギリシア語もトルコ語もできたのはもちろんだが、イタリア語も充分にできたから、途中入学でも問題はなかったのだが、少年の周囲に漂う雰囲気が、他のヴェネツィアの少年たちとはちがっていた。
父親は、当時はまだ、
ただ、オリエントからきたこの少年は、級友たちとの無邪気な遊びに熱中することはなかった。といって、大将格になって引っぱりまわすわけでもない。名誉ある孤立、と言ってもよい感じの雰囲気が、この少年の周囲には常にあった。教師や級友たちが一目おいたのは、ヴェネツィアにアンドレア・グリッティあり、といわれるほどの男の息子だからというのははじめの頃で、その後は、この、オリエントの血が半分流れている少年のかもし出す、異国風の
マルコとアルヴィーゼが親友の仲になったのは、まだ二人とも頬がふっくらとしていた少年時代だったが、成長するにつれて頬の線がきっかりとした直線に変わっていっても、二人の友情は、二人の髪と眼の色が変わらないのと同じにつづいた。
アルヴィーゼ・グリッティは、
マルコ・ダンドロも、背がすらりと高いことでは似ていたが、黒い髪は、なだらかなウェーブをつくって首すじまで流れている。濃い茶色の眼は、落ちついていながら若々しかった。学校では優等生で、しっかりした気質の持ち主であることが一目でわかるものだから、年配者の評判は常に良い。
まだ頬が丸味をおびていた時代から、アルヴィーゼはよくマルコの家にきていた。食事を一緒にするだけではすまず、ともに寝た夜も数えきれない。
アルヴィーゼの母親はコンスタンティノープルに残っていたので、優しいマルコの母親に、自分の母でもあるかのように甘えた。父親のアンドレア・グリッティは、当時はヴェネツィアの海軍提督の地位にあったので、ヴェネツィアにもどることすらほとんどなかったのだ。マルコの父のほうは、彼が四歳の年に、トルコとの戦争に参加していて戦死した。マルコは、一人息子でもあった。
「昔に食べていたのと同じ料理なのに、味がひとつ、母上のときとはちがっていたね」
「料理女は、母の生きていた頃と同じだけど、母は、調理の最後に、いつも自分で味を試していたから」
「母上が
「一年前。ぼくがまだ、元老院に入らない前だった」
「ああ、そうだったね。きみは今や、ヴェネツィア共和国の元老院議員殿なんだ」
二人はまた、愉快そうに笑い声をあげた。食後の酒が、十年ぶりの再会を、さらに優しいものにしていた。
十四歳になった年、二人とも、ヴェネツィアの上流に属す家の息子ならば普通の、道を選んだ。商船の石弓兵がそれである。
自衛のために商船でも乗船が義務づけられている戦闘員になって、戦闘や航海に必要な技術を学ぶわけだ。それに、船長以下、乗組員ならば誰にでも権利のある、商品をもっていってそれを目的地で売りさばいたりすることによって学ぶ交易上の技能も、この実地教育の中では重要な課目であった。
だが、なによりも、ヴェネツィア共和国が国家の将来をまかせるこの若者たちに学んでほしいと思っていたのは、外国の実情を見る眼を養うことであったろう。石弓兵制度は、こんなふうで、なかなか深い意味をもつ制度として定着していた。
だから、石弓兵を志願した若者たちは、同じ船につづけて乗ることはほとんどない。経済上の理由から、商船のたどる航路は一定していることが多いからで、アレクサンドリアに向かうエジプト航路の船は、戦争などの不都合が起こらないかぎり、毎年アレクサンドリア行きときまっている。
マルコとアルヴィーゼが、互いに打ちあわせた結果とはいえ、いつもともに乗りこんだ船の行き先は、こういうわけで種々さまざまな国になった。
大規模な商館をかまえ、ヴェネツィアにとってはオリエント貿易の拠点であったエジプトのアレクサンドリアには、もちろん行った。
同じくトルコ領になっているシリアも、欠かしていない。ダマスカスも訪れたし、ヴェネツィア商館のあるアレッポまで行ったのだ。
北アフリカでは、チュニスでもアルジェでも、海賊まがいのアラビア人たちと取引した。
スペインの各地に寄港した後もさらに西に向かい、ジブラルタル海峡を通って大西洋に抜け、イギリスのサザンプトンまで遠出したこともある。このときのヴェネツィアからの商品は、キプロス産の高級
四年にわたるこの経験は、マルコにとってさえ、机に向かう学校とは比べようもないほど、楽しく役に立つ学校になった。アルヴィーゼという、良き仲間に恵まれたからかもしれない。こちらの学校での優等生は、マルコではなく、常にアルヴィーゼのほうであったのだが。
石弓兵時代の思い出は、三十代に入った男二人にとっても、どんなに長く話してもつきない
ふと、マルコは、あることを思い出した。
「あのトルコの少年は、どうした」
「ぼくがコンスタンティノープルにもどってしばらくした頃に、訪ねてきたよ。それからは、ずっとぼくのところで働いている」
二人の乗りこんだヴェネツィア商船が、スペインのアリカンテに寄港したおりの話だ。その近くの海で難破したトルコ船から、ただ一人泳ぎついたのに住民に捕らえられ、イスラム教徒というだけで火あぶりにされるところだったこの少年を、救ったのがアルヴィーゼだった。
稼いだばかりの
少年はそれを恩にきて、一生をアルヴィーゼの
アルヴィーゼ・グリッティには、このように無限の優しさがあった。しかし、冷酷の度合いも極端であるのを、マルコは、思い出すともなく思い出していた。
船乗りたちから、冗談にしても「
授業中の優位ならば、断然マルコに軍配があがったが、大学の外に出れば、マルコは友の敵ではなかった。当時の大学生の二大関心事といえば、
しかし、学業も終えた二十歳の年、この二人の進む道は完全に分かれる。その年、マルコを待っていたのは共和国国会の議席だったが、アルヴィーゼにはそれはなかった。
今日の二人の再会は、あの年に別れて以来なのである。十年の歳月が流れていた。
ふと、思いついたとでもいうように、アルヴィーゼが口を開いた。
「きみは今朝、
マルコは、突然、現実に引きもどされた
3 元首 グリッティ
マルコ・ダンドロは、慎重な性格の持ち主であった。人もそう言うし、自分でもそう思っている。だが、この親友にだけは、感じていたことを言わないではいられなかった。
「どうしても、投身自殺とは思えないのだ。あの男はよく知っている。自殺するような人間ではない。
それに、あの派手な死に方はどうだ。ああいう死に方を選んだことからして、普通ではない。死に方からしても、この事件には不可解なことが多すぎるんだ」
アルヴィーゼの眼の色は、深い緑に変わっていた。そして、つき離すように言った。
「しかし、『
こう言われれば、マルコには返す言葉がないのである。彼だって、確たる証拠があって言っているわけではない。ただ、自殺と片づけてしまうには、なんとしても釈然としないのだった。
そんな
「もう、あのことは考えないほうがいい。きみは、これからは、元老院の重要なメンバーになる身だ。やることはいっぱいある。いや、やってもらわなければならないことは、山ほどあるんだからね」
マルコは、口をつぐむしか仕方がなかった。
この件については話はこれで切れてしまったが、久しぶりに再会した二人の間では、他に話すことならばいくらでもある。結局、二人はこの日、家を出なかった。夕食も家ですませ、アルヴィーゼは、マルコが友のために用意させた、これも十年昔と同じだったのだが、マルコの部屋の隣の部屋で眠った。それも、夜半すぎまで話に熱中した後で、二人はようやくそれぞれの部屋に別れたのだった。
だが、翌朝、マルコが寝覚めたときには、アルヴィーゼの姿は消えていた。老僕が伝えるには、また立ち寄る、と言って去って行ったという。昨日の乞食の服に着がえてのお
マルコは、しばらくの間、寝台の上でぼんやりしていた。昨日、あれほども話をしあったのに、アルヴィーゼが、自分のした質問にひとつも答えていなかったのが思い出された。
マルコは、友がいつからヴェネツィアに帰っていたのかを、まだ知らないのである。なぜ、「
それに、と彼は思った。十年ぶりのアルヴィーゼは、昔とはどこかちがっていた、と。
もみあげからあごの線をぼかしながらおおっている、ひげのせいかとも思った。そのうえ、十年ぶりに再会した友は、口ひげまでがトルコ式に整えられている。印象が同じでないのは、そのせいかとも。まして、会わないでいる間に、十年の歳月が流れたのだ。この時期、男の肉体は、若者から壮者のそれに変わる。
マルコのほうはまだひげらしいひげになっていないだけだし、肉体ならば少しはたくましくなったはずだと思ったら、マルコは、それまでもてあそんでいた疑いが
しかし、やはりなにかが変わっていた。どれほど愉快そうな笑い声をたてても、今のアルヴィーゼには、どこか暗いものが感じられる。奥のほうで暗い光を放つような、なにかが感じられてならなかった。
それは、もしかしたら、今のマルコが、アルヴィーゼの父親のほうと身近に接しているためかもしれなかった。それでつい、父と子ということで比べてしまうのかもしれなかった。
父のほうは、同じく光を放っても、それはあくまでも、明るい光だったのである。
七十二歳をむかえていても、
先任の
ヴェネツィア貴族独得の
ヴェネツィア共和国では、国会でも元老院でも、演壇というものがない。意見をのべたい人は、議場の両脇を埋める席の間に開いた中央の通路を行き来しながら、演説するのである。一段高い場所に自席をもつ
その通路を行き来しながら演説するときの、
足どりは力強く、その動きに
マルコは、周囲に光をまき散らすかのようなこの
アンドレア・グリッティは、一四五五年、ヴェネツィアの貴族グリッティ家の
マルコの生まれたダンドロ家ほど古い家柄ではないが、グリッティ家も、ヴェネツィアの統治階級を形づくる名門家系に属す。父親を早く
祖父は、中等教育を終えたばかりのアンドレアを、任地に同行することで、実地の教育を授けようとしたらしい。大使をつとめる祖父の任地がイギリス、フランス、スペインと代わるたびに、若いアンドレア・グリッティは、別の国を見、別の民族を知っていったのである。そのうえ、祖父は孫の識見を信頼していたらしく、政務の相談までした。事実上の大使秘書官まで、経験したことになる。それが終わると、パドヴァの大学で哲学を学んだ。
また、若いグリッティは語学の才能にも
それに、彼の美しい
だが、美質がこれだけならば、あれほどの成功までは望めなかったろう。この男はなぜか、彼に
戦闘を指揮していたとき、トリヴルツィオ将軍に捕らえられた彼は、まもなくこの敵将とは食卓をともにする仲になり、あげくのはてにはまんまと脱走に成功する。トリヴルツィオは、
フランス王フランソワ一世の捕虜になったときも、王に
スペインとフランスの間に起こった戦争で、フランス王フランソワ一世が捕虜になったときの話だ。ヴェネツィアにやってきたスペイン王の特使は、もはや敵なしのスペインの力を説きながら、ヴェネツィアも、フランスなどは見捨てスペイン側につくべきだと迫った。これに、
「二人の君主いずれとも友人であるところから、わたしの想いが複雑であるのはやむをえない。勝利を祝う王とはともに喜び、不幸を嘆く王とはともに泣くことにしよう」
外交辞令もここまでくれば、傑作というしかない。ヴェネツィア共和国は、以後も名誉ある中立を維持できたのである。
しかし、グリッティのような男は、一般の人の理解までは獲得しにくいものである。彼の貴族的な風貌や立ち居振る舞いからも、市民の人気が高い
「
この一見高慢な態度が、実は祖国への人一倍の危機意識から発していることを、少数の人々は理解していた。マルコも、そのうちの一人だと、自分では思っていた。
アンドレア・グリッティほど、ヴェネツィア共和国の危機のはじまりと、重なりあう生涯をもった者もいない。
彼の生まれる二年前の一四五三年、コンスタンティノープルの陥落が起こっている。一千年の間、ヨーロッパをオリエントから守っていた東ローマ帝国が滅亡し、それは、オリエントの新興の民、オスマン・トルコの興隆のはじまりになる。地中海の女王と呼ばれて繁栄を誇ってきたヴェネツィアにとっては、これまでとは比べようもない、危険な敵の登場を意味した。
一四七〇年、グリッティ十五歳の年、ギリシアの東端にある半島、ネグロポンテがトルコの手に
この講和のすぐ後、アンドレア・グリッティは、トルコの首都コンスタンティノープルにおもむく。二十四歳の年だ。長男を与えた直後に死んだ最初の妻の実家は、ヴェネツィア貴族のヴェンドラミン家だったが、その家の一人を共同経営者にしての、交易
商才のほうも、神はこの男に並み以上を恵んだらしく、コンスタンティノープルでの事業は大成功だった。トルコ語もたちまちものにしてしまったのは、この時期である。人を魅了する能力は異教徒との間でも発揮され、スルタンのバヤゼットも宰相のアーメッドも、商人グリッティをまるで友だちあつかいにした。魅了の才は異性にもおよび、ギリシア女との間に、三人の男子をもうける。アルヴィーゼは、三男にあたる。
だが、トルコ滞在も二十年目をむかえようとする一四九九年、第二次のヴェネツィア・トルコ戦争がはじまってしまう。今度は、ギリシアのペロポネソス半島の南端にあるヴェネツィア基地に、トルコが食指を動かしたのが戦因だった。
このような場合、敵国に滞在するはめにおちいった民間人の安全の保証はないも同然だが、じっと身をひそめて
だが、スルタンも宰相も、もともとからして彼に好意を持っている。そのうえ、トルコ宮廷中が、なぜかこの敵国人を好いていた。広範な助命運動が効果を発揮し、死刑をまぬがれたのだ。
それどころか、スルタンは彼を釈放し、早くも打診のはじまっていた講和の交渉のために、グリッティをヴェネツィアへ送り返したのだった。
三年後に調印を終えるヴェネツィア・トルコ間の講和条約は、ヴェネツィアとコンスタンティノープルの間を一人で何度も往復した、彼がまとめあげたようなものである。グリッティ、四十八歳の年だった。
しかし、ヴェネツィア市民にとっては再び平和の地となったコンスタンティノープルに、グリッティは再びもどることはなかった。ヴェネツィア政府が、手放そうとしなかったからである。
ヴェネツィアは、再び平和を回復したものの、海外植民地ならば、失ったのはヴェネツィアのほうである。二世紀もの間、「ヴェネツィアの二つの眼」と呼ばれていたペロポネソス半島南端にある二つの基地を失ったことは、その近海の制海権も失ったということである。地中海で攻勢に出ているのは、いまやトルコ帝国であり、海運立国ヴェネツィアは、守勢に立たざるをえなくなっていた。
アンドレア・グリッティは、自分でまとめあげたこともあって、トルコとの講和の内実を誰よりも理解している。彼は、商業を捨て、国政に専念すると決めた。コンスタンティノープルに確実な地盤を築いた交易業のほうは、成人した長男と次男にまかせればよかった。
だが、気質でも肉体でも父親似のアルヴィーゼだけは、手もとに呼びよせ、ヴェネツィアで教育を受けさせることにしたのである。
ただ、手もとに呼びよせたとはいっても、この父と子がともにすごすことはほとんどなかった。ヴェネツィア政府が、次々とグリッティを要職につかせたからだ。
陸上の戦闘で参謀長をつとめたと思えば、戦い終了後は海に送られ、提督として軍船団を率いる。これを終えたとたんに、海軍全体の司令官の地位に選ばれてしまうという有り様。その合間にも、重要な政府の役職を歴任する。
もうこれ以上なにをさせたらよいかわからないという感じで、
このアンドレア・グリッティに、政治信条と呼ばれるものがあるとすれば、それはただ一つ、ヴェネツィア共和国の独立と平和の堅持、であったろう。陽の当たる道ばかり歩んできたこの男は、かえってそれがために、祖国にとって最も重要なことを見通していたのである。領土を広げることで繁栄する型の国家でないヴェネツィアにとっての独立と繁栄の確保は、可能なかぎり他国との間に戦争状態を起こさないことにしかない、と。
元老院議員になったばかりでも、マルコは、この考え方に完全に賛成だった。
なぜなら、元首グリッティが進めようとしている不戦路線が、単なる平和主義から生れた考えではないことがわかっていたからである。
4 ローマからきた女
アルヴィーゼ・グリッティが、再びマルコの前に姿をあらわしたのは、あれから三日がすぎた夕暮れであった。
その日は、「
夏のこの季節に合わせて、といっても海風の涼しさも考えにいれて、上半身を完全にかくしてしまう上着は、薄く織った上質のサテンづくりだ。ゆったりと仕立てられた上着のえりと
下半身は、脚に吸いつくようにぴったりと仕あげられた、黒のタイツにおおわれている。上着の腰のところでしめるベルトも、黒のサテンに黒い絹糸で一面に
装飾品は、胸までとどく金の鎖だけしかつけていなかった。鎖の加工の驚くほど
この面でも父親の血をひいていると思えば驚きもしないが、アルヴィーゼがなにを身につけても彼独自のスタイルにしてしまうのには、マルコはいつも感心してしまう。
マルコのほうといえば、国政に関与するようになって、一年中黒の長衣ですごせるので気が楽だと思うほど、身なりに気を遣わない
いたずらっぽい笑みを浮かべながら姿をあらわしたアルヴィーゼは、部屋に入ってくるなり言った。
「今夜は、外に出よう」
外に出ようといえば、二人の間では説明はいらない。十年昔もそうだったから今も同じだろうと、笑いで応じながらマルコは言った。
「誰のところに」
「きみの女友だちのところさ。それが誰だってことぐらいは、知っている」
夕食は、ここですませてから行くことにした。
その夕食の席で、マルコは、三日の間胸にためていた疑問を、ようやく晴らすことができたのである。
アルヴィーゼ・グリッティがヴェネツィアに到着したのは、七月半ば、父親に
この説明は、老いた父親が久しぶりに息子と会う良い機会と、わざわざ息子を呼びよせたというわけだから、疑いの余地もない。だが、マルコには、細い線のようでもいちまつの疑問は、捨てきれなかったのだ。なぜ、アルヴィーゼ一人が
しかし、マルコは、そこまでは友に問いたださなかった。兄たち二人は地味な性質で、コンスタンティノープルで堅実に商いをするだけで満足しており、そういう兄二人のことを、アルヴィーゼは親身に話したことはなかったからである。アルヴィーゼには昔から、マルコと同じとでもいうように、一人息子であるかのように振る舞うことが多かった。
「
「あれは気まぐれさ。でも、あのかっこうは、観察にはもってこいだね。近づいていくと人は眼をそむけるんだが、こちらからは、いくらでも観察できる。それに、どこに入っていっても怪しまれない。話しかけられる
マルコは、苦笑するしかなかった。あの身なりをするには政府の委員会の許可が必要なはずだと思ったが、それは口にしなかった。
アルヴィーゼのことだから、なにかの方法で調達したのだろう。そして、観察を
夕食を終えていざ出かけるというときになって、友は、マルコが着ていく服を自分が選ぶと言いだした。これも、大学時代にもどったようだった。アルヴィーゼはよく、怠惰なマルコを追い立てるようにして、彼が選んだ服を身にまとわせたものだ。だが、マルコのほうも、そういう友の心遣いを、甘美な心地で受けていたところもあった。
その夜、アルヴィーゼが衣装棚から選びだした服を見たとき、さすがのマルコも絶望的な声をあげてしまった。一度も袖を通したことのない、一着だったからだ。
あざやかではあっても単純な色合いではない緑色の地には、一面に繊細な金糸の刺繍がほどこされ、タイツは、それより濃くても同色の緑。仕立屋は、断然似合います、と太鼓判をおしたのだが、派手すぎて身にまとう気になれなかったのである。
しかし、十年ぶりに再会した友は、十年昔と同じに強引だった。
「きみの髪の色に、実に合う」
と言っただけで、結局マルコは、これに袖を通すはめになったのだ。大鏡に
オリンピア、という名の女の姓のほうは、誰も知らない。だが、その名だけで、誰もがわかってしまう女だった。
一年前にローマから移ってきた女だが、その移ってきようが、人の
ヴェネツィアにきたばかりの旅館住まいの時期に、彼女がまずやったことは、画家のティツィアーノに肖像画を描いてもらうことだったのである。
この画家の名声は、まだ若いのに、ヴェネツィアを越えて他国にまでおよび始めている。それに、ティツィアーノは、白い寝衣からこぼれおちそうな豊満な裸身という、花の女神フローラを思わせるポーズで描いたから、出来の見事さもあって、完成当時から大変な評判になった。
こうしておいて、オリンピアは、客筋をしぼったのである。
このオリンピアとマルコの仲のはじまりは、彼女の借りた屋敷が、マルコの所有のものだったからである。オリンピアは、その仕事の性質上、ヴェネツィアでは経済の中心とされているリアルト橋近くに住みたかったし、マルコは、そのあたりにちょうど手頃な家をもっていた。
ちなみに、ヴェネツィア共和国の国政担当者が無給で働くのは、建国以来の伝統になっている。体面維持やその他の経費を無視できない元首や各国駐在の大使たちには、経費という感じの報酬が支払われるが、他はすべて、国内にいるかぎり無給なのである。
国政を担当する権利をもつのが、「
この権利と義務をとどこおりなく果たすには、当然のことながら、ある程度以上の経済的基盤が必要になってくる。マルコの場合は、自分の住む屋敷の他に二つ家作をもち、その一つは旅館として貸し、もう一つは貸住居だったが、その二つともがヴェネツィアでは最も家賃の高いリアルト橋かいわいにあるため、数では少なくても家賃収入ではかなりの額になるのだった。この他に、伯父が受けもっている交易事業への、投資からあがる利潤がある。
ヴェネツィア貴族としては、これはごく普通の生き方だった。
共和国国会には、嫡出の男子ならば全員が議席をもてるが、元老院は一家に一人ときまっている。一家系に権力が集中するのを防ぐ目的もあったが、それだけではない。政治をするに最も適した一人だけが国政に専念し、他の者は経済活動に力をふるってもらうという、ある意味では大変に合理的な配慮から生まれた分業制度であった。
マルコは、だから、ダンドロ家の代表なのである。一一九二年に
借家人オリンピアと家主マルコの間は、しばらくするともっと近い関係になった。
マルコ・ダンドロが、
それでも、これが二人の性格でもあったのだが、借家人はきちんと家賃を払いつづけ、家主のほうも、客として訪れるときは、その義務をおろそかにしなかった。今夜も、行くときまった段階で老僕を走らせ、来訪を告げさせてある。
二人が通されたのは、広すぎも狭すぎもしない、運河に面した二階の一室だった。
運河に向かって開いた二つの窓の間の壁面には、金色に塗られた唐草模様の額ぶちに囲まれた、ティツィアーノ描く女主人の肖像画が飾ってある。裸体と言ってもよいくらいの、等身大の上半身を描いたものだ。
そのちょうど反対側の壁には、同じ色で同じ大きさの額ぶちに囲まれた鏡が飾ってある。もう二つの壁面も同じ形の鏡で占められているので、この部屋に入ると、どこにいても、いやでも眼の中に絵がとびこんでくる感じになった。
しばらく待たされた後、ようやく女主人が姿をあらわした。
他の遊女ならば、乳首まで
このオリンピアを眼にするたびに、マルコは笑いを押さえきれないのだった。
なにもかもたっぷりという感じの裸身を、絵とはいってもさんざん見せつけておいて、その後で当人は肌もうかがわせない服をつけてあらわれるのだから、と、心の中では笑ってしまうのである。
これがオリンピアの利口なところだとわかっているのだが、慣れているマルコさえまんまと引っかかってしまうのだから、フランスやドイツからきた社会的地位も高く経済力もある男たちが、たちまち足しげく通うようになるのも当り前だった。
部屋に入ってきたオリンピアは、マルコには軽く
そのアルヴィーゼに、
「お友だちね。すぐわかったわ。それも、とってもお親しい仲でしょう」
マルコは、幼なじみであることと、友の名を告げた。オリンピアは、ほんの一瞬アルヴィーゼを見つめたが、すぐに華やかな声が二人をつつんだ。
「あちらの部屋へ行きましょう。ここでは、おおぎょうすぎますわ」
なに、誰にでもこうなのだ。ティツィアーノ描く絵から離すのが、オリンピアの、客に対する第二の戦術なのだ。別室に通されたとはいえ、男たちの眼の底には、あの見事な裸身がこびりついて離れないのを、充分に承知しての戦術なのである。
眼の底には豊潤な裸身がこびりついているのに、眼の前の当人ときたら、そのようなことは考えてはならないとでもいうかのような服に身をかためている。男ならば、誰でも、眼の底の像と眼の前の当人とを、同じにしてみたいと思うのは当然だろう。
二人が通されたのは、この家の女主人がたわむれに、音楽室と呼んでいる一室だった。クラヴィチェンバロがあり、リュートが立てかけてあり、マンドリンもおかれている。オリンピアは、楽器を
その夜は、三人だけの音楽会が催された。マルコは、クラヴィチェンバロを受けもつ。リュートをつま弾くのは、アルヴィーゼの役目だ。オリンピアは、マンドリンをかかえたり、歌ったり、リュートの独奏をしたり、クラヴィチェンバロに向かったりで、なんでもできるだけに忙しい。
涼しい海からの風が、
音楽の合間に交わされる話は、オリンピアがついこの間まで住んでいた、ローマの話題が中心になった。
マルコもアルヴィーゼも、あれほど外国を知っていながら、ローマにはまだ行ったことがない。それでも、オリンピアの話しぶりがとても生き生きとしているので、彼ら二人が学び聴き知っている永遠の都が、眼の前に浮かびあがってくるようだった。
それでもやはり、三人の話は、つい三カ月前に起こった「ローマの
この知らせが共和国国会で告げられたときの、二千人もの議員の全員が受けた衝撃の深さを、マルコは昨日の出来事のように思い出していた。これによって、スペインは、ますますイタリアへの攻勢を強めてくるだろう。イタリア半島内でこのスペインに対抗できる国は、ヴェネツィア一国になってしまった。
だが、「ローマの掠奪」は、起こるべくして起こったと言ってもよい不幸なのだ。法王庁は、対策を立てるのを怠った。そうなりそうなことを事前に察知し、沈没しようとする船から逃れたネズミも少なくない。噂では、オリンピアもその一人ということだった。
愉しく陽気であった夜の音楽の集いも、沈んだ雰囲気のうちに終わりそうになったが、それを救ったのもオリンピアだ。人の気分を引き立てるのが仕事といっても、彼女のそれは超一級だった。
ローマにいる
5 舞踏会
翌日は、日曜にあたっていた。共和国国会は、毎週日曜の午前中に開かれるときまっている。それに出席して帰宅したマルコを、思いもかけない客が待っていた。
オリンピアは、教会からの帰りに寄ったという。それらしい地味な身なりをしていた。一見しただけでは、ヴェネツィアでは中流階級にあたる、造船所の技師かガラス工場の親方の女房といわれたって、不思議ではないかっこうだ。だが、どんな身なりをしていようと、マルコにとってのオリンピアは、オリンピアでしかなかった。
その日は、誰に気がねすることもなく、二人は抱きあった。そして、召使の老夫婦が
小さなボタンで一列に閉じられた胸もとを、あけていくのさえもどかしかった。元老院議員の黒の長衣が、荒々しく脱がれ、床に放り出される。
首すじのところでまとめていた金髪の留め金を、はずしたのは女のほう。豊かな髪が、金糸をまき散らしたかのように流れおちる。この女は、まったく、なにもかもがたっぷりなのだ。大きく張りきった乳房は、男の手を待ってふるえおののき、バラ色の乳首は、もうすでに固く突きだしていた。
オリンピアの豊潤な、しかしこれ以上豊潤になったら崩れてしまう限度ぎりぎりで豊潤な、真紅の血を内に感じさせる白い裸体が眼の前にあった。
女のからだは、波うっていた。三十歳の男の健康な肉体が、存分に
マルコがオリンピアを好むのは、互いに欲するものを存分に味わいつくしたすぐ後でも、ごく自然に会話に入っていけるところにある。無防備で安らぎをたたえた表情のまま、女は言った。
「昨夜のあなたのお友だちは、ほんとうに素敵な方ね」
マルコは、ほんの少しだが不機嫌になって、そう、と答えただけだった。そんな男を、笑いをふくんだ眼で見やりながら、女はなおも言う。
「でも、心配はいらないことよ。あの方には、秘めた
「誰だい、それは」
マルコには、これは意外だった。女がいないアルヴィーゼではないとは思っていたが、秘めた愛人となれば話は別だ。だが、オリンピアは、
「わたしの
マルコは、それこそ眼を球のようにして、愛人を見つめるのだった。
話題を変えようとしたのか、オリンピアは、今夜催される舞踏会のことを話しはじめた。
もちろん、マルコは招待をうけている。だが、同行などは、考えもできないことなのだ。話題を変えたのは、今度はマルコのほうだった。
「アルヴィーゼには、会えるだろう」
「あの方は当然、出席なさいますよ。
でもあの方も、どんなお気持ちで行かれるのやら」
話題の変え方が充分でなかったと、優しい気質のマルコは反省する。それと同時に、昨夜もオリンピアの家を出て別れるとき、友は父親の住む
アルヴィーゼは、
現職の
――二十五日の朝、
花嫁は、慣習に従ってとき流した髪に白絹の衣装のすそを長く引き、行列は、
花嫁に従う婦人たちの衣装は、いずれも豪華で美しく、重い金の鎖や数々の色とりどりの宝石で飾られていた。とくに、見事な
男性側も、華麗さでは少しも見劣りせず、とくに、多くの宝石がちりばめられた、コルネール殿の胸飾りはすばらしいものであった。キプロス王の持ち物であった品という。
出席者は、
ただ、花婿のつきそいをつとめたコンタリーニ家の男たちが、花婿ともども黒地のビロードの衣装であったのは、わたしの思うには適当でなかったと思う。このような祝事の席では、せめて色模様もあざやかな絹服をまとうべきではなかったか――。
マルコは、元老院議員として招ばれたのではなく、コンタリーニ家と匹敵する名門ダンドロ家の代表として招待されていたから、
その夜のマルコは、空色の絹の服をつけていた。ところどころに銀糸のふちどりのある華やかなものだが、黒い髪と調和して若々しい。
夜会の会場には「
夕食中のマルコとアルヴィーゼの席は、だいぶ離れていた。アルヴィーゼが、親族のかたまったテーブルにいたからだ。
今夜のアルヴィーゼは、晴れた夜空を思わせる
袖のいくつかの箇所を割り、そこから下の白シャツをのぞかせるというのは、もともとが女の服の流行なのだ。それを男物に応用しだしたのは、ヴェネツィアでは若い貴族たちだったが、たちまち大流行になり、他国でもまねするようになっていた。
女たちだって、よいと思えば、誰からでもまねしたのである。その夜出席していた婦人たちは、未婚の娘は公式の場に出られないためにみな既婚の婦人ばかりだったが、いずれも色とりどりの豪華な衣装に身をつつんでいても、胸もとだけは深く開けている。
これは、ヴェネツィアでは
もちろん男の気をひくためだが、男の気をひく効用に眼をつけたのが、貴族の既婚婦人たちだった。どんなに政府が非難通告を発しても、この流行はすたれそうにはなかった。
食事が終わると、手ぎわよく食卓がとりのぞかれ、広間は舞踏の場に一変した。
まず花婿と花嫁が、次いでコンタリーニ家の男はグリッティ一族の婦人たちと、グリッティ家の男たちはコンタリーニ家の婦人方というふうに、舞踏のカップルがあちこちでできていた。
ゆるやかなバラードが、広間を満たしていく。男と女に分かれた列が、楽の音につれて、近づいたり離れたり、あるときは手をとってまわったりするたびに、舞踏の列に加わっていない人の胸までがときめいてくるのが、舞踏会というものの抗しきれない魅力なのだ。列は、いつのまにか三つに増えていた。一曲終わるたびに、列に加わる顔ぶれも変わる。それを抜け出たらしいアルヴィーゼが、いつのまにか背後に立っているのに、マルコは突然気がついた。
振りかえったマルコに、友は、軽く背をつついただけでなにも言わなかった。
ただ、マルコは、友の眼が、この場にそぐわない憂愁をおびているのに驚いた。そして、思わず追ったその視線の向こうに、一人の婦人の姿があった。
プリウリの奥方だった。夫は、グリッティが
年の開いた夫婦は珍しくないヴェネツィア貴族でも、この夫婦の年齢の差は、結婚した当初から評判だった。夫人はヴェネツィアの貴族コルネール家の出身だが、夫よりは三十は若い。だが、ヴェネツィアの上流階級では、結婚は、家と家の間で成されるのが常識だった。
プリウリの奥方といえば、誰でもまず「美しい人」という言葉が頭に浮かぶほど、彼女は美しかった。だが、他の婦人方とはちがった。
必死になって髪を陽にさらしてまで金髪に似せようとする女が多いヴェネツィアでは珍しく、彼女の髪は深い黒のままだ。それに、化粧をしていないのかと思うほどの薄化粧。胸もとも、他の婦人方とはちがって深くは開けてはいない。黒い豊かな髪は、それでも流行をとり入れ、耳もとでゆるく三つあみにしたのを、優雅に結いあげている。
その夜、プリウリの奥方がまとっていたのは、深い色合いの緑のあや織りの衣装。両側から結いあげた三つあみの束が出合うひたいには、しずくの形をした大粒の真珠がゆれている。首飾りも、見事なほど大きな粒のそろった真珠の一連を、首から胸にかけてゆるやかにまわして、中央部をブローチでとめてある。
そのブローチの出来がまたすばらしく、エメラルドとルビーをはめこんだ繊細な金細工は五センチ四方もあり、その下には、ひたいにかかっているのと同じ形の、大粒の真珠のしずくがゆれるというつくりだ。
黒と緑に真珠色だけのプリウリの奥方は、美しいことは美しかったが、近づきがたい美しさだった。子供はいないが、貞淑なことでも評判の婦人だ。女に不足するわけでもないのに、なにもあのようなむずかしい
召使たちが、銀盆にのった鈴をくばりはじめていた。金の鈴は、二つずつ、赤いリボンで結わえてある。いつのまにかそばにきていた
「アルヴィーゼ、モレッカはおまえのものだ」
父親に
モレッカとは、アラブ風のリズムをとりいれた、もともとは戦闘の踊りなのである。二人一組になった踊り手は、互いに両手に鈴の束をもち、足ぶみも強く激しい踊りをくり広げる。モレッカ、というかけ声がかかると、舞踏会では若い男女の目の色が変わるといわれたほど、イタリアでは好まれた踊りであった。
マルコが眼を丸くしたのは、アルヴィーゼの踊りの巧みさではない。この旧友がモレッカの名手であることは、大学時代にさんざん眼にしていた。驚いたのは、プリウリの奥方の変容であったのだ。
冷たい
マルコは、これまでにもこの婦人の踊るのを見たが、今夜のように激しく燃える舞い方を眼にするのははじめてだった。互いに見つめ合いながら踊る二人の眼は、解けそうもないほどにかたく結ばれ、この二人の他には、誰も存在しないかのようであった。
モレッカの後は、
召使から手渡された燭台を手にした女は、これと思った男に近づく。そして、女が差し出す燭台を受けとった男と連れだって、広間の中央に舞い出ていくという踊りだ。舞踏会では、モレッカとともに、人びとがなによりも待ちのぞむ踊りだった。
広間中の灯りは消された。女たちのもつ燭台の光だけが、あちこちできらめく。モレッカを踊ってもどってきたアルヴィーゼのそばには、何本もの燭台が近づいてきていた。
それにはすぐに応じず、アルヴィーゼは、かたわらのマルコにささやいた。
「眼かくしをしてくれ」
マルコは、袖口にさしこんであった空色の絹のハンカチを抜きとり、それで友の眼をかくす。
アルヴィーゼは、眼かくしされたままで手さぐりし、それにふれた燭台のところで手をとめた。けたたましい喜びの声をあげたのは、フォスカリの奥方だ。このときはじめて眼かくしをはずしたアルヴィーゼは、左手で奥方の丸々と肥えた腕をとり、右手で燭台をかかげながら、広間の中央に出ていった。
何十組にもなる踊りの輪が、蝋燭の光をきらめかせながら、ゆるやかなバラードの曲にのって舞いはじめる。いつものことながら、色とりどりのリボンを混ぜて投げだしたような色彩の洪水に、蝋燭ならではのやわらかい光が
自分も、誰かを気にしない相手と踊りに加わっていたマルコは、そのときになって、燭台を手にアルヴィーゼに近づいてきた婦人たちの中に、プリウリの奥方の姿がなかったことを思い出していた。