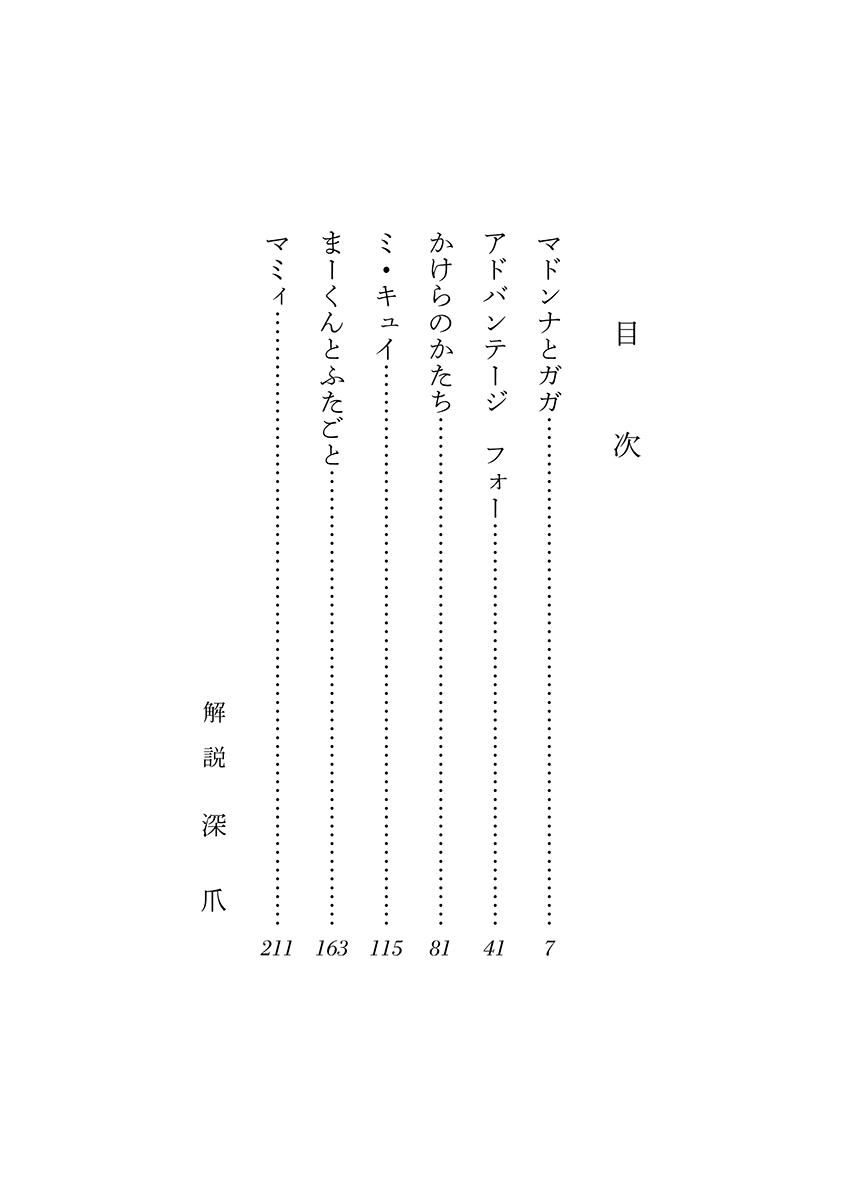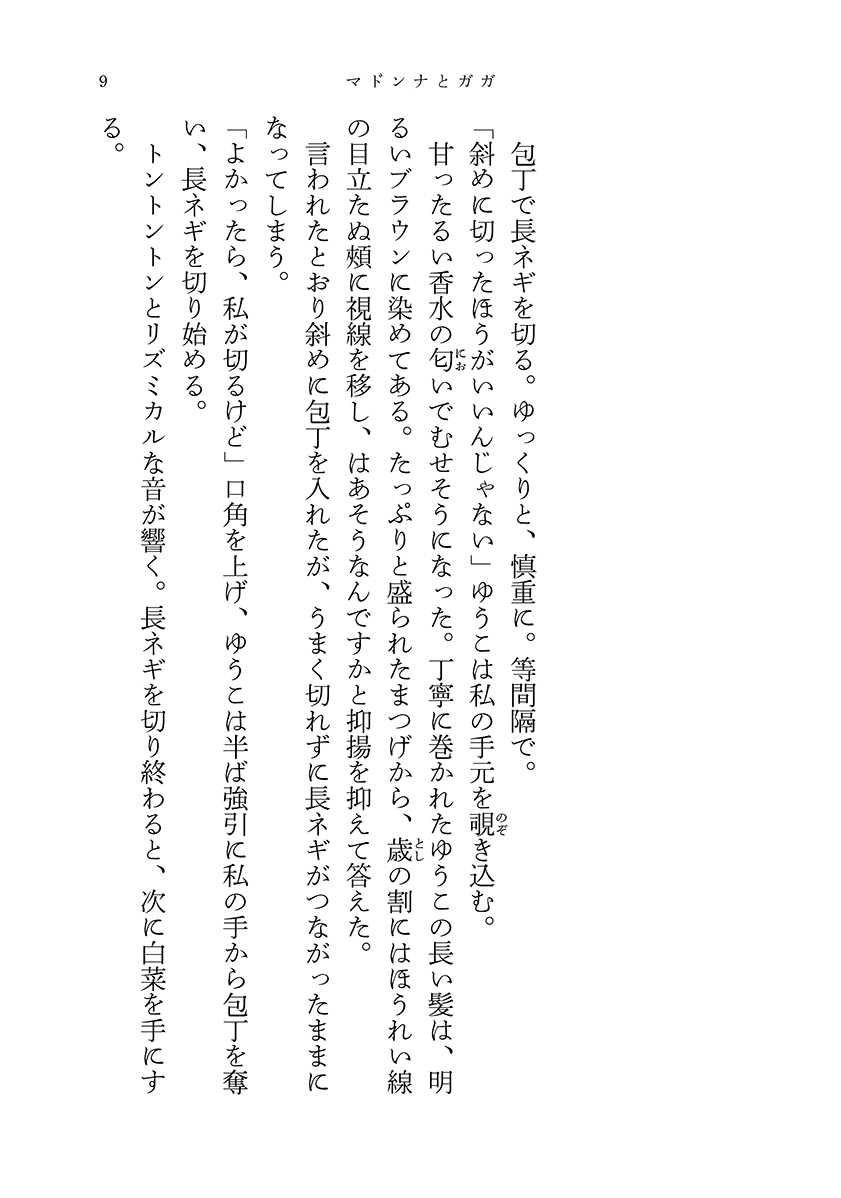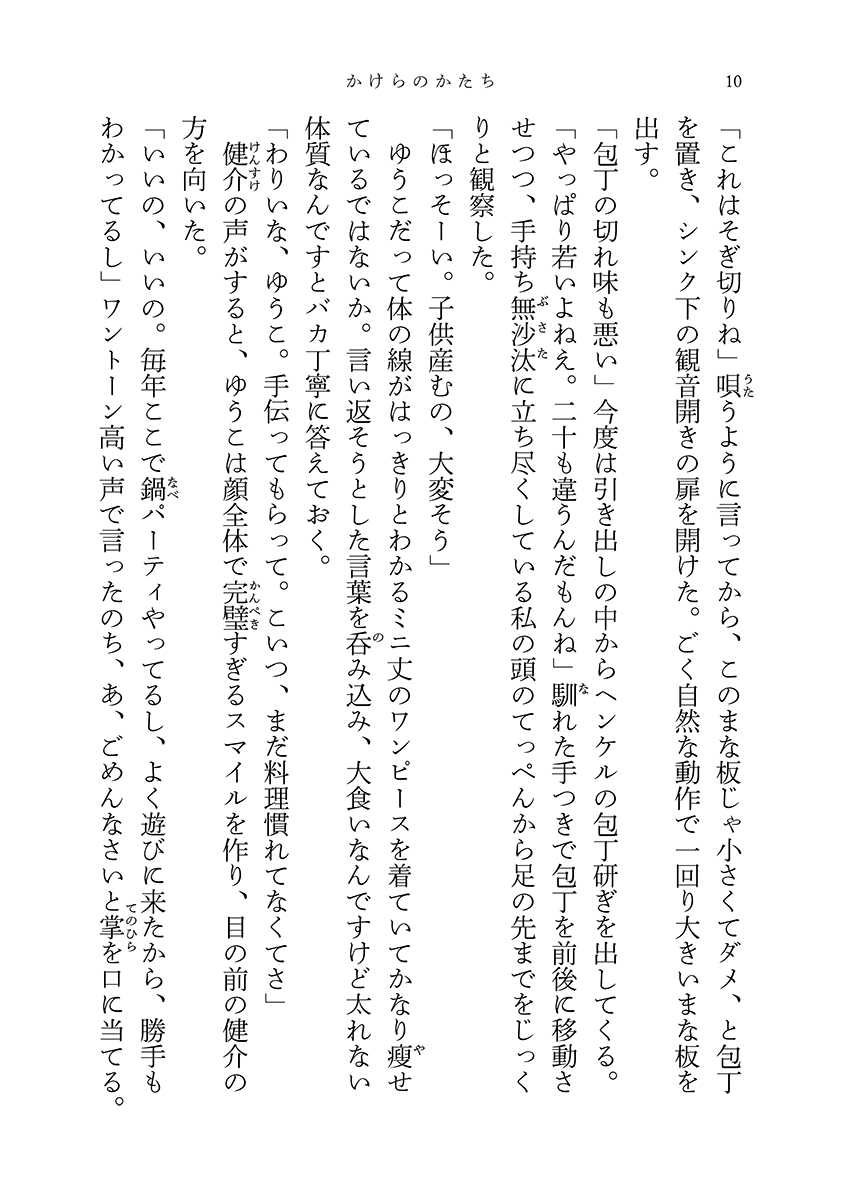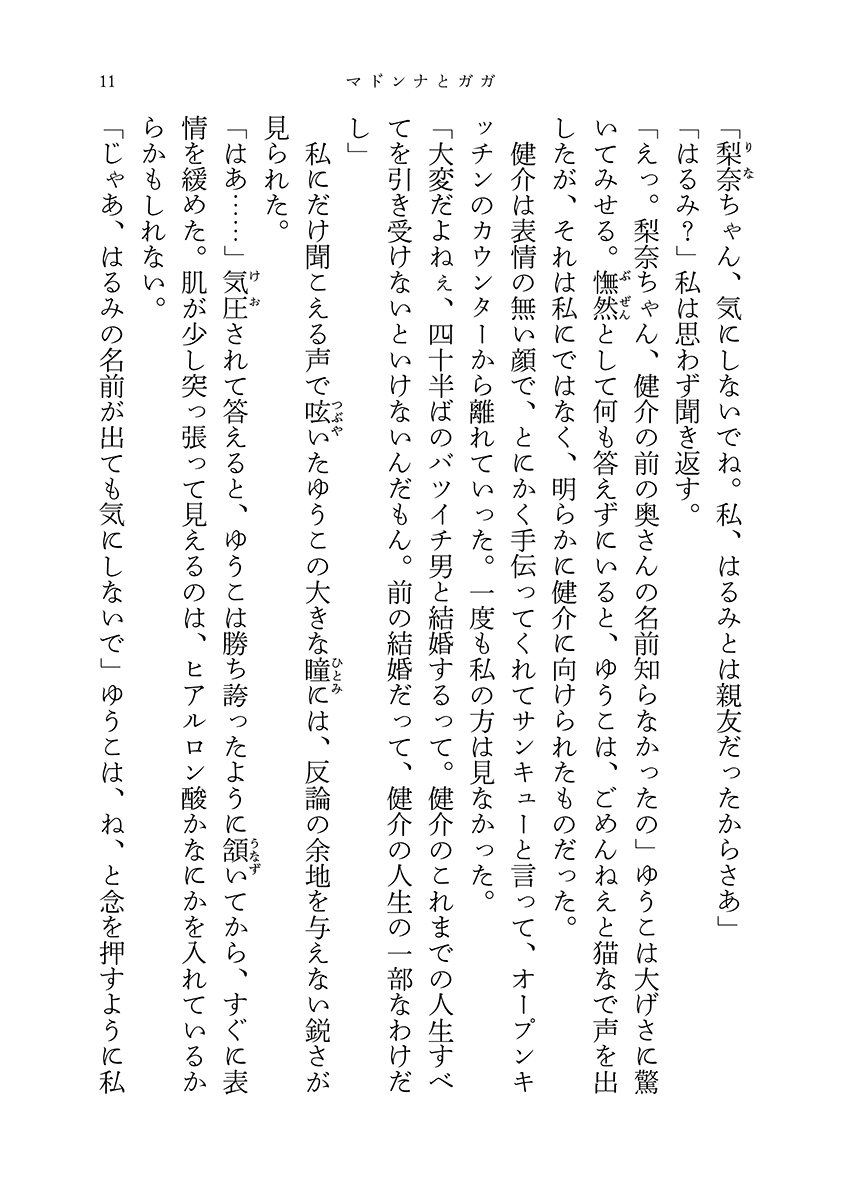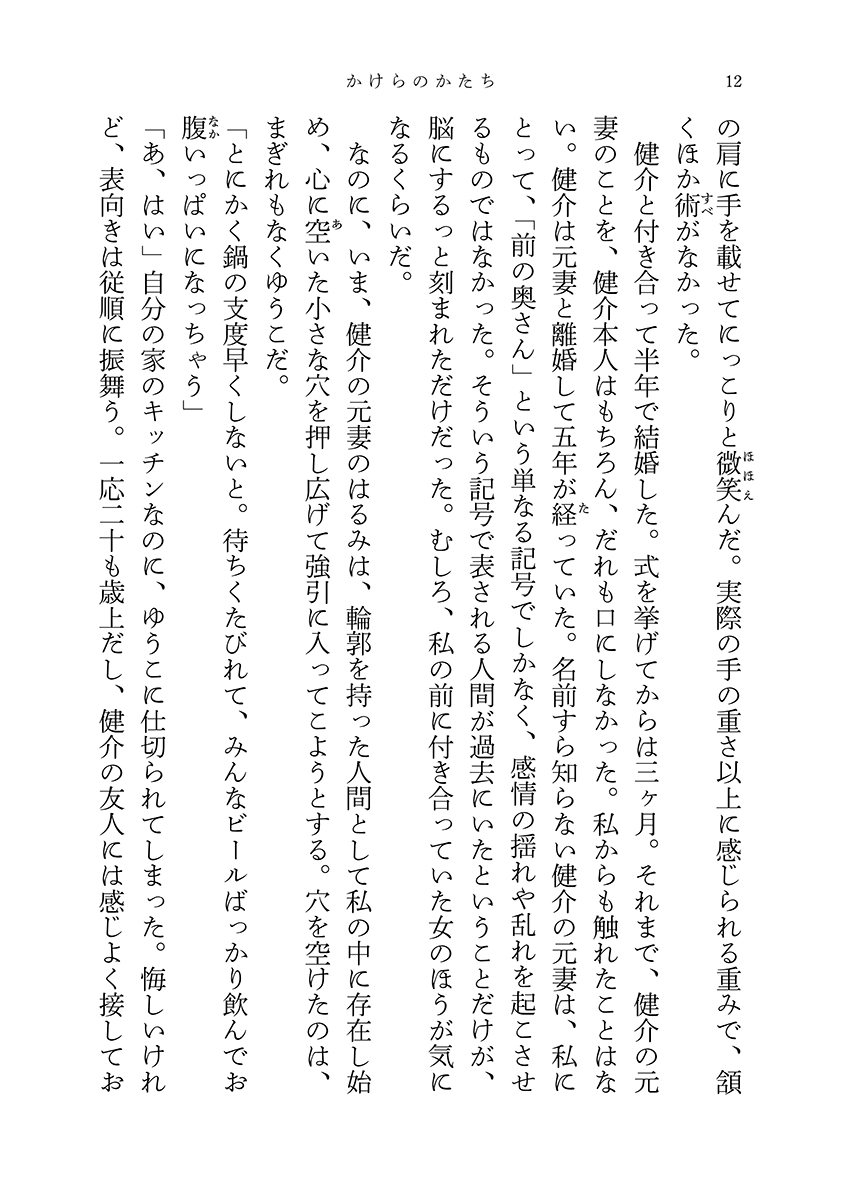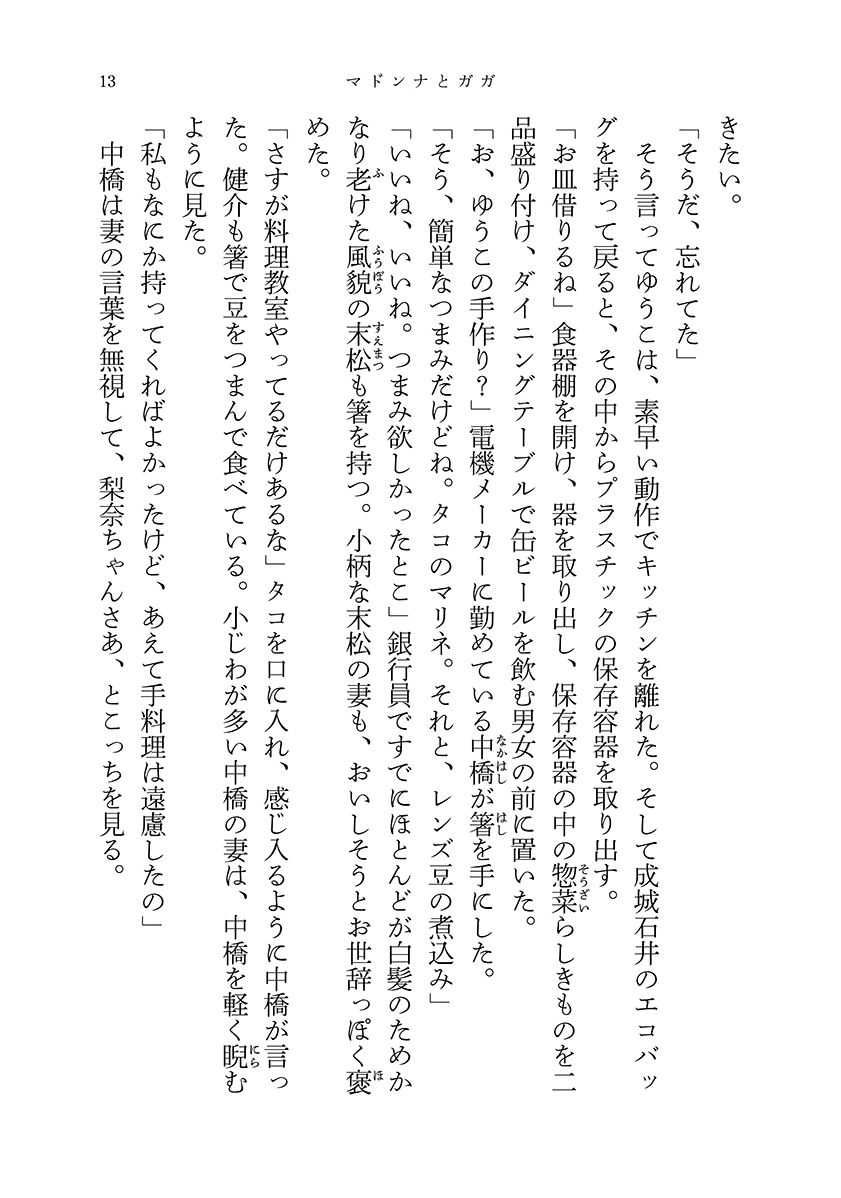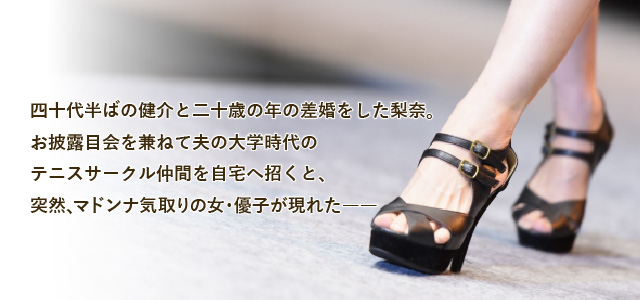
マドンナとガガ
包丁で長ネギを切る。ゆっくりと、慎重に。等間隔で。
「斜めに切ったほうがいいんじゃない」ゆうこは私の手元を
甘ったるい香水の
言われたとおり斜めに包丁を入れたが、うまく切れずに長ネギがつながったままになってしまう。
「よかったら、私が切るけど」口角を上げ、ゆうこは半ば強引に私の手から包丁を奪い、長ネギを切り始める。
トントントンとリズミカルな音が響く。長ネギを切り終わると、次に白菜を手にする。
「これはそぎ切りね」
「包丁の切れ味も悪い」今度は引き出しの中からヘンケルの包丁研ぎを出してくる。
「やっぱり若いよねえ。二十も違うんだもんね」
「ほっそーい。子供産むの、大変そう」
ゆうこだって体の線がはっきりとわかるミニ丈のワンピースを着ていてかなり
「わりいな、ゆうこ。手伝ってもらって。こいつ、まだ料理慣れてなくてさ」
「いいの、いいの。毎年ここで
「
「はるみ?」私は思わず聞き返す。
「えっ。梨奈ちゃん、健介の前の奥さんの名前知らなかったの」ゆうこは大げさに驚いてみせる。
健介は表情の無い顔で、とにかく手伝ってくれてサンキューと言って、オープンキッチンのカウンターから離れていった。一度も私の方は見なかった。
「大変だよねぇ、四十半ばのバツイチ男と結婚するって。健介のこれまでの人生すべてを引き受けないといけないんだもん。前の結婚だって、健介の人生の一部なわけだし」
私にだけ聞こえる声で
「はあ……」
「じゃあ、はるみの名前が出ても気にしないで」ゆうこは、ね、と念を押すように私の肩に手を載せてにっこりと
健介と付き合って半年で結婚した。式を挙げてからは三ヶ月。それまで、健介の元妻のことを、健介本人はもちろん、だれも口にしなかった。私からも触れたことはない。健介は元妻と離婚して五年が
なのに、いま、健介の元妻のはるみは、輪郭を持った人間として私の中に存在し始め、心に
「とにかく鍋の支度早くしないと。待ちくたびれて、みんなビールばっかり飲んでお
「あ、はい」自分の家のキッチンなのに、ゆうこに仕切られてしまった。悔しいけれど、表向きは従順に振舞う。一応二十も歳上だし、健介の友人には感じよく接しておきたい。
「そうだ、忘れてた」
そう言ってゆうこは、素早い動作でキッチンを離れた。そして成城石井のエコバッグを持って戻ると、その中からプラスチックの保存容器を取り出す。
「お皿借りるね」食器棚を開け、器を取り出し、保存容器の中の
「お、ゆうこの手作り?」電機メーカーに勤めている
「そう、簡単なつまみだけどね。タコのマリネ。それと、レンズ豆の煮込み」
「いいね、いいね。つまみ欲しかったとこ」銀行員ですでにほとんどが白髪のためかなり
「さすが料理教室やってるだけあるな」タコを口に入れ、感じ入るように中橋が言った。健介も箸で豆をつまんで食べている。小じわが多い中橋の妻は、中橋を軽く
「私もなにか持ってくればよかったけど、あえて手料理は遠慮したの」
中橋は妻の言葉を無視して、梨奈ちゃんさあ、とこっちを見る。
「ゆうこに料理習いに行けばいいんじゃない? こっから近いし」
「やだあ、近所のママたちに教えてるだけだから、それほど大層なものじゃないって。だけど、梨奈ちゃんがよければどうぞ」
私は切り分けた
「まあ、それなりにやってるし、大丈夫だよ」そう言って健介はビールを
今日は健介が親しくしている大学時代のテニスサークルの仲間を呼んでの鍋パーティだった。

二回目だから派手な結婚式はしたくないという健介と、一生に一度の晴れ姿だから思い出深いものにしたいという私との妥協点は、
しかし、まさか女友達も来るとは思ってもみなかった。健介の男友達とその妻だけを招待したのに、ゆうこは単身でやってきた。玄関でゆうこを見た健介は間の抜けた顔で、おお久しぶり、と応じていたから、ゆうこが来ることは知らなかったようだ。
勤めていた会社にも年齢を感じさせない先輩がいたが、ゆうこはでっぷりと太って
「ゆうこ、フェイスブックで今日のこと知ったんだよな?」中橋が
「私を呼ばないなんて水臭い。毎年恒例の鍋なのに」ゆうこは中橋の腕に手を添えた。中橋は、ま、そうだねとまんざらでもない様子だ。それを見た、ゆうこより格段に地味な見てくれの中橋の妻は、一瞬だが
「それに、健介の奥さんに会ってみたかったから」ゆうこは私を
鍋を囲んでの酒席が始まった。
「健介、ほんと鍋奉行だよな」
末松が言うように、健介は頃合を見計らって
二人の姿を見ていると、胸に綿が詰まっていくみたいに、息苦しくなってくる。
会話は、ちょっと前のゴルフのラウンドの話から、大学時代のエピソードまで幅広い。家族ぐるみの二十年以上の付き合いは、話題が尽きなかった。ときどき気を使って末松あたりが私に話をふってくれるのだが、自分の経歴や健介との出会いなどの一通りの質問に答えると、それ以上話は発展せず、すぐにゆうこが話を持って行ってしまう。私はもともと社交性がなくて、こういう席は苦手なのだ。気の
ひとり透明人間にでもなったような気がして、鍋からたちのぼる湯気をぼんやりと眺めていた。
インターホンが鳴った。
エントランスホールの扉を開け、高島を招き入れると、五分もしないうちに玄関チャイムが鳴った。高島の登場に、おっせえなと中橋が酔って赤くなった顔で
「なんでお前一人で来たんだよ。ちはるちゃんは?」
高島はサークルの後輩と結婚したそうだ。ゆえに、みんなが高島の妻のちはるを知っている。
「いいだろ、別にあいつがいなくても」高島は不機嫌に答え、レジ袋に入った缶ビールを立っている私にぶっきらぼうに渡した。
「こいつら相当飲むから、足りなくなると思ってさ」袋からすると近くのコンビニで買ったらしい。見た目と違って気が利いている。
高島も席に加わり、ますます話が盛り上がっていく。高島は歯に
胸の苦しさが、しだいに刺すような痛みに変わってくる。
鍋を見ると、汁が半分ぐらいになっていたので、立ち上がってキッチンに行った。冷蔵庫からだし汁を、冷凍庫から母が送ってくれた冷凍
席に戻り、鍋にだし汁を足し、カセットコンロの火を強めた。餃子を載せた皿をテーブルに置く。
「へえ、餃子を鍋に入れるの?」ゆうこが気づいた。
「これ、実家の母が送ってくれた餃子で、水餃子にしても
「梨奈ちゃんの実家って、茨城かどっかだっけ?」ゆうこが訊いてきた。
「いえ、栃木です」さっき言ったばかりなのにと腹がたったが、感情を抑えて答える。
「あ、そうなの。私、東京生まれ東京育ちだし、駐在でスペインとシンガポール行った以外は成城
「お前さあ」
「餃子っていやあ宇都宮じゃん。栃木と茨城がわからないって、いい歳して物を知らないってのは、
「それにお前の家も実家も成城じゃなく
「失礼しちゃう、駅は成城なんだから」ゆうこは、頬を膨らませすねたそぶりをして隣の中橋の
「変わんねえな、お前。いつまでもサークルのマドンナ気取りでいるのはみっともねえぞ」吐き出すように言った高島は、空いたビールの缶を握りつぶした。私はつい口元が緩んでしまう。
「ひっどーい」ゆうこは中橋の袖を放すと高島に、そうだ、と含みのある笑顔を向ける。
「私、高島がなんで今日一人で来たか、知ってるよ」そして、自分で持参した赤ワインをぐいっと飲み干した。
「なんだよ、うるせえな。お前も一人で来たんだろ。ダンナはどーしたんだよ」
「ダンナ?」目の縁を
「三年前から別居中」ゆうこの一言でその場がしんとなった。妻たちが驚いてゆうこの方を向く。男性陣は口を開けたり、目を見開いたりしてゆうこを見つめている。
「ふん。うちの主人、二十も下の女に熱あげちゃってんの。ばっかみたい」
ゆうこは手にしているグラスに自分でボトルのワインを注ぎ足そうとする。その手を高島が
「やめて、高島。高島だって別居してんじゃない。おんなじじゃない」ゆうこは高島の手を振り払って強引にワインを注ぐ。テーブルに赤い液体がこぼれる。

「お前、いい加減にしろよ。飲み過ぎだって」怒鳴るように高島が言ったが、ゆうこは構わずワインをがぶ飲みする。その様子を見守っていた健介は、眉を少しばかり上げて、心配そうな顔になっている。
「気持ち悪い」突然口を手で押さえてゆうこが立ち上がり、キッチンの方へ走る。高島も立ち上がり、ゆうこを追う。私も仕方なく後に続いた。
ゆうこは、派手な作りの顔を
キッチンの作業台は白っぽい人工大理石でできている。そこに飛び跳ねた赤い
ゆうこはキッチンのシンクで二回、トイレで三回吐いた。傍らには高島が付き添っていたが、吐ききって落ち着くと、高島がゆうこを送って先に帰った。その後、中橋と末松、その妻たちが、片付けと掃除を手伝ってくれた。便器周りが汚れたトイレの掃除は健介が受け持った。
掃除と片付けが済んで、中橋と末松の両夫婦が帰ったのは、午後十時を回っていた。マンションのエントランスホールで彼らを見送って部屋に戻り、健介と並んでソファに座る。
何を話したらいいかわからない。健介も黙っている。なんとなく私の視線を避けているような気がする。
健介がおもむろにリモコンでテレビを
箱の中には、健介の選んだものと私の選んだものが半分ずつ。
「コーヒー
「コーヒー飲むと眠れなくなるからいい。
私は、箱からショートケーキを取り出した。フィルムをはがし、立ったまま手づかみで口に押し込む。クリームが唇の周りについても、構わず食べる。むせそうになるが、三口で食べ終え、続いてシュークリームを手にし、口に入れる。
私はからだのなかの
三個目のチョコレートケーキを飲み込んでも、美味しいんだかまずいんだか、よくわからない。ちっとも甘さを感じなかったし、満腹感もなかった。四つめのモンブランに半分ほどかじりついてふとシンクの作業台を見ると、拭き忘れた小さな赤い
モンブランをその斑点めがけて投げつける。べしゃっという音とともにケーキが
寝室に入ると、健介はいびきをかいていた。酒を多く飲んだ日の健介はいびきがひどい。
自分のベッドに腰掛ける。
健介と私のベッドの間の一メートル足らずの距離が、今日はいつもより離れているように感じた。新婚だから当然一緒のベッドだと思っていた私の予想を裏切り、同じベッドだとよく眠れないという健介の希望で、健介がそれまで使っていたセミダブルのベッドの隣に私の使い込んだシングルベッドを運び入れた。せめて二つのベッドはぴったり付けるのかと思ったら、近くに人の気配がすると寝付けないと健介がこのようにベッドを配置した。
身体を横たえて、健介を眺める。白髪はそれほどないが、おでこは広くて、よく見ると頭髪もそう多くはない。羽毛
私にも過去があるように、当然健介には私以上に物語がたくさんあるのだろう。この寝室に何人の女が泊まったのだろうか。今まであまり考えたことがなかったのに、今日は気になってしまう。
はるみという名の健介の元妻がやはり一番長くこの部屋で過ごしたのだろうか。私の寝ている場所にはるみのベッドが置いてあったのか。それともダブルベッドで二人寄り添って眠っていたのだろうか。
はるみって、どんな女なのだろう。想像してみるが、思い浮かぶのは、化粧の濃いゆうこの顔なのだった。
頭を左右に振って灯りを消し、目を閉じた。だが、ケーキの後にティーバッグで淹れて飲んだ紅茶のカフェインのせいだろうか、なかなか眠りに入ることができなかった。胸焼けも残っている。健介のいびきも
目を開けて健介の方にまた視線をやる。少しすると目が慣れて、暗がりの中、健介のシルエットが浮かび上がってくる。
健介は勤務先の上司だった。成城育ちのぼんぼんのバツイチということで、飛び抜けていい男というわけでもない割には、結婚に

九ヶ月前の土曜日、シャトレーゼのケーキを買っておいたが勇太と連絡がつかなかった。私は翌朝までケーキの箱を開けずに待った。五年間、何度もこういうことがあった。他の女の影がチラついたこともあれば、単に携帯の充電が切れたまま友達と飲んでいた場合もあったが、要するに勇太が私を軽んじているということの表れであった。そしてその度に
会社で映画のチケットを二枚もらったので、勇太と週末に
私は
誘われて駅近くの安いそば屋に入った。
「休日に一人でご飯食べるの、寂しくてね。付き合ってくれてありがとう。ここはご
「部長って、実家がすぐ近くじゃないんですか」
「そうなんだけど、親んとこ行くと、内孫の顔を見たいから早く再婚しろだのなんだのうるさいし、ダンナが単身赴任中の妹がチビ二人連れてしょっちゅう来てて、落ち着かないんだ」
そうなんですかと適当に話を聞き流しながらそばをすすった。
「それにいつも接待で結構
そば屋を出た後スイーツでも食べてお茶しようと言った健介の誘いを断って、町田のアパートに戻ると、勇太がいて、ケーキを先に一人で食べてしまっていた。箱に残った一個を見つめて、一緒に食べようと思ったのにと呟いた。
「腹減ってたからさ」勇太は悪びれずに答える。
「出てって」私が低い声で言うと、勇太は黙ってさっさと玄関を出ていった。
うんざりしているのに、なんのために、どうして勇太と付き合っているのだろう。
私は箱からケーキを取り出し、皿に載せた。細いため息が
フォークで苺を刺して、口に放り込む。続けて生クリームとスポンジをフォークで
一人でケーキを食べるのは、ちっとも美味しくない。やっぱり嫌だ。
私は食べかけのケーキを箱に戻して、冷蔵庫に入れた。
翌週の金曜日にメールが来て、健介から映画に誘われた。週末家にいてもどうせ一人で暇なので行くことにした。勇太とはそのまま連絡が途切れていた。
健介との待ち合わせに向かう前に、冷蔵庫に入れっぱなしだったシャトレーゼのケーキを箱ごとゴミ箱に捨ててから家を出た。
映画に行ってご飯を食べるという付き合いが始まって三ヶ月後、健介の住むマンションに初めて足を踏み入れた。築十年だそうだが、ホテルのように
「結婚してここに住んでほしい。毎日一緒に飯を食おう。そして俺の子どもを産んでくれ」セミダブルのベッドの中でプロポーズをされた。
広々とした3LDKの成城のマンション。ここでの暮らしを想像して、自分がちょっとだけグレードアップしたような気持ちになった。
私は不思議なほどためらいなく頷いて、健介の胸に顔を
ほんの半年前なのに、ずいぶん昔の出来事のような気がした。天井を向いて、かけ布団を首まであげる。健介ってこの羽毛布団みたいだと思う。ふわっと私を包んで、ぬくぬくとさせてくれる。勇太とはいつも張り合っていたし、お互いに対して求めるものが多くて喧嘩もよくした。だけど健介といると、素直に甘えることができる。それがこんなに楽で心地いいとは思わなかった。
いびきは相変わらずうるさい。私は羽毛布団を頭までかぶって、目を閉じた。
私は毎朝、成城八丁目のマンションから最寄りの成城学園前駅まで初心者マークをつけた車で健介を送っていく。免許取り立ての私の練習になるからと健介が考え出したことだった。
二日酔いのせいか、それともゆうこの騒動のせいか、いつも優しい健介が今朝は言葉少なく表情も硬い。朝食も食べなかった。車内の空気が重苦しく、運転していても気持ちが乱れてしまう。
車を道路沿いに停めるとき、うっかり電信柱に車体をぶつけてしまった。ゴリッという音が響いたとき、健介の表情が明らかに険しくなった。
健介と私はすぐに車から降りて左側のボディを確認した。後部座席横のドアにへこんだ跡がくっきりとあった。この車は健介が大事に十年以上乗っているボルボだった。私は健介の顔を
健介は私を見ることなく、深いため息をついた後、ま、しょうがない、と自分に言い聞かせるように呟いて
マンションに戻ったが、立体駐車場はバックで入庫しなければならず、私には難易度が高かった。何度も車体を切り返していると、朝の送迎ラッシュの時間帯のため、後ろに渋滞ができてしまっていた。
余計に焦ってうまく入れられない。またぶつけたらどうしようと
部屋に帰って、ソファに身体を投げ出した。
健介の元妻のはるみは運転がうまかったのかもしれない。きっと料理だって得意だったのだろう。このソファだってはるみが選んだのではないだろうか。
ソファから勢い良く立ち上がり、ダイニングテーブルにノートパソコンを持ってきてフェイスブックのサイトを開いた。以前に自分のアカウントは作ってあったが、ほとんどサイトを開くこともなかったし、一度も記事をアップしたこともない。名前も旧姓のままで、友達も高校や短大の頃の同級生が中心だった。

検索のところに、ゆうこのフルネームを入れてクリックする。何人か同姓同名がいたが、大学名で絞ると、ドヤ顔で写る「優子」を見つけることができた。プロフィールの中の好きなアーティストに、「マドンナ」とあり、吹き出しそうになった。
アメリカの高校に通う一人娘の写真が頻繁にアップされている。優子に似て小生意気な感じがした。優子は主婦向けファッション雑誌に載ったことがあるとも書かれている。ジムの筋トレマシンの前で若い男性インストラクターと並んで写る画像では、派手なピンクのウェアを着ていた。マウイ島で撮ったビキニ姿まであった。さらに料理教室の様子も詳細にある。商社勤務の夫と家族で駐在したスペインの家庭料理と、シンガポールで習得した中華料理を教えているらしい。ピンチョスがどうのと料理の解説がしてある。
ゴルフ、ランチ、ワイン、エステ、ネイルなど、
「晴美」はすぐに見つかった。プロフィール写真の晴美は新生児の双子を抱いて写っていた。笑顔なものの、目の下にくまの目立つ
なんだか拍子抜けして、優子のページに戻る。昨日の優子の姿が頭に浮かぶ。そして、健介の不自然な態度。
優子の友達の中から健介と高島を探す。二人とも記事はなく登録だけしてあった。高島にメッセージを送る。
『
「健介さんは前の奥さんとなんで別れたんですか」
「それ知ってどうすんの」高島は
「どうするわけでもないんですけど、昨日から気になってるんです。それに、優子さんと健介さんもなんか変だなって」
高島は、煙草の煙を大きく吐き出した。そして半分ほど吸った煙草の火を灰皿でもみ消しながら、俺の知ってる範囲だけど、と話し始める。私は頷いて少し身を乗り出した。
「健介と晴美は子どもができなくても一緒にゴルフ行ったりして仲良くやってたんだ。けど晴美が四十前になったら、急に子どもが欲しくなったみたいで、不妊治療しようって言い出したらしい。そのあたりからおかしくなったみたい。晴美はちょっと怖いくらい子ども作ることで頭いっぱいで、健介があまり協力的じゃないように見えたらしい。晴美は、夫婦は同じ方を向いて手を取り合っていくべきだって
高島は別居していると優子が言っていたので、私は、ん、と首をかすかにかしげた。それに気づいた高島は、ああ、俺のカミさんね、と言った。
「なんか韓流好きが高じて、いま韓国に語学留学してんの。だから別居には違いないんだけど、優子は別居してるってことだけ誰かから聞いて、自分と同じく俺らもうまくいってないって思い込んでるみたい。説明するのも面倒だから昨日は黙ってたけど」
「そうだったんですか」うまくいっているのに別居というのも不自然な気がしたが、二十年近く連れ添っていると、そういう夫婦の形もあるのだろうか。
それでさ、と高島は続ける。私は、はい、と耳を傾けた。
「ごたごたあって別れて、それから二年もしないうちに、晴美は一回りも年下の男と再婚して、子ども産んだんだ。超高齢出産だよな。健介はそのことがすげえショックだったみたいでさ」高島は目の前の冷めたコーヒーを一口すすった。

「で、優子のことだけど」
私は小さく頷く。
「昨日の様子見たら誰だって変に思うよな。だから今日、君から連絡があって、やっぱり、と思って今ここに座ってんだけど」高島はもう一度コーヒーを飲んでしばらく黙っていた。肝心な話は、なかなか言い出しにくいのだろう。
「優子さんと健介さんって、なんかあったんですね」話を誘導してみる。
「いや、それはわかんないんだ。けど、優子が結構頻繁に健介を誘って飲みに行ったり、飯食ったりはしてたみたい。家近いしな。健介は学生の頃、優子のことすげえ好きでかなり熱心にアプローチしたんだけど、振られちゃってさ。だから優子は健介がいつまでも自分のこと好きだって勘違いしてんだと思う。健介が晴美と別れたし、自分もダンナと別居してるし、チャンスだと思ったんじゃないかな」
「それって不倫じゃないですか。優子さん、離婚はしてないんだから」
「二人が本当に付き合ってたかどうかは知らないよ。俺だって優子が別居してること昨日初めて知ったんだし。それに男同士って女みたいにベラベラ恋愛の話なんてしないからさ。でも優子は恐らく期待したんじゃないかな。健介がもし結婚してくれるんだったらダンナと離婚しようってさ」
「健介さんは優子さんのこと、実際はどう思ってたんでしょうか」訊くと高島は、うーんと言って吸殻を灰皿から拾ってライターで火をつけた。
「あくまで俺の想像だけどさ。男って
「それに、去年晴美が子ども産んでから、健介も自分の子どもが欲しくなったみたいでさ。そうすると、優子じゃキツイよな」
帰りの小田急線の中で高島の言葉を
ガガは私と同じ歳。
優子のページをふたたびのぞいた。優子の友達の中から昨日家に来ていたメンバーみんなに友達申請を送った。もちろん健介にも。
ひととき考えてから、優子にも申請して、優子のタイムラインを熟読していく。今朝のタイムラインと変化はなかった。優子は自分の努力と能力をひけらかしながら一生懸命幸せを
タイムラインをさかのぼっていくと、恒例の鍋パーティの時期ではない昨年の九月の日付に、うちにあるものとまったく同じデザインの鍋にパエリアが盛られている画像を見つけた。横に添えられたガスパチョの入ったガラスの器にも見覚えがある。背景のテーブルもうちのものと酷似している。説明には「久しぶりに作ったパエリアは、美味しいと大好評でした」とあった。私はそこでフェイスブックを閉じた。
家に帰って、収納してある食器と調理器具すべてをキッチンの床とシンクの作業台、カウンターの上に出して並べた。晴美が選んだのであろうブランドものの陶磁器から、優子も使ったかもしれない普段づかいの調理器具たちが足の踏み場もないほど床を埋め尽くした。
フェイスブックで見たガラスの器と鍋を見つけ、しばらく眺めていると、体の奥からふつふつと怒りがこみ上げてきて、だんだんと顔が
ガラスの器を手にしてベランダに出た。コンクリートの床に
高価なものだとしたら、もったいない。ネットオークションで売ってしまえばいい。そして入ったお金で、私好みの食器を新しく買えばいい。
デジカメを持ってきて、ガラスの器だけでなく、めぼしい食器をオークション出品のために撮影し始めた。
午後八時過ぎに帰宅した健介は、ダイニングテーブルでパソコンをいじる私と広げてある食器を交互に見て、なにこれ、と眉をひそめた。
「今日のごはんはデリバリーでいいかな」ぼそっと言って健介から視線を外し、パソコンの画面に戻った。いいけど、と答える健介の声が
「それと車のことだけど、あの車、初心者の私には大きくて運転しにくいし、修理代も高いから、この際コンパクトな日本車に新しく買い換えない? そのほうが燃費もいいし」ヤフオクサイトの画面を見つめて早口で言った。健介の返事はない。
「ついでに、マンションも売って引っ越そうよ。それとベッドもソファもテーブルも買い換えて……」最後の方は涙が
「最初からそうするべきだったね。ごめん」
健介が後ろからそっと抱きしめてくれた。健介の体はとても暖かかった。
引越しの当日、ほとんど荷物を運び出し終え、簡単に掃除をしているとき、玄関のチャイムが鳴った。エントランスホールの扉は荷物の搬出のためオートロックが解除されていたので直接玄関に来たようだが、呼び止められなかったのだからレセプションの女性の顔見知りの誰かだろう。業者か何かかもしれない。
私が応対に出ると、ドアを開け放った玄関に優子が立っていて、梨奈ちゃんこんにちはと微笑みながら馴れ馴れしく近寄ってきた。
「先週のゴルフで中橋から引っ越すって聞いたの。で、近いからお手伝いに来ちゃった。女手も必要でしょ」優子は持ってきた成城石井のエコバッグを私に押し付ける。
「これ差し入れ。食べやすいと思ってちまき作ったの。それと風月堂で
私はエコバッグを受け取らなかった。
「あっちでおそばをとるから、大丈夫です。それと、ここより狭いので女手は私一人で充分です。かえって気を使うので」恐縮したように言い、続けて丁重に、わざわざすみませんでしたと頭を下げると、優子は何も言い返さずに、下唇をきつく
リビングに戻ると、床に掃除機をかけていた健介が私を見て掃除機のスイッチを切った。
「誰だった?」
「なんか間違えたみたい」作り笑顔で答えた。
健介は、そうか、と言って、ふたたび掃除機のスイッチを入れる。
胸に痛みを感じなかった訳ではない。
私はレディー・ガガのBorn This Wayをあえて口ずさみながら
あとで引越しそばと新居のマンションの写真を撮って、フェイスブックに初めて記事をアップしてみようと思っている。