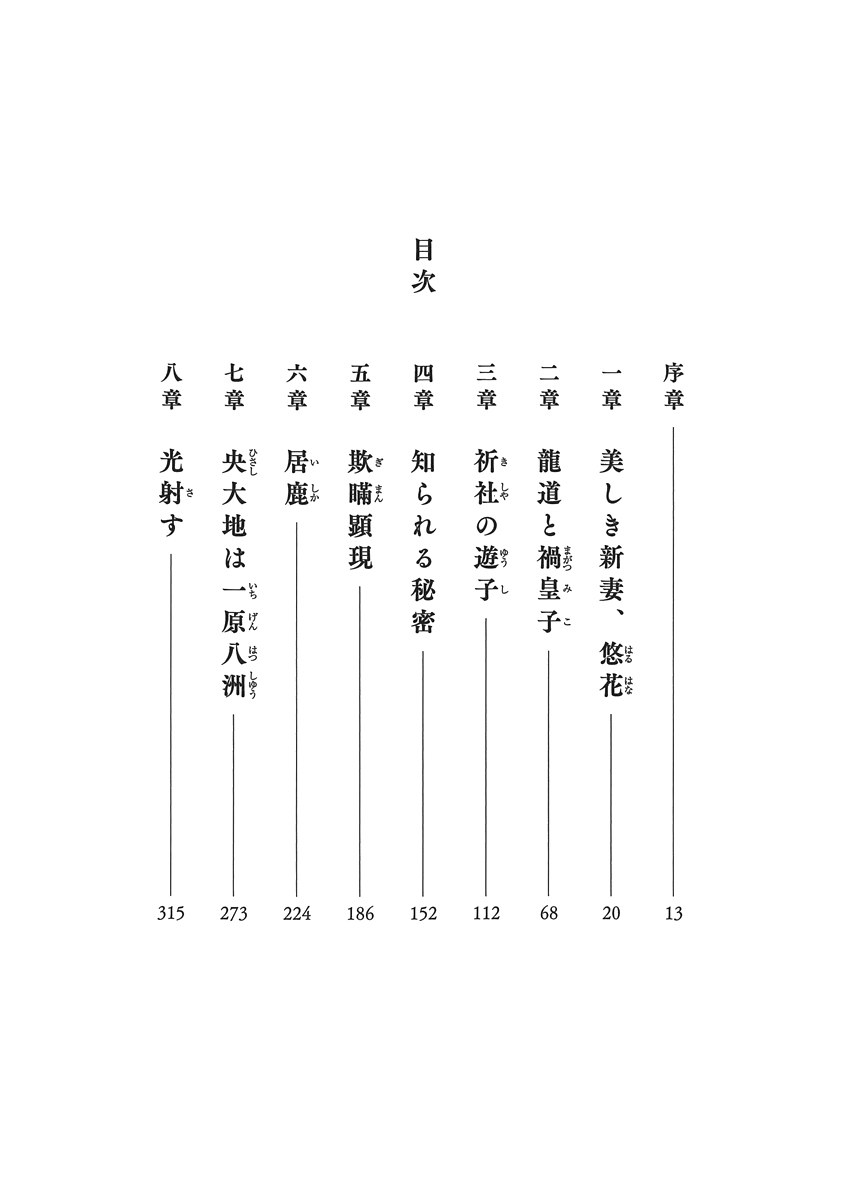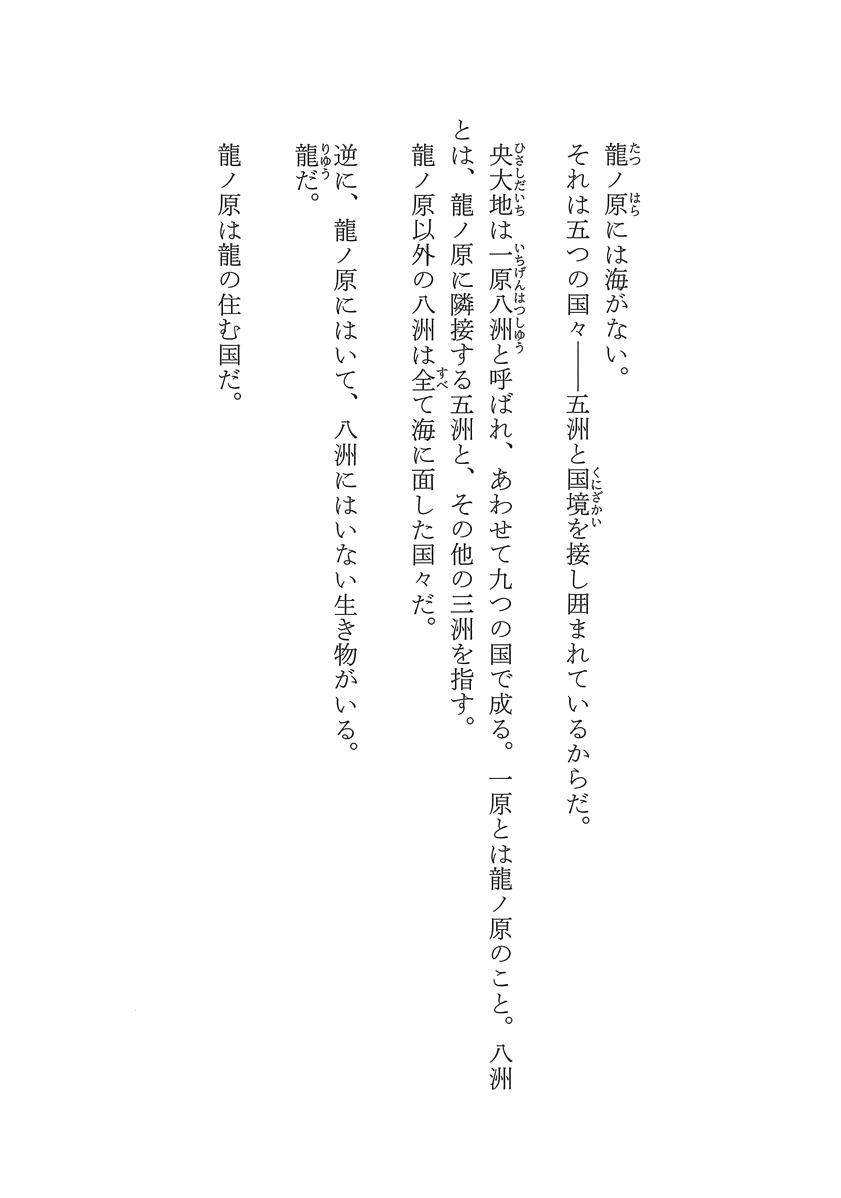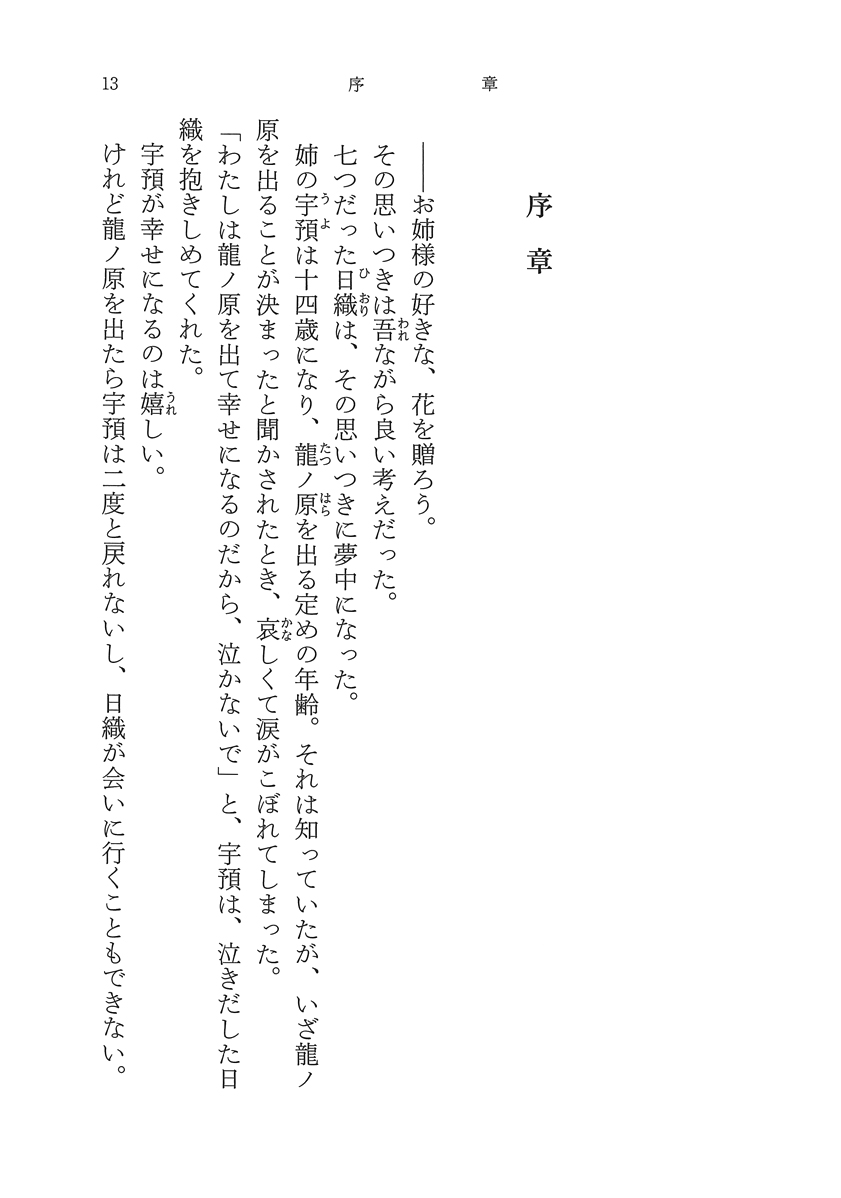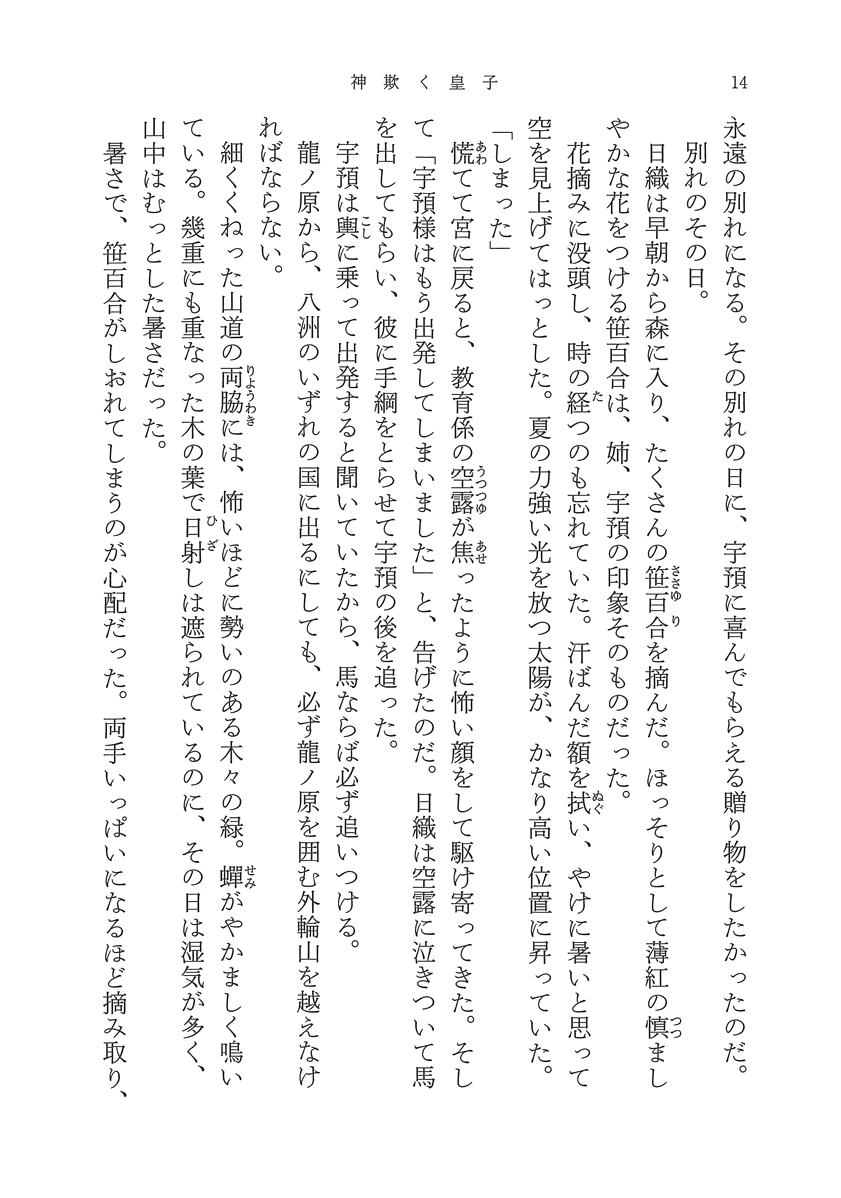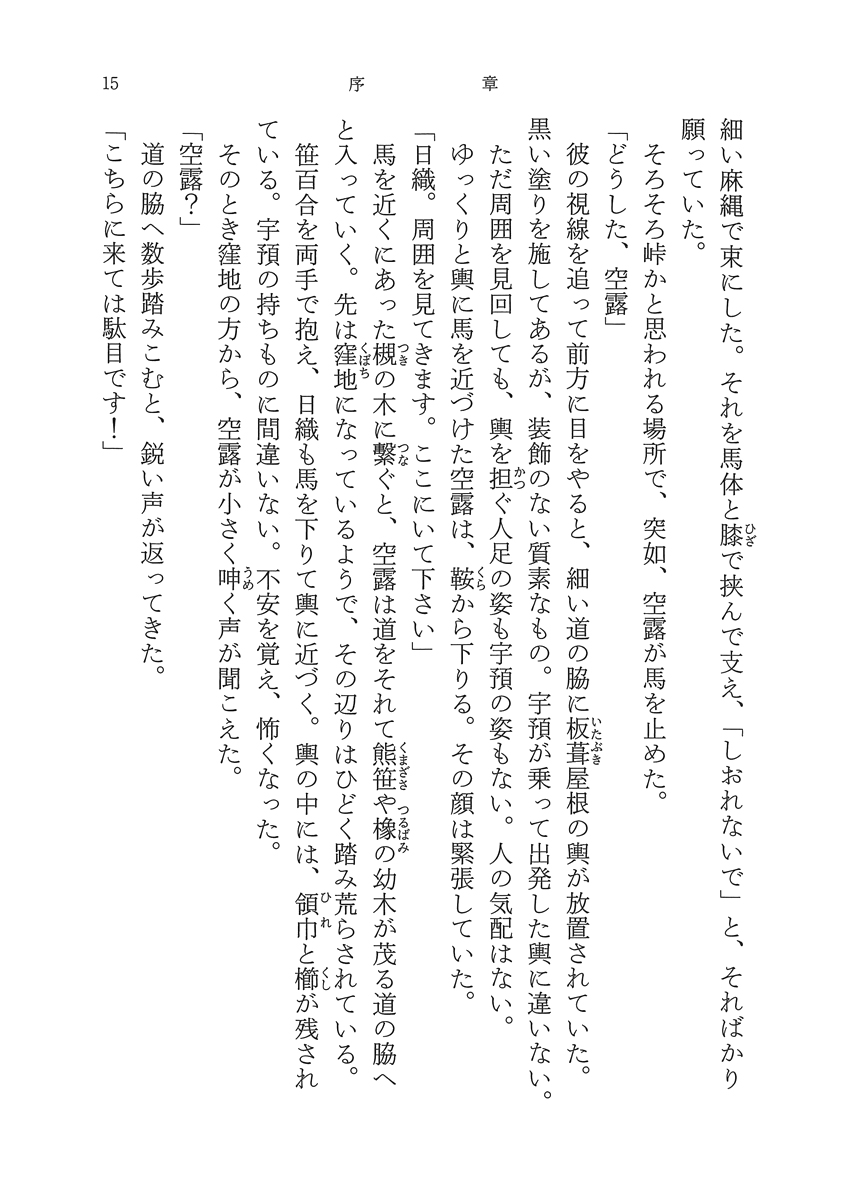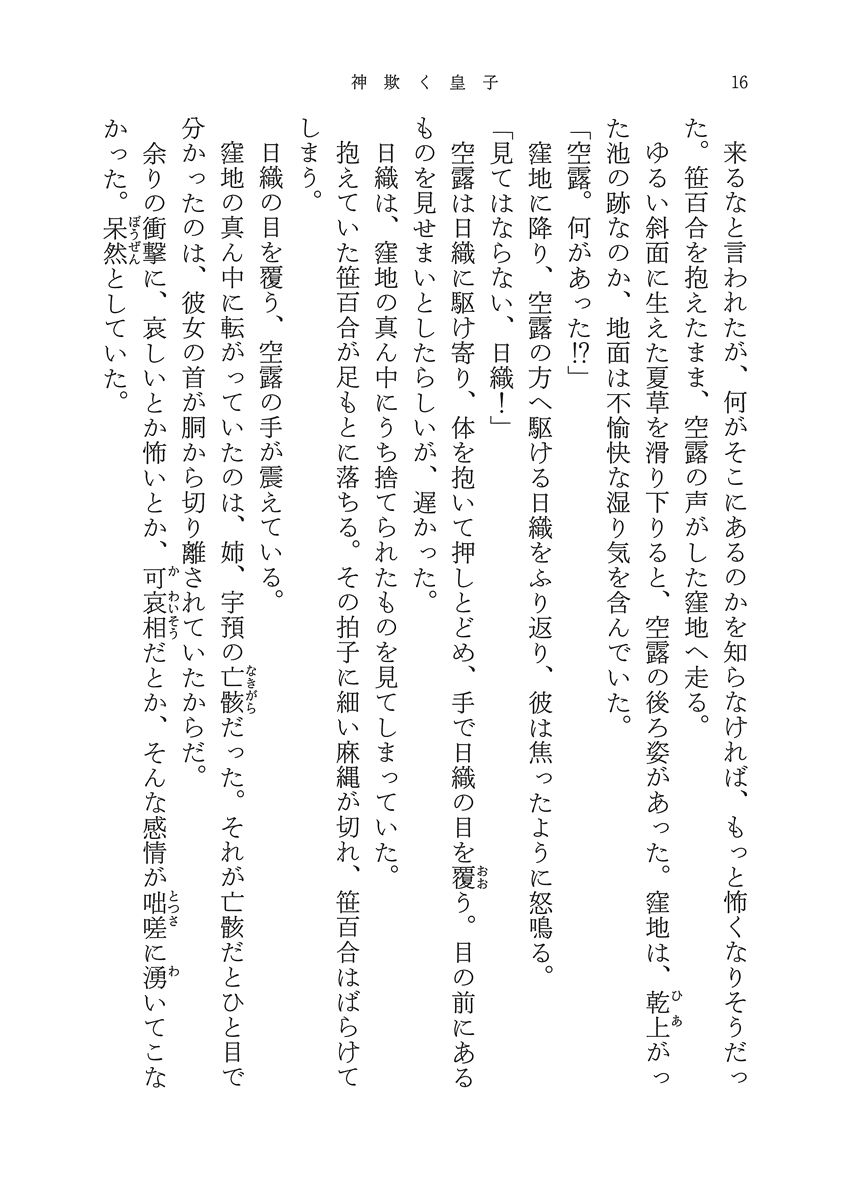龍ノ原には海がない。
それは五つの国々――五洲と国境を接し囲まれているからだ。
央大地は一原八洲と呼ばれ、あわせて九つの国で成る。一原とは龍ノ原のこと。八洲とは、龍ノ原に隣接する五洲と、その他の三洲を指す。
龍ノ原以外の八洲は全て海に面した国々だ。
逆に、龍ノ原にはいて、八洲にはいない生き物がいる。
龍だ。
龍ノ原は龍の住む国だ。
序章
――お姉様の好きな、花を贈ろう。
その思いつきは吾ながら良い考えだった。
七つだった日織は、その思いつきに夢中になった。
姉の宇預は十四歳になり、龍ノ原を出る定めの年齢。それは知っていたが、いざ龍ノ原を出ることが決まったと聞かされたとき、哀しくて涙がこぼれてしまった。
「わたしは龍ノ原を出て幸せになるのだから、泣かないで」と、宇預は、泣きだした日織を抱きしめてくれた。
宇預が幸せになるのは嬉しい。
けれど龍ノ原を出たら宇預は二度と戻れないし、日織が会いに行くこともできない。永遠の別れになる。その別れの日に、宇預に喜んでもらえる贈り物をしたかったのだ。
別れのその日。
日織は早朝から森に入り、たくさんの笹百合を摘んだ。ほっそりとして薄紅の慎ましやかな花をつける笹百合は、姉、宇預の印象そのものだった。
花摘みに没頭し、時の経つのも忘れていた。汗ばんだ額を拭い、やけに暑いと思って空を見上げてはっとした。夏の力強い光を放つ太陽が、かなり高い位置に昇っていた。
「しまった」
慌てて宮に戻ると、教育係の空露が焦ったように怖い顔をして駆け寄ってきた。そして「宇預様はもう出発してしまいました」と、告げたのだ。日織は空露に泣きついて馬を出してもらい、彼に手綱をとらせて宇預の後を追った。
宇預は輿に乗って出発すると聞いていたから、馬ならば必ず追いつける。
龍ノ原から、八洲のいずれの国に出るにしても、必ず龍ノ原を囲む外輪山を越えなければならない。
細くくねった山道の両脇には、怖いほどに勢いのある木々の緑。蝉がやかましく鳴いている。幾重にも重なった木の葉で日射しは遮られているのに、その日は湿気が多く、山中はむっとした暑さだった。
暑さで、笹百合がしおれてしまうのが心配だった。両手いっぱいになるほど摘み取り、細い麻縄で束にした。それを馬体と膝で挟んで支え、「しおれないで」と、そればかり願っていた。
そろそろ峠かと思われる場所で、突如、空露が馬を止めた。
「どうした、空露」
彼の視線を追って前方に目をやると、細い道の脇に板葺屋根の輿が放置されていた。黒い塗りを施してあるが、装飾のない質素なもの。宇預が乗って出発した輿に違いない。
ただ周囲を見回しても、輿を担ぐ人足の姿も宇預の姿もない。人の気配はない。
ゆっくりと輿に馬を近づけた空露は、鞍から下りる。その顔は緊張していた。
「日織。周囲を見てきます。ここにいて下さい」
馬を近くにあった槻の木に繋ぐと、空露は道をそれて熊笹や橡の幼木が茂る道の脇へと入っていく。先は窪地になっているようで、その辺りはひどく踏み荒らされている。
笹百合を両手で抱え、日織も馬を下りて輿に近づく。輿の中には、領巾と櫛が残されている。宇預の持ちものに間違いない。不安を覚え、怖くなった。
そのとき窪地の方から、空露が小さく呻く声が聞こえた。
「空露?」
道の脇へ数歩踏みこむと、鋭い声が返ってきた。
「こちらに来ては駄目です!」
来るなと言われたが、何がそこにあるのかを知らなければ、もっと怖くなりそうだった。笹百合を抱えたまま、空露の声がした窪地へ走る。
ゆるい斜面に生えた夏草を滑り下りると、空露の後ろ姿があった。窪地は、乾上がった池の跡なのか、地面は不愉快な湿り気を含んでいた。
「空露。何があった!?」
窪地に降り、空露の方へ駆ける日織をふり返り、彼は焦ったように怒鳴る。
「見てはならない、日織!」
空露は日織に駆け寄り、体を抱いて押しとどめ、手で日織の目を覆う。目の前にあるものを見せまいとしたらしいが、遅かった。
日織は、窪地の真ん中にうち捨てられたものを見てしまっていた。
抱えていた笹百合が足もとに落ちる。その拍子に細い麻縄が切れ、笹百合はばらけてしまう。
日織の目を覆う、空露の手が震えている。
窪地の真ん中に転がっていたのは、姉、宇預の亡骸だった。それが亡骸だとひと目で分かったのは、彼女の首が胴から切り離されていたからだ。
余りの衝撃に、哀しいとか怖いとか、可哀相だとか、そんな感情が咄嗟に湧いてこなかった。呆然としていた。
ただひたすら、なぜ? と思った。なぜ宇預が死んでいるのだろうか、と。
膝が震えた。突然、金切り声が自分の口から飛び出す。
「日織! 落ち着いて」
空露が叫ぶ。しかし金切り声が止まらない。頭の芯は空白で、何も考えられないのに、思考とは切り離された体が何かを拒絶するように金切り声を発している。
止まらない。
雑木林の奥のほうから、ぶわっと涼しい風が吹きつけてきた。
凄まじい速さで、木々の隙間をうねり、抜け、飛んでくるものの気配。
風圧で、日織を抱えたまま空露が地面に倒れると、目を覆っていた手が離れる。
仰向けに転がった衝撃で背中を打ち、息が詰まり、金切り声が止まった。日織の目は、木々が途切れた空へ向かって、銀色の鱗に鋭い輝きを反射させながら、身をくねらせ昇っていく生き物の姿を捕らえた。一抱えはある、まるまるとした胴体と、空をかき分けるように左右に動く長い尾。ぬめるような光沢のある、八十一枚の鱗に覆われた銀の腹。
龍だった。龍ノ原にだけ住まう生き物。神の眷属。
遠い山上に、あるいは遠い平地の空を、身をくねらせ飛ぶ姿を見たことはあったが、これほど近くで見たのは初めてだった。
樹皮を削り取ったような香りが、龍の巻き起こす風に含まれていた。風と香りが頬を打つ。
蒼天へ、龍は昇っていく。あっという間だった。
耳がじんじん痺れているのは、自分の悲鳴の余韻だ。
「なんで」
吾知らず呟やいていた。
なぜ今、現れた?
宇預の身に起こったことと、何か関係があるのか?
何が起こったのか?
たくさんのことを龍に訊きたい。神の眷属なのだから、たいがいのことは知っているだろう。
日織の一族の女たちは皆、龍の声を聞くことができる。もし日織にも同じ能力があれば、飛び去った龍の声が聞こえて、日織の疑問に、多少なりとも答えが得られたのかもしれない。
だが、日織には龍の声が聞こえない。
宇預にも聞こえなかった。
日織と宇預は、当たり前のものを、もたずに生まれてしまっていた。宇預が龍ノ原を出なければならなかったのも、そのためだった。
消え去る龍の姿が非情に思えた。
こちらに目もくれず飛び去った姿は、これが定めだとでも言いたげで。神の眷属は、宇預や日織のような『もたざる者』を、不要と斬り捨てていくのだろうか。
涙が頬を伝った。
哀しみのせいでも、怖さのせいでもなかった。純粋な怒りだった。
宇預の亡骸が山中に打ち捨てられ、その上を、気にもとめずに飛び去った神の眷属が憎らしかった。神に怒りを抱くなど不遜この上ない。ただ七つの日織には、神に対する畏怖が育ちきっていなかった。畏怖が育つ前に怒りを抱いた。
相手が神であろうが、理不尽さに屈するのが悔しい。
認めるものか、と胸の内で呻く。これが定めと言われても、認めたくない。
これが定めと飛び去るならば、自分はその定めに逆らってやりたかった。定めに屈するのは、宇預の死を「当然」と受けとめるのと同じ気がした。
当然と考えるのは、彼女に対する侮辱だ。宇預は死んで当然ではない。
宇預の死の事実を認めたくないかのように、強く、定めに抗いたくなる。
散らばる笹百合は、しおれてしまっていた。
一章 美しき新妻、悠花
一
そぼ降る雨の中、日織は鹿毛馬の手綱を握っていた。
銀灰色の雨除けの皮衣を羽織っていたが、それだけで雨は防ぎきれるものではなく、衣の袖や白袴の裾は水気を含んで重い。まつげの水滴をまばたきで落とし、馬上から、ぬかるむ道の周囲へ視線を向けた。
草木は雨粒に打たれ疲れ、項垂れていた。
すでに初夏と呼べる季節だったが、道端の、彩り鮮やかなはずの草花の蕾は開く気配がない。唯一咲いているのは山際に自生する白い雪笹のみ。それは薄暗い景色に色を添えるというよりも、もの寂しさを助長する。
(花も喪に服すか)
当然だろう。龍ノ原を支配する皇尊が崩御したのだから。
崩御の日から雨は降り続き、既に十日だ。新たな皇尊が即位するまで雨は必ず続く。これを殯雨と呼ぶ。皇尊の崩御と即位は、央大地が大海に浮かびあがった神代から今まで、何十代も繰り返されてきたが例外はない。
道の先に、白木の四本柱で支えられた檜皮葺の門が見えた。そこを潜ると、邸の舎人が現れて日織の馬の轡を取る。
「しばらくぶりですね、日織皇子様」
「たった五日だよ」
馬を下りながら苦笑して答えると、皺深い目もとを和ませた舎人は肩をすくめた。
「たった五日も、うちの媛様には百日にも思えるらしいですよ。毎朝毎夕、日織皇子様の姿は見えないかと門を覗きに……」
「日織様!」
少女の声が聞こえた。日織と舎人は同時にふり返り、牝鹿のようにほっそりとした少女が雨の中へ駆け出て、泥をはね散らしながらこちらに向かって来るのを認めた。
「ほらね。お待ちかねだったんです」
舎人は笑いを噛み殺しながら言うと、馬の轡を引いてその場を離れる。
「日織様! 来てくださったのね」
少女は日織の首に飛びつき、しがみつく。
髪は頭上二髻に結い、花をかたどった珊瑚の釵子を挿す。可愛らしい口もとの左右に、小さな星を描いた靨鈿。背子は鮮やかな鴨羽色に、纈裙は真朱。領巾はどこかに放り出してきたのか纏っていない。彼女の装いはいつも、溌剌として幼い印象だった。
笑うと片えくぼが出て、それがまた子どもっぽい。
「こら、濡れて風邪をひくよ。月白」
雨粒を気にもとめずに、嬉しさを隠せない明るい笑顔を向けてくれる無邪気な様子を見ると、日織はいつもほっとするのだ。庭に咲いた、明るい花の色を見るのに似た気持ちになる。
彼女は日織の妻で、名を月白という。
「もう濡れてます。風邪なんかひきません。寂しかったんです、日織様」
「たった五日じゃないか。甘えん坊だね。十六にもなって」
「だって日織様が、皇尊の候補に挙がったと聞いたんですもの。考えてみたら当然なのだけど。でもそれを知ったら心配になって。日織様はわたしを置いて、もう龍稜へ入ってしまわれたのかもって」
「行くのは二日後だ。しかも、あなたも連れて行く予定だよ、月白」
「一緒に行けるのですか!? 嬉しい!」
月白の乳母の大路が、領巾を手にして追って来る。夫にじゃれつく月白に、大路は呆れた顔をしながらも、無邪気さに毒気を抜かれた苦笑いだ。
「お二人ともずぶ濡れになりますわよ。中へお入り下さいまし」
「大路の言うとおり。中へ行こう、月白」
抱きついて離れない月白の腰を抱えるようにして一歩踏み出したそのとき、遠雷に似た音が響き、冷たい風がふっと頭上から降ってきた。
見上げると雨粒を降らせ続けている雲の中に、白銀の鱗で被われた、なめらかに丸い胴の一部が見えた。龍の腹だ。灰色の濃淡がいりまじる雨雲の中を、ひときわ目立つ白さで龍が泳いでいる。日織の身長の十倍はあろうか。その大きさならば年齢は百歳を越えているはず。
「龍の声は、なにか聞こえるか?」
日織が問うと、大路が眉根を寄せて空を見ながら言う。
「あの龍は不機嫌そうですね。ねぇ、月白様」
月白も、ゆっくり動く龍の腹を目で追っていた。
「ええ、とても。唸り声?」
「はい。わたしにも声ではなく、ただ唸り声に聞こえます。不安げな」
「当然かもしれないな」
日織は呟く。
「皇尊が不在なのだから」
皇尊不在の期間は雨が止まず、空位の期間が長引けば長引くほど雨は激しさを増す。
皇尊選定に手間取っていると、そのうち大水害が発生する。
崩御から数えて四十日を過ぎれば、雨で大地がふくらみはじめ、八十一日以上過ぎれば、稲田や建物が流され、山肌がずるずると滑り落ちて崩れ出す。それと同時に殯雨は、龍ノ原のみならず、隣接の五洲にまで降りはじめる。
さらに皇尊の不在が年単位におよべば、龍ノ原は水没し、八洲も水に襲われる。
四年を過ぎると、央大地の下に眠っている地大神、地龍が目覚め、大地鳴動し、一原八洲の九つの国がある大地は海に没すると言われている。
地大神、地龍は元来荒ぶる神、荒魂だ。それを眠らせ鎮めるのが、龍ノ原の皇尊の役割。その荒ぶる神を鎮める者がいなければどうなるか、ということだった。
(はやく皇尊が即位しなければ)
神代から今まで、最も長い皇尊の不在期間は一年。龍ノ原の正史『原紀』にも記されている三百年前のことだったが、そのときには龍ノ原の半分が水に沈み、民の三分の二が命を落とした。隣接五洲でも殯雨により川があふれ、人が多く流されたという。そのため龍ノ原の民ばかりでなく、隣接の五洲の民も、皇尊の一日も早い即位を望む。
雲の流れに逆らうように泳ぐ白銀の腹が、ひときわ濃い雲の中へと潜って消える。
龍を見送った日織は、大路に促され、月白とともに正殿へと入ると皮衣を脱いだ。皮衣の下にあった衣ですら、襟や袖はかなりの水気を含んで絞れるほどだった。
開いたままの枢戸と、押しあげてある半蔀からは湿った風がさかんに吹きこんでいた。月白は濡れた日織が冷えないように配慮して母屋の奥へと導き、乾いた布で背中や肩や腕を丹念に拭いてくれる。まめまめしい様子は、人の世話に慣れない若妻が夫に風邪をひかせまいと一生懸命になっている、不器用で可愛らしい真剣さだった。
「日織様、随分濡れてる。可哀相」
「仕方ないね。殯雨だもの」
「仕方ないじゃ、すまないわ。お風邪をめされたら大変だもの。もう少しご自分のことに気を遣ってほしいわ」
「おや、怒られてしまった。怖い妻だな」
「もう」
軽くぶつそぶりをした月白と目があい、自然と微笑みあう。月白は手を止めると目を閉じ、顔を寄せた。その頬に手を添えて軽く口づけると、紅の香りが日織の唇に微かに移る。
月白は頬を染め、満足したようにはにかんだ笑みを口もとに浮かべながら、またせっせと手を動かす。
(こんなことでしか、慰めてやれない)
心通わすための触れあいだからこそ、いつも心にある後ろめたさが首をもたげる。
ただ月白は、それで満足しているらしかった。逆にそれ以上のことなど望んでいないようなので、年齢のわりに彼女は幼いのかもしれない。
月白は、日織の祖父の妹皇女の家系だ。回り回れば血は繋がっているが、その存在は知らなかった。年齢的に妻を娶らざるを得なくなったとき、教育係の空露が探し出してきたのだ。日織の妻になるのに、ぴったりの媛がいると。
月白は「男は嫌だ」と言い張り、自分の父でさえ毛嫌いするらしい。人前に出るのも好まず、乳母とばかり過ごしたがる。
これではとうてい誰の妻にもなれないと、両親は頭を抱えていたという。
だからこそ空露は、月白が日織の妻に相応しいと考えたのだ。
会ってみると、月白はひと目で日織が気に入ったらしかった。日織は他の男とは雰囲気が違い中性的で、ひ弱ととられかねない様子なのだが、それが逆に良かったのだろう。
空露は、「月白様は、男という生き物に嫌悪感がある。日織ならば大丈夫」と言っていたが、その読みの通りだった。
月白が妻となって二年が経つ。
結婚前には不安に思ったが、意外にも仲良くやれていた。
「日織様と龍稜に入れるの、嬉しい。日織様はいつ即位なさるの?」
「わたしは、次期皇尊の候補に挙がっているというだけだ。他に二人の候補がいる。まだ、わたしと決まったわけではないよ。それを決めるために、二日後、龍稜に入るように言われているんだ」
「でも日織様が一番だわ、きっと。日織様が皇尊になられるはずだわ」
無邪気に決めつけると、はしゃいだ声で続ける。
「龍稜に入れば、お近くに寝起きできるんでしょう? どうせなら一緒に寝起きできればいいのに。二人きりで過ごす時間がもっと多くなるのに」
「月白とわたしが、一つ所に寝起きするのは無理だろう」
「あら、どうして?」
日織は月白に座るように促し、自分も藁蓋にあぐらをかく。月白は、きょとんとした顔をしている。
「わたしは、これからもう一人妻を娶ることになる。その知らせもかねて、会いに来た」
「……え? 妻?……」
言葉の意味を飲みこみかねるように、月白は繰り返した。
「知らないか? 皇尊が崩御されるときのことを。随分知れ渡っているのだが」
月白は、首を横に振る。
「皇尊が崩御される直前、わたしは、皇尊の病床に呼ばれたんだよ」
ことの起こりは十二日前。日織は、病に臥している皇尊に呼ばれた。
もう長くはないだろうと噂されていたので、そのような状態のときに、なぜ自分が病床にまで呼ばれるのか不可解に思った。皇尊は日織の叔父に当たるが、さして親しかったわけではなく、祭礼や宴で挨拶する程度の間柄だったのだ。
ただ、日織が叔父皇尊に対して常々抱いていた印象は悪くなかった。優しげな、おっとりとした人柄が表情に出ている、常に微笑んでいる人だったから。
病床を訪ねて日織が目にした皇尊は、痩せ衰え、青黒い顔の中で、潤み濡れた目ばかりが異様に目立った。死の予感に怯え、体を蝕む苦痛をこらえ、体面も礼儀も考える余裕などなく、ただ自分の不安にばかり支配されていた。
痛々しいほど衰弱していた皇尊は、日織の手を握り懇々と願った。
自分が亡き後、一人娘の悠花皇女が心配でたまらないのだと。悠花にはすでに母もなく、頼れる兄弟姉妹もおらず、父である自分が死ねば寄る辺がない。どうか日織の妻にして、生涯護って欲しいと。
皇尊の手は、骨と皮ばかりで皮膚はかさかさに乾いていたが、衰えた体の中で何かが燃えさかっているかのようにひどく熱かった。
その場には神職である大祇、太政大臣や、左右の大臣たちもいて、皇尊の言葉を聞いていた。
日織は、月白の他に妻をもつ気はなかった。そもそも日織は、妻を娶ることに罪悪感を抱いている。また妻となる女性も、月白も、双方とも可哀相な思いをするのは目に見えていたからだ。
だが、この時ばかりは「お約束します」と答えた。
「皇尊の願いを無下にはできない。心配のお気持ちも痛いほどわかる。だから悠花を娶ると承知した。今日中には、悠花に会いに行き正式に妻とするつもりだ。明日には、悠花はわたしの妻だ。だから龍稜へは悠花も一緒に連れて行く。月白も仲良く……」
言葉が途切れた。月白が日織を見つめ、ぽろぽろ涙を流しているのに気がついた。
「月白」
「日織様は、悠花様の夫になってしまわれるの?」
「そうだけれど。月白の夫であることに変わりはない」
「わたしだけの日織様では、なくなるの?」
その問いに胸が痛む。
(月白が哀しむだろうことは、わかっていた)
月白は日織を愛しているし、その愛情がいっそ幼いほどに純粋一途で、夫を自分だけのものだと思いたい、少女らしい独占欲を内包しているのも知っていた。
それでも承知したのは、悠花を娶れば、それが後々日織の有利に働くからだった。日織には、二十年前から抱く不遜な望みがある。そのためには仕方なかった。
(来るかどうかもわからぬままに、待ち続けた機会だ。それが来た。この機会を逸してはならないのだから)
そのかわり日織は、月白も、まだ会ったことのない悠花も、二人とも同様に生涯をかけて大切に護ろうと心に決めている。
月白を抱き寄せてやると、彼女は甘え、日織の衣の胸に額をこすりつけた。
「なにも変わらないよ。心配するな」
「でも、……嫌」
「我慢して」
今一度口づけて、月白を宥めた。
(罪なことをするものだ、吾ながら)
こうやって心から可哀相だと思い、大切にしたいと思う気持ちは本心だ。だが日織が抱える秘密がある限りは、日織が妻たちに心の内を全てさらけ出すことはない。
日織は物心つく前から、秘密を抱えて生きる運命。
ときどき自分でも嫌になるが、割り切る必要があるのだ。
それからしばらく月白は泣きやまなかったが、段々と落ち着きを取り戻し、辺りが薄暗くなる頃にはようやく機嫌が直ったらしく笑顔を見せた。それを見計らったように、空露が日織を迎えに来た。
雨雲が常に龍ノ原を覆っているので、夕暮れ時ながら辺りはひどく暗かった。
灰色に煙る景色の奥に、薄墨で描いたような連山の威容がある。その連山は護領山と呼ばれ、龍ノ原をぐるりと取り囲み国境を成す。日織の見つめる視線の先には、ひときわ高い峰が屹立していた。護領山で最も高いその峰は祈峰という名をもつ。
四季を通して濃い緑を失わないその峰へ向け、日織は馬を進めている。
「憂鬱になるな」
濡れながら呟いた日織の声を聞きとがめ、青毛馬を並べて歩いていた空露が淡々と、しかしいくぶん諭すような口調で言う。
「悠花様を娶ることがですか? 弱気は口になさいますな」
「殯雨の話だ。深い意味はないよ」
誤魔化したが、実際、悠花を娶ることによって、月白と悠花二人ともに可哀相な思いをさせるのは気が重い。
(彼女たちを哀しませたくない)
人として接するとき、日織は男性よりも女性が好きだ。女性の中で育ったので、彼女たちの優しさや柔らかさ、強かさや面白さは、なじみ深くて落ち着く。男という生き物は、どうしても父を連想してしまう。だからだろうか。男性全てに対して、理解できない考えで動く強引な生き物という印象をぬぐえない。
幼い頃から唯一身近にいた男性は教育係の空露だが、彼は神職。他の男性たちと、どこか佇まいが違う。
「娶ってすむのなら、娶りなさい。悠花様を妻として損はありません。先代の皇尊が、皇女を預けるほどに信頼されたとなれば、我々の望みを果たすのに有利です」
見透かされているらしい。かなわないなと、日織は首をすくめた。
「お見通しか」
空露は護領山山中にある、地大神とその眷属である龍を祀る社、祈社に所属し、護領衆を務めている神職だ。
護領衆の空露は髷を結わない。髪を肩で切りそろえ、衣も袴も黒一色だ。
「日織に覚悟があるのはわかっています。ただあなたは、全ての女性に宇預様の面影を重ねてしまいがちだ。それでは身動きが出来なくなります。冷静におなりなさい」
「月白の時も、同じようなことを言われたな。ただ全てを知っていて、わたしに妻を娶れと言うおまえは大したものだ。面影云々というよりも、彼女たちに申し訳ないと思うのは当然だろうが、おまえは平然としている。神職ならではか?」
嫌味半分、感心半分に言うと、空露は柔和に微笑する。
「わたしも、ようやく神職らしくなったようで、なによりです」
「面の皮が厚い」
「お褒めにあずかり光栄です」
「うん。褒めてはないがな」
日織は苦い顔をする。空露は平然と前を見ていた。
務めが長くなればなる程、神職は泰然とするものだ。空露は少年の頃から護領衆を務めているので、神職となって既に三十年近くは経っていた。
日織が向かっているのは、空露が所属している護領山の祈社。
今、悠花がそこに身を寄せている現実を考えると、亡き皇尊が娘の行く末を案じ、病床に日織を呼んでまで約束を取りつけたのは、杞憂とばかりは言えない。
皇女であろうとも後ろ盾がなければ生きられないのは、女には宮の一つも地領の一つも与えられないからだ。悠花も父の崩御とともに皇尊の住まいを出たが住む場所が定まらず、祈社に仮住まいしている。
祈社は、護領山中で最も高い峰、祈峰の中腹を段々に切り拓いて造られていた。
高床で白木の建物が、針葉樹の深い森の中にあちらに一つ、こちらに一つと点在し、それらは回廊で繋がっていた。祈社の周囲には龍も頻繁に現れるという。
大気が凝り空の一点で玉のような湧き立つ雲の群れになり、その中から龍は生まれる。
生まれ出た龍は空にあふれる神気を喰らい成長し、自在に龍ノ原を飛翔する。
龍は、眠れる地大神、地龍の一部だ。
神は、相反する二面性を抱えるからこそ力ある存在となる。荒ぶる魂と、和やかなる魂。その二つを抱えるからこその神。
荒魂である地龍のもつ穏やかな一面である、和魂。それが形となって地上に彷徨い出るのが、龍という生き物の正体。それらは皇尊に助言し、警告を発し、ともに龍ノ原を守護する。
地大神、地龍を鎮めるために、皇尊は龍ノ原を飛翔する龍の力を借りるのだ。
龍ノ原の人々にとって龍は見慣れた生き物ではあるが、人が触れられるほど近くに寄ってくるものではない。遠目に眺め敬うものだ。祈社はそれら龍を尊び祀り、龍ノ原と皇尊を守ってくれるようにと祈念するための社。
祈社に到着すると日織は空露に見送られ、采女に案内された。
(妻か)
後ろめたさはある。
(だが、後ろめたさがなんだと? わたしはそれで、躊躇っていられる身の上ではない。空露のように、目的のためならと平然としていなければ)
自分に言い聞かせながら、案内の采女について歩を進めていた。
前を行く采女の手には手灯があり、ぼんやりと行く先を照らす。
白木の柱が並ぶ回廊を、ひと気のない静かな方へと向かっていた。
回廊の軒端からは雨粒が間断なく滴り落ち、青く苔むした縁石に跳ね、ぴちぴちと微かな音を立てている。回廊に沿って野趣のある庭が続く。庭石や縁石は苔に被われており、辺りには特有の土くささが沈殿していた。
「こちらでございます、日織皇子様」
采女が立ち止まった。
回廊の先には高床で白木造りの殿舎があり、殿舎へあがる階の下には老女が待っていた。采女が日織に一礼して引き返すと、代わりに老女が近づいてくる。
「悠花皇女様の乳母、杣屋でございます。悠花様は中でお待ちです。お入り下さい」
鷹揚に頷き、日織は階をあがった。
乳母の杣屋は、ひどく不安そうに日織を見送っている。
素足で踏む床板は、ひんやりしていた。静謐な空気が柱や床にまで染みこんでいるかのようだが、それは神域だから当然かもしれない。ことに祈社の建物で使われるのは、護領山の一部にしか育たない白杉だ。一般的な杉よりも、加工すればなお白い木肌を見せる白杉の建物は、建物そのものを神域として隔絶する気品がある。
白杉は神域である祈社と、皇尊の住まいである龍稜にしか用いられない。白杉柱と言えば、神聖な場所というほどの意味をもつ言葉だ。
枢戸を開き、中へと歩を進める。
戸口の脇に油皿を載せた三本足の結び燈台があり、炎が揺れていた。灯りは一つのみで内部は薄暗い。その中でも、梁から垂れる五色の絹布の鮮やかさが際立つ。それで母屋は仕切られている。
悠花は五色布の向こうにいるのだろう。
一旦立ち止まり気持ちを整える。
五色布の向こうにいる女性は、十日前に崩御した皇尊が残した唯一の子だった。
(罪なことで可哀相なことだと、充分わかっている。だが必要なのだ)
迷いを斬り捨て、布の向こうへ声をかける。
「悠花皇女。わたしは日織です。入ります」
二
布を開いて中に入る。
白い領巾と纈裙が、しどけなく白木の床に広がっていた。悠花は挟軾にもたれかかり、足を横に流し、気怠げに座っていた。
頭上一髻に結った髪には、常夏の花を模した銀と翡翠の釵子。額には朱色の小さな花模様、花鈿が描かれている。紅をさした唇は艶やか。肌は白く、落ち着いた縹色の背子とあいまって、さらに青白くさえ見える。こちらを見つめる目はくっきりと形良く、眦には目の美しさを強調するように紅い色を添えてある。
彼女の座る周囲が、現実と薄皮一枚で隔てられているような気がした。誰かが夢に描いた女が、薄暗がりに浮かびあがってきたかのような――。
日織は息を呑む。
(綺麗な人だ)
亡き皇尊は、悠花を人前に出すのを極端に嫌った。誰もが疑問を抱き、なぜかと問うた者もいた。すると決まって「病弱ゆえに」と答えていた。
(亡き皇尊が悠花を人前に出さなかったのは、この妖しいまでの美しさがあったからではないのか。人が騒ぐのを嫌ったのではないか)
年は十九歳と聞いていた。目の前の女には人を惑わすような、えもいわれぬ色香がある。真っ直ぐこちらを見つめる瞳には強い意志が潜んでいそうで、それがまた物憂げな様子とはちぐはぐで、そのちぐはぐさも艶めかしく思えた。
「はじめてお目にかかるね、悠花。わたしが日織だ。貴方のいとこなのは知っているね」
悠花の前にあぐらをかいて座り、名乗った。
日織の父は、悠花の父の実兄。そして悠花の父が即位する前には、皇尊の位にあった。
要するに、日織の父が先々代皇尊であり、その人が亡くなった後に即位したのが、悠花の父皇尊なのだ。二人とも皇尊を父にもち、なおかついとこの関係にあたる。近しい血縁ではあるが、日織が悠花に会ったのはこのときが初めてだった。
無言で悠花は頷く。
「なぜ、わたしが貴方を訪ねて来たのか知っているか?」
手先の見えない長い袖で口もとを隠し、悠花は戸惑うように首を横にふる。怯えているのだろうか。
「あなたの父君、亡き皇尊から、わたしに御遺言があったのだ。だから迎えに来た」
一旦言葉を切り、姿勢を正す。
「あなたを、わたしの妻として迎えたい」
悠花は目を見開く。
「あなたをわたしの妻に迎えよと、それが亡き皇尊の御遺言なんだ。わたしには既に一人妻がいる。しかしあなたを妻に迎えれば、もう一人の妻と同様に、生涯大切にお護りすると約束する。ただし、わたしはあなたを女として愛することはないと思って欲しい」
静かな声で日織は告げた。
「勝手なことを言うが。それでも良いと思えるなら、わたしの妻になって欲しい」
綺麗な目で何度か瞬きして、悠花は日織を見つめている。
「どうだろうか? 答えて欲しい」
重ねて問いながら違和感を覚える。
(なぜ答えない? それどころかこの人は、対面してから一言も発していない。なぜ)
日織の表情を読んだらしい悠花は、床に手を伸ばし、硯と紙を引き寄せ筆を手に取った。さらさらと文字を書き、紙を差し出す。
『わたしは喋れません。歩くことも出来ません』
そう書かれていた。
驚き、彼女の顔と文字を交互に見返す。悠花は「そうなのだ」と応えるように、頷く。
(ああ、だから皇尊は)
亡き皇尊が、悠花を病弱と説明していたのは、あながち嘘ではなかったのだ。そして死の間際まで娘の行く末を案じた親心を感じた。自分が死んだ後、自分に代わり悠花が頼れる者がいて欲しかったのだろう。
(わたしは女性に対して品行方正だからな。お目にとまったか)
亡き皇尊は、悠花が可愛くて心配でたまらなかったのだろう。
子への愛情と眼差し。それに温かいものを感じる。
これがもし日織の父であれば、おそらく悠花は見向きもされない存在になったのだろう。日織の父であった先々代の皇尊は、皆とは違うところがある者が嫌いだった。侮蔑し嫌悪していたという。
「わたしの父と、悠花の父。兄弟でも違うものだな」
日織の表情が緩んだのに、悠花が問いかけるように小さく首を傾げた。日織は、紙を膝に置く。
「いや、なんでもない。このことは知らずにいた。失礼した。さっきも言ったように、わたしは御遺言の通り、あなたを妻に娶りたいと思っている」
さらさらと悠花の筆が動く。
『良いのでしょうか? わたしのような者を妻にして』
紙にはそう書かれていた。
「何か問題があるのか?」
問うと、悠花は自分の口と足を指さす。日織は苦笑した。
「それがなんの問題に?」
自分に比べれば悠花の問題など些細なことだ。そう言いたいのを飲みこむ。悠花は不思議そうな顔で日織を見つめている。まるで見慣れない生き物を観察するような目で。
「わたしには何の不都合もない。あなたはどうか? 応えてくれるか?」
思案するように悠花は白木の床に視線を落とすが、しばらくすると筆を紙に滑らせ、したためた文字を差し出す。
『あなたの妻になります』
そう書かれていた。
亡き父の思いを受け取った素直な言葉に、胸が痛む。
わずかな逡巡は見せたものの、駄々をこねるでもなく嫌な顔をするでもなく亡き父の遺言を受け入れたのは、従順に育った彼女が、父に逆らうことを知らないからだろうか。
もしくは誰かの妻にならなければ寄る辺がないと、わかっているからなのか。
日織は逆らうことを知らない、あるいは逆らうすべのない、純粋な女を騙しているのだろう。その痛みをあえて気にとめないよう、意識の外へ追い出す。
「では、これからよろしく頼む、悠花。仲良くしよう」
諦めに似た、哀しげともとれる微笑みを、悠花は紅をさした目もとに浮かべる。
(愛してはやれない。そのかわり大切に護ろう。月白と同様にこの人も)
不安を抱かせまいと日織も微笑み返す。
雨音に混じり、とととっと軽い足音が幾つか聞こえた。
「悠花様が、お立ちになるの?」
「祈社を出てしまうの? お迎えがいらしたって」
「悠花様に、会える? 今日も会える?」
聞こえてきた澄んだ高い少女たちの声に、日織はふり返った。枢戸の外で、乳母の杣屋に話しかけているらしい。杣屋が声をひそめて答えている。
「お静かに。今、日織皇子様がいらしていますから」
「悠花様は、日織皇子様の妻になられるのですか?」
「行ってしまわれる? もしかして今日、行ってしまわれる?」
不安げな声音がかわいそうになり、日織は立ちあがった。ひそひそと会話が漏れ聞こえてくる枢戸を開くと、そこにいた杣屋と二人の少女が、びっくりした声をあげた。
「悠花に会いに来たんだね。お入りよ」
少女たちは互いに目配せし、もじもじ躊躇った。一人は十三、四歳の利発そうな眼差しの少女で、もう一人は十歳ほどの、子犬のような、きょとんと丸い目をした少女。
日織は彼女たちの視線までしゃがむ。
「遠慮はいらないよ。いつも来ているのだろう?」
うんと、彼女らは頷く。
悠花をふり返って見ると、彼女はわずかに身を起こして嬉しげに手招きしていた。それを認めた少女たちは、日織の傍らをおっかなびっくりの様子で通り抜け、悠花のところへ駆けていく。彼女の前に座ると、甘えるように身を乗り出す。
「申し訳ございません、日織様。祈社に身を寄せたその日に、あの子たちがここに迷いこんできまして。悠花様が可愛がるものですから、毎日のように遊びに来るのです」
杣屋が申し訳なさそうに頭を下げる。
日織は立ちあがり、少女たちの後ろ姿を見つめた。
「あの子たちは、遊子だね」
「はい。今、祈社にはあの二人だけだそうです。どちらの宮や邸から預けられた子かは、存じませんが」
遊は『どこにも属さぬ』の意。遊子は、どこにも属さない子どもという意味だ。
皇尊の一族に生まれた女たちは、神の眷属である龍の声を聞く。
悠花も当然聞いているだろうし、日織の妻である月白も一族の媛だから、当然聞いている。この杣屋にしても、一族の末席に連なる者に違いないから聞こえるはず。
女たちによると、自分の近くに龍が現れるとその声が聞こえるのだそうだ。
不機嫌な唸り声だったり、たった一言だったり、笑い声だったり。明瞭なお告げのようなものがあるわけではない。ただ龍の気分がわかり、異変が起こっている程度は察せられるらしい。
一方で、一族の女に生まれながら龍の声を聞けない者がいる。
それを遊子と呼ぶ。
遊子は、神の眷属の声が聞こえない、生まれながらに神に見放された者とされ、昔から憐れまれる存在ではあった。時には疎まれた。
一族から憐れまれ、疎まれる女たち。
(まだ、それだけであれば)
少女たちの小さな背中を見つめながら、日織は吾知らず歯を食いしばる。
日織の父であった先々代の皇尊は、ことのほか遊子を嫌った。神を鎮める尊い一族の中に生まれた、出来損ない。忌むべき者。そう決めつけ、自分の即位とともに令を発したのだ。
遊子は祈社に集め、他の一族の者と隔てよ、と。
さらに女子の成人十四歳になれば、八洲いずれかの国主へ下げ渡すものとすると。
ひっそりと、人目を避けるように生きていた遊子は祈社に集められ、十四歳以上の者は八洲のいずれかの国主の妾として下げ渡された。
八洲の国主は、龍ノ原の一族を喜んで受け入れている。遊子たちは八洲のいずれかで、それなりに幸せに暮らしている――そう信じられていた。日織も信じていた。
姉、宇預の亡骸を見るまでは。
「あちらの子は、年はいくつ?」
年上の少女の方へ視線を向けて杣屋に問う。
「十四歳だとか。殯雨が止めば、反封洲の国主から迎えが来ると聞いています」
「反封洲? そのような遠国へ行くと?」
「はい。一旦、逆封洲に出て、そこから海路で反封洲へ入国されると」
「……あの子には、そのように説明がされている、ということか」
この二十年消えることのない怒りが、腹の底でじわりと熱さを増す。
(迎えだと? 誰もが、うすうす知っているくせに。迎えなどと言って卑怯にも、罪悪感をごまかしている。はっきりと口にすれば良い。我らはあの子たちを殺すのだと)
八洲の国主たちは神を鎮める国である龍ノ原を、けして侵略しない。神国である龍ノ原に対する畏怖からだ。その畏怖があるからこそ、龍ノ原から『遊子を受け取れ』と言われれば、抵抗なく受け入れる。
ただし、その後の遊子のあつかいは国主たちの裁量に任されていた。
遊子を妾として、大切にあつかう国主は少なかった。考えてみれば、皇尊から忌むべき者の烙印を押された女たちである。国まで連れ帰ってもらえれば、それは滅多にない幸運で、多くは龍ノ原の外輪山を越える前に殺されていたのだ。
遊子だった姉の宇預のように。
そして日織自身も、宇預と同じく疎まれるはずの遊子として生を受けた。
日織は、女だ。
妻の月白にさえ明かしていない。
日織は背が高く細身だ。髻を結い頭巾をつけ、衣と白袴を身につければ、繊細な印象の青年にしか見えない。思春期には、火柿という、皮膚に触れると痺れる毒気がある木の実を、声がざらざらに掠れるまで食べて喉を潰した。しかも用心のため、衣の襟を高くしつらえて喉元は隠している。
日織が女であり、さらに遊子であると知っているのは、今は空露しかいない。母と姉、乳母は知っていたが、その三人は既にこの世にいない。
本来なら日織も、宇預と同じように十四歳で龍ノ原を追放されていたはずだった。
日織が生まれた時、母と乳母はすぐに、日織が龍の声を聞いていないのに気がつき嘆き悲しんだらしい。
だがそこで、たった七つだった宇預が提案したという。
『この子を男の子にしちゃえば、龍の声が聞こえなくても遊子じゃなくなるよ』
と。
母と乳母は、その思いつきにかけた。
露見すればどんな罰が下るか予測できなかったが、産んだ子が二人とも追放されることに母は耐えられなかったのだろう。
日織を身籠もった直後、遊子追放の令が発せられたことにより、日織の母は夫である皇尊という存在に絶望していた。自らの娘すらも国から追い出そうとする夫の冷酷さに反発し悲嘆に暮れたが、夫の気持ちは変わりはしなかった。それにより母も一層頑なになり、憎しみに似たものすら抱いたという。
夫婦の溝は埋まることなく、臨月を迎えた母は生家の宮に戻り出産した。
本来ならば、ひと月あまりで誕生した皇子を連れ、夫である皇尊の待つ龍稜に帰るべきであった。だが彼女は、産後の回復がままならぬとして宮に留まった。
父皇尊にとっては、初の皇子である。
皇子の顔すら見られぬことに父皇尊は業を煮やし、「我が子を抱く」と言って、ひと月過ぎると、自ら宮にやって来た。
日織の母と乳母は、冷静だった。
近隣の里に住む娘が、日織の誕生と数日の差で男子を産んでいると聞きつけ、その子を一日借り受け、「日織皇子」として父皇尊に抱かせたのだ。
日織の母は体の不調を理由に、その後も生家の宮に留まり続け、必然的に日織も母の側にいた。時折、父皇尊が気まぐれに顔を見せはしたが、ひととき日織の元気な様子を見れば、それで良いとばかりに宮を去ったらしい。
父皇尊は、我が子を慈しみたい人ではなかった。
世継ぎの皇子が育っていれば、それで良かったのだ。
自らの発した令に不満を示し、暗い顔をする妻の機嫌をとるよりも、そうして離れた場所で世継ぎを育てていれば良いと考えていた節がある。
そもそも父皇尊は、日織の母を娶る前から心に決めた媛があったが、思いが遂げられず、その人のことが忘れられないのだとまことしやかに囁かれてもいた。
もともと夫婦の情愛など脆い――いや、なかったに等しい妻と夫。
父皇尊の冷淡さが、皮肉にも、日織の秘密を保つには好都合だった。
幸運にも日織は男子として育ち、今も無事でいる。
けれど自分だけ、母や乳母、姉の機転で生き残った。宇預は無残に殺されたのに、自分はその姉の機転で生きながらえた。それを思う度に胸に重苦しいものが溜まる。
利発そうな瞳を輝かせ、悠花に何事かを話しかけている少女の横顔が見えた。まだ幼さの残る表情が愛らしい。
(あの子が旅立つ前に、令を廃止しなければ。そのために)
皇尊の発した令を廃するのは、皇尊にしか出来ない。
(そのために、わたしが皇尊になるのだ)
二十年前に宇預の亡骸を目にし、その後に死の真相を知ったとき、強烈な怒りとともに決意したのだ。
女であり、遊子であることを隠し、周囲を欺き続け皇尊になると。
そして父が定め、姉を殺した令を廃すると。
それが姉宇預への弔いであり、その死を無駄にしない方法であり、自らの運命に抗う方法だった。
皇尊即位の機会が巡ってくるかどうかは、わからなかった。日織は継承権のある立場だったが、皇尊に皇子が生まれれば、その子が大兄皇子となり皇尊を継承するのだから。
(だが幸運だった。この二十年、皇尊は男子に恵まれず、あるのは皇女の悠花だけ。悠花には気の毒だが、彼女がわたしの妻になれば、令を廃するのに有利に働く)
崩御した皇尊に皇位を継承するべき皇子がいないため、必然的に皇位は、継承権のある一族男子の誰かが継ぐ。
今回は、三人が皇尊候補に挙がっており、日織もその中の一人に入っている。
皇尊となった後に、父であった皇尊の令を廃するのが、日織の最大の目的。
もし日織が皇尊となれたときは、亡き先代皇尊の遺言でその娘を娶っていることは、大祇や大臣たちの信頼を得る材料になる。先代皇尊が命じて皇女を娶らせたほどであるのだから、受け継ぐべくして受け継いだ皇位と見なされるはず。そうなれば令を廃することに関しても、反対派を黙らせるのは容易だ。
(だがまずは、皇尊とならなくては)
皇尊選びは二日後から始まる予定だった。
「誰が従うものか。定めなんぞ」
遊子の少女らの背中を見つめながら、小さく呟く。
それは何百、何千と唱えてきた呪文のような言葉。
遊子の女が皇尊となる。神を鎮める役目を負う皇尊の地位に、遊子の女が即こうなどとは不遜と、誰もが言うだろう。
しかし。
女は皇尊になれないと、神の言葉でしかと聞いた者はないのだ。
皇尊が男子直系とされているのは、地龍を眠りにつかせた皇祖、治央尊が男子であったためだ。
治央尊はその身をもって地龍を眠らせる封印となしたので、皇祖の血をひく者が神代から御位に即く。確かなことはそれだけ。男子直系のみを皇尊と決めたのは神ではなく、皇尊の性別が変わることにより、地龍が目覚めるのを怖れた人なのだ。
さらに遊子は追放せよと、それも神が決めたわけではない。日織にしてみれば、恐ろしく狭量で莫迦げた令を、父が勝手に定めたに過ぎない。
そもそも遊子が神に見放された存在だと、日織は思わない。龍の声を聞く聞かないは、特性だと信じている。
神職たちは、男よりも女の方が神への感応力が高いと言う。だからこそ一族の女たちは龍の声を聞く。ということは、ただの特性でしかないということではないだろうか。
もし龍の声が聞こえないのが神に見放されている証ならば、男の全ては神に見放されているということ。にもかかわらず男子が皇尊になるのは大いなる矛盾。しかし人は慣例と感情を便利に使い、自分たちに都合の良い理屈を考え、矛盾には目をつぶる。
人の解釈が、様々なものをねじ曲げていく。
ただの特性を、善し悪しと区別したがるのは常に、神ではなく人だ。
全て人が決めたことだとすれば、そんなものは欺いても痛くもかゆくもない。人が定めたものなら、人が破っても良いはずだった。
仮に神が決めたものだったとしても――神の目でも欺き抜く。
「二日後迎えに来る。その子たちと別れを惜しむがいいよ。まだ猶予はあるから」
日織の言葉に、少女たちは残念そうな目をした。悠花は長い袖で、彼女たちの頭を慰めるようにさらさら撫でる。
「二日後、ともに龍稜に入ろう。悠花」
悠花が、日織に目を向け頷く。
龍稜。それは龍ノ原の中心に位置する、皇尊の住む場所だ。
三
この大地は央大地と呼ばれ、一原八洲の九つの国で成っていた。
大海に浮かぶ大地は、巨大な眠れる龍の上にあると信じられている。
地の底で眠る龍は、地大神、地龍と呼ばれ、これが目覚めれば大地は海に没すると伝えられている荒ぶる神。世の根幹を支える荒魂。
龍ノ原は巨大な山稜に、ぐるりとほぼ円形に囲まれた国だ。これは龍ノ原が、途方もない大きさの火山の火口にあるからだった。龍ノ原を護るように存在する山の連なりは、火口の外輪山。それを護領山と呼ぶ。
央大地と呼ばれていたが、その実態は海から隆起したいびつな形の巨大火山島。ただその規模があまりに途方もなく大きいので、島と呼ぶよりも大地と呼ぶ方がしっくりくる。
龍ノ原の皇尊は、その巨大火山の下に眠る地龍が、目覚めないように鎮めるのが役割なのだ。
神代より央大地に伝わる口伝をまとめた『古央記』には、国造りの神話としてこうある――。
かつて大海には、つがいの二頭の、万能の神たる巨龍がいた。
つがいの一頭があるとき死に、残された巨龍は哀しみ荒れ狂い、大海はおそろしいばかりとなった。そのとき大海の向こうには、幾百億の民が住む古の大地があった。古の大地は争いが絶えず、争いのために大地は海に没し、そこから逃れた人々が大海に漕ぎ出した。
民を率いて海へ漕ぎ出したのが、龍ノ原の皇祖、治央尊。
荒れる大海で哀しみに荒れ狂う巨龍と出会った治央尊は、巨龍の哀しみを癒やすことはできずとも、眠らせて哀しみを忘れさせてやると約束し、その身をもって巨龍を眠らせる封印となした。
巨龍は眠りにつき、その上に大地ができた。治央尊と民はその大地に降り立ち新たな住処となしたのだ。
大地の下に眠る地龍は、眠り続けたいのだという。
眠り続けることこそが地龍の願いだと。
だから龍ノ原には龍がいる。
神とは穏やかなばかりの存在ではない。神としての力を有するためには、荒魂と和魂の双方を内包しなければならない。荒魂がなければ和魂にも力はない。また荒魂だけでも力はない。双方があっての神である。
故に、荒ぶる神である地龍と対をなす存在としての龍が、和魂として龍ノ原には生まれ飛翔し、地龍を鎮める皇尊に力を貸す。危険を知らせ、助言をするという。
実際、皇尊の一族の女たちは龍の声を聞く。
皇尊が空位となれば龍が不安がり、雨が止まない。
空位が四年におよべば、地龍が目覚め天変地異が起こり、一原八洲全てが海に没する。
龍ノ原の皇尊は、恐ろしい神を眠らせておくための重石。地龍の眠りを護る者。
その重責は、皇尊の存命中には、新たな皇尊に譲位できないことでも明らかだった。地龍と結縁できるのは、この世に一人のみ。その者の命が尽きない限りは、新たな縁を結べないのだ。
龍ノ原の皇尊とは央大地で、唯一無二の存在。
だからこそ、利権や領地を巡って小競り合いが絶えない八洲の国々でも、龍ノ原に手を出せないのだ。
細かい雨を透かし見て、日織は鹿毛馬の上で目を細めた。
「龍稜か。いつ見ても大きいな」
龍稜の周囲には里郷や田畑はなく、平坦でどこまでも見通せる。膝上に達するほど丈の長い草が一面を覆っていた。林や森がなく、雑木一本すら生えていない。誰が管理しているわけでもないのだが、龍稜の周辺には木が育たない。
そのかわりに草が生える。草の葉は細く龍の髭に似ていた。雨のために葉は項垂れていたが、晴れていればぴんと葉先が空を指し、山から吹き下りてくる風に筋をなして一斉になびく。その様は、見えない龍が草原を渡るようで清々しいのだ。
草原の中央に巨大な岩が一つ、地面から押し出されたように立ちふさがっている。
岩と呼ぶよりも、岩山と言った方がいい大きさだった。高さは龍ノ原を囲む外輪山、護領山に匹敵する。
護領山の最高峰である祈峰から望めば、緑の地面から、とてつもなく大きな龍の爪が一本突き出てきたように見える。頂上が微妙に湾曲しているから余計にそう見えるのだった。
山のように大きくとも、それは一つの巨大な岩石。
麓から岩に刻み込んだ石段が続き、その中腹をくりぬいて、高床、白杉柱の建物が収まっている。一箇所ではない。あちこちの岩がくりぬかれ、それぞれに大小の建物があり、蟻の巣のように石段と懸造りの回廊で繋がっている。
これが龍ノ原の皇尊の住むべき場所、龍稜だった。
雨に濡れた巨大な岩は黒ずみ、低く垂れ込めた灰色の雲に、爪を突き立てようとしているようにも見えた。
日織と馬を並べていた空露が、ひそめながらも緊張した声で言う。
「油断してはなりませんよ、日織。皇尊の候補は、あなただけではない」
「わかっている」
空露はさりげなく、視線だけを後ろに向ける。
彼らの背後には、舎人たちに支えられた板葺屋根で黒塗りの輿が二つ。二つとも布を垂らして中を隠してあるが、一つには月白、もう一つには悠花が乗っている。
「お二人と過ごす時間が多くなるでしょう。他の候補者たちとも、龍稜で過ごすことになります。知られてならぬことは、けして知られぬように」
耳もとで囁かれ、日織は無言で頷く。
空露が最も警戒しているのは、日織が女だと露見すること。
日織は早くから宮を持っていたので、日常生活で困ることはなかった。二年前に月白を妻にしたが、通い婚なので一緒に住んでもいない。日常的に他人の目が近くにある環境は初めてなのだ。
(露見すれば、即位どころか龍ノ原を追放になる)
ぞっとする。死に直面する怖さよりも、何もなしえず、ただ無為に命が終わる瞬間の悔しさを想像した。
(継承権のある者を集め、大祇や大臣たちは何をするつもりだろうか)
新たな皇尊を決めると知らされていたが、教えられているのはそれだけだった。
龍稜に入る総門は木王門と称され、巨岩の根もとに開いた隧道。巨大な岩の裂け目でありながら木王――梓と称されるのは、そこから先に邪なものを通さない意味がある。
岩の裂け目をぬって石段が刻まれ、上へ上へと続いている。
龍稜にのぼった日織は居所として、四つの殿舎が一つの窪みに収まる宮を与えられた。
月白と悠花はその宮に入ったが、日織は真っ直ぐ大殿へ向かう。
大殿は龍稜の頂上近くにある。くりぬかれた窪みに建てられた、高床、檜皮葺の白杉柱の建物。前庭におりる階の左右に桃の木が植えられていたが、殯雨に打たれ疲れているらしく、鮮やかな緑の葉は地面に葉先を向けて項垂れていた。簀子縁が崖のぎりぎりにせり出しているので、そこに立つと、草原を渡って雨粒と一緒に吹きあがってくる風が、体を浮かすのではないかと思えるほど強く吹きつける。
周囲には、雨音とは違う激しい水音が響いていた。
大殿の背後に、岩肌から湧き出て流れ落ちる滝が見える。
通常の滝とは様相が違う。滝は、川も池も見あたらない岩壁の途中からいきなり噴き出しているのだ。岩壁の向こうに溜め池があり、その横壁に穴が開いたかのようにも見えるが、溜め池などはない。そこは間違いなく固い岩盤。なぜそこから水が噴き出すのか、未だに誰も説明できない。
噴き出す水の奔流は深い滝壺に注ぎ込んでいる。それは地面にうがたれた、まさに壺を埋め込んだような大きな穴。流れ出ることはなく一定の水位を保っている。水は滝壺の底から、さらに地下へと流れ出ているらしい。龍稜の底へと。
龍稜は奇妙な場所だと、大祇や大臣たちはよく口にする。
大殿の階を上ると、枢戸の前に采女がいた。彼女は一礼し戸を開く。
一歩入ると、辛いような香木の香りが充満していた。儀式の場で焚かれる払邪香だ。
中に仕切りはなく広い板敷きになっている。白杉柱が規則正しく並ぶ空間の左右に、神職である大祇と三人の大臣たちが左右に分かれ座っていた。
龍ノ原を統治する皇尊の最も近くに仕え、実質的に龍ノ原の政を司るのが、大祇と三人の大臣たちだった。
大祇は護領衆の長であり、地大神である地龍と、龍ノ原に飛翔する龍の眷属を祀り仕える者として皇尊の傍らにある。
三人の大臣は、太政大臣と、左右の大臣。左右の大臣は政の実務の長であり、太政大臣は皇尊に最も近い相談役と言える。
彼ら重臣の手前には、こちらに背を見せて二人の男が座す。
最奥の壁には五色の布が垂れている。その前に、高足の黒漆塗りの台――宝案があり、紫色の絹布がかけられた何かが置かれていた。
「日織皇子様、ご到着です」
出入り口から采女が告げると、大祇と三人の大臣たち、さらに背を向けていた男二人が一斉にこちらを向いた。
日織は、両袖口を胸の前であわせて恭しく礼をし、采女に促され二人の男の隣に座る。
「久しいな、日織。何年ぶりだ。随分大きくなったな」
隣の男が小さな声で話しかけてきた。
日織より十二歳年上の従兄弟、不津王だった。肩幅が広く、逞しい体つきをしており、肌は浅黒く眉が濃い。唇も厚く、生命力が漲っている。華奢で細身、色白の日織と比べればよほど男らしい。
「とうに成人した者に、大きくなったはないだろう」
不津からすれば、日織など未熟な少年のように思えるのだろう。従兄弟ではあったが大して関わりがあるわけではなく、皇尊の催す宴で、時折顔を見ている程度の男だ。日織はそういった場を極力避けていたので、ほとんど話をしたことがない。
冷淡な反応にも不津はめげずに、にこやかに言う。
「二人、妻を娶ったそうだな。どうだ?」
(わたしの妻に興味でもあるのか?)
日織は従兄弟の顔をまじまじ見る。
(不津の興味をそそっているのは、月白よりも悠花だろうな)
不津には既に三人の妻がいる。左の大臣の娘である双子の姉妹二人と、皇尊の一族の中でも舞の上手と褒めそやされている媛だった。月白は重臣の娘というわけでもなく、美貌や歌舞の上手として名高いわけでもない。人前に出ることを好まず宴にも顔を出さない、一族の中でも存在感の薄い媛なので、彼が好む種類の女ではない。
「どう、とは?」
何が訊きたいのかと、不審がりながら問い返す。
「私語は控えよ、不津。日織」
鋭く注意したのは不津の隣に座るもう一人、山篠皇子だ。彼は不津の父。なおかつ日織の父の弟皇子の一人でもあった。要するに日織の叔父の一人。
この度亡くなった皇尊は、この山篠の兄に当たる。
息子とは違い、山篠は不機嫌そうな表情で日織を睨みつけていた。
(さもありなんか。彼らはこれから、わたしと皇尊の御位を争うのだから)
山篠の視線を横顔に感じながら、日織は正面を向く。
(わたしと、不津、山篠の叔父か)
この三人が皇尊となる継承権を持つ。
三人のうちの誰かが、新しい皇尊に選ばれるはずだった。そのために龍稜に呼ばれたのだから。
「お三方、揃われたようですな」
大臣のうちで、最年長であり最上位でもある太政大臣、淡海皇子が口を開く。
淡海皇子は日織や不津の大叔父で、二人の祖父の弟にあたる。髭と頭髪は白く、肌も異様な白さを呈す。年齢とともに漂白されたような姿は、三十年以上も太政大臣を務めた落ち着きの上に、さらに特異な風格を与えていた。
「こちらにお集まりいただいたのは、皇尊の継承権を有するお三方です。亡き皇尊のお子は、悠花皇女様のみで皇位を継ぐ男子がおりません。そこで一族の中で、皇位継承の権利をお持ちのお三方にお集まりいただいた。このお三方のいずれかを、皇尊として我々は戴くことになろうと思います」
日織に継承権があっても、皇尊が男子に恵まれていればこの機会は巡って来なかった。
この二十年、胸に秘めていたものがふつふつと滾ってくる。滾るのすら抑えこんでいた思いだ。流れが味方しなければどうにもならないと、空露も言い続けていた。
だがこの一点に関してのみは、流れは日織に向いたのだ。
(来てくれたのだ、わたしに。流れが)
ずっと抜け出せなかった沼地から、一歩踏み出す瞬間が来た心地だった。
「どうやって皇尊を決定する? 過去、同等の継承権を持つ数名がいる場合は、血の系統や周囲からの推挙で決まった例がある。時々によって違う。今回の決定の基準は?」
視線を大祇と大臣たちへ移すと、日織は静かな声で問う。かしこまっていた不津と山篠が、意外そうに日織を見やる。
人前にあまり姿を見せず、たまに宴に出席しても、黙って少し酒を飲んですぐに席を立つ、覇気も気力もない大人しい青年。日織は一族の者たちからはそんなふうに思われているだろうから、真っ先に口を開いたことに、その場にいた者は驚いただろう。
自らに皇位継承権があり、皇尊となれる可能性があると知ったときから、どんな条件が揃えば自分が皇尊になれるのかを、空露とともに丹念に調べていたのだ。
なにしろこの日まで、時間だけはたっぷりあった。
何年もの間、日織はことあるごとに、正史『原紀』は勿論、祈社に納められている記録文書をひもとき、過去の即位礼にかかわる記録を読んでいた。
大祇が、太政大臣の淡海皇子に代わって口を開く。
「お三方に、我々より一つ問いを差しあげる。その問いを解いた者を皇尊といたします」
大祇は、淡海とは対照的な黒々とした頭髪を肩に垂らしていた。年も若く四十代だが、こちらは神職だけあって、年齢よりも老成した気配がある。名を真尾といい、先頃崩御した皇尊の代になって大祇となった者である。
「問い?」
意外さに、日織は目を見開く。
(問いだと? 聞いたことがない)
聞いたこともないし、記録を読んだ覚えもない。真尾は落ち着いた様子で頷く。
「左様。問いです。過去、系統や推挙で決定したのと同様に、今回はその方法を用いるというだけのこと」
「なぜこの度に限って問いだと?」
不津が不満そうに訊くと、淡海が無表情な白い顔で答えた。
「皇尊が崩御の直前に、そうせよと仰った」
「神代にはあったと聞きます」
付け加えた真尾の言葉を、山篠が鼻先で笑った。
「神話であろう。莫迦莫迦しい。それをするというのか。大祇や太政大臣は、皇尊の言が第一という立場はわかる。だが左右の大臣もそれで承知なのか」
淡海の隣に控えていた左の大臣・阿知穂足は、大祇の真尾と年はいくらも変わらない。しかし濃い髭のせいか、真尾よりもずいぶん老けて見える。彼は濃い髭を軽くしごき、わずかばかり不満そうな色を目に浮かべながらも言う。
「いまわの際の皇尊から、直接頼むとお言葉をかけられましたからな。本来ならば一族と臣の合意で決定すべきことですが、このたびは致し方なしと」
穂足の言葉に、右の大臣・造多麻呂が頷く。父の跡を継いで数年前に右の大臣になった男だ。まだ三十代。若いながら有能と言われている。切れ長の目で山篠を見据える。
「わたしも、穂足殿と同様」
その答えを聞くと、大祇の真尾が深く頭を垂れ、
「皇尊のご遺志です」
亡き皇尊の遺志に敬意を表すかのように、口にした。淡海も穂足も多麻呂も、亡き皇尊の言葉を敬うかのごとく叩頭し、山篠は鼻白んだように顔をしかめる。
(皇尊は、何を考えて「問い」で次期皇尊を選べと言ったのだろうか?)
病に臥せって半年、一度も床を離れることなく皇尊は崩御した。日に日に弱っていくのを感じながら、自らの死後のことを思い悩んでいたのは間違いない。娘の行く末、龍ノ原の行く末を案じ、その結果なにを考え思いついたのか。
「それで問いとは」
日織は力強く訊いた。問いを解けと言うならば、解けば良い。一族の推挙を得るために、あちこち根回しをして回るよりも、日織にとっては単純でやりやすいはずだった。
一族への根回しとなれば、皇尊候補の中で最も有利なのは不津だ。左の大臣は彼の舅である上に、交際範囲も広く活発な男なのだから。
真尾が立ちあがり、最奥にある宝案に近づくと被せてあった布を取る。
「こちらです」
宝案の上には文箱に似た形の透明な箱が、蓋を外された状態で置かれていた。
中は空だ。
「水晶の箱か。ただの箱に見えるが」
日織は目を眇めた。水を凝らせたような透明度ではあるが、縁に簡単な文様の浮き彫りが細工されているだけの簡素な箱。
「これは皇尊に継承される遷転透黒箱というもの。地大神たる地龍の鱗と伝えられる宝物――龍鱗を入れる箱です。この中に龍鱗を入れれば蓋が閉まり、黒色に変化します。ただしこの箱は、中に龍鱗を入れぬ限りは蓋が閉まりません」
真尾が蓋を手に取り箱に被せようとするが、わずかに大きさが合わないらしく、蓋と箱の縁が微妙に擦れあい到底はまりそうもない。
「皇尊に皇子があり、その大兄皇子がこれを継承する場合、黒色のまま蓋も開かず大兄皇子に引き継がれます。しかし大兄皇子がいない場合、龍鱗は引き継がれません。新しく即位した皇尊が見つけるしかない。親から皇位を引き継がなかった歴代の皇尊は、即位後にこれを見つけるのが務めでした」
「見つけるとは、どういう意味だ。宝物はその中に入っているのでは?」
山篠が問う。
「皇位を引き継ぐ大兄皇子がなく皇尊が崩御した場合、龍鱗はこの箱の中から消えます」
「消える?」
さらに不可解そうに山篠が繰り返す。神職らしい落ち着きで水晶の箱に目を落とした真尾は、その中に何かを見ているような眼差しをする。
「はい。誰も手を触れておらぬのに、皇尊崩御の直後に自然と蓋が開き、箱は透明に変化し、中は空になっております。ただし消えた龍鱗は龍稜のどこかにあるのです。それを見つけるのです。崩御された皇尊は、兄である先々代の皇尊から龍鱗を引き継がれませんでした。即位後に皇尊は自ら探し、見つけられた」
真尾は改めて、三人の候補に視線を注ぐ。
「亡き皇尊は、こうお考えだったのです。即位した皇尊は、いずれ龍鱗を見つけなければならない。ということは、龍鱗を見つけられる者は皇尊の資格があるはず。それならば皇尊候補に龍鱗を探させ、それを見つけた者を皇尊とするべきだと」
「龍鱗とは、どんなものだ。色や形、大きさは」
訊いた日織に、真尾は首を横に振る。
「我々の誰も知りません。知っているのは皇位を継いだ皇尊のみ」
「形もわからないものを探せというのか? 無茶な」
不津が呆れた声を出す。
「しかし皇尊となった方々は全て、見つけられている。見つけられることこそが、皇尊にふさわしいということ。正しいものをこの箱に納めれば、必ず蓋が閉まります」
山篠も不津も、そんな莫迦なという顔をしていた。日織も唖然とした。
(龍稜の中で、その箱に入る何かを探せと?)
皇尊の崩御とともに、二十年もの長きにわたって停滞していた日織の運命が動き出していた。