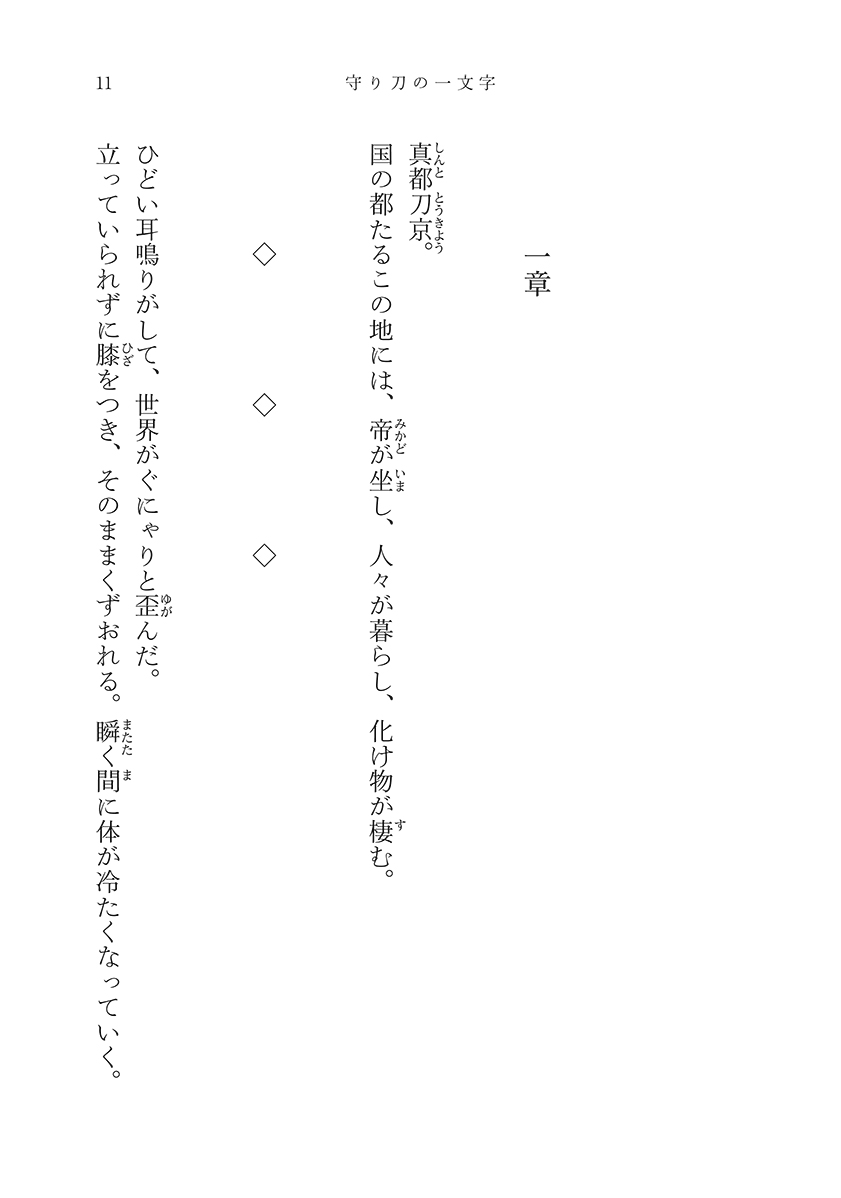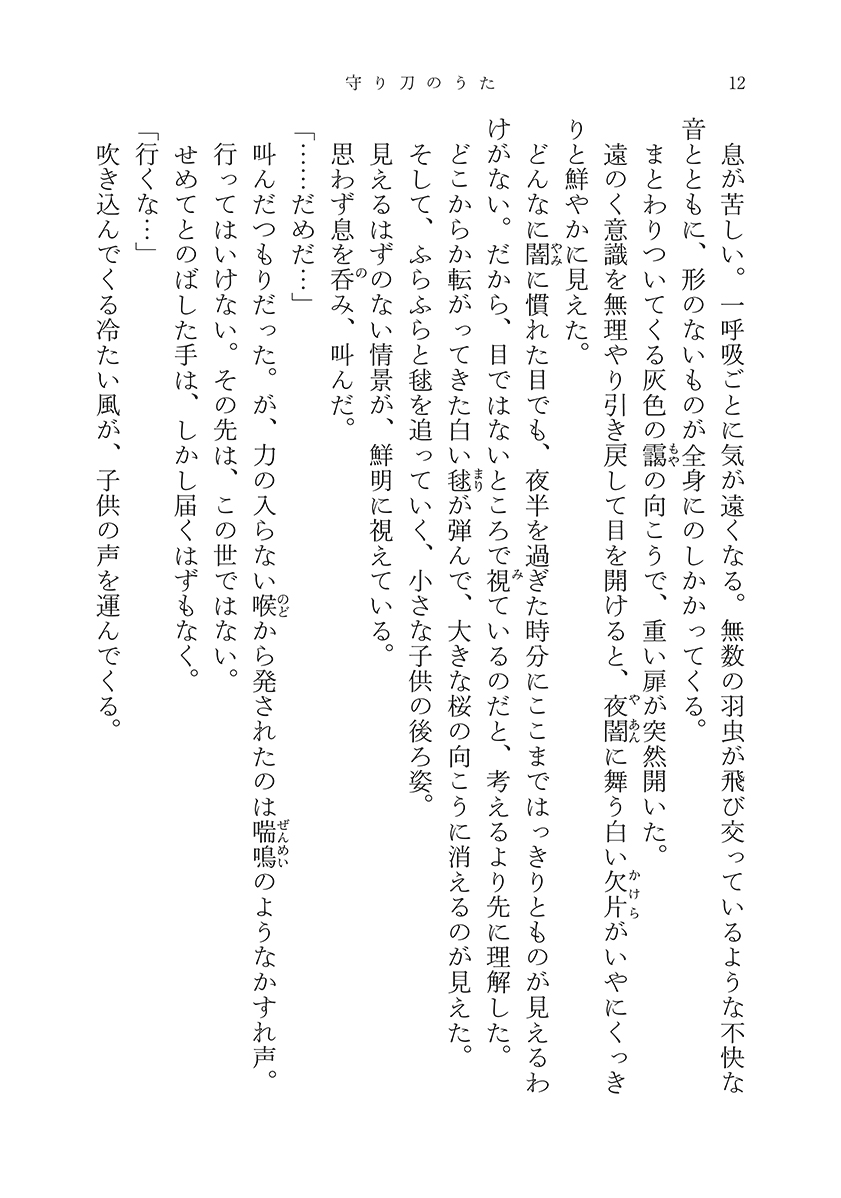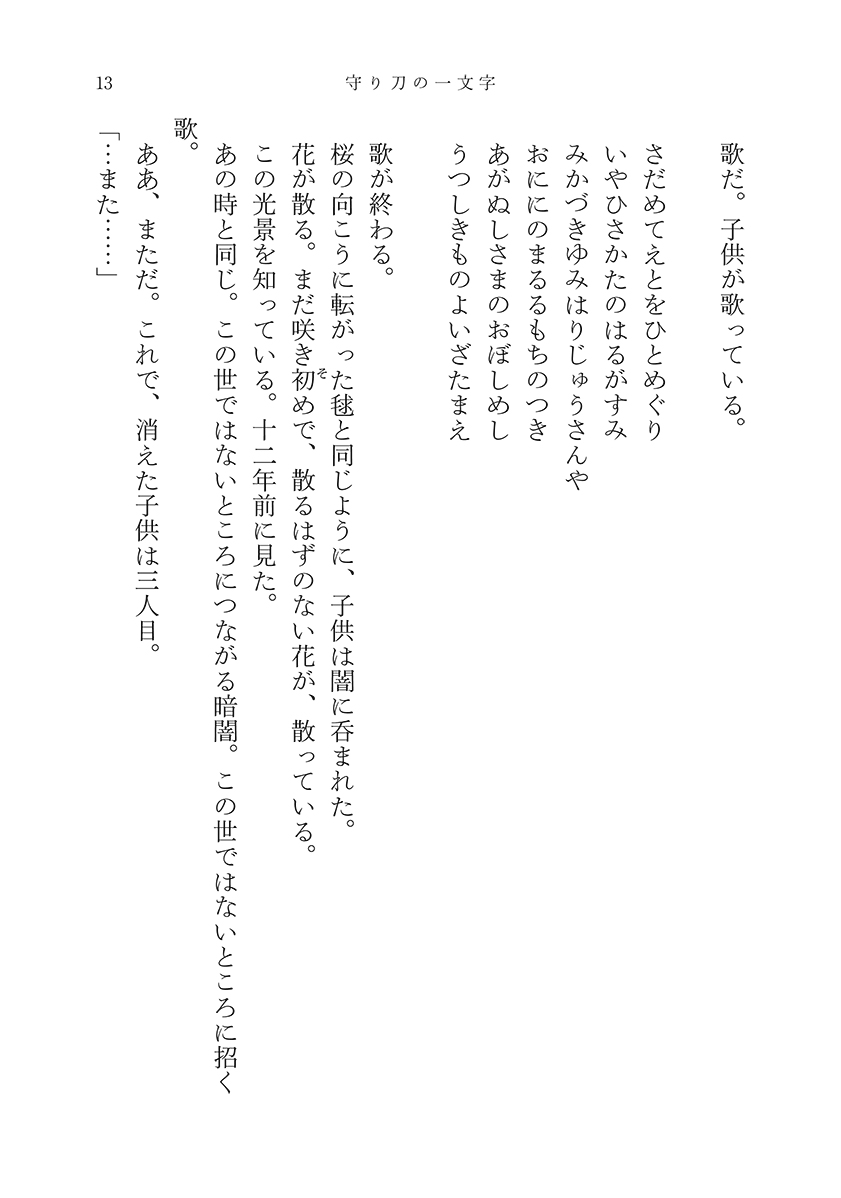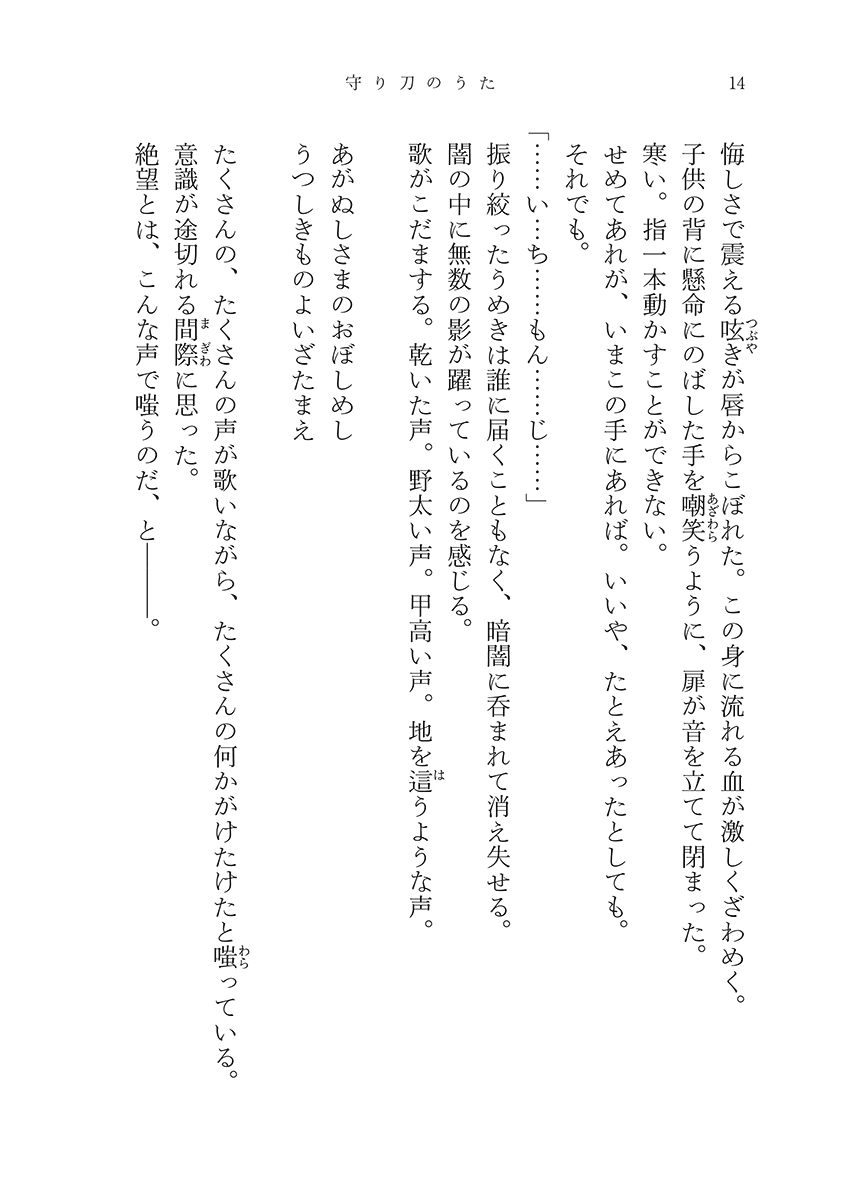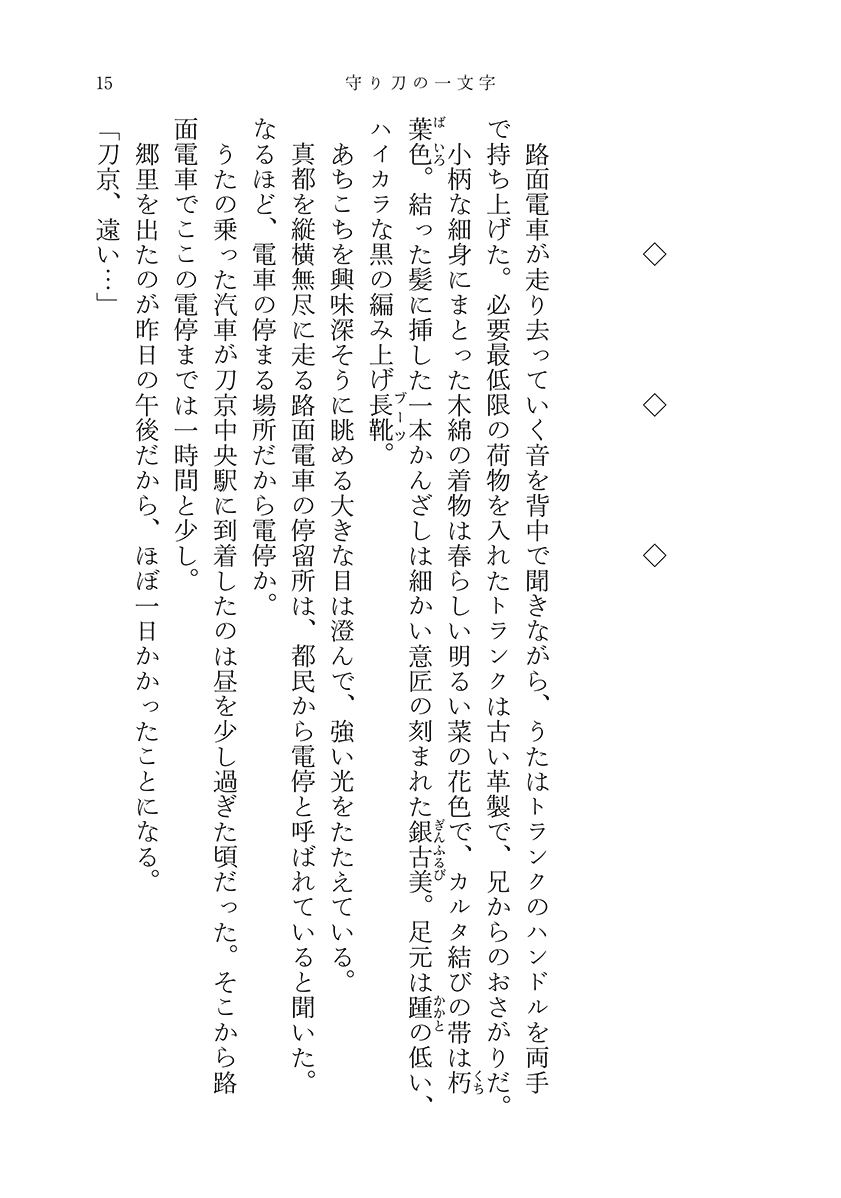一章
国の都たるこの地には、
◇◇◇
ひどい耳鳴りがして、世界がぐにゃりと
立っていられずに
息が苦しい。一呼吸ごとに気が遠くなる。無数の羽虫が飛び交っているような不快な音とともに、形のないものが全身にのしかかってくる。
まとわりついてくる灰色の
遠のく意識を無理やり引き戻して目を開けると、
どんなに
どこからか転がってきた白い
そして、ふらふらと毬を追っていく、小さな子供の後ろ姿。
見えるはずのない情景が、鮮明に視えている。
思わず息を
「……だめだ…」
叫んだつもりだった。が、力の入らない
行ってはいけない。その先は、この世ではない。
せめてとのばした手は、しかし届くはずもなく。
「行くな…」
吹き込んでくる冷たい風が、子供の声を運んでくる。
歌だ。子供が歌っている。
さだめてえとをひとめぐり
いやひさかたのはるがすみ
みかづきゆみはりじゅうさんや
おににのまるるもちのつき
あがぬしさまのおぼしめし
うつしきものよいざたまえ
歌が終わる。
桜の向こうに転がった毬と同じように、子供は闇に呑まれた。
花が散る。まだ咲き
この光景を知っている。十二年前に見た。
あの時と同じ。この世ではないところにつながる暗闇。この世ではないところに招く歌。
ああ、まただ。これで、消えた子供は三人目。
「…また……」
悔しさで震える
子供の背に懸命にのばした手を
寒い。指一本動かすことができない。
せめてあれが、いまこの手にあれば。いいや、たとえあったとしても。
それでも。
「……い…ち……もん……じ……」
振り絞ったうめきは誰に届くこともなく、暗闇に呑まれて消え失せる。
闇の中に無数の影が躍っているのを感じる。
歌がこだまする。乾いた声。野太い声。甲高い声。地を
あがぬしさまのおぼしめし
うつしきものよいざたまえ
たくさんの、たくさんの声が歌いながら、たくさんの何かがけたけたと
意識が途切れる
絶望とは、こんな声で嗤うのだ、と―――。
◇◇◇
路面電車が走り去っていく音を背中で聞きながら、うたはトランクのハンドルを両手で持ち上げた。必要最低限の荷物を入れたトランクは古い革製で、兄からのおさがりだ。
小柄な細身にまとった木綿の着物は春らしい明るい菜の花色で、カルタ結びの帯は
あちこちを興味深そうに眺める大きな目は澄んで、強い光をたたえている。
真都を縦横無尽に走る路面電車の停留所は、都民から電停と呼ばれていると聞いた。なるほど、電車の停まる場所だから電停か。
うたの乗った汽車が刀京中央駅に到着したのは昼を少し過ぎた頃だった。そこから路面電車でここの電停までは一時間と少し。
郷里を出たのが昨日の午後だから、ほぼ一日かかったことになる。
「刀京、遠い…」
思わずこぼした呟きに疲労がにじんでいるのが自分でも感じられる。刀京は遠いと聞いてはいたが、これほどに遠いとは。
うたはこれまで、生まれ育った郷里を出たことがない。国の大動脈と
本当は、年の離れた兄が一緒のはずだった。兄がいるから大丈夫、不安なことなどひとつもない。そう思っていたのだが。
「………」
こんなに遠いと、ほんの少し、心細くなる。
「……うた、顔をあげろ」
はっと視線を向ければ、足元にちょこんと座った白犬が、深く澄んだ目でうたをじっと見つめている。
三角の耳をぴんと立てた小柄な白犬は、郷里から一緒に出てきたうたの大事な相棒だ。
動物を連れて汽車に乗ることは、珍しいが禁止されてはいない。ほかの乗客たちが興味深げに視線を向けてきたが、シロはひと鳴きもしないでうたの足元にずっと伏せていたので、やがて誰も気にしなくなった。
「俺が一緒なんだから、心配するな」
シロの言葉は、うたやある一部の者以外には、わんわんと
「シロ…そうね、うん」
電停を出てすぐの道沿いを流れる
「ええと、ここから……」
着物の合わせ目に手を入れようとしたうたに、シロが前足で向こう岸をさした。
「あっちだ」
「ほんとに?」
「ほんと」
「一応確かめる」
合わせ目から出した地図を開くうたにシロの声が飛ぶ。
「地図、逆さま」
「……、いくわよ、シロ」
地図を着物の合わせ目に押し込んで歩き出すうたに並んだシロはため息をつく。
ふたりのほかにこの電停で電車を降りた客はいなかった。川にかかった花見橋を渡るのはうたとシロだけだ。
歩きながらシロがため息をつく。
「うた、俺はお前が心配だよ」
「大丈夫よ。シロもいるし。シロがいるんだから。シロがいれば」
「つまり俺がいなきゃ駄目じゃん」
「シロがいるから大丈夫ってこと」
言い合いながら橋を渡りきる直前、ひんやり冷たい風が吹いて頬を
うたは視線をめぐらせた。咲き初めの桜が震えるように揺れている。
ふいにあたりが煙り、どこからか歌声がした。
足を止めて見れば、桜の下で子供がふたり、毬をつきながら歌っていた。
さだめてえとをひとめぐり
いやひさかたのはるがすみ
みかづきゆみはりじゅうさんや
おににのまるるもちのつき
あがぬしさまのおぼしめし
うつしきものよいざたまえ……
咲き初めの桜の下で、毬をつきながら繰り返し繰り返し、楽しそうに、面白そうに、着古した
なんとなく、うたは違和感を覚えた。桜の下で毬つきをする子供たちの姿が、妙にかすんで見えたのだ。
子供たちが歌えば歌うほど、
「……なんだか、怖い歌」
大きなトランクを道におろして、うたはそっと呟いた。
風で流れてきた霞が、うたの前にわだかまり、静かに散って消える。
うたは
「妖気……。真都くらい人が多いと化生のものも集まるだろうが…」
刀京が都に定められてからおよそ五十年。帝に従ってきた貴族たちは、財産とともにあまたの家来とその一族郎党を連れてきた。やがて国中から出稼ぎの者も集まるようになり、結果、刀京の人口はこの十年で倍近くまで増えたという。
人がいれば善であれ悪であれ様々な思惑が渦を巻く。短期間で増えればその動きはより激しくなる。
それらの念はときに妖異や
しかし。
「これはちょっと、集まりすぎだろう」
シロの言葉にうたはこくりと頷く。
うたとシロの目には、あちこちに生じた
妖気が凝り固まって虫のような何かに変化し、それが集まって渦巻きながらうねっているのだ。
何ごともなければ渦巻いているだけだからさほど害はないが、生きもののようにうねる様はあまり気分の良いものではない。
妖気を見つめていたうたは、ふと気がついた。
「……ねぇ、シロ」
「ん?」
「
「うん」
大抵の妖気の渦は放っておけばじきに散っていくものだが、そうならないものもある。周りの妖気を取り込んで大きく育っていくのだ。そうやって育ったものを、
「あっちに、ひときわ大きな妖気の渦が見える気がするんだけど」
うたが道のずっと先を指さすと、シロは
「……」
「あれって……」
「うた、お前は見るの初めてだったよな。あれが禍柱だ」
「やっぱり」
「あのくらいになると……まずい」
シロの声音に緊迫した響きが混じる。
「じゃああとで……」
言いかけたとき、歌っていた子供たちがあっと叫んだ。
うたとシロが視線をめぐらせると同時に、転がってきた赤い毬がうたの足にとんとぶつかって跳ねる。そのまま転がっていきそうだった毬をシロが前足でたしっと押さえた。
毬を拾い上げたうたは、駆け寄ってきた子供たちと目線が同じくらいの高さになるようにひょいっとかがんだ。
「はい」
毬を返してやると、並んだ子供たちはくしゃっと笑った。彼らの履いた下駄は古びて、鼻緒は
向かって右側に六、七歳程度の女の子、左側に男の子。男の子は女の子よりやや年少に見える。きょうだいだろうか。
「ありがとう」
声を
「どういたしまして」
瞬間、きいんと耳鳴りがした。うたは眉をひそめて片耳を押さえる。
「………」
ほんのわずかな時間、視界が真っ白に染まって、そのあと徐々に色が戻ってきた。
「おねえちゃん、どこからきたの?」
「おねぇちゃん、どこまでいくの?」
大きなトランクと傍らの白い犬を興味
「西の方から来たの。このお
うたの言葉にふたりは意味ありげな顔をして、視線を交わした。
女の子の手から毬が落ちて、ころころと転がった。転がっていく先に、桜が並んでいる。どこまでもどこまでも。
見える世界に、桜以外何もない。
冷たい風が吹いた。霞が足元に流れてくる。
「おねえちゃん、よそからきたの」
「おねぇちゃん、どうしてきたの」
シロは耳を小さく震わせた。妙だ。子供たちの
「御用があるからよ」
答えるうたを、子供たちは大きく
「おねえちゃん、それって」
「おねぇちゃん、ぬしさまの」
そこでふたりの甲高い声がぴたりと揃う。
「ごよう?」
異口同音の問いかけに、うたはひやっとしたものを感じながら首を傾けた。
「…ぬしさま…?」
ふたりはもう一度視線を交わすと声を揃えた。
「かみかくし」
「え……」
「か、み、か、く、し」
「――――」
うたとシロはふっと息を詰めた。
故意に一語一語を区切った甲高い声が、強く吹き抜けた風にさらわれる。
「……かみ…かくし…?」
口の中で呟くうたに、ふたりはにっと笑う。
「あそぶ?」
「あそぼ?」
女の子の左手と男の子の右手がうたにのびてくる。
うたは反射的に身を引いて立ち上がった。
「ううん、遊ばない」
「あそぼうよ」
「あそんでよ」
言い募る子供たちとうたの間にシロが割って入る。
強い風に運ばれて霞が押し寄せてきた。子供たちとうたとシロのいる場所が灰色がかった白に煙る。
「遊ばない」
「ここにいて」
「いかないで」
ふたりがまた声をそろえる。
「ねぇ、おねえちゃん」
風と、風に揺すられる桜の立てる音が強くなった。
あがぬしさまのおぼしめし
うつしきものよいざ……
霞が視界を
うたは
「もう行かなきゃ」
「ここにいて」
「いかないで」
「むこうにいこう」
「おねぇちゃん」
「行かない。……そうだわ。ねぇ、教えて。
その途端、子供たちが甲高く叫んだ。
「おばけやかた!」
「え?」
虚をつかれたうたとシロは目をしばたたかせる。
さっきまでと打って変わり、子供たちの顔が
「おばけやかた!」
「おばけ!」
「おばけのなかま!」
「にげろー!」
男の子の叫びが合図のように、ふたりは
うたは
「おばけ、やかた……?」
それまでその場に
冷たい風に吹かれて、うたはふうと息を吐いた。
「……あの子たち、いったい…」
「…おばけのなかま、ときたか」
何やら複雑な面持ちで、シロが耳のあたりを後ろ足でわしゃわしゃと
「おばけ、じゃあないんだけどなぁ、俺」
変にくらくらする。額を押さえて何度か深呼吸をしたうたは辺りを見回した。
道を尋ねようにも、近くには誰もいない。
さっきより風が冷たく感じられて、肌寒さに身をすくめる。
「えっと……」
改めて地図を見る。地図に書き込まれた住所と目的地を示す赤丸。電停と呼ばれる路面電車の停留所のそばの川と桜並木。橋を渡って、対岸の桜並木沿いの道を。
地図をたどる指先がかじかんでいる。異様に寒い。
「牧原伯爵様のお邸は…まっすぐいって、角を曲がって……」
道順を確認しているうたの背に、突如として声がかけられた。
「ちょっとあんた、大丈夫かい?」
うたとシロが同時に振り返ると、木綿の着物にたすき掛けと膝まである無地の前掛けをした、まとめ髪の中年女性が険しい顔をしていた。
うたとシロはとっさに声が出なかった。
さっきまで誰もいなかったのに、この女性はいったいどこから出てきたのだろう。
「え、あの……」
当惑したうたは言葉に詰まって何度も瞬きをする。
「青い顔してるよ。こっちにきてお座り」
「え」
「ほら、いいから」
「ええ…」
手招きをする女性の後ろを見ると、さっきまでなかったはずの建物があった。茶店だ。店の前に
うたは、改めて女性を眺めた。
橋を渡ってすぐの、こんな近くに茶店があったとは。
気がつかなかった。川沿いにずっとつづく桜並木に隠れていたのか。
店の軒先に下がった品書きが、風を受けてひらひら揺れている。塩むすび、五目飯、うどん、みたらし団子、あん団子、ごま団子、甘酒、ほうじ茶。
促されるまま縁台に座ったうたは、出されたほうじ茶をすすった。熱いお茶が腹に
「ああ、顔色が良くなってきたね」
ほっとしたような女将の言葉に、うたは頬に手を当てた。
「そんなに、でしたか?」
「ああ。……あの世を
独特の言い回しが引っ掛かる。さっきの奇妙な子供たちを思い出し、うたは思わずこう言った。
「……まるで…かみかくしから戻ってきたような…?」
女将の顔が
「…あんた…さっき、牧原伯爵様のお邸とか、言ってたね」
「はい」
「伯爵様のお邸に、何の用?」
低く尋問するような語気の女将に、うたは居住まいを正して答えた。
「伯爵様に雇っていただいて、これからお邸に御奉公にあがります」
女将は驚いたように軽く目を瞠った。
「……あんた、いくつ?」
「十五です」
小柄なうたは、実際の
答えたうたに、女将は険しい顔で声をひそめた。
「……いきなりこんなことを言われて面食らうかもしれないけど」
「はい?」
「あんた、行くのはおよし。悪いことは言わないから」
「え?」
「あのお邸の
「噂…? でも、もう奉公に上がると決まっているので」
すると女将は
「……お邸は、ここをまっすぐ行って、曲がって、ちょっとのところなんだけどね」
女将はついと指さした。指の先を追うと、ちょうどあの禍柱の方角だった。
うたは、かばしら、と口の中で呟く。
子供たちが口にした「おばけやかた」という単語がうたの脳裏をかすめて消える。
「少し前…半月くらい前、だったかね……。邸の主に奉公人が全員、追い出されたって話だ」
「追い出された…?」
首を傾けるうたに、女将は辺りに目を配りながら口元に手を当てて顔を寄せる。
会話を聞かれないようにする
そんなことをしなくても、この道には自分たち以外誰も。
何気なくそう思って視線を動かしたうたは、はっと目を瞠った。
人が行きかっている。書生風の青年や洋装の壮年男性、
うたは何度もまばたきをした。
こんなに人がいたのか。いまのいままで気がつかなかった。
あの霞のせいだろうか。橋を渡ってから、どういうわけか、桜並木の下で毬つきをしていたあの子供たちしか見えていなかった。
神隠し、という言葉が脳裏をよぎる。奇妙なめぐりあわせや何かの大きな力に誘われて、こことは別の
「……女将さん、あの」
子供たちが遊んでいた辺りを指して尋ねる。
「さっきの子たち、どこの…」
「さっきの子?」
「その木の下で毬つきをしていたでしょう、女の子と男の子」
女将はさっと顔色を変えた。
「……あんたと一緒だったのは、その白犬だけだよ」
「え?」
うたは困惑した。うたの横にいるシロも眉をひそめている。
「そんな。だって、さっき…」
「あんた、それ、誰にも言ったらいけないよ」
うたの言葉をさえぎった女将は素早く辺りに目を配った。まるで、恐ろしいものが近くにいないかを確かめるように。
「その子たち…、消えたんだよ」
「え……」
「消えたんだ。どんなに探しても見つからなくて、神隠しだってことになった」
女将は苦しそうに一瞬視線を落とす。その姿に、ひんやりとした灰色の靄がかかったように、うたには見えた。
「……でも、違うんだ。本当はね、牧原伯爵様の御子息が、自分を食いにきたばけものに、代わりに差し出したんだ…」
「え……」
うたはぞくりとした。行きかう人々の気配が靄に包まれて遠ざかる。
「牧原様の御子息は…
すると、女将の悲痛な言葉に重なるように。
あがぬしさまのおぼしめし……
子供たちが歌っていた歌が、奇妙に甲高い声で紡がれる歌が、どこからかかすかに聞こえた気がした。