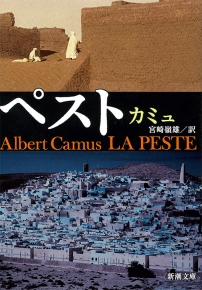試し読み 第1回
四月十六日の朝、医師ベルナール・リウーは、診療室から出かけようとして、階段口のまんなかで一匹の死んだ
同じ日の夕方、ベルナール・リウーは、アパートの玄関に立って、自分のところへ上って行く前に部屋の鍵を捜していたが、そのとき、廊下の暗い奥から、足もとのよろよろして、毛のぬれた、大きな鼠が現われるのを見た。鼠は立ち止り、ちょっと体の平均をとろうとする様子だったが、急に医師のほうへ駆け出し、また立ち止り、小さななき声をたてながらきりきり舞いをし、最後に半ば開いた唇から血を吐いて倒れた。医師はいっときその姿をながめて自分の部屋へ上った。
彼が考えていたのは鼠のことではなかった。鼠の吐いた血で、自身の心配ごとに引きもどされたのである。一年以来病んでいた彼の妻は、山の療養所へ明日たつことになっていた。帰ってみると、妻は、彼にそういわれたとおり、居間のほうに寝ていた。そうやって、転地の疲労に備えているのであった。彼女はほほえんだ。
「とても気分がいいの」と、彼女はいった。
医師は、枕もとの
「できたら眠るといいな」と、彼はいった。「看護婦は十一時に来るから、そうしたら十二時の汽車に連れてってあげるよ」
彼は軽く汗ばんだ額に接吻した。微笑が戸口まで追って来た。
翌四月十七日、八時に、門番は通りかかった医師を引きとめて、悪ふざけをするやつらが廊下のまんなかに死んだ鼠を三匹置いて行ったと訴えた。きっと大きな罠でとったものに違いない、なにしろ血だらけだ。門番は鼠の足をぶらさげてしばらく入口の
「まったく、やつら」と、ミッシェル氏はいっていた。「最後にゃ、とっつかまえてやるぞ」
何かいわくありそうな気がして、リウーは、患者のうちでいちばん貧しい人たちの住んでいる外郭の地区から往診を始めることにした。
訪ねた最初の病人は、道路に面した寝室と食堂を兼ねた部屋で、床についていた。これは、落ちくぼんでいかつい顔をした、年寄りのイスパニア人であった。彼は自分の前のふとんの上に、
「どうですね、先生」と、注射の間に彼はいった。「やつらの出て来るこたあ。見ましたかい」
「そうなんですよ」と、細君はいった。「お隣じゃ三匹も見つけたんですとさ」
爺さんはもみ手をしながら――
「出て来るのなんのって、芥箱って芥箱にはみんないまさあ。こいつは飢饉ですぜ」
リウーが、それに引き続いて、その界隈じゅうが鼠のうわさをしていることを確かめるのには、たいして手間はかからなかった。往診が終って、家へ帰って来た。
「あんたに電報が来てますぜ、
医師は、また鼠を見つけたかと尋ねた。
「見つけるもんかね」と、門番はいった。「こっちは見張ってまさ、ちゃんとね。で、あんちくしょうども、やれないんでさ」
試し読み 第2回
電報はリウーに母が明日着くことを知らせたものであった。病人の留守中、息子の家のめんどうを見に来るのであった。医師が家へはいると、看護婦はもう来ていた。見ると、妻はちゃんと起きて、テイラード・スーツのいでたちに、化粧のあとまで見せていた。彼はそれにほほえみかけて――
「ああ、いいな」といった。「とてもいいよ」
それから間もなく、停車場で、彼女を寝台車に乗り込ませた。彼女は車室を見まわした。
「たいした料金なんでしょう、あたしたちの身分じゃ。そうじゃない?」
「必要なことだもの」と、リウーはいった。
「いったいどういうんですの、今度の鼠さわぎは」
「わからない。まったく奇妙だ。だが、そのうち済んじまうだろう」
それから、彼はひどく口早に、彼女に向って、どうかゆるしてくれるように、ちゃんと気をつけてやるべきだったのに、ずいぶんほったらかしにしていてと、いった。彼女は、なんにもいわないでというように、首を振っていた。しかし、彼は付け加えた――
「何もかもよくなるよ、今度帰って来たら。お互いにまたもう一度やり直すさ」
「ほんとよ」と、目を輝かせながら彼女はいった。「やり直しましょうね」
それから間もなく、彼女は彼に背を向け、窓ガラスの外をながめていた。ホームの上では、人々が急ぎ合い、ぶつかり合っていた。機関車のシュッシュッという音が彼らのところまで聞えてきた。彼は妻の呼び名を呼んだが、振り向いたのを見ると、その顔は涙におおわれていた。
「だめだなあ」と、やさしく彼はいった。
涙の陰から、やや引きつったように、またほほえみが浮んできた。彼女は大きく息をついた。
「行っておいで。万事うまく行くよ」
彼は彼女を抱きしめ、そして今はもうホームに立って、窓ガラスの向う側に、ただ彼女のほほえみを見るばかりであった。
「くれぐれも体に気をつけてね」と、彼はいった。
しかし、彼女には、それは聞えなかった。
出口に近く、駅のホームで、リウーは予審判事のオトン氏が小さい男の子の手を引いているのにぶつかった。医師は、彼に旅行に出かけるのかと尋ねた。長身黒髪のオトン氏は、半ばはかつて社交界の人士と呼ばれたものに似、半ばは葬儀人夫に似た
「家内を待ってるんです。私の実家にご機嫌うかがいに行ってましたので」
機関車の汽笛が鳴った。
「鼠が……」と、判事がいった。
リウーは汽車の方角へちょっと身を動かしたが、また出口のほうへ向き直った。
「ええ」と、彼はいった。「なに、なんでもありませんよ」
この瞬間について記憶に残ったことといえば、死んだ鼠のいっぱいはいった箱を小脇にかかえた一人の駅員が通ったということだけであった。
同じ日の午後、診察時間の初めに、リウーは一人の若い男の訪問を受けたが、それは新聞記者で、すでに朝のうちにも訪ねて来たということであった。名はレイモン・ランベールといった。胴が短く、肩は厚く、はっきりした顔つきに、明るく聡明な眼をしたランベールは、スポーツ仕立ての服を着、生活には不自由のない人間らしく見えた。彼は単刀直入に切り出した。パリのある大新聞のために、アラビア人の生活条件について調査をしているところで、彼らの衛生状態についてききたいというのである。リウーはそれに対して、そのほうの状態はよくはない、といった。しかし、それ以上話を進める前に、いったい新聞記者というものはほんとうのことをいえるのか、それを知りたいといった。
「もちろんです」と相手はいった。
「僕のいう意味は、全面的にやっつけるというところまで行けるかということです」
「全面的とは行きません。それはどうしてもそうなんです。しかし、そのやっつけるというのは別に根拠はないことなんでしょうね」
穏やかな調子でリウーはそれに答えて、いかにもそんなやっつけるなどということは根拠のないことであろうが、しかしその質問をしたのは、ただランベールの証言が留保のないものでありうるか否かを知ろうとしたのだ、といった。
「僕は留保のない証言しか認めないんです。ですから、あなたの場合にも、僕の報告を提供することはしません」
「まさにサン・ジュスト(訳注 フランス革命当時の熱狂的な正義論者)の言葉ですね」と、ほほえみながら新聞記者はいった。
リウーは、それに対して別に声の調子を高めることもなく、その点はどうだか知らないが、これは自分の暮している世界にうんざりしながら、しかもなお人間同士に愛着をもち、そして自分に関する限り不正と譲歩をこばむ決意をした人間の言葉である、といった。ランベールはじっと首をすえて、医師の顔を見つめていた。
「あなたのお気持ちはわかるような気がします」と、立ち上りながら、最後に彼はいった。
医師は戸口へ送って行った。
「あなたがそんなふうに受けとってくださって、僕もうれしいんです」
ランベールは、じれったそうにした。
「ええ、わかってます」と、彼はいった。「おじゃましてすみませんでした」
医師は彼の手を握り、そして、目下市内で発見されている大量の死んだ鼠について興味ある報道記事をものすることができるだろう、といった。
「ほう!」と、ランベールは声をあげた。「そいつはおもしろいですね」
十七時に、医師がまた往診に出かけようとすると、階段の途中で、がっしりと彫りの深い顔に濃い眉毛を一文字に引いた、姿全体に重々しさのある、まだ若い男とすれ違った。その男には、時おり、このアパートの最上階に住んでいるイスパニア人の舞踊師たちのところで出会ったことがあった。ジャン・タルーは、しきりにたばこをふかしながら、足もとの階段の上で死にかけている一匹の鼠の最後の痙攣をながめていた。彼は医師のほうへ、その灰色の眼の、落ち着いた、やや見すえるような視線をあげ、挨拶の言葉をいい、そしてこの鼠どもの出現は興味あることがらだと付け加えた。
「ええ」と、リウーはいった。「しかし、こうなると、もう小うるさくなってきますよ」
「ある意味ではね。ある意味でだけですよ。つまり、こんなことは見たことがないっていうだけのことです。しかし、僕はこれを興味あること、まったく、実際に興味あることだと思ってるんです」
タルーは髪の毛をうしろにかきあげ、今はもう動かなくなった鼠を再びながめ、それからリウーにほほえみかけた――
「しかし、要するにですな、こいつは何よりも門番の問題というわけです」
ちょうどその門番を医師はアパートの前で見かけたが、入口のそばの壁にもたれて、いつもは血色のいいあから顔に、ちょっとぐったりしたような表情を浮べていた。
「ああ、知ってまさ」と、ミッシェル老人は、新たな発見を知らせたリウーにいった。「なにしろ二匹だの三匹だのって見つかるんだからね、今じゃ。だが、こいつはほかのアパートでもおんなじなんでさ」
彼の様子はいかにも打ちのめされたように、気づかわしげであった。機械的な動作でしきりに首をこすっていた。リウーは、体具合はどうかと尋ねた。門番は、体具合が悪いとは、もちろんいえなかった。ただ、どうも調子が十分でない。彼の意見では、つまり精神的なものが作用しているのだ。あの鼠どものためにショックを受けたわけで、やつらが姿を消してしまえば万事ずっと順調になるだろう。
試し読み 第3回
しかし翌四月十八日の朝、駅から母を迎えて来た医師は、ミッシェル氏がまた一層しなびた顔つきをしているのを見た。地下室から屋根裏まで、十匹もの鼠が階段に散乱していたのである。近所の家々の芥箱は鼠でいっぱいだった。医師の母親はその話を聞いても別に驚かなかった。
「いろんなことがあるものですよ」
黒いやさしい目をした、銀髪の、小柄な婦人であった。
「あたしはうれしいの、ベルナール、またお前の顔が見られて」と彼女はいった。「鼠だってなんだって、それをどうすることもできやしないさ」
彼もその言葉にうなずいた。そういえば、まったく、彼女の手にかかると、すべてがいつでも造作のないことに見えるのであった。
リウーは、それでも、そこの課長を知っている市の
「うん、命令さえあればね」と、メルシエはいった。「君がもしそうするだけのことがあると思うんなら、ひとつ、命令を出してもらうようにやってみてもいいんだが」
「そりゃ、やればやるだけのことはあるさ、いつだって」と、リウーはいった。
家政婦が今しがた伝えたところによると、彼女の夫の働いている大工場では、死んだ鼠が何百匹となく拾い集められたという。
いずれにしても、ほぼこの時期において、わが市民は不安になり始めたのであった。というのが、この十八日の日から、工場や倉庫は事実幾百という鼠の死骸を吐き出したのである。ある場合など、断末魔の長すぎるやつは手をくだして殺すことを余儀なくされた。しかも、外郭地区から市の中心に至るまで、およそ医師リウーの通りかかるところ、市民の集まるところには、至るところ山をなして芥箱の中に、もしくは長い列をなして溝の中に、鼠が待ち受けていた。夕刊紙はさっそくこの日から事件をとりあげて、市庁は果して動き出すつもりかどうか、また、この不快な襲来から治下の市民を守るために果していかなる緊急措置を検討したかを問題にした。市庁はまだ何をするつもりもなく、なんら検討もしていなかったが、そのかわり、まず会議に集まって評定することから始めた。毎朝、明けがたに、死んだ鼠を拾集するよう鼠害対策課に命令が発せられた。拾集が終ると、課の車二台がその鼠を
しかし、続く数日において事態はさらに悪化した。拾い集められる
事態はついに報知(情報、資料提供、ありとあらゆる問題に関するいっさいの情報)通信社が、その無料提供情報のラジオ放送において、二十五日の一日だけで六千二百三十一匹の鼠が拾集され焼き捨てられたと報ずるに至った。この数字は、市が眼前に見ている毎日の光景に一個の明瞭な意味を与えるものであり、これがさらに混乱を増大させた。それまでのところ、人々は少々気持ちの悪い出来事としてこぼしていただけであった。今や、人々は、まだその全容を明確にすることも、原因をつきとめることもできぬこの現象が、何かしら由々しいものをはらんでいることに気づいたのである。ひとり、例のイスパニア人の喘息もちの爺さんだけが、相変らずもみ手をしながら、「出て来るわ、出て来るわ」と、年寄りらしい喜びをもって繰り返していた。
試し読み 第4回
とかくするうち、四月二十八日には報知通信社は約八千匹の鼠が拾集されたことを報じ、市中の不安は頂点に達した。人々は根本的な対策を要求し、当局を非難し、海岸に家をもっている人々のうちには早くもそっちへ引きあげる話まで言いだすものもあった。ところが、翌日、通信社はこの現象がぱったりとやみ、鼠害対策課は問題とするに足りぬ数量の鼠の死骸を拾集したにすぎなかったと報じた。市中はほっとした。
しかもその同じ日の正午、医師リウーは、アパートの前に車をとめると、街路のはずれに、門番が、首をうなだれ、両手両足を広げ、あやつり人形のような格好で、難儀そうに歩いて来るのを見たのである。老人は一人の司祭の腕につかまっていたが、その司祭は医師も知っている顔であった。パヌルー神父という博学かつ戦闘的なイエズス会士で、彼も時々会ったことがあり、市では宗教上のことに無関心な人々の間にさえなかなか尊敬されていた。医師は二人を待った。ミッシェル老人は眼をぎらぎらさせ、せいせい息をきらしていた。どうも体の調子がよくなかったので、外の空気に当ってみようと思った。ところが、首と腋の下と鼠蹊部に激しい
「どうも
車の戸口から腕を出して、医師はミッシェルの差し出す首の付け根のあたりを指でさぐった。一種の木の節くれのようなものが、そこにできていた。
「寝て、熱をはかっといてください。今日、午後から来てみます」
門番が行ってしまうと、リウーはパヌルー神父に、例の鼠の騒ぎについてどう考えているか尋ねた。
「なに」と神父はいった。「きっと流行病でしょう」、そういって、彼の眼は丸い眼鏡の陰で微笑した。
昼食がすんで、リウーが妻の到着を知らせる療養所からの電報をまた読み返していると、電話のベルが鳴った。昔の患者の一人で、市役所に勤めている男からかかってきたのであった。ながらく大動脈
「ええ、私なんですが、おわかりですね」と、相手はいった。「ところで、実はほかの人のことなんですがね。至急おいで願います。隣のうちにちょっと事件が起りまして」
その声は息を切らしていた。リウーは門番のことを考えたが、そっちはあとでまわることにきめた。数分ののち、彼は外郭区域のフェテルブ街にある低い建物の入口をくぐった。ひんやりとして悪臭の漂う階段の途中で、迎えに降りて来た吏員ジョゼフ・グランに会った。長くたれ下った黄色い口髭をはやし、肩幅が狭く、手足のやせた、五十がらみの男である。
「どうやらいいようです」と、リウーのほうへやって来ながら、彼はいった。「しかし、もうだめかと思いましたよ」
彼はしきりに
二人ははいった。テーブルは片隅に押しやられ、ひっくり返った椅子の上方に、綱がたるめてかけ渡してあった。しかし、その綱はただぶらんと宙にたれていた。
「私が、まだ間に合ううちに下ろしてやったもんで」と、グランはいったが、最も簡単な言葉で話すくせに、いつも言葉を捜しながらしゃべっているように見えた。「私は出かけようとしたんですよ、ちょうどそのとき。すると物音が聞えました。あの文句を見たとき、まあどう説明したらいいか、私はいたずらだと思ったんです。ところが、そこへ妙なうめき声をたてたじゃありませんか、妙な、それこそ確かに不吉といってもいいくらいな……」
彼は頭をかいた。
「私の考えるところじゃ、こいつをやるときはきっと苦しむんでしょうね。もちろん、私ははいって行きました」
一つのドアを押すと、明るい、しかし家具の乏しい部屋の入口であった。丸ぶとりの小柄な男が、銅の寝台に寝ていた。男は荒い息づかいをしながら、血走った眼で二人を眺めた。医師は立ち止った。その呼吸の合間に、かすかに鼠のなき声が聞えるように思ったからである。しかし、隅っこのあたりにも、なんにも動いている気配はなかった。リウーは寝台のほうへ行った。男は、そう高いところから、あんまり急激に落ちたわけではなく、椎骨は無事だった。もちろん、多少窒息症状がある。レントゲン写真をとってみる必要があろう。医師はカンフル注射をし、二、三日ですっかり落ち着くだろうといった。
「ありがとうございました、先生」と、圧し殺したような声で、男はいった。
リウーはグランに、警察には知らせてあるかと尋ねたが、すると、グランはちょっと狼狽の色を見せて――
「いや、そいつは、そりゃまだ……。私はそう思ったんです、いちばん急を要することは……」
「そりゃもちろんですがね」と、リウーはさえぎった。「それじゃ、そいつは僕がやりましょう」
ところが、そこまでいうと、病人がしきりに気をもみだして床の上に身を起し、もうよくなったからそれには及ばないと反対した。
「まあ落ち着いて」と、リウーはいった。「別にどうこういうほどのことじゃないんですよ、大丈夫。とにかく、私は届け出をしなきゃならんのです」
「ああ!」と、相手はうなった。
そうして、仰向けに身を投げ出すと、しゃくりあげて泣いた。グランは、しばらく前からしきりに口髭をひねっていたが、そのそばへ寄った。
「まあ、まあ、コタールさん」と、彼はいった。「こいつはわかってくださいよ、なにしろ、先生には責任があるともいえるんですからね。かりに、万一、あなたがまた変な気を起したりしたら……」
しかしコタールは、涙の中から、自分は二度と始めはしない、あれは単に一時の錯乱であり、自分はただそっとしておいてもらいたいだけだと、いった。リウーは処方を書いた。
「よくわかりました」と、彼はいった。「その話はそれだけにして、二、三日したらまた来ます。しかし、ばかなまねをしちゃいけませんよ」
階段口で、彼はグランに、届け出はどうしてもしなければならぬが、しかし警官には取り調べを二日後でなければ行わぬようにいうつもりであることをいった。
「今晩は付いててやらなきゃなりませんね。家族はあるんですか」
「私も知らないんですよ、家族の人ってものは。しかし、私が自分で付いててやれますから」
彼は頭を振った。
「あの人だって、それがね、私は知ってるとはいえないんです。しかし、まあ、助け合わなきゃなりませんから」
アパートの廊下を通って行きながら、リウーは機械的に隅っこのほうを眺め、この界隈から鼠が完全に姿を消したかどうか、グランに尋ねた。グランはそれについてなんにも知らなかった。なるほど、そんなふうな話は聞かされていたが、しかし彼は町内のうわさ話にはたいして注意を払わないほうだった。
「私にはほかに気をひかれることがあるもんですから」と彼はいった。
リウーはもう彼の手を握っていた。妻に手紙を書く前に門番の様子を診に行こうと急いでいたのである。
試し読み 第5回
夕刊の呼び売りは鼠の襲来が停止したと報じていた。しかし、リウーが行ってみると、病人は半ば寝台の外に乗り出して、片手を腹に、もう一方の手を首のまわりに当て、ひどくしゃくり上げながら、薔薇色がかった液汁を汚物溜めのなかに吐いていた。しばらく苦しみ続けたあげく、あえぎあえぎ、門番はまた床についた。熱は三十九度五分で、頸部のリンパ腺と四肢が
「焼けつくようだ」と、彼はいっていた。「こんちくしょう、ひどく痛みゃがって」
黒ずんだ口のなかで言葉はくぐもりがちに、目玉の飛び出た目を医師のほうに向けていたが、その目には頭痛のために涙が浮んでいた。女房は、じっと黙りこんでいるリウーを不安に堪えぬ様子でながめていた。
「先生」と、女房はいった。「いったい、なんでしょう、これは」
「さあ、いろんなふうに考えられるんでね。しかし、まだなんにも確かな兆候はない。晩まで、絶食と浄血剤だ。うんと飲みものをとるようにしなさい」
ちょうど、門番はのどがかわいてたまらないところだった。
家に帰ると、リウーは同業のリシャールという、市内で最も有力な医者の一人に電話をかけた。
「いや」と、リシャールはいった。「べつに、とくべつ変ったことは目につかなかったが」
「局部的な炎症を伴った熱っていうようなものは、なかったですか」
「そうだ、あったよ、そういえば。二件ばかり、リンパ腺につよい炎症が来ててね」
「異常にですか」
「さあね」と、リシャールはいった。「普通っていうと、なにしろ……」
いずれにしても、その晩、門番はうわごとをいいはじめ、四十度の熱を出しながら、鼠のことを口走った。リウーは
リンパ腺はさらに大きくなり、さわってみると堅く木のようになっていた。門番の女房はおろおろしていた。
「ずっとついててあげなさい」と、医師は女房にいった。「それで、呼んでください、もし何かあったら」
翌四月三十日は、もうなま温かい微風が、青くしっとりした空に吹いていた。風は花の香を運んで、郊外のずっと遠くのほうからもそれが漂って来た。街々の朝の物音はふだんより一層生きいきと楽しげに聞えた。一週間を暮してきた暗黙の懸念から解放されて、この小都市の町じゅう、この日はおよそ一陽来復の一日であった。リウー自身も、妻から手紙があったのでまず安心して、軽快な気持ちで門番のところへ降りて行った。そして、事実、朝になって熱は三十八度に下っていた。衰弱して、病人は床のなかでほほえんでいた……
「だいぶいいようだけど、どうでしょう、先生」と、女房はいった。
「まあ、もう少し様子をみないと」
ところが、正午になると、熱は一挙に四十度に上り、病人は間断なく
「どうもこいつは」と、リウーはいった。「こいつは隔離して、まったく特別な手当てをやってみる必要があるな。病院に電話をかけるから、救急車で連れて行こう」
二時間の後、救急車のなかで、医師と女房とは病人の顔をのぞき込んでいた。いちめん菌状のぶつぶつでおおわれた口から、きれぎれの言葉がもれていた――「鼠のやつ!」と、病人はいっていた。土気色になり、唇は
「もう望みはないんでしょうか、先生」
「死んでしまった」と、リウーはいった。
******
その後、『ペスト』では同様の熱病者が続出し、次々と罪なき市民が命を奪われていく。感染拡大を防ぐために街は外部と遮断され、封鎖状態に。行政は対応に後れを取り続け、ペストの脅威は拡大の一途をたどっていくのであった……。