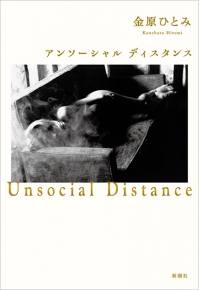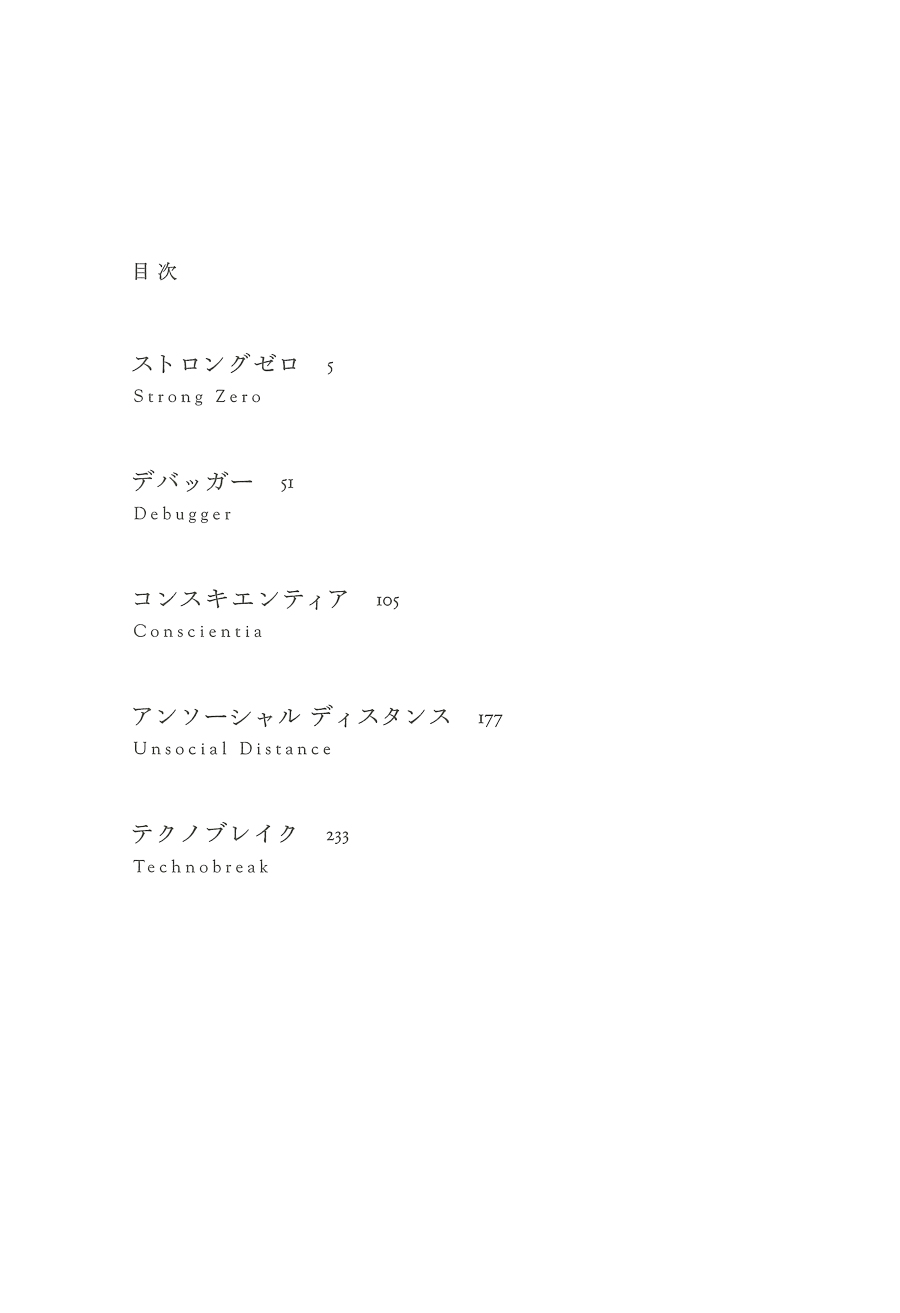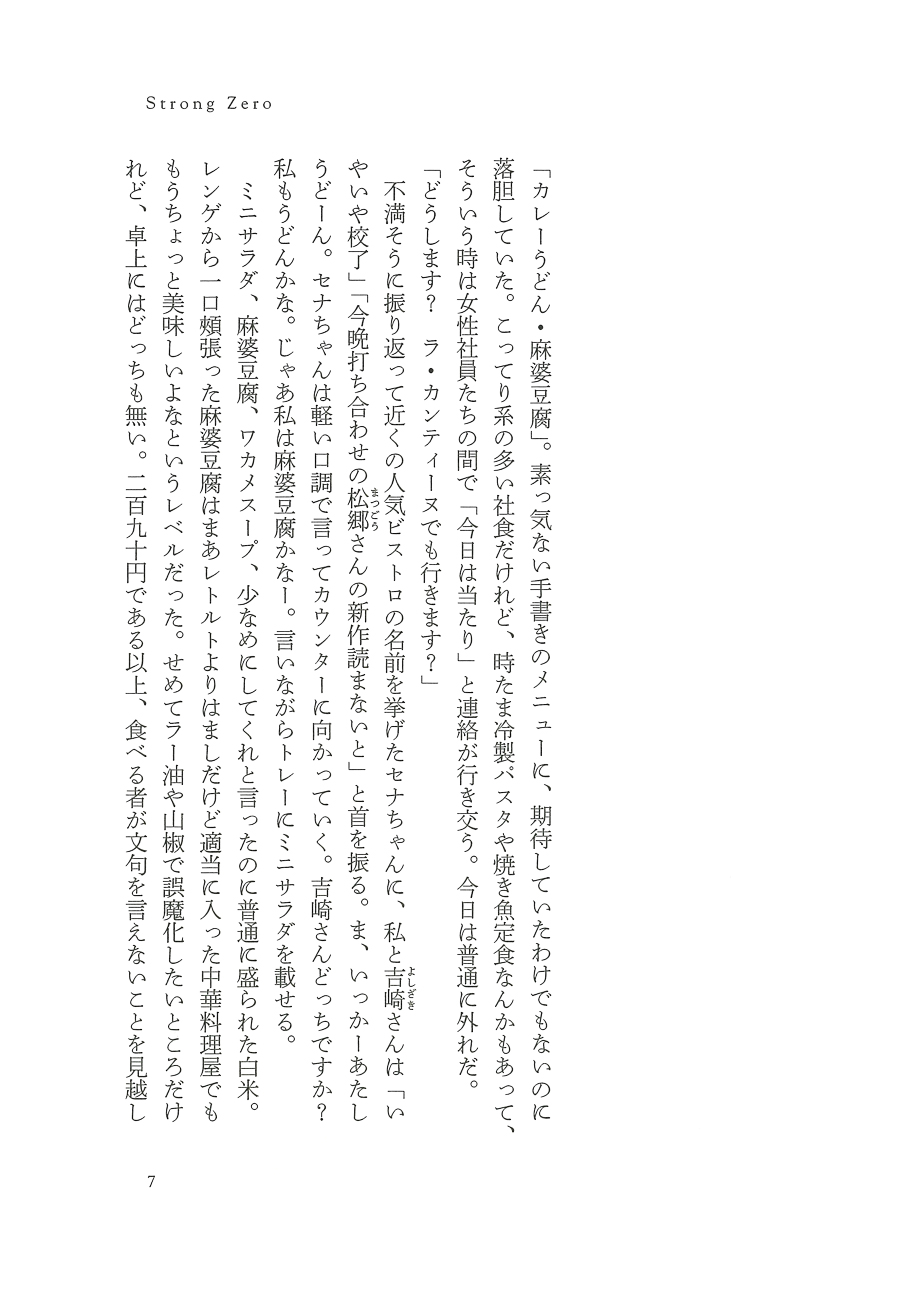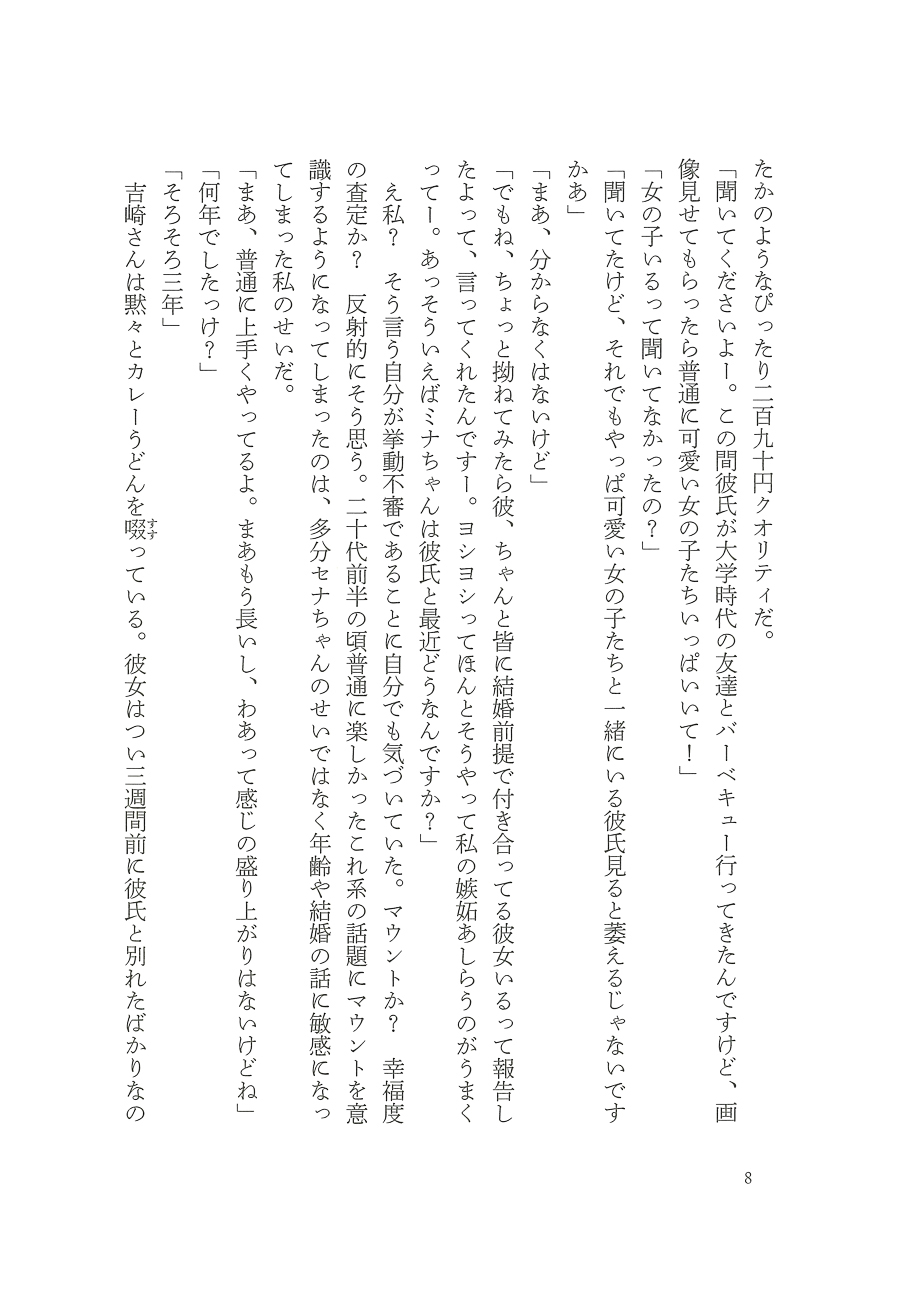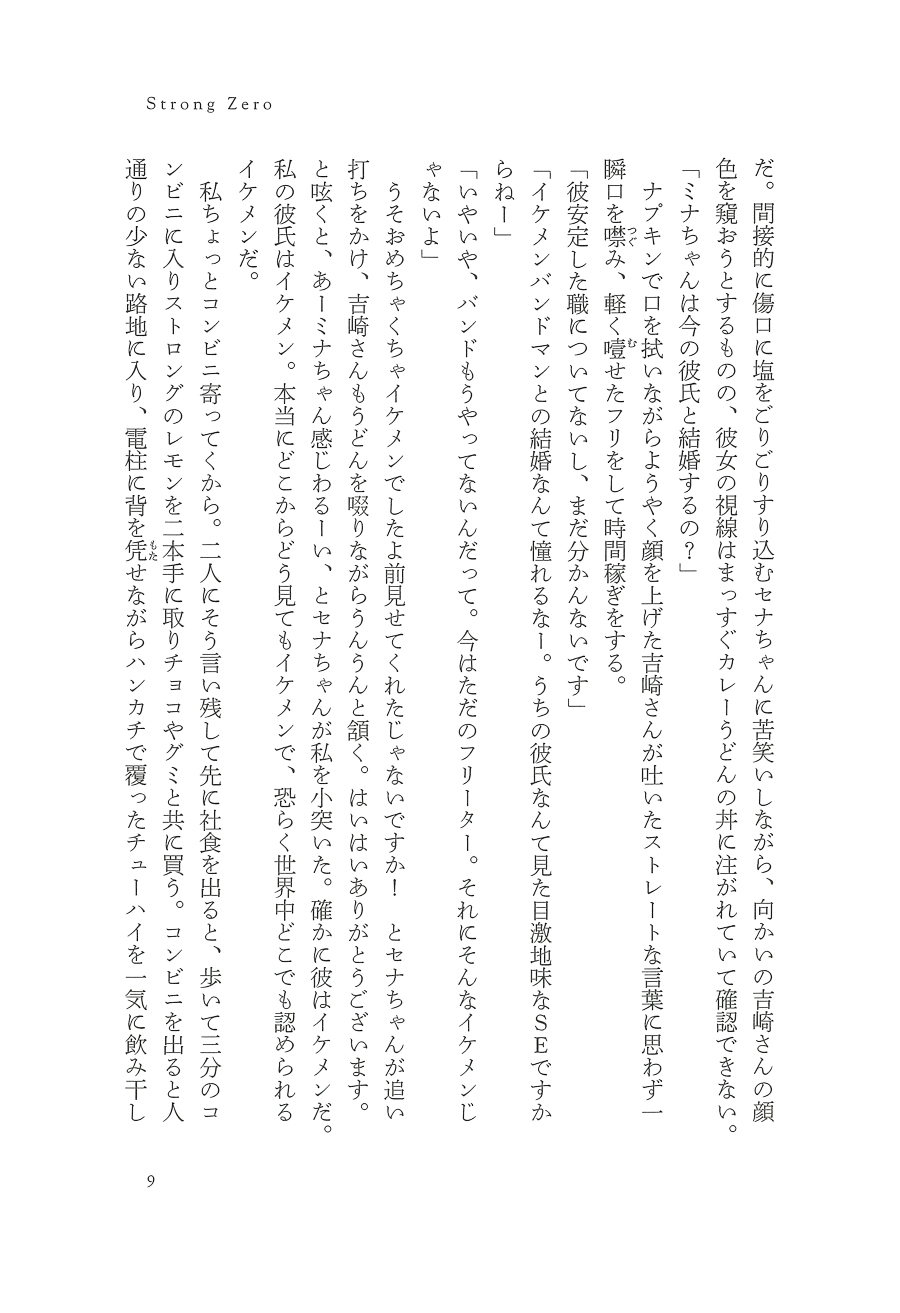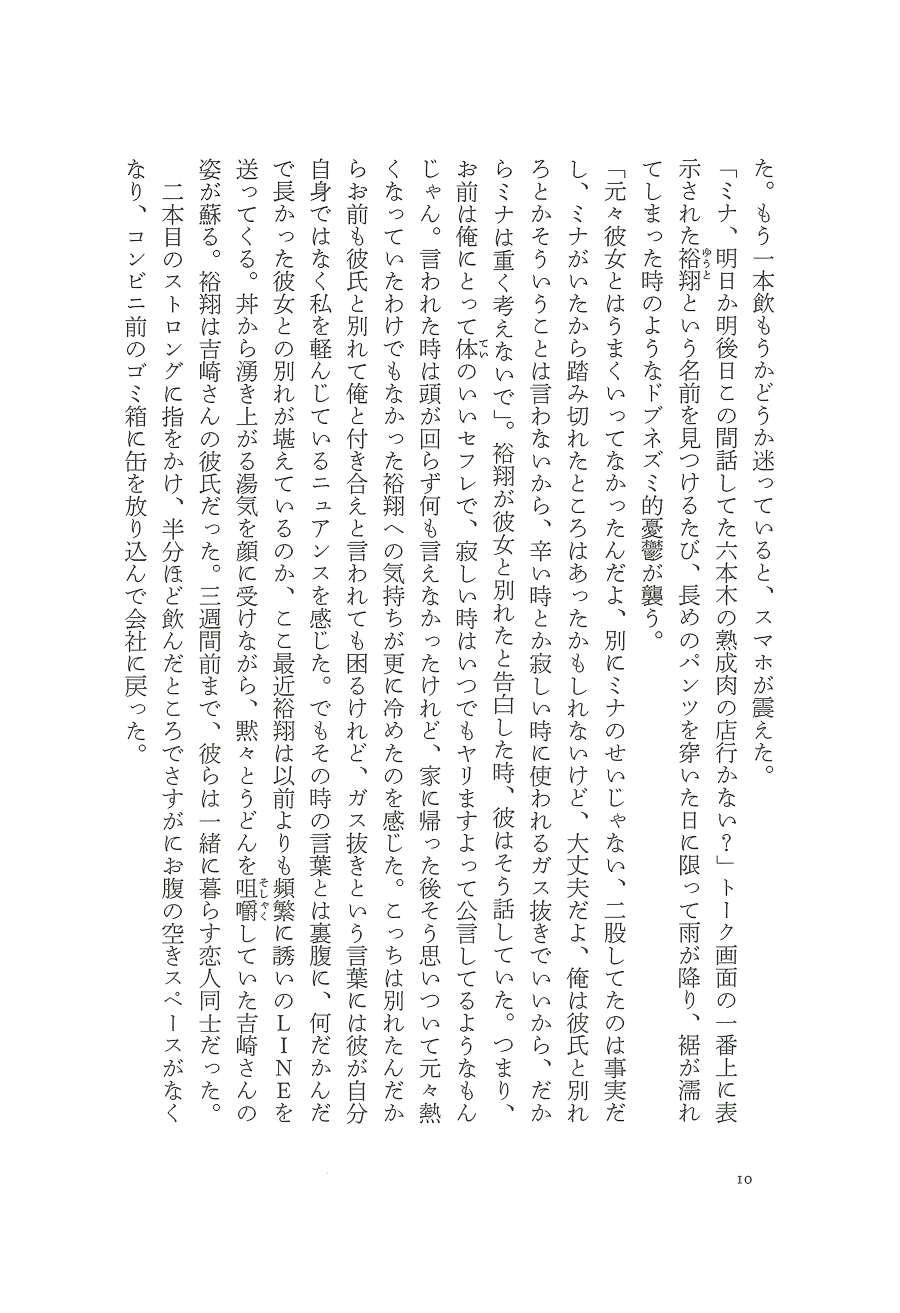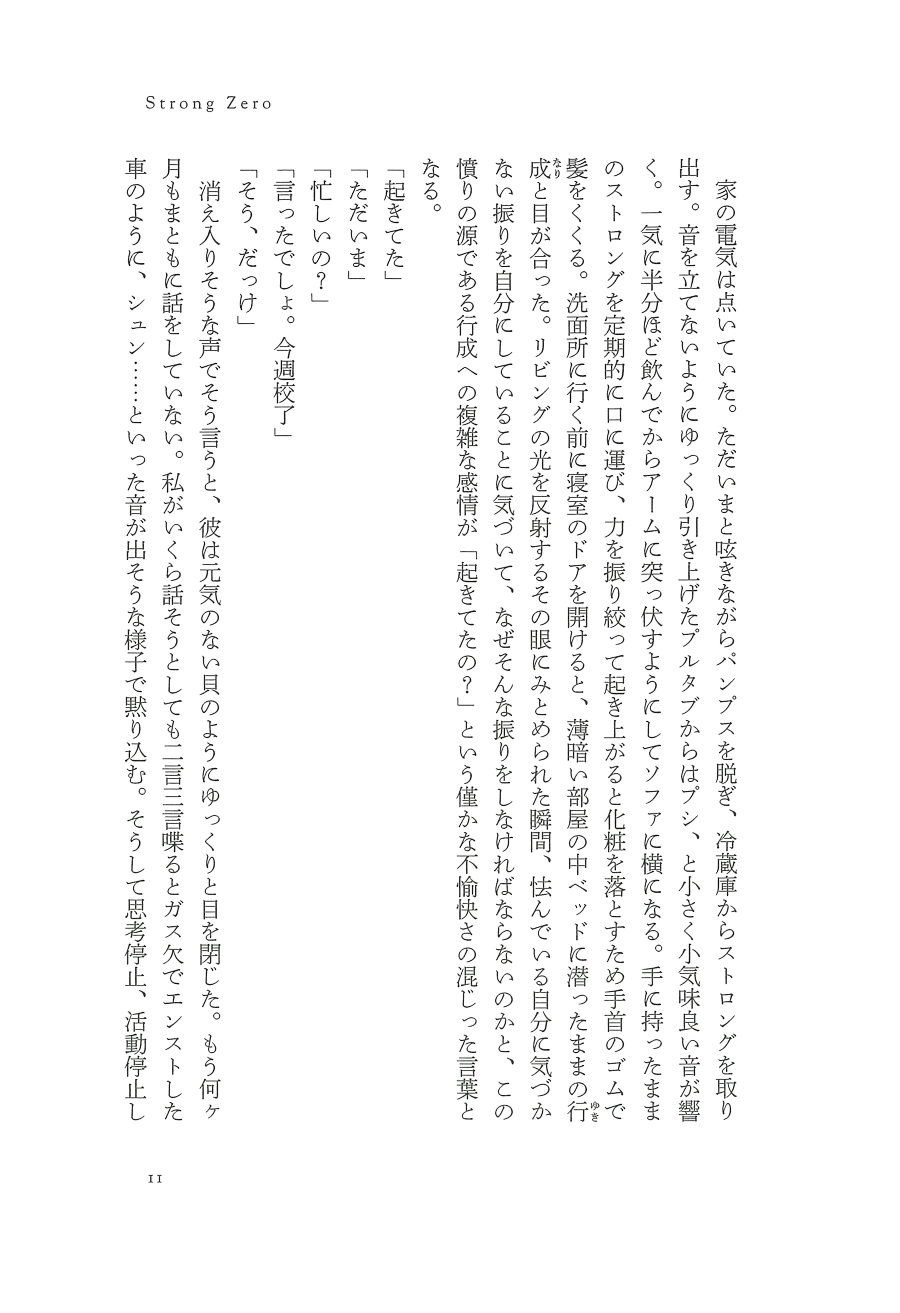ストロングゼロ
Strong Zero
「カレーうどん・麻婆豆腐」。素っ気ない手書きのメニューに、期待していたわけでもないのに落胆していた。こってり系の多い社食だけれど、時たま冷製パスタや焼き魚定食なんかもあって、そういう時は女性社員たちの間で「今日は当たり」と連絡が行き交う。今日は普通に外れだ。
「どうします? ラ・カンティーヌでも行きます?」
不満そうに振り返って近くの人気ビストロの名前を挙げたセナちゃんに、私と吉崎さんは「いやいや校了」「今晩打ち合わせの松郷さんの新作読まないと」と首を振る。ま、いっかーあたしうどーん。セナちゃんは軽い口調で言ってカウンターに向かっていく。吉崎さんどっちですか? 私もうどんかな。じゃあ私は麻婆豆腐かなー。言いながらトレーにミニサラダを載せる。
ミニサラダ、麻婆豆腐、ワカメスープ、少なめにしてくれと言ったのに普通に盛られた白米。レンゲから一口頬張った麻婆豆腐はまあレトルトよりはましだけど適当に入った中華料理屋でももうちょっと美味しいよなというレベルだった。せめてラー油や山椒で誤魔化したいところだけれど、卓上にはどっちも無い。二百九十円である以上、食べる者が文句を言えないことを見越したかのようなぴったり二百九十円クオリティだ。
「聞いてくださいよー。この間彼氏が大学時代の友達とバーベキュー行ってきたんですけど、画像見せてもらったら普通に可愛い女の子たちいっぱいいて!」
「女の子いるって聞いてなかったの?」
「聞いてたけど、それでもやっぱ可愛い女の子たちと一緒にいる彼氏見ると萎えるじゃないですかあ」
「まあ、分からなくはないけど」
「でもね、ちょっと拗ねてみたら彼、ちゃんと皆に結婚前提で付き合ってる彼女いるって報告したよって、言ってくれたんですー。ヨシヨシってほんとそうやって私の嫉妬あしらうのがうまくってー。あっそういえばミナちゃんは彼氏と最近どうなんですか?」
え私? そう言う自分が挙動不審であることに自分でも気づいていた。マウントか? 幸福度の査定か? 反射的にそう思う。二十代前半の頃普通に楽しかったこれ系の話題にマウントを意識するようになってしまったのは、多分セナちゃんのせいではなく年齢や結婚の話に敏感になってしまった私のせいだ。
「まあ、普通に上手くやってるよ。まあもう長いし、わあって感じの盛り上がりはないけどね」
「何年でしたっけ?」
「そろそろ三年」
吉崎さんは黙々とカレーうどんを啜っている。彼女はつい三週間前に彼氏と別れたばかりなのだ。間接的に傷口に塩をごりごりすり込むセナちゃんに苦笑いしながら、向かいの吉崎さんの顔色を窺おうとするものの、彼女の視線はまっすぐカレーうどんの丼に注がれていて確認できない。
「ミナちゃんは今の彼氏と結婚するの?」
ナプキンで口を拭いながらようやく顔を上げた吉崎さんが吐いたストレートな言葉に思わず一瞬口を噤み、軽く噎せたフリをして時間稼ぎをする。
「彼安定した職についてないし、まだ分かんないです」
「イケメンバンドマンとの結婚なんて憧れるなー。うちの彼氏なんて見た目激地味なSEですからねー」
「いやいや、バンドもうやってないんだって。今はただのフリーター。それにそんなイケメンじゃないよ」
うそおめちゃくちゃイケメンでしたよ前見せてくれたじゃないですか! とセナちゃんが追い打ちをかけ、吉崎さんもうどんを啜りながらうんうんと頷く。はいはいありがとうございます。と呟くと、あーミナちゃん感じわるーい、とセナちゃんが私を小突いた。確かに彼はイケメンだ。私の彼氏はイケメン。本当にどこからどう見てもイケメンで、恐らく世界中どこでも認められるイケメンだ。
私ちょっとコンビニ寄ってくから。二人にそう言い残して先に社食を出ると、歩いて三分のコンビニに入りストロングのレモンを二本手に取りチョコやグミと共に買う。コンビニを出ると人通りの少ない路地に入り、電柱に背を凭せながらハンカチで覆ったチューハイを一気に飲み干した。もう一本飲もうかどうか迷っていると、スマホが震えた。
「ミナ、明日か明後日この間話してた六本木の熟成肉の店行かない?」トーク画面の一番上に表示された裕翔という名前を見つけるたび、長めのパンツを穿いた日に限って雨が降り、裾が濡れてしまった時のようなドブネズミ的憂鬱が襲う。
「元々彼女とはうまくいってなかったんだよ、別にミナのせいじゃない、二股してたのは事実だし、ミナがいたから踏み切れたところはあったかもしれないけど、大丈夫だよ、俺は彼氏と別れろとかそういうことは言わないから、辛い時とか寂しい時に使われるガス抜きでいいから、だからミナは重く考えないで」。裕翔が彼女と別れたと告白した時、彼はそう話していた。つまり、お前は俺にとって体のいいセフレで、寂しい時はいつでもヤリますよって公言してるようなもんじゃん。言われた時は頭が回らず何も言えなかったけれど、家に帰った後そう思いついて元々熱くなっていたわけでもなかった裕翔への気持ちが更に冷めたのを感じた。こっちは別れたんだからお前も彼氏と別れて俺と付き合えと言われても困るけれど、ガス抜きという言葉には彼が自分自身ではなく私を軽んじているニュアンスを感じた。でもその時の言葉とは裏腹に、何だかんだで長かった彼女との別れが堪えているのか、ここ最近裕翔は以前よりも頻繁に誘いのLINEを送ってくる。丼から湧き上がる湯気を顔に受けながら、黙々とうどんを咀嚼していた吉崎さんの姿が蘇る。裕翔は吉崎さんの彼氏だった。三週間前まで、彼らは一緒に暮らす恋人同士だった。
二本目のストロングに指をかけ、半分ほど飲んだところでさすがにお腹の空きスペースがなくなり、コンビニ前のゴミ箱に缶を放り込んで会社に戻った。
家の電気は点いていた。ただいまと呟きながらパンプスを脱ぎ、冷蔵庫からストロングを取り出す。音を立てないようにゆっくり引き上げたプルタブからはプシ、と小さく小気味良い音が響く。一気に半分ほど飲んでからアームに突っ伏すようにしてソファに横になる。手に持ったままのストロングを定期的に口に運び、力を振り絞って起き上がると化粧を落とすため手首のゴムで髪をくくる。洗面所に行く前に寝室のドアを開けると、薄暗い部屋の中ベッドに潜ったままの行成と目が合った。リビングの光を反射するその眼にみとめられた瞬間、怯んでいる自分に気づかない振りを自分にしていることに気づいて、なぜそんな振りをしなければならないのかと、この憤りの源である行成への複雑な感情が「起きてたの?」という僅かな不愉快さの混じった言葉となる。
「起きてた」
「ただいま」
「忙しいの?」
「言ったでしょ。今週校了」
「そう、だっけ」
消え入りそうな声でそう言うと、彼は元気のない貝のようにゆっくりと目を閉じた。もう何ヶ月もまともに話をしていない。私がいくら話そうとしても二言三言喋るとガス欠でエンストした車のように、シュン……といった音が出そうな様子で黙り込む。そうして思考停止、活動停止した彼を見ているのが辛くて、何でこんなことにという行き場のない思いが募ってこのままでは行成に当たってしまいそうな気がして口を噤む。
付き合い始めて二年は天にも昇るような気持ちで毎日を過ごしていた。仕事が忙しかろうが彼の稼ぎが少なかろうが、家に帰れば超イケメンな彼が待っていて、ご飯一緒に作る? 何か食べに行く? それとも出前でも取ろうか、と話し合い、二人でお風呂に入り、夜には彼がギターを弾いて歌を歌ってくれたり、たまに奮発して買ったいいワインを飲んだり、映画や旅行番組を見たり、会社の近くに美味しいラーメン屋さんがあってねとか、今度霜降り牛食べに行こうとか話して、どんなに忙しくても疲れていても、彼の隣で眠るだけで、睡眠時間三時間でも肌や爪や髪がボロボロでも、全てがリセットされるように力がみなぎった。
狂い始めたのは一年前だった。バンド活動をしながら他社のファッション編集部で雑用のバイトをしていた彼が、新しく配属された女性編集長に気に入られ、ランチに誘われたり私的な話を一方的に聞かされた挙句、彼女いるんでとフライング気味に拒絶反応を示した時から彼女に嫌がらせを受けるようになり、彼は次第にバイトを休むようになっていった。家でも生気がなく、スマホでストラテジーゲームばかりやり、欠勤の連絡さえ怠るようになった頃、彼にそのバイトを紹介してくれた音楽関係の友人からもう来なくていいと伝えてくれという連絡が私にきた。いつもスマホでゲームをしていた彼が連絡を受けられなかったはずはないのだけれど、何度電話しても出ないとのことだった。心配ではあったけれど、私も当時新書編集部に配属されたばかりで余裕がなく、バイトのことくらい自分でどうにかしてよという苛立ちがあったのも事実だった。
バイトの解雇通知を知ると、彼は一時的に元気を取り戻した。派遣登録をして、短期でアパレルの販売員をしてみたり、日雇いで肉体労働をしてみたり、心配かけてごめんねと私を気遣う言葉を口にしたりもした。でもそれから一ヶ月ほど経ったある日、行成はまたおかしくなった。バンドメンバーと明け方まで飲んで帰宅した時だった。確か休日で、私は原稿を読んでいた。昼を過ぎてもベッドから出てこない彼に、何か食べる? と寝室を覗いて言うと、ベッドの中に彼の見開かれた目を見つけた。
「どうしよう」
「なに? どうかした?」
「怖いんだ」
訝りながらベッドに腰掛けて彼の手を握ると、震えていた。
「昨日、何かあったの?」
「何も。皆で楽しく飲んでた」
「何が怖いの?」
「分からない。ずっとおかしいんだ。頭の中がぐるぐるして、次々に恐ろしい映像とか、不安が湧き上がってくる」
パニック障害、自律神経失調症、真っ先に二つの病名が浮かんだ。二日酔いの時に憂鬱な思考に襲われるのは、誰にでもあることだ。大丈夫冷静になれと自分に言い聞かせながら、「どうしよう」と「怖い」を繰り返す彼に、私も動揺していた。イケメンでファッションセンスも良くてバンドをやっていてコミュニケーション能力の高かったはずの彼が、その時突然赤子のように見えた。
「俺おかしくなったのかな」
出版社に勤めていると、精神がもたついている人によく出会う。自分だって、取り立てて精神が安定している人間ではない。それでも、抽象的な考え方や議論をしない純度の高いリア充だと思っていた彼が突然不穏なものに囚われてしまったことに、動揺していた。
「大丈夫だよユキ、大丈夫。まだお酒が残ってるのかもしれないし、しばらく経っても変わらなかったら病院行こう。もうちょっと様子見よう」
布団に潜ったままの彼の背中を撫でながら、私は喪失感に苛まれていた。私の好きだった彼が少しずつ壊れ始めている。振られたわけでもない、浮気されたわけでもないのに、裏切られたような気持ちになっている自分に、裏切られたような気がしていた。
人は変わっていくものだ。人に絶対なんてない。全ての人が明日ドブに落ちて死ぬかもしれないし、明日交通事故に遭って顔面や四肢が崩壊するかもしれないし、明日原因不明の難病を発症するかもしれない。人は偶然性によってのみ存在し続け、偶然性によってのみ死ぬ。必然的に人が存在することも存在しなくなることもあり得ないのだ。彼が変わってしまったのも必然ではなく偶然で、むしろ偶然性を前提に考えれば彼は変わってなどいないとも言える。人は毎日、毎時毎分クジを引き続けているようなもので、引いたクジが交通事故死であったり、世界滅亡であったり、空からカエルが降ってくるであったり、彼が突然怖がるであったりすることに何ら訝る理由などないのだ。考えれば考えるほど、彼への憤りが緩和していくだろうと思ったけれど、偶然性が支配する世界について考えれば考えるほど、視界がひん曲がっていくような吐き気がした。
発作はその日中に治ったけれど、その日以降彼は明らかな鬱状態に突入した。みるみる生気をなくし、ベッドにいる時間が日増しに長くなった。不眠も進行し、二時間ベッドに潜って、ようやく寝付いたと思ったら一時間で起き、また二時間かけて寝たと思ったらまた一時間で目覚め、といった具合で、細切れ睡眠しかできないようだった。睡眠薬だけでももらいに行こうと病院に連れて行き抗鬱剤と睡眠導入剤を処方してもらったけれど、それから二ヶ月もするとどうしても外に出れない日が続き、病院に行くことも止めてしまった。それでも眠れる薬が欲しいと言う彼のために私が別のメンタルクリニックに行き、彼の症状をそっくりそのまま虚偽申告し、抗鬱剤と睡眠導入剤をもらってきた。
私の酒量が増え始めたのはその頃だった。仕事のストレスもあるし、ほとんど外に出れなくなってしまった彼を支える重圧もあるのだろうと、私はアル中という言葉が常に頭のどこかに存在しているのを感じながら、見て見ぬ振りをし続けた。酒に酔って少しずつあらゆる感覚が麻痺し、理性と冷静さを欠いていく自分を自覚しながら、それでもそれ以外の道を選ぶことはできなかった。
朝起きてまずストロングを飲み干す。化粧をしながら二本目のストロングを嗜む。通勤中は爆音で音楽を聴きながらパズルゲームをやり、会社に着くとすぐにメールや電話の連絡作業をこなす。昼はコンビニで済ませてしまうか、セナちゃんや他の同僚と社食や外食に行き、食事中あるいは戻る前にビールかストロングを飲む、午後は基本的には原稿かゲラを読み、夜遅くなる時はファミレスや中華料理屋で夕飯がてら、あるいはコンビニの前で酒を飲み、帰宅の電車やタクシー内でもパズルゲームをやり、帰宅後一分以内にストロングを開け意識が混濁するまで飲んでからベッドに入るかソファでそのまま寝付く。最近は最寄駅に着いた瞬間耐えきれずコンビニで買ったストロングを飲みながら帰宅することが増えた。最初はストロング一本だった寝酒が二本になり、三本になり、次第に二杯目からは焼酎やワインに切り替えるようになり、一人で出入りするようになったバーでウィスキーに手を出しその味を覚えてからはウィスキーも家に常備するようになった。この生活の中で、私がシラフでいる時間はほとんどなく、睡眠時間以外でお酒を飲んでいないのは会社にいる時間と移動時間だけと言っても過言ではなかった。
以前は、担当している本のことが常に頭の中にあった。寝ても覚めてもずっとそのテーマについて考え続け、本や映画、日常生活のあれこれをその視点から眺めていた。でも今、私は考え続けることができない。原稿に集中できるのは原稿を読んでいる時だけで、文章から目を離した瞬間、脳は安物のラクトアイスのように端から溶け始め、酒とパズルゲームしか受け付けなくなってしまう。それこそ、今まで何について考えていたのか次の瞬間忘れている時もあるほどに、文章に触れ合わない私は空っぽだ。そして空っぽなままできるパズルゲームをやり、ライフがなくなってしまうと回復するまでTwitterを延々スクロールする。友達や美容、面白動画、かわいい動物動画、ファッションや恋愛こじらせ系アカウントばかりをフォローしている空っぽなアカウントだけを見る。仕事関係用のアカウントを見ると情報の許容量を超えた脳みそがパンクしてしまうから、そっちはもう二ヶ月以上開いていない。
もうずっと、自分のことを把握できていない。私は今、自分は何をしたいのか、何を求めているのか、何が嫌で何がいいのか、何が好きで何が嫌いなのか、何も分からないままバスタブに浮く髪の毛のように使い古されたお湯の中に意味なくたゆたい、人々に疎ましがられるだけの存在だ。魂の抜けたダッチワイフのように求められるままに応え、少しずつ彼や彼を嫌いになり、それでも求められれば応えたいし何か力になりたいと根拠不明な原動力によって走り回っている。ここのところ本の刊行ペースが早く、行成の不眠のせいで私も受動不眠になっているし、裕翔は週に二度も三度も誘ってくるし、仕事と付き合いの合間合間に行成の薬をもらいに行ったり、外に出れない行成のためにご飯を作りだめしたり、前は行成がやっていてくれた洗濯や掃除も、今では完全に自分一人で担っていた。このままじゃ近いうちに破綻する。もうずっと、そんな漠然とした危機感がある。それでも私は自分がどうしたいのか分からない。行成を捨てたい訳ではない、行成と別れて裕翔と付き合いたい訳ではない、二股を継続したい訳でもない、どうしてもお酒が飲みたい訳ではない、仕事が嫌な訳ではない、安定が欲しい訳ではない、でもバイトもできなくなってしまった行成を介護し養い続けるのも本意ではない。今の私は全て否定形だ。こうだという肯定も、こうしたいという希望も一言も浮かばない。何かあるだろう、何か一つくらいあるだろう。そう考えている途中で私の思考は途切れ気づくと酔っ払っている。考えればきっと分かるんだろうけど、今はストロングを飲んでるから無理。いつも思考のゴールはそこだ。お酒が抜ければ、一度ゆっくりスマホもストロングもないところで自分と向き合って考えれば、自分の望み、今後の展望は見えてくるはず。そう思うけど、そんな機会は今の生活の中では完全に失われていた。
「今日、遅くなるから冷凍のピラフかカレー食べといて。今チンして、この辺に置いとこうか?」
「うん」
「どっちがいい?」
眉間に皺を寄せて、考えることが苦痛そうな行成に「じゃあピラフにするね」と言うと彼は解放されたように皺を解き無表情に戻った。彼にとって、私は自動販売機のような存在なのかもしれない。そして私にとって、行成は鳥かごの中で飼っている鳥のようだ。毎日毎日ご飯を用意され、食べては寝て、起きては食べての繰り返し。家から出ずにフィーディングされ続けた行成は、薬の副作用もあってか明らかに太ったけれど、どうであっても自力で動けない人を飢えさせるわけにはいかないのだ。レンチンすらできない日もある行成のために、帰りが遅くなる時はこうしてレンジで解凍しておいた食材を、ベッドの近くに置いておく。冷めていても彼は気にしない。餌が温かくても冷たくても鳥が文句を言わないように、彼は何の主張もしない。彼の生きている世界に、私はもう存在していない。彼はもう、私の名前を忘れてしまったかのように、私の名前を呼ばない。向き合う時間が減ったな、一年前はその程度に思っていた。今はもう、彼の目が私の姿を捉えているその瞬間にも、彼の中に私が存在していないことがありありと分かる。だから裕翔の会社の主催する出版記念パーティに出席していた時、以前外で吉崎さんと一緒にいるところに出くわしてちらっと挨拶をしただけだったのに、人混みの中で「桝本さんだよね?」と声をかけてきて、「桝本美奈さん」とフルネームを付け足した裕翔と、私は寝たのかもしれない。
「行ってきます」
寝室を出る前に言うと、うん、と小さい声が辛うじて聞き取れた。振り返って、行成を覆う掛け布団をじっと見つめる。分かっている。彼には治療が必要だ。自分でどうにかするなんて、無理なのだ。でも病院に行きたがらない彼を無理に連れて行ったり、入院させたりするのは抵抗がある。現在の精神医学に関しては私自身疑問に思っているところもあるし、精神薬の薬害について調べ始めると、やはり行成の言葉を引用して調子の悪いふりをすればしただけドサドサ薬を処方する精神科医に対して不信感は募る一方だった。
彼を連れて二ヶ所の精神科、ネットの口コミを読み漁って探したカウンセラーにも二ヶ所かかった。どんなに栄養アンプルを刺しても枯れゆく植物のように、彼はどこに行っても回復しなかったどころか、どんどん生きる力を喪失していった。ご両親に現状を伝えた方がいいんじゃないかとさりげなく提案したこともあったけれど、それは止めて、と彼は力を振り絞るように言った。心配をかけたくないのだろうと、あまり触れないようにしてきた。でもそうやって彼を刺激しないように、例えば親や友達の話を避けたり、あれしようこれしようという未来の話を避けたり、社内で聞いた面白い話や下らない話を避けている内、私たちの会話は今日遅くなるかどうか、ご飯をチンするかどうか、そろそろお風呂に入った方がいいんじゃないか、くらいしかなくなってしまった。そしてそんな会話すら、どんどん減少の一途を辿っている。もう十ヶ月以上セックスをしていないし、最後の何回かは彼が途中で萎えて棄権で終わっていた。その頃からキスもしていない。この関係に現存するスキンシップは、発作的なパニックを起こした彼の背中を撫でることと、寝返りの際に期せずして体のどこかが触れることだけだ。
私たちはどこに向かっているのだろう。目的もゴールもなく、楽しいから好きだからという理由で継続していたはずの関係は、今やもう何がそれを成り立たせているのか理解不能なものになってしまった。化粧をしながら飲んでいたストロングの残りを飲み干すと、家を出て鍵を閉めた。この鍵は私が帰宅するまで解錠されることがない。一人で住んでいた頃よりも私は一人で、もっと言えば鬱でアル中だった。
もう一本ストロングを飲んでから出社しようとコンビニに寄って気がついた。冷凍コーナーに並ぶアイスコーヒー用の氷入りカップにストロングを入れれば、会社内でも堂々とお酒が飲める。こんな画期的なアイディアを思いつくなんて、私はすごい。久しぶりに自分を褒められた瞬間だった。氷入りカップとストロングを二本買い、出社したらトイレでストロングを氷カップに移し替え、入りきらない分はトイレで飲み干してしまう。ストローを挿したカップを持ってデスクに戻れば最高の職場が完成する。何飲んでるのと聞かれたらレモネードか炭酸水と言えばいいのだ。一杯目がなくなると、即座にトイレに舞い戻り二本目のストロングをカップに投入した。質が良いのか氷もなかなか溶けない。「完全アル中マニュアル」、というタイトルの新書を誰かに書いてもらうのはどうだろうと思いついて久しぶりに気持ちが盛り上がる。「アル中力」「アル中が一戸建て買ったってよ」「転生アル中」タイトルを考え、お酒好きな著名人を思い浮かべながら企画書の草案を書いていると、向かいの席の真中さんに「販売の三瀬さんからお電話です」と言われ、座り直して受話器を取る。
「お電話代わりました、桝本です」
「三瀬です。桝本さんいい加減にしてくださいよ。何度言ったら送ってくれるんですかカバーのダミー、何日も前からメールしてるんですけど」
「ダミー? あ、すみません遅くなってしまって。すぐにお送りします」
あれ、返信してなかったっけと体中が焦りにひりつきながら平謝りして電話を切る。メールの履歴を見てみると、確かに四日前と昨日メールが来ていた。二通目のメールを見た瞬間、ヤバいと思って慌ててスマホで返信を書き始めた記憶はあるけれど、どうしてそれが送られずに保存フォルダに保存されたままだったのかについての記憶は一切ない。ダミーを三瀬さんに送信すると、私は過去のメールを見返し始めた。他に何か重要な連絡を見落としていないか確認するが、要返信のものには概ね返信してある。でも数日前にも同じようなことがあった。何だったっけ。あれ、何だったっけ。自分の確認不足で起こったはずのミスを思い出せないことに、更に焦りが増していく。そうだ、編集会議の日程を決めるための連絡を忘れていたせいで、皆の予定は出揃ってるのにいつまでも決められないと編集長から催促の連絡がきたんだった。あとそうだ、先週校閲からのメールに返信した時、向こうからの質問事項を完全スルーして今後のスケジュールのことだけ書いてさっさと返信してしまい、「ご返信ありがとうございます。質問事項へのご返答もお待ちしております」と若干卑屈な感じでリマインドされた。思い出せば出すほど恐ろしくなってきて、自分が社会生活をまともに送れていないことを痛感する。桝本さんは連絡が早くて、メールにも即座に返信するから、受信フォルダに常にメールが溜まっていない状態に整理整頓されてるんですよと隣の席の同僚に編集部の飲み会でバラされ、桝本さんは仕事が早くて助かるわと編集長に褒められていた、あの頃の私はもういない。あの健全で明るくて前向きだった彼がいなくなってしまったように、仕事のできる私もいなくなってしまった。
二本目のストロングを飲み終えた頃、久しぶりに人に怒られたという事実に意外に滅入っている自分に気がついた。呆れ半分といった感じで、怒られた内に入らないような言い方ではあった。でも、お前はゴミだ存在する意味がないと否定された気分だった。
やっぱここにして良かったなあ。裕翔は嬉しそうにメニューを見ながら言った。熟成肉の店の予約が取れなかった彼は、食べログのブックマークの中から肉寿司のお店を選んだのだ。あれこれ迷った挙句、肉刺し盛り合わせ、雲丹載せ肉寿司、梅ささみ、お新香盛り合わせ、クリームチーズの酒盗和えを頼んだ。
「校了お疲れ」
文芸編集者である彼もきっと忙しいだろうに、私にかけた言葉は晴れやかだった。文芸編集者にしては屈託がない人で、もっと言えばこんなに屈託がないのに何故文芸にいるのだろうと思わせるタイプだ。カウンター席はやけに近く、落ち着かない。美味しい、とか、ちょっと飲んでみる? などの言葉の拍子に隣の彼と目が合うと、私はどこか困ったまま目を逸らす。恥ずかしいわけではない。私は裕翔の顔が好きではないのだ。
気付いた時には面食いだった。初めて男の人に恋愛感情を抱いた時にはもう面食いだった。顔を妥協して付き合えばすぐに顔が好きでない人と一緒にいることに悶々とし、耐えられなくなって数ヶ月で別れることになった。行成は、そういう意味で特別だった。私は彼の顔が大好きなのだ。裕翔は別段不細工というわけではない。でもどこか雰囲気で誤魔化している系の顔だ。私が好きなのは、行成のように誰がどう見ても格好いいと言う正統派の美形なのだ。自分の顔見てから物を言えと人は思うかもしれない。でも駄目なのだ。自分と釣り合うような男では駄目なのだ。私は自分が心底美しいと思える顔でないとその人のことを心から求めることができない。裕翔に手を伸ばしてしまったのは、行成との関係に抱いている虚しさからであって、そうでなければ私が男として認識できない社内の九十九パーセントの男と同じように、心に僅かな風さえおこさない無害な男の一人に過ぎなかったはずだ。いやむしろ、言ってみれば裕翔も未だ無害な男でしかない。心も乱されなければ恋い焦がれることもなく、セックスをしてもキスをしてもどれだけ多くの面積を触れ合わせても、肌が離れた瞬間にはなんでこの人と触れ合っていたんだろうと思うような男でしかないのだ。それでも向こうが求めてくるから、そして私も気を紛らわしたいから、という軽はずみな敷居越えがあって、そこから惰性で進行し続けてもう半年だ。最初の内は、彼の存在に救われた。くだらない話をして、美味しいもの食べてお酒を飲んで、ホテルで抱き合う。それだけで行成との関係の中で満たされていなかった部分がなあなあに満たされた。でもお互いそれなりに需要が一致していたはずの私たちの関係は、裕翔が吉崎さんと別れてから明らかにバランスが崩れてしまった。
「彼は、相変わらずなの?」
控えめな言葉と、強い視線のアンバランスさに、また目を逸らしてハイボールのグラスをぐっと傾ける。
「うん。通常運転」
「よくやってるな、ミナは。すごいよ」
すごいのだろうか。よく分からない。私は今、自分の行動原理がよく分からないのだ。自分が行成の面倒を見ている意味も、別れないでいる意味も、付き合い続けている意味もよく分かっていないのだ。
「なんか、最近そっちから呼び出してくれないね」
裕翔はやはり軽い口調で言う。硬いカブのお新香をバリバリ頬張りながら眉間に皺が寄る。少し前までは定期的に自分から呼び出していたということだろうか。この数ヶ月、自分から裕翔を呼び出した記憶が、全く蘇らない。こっちから呼び出してたっけ? とは聞けず「そう、かなあ」ともごもご疑問形で言うけれど、裕翔は「忙しかったんだろうし、もちろん構わないんだけど」と恐らくこちらに気を遣わせないように微笑んだ。LINEの履歴があれば見返すところだけれど、行成に見られたらという不安から裕翔とのトークは全て消去している。実際には行成は、私が外でどんな仕事や人付き合いをしているかなど、もう異世界の出来事のように感じているのだろうから、トークを見たところで何とも思わないのかもしれない。と言うより、ベッドに潜りっぱなしの行成が私のお風呂中や睡眠中にいそいそとスマホを覗き見するとも思えない。彼が闘っているのは全く別の次元のもので、彼はもう私との関係に煩わされることはない。そう思いながらも敢えて消去している私は、自分はまだ行成と恋人同士であるという既成事実に縋りたいだけなのかもしれない。それでももう、行成との関係も裕翔との関係も、断ち切ることなど永遠にできない気がする。裕翔と関係を持って半年、求められるままに主体的な意思がないままここまできてしまった。
肉巻き雲丹の軍艦に醤油をつけて頬張る。雲丹と醤油の味が強く、ほとんど肉の味がしない。肉から滲み出るのは、脂の匂いばかりだった。行成は主役の雲丹、裕翔は味付けの醤油、私はこの味気のない肉。主役の恋人と見せかけた、映えるから海苔の代わりにやってみようという浅はかな思いつきで薄くスライスされた安い肉だ。やってみたらやっぱ海苔の方がよくね? と思われる代替可能が過ぎる罪深き薄い肉だ。
「ミナはさ、このままでいいの?」
いいと思ってるわけがない。でももうどうしたら良いのか分からない。そしてどうしたら良いのか分からないのは、あなたとの関係も同じだ。か弱そうな若い女性店員が危なっかしく一升瓶からぐい飲みに注いだ、庭のうぐいす、という初めての日本酒をぐっと飲み込み、その水のような飲みやすさに「うん」と納得の声が溢れる。
「本当に?」
このままでいいの? の答えだと思われてしまったことを悟り、慌てて「あ、ううん。何ていうか、今はまだ答えを出せないと思ってる」と正直な言葉を口にする。言いながら、既視感に気づく。今は答えを出せないと私が言い、それに対して裕翔の反応を窺うこの瞬間へのデジャヴュだ。きっと前にも同じようなやり取りがあったに違いない。何かフォローをした方が良いだろうかと思った瞬間、そっか、と裕翔は表情を柔らかくした。
「ミナに無理やり別れを迫る気はないんだ。でも、俺たちのこともきちんと考えて欲しいからさ」
何でそんな話になるんだろう。別に俺はガス抜きに使ってもらって構わないという話ではなかっただろうか。しかしその記憶にもどこか自信がない。自分が記憶を改竄している可能性を否定できない。あるいは何かしら、あの彼らの別れの日以降裕翔からきちんと付き合いたい的なアプローチがあったけれど私が完全に忘れているという可能性は。寝不足疲労飲みすぎが限界に達している今、その可能性も確実には否定できない。
私別にこの人のこと好きじゃないんだよな。カウンターの下で手を握ってきた裕翔の手を握り返しながら思う。でも行成のことも、今はそこまで好きじゃないことにも同時に気づく。男と笑い合って手を握り合いながら、ただ虚しかった。
これまでずっとホテルに泊まってきたのに、何故か裕翔は俺の家においでよと言って譲らず、別にホテル代払ってもいいよ? とまで言うと「そういうことじゃなくて、ミナに俺のことを知ってもらいたいんだよ」とどうしてここまで言わせられなきゃいけないのかという羞恥を滲ませて彼は言った。この人は、私が思っているよりもナイーブな人なのかもしれない。そう思った直後、どうして好きでもないナイーブな男と寝るためにホテル代を出すと申告するなんていう珍妙な状況に陥っているのだろうと一瞬笑ってしまうが、大量に飲んだ日本酒のせいで、まあたまにはそんなこともあるかと思い直す。
自分のことを知ってもらいたいという言葉とは裏腹に、私にとって裕翔の部屋はこの間まで吉崎さんと住んでいた部屋であって、細かな吉崎さんの痕跡を見つけては、こんな家に連れて来て俺のことを知ってもらおうだなんて、本気だとしたらこいつはお花畑だなという感想しか出てこなかった。やっぱりホテル代をケチりたかったんじゃないか? そう思いながら、近くのコンビニで買ってきたストロングを勢い良く飲み込む。残りのビールやストロングを冷蔵庫に入れると、中にたくさんの調味料があるのを見て、やっぱり吉崎さんの影を感じる。そういえば、結構前だけれど、自炊にハマっていると彼女が話していたことがあった。
でも私は裕翔を拒まない。初めて裕翔のベッドに横たわって広がった緊張は、匂いやシーツの感触、まだ未知数のそこに落ちているであろう埃や髪の毛や彼の皮膚片が許容レベルか、ダサい毛布やタオルケットを使っていないだろうかという不安、あらゆるものへの懸念が解消されていくにつれて水位を下げていく。
裕翔のセックスは普通で、居酒屋のホッケ一夜干しみたいだなと騎乗位に体位を変えて動きながら思う。取り立てて味が濃いわけでも、旨みがあるわけでもなくて、淡白だけど量はあって、居酒屋に行けば三回に一回くらい頼んでしまうし、頼めばまあそれなりの満足感がある。裕翔のセックスは長くて、声を上げながら薄目でさっきまで飲んでいたストロングを探している自分に気づく。集中しようと思えば思うほど、気持ちはストロングに向かっていく。彼がゴムの中に射精した時、「これで飲める」と思っている自分に気づき、この人とのセックスの意味がどこにあるのだろうと心底不思議に思う。
「歯磨きする?」
「あ、さっき買えば良かった」
「ストックあるよ。使う?」
うん使う、と答えながら、きっとその歯ブラシのストックは吉崎さんが買ったものなのだろうと想像する。罪悪感がないわけではない。それに、同僚の男を寝取ったということがどこかからばれ、噂が立つことへの懸念もあった。それでもこの人と別れられる気はしない。何一つ、私の意志で何かを動かすことは不可能な気がするのだ。この無力感は、行成が一向に回復する兆しを見せないままどんどん鬱を悪化させていった経緯の中で、強固なピラミッドのようなものへと進化し、私の心の真ん中に鎮座している。
歯磨きをした後、二本目のストロングを開けると裕翔に笑われた。
「まだ飲むの?」
うん、もうちょっと、と言いながらストロングを持ってベッドに入る。吉崎さんはいつもどっち側で寝ていたのだろうと思いながら、缶を置くためチェストのある側に横になる。裕翔はベッドに入ると私を抱きしめ、何度も髪の毛を撫でながら、今の生活に感じている空疎、こうして二人の時間を持っても私が彼と住む家に帰っていくことの虚しさ、彼女と別れたのも気持ちが私にあったからだということを一方的に話した。もちろん無理強いはしない、口癖のように最後に必ずそう言う裕翔。でも毎晩こうして眠れたらって思ってる。僅かばかりの母性がくすぐられ、私は裕翔の頭を撫でる。だから駄目なんだ。モラルも博愛も、慈愛も持っていないくせに、こうして求められると断れないし拒めない。そして信念も目的もなく自分から蟻地獄に落ちていく。自己分析しても無駄で、そこにあるのは「なんかちょっと可哀想だったから」とか「なんかちょっと寂しかったから」とか「なんかちょっと酔っ払ってて」とかいうしどろもどろな言い訳だけだ。その言い訳はしかも、本心なのだ。そんな私から、裕翔にかける言葉はない。適当に受け流したり、時間稼ぎをするような言葉しか出てこない。ストロングを一気にぐびぐびと飲む。
「寂しい思いさせてごめん」
そもそも、この人は自分をガス抜きに使ってくれと言っていたはずなのに、毎晩こうして眠りたいなどと言い始めたのは何故なのか、そんなことを言われたらこんな風に思ってもいない言葉を返す他ないじゃないか。大丈夫だよ、と裕翔は優しげに言う。
「ユキのこと」
言いかけて口を噤む。あれ、と思って隣を見ると裕翔が不思議そうな顔をしている。頭がクラクラして、心臓がはちきれそうなほど脈打った。同じ「ゆ」で始まるとはいえ、行成と呼び間違えるなんて、あまりにもだ。
「いや、裕翔のこと、適当な気持ちで考えてるわけじゃないから」
動揺のあまり元々何を言おうと思っていたのか忘れて、何だか不倫男みたいなことを言っている自分に更に動揺する。呼び間違えたことはバレていないのか、それとも気付かない振りをしてくれているのか、裕翔は分かってるよと優しい声で言って腕に力を籠めた。眠くて酔っていて疲れていて、もう限界だった。ストロングを飲み干すと、私はスマホでアラームを設定して目を閉じた。
気を失うようにして眠りについた割には、アラームが鳴る前に目が覚めた。いつもより分厚い掛け布団のせいで寝汗をかいている。まだ四時で外は暗く、アルコールは全く抜けていない。爪で目やにを削りながら体を起こしベッドを出るものの、ふらついて真っ直ぐ歩けず、あちこちに手をかけながら寝室を出てキッチンまで歩き、水道の水を手で掬って飲む。私がお酒を飲みたいと思わないのはこの二日酔いの時だけで、強烈に具合が悪くてもお酒を飲みたいと思わない時間は私にとってそれなりのオアシスとなるのだけれど、オアシスと吐き気がイコールで結ばれてしまうのはそれなりに最低なことでもある。
寝室に戻って服を身につけていると、リビングのソファに置いていたスマホからアラームが聞こえてきて慌てて全てのアラームを解除する。寝室を覗いてみるけれど、布団に動きはない。裕翔を起こしたくなかった。今ここで、じゃあねとかまたLINEするねとかのやり取りをする気力がなかった。アプリから現在地にタクシーを手配すると、到着まで六分と出た。さっさと出てしまおうと、上着を羽織ってスマホをバッグに突っ込む。裕翔が起きてきたら面倒だ。足早にリビングを出て玄関まで来たところで、奇妙なデジャヴュに陥る。この玄関を見たことがある。これは、まだ行成と一緒に住む前、行成が住んでいたアパートの玄関だ。
「ん?」
声となって溢れた疑問に、逆に慌てる。あれ? と言いながら私はリビングに引き返し、寝室のドアをゆっくりと押し開ける。寝室には小さなランプしか点いておらず、布団に顔を埋めた裕翔の顔は確認できない。私は今、さっきまで一緒にいたのが裕翔なのか行成なのか確認しようとしている。そのことに気づいた瞬間、思わず笑ってしまう。やばいな、と一言脳内で零した瞬間、ピコンとバッグの中でスマホが鳴った。取り出すと、間もなくタクシーが到着します、という通知が届いていた。布団から僅かに覗く指にスマホを近づけその光で確認する。白い部分が二ミリほどで丸く整えられた綺麗な指だ。当然行成の指ではない。彼はギターをやっていた名残でいつも見ていて痛くなるほど深爪をするのだ。息を大きく吐くと、私はまた玄関に向かった。
確かに玄関は行成の前住んでいた部屋に似ていた。でも、似ていただけでよく見れば靴棚の色も違うし、鍵の形状も違う。静かにドアを閉め、マンションを出ると、すぐ目の前に停まっていたタクシーに乗り込み、自宅近くの交差点の名前を告げた。
お客さん? そろそろ着きますけど? はっとして目を覚ますとタクシーの中で、訳が分からなくなる。裕翔とのデートに向かっているところ、いや、自宅に向かっているところだろうか。外の雰囲気的に、会食に向かう時間帯ではなさそうだ。「あの、ここって」と言いかけた瞬間、見覚えのある交差点が目に入って「自宅だ」と気づく。
「あ、すみません、ここでいいです」
アプリで決済をすると、タクシーを降りて交差点の角にあるコンビニに入った。ストロングを五本とハイボールを三本、あたりめとチーカマを入れてふらつきながらレジに向かっている途中、まるでアルコールを求めて徘徊するゾンビみたいだと思いついて鼻で笑う。
でもゾンビとは言い得て妙だ。正常な思考が働いておらず、酒と男と仕事だけで一日が過ぎていく。常に上の空で仕事をしているから、来月刊行の新刊も改めてどんな内容かプレゼンしろと言われたらしどろもどろになりそうだ。私は完全に、全ての本性を見失っている。コンビニからマンションまでの道のりで、自転車に二人乗りしているヤンキーっぽい若者のカップルを見つける。信号待ちしている彼らの隣で立ち止まり、彼らをじっと見つめる。「だからあ、イッチーとオソロがいいのー」「やだよ恥ずかしいじゃん有りえないよオソロとか」「何でそんなこと言うの? 信じらんない」「だって、え、じゃあイロチにしてよせめてさ」「やだよ私も黒が一番かっこいいって思うもん」。天に昇りそうなほど楽しそうな会話をしている彼らを見て、「どうして私はこの世界を喪失したのだろう」という疑問に眩暈がする。私もユキとこうだった。そして、こうであり続ける予定だったのだ。
彼らが青信号を渡って視界から消えてしまっても、私はじっとそこに佇み、その場でストロングを開けて一本飲みきった。一緒にこの道を歩いていた行成の穏やかな顔が脳裏に蘇る。私は彼の顔が好きだ。それは決定的なことだ。外面への執着は、きっと内面への恐怖の表れで、外面を愛することによってのみ、私は男性の底知れない内面と向き合う覚悟ができる。行成は完璧だったのだ。そして今思えば完璧すぎた。彼の外面と内面のイケメンさを尊んでいた私は、予測すべきだった彼の内面の底知れなさを度外視していたのだ。立ち直ってもらいたい、救いたい、支えたい、そう思うけど以前の彼が立ち直っていて今の彼が立ち直っていないと思う時点で、私は救済者として失格なのだろう。私が予測していなかっただけで、今の彼だって百パーセント彼なのだ。昔の楽しかった頃を思い出してたまに泣くのは、まさに彼の外面が好きな私を象徴した行為だ。今ああして浮き彫りになった彼は、彼の内面そのもので、私はそれを「治したい」と思っているのだから。私の好きな彼は失われた。でも私の好きでない彼もまた彼で、そういうのは好きじゃないの、それだったらいらないの、と振るほどには私は強くなく、彼は彼だからどんな彼でも大丈夫と言えるほどにも私は強くない。ずっと呆然としたまま足を踏み出すことができなかったけれど、顔の周辺に季節外れの蚊の気配を感じて手で払うと、私はゼンマイを巻かれたおもちゃのように機械的に足を踏み出し始めた。
帰宅すると、行成はベッドに入ったままだった。顔も見ないまま隣に横になる。今隣で眠っているのが裕翔でも行成でも構わない。私にとっては二人とも、何も満たしてくれない存在で、そういう意味では彼らはもう遜色ないのだ。
がくんと頭が揺れてハッとする。校了前でもないというのに、日中からデスクで船を漕ぐなんてさすがにひどい。氷カップに注いだストロングをストローで吸い上げると、氷がかなり溶けて味が薄くなりかけていた。しばらく意識が飛んでいたのだろうか。
月曜だというのに、疲れも寝不足も極まっていた。土曜日は夕方から朝まで約十時間大学時代の友達と飲み、昼過ぎに起きて二日酔いのまま原稿を読みつつ、ひどい状態だった部屋を掃除し、無理やり行成をソファに移動させて久しぶりにシーツを洗濯した。枕の染みがひどく、私はまた少し行成を嫌いになる。そのせいで、普段は土日は出ないと伝えていたのに、昔からの友達と飲んでるんだけど良かったら合流しない? と連絡してきた裕翔の飲み会に参加した。神奈川出身の裕翔の地元の友達には、普通に彼女だと紹介された。まだ彼女じゃありません、と笑って否定すると、付き合っちゃいなよと裕翔の友達二人に囃し立てられた。二人とも、普通に顔は良くなかった。一人は裕翔と同レベル、もう一人は更にレベルが低かった。気分は良くなかったけど、そこまで悪くもなかった。でもとにかく寝不足で酔っ払っていて、帰りのタクシーで目覚めた瞬間、やっぱり自分がどこに向かっているのか分からなかった。
足元に目をやるとコンビニ袋が散乱している。社内では捨てられないからとストロングの空き缶を毎回縛って置いておいたら、瞬く間に溜まってしまった。二つずつくらい外に持って出て、コンビニのゴミ箱に捨ててくるか、それともトイレのゴミ箱に捨ててしまうか。社内に張り巡らされた防犯カメラを思い、私が出した結論は「段ボールに詰めて自宅に送る」だった。お昼時の人が少ない時を狙って、袋ごと段ボールに詰め、あまりにも軽いと不審だからもう捨ててもいい何冊かの本を詰め、更にやっぱり缶の音がするから、動かないよういくらか緩衝材も詰めた。伝票と共にバイトの和田くんにこれお願いと渡したら、足元がすっきりしたと同時に、何やってんだろうという気持ちになった。
何やってんだろう。ずっとそれの繰り返しだった。私何やってんだろう。裕翔のこともそうだし、アルコールのこともそうだ。自分がやってきたことのほとんどは「何やってんだろ」と思うことばかりだ。ずっとずっと消去法で生きてきた。こっちは嫌だからこっちかな。そうやって気乗りしないまま二種類の社食を選ぶようにして、生きてきた。それなのに、は? 私何やってんの? ばっかりだ。
「あれ、桝本さん、奥滋さんのトークショー行かないの?」
原稿に赤入れをしている最中、編集長に言われて目を泳がせた後血が沸き立つように全身がカッと熱くなっていく。慌ててスマホで時間を確認すると、15:47だった。四時から開始のトークショーだ。今からタクシーに乗れば開始二十分後くらいには着けるだろうか。
「途中入退場大丈夫なんで、ちょっと遅れてもいいかなって思ってたんです。そろそろ行きますね」
もちろん覚えてますよ風を装って編集長に答えると、彼女は少し戸惑ったような表情を浮かべたけれど、じゃあ奥滋さんによろしくねとにっこり笑った。会社を出ると目の前ですぐにタクシーを拾う。何であんなバレバレの嘘をついてしまったのだろうと数分前の自分を悔やむ。奥滋さんは担当編集者が自分のイベントに出席するのは当然というタイプの人だし、時間に厳しい人だ。開始後に入場したことがバレた時の言い訳を考えながら、トークショー会場である本屋近くで渋滞に嵌って動かなくなったタクシーから降りた。小走りで本屋に向かう途中、駅のロータリーで座り込んでいる男がいて思わず目を取られる。皆素知らぬ顔をして彼の前を通り過ぎている。足を投げ出して植え込みに背を凭せぐったりした様子で半目を開けている彼を見てゾッとする。薬物かもしれない。自分が危害を加えられるのだけは嫌だと足早に通り過ぎようとした時、彼の胸ポケットに何か大きなものが入っているのが見えて目を凝らす。彼の胸ポケットに入っていたのは、私がいつも飲んでいるストロングの缶だった。一瞬彼の顔を凝視した後、足を速めた。私はあの男だ。自分が何をしているのか冷静に考えることもできない、酒を飲んで醜態を晒すあの男と同じだ。
大型書店内のトークショー会場までエスカレーターを駆け上がっている途中、不意に記憶が蘇る。確か先週、母親から連絡があって、家族で入っていたガン保険を継続するかどうか聞かれたはずだった。でも母親とのトーク履歴を見ても、母親と父親とのグループトーク履歴を見ても、メールの履歴を見てもそんな話は一切出てこず、着信履歴にも母の名前はなかった。でも、そう言えば保険なんて入ってたなと思った記憶と、確か二十歳の頃に入った保険だから保険料も安いんだろうし継続かなと思った記憶がある。社会人になって久しいのに親に払い続けてもらうのも申し訳ないから、私の分だけ引き落とし口座を自分の口座に変更するのと、年間の保険料をまとめて振り込むのとどっちが良いか聞こうと考えていたのだ。「あのさ、先週あたり、ガン保険を継続するかどうか私に聞いた?」もしかしたらそんな夢を見ただけだったのかもしれないと思いながら母にそうLINEを入れると、ちょうど奥滋美津子×村松勝トークショー、という看板が見えてきて歩調を緩める。規模の小さいトークショーだけれど、立ち見客もいて何となく人に紛れながら入場し、ずっとそこにいたような顔で会場の一番後ろの辺りにそっと立ち位置を定める。それでも顔見知りの編集者何人かと目が合い、目で挨拶をする。会場の随分前の方で見ている吉崎さんに気付いて、昨日一緒にいた裕翔のことが頭に蘇る。吉崎さんは村松さんの担当で、トークショー終了後に吉崎さんが担当した新刊のサイン会をするらしいから、きっと会場入りから、あるいは村松さんの自宅から付き添っていたのだろう。ここ最近の一連のボケと、奥滋さんたちが話す「ジェンダーと小説」というテーマが酔っ払っているせいか全く頭に入ってこないこと、その会場にいるすべての人が私よりも優秀で意義ある人生を送っているような気がすること、途中で届いたLINEに「先週転送した郵便物の中に、保険のことについて聞くメモを同封したよ」と母親から入っていて、ああそうかと思うもののそのメモに正確に何が書かれていたか全く思い出せないこと、メモがどこにあるのか、捨ててしまったのかさえ定かではないこと、あらゆる事象の数々から、棘のような自責の念と恐怖が襲ってくる。
トークショーが終わり、村松さんのサイン会が始まると、私は奥滋さんに挨拶をするため会場前方に向かった。動悸が激しかった。
「奥滋さん、お疲れ様でした。素晴らしいお話でした」
ああ、桝本さん、来てくれたの。眼光の鋭い奥滋さんには、今の私の体たらくが全て見透かされているような気になる。
「以前ご相談させて頂きました対談集の件、ぜひご検討ください。村松さんと改めて対談して頂くのも良いかもしれないと、今日お話を聞いていて思いました」
「そう? 村松さん、意外とシニシストだったわね」
どこがどうシニシストだったのか思い当たる節はなかったが、とりあえず「確かに、ちょっと意外でしたね」と相槌を打つ。ちょうどその時吉崎さんがやって来て、「教育制度についての話ですよね。小説では結構そういった面がぼかされているので気づかないんですが、本人は割と、まあああいうタイプなんです」とにこやかに言った。
「でも明るいシニシストは嫌いじゃないわ」
「だと思いました。だから今回の件依頼したんです。ああいう立場を取っていても、彼の考える理想は奥滋さんのお考えと大きくずれていないように感じていたので。今回の新刊は奥滋さんの著書を参考文献に挙げていますし、影響されている部分もあると思います」
私が今日こんなに寝不足なのは、昨日私を呼び出したあんたのブサイクな元彼のせいだ。訳のわからない呪詛を頭に思い浮かべながら、控え室にアテンドしていく書店員と奥滋さんの後ろ姿を見送る。
「桝本さん、酒臭いよ」
吉崎さんの言葉に凍りつき、思わず一歩後ずさる。いつもはミナちゃんと呼ぶ吉崎さんは、冷たい目で私を見つめ、村松さんの所に戻って行った。笑顔で書店員やお客さんに対応している吉崎さんをしばらく呆然と見つめた後、私は書店を出てタクシーに乗り、会社近くのファミレスの前で降りた。店内をずんずん歩いて席に着くと、ビールを頼んでバッグから原稿を取り出す。先週の木曜に届いて、これから拝読させて頂きますと連絡をして、まだ五十枚ほどしか読めていない原稿だった。いい加減感想を送らないとまずい。赤ペンを持ったまま原稿と対峙して三十分もすると行成から「お腹空いた」とLINEが入った。いつもはパンやご飯などすぐに食べられる状態にして置いておくのに、今日はすっかり忘れていた。お米も切れていたし、冷蔵庫にもほとんど物が入っていなかったはずだ。
「出前のチラシが入ってるクリアケースにお金が入ってるから、それで出前取るか、買いに行くかしてくれない?」
苛立ちから、突き放すようなLINEを送る。別に、私がUber Eatsや出前館で家に届くように手配しても良いのだけれど、彼が自主的に空腹を満たすために行動してくれるんじゃないかと、期待していた。少しずつでいいから、自分で自分のことをできるようになってもらわないと。そうでなければ私はもう近い内に潰れてしまう。でも彼への希望は、私が自分に対して持てなくなってしまった希望を仮託しているだけなのかもしれなかった。
レモンハイを注文してガリガリと原稿に指摘を書き込んでいく。これ以上誰も自分を煩わせないで欲しかった。しばらくすると、裕翔から「ミナ、昨日結構酔っ払ってたけど大丈夫? 俺は悲惨で午後出社」と情けない顔つきのLINEが入る。文芸と違ってこっちは午後出社できる空気じゃねえんだよと突然全てが許せない気持ちになって裕翔とのトーク履歴を消去する。消した瞬間メールの通知が入って受信ボックスを開くと、吉崎さんから「うちの編集部でも奥滋さんの単行本を検討してるから、内容が被らないよう今度打ち合わせしましょう」と入っていた。吉崎さんは何か勘付いているのだろうか。裕翔から何か聞いたか、或いは最近裕翔と会っているのを誰かに見られて又聞きしたか。この間まで普通にセナちゃんと社食を食べたりしてたのに、どうしていきなりこんな態度になるのだろう。返信をしないまま、再び原稿に視線を落とす。パワハラセクハラのルポルタージュという内容のせいか自分の精神状態のせいかお酒のせいか全く頭に入ってこない。どんなに文字を目でなぞっても一向にそれが意味のある文章として繋がらない。おかしい。おかしいな。訝りながら何度も同じ箇所を読んでいるとゲシュタルト崩壊してしまいもはや文字の意味さえ分からなくなってくる。どうしよう、そう思いながらレモンサワーのナカをお代わりする。ナカを注いだレモンサワーを一気に半分飲むと唐突に今日はもう酔っ払ってるから無理だ、と諦めがつき、赤ペンを放り出す。スマホのパズルゲームを開くと、私は延々ピースとピースをひっくり返し続ける。ハイボールとワイン数杯を経ると、もう夜の十一時を過ぎていて、原稿を読み終えたら一旦会社に戻ろうと思っていたけれどその気も失せていた。こんなところで時間を潰すくらいなら家に帰って眠りたいと思うが、家に帰れば行成がベッドにいる。ソファで寝ても彼がトイレに向かう音で目が覚めるし、大体腰か首を痛める。針山の中の小さなハゲに突っ立っているかの如く、私は疲れ果てても立ち続けなければならない呪いにかかったかのようだった。漫画喫茶にでも寄って一眠りしてから帰ろうか、或いはもうホテルにでも泊まってしまおうか。そう思いかけて、そんなことをして行成はどうなるんだろうと思い直す。でも、本当に私がずっと帰らなかったら行成はどうするんだろう。さすがにあの家で餓死するなんてことにはならないだろう。じゃあ彼はどうやって、誰に助けを求めるのだろう。ベッドとトイレを往復しながら徐々に腐敗していく行成を想像しながら、私はファミレスを出た。何でもない地面を見つめたまま歩き回り、ようやく観念して電車に乗る。
コンビニでストロングを買うことだけを考えながら駅から家に向かっている途中、わき道の奥に見える明かりに気を取られ、思わず足を向ける。何度か入ろうかなと思っては、もう家も近いし帰ろうと思い直して結局一度も入ったことのないバーだった。人が多かったらやめよう、そう思ってドアの小さな窓から中を覗くと、二十席くらいのバーには四人しか客が入っていなかった。
おしぼりをもらうと、ジントニックを注文する。CAFE・BARと書いてあっただけあってカジュアルな雰囲気だった。バーテンは二人いて、店主っぽい人がジントニックをコースターに置いた。手持ち無沙汰になる一人バーの時だけ吸う電子タバコを取り出し、カートリッジを用意する。ジントニックは普通に美味しいけれど少しジンが薄い気がする。二杯目を悩みつつ陳列棚のウィスキーを眺めていると、眼鏡をかけたオタクっぽい見習い風の男の子がウィスキーお好きですか? と声をかけてきた。
「何かおすすめはありますか?」
「フレッシュで飲みやすいものと、スモーキーで重ためのものとどっちがいいですか?」
「スモーキーな方がいいです」
「ボウモアは飲まれたことありますか?」
「ああ、アイラ島のウィスキーですよね」
「ご存知ですか?」
彼が嬉しそうな顔をして言うと、店主が「彼、アイラ島のウィスキーが好きで、今年アイラ島に行ってきたんですよ」と彼を指差して言った。思わず笑って、ウィスキーのために? と聞くと、一人で蒸留所巡りしてきました、と恥ずかしそうに微笑む。彼は私のウィスキーに関する質問に全て軽々と答え、お勧めのウィスキーを何本も出してきてそれぞれ嬉しそうに解説した。ウィスキーオタクだったのかと思いながら、笑顔の幼い彼に少しずつ警戒心が解けていく。もしかしたら年下かもしれない。この間友達とサイゼリヤで十二時間飲んでたんですよというバーテンらしからぬ話に声を上げて笑う。
割れるように頭が痛い。いやむしろ、頭の上でガラスをかち割られたような、いやもっとシンプルに壺で頭を殴られたような痛みだ。はっとして一瞬で上半身を起こす。私は何か交通事故にでも遭ったのだろうか。完全に記憶が欠落していた。右を見て、左を見て、後ろを振り返る。カーテンを通過する明るみ始めた空からの光を受ける男は、どう見てもあのバーテンの彼で、ベッドの脇に置かれた眼鏡はあのバーテンの彼の眼鏡だった。そして感触からして私は完全に裸で、でも触ってみた感じとりあえず中出しはされてなそうだった。ぼさぼさの髪を撫で付けると、事後特有のキューティクルが逆立っているような、ざらざらと指が引っかかる感触があった。一瞬だけ、この家に上がった時の記憶が蘇る。玄関に上がった瞬間キスをしていたはずだ。でもそれ以外、私とこの男との間に起こったことが全く思い出せない。
呆然としたままベッドを出ると、私はのそのそと下着と服を身につけた。ちらっとゴミ箱を見たけれどゴムは見当たらない。それなりの大きさのティッシュボールが入っているから、生で外出しが濃厚か。バッグを見つけ手を伸ばすと、財布の中身を確認する。カードも、現金も多分問題ない。スマホを取り出し、ほっとする。行成からの連絡は入っていない。6:35という時刻にため息をつき急いで帰らなきゃと思った瞬間、別に行成は私の帰宅なんて待ってない、とも思う。私はどうしていつも、毎日毎日行成のいる家に帰るのだろう。完全に力が抜けてバナナの皮のようになったままスマホの画面を見つめる。11月29日。なんか見覚えのある日付だなと思った瞬間、行成の言葉が思い出される。
「今日からミナは俺の彼女ってことでいい?」今日は、付き合い始めた記念日だった。初めて寝た日の朝、行成はそう言った。イケメンはこういうこと余裕で言えるんだなと、彼の顔と性格のイケメンさに感動しながら、うんと満面の笑顔で私は答えたのだ。そして三年後の今日、行成は根を生やした私のベッドに寝ていて、私は名前を知らない男の家で目を覚ました。泣けないのはアルコールのせいで、多分脱水症状だ。緩慢な動作で立ち上がりバッグを手に持つと、立ち上がってコートを羽織る。スチームパンクっぽい家具や置物で構成されたインテリアに、強烈に他者を感じる。ドアを開けて外に出ると、目が眩む。
「二十二だったらいい夫婦の日だったのにね」私の言葉に、行成は「十一月二十九かあ、いいフックの日、でどう?」と答えた。何いいフックって! と笑う私に、こんな感じ、と彼は右腕で鋭いフックをして見せた。あんなに幸せな日はなかった。自分の好きな人が私のことが好きで、彼は私が好きになった男の中でも一番のイケメンだった。
マンションのエントランスを出てマップアプリを開くと、ここは私の家まで十分ほどの所で、行成の寝ているベッドから歩いて十分の所で他の男と寝たのだという事実が判明する。裕翔と浮気を続けておいて今更かと思いながら、目に留まったコンビニに足を止める。
ただいま。呟いた声に返事はない。バッグも下ろさないまま寝室のドアを開ける。ベッドと一体化した行成と目が合う。
「おかえり」
黙ったまま、じっと彼を見つめる。彼の視線は私の手に握られたストロングに移動して、それからすぐに瞼がその目を覆った。
「ご飯、食べた?」
憂鬱に開いた目がまた私を捉え、彼が微かに首を振る。
「ねえユキ、ケーキ食べない?」
コンビニ袋からショートケーキが二つ入ったパックを取り出し、同じ袋からフォークを二本取り出す。怪訝そうな行成に、今日は付き合い始めた記念日なんだよと明るい声を出す。あ、だか、ああ、だか何か短い言葉を漏らした彼の傍に座り込み、パックを開ける。
「すっかり忘れてたんだけどね、ちょうど帰りに寄ったコンビニでこれ見つけてラッキーって思って。コンビニでショートケーキって、意外になくない? ユキ、イチゴ好きでしょ?」
ほら、俺栃木出身じゃん? いつか、イチゴが好きだという話をした後、彼はそう付け足した。そっか、とちおとめってあるもんね、と私は答えて、イチゴが好きな彼を愛おしく見つめていた。こんなに何の変哲もない、別段可愛くもないし大して面白いことも言えない私のことを好きになってくれてありがとう。いつも私のことを大切にしてくれてありがとう。荷物も持ってくれるしおかずは取り分けてくれるし洗い物もしてくれるしいつもいつも私が辛い時にはよく頑張ったねって頭を撫でてくれて抱きしめてくれて疲れでへたり込んでる時は拭き取りクレンジングで化粧を落としてくれたりマッサージをしてくれてありがとう。こんな私にはもったいない彼氏だ。ずっとそう思っていた。好きで好きで堪らなかった。彼が好きすぎて、好きがパンクして死んでしまうかもと思った。好きだよと毎日伝えても伝え足りなくて、伝え足りなさでパンクしてやっぱり死んでしまうかもと思った。
「ユキ、私のイチゴあげる。好きでしょ?」
その言葉は、私のこと好きでしょと迫っているようで押し付けがましく醜いと分かっているのに手は止まらずにフォークでイチゴを刺していた。
「脂肪分の多いもの、気持ち悪くなるんだ」
拒絶された私の押し付けは行き場を失い、フォークは空を立ち往生する。
「イチゴだけでいいから食べない?」
彼は空洞のような黒目でしっかりと私を見つめたまま微かに首を振り、また目を閉じた。うっと声が出て、次の瞬間には「うわあっ」と号泣していた。ぼろぼろと涙が出て止まらない。その様子はパチンコのフィーバーを思わせた。ぽろぽろぽろぽろと玉が排出されていくパチンコ台のようだった。私はパチンコ台になって玉を吐き出す。一銭にもならない玉を吐き出す。「どうして」「どうして」「ユキ」私の嘆きは無視されたまま、彼は目を開けない。溢れる涙は手元のショートケーキを濡らし生クリームが溶け、安っぽいスカスカのスポンジがふやけていく。号泣したまま衝動的にケーキのパックを床に投げつけ、バッグからスマホを取り出す。連絡帳をスクロールして一度も掛けたことのなかった彼のお母さんに電話を掛ける。初めて挨拶しに行った日、これからも行成のことをよろしくね、何かあったらいつでも連絡してと渡された電話番号だった。最初で最後の電話は、私の号泣で始まる。
お母さん、もう私では無理なんです。彼は働けない、バンドももうやってない、もう外に出ることもできないんです。コンビニにも行けないトイレに行くこととたまにお風呂に入ることとご飯を食べることしかできないんです。私はもう、私には限界なんです助けてください。お願いです助けてください。泣きながら一気に捲したてる。「駄目なんです私じゃ駄目なんです。私じゃ駄目なんです」。私の叫びは私に言い聞かせているようでもあって、言えば言うほど興奮が加速していく。「助けて」。いや違う。私は今ユキに呼びかけてるんだ。私は今、「助けて」とユキに縋っているのだ。電話の切るマークをタップして通話を切ると、私はスマホを床に投げつけ布団を剥がしてユキに馬乗りになる。
「ユキ!」
目をつむったまま、彼は眉間に皺を寄せ苦痛に顔を歪める。
「助けて!」
両手で胸元を掴まれた彼から苦痛の呻きが漏れる。
「私を助けて!」
馬乗りになった私の背中に冷たい彼の手が回る。死を間近に控えた末期患者のように今にも息絶えそうな弱い力で抱き寄せられた私は、ユキの胸に顔を埋めて久しぶりの安堵に肩で息をしながら耽溺する。
「無理だよ」
ユキの諦念が音と振動で伝わる。
「無理なんだ」
悲惨な泣き声は彼の胸に吸収されていく。それでもどんなに声をあげても、もう彼には届かない。何かの偶然で届いたとしても、彼は私を救えない。
「ごめん」
汗と涙でびしょびしょになった私に届いたのは簡潔な謝罪の言葉で、それでも私は、彼が数ヶ月、いや、ほとんど一年ぶりに私に声を掛けてくれたことに気づく。ずっと自分の話しかしなかった彼が、私という存在を認識して私に声を掛けてくれたことに気づく。悲しくて寂しくて、悔しくて情けなくて、本当に馬鹿みたいに、南極の氷の上に裸足で佇むみたいに寒くて一人だった。私を抱きしめる彼の腕には何のエネルギーも感じられない。カカシみたいだ。私は人形に縋る頭のおかしい人間のようだ。美しい人形に魅せられた。夢中になって愛した。美しい彼に魅せられた私は、こうして剥き出しになった彼の本性に触れ、恐れ戦きながらも彼に縋り結局彼を諦める。無理なのだ。私も彼も、もう無理なのだ。
「無理なんだよ」。寄り添うように、行成は優しい声で囁いた。散々泣いて、行成の胸から顔を上げると暗いところから突然明るいところに出た時のように激しい眩暈がして視線がふらつく。霞んだ視界の端に、生クリームに突っ込んだスマホが見えた。
行成の両親は次の日の朝家にやって来た。両親がやって来てもほとんど言葉を発することのできない息子を見て、二人は驚いた様子だったけれど、彼や私を責めることはしなかった。行成、一緒に家に帰ろう、しっかり休んで、ゆっくりでいいから、少しずつ治していこう、ミナさんも大変だったでしょう、迷惑かけたね、ちゃんと責任持って面倒見るから心配しないでね。彼の状態を把握したお母さんはそう言った。
「行成、高校生の頃にもしばらくこうして鬱みたいになって引きこもったことがあってね、その時は半年くらいで治ったんだけど」
お母さんの言葉は、彼が鬱の症状を現し始めてから半年ほどで浮気に走った私に僅かに罪悪感を与えた。
「経過、連絡しますね」
じっと視線を落としたまま逡巡して、いいですと呟く。
「彼も、それを望んでいないと思います」
私がそう言った時、お父さんが行成の肩を抱いて寝室から出てきた。お父さんは息子の症状を受け入れられないのか、ここに来てから寡黙なまま私には何も言わなかった。もう行くの? と慌てた様子のお母さんは、荷物とかそういうことはまたメールか電話でやりとりしましょうと言って立ち上がった。玄関まで連れて来られた行成は一度だけ私を振り返る。でも何も言わないままお父さんに促されて靴を履いた。エレベーターに乗るところまで見送ったけれど、行成はもう二度と私と目を合わせなかった。一言声をかけたいという思いは、私の視線から逃げるユキの淀んだ目によってかき消された。ちゃんと治してね、出かかっていたその言葉は、自分の狭量と無力さの証にしかならず自分をより苦しめることも分かっていた。
行成のいない部屋は寂しいようで清々しくもあり、まるで市に電話を掛けて粗大ゴミを捨てたような気分になる。私は彼を捨てたのだろうか。いやずっと前に私は捨てられていた。どうしてこんなことになったのか、自分にもっとできることがあったんじゃないか、何か自分に間違いがあったんじゃないか、そんな風に思うだろうという予想は裏切られ、私にはもうただの一ミリも感情らしきものは残っていなかった。
今日三本目のストロングを傾けながら、寝室でぼんやりと抜け殻になったベッドを見つめる。ふと、彼のギターケースがクローゼットに入れっぱなしのままだったことを思い出す。彼がこのベッドで歌ってくれた曲の歌詞は一字一句記憶していて、それでもこの状況で彼の作ったセンチメンタルな歌詞を口にすることに躊躇して、鼻歌を歌う。涙は出なかった。涙を流すには、この世界はあまりにも濁っている。ストロングを呷りながら、行成分広くなったベッドに大きく寝転び、スマホでパズルゲームを始める。
ピンポーンとインターホンが鳴ったのは、五本目のストロングが空いた頃だった。行成が普通にバイトから帰ってきていた頃の記憶が蘇り、ユキ? と思わず呟きを漏らしながら玄関に駆け寄る。
「宅配便です。サインお願いします」
顔見知りの宅配便業者から段ボールを受け取りドアを閉めると、その場で無表情のまま段ボールのガムテープを引っぺがす。大量のストロングの空き缶が、そこにあった。
「ストロングゼロ」了