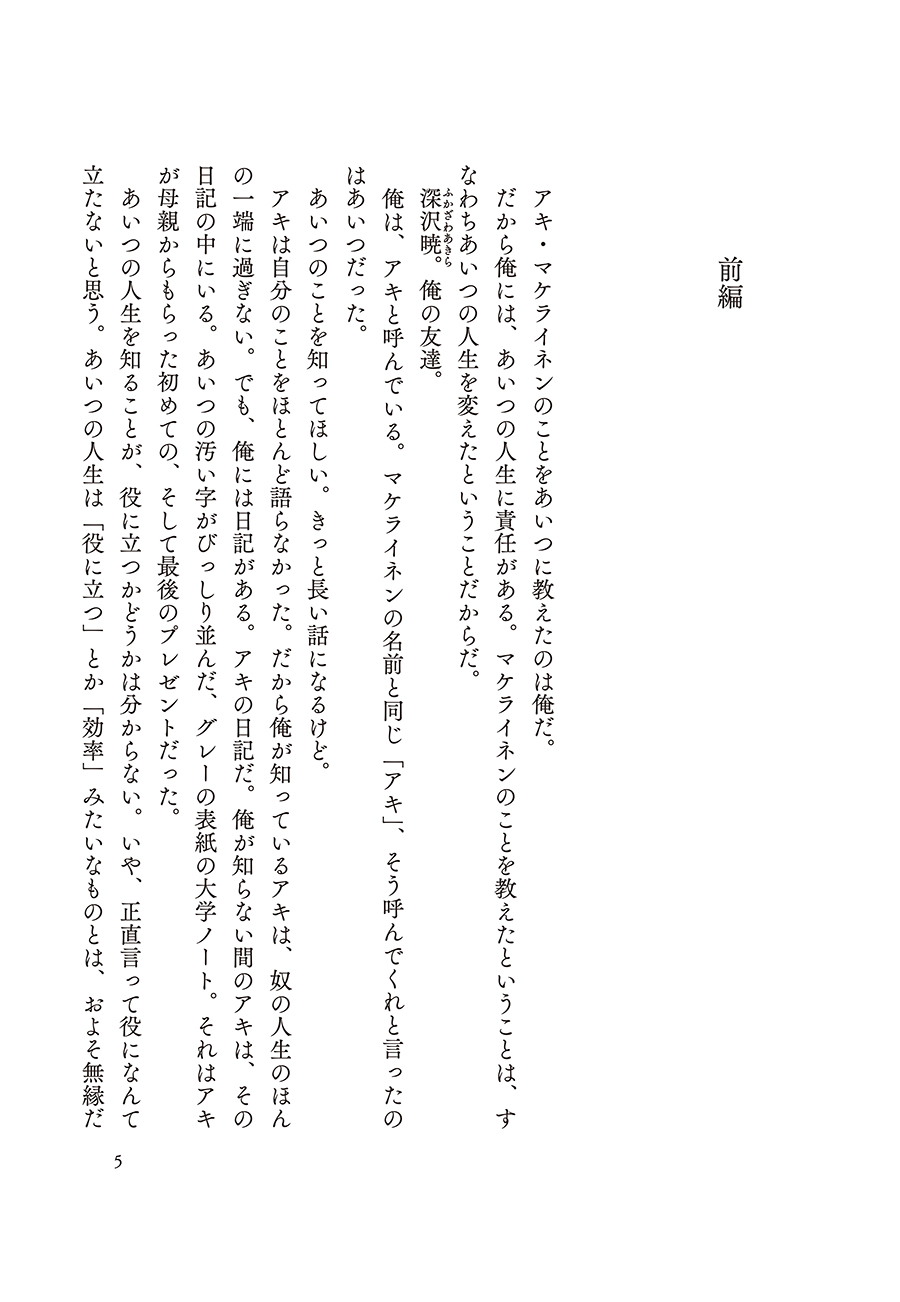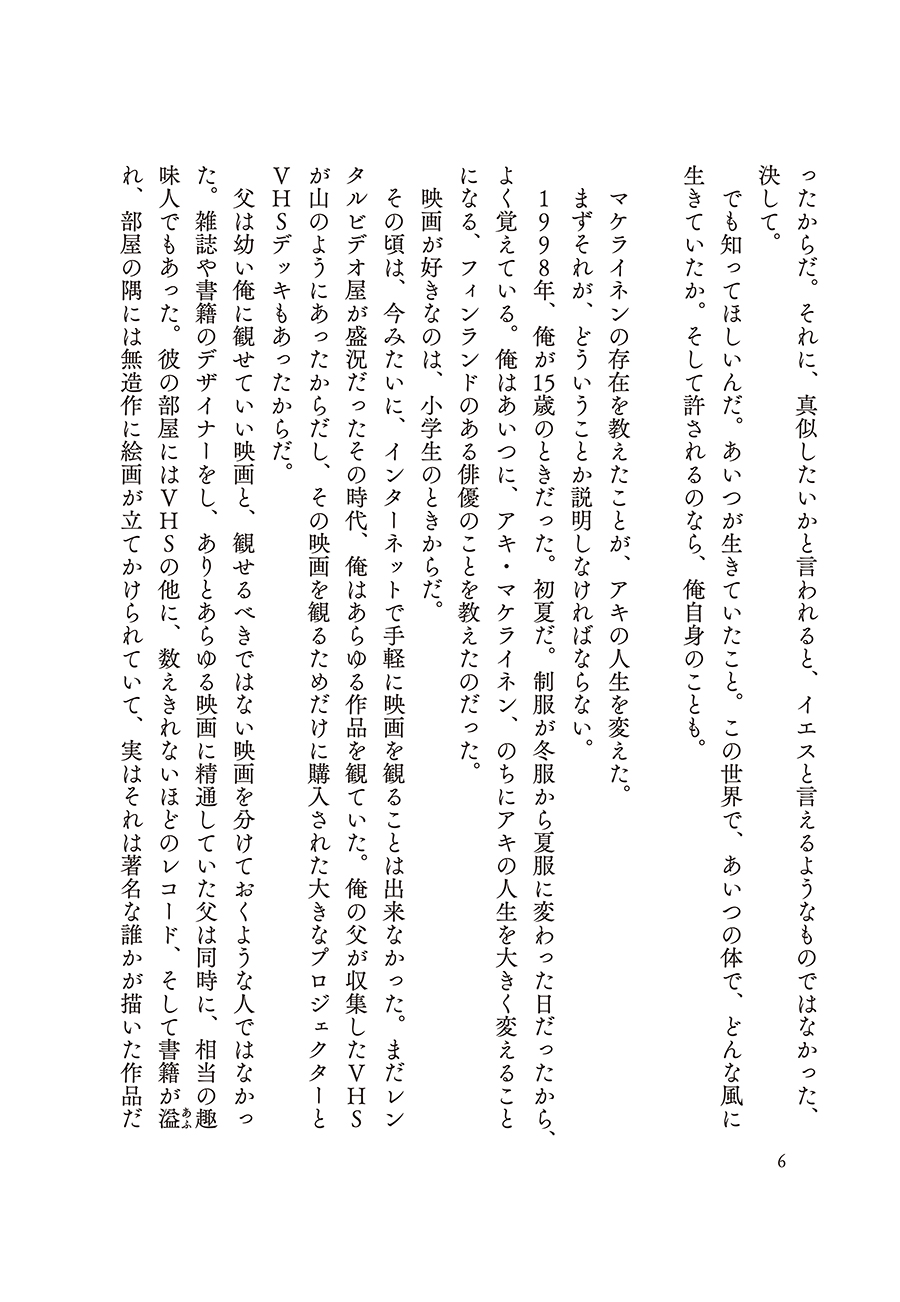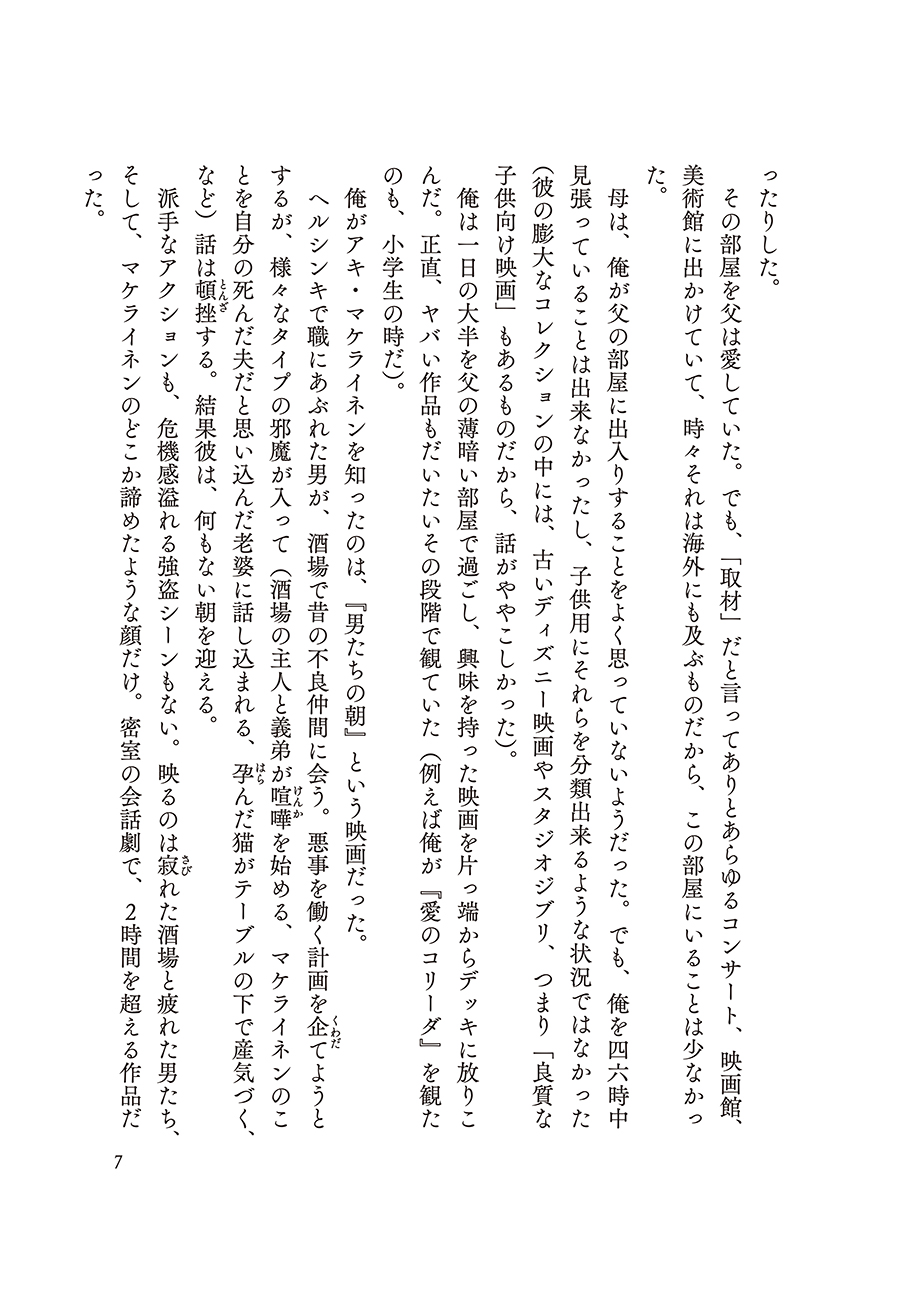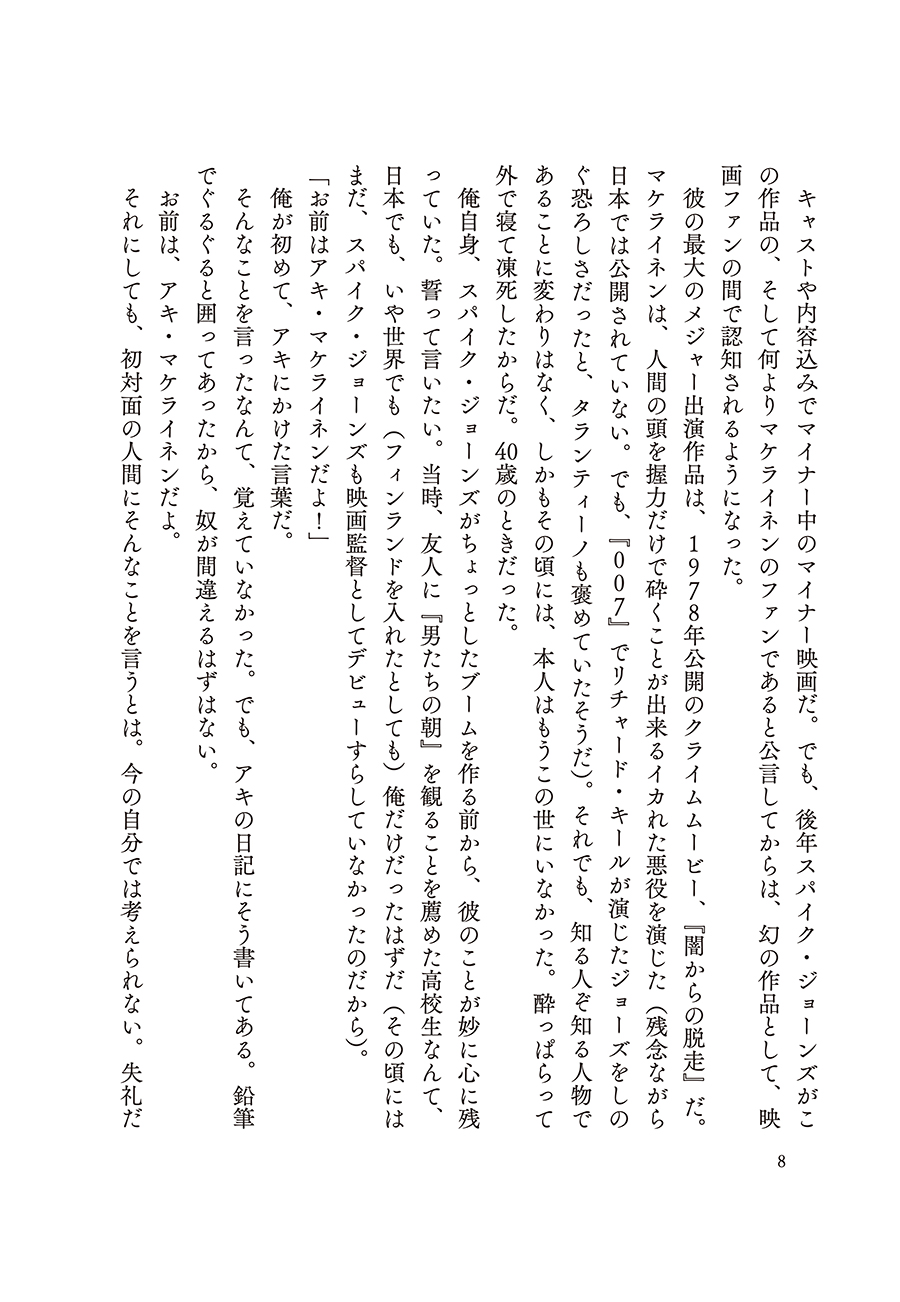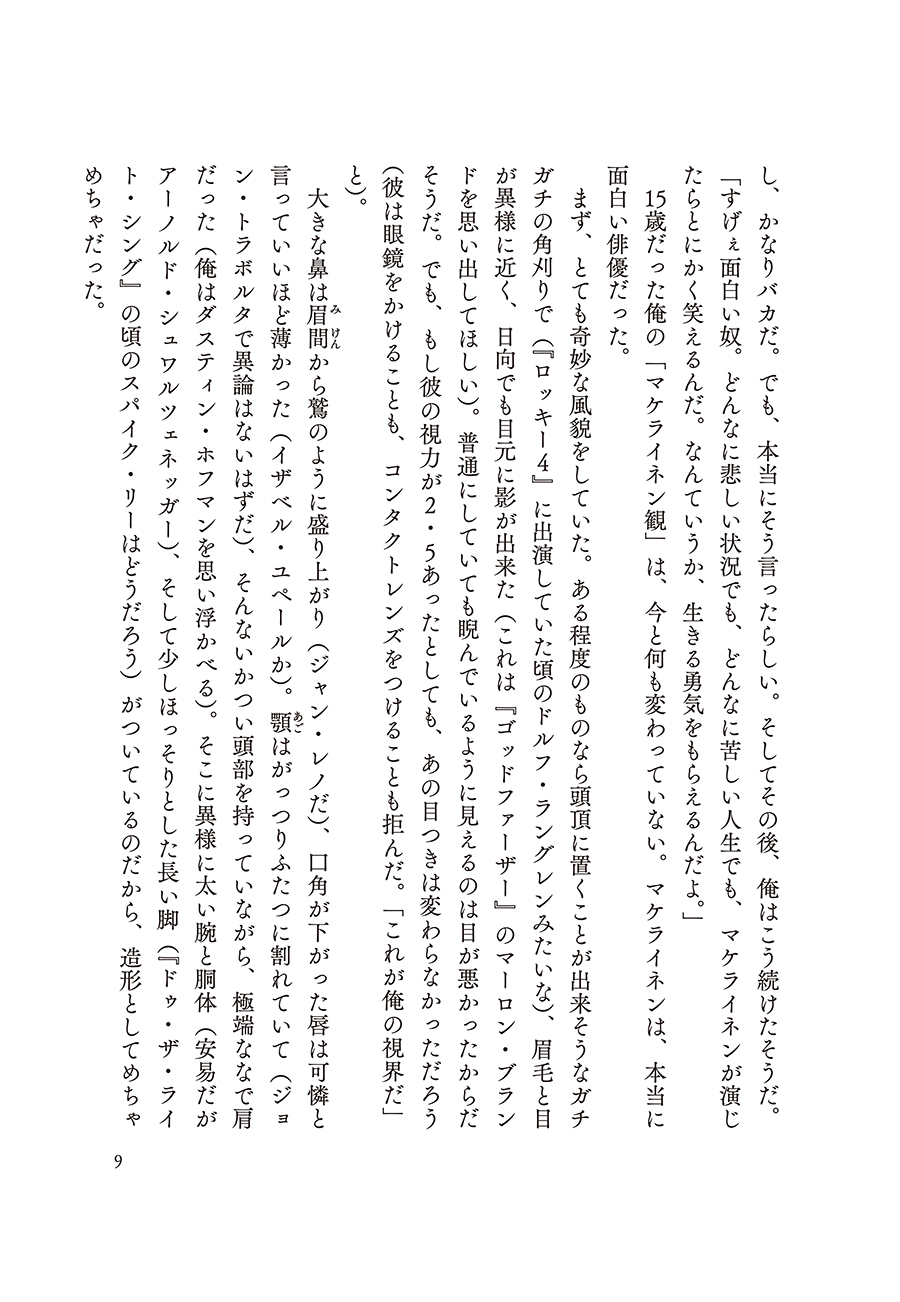あなたの子供は、あなたの子供ではない。命そのものが再生を願う、その願いの息子であり、娘である。彼等はあなたを通して産まれてくるが、あなたから産まれてくるのではない。彼等はあなたとともにいるが、あなたのものではない。あなたは彼等に愛情を与えても、あなたの思考を与えることは出来ない。何故なら、彼等の心は、あなたが夢の中で訪ねてみることもできない、あしたの家にあるからだ。
――カリール・ジブラン「預言者のことば」
貧困とは、潜在能力を実現する権利の剥奪
――アマルティア・セン
悪人善人というのはない。人には美しい瞬間と醜い瞬間があるだけだ。
――市原悦子
前編
アキ・マケライネンのことをあいつに教えたのは俺だ。
だから俺には、あいつの人生に責任がある。マケライネンのことを教えたということは、すなわちあいつの人生を変えたということだからだ。
俺は、アキと呼んでいる。マケライネンの名前と同じ「アキ」、そう呼んでくれと言ったのはあいつだった。
あいつのことを知ってほしい。きっと長い話になるけど。
アキは自分のことをほとんど語らなかった。だから俺が知っているアキは、奴の人生のほんの一端に過ぎない。でも、俺には日記がある。アキの日記だ。俺が知らない間のアキは、その日記の中にいる。あいつの汚い字がびっしり並んだ、グレーの表紙の大学ノート。それはアキが母親からもらった初めての、そして最後のプレゼントだった。
あいつの人生を知ることが、役に立つかどうかは分からない。いや、正直言って役になんて立たないと思う。あいつの人生は「役に立つ」とか「効率」みたいなものとは、およそ無縁だったからだ。それに、真似したいかと言われると、イエスと言えるようなものではなかった、決して。
でも知ってほしいんだ。あいつが生きていたこと。この世界で、あいつの体で、どんな風に生きていたか。そして許されるのなら、俺自身のことも。
マケライネンの存在を教えたことが、アキの人生を変えた。
まずそれが、どういうことか説明しなければならない。
1998年、俺が15歳のときだった。初夏だ。制服が冬服から夏服に変わった日だったから、よく覚えている。俺はあいつに、アキ・マケライネン、のちにアキの人生を大きく変えることになる、フィンランドのある俳優のことを教えたのだった。
映画が好きなのは、小学生のときからだ。
その頃は、今みたいに、インターネットで手軽に映画を観ることは出来なかった。まだレンタルビデオ屋が盛況だったその時代、俺はあらゆる作品を観ていた。俺の父が収集したVHSが山のようにあったからだし、その映画を観るためだけに購入された大きなプロジェクターとVHSデッキもあったからだ。
父は幼い俺に観せていい映画と、観せるべきではない映画を分けておくような人ではなかった。雑誌や書籍のデザイナーをし、ありとあらゆる映画に精通していた父は同時に、相当の趣味人でもあった。彼の部屋にはVHSの他に、数えきれないほどのレコード、そして書籍が
その部屋を父は愛していた。でも、「取材」だと言ってありとあらゆるコンサート、映画館、美術館に出かけていて、時々それは海外にも及ぶものだから、この部屋にいることは少なかった。
母は、俺が父の部屋に出入りすることをよく思っていないようだった。でも、俺を四六時中見張っていることは出来なかったし、子供用にそれらを分類出来るような状況ではなかった(彼の膨大なコレクションの中には、古いディズニー映画やスタジオジブリ、つまり「良質な子供向け映画」もあるものだから、話がややこしかった)。
俺は一日の大半を父の薄暗い部屋で過ごし、興味を持った映画を片っ端からデッキに放りこんだ。正直、ヤバい作品もだいたいその段階で観ていた(例えば俺が『愛のコリーダ』を観たのも、小学生の時だ)。
俺がアキ・マケライネンを知ったのは、『男たちの朝』という映画だった。
ヘルシンキで職にあぶれた男が、酒場で昔の不良仲間に会う。悪事を働く計画を
派手なアクションも、危機感溢れる強盗シーンもない。映るのは
キャストや内容込みでマイナー中のマイナー映画だ。でも、後年スパイク・ジョーンズがこの作品の、そして何よりマケライネンのファンであると公言してからは、幻の作品として、映画ファンの間で認知されるようになった。
彼の最大のメジャー出演作品は、1978年公開のクライムムービー、『闇からの脱走』だ。マケライネンは、人間の頭を握力だけで砕くことが出来るイカれた悪役を演じた(残念ながら日本では公開されていない。でも、『007』でリチャード・キールが演じたジョーズをしのぐ恐ろしさだったと、タランティーノも褒めていたそうだ)。それでも、知る人ぞ知る人物であることに変わりはなく、しかもその頃には、本人はもうこの世にいなかった。酔っぱらって外で寝て凍死したからだ。40歳のときだった。
俺自身、スパイク・ジョーンズがちょっとしたブームを作る前から、彼のことが妙に心に残っていた。誓って言いたい。当時、友人に『男たちの朝』を観ることを薦めた高校生なんて、日本でも、いや世界でも(フィンランドを入れたとしても)俺だけだったはずだ(その頃にはまだ、スパイク・ジョーンズも映画監督としてデビューすらしていなかったのだから)。
「お前はアキ・マケライネンだよ!」
俺が初めて、アキにかけた言葉だ。
そんなことを言ったなんて、覚えていなかった。でも、アキの日記にそう書いてある。鉛筆でぐるぐると囲ってあったから、奴が間違えるはずはない。
お前は、アキ・マケライネンだよ。
それにしても、初対面の人間にそんなことを言うとは。今の自分では考えられない。失礼だし、かなりバカだ。でも、本当にそう言ったらしい。そしてその後、俺はこう続けたそうだ。
「すげぇ面白い奴。どんなに悲しい状況でも、どんなに苦しい人生でも、マケライネンが演じたらとにかく笑えるんだ。なんていうか、生きる勇気をもらえるんだよ。」
15歳だった俺の「マケライネン観」は、今と何も変わっていない。マケライネンは、本当に面白い俳優だった。
まず、とても奇妙な風貌をしていた。ある程度のものなら頭頂に置くことが出来そうなガチガチの角刈りで(『ロッキー4』に出演していた頃のドルフ・ラングレンみたいな)、眉毛と目が異様に近く、日向でも目元に影が出来た(これは『ゴッドファーザー』のマーロン・ブランドを思い出してほしい)。普通にしていても睨んでいるように見えるのは目が悪かったからだそうだ。でも、もし彼の視力が2・5あったとしても、あの目つきは変わらなかっただろう(彼は眼鏡をかけることも、コンタクトレンズをつけることも拒んだ。「これが俺の視界だ」と)。
大きな鼻は
とにかく目を引く男だったし、どんなシリアスな場面でも彼が登場したら、まず笑ってしまうような俳優だった。でも、例えば酒場の椅子に黙って座っているだけで、泣けてくる哀愁があった。
彼が
マケライネンみたいな奴は、アメリカにもフランスにもいなかった。スティーブ・ブシェミが彼に憧れて歯の矯正をしないでいると言っていた。でも、あの怪優ブシェミでも、
マケライネンに似ている15歳の日本人がいた。きっと今、あなたは Google でマケライネンの画像を検索しているだろう。そして、信じられない思いでいるだろう。
アキは入学式から異彩を放っていた。まず、一見して絶対に高校生には見えなかった。身長191センチ、みんなから頭ひとつ飛び出していて、ほとんど巨人と言っても良かった(アキ・マケライネンの身長は194センチ。アキは残りの3センチを、日常のあらゆる場面で背伸びをしたり、靴に細工をすることで稼いだ)。
もちろん高校生にもなると、身長が高いだけで大人びて見えるというわけではない。アキは実際に老けていたのだ。頬にはすでに深く皺が刻まれていて、綺麗に剃れないのか、鼻の下や顎には黒々とした髭がこびりついていた。何より10代にはセットでついてくるはずの「
でも結果、アキは間もなく、「取るに足らない奴」のレッテルを貼られることになった。アキはそんな風貌を持っていながら、とにかくオドオドしていた。バスケ部やバレー部、野球部に柔道部、山ほど部活の誘いを受けていたが、アキはそのたび肩を縮こまらせ、まるで今まさにカツアゲに遭っています、とでもいうような顔をした。
だから、入学から1ヶ月もすれば、アキの認識は「無駄にデカい奴(それだけの奴)」または「ただの醜い奴(アキの風貌は、10代の人間からすればそういうことになった)」ということに落ち着いた。みんなを見下ろす位置にいながら、アキは常に、みんなを見上げているようなものだった。
アキにずっと注目していたのは、俺だけだったと思う。注目といっても、廊下で見かけたら目で追ってしまう、というくらいのものだったが。でも、とにかく、奴がマケライネンに似ていることが、ずっと気になっていた。こんなに似ている奴を見たことがなかった。マケライネンに似ている奴の中で一番似ている、ということではなく(そんな奴いなかったし)、誰かが誰かに似ている、というカテゴリーの中で頂点だったのだ。俺に言わせると、アキは「ほとんどマケライネン」だった。
でも、俺がそれを誰かと共有することはなかった。VHSの『男たちの朝』を観ている同級生がいるとはとても思えなかったし、クラスメイトや、所属していた陸上部の仲間の間で、アキのことが話題に上ることなんてなかったからだ(誰も知らないことをわざわざ話の俎上に載せるほど、俺は空気の読めない奴ではない)。
アキはその風貌をものともせず、気配を消すことにいつも成功していた。朝は誰よりも早く教室に来て席に座り、教科書を広げていた(教科書を授業以外で読む高校生がいるなんて!)。休み時間は冷水器で水を長い時間飲んでいたが、誰かが来るとすぐに譲った。廊下を歩くときは大きな体を折り曲げて人の邪魔にならないように注意し、どの部活にも所属せず、授業が終わったらすみやかに帰宅した。
でかい空気。
変な言い方だけど、アキはそんな奴だった。
俺がアキに「それ」を告げることになったのは偶然だ。
担任に呼ばれ(どういう用事だったかは記憶にない)、俺はその日職員室にいた。担任は生物の教師だった。次の授業の実験器具を運ぶ役を頼まれたのが、体の大きなアキだった。
俺とアキを待たせておきながら、担任は他の教師とぺちゃくちゃ話していた。ふたりで放っておかれて、多分気づまりだったのだろう。俺はやむにやまれず、アキにこう話しかけたのだ。
「お前はアキ・マケライネンだよ!」
多分俺は、まだアキを恐れていた。「取るに足らない奴」だと認識してはいても、アキの体が巨大であることに変わりはなかったし、3、4人殺してきた雰囲気だって健在だった。きっと俺は、思春期の男子が皆きっとそうするように、「ビビってないぜ」という態度を見せようとしたのだ。そして願わくば、ちょっと変わった奴、として認識してほしかったのだろう。
「お前はアキ・マケライネンだよ!」
アキがマケライネンを知らないことは、もちろん承知の上だった、はずだ(知識を誇るのは俺の悪い癖だった。特に皆が知らない知識を)。アキは俺に突然話しかけられて驚いていた。というより、明らかにビビっていた。肩を震わせて、音が聞こえそうなほど、体を固くした。身長165センチの俺を明らかに見下ろす位置にいながら、アキはやっぱり、俺を見上げているみたいな顔をしていた。
「だ、だ、だ誰?」
その上、アキはひどい
「すげぇ面白い奴。どんなに悲しい状況でも、どんなに苦しい人生でも、マケライネンが演じたらとにかく笑えるんだ。なんていうか、生きる勇気がもらえるんだよ。」
信じられないことに、俺はその日アキを家に誘ったらしい。『男たちの朝』を観にこないか、と。アキみたいな奴と話が弾むとは思えなかったし、得体の知れない人間を家に誘うような根性は、俺にはなかった。でもそう言ったらしいのだ。
アキは日記に、こう書いている。
『家にさそってくれた。アルバイトがあったから断った。くやしい。すごく行きたかった。』
翌日、アキは廊下で急に話しかけてきた。
「そ、そ、その人のこと、おお教えてほしいんだ。」
その様子は「必死」以外の何ものでもなかった。ほとんど命乞いするような勢いで、アキは俺に頼んだ。俺が断ったら、土下座でもなんでもしたんじゃないだろうか。
アキの期待にはできるだけ応えてやりたかった。でも、俺だって知識は限られていたし、そもそもアキ・マケライネンの情報なんて日本に流通していなかった(みんながインターネットという「辞書」を持つようになるのは、そこから数年後の話だ)。だから俺は、アキに『男たちの朝』を貸すしかなかった。それだって一苦労だ。父の膨大なコレクションの中から、随分前に観た1本のビデオテープを探すのだから。日付が変わる頃に探し始めた結果、埃だらけのそれを見つけたのは、たしか明け方だったと思う。
アキは、そのビデオテープを宝物のように抱いて帰った。そして数日後、
「み、み、みみみ観たよ。」
俺の教室に、息せき切ってやって来た(何人か殺したようなあの顔で突進してくるものだから、クラスメイトの何人かは、本当に俺が殺されると思ったようだ)。
「ぼ、ぼ、僕かと思った。」
「だろ? 似てるってレベルじゃないよ。」
アキが、顔を真っ赤にしたのを覚えている。恥ずかしかったのではなく、興奮していたのだ(それとも、そのどちらもか)。
「やっぱりお前は、マケライネンだよ!」
俺の言葉に背中を押されたのだろうか。アキはその日から自身のことを、マケライネンだと名乗り始めた。
「ぼ、ぼ、僕はマケライネンだ。」
俺に「深沢」ではなく「アキ」と呼ぶことを求め、マケライネンと同じように無精髭を生やし、あげくの果てには、40歳で凍死すると宣言した。
40歳で死ぬなんて若すぎる。しかも凍死だなんて。健康な男子高校生の夢としては、あまりに悲惨な末路だ。
でも、当時15歳だった俺たちにとって、それは永遠に来ない未来の話だった。40年生きている奴なんて完全なおっさんだったし、40歳の人間のことを話すのは、ほとんど70歳の老人のことを話すのと同じだった。高校生にとって世界は「俺たち高校生とそれ以外」だ。未来なんて、遠くにありすぎて考えられない。しかも「フィンランドってどこ?」、そんな感じだ。
何よりアキにとって重要だったのは、マケライネンがもう死んでいる、ということだった。出逢ったときにすでに死んでいるということは、二度と死なないということだ。つまりマケライネンは、アキの中で永遠に生きているのと同じことになった。
アキは毎日俺の教室を訪れ、とにかくマケライネンのことを話したがった。
「か、か、顔の前でて、て、手を振るの、いい、い、いよね。」
「あ、あ、あの煙草をすす、吸うシーンでさ。」
自分に似ている、というだけでこんなに誰か(しかも奴が似ているのはウィル・スミスでもブラッド・ピットでもない。フィンランドのスーパーマイナーな役者なのだ)に夢中になるなんて、俺には理解出来なかった。アキの熱意は普通じゃなかった。それでもその時間が、俺は楽しかった。
俺とアキの交流を奇異な目で見ていたクラスメイトも、それが日常のことになると、みんなアキに興味を持ち始めた。俺がアキと楽しそうに話していると、初め恐る恐る話しかけてきて、それから結局、アキに夢中になった。
アキは面白い奴だった。
アキ・マケライネンだと名乗る。つまりアブない奴ではあるが、アキは基本めちゃくちゃいい奴だった。そしていわゆる天然だった。俺たちの質問に、いつも素っ頓狂な答えを返し、俺たちが「なんだよそれ!」と笑うと、申し訳なさそうに頭を下げた。
「ご、ごごごめん、目が悪いから。」
「目じゃなくて耳だろ!」
それはお決まりのやり取りになったけど、アキは本当に目が悪かった。なのに眼鏡をかけていないしコンタクトもつけていないのは、マケライネンと同じだった。アキはそれを喜んだ。
「じゃあ授業中どうやってノート取ってんの? お前席一番後ろだろ?」
出席番号やくじ引きなどに関係なく、その驚くべき座高の高さで、アキはいつも自動的に一番後ろの席にされていた。
「あ、あ、あの、よ、よくみ見えないからせん、先生の言葉を書いてる。」
「先生の?」
「せ先生が話す言葉。」
「なんだよそれ!」
「意味ねーよ!」
俺たちはアキにノートを持ってこさせ、みんなで笑った。アキの汚い字は、誰も読むことが出来なかったからだ(何故か、俺だけは読むことが出来た)。
「読めねーよ!」
「こえぇ!」
俺たちが笑うと、アキは不思議そうな顔をした。どうして笑われているのか、分からなかったのだろう。それでも1学期が終わる頃には、アキは学年中の男子の人気者になっていた。廊下を歩いていると声をかけられ、乱暴な愛情表現しか出来ない奴には、ケツを思い切り蹴られていた。
「アキ、ものまねやってくれよ!」
アキはみんなに「アキ」と呼んでもらうことに成功していた。そして、マケライネンになる、と宣言していることも知れ渡らせた。
みんな、もちろんマケライネンのことなんて知らなかった。だからアキがそっくりそのままマケライネンの歩き方(肩を下げ、左足を少しひきずる)をしても、
「だから誰なんだよ!」
そう叫んで笑っていた。
「正解を知らねぇから!」
「似てるかどうか分かんねんだよ!」
正解を知っているのは、ずっと俺だけだった。俺から言わせるとアキのそれは、完全に「正解」だった。制服を脱いで髪を白く染めれば、本当にマケライネンそのものだった。たった数ヶ月の間で、アキはますますマケライネン化していた。
でももちろん、みんなそんなこと、どうでも良かった。まったく知らないフィンランドの俳優に似ている、だからそいつになると宣言している変な奴。それだけで笑うには十分だった。
アキは、ひひひひ、と口を横に広げる、
『男たちの朝』は、アキにあげた。父が部屋にある作品をすべて把握しているとはとても思えなかったし、俺も今後『男たちの朝』を観返すことはないだろうと思ったからだ(そしてその予想は当たらなかった。俺は後年、ある理由から、何度もそれを観直すことになる)。
ビデオを手渡すと、アキは「信じられない」という顔をした。神様に会ったみたいな顔で俺を見て、何度も何度も頭を下げた。
「あ、あ、ありがとう。本当にありがとう。あありがとう。ありがとう。」
人にここまで感謝されて、正直悪い気はしなかった。ただ、アキのそれは常軌を逸していた。まるで俺が、沈没船から離れるボートの最後の1席を、アキに譲ったみたいだった。
「ほ、ほ、本当にありがとう。ぜ、ぜ、絶対にわ、忘れないよ、ほほ、ほ、本当にありがとう。ありがとう、あ、ありがとう。ありがとう。」
アキの中で俺は、ほとんど「命の恩人」と同等の扱いになった。それはつまり、「自分の命をかけてでも守る人」ということだった。
実際俺は、アキに命を助けられている。
学校帰りだった。部活が休みになる中間試験か期末試験の前は、帰宅部のアキと俺たちで一緒に帰ることにしていた。
学校は東京の西の端にあった。線路への飛び込み自殺者が日本一だと言われる、悪名高い路線にある駅まで10分ほどの距離を、俺たちは歩いていた。その日は曇りで、天気予報では雨のはずだった。でも帰宅まで雨は降らず、俺たちはそれぞれ畳んだ傘を手に持っていた。
何がきっかけだったか、その傘を奪って出来るだけ遠くまで投げる、という流れになった。傘を奪い合い、奪ったものを槍投げの選手を真似て遠くへ、それも選手と同じように大声で叫びながら投げる、ということを、俺たちは繰り返した。
「おおうらぁあああああっ!」
「どぁああああああああ!」
全力でやればやるほどウケた。何度やっても飽きなかった。遠くに飛んだ傘をまたみんなで走って拾いに行き、持ち主の手に渡る前にまた投げた。杉本って奴の傘は木にひっかかり、元木って奴の傘は持ち手が欠けた。
もちろん、俺の傘も狙われた。なんの変哲もないビニール傘だったが、みんなに引っ張られた瞬間「先祖の形見なんだ!」と叫んだ。
「なんだよ先祖って!」
「その時代にビニール傘なんてねえだろ!」
もちろん俺は、傘なんてあきらめていた。奪われてずたずたに折られて放り投げられることを覚悟していた。
「やめてくれぇええええ!」
俺たちの間では、そういう暴力的なことが流行っていた。自分たちの体のせいだ。急激に増殖する男性ホルモンというやつを、俺たちは持て余していた。自慰をしてもしてもしても(本当に、どれだけこすってもこすってもこすっても)それは次から次へと溢れ、俺たちを
廊下ですれ違うときに思い切り肩を殴ったり、「わっ」と驚かされた勢いでそのままグラウンドを何周もしたりした(2階から飛び降りて足を骨折した奴もいた)。もちろん悪ふざけだが、切実だった。そうしないと死んでしまうとすら思っていた。
「こいつ全然離さねぇ!」
「一番安そうな傘のくせに!」
俺は傘にしがみついた。地面に転がり、スタントマンさながら引きずられた。そのまま数百メートル引きずられても、絶対に離さないでいるつもりだった。つまらないことであればあるほど必死にやる、そうすれば、よりウケると分かっていたからだ(その論理で、消しゴムや定規なんかを借りるとき、頭を地面にこすりつけて土下座するのも流行った)。
「形見なんだぁあああ!」
皆も俺の意図を察したようだった。死ぬ気で傘を取りにかかった。傘を振り回し、つまり俺の体を振り回した。俺は地面でごろごろ転がった(闘牛に突かれたマタドールみたいなイメージだ)。膝がすりむけ、靴が脱げ、制服がドロドロに汚れた。
アキは、少し離れたところで俺たちを見ていた。アキの、この「少し離れたところから俺たちを見ている」スタンスは、基本変わらなかった。アキは俺たちに話を振られたときだけ参加し、ひひひと笑い、決して俺たちと同じような馬鹿騒ぎはしないのだった。
遠心力で、俺の体が転がった。そうやって倒れたままでいても、十分面白かった。でも俺は、車道へごろごろと転がることを選んだ。皆が笑う声が聞こえた。よし、やった、そう思った瞬間、参議院議員選挙立候補者の選挙カーが、角を曲がってやって来たのだった。
「危ない!」
選挙カーというものは、馬鹿みたいにうるさく、のろのろ運転をするものと相場が決まっているはずだ。なのに、それは無音だった。そして、めちゃくちゃ速かった。
「危ない!」
俺はそのまま
目を開けた俺が見たのは空だった。青く、突き抜けた空だ。俺の周りには誰もいなかった。顔を上げても、どこも痛くなかった。ぼんやりした視界が捉えたのは大声で叫ぶ友人たちで、起き上がった俺が見たのは、道路に大の字で寝転がるアキだった。
「アキ!」
「大丈夫か!?」
死んだ。
そう思った。
体全体が冷えた。本当に、氷水をかけられたみたいにゾッとした。
横たわったアキの体は、横たわった分大きかった。こんな大きな体が「死んでいる」ことが信じられなかった。こいつが入る棺ってあるのかな、そんな不謹慎なことを、一瞬思った。
でも、アキは起き上がった。
「うわ!」
後で皆に聞いたところ、アキは俺とハイエースの間に大きく手を上げて割って入ったそうだ(「スローモーションで見えた」「弁慶の最期みたいだったぜ! 見たことないけど」)。運転手が
「アキ!」
選挙カーから、わらわらと大人たちがおりて来た。立候補者のおっさんはハイエースから出てこず、窓からこちらを見ているだけだった(何故分かったかというと、車体に貼られていたポスターと同じ顔だったからだ。名前は「あんべたくま」、どこからどこまでが苗字なんだよ!?)。
大人たちは焦っていた。肩にかけられた「あんべたくま」のタスキが震え、顔面蒼白になっている奴もいた。それはそうだろう。大事な選挙運動の最中に、罪なき高校生を轢いたのだから。散々脅して、大金をふんだくってやれば良かった。でも悔しいことに、当時の(バカな)俺たちに、そんな知恵はなかった。
「アキ!」
俺たちはとにかく興奮していた。アキの無敵さに、その勇敢さに。
「アキ、すげぇ!」
俺たちはアキの肩を、腕を、触れられるところはすべて叩いた。今思うと、怪我をしているかもしれない友人にその仕打ちはない。でも、俺たちの興奮と称賛を伝えるにはそうするしかなかった。場所中一番活躍している力士を叩くみたいに、俺たちはアキを自らの体温で讃え続けた。
「アキ!」
「アキぃ!」
でも、そんな俺たちの歓喜を邪魔する奴が現れた。大人のひとりがこそこそと割って入り、アキに名刺を渡したのだ。
「何かあったら、連絡を……。」
そして逃げ去った。俺たちは全員でそいつらに中指を立てた。杉本は中指を立てたまま雄叫びを上げた。
「あんべたくまぁ!」
みんな吹き出した。そしてもちろん、すぐに後に続いた。
「あんべたくまぁ!」
「あんべたくまぁ!」
誰だか知らない立候補者の、ただの名前だ。でも、その響きはどこか麻薬的な魅力があった。俺たちはアキを正式に讃える言葉を見つけたのだ。とにかく言葉よりも先に衝動が勝つ、そんな俺たちにとって、意味をなさない叫びであればあるほど、それは意味をなすのだった。
アキは英雄になった。俺たちの、そして特に俺のだ。当然だ。マケライネンのことを教えた、そして『男たちの朝』を譲った恩があるとはいえ、それが自分の身を挺して守ってもらうことと同等のことだとは思えない。俺はアキに、命を救われたのだ。
アキは次の日、いつもと同じように登校し、いつもと同じようにオドオドしていた。俺たちはもちろん、あの叫びでアキを讃えた。
「あんべたくまぁ!」
授業中に、どこかの教室から聞こえてくることもあった。その来歴は俺たちしか知らないはずなのに、いつの間にか学年中に広まっていた。アキの英雄的行為は、皆の知るところとなったのだ。
男子生徒だけではなく、アキのことをまだまだ遠巻きに見ていた(あるいは
「ひひひひひ。」
妖怪みたいに、いつもアキは笑っていた。
今も、アキの笑う顔を思い出すことがある。
アキの歯は黒くてガタガタで、ひとつひとつが異様に小さかった。奥まっていた目はつぶれ、ただの黒い傷みたいになった。鼻の穴はふくれあがって、太い鼻毛が飛び出た。びっくりするくらいみっともなくて、
ふゆのあさに、ぼくはうまれた。
すごくさむいひだったと、おかあさんがいっていた。
ぼくはとてもおおきいあかんぼうだった。でもなくこえがちいさくて、みんなとてもしんぱいしました。からだはむらさきいろでした。あしはぶるぶるとふるえていました。ぜんしんにびっしりけがはえていました。おおかみのこどもみたいだった。
けはだんだんぬけていきましょうと、さんばさんがいったけど、ぼくはずっとけがたくさんあった。みんなはぼくのことを「ひげおとこ」とよんで、おかあさんはぼくのことを「わたしのおおかみちゃん」といった。
おおかみはつよい。
どれだけさむくてもがまんして、にんげんよりもかしこくて、ふといあしをもっている。ぼくのゆめはずっとおおかみをみることです。よるのもりで、まっくらの、なかで、おおかみをみることが、ぼくのゆめ。