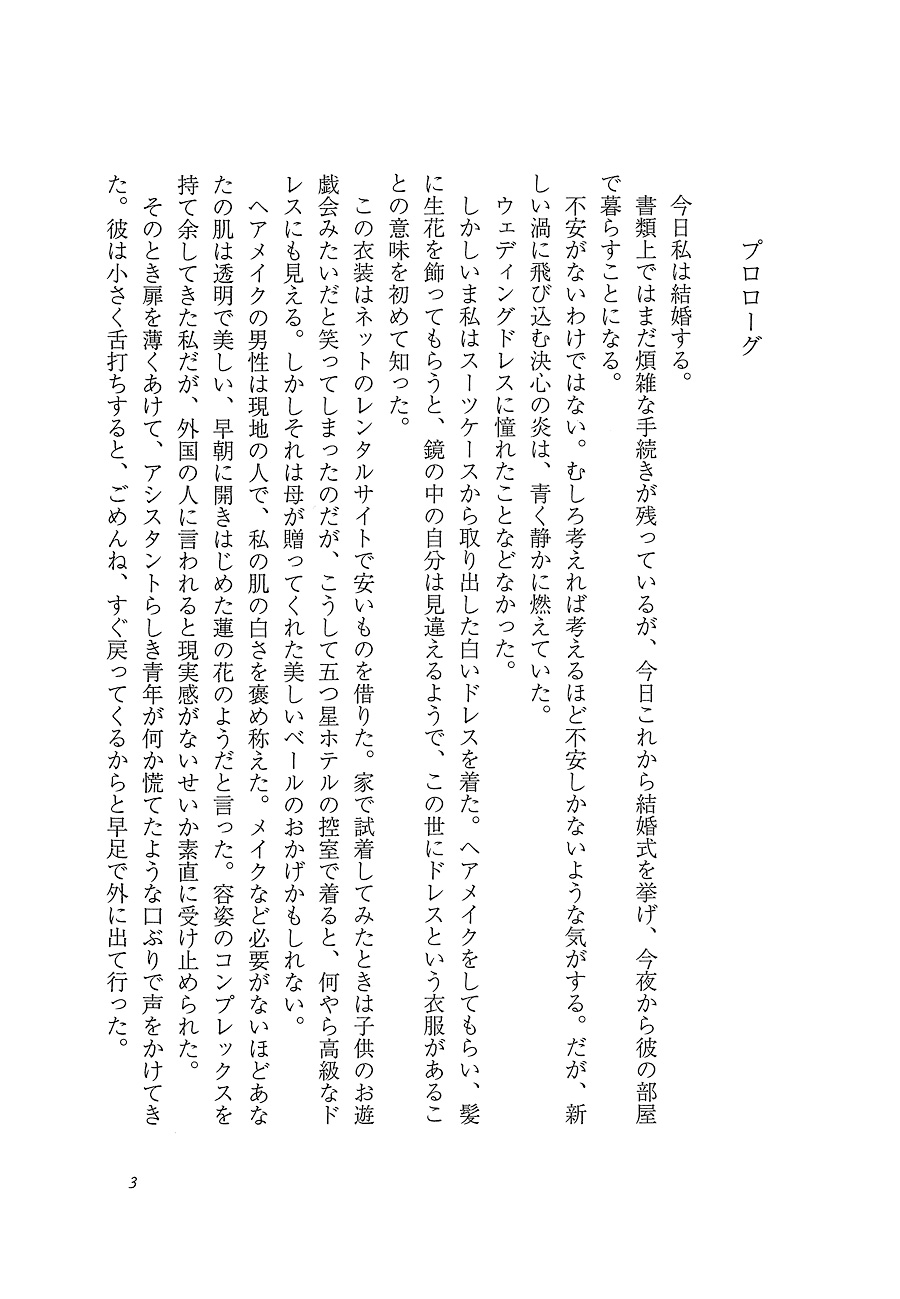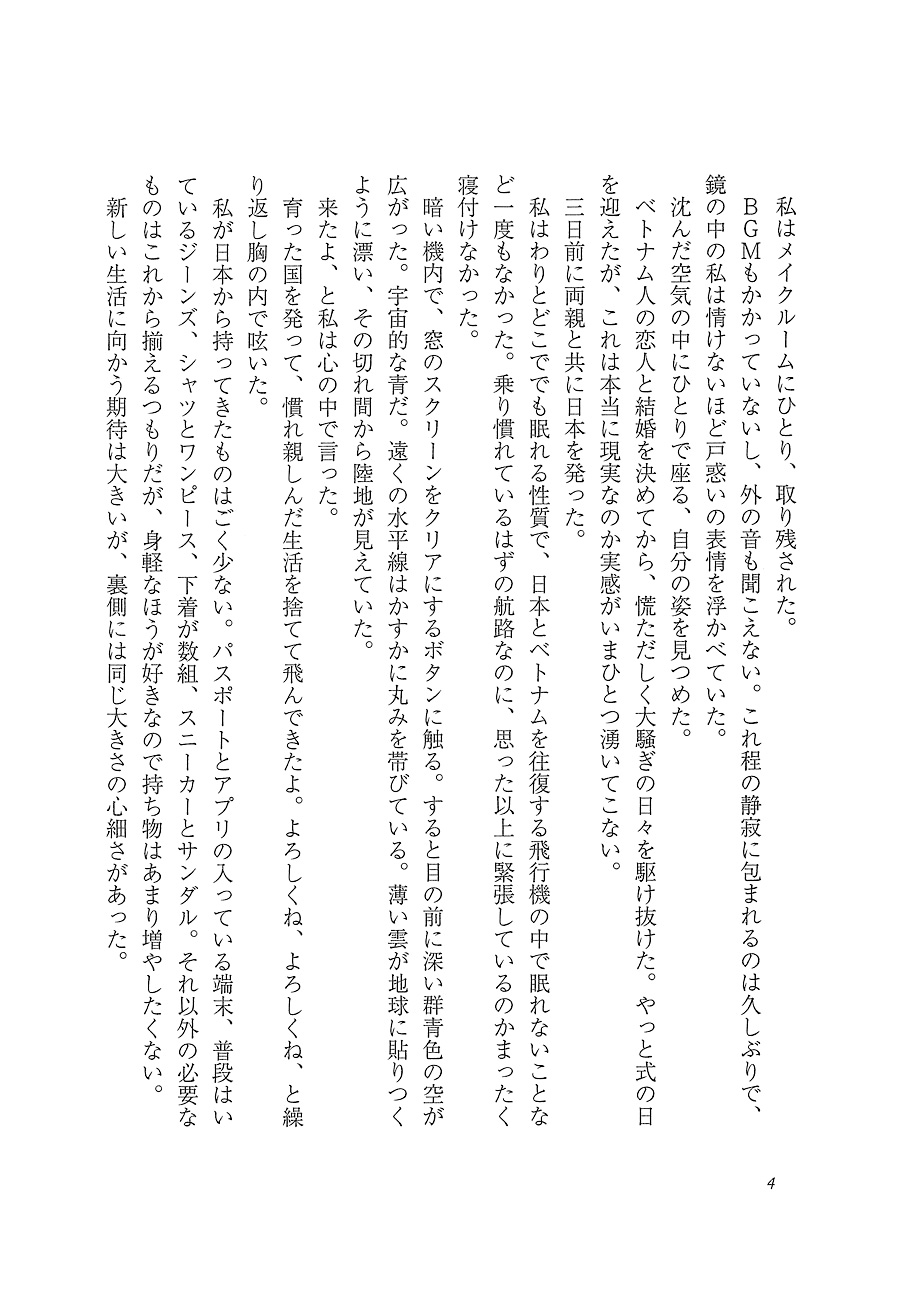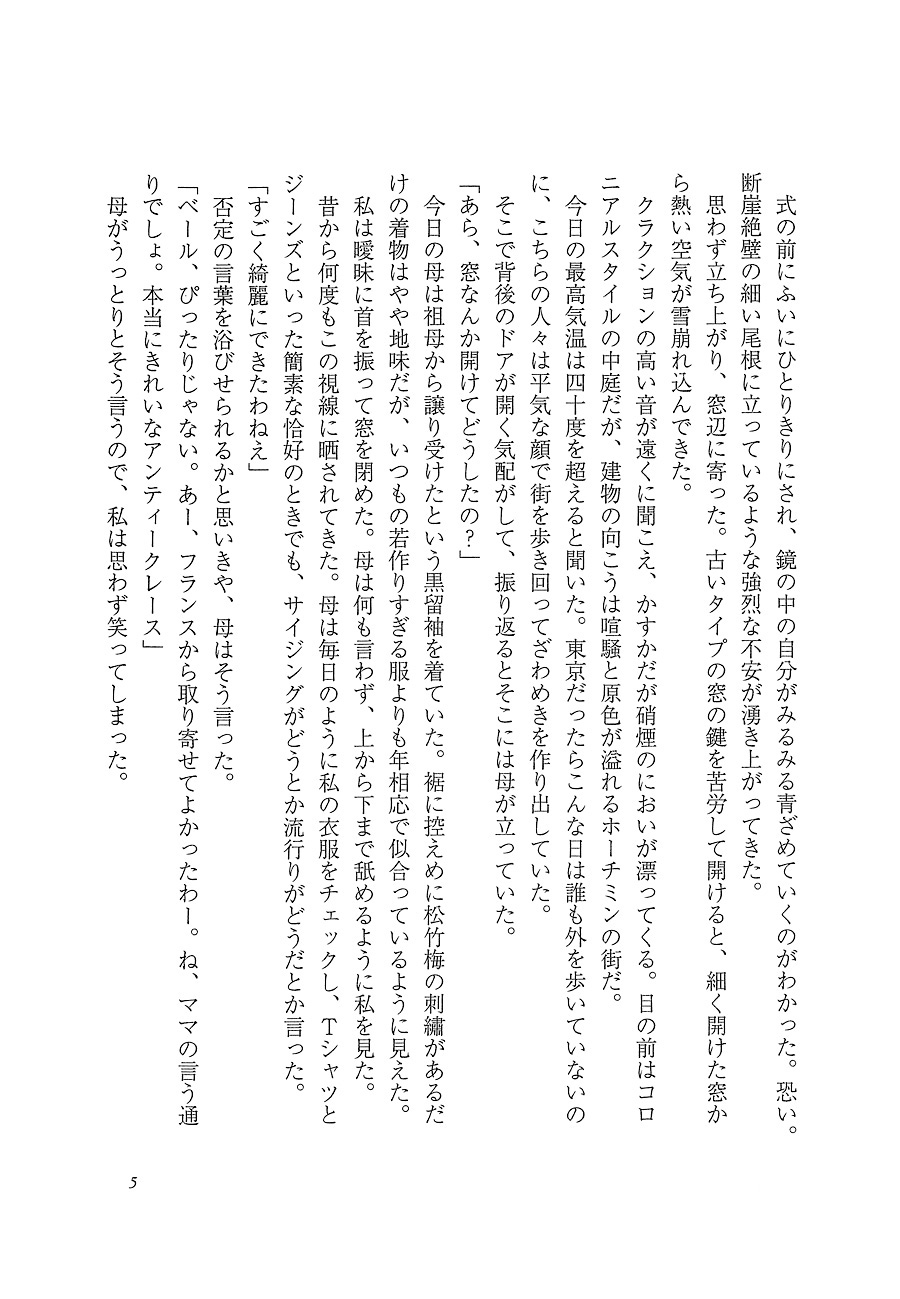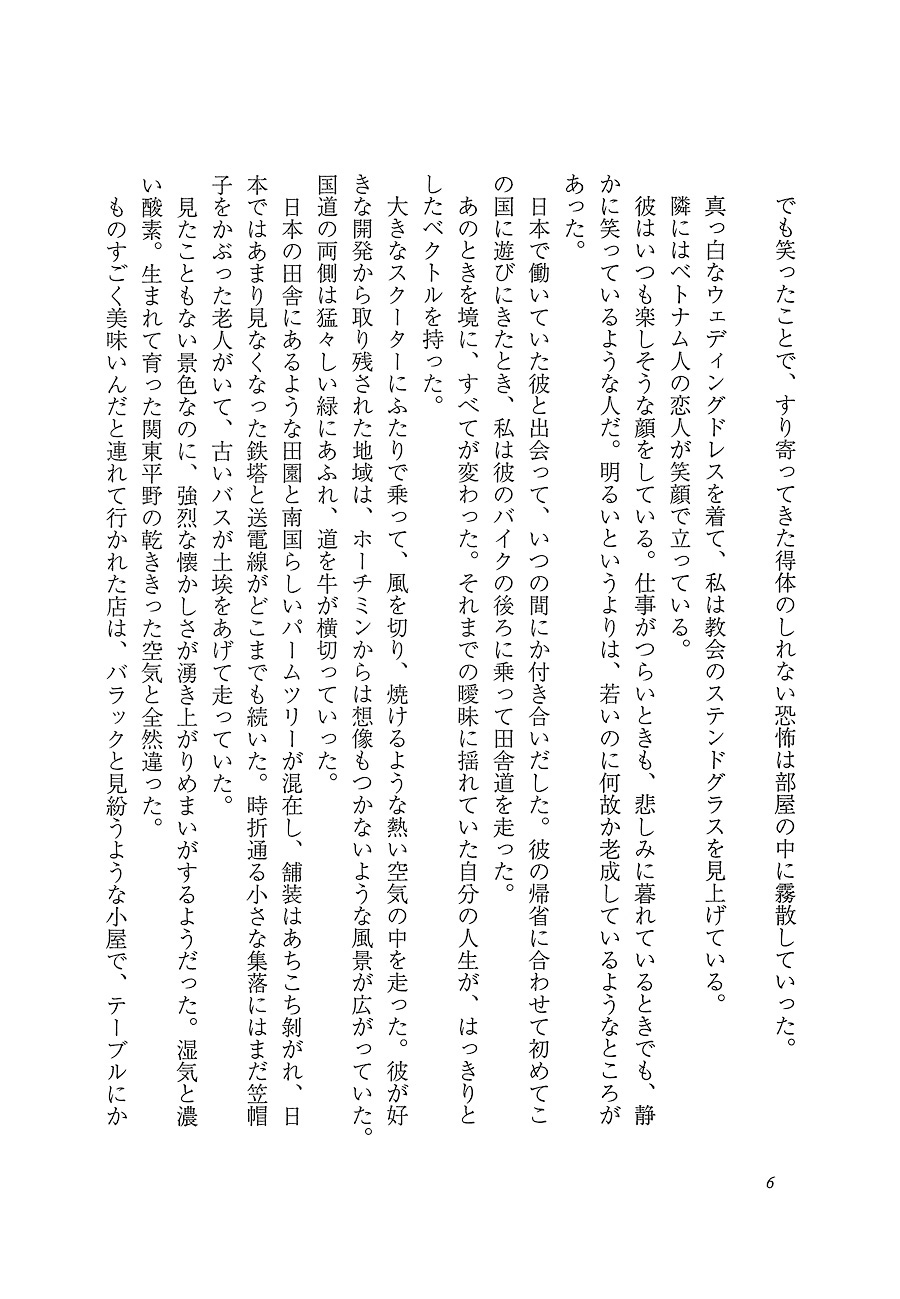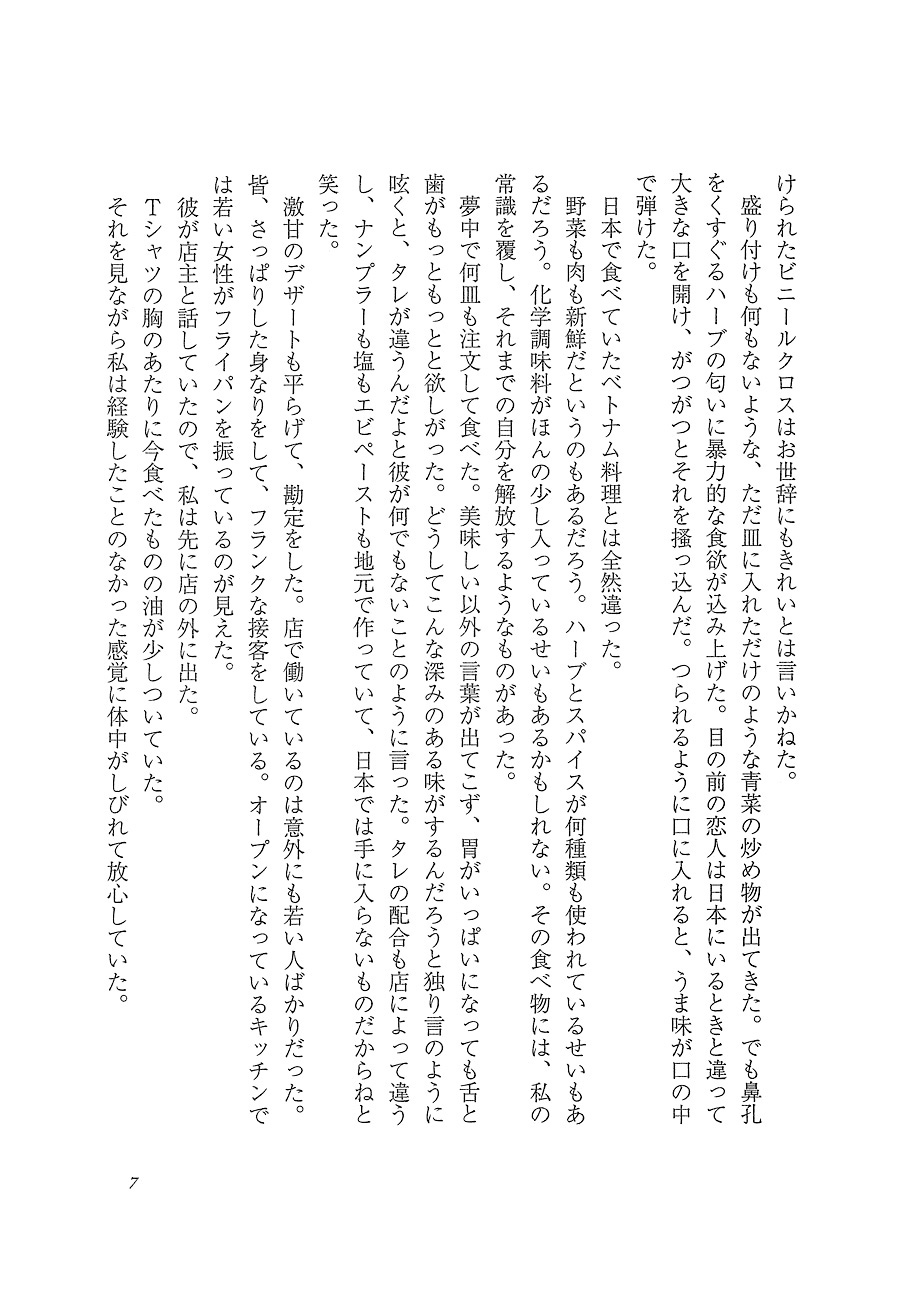毎朝
二年前まで朝の習慣は駅ビルのカフェに寄ることだった。隣の人と肩が触れ合いそうなほど窮屈なカウンター席で、足早に行き交う都会の人々を眺めながらソイラテを飲んだ。雑踏の中で埋もれるようにして、人々の服装が薄着になったり厚着になったり変化してゆくのを見るのが好きだった。近い将来、雑木林の向こうにそびえ立つ大仏を車の中から毎日眺めるようになるとは微塵も思わなかった。
牛久大仏は都が子供の頃に建立された。台座を含めた高さが一二〇メートルという馬鹿みたいな大きさで、送電線が張られた大きな鉄塔よりもはるかに高い。自由の女神の像高だけと比べても三倍はあるという。
田圃と畑しかなかった真っ平らな田舎の真ん中に、縮尺を狂わすような大きさで忽然と現れた立像に、大人も子供も面白がったり眉を
だが都会での一人暮らしを解消して地元に戻って来てから、何故だか視界に入ってくる度いちいち「あ、大仏」と見入ってしまうようになった。東京に住んでいた時、東京タワーを見る度にふと立ち止まっていた気持ちと似て非なるものではあるが。大仏は相変わらず何を言われても気にしない顔で優雅なポーズを取っていた。
車のエンジンを切ると、オーディオから流れていたボサノバとエアコンの冷気も途切れた。バッグを持って外へ出る。暦は九月になったが日差しはまだ真夏と変わらずに強く、手をかざして顔の前に
歩き出すと、そこには大仏と同じような唐突さで作られた新しい町があった。
巨大な平置き駐車場の向こうに、パステルカラーの塀に囲まれたアウトレットモールが広がっている。パームツリーと噴水が配置されたエントランスは海外のアミューズメントパークのようだ。このアウトレットモールは都が東京で暮らしている間に建設された。にょきっと天を衝く大仏と対照的に、這いつくばるように延々と平屋のショップが立ち並んでいる。こちらは広すぎて縮尺が狂う。
真っ平らな関東平野に貼り付くように広がる田畑と雑木林、その中に出し抜けに作られた大仏と
田舎といっても、実は都心から電車で一時間ほどしか離れていない。
このちぐはぐな場所で都は働き、暮らしている。
従業員用の駐車場は客用のものとは別にやや離れた場所にある。モールを囲む壁は目の前に見えているのだが歩くと存外時間がかかった。開店前の時間には、通用口へ続く舗装された細い道を従業員達が一列になってぞろぞろ歩く。何も遮るものがないので日差しにも風雨にも晒される。
照りつける太陽の下を延々歩いてやっとショップに辿りつくと、社員の中では一番若い
「都さん、おはようございます。暑いですねー」
彼女は顔を上げて人懐こく笑った。
「おはようございます。ほんとうに暑いね。駐車場から来るだけで汗だく」
「空調最強にしときましたから涼んで下さいー」
天井に嵌め込まれたエアコンの真下に立って埃っぽい冷気を顔に浴び、胸のボタンをひとつ外して首元をはたはたさせた。秋冬ものの厚手のカットソーで来たので大汗をかいてしまった。平屋のショップはダイレクトに気候の影響を受け、通勤路と同じで夏は蒸すし冬は底冷えする。今まで勤めたことのあるテナントビルはどこも室温が安定していたから最初は驚いた。
早番のスタッフが揃って、レジを開けたり掃除をしたりしていると業者が納品にきた。軍手をはめてカッターで次々と大きな段ボール箱を開けてゆく。今日はまだ週の始めなのでそれほどの量はない。伝票をチェックしつつ皆で手際よく並べてゆくと開店前にはショップの中は整った。
都は外からウィンドウをチェックしようとクロスを手に外へ出た。左右に軒を連ねるショップの前に客らしき人影は見えない。日差しは白く、石畳を模した通路が光っている。向かいの店舗の女性が脚立に乗ってディスプレイされていた造花の
お盆の繁忙期が終わると、本格的に秋冬ものが入ってくるまでモールはしばし眠ったようになる。今日は
その日の昼前、本社の女性がふいにショップへやって来た。
「あれ、長谷部さん! びっくり! どうしましたか」
杏奈が挨拶より先に素っ頓狂な声で言った。彼女は本社のマーチャンダイザーで、週末から翌週にかけての販売戦略伝達のため木曜日か金曜日にいつもやって来る。週頭の午前中に現れることはまずないので都も少し驚いたが、それよりも本社のMDにあけすけな物言いをする杏奈にひやひやした。
「つくば店のほうに用事があったから寄ってみたの。これ差し入れ」
わーありがとうございます、と杏奈が洋菓子の紙袋を受け取った。
長谷部は都に「店長は休憩中かしら」と小声で聞いてきた。
「あ、それがついさっき電話があって、お子さんが
「……そう、お子さんが」
長谷部は拍子抜けしたような顔をした。
「何かご用事でしたか? 携帯に連絡してみましょうか?」
「いいのいいの、用事じゃないの。携帯だったら私も知ってるから。本当についでに来ただけだったからいいの」
そんなふうに言われるとますます何かあったのではないかと勘ぐってしまうが、それ以上は何も言えず気まずい空気になった。
「
質問の意図が掴めないまま都は首を振る。
「今日は違います。作ってくる日もあるんですけど」
「じゃあお昼一緒にどう? ここ回転寿司あったよね。暑いから酢飯が食べたくて」
長谷部が妙に熱心な様子で誘ってきた。
「え、でも」
そばで聞いていた他のスタッフが「お店暇だしゆっくりどうぞ」と言ってきた。何となく釈然としない気持ちのまま都は彼女に続いてショップを出た。
モールはやはり人影が少なかった。犬をつれた人や年輩の夫婦が、買い物というより散歩をするようなのんびりした顔で歩いている。お盆の時の人でごった返した様子が夢のようだ。
寿司店も空いていて、詰めたら六人は座れそうな大きなテーブル席に通された。
この店に入るのは初めてだった。間口に比べて中は広々としている。つけ場には板前が数人おり、店の奥には別に調理場があるようだし、フロア係の女性も多い。テーブルに置かれていたメニューを見ると値段は決して安くはなく、街道沿いにあるパネルで注文するような家族向けの回転寿司より高級な感じがした。ふたりともサービスランチを注文する。
従業員はモール内の飲食店で食事をしてはいけない、という決まりは特にない。人出の多い時は店が忙しくて行けないし、そういう時でなくても普通の店より割高なのであまり行かないだけだ。時々フードコートには行くが、それだってこうして本社の人が来た時や、地元の友人が買い物に来てくれた時に休憩をもらって一緒に寄るくらいだ。
長谷部とふたりで食事をするのは初めてだった。打ち合わせの時も店長か他の社員が一緒だったので、面と向かうと何を話していいかわからない。都はテーブルの横を回ってゆく寿司を所在なく見ていた。
「与野さんはお店、もう一年くらいでしたっけ?」
彼女がふいに口を開いた。
「はい。去年の六月からなので一年と三か月くらいです」
「そう。すっかり慣れた?」
「慣れた部分もありますけど、まだまだ至らないところもあるなあって思います」
言葉を選んで返事をする。査定のようなことをされているのかもしれないと思うと緊張する。そして長谷部は黙り込んだ。話題話題と思いながら粉っぽい緑茶をすする。
「この夏もあのフリルカットソーはよく動きました。マカロンカラーのシリーズは全色入った日になくなって」
「そうね、追加分も予定より早く完売したみたい。来年はフレンチスリーブも作りたいってデザイナーが言ってた」
「わー、私もそれは欲しいです」
数年前に爆発的に売れて、今も売れ続けている春夏のカットソーの話などをした。
「お待たせしました」
その時、都たちの前に割り込むように寿司の皿が差し出された。顔を上げると、若い職人が何故かそっぽを向いたままこちらが寿司を受け取るのを待っていた。
何この人、と反射的に思った。寿司屋の板前が客の顔を見てにっこりする必要はないと思うが、それにしても態度が悪い。照れなのか仕事が嫌なのか、ずっと顔を横に向けたままだった。
仕方なく受け取ると次々と皿を渡された。長谷部と分け合って割り箸でつまんで口に入れ、ゆっくりと噛みしめる。寿司を食べたのは久しぶりで、確かにこう暑いと酢飯の風味が嬉しかった。シャリは大きくてネタはそこそこ肉厚だ。サービスランチは寿司十貫に加え巻物とみそ汁が付くようなので、男の人でも満足する量だろう。だが味は期待してしまった分、落胆が大きかった。スーパーの惣菜売場で売っているものとそう変わらない。
かつて食べた青山の高級寿司の味がふと蘇る。幸せな記憶とは言いがたいが、宝石のような寿司だった。あんな美しくて衝撃的においしい寿司を口に入れることはもう一生ないかもしれない。
今日はなんだかよく東京でのことを思い出すなと、都は口元を手でおさえ大きなシャリを
少し空腹が落ち着くと、回転寿司は回転寿司というジャンルであってこれはこれでいいものだというふうに気持ちが持ち直してきた。
長谷部はいつもわりとモード寄りで隙のないスタイルなのだが、今日はベージュのてろんとしたチュニック丈のブラウスに黒のスキニーパンツとやはり黒のバレエシューズで、シンプルというよりはかなり気の抜けた服装だった。四十は超えているらしいと誰かが言っていた。いつもはその年齢よりはるかに若く見えるのに、今日は髪も艶がなく、ファンデーションが小鼻のまわりでよれていて年相応に見える。どう見ても調子が悪そうだ。なのに本社から二時間以上はかかる不便なアウトレットまでわざわざやって来て、特に親しくもない自分を食事に誘ってきたのは、やはり何か言いたいことがあるのではないだろうかと都は思った。
「あの、店長に何かお話でしたか?」
先ほどと同じ質問を口にしてみた。ぼんやりと散漫になっていた彼女の視線が都の顔へと戻ってきた。かすかに彼女は微笑む。
「……ちょっと伝えたいことがあって」
「私でよければ伝えておきましょうか」
「実は私、子供ができたの」
「え?」
「まだみんなには言わないでもらっていいかしら。ぎりぎりまで働く予定だし、産休が明けたらすぐ復帰するつもりだから」
「それは、あの、おめでとうございます」
長谷部が結婚しているという話は聞いたことがなかったので、都は一瞬口ごもってしまった。
「ありがとう。でもおめでたいかな」
「おめでたいに決まってるじゃないですか」
「
堅い表情で彼女は言う。照れではなくて本当にあまり嬉しくなさそうでどういう返答をしていいか困惑する。
「体調は大丈夫なんですか? つわりとかは?」
「大丈夫って言いたいところなんだけど、先週は二日くらい休んじゃって」
「そうなんですか、今はお体大事にしてください」
「ありがとう。与野さんは優しいね」
そこで「お待ち」と荒っぽい声が降ってきて、再び板前が寿司を突き出してきた。顔を上げると、やはり彼はそっぽを向いて腕だけで投げやりに鮪の乗った皿を差し出している。
今度はそれを受け取らなかった。何故だか大きな怒りの塊が胃の底から突き上がってくるのを感じた。
普段は店の人の態度に違和感があっても、長年販売員をしている都は店員の気持ちが分かるので、怒ったりクレームをつけたりしたことは一度もなかった。
けれど不思議なほど不快な気持ちが抑えられなかった。都が皿を受け取らず、板前を睨んでいることに気がついた長谷部は戸惑って彼と都を交互に見た。そして彼女が代わりに手を出そうとした時、都は強い口調で言い放った。
「さっきからどこ見てるんですか」
板前がぎょっとしたように顔を向けた。都は正面からその男の顔を見た。思っていたよりも若い。馬面、というのが都の頭の中に浮かんだ第一印象だった。背が高くやや猫背で、つまらなそうに結んだ口は大きくて唇が厚い。目は大きいが重そうな
「いくら何でも失礼ですよ、バイトの人ですか?」
隣のテーブルにいた客がちらりと都のほうを見た。彼の削げ気味の頬に徐々に赤味がさして、耳の先まで色が変わっていった。やがて「すみませんでした」という形に口をもごもごさせ都の前に寿司の皿を置いた。そして逃げるように背中を向けてつけ場に行ってしまった。
「与野さん、大丈夫?」
感情を抑制できなかったこと、その羞恥と、屈辱にも似た気持ちが入り混じり、本当は泣きたかったが上司の前なのでなんとか
「あの、どうもすみません。食事中に変な空気にして」
取り繕うように何とか笑って都は頭を下げた。長谷部は「いいのいいの、気にしないで」と顔の前で
「アウトレットの中のレストランなんてこんなものよ」
慰める口調で彼女は言った。都は一瞬動きを止めた。
自分のショップも何か不備があったら「アウトレットだから」とやはり言われるのだろうか。すっかり食欲がなくなり都は箸を置いた。

仕事を終え運転して家に帰る。実家に戻ってアウトレットの仕事が決まった時に、父に半額だしてもらって買った中古の軽自動車だ。
二十分程の道のりだが、仕事を終えたあとに運転するのはいつまでたっても憂鬱だ。何しろ田舎で街灯が少なく駅に近づくまで真っ暗な道が続く。東京でぎゅうぎゅうに混んだ地下鉄の中、身動きできずに見知らぬ男の酒臭い息を嗅がされて帰るのとはまた違う種類のストレスだ。
携帯に父親から買い物リストが送られてきていたので沿道の大きなショッピングセンターに寄った。アウトレットに比べたら小さいが、それでも
昼、寿司屋の店員にクレームをつけてしまったことでの動揺がまだ収まっていなかった。きっと人に話したら、文句を言われた方ではなくて言った方なのにどうしてくよくよするのかと不思議がられるだろう。自分が理に適わないことで憂鬱になっているのだということは都にもわかっている。ただ、言いたいことを言う、ということが必ずしも気の晴れることではないことを最近都は痛切に感じることが増えた。気持ちを抑えて黙っていたほうが楽なことも沢山ある。
気晴らしに雑貨店や書店を覗いてみたい気がしたが、寄り道すると果てしなくなりそうでスーパーにだけ寄って店を出た。常磐線の駅を越え、大型マンションが立ち並ぶ通りを抜けたところに都の家はある。新しく開発された住宅地なので周囲の家はみな新しい。家に着いて父親のセダンの隣にそろそろと車を入れる。
玄関を開け二階へ上がると、エプロンをした父が廊下に顔を出した。
「ただいま。梨も買ってきたよ。ママ、好きだったと思って。ママは?」
ビニール袋を渡しながら都は言った。
「今日はもう寝ちゃったよ」
「もう? また具合悪いの?」
「いや、今日は暑い中ずいぶん散歩したから疲れたみたいだ。眠れる時は寝たほうがいいって先生も言ってたし、まあいいだろ」
「そっか。先に着替えてくるね」
自室で部屋着に着替えながら、明日は休みを取っているし、母が寝ているならやはり寄り道してくればよかったと思った。一度帰ってから出かけるのは気が進まない。夜の運転は恐いし、父親もいい顔はしない。
父と向かい合って食事をした。音量の絞ってあるテレビの画面を眺める。
「あ、これ、おいしいね」
鶏肉のソテーがいつもと風味が違っていて都はそう言った。
「ヨーグルトで漬けてみたんだ、うまいだろ」
「なにパパ、どこでそんなの覚えたの」
「朝のテレビでやってた。まだあるから明日の弁当に入れていっていいぞ」
得意げな顔で父は笑った。
「明日は休み。ママの病院」
「そうだったな。助かるよ」
父はまだ五十代だし、最近カジュアルな服装が板についてきて以前より若く見えるようになった。ふたりで出掛けると年の離れた夫婦に間違われることもあるくらいだ。
都は前よりずっと父と気が合うと感じている。以前は苦手意識があったが、今は母の看病という同じ使命を持つ仲間意識もあって、軽口も叩けるようになった。
「パパ、片付けはやっておくから先にお風呂入ったら」
「うん。じゃあ頼む」
父がいなくなったキッチンは急によそよそしくなって、都は手早く後片付けをした。
灯りを落とそうとして、果物籠に入れておいた梨をしばらく見つめる。ひとつ手に取り、果物ナイフで櫛形に切り、
──ママへ。ピンクの蓋のタッパーに梨が入ってるから食べてね。ミャー。
丸顔の自分の似顔絵とハートも添える。
壁の時計を見上げるとまだ十時前だった。テレビと電灯を切ると、深夜のようにしんとした。自室へ行ってベッドを見たとたん、都は吸い寄せられるようにしてそこに転がった。
都の部屋は三階建ての家の一階にある。庭に面したこの部屋は元々夫婦の寝室として設定されていて、この家の中でリビングの次に広い。母は屋根裏部屋風の三階の小部屋を気に入ってそこを自室にし、父は二階のリビング脇の和室で寝起きしている。
一階の寝室のウォークインクローゼットは大きくて、都の大量の服が全部収まり最初は嬉しかった。一人暮らしの部屋から持ち帰ったシングルベッドや小型のテレビ、一人掛けソファを置いてもまだかなりの余裕がある。
東京で住んでいた部屋よりもずっと広い寝室で都は夜を持て余している。昼間の寿司屋で味わった最悪な気分がやっと薄れてきて、カバーをかけたままのベッドの上で眠りに落ちた。

翌日は母の通院日で、隣の市にある総合病院へ出かけた。自宅から病院まで直線距離にするとそれほど遠くはないのだが、電車とバスの両方に乗る必要があり結構時間と体力を使う。母は運転ができないので、都か父が車を出して付き添うのが常だった。
県道と農道を駆使して最短距離で病院へと向かう。田んぼの稲穂が色づいてきていて、
予約をしていても総合病院の待ち時間はとても長い。どうせ一時間以上は順番が回ってこないのだからお茶でもしに行こうと誘うのだが、母は「急に呼ばれるかもしれないし」と言って、診察室のドアが見える長椅子から動こうとはしない。
「売店行って雑誌買ってくるね。ママも飲み物か何か要る?」
一応聞くが母は首を振った。廊下をエレベーターへ向かって歩きかけ、癖で後ろを振り返る。母はじっと座って目をつむっていた。
若返った父と逆に母はすっかり老け込んでいた。太ったというほどではないが全体的に
元気な頃、母はごく普通の中年女性だった。基本的には専業主婦だが、着付けと簡単な和裁ができるので、近所の美容室に頼まれると成人式や七五三の時に着付けの手伝いをしたりしていた。屈折したところも意地悪なところもなく、普通に陽気な母親だった。
その母が病気で別人になってしまった。母の病気は、簡単に言ってしまえば更年期障害だった。
父からの電話で母の具合がよくないと初めて聞かされたのは、仕事と遊びで毎日目いっぱいで親の存在など思い出しもしない日々の中、突然のことだった。社会人になって父親から直接電話がかかってきたのはそれが初めてだった。精密検査をすると聞いていきなり顔を
母は電話口には出なかった。父がその時言ったことに耳を疑った。
「ママは今、人と話す気力がないんだって」
人? と都は思った。母のおなかから生まれた自分は母とこの世の中で一番他人ではない間柄だったはずなのに、いつそんなに遠く離れてしまったのだろうと
検査の結果はやはり父からの電話で、更年期障害だと聞かされた。その時都は安堵のあまり笑った。なーんだ更年期障害か、じゃあ大丈夫だね、とも言った。二十代の都には、それは中年以降の女性がかかる
だがそうはいかなかった。母は不定愁訴を訴え続け、激しく情緒不安定で、症状は悪くなるばかりだった。様々な治療を試してみたが改善されず、婦人科の担当医に勧められて精神科にも通院するようになった。
都は生まれて初めて更年期障害について自分から調べ、いかに症状の個人差が激しいものか、治るまでの期間も長ければ十年以上に及ぶ場合もあることや、鬱病との境目が曖昧なものであることも知った。母の体調と精神状態は複雑に入り組んで、事態は家族が想像していたものより深刻になった。
父は母の看病のため勤め先を一時休職し、都も結局仕事を辞めて実家に戻ることになった。都が仕事を辞めた理由は母のことだけではなかったが、大きなきっかけにはなった。父は最近復職したが、残業も少なく休暇が取りやすい部署へと異動を希望した。父ははっきりとは言わないが、それが閑職だということは都にもわかっていた。
家族が病気になるということがどんなことか都はまったく知らなかった。一番苦しいのは病気をしている本人だし、自分よりも父親のほうが大変な思いをしていることもわかっていた。けれどそれは去らない台風の中に突然放り込まれたような出来事だった。
つらすぎて、憂鬱すぎて、あまりにシャレにならなさすぎて、都は未だにこのことを詳しく人に話せないでいた。
母が昔の母に戻って、都が自分のことだけを考えていい日々を取り戻せるのはどのくらい先なのだろう。そんな日はこないのかもしれないと思うと背筋が寒くなる。母のことが嫌いなわけではないのに、そのことを考えると気持ちが鉛のように重くなった。
暗くなった気持ちを拭おうと都はファッション雑誌を買った。それを持って母のところへ戻ると、いつもと違う光景を目にして立ち止まった。
待合室のソファ、先程と同じ位置で、母が自分で持ってきたらしい文庫本に目を落としていた。診察を待っている間に何か読んでいる母を都は初めて見た。
「ママ?」
恐る恐る呼ぶと母は本から顔を上げ、首を
「どうしたの? なんかあった?」
都が答える前に受付の女性が母親の名前を呼んだ。
診察室に入ると、医師の正面に母が座り、後ろの補助椅子に都は腰を下ろした。
担当医は体格がよく厳つい風貌の壮年男性だ。白髪頭を短く刈り込んでいて、霜のおりた冬の芝生みたいに見える。白衣より柔道着が似合いそうだ。以前は違う医師にかかっていたのだが、その先生が病院を移り、春から彼が担当医になった。
母の診察の時、それが婦人科でも精神科でも父か都のどちらかが付き添う。母がしきりに「先生の言うことの意味がわからない。聞いても覚えられない」と不安を訴えたからだ。確かに医者の説明というものは、向こうは噛み砕いているつもりでも専門用語が混じっていたりして集中しないと理解できないことがある。
問診を終えると先生は大きな笑みを見せた。
「うん、だいぶいい感じに安定してきましたね」
母がどんな表情をしているかは都の位置からは見えない。こくりと
「お薬、今回からそろそろ減らしていきましょう」
きっと母親よりも都の方が驚いた顔をしていたに違いない。医師は都の方に顔を向け「次回から、お嬢さんは外して下さって大丈夫ですよ」と柔らかく言った。
母が良くなってきている。そう思うと体の底から嬉しい気持ちが湧きあがってきた。母と手を取り合って笑い合いたかったし、すぐにでも父に電話をしたかった。だがぬか喜びをしてあとでがっかりするのも恐ろしく、都は顔に力をぐっとこめて無表情を装った。
本当? 本当に? やっと憂鬱な日々から解放される?
会計をして調剤薬局に寄っている間、ずっと胸の内で呟き続けた。母も同じ気持ちなのだろうか、喜びを露わにはせず平静な様子だ。
病院を出ると車でスターバックスに寄った。病院の帰り、母の調子が良ければほんの少しドライブし、どこかカフェに寄るのが習慣になっていた。ケーキと飲み物を買って向かい合うと、母の表情は家を出た時に比べて見違えるほど明るく、都はもう嬉しさを堪えきれずに言った。
「ママ、お薬減らせるって、本当によかったね!」
はにかんだ様子で母は頷いた。
「うん、ありがとう。先週あたりからずっと調子がいいの。朝も起きられるし」
母は手にフォークを持ったまま、ケーキを食べることも忘れた様子で続けた。
「今の先生になってずいぶん薬も変えてくれたし、よく話も聞いてくれるから」
「そうだね、いい先生だもんね」
「前の人はひどかった。きんきん喋って恐かったし、デリカシーがなくて」
「まあねえ、元気な先生だったよねー」
以前の担当医は若い女医で、母とは確かに相性が悪かったかもしれない。けれど都にはそれほど悪い人には見えなかった。母は人の好さそうな見かけと違い、案外気難しいところがある。
母は息を
「ねえ都、ママね」
都はどきりとする。思い詰めた顔で母が何か言い出す時、いいことだった
「ママ、もう大丈夫な気がする」
「……ほんと?」
「都にもパパにも気を使わせて、時間を奪って、本当に申し訳なかったってママ思ってる」
「そんなことないよ」
都は語気を強めた。
「だからもう、アルバイトじゃなくてフルタイムで働いていいのよ。パパにもそう言うつもり。会社まで辞めさせてごめんね。今までありがとうね」
嬉しいはずのその言葉に、何故だか鋭い痛みを感じて都は絶句した。動揺を悟られまいとして娘らしく唇を尖らせる。
「ママのために会社辞めたんじゃないよ。それに今の仕事、ただのバイトじゃなくて時間労働契約で一応社員なんだよ。社会保険も入ってるし」
「そっか、ママ、世間知らずでごめんね」
都は慌てて首を振った。
「ううん、ちゃんと言ってなかったもんね。でも焦らないでゆっくり治していこうね。私もパパもついてるから。さあ、ケーキ食べよう!」
母は微笑んで頷いた。都も笑い返す。喜びと痛みが皿の上のマーブルケーキのように入り混じっていた。

九月の連休、モールでは大セールが企画され、都の勤めるショップにも夏物を売り切るため在庫が山のように届いていた。
このアウトレットにはハイブランドはほとんど入っておらず、有名な巨大アウトレットモールに比べたらぱっとはしない。だが広大な駐車場が無料ということもあり、休日には近隣の住民がレジャーがてら日常の買い物にやって来て混雑する。
連休は天候に恵まれ、モールは過ぎたはずの夏が戻ってきたような人出となって毎日へとへとになるまで働いた。ところが連休の最終日、運悪く台風に直撃されてしまった。
ショップの列には大きく軒が張出していて店を巡るのに傘は必要ないが、それでも荒天の中、アウトレットにやってくる客はごく少ない。
開店してもまったく来客がなく、都と店長で、届いたばかりの秋物をマネキンに着せることにした。昨日の段階で連休での売り上げ目標に達していたので、店長は機嫌がよかった。
「そういえば長谷部さん、赤ちゃんできたんだってね」
店長が顔を寄せてきてそう言った。
「あ、はい。聞いています」
「なんだかあんまり具合がよくなくて、早めに産休に入るかもって」
「そうなんですか」
「付き合ってた人と急いで籍入れるらしいよ。相手の人、繊維メーカーのマネージャーなんだって。マネージャーってことはもうずいぶん年なのかな。略奪婚だったりして。でもまあ、経済的にも頼りになりそうだから安心して産めるんじゃないかな」
都は「それはよかったですねー」と彼女の目を見ないように返答した。
店長は若い時に社内結婚してもうふたりの娘がいる。仕事熱心な人ではあるが、本社勤務の夫やその周辺から社内情報を聞き出しては耳打ちしてくるので対応に困る時がある。噂話に興味がないわけではないが、彼女の話には大抵何かの意図や愚痴が含まれているので都は注意深くなっていた。
「本社もさ、早めに後任の人を決めてくれないと困るよね」
同意を求められて都は「そうですねー」と曖昧に頷いた。
長谷部は体調不良で二週続けてショップに来なかった。代理の若い人がやって来て販売戦略の打ち合わせと週末の手伝いをしていったが、店長はそれに対応するためシフトの休みを返上して連休はぎっちり出勤していた。両親と二世帯住宅で同居している彼女は急な出勤でも対応しやすいそうでそこは有難い。
「来月バイトの人、ひとり辞めるじゃない。補充してもらう話があったんだけど、それもうやむやだし」
独り言めいた口調で店長は言った。都はマネキンにストールを巻き付けながら聞き流す。
「ねえ、与野さんて、やっぱり週五日入るのはきついかしら」
はっきり聞かれて都は店長の方を見た。
「こんなところで聞いてごめんね。事情があって時間勤務なんだもんね。でも与野さんは何でも安心して任せられるし、フルで入ってくれると本当に助かるんだ。一応頭に入れておいてくれるかな? 駄目なら駄目でいいから」
「あの」
都は店長に向き直った。
「シフトもう少し増やせるかもしれません」
「え、本当に?」
店長の顔がぱっと輝く。都は慌てて顔の前で掌を振った。
「今すぐにはお返事できないんですけど、実は家族の体調が悪くて週四日だったんです。でもだいぶ快復してきたので」
「そうだったの。そういうことならちゃんとお家の方と相談した方がいいね。でも早めに考えてみてくれたら助かる」
店長は都の二の腕あたりを親しげに叩いてレジのほうへ戻って行った。
都は彼女に触れられたあたりに目を落とし、職場の上の人に言うのは早かったかもしれない、もう少し様子をみて、母が一時の気分だけで「もう大丈夫」と言ったのではないことを確かめてからのほうがよかったのかもしれないと少し思った。でも言わずにはいられなかったのだ。
その日は遅番だったので昼休憩も最後に取った。
アウトレットモールは敷地が広くショップ数も多いので、一カ所だけではなくていくつも従業員用の休憩室がある。都のショップから近い休憩室はその中でも一番広さがあり、飲み物だけではなくカップラーメンや菓子など様々な種類の自動販売機が設置してあり、ここで簡単に食事を済ませる人も多い。
昼食時はとっくに過ぎていたので、休憩室には書類を広げて打ち合わせをしている人達が一組いるだけだった。
彼らから離れた窓際の席に座って、都は携帯をチェックした。高校時代の友人から飲み会の誘いがきていた。ちょうどシフトのない日だったので
ふいに雨が窓を叩く音が強くなって、都はぎくりとする。台風がかなり近づいてきているようだ。この風雨の中、運転して帰るのは気が重かった。あまりにひどい天候だったら父親に迎えに来てもらおうかと考えた。
都はバンダナでくるんだ弁当を広げた。父が夕飯に作る惣菜の余りがあれば、それに自分で焼いた不格好な卵焼きを合わせて弁当を詰めてくる。料理が不得意な都にはそれだけのことでも
店長は子供ふたりの弁当を毎日作っていると言っていた。まだ結婚する展望などかけらもないのに、今からそれが憂鬱だった。もしも結婚するのなら絶対料理のできる男の人がいい、そして店長のように親の近くに住めば助けてもらえることも多いのかもしれないと、頭に浮かぶままにつらつら考える。
週に五日働くようになったら時間契約から正規の社員になれるだろうか。そうしたら月々の給料は上がるだろうし、賞与も貰え、キャリアアップの道も拓ける。
都は箸の先を軽く噛んで、自分がそれを本当に望んでいるのかと考えた。
今のショップは、若い社会人女性をターゲットにしたきれいめの服を扱っている。仕事やデートに着ていけるフェミニンなデザインで、素材も扱いやすいものが多い。都が以前に勤めていた麻やオーガニックコットンを主な素材としたブランドとはまったく客層が違う。
都は十八歳の頃、自然素材を使ったそのブランドの虜になった。一見素朴に見えるが実はとてもデザインが凝っており高価だった。ただの客では月に一枚買うのがやっとだと思い、高校を出て、東京でアルバイト店員になった。ナチュラルラインのワンピースや、ざっくりしたウールのトップスが可愛くて大好きだった。好きで好きでたまらないブランドの服をシーズンの最初から着ることができて都は幸せだった。食費を削ってでもその店の新作を一枚でも多く買うことを迷いなく選び、やがて努力が実って社員に登用された。
今の都はその頃と違って、自分のショップで売っている服にそれほど興味がなかった。仕事だから制服のように着ているだけだ。だが着てみればいいところは沢山あった。化繊とひとくちにいってもぺらぺらなものはほとんどないし、皺にもならず、洗濯も楽で麻などに比べると嘘のように軽い。廉価なので流行りのスタイルを取り入れやすいのもいい。シーズンのはじめにベーシックでサイズがきちんと合っているものを選んでおけば、プロパーの店ほど厳しくないので来シーズンも店頭で着ることができる。
だが正社員になるとしたらどうなのだろうと、都は弁当を食べながら考える。好きでもない服の会社に勤め続けることができるのだろうか。好きなブランドの服だって、最後の方は
いや、そのブランドが好きとか嫌いとか言っている場合ではないのかもしれない。仕事があるだけで有り難いのだ。今はよくても、そのうちこのショップで店頭に立つのは難しくなるだろう。でも正社員になって、内勤や同じグループ内の年齢層の高いブランドへ移ることができればずっと働ける。
来年も着られる服や、正社員になって昇進するには、というようなことを考える反面、都にはたとえば半年先に自分がどうなっているのかうまく想像することができなかった。結婚など本当は宇宙旅行と同じくらい現実味のない遠いことだった。
その時休憩室のドアが開いて、背の高い白い服の男が入ってきた。アパレルの店員とは明らかに雰囲気が違って、都はすぐにあの寿司屋の店員だと気が付いた。
反射的に目をそらしてうつむいた。彼は都の方へは視線を向けず、自動販売機コーナーの方へ歩いていった。
どきどきしながら様子を窺うと、彼は自動販売機でたこ焼きを買っていた。都が座っている場所から四角い休憩室の対角線上になる位置に、彼は横顔を向けて座った。ペットボトルの茶を飲みつつ、たこ焼きをつまんでいる。
向こうの視界に自分が入っていないとわかって、都は少し安心して彼を観察した。短く簡素な髪型で、薄手の白い作務衣を着ている。首筋から肩にかけての線が意外にきれいだ。この前はひょろりとした人だと思ったが、改めて見ると胸と腕には結構筋肉がついていそうだ。
彼はたこ焼きを食べ終わると、ズボンの尻ポケットから本を取りだして読み始めた。あ、本なんか読むんだ、まったく読まなそうな外見なのにと都は思う。
ふと彼が都の方を振り返った。慌てて下を向く。弁当箱を包んで都は立ち上がった。
休憩室の扉に手を伸ばすと、向こうから扉が開いて眼鏡をかけた男性が入ってきた。うつむいて横をすり抜ける。いかにもアパレルの男性らしいデザイン過剰な眼鏡だ。
「お、カンちゃん、久しぶり」
その人が誰かに声をかけたのでちらりと振り返る。眼鏡の人が寿司屋の店員に近寄っていくのが見えた。

台風の影響で営業時間が短縮されるかと思っていたが、結局モールはいつも通りの閉店時間だった。
店長は子供を迎えに行きたいからと早めに帰った。都はアルバイトの子を先に帰してひとりで店を閉め、自分も駐車場へと急いだ。
モールを出ると、大粒の雨が正面から吹き付けてきて、傘をさしていてもみるみるうちに足下とスカートの裾がびしょ濡れになった。風がうなり植栽された細い木がひどくしなっている。
従業員達は身を縮めてぞろぞろと駐車場に向かう。パンプスの中敷きがぶかぶかと水をふくんで気持ちが悪かったが、前をゆく人の踵のあたりだけ見つめ、感覚のスイッチを無理にオフにして黙々と歩いた。
ようやく自分の車に行き着き、乗り込もうと傘を閉じた一瞬で肩から背中までぐっしょり濡れてしまった。何故レインコートを着てこなかったのかと舌打ちしたい気持ちになる。
濡れてまだらになってしまった革のバッグを助手席に放り、車のキーを差し込んだ。いつも通り回したが何も反応がない。あれ? と思ってもう一度差し直して回した。まったく手応えがかえってこない。濡れた前髪を額に貼り付けたまま何度もキーを回すがエンジンはかからなかった。
「もー! なんでよ!」
都はハンドルに突っ伏した。風雨はまたさらに強くなって、フロントガラスには滝のような雨が流れている。寒くて背筋が震えた。
解決策がまったく思いつかず、都は携帯を取り出し父親に電話をかけた。もう家に戻っているはずの時間なのに電話は繋がらない。家の固定電話にも母の携帯にもかけてみたが誰も出なかった。その間にまわりの車は一台一台いなくなる。遠くの照明灯が雨に滲んでいるのを、都は途方に暮れて眺めた。
頭の中が真っ白で動けなかった。こういう時、誰に連絡したらいいのだろう。ロードサービスを呼んだらいいのかもしれないがそれも大袈裟な気がした。東京時代の恋人が頭を
大きな溜め息をついた。落ち着け落ち着け、と口の中で唱える。
腕時計を見ると、モールから駅に向けて出るシャトルバスのことを思い出した。最終の便に急げば間に合いそうだった。
決心して都は車の外へ出た。駐車場にもモールへの道にも外灯は少なく、あたりはとても暗かった。まだ照明の点いているモールのショップの灯りだけが、空から舞い降りた巨大UFOのように雨の中でぼんやり光っている。
大粒の冷たい雨に背中や肩がさらに濡れ、やっとの思いで通用口にたどり着いた時、ずっと向こうのロータリーから四角く光るバスが離れていくのが見えた。あ、もう走っても間に合わない。そう思ったとたんに膝から力が抜けた。立ち止まった瞬間突風にあおられ、傘の骨が音をたてて折れる。思わず手を放すとあっけなく傘が遥か後ろへ飛んでいった。重い雨粒が盛大に顔にかかった。
その時、体の横を大きなビニール袋のようなものが通り過ぎて都はぎょっとした。見ると、こんな天気に薄っぺらのビニール雨合羽を着て自転車に乗った人だった。その人が都の方を振り返った。
「どうした?」
警備員かと思ったら、馬面に眠たげな目の、あの寿司屋の店員だった。
「なに泣いてんの?」
泣いているつもりはなかった。顔が濡れているのは雨のせいだと言いたかったが、都は一言も言葉を発することができなかった。