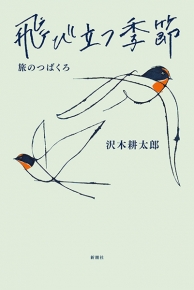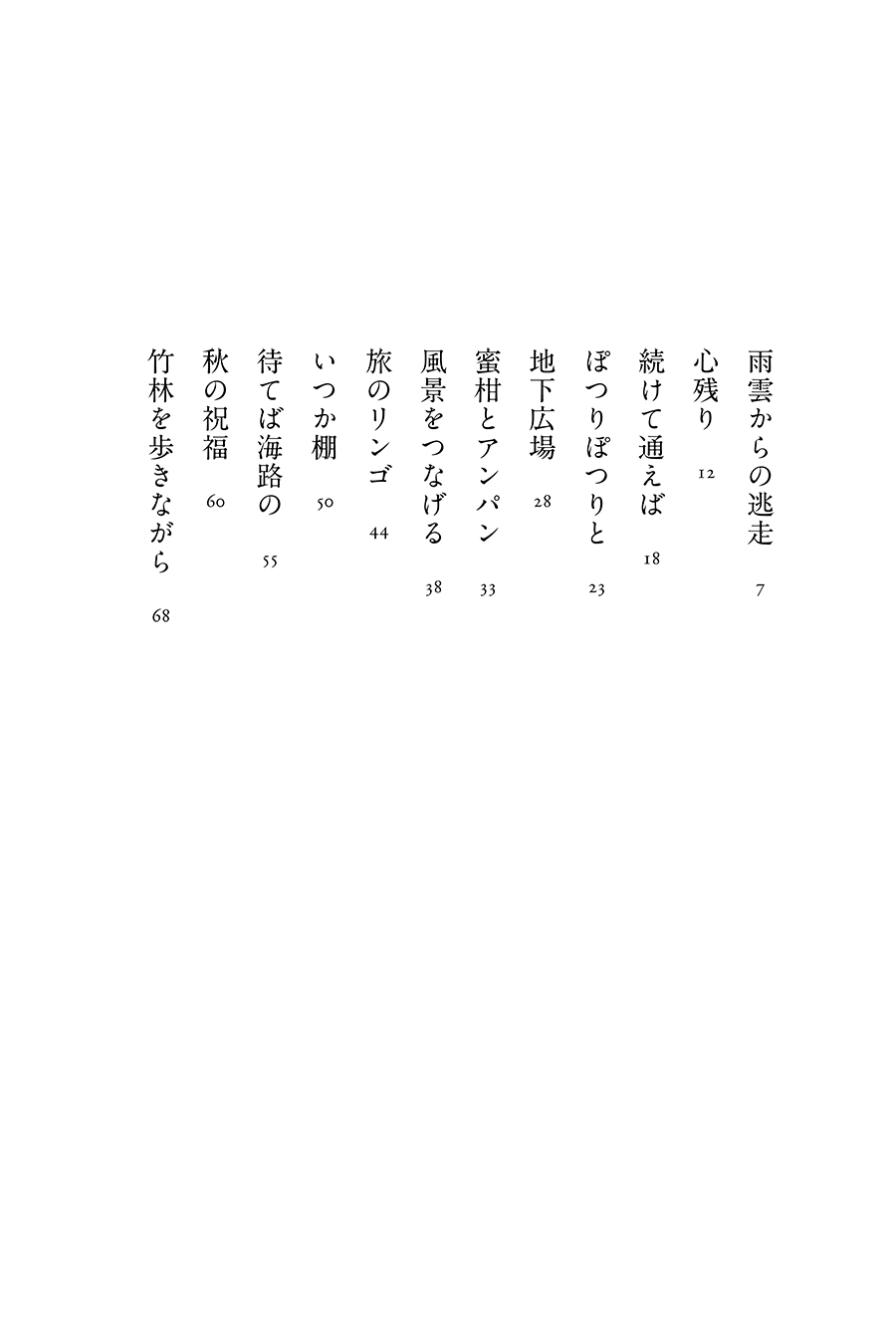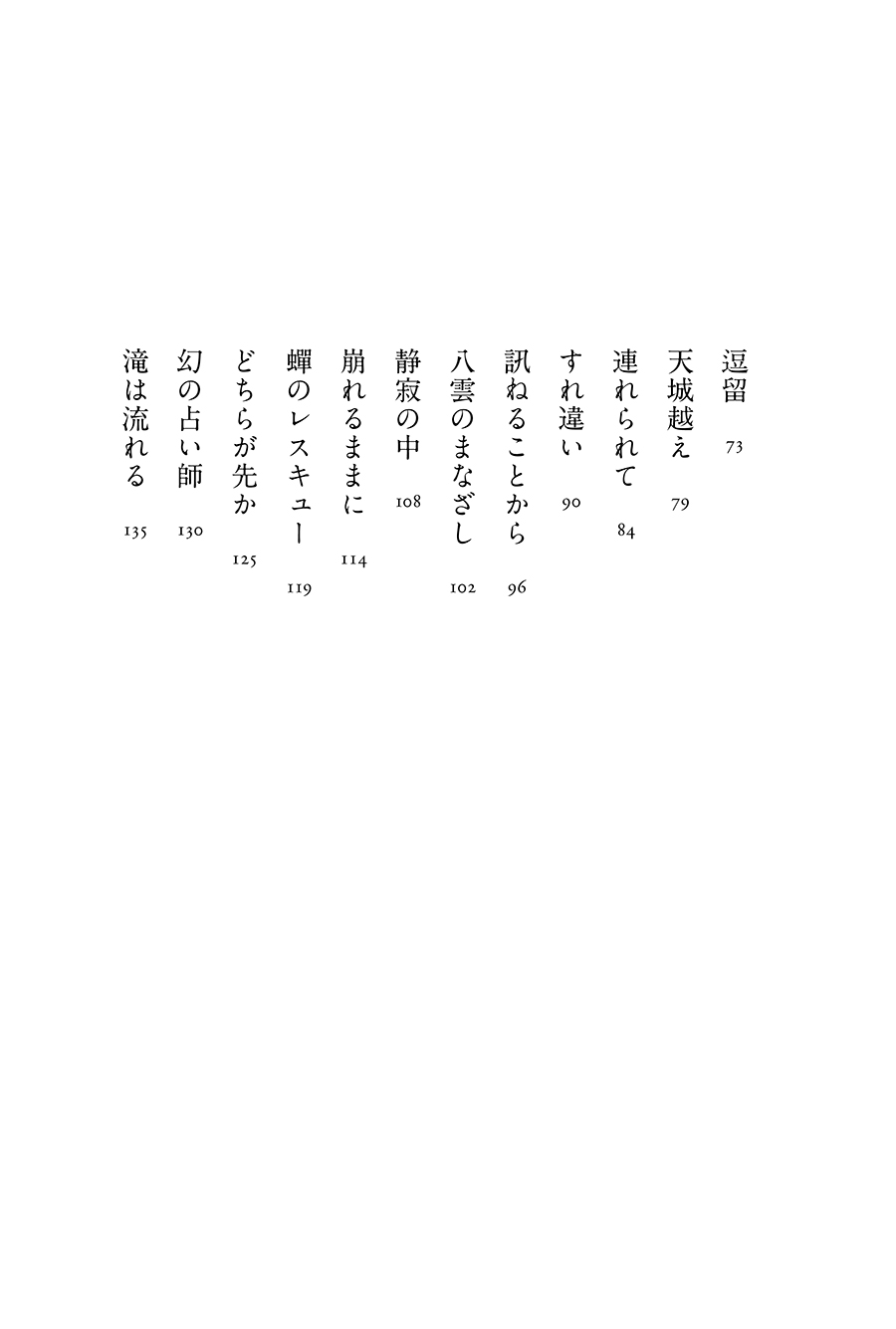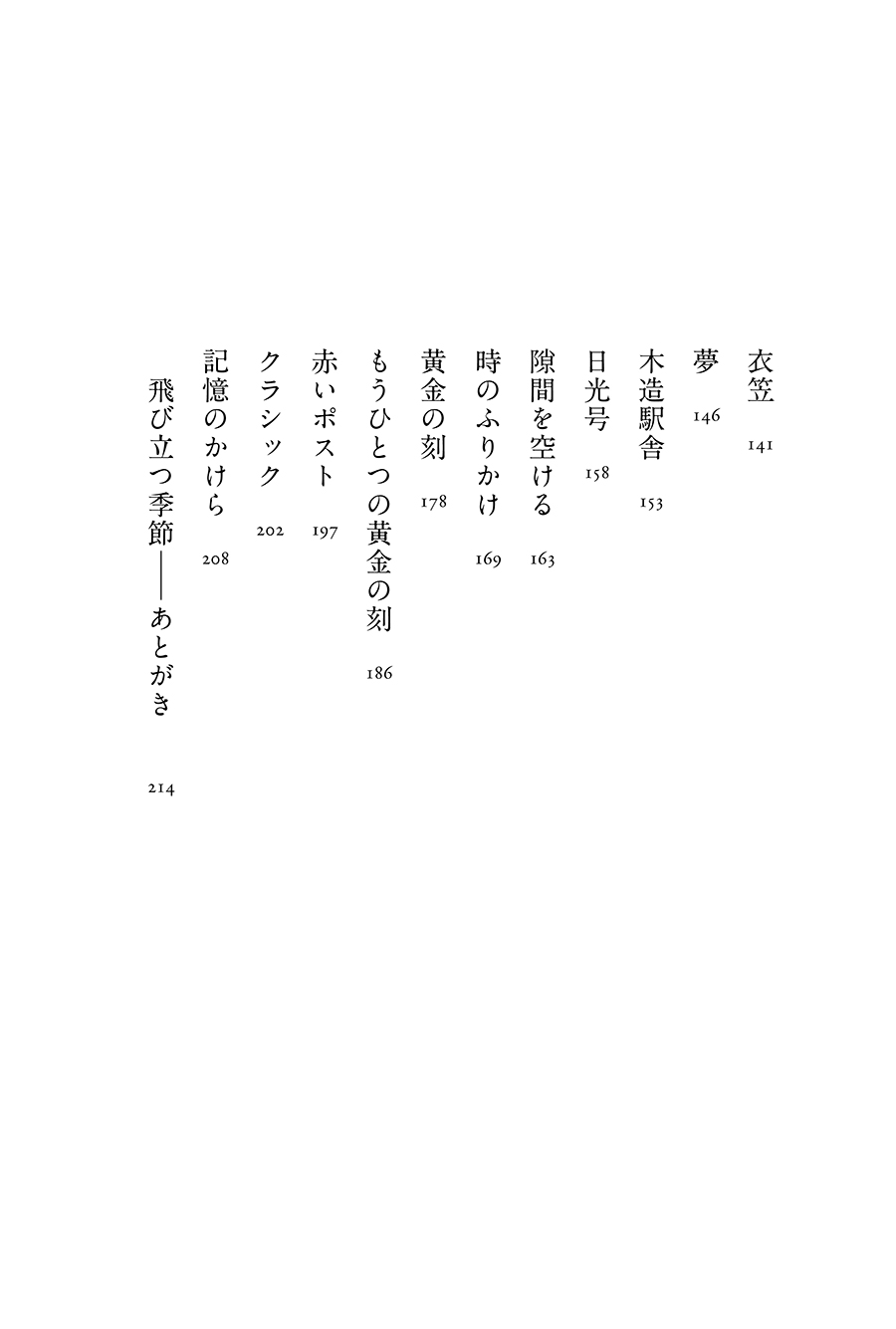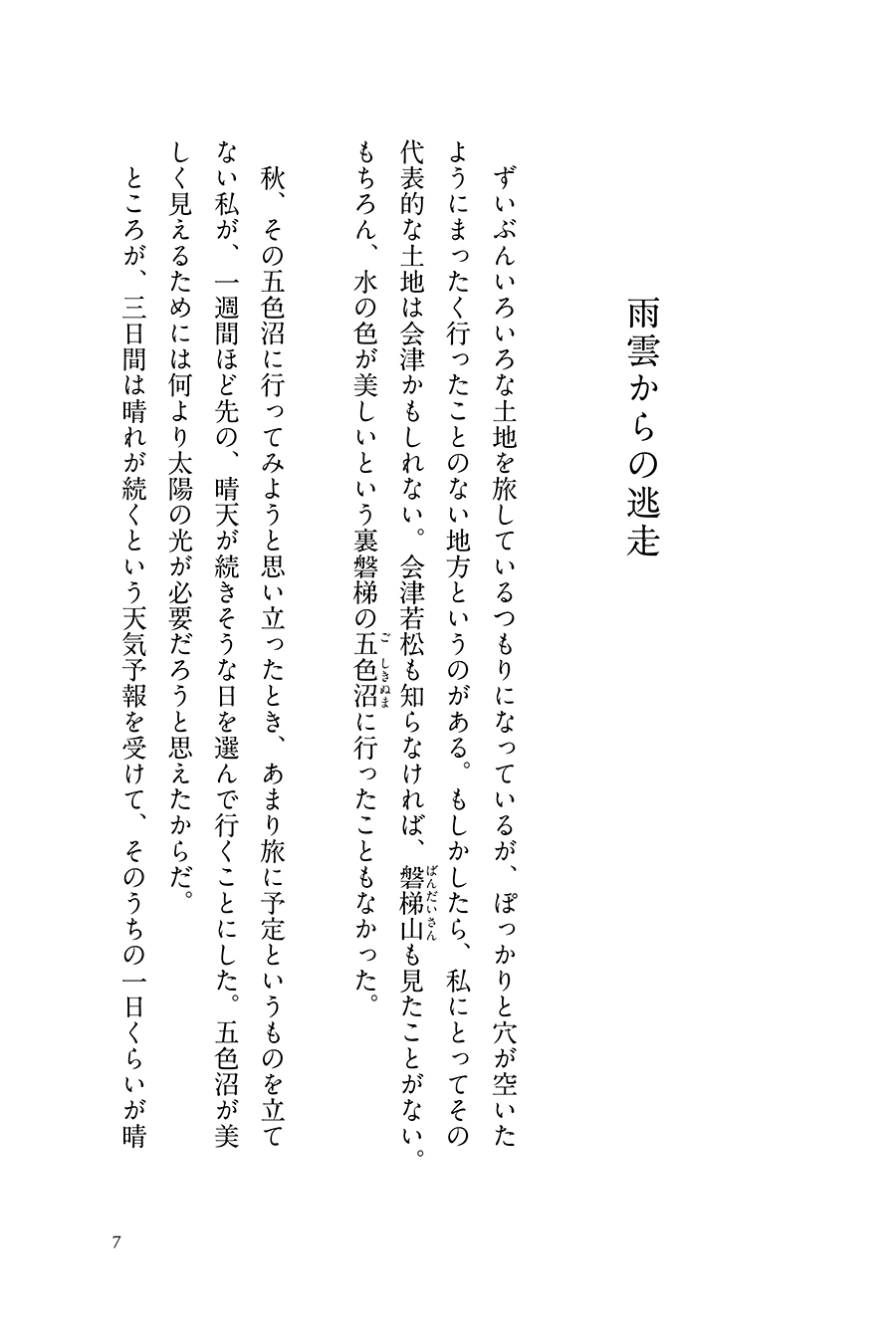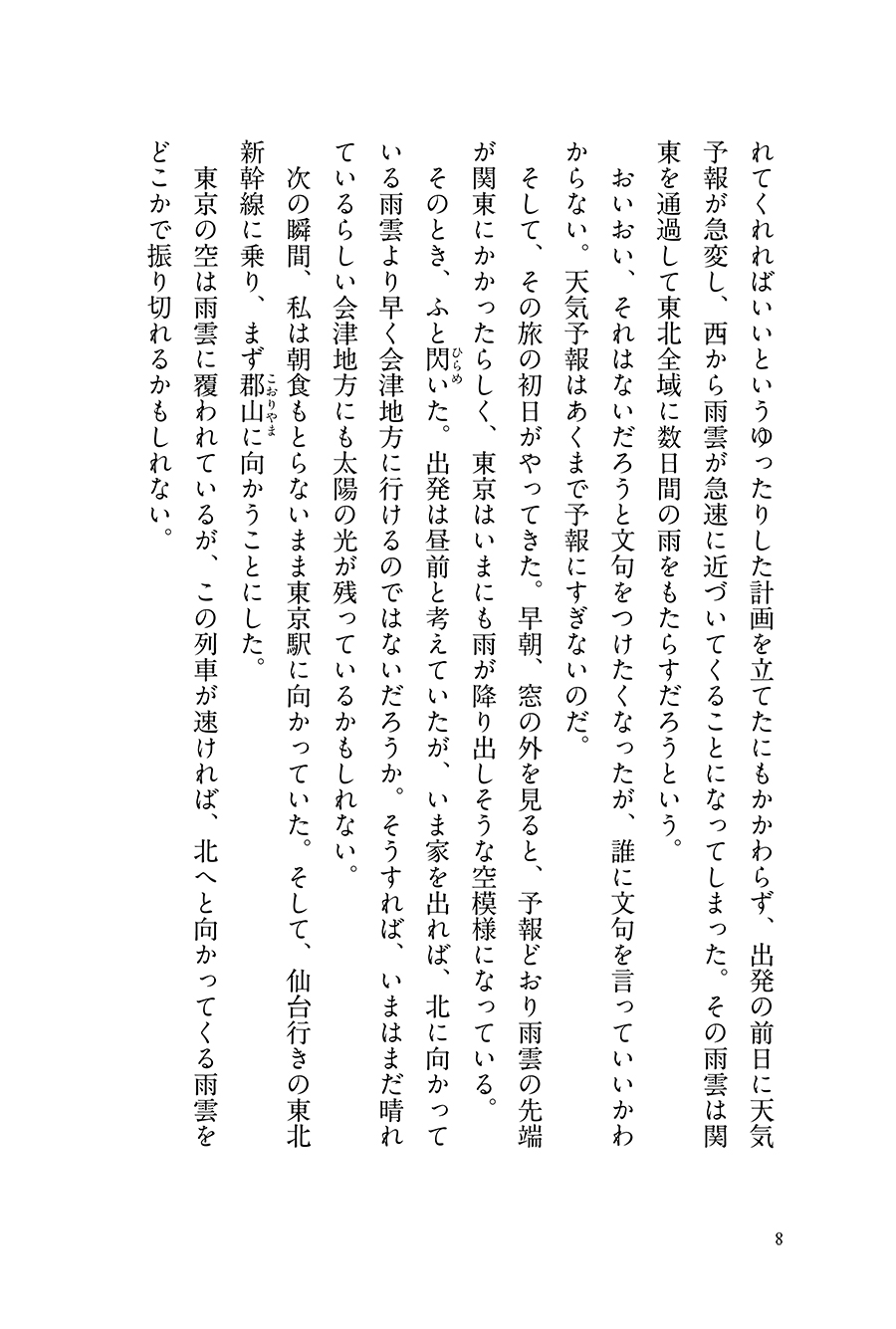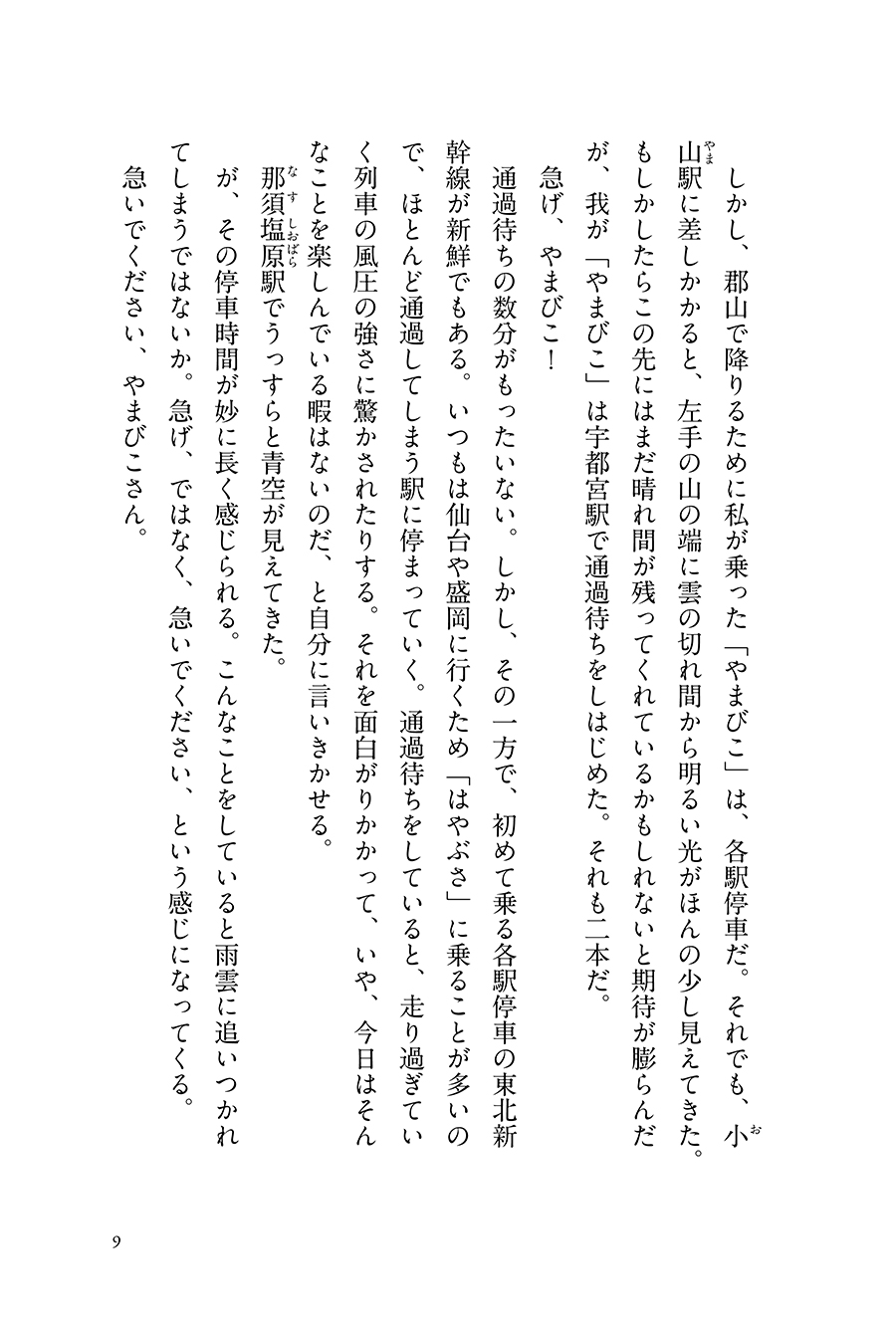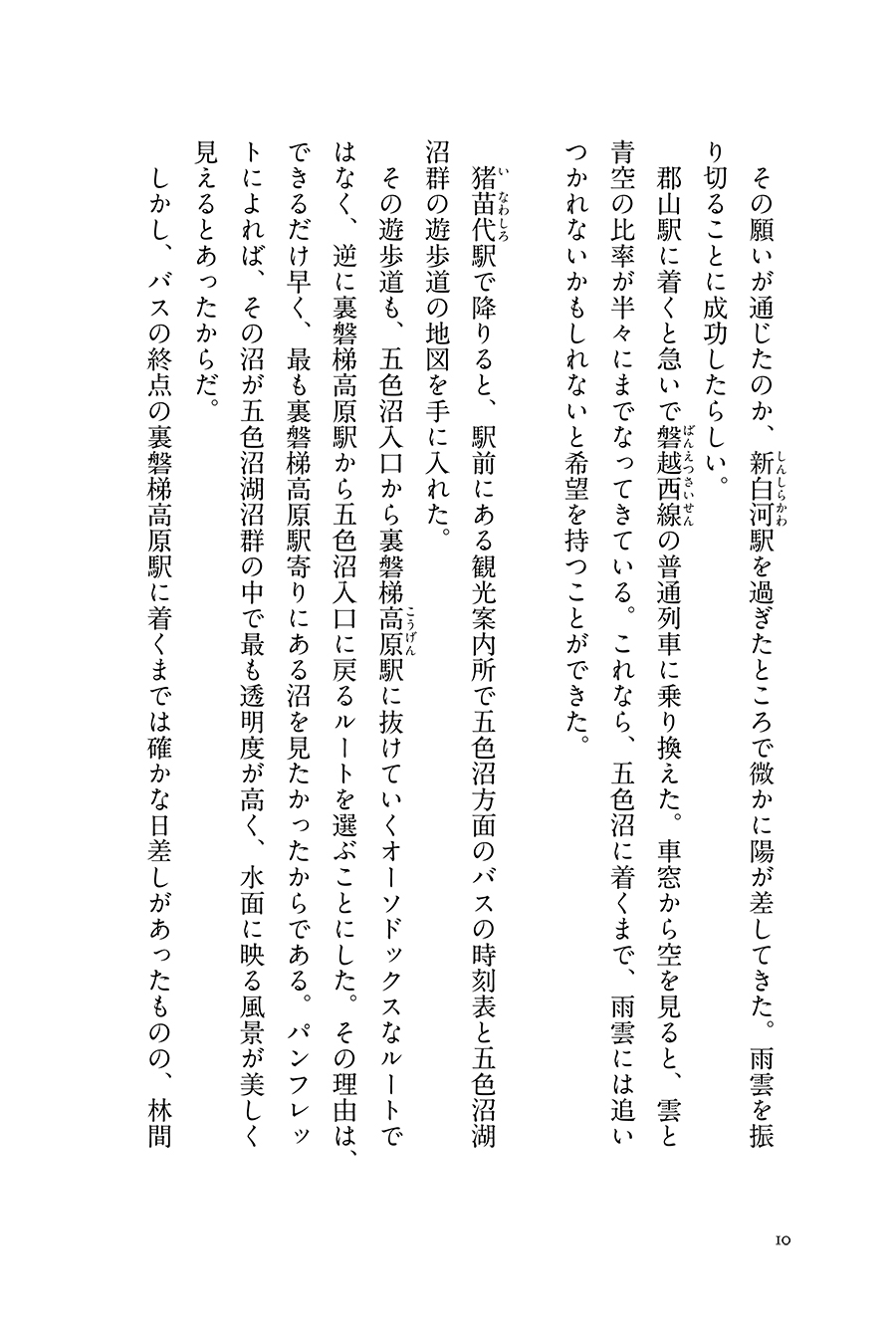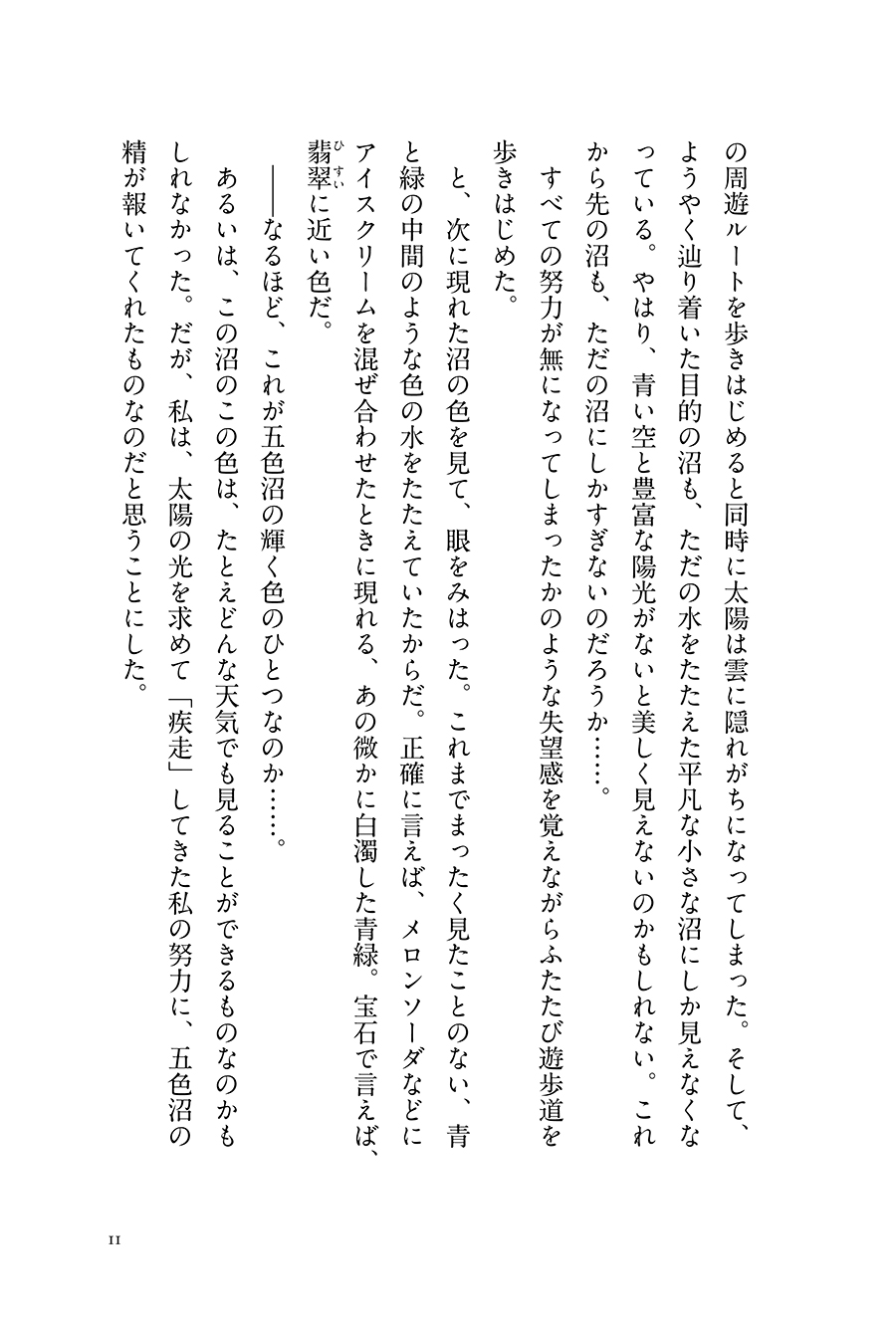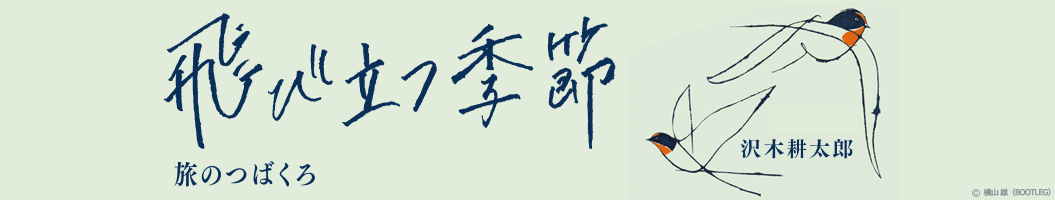
雨雲からの逃走
ずいぶんいろいろな土地を旅しているつもりになっているが、ぽっかりと穴が空いたようにまったく行ったことのない地方というのがある。もしかしたら、私にとってその代表的な土地は会津かもしれない。会津若松も知らなければ、
秋、その五色沼に行ってみようと思い立ったとき、あまり旅に予定というものを立てない私が、一週間ほど先の、晴天が続きそうな日を選んで行くことにした。五色沼が美しく見えるためには何より太陽の光が必要だろうと思えたからだ。
ところが、三日間は晴れが続くという天気予報を受けて、そのうちの一日くらいが晴れてくれればいいというゆったりした計画を立てたにもかかわらず、出発の前日に天気予報が急変し、西から雨雲が急速に近づいてくることになってしまった。その雨雲は関東を通過して東北全域に数日間の雨をもたらすだろうという。
おいおい、それはないだろうと文句をつけたくなったが、誰に文句を言っていいかわからない。天気予報はあくまで予報にすぎないのだ。
そして、その旅の初日がやってきた。早朝、窓の外を見ると、予報どおり雨雲の先端が関東にかかったらしく、東京はいまにも雨が降り出しそうな空模様になっている。
そのとき、ふと
次の瞬間、私は朝食もとらないまま東京駅に向かっていた。そして、仙台行きの東北新幹線に乗り、まず
東京の空は雨雲に覆われているが、この列車が速ければ、北へと向かってくる雨雲をどこかで振り切れるかもしれない。
しかし、郡山で降りるために私が乗った「やまびこ」は、各駅停車だ。それでも、
急げ、やまびこ!
通過待ちの数分がもったいない。しかし、その一方で、初めて乗る各駅停車の東北新幹線が新鮮でもある。いつもは仙台や盛岡に行くため「はやぶさ」に乗ることが多いので、ほとんど通過してしまう駅に停まっていく。通過待ちをしていると、走り過ぎていく列車の風圧の強さに驚かされたりする。それを面白がりかかって、いや、今日はそんなことを楽しんでいる暇はないのだ、と自分に言いきかせる。
が、その停車時間が妙に長く感じられる。こんなことをしていると雨雲に追いつかれてしまうではないか。急げ、ではなく、急いでください、という感じになってくる。
急いでください、やまびこさん。
その願いが通じたのか、
郡山駅に着くと急いで
その遊歩道も、五色沼入口から裏磐梯
しかし、バスの終点の裏磐梯高原駅に着くまでは確かな日差しがあったものの、林間の周遊ルートを歩きはじめると同時に太陽は雲に隠れがちになってしまった。そして、ようやく辿り着いた目的の沼も、ただの水をたたえた平凡な小さな沼にしか見えなくなっている。やはり、青い空と豊富な陽光がないと美しく見えないのかもしれない。これから先の沼も、ただの沼にしかすぎないのだろうか……。
すべての努力が無になってしまったかのような失望感を覚えながらふたたび遊歩道を歩きはじめた。
と、次に現れた沼の色を見て、眼をみはった。これまでまったく見たことのない、青と緑の中間のような色の水をたたえていたからだ。正確に言えば、メロンソーダなどにアイスクリームを混ぜ合わせたときに現れる、あの微かに白濁した青緑。宝石で言えば、
――なるほど、これが五色沼の輝く色のひとつなのか……。
あるいは、この沼のこの色は、たとえどんな天気でも見ることができるものなのかもしれなかった。だが、私は、太陽の光を求めて「疾走」してきた私の努力に、五色沼の精が報いてくれたものなのだと思うことにした。
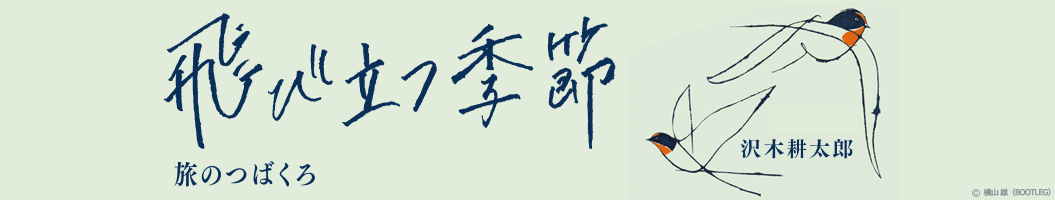
心残り
会津と聞くと、日本人の多くは、反射的に「磐梯山」か「
それが会津という地方ではなく、都市としての会津若松となれば、これはほとんどすべての人が
その日、会津若松にいた私は、時間がたっぷりあったので、白虎隊の隊士の墓があるという飯盛山に行くことにした。
駅前から延びる一本道を、真っすぐ歩いていくと三十分足らずで飯盛山に着く。
飯盛山は、山と名前はついているが「鎮守の森」風の小さな丘に過ぎず、頂上に向かっていくらか長めの石段が続いている。
驚いたことに、その石段の隣には有料の動く歩道が設置されている。
やれやれ、と思いかけて、老齢のご夫婦がチケットを買っているのを見て、そういう方たちにとってはありがたいものなのかもしれないと思い直した。
さすがに私は階段で上がることにしたが、頂上に着いたときには、ほんの少しだが息が切れていた。
その頂上には寺社の
墓からの案内板によって、丘の南側に続く細い道を下っていくと、途中に狭い平坦な空間があり、若者たちが自刃した場所とある。
なるほど、そこからは、南西の方向に鶴ヶ城を望むことができる。そこまで辿り着いた若者たちは、城の方向に煙の立つのを見て落城したと思い込み、いまはこれまでと全員で自刃した、ということになっている。
私が茫然と遠くの鶴ヶ城を眺めていると、そこに初老の女性に率いられた七、八人ほどの女性のグループがやってきた。そして、その初老の女性がガイド風に説明を始めた。私も近くに立っているため、いやでも耳に入ってくることになったが、その女性が力を込めて説明していたのは、彼らがなぜ自刃したのかという理由であった。
「よく、白虎隊の方たちについて、まだ落城もしていないのに
言われてみれば、そうかもしれない。その考え方の方がはるかに説得力がある。私は新しい知見を得て、なんだかとても得をしたような気分になり、もういちど白虎隊の隊士たちの墓に
だが、東京に戻って、あらためて白虎隊関係の本に眼を通して、「しまった!」と思った。私はただ単に墓を見ただけで帰ってきてしまったが、実は、飯盛山にはまだ見るべきものがあったことに気づかされたのだ。
頂上へ急いでいた私はまったく気がつかなかったが、石段の途中には「白虎隊記念館」なるものがあったらしい。そこには、酒井
酒井は、仲間とはぐれたあと、ひとり鶴ヶ城に入り、籠城戦に加わる。しかし、その戦いに敗れ、新政府軍に降伏したあと、なんとか生き延びることになる。明治維新後は北海道に渡り、そこでひっそりと一生を終えた。
その酒井は、生涯ほとんど白虎隊のことを口にすることはなかったが、死後、家族は、白虎隊とはぐれてからのことを簡潔に記した文書を発見する。それは白虎隊に関する一級の資料となるものだった……。
その酒井の存在を知って、私が思い浮かべたのは、イギリスのケン・ローチが監督した『大地と自由』という映画である。
一九三六年に勃発したスペイン戦争には、ヨーロッパやアメリカから多くの義勇兵が反ファシズムの戦いのために参加した。その中には、多くの若い労働者がいたが、やがてフランコらの反乱軍の攻勢の前に、失意のうちに自国に帰っていかざるをえなくなっていく。
イギリスの若い女性が、祖父の死後、遺品を調べると、古いトランクの中から、スペイン戦争に義勇兵として参加し戦ったことを示す品々が出てくる。セピア色の写真、古い新聞記事、そして手紙……。映画は、その孫娘が、スペイン戦争について何ひとつ語らず、一介の労働者として生き、死んでいった祖父の青春の戦いを、それらの遺品を通して辿り返そうとするところから始まるのだ。
飯盛山の「白虎隊記念館」には、同じように、戦いを生き延びた酒井の書き残した文書が展示されているという。
それは見たかった。多くの同輩と共に死を覚悟して戦った若者が、ひとり生き残ってしまったという現実を引き受け、敗北後の人生をどのような思いで生きつづけていたのか。その一端でも
もっとも、私は旅先に心残りを作ることも悪くないと思っているようなところがある。そこに心を残しておけば、いつかまた訪れることができるだろうから、と。そう、残した心を「回収」するために。
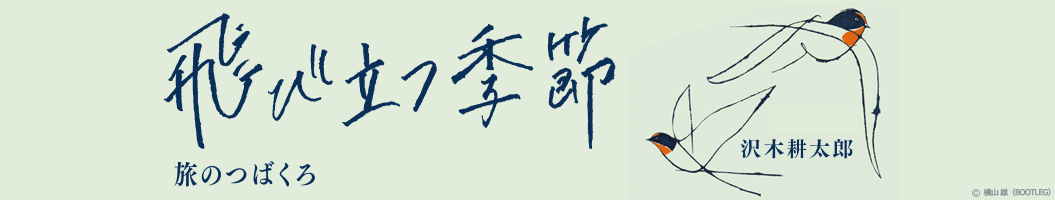
続けて通えば
会津若松に滞在しているときのことだった。
二日目は会津若松から
会津若松を出たのは昼前だったが、帰るのは夕方遅くになってしまった。その理由は、駅から少し離れた美術館に行くまでに思わぬ道草を食ってしまったこともあり、また、帰りの只見線の列車が三時間に一本しかなかったからでもあった。
だが、いずれにしても、すっかり暗くなった会津若松駅に着くと、駅前に停まっているタクシーに乗り込み、繁華街のある七日町方面に向かってもらうことにした。私は、そのはずれにある一軒の居酒屋に行くつもりだったのだ。そして、その居酒屋といえば、前日の夜にも行った店だった。
せっかく初めての土地に来ているのにどうしてもっといろいろな店に行かないのか、と思われるかもしれない。
しかし、私は「あえて」同じ店に行こうとしていたのだ。
私は同業の作家との付き合いがほとんどないが、それでも年長の作家の何人かとはささやかな交流を持った。
そのひとりに、いまはもう亡くなってずいぶんになる山口
銀座の小さな酒場で知り合った山口さんとは、何度か酒席を共にすることもあったし、その酒場の
対談の内容は、それがスポーツ雑誌だということもあって、プロ野球や競馬の話が中心だったが、途中で、ふと思いついて、山口さんに質問してみることにした。
紀行文を書くための
山口さんは、主として小説雑誌に連載するというかたちで国内旅行を中心に多くの紀行文を書きつづけていらした。
私のその質問に対して、山口さんはこう答えた。
第一 相棒を誰にするかをよく考える
第二 滞在中ひとつの店に何回も行く
第三 書く枚数を長く用意してもらう
第四 とりわけ枕の部分を長く書く
第五 書く媒体を選ぶ
このうち、第一のどんな相棒にするかは確かに大事なことだが、私のように一人旅を好む人間にはあまり重要ではない。第三と第四と第五はプロの書き手向けの要諦かもしれない。
しかし、第二の、ひとつの店に何回も行くというのは、単に紀行文を書くための要諦というだけでなく、旅をする人にとって極めて有効な旅の「技術」であるように思われる。
私も、山口さんからそれを聞いて以来、二日以上同じ場所に滞在する場合は、意識的に同じ店に通うようになった。すると、その土地との親密度がぐっと増すということに気がついた。
会津若松駅からタクシーに乗ると、私は目的の居酒屋に電話を入れた。すると、店はもう一杯で、空いている席も予約が入っているが、短時間でいいならいらっしゃい、ということになった。
入っていくと、居酒屋としては早い時間と思われるのに、すでに大勢の客がいて、カウンターも二席しか空いていない。
その一席に案内され、座ると、女将が常連を迎えるような笑顔を向けてくれた。
その笑顔に勇気を得て、お飲み物はと訊ねられた私は、たぶん常連でなくては頼めないような注文の仕方をした。
この日は、朝から歩きまわっていたため昼に何も食べていない。そんな胃の状態で酒を飲むと酔っ払いかねない。そこで、と私は女将に頼んだのだ。昨夜、締めに特製カレーというのを食べている人がいたが、とてもおいしそうだった。飲む前に、それを食べさせてもらえないだろうか。女将は、私のその頼みを聞くと、それは大変でしたね、飲む前に少し食べ物を胃に入れておいてもらいましょう、と愛想よくカレーの用意をしてくれた。
居酒屋で、酒を飲む前にカレーを注文するというわがままを許してもらった私は、それをきれいに平らげてから、おもむろに会津の酒に向かうことができたのだ。
そして、調理人の御主人が勧めてくれる、受け皿にたっぷりとこぼれるグラスの酒を三杯も飲むころには、もうこの店には二日ではなく二年は通っているような気分になり、隣の一席に座った初来店の客には、この店のおいしい料理について講釈しているという状態になっていた。
山口さんの第二の要諦は、こういう幸せな夜を用意してくれるものであったのだ。