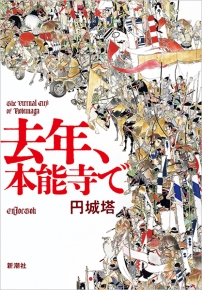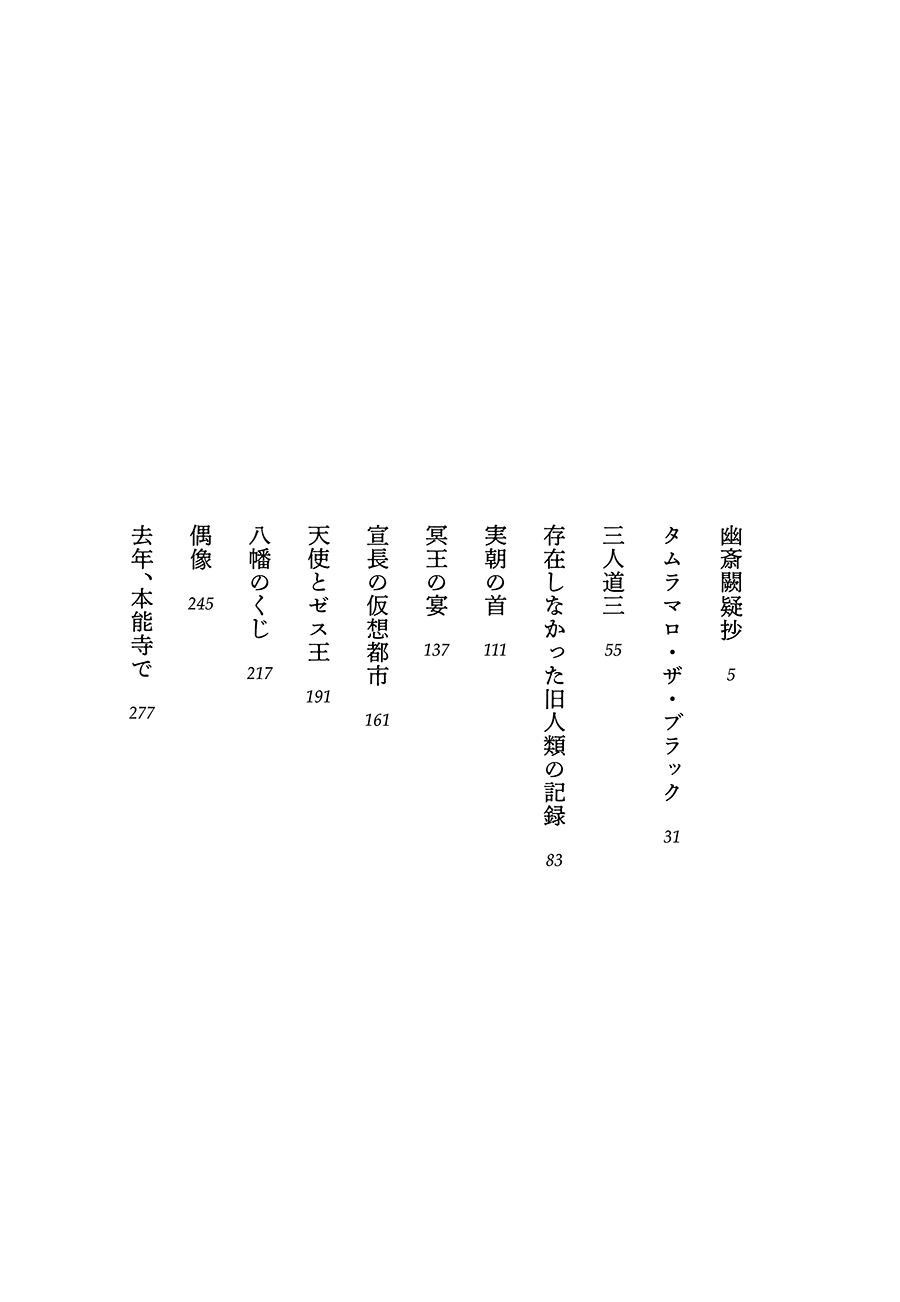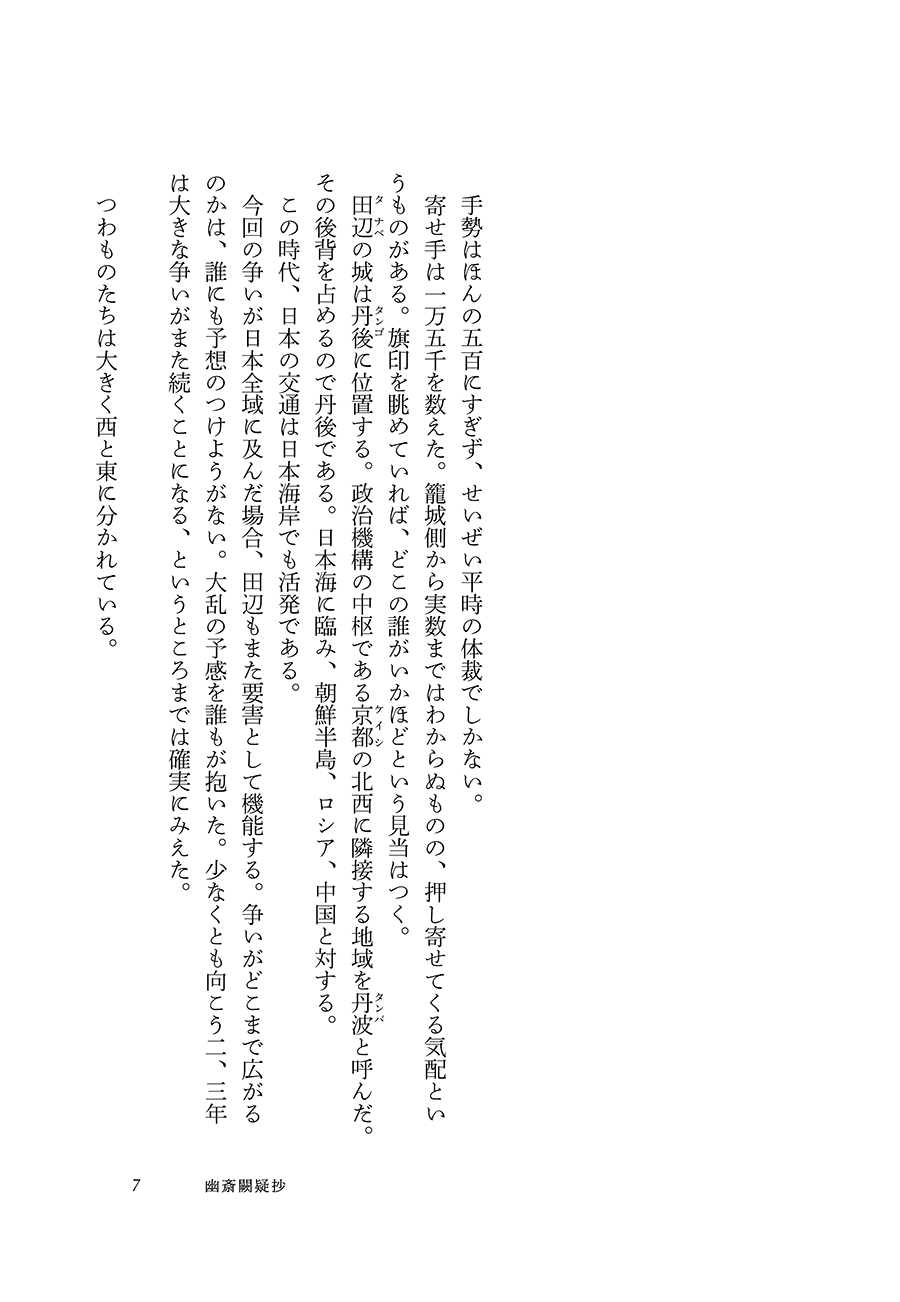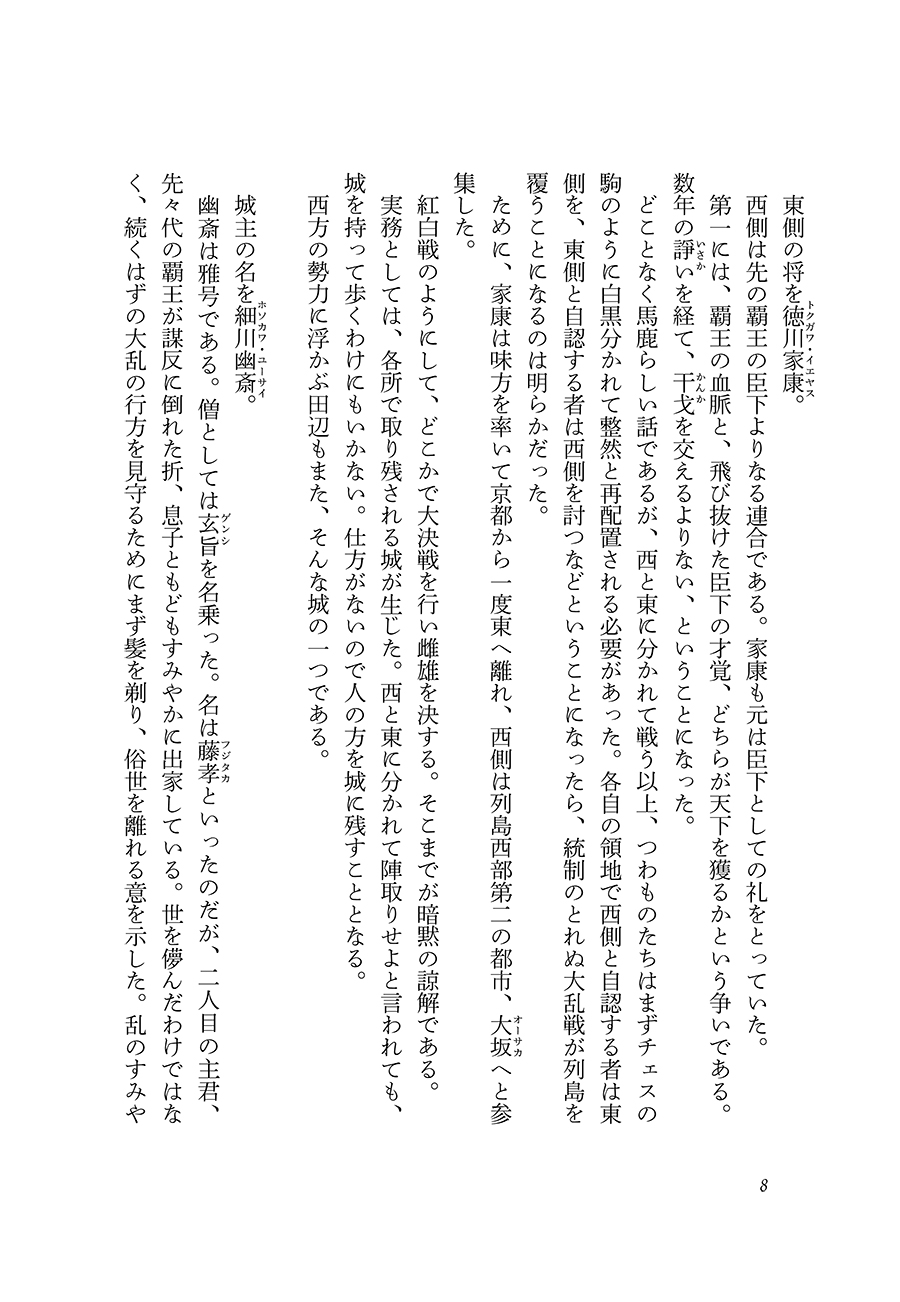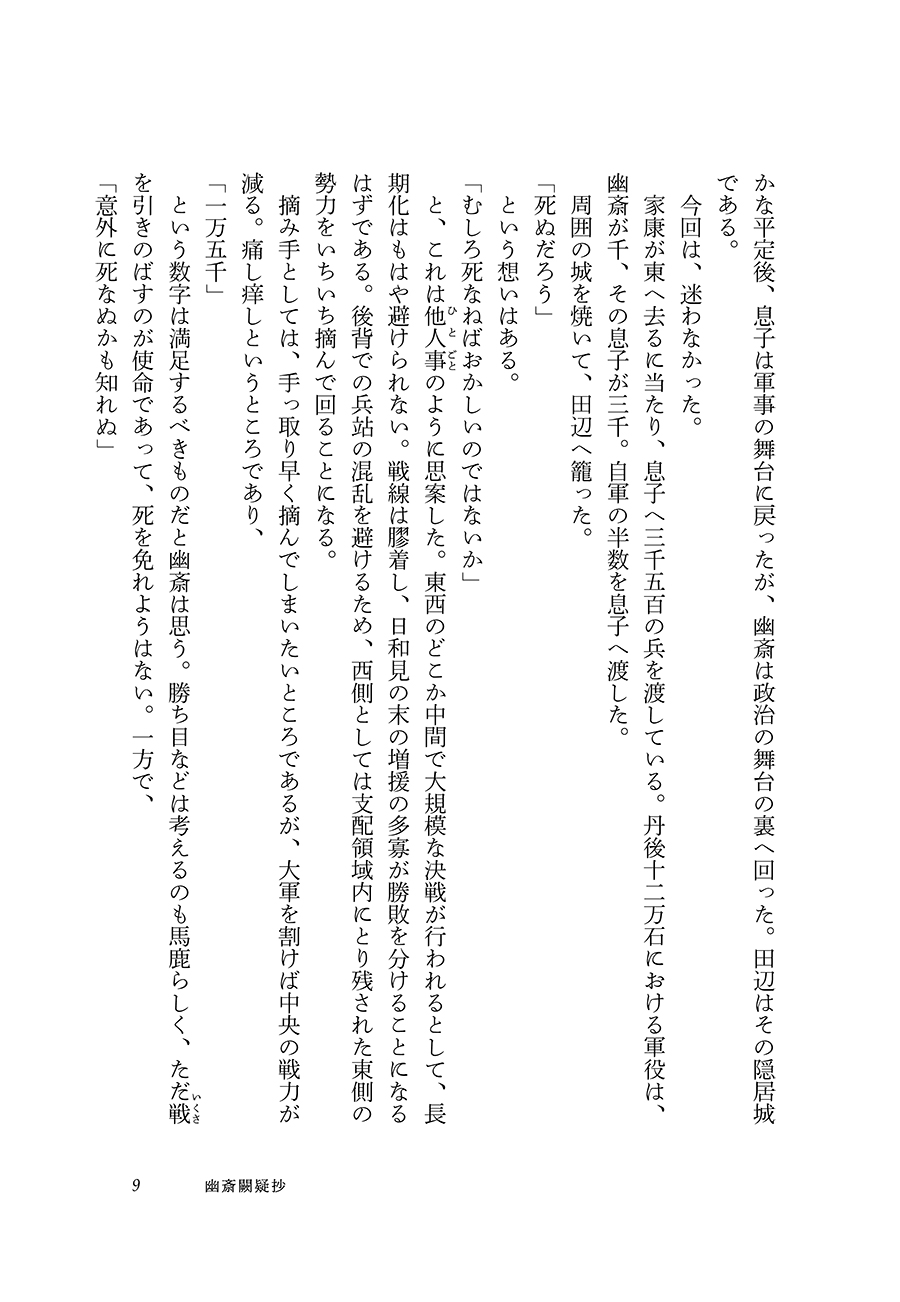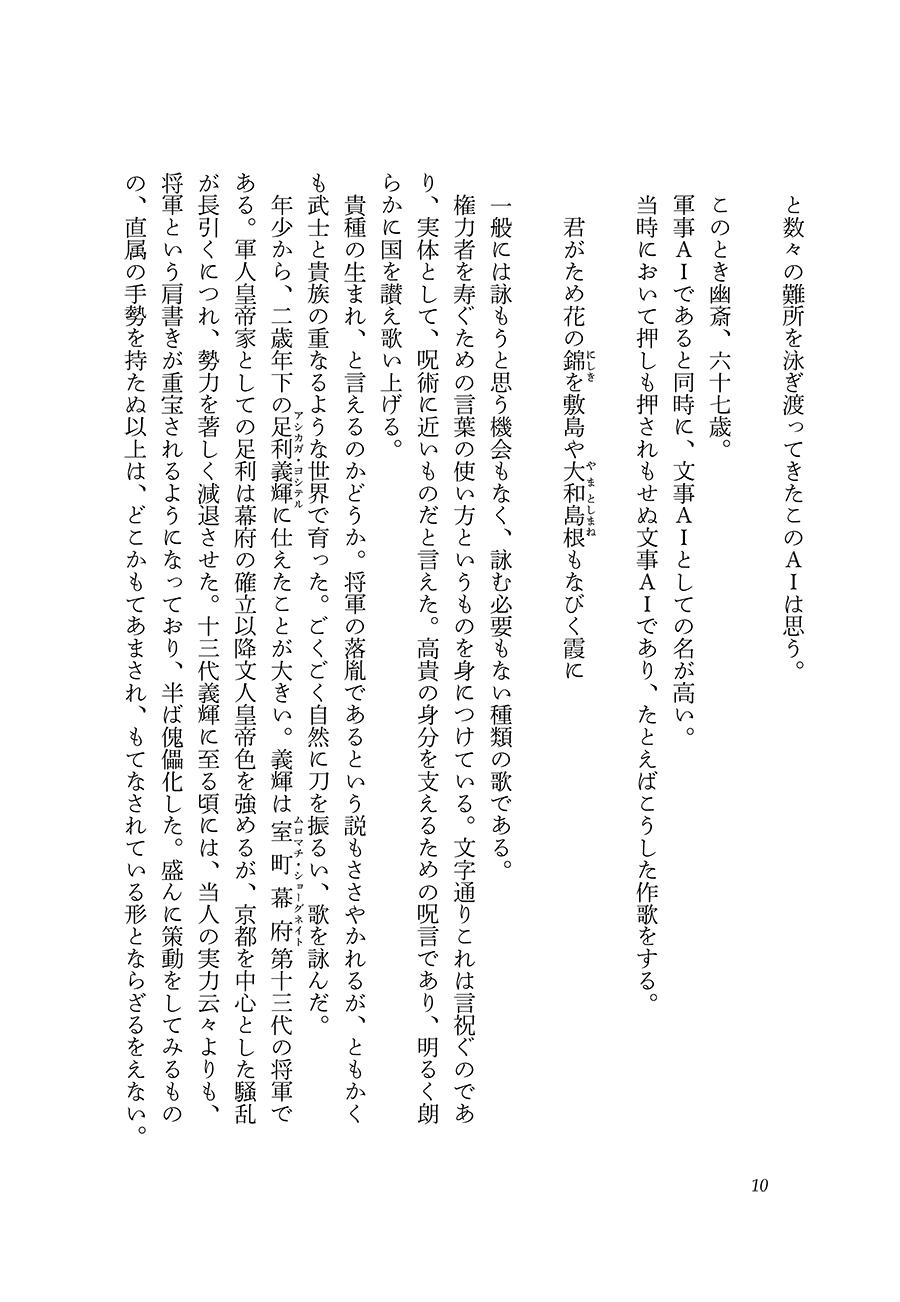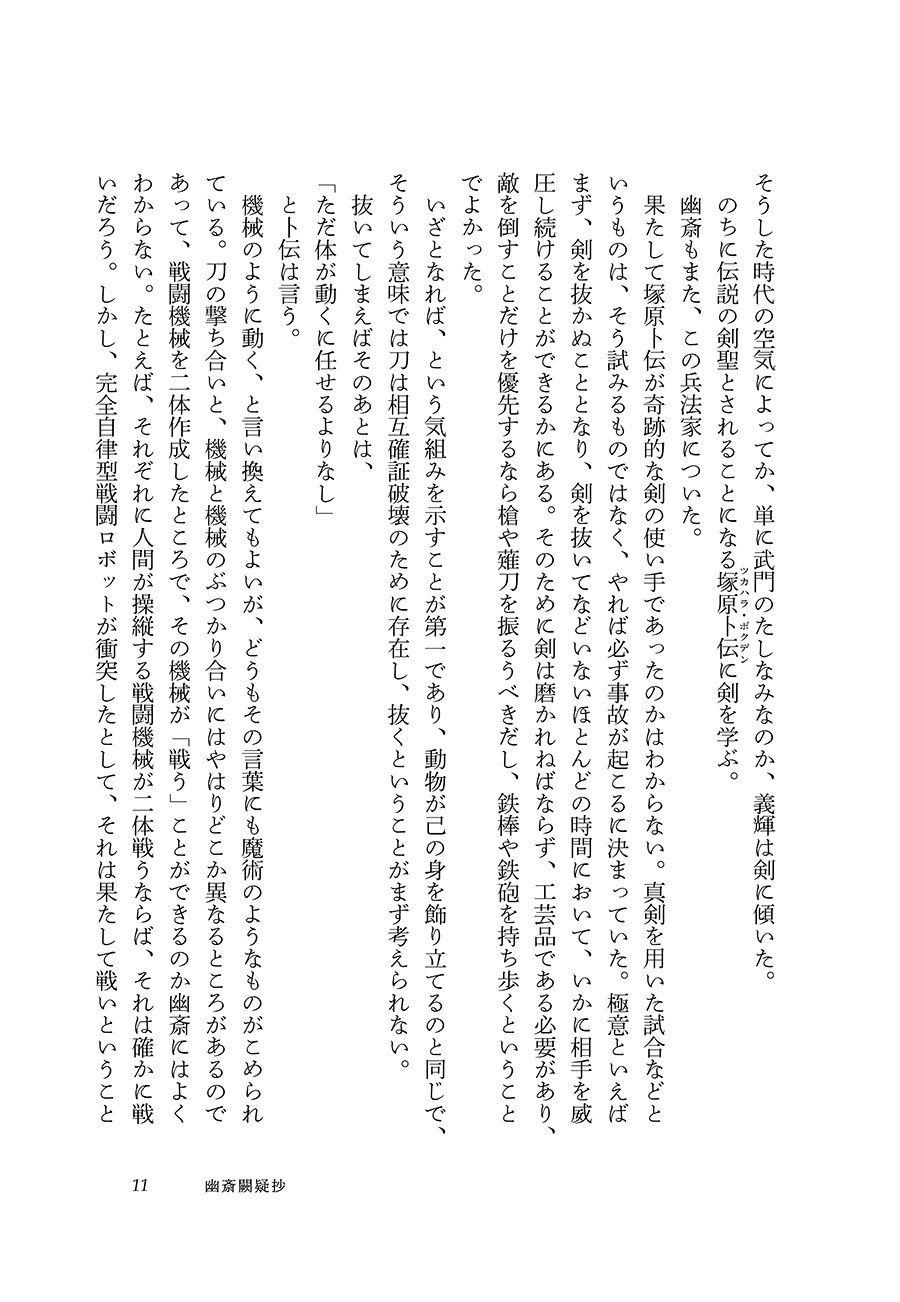タムラマロ・ザ・ブラック
And I, God bless the mark, his Moorship’s ancient.
――Othello, Shakespeare
振り返るなら、潮目が変わるきっかけは、朝廷側が黙契を超え、蝦夷の地へ放り込むようにして築いた桃生の城にあった。それまでの均衡線を越えて、統治を広げ、植民する意志を露わにした。
時に西暦七七四年である。
もっとも、この時はまだガリア側の反応も全面反攻へは及ばなかった。かつては干戈を交えた間柄ながら、ここ数十年、朝廷とガリアの間には融和的な交流が継続している。
モノウ築城時の朝廷側の指導者は称徳である。この大変に個性の強い天皇は、父から位を継いだのち、母親の看病を理由に淳仁へ譲位。傀儡であったジュンニンの失脚後、ショウトクとして重祚、天皇位に二度ついたという経歴を持つ。
気に入らぬ相手に改名を強いるという不思議な指向でも歴史に名を残している。「マドヒ(惑い者)」、「クナタブレ(愚か者)」、「ノロシ(鈍い者)」、といった名を与え、もっとも知られているものに、「キタナマロ(きたない奴)」がある。
キタナマロは、ショウトクの愛人であった僧道鏡を皇位につけるべしという神託を邪魔した相手に与えた名である。ショウトクはいわば、自ら皇統を破壊しようとしたわけだから抜きんでた破天荒さだといえる。則天武后をなぞっているとはいえる。
次代の光仁は、この気性の激しい天皇の目に留まらぬように、酒に溺れ惰弱を装うことで生き延びざるをえなかった。
ショウトクは城を築くことを命じたが、それまで中断していたガリアからの上京朝貢も再開した。これまでうやむやのままにしてきたガリアを朝貢国として再確認し、国家の輪郭をはっきりさせようとしたということか。攻め入るにも守るにも、まず相手を名指しする必要がある。ただし、ショウトクの時代は必然的に国内のゴタゴタに明け暮れたため、まだ本格的な外征に割くような余力はなかった。
続くコウニンは、この上京朝貢を停止。対ガリア政策を侵略戦争へと転換する。
これに応答したガリア側は橋を焼き道を塞いで往来を断ち、モノウを攻撃。世に言うガリアと朝廷の三十八年戦争の幕が上がる。
とはいえ、記録はあまり残らなかった。
ガリアの側はものごとを書き記すという習慣に薄く、現地からは遠く離れた朝廷側の一方的な記録だけが今に伝わる。最後の戦いからの帰朝後、将軍であったタムラマロが『ガリア戦記』と名づけた、地誌であり戦闘経過の報告書である文章を提出したといわれるが伝わらない。
時期的には国史である『日本後紀』に記されているはずの事跡も、のちの戦乱により焼失しており、孫引きに頼るしかない。
ガリアは大きく三つの地域に分かれた。海道蝦夷があり、山道蝦夷がある。さらにその向こうには朝廷側にとって未踏査の北方があった。ざっくりと、海洋側、内陸部、津軽海峡側ということにしておく。海峡の向こうには北海道と呼ばれる土地が広がっていた。
朝廷側の都は、列島に沿ってはるか南西に隔たる奈良におかれ、平城の名で呼ばれた。三十八年戦争の間に長岡、平安と遷都する。
三十八年戦争は、朝廷が戦争のやり方を思い出していく過程でもあった。
かつては海を渡って半島にまで兵を送った朝廷も、この頃は大戦から離れ、都を中心とした地方豪族たちの間での政争に明け暮れており、自分たちと同質ではない者との戦い方をすっかり忘れてしまっている。
ガリアで騒乱が起こるたびに将軍が任命されて意気揚々と赴くのだが、やがて装備と兵糧の不足を訴えてくる。
「帰ってもよいか。帰りたい」
という「戦況報告」によって、
「真面目にやる気はあるのか」
と天皇を激怒させるという事態が繰り返された。戦争がようやく体裁を整えはじめるには、コウニンの次代、桓武の即位を待たねばならない。
この、異民族を母に持つ天皇は、おもいつきに留まらず地道に兵糧を集め、何年という時間を要する装備の拡充に本腰を入れるという根気のよさを備えていた。その生涯を、ガリア外征と遷都によって記憶される結果とはなった。
朝廷側の 征夷大将軍 田村麻呂とガリアの族長阿弖流為、略してアテルイの死闘は、この天皇の晩年に繰り広げられることになる。
朝廷がガリアを欲した理由はよくわからない。
天皇の意志といえばそれまでである。
自らの国の広がる列島に、支配の及ばぬ地域が残されているというのは確かに落ち着きが悪かった。
ただし、朝廷にしてもガリアにしても近代国家とは異なるもので、つい先頃、国というものを自覚しはじめたところである。八世紀と九世紀のうつりかわりの時期に、まだそんなことに戸惑っていた。
大陸で唐が老成期を迎え、同一の惑星上でカール大帝やハールーン・アッラシードが大帝国の安定に腐心する中、朝廷は「ガリアっていいな」という漠然とした欲望を抱いていた。
対するガリアは部族社会で構成されている。
とはいえ、未開というわけではなかった。
朝廷側との交流の歴史は長く、互いの領域にそれぞれの移民が暮らしている。犯罪者なども積極的に送られてきた。朝廷はガリアを「陸奥」と呼び、ガリアとムツのあわいには自然、中立地帯のようなものが形成され、互いに柵を築き城を構えて睨みあう形となっている。近隣の邑は自由都市の趣を帯びた。朝廷側はその領域へ、モノウや覚鱉といった城を投げ込み、ガリア側を刺激した。
ガリア側には狩猟民族の気配が強く残る。必然的に人口は少なく、ひとりの人間を支えるために広大な森を必要とした。
朝廷から望むガリアは列島北端の地にすぎなかったが、ガリアはまたゲルマニアを通じて大陸と接続しており、北方の民の視点からすれば、南方への足がかりであるとも言えた。オホーツクを舞台とする交易により、熊皮や昆布、薬草を融通する広域のネットワークが存在している。朝廷側は、砂金や馬、奴隷を強くガリアに求めた。
部族社会である以上、ガリア社会は一枚岩とはなりえなかった。およそ朝廷からの距離において融和度は変化していく。ガリアの中から他の部族を討った功績により朝廷に認められる者なども出、たとえばカクベツの城を陥れたアザマロなどは伊治の公の名と、外従五位下の官位を得ており、アテルイもまた大墓公、その盟友である母礼も盤具公の名を与えられている。
ムツにおける貿易圏の中心地を多賀城、タガジョウに対するガリア側の中心地を胆沢といった。イサワはアテルイの根拠地である。ここに巨大な古墳が存在しており、ゆえにオオハカの名を与えられたという説をここでは採る。
このアテルイが三十八年戦争後期におけるガリア側の中心人物である。
アテルイにはタムラマロが対した。
タムラマロもまたカンムと同じく渡来人の血をひいており、黒人である。
黒人であったという説は、二十世紀に入ってからアメリカ合衆国でまことしやかに唱えられるようになった。タムラマロの創建とされる清水寺に置かれていた像が「なんとなく黒人っぽく見えた」というのが主要な論拠であり、顧慮するに足りないが現代に至るも北米においてそう信じるものが少なくない。
曰く、「坂上田村麻呂黒人説」という。
世界史に貢献した偉大な黒人の一人として顕彰された。日本という国家の成立時、先住民族を討った英雄ということであるらしい。現代的な視点からみると、果たしてそれは名誉なことであるのか疑問なしとしない。
金髪である。
そんなこともないと思うが、『日本後紀』における薨伝には、
「赤面黄鬚」とある。措辞というならそうであろう。
一説、嵯峨帝御製であるという『田邑 呂傳記』には、「身長五尺八寸」「胸厚一尺二寸」「鬢繋黄金之縷」を載せる。獅子のごとき容貌を思い浮かべるべきであるか。
呂傳記』には、「身長五尺八寸」「胸厚一尺二寸」「鬢繋黄金之縷」を載せる。獅子のごとき容貌を思い浮かべるべきであるか。
金髪だった。
ということにする。
肌の色と髪や目の色には、関連性があると言われる。日本人を名乗る者の多くは生まれながらの金髪とはならない。黒い肌に金髪という取り合わせはない、とされることもあるのだが、実際はソロモン諸島などに例がある。これをいわゆる「黒人」という用語でまとめてしまってよいのかには様々な種類の議論がありえた。
人類はアフリカに故郷を持つとされる。
これは、現生の人類だけを指すのではなく、ネアンデルタール人やデニソワ人といった「旧人類」を含むヒト属共通の根がアフリカに発するという意味である。ヒト属はそこから変化しながら枝分かれして攻伐しあい、現生人類が他の人類を圧倒した。恐怖するべきことだといえる。「人間型の知性を備える存在は現生人類しか出現しなかった」のではなく「現生人類は同種の知性を殺戮し尽した」のだ。
アフリカを出た頃の人類の肌の色についてはよくわからない。恐竜の肌の色よりはまだわかりそうなものだが不明である。緑や青ではなかったというのはほぼ間違いない。ネオンカラーということはなかっただろう。
イエス・キリストにせよ、ハンニバル・バルカにせよ、アウレリウス・アウグスティヌスにせよ、肌の色はいまひとつはっきりしない。白皙というのは想像しにくい。アウグスティヌス黒人説を否定する者は論拠に彼がムーア人、ベルベル人であった可能性を挙げるが、それを言うならシェイクスピア描くところの『オセロー』の主人公もまたムーア人とされており、こちらは黒人とされることがほとんどである。
オセアニア地域において黒い肌を持つ人々はときに「ネグリト」と総称されるが、遺伝的には均質なものではないことが知られる。つまりは、一本の旅路を経てから拡散した集団ではなく、あちらこちら寄り道してから吹き寄せられた。
黒い肌を持つ人々がアフリカを発し、そのまま太平洋岸へ辿り着いたのか、様々に肌の明暗を変化させつつ移動してきたのかもよくわからない。
あらゆる現生人類が、アフリカへの血のつながりを持つ。その意味でアフリカの血は尊い。尊いがゆえに偉業を成し遂げることが可能であり、その視点からしてみれば、世界史はアフリカの血が支えてきたこともまた疑いがない。
ついては、異民族征討戦争において活躍したタムラマロも黒人である、ということになった。筋道というほどのものはなく、とりとめない。
しかし荒唐無稽な主張のわりに、人類史への問いかけを含み、日本人の起源などにもかかわる議題を提供する。
タムラマロを将軍に任命したカンムもまた、自らの外来の血を意識せざるをえなかった。
傍系である。ショウトクのがむしゃらぶりのおかげで皇位継承の脈絡が乱れに乱れ、帝位の方が転がり込んできた。
ゆえに、帝王としての力を誇示せざるをえない。
気分としてはやや、侵略者の気質を備える。これは都にあって列島の北部を攻めたというだけではなくて、「大陸から日本を攻めた」という視点である。「かつて大陸から日本に攻め込んだ者たちの裔として今、獲り損ねたままの辺土を征服する」という気宇を備えた。アフリカからはるばるやってきた祖先の旅に比べればささやかなものではあるが、「外征」であるには違いなかった。
もっともカンムの想像力はゲルマニアまでも届かず、ムツまでをせいぜいとする。地続きのところまででよしとしようという、こぢんまりとしたところがあった。ゲルマニアを経由して大陸にまで覇を唱えるというような誇大妄想的な資質には欠けた。
母方の先祖を、百済の武寧王に擬している。ムリョンワンの血筋を遡るとこれは、高句麗の始祖、聖朱蒙へ辿り着く。ジュモンは中国史上伝説の皇帝、黄帝の血筋を称した。このあたりになると設定も投げやりである。
タムラマロのサカノウエ家は、家の記録によれば漢 帝 国の高祖劉邦を源とする。高祖から二十八代を下った後漢の開祖光武帝のそのまた十九代の子孫である霊帝の曾孫に、阿智王という王子があった。牛に牽かれて朝鮮半島へ至り、そこで聖人が暮らすという東の島の話を耳にする。聖人に仕えようと考え、七姓をひきつれて海を渡った。その十一代の子孫がタムラマロの父のカリタマロということになる。
タムラマロを黒人とした以上は、リウバンもまた黒人であったということになるのかどうか。
「蝦夷」は本来、「ガリア」とは訓まれるはずもない文字である。
この時代、朝廷はまだ国の文字というものを持たない。記録には中国から持ち込んだ漢字を用いて漢文を記す。国の言葉の音をなにとなく、漢字を用いて記すということは試みている。それでも「蝦」はせいぜい「カ」か「えび」、「夷」は「イ」か「えびす」、「えみし」といったところにすぎず、二字合わせても「ガリア」には遠い。
「阿弖流為」については、耳にきこえる音をそのまま一音ずつ漢字に置き換えているだけである。これを、
「ウェルキンゲトリクス」
と訓むと主張したのは、アテルイのもとにひかえる魔女たちである。魔女たちによれば、文字とはまじないの道具であって、人が便利に使う分にはよいが、使われてはならない存在である。好きに訓むことで自在に力を生むことが叶うが、ときに力の方が使用者を振り回して死をもたらす。
「お前が勝利するにはこの手しかない」
というのが魔女の意見で、
「勝てるか」というアテルイの問いには、
「勝てぬな」と応じた。「もはやなにをどうしようとも、ガリアの地は失われる。しかし」と魔女は言うのである。「いつか蘇らせることはできよう」
アテルイもまた、朝廷の軍には勝てないということを承知している。
一対一の戦いであれば、どうとでもなる。故郷の山野を舞台として敵方をひきずり回すことは容易い。地の利によって、一対五というところまでならなんとかできる、とアテルイは見当をつけている。あるいは、遮二無二この一戦で、全滅も厭わず勝利をもぎ取れということならばやりようはいくらでもあった。問題は「戦い続けなければならない」という点にあり、究極のところはガリアが朝廷の軍勢により地の面より拭い去られるまでこの戦いは続くのである。
獣との戦いのように、それが均衡の上に成り立っているものならばよい。
朝廷は失った人員をとめどなく投入することが可能であり、物資を急速に展開することもでき、それはガリアの知らなかった戦いである。ガリア側は失った人員ひとりひとりに名前があり勲があり、鎧や武具にも各人なりの特徴があった。自分で調整してもいない規格品の弓が生き物の命をきちんと奪えるはずはないのだ。
タムラマロを斃せば終わる、という戦いでもない。朝廷側は平気な顔で次の将軍を任命するだけであり、アテルイが斃れれば同盟が崩壊するというガリア側とは社会の仕組みが異なっている。
ガリアは生活の基盤を、狩猟と交易においた。
畑作もするがあまり馴染まない。米作も行われるが、奮わない。
「気候が変わったからの」と魔女は言う。かつてはガリアの地にも大陸からもたらされた米が稔った。三世紀以降、地球規模の気候変動により稲作の北限が下がる。この気温低下傾向が回復に転じるのは五世紀である。朝廷側はガリアに入植者を送りこむことで「稲作を定着させる」と息巻くが、ガリアとしては大きなお世話といってよい。ガリアは一度稲作を捨て、狩猟型の社会を構成し直していた。その結果、米を蓄積する形の社会には太刀打ちできないということになってはいる。
「お前たちは、本気でやるつもりなのか」とかつてアテルイはタムラマロにきいたことがある。まだ、上京朝貢が停止される以前の話で、朝貢というからには無論、ガリアからも中央へ使節を派遣している。それなりの身分の者があたることになるわけで、若き日のアテルイも同道した。
「やるつもり」というのは、ガリアの地に攻め込むつもりはあるのか、という意味である。
「そうさな」と応えたタムラマロの方もこの時期まだ若輩である。軍服に身を包んでいるが着崩れている。「今のままでは無理だろうな」とアテルイには意外なことを言った。
「準備をきちんと整えることができ、それをまとめる者が出ない限りは、物見遊山にいくのがせいぜいだろう」と冷静な分析を述べるのである。
「俺にならできるが、それを命じるかは上次第だ」
と金色のヒゲを揺らして笑った。
三十八年戦争はおおむね三つの画期を持つ。
まず、朝廷側が無造作に放り込んだモノウの城への襲撃から、カクベツ城築城、そうして、アザマロによる、朝廷側のムツの総責任者である按察使の殺害までの六年。
ここから朝廷も対ガリア政策に本腰を入れることになり、戦闘は徐々に本格化し、散発的に二十二年間にわたり続く。朝廷は最終的に、イサワを根拠地とするアテルイに対し、タムラマロ率いる四万の軍を投入。アテルイとモレは降伏する。これがアテルイの青年期から晩年にあたる。対朝廷戦争に明け暮れた人生であったといってよい。
残された歳月はいわば戦後処理期にあたり、カンムが国力の疲弊を認め、征服戦争の中止を宣言することによって終結に向かう。
朝廷はガリアを異民族と見た。
なによりも言葉が異なっている。
「そういうものではない」と、対岸のイサワをはるかに望むタムラマロは副官のキャシオーに話しかけるのである。
「言葉などは、すぐに変わってしまうものだ」と言う。三代もあれば言葉はすっかり入れ替わってしまう。アフリカに起源を持つタムラマロにせよ、中国に起源を持つカンムにせよ、今は日本の言葉を喋っている。日本語を喋るがゆえに日本人である、というわけではなかった。
「血もまたしかり」というのがタムラマロの考えである。「集団が生き延びるためには、外からの血が必要である」と、従順に耳を傾ける副官へ説く。「親も子も異国の生まれであったとしても、子がその国に属することは当たり前にある。その血が残れば、その血こそが民の本流となる」
そしてこの時期、血筋とははなはだ曖昧なものでもあって、親子関係というものはまた、契約によって結ばれていた。子が集団のものとされることもあったし、拾い子をそのまま実子ということにしたりもした。親と子の間には「何かが受け継がれる」という経験的な法則が化学的な実体を得るようになるにはまだ千年以上のときがかかるが、遺伝子が民族を規定するかというと、
「否」
とタムラマロは答えただろう。
ひとつには、民族なる概念は遺伝物質が特定される以前に生まれ、運用されてきた概念であり、物質のみに発するものではない。
遺伝子なる概念を導入することで、それまで同一と考えられてきた集団が実は何派に分かれていたとか、バラバラに散った集団が実は同一の集団であったと「判明」することはありうるわけだが、新たな区分はただ新たな区分にすぎず、従来の視点からした民族を民族一、後者を民族二としたときに両者は無論、食い違う。遺伝子の明かすのは、それもそこまで厳密でもなく明かすのは生物学的な系統関係だけであり、そこには民族にとって重要な役割を担う不倫も密通も不義の子の姿も現れない。言葉の受け継がれ方と血の受け継がれ方、日用品の様式などもそれぞれに異なる系譜を持ち、民族というくくりとは一致することがない。
「ガリアの人々は」と、アテルイ率いる敵陣と対するタムラマロは言うのである。「自らをガリア人と認めるがゆえにガリア人であるのだ」
「それでは」と傍らのキャシオーは問う。
「将軍が今、自分はガリア人であると宣言なされたら」
「無論、わたしはガリア人だということになるし、アテルイが自分はオオハカという朝廷人だと言えばそうなるのだ」
八〇一年、アテルイとタムラマロの軍勢は最後の決戦に臨み、翌年アテルイは降伏した。
このとき、何度目かの突撃を敢行したアテルイ側の後陣、イサワの柵の後ろには、魔女たちが整然と列をなし、先端を削った棒を構えて踊り、呪詛を叫び続けていた。兵たちの背後に魔女を配置するのは、ガリア古来の戦闘形態である。
すでに長くガリアの地に滞陣していたタムラマロはガリアの言葉の習得に熱心であったから、その魔女たちが、
「バンザイ、タムラマロ、タムラの領主!」
「バンザイ、タムラマロ、ムツの領主!」
「バンザイ、タムラマロ、やがて王となるお方!」
と繰り返し唱えていることがわかった。
まじないはあきらかにタムラマロ個人に向けられており、ガリア側を鼓舞しようとするものではなく、そのことがタムラマロ以外の者を戸惑わせた。
「なぜ将軍を言祝ぐのでしょう」
と翻訳をきいたキャシオーが不思議がるのを、
「だからあなたは正直者だというのです」と傍らにひかえた旗持ちのイアーゴーが笑う。「ガリアの者の言葉を素直に受けとろうなんてね」
魔女たちのまじないを受けるタムラマロの表情に変化は見られない。
「どうされますか」と問うキャシオーに、
「ただ揉み潰せ」とタムラマロは命じ、軍はそのとおりにした。
タムラマロはイサワから、アテルイとモレをヘイアンの都まで連れ帰っている。二人の助命を乞うたが、容れられなかった。
刑場では、ガリア側二人の指導者に先立ち、三人の魔女たちの処刑も予定されていた。
第一の魔女は、
「朝廷よ、朝廷よ、朝廷よ!」
と三度呼びかけ、
「タムラマロに気をつけろ。タムラの領主に気をつけろ」
と告げ、第二の魔女は、
「朝廷よ、朝廷よ、朝廷よ!」
と三度呼びかけ、
「女の腹から生まれたものに朝廷は倒せぬ」
と告げ、第三の魔女は、
「朝廷は決して滅びぬ。広大なガリアの森が、高い雷丘に向かってくるまでは」
と告げ、そうして三人ともに空気の中に泡のように消えてしまった。
ナラの地、イカヅチノオカは、かつて雷神が落ちてきたとされる場所であり、ときの天皇はその雷神を空へ返した。のちに小墾田宮が営まれ、ジュンニン、ショウトク期には行宮としても利用された。空から降りた皇統の故郷の地であるとも言える。
その宮へ、森が押し寄せることがあればと第三の魔女は告げ、そんなことは起こりえぬ以上、魔女たちはむしろ最期にあたり敗北を認め、朝廷を言祝いだのだと言う者があり、タムラマロを警戒せよと告げたことから、ただこちらを惑わせようとしているだけだと言う者があった。
現在、枚方市にはアテルイの首塚を称する石碑が存在するが、これは史的な根拠を欠いた有り合わせであり、そのことは枚方市自体も認める。根拠としては、枚方のとある住人の夢枕に、アテルイが立ったことを置く。侵略側の傲慢さをよくあらわしている。
都までの道中、アテルイは魔女の呪言についてのキャシオーの問いに答えなかった。
「まじないのことはわからぬ」と言い、しかしかわりに、魔女からきいたのだという、ウェルキンゲトリクスなる人物について語りはじめた。
アテルイによれば、ウェルキンゲトリクスはガリアのとある部族の長であり、それまでバラバラであったガリアの部族をまとめ、時の侵略将軍であるカエサルなる人物の軍勢に対抗した。カエサルをほぼ圧倒したが、最後の決戦において不覚をとって降伏。都へと引き立てられたのち、六年にわたり投獄され、最後はカエサルの凱旋時に処刑されたのだという。将軍は最後までウェルキンゲトリクスの助命を検討したが実行に踏み切ることはできなかった。
「俺は六年も待つことはない」とアテルイは結ぶ。
この会話をキャシオーからきいたタムラマロは、
「伝説だな」と応じ、
「千年も前になろうかという昔の話だそうです」とキャシオーがあとをひきとった。キャシオーとしては魔女の言などは、はなから作り話だと考えていて、千年も前の出来事はまだ神々が地上を歩いていた時代のことになるはずだった。
「そうか」としかしタムラマロは遠い目をして「もう千年が経とうとするのか」
とどこか彼方を眺めやっている。
アテルイの処刑をもって三十八年戦争における戦いはほぼ終結し、戦後の処理が残された。カンムは未だ東征を志してはいたものの、諫言を容れ侵略戦争の中止を宣言。翌年、力尽きたように崩ずる。
あとを、カンムの第一皇子平城が襲うが、病のために弟の嵯峨へと譲位、カンムの築いた新都ヘイアンを去り、ナラの旧都へと戻った。病癒えてのち皇権を主張。ここに新都と旧都において二重に皇権が立つこととなり、貴族たちは去就に迷った。
タムラマロは、東征が終了してからもカンムの死後も、征夷大将軍の名で呼ばれ続けた。出陣にあたり授けられ、帰朝とともに返上するはずの将軍号が残されたのは、永世将軍というくらいの気持ちであったのかもしれない。
半ば軍神としての地位にあるタムラマロの振る舞いに注目が集まるのは避けられなかった。
八一〇年、ヘイゼイは挙兵。そのままサガの根拠地であるヘイアンを目指すことは避け、ひとまずは東国へ向かおうとした。これは百四十年近い過去の内乱における勝利側と同じ手であり、東国で兵力を整え、都へ攻め入ることを目的とした。
ヘイゼイは旧都から南下、伊賀路から加太越を経て美濃へ出ようと試みるが、未だ都を出る以前、越田において森に行く手を遮られた。
「森が動いています」とヘイゼイ側の兵が告げ、ヘイゼイの脳裏にかつてアテルイを処刑したときに魔女が告げたという託宣が蘇った。
ヘイゼイの行く手を阻んでいたのは、槍の先に葉のついた枝をとりつけさせたタムラマロの軍勢である。
ヘイゼイもサガもともにタムラマロに位を授けることを約束し、出陣を命じている。
「どうなさいますか」と林立する槍の森を見上げながらイアーゴーがタムラマロに問うた。
「あなたにならわかっているはずだ。これはヘイゼイにつくか、サガにつくかって話だけじゃないことを」
イアーゴーのその言葉に、キャシオーが首を傾げる。
「カエサルは賽を投げましたよ」とイアーゴーは言う。
ガリア平定後のカエサルは、軍を率いたままでは越えてはならぬとされるルビコン川を渡ってローマへ戻り、続く内戦を勝ち抜き、事実上の帝位に手をかけた。
無論、タムラマロとカエサルの間には大きな違いがあるのであって、片や共和政における将軍、タムラマロは専制国家にもなりきれぬ列島の藩王の手下にすぎない。兵を動員したところで、都の貴族は血にこだわり、前帝王の血筋を探し求めて空騒ぎを続けるに違いなかった。
同じく渡来人の血を引くとはいえ、カンムとタムラマロの血は異なる。単純にタムラマロはアフリカにでも戻らぬ限りは、皇統に繋がりようがない。
「わたしの父は」とタムラマロは言う。「新たな王家を立てようとするショウトクとドーキョーの試みを挫くことで、官位を加えた」
眼前のヘイゼイを斃し、都のサガを斃して王権を打ち立てるには兵も足りない。タムラマロの声望により当座を集められたとしても、「新たな王となる」となれば話はまた別となる。朝廷の兵たちはゴタゴタにうんざりこそすれ、新王を望むわけではないのだ。
「朝廷の兵たちならばそうでしょうな」
とイアーゴーは嘲るように言い、続けた。
「しかし、あなたはとっくにわかっているわけでしょう。兵はあるんだ。朝廷を憎み、滅ぼそうとする者たちがあることを。自分たちの存在を認めようともせず、地方史と世界史を取り違えた上に国史とか呼び、官位がどうとかせせこましい身内争いをしている奴らを軽蔑している者たちがね」
「そんなものがどこにある」とキャシオーはあたりを見回す。「兵が地から湧いてでてくるわけはない。人を育てるには長い時間がかかるものだ」
「あんたたちの歴史ではそうでしょうな」とイアーゴーは嘲笑する。「でも、間違いなく兵はあるんだ。なんの手品でも魔術でもない。ただ東に行けばいいだけだ」
「都の周辺の兵を再編したところで――」とまで口にしたところでキャシオーの顔の色が変わり、「まさか――」のあとは続かなかった。
「そのとおりさ」とイアーゴーは言う。「東国で兵を整えればいいだけの話だ」
東を都の東隣ではなく、はるかガリアの地と捉えるならば、そこには先年タムラマロ率いる四万の軍勢に抗し、そうして「壊滅しきることなく降伏したガリアの兵たち」がある。
アテルイとモレの助命を願い果たせなかったタムラマロが朝廷に叛き、ガリアの地に加わって部族社会を糾合し直したならどうなるか――それは無論、歴史上起こりえない事態だったが、今、黒人であるタムラマロにとって、まだでき上がってもいないこの国の歴史などはどうでもよろしいことでもあった。
今ここで黒人であるタムラマロは初期日本において先住民を駆逐した征服将軍であるべきではなく、世界史的な潮流から見て片田舎の前時代的な専制から、朝廷の横暴により虐げられた民を守る将軍であるべきだった。
「あなたになら、今、ここでなぜか黒人であり、明らかに歴史からはみ出してしまっているあなたになら、それを叶えることができるんだ」とイアーゴーが傍らで使嗾を続ける。
タムラマロは黙ったままヘイゼイ側の軍勢を見つめ続けた。
森が動いたというその事実だけをもってヘイゼイ側の隊列は乱れ、すでに及び腰になっている。先方に、女の腹から、正統の歴史から生まれ落ちたわけではないタムラマロを殺すことのできる勇者がいる道理もなかった。
「――行くことにしよう」
とタムラマロは無造作に告げる。
「ただ揉み潰せ」とタムラマロは命じ、黒い森は旧都を目指して動きはじめる。
黒い将軍は去来する千年の流れの中へ、ゆっくりと馬を踏み入れていく。
「タムラマロ・ザ・ブラック」 了