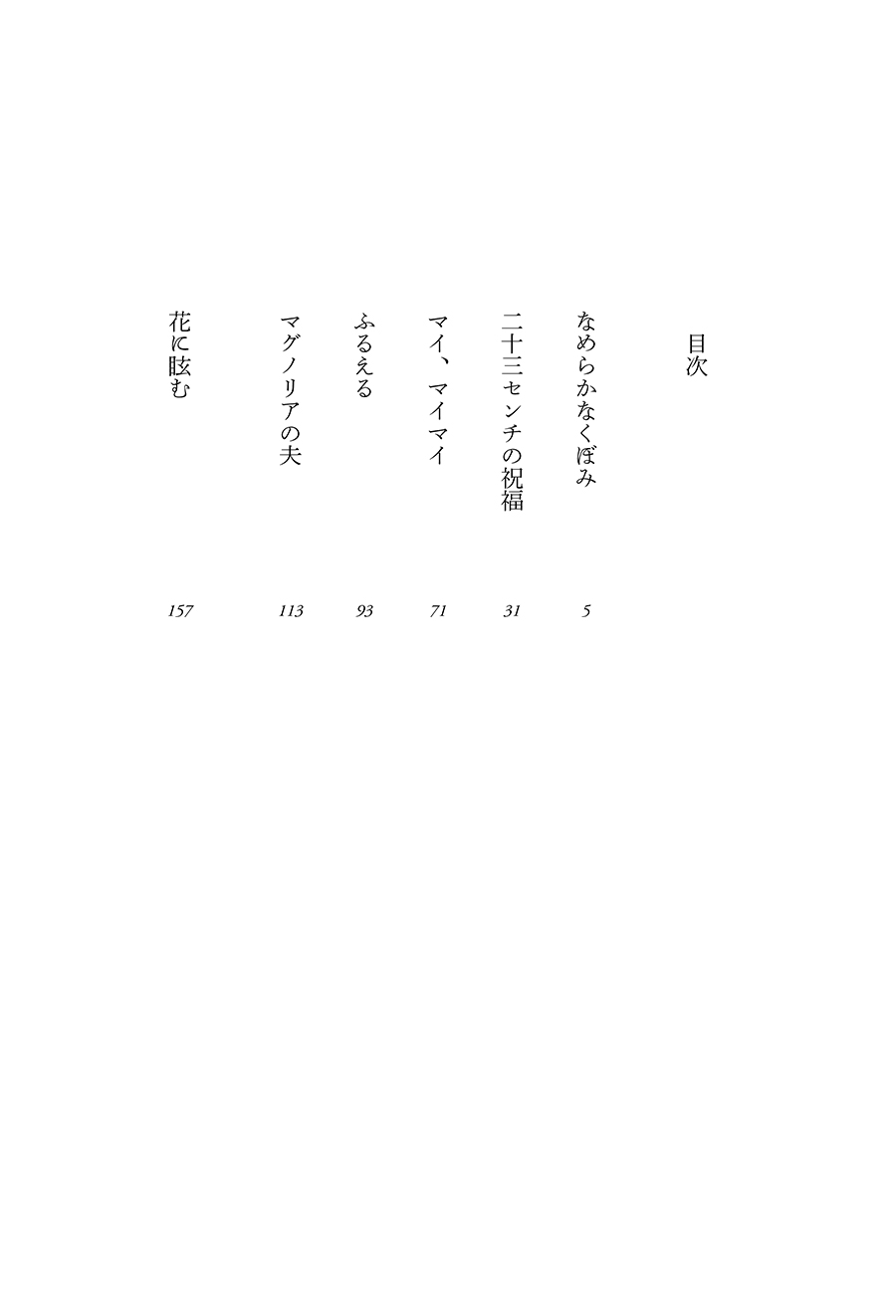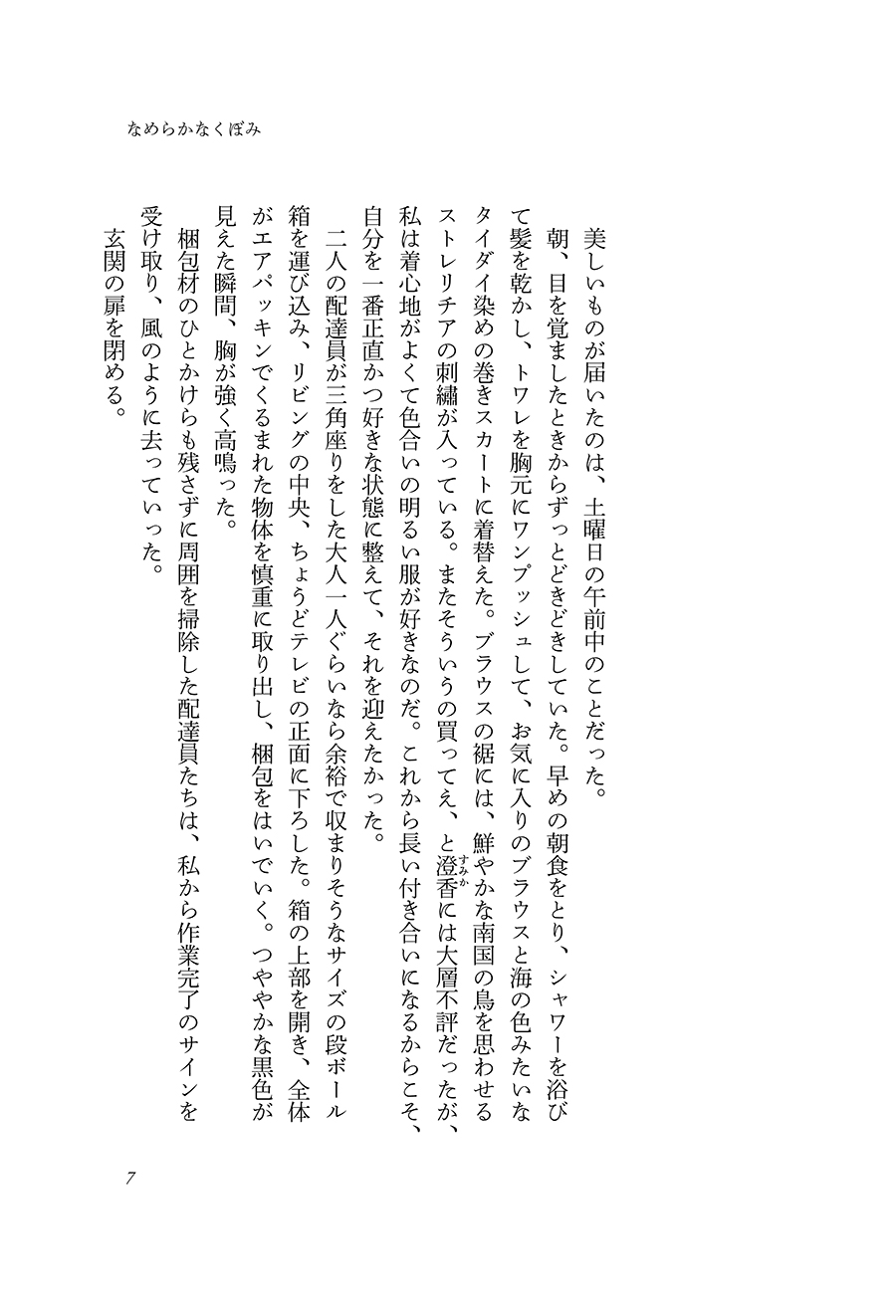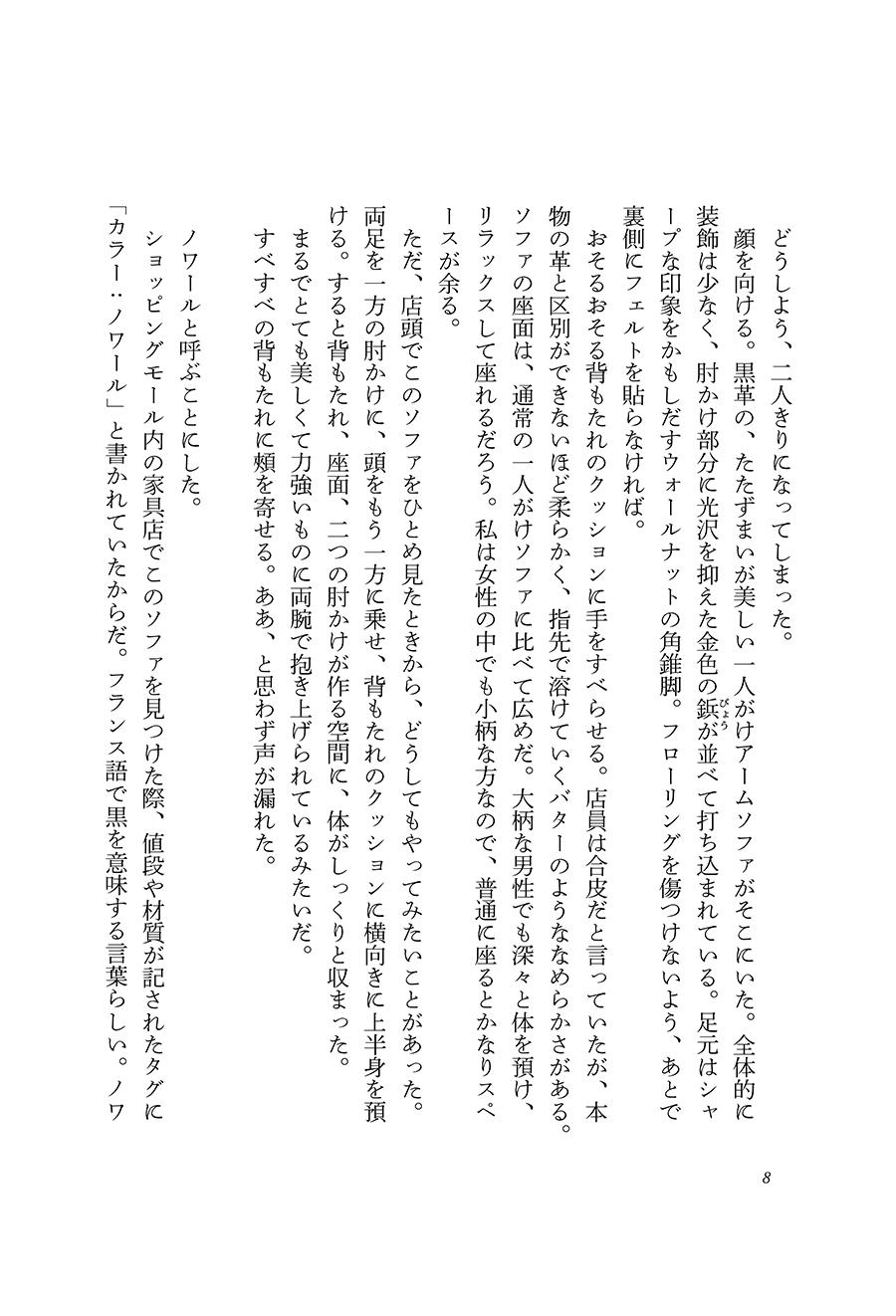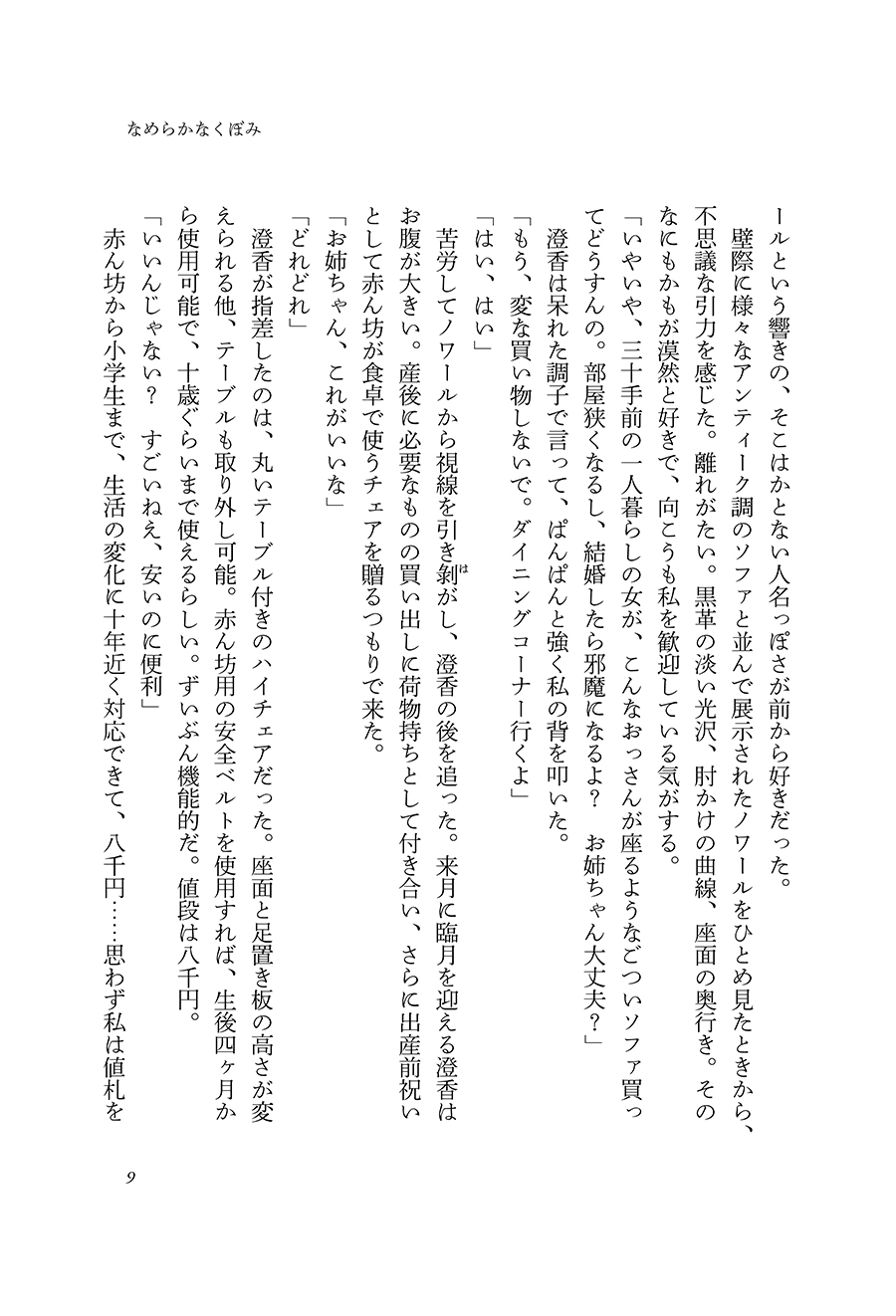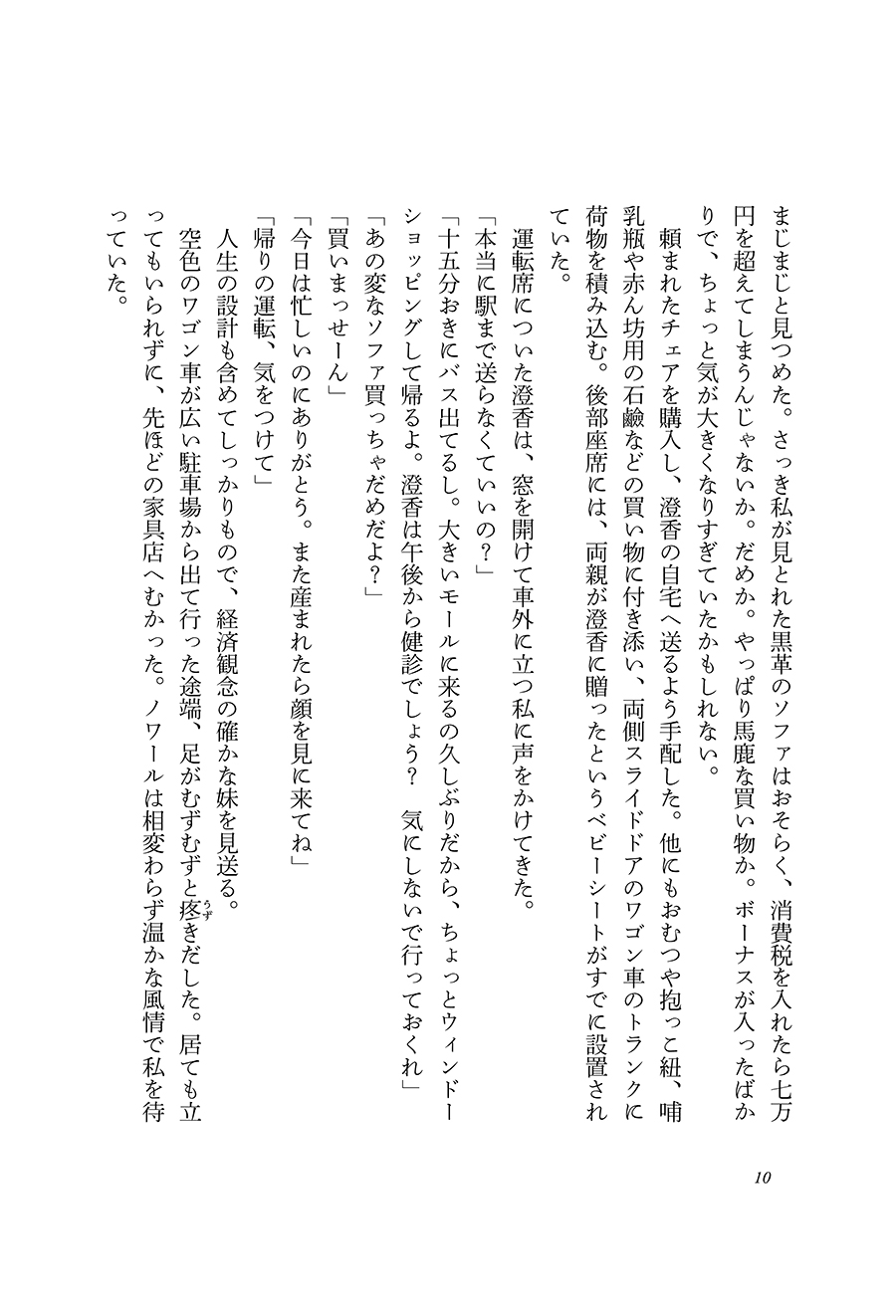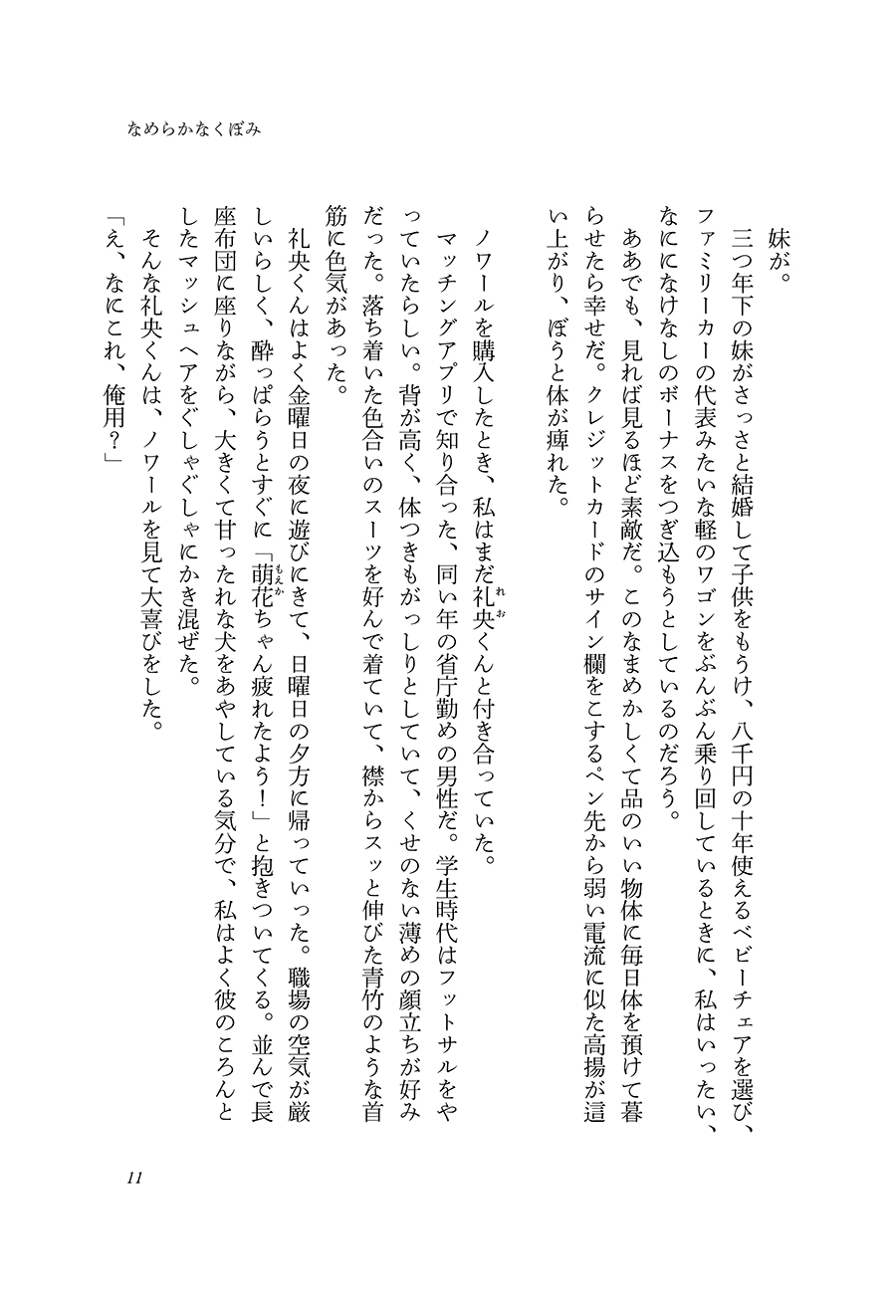ふるえる
どこかで雨が降っている。問い合わせがあったアプリコットグミの入荷予定を確認している最中にそう思った。大きな雨粒が傘の表面で続けざまにつぶれる、少しくぐもった音が鼓膜をくすぐる。私は子供の頃から傘を差すのが好きで、大人になった今もこの音を聞くと少し楽しくなる。
ただ、道端ならともかくオフィスでそんな音がするのは変だ。ぱたたた、と軽やかな音がふたたび響く。左斜め向かいに座るシライさんの手元からだった。来月十日以降の納品になりますがよろしいですか、と書きかけのメールの文章を結び、目だけそちらに動かす。シライさんの左手の、親指を除いた四本の指がノートパソコンの左隅を叩いていた。小指から順に薬指、中指、人差し指がドミノ倒しのごとく連動し、黒く染色されたプラスチックの上を弾む。白っぽい指の腹と短く切りそろえられた爪が、柔らかで歯切れのよい、雨音に似た音を刻む。
もう二年近く同じ部署で働いているのに、シライさんの指を意識して眺めるのは初めてだ。シライさんは考え込んだようすで、少し首を傾けている。きっと手元の仕事になんらかのトラブルが生じ、対応を検討しているのだろう。深く思考するときの癖なのだろうか。これまで気づかなかった。
私よりも少し年上のシライさんは声の小さな落ち着いた雰囲気の人だ。部署の飲み会に出席していてもいなくても気づかれないタイプ。でもほどよく酔いが回った二次会で、私は賑やかな一帯を離れてシライさんの隣に座るのが結構好きだった。普段はあまり無駄話を好む人ではないが、酒が入ったシライさんはいくぶん口がなめらかになり、飼っているカナリアの話をよくした。私の実家には文鳥がいて、小鳥を愛好する者同士の話題は尽きなかった。シライさんは基本的に人の悪口を言わず、声を荒らげることがなかった。くぐもった声を聞きとるために彼の口元へ耳を近づけると、自分がまるで慣れた茂みに隠れた野鳥になったような安らぎを感じた。
素敵さを知っている同僚。それが私のシライさんへの印象だった。
それなのに、どうしてだろう。そのとき私は視界の端でひらめくシライさんの指から目を離せなくなった。端整なオーバル形に整えられた爪がそよぐように浮き、なめらかに落ちる。ぱたたた、と響く音。彼の無意識のリズムを、ずっと聴いていたい気持ちになった。
うなじに小さな針で刺されたような痛みを感じ、あ、まずい、と思った。そして実際に、まずかった。
その日から私はシライさんの挙動のなにもかもが好ましく思えて仕方がなくなった。シライさんと目が合うとうなじが熱っぽく疼いて心臓が高鳴り、まともにしゃべることができない。あっさりしている、とそれ以外の感想を持たなかったシライさんの風貌は吸い込まれるほど魅力的に、周囲の人間にあまり興味がなさそうな話題選びは慎み深い理性の反映だと感じるようになった。
意識しないようにしようと思っても、職場が同じなのだから否応なくシライさんとは会ってしまう。オフィスで、食堂で、ロッカールームで、すれ違うたび雷に打たれたように体をこわばらせる私は、そうとうに不審だっただろう。シライさんに会うと苦しい。なのにもっと近づきたくて仕方がない。ことことと、体の内部で震えが起こる。
「ピアノとか、やってたんですか?」
食堂で近くに座った際に、紅茶が入った温かい紙コップを両手で持って震えをこらえながら聞いた。指を順々に動かすあの可憐な癖の由来をあれこれ想像していたのだ。シライさんは不思議そうに目を見開いて、「いいえ」と短く返した。驚きで持ち上がった眉の可愛らしさに胸がいっぱいになり、「そうですか、それでは」と不自然に会話を切り上げて席を立った。シライさんの口に耳を近づけて穏やかな心地で小鳥の話を聞くなんて、もう二度とできそうにない。とても好きな時間だったのに。
シライさんに近づくたび私の体内で細かに弾み、存在を訴えるものが既に生まれていた。その振動がどうしようもなく私の感情の調律を乱し、シライさんに対して極端な行動をとらせ続ける。これ以上こらえていては、私が私ではなくなってしまう。
指に見惚れた日から二ヶ月ほど経った薄曇りの水曜日。通勤途中の公園でほころんでいた桜のつぼみに励まされ、昼休みにシライさんを空き会議室に呼び出した。シライさんは胚芽入り食パンにスモークサーモンとクリームチーズとレタスを挟んだサンドイッチと紙パックのミルクティという、会社近くのコンビニで売られているいつも通りのランチの組み合わせを持って現れた。
「ネムさん、もしかして」
「はい」
指も、体も震えている。特有の振動が脳の神経伝達物質を放出させる。飲み会で隣に座ると、シライさんはいつも微笑んで迎えてくれた。望みはゼロではないはずだ。彼の体内にも、それは生まれているかもしれない。
「私と、石を交換してもらえませんか」
シライさんは口を真一文字に結んだ神妙な顔つきになった。
「残念ながら、私の内部に石は発生していません」
はっきりと告げられ、体中の力が抜けた。膝がふらつき、その場にしゃがみこんでしまう。
「ああ、残念、です……」
「そういうことだったんですね。ここのところ、なんだか落ち着かない様子だとは思っていました」
「失礼な態度をとってしまい、すみませんでした」
「いえいえ、そんな大変なことだったなんて」
背を撫でられて、涙が出た。シライさんに触れられてうれしい。願いは叶わなかったのにうれしい。高い位置から、いたわりに満ちた声が降ってくる。
「こうしているのも辛いですよね。じゃあ早く取ってしまいましょう。石の位置は分かりますか?」
すぐに返事ができなかったのは、惜しいと思ったからだ。苦しくて楽しい、甘ったるい錯乱から抜け出すのが惜しい。石に蝕まれているときはいつもそう思う。
でも、このままでいるのはとても危険だ。桃色の石を嚙み砕いた、オキナ先輩の笑顔が脳裏をよぎる。
「うなじ……うなじだと思います」
「失礼します」
辛うじて皮膚が重なるくらいの控えめな手つきで、シライさんの指が首に触れた。振動が強くなる。それが体の中を移動して、喜びで発熱しながら彼の指に近づいていくのがわかる。
「ああここだ。脈打っている」
やりますね、と声をかけられてすぐ、冷たさに似た痛みがスッと皮膚の表面を這った。薄皮を爪かなにかで切られたのだろう。温度の低い指先が肉と肉の間にもぐりこみ、こごった塊をかき出す。ああ、シライさんの指が体の中で動いている。彼の動きが伝わる。うれしい、うれしい、うれしい!
塊が完全に体から離れた瞬間、うれしい、と感じていた心がぷつりと絶たれたように消え失せた。
代わりに不定形の、濃霧に似た喪失感が押し寄せる。中の湯を捨てた茶碗のように、鈍く体に残る熱がじわじわと下がっていく。満たしていたものがなくなったさみしさで目尻に涙が浮かび、それなのにほんの数秒前に自分を満たしていた甘く苦しい感覚はまるで思い出せない。
「ちゃんと取れました。かわいらしいオレンジ色だ」
明るい声につられて顔を上げる。するとシライさんは私の前にしゃがんで、てのひらにのせた石を見せてくれた。サイズも形もそら豆みたいなその一粒は、たしかに少しミルキーな色合いのオレンジ色だった。うちの会社が販売している業務用のアプリコットグミに少し似ている。とはいえ、石にかわいいもかわいくないもあるものか。一歩間違えば命を奪うこともある危険な物体だ。
のんきな人だなと呆れに近い、なんの熱も孕まない感情がすっと湧き上がり、私は肩をすくめた。オレンジ色のそら豆が、シライさんのてのひらの上でかすかに揺れる。まばたきしていたらわからなくなりそうな、一ミリにも満たないかすかな震えを数秒ごとに繰り返す。体の中に在るときはずいぶん大きく感じたのに、こうして眺めると本当に些細な物体に振り回されていたんだなと不思議な気分になる。
「もう捨てちゃってください、そんなの」
「いえ、本人の前で捨てるのはマナー違反なので、ひとまず持ち帰ります」
シライさんはオレンジ色の石をハンカチでくるみ、ポケットに入れた。
「ああ、震えている」
おかしそうに言うので少し腹が立ち、続けて私にもおかしさが込み上げた。
「シライさん」
「はい」
「また飲み会でカナリアの話をしてくれますか?」
「もちろんです。それじゃ、ネムさんも早くお昼食べないと休憩時間が終わっちゃいますよ」
サンドイッチとミルクティを大事そうに持ち直し、シライさんは会議室を出て行った。
シライさんにふられた私の話に、「あいかわらず軽率な恋をしてるね」としみじみ相槌を打ったのはクレハだ。
「軽率って」
「相手になんの働きかけもしないうちに告白してどうするの。いきなり打ち明けたって、石なんか生まれてるわけないじゃない。もっとその気にさせてからにしなきゃ」
「えー。どうすればその気になるのよ」
「親しく話しかけるとか、適当な方便で遊びに誘うとかさ」
「シライさん、職場であまりおしゃべりしたいってタイプじゃないもん。遊びも、なにが好きかなんて知らないし」
「そんなよく知らない人のことをどうして好きになったの?」
まさかパソコンの縁を叩いていた指が気になって、だなんて言えない。私はぬるくなった缶ビールをあおって八分咲きの桜を見上げた。二畳ほどのビニールシートにはビールの他にタッパーに入った炊き込みご飯のおにぎりと唐揚げ、きゅうりと人参の糠漬けが並んでいる。
「まあ、こういうのは交通事故に遭うようなものだからさ」
クレハの横であぐらをかいたゼンが取りなすように言ってくれた。ゼンの膝の上では、父親の胸板に柔らかい頰を押しつぶして生後四ヶ月のミツくんが眠っている。小学校の先生をしているゼンは同じ職場の人と結婚して、今年の始めにミツくんを授かった。赤ん坊がいては外出は厳しいかとも思いつつ、ダメもとで花見に誘ってみたら、むしろ妻を休ませたいからミツも連れてっていい? と聞かれた。拒む理由はなく、つい先ほどまで芝生で寝返りを打たせたりおもちゃを揺らしたりと一緒に遊び、一時間経ってようやく寝てくれた。私とクレハとゼンは高校の合唱部の同期生だ。今でも家が近所で、ゆるやかな交流が続いている。
「実際、ゼンとパートナーさんの関係は交通事故みたいな感じで始まったの?」
多少のやっかみもあって聞いてみる。ゼンは遠くの景色に目を凝らすような顔でうなりながら首を傾げた。
「どうだろう? 俺はあの人のことを会ったときからいいなって思ってて、だんだん石がふくらんでいって、そうしたらあの人が石を交換しないかって言ってくれて、それで」
「スムーズすぎてなんの参考にもならない」
ねえ、と同意を求めてクレハを振り返る。するとクレハは米粒でも食べこぼしたのか、ビニールシートからなにかをつまみ上げていた。ウェットティッシュを差し出すと、ありがとう、とうなずかれる。
「うまくいくときってそういうものかもね。それに……いいじゃない。もう辛くないんだから。シライさんがちゃんと取り出してくれたんでしょう? いい人だね。病院で取り出すとなると結構お金かかるし」
「医者の指をいやがって体の奥に逃げるから、痛いんだよな」
「あー、そうだね。シライさん、親切だった。ぜんぜん痛くなかった」
今となってはなにも思うことはないが、あの人と共鳴できたらきっと私は幸せになれたのだろう。好き合った相手と取り出した石を交換し、それぞれの体に空いた裂け目に入れる。すると喜びに震える石同士が共鳴し、私たちは一人で石を膨らませていた頃よりもずっと深い、たゆたうような喜びを得られるのだという。
「ねえ、共鳴ってやっぱり幸せ? いいもの?」
三人の中で、恋が成就した体験を持つのはゼンしかいない。ゼンはまた遠くを見るようなしかめっ面をして、んー、うん、とうなずいた。
「いいものだと思うよ。すごく落ち着くし……こういう感じになりたかったんだって、わかる。でも、うーん」
「でも?」
「もう俺はこのまま、どこにも行かないんだなって変な気分になる」
私とクレハは顔を見合わせた。どうやらゼンは私たちのそれとは全く異なる、ややこしい悩みを抱えているようだ。
「ゼンはもっと多くの悲恋を重ねたかったってこと?」
「いや、そうじゃなくて。たぶん誰かやなにかを好きになって石を捧げるのは、命の使い方を決めることなんだ。俺はもう決めたことになる。だから、ときどき決めてなかった頃がなつかしい。なんだろう……なにかを失った気分になるのかな?」
クレハが顔をしかめてゼンの背中を叩いた。
「贅沢な悩み! こっちは捧げたくても捧げられなくて苦しんでるっていうのに」
ミツが起きるだろ、とゼンは迷惑そうに肩をすくめた。
りり、と涼しげに響くかすかな音がどこからやって来るのか、初めはわからなかった。そのくらいその音は小さくて、しかもすぐに鳴り止んでしまった。
ロッカールームで聞くことが多いと気づいてからは、意識して耳を澄ませるようにした。不思議とその音は私の心を引きつけ、聞き流すことができなかった。
シライさんがロッカールームにいるときによく鳴っている。そこまでわかれば、探す場所は一つだ。他の社員がいなくなったタイミングを見計らって、四つ離れたシライさんのロッカーの扉を開けた。音をなるべく立てないよう、慎重に。
コートや鞄がかけられたハンガーパイプの上の棚に、ガラス製の小瓶が八つ並べられていた。左端の小瓶の中身に見覚えがある。ミルキーなオレンジ色の石。その隣の石は、透き通った深い緋色だ――ずいぶん高い純度で思い詰めたのだ、きっと。その隣は眺める角度によってうっすらと虹色の光をまとう淡いグレー。さらに隣は、星々に似た無数の銀の粒を内部に閉じ込めた紺碧。さらに隣はこっくりと濃厚なピンク。さらに隣は――
「了解もなく人のロッカーを開けないでください」
私は一体どれだけの時間をそこで立ち尽くしていたのだろう。いつのまにか、シライさんが顔をしかめて傍らに立っていた。
「すみません」
「本当ですよ。なんですか、まだ石が体に残っているんですか?」
「そうじゃなくて」
「とにかく、そこをどいてください」
シライさんがロッカーの扉に手をかける。その途端。
りり、と左端の小瓶が鈴のような音を立てた。シライさんの接近を感知した私の石が喜びに震え、小瓶に体を打ちつけている。その音色が、リズムが耳に届いた途端、奇妙な焦りが込み上げた。シライさんが好きだ。いや、好きじゃない。シライさんを体の中にいれたい。シライさんの体にもぐり込みたい。いや、もうそれは終わったじゃないか。衝動に振り回されて胸が悪くなる。
「シライさん、それを捨ててください。それか瓶から取り出して。音が……気になって」
「え」
シライさんは急いでガラス瓶を開け、私の石を取り出した。手の中に握りしめる。音は止んだけど、きっとそれはますます喜んでいるんだろうな、と他人事のように思う。
「そうか。あなた以外の人たちはここのロッカールームを使っていないから、今まで気づかなかった。ごめんなさい、迷惑をかけました。ここに保管するのはやめます」
「保管……変わった趣味をお持ちですね」
「そうですか?」
「というか、すごくモテるんですね、シライさん」
目立たない人だと思っていたので、意外だった。シライさんの指先のひらめきに惹かれたのは、私だけではなかったのか。石を取り出すのが上手なわけだ。
「モテてるんですかね?」
「十分だと思いますよ」
「ネムさんはこれまでにいくつの石を受け取りましたか」
「そういうこと聞くんですかあ? 学生時代に一つだけです」
あいにく私は、石の交換を提案してくれた他クラスの生徒の名前すらおぼろげだった。丁重にお断りし、ぽろぽろと泣いているその人の鎖骨のくぼみから慎重に石を取り出した。表面の薄皮が爪ではうまく切れず、カッターを使ったら少し血が出てしまって、申し訳なかった。摘出した石は
「八つもあると壮観です。少し怖い」
「怖いものですか?」
「私は高校時代の先輩が結晶死したので、石には怖い印象があります」
私が初めて石を発生させた相手だった。快活で笑顔が人なつこい、ハンドボール部のエースだったオキナ先輩。多くの学生があの人に心を奪われ、石を捧げた。私もその一人だった。うれしいよ、でもごめん、今は部活のことしか考えられなくて。まるでセリフのように同じ断り文句を繰り返し、泣いている相手を慰めるように先輩は摘出した石を口に含み、嚙み砕いて呑み込んでみせた。それが当時の
数十人分の石を笑顔で飲み下した先輩は、しかし卒業間際に自室で死んでいるのが見つかった。まことしやかに広まった噂によると発見当時、先輩は喉から左胸にかけてが赤紫色の石に変化し、喉を掻きむしるような姿勢で硬直していたらしい。石が育つ速度にはばらつきがあるとはいえ、体表を侵食するほど巨大な石となると年単位の恋だ。誰も先輩の恋に気づかず、先輩も誰にも打ち明けなかった。
オキナ先輩の話を聞きながら、シライさんは要領を得ないとばかりに首を傾げた。
「慕った相手に打ち明けたっていいし、言いにくいなら病院に行って摘出してしまえばいい。ときどき結晶死する人の話は聞くけど、正直わからないですね。なんでそんな妙な行動をとるのか」
「えー……石が育っているときは、情緒がぐちゃぐちゃになってるから冷静な判断なんてできませんよ。秘めた想いと心中するような気分になっちゃったんじゃないですか? え、シライさんってもしかして」
「そうですね、石が発生したことはありません。誰かに気安さを感じるくらいなら、あるんですが」
平然と言われて驚いた。私は人よりも石ができやすいくらいなので、石をまるで発生させずに長い年月を生きるイメージがまるでもてない。
「たまに……ほら、月とか海とか火山とか、そういうものに焦がれて石ができる人の話を聞きますが」
「いや、特にそういうこともなく」
「仕事とか、国とか」
「仕事は、まあ普通ですね。国も特には。きっと私は、全般的に情熱と呼ばれるものが人より乏しいんだと思います。思い詰めるほど欲しがるということがない」
「カナリアは?」
「これらの石と同じです。美しいなと思って、大切に世話しています」
はあ、と思わず深いため息がもれた。
「私の恋って、本当になんの望みもなかったんですね」
「そうですね。残念ですが」
「私の石だけでなく、こんなにきれいな他の七つも」
壮大なエネルギーの無駄だ。どうしてこの世はこうも成就しない恋を発生させ続けるのだろう。誰にも必要とされなかった石たちを集めて、世界平和とかに役立てられたらいいのに。
「そういえば、他の七つは鳴らないんですね。シライさんが近づいても」
「あれ、ご存じないですか? 石は摘出して二週間経つと動かなくなります。それまでに思う相手の体内にもぐり込めば動き続けられるようですが。たぶん元の持ち主から分けられた命が、その期間で尽きるんでしょうね」
口にして、シライさんはううん、とうなった。自分で言った内容に納得していない素振りで、もう一度口を開く。
「分けられた、というより、生まれた、ですかね。あなたから生まれ、時々あなたの脳にいたずらし、人体を離れると二週間しか生きていられない、小さくて美しくて厄介な生き物がこれです。かわいいでしょう?」
そう言って、自分の手のひらにのせたオレンジ色の石を見せてくる。
「ぜんぜんかわいくないです」
私は苦々しい気分で、振動するそら豆から目をそらした。
「かわいくないけど、生まれるものなら、意味がなくても仕方ないですね」
「仕方ないんじゃないですかね。私にはわかりませんけども」
ふふ、とシライさんは少し楽しそうに笑う。
この人にはあんがい人が困っている姿を楽しむような意地の悪い性分があるのかもしれない。石に蝕まれていた頃より、シライさんのことがよく見える。そうして見えた新しいシライさんのことを、私は、それほどきらいではないと思った。
夕方になるとミツくんがぐずってしまうからと、ゼンは一足早く荷物をまとめて帰っていった。ゼンが持参した唐揚げと糠漬けが入っていたタッパーもなくなり、クレハと二人で広くなったビニールシートに足を伸ばして座る。風が吹くたび、光沢のある花びらが雨のように降ってくる。
クレハは飲みものの入ったクーラーボックスを覗いた。
「ビール、ラスト一缶でーす」
「半分こにして飲もうか」
「そうしましょ」
「クレハ今日ちょっとピッチ早くない?」
「そんなことないよん」
タブを起こし、一口飲んでこちらに缶を差し出す。その友人の袖口から、ぽとりと青色の石が落ちた。南国の海をくり抜いたようなネオンブルーが、私たちの動きに合わせてビニールシートの上を転がる。
「え?」
クレハはビールの缶を持ったまま、落ちた石を見つめて黙っている。私はひとまずビールの缶を受け取り、続いて石をつまみ上げた。
「これ、誰の石かわかる? クレハの石?」
聞いてみたものの、自然に体から落ちたということはきっと、彼女自身の石ではないのだろう。
長いためらいを経て、クレハはやけに平べったい、抑揚の乏しい口調で言った。
「私の石じゃない」
「じゃあ誰の?」
「ソラチカさんの」
ソラチカさん、はクレハが以前から秘かに石を膨らませていた同僚の理学療法士の名前だ。え、交換できたの? とはしゃぎかけて、それならこんな風に彼女の体から石が落ちるはずがないと思い直す。クレハは歯でも痛むかのような、左右のバランスを欠いたぎこちない表情で続けた。
クレハとソラチカさんの勤め先は地域医療を一手に担う大きな総合病院だ。だから、退勤したソラチカさんがバイクで帰宅する途中に信号無視のトラックに側面から衝突された際、運び込まれたのは他でもない、つい先ほどまで勤務していた彼自身の職場だった。
「もう運び込まれたときには亡くなってた。けどさ、彼のご家族が見る前に少しでもご遺体の様子を整えたくて、それで」
止血を始めとする死後処置を行っていたクレハの手に、たまたまこの石が転がり込んできたらしい。彼の印象そのままの、きっぱりと潔いネオンブルーをどうしても手放すことができず、彼女はそれを自分のポケットにすべり込ませた。
「ああ運命だ、あの人の石と一緒に生きていこうってボロ泣きしながら自分の石の摘出手術を受けて、代わりにこれを入れたのに。私の体をいやがって出てくるの。ぴくりとも震えないくせに、気がつくとぽったーんって落ちるの。私じゃないの。この石が行きたかったのは、他の人の体なの。そばにある私の石ばっかり震えてて、こっちは微動だにしないの。結局一度も共鳴しないまま、おとといやっと私の石が死んだ」
クレハはもどかしげに眉間にしわを寄せ、トートバッグの内ポケットからマスカットグリーンの石を取り出した。こちらが彼女の石だろう。石を摘出し、恋心はすでに失っているのに彼女はまだ苦しそうだった。目を射るネオンブルーと、とろりと曇ったマスカットグリーン。まったく色合いの異なる二つの石がビニールシートの上で静かに触れ合う。二つとも動かなくなって、やっと。
「やっぱり基本的につじつまって合わないよね」
「合わない。合ったためしがない」
力を込めてうなずいたクレハは、自分でも困惑した様子で眉をひそめ、ぽつぽつと続けた。
「でも、楽しかったんだよ。なんにもうまくいかなかったのに、あの人を好きでいるあいだ、本当に楽しかった」
「うん」
「きっと、ソラチカさんもそうだったと思う」
私はクレハの背後に座り直し、両腕で友人の体を抱いた。コットン素材のニットに覆われた柔らかな背中に耳を当てる。意味もなく生まれて震え続けるのは、石じゃなくて私たちの方だ。本当は誰ともそろってない、たった一人のリズムで。
「来週もお花見しよっか」
今の花が終わる頃には、遅咲きの花が咲くはずだ。クレハは答えず、二粒の石を握ってうつむいている。
「シライさんも呼ぼうかな」
てんでばらばらに震えることも、微動だにしないことも、そう変わりはしないだろう。きっと楽しい宴になるはずだ。白っぽい花びらが頰へ貼りつく。ふ、と曇天へ向けて吹き飛ばした。