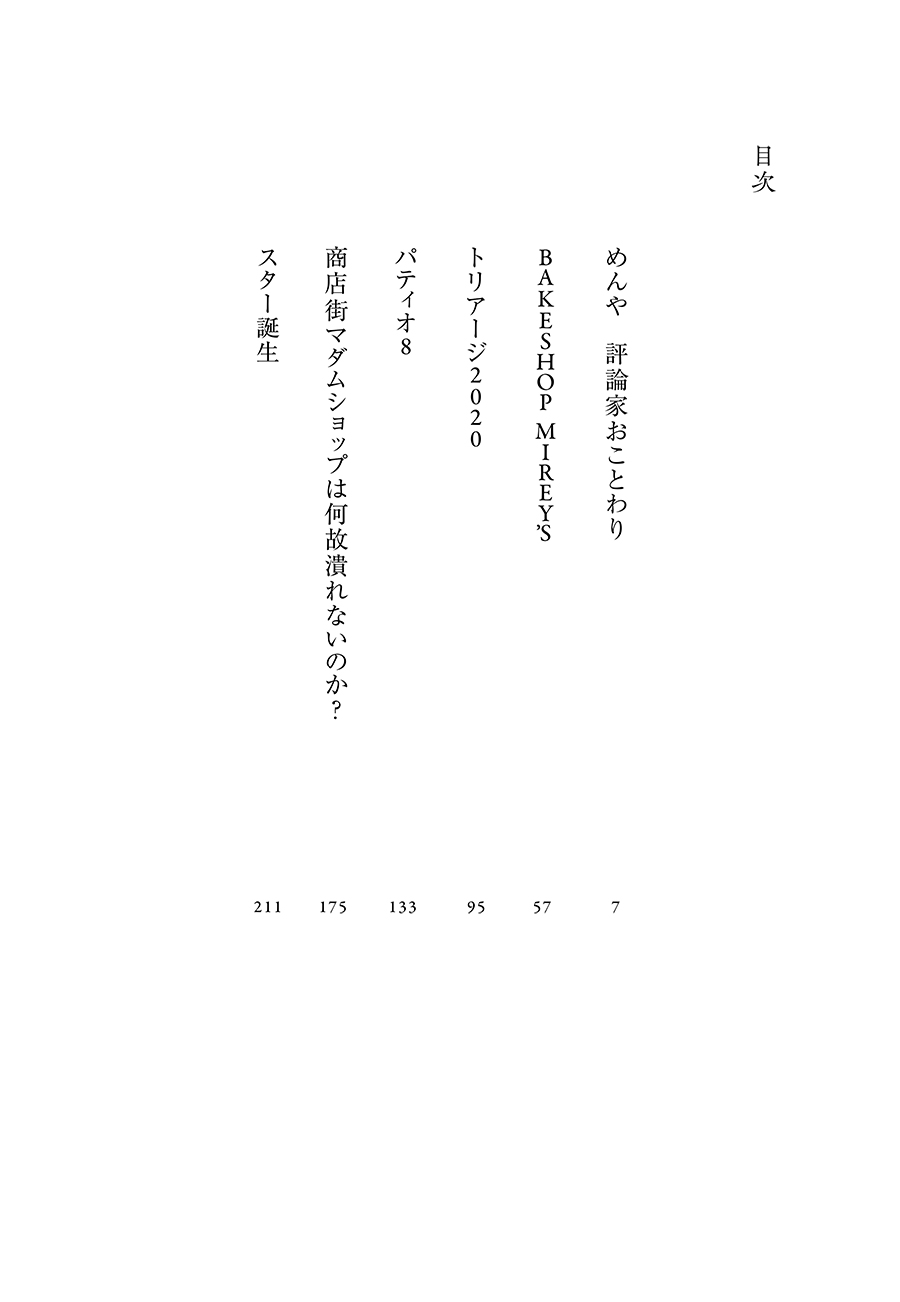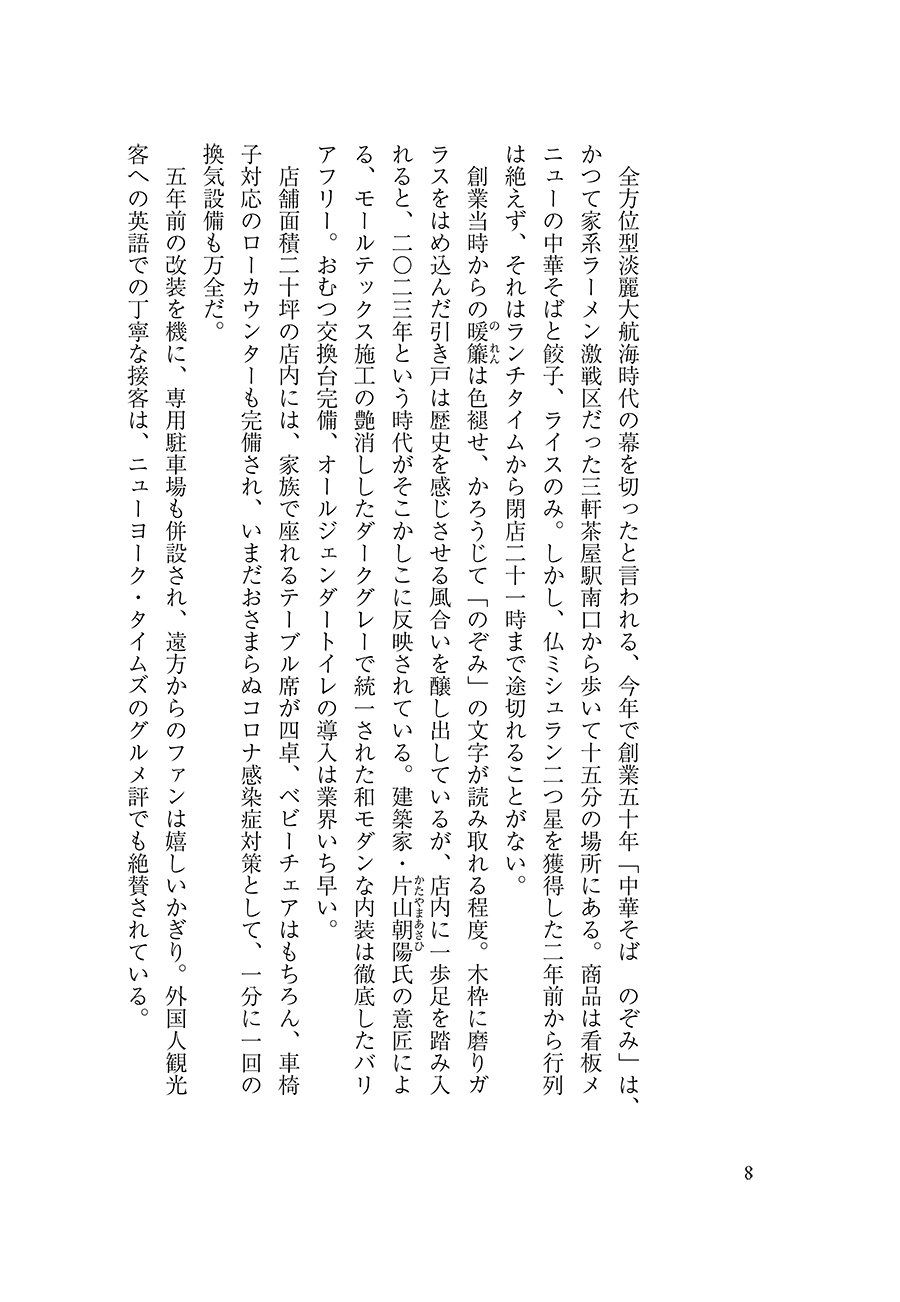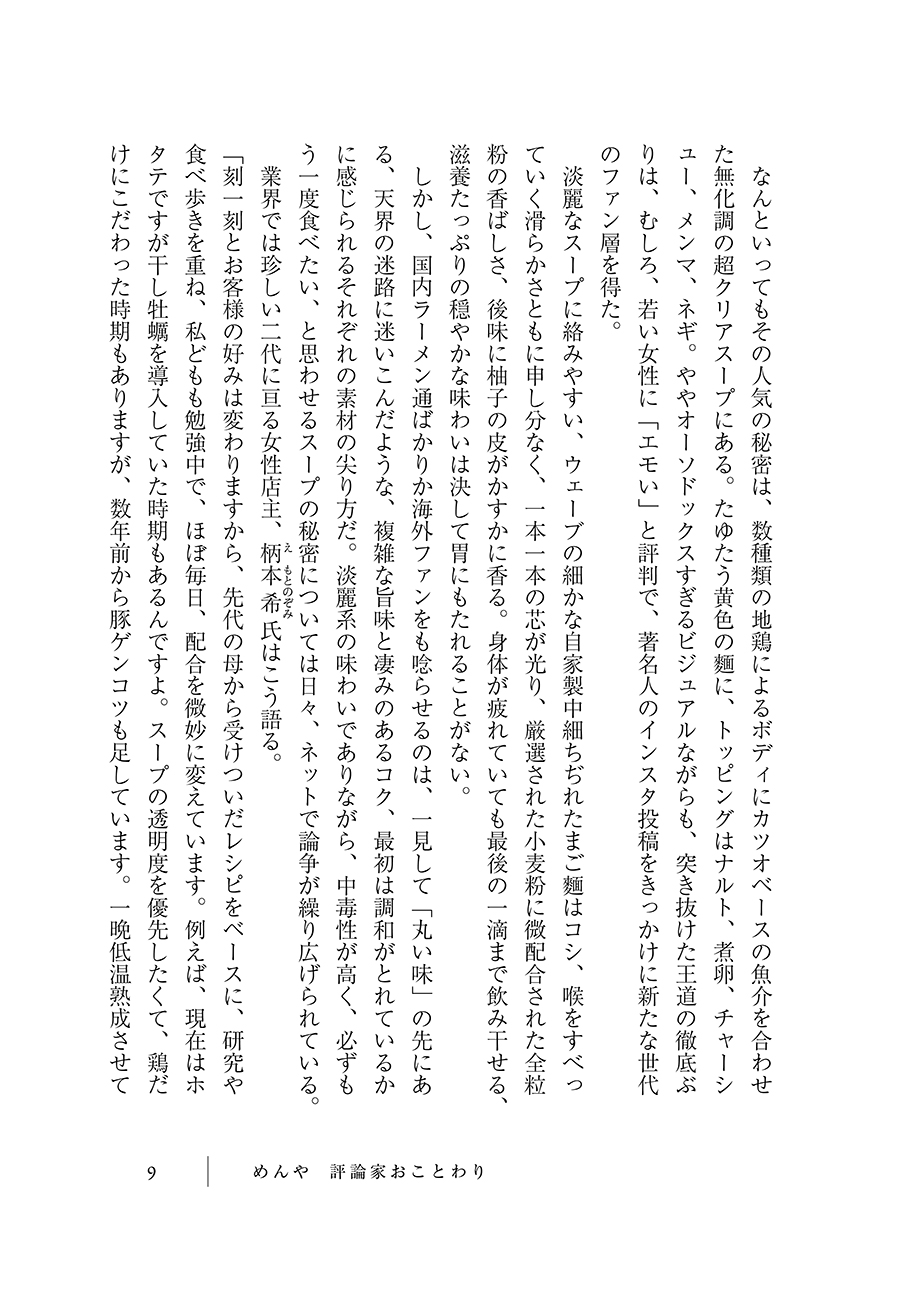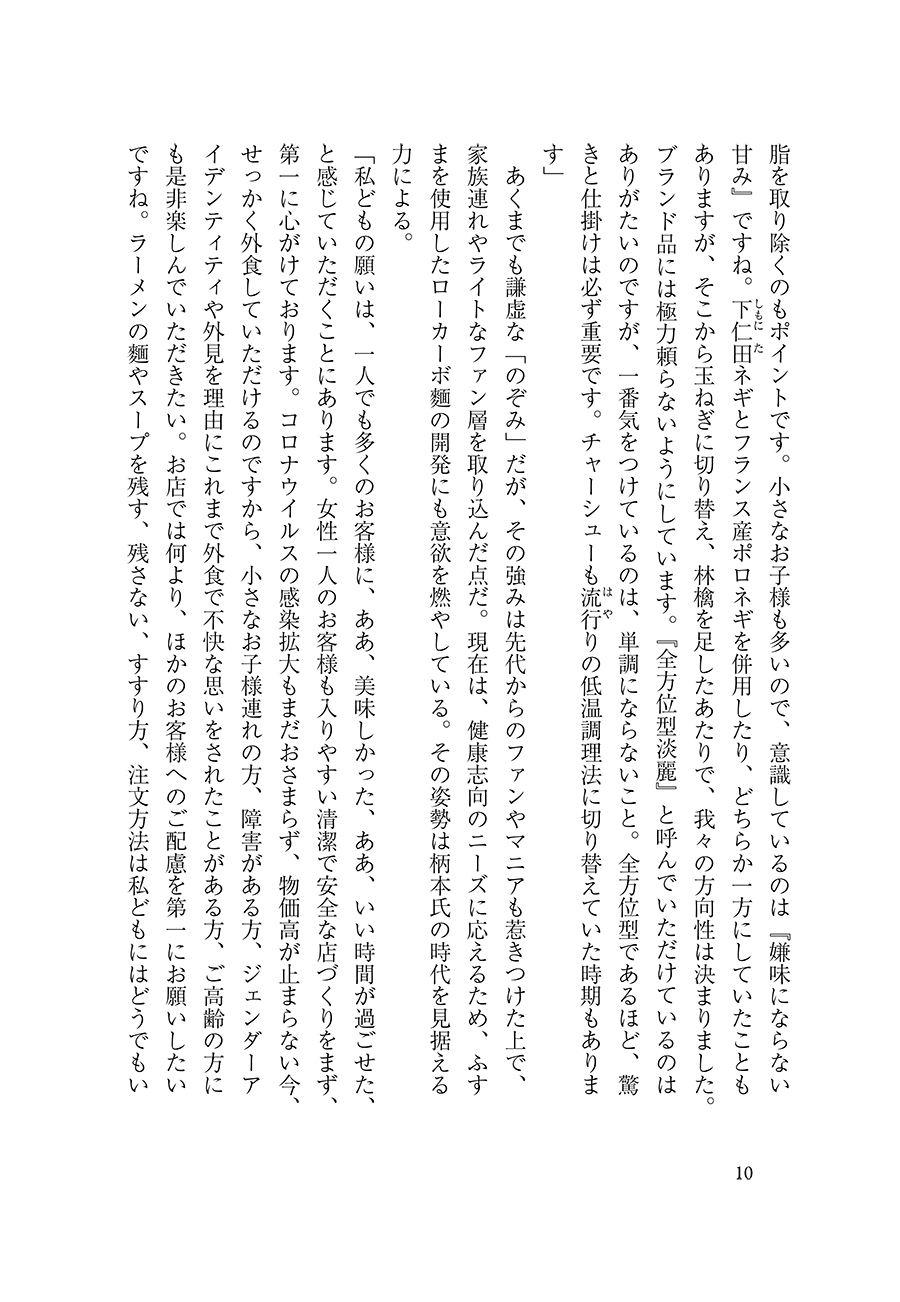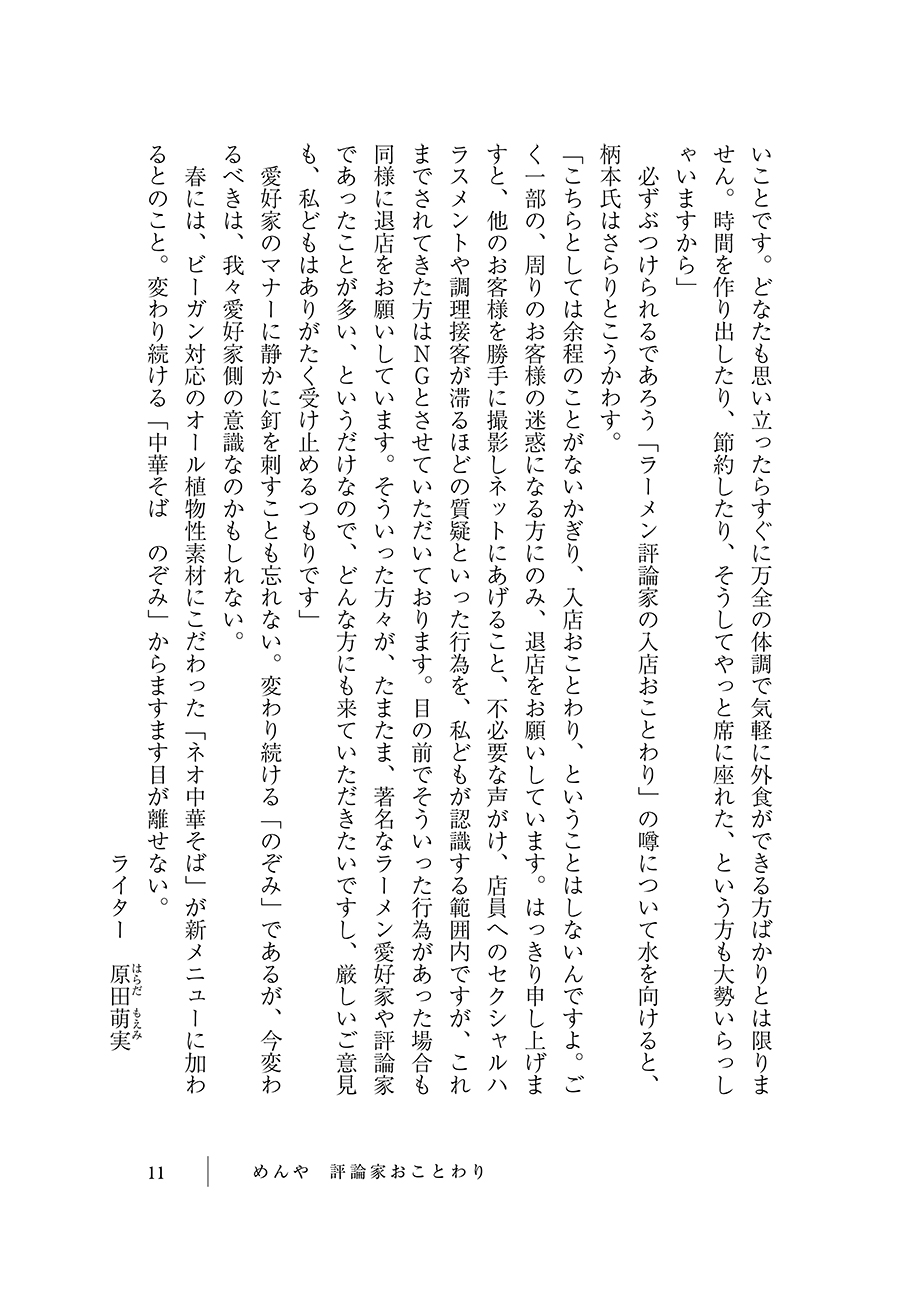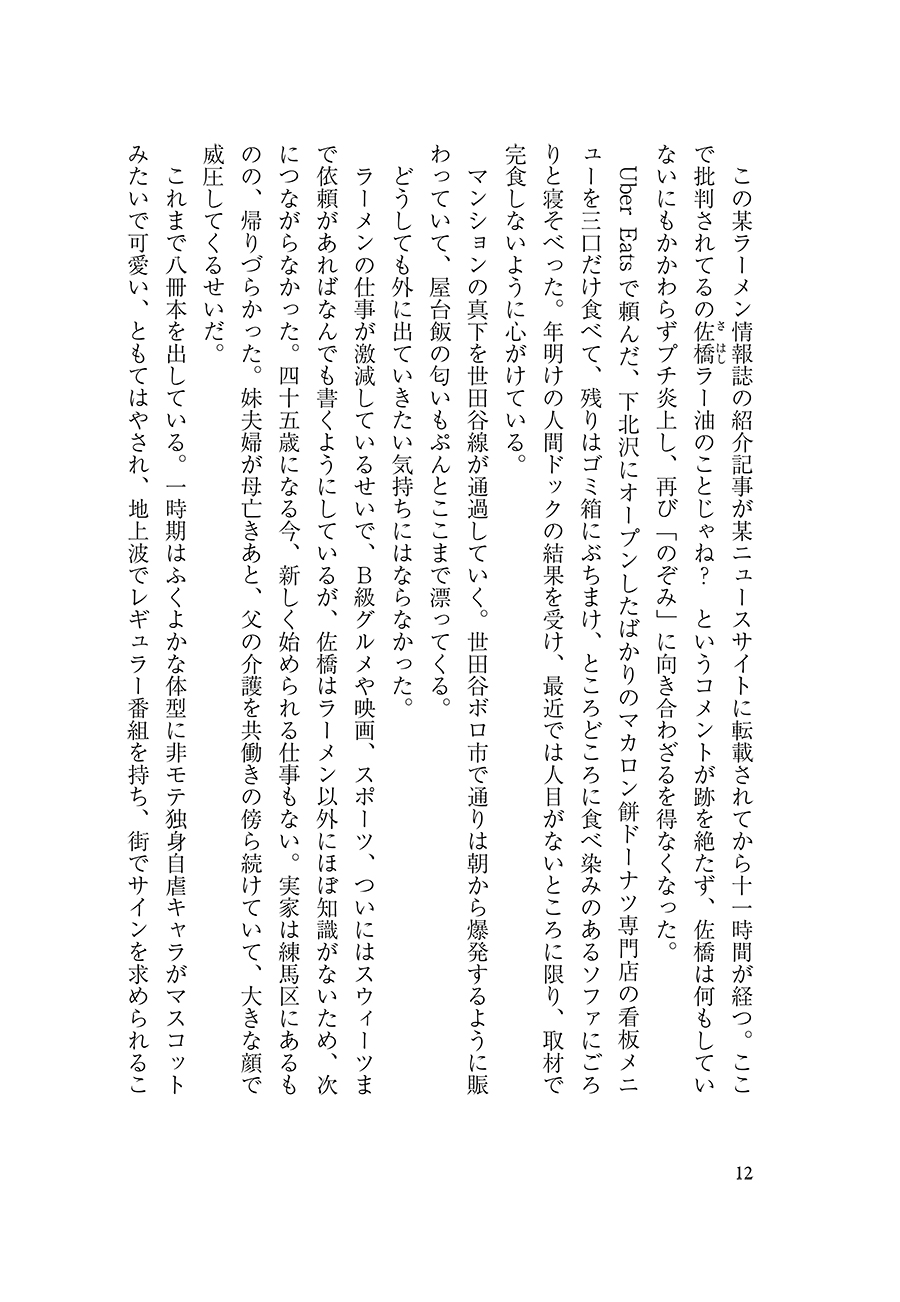めんや 評論家おことわり
全方位型淡麗大航海時代の幕を切ったと言われる、今年で創業五十年「中華そば のぞみ」は、かつて家系ラーメン激戦区だった三軒茶屋駅南口から歩いて十五分の場所にある。商品は看板メニューの中華そばと餃子、ライスのみ。しかし、仏ミシュラン二つ星を獲得した二年前から行列は絶えず、それはランチタイムから閉店二十一時まで途切れることがない。
創業当時からの暖簾は色褪せ、かろうじて「のぞみ」の文字が読み取れる程度。木枠の引き戸は歴史を感じさせる風合いを醸し出しているが、店内に一歩足を踏み入れると、二〇二三年という時代がそこかしこに反映されている。建築家・片山朝陽氏の意匠による、モールテックス施工の艶消ししたダークグレーで統一された和モダンな内装は徹底したバリアフリー。ベビーベッド完備、オールジェンダートイレの導入は業界いち早い。
敷地面積二十坪の店内には、家族で座れるテーブル席が四卓、ベビーチェアはもちろん、車椅子対応のローカウンターも完備され、いまだおさまらぬコロナ感染症対策として、一分に一回の換気設備も万全だ。
五年前の改装を機に、専用駐車場も併設され、遠方からのファンは嬉しいかぎり。外国人観光客への英語での丁寧な接客は、ニューヨーク・タイムズのグルメ評でも絶賛されている。
なんといってもその人気の秘密は、数種類の地鶏によるボディにカツオベースの魚介を合わせた無化調の超クリアスープにある。たゆたう黄色の麺に、トッピングはナルト、煮卵、チャーシュー、メンマ、ネギ。ややオーソドックスすぎるビジュアルながらも、突き抜けた王道の徹底ぶりは、むしろ、若い女性に「エモい」と評判で、著名人のインスタ投稿をきっかけに新たな世代のファン層を得た。
淡麗なスープに絡みやすい、ウェーブの細かな自家製中細ちぢれたまご麺はコシ、舌をすべっていく滑らかさともに申し分なく、一本一本の芯が光り、厳選された小麦粉に微配合された全粒粉の香ばしさ、後味に柚子の皮がかすかに香る。身体が疲れていても最後の一滴まで飲み干せる、滋養たっぷりの穏やかな味わいは決して胃にもたれることがない。
しかし、国内ラーメン通ばかりか海外ファンをも唸らせるのは、一見して「丸い味」の先にある、天界の迷路に迷いこんだような、複雑な旨味と凄みのあるコク、最初は調和がとれているかに感じられるそれぞれの素材の尖り方だ。淡麗系の味わいでありながら、中毒性が高く、必ずもう一度食べたい、と思わせるスープの秘密については日々、ネットで論争が繰り広げられている。
業界では珍しい二代に亘る女性店主、柄本希氏はこう語る。
「刻一刻とお客様の好みは変わりますから、先代の母から受けついだレシピをベースに、研究や食べ歩きを重ね、私どもも勉強中で、ほぼ毎日、配合を微妙に変えています。例えば、現在はホタテですが干し牡蠣を導入していた時期もあるんですよ。スープの透明度を優先したくて、鶏だけにこだわった時期もありますが、数年前から豚ゲンコツも足しています。一晩低温熟成させて脂を取り除くのもポイントです。小さなお客様も多いので、意識しているのは『嫌味にならない甘み』ですね。下仁田ネギとフランス産ポロネギを併用したり、どちらか一方にしていたこともありますが、そこから玉ねぎに切り替え、林檎を足したあたりで、我々の方向性は決まりました。ブランド品には極力頼らないようにしています。『全方位型淡麗』と呼んでいただけているのはありがたいのですが、一番気をつけているのは、単調にならないこと。全方位型であるほど、驚きと仕掛けは必ず重要です。チャーシューも流行の低温調理法に切り替えていた時期もあります」
あくまでも謙虚な「のぞみ」だが、その強みは先代からのファンやマニアも惹きつけた上で、家族連れやライトなファン層を取り込んだ点だ。現在は、健康志向のニーズに応えるため、ふすまを使用したローカーボ麺の開発にも意欲を燃やしている。その姿勢は柄本氏の時代を見据える力による。
「私どもの願いは、一人でも多くのお客様に、ああ、美味しかった、ああ、いい時間が過ごせた、と感じていただくことにあります。女性一人のお客様も入りやすい清潔で安全な店づくりをまず、第一に心がけております。コロナウイルスの感染拡大もまだおさまらず、物価高が止まらない今、せっかく外食していただけるのですから、小さなお子様連れの方、障害がある方、ジェンダーアイデンティティや外見を理由にこれまで外食で不快な思いをされたことがある方、ご高齢の方にも是非楽しんでいただきたい。お店では何より、ほかのお客様へのご配慮を第一にお願いしたいですね。ラーメンの麺やスープを残す、残さない、すすり方、注文方法は私どもにはどうでもいいことです。どなたも思い立ったら万全の体調ですぐに気軽に外食ができる方ばかりとは限りません。時間を作り出したり、節約したり、そうして今やっと席に座れた、という方も大勢いらっしゃいますから」
必ずぶつけられるであろう「ラーメン評論家の入店おことわり」の噂について水を向けると、柄本氏はさらりとこうかわす。
「こちらとしては余程のことがないかぎり、入店おことわり、ということはしないんですよ。ごく一部の、周りのお客様の迷惑になる方にのみ、退店をお願いしています。はっきり申し上げますと、他のお客様を勝手に撮影しネットにあげること、不必要な声がけ、店員へのセクシャルハラスメントや調理接客が滞るほどの質疑といった行為を、私どもが認識する範囲内ですが、これまでされてきた方はNGとさせていただいております。目の前でそういった行為があった場合も同様に退店をお願いしています。そういった方々が、たまたま、著名なラーメン愛好家や評論家であったことが多い、というだけなので、どんな方にも来ていただきたいですし、厳しいご意見も、私どもはありがたく受け止めるつもりです」
愛好家のマナーに静かに釘を刺すことも忘れない。変わり続ける「のぞみ」であるが、今変わるべきは、我々愛好家側の意識なのかもしれない。
春には、ビーガン対応のオール植物性素材にこだわった「ネオ中華そば」が新メニューに加わるとのこと。変わり続ける「中華そば のぞみ」からますます目が離せない。
ライター 原田萌実
この某ラーメン情報誌の紹介記事が某ニュースサイトに転載されてから十一時間が経つ。ここで批判されてるの佐橋ラー油のことじゃね? というコメントが跡を絶たず、佐橋は何もしていないにもかかわらずプチ炎上し、再び「のぞみ」に向き合わざるを得なくなった。
Uber Eatsで頼んだ、下北沢にオープンしたばかりのマカロン餅ドーナツ専門店の看板メニューを三口だけ食べて、残りはゴミ箱にぶちまけ、ところどころに食べ染みのあるソファにごろりと寝そべった。年明けの人間ドックの結果を受け、最近では人目がないところに限り、取材で完食しないように心がけている。
マンションの真下を世田谷線が通過していく。世田谷ボロ市で通りは朝から爆発するように賑わっていて、屋台飯の匂いもぷんとここまで漂ってくる。
どうしても外に出ていきたい気持ちにはならなかった。
ラーメンの仕事が激減しているせいで、B級グルメや映画、スポーツ、ついにはスウィーツまで依頼があればなんでも書くようにしているが、佐橋はラーメン以外にほぼ知識がないため、次につながらなかった。四十五歳になる今、新しく始められる仕事もない。実家は練馬区にあるものの、帰りづらかった。妹夫婦が、亡き母のあと、父の介護を共働きの傍ら続けていて、大きな顔で威圧してくるせいだ。
これまで八冊本を出している。一時期はふくよかな体型に非モテ独身自虐キャラがマスコットみたいで可愛い、ともてはやされ、地上波でレギュラー番組を持ち、街でサインを求められることも多かった。SNSで自分のファンだと名乗る若い女性たちを見つけては、自らせっせとDMを送り、それをきっかけにして彼女たちと立て続けに交際もしていた。雲行きが怪しくなったのは、この「のぞみ」が頻繁にメディアで取り上げられるようになってからだ。
二年前、ミシュランの星獲得の報を聞き、お祝いついでに久しぶりに「のぞみ」を訪れたら、手首に豚のタトゥーが入った、うでっぷしの強そうなアスリート風の店員に「お引き取りください」とすごい目で追い返された。二度目もそうだった。理由はわからなかったが、デビュー当時から親しくしている愛好家の男たちのコミュニティでも、そういった追い払われ方をされている者がけっこう居て、自分だけじゃないんだ、とほっとした。排除された仲間たちとネット上で「のぞみ」批判を盛大に繰り広げ、むしろ結束は強まった。
最初「のぞみ」はラーメン評論家を店から締め出している、厳しい意見を恐れる腰抜け、男性差別、という批判の声が多かった。しかし、またたく間に、佐橋と仲間たちの過去ブログやTwitterでのやりとりが槍玉にあがるようになった。
当時は「ラーメン武士」の名で活動していたが、もう十年も前のことだ。情報誌の編集者とブロガー、二足のわらじだった頃の、毒が強めのブログは反省の意も込めて、最初の本が出るタイミングで削除している。ところが、魚拓をとっていた連中が得意満面にその内容を公開したため、いつの間にか、佐橋らは入店拒否されて当たり前という風向きに変わっていった。連載やテレビ、ラジオのレギュラーが次々に打ち切られた。「のぞみ」に追随する形で、門前払いをくらわせる二郎系、家系の有名店が現れ始めた。その上、「のぞみ」ファンを公言する新参の評論家やユーチューバーがその味わいを饒舌に語るようになり、ますます肩身は狭くなっていく。そうなると、面白いように人が離れていった。
やがて、仲間たちまで裏切り始めた。それぞれがTwitterやブログで、過去の「迷惑行為」を認める形で、謝罪したのだ。彼らを問い詰めたところ、謝罪文を出してすぐに、「のぞみ」から仕事関係者を通じてコンタクトがあったらしい。彼らは入店を許されるようになり、今ではすっかり「のぞみ」絶賛側に回っている。「ラー油さんも、意地はらずに早く謝っちゃえばいいのに」と、呆れた顔でさとされる始末だ。もはや「のぞみ」は絶対王政を築きつつあった。噂では、来年には、アメリカNetflix制作の密着ドキュメンタリーが世界公開されるという。
世田谷線は今日、ボロ市のために臨時ダイヤで運行しているようだ。いつもと停車、発車の間隔が微妙に違う。正月以降ずっと家に引きこもってごろごろしているので、佐橋の身体はそうしたささいな変化に敏感になっていた。
SNSなんて関心ありません、という顔をして、「のぞみ」はしっかり、佐橋らの動向を見張っているし、ネットの時流を読むセンスも高いではないか? やれやれ、仕事そっちのけでSNSの人気とりにかまけてばかりいるなんて、職人としてはどうかと思いますよ? と、佐橋はスマホでもう一度、記事の最後に添えられた、にこりともしない、鶏ガラみたいに痩せた五十代の女の画像を見遣った。
化粧気のない乾いた浅黒い肌と目尻に刻まれた皺のせいで、年よりずっと老けて見える。すっかりばあさんだ。おまけに先代にはあった、包容力みたいなものが、とげとげしい目つきや、硬い口元には微塵もない。昔はもうすこしは見られる見た目だったのに——。
執念深さにぞっとさせられる。この女のラーメンを食べたのは今から約十五年前、その母親が亡くなったばかりの頃だった。そういえば、先代の時から、佐橋は「のぞみ」を割と買っていたのだ。当時はまだ注目している同業者は少なかったから、やはり自分には先見の明がある、とつくづく思う。「おしゃれタウンで愛される懐かし系おふくろ風味のほっこり中華そば」として何度かブログで取り上げただけではなく、「部活帰りに友達の家で、お母さんがチャチャッと作ってくれた醤油ラーメンを思わせる、愛情たっぷりの手作りの味。郷愁の味わいに毒舌ラーメン武士も涙がにじみそう」として長文で褒め称えたはずだ。
木目調のいなたい雰囲気の店内を、柄本希は一人で回していた。先代の良さをまるで受け継いでいなかった。接客はつっけんどん、笑顔はとぼしく、挨拶は小さい上、こちらの食欲が減退するほど、顔色が悪かった。ラーメンを差し出す手の指先は水気がなく、爪には干し貝柱のような今にも割れそうな筋が何本も入っていた。柄本希のためを思って、カウンター越しにそこを指摘した。ただし、麺もスープも個性はややとぼしいものの、すでに一定のレベルをクリアしてはいた。佐橋はブログで二代目「のぞみ」の悪い点を綴ったが、ちゃんと評価もしたはずだ。たったそれだけのことをまだ根にもっているのだ。最近の、批評に耐えきれない職人たちのメンタルの弱さには辟易する。
口の中に、まだマカロン餅ドーナツの脂っこさが残っている。
バッシングされるようになってから、ずっと胃が痛い。何を食べてもものの味がしない。あっさりした汁物なら喉を通りそうだが、自分で作る気はない。歴代の彼女たちを呼び出そうとしても、全員からブロックされていた。昔から、佐橋は台所には立たない主義だった。それは職人への敬意からだ。同業者の中には、自らラーメンを手作りする者がいるが、それは文芸評論家が小説を書く、映画評論家が自主映画を撮るようなものだと軽蔑している。記事に添えられた「のぞみ」看板商品である中華そばの写真を、気づけば見入っていた。
こんなスープなら、飲めるかもしれないな。
見れば見るほど、美しい、黄金色だった。ここまで澄ませるには、鶏ガラが鍋の中でほとんど動かないよう、つきっきりで立っていなくてはならない。丸い味ながらも、奥行きが複雑で食べ飽きないともっぱらの評判だが、たくさんの素材をこんなに淡く、透明にまとめるとはどんな技術を持っているのだろう。とめどなく溢れ出る好奇心を慌てて打ち消す。
「のぞみ」の味を知らない、というのは現在、日本でラーメン愛好家の看板を掲げて活動する上で、致命傷といっていいハンデだった。そういえば、つい最近出たばかりの、替え玉太郎のラーメンガイドの表紙はよりにもよって、有名写真家の手による「のぞみ」の芸術品のような中華そばである。Amazonの新刊一覧で書影を見たとき、自分に対する当てつけではないか、と佐橋は憤った。
佐橋を批判するときにネット民が必ず引き合いに出して褒め称えるのが、この替え玉太郎である。このネット記事のコメント欄でさえ、その名がちらほら見受けられるほどだ。替え玉太郎はその名に似合わず、すらりとした薄い体型にすべすべの毛穴一つない白い肌、甘い顔立ちにぽきりと折れてしまいそうな細く長い首、髪と目は明るい茶色で、張りのある白いTシャツとブランドものの赤いキャップが目印の人気You Tuberだ。三十代ぐらいのはずだが、もっと若く見える。ラーメンをすする顔が女こどもに「かわいい」「おいしそう」と評判で、彼が紹介した店は翌日必ず満員になる。しかし、何を食べても「うまいッス!」とダブルピースをして顔をくしゃくしゃにして微笑むくらいしか表現手段を持たないので、佐橋やその仲間たちは彼を軽蔑している。だいたい、替え玉していない時もけっこうある。
うまいものを食べて「うまい」としか言えないような評論家は評論家とは呼べない。それはラーメン武士時代から、佐橋が繰り返し書いていることだ。言語化できない複雑な旨味や素人には気づかない美点をキャッチして文章にすることが、評論家の役目ではないか。そうやって廃れていきそうな、そうかと思うと大衆化しすぎてしまうラーメン文化を守り、つなぎ、そして新たなファン層を獲得していくこと。そのためには、時に憎まれ役を担うはめになったとしても構わない。それは佐橋の使命であり、人生の矜持だった。
佐橋はパソコンを立ち上げ、しばらくの間、さめざめと泣いた。涙が乾いた頃、ティッシュで鼻をかんだ。そして、noteを更新した旨をTwitterに投稿した。
「佐橋ラー油は、2003年から2013年まで更新していた自身のブログ『辛口ぶった斬りラーメン武士が行く!』でラーメン店の店員さんやお客さんの写真を、本人に許可なく撮影し、コメント付きで勝手にアップしてしまったことを、この場を借りて、謝罪します。
アカウントはすでに削除し、今はもうそのブログは見られなくなっていますが、画像の多くは今も、ネットに出回っている、と知人に聞きました。傷つけてしまったみなさん、本当に、本当に申し訳ありません。
あの頃の僕はどうかしていました。勤めていた会社での人間関係もうまくいかず、失恋もして女性が怖くなっていて、心身が壊れかけていた。ラーメンだけが心の救いだった。
僕はあの頃、僕の愛するラーメン文化が廃れてしまうことが恐ろしくて仕方がなかった。コミュ障気味の少年だった僕は、大学一年生の時に、美味しいつけ麺に出会い、世界が変わりました。もっと美味しい麺を、もっと美味しいスープを求めて、食べ歩くうちに、仲間に出会いました。一人でも多くの人にラーメンの魅力を知って欲しくなりました。日本にしかない、この特殊な、大切な様式美を守り、継承していきたかった。そのためには自分が悪者になっても構わなかった。
それが評論家としての、筋の通し方で、僕に出来るたった一つの正しい戦い方だった。その一心で、悪気なくやってしまったことです。
本当に、本当に、ごめんなさい」
十回以上は読み返したにもかかわらず、このnoteも、またもや炎上した。ラーメン愛好家仲間までまったく擁護してくれなかった。認めなければよかった、と目の前から光が消えていく。
一つでいいから佐橋ラー油擁護を見つけたくて、エゴサーチする手が止まらない。いつの間にか、辺りは暗くなっていて、ボロ市の屋台は次々に解体されていく。結局、佐橋は丸二十四時間、ネットに張り付き続け、自分への罵詈雑言をただただ眺めるはめになった。
あの男から初めての連絡が届いたのは真夜中だった。いつもなら無視するところだが、今の佐橋にはたった一人の味方が、本当にありがたかった。
「替え玉太郎です。初めてDMします。つねづね佐橋ラー油さんの文章が好きで、ラー油さんの筋が通った主張は、ぼくの目標でもありました。謝罪note素晴らしかったです。すごく勇気がある発言だと思います。ぼく、『のぞみ』さんと親しいんですが、よければ、ご店主にこのnoteのこと伝えておきましょうか?」
「『のぞみ』さん、謝罪文、読まれたそうです。ラー油さんの気持ち、しかと受け止めたとのこと。これからはいつでもご来店ください、死んだ母も喜びます、だそうです。よかったですね。来店する日にちと時間を伝えてくれたら、必ず席を空けておくそうですよ。よければ、ぼくもご一緒したいです、一度ご挨拶したいと思っていたし。いつ行きましょうか?」
それは佐橋にとって五日ぶりの外出であった。
閉店まで行列は途切れない、と例の記事にはあったが、佐橋がたどり着いた二十時半、三軒茶屋駅から割と歩く「のぞみ」は、意外なくらいに空いていた。入店するなり、例のたくましい豚のタトゥーが入った強面の店員がつかつかとこちらにやってきて、咄嗟に殴られるかと身構えたが、佐橋の真横を通り過ぎ、すぐに「営業中」の看板を裏返し、暖簾を外したから、自分のために客の入りを制限しているのかもしれなかった。
外観や入り口の雰囲気は昔のままだが、一歩入るなり、しんと静かな質感に包まれた。建物全体が、すべすべした硯のような素材でできていて、照明の具合は落ち着いている。天井からアルミ製の笠付きランプがいくつも吊り下げられていて、客のもとに運ばれてきたラーメンや足元だけが照らし出される仕組みになっていた。これが流行りなんだろうが、なんか冷たい感じがする、以前の古びた木目の店内が好きだっただけに、さっそく嫌な気持ちになった。メニューが絞られたせいか、以前はあった古い券売機まで消えていた。
カウンターの中で黒い作業着姿で働くのは店主の柄本希。こちらをちらっと見るなり、すぐに手元に視線を戻す。すでに明日の仕込みが始まっているのか、鶏ガラらしきものを出刃包丁でたたき切っている最中のようだ。てっきり、こちらまで来て握手を求めるくらいのことはすると思っていたので、拍子抜けしてしまう。面と向かっての謝罪を覚悟していたが、そういったことを求められるわけでもなさそうだ。
カウンター席ではパーマっ気のある髪のサラリーマン風の男が一人、静かに麺をすすっている。彼から二席ほど離れた角の席には、あの替え玉太郎が座っていた。目が合ったので、佐橋はすぐに会釈をしたが、彼は何故かこちらを一瞥したきりで、無言のまま頬杖をつき、ただ目線を落としている。メディアで見る印象と違い、笑顔も愛嬌もない。白いTシャツ姿の男なんていくらでもいるし、全体的に薄暗い店だから、人違いかもしれない、と思い直した。
店員に誘導されるままに、テーブル席に腰を下ろした。隣のテーブル席には有名私立中学の制服を着た小柄な女の子と、その母親らしき中年女が向かい合って座って、こちらもやはり中華そばを食べている。母親の方はこちらに背中を向ける形である。高級そうなツイードのジャケットによく手入れされた茶色の髪。傍に置いてある大きなバッグはブランドものだ。
やれやれ、と佐橋は顔に出さないようにして思う。時代は変わった。母娘がこんな遅くに外食、それもラーメン。暮らしにゆとりがあるなら、せめてファミレスを選ぶくらいのわきまえ方をしてもらいたいものだ。
「いらっしゃいませ」と水を運んできたのは、ベリーショートに鼻ピアスを光らせた、もう一人の店員だ。あまり若くないし化粧気もないが、色白で黒子が多いところは好みだ。このままじゃ声も低いし、なんだか男みたいだから、髪を長く伸ばし、ちゃんと化粧をしてスカートを穿いたらどうだろうか。
柄本の厳しい視線に気付いて、佐橋は慌てて店員の身体から目を離し、「中華そば、ひとつ」と小さな声で言った。ベリーショートの店員はデニムの尻を左右に振って去っていった。
ちょっと見ただけで、ペナルティかよ。なんて息苦しい店なんだ、とげんなりした。昔の「のぞみ」は違った。先代の柄本望はふっくら体型で色白、細かな皺が柔らかな印象だった。酔って入ってきても、あたたかく迎え入れてくれた。まるで母親の待つ実家に帰ってきたようなくつろぎがあった。だいたい、こんなに厳しく見張られている中じゃ、味なんてまともにするわけがない。日々新しいマナーが勝手に更新され、それに乗れないものは容赦なく排斥される。そんな息苦しい昨今の風潮がこの聖域にまでついになだれ込んできたのか。そういったことから解放された豊かな文化を形作ってくれるから、佐橋はラーメンが大好きだったのに。
ベリーショートの店員がカウンター越しに佐橋からの注文を告げるなり、柄本希がいきなり、手を一回、大きく叩いた。
「佐橋ラー油さんから、中華そば、ひとつ、ご注文いただきました」
それをきっかけに店にいた中学生の母親を除く全員が、一斉にこちらを見た。中学生もサラリーマンも、店員二人も、佐橋を見ている。替え玉太郎か、と思っていたあの男、正面から見るとやはり本人だった。
「いらっしゃいませ! ようこそ『中華そば のぞみ』へ!」
と、それぞれが声を張り上げて叫んだ。なんだこれ、フラッシュモブとかいうやつか、と佐橋は狼狽えた。もしかして自分を歓迎するためのサプライズかと思いきや、その顔は誰一人として笑っていないのだった。
「佐橋ラー油さん。私がこれから中華そばを作り始める前に、周りにいる皆さんをよく見ていただけますか」
柄本希は静かだが圧のある口調で言った。
母親を除く店中の人間が、手を止め、自分に射るような視線を向けている。何が起きているのかよくわからず、佐橋はたじろいだ。
「テメエ、マジでなんも、覚えてないのな? ふっざっけんなよ!」
声がした方を見ると、替え玉太郎が厳しい目で中腰になり、こちらを睨みつけている。中学生の娘がふいに席からプリーツスカートの襞をさらりとこぼして、スマホを向けた。佐橋はとっさに顔を隠した。
「客の許可のない撮影をしたら、退店させるんじゃなかったのか……?」
そう問い質しても、柄本も店員二人も、肩をかすかに揺らして笑うばかりだ。
「ご心配なく。お店全体を撮影しているだけで、おじさんだけを撮ってるわけじゃないんで。自意識過剰じゃないですか?」
いかにも生意気そうな口調で女の子は言い放つ。
「勝手に撮影される気持ち、これで少しはわかった? あ?」
と、ベリーショートの店員が唇の端を曲げ、低い声で凄んだ。
「本当に何も覚えてないんですね。あなたのせいで、僕は仕事を辞めたのに」
サラリーマン風の背広の男までが青い顔で声を震わせている。とっさに入り口を見たら、先ほどの用心棒みたいな店員が、立ちふさがって腕組みをしていた。冷たい汗が背中を伝う。
「ねえ、おじさん、私たちの顔をさあ、一人一人、よーく見てみなよ?」
と、中学生がこちらまでやってきてしゃがみこむと、下からぐっと佐橋を覗き込んできた。まん丸な目が黒々と濡れていて、暗い灰色で統一された店全体がそこに映りこんでいる。ずっと黙って背を向けていた彼女の母親が、ようやく振り向き、目を見開いて、にっこりした。
「どうしてわからないんですか。私たち全員、すごく『有名』じゃないですか?」
店中の七人がこっちへ焦がすような視線を向けている。その一人一人の顔を見返して、佐橋は「あ」と叫び、手元のコップを倒した。つや消ししたマットな質感の石の床に水滴が落ち、玉の形で跳ね返されていく。
赤山美香が高校卒業後、池袋駅西口から歩いて五分の豚骨ラーメンの有名店で働いていたのは、二〇一〇年頃。まだXジェンダーという言葉を、自分も周囲も知らなかった。あの頃はバイトの履歴書の性別欄はとりあえず女に丸をつけていたものの、本心ではどうしてもしっくりこなくて、自分は悪くないにもかかわらず、いつも雇い主や同僚を騙しているような気持ちになった。
中学一年の頃から女子の制服を着ると落ちつかなかった。どちらかというと男子の制服の方がしっくり来る気はしたが、それが本当に着たいかというと違う気もする。とても消極的な、スカートよりかは、という感じだった。学生時代はもちろん現在もなお、誰かに恋することはない。でも、その分、やるべきことに集中できたと思う。責任感が強く、はしゃぐタイプではないがどんな行事もひとしれず楽しむタイプの美香は、男女問わず信頼され、総じて充実した学生時代だった。
両親は若く、裕福とは言えない団地暮らしだったけど、妹ともども愛されて育った。美香という名前はいかにも女の子だが、母親から名前に込めた気持ちを妹と一緒に聞いてから、気に入っている。髪が短くがっしり体型で、小さいブラジャーで胸をぎゅっと押さえつけていたため、よく男だと思われたが、それを揶揄してくるのは話したこともない連中ばかりなので、気にならなかった。
背が高く手足も長く、体力に恵まれた美香は女子サッカー部の活動に夢中だった。ただ、仲間たちと同じ性別か、と問われれば自信がないので、トイレや更衣室はなるべくみんなが居ない時を狙って、使うようにしていた。コーチには推薦で体育大学に進むように言われたが、本格的にスポーツに打ち込むようになれば、きっと性別は常に明らかにしなければならなくなるだろう、とその時は判断した。
だから高校卒業後は、将来の仕事に結びつけば、と西武池袋線で都内に通い、あらゆるバイトを経験した。どこでも重宝されたが結局、裏方のコツコツした仕事は体を存分に動かしたい性分に合わなかった。接客だとウェイトレスだったりウェイターだったりと性別に準じた役割を求められることが多く、居心地が悪くなる。ただ、職場を一つ去るたびに、自分に向いている場所の輪郭がだんだんと浮かび上がるようになった。
——なるべく忙しいところ。従業員の人数が少ないところ。制服はブカブカの作務衣。力仕事が必要なところ。明確な更衣室はなくてトイレは一つのところ。つまり、カウンターだけの坪数が少ない人気ラーメン店がベスト。
美香は妹にそう語った。妹にだけは昔から自分の違和感を打ち明けることが出来た。妹は美香にわかりやすさを求めず、まとまらない話をうんうんと聞いてくれる。
なにより、美香は小さい頃からラーメンが大好きだった。いわゆる名店の味をその時はまだ知らなかったが、家族で週末に出かけるフードコートで食べる、こってりした豚骨スープとガシガシ硬い細麺、それに水気少なめのご飯を添えて食べるのが好物だった。
実際、豚骨醤油ラーメンの硬派系名店「めん屋 足穂」にひっきりなしにやってくる男性客たちは、美香に見向きもしなかった。ほとんどが一人でやってきてこちらと目を合わさずに食券を差し出し、山吹色のクリーミーなスープから硬い細麺を競うようにすくい上げ、丼を抱えて飲み干すなり、一言も発さずさっさと店を立ち去る。接客は好きだが、仕事と関係ない話をされると、いつも何も言えなくなってしまうので、それも助かった。
客たちにある一定のリズムと秩序があるのは、店長の荘厳なオーラのおかげだと美香は思っている。六十代の男性店長・森さんは決して従業員を怒鳴ったり、こうあれ、と示すことはないが、素早く無駄のない動きを求めた。それは厳しいというより、彼の納得するクオリティの一杯を注文から三分以内で客に出すためだ、と美香はすぐに気付いた。ピーク時はあまりにも忙しいので、美香よりずっと年上の男たちが何度も注文を取り間違え、店長の無言の一瞥に耐え切れず、次々に辞めていった。
そんなわけで働き始めてすぐに、美香が一番の古株となった。店長の言葉の少なさが、美香にはむしろ心地よかった。「足穂」ではただの赤山美香でいられた。なにより、まかないのチャーシュー温玉丼や餃子はもちろん、ラーメンが楽しみで仕方ない。フードコートの味とは根本からして違う。ただのこってりで終わらない、丁寧に重なっている、野菜や煮干しの香りが爽やかでさえあり、極限まで硬い麺も、攻撃的というより、香ばしくて歯切れがよく、どこを切り取っても飽きるということがないのだった。
ある日の昼休憩、
「スープの仕込み、明日から手伝えるか?」
と店長に短く告げられた。美香は大きくうなずいた。そのせいで、柄にもなく、接客中に口元をにまにまさせていたせいで、あの男に目をつけられてしまったのだ。食券を受け取った時から、あの男の態度にはどこか妙なところがあった。
「ねえ、君、男なの? 女なの?」
カウンター越しにラーメン丼を置いた時、唐突にそう問われた。適当にあしらえないのは、なんでなんだろう。不意打ちをくらい、美香は完全に硬直してしまった。
「男なの? 女なの? ねえ、どっちなの? いや、どっちにも見えるんだけど?」
男はごく気軽な調子を装ってはいるが、しつこく食い下がった。何か言わなければ。たった今、大勢の男が見ている前で、美香は、自分のあいまいさを、明快に説明しなければならなくなった。妹にだってとりとめのない調子でしか話せないのに。それに、どうしよう、言葉が口からでてこない。常連たちまでが、ちらちらと自分の胸のあたりを見ている。それで頭が真っ白になった。普段は食欲を刺激してくる、豚骨の強い匂いで立ちくらみしそうになる。
「どっちか、ちゃんと教えてくれないとさ、味に集中できないんだよねー? みんなもそうじゃないの? 気になる人もいるんじゃないの?」
「お客さん、悪いけど、店員に絡むのはやめてくんないかな? お代は返すから、出て行ってくれ」
店長がぴしゃりと遮ってくれたおかげで、他の客たちも、ようやくいつもの、何が起きても食事最優先の軍隊のようなトーンを取り戻した。店中から冷たい気配を浴び、男は急にへらへらし始めて去って行った。
しかし、後日、その男は有名なブロガー「ラーメン武士」だと判明する。最新の記事では「足穂」の暴力的な威圧系接客にドン引き、ハードボイルドは味だけにしろ、と店長がおもしろおかしくこき下ろされていた。それだけではなく美香を隠し撮りした写真まで貼られていた。そこに添えられた言葉は、性別を明らかにしない美香は、ずるくて卑怯で、人を不安にさせる存在だと糾弾するものだった。
それからしばらくして、美香は自ら店をやめた。店長は不器用な熱心さで引き止めてくれたけど、彼にも迷惑をかけてしまったし、もう働き続けられる気がしなかった。あれ以来、客たちが自分の身体や顔をじっと見ている気がしてならない。親も妹も何も言わなかったが、おそらくネット上で美香の写真が出回っていることをうすうす知っていたのだろうと思う。新しいバイトを探さなくても何も言わなかった。
誰かに声をかけられ、また同じ質問をぶつけられそうで、しばらくは外出もできなかった。二ヶ月半してようやく、ぶかぶかのトレーナーにキャップを被り、日が落ちてからであれば、恐る恐ると街に出られるようになった。その夜は、渋谷でレイトショーを観たら終電を逃してしまい、ネットカフェで始発まで時間を潰そうとしていた。すると、かつて大好きだった、フードコートに入っていた博多系豚骨チェーンのロゴが目に入った。森さんの作るような個性やキレはないけれど、リーチが広い、まろやかでシチューめいた甘味の強い白濁スープ。暖簾をくぐりながら、あんな目に遭ってもなお、ラーメンが好きだ、と自覚した。食券を買い、カウンターの隅にある、できるだけ目立たない席に腰を下ろす。
「あのう、ごめんなさい。隣、いいですか」
自分と似たようなパーカー姿で、キャップからつるつるしたポニーテールを逃した、同い年くらいの子が立っていた。実を言うと、さっき入店した時から、ずっと視線を感じていたのだ。
「私、佐渡恵っていいます」
と、その人は唐突に名乗った。ここから歩いて数分の大学の三年生だと言い、怪しいものではない、と素早く学生証を見せてくれた。断りなく隣に座ると、美香と同じように、食券をカウンターに載せる。
「私、ネットであなたの画像を見ました」
それを聞いて、すぐに逃げようとしたが、恵さんは閉まりかけの電車のドアに滑り込む勢いでまくしたてた。
「ねえ、誤解しないで。私も同じだから。ラーメン武士に勝手に写真、撮られたんです」
その整った顔だちや目尻が優しげな大きな瞳をまじまじ見ているうちに、美香は恵さんが誰だかわかった。「日本一可愛い超巨乳ラーメン屋店員」として、ラーメン武士のブログで写真が紹介されていた人だ。ラーメン武士のブログなんて絶対読まないが、あまりにも話題になっていたため、ついうっかり見てしまった。正面からの顔だちを咄嗟に思い出せなかったのは、何故か胸の真下からその張り出した高さを強調するように撮られていたせいだ。美香のものと同時に出されたラーメンを前に、恵さんは割り箸を割る。紅ショウガをどっさり入れながら、こう続けた。
「あれ、撮影に同意しているように見られちゃって、勘違い変態女とか、ネットですごい叩かれているんですよね。それだけじゃなく、ストーカーみたいなのが何人も店に詰め掛けた。店長に相談したら、お店にはいい宣伝になったし、君も外見を褒められたんだから、いいじゃないかって、笑って取り合ってくれなくて。だから、店はもうやめた」
恵さんは唇をすぼめ、溶け出した紅ショウガでピンク色に染まったスープがからんだ麺をズズッとすすりあげた。
「あの写真、許可なく撮られたの?」
美香も割り箸を割ったものの、さっと食欲が失せていく。
「うん、あいつさ、店員さん、ラーメンと一緒に写ってくださいよって声かけてきたの。ラーメンがメインの写真だと思って、うっかり愛想笑いしちゃったんだよね。好きだったんだ。私が働いていた、五反田の横浜家系ラーメン。あの日はさ、私が海苔をぐるっと丼に飾らせてもらった記念日だったんだよね」
食べなよ、という風に恵さんに大きな瞳で促され、美香はようやく麺を少しだけ口にした。そうするとやはり、だんだんとお腹がすいてくる。替え玉お願いします、と恵さんはごく普通の調子で、カウンターの中に向かって言った。
本格的に麺をすすり始める前に、美香はどうしてもこれだけは吐き出しておきたかった。
「あのね。昔から、どっちの性別もピンとこないんだ。だから、性別が関係ない場所で働けたらいいなってずっと思ってた。それをまだ上手く説明できない」
妹以外に、初めてこの話をした。こうしていても、カウンターの奥の店主やアルバイト、客の目が気になる。あの時と同じように、舌がもつれる。それでも、恵さんがまるで周囲からかばうように身を乗り出し、目の前の壁になってくれるおかげで、最後までなんとか話し終えることができた。
「当たり前だよ。そんなデリケートなこと、突然聞かれてすぐに応えられないでしょ。私みたいな初対面の人間なんかに話してくれて、どうもありがとう」
恵さんも替え玉だけではなく、スープは残さず、ご飯も一緒に食べるタイプだった。そのせいか、美香も三ヶ月ぶりに替え玉を頼んで、餃子もライスも食べた。会計を終え、別れ際になって、恵さんはこう言った。
「私さ、ネットで騒ぎになってから、大学でも知らない人に話しかけられることが増えて、もうずっと行ってない。友達は心配してくれたけど、疎遠になっちゃった。あの、これから時々、ラーメン屋めぐりしませんか? 私の周り、あんまり友達にラーメン好きな女子いなくて。あ、朝山さんが女子って決めつけてるわけじゃないよ」
「もちろんだよ。自分でよければ、いつでも連絡ちょうだいね」
そして連絡先を交換した。恵さんからはその夜のうちに次の約束を取りつけるメッセージが来た。再会した時、恵さんはショートカットにして雰囲気をがらっと変えていた。新宿、原宿、渋谷で落ち合い、二人で気になるラーメン店に行き、その後は、スタバでゆっくりおしゃべりをする、そんな関係が続いた。高校時代、仲間は多かったが、集団での付き合いのため、こんな風に一対一で語り合える相手はいなかった。なにより、自分と同じくらいよく食べる恵さんとの付き合いは楽しかった。ショッピングに誘われることがないのもありがたい。昔から着たい服、身につけたいものが皆無で、自分なりの好みというものがよくわからないのだ。
「Twitterでラーメン好きだっていうと、変なのに絡まれるんだよねー」
恵さんが、新宿の魚介ベースの塩ラーメン屋でぽつりと言った。この後、替え玉いくでしょ、と互いに確認しあった直後だった。はまぐりや魚のダシをベースにした来るたびに微妙に味が変わるスープに、へしこのしょっぱいおにぎりが抜群に合う、美香のおすすめ店を恵さんが気に入ってくれて嬉しかった。
Twitterが爆発的に流行るのは東日本大震災が起きてからで、美香は二〇一〇年当時その名前をかろうじて聞いたことがあるくらいだったが、あの頃、恵さんはすでに上手く使いこなしていた。彼女はSNSが怖くないようだ。美香はあれ以来、ネットに近寄れない。ラーメン界隈の口コミ情報さえ見ることができず、雑誌や本、ラーメン屋で盗み聞きした愛好家たちの会話が貴重な情報源だった。
「彼氏の趣味でしょう、とかリプライくるの。なんで女がラーメン好きなのって許されないんだろうね」
「私の妹も同じようなこといってたな。ラーメン文化ってなんか面倒っていうか、怖いって」
美香は「めん屋 足穂」のストイックな雰囲気が好きで、森さん含め今なお悪い印象はないが、妹はあの感じをおおいに苦手とし、姉に会いに店の前まで来てみても、怖がって入ることは一度もなかった。
「うんうん、下手にラーメンの話したら、変な愛好家に絡まれるんじゃないかって思われてるよね。麺やスープを残したら誰かに叱られそうだから、入れないって人の話も聞く」
「そういえば、有名なラーメン屋さんって男の人ばっかりで、店長も絶対に男、だしね」
「あ、待って。一人、知ってるかも。女の店長の店。フォローしてるラーメン愛好家さんが、勧めてくれた店なんだけど」
恵さんはそう言ってスマホを取り出し、きらきらした目で見つめている。ラーメンを擬人化したような可愛いアイコンがちらりと窺えた。
「あ、ここでの替え玉やめて、これから二杯目行かない?」
美大卒業後に入社した、大井町線沿線にある有名な建築事務所をたった二年半でやめた理由を、片山朝陽は、長野県で暮らす母親と祖母にまだちゃんと話してない。薄々は気づいているだろうが、二人にはゲイであることは告げていなかったし、「ネットを見て」と言ったら、父亡き後、近所のホテルでフロント係として働きながら、農園を手伝う祖母と二人三脚で子育てしてきた母は、息子に寄せられた罵詈雑言や揶揄を読んでしまい、深く傷つくことになる。
アパートに引きこもり二週間が経つ。事務所のすぐ傍という理由で借りた部屋のため、元同僚とどこで出会うかわからない。もはやスーパーやコンビニに行くことさえ、怖かった。健人から「なんか食べてます?」とメッセージが届いた時は、ありがたくて、夢中で欲しいものを打ち返した。今、まともに目を見て話せるのは世界中で彼だけだ。
——あのよく食べるバイトくんと片山くんって、付き合っていたんだね。
クライアントの自由が丘のバーの店長になんの悪気もなく、そう言われた時、何が起きたのかわからなかった。世界中で自分をゲイだと知っているのは健人だけのはずだった。一瞬、彼が裏切ったのかと思った。
その店長が教えてくれた有名なラーメンブログには、隠し撮りされた朝陽と健人の写真が添えられていた。あれを初めて目にした時の、高層ビルのエレベーターに足を踏み入れた瞬間、そこに床がなかったような衝撃と、どこまでも続く落下の恐怖は、今なお夢に見る。
健人がアルバイトとして、事務所に現れた去年の春からずっと気になっていた。朝陽が通っていた美大の後輩で、共通の知り合いも多い。つやつやした色白の肌で肉付きがよくて、誰からも好かれていた。なにより、ドーナツであれ、海苔巻きであれ、どんな差し入れでも美味しそうに頬張る様子に視線が吸い寄せられた。女性だけの飲み会にも屈託なく出入りし、そこで彼が自分は男性が好きだとあっさり認めたせいで、周囲の視線が微妙に変化したが、健人は別に気にする様子もなかった。
それでも、下っ端であれ正社員という立場上、年下のアルバイトに気持ちを打ち明けるのは気が引けた。だから、彼が卒業制作のために職場を去る日を待って、勇気を振り絞って食事に誘った。彼は、え、マジで嬉しいんですけど、と目を輝かせた。
——じゃあ、俺が行きたい店でもいいですか。環八沿いにめちゃくちゃうまいって評判の二郎インスパイア系ラーメン屋があって。いつもすごい行列なんで、一緒に並んでくれる人がいたらいいなって思ってたんすよね。
排気ガスまみれの三十分の行列の間に、健人が自分の生い立ちをぺらぺらしゃべるので、朝陽もつられて、初めて他人にこれまでの人生の話をした。小さい頃は食が細くて野菜が嫌いで、祖母の手を焼かせたこと、好きな映画監督は伊丹十三とスパイク・リーだと言ったら、俺も! と健人は飛びはねた。健人が「スーパーの女」の津川雅彦の真似があまりにも上手いものだから、涙が出るまで大笑いした。間違いなく、これまでの人生で一番楽しくて、リラックスした三十分だった。
だから、柄にもなくはしゃいでしまった。健人がごく自然に「あの、嫌だったらいいんすけど、手つないでもいいっすか」とささやいた時も、どきどきしながら指先をからめた。コの字型のカウンターに並んで座り、食券を同時に出した。けっこう注文めんどいんで、俺に任せてくれますか、と健人が言うので、朝陽は彼のカスタマイズに聞き惚れた。背脂やにんにく、麺、野菜の量を、いちいち朝陽にこれでいいかと確認しながら、彼は店長に伝えていく。初めて一緒に外食するのに、健人は、朝陽の食べる量や好みを正確に言い当てていた。彼も自分をずっと見ていたのか、と思ったら、ふと泣きそうになった。その時、ふいに、健人の表情がみるみる険しくなった。
——おい、てめえ、勝手に撮ってんじゃねえよ。警察呼ぶぞ、コラ。
湯気の向こうの、厨房を挟んで座る、太った男を健人はどなりつけた。一瞬、店内が静まり返った。その薄汚い印象の男はこちらにずっとスマホを向けていたようだ。彼は健人の剣幕に押されたのか、そそくさと店を後にした。まもなく二人のラーメンは到着したが、朝陽が青ざめているのを見て取ったせいか、健人は店長に謝り、丼には手をつけずに店を出た。
——また、リベンジしましょうよ。今度は朝陽さんが休みの前の日にしましょ。それなら、にんにくマシマシできますしね?
と健人が締めくくってくれたおかげで、明るい気分でその日は別れることができた。もしかして、ああ見えて昔やんちゃだったりするのかな? そう思うと、ひどい目に遭ったばかりなのに、彼に対しての興味が倍増して、何も食べていないにも拘わらず、ずっと体の奥が熱かった。
でも、そんな風にときめいて暮らしていられたのは、二人の画像がネットで拡散される前、わずか数日の間だけだった。
ラーメン屋にふさわしくない、注文に異様に時間がかかり、周りに迷惑をかける、過剰にベタベタした同性愛者のカップル、というような悪意ある文章を読み、朝陽はベッドから起き上がれなくなった。職場にはもう二度と行けないと思った。朝陽と健人の仲睦まじい雰囲気が可愛い、という擁護のコメントにも、まるで珍しいペット扱いしているような気配を感じ、かえって傷ついた。声がうまく出ないし、胃が焼けるように痛くて、水しか口にできない。
何日も掃除もしていない部屋に、健人はいつもの雰囲気のままで、スーパーの袋を両手に現れた。本当ならもっと片付いた状態で、祖母から送られてきた蕎麦でもゆでてもてなしたかったのに。窓開けますね、おかゆなら食えますか、台所借りていいすか、とぽんぽん声をかけ、鍋やフライパン、冷蔵庫の中身を見て回りながら、健人は何気なくこう続けた。
「どうします。訴訟する?」
「やめとく。これ以上、自分の属性だけで、注目されたくない」
そっか、と健人はつぶやき、ベッドのそばまでやってきて、体育座りをして、こちらの顔を覗き込んだ。
「ごめん。僕が食事に誘ったせいで……」
朝陽が小さな声で謝ると、あっけらかんとした口調で彼は言った。
「いやいや、謝るのはこっち。だって、ラーメンを提案したのは俺っしょ。あんなもん、俺、別に気にしてないっす。俺の地元、あ、ここから電車で通える神奈川の僻地だけど、めっちゃ荒れてたから昔から男と歩いているだけで、めちゃくちゃ叩かれて、ああいうの慣れてたし。勝手に言ってろよって感じ」
こちらの顔つきを別の意味ととったらしく、健人は急におだやかな表情になった。
「でも、そんなスタンス、人それぞれじゃん? 朝陽さんが傷ついたのなら、それは許せないですよ。こうやって、時々会えたら、嬉しいっす。おうちデートだっていいじゃないですか」
彼はしばらく迷った後で、こちらにスマホを差し出した。
「慰めにならないけど、ラーメン武士のせいで、俺らより、ひどい目に遭ってる人、まだまだたくさんいる。この親子とか、やばくね? この子、まだ赤ん坊じゃん」
それは、この一件でラーメン武士のブログをちゃんと読む前から、すでにネット上では有名だった画像と文章だった。朝陽と健人の比ではないほど拡散されている。悪質なコラも多数作られていて、もはやネット民の定番のおもちゃだった。でも、この画像を初めて見た時、朝陽は別に同情を感じなかったのだ。むしろ、何でこんな、子どもが小さな、大変な時にわざわざ無理に外食するんだよ、と苦笑し、ネタとして受け止めていたのではないだろうか。男ばかりのラーメン屋のカウンターに窮屈そうに座り、片手で赤ちゃんを抱え、必死の形相で麺をかきこむ母親の隠し撮り画像。すっぴんで髪はほつれ、寝巻きのような服には汚いシミがいくつもついている。
どうして笑ったりしたんだろう。幼い頃、朝陽が見上げた母の姿にこんなにもよく似ているのに。
『今にも授乳始めるんじゃないかって気が気じゃなかった。おっぱい見れたらラッキーではありますが、こんな顔のおばさんですしね〜』
かつては意地悪だなあ、くらいにしか思わなかったラーメン武士のコメントに、今の朝陽は吐き気を催す嫌悪感を覚えた。
「ラーメン武士のせいで、生活めちゃくちゃになったのは俺らだけじゃないよな」
傍の健人は頬が触れ合うくらい近くにいる。
「なんか、急にラーメン食べたいかも……」
彼の体温とにおいにほっとしたせいか、朝陽は気付くと、そうつぶやいていた。
三年以上経つが、アキはあの日から絶対にラーメン屋に行かないようにしている。写真がネットで拡散されて半年後、夫と別れた。
二人が勤務していたのは京橋の小さな冷凍食品メーカーで、保守的な職場ながらも、育休をとっている男性社員はいくらでもいた。しかし、夫は「夫婦そろって育休なんて、タイミングずらしたとしても、顰蹙だろ」と言って、それをしなかった。アキの産休が終わって本格的に共働きとなっても、夫は相変わらず飲み会皆勤賞で、一向にワンオペ育児は終わらなかった。でも、離婚の決定打は、
——盗撮した方もよくないけど、お前も悪いだろ、小さな子連れでラーメン屋いくなんて、それは叩かれて当然なんじゃないの?
という一言だった。部署は違えど、小さな会社なので、別れてからもしょっちゅう顔をあわせることになった。気まずさに耐えかねて、アキは退職した。両親が、わがままだ、孫の春がかわいそうだ、と激怒したせいで、もともと疎遠気味だったが、現在はほぼ絶縁状態にある。
ラーメンを子連れで食べたことで全部失うなんて、自分の身に起きたことが未だにアキは信じられない。今は松陰神社前にアパートを借り、派遣社員として必死に働きながら、一人で春を育てている。ネット上でもっとも有名な赤ちゃんだった春も、とうに自分でスプーンとフォークを使えるようになっている。少し前までは、街を歩いていても、誰かに見られている気がして仕方がなかったし、実際「あの、ラーメンおばさんと赤ちゃんじゃん?」と学生服を着た連中にスマホを向けられたこともあった。
最近、ようやく仕事相手の目をみて話せるようになった。
元の会社で広報を務めていた同期の早希がいなかったら、自分はどうなっていたかわからない。彼女が「アキが書く新商品アンケートって、うちの部署で評判良かったんだよね」と言い、普段はプロに外注している社内パンフレット用の新商品紹介記事の仕事を振ってくれたのが始まりだ。元いた会社からお金をもらうのは気がひけるといったら「じゃ、ペンネームにしなよ」と提案してくれた。それをきっかけに、他媒体からも小さなライター仕事がちらほらと舞い込むようになった。いつしか、育児サイトとグルメサイト、二つに連載を持つようになった。微々たる原稿料だが、手取り十五万円の二人暮らしには貴重な収入源になった。
三宿にある無認可保育園で春を引き取った帰り道、偶然目に入ったのは「中華そば のぞみ」のくたびれた暖簾だった。この店の存在を知ったのは、悔しいが、ラーメン武士のブログがきっかけだった。自分より悪く言われている人を探して心の慰めにしようとしたら、この店の記事を読んでしまい、かえって痛みが倍増したのだった。
『おばさん店長の爪が今にも割れそう、食欲が激減するほどの、ささくれとひび割れ。皮膚や爪のかけらがスープに入っているんじゃないの?』
読むに堪えない食欲をなくす言葉のオンパレード。そこにはただの批評ではない、徹底的に「のぞみ」の店長をこの世界から排斥したいという欲求が感じられた。他人事とは思えなかった。というのも、佐橋が批判していたのは「のぞみ」の味ではない。アキ同様、槍玉にあげられていたのは、その「おふくろらしくなさ」だった。
気付くと、春の手を引いて暖簾をくぐっていた。使い込まれた濃い色の木目調の店内は隅々まで清められ、澄んだカツオと鶏のスープの香りが漂っている。最後に食べたあの札幌みそラーメンの人気店とは何もかも違っていて、ほっとした。ラーメン武士のブログにこの店の評が出たのは随分昔だが、もしかして、今なお影響しているのかもしれない。夕食時なのに、店内に客の姿はなかった。
「いらっしゃいませ」
そう言うなり、女主人はこちらをまじまじと見た。そして、一瞬、なんとも言えない表情になった。女主人はもう十分に理解したようだ。同じだ。この人もラーメン武士のブログを全て読んで、自分より悲惨な人を探して、かえって傷ついたクチ。似た者同士。アキはぎこちなく微笑み、券売機で中華そばとライスのボタンを押した。春にラーメンを食べさせたことはまだないが、白米ならこの子はそれだけでいくらでも食べる。プラスチックの子ども用のスプーンとフォークはいつも持ち歩いていた。
「子連れ、大丈夫でしょうか」
そう尋ねると、女主人は「もちろんですよ」と頷き、カウンター越しに食券を受け取った。
女主人が子ども用の椅子を運んできてくれたので、カウンター席に春と並んで座ることができた。あの日以来、初めての娘との外食だった。
春は厨房のぐらぐら煮立つ湯や巨大な丸ごとの鶏を眺められるのが嬉しくて仕方がないようで、鼻歌を歌っている。やがて現れた、澄んだスープの中華そば、ライスの横にはサービスなのか、チャーシューと煮卵を細かく刻んだ小皿が添えられている。それを差し出す両手は、浅黒く大きく、皮膚のあちこちが割れ、皺が深かった。
「ラーメン屋さんってだいたい、みんな手荒れしているのに、ね」
こちらの気持ちに先回りするように、柄本希さんはそう言った。アキは思わずこう返した。
「指先がふっくらつやつやで、マニキュアをしたらしたで、叩くくせに、ね」
ラーメンの湯気越しに、目が合った。おそらくは一回り年上で、アキよりずっと厳しい自営業の人生を歩んできた人。でも、その目はアキの苦しさを知っていた。ずっと誰かとあの話をしたかった。友達も保育園のママ友も、早希でさえも、腫れ物に触るようにあの画像の話を避けている。
チャーシューと煮卵をたっぷりのせたライスを頬張るなり、おいしい、と春は笑った。それを見ていたら、アキは泣き出してしまった。春に絶対に気づかれないように、声を殺して、慌てて下を向く。すると柄本さんがカウンターからこちらに出てきた。店の外に姿を消すと、暖簾を持って戻って来た。今日はもう閉店、とつぶやき、一つ離れた席に座り、こちらにそっとおしぼりを差し出した。
「ゆっくりしていってください。うちのラーメンのスープは子どもでも飲めますよ。無化調……、あ、化学調味料は使っていないですし、塩分は控えめです」
三年ぶりに食べるラーメンは、身体全体にすっと染み渡っていった。あの日、周囲の目を気にしながら夢中でかきこんだこってり味も美味しいことは美味しいが、こちらはずっと滋味深く、身体の部分部分が生き返っていくような気持ちがした。これを言葉にできたらいいのにな、と思った。
「美味しい……。このスープ、透き通っているのにパンチがある」
縮れ麺を夢中ですすると、アキはれんげでじっくりスープを味わった。柄本さんは静かに言った。
「いや、私はまだまだ。母のラーメンにはかなわない。すごく考え抜かれた無駄がない仕事をする人で、最後の一滴まで飲めるクリアなスープなのに、あっさりだけじゃなくて、味に迫力があった。かっこいい、尊敬に値する職人でした」
柄本さんが小さなプラスチックカップを出してくれたので、アキはそこに麺とスープを少しだけ取り分ける。春はしばらくじっと見つめていたが、やがて躊躇なく、麺をすすり始めた。
「だから、母が男の客たちに『お母さん』とか『おふくろ』って呼ばれるのを見るのが、すごく嫌でした。母は私の母で、あんたたちのお母さんじゃないって、小さい頃からずっと思っていた。ちゃんと職人として評価しろよって悔しかった」
ラーメン武士にとって女の優しさは「おふくろ」でしかないのだろう。でも、柄本さんのざっくりとした優しさが、今のアキには滲みていく。
その夜はずっと身体がぽかぽか温かく、いつもは不安が襲ってきてなかなか寝付けないのに、春と同時にふんわりと眠りにつくことができた。翌日ふと思いついて、連載を持つ育児情報サイトに「ラーメン、最後にいついった? 子連れにも入りやすい、『中華そば のぞみ』」という記事をアップしてみた。
三回目に店を訪れたら「アキさんの記事のおかげで、子連れのお客さんが増えた気がする」と柄本さんがわざわざ嬉しそうに教えてくれた。
「ラーメン屋ってなんか怖いと思われがちなの、なんでなんだろうかって、ずっと考えていたんですが」
その夜、カウンターに若い女性二人と、男性一人客だけになったのを見計らって、アキは柄本さんに声をかけた。隣では、すっかり外食に慣れた春が、小盛りの中華そばをプラスチックフォークですすっている。
「ラーメンってなんか、すごく男のものなんですよね。我々は異物だから叩かれたのかもしれません」
あの日の自分は、一刻も早く、周囲に迷惑をかけないように食べ終えねば、と怯えていた。そのせいで、すごい形相で掃除機のように麺を吸い上げていた。そのことが今なお、ネットで揶揄されている。こんなひどい顔で乳児を押しつぶすように抱えながら、ラーメンを食べなくてもいいじゃないか、と誰もが言う。あまりにも批判を見てきたせいで、アキまでそう思うようになっていた。
あの頃は毎日、朝から晩まで、春と二人きりだった。たった一人で緊張しながら育児をし、自分の料理しか食べていないと、外食が恋しくて仕方がなくなる。誰かが作った、あつあつでパンチのある、高カロリーのエネルギッシュな、味に間違いない一品。どうしても美味しいラーメンを食べたくて、授乳の合間を見計らって、近所の行列ができる店に飛び込んだ。それがそんなにいけないことだったのだろうか。
「煮干しに昆布、干し椎茸、かつおぶし、干し貝柱。丸鶏にネギ、しょうが、卵に小麦、かんすい」
柄本さんが呪文のようにつぶやき、アキは首を傾げた。
「うちの中華そばの素材。まあ、アレルギーの問題はあるけれど、全部、子どもでも食べられるものでできている。ラーメンって、みんなに開かれたものなのに、いつの間にか、難しいジャンルになってしまいましたよね」
そう言って彼女は、ラーメンをすする春を見守った。澄んだスープを喉を見せて飲み干し、春は満足そうに、ほう、と息を一つついた。
その時だった。先ほどからずっとこっちをちらちら見ていた、若い女性たちが立ち上がり、やってきた。どちらもボーイッシュでぶかぶかしたパーカー姿で、姉妹かもしれない。
「あのう、もしかして、赤ちゃん連れ写真をさらされた人ですか?」
アキが咄嗟に春を抱き上げて店を立ち去ろうとすると、体格の良い一人が慌てて立ちふさがった。
「ごめんなさい。ごめんなさい。待って!」
「私たちも同じなんです。ラーメン武士にさらされて、すごい有名になっちゃって」
二人は必死の顔で口々にそう言った。そういえば、どちらの顔にも見覚えがあるような気がした。一人は佐渡恵、もう一人は朝山美香とそれぞれ名乗った。
「おふくろ、部活、愛情、ノスタルジー、癒し」
離れた場所に座っている、ラーメンのキャラクターが描かれたTシャツをムチムチした身体に貼り付けた、若い男性が突然、こう唱えた。
「ラーメン武士が、オーソドックス系中華そばを褒める時の語彙はこの五つの使い回し。うまいしか言えない評論はダメだとかくさすくせに、あいつだっていつも同じこと繰り返してるよね?」
恵と名乗る人が、彼をしばらく怪訝そうに見つめていたが、あっと声をあげた。
「もしかして、そのキャラT、替え玉太郎さんですか? いつもラーメン情報、楽しみにしているんです。今日、ここにきたのも、替え玉さんのつぶやきがきっかけで」
と、目を輝かせている。ネットでラーメンについて書いている男。そう思ったら急に怖くなって、アキは春を胸に引き寄せ、顔を伏せた。そんな様子に、恵さんはすぐに気付いたらしい。
「あ、安心してください。ウチら、Twitterで相互フォローの関係で。替え玉さん、ラーメン詳しいけど、おじさんラーメン愛好家とかとは全然、違うんで、説教とかうんちくとかないし」
「そうですよ。それに、俺だって、ラーメン武士にさらされた人間でもあるんで。俺ら、仲間っすよ」
恐る恐る顔を上げると、替え玉太郎という男は「これ、美大の卒業制作で作った、替え玉太郎公式グッズ! 君にあげるよ」と言いながら、彼のTシャツにプリントされたキャラクターそっくりのぬいぐるみをリュックサックから取り出し、春に渡した。春はたちまち打ち解けた顔で、きゃっきゃとはしゃいだ声をあげ、ぬいぐるみを抱きしめている。
その時、木の引き戸が横に開き、顔色の悪い痩せた青年がふらりと姿を現した。
「あ、朝陽さん、来てくれたんだ」
と、替え玉太郎は、何故か顔を赤くし、早口でそう言った。
「俺の、前の職場のせんぱ……、じゃなくて友達です」
「違う。僕、この人の彼氏です」
その朝陽さんという男性は、彼の言葉にかぶせるように真顔で言い直した。胡椒が舞っているわけでもないのに、替え玉太郎は激しくむせた。そして泣きそうな顔で彼の肩を抱き、隣の席に引き寄せた。
「二〇一〇年の十月十日。私たち六人は偶然ここに集まって、それで、常連になったの」
原田萌実ことアキは、すべて話し終えた後で、こう締めくくった。
その間、佐橋は何度も逃げようとしたが、腕っ節の強い店員に椅子に何度も押し戻され、結局、石調の冷たい床に座り込んでいた。カウンターの中の柄本希は立ったまま、ぐらぐら煮立つ、鍋を見下ろしながら、話を引き継いだ。
「あなたに復讐するために一番の方法を話し合った。そして、我々があらゆる人間に開かれた名店を作ること、愛好家が絶対に無視できない、新しい時代の成功のモデルプランになることを最優先の目標とした。目指すのは全方位型の味わいの淡麗中華そば。なぜなら、あなたはクリア系のスープの味わいに語彙力をもっていない。美香さん、恵さんとスープのクオリティをあげるために、徹底的に研究を重ねた。佐橋ラー油がここに来るその日までは、話し合って全員、タバコもコーヒーもやめた。そうだよね」
柄本希は麺をほぐし、鍋に投入しながら、入り口のところに寄りかかっていた、例の用心棒のような体型の店員に目を向けた。
「うん! 今夜からやっと、私たちはスタバに行けるってわけ」
その声で、佐橋はその店員が女性だとようやくわかった。鋭い目つきと鍛え抜かれた身体にばかり目が行って、性別まで気が回らなかったのだ。彼女はカウンター前までやってきた。
「調理のほとんどは希さんが担当するから、私は自分に何ができるかなって考えた。そこで、お客さんが安心して食事を楽しめる店作りを目指した。セクハラ野郎には力が一番効くと思って、空いた時間で、格闘技と重量挙げを習って、身体を鍛えた。そうしたら、もう誰も私のことを『日本一可愛い超巨乳店員』だなんて言わなくなった」
そうしている間にも、柄本希が茹で上げた麺の水気を勢い良く切り、スープを注いだどんぶりに移す様子が、ショートカットにピアスの店員の肩越しに見えた。
「恵の頑張りを見て、私もなんかしなくちゃって気持ちになった。私は海外からのお客さんに対応できるように、英語を学んだ。ここにいるみんなが少しずつお金を出してくれたおかげで、一年間、ニューヨークに留学して、ラーメンブームの広がりを間近でみることができた。カレッジで誰もが生きやすい街作りを学んだ。それは店のリニューアルにおおいに役立った」
店員二人に同じ豚のタトゥーが入っていることに、佐橋はようやく気付き、震え上がった。原田萌実が余裕たっぷりの調子で割って入ってきた。
「店を人気店に押し上げるためには、キャッチフレーズが何より大切。私はグルメ専門のライター一本で食べていけるように死に物狂いで頑張った」
「どこかの誰かさんと違って、ママは守備範囲が広いからそりゃ売れるよね」と、中学生がふふっと笑う。萌実が得意げに続けた。
「署名記事を書けるようになったタイミングで『全方位型淡麗』という言葉を生み出した。『のぞみ』がリニューアルする前から、意識的に広めておいてブレイクの土壌を作り、ことあるごとにメディアで援護射撃した」
これからどうぞよろしく、同業者ですもんね、先輩、と付け加え、萌実は高級そうな革製のケースから「ライター 原田萌実」という名刺を優雅に取り出すなり、床に座り込む佐橋に強く押しつけた。替え玉太郎は長いアームのついた小型カメラを高く掲げながら、佐橋のおびえきった顔を勝手に撮影している。
「俺は、あんたの居場所を業界から奪うために、ラーメン専門You Tuberになることを決めた。あんたがバカにする『うまい』連発の戦術で、小さい子どもや女性ファン層を取り込んだ。白いTシャツを着ているのは媚びているからじゃない。それがラーメンが一番美味しそうにみえる清潔なレフ板だからだよ。汁を飛ばさないで麺をすするために特訓を積んだ。白Tが完璧に似合うようになるために、恵さんと一緒にジムに通い、二十キロ痩せたよ。ダイエットはきつかったけど朝陽がサポートしてくれたから……」
替え玉太郎の横に親しげに寄り添うスーツの男は、よく見れば、ライフスタイル情報誌で最近顔を見ることが増えた、若手建築家の片山朝陽だった。
「僕は『のぞみ』の居心地の良い店作りを目指し、建築家としての経験を積んだ。世界中のレストランを見て回り、研究を重ねた。ニューヨークでは美香さんと合流して、現地のラーメン屋を見て回った。調理はほぼ柄本さん一人だから、彼女の体格から逆算した厨房の動線づくり、そして、一見シックで都会的だが、女性一人客はもちろんあらゆるジェンダーアイデンティティ、障害をもつ人にも対応できる独自のデザインを編み出した。足元や手元は良く見えるけど、客同士の顔はあまり良く見えない、落ち着いた照明になるよう心がけた」
「おじさん、これら全部の努力は、『のぞみ』をおふくろ、部活、愛情、ノスタルジー、癒し、のキーワードで語れないようにするためなんですよ」
中学生が腕組みをして、佐橋を見下ろしている。耐えられなくなって、佐橋は叫んだ。
「お前ら全員暇かよ!! なんで人生かけて、そこまでやるんだよ。もっと有効に時間を使え! 他に建設的なやり方はいくらでもあるだろうが!!」
赤山美香がこちら側のテーブルに、中華そばを両手でことりと置いた。さっきからずっと気になっていた、鶏と魚介ベースの、ふんわりと食欲をくすぐる、雑味のない香りが一層強まる。逃げたいという気持ちとどうしても食べたいという気持ちが拮抗し、佐橋は涙ぐんだ。結局、佐渡恵の手によって無理やり椅子に座らせられ、しぶしぶと箸を取る。
あらゆる媒体で取り上げられていた、のぞみの中華そばは、黄金色のスープにちぢれ麺が沈み、ネギ、メンマ、チャーシュー、ナルト、煮卵がバランスよく配置された、ごくごく王道を行く見た目だった。しかし、その澄み切ったスープの美しさに、佐橋はただごとではない迫力を感じた。震える手で一口ちぢれ麺をすすり、舌や喉に心地よい波を感じさせながらすべりおちていく、コシと香ばしさ、歯切れの良さに目を見開いた。そのウェーブにからみつくスープの爽やかさと香り高さ。そして、飲み込んだ後に押し寄せてくる、一口目の印象とまるで違う攻撃性は一体なんだろう。
「なんでそこまでやるかって? あなたに勝手に名付けられた自分を取り戻すためですよ。自分たちの手で」
春はいつの間にか向かいに座り、夢中で麺をすする、父親より年上であろう佐橋を見据えている。一見、丸い味わいの先の方に、ゴリッとした荒々しさがある。この味の正体は——。佐橋はこれまでのラーメン人生を振り返った。あらゆる経験、言葉、知識を総動員しながら、薄さに反して十分な肉汁とかみごたえを感じさせる、とろけるようなチャーシューを堪能した。
「あたしは、ばか親に育てられたかわいそうな赤ん坊じゃない。それに、ママはばか親じゃない。恵さんの体は恵さんのものだし、店長は誰のおふくろでもない。替え玉さんと朝陽さんがどこでどんなふうに仲良くしようが、美香さんの性別がなんであろうが、たとえ自分の中で答えが出なかろうが、あなたなんかにくだらない名前でなれなれしく呼ばれる筋合いはないんですけど!」
怒りに燃えて、こちらを睨みつける春を前に、佐橋は震えながら麺をすすり終え、再び、スープに向き合った。もう一度じっくりと味わった後で、柄本希に向かって問うた。
「一つだけ質問させてくれ、頼む。味の決め手は、最後に足した追いガツオ、おそらく薄くスライスした……違うか」
柄本希はしばらくこちらを見た後で、ゆっくりとタオルで手を拭きながら、カウンターの外に姿を現した。こうしてみると、思ったより小柄で肩幅も狭い。なにより、四十五歳の自分と年がそう変わらないことに、佐橋ははっとした。
「正解。最後に魚介スープに大量に足しているのは、ふわふわの花ガツオ。家庭で食べるような。春ちゃんが小学校に入ったばかりの頃、私の家に遊びに来た時食べていた、ねこまんまがヒントになった。それが調和のとれた淡麗に、中毒性を足している。ベースの本枯節だけじゃこの味にならない」
「それで後味に、最後の油っぽさと荒々しさがブーストされたってわけか……」
佐橋はため息混じりにつぶやき、残ったスープを眺めた。
「優しさだけじゃ、全方位にはなれない。強い気持ちがどこかに見え隠れしないと。単調になるんだよ、なにごとも、な」
替え玉太郎の口調がふと、親しげになった。原田萌実までがこちらに言い含めるように目を細める。
「本当はどんなに頑張っても完全な全方位なんて、無理なんです。でも、自分ができる範囲で、取りこぼす層を少しでも減らしたいという気持ちは絶対に、どんな仕事にも必要。全方位型って言葉を私が好んで使うのは、それを忘れちゃいけないって気持ちがあるからなんです。あなただってそうなんですよね。きっとお母さんや子ども時代にすごく愛着があるから、ああいう言葉を選ぶんですよね」
カウンター席に座った柄本希が、タバコに火を点けた。ここ禁煙ではないか、と言おうとしてやめた。おそらく、十二年三ヶ月ぶりの一本を、希は実に美味そうに吸った。吐き出した煙がゆっくりと舞い上がり、片山朝陽が考え抜いた、天井にスマートに隠された換気口に吸い込まれていく。
おふくろ、部活、愛情、ノスタルジー、癒し。
小さい頃は友達もいなかった。部活に入っていたことは一度もない。母親の顔は、いつもぼんやりとしか思い出せない。幼い頃、母はなんでもいうことを聞いてくれたし、成人してからもライター一本で食べられるようになるまでは欠かさず仕送りしてくれた。佐橋が出たテレビはいつも録画して、近所に自慢して回っていた。にもかかわらず、母が亡くなった時、佐橋はあまり悲しいと思わなかった。記憶はこうしている今もどんどん薄れていく。母が最初に倒れた時、ずっと海外で働いていた妹は慌てて夫とともに帰国し、病院に泊まり込みとなった。そして、
——お父さんとお兄ちゃんはママをお手伝いさんくらいにしかいつも思っていなかったじゃん。だから、ずっと体調が悪いことにも気づかなかったんだよ
と、なじった。
どの言葉も使用不可となった今、佐橋は「うまい」と言うのを必死で堪えている。
「追い花ガツオに気付いたなんて、あなたにも、まあまあいいところがあるんだね。そういえば、母はあなたのこと、嫌ってはいなかった」
と思いがけず、懐かしそうな口調で柄本希が言った。スープで胃が温かいのに、七人がこちらを見るのをやめた今、佐橋の背中はいっそう冷たかった。もはや彼らは気が済んだのか、佐橋から完全に興味をなくしたようで、和気藹々としゃべりながら、中華そばの替え玉だの餃子だのを注文している。
そのうち、柄本希はタバコを空き瓶にねじ込むと、厨房へと戻っていった。
「うまい」で身体がいっぱいだった。大学生の頃、初めて池袋でつけ麺を食べた時のように、身体中の細胞という細胞が喜びで満ちていた。スープを夢中で飲みながらも、丼を置くのが、佐橋は怖かった。この店を一歩出てからが、本当の地獄なのかもしれない。
一見、澄み渡っているが、こうして顔を近づけてみると、スープには無数の小さな輪が輝いている。その一つ一つに、幼い頃よく、お母さんにそっくりだね、と言われた、自分の泣き顔が映っている。
「めんや 評論家おことわり」 了
この試し読みは校了前のデータで作成しています。ご了承ください。