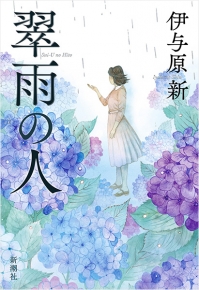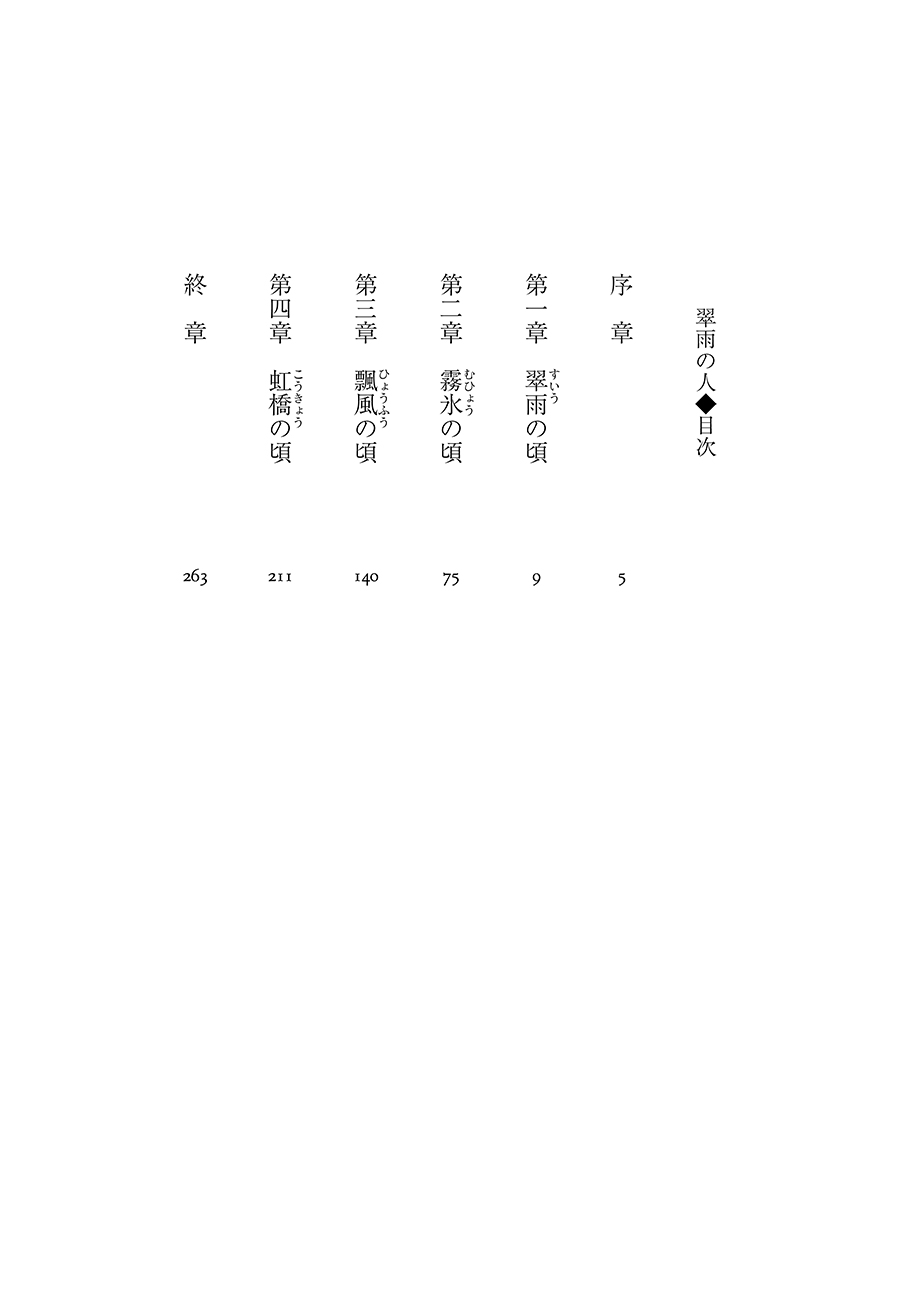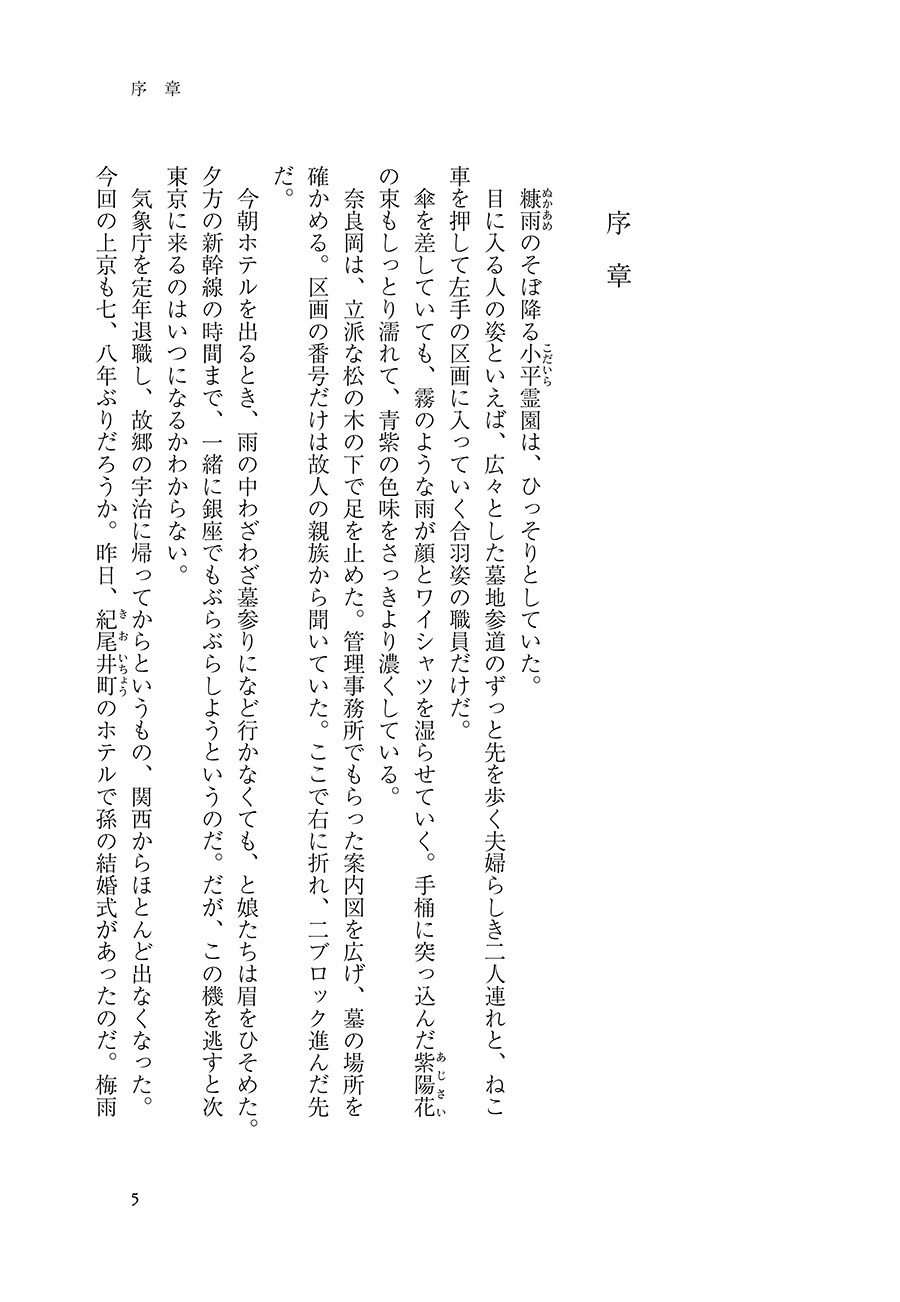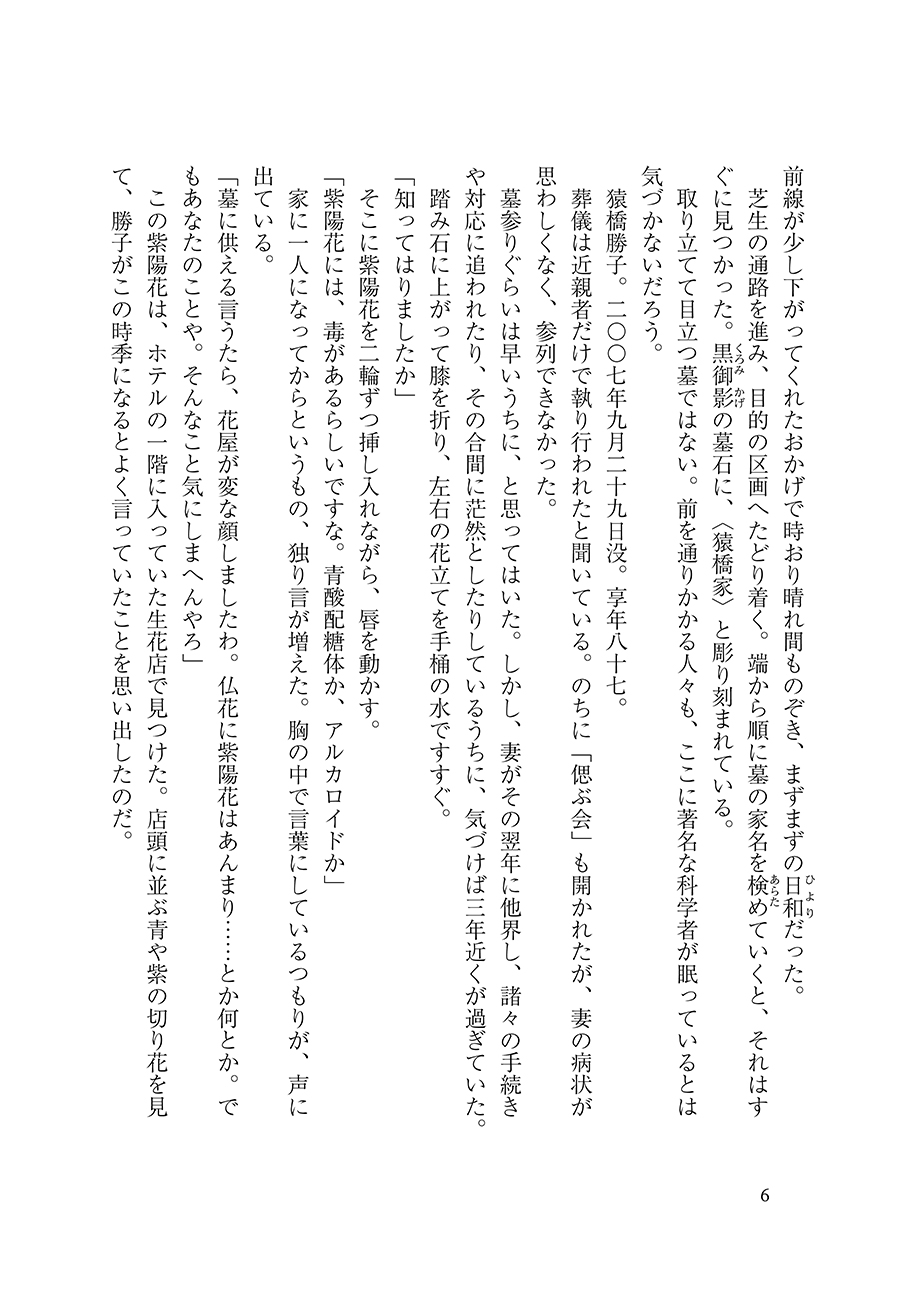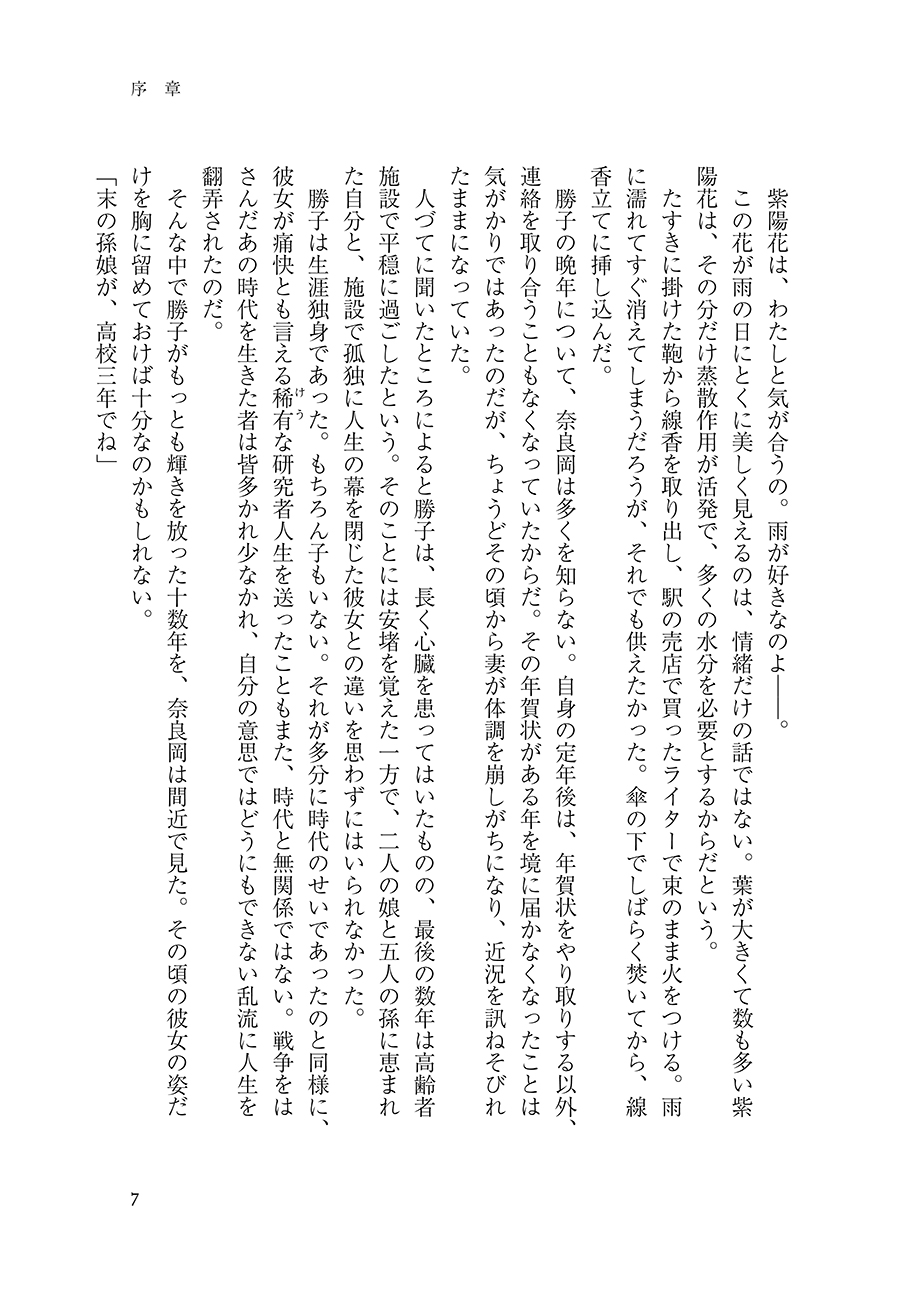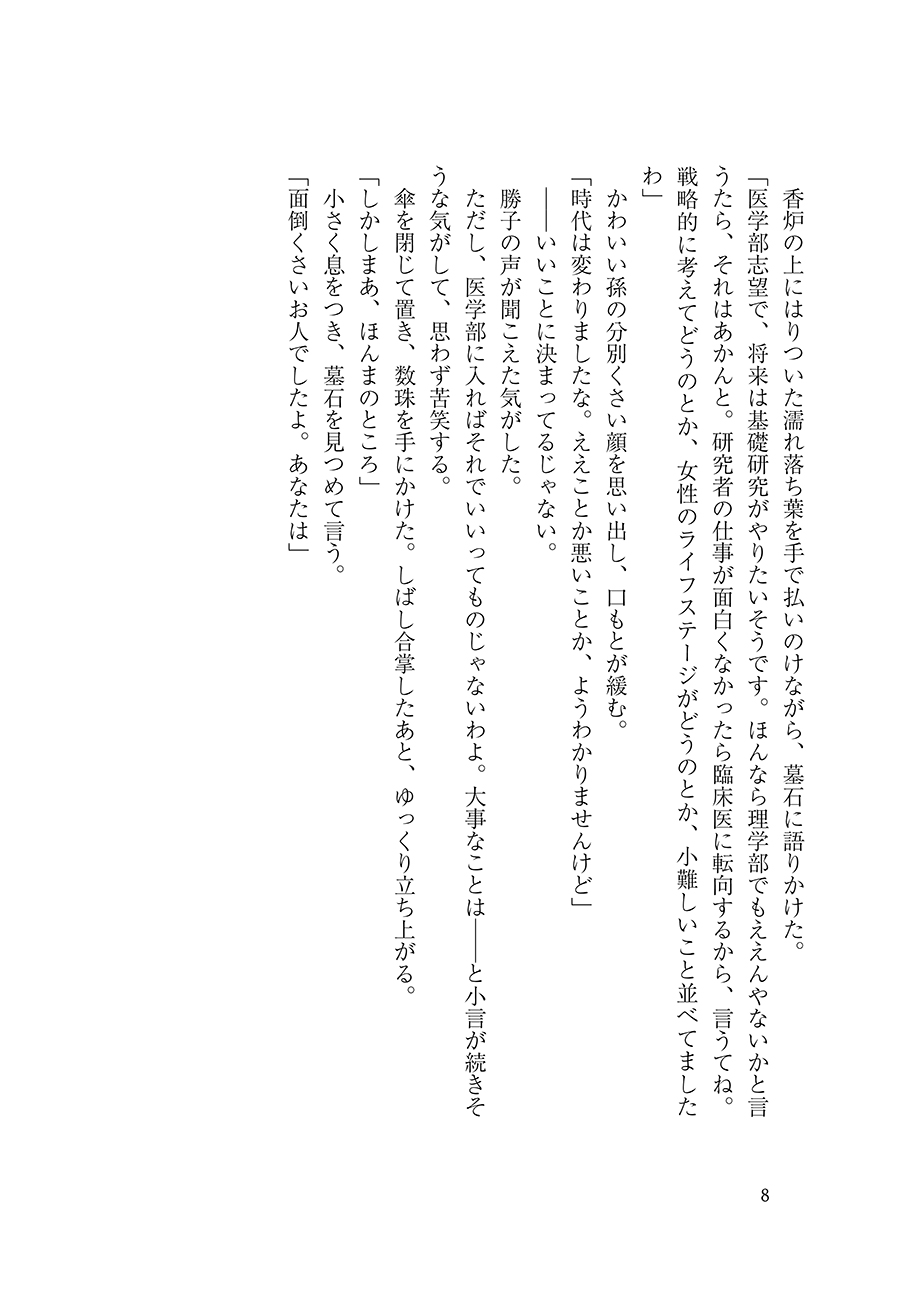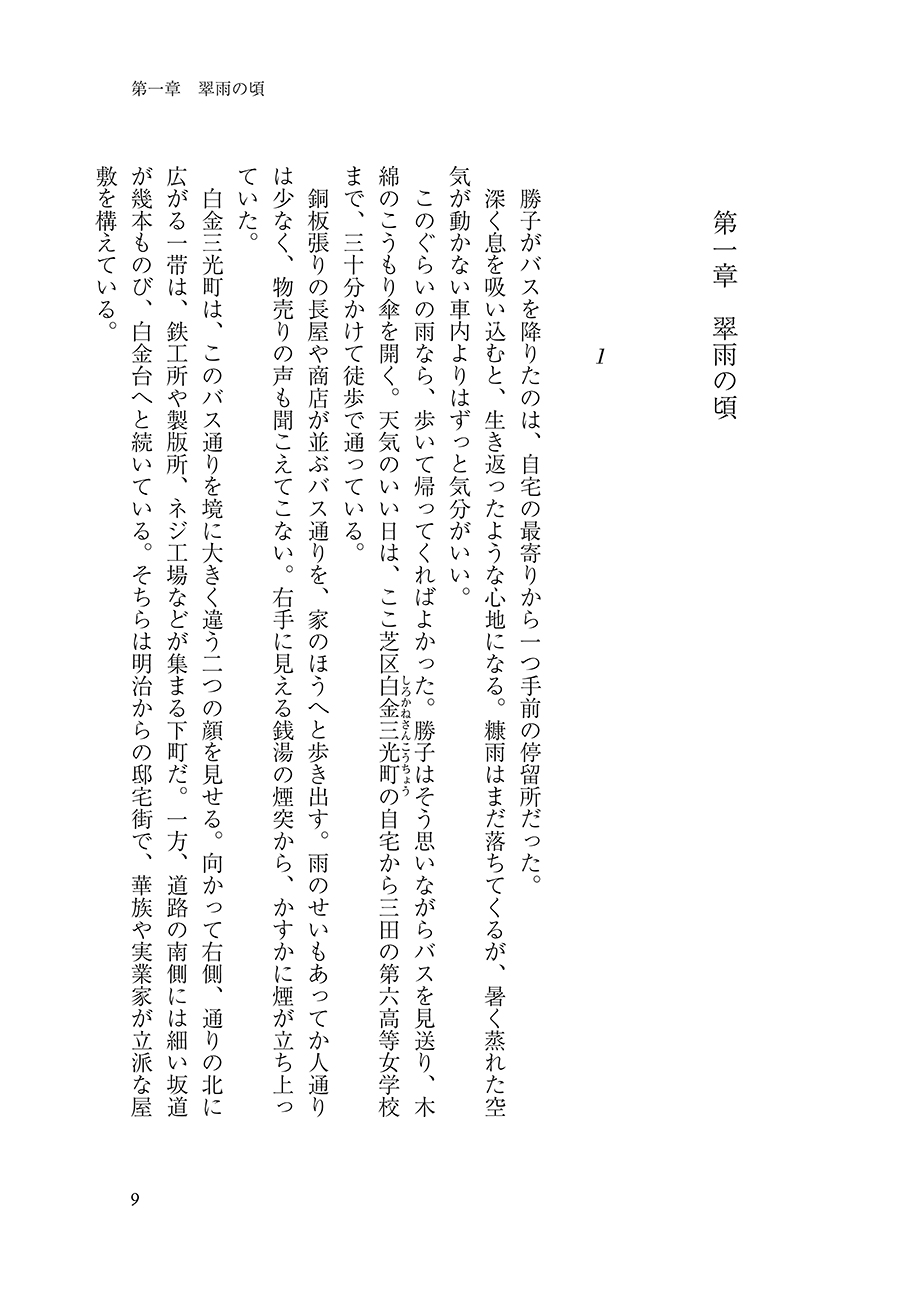序 章
糠雨のそぼ降る小平霊園は、ひっそりとしていた。
目に入る人の姿といえば、広々とした墓地参道のずっと先を歩く夫婦らしき二人連れと、ねこ車を押して左手の区画に入っていく合羽姿の職員だけだ。
傘を差していても、霧のような雨が顔とワイシャツを湿らせていく。手桶に突っ込んだ紫陽花の束もしっとり濡れて、青紫の色味をさっきより濃くしている。
奈良岡は、立派な松の木の下で足を止めた。管理事務所でもらった案内図を広げ、墓の場所を確かめる。区画の番号だけは故人の親族から聞いていた。ここで右に折れ、二ブロック進んだ先だ。
今朝ホテルを出るとき、雨の中わざわざ墓参りになど行かなくても、と娘たちは眉をひそめた。夕方の新幹線の時間まで、一緒に銀座でもぶらぶらしようというのだ。だが、この機を逃すと次東京に来るのはいつになるかわからない。
気象庁を定年退職し、故郷の宇治に帰ってからというもの、関西からほとんど出なくなった。今回の上京も七、八年ぶりだろうか。昨日、紀尾井町のホテルで孫の結婚式があったのだ。梅雨前線が少し下がってくれたおかげで時おり晴れ間ものぞき、まずまずの日和だった。
芝生の通路を進み、目的の区画へたどり着く。端から順に墓の家名を検めていくと、それはすぐに見つかった。黒御影の墓石に、〈猿橋家〉と彫り刻まれている。
取り立てて目立つ墓ではない。前を通りかかる人々も、ここに著名な科学者が眠っているとは気づかないだろう。
猿橋勝子。二〇〇七年九月二十九日没。享年八十七。
葬儀は近親者だけで執り行われたと聞いている。のちに「偲ぶ会」も開かれたが、妻の病状が思わしくなく、参列できなかった。
墓参りぐらいは早いうちに、と思ってはいた。しかし、妻がその翌年に他界し、諸々の手続きや対応に追われたり、その合間に茫然としたりしているうちに、気づけば三年近くが過ぎていた。
踏み石に上がって膝を折り、左右の花立てを手桶の水ですすぐ。
「知ってはりましたか」
そこに紫陽花を二輪ずつ挿し入れながら、唇を動かす。
「紫陽花には、毒があるらしいですな。青酸配糖体か、アルカロイドか」
家に一人になってからというもの、独り言が増えた。胸の中で言葉にしているつもりが、声に出ている。
「墓に供える言うたら、花屋が変な顔しましたわ。仏花に紫陽花はあんまり……とか何とか。でもあなたのことや。そんなこと気にしまへんやろ」
この紫陽花は、ホテルの一階に入っていた生花店で見つけた。店頭に並ぶ青や紫の切り花を見て、勝子がこの時季になるとよく言っていたことを思い出したのだ。
紫陽花は、わたしと気が合うの。雨が好きなのよ――。
この花が雨の日にとくに美しく見えるのは、情緒だけの話ではない。葉が大きくて数も多い紫陽花は、その分だけ蒸散作用が活発で、多くの水分を必要とするからだという。
たすきに掛けた鞄から線香を取り出し、駅の売店で買ったライターで束のまま火をつける。雨に濡れてすぐ消えてしまうだろうが、それでも供えたかった。傘の下でしばらく焚いてから、線香立てに挿し込んだ。
勝子の晩年について、奈良岡は多くを知らない。自身の定年後は、年賀状をやり取りする以外、連絡を取り合うこともなくなっていたからだ。その年賀状がある年を境に届かなくなったことは気がかりではあったのだが、ちょうどその頃から妻が体調を崩しがちになり、近況を訊ねそびれたままになっていた。
人づてに聞いたところによると勝子は、長く心臓を患ってはいたものの、最後の数年は高齢者施設で平穏に過ごしたという。そのことには安堵を覚えた一方で、二人の娘と五人の孫に恵まれた自分と、施設で孤独に人生の幕を閉じた彼女との違いを思わずにはいられなかった。
勝子は生涯独身であった。もちろん子もいない。それが多分に時代のせいであったのと同様に、彼女が痛快とも言える稀有な研究者人生を送ったこともまた、時代と無関係ではない。戦争をはさんだあの時代を生きた者は皆多かれ少なかれ、自分の意思ではどうにもできない乱流に人生を翻弄されたのだ。
そんな中で勝子がもっとも輝きを放った十数年を、奈良岡は間近で見た。その頃の彼女の姿だけを胸に留めておけば十分なのかもしれない。
「末の孫娘が、高校三年でね」
香炉の上にはりついた濡れ落ち葉を手で払いのけながら、墓石に語りかけた。
「医学部志望で、将来は基礎研究がやりたいそうです。ほんなら理学部でもええんやないかと言うたら、それはあかんと。研究者の仕事が面白くなかったら臨床医に転向するから、言うてね。戦略的に考えてどうのとか、女性のライフステージがどうのとか、小難しいこと並べてましたわ」
かわいい孫の分別くさい顔を思い出し、口もとが緩む。
「時代は変わりましたな。ええことか悪いことか、ようわかりませんけど」
――いいことに決まってるじゃない。
勝子の声が聞こえた気がした。
ただし、医学部に入ればそれでいいってものじゃないわよ。大事なことは――と小言が続きそうな気がして、思わず苦笑する。
傘を閉じて置き、数珠を手にかけた。しばし合掌したあと、ゆっくり立ち上がる。
「しかしまあ、ほんまのところ」
小さく息をつき、墓石を見つめて言う。
「面倒くさいお人でしたよ。あなたは」
第一章 翠雨の頃
1
勝子がバスを降りたのは、自宅の最寄りから一つ手前の停留所だった。
深く息を吸い込むと、生き返ったような心地になる。糠雨はまだ落ちてくるが、暑く蒸れた空気が動かない車内よりはずっと気分がいい。
このぐらいの雨なら、歩いて帰ってくればよかった。勝子はそう思いながらバスを見送り、木綿のこうもり傘を開く。天気のいい日は、ここ芝区白金三光町の自宅から三田の第六高等女学校まで、三十分かけて徒歩で通っている。
銅板張りの長屋や商店が並ぶバス通りを、家のほうへと歩き出す。雨のせいもあってか人通りは少なく、物売りの声も聞こえてこない。右手に見える銭湯の煙突から、かすかに煙が立ち上っていた。
白金三光町は、このバス通りを境に大きく違う二つの顔を見せる。向かって右側、通りの北に広がる一帯は、鉄工所や製版所、ネジ工場などが集まる下町だ。一方、道路の南側には細い坂道が幾本ものび、白金台へと続いている。そちらは明治からの邸宅街で、華族や実業家が立派な屋敷を構えている。
勝子の自宅はもちろん下町の側だ。こぢんまりした一軒家が肩を寄せ合う一画で、古い二階建てに両親と兄と暮らしている。
だが勝子は通りを渡ることなく、途中で左の路地に入った。小高い丘を上っていき、右に折れて細い石畳の道に入る。地元で「雷神様」と親しまれている、雷神社の参道だ。
思ったとおり――勝子は顔をほころばせた。参道に沿って植え込まれた紫陽花が、満開に咲きこぼれている。バスをあそこで降りたのは、これを見に来るためだった。ここの紫陽花はすべて深い青色で、毎年見事な花をつける。
勝子は傘の柄を肩にのせ、誰もいない参道をゆっくり進んだ。日に照らされているわけでもないのに、霧吹きで濡らしたような青い花びらも、水滴で覆われた緑の葉も、眩いくらい鮮やかな色彩を放っている。背後の桜の木から落ちてきた雨粒に葉が揺れると、まるで、雨こそ我が命と花が笑っているかのように見えた。
紫陽花と同じように、勝子も雨が好きだった。
幼い頃は、好きというより、不思議でならなかった。空気の他には何もないはずの空から、とめどなく水が降ってくる。雨で外へ遊びに行けない日などは、二階の窓から灰色の空を眺めながら、「雨とは何だろう。なぜ降るのだろう」と考え続けていた。
十六歳になった今はもちろん、その仕組みをひと通り知っている。それでもなお、雨という現象がもたらす不思議な感動に心を揺さぶられることがよくある。
例えば今、傘の露先から雨粒が一つ手の甲に落ちた。このひとしずくは――正確に言うとそこに含まれる無数の水分子は、ここへ来るまでにどんな場所を巡ってきたのだろう。
遠く大西洋やインド洋も旅してきただろうか。アマゾン川やビクトリア湖も見てきただろうか。もしかしたら、アルプスの氷河や南極の氷床に、何千年、何万年と閉じ込められていたこともあったかもしれない。そんなふうに想像をふくらませていると、この一滴が、勝子の知らない広い世界のことを何でも知っているような気がしてくるのだ。
鳥居をくぐり、せまい境内に入る。いつもなら近所の子どもたちがメンコやゴムとびをして遊んでいるのだが、さすがに今日は静かなものだ。境内を右へ進むと、三十段ほどの石の階段で下の道まで下りていけるようになっている。神社のすぐ近くにある神応小学校へ通っていたときは、この階段を上って境内を通り抜けていくのが近道だった。
だからここへ来るといつも、懐かしさと気恥ずかしさで胸がいっぱいになる。まだ低学年の頃の話だが、今日のような雨の日には、道が滑るからと母のくのに付き添ってもらったり、ときにはおぶってもらったりして登校したのだ。下校時に雨に降られたときは、学校の玄関でくのが傘を手に待っていてくれた。
勝子が大正九年に生まれたとき、両親は三十代半ばを過ぎていた。兄の英一とは九つも歳が離れている。三月生まれということもあって、小学校のクラスでは一番体が小さく、幼さの抜けないひ弱な甘えん坊であった。
くのは礼儀にこそ厳しかったが、それ以外の面ではずいぶん過保護だったと思う。冷たいご飯が嫌いだった勝子のために、くのが毎日昼休みに作りたての弁当を学校まで届けてくれたことは、今も時どき食卓で話題に上る。すると英一が決まって口にするのが、「勝子はうちのペットみたいなもんだったからな」という台詞だ。
背が低かったこともあって低学年の頃はゴムとびも下手で、かけっこをすればたいていビリ。同級生たちからは「勝子なのに、勝てないね」とよくからかわれた。それに言い返すことさえできない自分の、どこが「勝子」なのか。だからとにかくその名前が嫌いで、両親はなぜこんな似合わない名前をつけたのだろうと思っていた。
こんな話を女学校の同級生たちが聞けば、きっと驚くだろう。第六高女ではスポーツが盛んで、勝子もずいぶん鍛えられた。室内温水プールのおかげで水泳が得意になり、グラウンドを走ればリレーの選手。毎日暗くなるまで軟式テニスに熱中し、弓道部まで掛け持ちしている。今では「スポーツ万能の猿橋さん」で通っているのだ。
そんな勝子ももう五年生。来春には卒業だ。いつまでもスポーツばかりに興じてはいられない。友人たちとの他愛ないおしゃべりも、近頃は気づけば進路の話になっている。
井戸で手水を使ってから、傘を閉じて社殿の正面に立った。手を合わせ、願いごとの代わりに、「わたしは将来、何になっているのでしょうか」と心の中でつぶやいてみる。
帰りのバスの中でも、曇った窓を見つめながらずっとそのことを考えていた。
雨の日は、一人静かに考えごとをするのに向いている。それが、勝子が雨を好きなもう一つの理由だ。
喉が渇いていたので、家に着くとまず台所へ向かった。くのは流しの前で糠床をかき混ぜていた。
「遅かったわね。バスじゃなかったの」
「雷神様に寄ってたの。紫陽花、今年もきれいに咲いてるよ」
父も兄も勤め人なので、夜まで帰ってこない。父の邦治は電気技師、英一は東横電鉄の劇場部門に勤めている。
勝子はくのの横から糠床に手を伸ばし、小茄子を一つ、つまみ取った。それを流しでさっと洗い、立ったままおしりからかじる。
「うん、よく漬かってる」
「これ、お行儀」
顔をしかめたくのが、冷たい麦茶を出してくれながら言う。
「あそこの紫陽花、近所の人が毎年剪定してるのよ。ほら、佐々木さんて、中学校で英語の先生してた人」
「へえ、そうなんだ」
その人のことは知らないが、うまい具合に教師の話が出た。勝子はコップを握ったまま、ふと思い出したという体で水を向ける。
「先生と言えばね、うちのクラスの坂田さん、二つ上のお姉さんがお茶の水に行ってるんですって。だから彼女も、頑張ってそこを目指すんだって」
「お茶の水」というのは、東京女子高等師範学校のことだ。大学への入学が許されていない女子が女学校からさらに上の学校へ進む場合、行き先は専門学校か女高師しかない。官立の東京女高師は、第六高女の生徒たちにとって最高の進学先の一つだった。
「姉妹で学校の先生になるの?」くのが訊いた。
「そうだと思う。お姉さんが文科で、彼女は理科」
「立派なことには違いないんだろうけどねえ。親としては心配よ」
くのが真顔で言ったことの意味はわかった。お嫁に行くのが遅くなる。もっと言うと、女子は学歴が高すぎると結婚相手を見つけるのに苦労する、と言いたいのだ。
二階にある四畳半の自室へ行き、ジャンパースカートの制服からうぐいす色のスカートにはき替えた。
庭に面した窓を開け、その際に座って窓枠にもたれかかる。糸のような雨が音もなく降り続いていた。
くのの反応は、半分予想通りのものだった。それでもやはりもう半分は、がっかりした。女高師ならば少しは肯定的なことを言ってくれるのではないかと、淡い期待を抱いていたのだ。
地方から出てきた両親は、とくに高い教育を受けているわけではない。英一は横浜高等商業学校を出ているが、それは彼が男だからだ。娘の勝子については、女学校まで出してやれば十分だと考えていることは、確かめるまでもなく言葉の端々に感じられた。
二十歳ぐらいで見合いをし、結婚して家庭に入る。おそらくくのは、それが娘の一番の幸せだと信じて疑っていない。第六高女にも、結局は自分もそうなるのだろうと何とはなしに思い込んでいる同級生がかなりいる。
だが勝子は、結婚のことはともかく、一生続けられる仕事を持ちたいと考えていた。“自立した女性”のイメージを植え付けられたのは、小学校時代。担任だった三人の教師はいずれも女性で、子育てをしながら教壇に立っていた。
とくに一、二年生のときの担任、杉田と、三年生のときの大庭は、ともに若くして夫を亡くしていた。今思い返してみても、二人の姿はいつも凜として、生活のためというだけでは決してない、教育への情熱にあふれていた。自立するというのは、きっとそういうことなのだ。
帰りのバスで乗り合わせた、二人連れの男性の会話を思い出す。年かさのほうの男性の息子が先月、支那駐屯軍の一員として天津に派遣されたという。「どうも北支の情勢がまた緊迫しているらしい」と難しい顔で言っていた。
きな臭いのは大陸だけではない。居間でよく聴いているラジオでは、今年――昭和十一年二月二十六日に起きた青年将校の反乱事件のニュースが今も毎日のように流れる。あのときは東京市内がすべて麻痺したようになって、勝子たちも何かと難儀した。市民生活はもう落ち着いているが、戒厳令はまだ解かれていない。
英一は、廣田内閣について書かれた新聞記事を見ながら、「反乱事件のせいで、軍部のファッショが進むな」と口もとをゆがめていた。勝子にはその理屈がよくわからなかったが、世の中がそういう流れにあることは肌で感じている。
あのバスの男性の息子が、徴兵されて天津へ送られたのだとすれば、きっと他に将来の夢や目標があるだろう。一度きりの人生を、精一杯生きようと思っているだろう。しかし、もし戦闘が起きて命を失ってしまったら、そこですべてが終わるのだ。望みもしなかったことで人生を無に帰するばかりか、本来何の恨みもないはずの他人の生命まで奪う戦争という名の殺し合いが、勝子には泣きたくなるほど愚かなことに思える。
この東京にいる限り、今にも大規模な戦争が起きて大勢の人が死ぬという想像はなかなかできない。さりとてこのまま平穏な日々が続くとは、どうしても思えなかった。勝子の自立への渇望の裏面には、そんな予感めいた思いがわずかにこびりついている。
自立するにしても、杉田や大庭のように、心から情熱を注げる職業に就きたい。そのためには、自分の好きな分野、得意な分野でなければならないだろう。女学校の科目で言えば、勝子にとってそれは数学と物理であった。
理科系の得意な女子がそれを活かせる職業というと、まず第一に教師だ。同級生の坂田も、東京女高師の理科の教授陣がいかに素晴らしいかという話を、よく勝子にしてくれる。しかし勝子には、まだ誰にも打ち明けたことのない夢があった。
医師になること。
小学生の頃に何度か診てもらった小児科の優しい女医に、勝子は深い尊敬の念を抱いた。以来、医師という職業に憧れを持ち続けてきたが、今はそれだけではない。人より多く学ばせてもらうのであれば、その分社会に多くのものを還元しなくては。勝子にとって、医師というのはそれを理想的な形で実現できる職業に思えた。
当然ながら、簡単なことではない。女子が医学を学べる専門学校は、日本中でたった三校しかないのだ。
勝子の意中の学校は、その中で一番の名門、東京女子医学専門学校であった。全国の秀才が受験して競争率が六、七倍あるというから、大変な難関だ。
だが勝子の心を萎縮させているのは、入学試験の厳しさなどではなかった。この希望を両親に伝えた場合の、二人の反応だ。女性が医師になるというのは、社会的地位を得て自立することを意味する。それは反面、生涯一人で生きていくのも厭わないということ――両親はそんなふうにとらえるのではないか。驚き、心配し、場合によっては嘆き悲しむかもしれない。
親にそんな思いをさせる選択を、子はなすべきではない。父母の愛を一身に受けて育ったという自覚があるだけに、二人の期待にわずかでも背くことへのほとんど本能的な恐怖感が勝子の中にはあった。
階段の下から、「勝子」とくのが呼ぶ声がした。
「頂き物の水羊羹があるんだけど、食べる?」
「はーい、今行きます」
声だけ張って応えたが、すぐには立ち上がらなかった。
幼い頃、チョコレートなどの珍しい到来物があると、くのは少しも口にせず、すべて勝子に食べさせてくれた。くのにとって勝子は今も、小さな女の子のままなのだ。毎朝小学校へと家を出るたびにべそをかいていた、六歳の頃のままの。
窓の外、手をのばせば届きそうなところで、庭木の楓が揺れていた。空が灰色だからこそだろう。雨に濡れた青葉の緑がいつもより濃く鮮やかに映る。
近所の家から、お琴を練習する音が聞こえてきた。なぜかいつもよりうるさく感じて、勝子はぴしゃりと窓を閉めた。
2
放課になり、帰り支度をしていると、経子と佳子が勝子の席までやってきた。
「勝子ちゃん、お正月、うち来るでしょ?」経子に訊かれた。
「ああ……かるた会」
「絶対来てよね」佳子も横から言う。「女王がいないと盛り上がらないもん。お兄さんのお友だちも、またたくさんいらっしゃるんだって」
佳子は三つ編みの髪に手をやり、おどけてしなをつくった。その二の腕を経子が笑いながら軽く叩く。
横山経子と峯崎佳子は、勝子が第六高女で出会った一番の友人たちだ。毎年正月には、渋谷区宇田川町にある経子の自宅を佳子と訪ねるのが恒例となっている。立派な屋敷で盛大に催される百人一首のかるた会に参加するのだ。振袖で着飾った勝子たちは、早稲田大学に通う経子の兄とその友人たちにいつも大歓迎される。おまけに勝子は小学生の頃から大人を負かすほどかるたが得意だったので、しばしば主役になった。
毎年楽しみにしていた行事だったはずが、今回ばかりは気が乗らない。このところ勝子の心の大部分を占めているのは、進路の問題だ。あと三カ月で卒業だというのに、医学の道へ進みたいということをまだ両親に言い出せずにいる。このままでは、晴れやかな気持ちで正月を迎えることなどとてもできそうになかった。
「かるた会に行けるのも、最後かもしれないしね」佳子が真顔になって言う。
「さびしいこと言わないで。卒業してからだって、会えるわよ」
不意にまつげを震わせた経子を見て、やはり断ることはできないと思った。無理に声を明るくして告げる。
「お正月、もちろんわたしもうかがうよ。経子ちゃん家でかるたをしないと、新年って感じがしないもんね」
三人で教室を出ようとしたとき、教卓で生徒の質問を受けていた担任の安河内に「あ、猿橋さん」と呼び止められた。
「例の記事、見つかりましたよ」一冊の婦人雑誌を差し出して言う。
勝子は教卓に駆け寄ってそれを受け取り、洒落た帽子の女性が描かれた表紙に目を落とす。今年の九月号だ。「お借りしていいんですか」
「家内ももう読まないと言ってますし、必要なら差し上げますよ」
「ありがとうございます!」勝子は雑誌を胸に押し抱き、勢いよく頭を下げた。
廊下に出るなり、両脇から二人にはさまれた。歩きながら佳子が「さっきの雑誌、何? 例の記事って?」と訊いてくる。
「うーんとねえ」はっきり明かすことはできず、言葉を濁して答える。「わたしの尊敬する人の記事よ」
「誰のこと?」今度は経子に問われる。
「まだ内緒。いつか話すよ」勝子は足を止めずに、なるべく軽い調子で言った。
夕食後、二階の自室で雑誌を開いた。目次を順に追っていくと、その人物の名前が目に飛び込んでくる。
吉岡彌生。医師にして、東京女子医学専門学校の創設者だ。
まだ女医などほとんどいなかった明治の半ば、十八歳で私立医学校、済生学舎の門を叩き、二十一歳のときに内務省の医術開業試験に合格。東京市内で医院を営みながら、二十九歳にして夫の荒太とともに日本初の女医養成機関、東京女医学校を設立した。吉岡はそれを専門学校、さらには文部省指定校へと昇格させて、現在の名門、東京女子医学専門学校に育て上げたのである。
吉岡は今も医業のかたわら、日本医師協会評議員や全国女子教育者同盟会長といった要職にいくつも就いている。津田英学塾の始祖、津田梅子や、女子美術学校の横井玉子と並んで、女子高等教育の普及に尽力した教育者としてもっとも尊敬を集める女性の一人だ。勝子が密かに東京女子医専への進学を望んでいるのも、吉岡に対して崇拝に近い気持ちを抱いているからに他ならない。
勝子は先日、吉岡への憧れを「自省録」に綴った。生徒たちが一週間の出来事や感じたことを書き留めて、担任の安河内に毎週提出しているノートだ。両親に伝わっては困るので、医師を目指したいとまでは書かなかったが、胸の奥の煩悶をほんの一片でもおもてに吐き出したいという衝動を抑えることができなかった。
安河内から返却されたノートには、赤インキで〈妻が讀んでゐる雜誌に、以 吉岡先生が手記を寄せてゐました。さがして今度持つてきませう〉と書き込まれていた。それがこの婦人雑誌で、手記は今年六十五歳になった吉岡が自らの半生を振り返ったものだった。
吉岡先生が手記を寄せてゐました。さがして今度持つてきませう〉と書き込まれていた。それがこの婦人雑誌で、手記は今年六十五歳になった吉岡が自らの半生を振り返ったものだった。
文机に開いた手記のページを、勝子は夢中になってめくった。知らなかったことや意外な事実ばかりで、驚いた。
例えば、吉岡もまた、医学の道へ進むのを父親に反対されていたということ。彼女の生まれは静岡の田舎だが、父親は江戸で蘭方も学んだ医者であった。だから彼女も医師になるべくしてなったのだろうと勝手に思い込んでいたのだが、そうではなかったらしい。女性には学問より良縁が大事ということで、彼女の希望はなかなか聞き入れられず、二年間嘆願し続けてやっと上京の許しを得たという。
二十九歳で東京女医学校を設立したときの状況も、勝子の想像とはかけ離れていた。医師としてすでに名声を得ていたとばかり思っていたら、地位も資産もない一介の町医者に過ぎなかったという。学校といっても、医院の一室を教室に当て、〈東京女医学校〉という看板を掲げただけ。最初の年に集まった学生は、たった四人だったそうだ。
無謀だと後ろ指をさされながらも、吉岡はあきらめなかった。金策に駆け回りながらあちこちに頭を下げて講師と学生を集め、少しずつ学校を大きくしていった。その原動力はひとえに、悲壮ともいうべき使命感。当時、済生学舎などの医学校が女子の入学を拒絶し始めたために、医学を志す女学生が行き場をなくそうとしていた。吉岡は、数少ない先達の女医たちが死にもの狂いでこじ開けてきた女性の医師への道を閉ざしてはならぬ、と固く誓ったのである。
「――すごい」手記を読み終えた勝子は、知らぬ間に目頭を熱くしていた。
やはり、この人の創った学校で学びたい。切ないほどの思いが、一段と強くなって胸に湧き上がってくる。
手記の最初に戻り、ページの隅にのせられた和服姿の近影を見つめた。髪を後ろで結ったふくよかな輪郭。口もとを引き締め、力のある目をこちらに向けている。優しい女医というよりは、威厳にあふれた教育者という雰囲気だ。
吉岡先生は、今も教壇に立たれることがあるのだろうか。どんな声で、どんな話し方をするのだろう。そんなことをぼんやり考えていると、襖の向こうで「勝子」と英一の声がした。今日は残業だと聞いていたが、手記に夢中になっているうちに帰宅していたらしい。
「おかえりなさい」と部屋に招き入れると、ワイシャツの上にどてらを羽織った英一が文机をちらりと見る。
「何だ、雑誌読んでたのか。英語をやってるなら、見てやろうと思ったんだけど」
「今からやるところだったの」
勝子は慌てて雑誌を閉じ、代わりに本立てから原書を抜き出した。W・ブラッドフォード・スミスという学者が著した『英米戯曲総覧』。勝子は今、卒業の記念として、戯曲の歴史をまとめたこの本の全訳に取り組んでいる。
それを勧めてくれたのは、英一だ。彼は横浜高商時代に外国人相手のガイドのアルバイトをしていたことがあり、英語が得意だった。高女に入るまでほとんど英語に触れてこなかった勝子が、私立小学校で英会話に親しんできた同級生たちにすぐに追いつくことができたのは、一から丁寧に教えてくれた兄のおかげだ。ご自慢のレミントンのタイプライターを使って、英文タイプの手ほどきも受けている。
英和辞典と原稿用紙を準備する横で、英一があぐらをかく。
「今度の日曜のこと、母さんから聞いたか」
「うん」手を止めて、正座のまま英一ににじり寄る。「お会いできるのは楽しみだけど、やっぱり少し緊張する」
「なんでお前が緊張するんだ」
「だって、わたしにとっても家族になる人なのよ」
「大丈夫。さっぱりした人だし、すぐ仲良くなれるさ」
「久枝さんのこと、何て呼べばいいんだろう。“お義姉さん”ていうのは、まだ早いよね」
「だな」英一は頬を緩めた。「ちょっと早い」
仲に立つ人があって、英一はこの秋、見合いをした。相手は北海道出身の若林久枝という女性だ。話はとんとん拍子に進み、来年二月に祝言をあげるということでまとまったそうだが、勝子はまだ彼女と対面していない。
次の日曜、久枝とその両親がこの家へ挨拶に来る。両親はそのために丸一日かけて北海道から出てくるそうだ。結婚前に、娘が東京で嫁ぐ家の様子をその目で確かめておきたいということなのだろう。
「兄さんは、結婚したらすぐにうちを出ていくの?」この家も広くはないし、当面同居はしないということは聞いていた。
「ああ。年が明けたら借家をさがすよ」
「どの辺り?」
「まだ決めてないけど、杉並なんかどうだろうと思ってる」
「杉並……結構遠いね」勝子は目を伏せた。
歳の離れた兄はいつも、勝子の一番の理解者であり、頼れる助言者でもあった。離れて暮らすことを想像すると、たまらなくさびしくなる。
「遠いったって、同じ東京市内だよ」英一が微笑みかけてくる。
「うん」勝子は気を取り直し、文机に向かって本を開いた。「これ、頑張って二月までに完成させないとね」
客間の隅でかしこまっていた勝子は、ふと縁側のガラス戸に目をやって、「あ――」と声を漏らしてしまった。座卓を囲んで談笑していた六人が、一斉にこちらを見る。
「ごめんなさい」勝子は縮こまった。「雪が降ってきたので、つい」
「あらほんと」くのが外を見て言う。「やけに冷えると思ったら」
小雪がちらちらと舞い始めていた。この冬初めて見る雪だ。床の間側に並んで座る若林家の三人も、庭のほうへ顔を向けている。北海道の人たちだったことを思い出し、余計に恥ずかしくなった。
「雪、お好きなんですか」流行りのウェーブヘアで耳を隠した久枝が訊いてくる。生まれ育った土地がそうさせるのか、その両親同様、飾らない笑顔を向けてくる人だった。
「ええ、その、好きというか……」
どう説明すればいいかわからずにいると、英一が横から助け船を出してくれる。
「勝子は小さい頃からちょっと変わっていましてね。東京の子どもたちは普通、たまに雪が降ると喜んでおもてを駆け回ってみたり、口を開いて受けてみたりするわけです。でも勝子は、ただじっと空を見上げてるんですよ。不思議そうな顔で、飽かずにいつまでも」
「へえ」久枝は感心したように言う。「風雅なお嬢さんだったんですねえ」
「風雅というより」英一がこちらに首を回した。「科学的な興味だよな」
「科学?」久枝が目を丸くする。「なおさら素敵。わたし、そっちのほうはからっきしだめだから」
これをきっかけに、はからずも末席の勝子が話題の中心になった。
「雪がお好きなら、いつでも北海道に遊びにいらしてくださいな」訪問着を着た久枝の母親が言った。「スキー地なんかもありますし」
「女学校は、この春ご卒業でしたか」ゴールデンバットをふかしていた背広姿の久枝の父親も訊いてくる。
「はい、そうです」勝子は背筋をのばして答えた。
「この久枝も、室蘭の高等女学校を出とるんですよ」
「ええ、うかがっています」
「ほんとにねえ」くのが久枝と勝子の顔を見比べる。「そういうところもぴったりというか、気が合いそうで」
どこか繕ったようなくのの笑みに、その内心が透けて見える気がした。母はおそらく、義理の姉妹となる勝子たちのことにかこつけて、家の格の釣り合ったちょうどいい学歴の嫁が来てくれてよかったと言いたいのだ。
「卒業したら、どうなさるの?」久枝の母親が勝子に訊く。
「それは、まだ……」勝子は言い淀んだ。
「しばらくお勤めか、おうちのことをして、って感じかしら」久枝の母親は独り合点してうなずき、くのに向き直る。「でもね、女学校を出たら、二十歳なんてあっという間ですよ」
「そうですよねえ」くのも我が意を得たりという表情で同意する。
母親たちが何を言いたいのかは勝子にもわかった。ぐずぐずしていると行き遅れる、というのだ。
すっかりしらけて口をつぐんだ勝子を尻目に、くのが久枝の両親に向かって言った。
「どなたかいい方がいらしたら、よろしくお願いしますね」
午後三時過ぎ、若林家の三人は邦治が呼んでいた円タクで帰っていった。今夜は上野で宿をとり、両親は明日浅草見物をしてから北海道へ戻るそうだ。市内を案内しがてら宿まで送ると言って、英一も同乗していった。
車が見えなくなるまで見送って家に入るやいなや、勝子は珍しくくのに食ってかかった。
「『いい方がいらしたら』なんて、勝手なこと言わないでよ。わたし、十七にもなってないのよ」
「今すぐってことじゃないわよ」くのは客間の湯呑みや菓子を片付けながら言う。「その年頃になったらって話じゃない」
盆を抱えて台所に入っていくくのを追いながら、「そうだとしたって」と口をとがらせる。流しの前に立ったくのは、こちらを見もしない。
「あちらとは親戚になるんだし、気にかけておいていただくのは当たり前のことでしょう? どこの家でもある会話よ」
「とにかくわたし、当分そんなつもりはないから」
「じゃあ、勝子はどういうつもりなの?」
くのはやっと振り返ったが、勝子は何も答えられなかった。
英一が一向に帰ってこないので、三人で先に夕食をとった。邦治の口数が少ないのはいつものことだが、勝子もくのとの口喧嘩を引きずっていたので、やたらと静かな食卓となった。
後片付けを済ませ、二階の自室へ行こうとすると、居間で新聞を広げていた邦治に呼び止められた。
「ちょっと座りなさい」
「――はい」何ごとだろうと思いながら、卓袱台まで戻る。
さっきの口論のことをくのから聞かされたのだろうか。だが、幼い頃から何をしでかそうと、父に叱られた記憶はない。たまにくのや英一と喧嘩をしても、邦治は我関せずというのが常だった。
勝子が膝を折ると、邦治は新聞を畳んで切り出した。
「お前にも、一つ話が来てるんだ」
「え?」驚いて目を見開く。「そんな、だってわたしまだ――」
縁談かと思ってそう言いかけると、邦治は笑いながらかぶりを振った。
「見合いじゃない。就職だよ」
「お勤め……」いずれにしても、今までまともに考えてこなかったことだ。「どういうところですか」
聞けば、勝子もよく知っている親戚が生命保険会社につてがあり、就職を世話してやろうと言っているらしい。
「大きな会社だし、うちからも通いやすい」邦治が穏やかな眼差しを向けてくる。「いい話だと思うんだが、どうだい?」
勝子は放心して言葉も発せないまま、膝の上の両手を固く握りしめた。
3
省線を新宿で降りて駅前に出ると、雑踏の中に千人針を持った女性の姿があった。
一メートルほどのさらしの布に、千人の女たちが赤い糸で一針ずつ刺していき、千個の玉止めを作る。出征する兵士に武運と無事を祈って贈られるのだ。玉止めには「弾を止める」という意味がある。「死線(四銭)や苦戦(九銭)を越えるように」と、五銭玉や十銭玉が縫いつけられることも多い。
勝子もこれまで何度か通勤の途中に呼び止められて、縫ったことがある。未婚女性の一針のほうが価値があるからと、家まで布を持ってくる近所の人もいた。
千人針を呼びかける和服の女性がこちらに目を向けた気がしたが、勝子は襟巻きに顔をうずめて足早に通り過ぎた。奉仕したい気持ちはあったけれど、今日は心の余裕がなかったし、何より、指定された時間には一分たりとも遅れるわけにはいかない。
空はどんよりとして、今にも雨粒が落ちてきそうだ。真冬に戻ったかのような冷たい北風に体が強張り、緊張感まで増してくる。
それを少しでもほぐそうと、勝子は外套のポケットに手を差し入れ、二つの小さなお守り袋を握った。先月、くのが勝子のためにわざわざ湯島と亀戸の天神様を回って買ってきてくれたものだ。
市電の乗り場まで歩き、飯田橋行きに乗った。出勤の時間帯を過ぎているとはいえ、車内は意外なほど空いている。国民の体力向上のため、先月から徒歩での移動が奨励され始めたので、その影響もあるのかもしれない。
市電が走り出すと、歩道の電柱に立てられた〈ぜいたくは敵だ!〉の看板が目に入った。去年あたりから、日々の暮らしが急速に息苦しいものになり始めている。ガソリン、ガス、電気の家庭での使用には制限がかかり、コーヒーやバターは代用品、マッチや砂糖は切符制になった。
外米と麦の混ざった米でもなるべく食べやすいようにと、くのは限られた食材を近所の主婦たちと融通し合いながら、おかずをあれこれ工夫している。その米も、東京などの大都市では来月からいよいよ配給制になるらしい。
勝子が解せないのは、こうしたことに不平を漏らすどころか、むしろ進んで協力し、他人の生活まで監視するような人々が思いのほか多いということだ。そうでない人たちも、物資が不足して暮らしが不自由になったのは、米国による理不尽な締めつけのせいだと敵意を募らせている。
米国といえばついこの間まで、皆の憧れの国だったはずなのに。去年――昭和十五年の秋に三国同盟が結ばれてからはとくに、それまでハリウッドの映画やジャズに夢中だった人たちまでもが急にドイツびいきへと変節している。
支那の情勢が長らく膠着している中、もし本当に米英とも事を構えるようなことになれば、いったいどれほどの犠牲が生じるのだろう。
そんな漠とした不安は常に胸の片隅にあったものの、勝子の心は決して暗く沈んでなどいなかった。この国の行く末よりも、今ようやく扉が開こうとしている自分の人生のことで頭はいっぱいだった。
二十一歳になろうというこの春。憧れ続けていた東京女子医学専門学校の受験がやっと叶い、筆記試験を突破して今日の面接試験にまでたどり着いたのだ。
四年前、高等女学校を卒業した勝子は、両親の勧めに従って生命保険会社に就職した。任されたのは細々とした事務仕事ばかりだったが、嫌々働いていたわけではもちろんない。会社や保険の仕組みはとても興味深く、伝票の処理や書類作りにもやりがいを持って取り組んだ。持ち前の勤勉さと飲み込みの早さを発揮して、すぐに同僚たちからも頼りにされる存在になった。
それでも、入社二年目を迎えた頃には、渇きにも似た焦燥感をはっきり自覚するようになっていた。一つのきっかけは、東京女子高等師範学校で学ぶ坂田をはじめ、上の学校に進学した元同級生たちの近況が次々漏れ聞こえてきたことだ。
やっぱり、わたしももっと学びたい。医師になりたい。ずっとふたをしてきた思いが溢れ出しそうになっていた頃、勝子をさらに悩ませる話が舞い込んできた。見合いだ。
叔母が持ってきた話なので、相応の理由がなければ断れない。困り果てた勝子は、結婚して高円寺に住んでいた英一を訪ね、秘めてきた胸の内をすべて打ち明けた。そのときかけられた言葉が、勝子を救った。英一は、「勝子らしいな」と笑ったあと、「心配しすぎだよ。あの父さんと母さんが、お前が本当にやりたいことを許さないはずがないじゃないか」と言ったのだ。
英一の口添えも得て、ついに勝子は両親に進学の希望を伝えた。英一の言ったとおり、二人とも頭ごなしに否定などしなかった。数回に及んだ話し合いの間、勝子を心の中で励まし続けたのは、二年間かけて父親を説得したという吉岡彌生の存在だ。娘の願いが安易な思いつきなどではなく、少女の頃からの夢だったことを理解した両親は、最終的に東京女子医専の受験を許してくれた。
その夜から早速、押入れにしまってあった教科書を引っ張り出し、猛然と勉強を再開した。三年以上に及ぶ空白を埋めるのは簡単ではなかったが、苦だとは露ほども感じなかった。
わがままといわれても仕方のない思いを静かに受け止めてくれた父と、娘のために毎晩夜食を用意してくれる母に報いるためにも、必ず合格してみせる。そんな覚悟で、来る日も来る日も深夜まで机に向かった――。
途中の停留所で、目の前に座っていた国民服の男性が降りていった。
勝子は空いたところに腰掛け、気を紛らわせるために持ってきた雑誌を鞄から取り出す。女学校時代、担任の安河内からもらった婦人雑誌だ。すっかり開きぐせのついたページに載った、吉岡彌生の写真を見つめる。
入学試験の要項には、面接官の筆頭に吉岡の名前があった。もしかしたら、たとえひと言でも先生と言葉を交わすことができるかもしれない。そう思うと、かえって胸の鼓動が激しくなってきた。
河田町で市電を降り、数分歩いて東京女子医専の校門をくぐった。
守衛が教えてくれた校舎に入り、玄関の掲示に従って待機場所の教室へ向かう。二階のその部屋に入ると、勝子と同じ集合時間を指定された受験生がすでに十数人待っていた。
ほとんどは女学校の制服姿で、賢しげな顔を緊張で強張らせている。襟付きの紺のワンピースに細いベルトを締めた通勤着で席についた勝子に、何人かの受験生が不思議そうな目を向けてきた。
面接試験は朝早くから始まっている。事務員らしき女性がおよそ十分おきにやってきては、受験生を二人ずつ教室から連れ出していく。やがて、勝子ともう一人が呼ばれた。
ひんやりした廊下をしばらく進み、二脚並べて置かれた丸椅子に座らされる。目の前の二つの部屋が面接会場らしい。それぞれの入り口に張り紙がしてあり、面接官の名前が記されていた。〈吉岡彌生〉とあるのは、向かって右側の部屋だ。
この扉の向こうに、先生がいる。期待と不安に身じろぎもせず見つめていると、まさにその扉が開き、受験生が一人出てきた。次に呼ばれるのはどちらだろう。隣の椅子をそっとうかがおうとしたとき、事務員の女性が勝子の受験番号を告げ、無表情に「どうぞお入りください」と言った。
胸に手をやり、一つ深呼吸をしてから扉をノックした。中から声がかかるのを待って部屋に入り、真ん中にぽつんと置かれた椅子に浅く腰掛ける。正面の長机に三人の面接官。尊敬してやまぬ人は、その真ん中に姿勢よく座っていた。
これが本物の、吉岡彌生。いかにも仕立ての良さそうな和服でふくよかな体を包み、根もとの白くなった髪を後ろで結っている。婦人雑誌の写真と違うのは、丸眼鏡をかけているところだけだ。万年筆で書類に何か書き入れていて、まだこちらを見てはくれない。
右端の面接官に訊かれるまま、受験番号と名前をなるべくはきはきと告げる。すると、ようやく吉岡が顔を上げた。眼鏡の奥の小さな目が、思ったより鋭い。最初の質問は、彼女から発せられた。
「どうしてこの学校を受験しましたか」ややかすれ気味の、高い声だった。
「はい――」まずこの質問が来るだろうことは、もちろん予想していた。準備してきた文言を、胸を張って答える。
「一生懸命勉強して、先生のような立派な女医になりたいと思ったからです」
すると次の瞬間、我が目を疑うようなことが起きた。吉岡が天井を見上げ、からからと笑ったのだ。
「私のようになりたいですって?」一転真顔になり、射るような視線を向けてくる。「とんでもない。なりたいと言ったって、そうたやすくなれるもんじゃありませんよ」
「え――?」
驚きに血の気の引いた顔で、吉岡を見つめ返す。何か言わなければと、「それは……」と口を動かしたものの、言葉は続かない。ただ唇を震わせる勝子を気にも留めず、吉岡はまた手もとの書類に目を落とした。
呆然としたままの勝子を訝しげに見つつ、今度は両脇の面接官が交互に質問してくるが、ほとんど耳を素通りしていく。まともに答えられていないのは自分でもよくわかっていたけれど、無言で万年筆を走らせる吉岡からどうしても目が離せなかった。
こんな人だったのか。こんな人を、わたしはずっと――。
信じられない思いは失望へと変わり、やり場のない怒りまでが滲んできて、勝子は唇を噛んだ。
和服の背中を丸めた吉岡の姿は、みるみるうちに遠くなり、煤けていった。
校舎を出ると、ぽつぽつと小雨が降り出していた。傘は持っていないが、この程度なら大して濡れはしない。急ぐでもなく、襟巻きを頬まで上げて校庭を歩き出した。
本当に立派な学校だ。校舎は古い木造だが、十年ほど前にできた名高い附属病院は鉄筋コンクリートの六階建て。向こうには四階建ての大きな寄宿舎も見える。
でも――。こんな学校には来たくない。たとえ合格したとしても、入学するものか。歯を食いしばり、地面を踏みしめて歩かないと、涙があふれてきそうだった。
吉岡彌生になれないことなど、わかっている。わたしはただ、先生への憧れを、尊敬する気持ちを、ああいう形で言い表しただけなのに。
それをわかってもらえなかったことが、悲しかった。一笑に付されたことが、悔しかった。吉岡への敬慕の念は、跡形もなく消えていた。
校門を出たところに、一人の若い男性が立っていた。にこやかに「お疲れさまでした」と言いながら、一枚の紙を差し出してくる。出てくる受験生を待ち構えて、ちらしを配っているらしい。勝子は足を止めることなく、受け取ったガリ版刷りを見た。
〈学生募集 帝国女子理学専門学校〉
聞いたことのない学校だと思ったが、無理もない。よく見れば、〈四月開校〉と書いてある。新設の学校が、女子医専の受験に失敗した者を拾い上げようという魂胆に違いない。
市電に揺られながら、もう一度ちらしを開いた。理学専門学校というからには、物理学や化学、生物学といった学問だけを学ぶのだろう。それに特化した女子の学校を、勝子は他に知らない。
医学が相手にするのは、当然ながら人間だ。女高師の理科の課程も、結局は教員の養成機関に過ぎない。
女子がただ理学だけを修めたとして、その後はどうなるのだろう。社会や職業とのつながりがうまく想像できない。それでも、胸がえぐられるような幻滅を味わったばかりの勝子にとっては、人間ではなく自然を対象に学問をするということが、何かとても純粋で、尊いことのように感じられた。
夕方、邦治が勤めから帰ってきた音を聞いて、二階の自室から居間へ下りた。
着物と股引に着替えた邦治が、「どうだった?」と訊きながらあぐらをかく。
「訊かれたことには、全部答えたと思います。たぶん」正座した勝子はにこりともせず、帰宅したときくのに伝えたのと同じように言った。
「たぶんとは、勝子にしちゃあ頼りないじゃないか」邦治は笑みを浮かべ、たもとから金鵄の箱を取り出して一本火をつける。以前の「ゴールデンバット」という商品名は、敵性語にあたるとして改称された。
灰皿を持ってきたくのが、邦治の隣に座って心配そうに言う。「この子、帰ってからずっとこんな調子なんですよ。ろくに口もきかないで」
勝子は両親の顔を交互に見て、きっぱりと告げた。
「わたし、東京女子医専には行きません」
「ええ?」「どういうことだい?」くのと邦治が同時に声を上げる。
「あの学校は、わたしには合わない。それが今日はっきりわかったんです」
勝子は面接での出来事をありのまま話して聞かせた。
「そんなことぐらいで……」くのが眉をひそめる。
「ごめんなさい。あんなに応援してもらったのに。でも、自分の気持ちに嘘はつけません」
「でもね、勝子――」と言いかけたくのを、邦治が制する。「女子医専に行かないんだったら、これからどうするんだ。勉強を続けたかったんだろう?」
勝子は二つ折りにして持っていたちらしを開き、卓袱台に置いた。
「この学校に入ります」
「帝国女子理学専門学校」邦治はちらしを手に取った。「これは、どういう学校だい?」
「それは……これから調べます」
両親は顔を見合わせた。
続きは本書でお楽しみください。