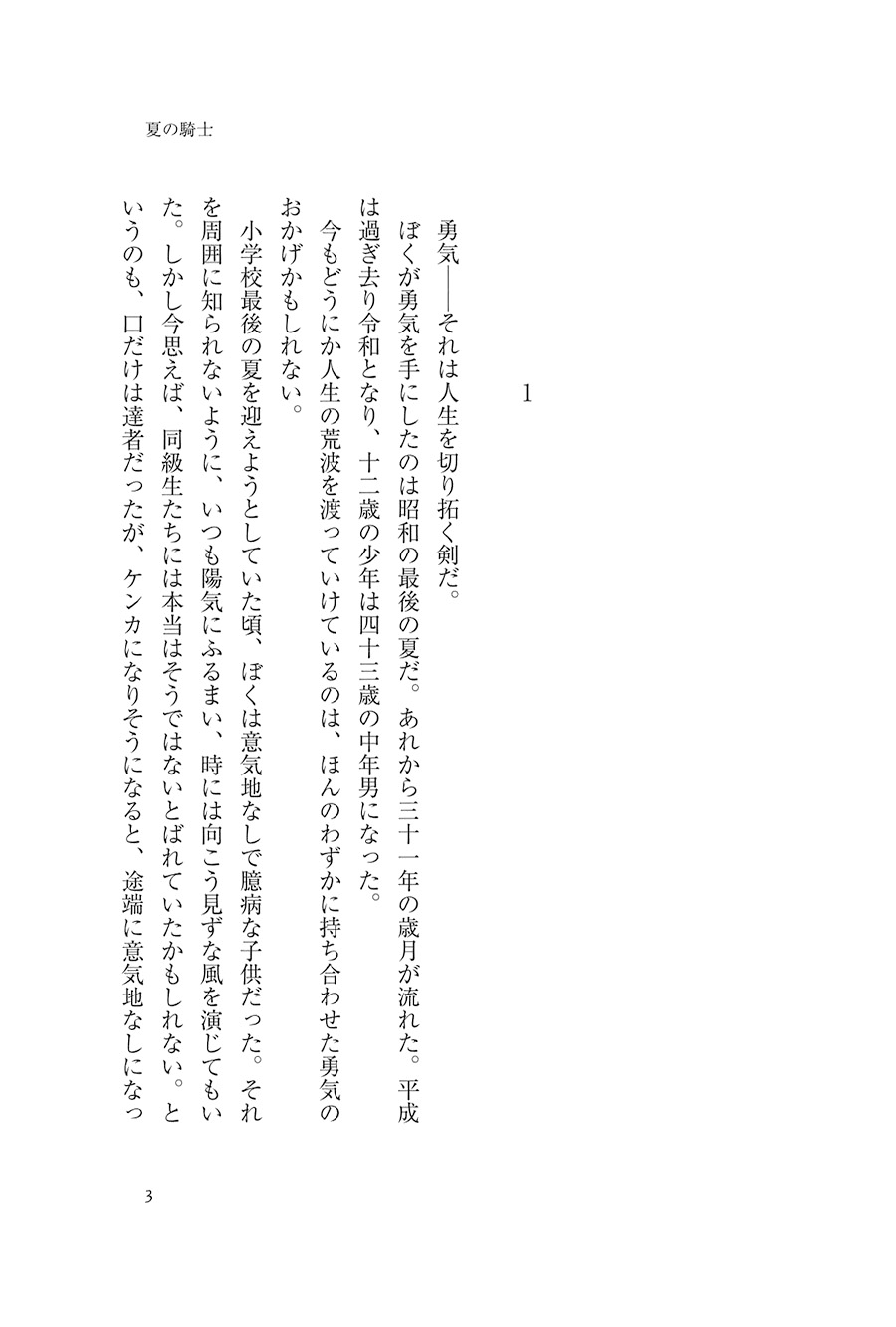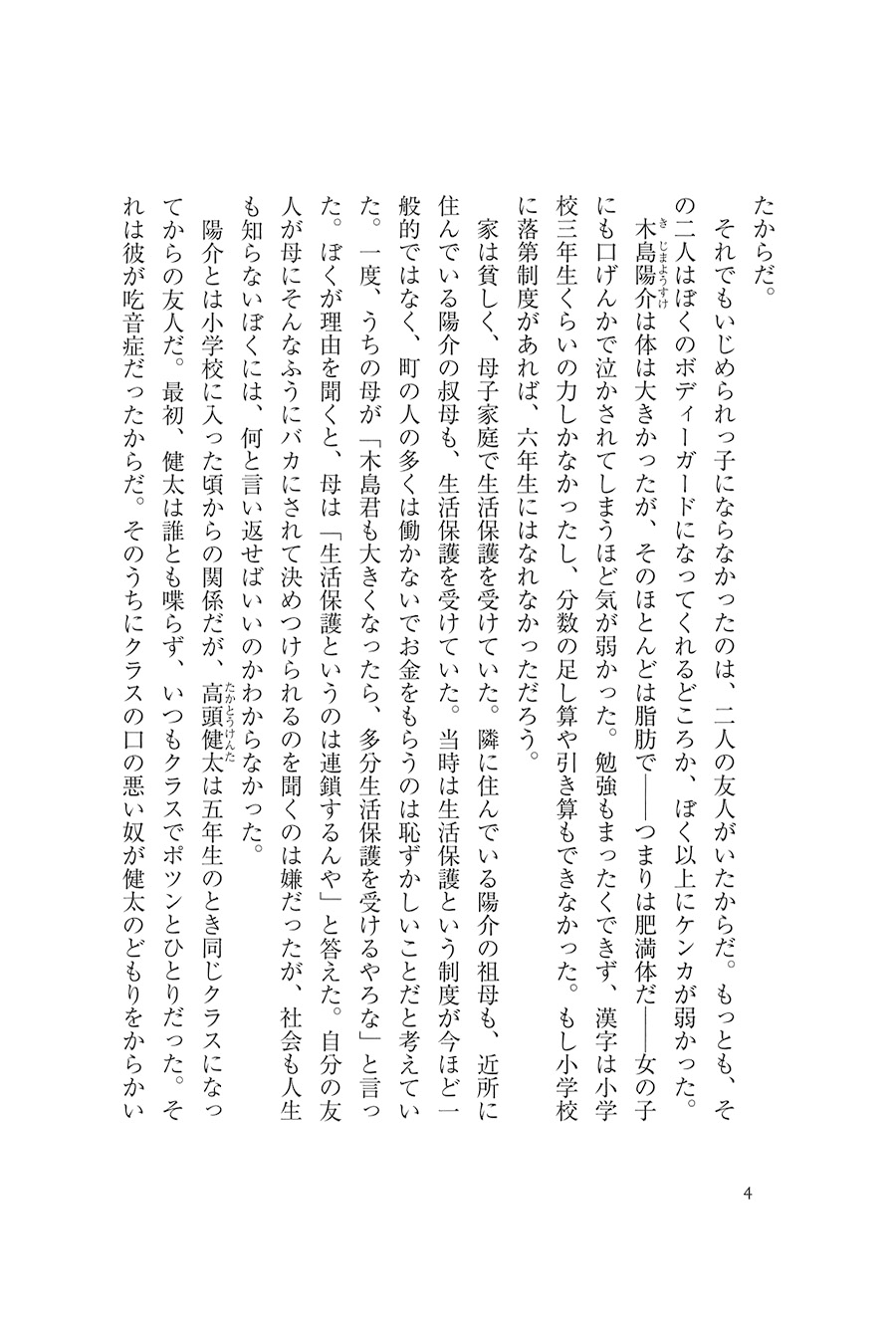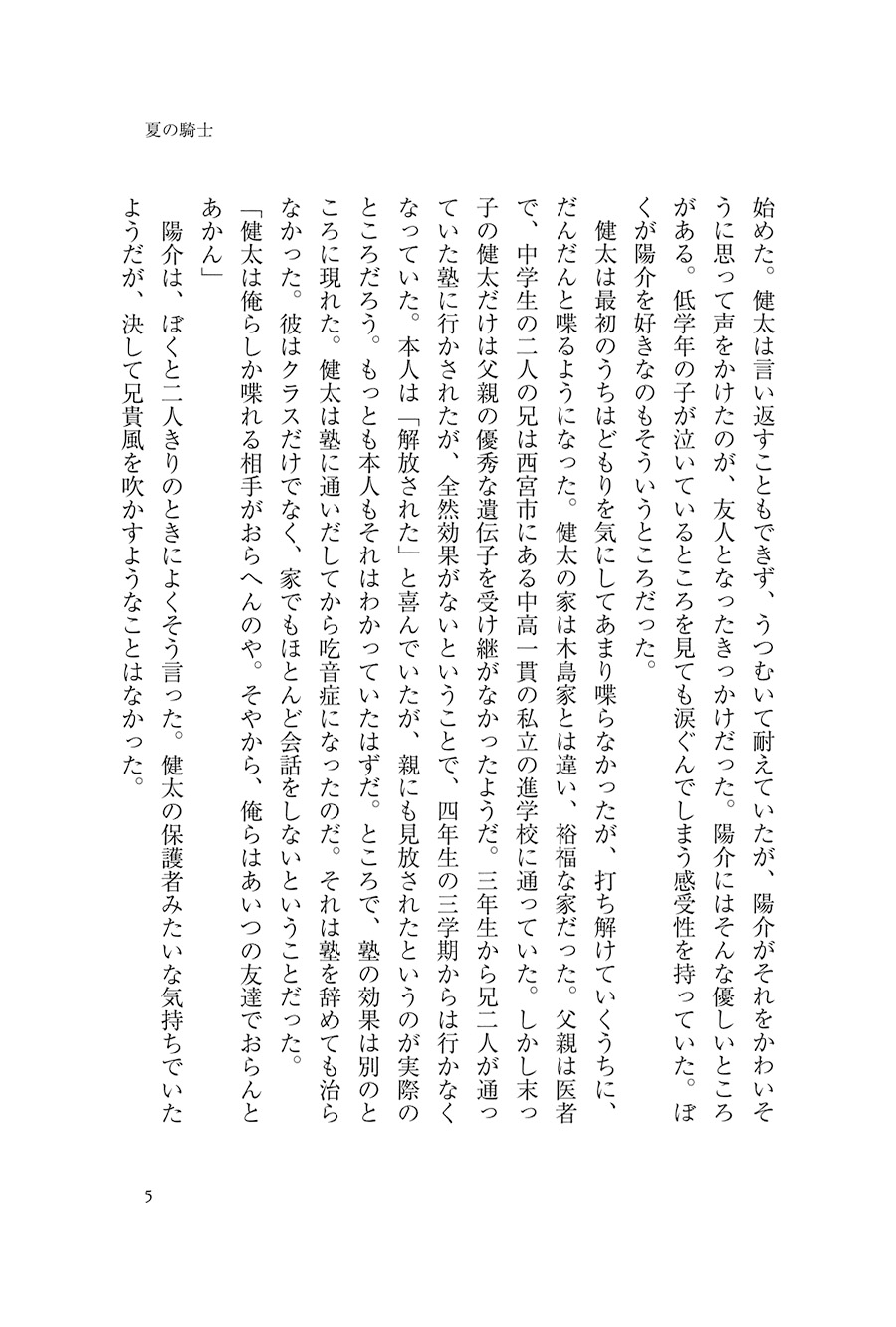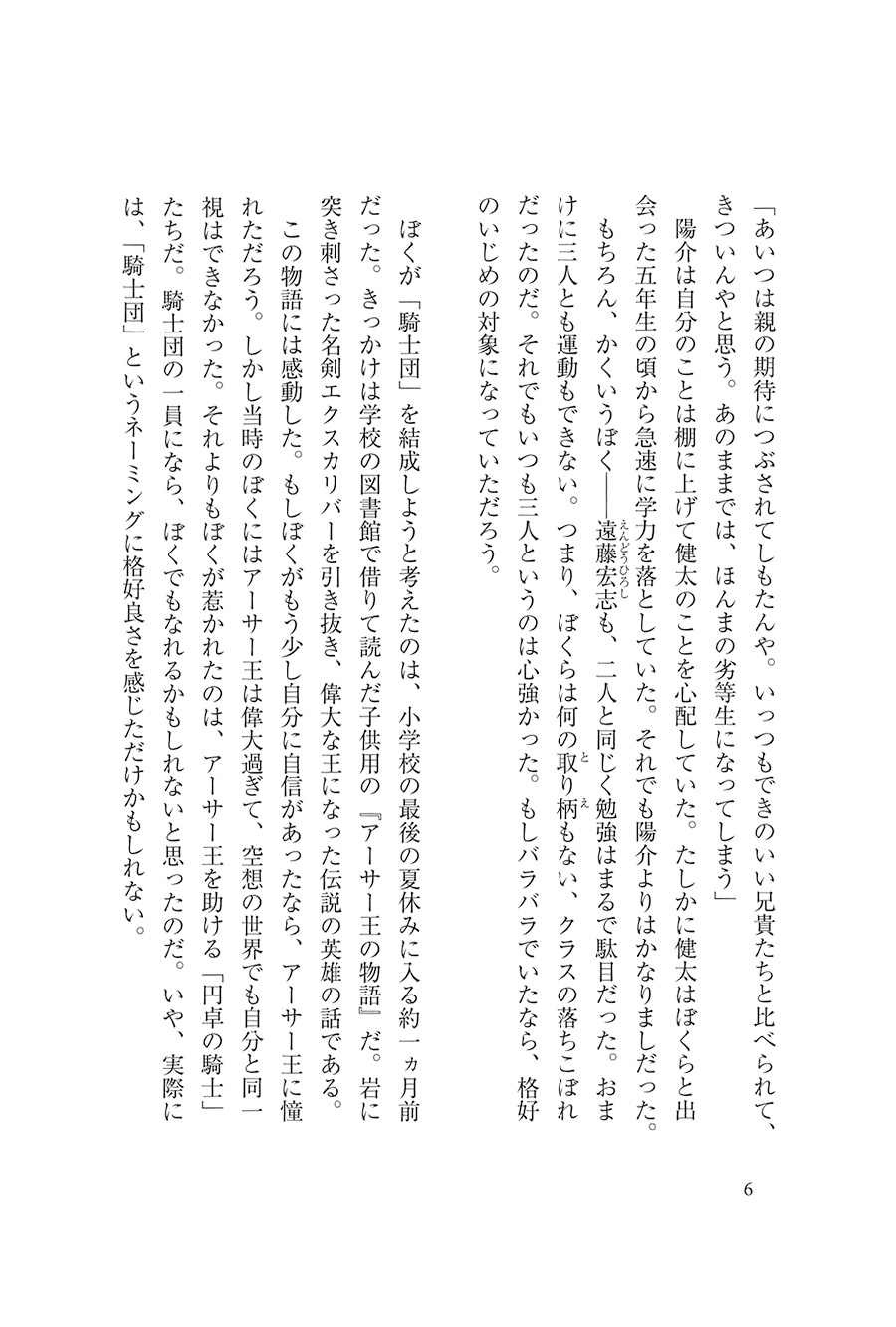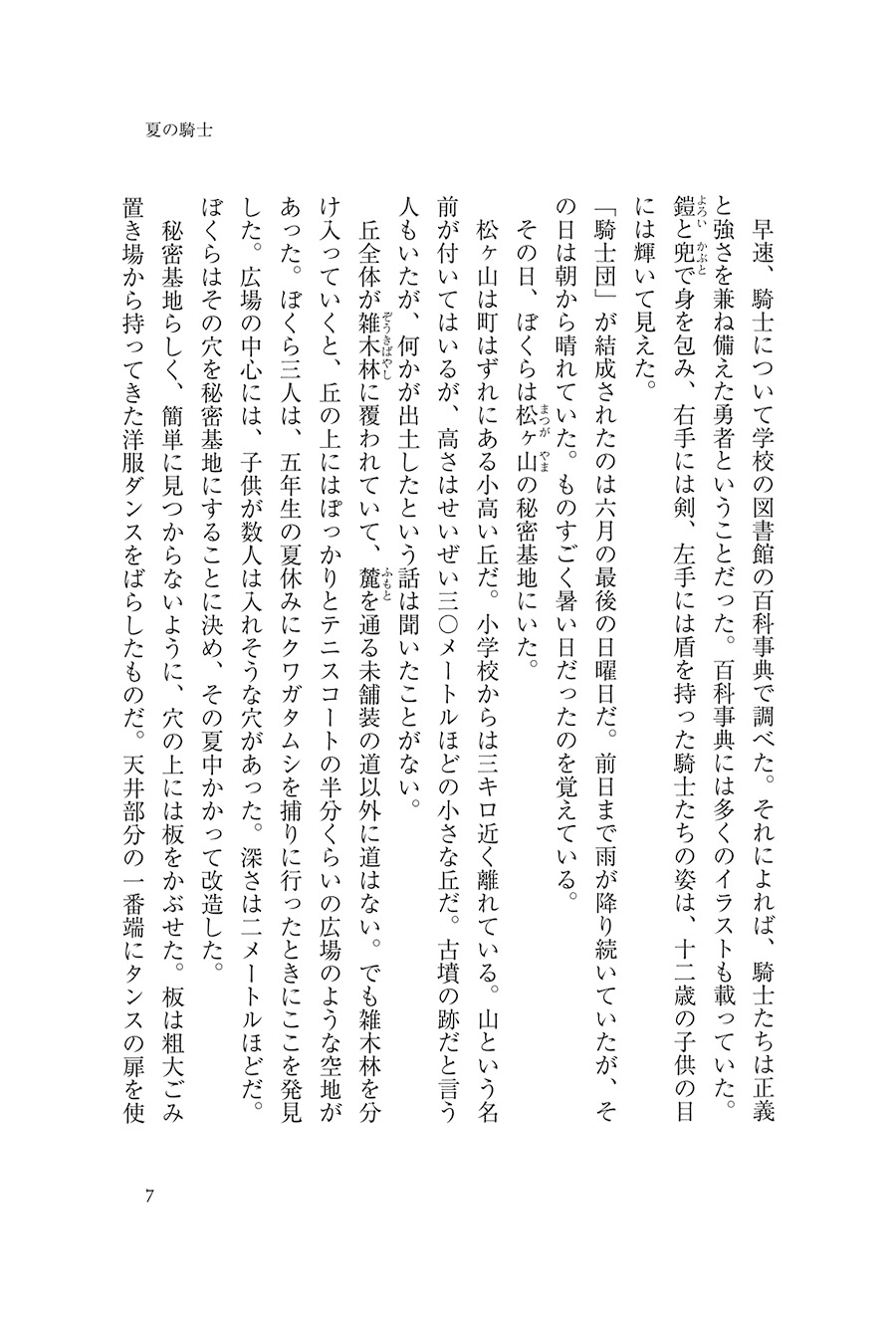1
勇気――それは人生を切り拓く剣だ。
ぼくが勇気を手にしたのは昭和の最後の夏だ。あれから三十一年の歳月が流れた。平成は過ぎ去り令和となり、十二歳の少年は四十三歳の中年男になった。
今もどうにか人生の荒波を渡っていけているのは、ほんのわずかに持ち合わせた勇気のおかげかもしれない。
小学校最後の夏を迎えようとしていた頃、ぼくは意気地なしで臆病な子供だった。それを周囲に知られないように、いつも陽気にふるまい、時には向こう見ずな風を演じてもいた。しかし今思えば、同級生たちには本当はそうではないとばれていたかもしれない。というのも、口だけは達者だったが、ケンカになりそうになると、途端に意気地なしになったからだ。
それでもいじめられっ子にならなかったのは、二人の友人がいたからだ。もっとも、その二人はぼくのボディーガードになってくれるどころか、ぼく以上にケンカが弱かった。
家は貧しく、母子家庭で生活保護を受けていた。隣に住んでいる陽介の祖母も、近所に住んでいる陽介の叔母も、生活保護を受けていた。当時は生活保護という制度が今ほど一般的ではなく、町の人の多くは働かないでお金をもらうのは恥ずかしいことだと考えていた。一度、うちの母が「木島君も大きくなったら、多分生活保護を受けるやろな」と言った。ぼくが理由を聞くと、母は「生活保護というのは連鎖するんや」と答えた。自分の友人が母にそんなふうにバカにされて決めつけられるのを聞くのは嫌だったが、社会も人生も知らないぼくには、何と言い返せばいいのかわからなかった。
陽介とは小学校に入った頃からの関係だが、
健太は最初のうちはどもりを気にしてあまり喋らなかったが、打ち解けていくうちに、だんだんと喋るようになった。健太の家は木島家とは違い、裕福な家だった。父親は医者で、中学生の二人の兄は西宮市にある中高一貫の私立の進学校に通っていた。しかし末っ子の健太だけは父親の優秀な遺伝子を受け継がなかったようだ。三年生から兄二人が通っていた塾に行かされたが、全然効果がないということで、四年生の三学期からは行かなくなっていた。本人は「解放された」と喜んでいたが、親にも見放されたというのが実際のところだろう。もっとも本人もそれはわかっていたはずだ。ところで、塾の効果は別のところに現れた。健太は塾に通いだしてから吃音症になったのだ。それは塾を辞めても治らなかった。彼はクラスだけでなく、家でもほとんど会話をしないということだった。
「健太は俺らしか喋れる相手がおらへんのや。そやから、俺らはあいつの友達でおらんとあかん」
陽介は、ぼくと二人きりのときによくそう言った。健太の保護者みたいな気持ちでいたようだが、決して兄貴風を吹かすようなことはなかった。
「あいつは親の期待につぶされてしもたんや。いっつもできのいい兄貴たちと比べられて、きついんやと思う。あのままでは、ほんまの劣等生になってしまう」
陽介は自分のことは棚に上げて健太のことを心配していた。たしかに健太はぼくらと出会った五年生の頃から急速に学力を落としていた。それでも陽介よりはかなりましだった。
もちろん、かくいうぼく――
ぼくが「騎士団」を結成しようと考えたのは、小学校の最後の夏休みに入る約一ヵ月前だった。きっかけは学校の図書館で借りて読んだ子供用の『アーサー王の物語』だ。岩に突き刺さった名剣エクスカリバーを引き抜き、偉大な王になった伝説の英雄の話である。
この物語には感動した。もしぼくがもう少し自分に自信があったなら、アーサー王に憧れただろう。しかし当時のぼくにはアーサー王は偉大過ぎて、空想の世界でも自分と同一視はできなかった。それよりもぼくが惹かれたのは、アーサー王を助ける「円卓の騎士」たちだ。騎士団の一員になら、ぼくでもなれるかもしれないと思ったのだ。いや、実際には、「騎士団」というネーミングに格好良さを感じただけかもしれない。
早速、騎士について学校の図書館の百科事典で調べた。それによれば、騎士たちは正義と強さを兼ね備えた勇者ということだった。百科事典には多くのイラストも載っていた。
「騎士団」が結成されたのは六月の最後の日曜日だ。前日まで雨が降り続いていたが、その日は朝から晴れていた。ものすごく暑い日だったのを覚えている。
その日、ぼくらは
松ヶ山は町はずれにある小高い丘だ。小学校からは三キロ近く離れている。山という名前が付いてはいるが、高さはせいぜい三〇メートルほどの小さな丘だ。古墳の跡だと言う人もいたが、何かが出土したという話は聞いたことがない。
丘全体が
秘密基地らしく、簡単に見つからないように、穴の上には板をかぶせた。板は粗大ごみ置き場から持ってきた洋服ダンスをばらしたものだ。天井部分の一番端にタンスの扉を使い、そこを入口とした。扉は
天井の板の上には土を置いて擬装したが、扉部分はそうはいかない。でも陽介がいいアイディアを思い付いた。発泡スチロールを細かくちぎって扉一面に貼り付け、その上に茶色の塗料をぶっかけるというものだ。それで一見すると、土に見えた。陽介は勉強はからきしできないが、そういう発想はすぐれている。
ぼくらはこれらの作業に三日をかけた。出来上がりは見事なもので、相当近くから見てもただの地面に見えた。もちろんその上を踏めば土ではないことはわかるが、扉を閉めている限り、ここが秘密基地だと発見される恐れはまずない。扉の取っ手には茶色に塗った紐を付けた。入口の扉から穴へ降りるはしごもぼくらの自作だ。扉を閉めると中は真っ暗になるので、照明には健太が家の仏壇からくすねてきた
その後、ぼくらは折を見ては秘密基地を整備していった。じめじめしていた床にも板を敷き、その上に
収納ケースの中にはいろんなものがあった。いざというときのための懐中電灯、夏のやぶ蚊対策のための殺虫剤と蚊取り線香、トランプ、非常食の乾パン(これは缶に入れたうえで、乾燥剤をたっぷり入れた密閉ビニール袋に入れていた)などだ。
松ヶ山はそれから十年後に大規模な宅地開発がなされ、今は丘全体が住宅街になっている。地名も変わり、桜ヶ丘という洒落た名前の町になった――当時は桜の木なんか一本もなかった。もちろん秘密基地があった形跡などどこにもない。
宅地造成業者が秘密基地の跡に気付いたかどうかはわからない。そのころには基地の天井も扉もなくなっていたし、中にあるソファーやテーブルを見て、ゴミ捨て場と勘違いされたかもしれない。あるいは、ホームレスの住居跡とみなされたかもしれない。ただ、作業員の中に、何かを思い出した者がいた可能性はある。というのは、騎士団が結成された年の夏の終わり、基地周辺はニュース映像で何度も取り上げられたからだ。
今でも惜しいなと思うのは、秘密基地の写真を撮っておかなかったことだ。息子たちに見せてやれば、父は大いに尊敬を集めたに違いない。
秘密基地の存在は他の誰にも明かさなかった。三人だけの秘密だ。松ヶ山に行くときは、いつも三人一緒で、麓の道から雑木林の中に入るときには、誰にも見られないよう細心の注意を払った。松ヶ山まではたいてい自転車で行ったが、自転車は誰にも見つからないように
もっとも秘密基地で何をやるというわけでもなかった。パンを食べたり、バカ話に花を咲かせたり、トランプの大貧民をやったりするだけだ。でも、ぼくらにとって、そこはどこよりも神聖な場所だった。
話を騎士団結成の日に戻そう。
ぼくらは基地内の小さな丸テーブル(これも粗大ごみ置き場から持ってきたものだ)を囲んで座っていた。入口の扉を開けていたから、蝋燭をつけなくても互いの顔がよく見えた。
いつもは野球の話で盛り上がるのに、阪神タイガースが早々にペナントレースから脱落して大洋ホエールズと最下位争いをしていたこともあって、話題にすら出なかった。おまけに頼みのバースはアメリカに一時帰国したまま一向に帰ってこなかった――結局、そのまま退団となった。
ぼくは陽介と健太を前にしておごそかに言った。
「三人で騎士団を作ろう」
二人はいったい何のことだという顔をした。
「昔のヨーロッパには騎士というのがいたんや」
「知ってる。映画で見たことある」
ぼくは陽介の言葉を無視して続けた。
「騎士はまず強ないとあかん。ほんで、何よりも名誉と勇気を重んじるんや。正直で、礼儀正しいふるまいをせなあかん。どんなときでも仲間を大事にする。そういう騎士団を作るんや」
二人は目を輝かせた。
「そ、そやけど、な、なんで俺たちで騎士団を作るんや?」
健太の質問は予想していなかった。
騎士団を作りたかった本当の理由は、そうすれば勇敢な男になれるかもしれないと思ったからだが、二人の前で、それを口にするのは、自分が臆病な男だと認めるような気がして言えなかった。
ぼくはずっと自分の臆病さをなくしたかった。ぼくの臆病は父譲りだった。そんな遺伝があるのかどうかは知らなかったが、少なくともぼくはそう信じていた。
父は学生時代の同級生が経営している中古車販売の会社で働いていた。前に働いていた会社が倒産して、お情けで雇ってもらったのだ。給料は安かった。家の中では母やぼくに偉そうにふるまったが、それは会社でのうっぷん晴らしの面があった。幼稚園に通っていたとき、父が働いているところを見たことがある。夏、駐車場で車を洗っていたのだが、二十歳を少し超えたくらいの若い支店長に「おっさん、手を抜かんと洗っとけよ」と怒鳴られて、へらへらと愛想笑いを浮かべていた。その日以来、父が働く店の前は決して通らなくなった。
でも、もっと辛い記憶がある。あれは小学校二年生のときだ。家族で行った神社での祭りの夜、町内会の人が、壇の上から
ぼくは団扇を取ろうと懸命に手を伸ばしたが、背の低い子供では団扇を取るのは無理だった。父はそんなぼくのために何とか団扇を取ろうと頑張ってくれた。たまたまぼくの頭上に団扇が落ちてきて、父はそれを掴んだ。その瞬間、ぼくは歓声を上げた。ところが、父よりもわずかに遅れて、背の高い中学生が同じ団扇を掴むと、そのまま父から団扇を奪い取った。父は中学生から団扇を奪い返した。ぼくの目には父はスーパーマンのように見えた。しかしその喜びは次の瞬間に悪夢に変わった。その後のことはこうして書くのも気が重い。
父と中学生は団扇の取り合いで揉み合いになり、それは殴り合いに発展した。父は中学生にさんざんに殴られ、地面に叩きつけられた。鼻血で顔も服も真っ赤になって地面に這いつくばる父の姿は、その後、何年も夢の中に現れた。今でも、鼻血を見ると、そのときの嫌な記憶が蘇る。
父は泣きながら、中学生の背中に向かって、履いていた
その日以来、ぼくは同級生と本気でケンカができなくなった。口ゲンカの間はいいのだが、それが殴り合いに発展しそうな空気になると、恐怖で体がすくんだ。自分でも情けなかったが、父からその性質を受け継いだのだから仕方がないと思った。
ぼくが騎士団結成の理由をこじつける前に、陽介が「面白いやないか」と言った。
「強くて、名誉と勇気を重んじる――ええなあ、騎士団」
「お、俺たち、騎士団を作ったら、そ、そんな風になれるかな」
健太がどもりながら期待に満ちた顔で言った。
「なれるよ」とぼくは言った。「それを目指せば、きっとそうなるんや。ひとりやったら無理かもしれんけど、三人おったら頑張れる」
それはぼくの願望でもあったが、二人はふんふんとうなずいた。
「今までもぼくらは仲良かったけど、騎士団を作ったら、もっと団結力が高まる」
ぼくは前に読んだ
陽介が「やろう」と言うと、健太もうなずいた。
「よし、今からぼくらは騎士団や」
二人は「賛成」と言った。こうして騎士団が結成された。
「騎士団の名前は何にするんや?」
「円卓の騎士や」
「円卓て何や?」
ぼくは丸テーブルを叩いた。
「これが円卓や。丸いテーブルは上座とか下座がなくて、すべての騎士に上下の区別がないんや」
「おお、ほんまや。何かわからへんけど、かっこええぞ」
そんなわけで、騎士団の名前は「円卓の騎士」にあっさりと決定した。
「ところでや」
とぼくは一呼吸おいて言った。これから最も重要なことを二人に言わなければならない。
「騎士にはもうひとつ大事なことがあるんや」
「なんや?」
「レディに愛と忠誠を捧げることや」
「レディって何や?」
「貴婦人のことや。高貴で美しい女性や。まあ、ぶっちゃけて言えば、お姫様やな」
二人は笑った。
「笑うなよ。これは真面目な話や」
「そやけど、お姫さまって、おとぎ話かファンタジーの世界みたいやないか」陽介が言った。「ドラクエみたいやで」
五年生の終わりに発売された「ドラゴンクエストⅢ」は、ぼくらの大好きなゲームだった。いや、ぼくらだけではない、クラスのほとんどの男子がやっていた。
「今はドラクエは忘れよう。実際に、中世の騎士は姫に愛と忠誠を誓ったんや。これは本当の話や。おとぎ話やないんや」
ぼくの真剣な言い方に、二人は笑うのをやめた。
「愛と忠誠か、なるほど」陽介は呟くように言った。
「でも、その愛は普通の愛やない。宮廷的愛とゆうて、肉体的な愛やなくて、精神的な愛なんや」
「肉体的な愛ってなんやねん。精神的な愛というのも、意味不明やで」
「そのあたりはぼくもようわからへんけど――多分、付き合いたいというもんやないんやないかと思う。そやけど、それは付き合ったりするよりもずっと素晴らしい愛なんや」
二人はちょっとがっかりしたような表情をした。
「騎士はときに主君の奥さんに愛を捧げたりするんや」
健太は驚いた声を上げた。
「そ、それって、う、浮気やないんか」
「違うんや。なんでかと言うと、さっき言うたように、付き合ったりはせえへんからや。これはミンネと言うて、普通の愛よりもっとすごいんや」
「ミンネってなんやねん」
「騎士の愛やな。これは何か見返りを求めるものやないんや。すごく尊いもので、ドイツでは騎士の『宮廷的恋愛』をうたった歌をミンネザングといい、それを歌う吟遊詩人はミンネゼンガーと呼ばれてたんやで」
これは百科事典そのままの受け売りだったが、二人は感心して聞いていた。
「まあ、ええわ。ほんで、その貴婦人というのは誰なんや」陽介が訊いた。
「
ぼくがその名を出したとき、陽介と健太の顔がぱっと明るくなった。
実はぼくが騎士団を作ろうと思いついたもう一つの理由は、「騎士はレディに愛と忠誠を捧げる」という一文を見たからだ。実際のところ、宮廷的愛というのはぼくにもよく理解できないものだったが、何かとてつもなく尊いものらしいということは感じた。このとき
有村由布子は同じクラスの女子で、学校一の美少女だった。背はぼくよりも頭ひとつ分は高く、長い髪の毛は背中の真ん中近くまであった。とても大人びた魅力があり、近寄りがたい雰囲気を醸し出していた。実際、有村由布子はぼくらよりも一歳上だった。彼女は帰国子女で、アメリカで病気をしてしばらく学校へ通っていない期間があったのと、学期の始まる関係か何かで、一年前、アメリカから転校してきたとき、本来は六年生なのに五年生からスタートしたのだ。それにおそらく両親が東京出身なのだろう、きれいな標準語を喋った。
帰国子女というだけでも、地方都市の小学生にとっては未知の魅力があったが、美人で背が高く、おまけに勉強もできたから、たちまち学校中の評判になった。その上、英語がペラペラだった。これは一度、駅で外人と会話していたのを見ていた者がいたから間違いない。それだけでも十分すぎるほどの美点だったが、彼女はピアノも上手だった。ぼくらの学校の文化祭である
当然、クラスの男子の憧れの的だったが、有村由布子はクラスの幼い男子など眼中にない感じだった。ぼくらのクラスでは、男子は女子を呼び捨て、女子は男子を君付けで呼ぶことが多かったが、有村由布子だけは男子からも女子からも「さん付け」で呼ばれていた。つまりそれくらい独特のオーラがあったのだ。
五月に教育実習でやってきた大学生も、有村由布子に対する態度だけはほかの生徒とは違って見えた。なんというか、まるで自分と同じくらいの女性と接するような感じだった。ちなみにその大学生は背が高く結構イケメンで、女子たちの人気をさらっていた。「光GENJI」の
もちろん、ぼくも密かに有村由布子に憧れていたが、あまりにも
陽介と健太の前でそれを思い出して、少し顔がほてった。
「有村さんかあ――」陽介は言った。「たしかに奇麗やし、お姫さまって感じやな。有村さんやったら賛成や」
「そ、そやけど、お姫様というよりも、じょ、女王様って感じやけどな」
たしかにそうかもしれないと思った。それならなおのこと騎士が愛を捧げる相手としてふさわしい。
「レディは有村さんでええか」
陽介と健太はうなずいたが、同時に二人の顔が少し赤くなった。ぼくは見てはいけないものを見てしまった気持ちになって、視線を頭上の入口に向けた。開けた扉から見える小さな青い空に、一条の白い線が引かれるのが見えた。あっと思った。それは飛行機雲だった。飛行機雲なんて何度も見ていたが、あれほどくっきりとしたのを見たのは初めてだ。今も、飛行機雲を見ると、あの騎士団結成の日を思い出す。
ところで、有村由布子を騎士団のレディにするとして、それを彼女に告げるかどうかが、騎士団の会議の最初のテーマになった。
人知れず忠誠を誓うのが騎士の姿だと、ぼくはぼんやりと考えていたが、二人の意見は、それでは意味がないというものだった。一時間以上議論した末に、本人に告げることになった。このとき、今後、騎士団としての行動は話し合いで決め、意見が分かれたときは多数決で決定するということも決まった。
大人になってから何度も考えたことがある。それは、あのとき、二人が騎士団結成を「くだらない」と思って興味を示さなかったなら、ぼくの人生は全然違ったものになっていたかもしれない、ということだ。いや、もしかしたら、ぼくは勇気を得ることさえできなかったかもしれない。
今、ぼくの書斎の机の引き出しの中には、騎士団のバッジが眠っている。盾がデザインされた二センチほどの小さなもので、陽介がハンダを溶かして作った。当時は裏に安全ピンをハンダで付けていたが、今は取れてバッジ本体しか残っていない。あの夏、ぼくらはそれをシャツに付けていた。