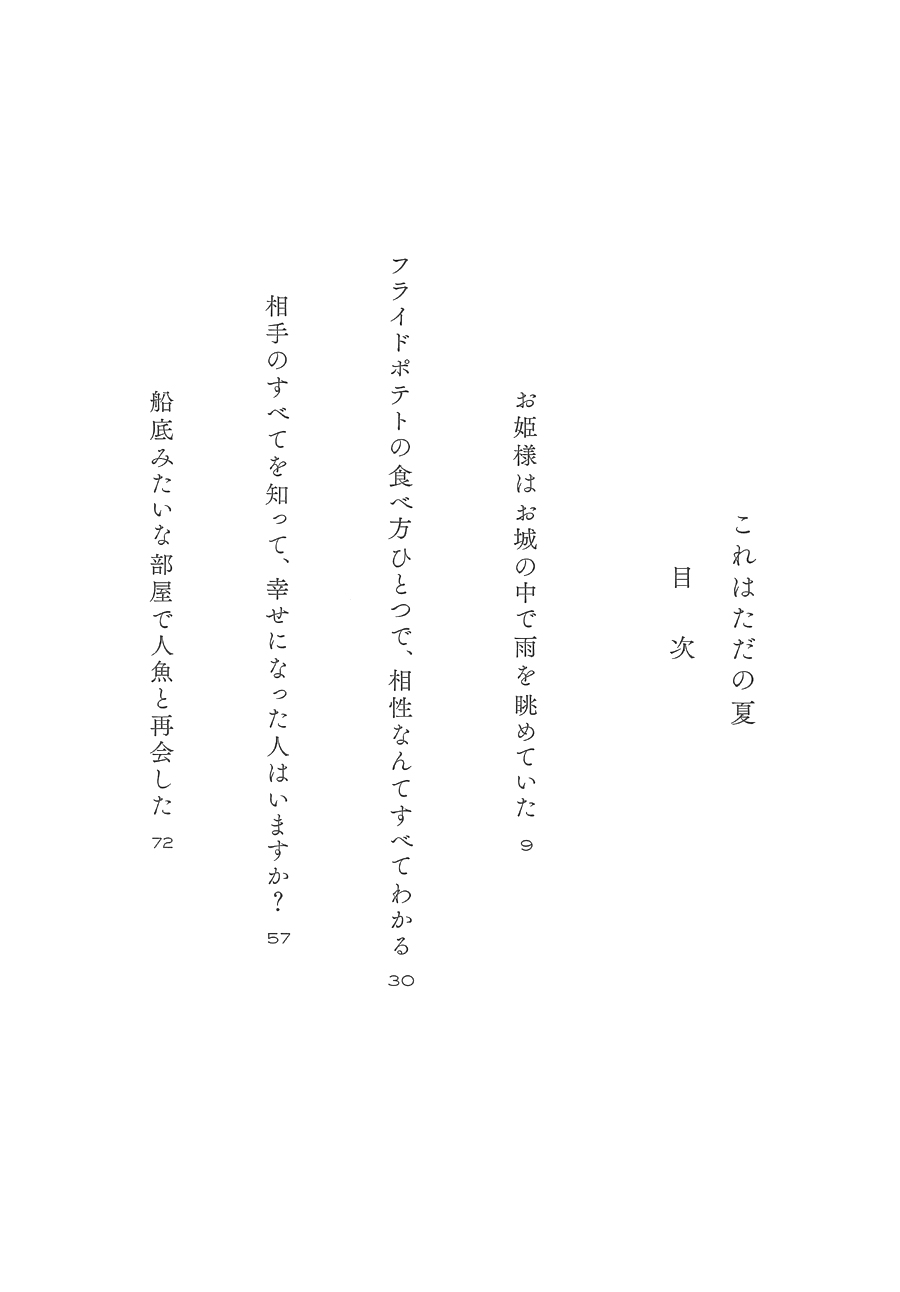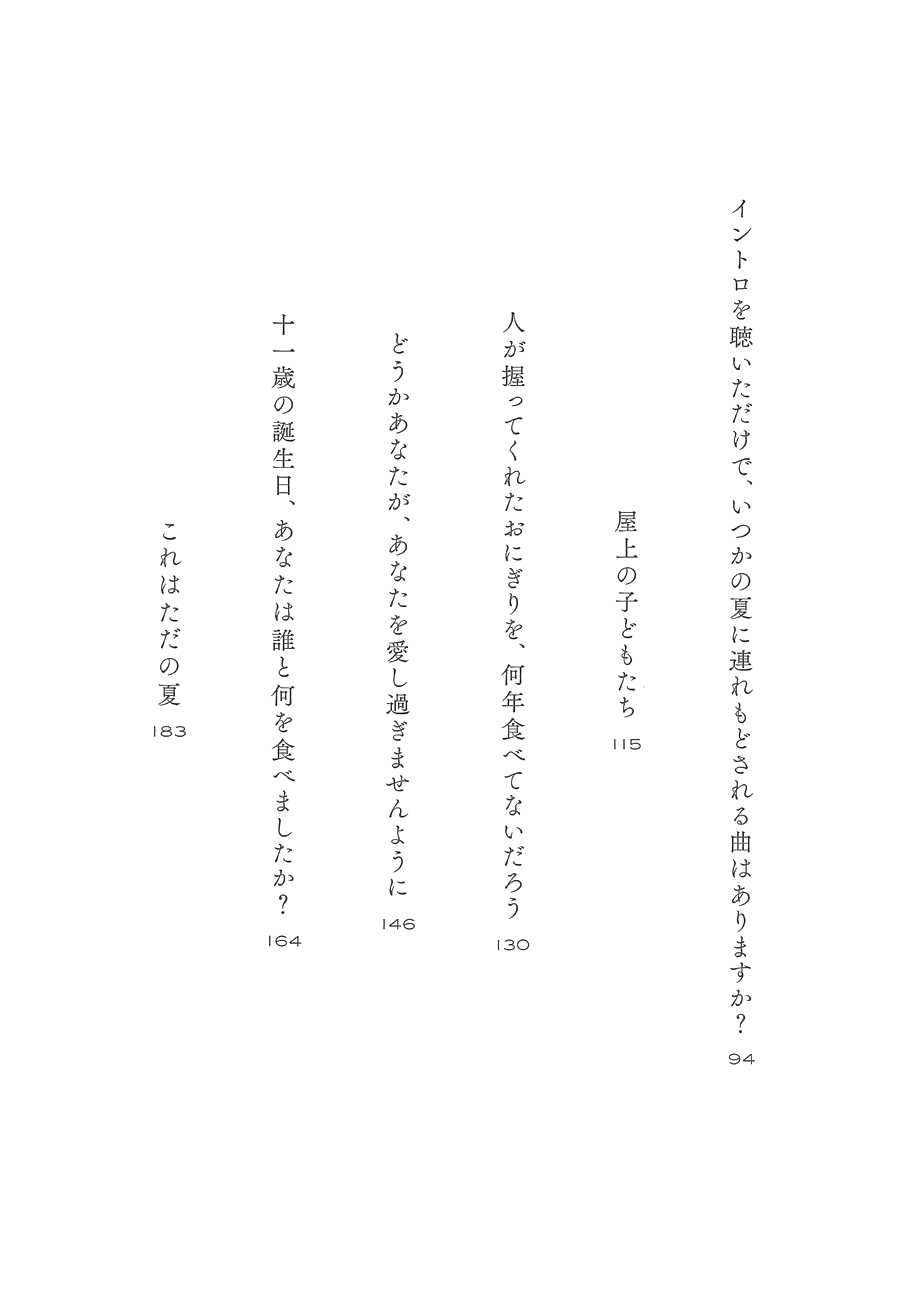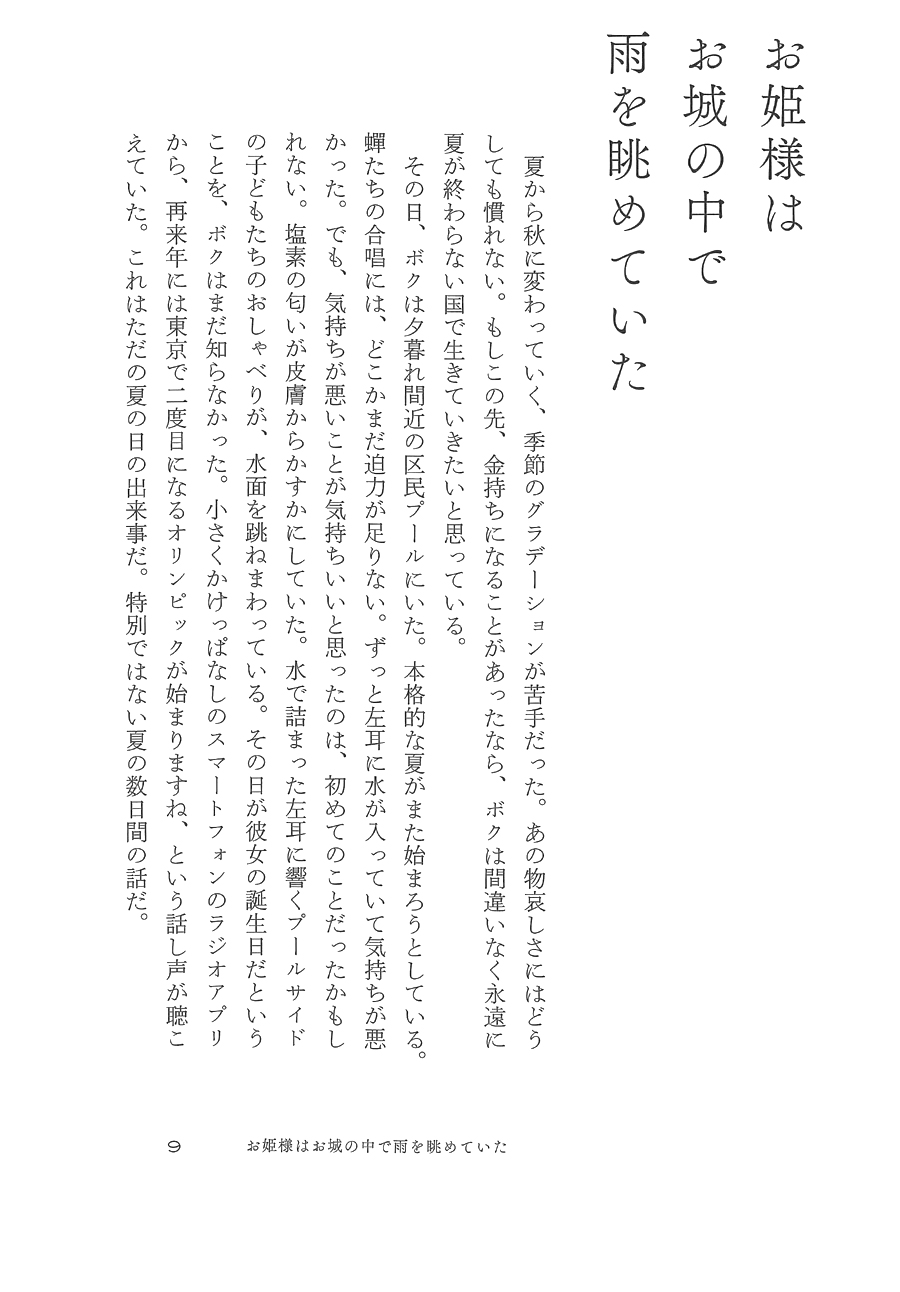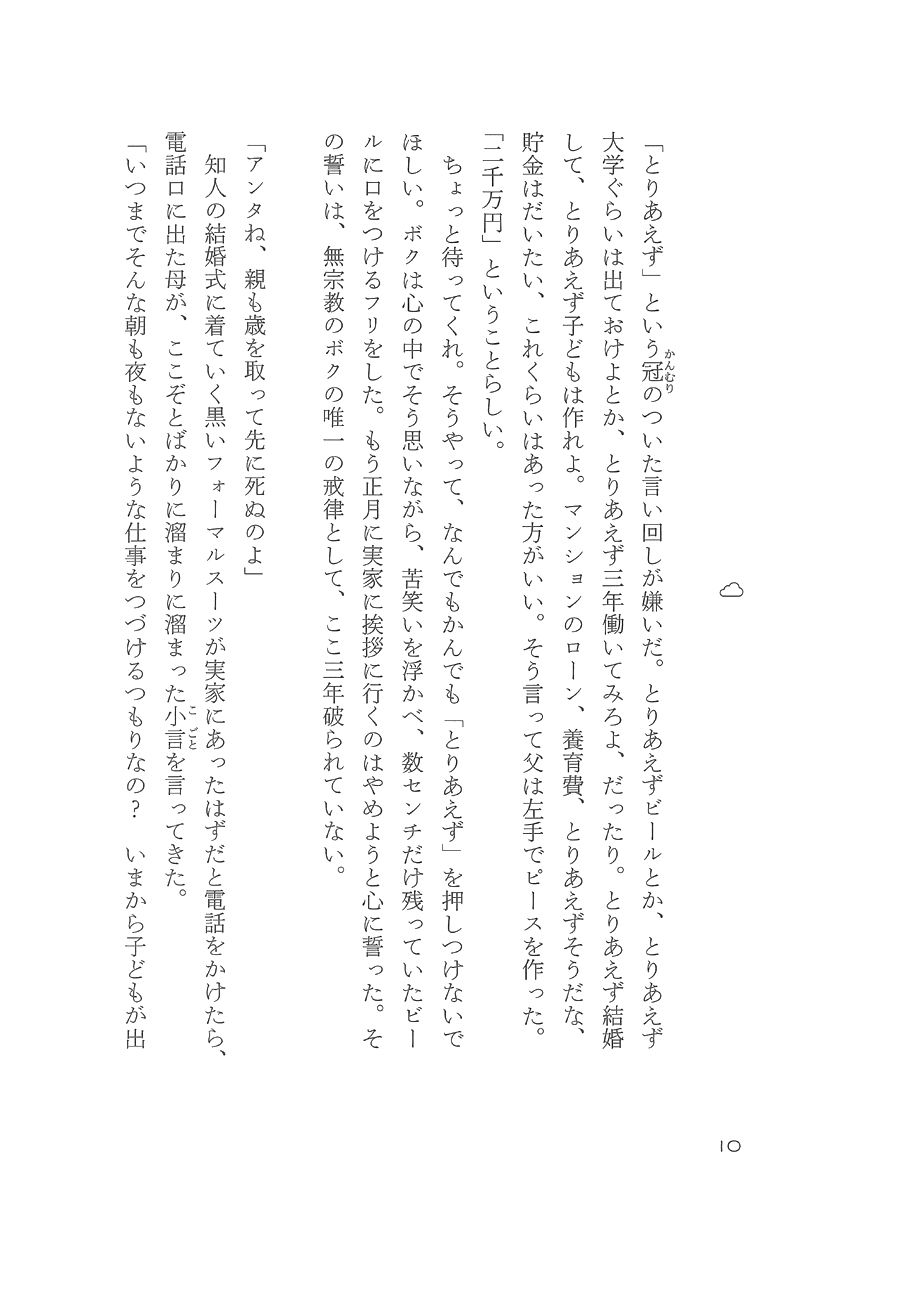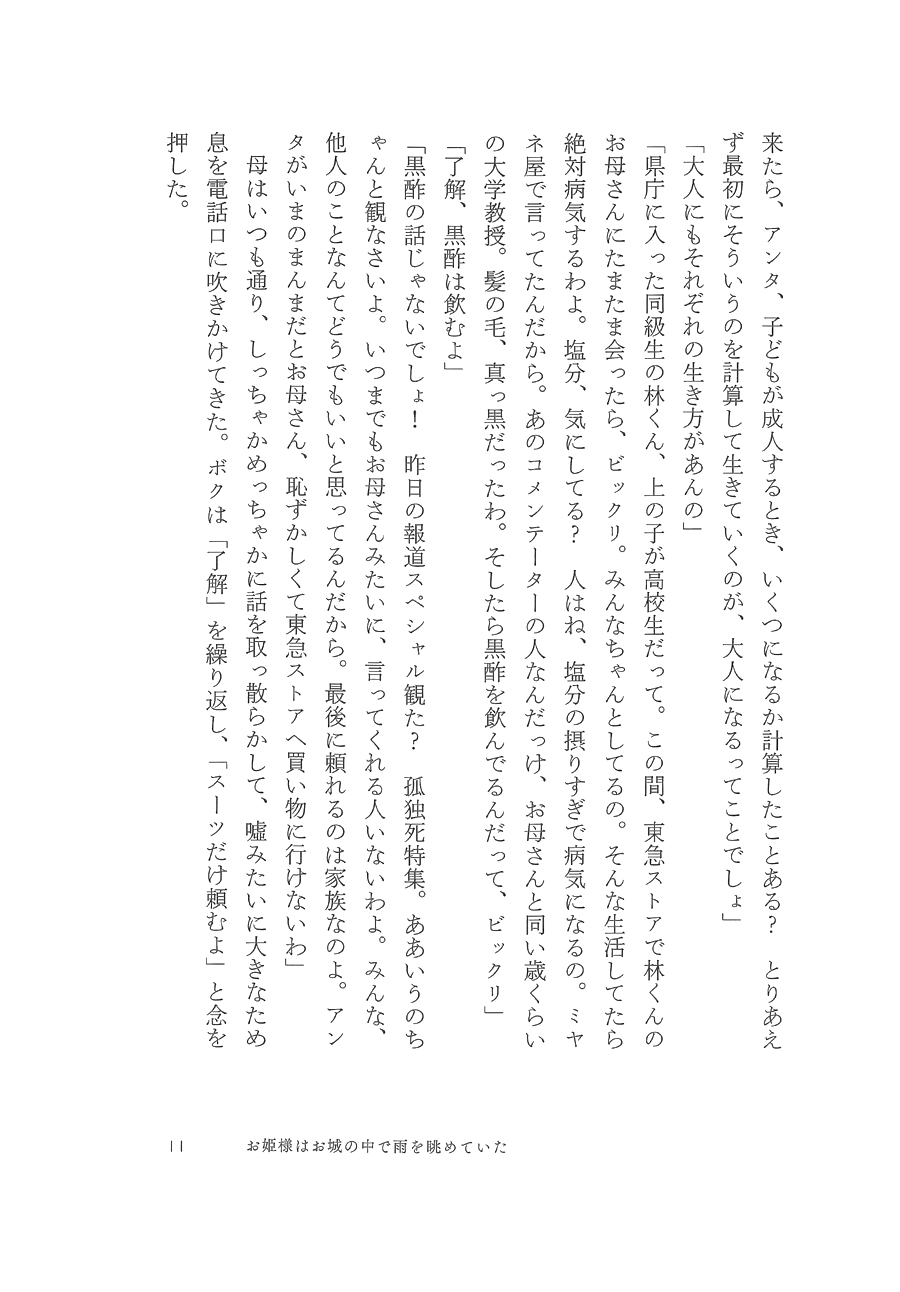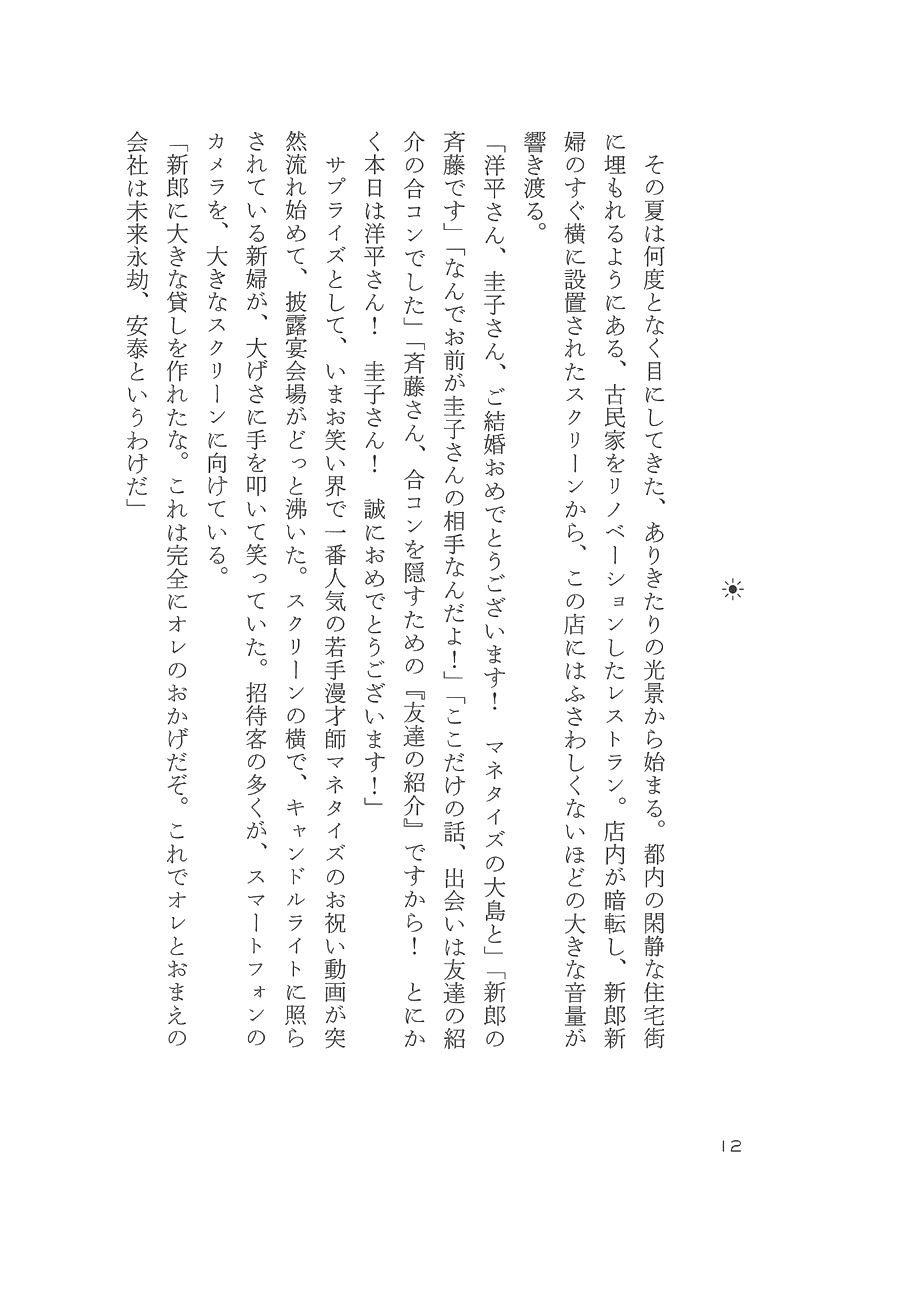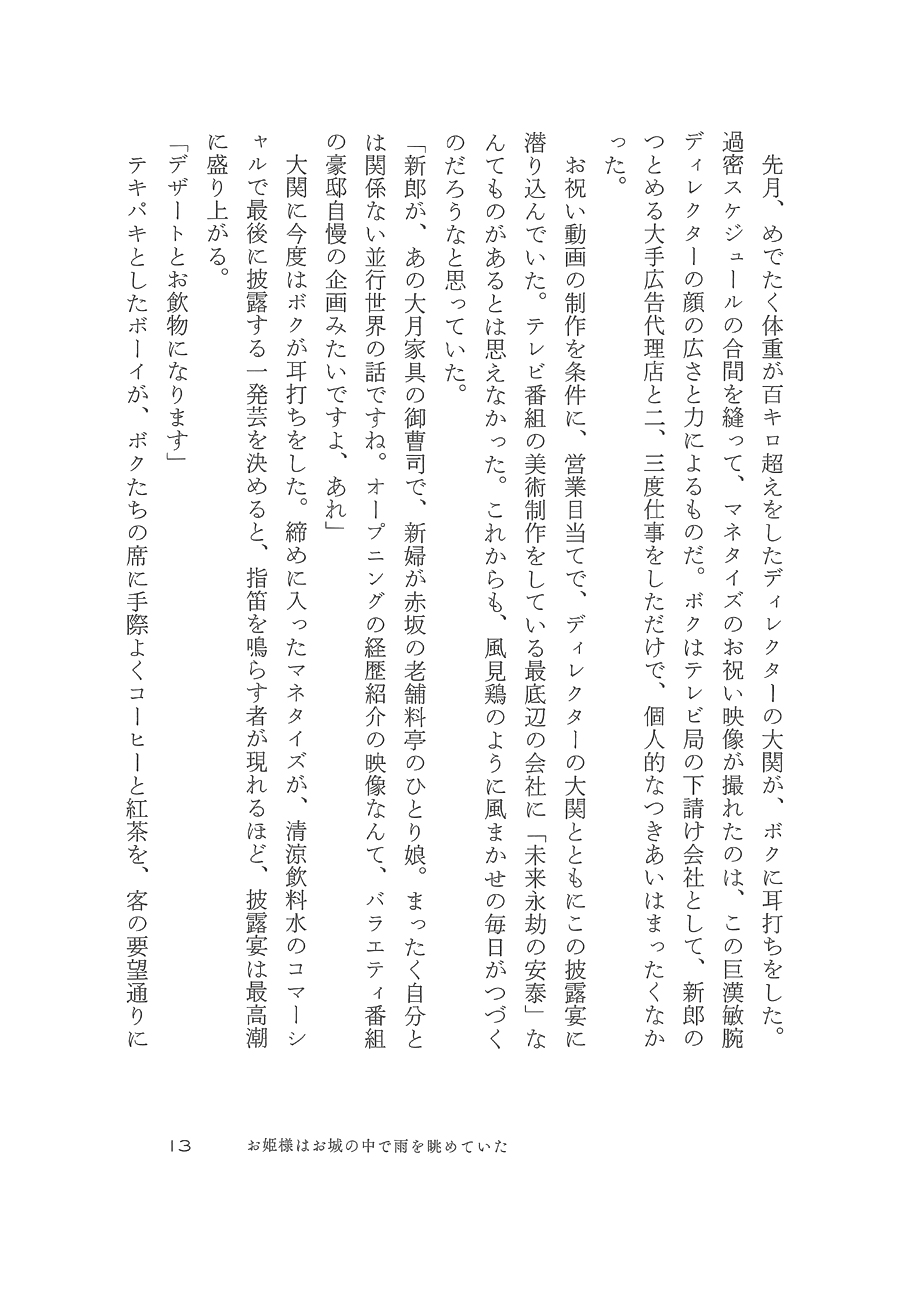お姫様は
お城の中で
雨を眺めていた
夏から秋に変わっていく、季節のグラデーションが苦手だった。あの物哀しさにはどうしても慣れない。もしこの先、金持ちになることがあったなら、ボクは間違いなく永遠に夏が終わらない国で生きていきたいと思っている。
その日、ボクは夕暮れ間近の区民プールにいた。本格的な夏がまた始まろうとしている。蝉たちの合唱には、どこかまだ迫力が足りない。ずっと左耳に水が入っていて気持ちが悪かった。でも、気持ちが悪いことが気持ちいいと思ったのは、初めてのことだったかもしれない。塩素の匂いが皮膚からかすかにしていた。水で詰まった左耳に響くプールサイドの子どもたちのおしゃべりが、水面を跳ねまわっている。その日が彼女の誕生日だということを、ボクはまだ知らなかった。小さくかけっぱなしのスマートフォンのラジオアプリから、再来年には東京で二度目になるオリンピックが始まりますね、という話し声が聴こえていた。これはただの夏の日の出来事だ。特別ではない夏の数日間の話だ。
(略)
その夏は何度となく目にしてきた、ありきたりの光景から始まる。都内の閑静な住宅街に埋もれるようにある、古民家をリノベーションしたレストラン。店内が暗転し、新郎新婦のすぐ横に設置されたスクリーンから、この店にはふさわしくないほどの大きな音量が響き渡る。
「洋平さん、圭子さん、ご結婚おめでとうございます! マネタイズの大島と」「新郎の斉藤です」「なんでお前が圭子さんの相手なんだよ!」「ここだけの話、出会いは友達の紹介の合コンでした」「斉藤さん、合コンを隠すための『友達の紹介』ですから! とにかく本日は洋平さん! 圭子さん! 誠におめでとうございます!」
サプライズとして、いまお笑い界で一番人気の若手漫才師マネタイズのお祝い動画が突然流れ始めて、披露宴会場がどっと沸いた。スクリーンの横で、キャンドルライトに照らされている新婦が、大げさに手を叩いて笑っていた。招待客の多くが、スマートフォンのカメラを、大きなスクリーンに向けている。
「新郎に大きな貸しを作れたな。これは完全にオレのおかげだぞ。これでオレとおまえの会社は未来永劫、安泰というわけだ」
先月、めでたく体重が百キロ超えをしたディレクターの大関が、ボクに耳打ちをした。過密スケジュールの合間を縫って、マネタイズのお祝い映像が撮れたのは、この巨漢敏腕ディレクターの顔の広さと力によるものだ。ボクはテレビ局の下請け会社として、新郎のつとめる大手広告代理店と二、三度仕事をしただけで、個人的なつきあいはまったくなかった。
お祝い動画の制作を条件に、営業目当てで、ディレクターの大関とともにこの披露宴に潜り込んでいた。テレビ番組の美術制作をしている最底辺の会社に「未来永劫の安泰」なんてものがあるとは思えなかった。これからも、風見鶏のように風まかせの毎日がつづくのだろうなと思っていた。
「新郎が、あの大月家具の御曹司で、新婦が赤坂の老舗料亭のひとり娘。まったく自分とは関係ない並行世界の話ですね。オープニングの経歴紹介の映像なんて、バラエティ番組の豪邸自慢の企画みたいですよ、あれ」
大関に今度はボクが耳打ちをした。締めに入ったマネタイズが、清涼飲料水のコマーシャルで最後に披露する一発芸を決めると、指笛を鳴らす者が現れるほど、披露宴は最高潮に盛り上がる。
「デザートとお飲物になります」
テキパキとしたボーイが、ボクたちの席に手際よくコーヒーと紅茶を、客の要望通りに置いていく。「新郎ご友人」という雑な括りのテーブルに座らされ、隣の大関以外、まったくの初対面といったアウェーな状況がつづいていた。何度目かの「ご歓談」で、やっと宴は幕を閉じようとしている。
新郎新婦が目配せをして、おもむろに席を立つ。ふたたび照明が暗転し、スポットライトがマイクの前に立つ新郎新婦だけを照らし出す。ボクは眩しくて、思わず目をつむった。
「ここで、新婦がこの日のために、ご両親さまへ、お手紙をしたためてこられたということです。圭子さん、ご準備はよろしいでしょうか」
いまひとつ心のこもっていない抑揚のない話し方の司会者の紹介とともに、新婦が手紙を広げ、漫画みたいに深呼吸をひとつした。新郎が背中にそっと手を添える。新婦はすでに泣き顔になりながら、手紙を読み始めた。
「わたしは皆さんご承知のように料亭の家に生まれ、家での食事はいつもプロの料理人が作り、いわゆる家庭の味を知らずに育ちました」と、イヤミにもなりかねないことを、出席者の顔ぶれも相まって、しっかり笑いに変えて始まった。「洋平さんのご家族とわたしの育った家のように、笑いのたえない家庭を築いていけるよう精進する所存です。お義父さん、お義母さん、不束な嫁ですが、よろしくお願いします」
新婦がそう言ってスピーチを締め、深々と頭を下げた。
「そして、わたくしの方も、お義父さんとお義母さん!」
新郎が横からマイクに顔を近づけて言う。
「これからも料亭の味、ごちそうになりまーす!」と新婦の両親に語りかけると、新郎の会社の同僚たちの席から「羨ましいぞ!」と大きな声が飛び、列席者たちから、正しい笑い声が漏れた。
「気が合いそうにないな、アイツら全員」
大関がデザートのゆずシャーベットをべちゃべちゃ食べながら、独り言のようにつぶやく。中島みゆきの『糸』が大音量でかかり、新郎新婦と両家の親が、並んでお辞儀をして万雷の拍手に包まれ、披露宴はとどこおりなく終了した。
(略)
帰りは「反則」とふたりになった。大関が完全に酔いつぶれたのをいいことに、彼女を連れ出したような気がする。
「今日が昨日になろうとしているね」
ボクはとってつけたようにそんなことを彼女に話したらしい。次の日の朝、彼女が口真似をしながら教えてくれた。彼女と何を話し、どうやって夜を過ごしたか記憶が飛んでいる。かすかに覚えているのは、彼女と手をつなぎながら、ストロング缶を持ってどこかもわからない商店街の真ん中を、笑いながら千鳥足で歩いていたことだけだった。
目が覚めたのは、喉の奥が渇きでひっつくような感覚に襲われた午前八時を少しまわった頃だ。目を開けると、そこはファミレスの四人席だった。テーブルに突っ伏して眠ってしまっていたらしく、両手が痺れて頭が割れるように痛い。
「おはよう、昨日のこと覚えてる?」
彼女がテーブルを挟んだ向かい側から、頬杖をついて話しかけてきた。ボクと彼女の間には、ドリンクバーの残骸のマグカップがたくさん並んでいる。ボクはどうにも喉が渇いて、その中の一つのカップを手繰り寄せ、ひと口すする。それは完全に冷めきったコーヒーで、二日酔いの胃が悲痛な叫びをあげた。
「ごめん、あんまり覚えてなくて」
千切れそうな内臓を抑えながら言うと、「だよねえ」と彼女は呆れるのと哀しいのがないまぜのような表情を浮かべた。
「明け方にこのファミレスを見つけるまで、ずっと歩きながら話してたんだよ、ウチら高校生みたいに。私は忘れられないかもな」
ファミレスを出ると、空には重たい灰色の雲が広がっていた。まったりとした雨の匂いがして、いつ降り出してもおかしくない気配がする。ファミレスの外観は、中世のお城を模したような白い造りになっていて、やけに大げさで安っぽさに磨きをかけている。
ボクは黒いフォーマルスーツ、彼女はキラキラひかる黒いワンピース姿。スーツを着たビジネスマンが増えてきた午前八時半の街中で、ボクたちはかなり浮いていた。大通りの車の量は結構あったが、なかなかタクシーがつかまらない。
「圭子、幸せそうだったな」
「そうだったね」
「でも、私たちもわりと幸せだったか」
「そうかもね」
「覚えてないくせに。でも、覚えてなくてよかった。私、いらないこといっぱい話しちゃったから」
若い保育士が、幼い子どもたちの乗った車輪付きのカートを押して、童謡らしき歌を口ずさみながら散歩している。その様子を視線で追ったあと、彼女はつぶやく。
「また会おっか」
彼女がこちらも見ずに、スーツのジャケットの端を掴んだ。
「そうだね」
ボクは約束するでもなく、相槌みたいに応えていた。そのタイミングでタクシーが視界に入り、とっさに手を挙げる。
「うちに帰って、着替えないと。この格好じゃ現場に行けないから」
ジャケットを掴んでいた彼女の指に、自分の指を絡ませる。
「一緒に乗ってく?」
「私、もう暫く散歩していく」
彼女は絡ませた指を、ゆっくりと解いた。
「わかった」
「優香。優しいに香水の香で優香」
「え?」
「名前くらい訊いてよ」
「ごめん」
彼女に頭を下げ、ボクはタクシーに乗り込んだ。ドア越しに彼女がつまらなそうに、小さく手を振っている。それに応えて手を振った。
彼女と昨日、何を話したのだろう。おぼろげな記憶をたどっていくと、真剣に何かを語る彼女の顔が薄っすらと脳裏に浮かんできた。彼女がわりと幸せだったのならそれでいい。ボクはほとんど何も覚えていないのに、彼女のどこか寂しげな表情だけは、頭にこびりついていた。タクシーが大きな交差点を右折した瞬間、さっきまでこらえていた雨が雨雲から勢いよく降り出した。
目をつむったら、あっという間に寝ていて、運転手の「お客さん、お客さん、目黒のこの辺りだよね?」という怒鳴るような声で、泥みたいな眠りから目醒める。頭痛なんてもんじゃない左側頭部の痛みに耐えながら、辺りを見回す。自宅マンションから三百メーターは行き過ぎていた。ちょうどコンビニの前だったので、グレープフルーツジュースと錠剤の胃薬、ヘパリーゼ二袋を購入した。全部の錠剤をラムネのように頬張り、グレープフルーツジュースで一気に飲み下す。とにかく頭痛が酷かった。こういう朝は本当にもうやめにしようと、週に一度、恒例となった誓いを心の中でつぶやく。とどめとばかりに自販機で買ったミネラルウォーターをガブガブとこぼしながら飲む。
ポケットの中の違和感を確かめると、出てきたのはくしゃくしゃのコンビニのレシートだった。ストロング缶を買ったことが明記されたレシートの裏には、「ユカ」という文字が、赤いボールペンで書き殴られていた。鍵を失くしたかと一瞬凍りつくが、財布の小銭入れの中に用心深くしまってあった。朝帰りは珍しくなかった。ただ、くたびれたフォーマルスーツ姿は、いつもの朝帰りより罪悪感と後悔が高まる。そそくさとエントランスを通り抜けようとしたところで、足が止まった。
小学生くらいの女の子がコンビニのビニール袋をソファの脇に置いて、分厚い漫画誌を読んでいる。綺麗に切りそろえられたボブカットに、ごぼうのように細い手足が特徴的だった。前にも、何度か見かけたことがあった。登校拒否だろうか?
もっとも、女の子からは「そうしたいから、いまここにいる」といった感じも受ける。一人がけのソファに浅く座って、足をぷらぷらさせながら、女の子がこちらをジッと見つめている。優香と同じような、真っ黒のシンプルなワンピースを着ていた。
「学校には行かないの?」
自然と声をかけていた。女の子が分厚い漫画誌をパタンと閉じた。
「今日、月曜日だよね?」
恐るおそる訊くボクに、わかりきったことを訊くなよ、といった表情で彼女はため息交じりに吐き捨てた。
「傘がないの。雨に濡れたくないの。いまは雨宿り」
「家に傘ないの?」
「折りたたみ傘、学校だし。お母さんの傘ならあるけど、大きいし、ヘンだから」
「ヘン?」
「色がヘン」
「ビニール傘、あるよ。それに、派手じゃない女の子が使う折りたたみ傘もあるから、貸そうか?」
「いいの?」
「いいよ、全然。どっちがいい?」
「見て決める」
ボクは急いで8階の自分の部屋に戻る。傘立ての中には靴磨きクリームや、番組の小道具として使った木製バットや木刀などのガラクタばかりで肝心の傘がない。靴を脱いで、引き出物の入った袋を玄関近くに放り投げ、部屋の中を探す。ゴミ屋敷とまではいかないが、物が多すぎる。使用済みの仕事の資料、本、サンプルのDVD、CDがうずたかく積まれ、「いま大地震が起きたら、この部屋の荷物の下敷きになって死ぬね、私ら」と天井を眺めながらつぶやいた全裸の女のことを、ふと思い出した。
雑誌の山に埋もれていた女性用の折りたたみ傘と、木刀の後ろに隠れて埃まみれになっていたビニール傘を見つけた。鍵もかけずに、ボクはエントランスに戻った。
「どっちにする?」
彼女は折りたたみ傘を手に取って、開く。
「こっちがいい。可愛い」
女の子は棒読み風に応え、絵本のような街並みがブルーの蛍光色で描かれた折りたたみ傘を選んだ。傘を持ちながらくるくると回ってみせる。黒いワンピースにブルーがよく映える。
「その傘、あげるよ」
「わたしのうち、808」
「えっ、うちは805だよ」
この子になぜ話しかけ、親切にしているのか、自分でもわからなかった。自分は他人に親切ではないし、社交的でもない。子ども好きでもない。どちらかといえば、子どもは苦手だ。最近は苦手意識がどんどん顕著になっている。けれどこの女の子には、最初から壁のようなものを感じなかった。同じ高さの壁を持った者同士だったのかもしれない。
彼女が折りたたみ傘をもう一度、確かめるようにバサッと開いた。微笑んだ彼女につられ、ボクも微笑んでいた。この光景の不思議さはなんだろう。さっきマンションに着いたときよりも強い非日常感に襲われる。
「その漫画、好きなの?」
「別冊マーガレット。見て、一九九九年八月号」
「一九九九年?」
「お母さんの。うちのお母さん、ずっと別マを買いつづけてるんだよ。ぜったい捨てないの。別マだけの部屋があるの。見にくる?」
「すごいね。ネットで売ったら、かなりの値段がつきそうだ」
ボクは彼女の読んでいた年代物の分厚い別冊マーガレットをペラペラやりながら感心した風を装った。
「わたし、会ったことある」
「誰に?」
「あなたに」
「こっちもだよ。そりゃそうか、同じ階だもんね」
「この傘の女の人にも会ったことある」
「それはそれは」
「それはそれは」
彼女はボクの口真似をして、ニヤニヤしている。
「君、いくつ?」
「十歳」
「小四か」
「小五なんだけど」
「ごめんなさい」
「どうして謝るの? まあいいけど」
彼女は、笑うのと怒るのとの中間みたいなふくれっ面をして、ランドセルを取ってくると言って、突然のダッシュでエレベーターホールに走って行った。雨音が一段と強くなった気がする。タレントくずれの気象予報士が豪快に予報をハズしていることに、そのとき、ボクはまったく気づいていなかった。