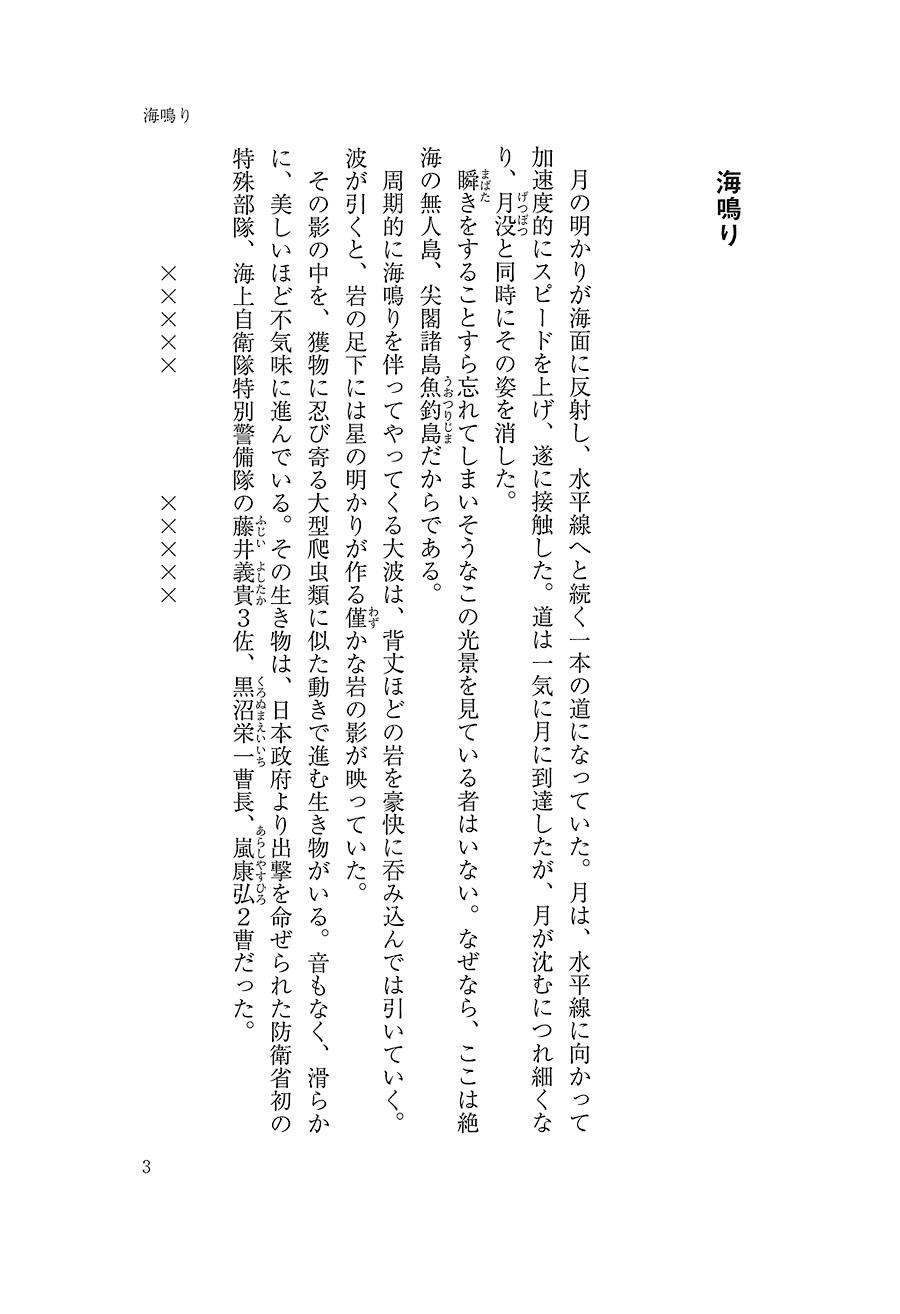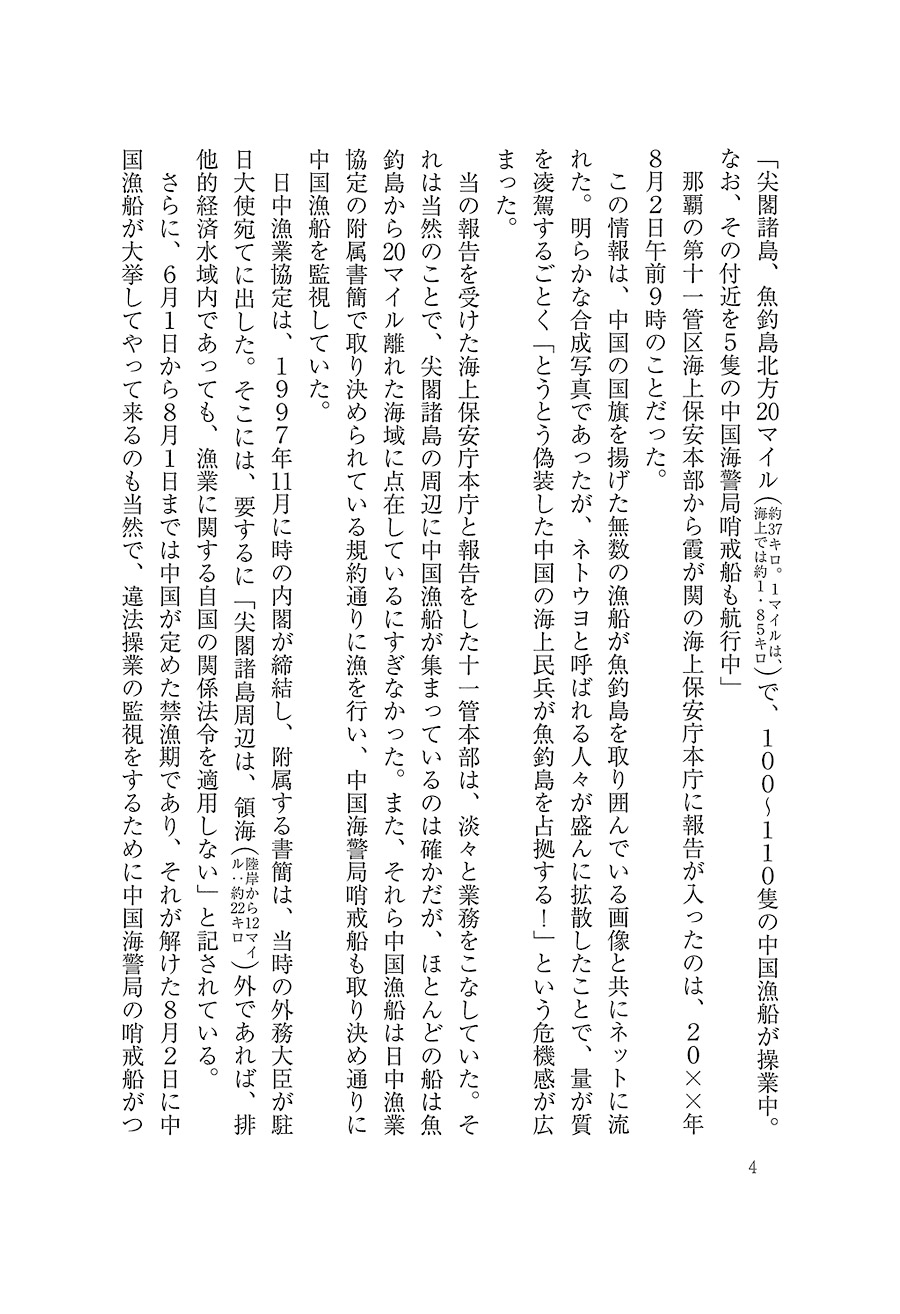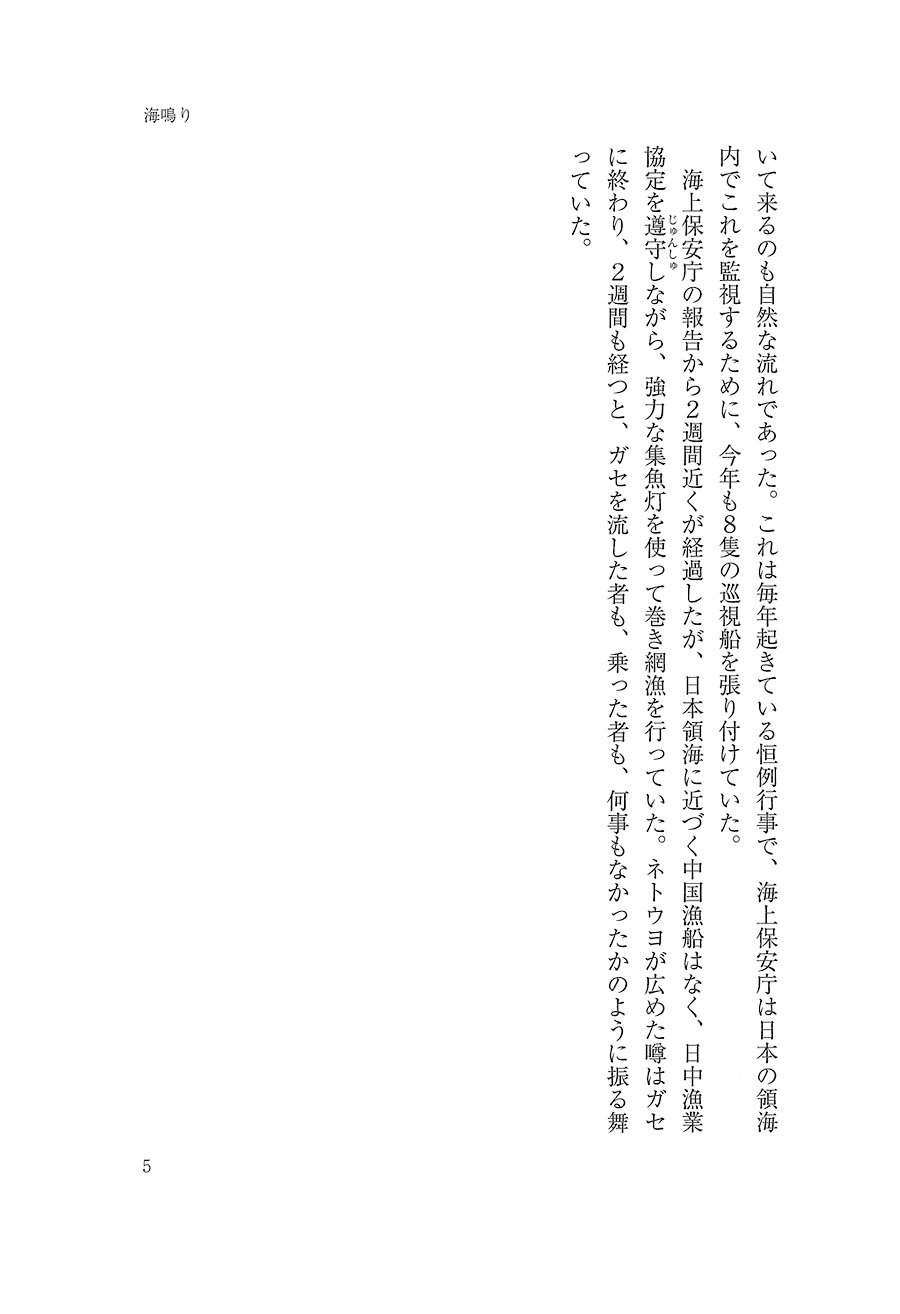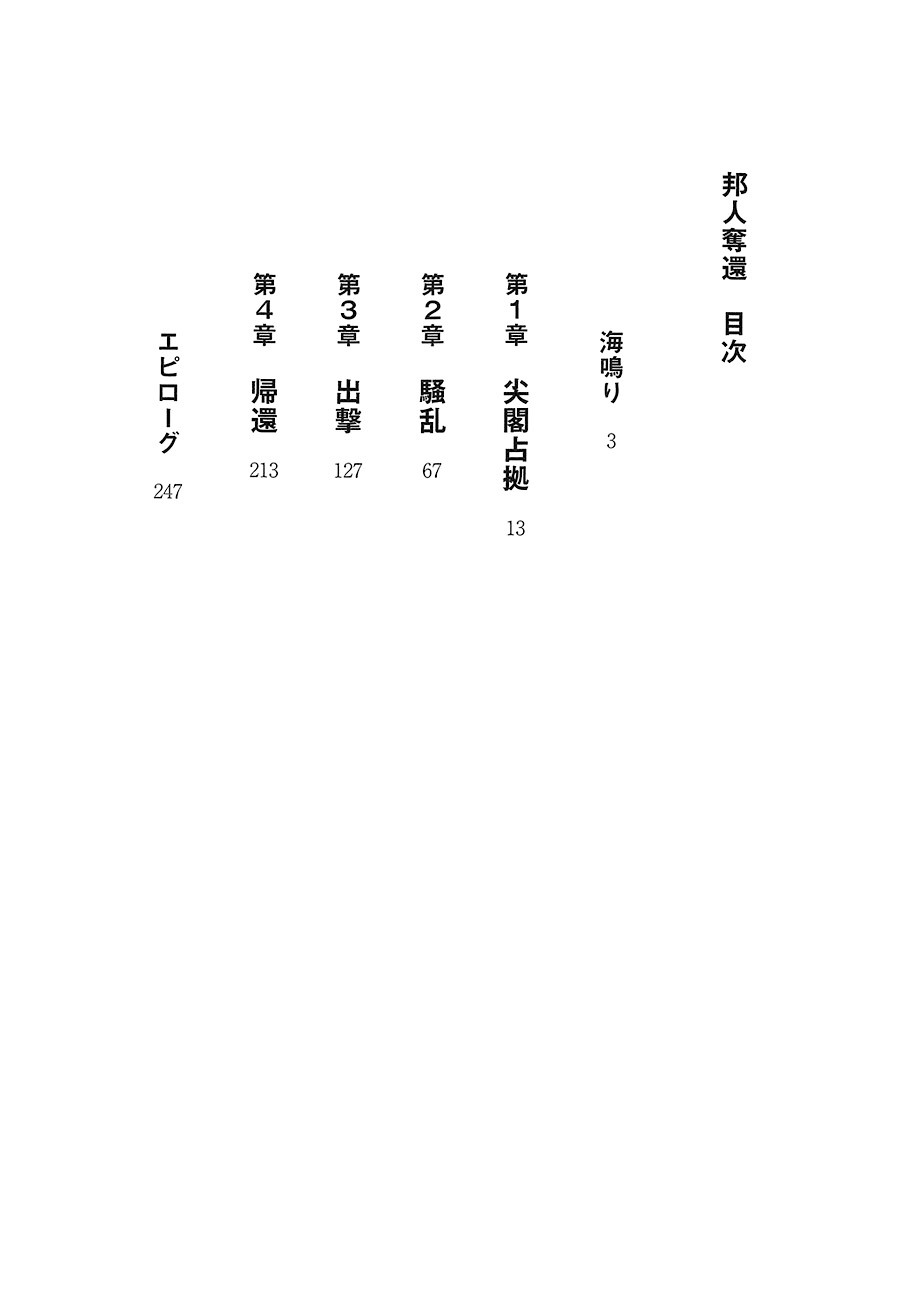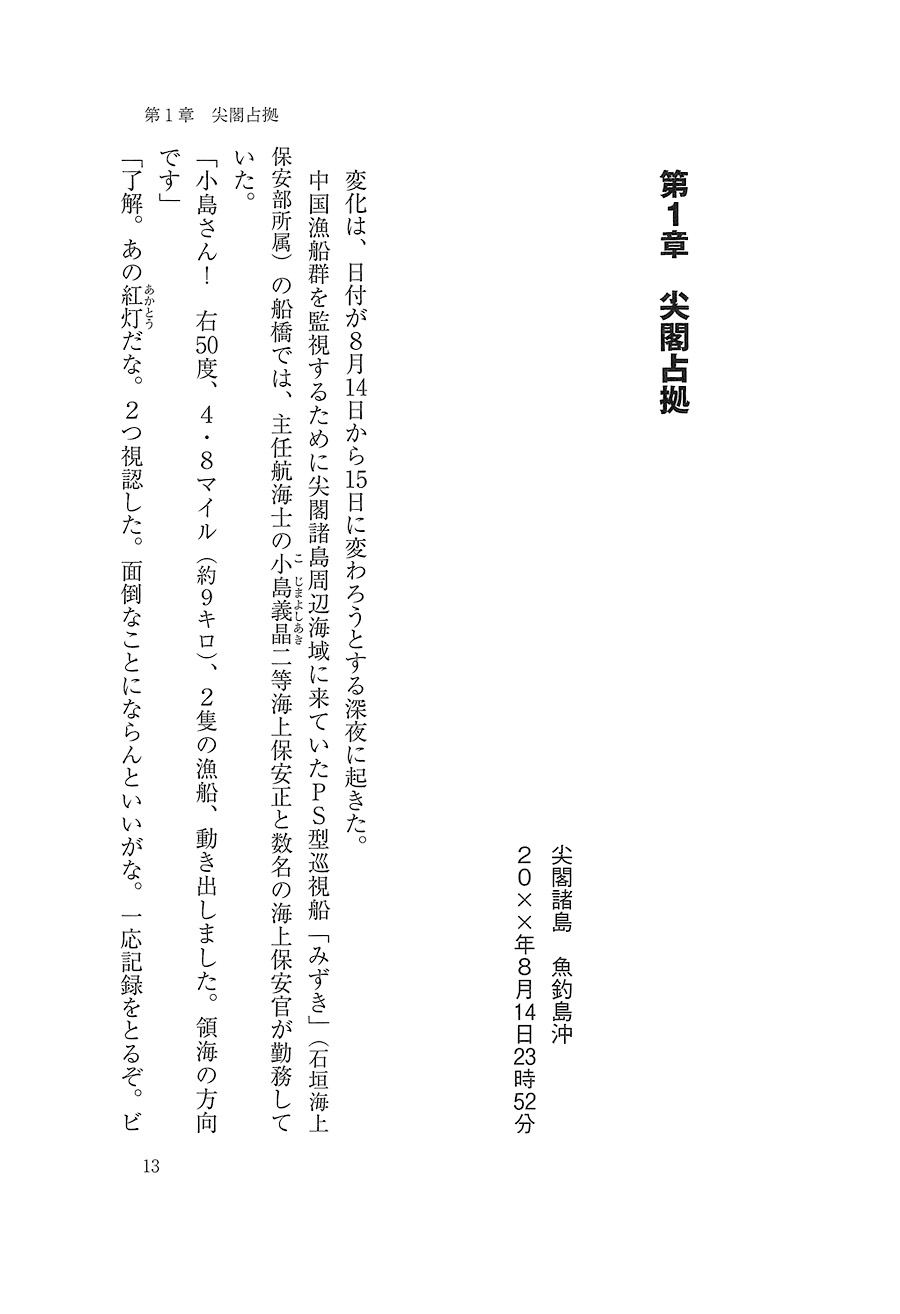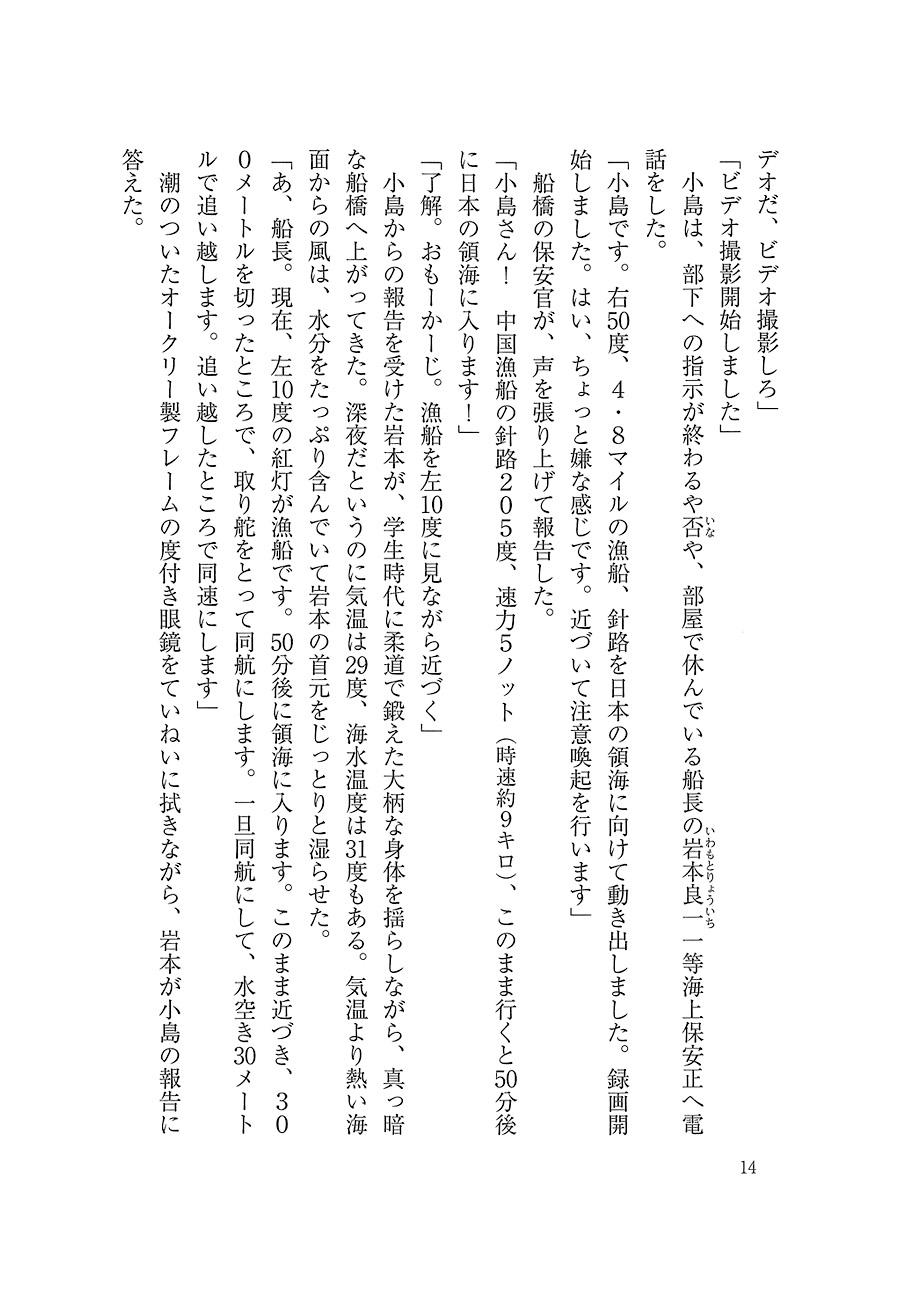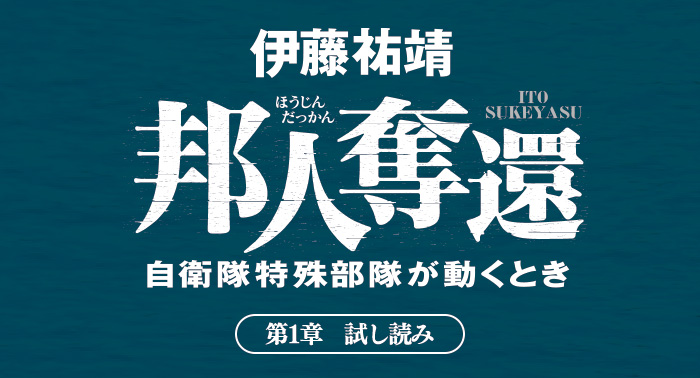
海鳴り
月の明かりが海面に反射し、水平線へと続く一本の道になっていた。月は、水平線に向かって加速度的にスピードを上げ、遂に接触した。道は一気に月に到達したが、月が沈むにつれ細くなり、
周期的に海鳴りを伴ってやってくる大波は、背丈ほどの岩を豪快に呑み込んでは引いていく。波が引くと、岩の足下には星の明かりが作る
その影の中を、獲物に忍び寄る大型爬虫類に似た動きで進む生き物がいる。音もなく、滑らかに、美しいほど不気味に進んでいる。その生き物は、日本政府より出撃を命ぜられた防衛省初の特殊部隊、海上自衛隊特別警備隊の
××××× ×××××
「尖閣諸島、魚釣島北方20マイル(約37キロ。1マイルは、海上では約1・85キロ)で、100~110隻の中国漁船が操業中。なお、その付近を5隻の中国海警局哨戒船も航行中」
那覇の第十一管区海上保安本部から霞が関の海上保安庁本庁に報告が入ったのは、20××年8月2日午前9時のことだった。
この情報は、中国の国旗を揚げた無数の漁船が魚釣島を取り囲んでいる画像と共にネットに流れた。明らかな合成写真であったが、ネトウヨと呼ばれる人々が盛んに拡散したことで、量が質を凌駕するごとく「とうとう偽装した中国の海上民兵が魚釣島を占拠する!」という危機感が広まった。
当の報告を受けた海上保安庁本庁と報告をした十一管本部は、淡々と業務をこなしていた。それは当然のことで、尖閣諸島の周辺に中国漁船が集まっているのは確かだが、ほとんどの船は魚釣島から20マイル離れた海域に点在しているにすぎなかった。また、それら中国漁船は日中漁業協定の附属書簡で取り決められている規約通りに漁を行い、中国海警局哨戒船も取り決め通りに中国漁船を監視していた。
日中漁業協定は、1997年11月に時の内閣が締結し、附属する書簡は、当時の外務大臣が駐日大使宛てに出した。そこには、要するに「尖閣諸島周辺は、領海(陸岸から12マイル:約22キロ)外であれば、排他的経済水域内であっても、漁業に関する自国の関係法令を適用しない」と記されている。
さらに、6月1日から8月1日までは中国が定めた禁漁期であり、それが解けた8月2日に中国漁船が大挙してやって来るのも当然で、違法操業の監視をするために中国海警局の哨戒船がついて来るのも自然な流れであった。これは毎年起きている恒例行事で、海上保安庁は日本の領海内でこれを監視するために、今年も8隻の巡視船を張り付けていた。
海上保安庁の報告から2週間近くが経過したが、日本領海に近づく中国漁船はなく、日中漁業協定を
第1章 尖閣占拠
尖閣諸島 魚釣島沖
20××年8月14日23時52分
変化は、日付が8月14日から15日に変わろうとする深夜に起きた。
中国漁船群を監視するために尖閣諸島周辺海域に来ていたPS型巡視船「みずき」(石垣海上保安部所属)の船橋では、主任航海士の
「小島さん! 右50度、4・8マイル(約9キロ)、2隻の漁船、動き出しました。領海の方向です」
「了解。あの
「ビデオ撮影開始しました」
小島は、部下への指示が終わるや
「小島です。右50度、4・8マイルの漁船、針路を日本の領海に向けて動き出しました。録画開始しました。はい、ちょっと嫌な感じです。近づいて注意喚起を行います」
船橋の保安官が、声を張り上げて報告した。
「小島さん! 中国漁船の針路205度、速力5ノット(時速約9キロ)、このまま行くと50分後に日本の領海に入ります!」
「了解。おもーかーじ。漁船を左10度に見ながら近づく」
小島からの報告を受けた岩本が、学生時代に柔道で鍛えた大柄な身体を揺らしながら、真っ暗な船橋へ上がってきた。深夜だというのに気温は29度、海水温度は31度もある。気温より熱い海面からの風は、水分をたっぷり含んでいて岩本の首元をじっとりと湿らせた。
「あ、船長。現在、左10度の紅灯が漁船です。50分後に領海に入ります。このまま近づき、300メートルを切ったところで、取り舵をとって同航にします。一旦同航にして、水空き30メートルで追い越します。追い越したところで同速にします」
潮のついたオークリー製フレームの度付き眼鏡をていねいに拭きながら、岩本が小島の報告に答えた。
「そうか、それでいい。船隊指揮には報告したんだな?」
「報告しました。他にもおかしな動きをしている中国漁船がいるらしく、1隻で対処しろとのことです」
「他にもか……。わかった」
にこりと岩本が
岩本は「なるほどな」と小声で
巡視船の真正面には、水平線に沈む月があった。鏡のような海面に自らを映しながら沈んでいく月を、岩本は
「小島、月ってこんなに赤いんだな」
「はい」
酒と仕事以外に関心の薄い小島にとって、月はただのまぶしい物体だった。
「不思議に思わんか? 月自体は赤いのに、月の光は青いんだぞ」
「はい。船長、取り舵をとって、同航にします」
「うん」
岩本は、話に乗ってこない小島に苦笑した。そんな岩本にお構いなく、小島は先を見越した適切な指示を出していった。
「おい、5分後に右舷のライト・メール(電光掲示板のようなもの)で、『貴船は、日本の領海に向かっている。直ちに針路を変更せよ』と中国語で流すぞ。準備しておけ」
巡視船「みずき」は、中国漁船2隻を右舷に見ながら同じ針路で30メートルの水空きを保ち、ライト・メールで針路変更を要求しながら追い越して行った。先頭の漁船を追い越し、2隻の漁船からライト・メールが見える位置につくと、速力を落として同速とした。
それから1分ほど過ぎた時だった。突然、船橋のVHF無線のスピーカーから
「ジャパン・コースト・ガード、こちらは中国漁船。我々2隻は、現在操業をしていない。漁場を変更するため、一時的に日本の領海を横切る。無害通航権を行使する」
漁船からの応答とは思えない無線に、ついさっきまでテキパキと仕切っていた小島は驚き、固まってしまった。
全員の様子を見ていた船長の岩本が指示した。
「応答しろ。『ディス・イズ・ジャパン・コースト・ガード、ラジャー・アウト』だ!」
岩本は、まだ固まっている小島に
「立入検査は実施しない。寝ている者をわざわざ起こすことはない。漁具は甲板上になかったから、漁業準備行為もなかった。今の位置関係を維持して、領海外に出るまで併走する。ライト・メールを消せ」
「はい、わかりました。……すいません、船長。自分は頭が白くなってしまいました。まさか中国漁船からVHF無線で英語の応答があるとは。それに、尖閣周辺海域は中国の領海だといつも主張しているのに、無害通航権を言ってきました。そこが日本の領海であることを認めたことになりますよね?」
「公船、海警局の哨戒船が言ったとなりゃ、中国政府が認めたことになるけどな。しかし、不自然だ。あの反応は漁船からとは思えない。漁師が無害通航権なんて言葉を使うか? しかも英語でだぞ。海警局からの入れ知恵に決まってる。こっちの体力を消耗させるのが狙いだよ。こんな時間に立入検査をするとなりゃ、寝ている者を起こさなきゃならない。その手には乗らんぞ。おい、ビデオは回しているな」
「大丈夫です。証拠映像は撮ってます」
「あとは、伴走して漁業準備行為の監視だ。やりやがったらしょうがない。直ちに止めて立入検査をする」
2隻の中国漁船は一列で航行しており、その左側30メートルを巡視船が追い越して行った。海上保安官たちは、追い越して行く際に甲板上を注意深く見ていた。漁具が置いてあれば、操業をしていなくても漁業準備行為として無害通航権は認められないからである。
当初は後ろの漁船を注視していたが、追い越した途端に意識は前の漁船に集中していった。それが相手の狙い通りだったとは、「みずき」の誰一人気づくことはなかった。
後ろの中国漁船の船倉にあるのは、小さな赤い明かりだけだった。
魚の血かぬめりか、それともオイルか他の液体か、シミだらけの木の床に5人の男たちがあぐらをかいて頭を突き合わせていた。
「とにかく潮に乗れ。西から4ノット(時速約7キロ)程度の黒潮がある。これに乗ればフィン・キックなしで釣魚島に着く。潮に乗れなかったら島にはどうやっても到達できない。だから、バディーとはぐれても、慌てる必要はない。釣魚島灯台のライトを常に東に見て潮に乗っていれば、必ず灯台付近に全員集結できる。いいな?」
「はい」
リーダー格の男の話を、他の4人が床を見つめながら聞いていた。
男の声は、夜間戦術行動をする者が用いる独特な出し方だったので響かず、至近距離の者にしか聞こえない。声が通る北京語でさえ、3メートルも離れると音として届かない。
「上陸したら、まず、灯台の日本国旗を捨てる。そして、中国国旗を揚げる。揚げ終わったら山を上がり、標高100メートル付近の水が出る可能性の高い2ヶ所へ行き、掘って水が出て来るかを確認する。出て来れば、さらに掘って水が貯まるように簡単な井戸を作る。場所はここだ」
リーダーは、日本の国土地理院が発行した精巧な魚釣島の地図を広げて言った。
「水場さえ押さえれば、長期
「高い場所に水場を確保することと、長期籠城とどんな関係があるんですか?」
「この島の
「わかりました。日本の軍隊はどの段階で動きますか?」
「日本という国は、そうそう簡単に軍隊を出さない。最初は警察、おそらくコースト・ガードだ。それを出すのにも時間がかかる」
「具体的にいつ頃と予想していますか?」
「明るくなって水平線が見えてくるのは朝の5時くらい。コースト・ガードが灯台の中国国旗に気づくのは、完全に明るくなる日の出以降。早くて6時過ぎだ。これが東京に報告され、大騒ぎになり、議論の末に出動命令が下るのは半日後だ。奴らが灯台付近に来るのは夕方、どんなに早くても15時だろう。だから、我々は水の確保がうまくいかなかったとしても、15時までには灯台に戻る」
リーダーの淀みのない説明に、4人は頷いていた。
「コースト・ガードは旗を日本国旗に戻すため、灯台付近に来る。そこを攻撃する。ただし、絶対に殺すなよ。怪我までだ」
4人のうちの一人が質問した。
「反撃して来たらどうするんですか? 手負いの獣ほど恐ろしいものはない」
「撃ち返しては来ない。現場が撃とうとしても、日本のトップが絶対に許可しない」
今度は、別のメンバーがリーダーに食ってかかった。
「許可しないって、そんな……。そうしたら、ただ撃たれるだけです。それでも日本は許可しないんですか? 第一、そんな指示に日本人は従うんですか?」
「そうだ。日本人は、信じがたいくらい権威に弱い。上位者からのどんな指示にでも黙って従うから、政治家や官僚は現場の者に命があることを忘れてしまっている。それにすら異を唱えないのが日本人だ」
「本当ですか?
「いない。しかも、あの国は決断を嫌い、どこまでも譲歩をしてくる。際限なしの泣き寝入り国家だ。ところが、ところがだ。ある一線を越えると大変なことになる」
「え?」
「お前の一発で日本人が死んだ時は、どうなるかわからない。国民の性格が180度変わって、手がつけられなくなる。だから、もし反撃されても、絶対に私の指示なく撃つな」
「はい、わかりました」
「よし、3時30分に
5人の男たちは、2ミリの薄いウエットスーツを着て、防水のバックパックに注意深く息を吹き込んでいた。中には中国製のノリンコ拳銃と予備弾倉3つ、銃床部が折り畳めてコンパクトになるロシア製のAK-47ライフルと予備弾倉5つ、オリーブ・ドラブ(濃い緑色)に塗装された手榴弾3つ、刃渡り20センチのサバイバル・ナイフ、通信機、メディカル・パックが入っている。地上では重量が30キロ近くになるバックパックだが、空気で浮力をつけて水中での重量を1キロ程度にしようとしていた。作業中の彼らの
5人は入水するために漁船の右舷に集まり、互いに装備品の装着状況をチェックする。
リーダーが入水することを無線で伝えると、前方の漁船の甲板上で小さな赤いライトがチラチラと動き出した。
「小島さん! 奴らが動き出しました。漁具の準備をするかもしれません」
巡視船「みずき」の海上保安官たちは小さな赤いライトを見逃さなかった。ある者は双眼鏡で、ある者は暗視装置で、その小さなライトを追っていた。見えそうで見えないのが
「見えたか?」
「いや、漁具はいじってないです」
海上保安官の視野は、完全にコントロールされていた。前方の漁船でちらつくライトを注視するゆえ、その1分、2分の間に後方の漁船から入水した5人に気づく者はいなかった。
相手の心理を利用し、少しの時間でも操ることが作戦の成否を大きく左右する。これを戦闘センスと言う。
その後も、「みずき」は2隻の中国漁船に伴走し続けた。何事も起こることなく、数時間が経っていった。
はっきり見えていた天の川も、いつしか認識できなくなっていた。
一番早いのが天文薄明で、日の出の
巡視船「みずき」の船橋にいる保安官たちは、何となく浮かれていた。
それは、中国漁船がトラブルを起こさずに日本の領海を出て行きそうだったからだけではない。日の出が近づいていたからである。
天文薄明を過ぎて星の数が減り始めると、東の空が白み始めて航海薄明となる。この時間帯の空にはすべての色がある。西の水平線付近はまだ夜の闇だが、天頂に向かうにつれて黒から藍、紫、青となり、天頂から東の水平線に向かって青、緑、黄、橙となる。天空を彩るすべての色は刻々と無段階に変化し、やがて東の水平線より一点の深紅が現れて日の出となる。
人間は、自らの身体の奥に動物としての本能があることを思い出し、空が明るくなってくると気分が高揚する。これはおそらく、何万年もの昔、夜行性動物に捕食される危険から解放された遠い記憶によるのだろう。
「船長、まもなく中国漁船、領海外へ出ます」
「了解。月没と同時に騒動を起こした連中が、
船橋の椅子に身体を預けていた岩本は、大きく伸びをすると、椅子から立ち上がって左舷の方に行き、水平線から姿を現した太陽を見た。
「船長、漁船が領海を出ました。レーダーで動きを監視しつつ、本船は魚釣島に近づき定期観測のため島を一周します」
小さな深紅の点だった太陽が
船で一周するとよくわかるが、魚釣島は南から見る景観と北から見るそれがまるで違う。島の南側は岩肌
「みずき」は、一周5・4マイル(約10キロ)ある魚釣島の南西端から反時計回りに定期観測を開始、陸岸から200メートル沖合を注意深く時速3ノット(時速約6キロ)で航行した。途中、こちらをうかがっているヤギを発見するたびに停止し、正確な位置や頭数等を記録する。ヤギは1978年、灯台建設時に緊急時の食糧として持ち込まれた2頭が、30年を超える長い年月を経て数千頭に繁殖したと推定されている。
定期観測を始めて3時間近くが経過、「みずき」は魚釣島の北西端近くの灯台沖を航行していた。
昨晩は徹夜に近かった岩本は、船橋の椅子にもたれて、魚釣島の情景を眺めていた。東京のアスファルトの中で育った岩本にとって、青い空、濃い緑、白い砂浜の魚釣島は別世界だ。漂ってくる樹木の香りで眠気が覚めていく気がしていた。
その岩本が、最初に異変に気づいた。何気なく灯台を見ると、赤いものがはためいている。日の丸の赤はこんなに目立っただろうかと双眼鏡を覗き、
「あっ!」
と思わず声を出した。船橋にいた海上保安官全員が岩本に目を向けた。そして、すぐさま岩本が見つめる先、魚釣島の灯台付近に目を移した。
「頭(船首)を灯台に向けろ!」
双眼鏡で灯台を見つめたまま、岩本がしゃべり始めた。
「昨日は日の丸だったよな。というか、日の丸以外、ありえないよな」
船橋にいた保安官の誰もが、慌てて双眼鏡で灯台を見た。最初に目に飛び込んできたのは灯台最上部の光源部分だったが、双眼鏡の視線を少しずつ下にずらしていくと、ありえない光景がそこにあった。灯台のやぐら部分に3つの中国国旗がはためいている。
「写真を撮って、すぐに船隊指揮に報告だ。このままぎりぎりまで近づけ」
魚釣島の灯台に中国国旗が掲げられている写真は、直ちに霞が関の海上保安庁本庁に報告された。そして、海上保安庁長官から国土交通大臣へ、国土交通大臣から官房長官を通じて内閣総理大臣へと報告が上がった。
事態を重く見た官房長官は、緊急事態大臣会合を総理に提案し、10時30分からの実施が直ちに承認された。盆の真最中で国会議員の多くが地元に戻っていたが、箱根で観測された火山性群発地震により、
官房長官の
官邸に参加者が全員揃うと、威圧的なトーンで早口な手代木が切り出した。
「総理、集まりましたので、早速開始させていただきます」
総理大臣の葛田は、政治家一族の出で、参議院議員だった父親の秘書官として政治の世界に入った。タカ派として鳴らした父親譲りの強気な愛国者ぶりを保守層から期待されて、総理大臣の座まで上り詰めたのだが、性格は父親とは真逆で、子供の頃から自分の意見や願望を持たず、他人の意見に左右されやすい男であり、総理大臣となった今、最大の悩みはイメージとのギャップであった。
バックグラウンドも性格も正反対の手代木官房長官とは同い年で、お互いが自分に足りないものを持ち合わせていた。手代木は、政界のサラブレッドである葛田が持つ有力者の強力な人脈を利用し、血筋ばかりが先行して実は決断力もなければ統率力もない葛田は、手代木に何でも相談し、指示を仰ぐ。どちらが欠けても、総理と官房長官ではない。
「海上保安庁長官、現状を説明してくれ!」
海上保安庁長官の
「はい! 今朝9時14分に巡視船『みずき』が、魚釣島灯台に中国の国旗が掲げられているのを発見しました。報告によりますと……」
正面スクリーンには、灯台に掲げられている中国国旗が映し出されていた。説明を終えた海上保安庁長官に、総理大臣が質問した。
「最後に日の丸を確認したのはいつですか?」
「24時間前です。巡視船8隻が付近にいますので、昼間は誰も魚釣島に近づけません。昨晩、何者かが上陸し、夜のうちに日の丸から中国国旗に揚げ替えたことになります」
官房長官が、割り込むように言った。
「総理、世間にこの話が広まる前に元の状態に戻すことが大切です。さっさと日の丸に揚げ替えなければなりません。幸い、あの島は人の目が極めて限定されていますので、今なら十分に間に合います。なあ、海上保安庁長官、簡単なことだろ?」
「近くにいる巡視船に日の丸はあるので、揚げ替えは可能ですが……」
海上保安庁長官は、魚釣島に何者がいるかわからない状態で海上保安官を上陸させたくなかった。だが、真正面から官房長官の意見に異を唱えることはできず、直属の上司である国土交通大臣の顔を窺いながら歯切れの悪い回答をした。
国土交通大臣の
「問題は、中国の国旗を揚げた者が今も魚釣島にいて、武装している可能性を否定できないことです。昨晩、中国漁船2隻が領海を横切っております。島に最接近した際の距離が6マイル(約11キロ)です。巡視船が30メートルの距離で伴走し、監視しておりましたので、ボートを降ろすことはできません。漁船から飛び込んで泳いだか、潜って上陸したわけです。とすれば、並みの者ではないわけですから……」
無表情で説明を聞いていた手代木官房長官は、吐き捨てるような口調で言った。
「じゃあ、旗を揚げ替えるのに自衛隊を出すべきだって言うのか? 名目は何にする? 旗の揚げ替えは海上保安庁の能力を超えておりますとでも言うのか?」
桜井は自分の顔が見えないよう手代木に背を向け、塚本に対して「ダメだ。やれ」と表情で伝えた。
官房長官は、畳みかけるように言った。
「塚本長官! できるんだろ?」
「は、はい! できます」
海上保安庁長官の口から「できます」を引き出した手代木は、今度は総理に畳みかけた。
「総理、今すぐやらせるべきです。塚本長官、今すぐだ! 13時までにできるな?」
総理大臣の葛田が頷きながら言った。
「海上保安庁長官、ご苦労だが、そうしてくれるかな」
「はい!」
自分の思い通りに話を進めた手代木は、さらに続けた。
「皆さん、秘密裏に緊急会合を開いたのには、この情報を知っている者を限定するという目的があります。番記者に
魚釣島沖の巡視船「みずき」から、5人の海上保安官が乗ったゴムボートが降ろされた。
一番若い石塚が不安そうに艇長の成田に訊いた。
「成田さん、旗を揚げ替えた連中は本当にもういないんですよね?」
「当たり前だろ。この話はうちの船長が言い出したことじゃないんだぞ。今朝開かれた、大臣とかの会議で決まったことなんだ。その場には総理もいた。ヤバい連中がいるところに俺らを行かせるわけがないだろ」
「本当ですか?」
「ちゃんと内閣情報調査室とかからの情報があって、いないことがわかってるんだよ。でなきゃ、船長もそうだし、第一あの小島さんが黙ってるわけないだろ。そんなことよりお前、島に上がるの初めてだろ。驚くぞ。ちゃんと水路の奥に船着き場があるんだよ。明治時代にこんなところまで来て、珊瑚礁を削って水路を掘って船着き場を作ったんだ。鰹節工場は跡しか残ってないけどな」
保安官を乗せたゴムボートは、魚釣島の幅10メートル長さ100メートルある人工の水路に入っていった。水路の一番奥から100メートルほど先に灯台があり、そこに中国の国旗が3つもはためいていた。
ゴムボートは水路の一番奥に横付けしたが、誰も降りようとしない。全員が譲り合っている。成田が石塚に人差し指を向けながら「お前から行け」と口を動かすと、観念した石塚が最初に降りた。
船着き場に上がった石塚は、どういうわけだか上半身を前に折り曲げた妙に低い姿勢で、ソロリソロリと足音を立てないように灯台に向かって歩き始めた。艇を守る艇長と通信員を残し、石塚に続いてボートを降りた2人も同じ姿勢で灯台に向かう。体重をかけることにより、足下のこぶし大の石がゴロッと小さな音を立てると、3人は一斉にうずくまり、ジッと動かないでいた。20秒もすると先頭の石塚が後ろの2人の方を振り向きゆっくり頷くのに意を決したのか、3人はゆっくりと立ち上がり、再び低い姿勢で歩き出した。エンジン音を響かせたゴムボートに乗ってきた後で、今さら音を気にしても何の意味もなかったが、3人はとにかく音を立てないように注意深く歩いていた。
ようやく灯台にたどり着くと、3人は急に動きを早め、中国の国旗を外し、持ってきた日の丸を縛りつけた。最初に四隅を縛り終えた石塚がボートへ走り始めると、残された2人は旗の四隅すべてを縛り終えていないのに、慌てて後を追った。3人がほぼ同時にボートに飛び乗ると、来た時とは裏腹に全速で狭い水路を抜けて巡視船に向かった。
急斜面を100メートルも登り、2つの井戸を掘り終えて灯台に戻ってきた中国漁船の5人は、呆然と立ち尽くしていた。当初の計画より2時間早い13時に戻ってきたというのに、揚げ替えたはずの中国国旗が再び日の丸になっていたからである。日本のコースト・ガードに出動命令が下るのは半日後、灯台付近に来るのは夕方、どんなに早くても15時だと言ったリーダーへの信頼が一気に揺らいだ。
5人の中でも焦りを
この程度のミスであれば作戦の遂行に致命的ではないし、上級司令部がリーダーの犯した失敗に気づくこともない。しかし、無人島で完全に孤立して行動するようなチームでは、淘汰されてしまうこともある。なぜなら、能力の低い味方は敵より怖く、それがリーダーであればなおさらだからである。全員が武装し、人を
「日本の国旗を燃やせっ!」
「えっ、なぜです?」
「いいからお前がやれ!」
「わ、私が、ですか……?」
いきなり指名された若いメンバーが戸惑っていると、リーダーはより声を荒らげた。
「聞こえたなら、返事をしろ!」
「はい」
「旗の縛り口に水をかけてから火をつけろ! 燃えかすを残すんだ。それを見た日本のコースト・ガードは再び揚げ替えに来る。攻撃はその時に開始する!」
首相官邸に、再び裏の荷物搬入口から大臣たちが集まってきた。
1日に2度も緊急事態大臣会合が開かれるなど、極めて異例の話である。それも、前の会合からわずか4時間後である。
全員が揃うと、手代木官房長官がいきなり本題を切り出した。
「皆さん、既にお聞きの通り、揚げ替えた国旗がまたやられました。しかし、中国政府に動きはまったくない。マスコミに漏れている情報も皆無だ。だから、この問題は処理できる。いや、できるだけ早く処理しなければならない」
いつにも増して威圧感のある官房長官の手代木に、場が緊張した。ところが、集まった中で最も年齢が若く、気が弱い塚本海上保安庁長官が、指名を待つことなく発言し始めた。一点を
「最初に申し上げさせていただきます。私どもは海の警察であります。バックに国家があり、組織的な訓練を受けた人間を相手にするだけの人も装備品も準備しておりません。SST(海上保安庁特殊警備隊)は、島へ上陸しての地上戦は想定していません。サメがうじゃうじゃいる海域を泳いだのか潜ったのか知りませんが、夜中の海から魚釣島に上陸したような連中が確実にいる島へ、保安官を行かせるのは無理があります。しかも、連中は挑発をしています。こちらを待ち構えています。軍人、もしくはそれと同等の人間ですよ。軍人が待ち伏せしているところに保安官を行かせるわけにはまいりません。軍人に対処するのは防衛省のはずです」
自分の話を遮られる形になった手代木は、険しい目つきで海上保安庁長官の塚本を見ていたが、話が終わると「たしかに国旗を燃やすというのは挑発だな」と呟いて、今度は防衛大臣に顔を向けた。
「軍人に対処するのは防衛省。そうだよな」
振られた
「はい。官房長官のおっしゃる通りかと存じます」
防衛大臣の田口は、当選回数が多いというだけの理由で閣僚入りした。選挙区に大きな支持母体を持っていること以外に、これといった強みはなく、防衛問題に関しても素人に近い。
ただ、防衛省内の評判は悪くなかった。素直だからである。国会の質疑応答では、ペーパーなしでは何も答えない。マスコミから「読み上げ大臣」と
それゆえか、田口防衛大臣には、自分から何かをしようという気概が、不気味なほどなかった。そんな田口を、手代木は無視してきた。まともに関わると、事なかれ主義の権化のような存在に腹立ちが抑えられなくなる。
「防衛大臣、魚釣島のお尋ね者は自衛隊が処理するしかないだろう。問題はそれをどうやるかだが……」
「どう行うかについては、各幕僚長としっかり相談して決めようと思います」
型通りに田口が口にした瞬間、手代木が感情を爆発させた。
「防衛大臣、相談なんかするな! 制服組に方法を考えさせるんだぞ。相談じゃない。政府の意向を君が伝え、具体的な手段を考えるように命じるんだ。勘違いするな」
手代木の激情ぶりに、葛田総理が口を挟んだ。
「官房長官、元防衛庁長官としては歯痒いのかもしれないが、それぞれキャラクターがあるんだから」
幼なじみをフォローするかのような声かけだった。
「失礼……」
「ところで官房長官、解決策はもう考えてあるんですよね?」
「はい。特殊部隊を使うべきだと思っています」
「ほう、特殊部隊……」
「彼らの手で、島にいる連中を隠密裏に蒸発させるのが得策だと思います」
「自衛隊の特殊部隊に、そんなことができるのですか?」
「はい。私は、日本に特殊部隊を創設するきっかけになった能登半島沖不審船事件の時に防衛庁長官をしておりましたので、創設にも関わりました。海自の特殊部隊に何度も視察に行っておりますし、その3年後にできた陸自の特殊部隊も視察しましたので、そこはよく知っているつもりです。防衛大臣、能力は十分だろ?」
「はい。十分です」
特殊部隊と言われても存在を知っている程度で、視察にさえ行ったことがない田口防衛大臣は正直何もわからなかったが、官房長官の意見を否定するはずもなく、これに気を良くした手代木は続けた。
「ただ今回は、陸自の特殊作戦群よりも、海自の特別警備隊を使う方がいいと思います。両部隊とも特殊部隊ですので、海だからとか山だからとかでその能力に甲乙はつけられません。違いがあるとすれば、短期集中型か、長期にわたる作戦かになります。今回は3日以内の作戦になるでしょうから、短期集中型の特警隊の方が得意でしょう」
葛田は、黙って頷いていた。
「陸と海の自衛隊が持つ特殊部隊は視察に行かれるべきです。総理の場合、内外の反応も大きいので慎重に計画致します。英国の鉄の女、サッチャーのこともありますし」
会議に参加している一同は、発言こそしなかったが「何それ?」という表情だった。
「有名な話です。サッチャー首相は、SASイギリス陸軍特殊空挺部隊の視察で、自分が人質役になってテロリストに見立てた標的の隣に立ち、突入させて実弾で標的を撃たせました。その際、自分の髪の毛が焦げたと言われています。その後、駐英イラン大使館占拠事件が発生し、人質の殺害が開始されるや直ちに、サッチャー首相は警察の指揮権をSASに委譲させ、突入させた。これは、視察時の経験があってこその政治判断だったと聞いています」
このエピソードに感銘を受けたのか、普段は官房長官に促された時しかほとんど発言しない葛田が発言した。
「時期についてはお任せしますが、視察を計画してください」
「承知しました。行ってこの目で見ないことには理解できません。私は、髪の毛を焦がしてもらってはいませんが、彼らの能力は、創設時に目指したもの以上になっています。何より、陸自の特戦群も、海自の特警隊も、国家の重大危機のために自分たちは存在するという自負心を持っています」
特殊部隊について熱く語り始めた官房長官の姿に、参加者は一様に驚いた。
話し終えた官房長官は、葛田の目を直視しながら言った。
「総理、今回は海上自衛隊の特別警備隊に作戦を遂行させる方向で進めます」
葛田は、目をつぶりながらゆっくりと頷いた。
「皆さん、隠密裏の作戦ゆえ、他言は無用です」
言い終えた手代木は、再び葛田の方を向いて心の内側を吐き出すように小声で言った。
「総理。まったくあの国は訳がわからない。拉致問題解決の橋渡しをあそこまでやってくれて、ようやく友好的な関係になってきたというのに……。これで、中国との関係も終わりですし、拉致問題解決の糸口は消えたも同然です」
葛田は、小さく何度も頷きながら言った。
「まさにディス・イズ・チャイナ。これこそが、太古の昔より、どこの国もあの国を信用しない理由なのでしょうな」
隠密裏に自衛隊を動かすという重大な政治決断がなされたにもかかわらず、十分な議論はなく、官房長官の意見のまま押し切られていた。
15時30分、特別警備隊長のデスクにあるホットラインと呼ばれる秘話装置が内蔵された電話から、突如けたたましい着信音が響いた。着任してまだ2週間の
「はい、内線35××です」
「特別警備隊長でいらっしゃいますか? 自衛艦隊司令官副官の別井1尉です。司令官からのお電話をお繋ぎ致します」
1999年3月に北朝鮮の不審船と海上自衛隊のイージス艦とが一触即発の状態になる能登半島沖不審船事件が発生した。この事件をきっかけに、当時の首相の声かけで創設されたのが、自衛隊初の特殊部隊、海上自衛隊特別警備隊である。広島県
「了解。はいっ。隊長の久遠でございます。はい。隠密裏に人間を蒸発させる?! ……えっ、3日以内に? ……はい、承知しました」
ホットラインを切ると、久遠は副長の
「バッドマン(藤井のコールサイン)、ディス・イズ・XO(エグゼクティブ・オフィサー:副長)」
「ゴ・アヘッド(内容を送れ)」
「CO(コマンディング・オフィサー:隊長)まで、ASAP(エイサップ=アズ・スーン・アズ・ポッシブル:可及的速やかに)」
副長からの、藤井を呼び出す無線が流れた。
藤井は、第3小隊で導入予定の水中スクーターを確認試験中だった。電動水中ジェット・スクーターは、外観はジェット・スキーに似ている。
無線を受けた藤井は、急いでウエットスーツを脱ぎ、海水を洗い流しただけだったが、潜水用品庫から隊長室に来るまで約20分を要した。その間に、久遠は自衛艦隊司令官から、尖閣諸島魚釣島で起きていることに関する細部情報を伝えられていた。
やきもきしながら待っていた久遠は、副長が藤井に状況を説明し終わると、すぐに尋ねた。
「藤井、3日以内だ。3日以内に隠密裏に蒸発させることなんてできるか?」
「はい」
「説明してみろ」
「魚釣島に潜んでいる奴らには、焦りと不安があります」
「なぜ?」
「奴らはミスってます。間違いなくリーダーのミスです。おびき寄せた海上保安官にスリップされてしまったんですよ。灯台の日の丸を中国国旗に替えたのは、海上保安官を招き入れるためです。その一番大事な時に現場を離れていたため、すり抜けられてしまった。時間の読み違いでしょう。しかも、持って行った中国国旗を3枚全部揚げてしまった。1枚も残っていないから、次は日の丸を燃やすしかなかったわけです。時間の読み違いは決定的なミスです。決定的なミスをしたリーダーは、部下に高圧的に出る場合がほとんどです。そうなりゃ仲間割れ、内紛が起きてるかもしれません」
「そういう細かい話はいい。お前たちは何人で行くんだ?」
「3人ですね」
「3人? たった3人でいいのか?」
「向こうは、特殊部隊ではない4人程度の兵力です」
「なぜそう言い切れるんだ?」
「単独行動を常としている特殊部隊員であれば一人でも作戦行動がとれますから、灯台付近に待ち伏せ要員を張り付けておけます。通常は、4人1チームが最小単位です。その分離ができなかったとすれば、4人程度しかいないということになります」
隊長の久遠にとって、滑らかな藤井の説明は、
「こちらが3人なのは、数が少ない方が居場所を
「そうか。で、誰を連れて行くんだ?」
「主戦場は夜の山なので、うちの小隊の黒沼と嵐ですね。1時間半ください。エムエムをしながら詳細な作戦を立てます。18:00(ヒトハチマルマル)までには終わるでしょうから、出撃18:45(ヒトハチヨンゴウ)。魚釣島上陸を
「エムエム?」
「マップ・マニューバー、陸軍式の作戦会議です。実際に地図を広げて、その上でコマを動かして、シミュレーションしながらやるから、そう言うんでしょうね」
海上戦闘が主任務の海上自衛隊ではまったくなじみのない陸軍式の会議を、特別警備隊は取り入れている。さっぱり想像がつかない久遠だったが、これ以上、藤井に質問するのも
「わかった。それでいいだろう。副長、航空部隊と調整してくれ。そして藤井、そのエムエムはここでやれ。俺も参加する」
「ここって、隊長のお部屋で?」
「そうだ」
「構いませんけれど、行儀の悪い奴らで……」
「そんなことは構わん」
「では、今から二人に魚釣島で起きていることを説明して、15分後に始めます。副長、航空部隊とは、18:45(ヒトハチヨンゴウ)にうちのヘリポートを飛び立って、奄美あたりで給油して、直接魚釣島の沖合2マイル(約4キロ)に00:30(マルマルサンマル)に3名をキャスティング(海面に飛び降りる)させる、ということで調整してください。キャスティングするポイントと、そこへの進入針路、最終高度、最終速度の調整は、後ほど私が飛行隊長と直接すると伝えてください」
藤井がそう言ってから、ぴったり15分後に3人が隊長室に入って来た。手ぶらの藤井を先頭に、藤井に比べて横幅のある、がっちりとした体格の黒沼栄一(曹長・37歳)第3小隊チーフ(下士官のトップ)、その後ろから、藤井や黒沼よりも長身で第3小隊の戦術を担当している嵐康弘(2曹・33歳)が続く。3人は挨拶もなく部屋の奥へ進み、そのまま久遠のいる応接セットのソファに座るなり、嵐の持ってきた、A3に拡大コピーした魚釣島の地図をテーブルに広げた。久遠は礼儀知らずとばかりに睨みつけた。
「まず、任務分析。黒沼はどう考えた?」
いきなり会議を始めようとする藤井に、隊長の久遠が右の手のひらで待ったをかけた。
「任務の詳細に関しては、自衛艦隊司令官から直接、俺が電話を受けている! 政府の意向はな……」
「隠密裏に蒸発させることですよね。9時間後に魚釣島に上陸するとなると時間がございませんので、私たちのやり方で進めさせていただきたく……。ご指導は後ほどお受け致しますので、お願い致します」
久遠はムッとしたが、黙るしかなかった。
「黒沼! さっさと言え」
「まあ、奴らの最終的な任務は、魚釣島で中国海警局に逮捕されることでしょうねえ」
久遠は、顔から火が出る思いだった。「任務分析」とは当然、自分たちに与えられた任務に関してだと思っていたら、敵が受けている任務をどう推測するかという話だったからである。
「嵐は?」
「見え見えよ。上陸している奴らは旗の揚げ替えにきた保安庁クンに発砲する。保安庁は撤退する。中国の海警局が強引に上陸してくる。撤退する保安庁とすれ違いに、見せかけの銃撃戦をしながら海警局は島に突っ込み、奴らを拘束する。魚釣島で中国国家機関が中国人を拘束した。日本の国家機関の目の前で問題を解決した。その島はどの国の領土ですかって話よ! 国際司法裁判への実績作りじゃろ!」
出身地の鳥取弁と、もう長く住んでなじんだ呉弁の混ざった口調でそう言うと、嵐はソファに身体を投げ出した。その隣の黒沼も「そんなとこでしょう。私も同じです」と同調した。藤井は準備体操の首回しのような仕草をしながら話を聞いていたが、その動きを止めると二人に問うた。
「そんな気もするけど、なんかよ、違うんだよ。もっと大がかりじゃねえと世界ニュースにならねえよ」
嵐は反射的に上半身を起こし、黒沼はもともと大きな目をさらに広げて、藤井の口元に注目した。
「だって、嵐の絵柄では世界的なニュースになんねえよ。中国側が動画を配信したところでインパクトが小せえ。中国人が魚釣島に潜伏している、今現在も魚釣島のどこかにいる、それを巡って、日本と中国が揉めている、となれば、面白れえよ。そりゃ注目するだろ。今後どうなるかに興味が湧くもんな……」
顔をしかめて聞いていた嵐が言った。
「確かにな……。中国とすれば魚釣島に籠城させて、世界の注目を集めたところで、ひと芝居打ちたいのか……」
藤井は手品の種明かしを得意げにする子供のように、説明を始めた。
「保安庁は一回、旗の揚げ替えに成功してるんだ。それは中国の奴らが灯台を離れていたからできたわけで、奴らには離れなければならない理由があったってことだ。拠点を作る必要があったんじゃねえのか? それは籠城しろと命じられているからだ。魚釣島に中国人が上陸して、海上保安官がそいつらに撃たれ、撃った中国人が今も魚釣島に立て籠もっているとなれば、世界が放っておけねえニュースになる。そうなりゃ、日本政府も警察のSAT(特殊急襲部隊)や防衛省の派出を考える。領土問題で揉めている国とその現場で銃撃戦になることは避けたいから、なんとか穏便に話し合いで済まそうと奔走する。2、3日はすぐに経っちまうさ。騒ぎがどんどん大きくなったその頃、奴らが中国海警局にならば投降すると言いだし、海警局が強引に上陸して逮捕する、これならわかる」
嵐は腕を組み、藤井を
「黒沼、敵の任務のキーワードは?」
目をつぶったまま黒沼は即答した。
「海上保安官に負傷以上を負わせること。籠城して世界的なニュースにすること。海警局に投降して日本のメンツを潰すこと。この3つでしょう」
「キーワードはそんなところだろう。よし次、敵の
「強点なぁ……。先に上陸しとるけぇ、地の利があるくらいかのう。要は拠点が作れる。水場を押さえたはずじゃ。弱点は、泳いで行ったんじゃけぇ、物資が乏しい。しかも、籠城せにゃいかん。水がネックになる。水場を取られたら終わりということかのう」
「そこだな、やつらのアキレス腱は、水場だ」
ここで、先ほどからずっと目をつぶって考えごとをしていた黒沼が、吹っ切れたようにしゃべり出した。
「わかった! そうだよ。おかしいと思ったんだ。あいつらは、夜、歩けないんだよ。だから、明るくなる頃に上陸してきたんだ。明るいから保安庁に旗を揚げ替えたのがすぐに見つかって、山で拠点を作っている最中に日の丸に替えられちまったんだ。夜歩けるなら、もっと早い時間に上陸して、暗いうちに拠点を作るだろう。俺らならそうするよ」
丸々とした両目を輝かせる黒沼に、嵐も興奮気味に答えた。
「なるほど、そうじゃ、それじゃ! 俺らだって、夜間ノー・ライトで動けるようになるまでには結構時間がかかったもんな。奴らには、物が見えない状態で地形の特徴を読み取り、自己位置を判断する能力がないんじゃ!」
盛り上がる二人の前で藤井は、
「黒沼、電子チャートを起動しろ」
指示された黒沼は、待ってましたとばかりにパソコンを開けた。
「この尾根を通って、奈良原岳山頂へ上がる。上陸ポイントはここだ。東へ強い潮があるからな、流されながら陸岸に近づけば、この小さな湾には入りやすい。衛星写真を見ろ、ビーチがあるはずだ。岩場とビーチの境目に上陸する」
藤井が紙の地図上に示したルートを、黒沼がパソコンの電子地図にマウスでなぞった。
「上陸してから山頂まで、距離1・1キロ、高低差362メートル。20キロ担いで、所要時間は余裕をもって1時間です」
黒沼の背筋がピンと伸び、口調が早く、丁寧になった。
「そうか、01:00(マルヒト)に上陸だから、02:00(マルフタ)に山頂到着か」
「明日の日の出は、石垣島で06:18(マルロクヒトハチ)です。航海薄明は、05:15(マルゴウヒトゴウ)です。月齢8、上陸直後に沈みます」
嵐は動きを早め、標準語を使い始めた。
言動を変えたのは、自分の役目が変わったからだ。敵の腹を探るために3人で知恵を出し合う作業から、藤井が練る作戦の基本構想をサポートする立場となった。
藤井が今何を考えているか、黒沼と嵐は手に取るようにわかる。どのタイミングでどの情報を藤井に与えるべきかだけを考えている。藤井の頭の回転速度とともに、二人も同期して回転が速くなり、結果的に早口になる。
役目によって口調も態度も変わるのは、特別警備隊員の特徴の一つである。
「水が出る場所を考えると、拠点を作りそうなのは3ヶ所、いずれも山頂から750メートル離れています」
黒沼は、藤井の指示を待つことなく、パソコンの電子地図から魚釣島の連中が拠点を作りそうな場所を探し、山頂からそこまでの距離を計測した。
「3ヶ所あるのか……。山頂からは3人が分離して、単独でその3ヶ所へ向かうしかないな。奴らに感づかれないように、3時間かけてスネーク・オペレーション(音を出さない匍匐前進)とする。嵐、分速にしたら?」
「時速250メートルだから、分速4メートル」
「分速4メートルか、15秒で1メートル……。ギリギリだな。それ以上スピードを上げると音が出る……。そこに着くのが05:00(マルゴウマルマル)、航海薄明の15分前だ。奴らじゃまだ灯台付近に向けて移動開始できないが、動きはあるはずだ。夜の山を歩けない奴らだから、必ず音を出す。下手すりゃライトを使うかもしれない。動けばその瞬間に場所がわかる。よし、もういいな?」
黒沼と嵐は、二人揃って
「隊長、エムエム終了します」
「えっ、藤井、まだなんにも決まってないじゃないか」
「ここから先は、そこの空気を吸わないと決められません。そこには、奴らの不安、自信、恐怖、戸惑い、すべての感情が溢れ出しています。それを感じてから決めます」
「ああ、そうなのか……」
「確認しますが、政府の内意は、島の奴らを蒸発させろ、なんですね?」
「ああ。司令官はそう言ってる」
「必成目標(必ず達成しなければならない目標)は奴らを島から消す。なら、生かすも殺すもこちらの裁量ですね?」
「3日以内、隠密裏、蒸発。俺が直接聞いたのはその3点だ」
「ならば、奴らの心を完全に壊すことにします。思い出すだけで精神に支障をきたすぐらい追い込み、身体は無傷、心だけをササラモサラにしてから、島を出します。日本での恐怖体験を
「何だ、ササラモサラって? メチャクチャにするということか? とにかく隠密裏にやれ。わかったか」
隊長の久遠は、「自分が許可しなければお前たちは何もできないんだ」と伝えたかったが、うまく表現することができず、その場を去る藤井たちの後ろ姿を、ため息とともに見送った。
18時43分、日没の10分前に山口県岩国基地所属のMCH-101ヘリコプターが着陸した。全長が22・8メートルにも及ぶ大型の掃海・輸送ヘリであり、航続距離900キロを誇る。薄暗い機内に濃紺の突入服というつなぎを着た3人が乗り込んできた。クルーに示され、キャンバス生地の座席に座ると、クルーは藤井にだけヘッドセットを持ってきた。機長と会話をするためである。
「機長、感度ありますか? 特警隊の藤井です。お世話になります」
「はい、機長の
「了解です。我々は那覇をテイクオフしてから最終準備を開始します」
藤井は、左隣に座っている黒沼と嵐に、目をつぶりながら左手を枕のようにする仕草をして「寝ろ」と指示した。
ヘリが離陸すると、背負っていたバックパックの中から厚さ1ミリのワンピース型のウエットスーツを取り出し、冷たいヘリの床に布団を敷くように置く。バックパックを枕に、あっという間に眠りに落ちた3人が目を覚ましたのは、那覇空港へほぼ予定通りに着陸した時だった。
給油を開始した機内は、窓から入る空港ビルの明かりで人の存在はわかったが、3人がフェイス・ペイントをして顔を黒く着色すると見えなくなった。
布団代わりにしていたウエットスーツに着替え終わると、黒沼と嵐は、藤井に親指を突き立てた。最終準備が完了したという意味である。藤井は、右手の人差し指と中指を額に当てて、ゆっくりと回した。ヘリから洋上に飛び降りてから作戦が終了するまでを何パターンも想像し、シミュレーションしておけという意味だ。3人は、あぐらをかき、腕を組みながら、イメージ・トレーニングを開始した。
藤井の意識がシミュレーションから、機内にいる現実の自分に戻ったのは、クルーから肩をポンポンと2回叩かれたからである。クルーは、藤井の顔の前で指を3本突き立てた。降下ポイント到着3分前、3人は立ち上がり、機体右側の機長席後方の扉に向かった。職業ダイバーが使用する黒いダイビング・フィンのストラップに手首を通す。着水してからフィンを足に装着するためだ。
クルーが扉を開けると、眼下5メートルには時折白波の立つ真っ黒な海面が見えた。藤井は、扉から顔を突き出し、ヘリの進行方向に魚釣島灯台の弱い明かりを確認した。クルーに挙手の敬礼をすると、両手を胸の前で交差させフィンを抱えて飛び降りた。それに黒沼、嵐が3秒間隔で続く。
着水後、素早くフィンのストラップをかかとにひっかけ、足に装着すると、魚釣島に向かって藤井は進み出した。ダイビング・マスクもシュノーケルも装着していない。必要ないのだ。仰向けで額越しに灯台の明かりを見ながら、空中と、水面と灯台付近を警戒しつつ、強い海流に乗っていることを感じながら進んだ。魚釣島の北側を東に進む黒潮に乗って、徐々に島に近づいていく。
藤井は、砂浜と岩場の境目に海に向かって突き出ている大きな岩を発見すると、カウンター・ダイバーが潜んでいないかを確認しながら近づいて行く。右手はだらりと海底に向けている。
「ザクッ」指先が海底の砂に触れた。
水深が50センチ程度になった。くるりと身体を回転させ、顔を下に向けると、両手で海底の砂をかきながら進む。水深が20センチ程度になり胸が海底に触れるようになったところで、腕に装着していた刃渡り28センチ、グリップ14センチの水中格闘用ナイフを砂に突き立て、身体が波に持っていかれないようにしながら、
波の届かない位置まで来ると3人はゆっくりと仰向けになり、動きを止めた。視覚、聴覚、嗅覚に加え、皮膚の露出した前頭部で外気温を感知し、付近の状況を確認する。3人の脳内には、全身のセンサーが捉えた付近の状況が、暗視装置で撮影したような映像として浮かんでいた。そこには自分以外に体温を持つ2体が映り、それらを仲間として認識していた。さらに、その映像は3体の意識の中で同期しており、言葉、ハンド・シグナル、無線機などを使わなくても、仲間の意思を感じ取り、自分の意思を伝えることができた。
訓練あっての特殊部隊員の能力だが、彼らにしか使えない超能力というわけではない。一流のサッカーやバスケットの選手たちは、同様の能力を使って試合状況を把握し、チームメイトとの間で、高速で高度な意思疎通を図る。
藤井は顔を
失策とは、虫の
コオロギとバッタ類の虫が、無数に鳴いている。山に向かえば向かうほど盛んに鳴いている。人の住む地ではありえない音量が島全体に響いている。
平和の象徴の虫の音だが、スネーク・オペレーションにとっては最大の敵である。連中の拠点に近づく際、1分間で4メートル前進する計画だった。このスピードなら、相手が人間であれば、10メートル圏内を通過しても決して気づかれない。しかし、自然界の生き物はそこまで
のっけから予想外の敵が現れたが、どんな作戦計画にも必ず失策は含まれているものだ。そもそも事前情報がすべて正確なわけではないし、人はミスを犯すものなのだ。
[山頂までのスピードを上げて時間を稼ぐしかねえ。敵の拠点がいよいよ近づいたら、虫が鳴き止まないスピードにまで落とすだけのことだ]
集まってきた黒沼と嵐に、藤井は右手の人差し指と中指で腕時計を2回叩き、前方に素早く2回振り下ろした。「急げ」という意味である。二人は、藤井の意図を理解していた。彼らも上陸してすぐ、虫の音に気づいたからだ。
嵐が軽く頷いて藤井の脇を通り、山に向かって足早に進んだ。藤井は、嵐をぎりぎり認識できる3メートルの間隔で続き、最後尾の黒沼も同じ距離を藤井との間にとった。手榴弾や対人地雷のような爆発物が炸裂した場合の被害を最小限にするためである。
道のない山中を移動する際は、傾斜以上に植生の状態がスピードに大きく影響する。膝まで埋もれるようなシダが群生していたら、スピードは4分の1、体力の消耗は10倍になる。
幸い魚釣島は、植生が弱く、歩きやすかった。野生のヤギが下草を食べているからだ。海から上がった3人はずぶ濡れだったが、平均傾斜25度の斜面を時速1・5キロ、分速25メートルで歩を進め、ずぶ濡れの身体は体温が上昇して急速に乾いていった。
このスピードで山頂にいつ到着となるか、休憩を何分取ると体力がどれほど回復するか。藤井は計算しつつ、潜んでいる連中の身体から溢れ出るはずの感情のオーラをキャッチしようとした。この「感じる」というセンサーは、視覚や聴覚と同様に、訓練により研ぎ澄まされていた。人間にはまだ、科学で解明されない第六感や第七感があるのかもしれない。
突然、前方を歩く嵐がその場に伏せた。藤井も黒沼も慌てて伏せた。3人とも音を立てずに伏せたが、動きに驚いた蛍が一斉に光り出し、彼らのシルエットを浮き上がらせた。
こうなってしまうと、人間はどうすることもできない。ただじっとして、心の中で「蛍よ、落ち着いてくれ、落ち着いてくれ」と念じるしかなかった。
伏せた姿勢のまま藤井が前方をうかがうと、確かに嵐の先に“人”の気配を感じたものの、体温を感じることはなかった。生き物ではない。
「こっち側の人間じゃねえ、行け」と藤井が言うと、嵐は、何の
[なんの未練があるんだか知らねえけど、邪魔しねえでくれ。あっちの世界に行っちまった人の相手なんかしてる余裕はねえ]
歩き始めてから30分、毎日10キロ走っていても、口から心臓が出て来そうなほどキツい。あと10分で山頂に着き、そこで5分間動かなければ体力は回復するとわかっている。それでも、キツいものはキツい。
このキツさを少しでも和らげるために、藤井は自分の恐怖心を
[おかしい。何かがおかしい。奴らの警戒心をなぜ感じないんだ? 警戒心は必ず何かしらのシグナルを出す。なのに、ない。俺の感性が鈍っているのか? 奴らがシグナルを隠す技術を持っているのか? 俺が奴らの術中にはまっているのか?]
煽った恐怖心の効果は表れない。苦しさはピークだった。敵の存在圏まで1キロになろうというのに何も感じることができず、藤井は自分の感性を疑い始めた。
すると、3メートル先の嵐がこちらを向いて止まった。山頂に着いたのだ。
服で覆われていない嵐の顔だけが、宙に浮いていた。人間の身体は発光するのである。極めて微弱な光だから服を通すことはないし、肉眼では見えないとされているが、暗闇での訓練を重ねている藤井と黒沼の目にはぼんやり映る。
藤井は、右手の人差し指と中指の2本を立て、耳のあたりで横に2回グルグルと手首を回した。集合せよ、という意味だ。
3人はその場であぐらをかき、両肘を両膝の上に置いて、全員の額を突き合わせた。藤井がほとんど音になっていない声で話し始めた。
「奴らは、明るくなってから灯台付近に移動する」
黒沼が右手で藤井を制止するような仕草をした。
「それより、おかしくないですか? 奴らは今何をしているんでしょう? 何も感じない」
藤井は、嵐の顔を見て顎をしゃくった。
「俺もなんにも感じねえんだよ。まさか全員寝てる?」
「俺もだ。人間から漏れ出ちまう気のようなものがまったくない。このタイミングで俺たちが上陸してくることを、まったく予想していないのかもしれない。それほど日本をナメている可能性はある。甘く見ちゃいかんが、慎重になりすぎても“いくさ”にならねえ。予定通り、今から3人が分離してスネーク・オペレーションを行う。二人とも不安だけだな、嫌な予感はねえな?」
黒沼と嵐は首を横に振った。
「3人がそれぞれ向かう、水が湧きそうなところの1ヶ所は、今現在奴らがいる拠点だ。1ヶ所は、水場は作っただろうけど予備拠点で今は誰もいない。もう1ヶ所は、水場を作っていなければ誰もいない“はずれ”だ。奴らは日の出前に必ず動く。動けばピンポイントで場所がわかる。その時点では何もするな。そのまま行かせろ。3つのうちの拠点がどれなのかさえわかればいいんだ。奴らは保安庁が上陸する可能性のある昼間に灯台を離れることはない。一回すり抜けられてるから、離れるわけがない。だから、拠点さえわかれば、俺らは昼間ゆっくり、たっぷり、仕込みができる」
「仕込み?」
嵐が訊いたが、黒沼が制した。
「質問は最後だ。指示を全部出しちゃってください」
「よし。拠点と予備拠点それぞれに、水場が作ってあるはずだ。そこに、持ってきた
二人は親指を立てた。
「拠点を荒らされた奴らは、予備拠点に必ず移動する。その道中で仕留める。だから、俺らが次にすることは、拠点から予備拠点への移動ルート上にキル・ポイント(敵を引き込み、仕留める場所)を設定することだ。拠点を見つけた者は、予備拠点へのルートを探せ。簡単に見つかるよ、奴らは昨日の昼間そこを通ってるからな。4人以上が草を踏みしめ、蜘蛛の巣を引きちぎりながら、枝を折って往復したんだ。予備拠点を見つけた者は、拠点へのルートを探せ。これも簡単に見つかる。奴らは往復してるからな。キル・ポイントの細工は全員でやる。5分後に出発。ヘッドセットを装着しろ。今からは無線を使う」
3人が分離し、それぞれ自分の進むべき方向を確認していると、骨伝導式のヘッドセットから藤井の声が聞こえてきた。
「オール・ユニット、ディス・イズ・バッドマン(藤井のコールサイン)、ロメオ・チャーリー(「レディオ・チェック」:感度試験の頭文字RC)」
「ディス・イズ・スタッド(黒沼のコールサイン)、リマー・チャーリー(「ラウド・アンド・クリアー」:感明良好の頭文字LC)」
「ディス・イズ・アグレッサー(嵐のコールサイン)、リマー・チャーリー」
「ディス・イズ・バッドマン、ラジャー、コメンス・オペレーション(作戦開始)」
藤井は、ルミノックスの腕時計に付いているコンパスを、釣り用の極小ケミカル・ライトで照らし、自分が進む方向を確認していた。進行方向を確認すると、
この移動法を使ったのは、小枝を踏み折って音を出すことを避けるためである。静まりかえった山中において、ほんの数ミリの太さでも枝が折れる音はかなり響く。3人とも、つま先に鉄芯を入れた底の薄い地下足袋を履き、足の裏に意識を集中している。
山の頂上から拠点と思われる場所までの距離は750メートルだが、藤井は250メートルをキャット・ウォークで進み、残りの500メートルをスネークで進んだ。うつ伏せになって尺取り虫のように動くスネークを開始すると、全身で魚釣島を感じた。
1分間で3メートル弱しか進まないスネークで、最初に感じたのは島の匂いである。それは、虫、落ち葉、ヤギの排泄物、コケなど、魚釣島を形成する物すべてが発する匂いだ。一番強烈なのは蛇だった。やたら臭い。5メートル圏内に入れば必ずわかる。それもそのはず、蛇の名はシュウダ(臭蛇)である。危険を感じると、
藤井の位置は、目的地まで200メートルを切った。だが、いまだに何も感じず、まったく人の気配がない。かわりに地面の湿度が上がってきた。身体の前面がジメッとして、土の匂いが湿っぽい。
この付近で水が出る。藤井は確信した。同時に、ここが拠点でも予備拠点でもないこともわかった。
ここには100年近く、人間が入っていない。大自然の掟に従って、すべての生物が生態系という共助社会を形成している。すべてが噛み合い、リンクして生きている。
藤井は仰向けになり、大自然のリズムに自分の心拍と呼吸を合わせようとした。何かが繋がり、肉体が自然と同化し、魚釣島を形成している一部になっていく。このままずっとそうしていたいような、なんとも心地のいい時間だ。
そのうち、東の空が白み始めたが、誰からの報告も来ない。
[この時間に連中が動かないはずはない。動いたのに、それをあの二人が見逃すはずもない。何かがおかしい……。自分の無線が壊れていて、報告を受信できていないのか? 黒沼と嵐が奴らに見つかり、処理されてしまったのか? 奴らを術中にはめるはずが、実はこっちがはめられていて、包囲網がどんどん狭められている最中なのか?]
自分の作戦にどれほどの自信があろうと、派出した部下をどんなに信頼していようと、不安はつきまとう。その不安に耐えきれず、余計なことをした瞬間にすべてが崩れる。それが特殊戦であるということが藤井には痛いほどわかっていたが、無線で「状況知らせ」と訊き出したい衝動が消えることはなかった。
無線が正常に機能しているかどうかを確認するために……二人の生存を確認するために……と、衝動を正当化する理由は次から次へと湧いてきた。それらを抑え込んでいるうちに、完全に夜が明けた。
藤井の不安は頂点に達していた。
[俺が予想し、予定した通りに作戦が進んでいないことは間違いねえ。それなら、すぐに状況を掴み、作戦を変更しなきゃならない。不安に耐えるだけで成功するほど、特殊戦は甘くねえ。でも、今この不安に負けて動いたら、すべてをぶち壊すかもしれない……]
藤井は、決して答えの出ない堂々巡りの中にいた。
[よし、あと10分だけ待つ]
12分後、骨伝導式の無線スピーカーから声が流れてきた。
「ディス・イズ・アグレッサー、拠点への処置終わり。予備拠点へのルート上にキル・ポイント最適地を探す」
嵐だった。藤井は、ゆっくり長い息を吐き終えると、無線機のプレス・ボタンを素早く2回押した。了解したという意味である。その直後、「パチッ、パチッ、パチッ」と聞こえた。黒沼が了解したという意味である。藤井は、もう一度長く息を吐き、うつむいて「こんなもんだ。俺がはずれで、アグレッサーが拠点。スタッドが予備拠点か」と小さな声で呟いた。
10分だけ待つと決めたが、結局、10分以上待った。10分経った時に、堂々巡りの不安の中で、いくつかの歯車が噛み合い始め、いい波が手の届く距離まで来ている、5分以内に無線連絡が来る、という気がしたからだ。
流れに乗るか乗らないかの分かれ道は、10分が経過した時だった。あそこで動いてしまえば乗れなかっただろう。これが運を掴む、運を引き寄せるということなのだ。自分を信じて行動できないのなら、勝負事はしない方がいい。勝ち負けは、結果が出るだいぶ前に決まっている。
3分もしないうちに、今度は黒沼から無線が入った。
「ディス・イズ・スタッド、予備拠点への殺鼠剤の仕込み終了。拠点へのルート上にキル・ポイント最適地を探す」
要するに、拠点を作りそうな3ヶ所のうち、彼らが潜んでいた拠点を嵐が、予備拠点を黒沼が発見し、二人とも、殺鼠剤漬けの蟹を撒く等の処置を終えた。嵐は拠点から予備拠点の途中に、キル・ポイントに都合のいい場所を探し、黒沼は予備拠点から拠点へ向かいながら同様の場所を探しているのだ。
自分も移動しようと考えた藤井が足跡を消したり、倒した草を起こしたり、痕跡を消していると、再び嵐から無線が入った。
「ディス・イズ・アグレッサー、キル・ポイント最適地発見、ポジション113425。こちらへ来い」
嵐は、MGRS(ミリタリー・グリッド・リファレンス・システム)方式、NATO軍で使われる位置表示法で、自分のいる場所を知らせてきた。
「パチッ、パチッ、パチッ」(黒沼、了解)
「バッドマン、ラジャー。そちらへ向かう」
30分後、3人は顔を揃えた。
藤井は、つい先ほどまで不安や逡巡によどんでいたことなど嘘のように、自信に満ち溢れた表情で語りだした。
「奴らは夕方、最高の状態で拠点に戻ってくる」
「最高の状態?」
黒沼と嵐は、眉間に
「1日待っても保安庁は来ない。リーダーは焦るさ。日の丸を燃やしたことで保安庁がもう一度来てくれれば襲撃ができるから、一度すり抜けられた件も上級司令部にバレないが、来ないとなると、ミスを報告した上で作戦変更の打診もしなけりゃならない。上司に自分のミスを隠そうとする奴は、必ず部下に無理強いをする。やられた部下にしたら不信感しか湧かねえよ。焦燥感に駆られるリーダーと不信感にまみれる部下。最高の状態だ。拠点に戻ってみたら、水場に毒は撒かれてるわ、荷物は持ち去られてるわだ。負け“いくさ”のスパイラルの中を予備拠点に向かうはずだ。その時にここを通る。ワイヤーをキツめに張れ。キツめに張ればワナ線を切る寸前で気づく。そうなったら、嵐ならどうする」
「どこにまた、ワナ線が張ってあるかわからんから動けんよ。明るくなるまで、その場で耐えるしかないじゃろうな」
「そうだ。暗闇の中で動けない。そんな時に付近の虫の音が一斉に鳴き止んだだけで、途方もない不安に駆られる。突然、蛍が一斉に発光したら……。あの臭え蛇も上から落とせ。足音以外で生き物が移動している音も恐怖心をかき立てる。奴らの怯えのスイッチを際限なく入れさせろ。30分で仲間割れ、1時間で戦意消滅だ。3時間で精神がぶっ壊れる。こっちの姿を見せずに恐怖心を徹底的に煽れ。壊れたくらいで手を緩めるな」
嵐の目が
「ここまで来れば、もう軍事作戦じゃねえ。いじめの世界だ。アグレッサー、いじめとなれば、お前に敵う奴はいねえ。スタッドはアグレッサーがやり過ぎないように注意しとけ。いいな、仕留めるんじゃねえぞ。生かしたままだ。徹底的に追い込んで、最後に海に逃がせ。俺は山頂に用事がある」
翌朝、東の空が白み始めた頃、藤井は山頂で寝そべって、うつらうつらしていた。無線から黒沼の声が聞こえてきた。
「バッドマン、ディス・イズ・スタッド、マイク・チャーリー(ミッション・コンプリート:任務完遂の頭文字MC)、オーバー」
「ラジャー、カム・アップ・ヒア」
山頂に着いた黒沼と嵐は、垂直に切り立った崖の縁に10メートルほどの白い布が置いてあるのを発見した。黒沼が尋ねた。
「何ですかこれは」
「表札だ」
「表札?」
「ああ、特大の日の丸だ」
嵐が
「それをここから垂らすんかい? そういうの嫌いじゃん?」
「そういうのって何だ?」
「国旗とか、武士道とか、愛国心とか、嫌いじゃろ」
「そんなことねえよ。俺は、明確な意思も覚悟もないくせに、そういうものを担ぎ出して徒党を組もうとする自称愛国者とかが嫌いなだけだ。世の中の風潮が変わったら、あっと言う間に意見を180度変えそうで信用できねえ」
藤井の語りが勢いづいたところで、黒沼がストップをかけた。
「バッドマン、私たち相手なら構いませんがね、他では言わんでくださいよ。
「利用される?」
「隊長を見ていればよくわかるじゃないですか。奴のようにバッドマンのことを快く思ってない奴は、山ほどいます。あなたをコントロールする自信がないんですよ。そういうあなたがこの部隊にいることを是とする人もいますが、問題視している人の方が遥かに多いんです。平時はおとなしくしていてください」
「わかったよ」
藤井は、地面にあぐらをかいて、腕を組んで下を向いたまま答えた。
「ほんとにわかってますか? 勝負は、有事にしてください」
顔を上げ、黒沼の顔を見ると、眉毛を一瞬上に動かしてから、軽く頷いた。
「わかった。アグレッサー、表札を垂らして来い。この島に誰の息がかかっているのか示すんだ。奴らは、海にいる。そうならば、4ノット(時速約7キロ)以上ある潮で必ず南東に流されて、間違いなく魚釣島山頂の巨大な日の丸を見ることになる。死ぬ目に遭わせ、最後に逃がしてくれたのが誰かを思い知るさ。スタッド、酒を出せ。飲もうや」
「酒なんかないですよ。誰が持って来るんですか?」
「あるよ、お前のバックパックの一番下にヴォッカが入れてある」
「はあ、自分で持ってくればいいでしょ。何で俺のに入れるんですか」
「結構、重いからな」
「バッドマン、人としておかしいですよ……」
「まあ、怒るなよ。もうすぐ夜が明ける。夜明けを見ながら飲もう。最高の景色が見れる」
黒沼が苦笑して、自分のバックパックからヴォッカのボトルを取り出して開けた。
「アグレッサー、どうやって追い込んだんだ?」
「どうやって追い込んだ? バッドマンがヒントを言ってたじゃねえかよ。そんなことより、強さと弱さの違いがよくわかったよ」
黒沼から渡されたヴォッカを一口飲み込んだ藤井は、嵐を見ながら、ヴォッカを黒沼に戻した。
「なんだそりゃ?」
「あいつらの不安と恐怖が最高潮に達したのは、深夜、暗闇で追い込んでる時じゃなかったよ。俺は、いつ、どこから、どんな者が、どうやって襲ってくるのかがわからない状態で追い詰めて、メンタルをブチ壊してやろうと思っとった。でも、壊れそうで壊れねえんだ。『背水の陣』とは、よく言ったもんよ。奴らは、明るくなるまで、ここで耐えるしかないと思ってるから強いんだ。それがよ、明るくなってきて、作っといてやった海へと通じるたった一つの退路に奴らが気づいた瞬間に壊れたよ。見えない敵にでも対峙している時は耐えられるんだよな。それが一旦背中を向けちまったら最後、とめどない恐怖にかられて、仲間を蹴散らし、我先にと、そこに殺到して行った。その時の奴らの顔が忘れられねえ。俺たちも一緒だぜ。ああなるよ。任務を捨てて、敵に背中なんか見せたら途端に弱くなるぜ。奴らを見てて、こっちが怖くなった」
藤井から渡されたヴォッカを、喉を鳴らしながら2回流し込んだ黒沼は、ボトルを嵐の目の前に突き出した。
「バッドマンはアグレッサーがやり過ぎないように見とけと言いましたがね、逆でした。奴らがパニックになって、任務を捨て、仲間を忘れ、我が身だけを考え始めたら、アグレッサーの情が揺れてました。手を緩めるんじゃないかと思うほどでしたよ」
藤井は、飲み終わった嵐からボトルを受け取って、一口飲んだ。
「そこがアグレッサーのいいところだし、ダメなところよ。時には、その似合わねえ優しさを捨てて、お前の顔みたいに残虐にならんと、任務を逃すぞ」
黙ってうつむきながら、一回だけ頷く嵐を見ながら、藤井は続けた。
「でもよ、半狂乱で逃げ惑う奴らを見て有頂天になるような奴と生きていく気はしねえし、一緒に死ぬ気にもなんねえよ。矛盾してんだけど、その
藤井は空を見て大きく息を吐くと、すっくと立ち上がって、嵐にボトルを渡して言った。
「残りは飲んじまいな。帰ろう。ヘリを呼べ」
現場で作戦を実行した藤井、黒沼、嵐の3人は、任務を完全に達成したというのに虚脱していた。
一方、この作戦を強引に推し進めた手代木は、得意満面だった。自分の主張した方針で危機は収まった。防衛庁長官時代に深く関わった海上自衛隊の特殊部隊が期待通りの成果を収めたのだ。
しかし、誰にもホッとしている暇はなかった。まもなく、日本の安全保障を揺るがす大きな事件が勃発し、陸海の特殊部隊が投入される時が迫っていた。自分の運命が時代の渦に巻き込まれていくことを予期した者は、誰一人としていなかった。