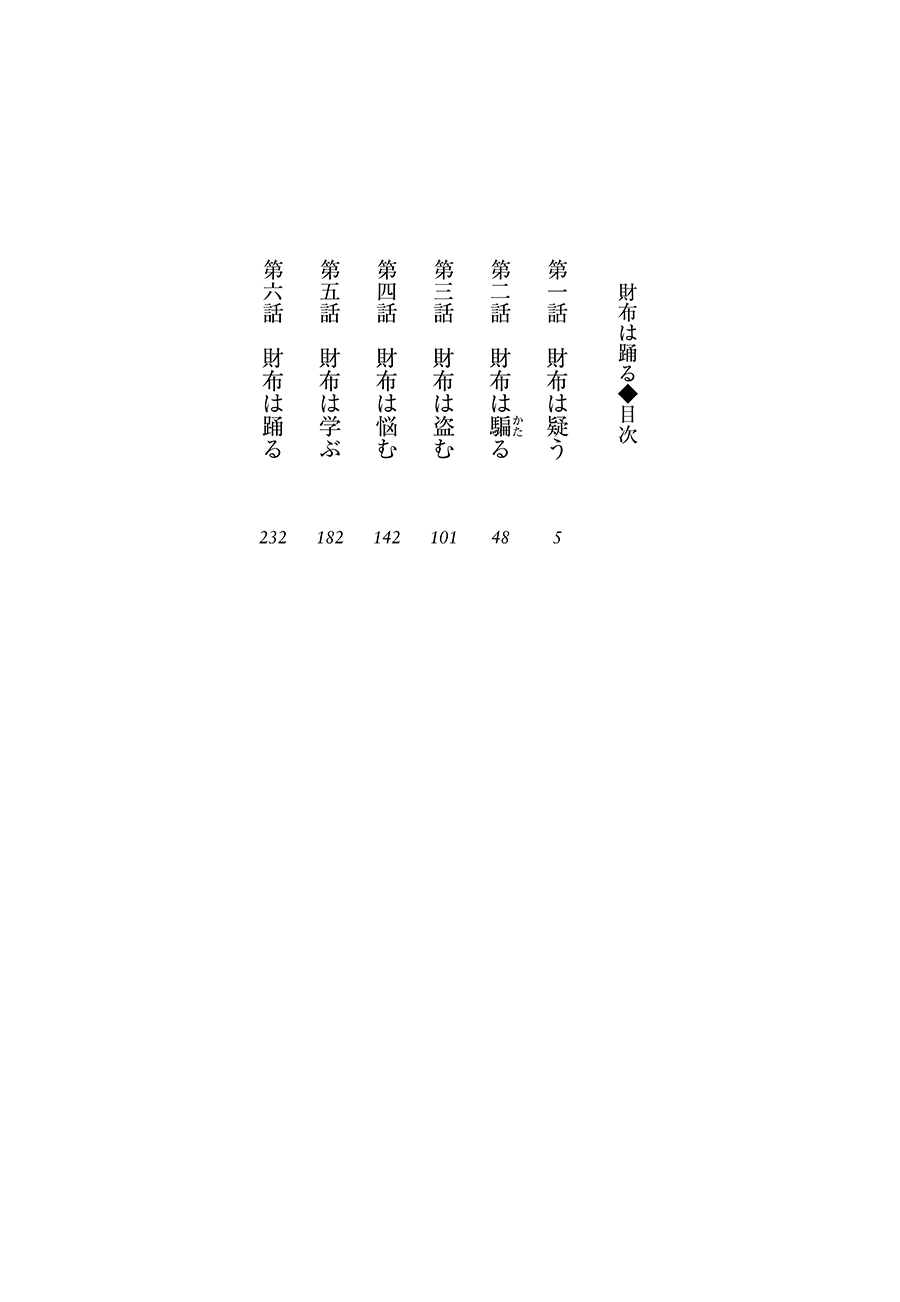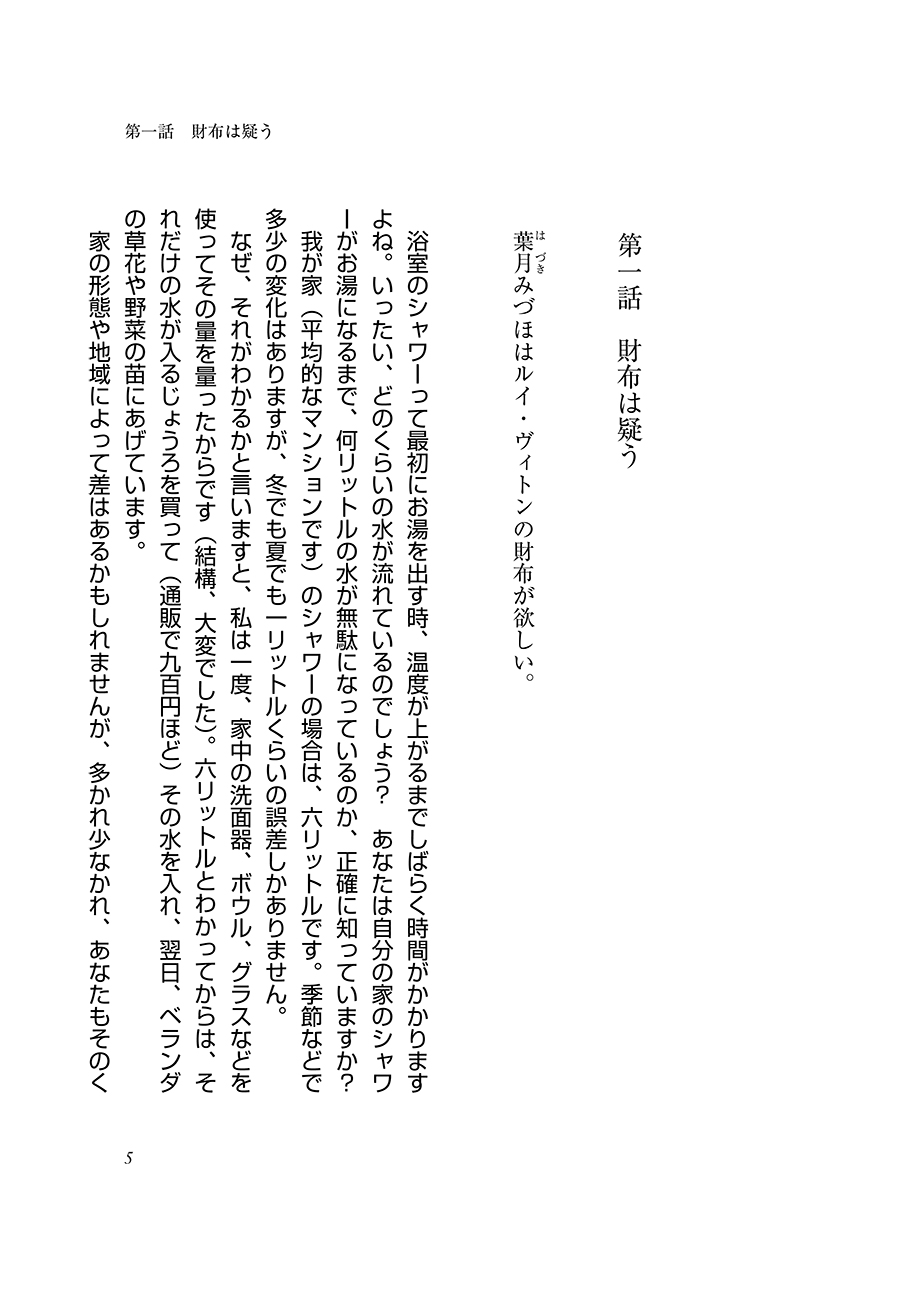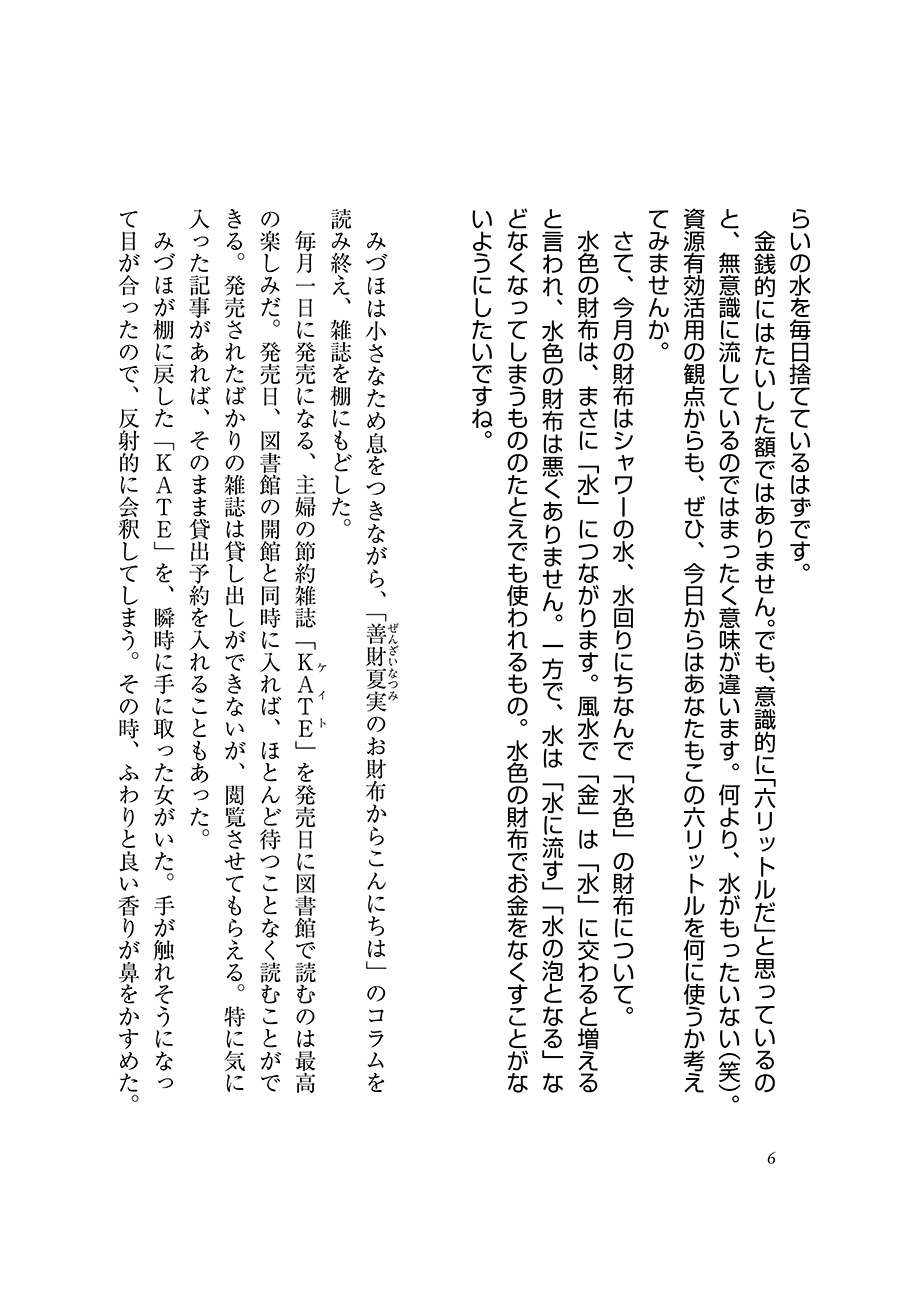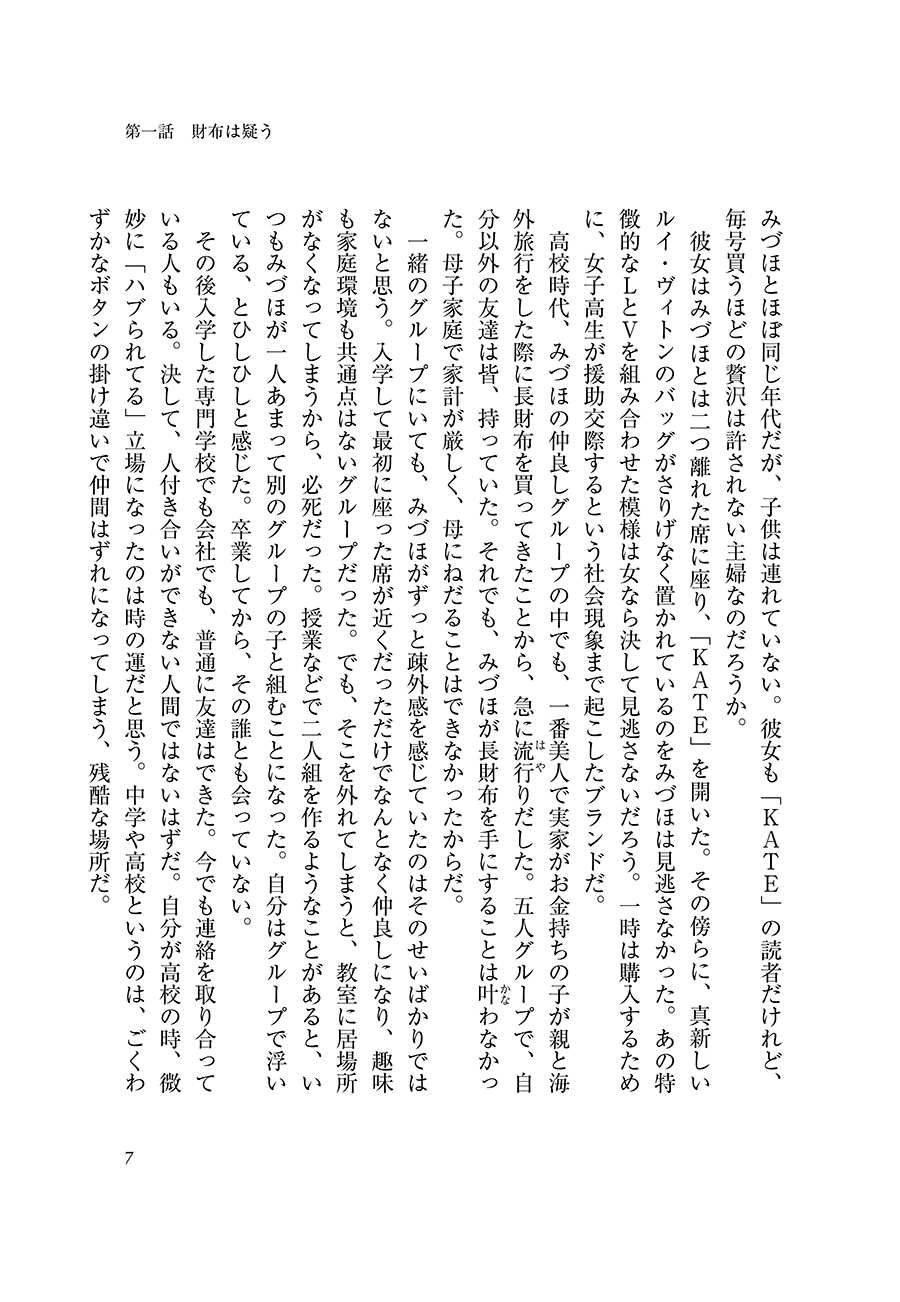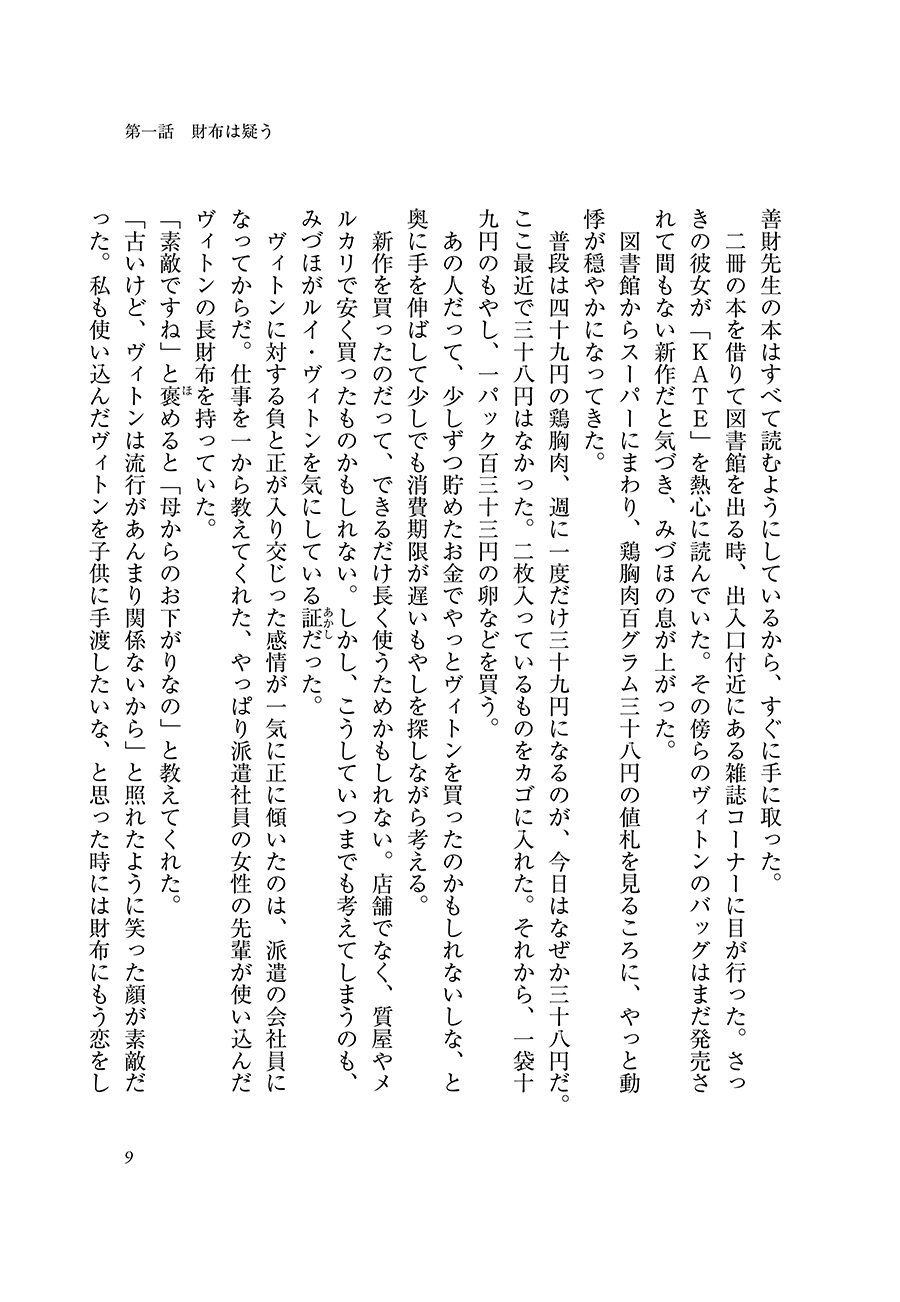第一話 財布は疑う
葉月みづほはルイ・ヴィトンの財布が欲しい。
浴室のシャワーって最初にお湯を出す時、温度が上がるまでしばらく時間がかかりますよね。いったい、どのくらいの水が流れているのでしょう? あなたは自分の家のシャワーがお湯になるまで、何リットルの水が無駄になっているのか、正確に知っていますか?
我が家(平均的なマンションです)のシャワーの場合は、六リットルです。季節などで多少の変化はありますが、冬でも夏でも一リットルくらいの誤差しかありません。
なぜ、それがわかるかと言いますと、私は一度、家中の洗面器、ボウル、グラスなどを使ってその量を量ったからです(結構、大変でした)。六リットルとわかってからは、それだけの水が入るじょうろを買って(通販で九百円ほど)その水を入れ、翌日、ベランダの草花や野菜の苗にあげています。
家の形態や地域によって差はあるかもしれませんが、多かれ少なかれ、あなたもそのくらいの水を毎日捨てているはずです。
金銭的にはたいした額ではありません。でも、意識的に「六リットルだ」と思っているのと、無意識に流しているのではまったく意味が違います。何より、水がもったいない(笑)。資源有効活用の観点からも、ぜひ、今日からはあなたもこの六リットルを何に使うか考えてみませんか。
さて、今月の財布はシャワーの水、水回りにちなんで「水色」の財布について。
水色の財布は、まさに「水」につながります。風水で「金」は「水」に交わると増えると言われ、水色の財布は悪くありません。一方で、水は「水に流す」「水の泡となる」などなくなってしまうもののたとえでも使われるもの。水色の財布でお金をなくすことがないようにしたいですね。
みづほは小さなため息をつきながら、「善財夏実のお財布からこんにちは」のコラムを読み終え、雑誌を棚にもどした。
毎月一日に発売になる、主婦の節約雑誌「KATE」を発売日に図書館で読むのは最高の楽しみだ。発売日、図書館の開館と同時に入れば、ほとんど待つことなく読むことができる。発売されたばかりの雑誌は貸し出しができないが、閲覧させてもらえる。特に気に入った記事があれば、そのまま貸出予約を入れることもあった。
みづほが棚に戻した「KATE」を、瞬時に手に取った女がいた。手が触れそうになって目が合ったので、反射的に会釈してしまう。その時、ふわりと良い香りが鼻をかすめた。みづほとほぼ同じ年代だが、子供は連れていない。彼女も「KATE」の読者だけれど、毎号買うほどの贅沢は許されない主婦なのだろうか。
彼女はみづほとは二つ離れた席に座り、「KATE」を開いた。その傍らに、真新しいルイ・ヴィトンのバッグがさりげなく置かれているのをみづほは見逃さなかった。あの特徴的なLとVを組み合わせた模様は女なら決して見逃さないだろう。一時は購入するために、女子高生が援助交際するという社会現象まで起こしたブランドだ。
高校時代、みづほの仲良しグループの中でも、一番美人で実家がお金持ちの子が親と海外旅行をした際に長財布を買ってきたことから、急に流行りだした。五人グループで、自分以外の友達は皆、持っていた。それでも、みづほが長財布を手にすることは叶わなかった。母子家庭で家計が厳しく、母にねだることはできなかったからだ。
一緒のグループにいても、みづほがずっと疎外感を感じていたのはそのせいばかりではないと思う。入学して最初に座った席が近くだっただけでなんとなく仲良しになり、趣味も家庭環境も共通点はないグループだった。でも、そこを外れてしまうと、教室に居場所がなくなってしまうから、必死だった。授業などで二人組を作るようなことがあると、いつもみづほが一人あまって別のグループの子と組むことになった。自分はグループで浮いている、とひしひしと感じた。卒業してから、その誰にも会っていない。
その後入学した専門学校でも会社でも、普通に友達はできた。今でも連絡を取り合っている人もいる。決して、人付き合いができない人間ではないはずだ。自分が高校の時、微妙に「ハブられてる」立場になったのは時の運だと思う。中学や高校というのは、ごくわずかなボタンの掛け違いで仲間はずれになってしまう、残酷な場所だ。
それでもあの時、自分がヴィトンの財布を買うことができていたら、もう少し楽に青春時代を送れていたのではないかと時々考えてしまう。
図書館で会った女性が「KATE」を開いているのを見て、最初は「仲間だ」と嬉しくなったのに、ヴィトンのバッグを見てから急に、自分が手放した雑誌が惜しくなった。ヴィトンからは強烈な憧れと苦味の感情がないまぜになって漂ってきた。もっと隅から隅までよく読めばよかった。最後の方の「夏の麺料理三十番付!」の特集はいつもと同じだから、と読み飛ばしてしまった。
しかし、一度手放した「KATE」はもうしっかり彼女の手に握られてしまって返ってこない。
「ヴィトンのバッグを持てるなら、雑誌くらい買えばいいのに」
気がついたら小声でつぶやいていた。
みづほは諦めて、ベビーカーを押しながら雑誌コーナーから小説コーナーに向かった。ベビーカーの中の息子、圭太はよく寝てくれる。今、十ヶ月だが、はいはいができるようになった一ヶ月ほど前から急に寝付きがよくなり、聞き分けもよくなった気がする。
小説は最近、ミステリーしか読まない。宮部みゆきの時代ミステリー小説があったから借りることにした。みづほは自分でもよく本を読む方だと思う。今は子供が小さいからまとまった読書時間を取ることはできないが、宮部みゆきの小説は切れ切れでも内容が頭に入ってくるから好きなのだ。
それから、「家庭・家計」のコーナーも見る。そこで、善財夏実先生の『婚活女子はピンクの財布を持て』を見つけた。婚活女子というところは既婚のみづほには合わないが、善財先生の本はすべて読むようにしているから、すぐに手に取った。
二冊の本を借りて図書館を出る時、出入口付近にある雑誌コーナーに目が行った。さっきの彼女が「KATE」を熱心に読んでいた。その傍らのヴィトンのバッグはまだ発売されて間もない新作だと気づき、みづほの息が上がった。
図書館からスーパーにまわり、鶏胸肉百グラム三十八円の値札を見るころに、やっと動悸が穏やかになってきた。
普段は四十九円の鶏胸肉、週に一度だけ三十九円になるのが、今日はなぜか三十八円だ。ここ最近で三十八円はなかった。二枚入っているものをカゴに入れた。それから、一袋十九円のもやし、一パック百三十三円の卵などを買う。
あの人だって、少しずつ貯めたお金でやっとヴィトンを買ったのかもしれないしな、と奥に手を伸ばして少しでも消費期限が遅いもやしを探しながら考える。
新作を買ったのだって、できるだけ長く使うためかもしれない。店舗でなく、質屋やメルカリで安く買ったものかもしれない。しかし、こうしていつまでも考えてしまうのも、みづほがルイ・ヴィトンを気にしている証だった。
ヴィトンに対する負と正が入り交じった感情が一気に正に傾いたのは、派遣の会社員になってからだ。仕事を一から教えてくれた、やっぱり派遣社員の女性の先輩が使い込んだヴィトンの長財布を持っていた。
「素敵ですね」と褒めると「母からのお下がりなの」と教えてくれた。
「古いけど、ヴィトンは流行があんまり関係ないから」と照れたように笑った顔が素敵だった。私も使い込んだヴィトンを子供に手渡したいな、と思った時には財布にもう恋をしていた。
ヴィトンの財布は修理しながら何十年も使えるらしいし、古くなっても売ることができる。無駄遣いを絶対許さない雑誌「KATE」でさえ、「良いものを買って長く使う」ことの象徴としてヴィトンだけは勧めているくらいだ。善財先生も、著作の中でブランドものの長財布を持つことを奨励し、中でもヴィトンは「値段と品質が釣り合い、運気もいい」「日本で一番始末がいいと言われている名古屋人もヴィトンには財布の紐を緩める」と書いていた。みづほが今使っているのは、OLの時に買った黒いエナメルの二つ折り財布だ。始めての給料が入った時に、なんとなくデパートの小物売場で買った。悪くはないがこれといった特長もない。
「KATE」には、毎月必ず、主婦が登場して一ヶ月の家計簿を公開するコーナーがある。皆、食費を切り詰め、無駄を省いて、二十万円台、三十万円台の給料の中から五万、八万と貯金している。このコーナーに載ることは「KATE」愛読者の憧れであり、彼女たちはスター主婦だった。
記事は大抵、昔はダメダメ主婦で貯金ゼロだったとか、独身時代、給料を湯水のように使っていたというところから始まり、結婚、出産、または夫のリストラ、転職などの経験を通して、節約と貯蓄に目覚める様子が描かれている。
彼女たちがお金を貯める理由で、「マイホーム購入」「子供の学費」と並んで多いのが「海外旅行」と「ブランド財布購入」だった。
みづほもヴィトンの財布を手に入れたら、何十年も使うつもりだ。これから圭太が大学を卒業するまでの二十二年は続く節約生活も、ヴィトンの財布を眺めながらだったら頑張れると思う。洋服や靴はGUや古着でも、バッグからヴィトンの財布を出せば、そうみすぼらしくは見えないはずだ。
海外旅行は、専門学校時代に女友達と韓国のソウルに行ったことがある。冬の韓国はやたらと寒く、街はごちゃごちゃしていた。食べ物はどれもおいしかったけど、ガイドブックどおりに格安コスメを買って、マッサージを受けただけで帰ってきた。特に大きな思い出はない。
あの時、ヴィトンのものを何か一つでも買ってくれば良かった、といまだに後悔が残る。長財布を買えるほど貯金はなかったが、キーケースでも買っていれば今頃少しは気持ちが違ったはずだ。
新婚旅行は沖縄だった。本当はハワイに行きたかったけれど、夫の「パスポートとかめんどい」「英語話せない」「高い」という声に押し切られて沖縄にしてしまった。とはいえ、せっかくだからとそこそこ高級なリゾートホテルに五日間も滞在したから、今思えば、結果的にはハワイとそんなに費用が変わらなかったかもしれない。
どちらも、もっと主体的に旅行を楽しめば良かった。次は絶対に後悔しない旅にするつもりだ。
そのため、みづほは二年近く、ずっと計画を練っていた。
帰宅したみづほは、息子と一緒に昨夜の残り物で昼ご飯をすませ、お昼寝させて、夕食の下ごしらえをした。
買ってきた鶏胸肉は繊維を断ち切るようにして縦に七、八ミリの厚さに切って、スーパーでもらってきたポリ袋に入れた。肉一枚に醤油小さじ二杯を揉み込み、マヨネーズを大さじ一入れてさらによく揉んだ。
夕方、夫の雄太からLINEで「帰宅します」という連絡がくると、漬け込んだ胸肉に片栗粉大さじ二を加えてまたよく揉んだ。あとはそのまま揚げるだけで柔らかく癖のない「鶏胸肉の唐揚げ」ができる。
買ってきたもやしと卵もごま油で炒めた。最後に鶏がらスープの素と片栗粉、小さじ一ずつを水に溶かしたものを加える。うまみがこってりともやしにからんだ、中華風の炒め物ができ上がった。
この唐揚げともやし炒めはみづほ自慢の献立だ。もやし十九円、卵二つで二十六円、胸肉一枚が百二十円弱だから、二百円以下でボリュームも味も満点の夕食ができる。これにご飯とわかめスープをそえた。
唐揚げは時に甘酢で和えたり、カレー粉を加えたりすると、味が変わって飽きない。どれも夫の大好物である。
夕食ができ上がると、離乳食を圭太に食べさせた。昨日、カレーを作る時に煮た、ジャガイモや人参をつぶしたものだ。他に、手作りのプリンもデザートに用意した。
しかし、口に入れたジャガイモも人参も、圭太はべーっと舌を使って出してしまう。そのままベビーチェアのテーブルに落ちた野菜を指でいじっている。
みづほは大きなため息をついた。
圭太が小食なことが、唯一の、でも、大きな悩みだった。
とにかく、食べない。食べ物を落としたり、それで絵を描いたり、食べ物で遊ぶ。みづほが怒ると、かまってもらえると思うのか嬉しそうにきゃっきゃっと笑い、もっと怒ると泣き出して、それ以上何も食べなくなる。一度、あんパンを食べさせたらよく食べたので、次の日も買ったら一口も食べなかった。そんなふうに、初めだけよく食べてぬか喜びさせることも、よくあった。
なだめたりすかしたりして、あれやこれやとやってみるのだが、いまのところ、これといって有効な対策はなかった。
「体重が増えていれば大丈夫ですよ」と小児科の先生にも言われるし、「そのうち食べるようになるわよ」と母にも言われる。
「親が気にしすぎるのもよくないみたいよ」
母親教室で出会ったママ友の「彩花ちゃんママ」もそう言う。それは、彩花ちゃんがなんでも食べる健康優良児で、お相撲さんみたいに太っているから言えるのだ。
まあ、圭太みたいにほっそりしているのと、白鵬をミニチュアにしたみたいな彩花ちゃんとどっちがいいのか、と聞かれたらちょっと返事に窮する。
みづほの心づくしの手作りプリンも圭太は二口ほどしか食べなくて、三口目からはべーっと吐き出した。
圭太がベビーチェアのまわりにこぼした食べ物を、床を這いずるように拭いていると、ドアが開く音がして夫の雄太が帰ってきたことがわかった。
「お帰り!」
ただいま、と答えてくれたのかどうか、下を向いていたからよく聞こえなかった。でも、あまり気にしない。雄太はそういう人だ。ただ、「暑い、暑い」とつぶやいているのだけが聞こえてきた。
ベビーチェアの下から立ち上がって、顔を上げた時に雄太は居間にいなかった。寝室で着替えているのだろう。
「ねえ、そんなに暑いならシャワーで先に汗を流したら」
寝室の入口まで行って呼びかける。思った通り、彼はシャツ姿になり、鞄を床に置きながらネクタイをほどいていた。やはり返事はない。
新築の1LDKの賃貸マンションは、西新宿から電車で約三十分の練馬区の駅から、歩いて八分と言われて借りた。実際には十分以上かかる。みづほはもう少し埼玉よりなら家賃もずっと安いのに、と思ったけれど、「通勤時間が長くなるのが嫌だ」と夫に言われて、折れた。
母が住んでいる川越まで行けばずっと安いはずだ。けれど、実家に近いところに住みたいのか、と夫の両親に嫌味を言われるのが怖くて言い出せなかった。
駅から少し坂になっているから、蒸し暑い日はつらい。
「ねえ、先にお風呂に入ったら?」
雄太はまだ鞄から何かを取り出そうとしている。
「ねえ?!」
きつめの声を出して、やっと「ん」と振り返った。
「先にお風呂に入ったら、って言ってるの」
「……いい」
雄太は無表情で答えた。
「さっきから何度も言ってるのに……鞄になんかあったの?」
「いや、パソコン出そうと思って」
そんなに暑いなら、先にシャツを脱いで汗を拭くか、部屋着に着替えるかしたらいいのに。夫の行動に軽いいらだちを覚える。
「シャツ脱いでくれたら、洗濯機に入れるけど」
「いい、まだ」
鞄からうまくパソコンがでてこないらしく「ああっ、暑いなっ」と、怒鳴っていた。
寝室を離れながら、小さくため息をつく。
夫の雄太にはこういうところがある。何か一つのことに夢中になってしまうと周りが見えなくなり、声も聞こえなくなること。正常な判断ができなくなること。
だからといって彼が嫌いになったりするわけじゃないし、男性にはありがちな不器用さだなとも思うのだが、いちいち細かいことを注意しなければいけない時は、「私、お母さんみたい」と思って情けなくなる。
一度、夫の実家で「雄太さんて、夢中になると周りが見えなくなりますよね」「物事の順番を正しくわからない時がありますよね」とさりげなく聞いてみたことがあった。
「そうなの、子供の頃からなのよお」
困っちゃうわね、と言いながら、義母は嬉しそうだった。そして、なぜか、雄太が小学生の頃、どれだけ成績が良かったか、特に算数はよくできて、先生を困惑させるような質問までした、というようなことを自慢げに話された。
あんたがちゃんと育てないから、生活音痴な息子になるんだよ、と心の中で毒づいたけれど、確かに彼にそういう、強いこだわり、オタク的要素があるからこそ、今のシステムエンジニアという仕事に向いているのかもしれない。
しばらくして、雄太はやっとTシャツに着替えて寝室から出てきて、食卓についた。彼は服装にこだわらない。高校時代に買ったという、プリントの消えかかったガンダムのTシャツを着ている。
「今日、ゆうちゃんが好きな唐揚げだよ」
「うん」
あまり反応はないが、これもまた気にしないことにしていた。おかずを並べてやると、もくもくと食べ始めた。
「おいしい?」と尋ねて、やっと思い出したように「ああ」と素直にうなずいた。
多少は不満もあるが、彼にはいいところもたくさんある、と唐揚げを頬張っている口元を見ながら思う。
家庭のことについてはみづほの好きなようにやらせてくれる。喧嘩すれば大きな声を上げることはあっても、暴力なんかは振るわない。ちゃんとお給料を稼いでくれて、特別ケチということもない。月給は手取り三十万前後で、二十代後半の男性としたらまあ平均的ではないだろうか。ボーナスも入れれば、年収四百五十万以上はなる。
今の時代、このくらいのところで十分満足だと思うべきではないだろうか。
みづほは埼玉県の川越市で生まれた。今でも母はそこに住んでいる。両親はみづほが高校生の頃、離婚した。
父は細かい男で、時々怒鳴ることもあった。母がおおざっぱな性格だったから、うまがあわなかったのだろう。離婚すると言われた時も正直、あまり驚かなかった。みづほも高校生になっていたし、二人がほとんど口を利いていないことも知っていた。
父が養育費を払ってくれたので、ヴィトンの財布は買えなかったが専門学校には行けた。IT関係の専門学校を出た後、西新宿に本社がある、雄太と同じメーカーに派遣社員として入った。
みづほは営業部の営業補助だった。舌先三寸で仕事をし、多少強引な行動もむしろよしとするような、偽悪的でマッチョな営業マンたちに馴染めないものを感じていた。ある時、営業マンたちの同期と飲み会をすることがあり、出会ったのが三歳年上のエンジニア、雄太だった。身体を鍛えるのが流行っていた営業部の男たちを見慣れている中で、ほっそりした雄太の体型と横顔は清潔感にあふれて見えた。みづほから声をかけたのがきっかけで二年間の交際の末、結婚した。
結婚当初は二人で社宅に住んでいたけれど、息子の妊娠とともにそこを出て、このマンションに引っ越した。妊娠初期からつわりがひどく、人員削減一辺倒の部内にかばってくれる人もいなくて、結局、仕事はやめてしまった。仕事を教えてくれた先輩も、ステップアップのために転職をしたあとで、心の拠り所を失ったような気もしていた。
雄太のお小遣いは本人の希望も受け入れて、毎月五万。家賃は管理費も含めて十万八千円、みづほは食費、日用品代、そして、お小遣いを含めて五万円を渡されていた。他に、水道光熱費、通信費、子供の学資保険、雄太の貯蓄型保険などを引くと、ほとんど残らない。
雄太の小遣いも「KATE」に出ている家計などを見ると少し多い気がしているが、外食をしたり、レジャーに行ったりする時は彼が払ってくれることになっている。ただ、お給料日に、雄太は「僕の小遣い五万、それから、みづほちゃんも五万」と言いながら渡す。五万は食費や日用品代も含んだ金額で、節約しなかったらいくらも残らないのに彼は私のお小遣いのように考えているのではないか。毎月そう言われるたびに密かに不満だった。
本当は、家賃ももう少し安くおさえたい。でも当時、新築だったマンションを夫が一目で気に入って、ほとんど独断で決めてしまって住み続けている。
結婚前、気が合わない両親を見てきて、穏やかな家庭さえ築ければ収入は普通でいいと思っていた。今は仕事をやめたことを後悔している。あの時、無理をしても頑張って働き続けていれば生活にもっと余裕があったのではないか。圭太がもう少し大きくなれば、また派遣かパートで働くつもりだ。
そんな不満も、この秋には多少解消しそうだった。
二年ほど前から、みづほは月に二万円ずつ貯めていた。
五万の中から、食費約二万に日用品代(そこには十ヶ月前からは圭太のおむつ代なども含まれている)を引いたら、二万を貯金するためには自分が自由にできるお金はほとんど残らない。
みづほは貯金を始めてから、ほとんど服を買っていなかった。
実家に帰った時に、母に「これ、派手すぎるからみづほ着ない?」などと手渡されたチュニックやカットソーをもらう。母には行きつけのブティックがいくつかあって、店員とはほぼお友達状態だ。勧められるとすぐに買ってしまうらしい。通販も好きで、下着やストッキングはまとめ買いしている。そんなものも、実家に行くたびにもらってきた。
他にはメルカリでシーズン遅れの千円台の服をさらに値切って買う。ユニクロは高いし、ママ友とかぶる可能性大だ。それなら、駅ビルに入っているようなブランドの服を千円台で落札した方が安いし、よく見える。
お金がない分、みづほのワードローブには不要なものが一つもない。ワンシーズン着なかった服はすぐにメルカリに出品し、数百円でも利益が出ればそれを資金に、次シーズンの服を買う。おしゃれだと褒められることはなくても、みすぼらしいほどではないはずだと自負している。
「爪に火を点す」ほどではないが、無駄は一つもせずに五十六万まで貯めてきた。あと数ヶ月で六十万を超える。六十万を超えたら雄太に告白し、ハワイ旅行を提案するつもりだ。最初は三人で三十万くらいでなんとかならないかと思っていたけれど、それではビーチから遠い最低ランクのホテルにしか泊まれないし、向こうでもろくなものを食べられないとわかってきた。ハワイのことを知るにつれ、欲が出てくる。貯金が四十万を超えた時、せっかくだからもう少しがんばろうと思った。
みづほには学生時代のアルバイトや会社員時代に貯めたお金が、合わせて四十万ほどある。それで、ヴィトンのお財布を買い、ウルフギャングでステーキを食べたい。圭太にもハワイにしかないような鮮やかな服を買ってあげたい。いつもはメルカリやフリーマーケットで買ったものばかりだから。
みづほはハワイについてのスクラップブックを作っていた。行ってみたい店、食べてみたい料理、泊まりたいホテル、ハワイ旅行のツアー広告……素敵なハワイの写真があれば、なんでも切り取って貼っておく。節約に疲れたり、ママ友の高そうな服やバッグを見て悲しくなったりした時には、それを広げる。
一ページ目は、ハワイのどこかの海岸で手をつないでいる親子の後ろ姿の写真だ。二人はおそろいの派手なドレスを着て、髪を風になびかせている。自分もこんな写真が撮りたい。撮った写真はインスタやLINEに載せよう。いや、あまりこれ見よがしにするとママ友から褒められているのか、ディスられているのか、わからないようなコメントをもらってしまうかもしれない。
でも、二年も貯金をしてきたのだ。一枚くらいはいいだろう。自分と息子が海辺に立つ後ろ姿の写真、ベスト・ショット一枚だけならいいということにしよう。それ以上は、「ハワイに行ってきたの? 写真を見せて」と言ってきた人だけに見せることにしよう。
ヴィトンの財布を買う時のこともずっと考えている。一度新宿店に行って下見もしてきた。店内は外国人の観光客ばかりで、ショーウィンドーをこわごわのぞいただけで、店員に声をかけることもできずに帰ってきた。けれど、ハワイではちゃんと「これ、いただくわ」と言うつもりだ。
あ、英語じゃないといけないのかな、と心配になる。韓国に行った時は買いたいものを指差して「ディス、ディス」と言った後、「全部ちょうだい」と身振り手振りと日本語で買い物できたけど。いや、きっとハワイだってそんな感じで大丈夫だろう。
「これ、いただくわ」
「これ、ください」
「あれも見せて」
息子を寝かしつけ、残業の夫の帰りを待つ間、気がついたら独り言を言っていた。ルイ・ヴィトンの店舗で買い物できるのは一生に一度きりかもしれないのだから、わがままを言わせてもらおうと思う。
テレビもつけずにスクラップブックを見ながら、想像するだけで十分楽しい。テレビはかなり電気代がかかると善財先生も言っているし。
やっと目標額に達した日、晩ご飯に普段通りの節約メニューが並んだ食卓の前で、夫の雄太が箸を取る姿を見ながら、みづほはちょっと震えていた。
ハワイに行きたい。お金は貯めた。
それを言って、彼がどんな反応を示すのか。
雄太は厳しい夫というわけでもないし、ケチでレジャーに一円も使いたくないというような人間でもない。たぶん、喜んでくれると思う。ただ、早急にことを運び過ぎたり、変化が大きいと、みづほが思ってもみないような反応をすることがある。以前、海外で暮らしている日本人の特集番組を観ていて、「圭太を外国の学校で勉強させるっていう選択肢もこれからの時代はあるのかもしれない」と何気なくつぶやいたら、「俺は英語もしゃべれないし、海外で仕事なんかできないからな! 親を残して日本から出ていけないし」と急に怒り出したことがある。
今回も上手に話を進めないと、「まとまった金はマイホーム購入にまわしたらどうか」とか、「そんなに金があるなら、茨城の自分の実家にもっと頻繁に帰りたい」というようなとんでもない提案をされそうだ。
これまでも時々、「ハワイって一度は行ってみたいな」だとか「子供が二歳になるまでは旅行代金も安いらしいから、海外旅行に行くチャンスかもしれない」などと会話に織り交ぜてきたが、雄太は気がついているだろうか。今のところ、特に大きな反発もなく、「ふーん」と返事をしてくれていたけれど。
とにかく、お金はあるし、あなたは何も心配しなくていい、ということを強調しようと心に決めた。
夕飯はカレーにした。百グラム九十八円の豚挽肉と夏野菜のなすを使ったキーマカレーだ。雄太も他の家の夫と変わらず、カレーが好きだった。
今日は夏のボーナスの支給日だ。そろそろ夏休みの予定を会社に提出する時期でもある。雄太の会社は夏期休業として三日の休みを取ることができる。それに有休を足して、一週間ほどの休みを九月頃に取ることはできないかということも打診しなければならない。
帰宅した雄太は思った通り、カレーをおかわりして食べ、第三のビールも上機嫌で飲んで、「みづほも好きなものを買っていいよ」と言った。
「ほら、この間、乾燥機付き洗濯機か食洗機が欲しいって言ってたじゃんか。どっちか検討しようか」
電化製品は家庭に必要な買い物じゃなくて、私の「欲しいもの」「プレゼント」だと考えているのだろうか。でも、ここでそれを問いただして、彼の気分を悪くしてもしかたがない。
「……ものを買うのもいいけど、私、行きたいところがあるんだよね」
「え? 温泉とか? ディズニーランドとか?」
雄太は上唇に白い泡を付けたまま、問う。
「それなら、俺も行きたいし、かまわないけど?」
「違うの。ハワイ……とか」
「えー、ハワイ? そりゃいいけど、高いだろ?」
反応と表情から、意外に好感触で嬉しくなる。「高い」というところ以外に問題はないようだ。それなら、とみづほは立ち上がる。
「実は、ずっとお金を貯めてたんだよね」
食器棚の引き出しから、通帳を出して雄太に広げて差し出した。今はネットバンク全盛で、銀行からもたびたび「通帳をデジタル通帳に替えませんか」という通知が来ていた。それを無視し続けていたのは、毎月「20000」の印字が並んでいくのを見るのが喜びだったし、こんな時を想定していたからだ。
夫に「600000」の数字を見せる日を。
彼はちょっと眉をひそめて通帳を引き寄せた。しばらく眺めている。
「へえ」
数分見つめて、やっと声を出した。
「へえって何?」
「よく貯めたじゃん。どうやって貯めたの?」
「あなたから毎月もらってるお金を節約して」
みづほは説明した。どうやって食費を倹約してきたのか。服も新品はずっと買っていない。時にはネット上のポイントサイトを使って「プチ稼ぎ」もしてきた。
話し出したら止まらなかった。自分がどれだけ頑張ってきたかを。
「ストップ、ストップ」
雄太は笑いながら、手を振った。
「わかったけど、このくらいでハワイなんか行けるの? 今、円安でしょ」
みづほは大手旅行会社のハワイツアーのパンフレットもいくつか並べた。ハレクラニとはいかないが、そこそこいいホテルと飛行機代が含まれたツアーが予算以内だということも説明した。
「隙のないプレゼンだなあ」
「だって、ずっと計画してきたから」
「じゃあ、俺もハワイに行けるのか」
「もちろんだよ。そのために貯金してきたんだし。本当にゆうちゃんは何も心配しなくていいの。一緒に来てくれれば」
「そこまでしてくれたなら、こっちには異論はないよ」
みづほはやっと気が楽になった。そう、雄太は決してケチだったり、気難しい人間ではないのだ。時々、へそを曲げるけど。
「みづほがここまで頑張ってお金を貯めてくれたなら、俺が向こうでのお金を出すよ。メシとか土産物とか、プールとかも大きいのがあるんでしょ」
「へえ、ゆうちゃんもそういうの知ってるんだ」
「課長が話してたんだよ。ほら、高岡さん」
みづほも知っている名前を出した。同じ会社で働いていたし、結婚式にも来てもらったから、知らない仲ではない。
「去年の夏にハワイに行ったんだって」
「あ、年賀状がハワイの写真だったもんね」
みづほは思い出した。特徴的なビーチの風景で、すぐにハワイだとわかった。我が家も来年の年賀状はハワイにしたい。
「めちゃくちゃ大きい、流れるプールがあって子供が喜ぶって言ってた」
「圭太はまだ小さいからそんなに遊べないけどね」
「まあ、いいじゃん、思い出になるし」
「嬉しいけど、大丈夫なの? ゆうちゃんも貯金あるの?」
月々の給料以外に、彼がどのくらい貯金があるのか、今までほとんど聞いたことがなかった。
「ぜんぜん」
雄太は無邪気に微笑む。
「でもクレジットカードもあるし、問題ないよ。俺、普段からあんまり金使わないじゃん。クレカの請求もいつも三万くらいだし、大丈夫だと思うよ」
その後、雄太の有休も思い通り、九月の半ばに一週間認められ、ツアーも予約できて、ハワイ旅行の準備はちゃくちゃくと進んだ。
二年半かけて金を貯め、ルイ・ヴィトンの店の門をくぐった時、みづほの胸にさまざまな思いがよぎった。
実際にはアラモアナショッピングセンターの一角にあるのだから、「門をくぐる」というのとは違うけれど、入口には屈強なレスラーのような警備員が二人立っていて、門と言って差し支えないような物々しさだった。緊張し過ぎて、雄太が店内を見て、「すっげえ人だなあ」と無邪気に言うのに素直にうなずけない。
これまでネットで情報を集め、一度は新宿のヴィトンに行って下調べまでしていたのに、ガラスケースの前に行ったら、どうしたらいいのかわからなくなってしまった。
「何買うか、決まってるんでしょ。早くしようよ。人がたくさんいるところ、俺、苦手なんだよ」
ケースに張り付くようにして見ているみづほに、圭太を抱いた雄太が無遠慮に言い放った。
「悪いけど」
みづほは振り返って、低い声で言った。
「私、このためにお金を貯めてきたんだ。二年、ううん、二年半。ずっとずっと、新しい服もバッグも一つも買わないで、節約メニューを研究してやってきた。だから、これだけはゆっくり選びたい」
もしかしたら、日本人客や店員がいて、話を聞かれているかもしれない、と思ったけれど止まらなかった。
「私、結婚して今まで、ゆうちゃんにこんなに真剣にお願いしたこと、なかったよね。だから、これだけでいいから聞いて」
「……どうすればいいの」
みづほの迫力に雄太がこわごわとうなずく。
「このビルのカフェかどこかで待っていてくれる? 圭太と一緒に」
このくらいはっきり言わないと、彼は圭太を置いて行きかねない。
「じゃあ、場所が決まったら、LINEするから」
ビルの中には無料のWi-Fiがあって、お互い連絡を取ることができた。
「うん、買い物が終わったらそっちに行くから」
彼らが行って、やっとゆっくり品物を見ることができた。
色も形も決めていたはずだった。「ポルトフォイユ・クレマンス」の長財布、柄はヴィトンの象徴的な市松模様のもの。ヴィトンのジップ付き長財布は十万近くするが、これなら、小ぶりで六万くらいだ。しかも小さめだから、女性が持っていても邪魔にならない。
「あー、これ」と言いながら、目の前の褐色の瞳の若い店員に指さすと、にこやかに何か英語で言って、奥に引っ込んでしまった。
なんだか馬鹿にされたようで不安になっていると、「お待たせしました」とアジア系の女性が日本語で対応してくれた。日本語ができる店員を呼んできてくれたらしい。
「これ、かわいいですよねえ。長財布のなかでも女性に人気なんです」
彼女は慣れた手つきでガラスケースの鍵を開けて出してくれた。みづほが何か言う前に、他の色や形のものもずらりと並べてくれた。
おずおずと手を触れると、小さいのにずっしりと重い。それもまた高級感があった。
「どうぞ、開けてみてください」
言われた通り、開けると真っ赤な革の色が目に飛び込んでくる。
「この色、きれいですよねえ」
すてき……本当にすてきだけれども。
思った以上に小ぶりだ。これでは札の端が少し欠けてしまう……ということはなくても、いつもジッパーに札やレシートを挟みそうと気にしながら使うことになる。それにカード入れや、他の場所も心許ないからもう少し大きい方がいい。新宿のヴィトンでは手に取る勇気がでなかったからわからなかったけれど。
かわいい、かわいいを連発する店員に聞いてみる。
「あの……他の財布も見ていいですか」
「もちろんです。何をお出ししますか」
「……じゃあ、これより大きい」
みづほは店内に目を泳がす。隣のガラスケースを指さした。
「あの長財布と、あと、二つ折り財布も見てみたいんですけど」
「わかりました」
店員は嫌な顔ひとつせずに、用意してくれた。ただ、みづほの前に並べた財布は一つ残らずすべて、元のケースの中にしまってから取りに行った。なんだか、泥棒扱いされたようでちょっとむっとする。アメリカではこれは普通なのかもしれない。それでも、肘が触れるほどの距離で、別の客と店員が話しているのに、万引きなんてできるわけないのに。
彼女はヴィトンのロゴの入った長財布、そして、二つ折り財布を持ってきてくれた。どちらも定番中の定番だ。他に小さな三つ折りの財布も持ってきてくれた。
「最近はこのタイプも人気なんですよ。小さいバッグにも入りますしね」
小さな小さな財布。それは本当にかわいいけれど、やっぱり若い女性……お金もカードも支払いは男が出してくれるような女が持つべきもののような気がした。
長財布がハワイでも十万以上することはわかっていた。けれど、手に取ってそのジッパーを開けると、やはり造りが違う。しっかりしていて、心なしかジッパーの動きもいいような気がする。
これまで欲しいと思っていたクレマンスが急にちゃちに見えてきた。
「やっぱり、こちらですよねえ」
店員がささやく。
「そう思いますか?」
「ええ。やっぱり、他のものとはちょっと違いますよ。ヴィトンを長年使っていらっしゃる方は、結局、こちらの長財布になさいます。造りがしっかりしているから何年も使えますしね。修理も利きますよ」
しかし、十万……。
自分が十万もする財布を持つ人間だと思ったことはなかった。けれど、買えないわけでもない。だから、迷うのだ。
そこに彼女が悪魔のようなささやきをした。
「一説には、年収は財布の二百倍って言いますよね」
「どういう意味ですか」
「ご存じないですか。先日、お客様から、日本じゃそう言うって聞いたんです。財布の値段の二百倍の年収になれるって。こちらだったらだいたい日本円で十万ですから……年収二千万になれるってことじゃないですか」
彼女は他意なさそうに笑った。
「年収二千万……」
無理だわ、私、今は働いてないし、と心の中でつぶやく。それでも、悪い気はしない。年収二千万だって、本当にそんなことになったらどれだけ嬉しいだろう。
そこに店員が追い打ちをかける。
「奥様がならなくても、旦那様がなるかも、ね? 二千万に」
彼女はいたずらっぽい笑みを浮かべた。共犯者のようにも、からかわれているようにも見える。
「ああ」
「お名前入れも無料でできるんですよ。お客様だけのお財布になるんです」
「私だけのお財布……」
お金を貯め始めた頃からずっと夢見てきた。
自分がヴィトンの財布を買う時はどんなふうに「これ、ください」「これ、いただきます」と言うんだろうと。
できるだけ優雅に、できればちょっと高飛車に言いたいと思っていた。時には指をぴんと立てて想像上のガラスケースを指さし、「これ、いただきます」と予行演習さえしてきた。
しかし、どれも実際に自分の口から出たのとは違っていた。
「これ。買ってもいいですか」
こわごわと震える声になった。
妙な胸騒ぎを感じるようになったのは、ハワイの記憶がまだ残る、十月の末のことだった。
発端は、雄太が預金通帳を開きながら「お、俺ってすごいなあ。クレジットカードをあれだけ使っても、やっぱり請求額三万なんだよな」と言ったことだった。
一瞬、首をひねった。そんなことあるわけがない。
ハワイでは思いっきり散財した。ウルフギャングでステーキを食べたし、なかむらのラーメンも食べたし、ハレクラニの海の見えるレストランで朝食も食べた。ヴィトンの財布を買った後、アラモアナで家族の買い物もした。圭太にはTシャツ二枚とアロハシャツを買ってやった。華やかなブルーに黄色のひまわり模様があしらわれたシャツで、よく似合った。まだ、自分で服を選ぶような歳ではないが、みづほと雄太が「かわいい、かわいい」と交互に褒めるとやはり嬉しいのか、圭太はきゃっきゃっと声を出して笑った。
雄太自身もTシャツと帽子を新調していたし、スニーカーも買った。ヴィトンの財布以外、それらは全部、彼のカードで支払った。
それだけではない。手持ちのドルがなくなった時は、クレジットカードでATMから現金を引き出していた。ホテルよりこの方がレートがいいらしいよ、と言って。
「大丈夫だよ。だって、みづほちゃんも貯金頑張ってくれたでしょ」
彼はずっと笑顔だった。それがハワイにいる間、どれだけ嬉しかったか。
カードの請求というのは少し遅れてくる、と一度は不安を打ち消した。来月にはきっと多額の請求が来るだろう、と。
再び違和感を感じたのは十二月に入ってからだ。来年の年賀状の注文をするために、家族写真を整理した。今年はやっぱり、ハワイ旅行の写真を大きく使おうと考えながら、ふと手を止めた。
「ねえ、ゆうちゃん?」
「ん?」
休日の夕食のあとだった。彼はスマホをいじっていた。
「そういえばさ、クレジットカードの請求書、来た?」
「クレカの? うん」
スマホゲームに夢中になっていて、ろくに聞こえていないようだ。こういう時は一度時間を置いて、彼がスマホを止めてから話さないとすごく機嫌が悪くなる。それを知りながら、どうしても、今聞きたかった。
彼が「ああ、あれ。来たよ、すっごい金額だった!」だとか、「もう、払うの大変だったよ!」とか言わないことが逆に不安だったのだ。
「ねえ、ゆうちゃん、ゆうちゃんてば。ちょっと一度、こっち見て。スマホ止めて。ちゃんと答えて!」
「んんん?」
案の定、彼は不機嫌になった。
「なんだよ」
「だから、カードの請求書来た? って聞いているの。先月の」
「先月って、十一月末の? 来たよ? 普通に払ったもん」
雄太はゲームを中止させられて、少しイラついているのが口調でわかる。
「普通にって……いくら?」
「普通に、いつもと同じだよ、三万くらい?」
「……おかしくない? だって、ハワイ旅行でいろいろ使ったじゃん」
「だって、カード会社から請求来たのをちゃんと払っているんだから、別に大丈夫だろ」
「いや、でも……一度、その請求書を見せてよ」
雄太は黙りこくった。
「ねえ、ねえって」
「知らないよ。だいたい、請求書なんてないよ。今は全部ネットだもん」
「じゃあ、そのネットの画面を見せて。先月と先々月のだけでいいから」
雄太は急に立ち上がった。
「俺がちゃんとやってるんだから、大丈夫だよ!」
そう大声で怒鳴ると、彼は寝室に入り、ばたん、と大きな音を立ててドアを閉めた。驚いた圭太がおびえたように泣き出した。
みづほはハワイでの出費を思いつく限り書き出し、夫が払ってくれたもの、特にカードを使ったものにマーカーで印を付けた。
書き出している途中で何度も投げ出したくなった。そのリストを作る途中で、頭の中で、何かがおかしい、何かがおかしい、とちかちかと警告灯が瞬いていたからだ。
終わった時はっきりしたのは、レートによって変わるので正確な金額はわからないまでも、少なくとも十五万、多ければ二十万以上、雄太はハワイで使っているということだった。他に彼自身が日本で使っている分もあるだろう。夫婦二人の携帯代は家族割になるので彼が払ってくれている。一人八千円ほどで二人で一万五千円以下ということはないと思う。
おかしい。
翌朝、みづほは朝食の席でもう一度、尋ねてみた。
彼はトーストとヨーグルト、目玉焼きを食べていた。そのヨーグルトはみづほがヨーグルトメーカーで作っているものだ。一リットル九十八円の低脂肪乳を使って、少しでも倹約して、少しでも雄太に健康になってほしいと願っているから。ネットのポイントサイトのアンケートに答えて、毎日一ポイント、二ポイントと少しずつ貯めた二千ポイントでヨーグルトメーカーを手に入れた。本当は自分のものを手に入れてもよかったのに、家族のために使った。
それを呑気に食べている夫を見ていたら、自分の不安を解消してくれてもいいのではないか、とつい思ってしまった。
「あのさあ、前もちょっと聞いたけど、ハワイの支払いのことだけど……」
雄太は何も言わず、ヨーグルトのスプーンを口に入れたまま、上目遣いにみづほを見た。
「やっぱり、ちょっと心配だから、確認してくれる? 支払いどうなってるの? ゆうちゃんにいろいろ払ってもらったよね? 私、ざっと計算してみたけど、あれ、二十万近くになってない? もしも、支払いが大変だったら、私も出すから……」
そこまで譲歩して柔らかい口調で言っても、彼は黙ってヨーグルトを食べている。
「確認してくれるだけでいいんだ。ハワイで使ったお金がどのくらいかかったか……」
「だから、ちゃんと払ってるって言ってるだろ」
そう言いながらスプーンをテーブルに置いた。しかし手元が狂ってそれは床に落ちてしまった。カキーン、という乾いた音がした。
「俺がちゃんと払ってるんだから、大丈夫なんだよ」
雄太が拾わないので、みづほは長い人生の中で、いったい、何度、自分は床にひざまずくのだろうと思いながら、這いつくばってテーブルの下のスプーンを拾った。
前はここで尋ねるのを止めてしまった。でも、今朝はどうしても止められなかった。
「毎月三万ておかしくない? 携帯代だけでもその半分くらいはいってるはずでしょ?」
スプーンをキッチンで丁寧に洗い、彼に渡しながら尋ねた。
「だから、ちゃんと払ってるって」
「九月の半ばに旅行に行って、十月末の支払いも、十一月末の支払いも三万だなんて……計算が合わなくない?」
雄太は乱暴に立ち上がった。
「もう行かないと間に合わないから」
「どうしてそんな風になっちゃうの? なんで怒鳴るの? ただ、聞いただけじゃない。不安だから聞いているの。どうしたのかなって。あのハワイは私が貯めたお金で……」
「私が貯めた、私が貯めたって偉そうに言うなよ。俺が働いた俺の金だろ。でかい顔すんじゃねえよ! 全部、俺の金だろうが。なんで、そんなことを言われなくちゃならないんだよ」
俺の金、という言葉が胸に刺さって、文字通り、鋭い痛みを感じる。みづほが苦労して一円一円と貯めてきた労力はなんでもないんだろうか。
「ただ、確かめたいだけなの」
みづほは小さな声でつぶやいた。
雄太はそれに応えずに、寝室から上着と通勤鞄を取って、乱暴に玄関を閉めて出て行った。
結局、何もわからないまま、年を越してしまった。
あれから数日はお互いにむっとしたまま過ごし、雄太も年末の忙しさや忘年会などもあって、夕飯を一緒に食べることも少なく話し合いもできなかった。
何より、あそこまで機嫌が悪くなられると、また怒られるのが怖い。
前から少し気づいていたのだが、雄太はお金にルーズというか、ザル勘定なところがあって、それを指摘されるのをすごく嫌がる。不得意なことを自覚しているのかもしれない。
ボーナスが支給されると、雄太はみづほに三万円をくれた。銀行の封筒に入れたものを、ぶっきらぼうに「はい」と渡した。
「何、これ?」
「クリスマスに、なんか好きなもの買ったら」
彼なりの謝り方なのかもしれなかった。けれど、みづほにはプレゼントの三万も、不安を思い出す材料になっただけだった。
それでも表面上は変わりなく、家族として普段通りに生活した。
正月には彼の実家に子供をつれて帰り、二泊した。義母が「この子はちょっとぶっきらぼうだけど、優しい子なのよ」「子供の頃からとにかく頭が良くて、計算がよくできた」といつもの自慢をし、みづほはそれを上の空で聞いた。
そんなに計算ができる息子が、ハワイで使ったお金のこともわからないのだろうか。みづほの実家には雄太が「疲れたから行きたくない」と言うので、圭太だけを連れて四日に帰り、夕食を共にして泊まらずに自宅に戻った。
「雄太さん、一人にしておけないものねえ」
悪気なく笑う母に、申し訳ないと思いながら、電車に乗り込んだ。
実は、年末にみづほは思いあまって、カード会社に電話していた。彼の名前とカード番号でなんとか支払い実績や請求額がわからないかと考えたのだ。彼のカード番号は、夜中密かに財布からカードを抜いて調べた。
「……申し訳ないですが、ご本人様じゃないとお答えできかねます」
電話口の女性がそっけなく言った。
「やっぱりそうですか」
「カード番号とお名前だけでは」
「……実は、夫がカードを使っている形跡があるのに毎月三万の支払いしかしてないと言っていて、ハワイに行っていろいろ使っているはずなのに、なんだか、おかしいなと思って……」
気がついたら顔も見えない相手に、何かが零れるようにすべてを話してしまっていた。相談できるのは彼女しかいなかった。
「どういうことになっているのかと思って」
「……それはリボ払いになっているのかもしれませんね」
相手はなぜか声を潜めて言った。
「え」
リボ払い。聞いたことがある言葉だったがどういう意味なのかよくわからない。
「旦那様とご一緒に当社にいらっしゃってくだされば、『リボ取引明細照会』ができます。これまでどのくらいお使いになっているのか、どのくらいお支払いが残っているのかわかります。一括払いやもう少し金利の低い分割払いに変えることもできますので、ぜひ、ご相談ください」
そう言って相手はそそくさと電話を切ってしまった。
仕方なく、みづほはネットで「リボ払い」を検索してみた。
驚いたのは「リボ払いとは?」で検索しているのに、その用語の意味の説明より前に「広告」と銘打って、「リボ払いで苦労してない? 毎月の支払い額を簡単に減らせます」という怪しげなページがたくさん出てきたことだ。漫画で作られた、「リボの返済額で苦労していた私が一分で楽になった!」という美容広告のようなものまであった。
それをかき分けてやっと探し出した、多少まともそうなページに書かれていたのは、「毎月の支払い額を一定の金額に固定して、金利とともに返済していく仕組みです」「手数料として使った額の十五%程度がかかる場合があります」という衝撃的な言葉だった。中には「リボ払いというのは結局、借金です」と書いている人もいた。
まだ、全容は見えてこなかったが、もしかしたら雄太がカード会社から借金をしているのかもしれない、ということだけはわかった。
しかし、どうやって彼にこのことを伝え、どうやって話し合えばいいのかわからない。
前は朝食中というタイミングが悪かったのかもしれない。起きたばかりで、会社に行く前の慌ただしい時にする話じゃなかった。
次はもう少し、時間帯や話し方を考えよう、と思った。
一月二十五日が新年最初のお給料日だった。雄太はまた、五万円をみづほに渡してくれた。
「はい、これ」
「ありがとう。お疲れ様でした」
今夜は餃子にした。キャベツをたくさん刻んで塩揉みし、ぎゅうっと力を入れて水分を絞る。それに塩を加えてもっちりするまでよく練った豚挽肉を加え、特売で買った、一袋六十八円の餃子の皮にぎっしり詰めた。
お肉は百グラムしか使っていないのに、満足感の高い、みづほの得意料理だった。その分、手間はかかる。
餃子を焼く時に加える水に片栗粉を足して、羽根つき餃子にすることも忘れなかった。もやしをナムルにして、第三のビールもそえ、切り詰めているけれど、お給料日にふさわしい華やかな献立にした。
「なんか、お店に来たみたいだなー。みづほの餃子おいしいから、店に行く必要ないよね」
そこまで機嫌良くなってくれたところで心苦しかったが、みづほはもう一日も待てないと思っていた。
夕食を半分ほど食べたところで、みづほは箸を置いた。
「……ゆうちゃん、本当にごめん」
「え、何?」
「今日はお給料日で、せっかく、機嫌良くしているのに、こんなこと言いたくないんだけど、だけど、どうしても言わせて。私、どうしても聞きたいんだ。あの……カードの支払いどうなっているの? 今月も前と同じで三万だったんでしょ? それだと、どうしても計算が合わないと思うんだ。もしかしたら、リボ払いっていうのになっているんじゃないかな。本当に、本当にこんなこと聞いてごめんなさい。だけど、一度だけ、確かめさせて。それをしてくれたら、私、もう二度と言わないから。絶対、あなたを責めないから、お願い」
雄太の顔を見ずに、自分が精魂込めて作った餃子を見ながら、一気に言った。言っている途中から涙があふれてきた。
「ごめんね。だけど、もしも、借金があるなら教えて欲しいの。これは私やゆうちゃんのためだけじゃない。子供の……圭太のためなの。この子には大学に行ってもらいたいし、でも、今のままじゃ、私たち、学資保険以外に貯金もできてないよね。これを機会にお金のこともちゃんとしたい。見直したいんだ」
雄太が深々とため息をついた。
「……それを言われたら、ずるいわ」
みづほはやっと顔を上げた。息子の名前に効果があったようだ。
「私も頑張るから。圭太を保育園に預けて働いてもいいし」
「でも……カードの利用履歴なんて、よくわからないよ。もう、何年も見てないし、明細書も来てない」
「前にネットで調べられるって言ったじゃん」
しぶしぶ、彼はスマホを出した。
それからもまた大変だった。紙の明細書からネットに変えた時に一度ログインしただけで、その後、一度も見ていなかったらしく「どこを調べればいいのかわからない」「パスワードがわからない」と文句を言ったあげく、みづほがスマホ画面をのぞこうとすると嫌がって、手で払いのけた。
しかし、その間に、彼がクレジットカードを持ち、リボ払いにした経緯を聞き出すことができた。
学生時代にiPhoneの機種代金が無料になる契約を携帯会社とした時、新しいクレジットカードを作って支払いをすることが条件だったらしい。
「リボ払いにするって言われなかったの?」
「さあ。どうだったか……携帯の支払いが月八千円くらいで、支払いが三万までなら手数料もかからないから、普通のカードと同じですって言われたような気がする。とにかく、これなら大丈夫です、って」
「ぜんぜん、大丈夫じゃないじゃん」
「でも、そんなに悪いことかな。定額払いならサブスクみたいなもんでしょ。永久に毎月三万払えばいいじゃないか」
雄太は何度も理屈をこねて、調べる手を止めた。
みづほもそう言われると、急に自信がなくなったし、本当は彼の説明を鵜呑みにした方が自分だってずっと楽だった。それでも、「とにかく、今、払わなきゃいけないお金がどれだけ残っているのかわかってから、考えようよ」と、なだめすかした。
やっとカード会社のサイトを見つけ、いくつかのパスワードを試した後、彼は手を止めて、スマホ画面を見つめた。彼がじっとしているので、みづほも横からのぞき込むことができた。
「二百……二十八万……?」
みづほが雄太の顔を思わず見ると、彼も、目を大きく見開いていた。
そこからは怒濤の日々だった。
まず、次の休日に、みづほと雄太は圭太を連れてクレジットカード会社に行き、「リボ取引明細書」というものを出してもらった。
電話で話した時に聞いた通り、リボ払いの手数料という名の金利は十五%だった。
「二百二十八万の十五%は三十四万二千円になります。それを十二ヶ月で割りますと、二万八千五百円になりますので……」
「二万八千五百円ということはつまり」
「つまり、毎月お支払いいただいている三万円は、手数料分が二万八千五百円で、元金のお支払いは千五百円ということになります。ざっくりとですが」
では、借金の元金はほんの少ししか減っていないということになる。さらに、毎月使う金額があるのだから手数料分はどんどん増えているはずだ。
「手数料を抑えたいということでしたら、早めに全額支払っていただいた方がいいですよ」
救いなのは、担当者が優しい雰囲気の中年女性で、親身になって相談に乗ってくれたことだった。
「今のままでは、一日に千円くらいも利息……手数料を支払っているということになりますから」
どこを探してもそんなお金はない。
思いつめて雄太の実家に相談してみた。大学時代、仕送りが足りない時にカードを使ったこともあったらしい。決して、雄太の親が悪いというわけではないが、理由を話してお金を貸して欲しいと頭を下げてみた。
しかし、あっさり断られた。
「もう二人は立派な大人なんだから、自分たちでなんとかしなさい」
義母がにこりともせずに言った。
「でも……」
「ない袖は振れない。うちだってお金があるわけじゃないし、老後のこともあるんだから」
「本当にすみません。でも、今の状態だと毎月利息だけを払っているような状態なんです。必ず返済しますので」
「だから、お金がないって言ってるのよ」
ずっと下を向いていた雄太が「その、老後のお金っていうのを一時的に貸してもらえないか」とぽつんと言った。
隣にいた雄太の父親が「退職金から少し」と言いかけた。
「退職金? もうないわよ!」
「え?」
「だから、それがないって言っているの! 老後は老後であんたたちに助けてもらうつもりだから、しっかりしてよ」
いつも上品にしている義母が筋の通らぬことを叫んだ。みづほはこの時の義母の引きつった顔を死ぬまで忘れないだろうと思った。
シングルマザーで自分を育ててくれた母親に、お金の相談をしても無駄だとわかっていた。でも、誰かに聞いて欲しくて、実家に息子と二人で帰った。
「これ、使いな」
話し終わると、母親は通帳をぽん、と出してきた。手に取って開いてみると、百三十万ほどの残高があった。
「使えないよ。これ、お母さんが貯めたお金でしょ」
「でも、しょうがないじゃないの。そのままにしておけないでしょ」
通帳を見ればすぐにわかる。母が毎月、一万、二万と貯めている金だった。
「どうしてもつらかったら、この家で一緒に住む? 雄太さんは気詰まりかもしれないけど、新宿まで通えない距離じゃないし、あたしが圭太の面倒をみて、みづほが働くこともできるでしょ。家賃もかからないし」
この家を売るわけにもいかないから、そのくらいしかできないけどね、と母はつぶやいた。実家は両親が結婚している時に買った中古の一軒家で、離婚後は母が一人で苦労してローンを払ってきた。言わば、母の最後の砦だった。
実母から借りた百三十万とボーナスの残り四十万、みづほの預金の残りなど家からかき集めた十万を持って、またカード会社に行った。残りは分割で払うことになった。
ヴィトンの財布は一度も使うことなく、メルカリで売った。もったいなくてまだ箱からも出していなかったのだ。十万の財布だったけれど、「M・H」とイニシャルを入れていたことが仇となって、なかなかよい値段がつかなかった。
出品する時、商品の写真を撮るために財布を箱から出した。箱、内袋、紙袋が全部そろっていた。捨てたり失くしたりしなくてよかった、と心から思った。それらがあるのとないのとでは値段が違うのだ。さらに、ハワイの店で買った時のレシートも個人情報のところをマジックで消して画像をアップすることにした。正規店でちゃんと購入したことの証になる。
写真に撮るためにそれらをテーブルに並べていたら、胸が押し潰されそうになった。長財布を手に取り、「このくらいはいいよね」と言いながら、すっぴんの頬に押し当てた。大きく息を吸い込んで匂いを嗅ぐ。革とビニールの混じったような匂いがした。
これを使いたかった。一緒に時を過ごし、一緒に笑い、一緒に歳を取りたかった。この財布は未来の幸せに寄り添ってくれるもののはずだったのに。
九万九千円で売り出したが、出品して一分も経たないうちに「六万円で即決できませんか?」という値下げ交渉のコメントが来た。
「まだ新品ですし、出したばかりなので六万はつらいです」
屈辱の気持ちを抑えて、返事をした。
「でも、イニシャル入りですよね? なかなか買い手が付かないと思うんですけど」
「九万円以下では無理です」
「では、六万二千円ではいかがですか?」
返事をするのもいやだった。
次の日には、「五万五千円になりませんか? よろしくお願いします!」「六万五千円でお願いできないですか」「六万三千円で、月末までお取り置きできませんか」と次々とコメントが来た。
どれも図々しい話ばかりで、身を削られる思いだった。
三日ほど、そんなやりとりを続けて精神的にも疲れ果て、「七万で即決お願いします」という一文に「わかりました。では七万でお譲りします」と答えてしまった。すると「やっぱり、六万八千円にしてください。今月苦しいんで」と畳み掛けられた。
なんだか、新品のヴィトンの財布がどんどん汚されていくようだった。ヴィトンを買いたい人種はこんなに厚顔無恥なのだろうか。
返事を躊躇しているところに、「自分、ちょうどイニシャルが同じなんで、大切にします。よろしくお願いします!」とコメントされた。何か背中を押されたように、「わかりました」と返事をしてしまった。
値下げをすると、あっという間に「売却済」のマークがついた。
それを見た時、みづほにこみ上げてきたのは、悲しみ以上にどこかほっとした気持ちだった。
メルカリのコメント欄を改めて読んだ。数日の間に多くの人がこの財布に群がった証が残っていた。新品の財布を一円でも安く手に入れようとして懇願するもの、恫喝するもの、自らを卑下するもの……中には自分の思い通りにならないとわかったとたん、こちらを馬鹿にしてくるものもいた。
まるで、漫才やコントのようで、思わず小さく笑ってしまった。
「結局、自分にはふさわしくなかったのかもしれない」
清々しい気持ちで財布を梱包した。
とたんにいつか必ず、見返してやりたいという気持ちがわいてきた。それは何に対してだろう。財布に群がった人々なのか、この財布そのものなのか、お金なのか、カード会社なのか。夫なのか、夫の親なのか、あるいは自分自身なのか。
みづほにはまだわからなかった。
第二話 財布は騙る
新品のヴィトンの財布を六万八千円でゲットして、水野文夫は「イエッス!」と机の下でガッツポーズをした。
抑えた声のはずだったが、隣の若い会社員風の女がちらりとこちらを見て小さく舌打ちした。淡いピンクのブラウス、薄茶色の髪は肩のあたりできれいにカールしている。
うぜえ。お前みたいな見た目も性格もブスな、婚活パーティの代わりにお財布セミナーに来ているような女とは絶対に結婚しないから覚えとけよ、という気持ちを込めてにらみかえした。
しかし、このセミナーには四千九百八十円も払っているんだから、確かにちゃんと聞かないともったいない。文夫は目の前の講師、ハイパースペシャルお財布アドバイザーの善財夏実に目を戻した。
「財布というのは、お金のすべての源です。お財布が貧しい人に豊かな未来は訪れません。フレンチレストランでお会計の時にマジックテープのお財布を広げる男と結婚しますか? しないでしょ?」
善財夏実が最近、お財布と婚活をテーマにした『婚活女子はピンクの財布を持て』という本を出してから、急にセミナー受講者にいき遅れOLみたいな女が増えた。あの本はなかなか売れているらしい。セミナーも婚活を意識した話が多い。
「まあ、私のセミナーの講習生で、マジックテープ財布を使っている人はいないでしょうが……」
大きな会議室いっぱいの受講者たちはどっと笑った。
彼女がツイッターに「マジックテープの財布を使っている男は一生年収三百万以下だし、結婚もできない」と書き込んで大炎上し、そのおかげで「お財布アドバイザー」としてデビューしたのは周知の事実だ。それまではぱっとしない風水師でネットの占い記事を主に書いているライターだったのが、そのツイート一つで今の地位をつかんだのだ。
インターネット黎明期に個人の意見を書き込める掲示板を立ち上げ、それを売却したことで大富豪となっている有名起業家が、「自分はマジックテープ財布を使って年商二十億稼いでますけど? 妻はみるくくるみですけど?」と善財のツイートを引用リツイートしたことも大きかった。
みるくくるみは売れないグラドルから地下アイドルになって、たまたまイベントで知り合った起業家をゲット。その後グラドルたちのアイドルグループを立ち上げて、夫からの莫大な資金を元に秋葉原に大きな劇場まで作ったやり手の元タレント実業家だ。美人で商才もある妻がいて、今もコンサルとして稼いでいる彼が使っているなら、マジックテープの財布が云々という話は嘘だということになる。けれど、善財夏実はまったく動じず、ちゃっかり彼のツイートをリツイートして、さらに拡散した。
彼らを見ていると、自分もいつかはSNSでバズったり、起業したりして、一攫千金を狙えるのではないかと思う。そのきっかけはすぐ近くにありそうな気もするし、とんでもなく遠いような気もする。でも、宝くじに当たるより確率は高いのではないか。
急に、自分のスマホがりーんと鳴って、血の気が引くほど驚いた。セミナーの間、電話は集中モードに設定していたのだけれど、今は善財の言葉をメモするために開いていたのだ。慌てて音を消したが、会議室中の注目を浴びてしまった。
しかし、善財はこういうことには慣れているのか、文夫の方をちらっと見ただけで何事もなかったかのように話を続けた。彼女がこちらを見てくれているのかわからなくても、文夫は何度も頭を下げた。
善財夏実は常に財布をきれいな状態にしておくこと、財布のどこに何が入っているのかいつでも言えるようにしておくこと、何より今いくら入っているかすぐに言えることが大事だということなどを話した。
「財布の中身はあなたの頭の中身です。財布が整頓されているということは、あなたの頭もいつもクレバーで澄み切っているということなのです」
文夫は今日、ヴィトンの財布を買った自分が誇らしくなった。これから、先生の言う通り、大切に使おう。自分の頭はもうヴィトンと同じ、一流ブランドということなのだ。
今日の善財は財布だけでなく、成功に導くSNSの使い方にも少し触れた。必ず毎日更新すること、何か自分の強みを見つけること、ライフハックを箇条書きにしたツイートを一日に一回はすること、炎上を恐れないこと。
善財は最後に、「私がなぜ、こんな成功の秘訣をすべて洗いざらい、あなたたちにさらけ出すと思いますか。手の内を教えてしまえば、もしかしたら、あなたたちが自分のライバル、脅威になるかもしれないのに」と言って、教室の隅から隅までずうっと見渡した。受講者たちが、いったいどういうことだろう? と思ったところで、すかさず善財は言った。
「それは、皆さんがきっとやらないと知っているからです。私がこんな話をしても、ここにいる百人の中で家に帰ってすぐに財布の整理をしたり、すぐにSNSの更新をする人は十人いるかいないかでしょう。その中で、一年以上持続できるのは一人いるかどうか。学んだ通りに行動できる人はほとんどいません。そうわかっているから、私はなんでもあなたたちに教えるんです」
善財はにやりと笑った。不敵な笑みだった。