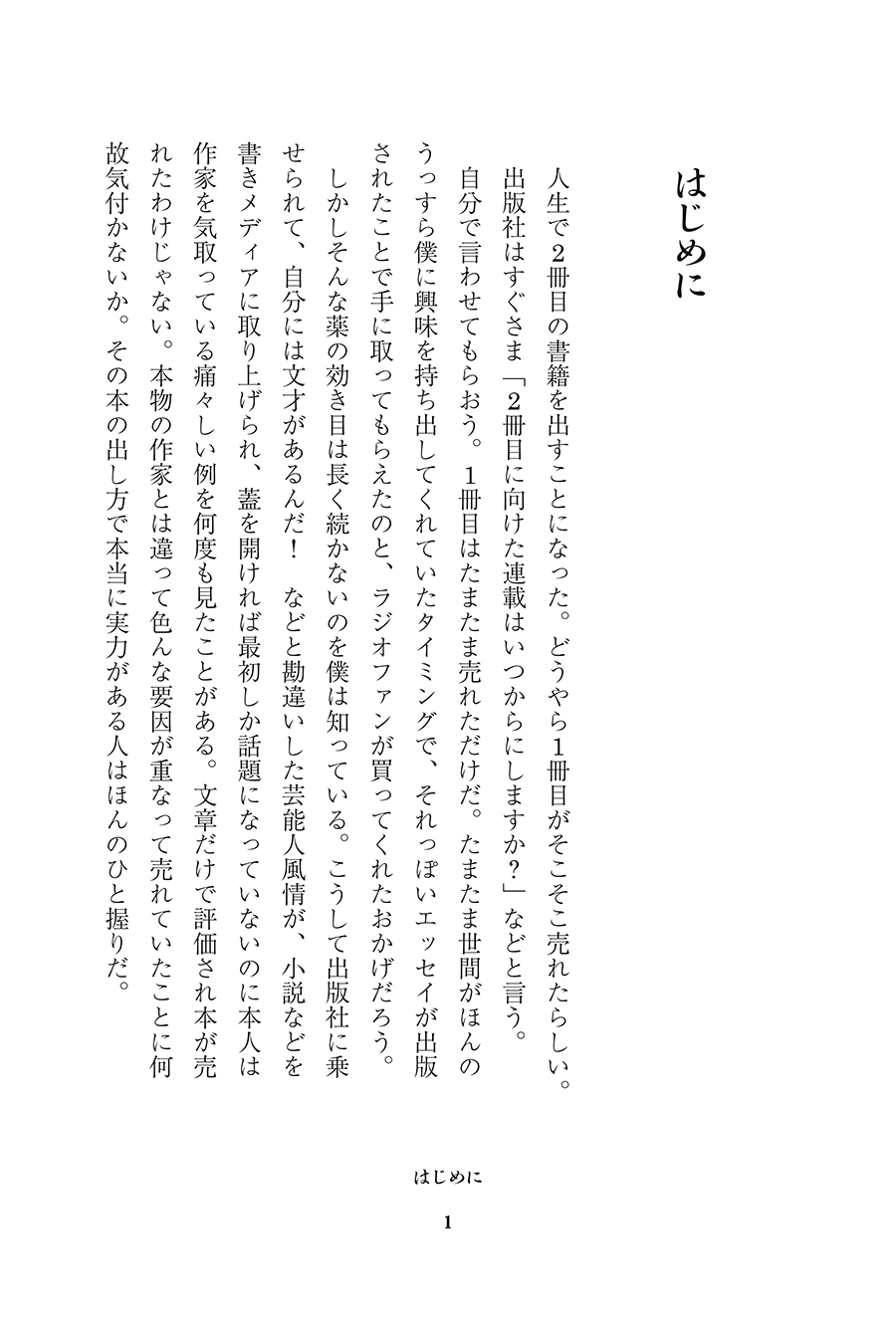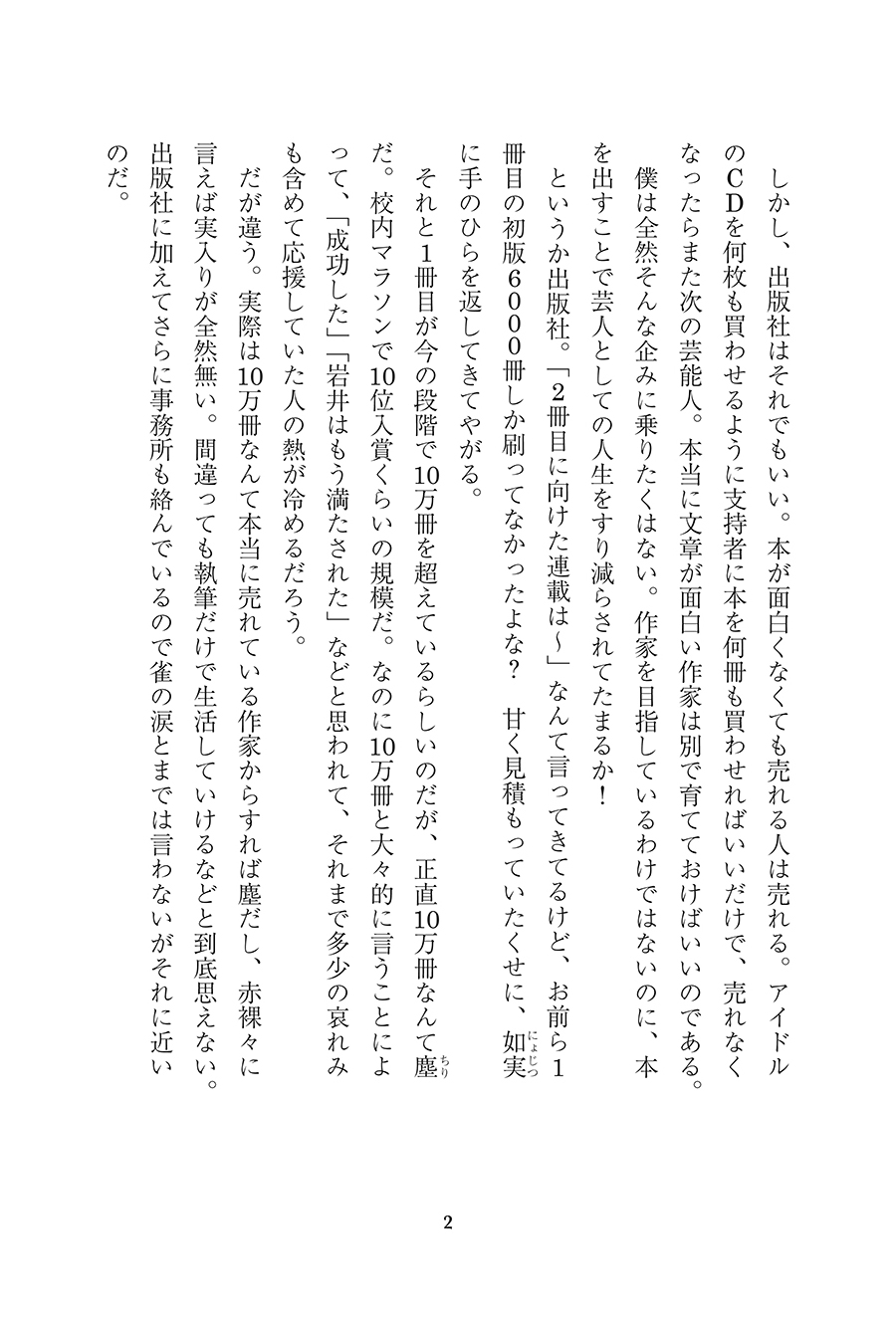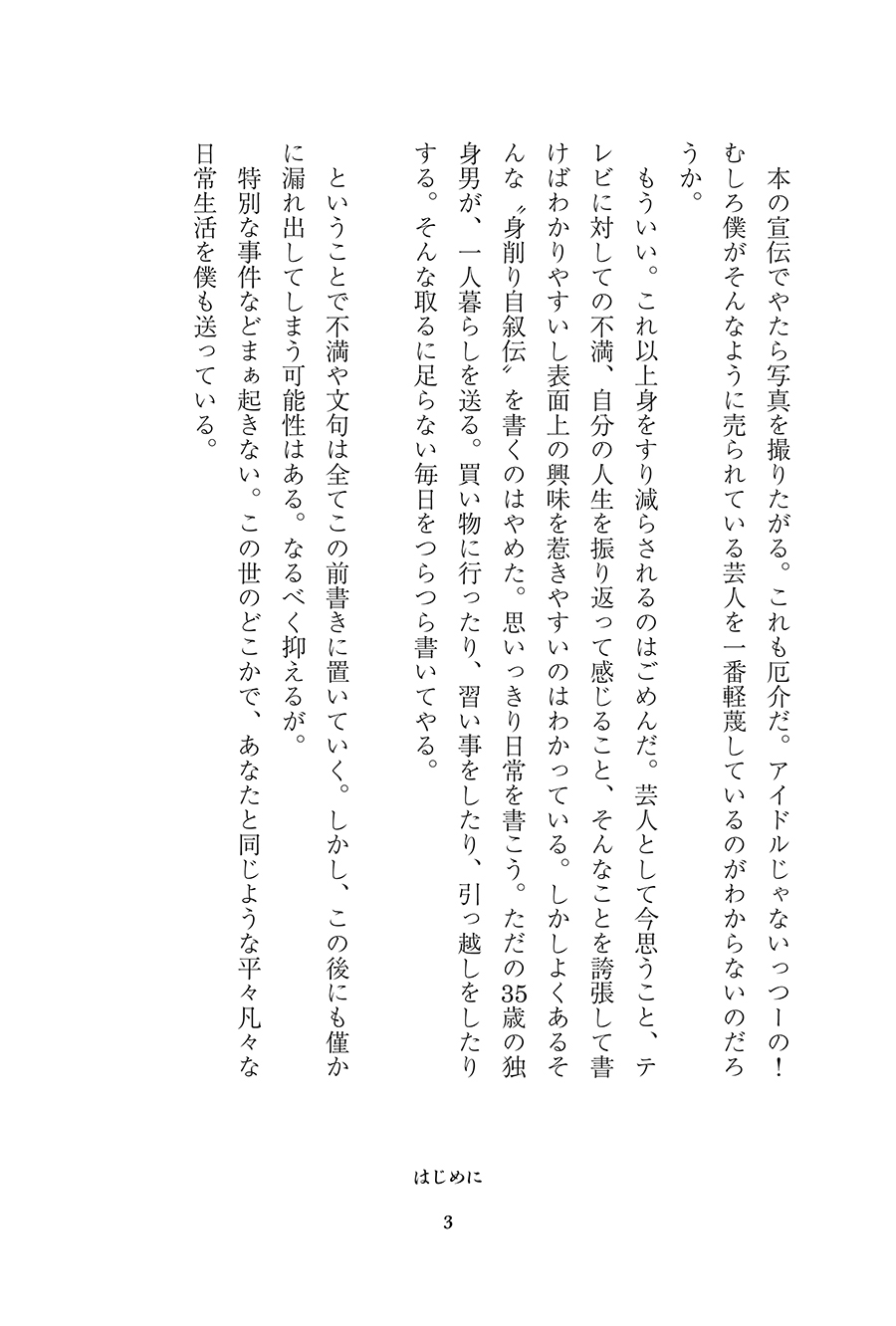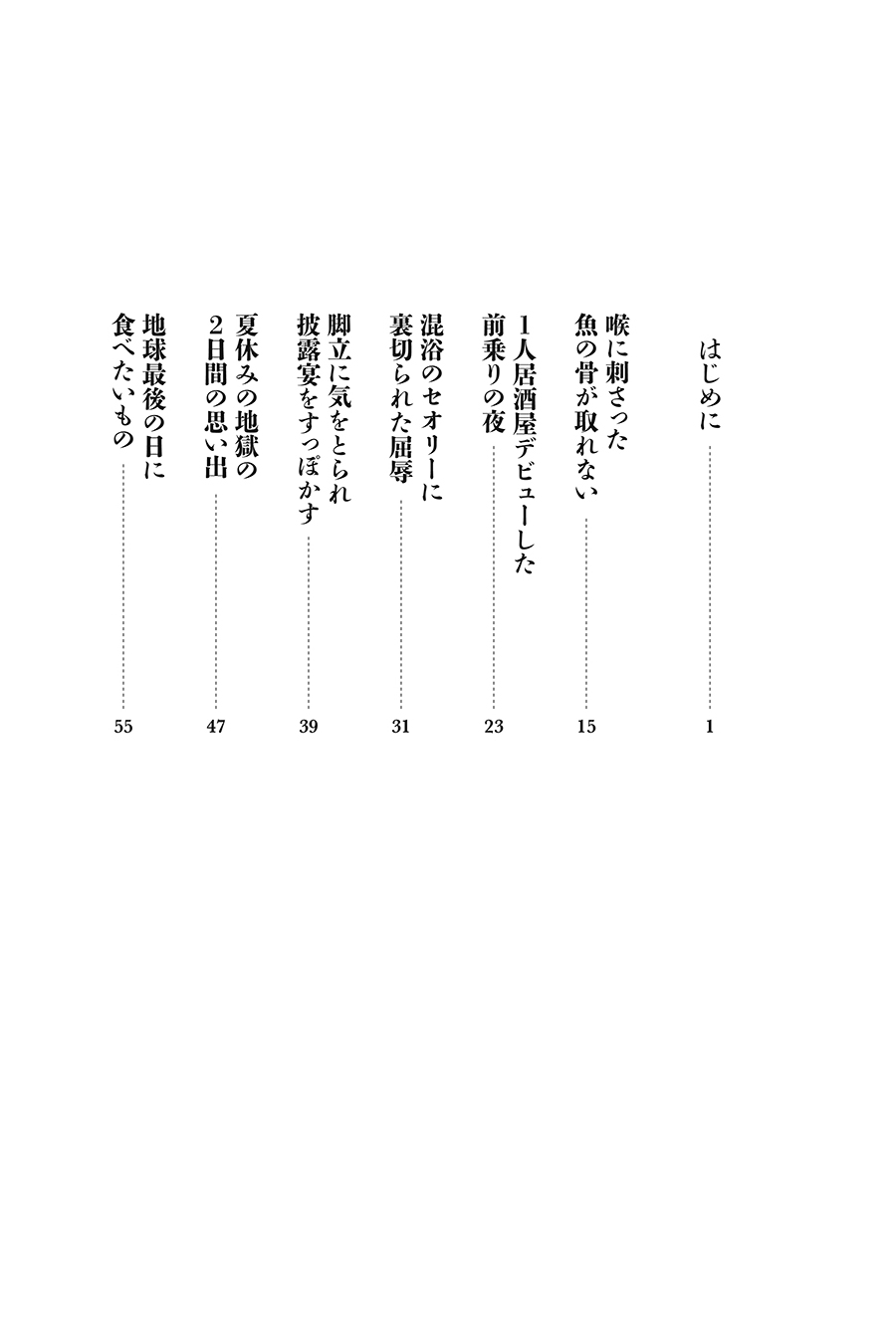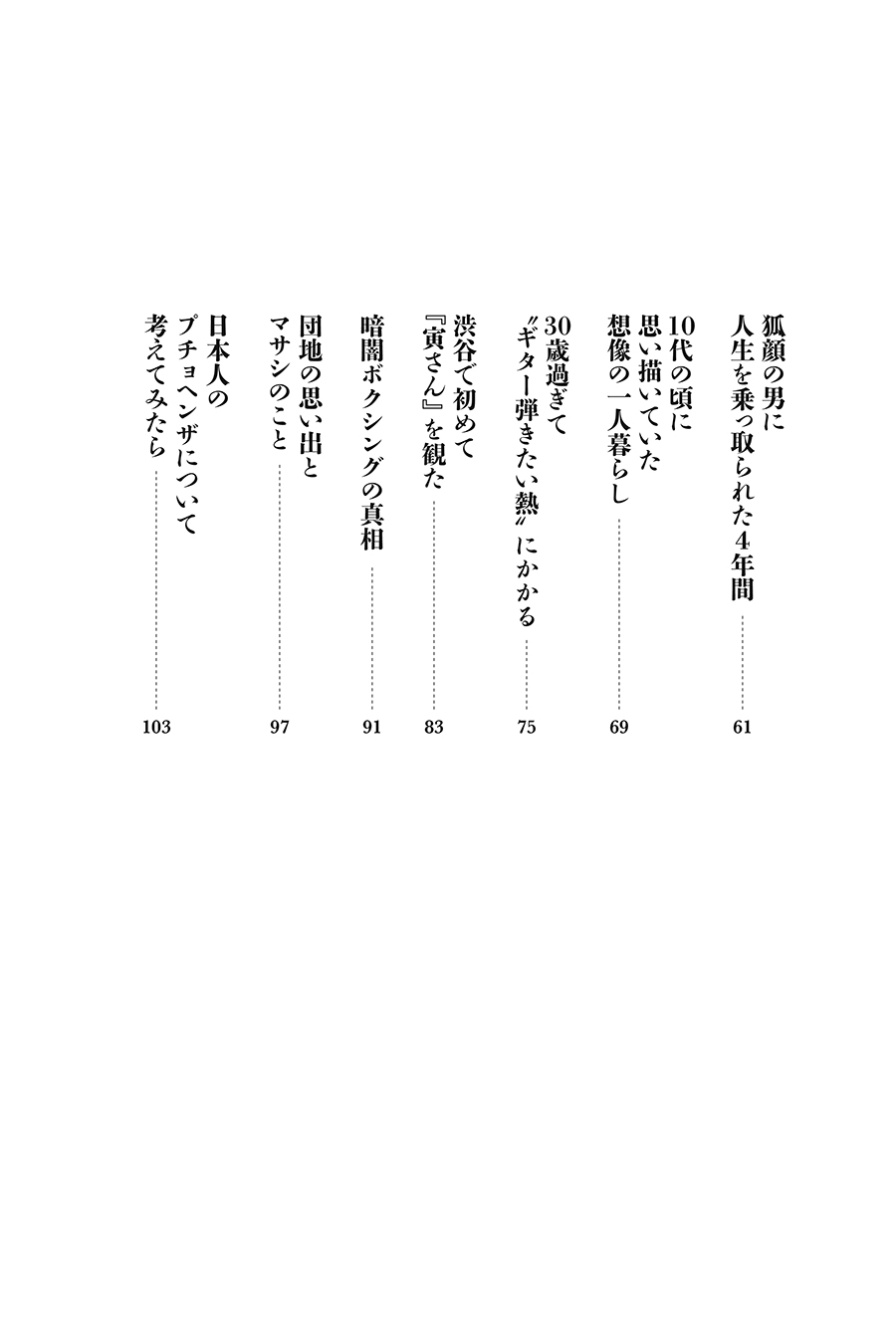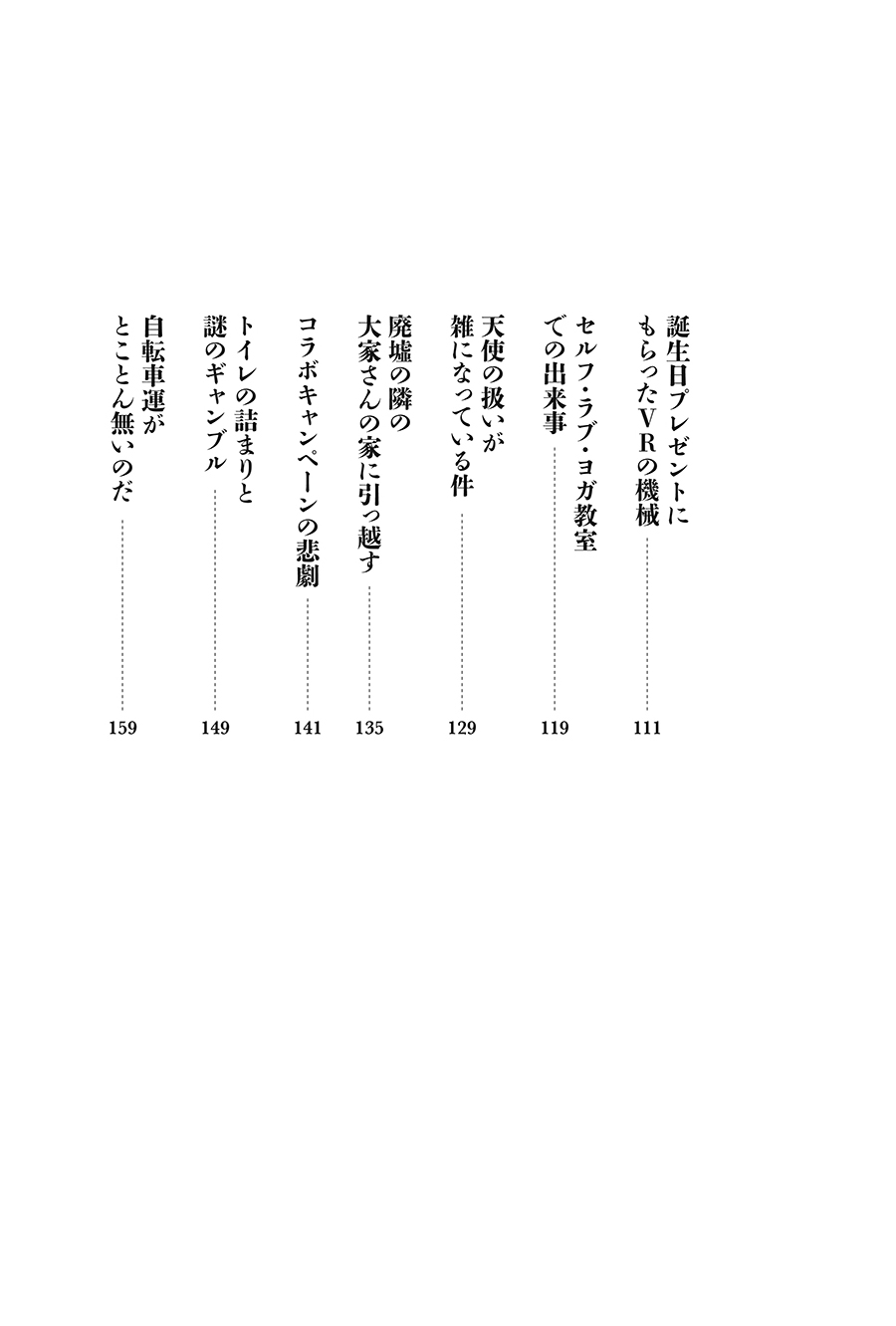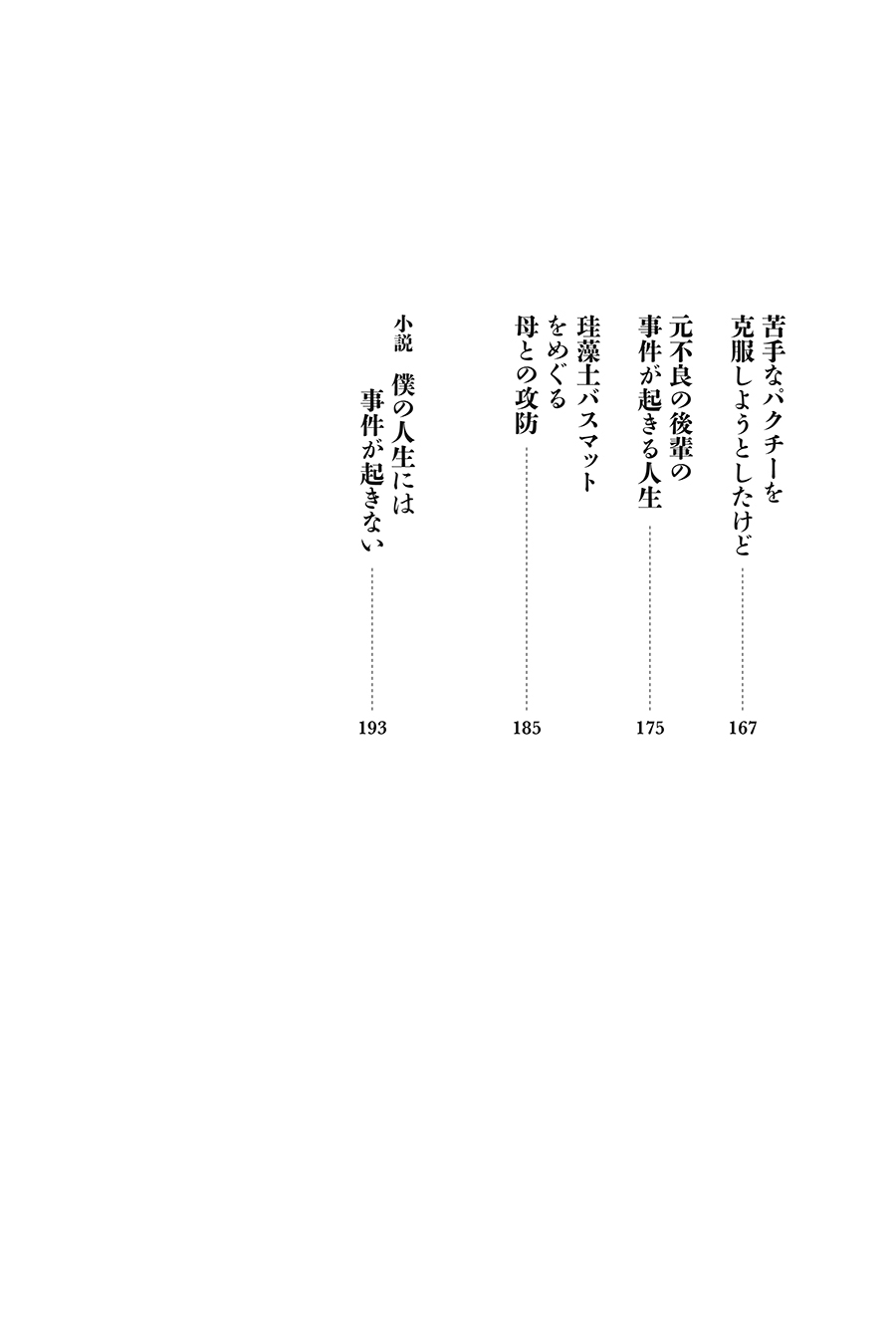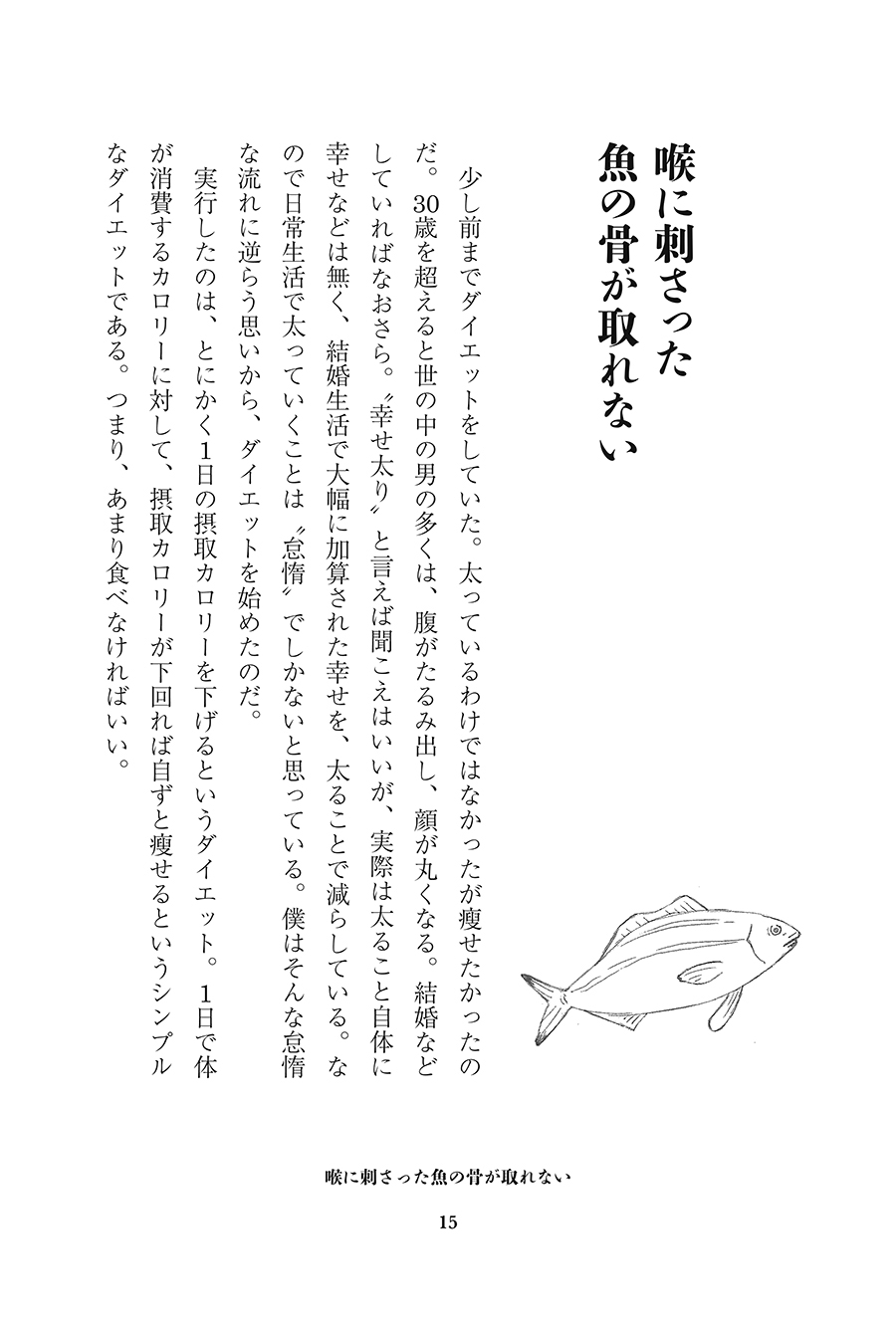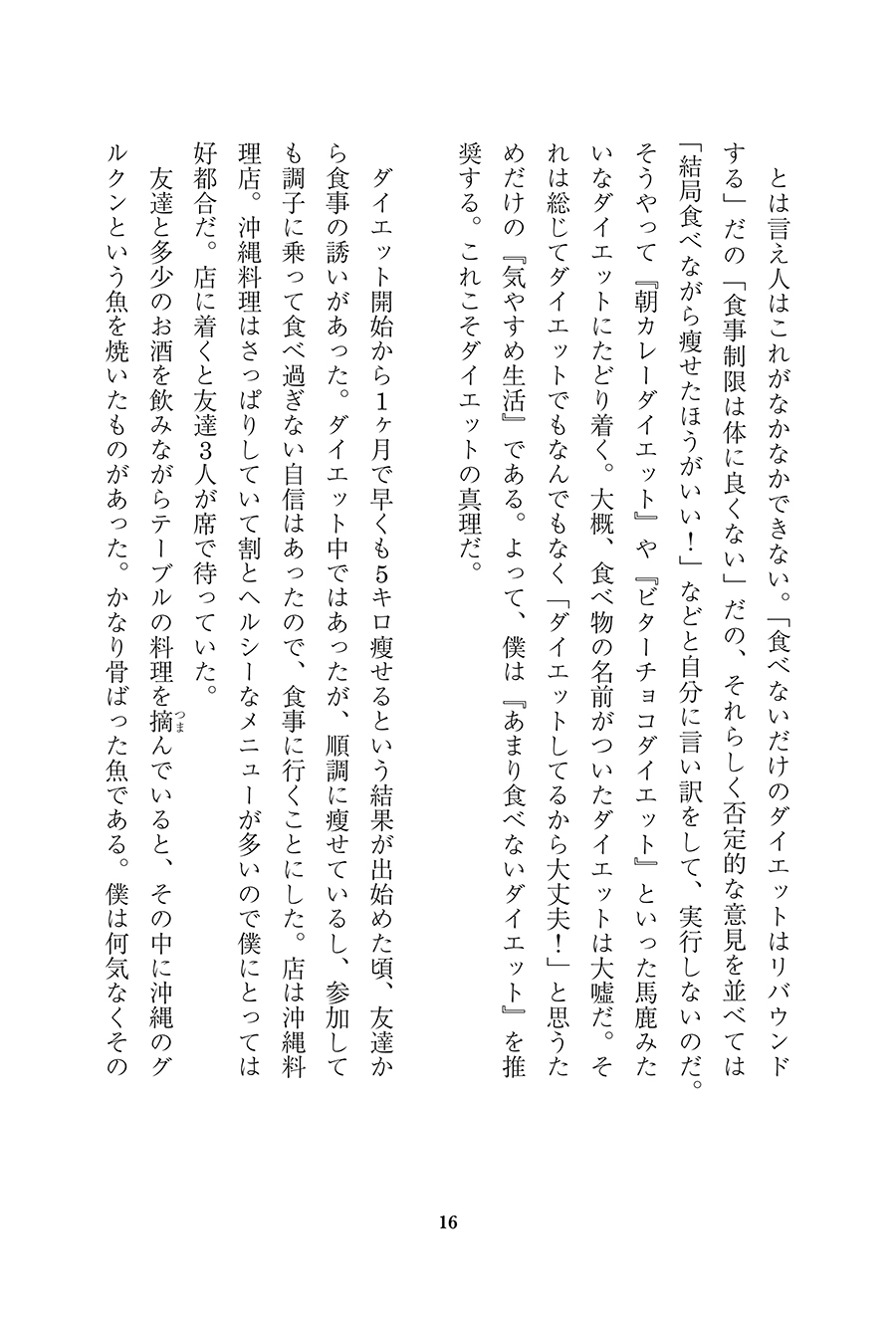喉に刺さった
魚の骨が取れない
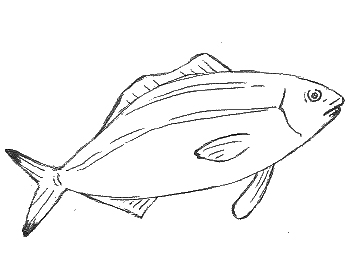
少し前までダイエットをしていた。太っているわけではなかったが痩せたかったのだ。30歳を超えると世の中の男の多くは、腹がたるみ出し、顔が丸くなる。結婚などしていればなおさら。“幸せ太り”と言えば聞こえはいいが、実際は太ること自体に幸せなどは無く、結婚生活で大幅に加算された幸せを、太ることで減らしている。なので日常生活で太っていくことは“怠惰”でしかないと思っている。僕はそんな怠惰な流れに逆らう思いから、ダイエットを始めたのだ。
実行したのは、とにかく1日の摂取カロリーを下げるというダイエット。1日で体が消費するカロリーに対して、摂取カロリーが下回れば自ずと痩せるというシンプルなダイエットである。つまり、あまり食べなければいい。
とは言え人はこれがなかなかできない。「食べないだけのダイエットはリバウンドする」だの「食事制限は体に良くない」だの、それらしく否定的な意見を並べては「結局食べながら痩せたほうがいい!」などと自分に言い訳をして、実行しないのだ。そうやって『朝カレーダイエット』や『ビターチョコダイエット』といった馬鹿みたいなダイエットにたどり着く。大概、食べ物の名前がついたダイエットは大嘘だ。それは総じてダイエットでもなんでもなく「ダイエットしてるから大丈夫!」と思うためだけの『気やすめ生活』である。よって、僕は『あまり食べないダイエット』を推奨する。これこそダイエットの真理だ。
ダイエット開始から1ヶ月で早くも5キロ痩せるという結果が出始めた頃、友達から食事の誘いがあった。ダイエット中ではあったが、順調に痩せているし、参加しても調子に乗って食べ過ぎない自信はあったので、食事に行くことにした。店は沖縄料理店。沖縄料理はさっぱりしていて割とヘルシーなメニューが多いので僕にとっては好都合だ。店に着くと友達3人が席で待っていた。
友達と多少のお酒を飲みながらテーブルの料理を
その時も、僕は大方骨を噛み砕いて飲み込んだ。するとその瞬間、喉の奥に激痛が走った。それと同時に僕は「かはっ! かはっ! うえぇっ!」と、むせ返った。グルクンの骨が喉に刺さったのだ。とっさに目の前の飲み物を飲む。しかし良くならず、食べ物と一緒に流しこもうと思い、テーブルにあったゴーヤチャンプルーをかき込んだ。すると骨の位置が変わったのか、刺さった直後よりは少しマシになった。だが、むせ返らなくなっただけで、痛みは続いている。唾を飲み込むだけでも喉の奥がかなり痛むのだ。
友達も僕が悶絶していたのを見て心配し「何か大きめの食べ物を飲み込んだら治るんじゃない?」と唐揚げを差し出してきた。僕は何故かその時、ふと自分がダイエット中だということを思い出した。唐揚げは高カロリーでダイエットとは真逆の食べ物である。魚の骨が喉に刺さったせいで、今それを食べることを勧められている。
しかし、背に腹は代えられない。僕は差し出された唐揚げを箸で取り、そのまま口に運び、半ば丸飲みした。悲しいことだ。ダイエット中、散々我慢していた高カロリーな食べ物を、痩せ切った後存分に味わおうと楽しみにしていたのに、こんな形で丸飲みさせられるのだ。人生で一番悲しい丸飲みである。悲しみの丸飲みである。心の中では泣きながらその唐揚げを丸飲みしたが、骨は取れなかった。丸飲み損だ。おばあちゃんの“はっさく吐き出し”を気持ち悪がらなければよかった。最悪である。
その後も喉の痛みは続いていたので、僕は携帯電話で魚の骨が喉に刺さった時の対処法を調べた。するとやはり「食べ物を飲み込むと取れる」とあったが、そこには「ご飯を多めに飲み込むと取れることがある」とも書かれていた。メニュー表を手に取り、何かご飯を使った料理がないか目を通す。すると『ジャンボおにぎり』というメニューがあった。このおにぎり、中身は沖縄で良く使われる油味噌らしい。油の味噌である。『油味噌を使ったジャンボおにぎり』など、ダイエット中の僕にとってみれば『カロリー』と言っているのと一緒だ。だがご飯を使ったものはそれしかないようなので注文し、しばらくするとその『ジャンボおにぎり』が届いた。
かなり大きい。通常のおにぎりの2・5倍はありそうな大きさだ。魚の骨が喉に刺さっている僕は、そのおにぎりを多めに頬張った。味が濃そうな油味噌も、かなりの量がおにぎりの中に入っている。そして、ろくに噛まずにそれを飲み込んだ。飲み込んだ直後にわかった。骨は取れていない。痛みは続いている。なので一口、もう一口と、僕はカロリーを飲み込んでいった。摂取したくないカロリーを
友達3人もしばらくすると、テンションが下がっている僕にも慣れてしまって、キツめのハブ酒を飲んだり、サーターアンダーギーにアイスがかかったデザートを食べながらはしゃいでいる。僕はその楽しそうなノリに参加する気になどなれない。何故なら魚の骨が喉に刺さっているからである。しかしながら、魚の骨が喉に刺さっている友達が目の前にいるのに、酒や甘味ではしゃぐのもどうかしている。きっとコイツらは魚の骨が喉に刺さったことがないんだろう。この世には2種類の人間がいる。それは魚の骨が喉に刺さったことのある人間と、ない人間である。魚の骨が喉に刺さったことのない人間は、得てして魚の骨が喉に刺さっている人間を見下しがちである。
僕は、喉の奥の痛みを抱えながら、魚の骨が喉に刺さっていなかった頃は良かったなぁ、などと考えていた。普段何気なく生活してきたけれど、いざ魚の骨が喉に刺さってみると、あの普通の日々は幸せなことだったんだと気付くのだ。しかしその頃にはもう遅く、魚の骨が喉に刺さっていない日常はもう戻って来ない。この先は魚の骨が喉に刺さった人生なのだ。魚の骨が喉に刺さると、それらを思い知らされるのである。
もう家に帰って寝たい。もしかすると寝て起きたら魚の骨が取れているかもしれない。そう思った僕は、友達3人に「今日はもう帰るわ」と告げた。それが恥ずかしいことだというのはわかっている。何故なら大人なのに魚の骨が喉に刺さったくらいで帰るからだ。だが魚の骨が喉に刺さったまま何をしていても楽しくないし、友達も魚の骨が喉に刺さった奴と一緒に居ても楽しくないだろう。お金を置いて店を出て、家に帰った。そしてその日は早めに寝たのだ。
次の日、早朝に目が覚めた。すぐにわかった。魚の骨は取れていない。寝てる間に取れてくれるか、どこかで骨が喉に刺さったことが夢であってくれとも思っていたが、魚の骨が喉に刺さったという事実は確実にあったのだ。その日は朝から仕事だった。仕事は嫌いではないし、むしろ好きだ。しかし、それは魚の骨が喉に刺さっていない状態でする仕事が好きなだけであって、魚の骨が喉に刺さった状態でする仕事は辛いものでしかない。むしろ、魚の骨が喉に刺さった状態で仕事をするなら、魚の骨が喉に刺さっていない状態の無職の方がマシである。
だがそうも言っていられず仕事に行き、どうにか痛みに耐えながら仕事を終わらせた。その後で、僕はもういっそのこと病院に行くことにした。
耳鼻咽喉科を携帯電話で調べて電話したが、やっていなかった。運悪く、その日は祝日だったからだ。何が祝日だよ! 人が魚の骨が喉に刺さって苦しんでる時に祝ってんじゃねぇよ! と、僕は思った。しかも海の日だったのだ。魚の骨と休診日という、とんだ海からの贈り物である。
何軒も病院を調べたが、どこもやっておらず絶望していると、一か八かの手段を思いついた。行きつけの歯医者なら骨を抜いてくれるんじゃないかということだ。早速、歯医者に電話すると「見ないとわからない」ということなので僕は歯医者に向かった。
歯医者に着くなり「どうぞ」と案内され、治療室に通される。そして先生が来て、喉の奥を明かりで照らしながら覗くと「あー。刺さってる刺さってる」と言った。そして長めのピンセットを取り出し、その骨を摘んで、引き抜いたのだ。一瞬痛みが走ったものの、今までの痛みが喉の奥からかなり消えたことに気づく。その後、先生が念入りに僕の喉の奥を見て「これで大丈夫だと思う」と僕に言った。先生のその言葉に僕は安堵した。
すると先生は「喉は大丈夫だけど、虫歯になりかけの歯があるからついでに治療しとくね」と言いながら、歯の治療を始めた。素晴らしい。ここは歯の治療もしてくれるのか。いい魚の骨抜きクリニックだ。治療が終わると、先生が「骨は抜けたけど、刺さってたところが傷になってるから、まだしばらく少しだけ痛むと思うけど2、3日したら治るから」と僕に告げた。そして僕は歯医者を後にした。
楽しかった日常が一瞬で暗い日々に変わってしまうことがある。自分は大丈夫、と思っていても、魚の骨が喉に刺さるというのは誰にでも起こりうる災厄なのだ。
そして骨が抜けた後もしばらくは気持ちが沈んでいたので、あまり何かを食べる気になれず、少し体重が落ち、僕はダイエットに成功したのだった。
1人居酒屋デビューした
前乗りの夜
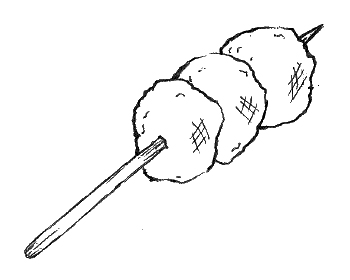
大阪で仕事があった。久しぶりだ。前日の夕方に東京を出て大阪へ行き、ホテルで1泊して仕事当日を迎える、いわゆる“前乗り”というやつだった。だが、僕はこの“前乗り”というやつがあまり好きではない。
そもそも前乗りが好きな人の理由としては、前日の夜に現地のご飯を食べに行ったり、夜遊びできることが大半を占めると思うのだが、僕が前乗りで地方に泊まる時は大概1人であり、僕は1人で何処かに行くことが非常に苦手なのだ。
住んでいる東京都内にいても、1人で何処かに行くことが苦手なのは変わらない。一人暮らしだと、一般的には夕食をどこかの店に1人で入って済ませることや、1人で飲みに行くこともあるのだろうが、僕にはそれができない。ラーメン屋やファストフード、カフェといった1人客が沢山いるような店ならまだしも、ファミレスや居酒屋といった飲食店に僕1人で入ったことがほとんど無い。
旅行もしかり。1人旅はもってのほかで、必ず誰か友達を誘って行く。これは、1人で店に入ったり観光地を回ったりするのが恥ずかしいという、大人らしからぬ気持ちも多少あるが、それよりも僕は1人で知らない場所へ行って帰ってきた時に、本当に行ったのか? と思ってしまうからだ。
例えば自分が知らない土地へ旅行に行き、観光地を回って、美味しいものを食べて帰ってくるとしよう。1人旅の場合、何を見ても食べても、それを知りうる人物が自分しかいない。現地の人は僕のことなど知る由もなく、そうなると帰ってきた時に、本当に旅行に行ったのか? と思っても、誰にも確認ができないのだ。
旅行中見たものや、食べたものも怪しくなり、観光地に行っても旅館でダラダラしていても、その土地の美味しい料理を食べてもチェーン店のハンバーガーで済ませても、一緒のように思えてきてしまう。
その旅行をしていた時間、自宅で現地の観光名所や名物をパソコンで調べて、妄想を膨らましていただけだったんじゃないか? と疑い始めても、1人ではそれを完全に否定することができないのだ。
そんな理由で、夜に1人でご飯を食べに行けない僕は、前乗りしても時間を持て余してしまう。
大阪に着いたのが夜7時で、少しお腹は空いていたのだが繁華街に行くことに尻込みしてしまい、一旦ホテルにチェックインしたのだった。ホテルの部屋に入って荷物を置き、やることも無い僕はベッドの上でぼーっとしていた。そして、ふと時計を見ると、なんともう10時半になっていたのだ。
僕は一瞬目を疑った。大阪に着いたのが夜7時。駅からホテルの部屋に着くまではせいぜい30分といったところだろう。7時半から10時半までの3時間、何もせず、ぼーっとしたまま過ごしてしまった。ぼーっとするとは、何かをぼーっと考えていた訳ではなく、ただ単にぼーっとしてしまっていただけなのだ。
全く無駄な3時間。時空が歪んで7時半の世界から10時半の世界に飛ばされていたとしても、全く同じことである。
精神上、空白の3時間に僕は恐怖を覚えた。もしかすると僕の中の別の人格が現れていたのかもしれない。別の人格が、ぼーっとしている僕の隙を突き、体を乗っ取ったのだ。
そいつは大阪好きの人格で、大阪に来る機会をずっと窺っていて、まんまと体を手に入れた。そして大阪の街に繰り出し、たこ焼きを食べ、お好み焼きをおかずに白米を食べ、道行く大阪のおばちゃんからアメちゃんを貰い、通天閣を見に行った後、道頓堀に飛び込み、カラオケで服を乾かしながらドリカムの「大阪LOVER」とウルフルズを歌って、最後は大阪の街に「おおきに!」と言い放つ“大阪フルコース”を、3時間で回って帰ってきたのではないだろうか。そんな人格が現れていてもおかしくないほど無意識の3時間だった。
こんな時間を続けていたら、その大阪好きの“なにわ太郎”の人格に体を完全に奪われかねない。そう思った僕は、意を決して1人で何処かの店に夕食を食べに行くことにした。しかし周辺の店を調べてみると、時間的に夕食を食べられるような飲食店は終わっていて、営業しているのは何軒かの居酒屋のみだったので、その1つに行くことに決め、ホテルを出た。
しばらく歩くと、その店の灯に照らされた看板が見えてきた。前まで行くと、外から店内が見えるようになっていて、そこはカウンターだけの8席ほどの古びた焼き鳥屋であった。
店の前まで来ると少し緊張する。なにせ1人で飲み屋に入ることなど初めてだ。しかし店内が見えるということは、向こうからも店の前で僕がまごまごしている様子を見られてしまうということだ。僕は勇気を振り絞って店の扉を開けた。
「いらっしゃい」と、40代くらいの男性店員と30代くらいの女性店員が落ち着いたトーンで言った。僕は軽く頷き、カウンターの一角に座った。店内を見回すと、かなり昔からあるような年季の入った店内。僕の他には2人の客がいる。
女性店員が僕におしぼりを渡しながら「飲み物何にします?」と聞いた。その時、女性店員の首元にタトゥーが入っているのが見えてしまい、僕の緊張感をより一層高めた。そして、そんなざわついた心で飲み物を注文したため「生の……ち、ちゅうで……」と、恐ろしいほど小声になり、店員に「はい?」と強めに聞き返されてしまうという、1人居酒屋デビューとしては最悪の幕開けとなったのだった。
名誉挽回を図るため、焼き鳥を注文する際「焼き鳥5本、お任せで」という、恐らく焼き鳥屋上級者がやるであろうお任せスタイルをとった。他にもホヤ酢という渋いメニューの選択で、鋭さを見せつけるのだった。
その後すぐに、僕の目の前にビールが運ばれてきた。普段は家でも1人で酒など飲まないのだが、運ばれてきた冷えたビールを一口飲んだ。それは、今まで飲んできたどのビールより美味しい気がした。
それまで知り合いと一緒の場でしかお酒を飲んだことがない僕は、知り合いにかまけてビールと1対1で向き合ったことがなかったのだ。それは、大学のサークル内の男女数人でよく遊んでいたが、ある日その中のあまり喋ったことのない女子と一緒に帰ることになり、なんとなく喋っていて「あれ? この子意外と可愛くね?」と気付いた時のような感覚だ。大学に行ったことがないのでわからないが。
ビールを二口、三口と飲んでいると「ホヤ酢ですー」と言いながら店員が僕の前に器を置いた。僕は一瞬目を疑った。渋いメニューの選択と思って頼んだはずのホヤ酢が、なんとコンビニのパンに付いてくるシールを集めて貰ったような可愛いクマのキャラクターの描かれた器に盛られていたのだ。
ホヤ酢とこの器の辻褄の合わせ方がわからない。ウツボが描かれた器ならなんとなくわかる。しかし描かれているのは可愛いクマだ。クマ自身もできればチョコレートやグミや小さいシュークリームなどを、何個か乗せてほしかったことだろう。ホヤを酢で和えたものという、可愛さのかけらもない珍味を乗せられ、どこかクマも苦笑いである。
それからしばらく経って、お任せで頼んでいた焼き鳥が1本ずつ運ばれてきた。
まず鳥もも、そして手羽先、つくね、白レバー、牛ハラミ。なんだか良さそうな串ばかりだな……と思い、何気なくメニューを見てみると、出てきた5本は綺麗に、焼き鳥の値段の上から順に5本だったのだ。
やられた。元々僕が上級者の頼み方をしようとしていたことなど見抜かれていて、そこを利用されたのだ。悔しい。白レバーなど一番高い串で、鳥皮の3倍の値段だ。正直鳥皮が食べたかった。
僕は店員のやり口に怖くなり、そそくさと焼き鳥を食べ、ホヤ酢をかっ込んで、すぐ会計を頼んだ。ホヤ酢をかっ込んだことなど初めてである。
そして会計はやはり思ったより少し高い。見事に1人飲み初心者への洗礼を受けた。渋々会計を済ませ、店を出る。その時の店員の「ありがとうございました〜」という声が、少し酒の回った僕の頭の中に不気味に響いたのだった。
大阪の夜、僕はホテルに帰りながら、飲みに行く時は誰かを誘ったほうがいいな、と再確認したのだった。“前乗り”というやつもどうやら好きになれそうにない。そう思った。
狐顔の男に
人生を乗っ取られた4年間
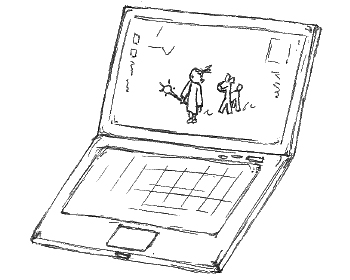
高校を卒業して進学しなかったので、暇だった。1日6時間程度のバイトに週4、5回行き、実家暮らしだったので他にすることも無く、バイト以外の時間をダラダラ過ごしていた。
そんなある日、暇を持て余した僕は、ふとCMで観た無料で遊べるパソコンゲームを、無料という触れ込みにまんまと誘われて、実家のノートパソコンを使ってやってみることにしたのだ。
選んだのはオンラインのロールプレイングゲームだった。冒険をしながら敵を倒してレベルを上げてまた冒険、といったゲームなのだが、オンラインなのでゲーム画面に他のプレイヤーが存在している。一緒に戦うこともできるし、もちろんチャットを使って会話もできる。
僕は初めてのオンラインゲームにワクワクしながら、インターネットでゲームをダウンロードしたのだった。
パソコンにゲームが入ると、まずは自分の使うキャラクターを作る画面になる。顔のパーツも細かく選べるので、とりあえず僕に似せた目の細い狐顔のキャラクターを作った。今考えれば、ゲームの中くらいパッチリした目の男前になれば良いのに、なぜ狐顔にしたのだろう。
作った後は、そのゲームの中心となる街からスタートするのだが、初めてのオンラインゲームの世界は新鮮だった。とにかく街を人が行き交っている。それもゲームの運営側が用意したキャラクターではなく、今まさに誰かが操作しているキャラクターなのだ。
動きが規則的ではなく、自由に走り回っている。さらにプレイヤー同士のチャットでは「あのボスが倒せなくてさ〜」「最近、洞窟に新しいモンスター出るらしいよ」といった色んな会話がなされていた。ゲーム上に知らない人がたくさんいる。それだけで閉鎖的だった家庭用ゲームとは全く違う感覚だった。
僕は自分の作った狐顔の男を操作して、近くの建物に入った。そこにもプレイヤーが何人か居たが、操作に慣れる為、建物内を歩き回った後、部屋の端の椅子に腰をかけた。
すると丁度同じタイミングで隣の椅子に、
突然見知らぬ狐顔の男に話しかけられた甲冑の剣士は、僕に「?」と返した。言葉にならない返答に、若干怪しんでいるのが伝わってくる。僕は慣れないチャットで「今日このゲーム始めたばかりなんですけど、どうしたら強くなれますか?」と続けた。少しの沈黙の後、甲冑の剣士が「そりゃあ……こうやって街でぼんやり会話するのをやめて戦いに行くことだろうねぇ」と答えた。
僕にはその一言がすごく印象的だった。なんというか、その気の利いた見事な返しに、他のプレイヤーとコミュニケーションがとれるゲームって面白いかも、とゲーム初日で思えたのだ。僕はその後23歳くらいまで、4年近くオンラインゲームを続けていたのだが、それはその言葉に面白さを感じたからかもしれない。その剣士とは、それっきり会うことはなかった。
それから僕はそのオンラインゲームに熱中し、ゲーム、バイト、ゲーム、睡眠という1日を繰り返し、バイトのない休日もゲームに明け暮れた。次第にゲーム上でも知り合いができ、敵を一緒に倒しに行ったり、ゲーム内の情報を交換し合ったりと、その世界で充実した生活を送っていたのだった。
しかし、あの頃ののめり込み方は今考えると怖いところがある。オンラインのロールプレイングゲームの多くは、やり込めばやり込むほどキャラクターが強くなるように作られている。ということは、ゲームに時間を費やすことのできる人ほど強い。
ゲーム内の知り合いにも強い人は沢山いて、その人達は大概僕がゲームを開いた時にはそこに居るのだ。どんな仕事をしているのかは分からないが、生活の比重を相当ゲームに置いている。
しかし、ゲーム好きという共通点のある知り合いなので気の良い人も多く、僕が1日2日ゲームをやれなかったりすれば、次にゲームを開いた時にその人たちとの会話の中で「昨日と一昨日来てなかったね、どうしたの?」などと何気なく聞いてくれるのだ。大して深い意味はないのだろうが、それが積み重なっていくと、毎日少しでもいいからあの世界に行かなくちゃ、という考えになってくる。
そうしてどんどん生活の比重がゲームに持っていかれてしまい、その内バイトも少し減らし、睡眠時間もできるだけ削りながらゲームをするようになった。
一番のめり込んでいた時期は、僕でいる時間より狐顔の男でいる時間の方が多くなってしまい、僕の人生は狐顔の男に乗っ取られていたのだ。挙句、睡眠時間も削っていたので寝不足の僕の目はどんどん細くなり、僕自身もより狐顔になっていった。
僕が今でも目の細い狐顔と揶揄されるのは、狐顔の男に人生を乗っ取られていた、その頃の後遺症があるからである。昔から狐顔ではあったが、そこまで狐顔狐顔と言われるほど狐顔ではなかったので、より狐顔と言われてしまうようになったのは、あの狐顔の男のせいだろう。
4年近く狐顔の男の生活を送り、僕が僕の人生をどうやって取り戻せたかというと、突如そのゲームのサービスが終了することになったからだ。つまり、ゲーム自体が終わってプレイすることができなくなることが決まったのである。
長年その世界に居たからわかるのだが、僕がそのゲームを始めた頃より、確かにプレイヤーの人数は減っていた。プレイヤーが減っては運営が立ち行かなくなる。
狐顔の男の生活をしていた僕は落胆した。今までいた世界が無くなる。言うならば地球が破滅するのと同等である。地球は滅び、今まで培ってきた経験や文明は消し飛んで価値を失うのだ。
そして狐顔の男の存在も消滅する。そう思った瞬間、僕の意識は狐顔の男から離れ、僕は僕を取り戻したのだ。
終了するまでの数週間で、そのゲームから離れていっていたプレイヤーがちらほら戻ってくる。懐かしい知り合いと思い出話をしたり、久々に一緒に冒険に出て遊んだ。
そして、ついにその世界の最後の日がやってきた。よく遊んでいた知り合いは全員ゲームを開いていた。お互いどんな人なのか、なんの仕事をしているのか、年齢さえも知らない。しかしゲーム内の名前で呼び合うその人達にすごく親近感を覚えている。
僕等はよく集まっていた場所で最後の時を過ごした。一番気に入っていた装備を身につけ、ゲーム内で1対1で何度も対決して全く勝てたことのなかった知り合いともう一度対決した。そして負けた。「やっぱり一度も勝てなかったなぁ」と、しみじみ話すのだった。
集まった知り合い同士で「また違うゲームで見かけたら声かけて。同じ名前でやってるだろうから」「こんなにハマれるゲームなかったー」「まだ攻略できてない場所あったのになぁ」などと雑談していると、ゲーム終了まで残り数分となった。僕は何気なく集会所の隅の椅子に腰をかけた。そこはゲームを始めた時、座って甲冑の剣士と話したあの場所だった。
それを思い出した時、同時にゲーム内での色んな思い出が蘇ってきた。なかなか倒せない敵を知り合いに手伝ってもらって倒したこと。自分のミスで仲間が全滅してしまい怒られたこと。ただただ雑談だけして1日終わったこと。始めたてのプレイヤーが強くなれるようにみんなで手伝ったこと。
僕は狐顔の男としてこの世界で生活していたのだ。
やがて、知り合いの1人が口を開き「俺はこれから仕事が忙しくなるから、もうこういうオンラインゲームはできないけど、このゲームにみんなが居てくれたから楽しかったよ」と言った。
僕は泣いた。両目から涙が出た。自分の住んでいる世界とは違うけど、この世界は確実にあったのだ。チャットなのでわからないが、他のプレイヤーも泣いていたかもしれない。
各々「またね」「さよならー」と挨拶をし、ついにその時がきた。ゲーム画面が止まり「長らくのご愛顧ありがとうございました。ゲームのサービスを終了しました」という文字が表示された。僕はパソコンを閉じた。これを機に、僕もオンラインゲームを辞めたのだった。
あのゲームをしていた4年間のことはたまに思い出す。そして、もしまたオンラインゲームをやることがあれば、その時はまたキャラクターを狐顔にしようと思うのだった。
10代の頃に
思い描いていた
想像の一人暮らし
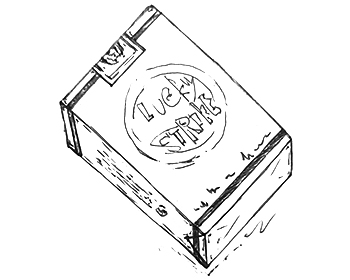
30歳になった頃、僕の遅めの一人暮らしは始まった。30代であろうが、初めての一人暮らしにはそれなりにワクワクした。お風呂に入る時間も決まっていなければ、何時に寝てもいい。食パンにマーガリンをどれだけ塗ろうが文句を言われないし、ベッドの上でアイスを食べても怒られない。アイスを布団にこぼしてカバーを汚してしまっても自分で洗えば済む話だ。一人の王国は、良くも悪くも無秩序だった。
しばらくその無秩序を楽しんでいたのだが、徐々に新鮮さは薄れ、始めたての興奮は、4年も経てばほとんど効き目を失っていた。そして、冷静になって自分の一人暮らしを思い返してみると、僕が求めていた一人暮らしは、どこかこうじゃなかったような気がした。
この違和感の正体をなかなか掴めずにいたのだが、最近分かったのである。恐らく今の一人暮らしが、僕が10代の頃に思い描いていた“一人暮らし”と違うからだ。
僕の遅めの一人暮らしは、20代で始める一人暮らしよりも経済的に余裕があったので、メゾネットタイプのアパートに住み、好きな家具を買い揃え、さらには車にも乗って快適に暮らすというものだった。これが10代の頃の僕の想像とのずれを生んだのかもしれない。
僕が10代の頃に思い描いていた一人暮らしのイメージはなぜか詳細だ。
外観が団地とも取れる
雲がぽかんと浮かぶ晴れた日、僕はフリーターなので昼の3時くらいにベランダに置いてある洗濯機を回し、その横に座ってタバコをスパーっと吸いながら、下を通る下校途中の小学生をぼーっと眺めている。
別の日は、バイト終わりの夕方。肉屋でコロッケを買って、袋をぶら下げながらマンションに帰ると、入り口を大家さんがほうきで掃除しており「ちわー……」と挨拶をしてマンションの階段を上る。
わかるだろうか。10代の頃に思い描いていた一人暮らしとは、この感じの一人暮らしだ。サイケデリックな色の、
夏の暑い日。エアコンが壊れているので、青と白のストライプのトランクス一丁になりながら扇風機だけでしのいでいたが、それが限界に達する。そこで冷蔵庫の冷凍室を開けて、箱に入った3種類くらいの味があるフルーツの棒アイスを食べようとするが、箱の中にはアイスが1本しか入っておらず「最後の1本か……」と、こめかみから汗を流すのだ。
同い年くらいの彼女がおり、髪はストレートロング、明るめに染めてはいるが脳天は真っ黒で、完全にプリンになってしまっている。僕が家で寝ているとガチャっと入ってきて、部屋に散らかっているゴミを2、3個拾ってゴミ箱に捨てる。そして、ちゃぶ台の上にある3日前くらいに食べたカップ麺の残り汁の入った容器を見て「ウゲー……」と、舌を出しながら言うのである。
別の日、僕がバイトの給料日前に金欠でいると、また家に彼女が来る。彼女は空腹でゴロゴロしている僕を見て「ほらよ」とタバコを1箱投げてくれるのだ。僕は彼女に向かって手を擦り合わせながら「神様仏様〜!」と言い、彼女からもらったラッキーストライクをスパーっと吸って煙を部屋の電灯に吹きかけながら「やっぱ空きっ腹で吸うタバコが一番うめーよなー」と呟く。それを見た彼女は、呆れたようでも嬉しそうでもある表情をうっすら浮かべ、ぶっきらぼうに「ばーか」と言うのである。
そんな彼女に、たまに「ごちそう食わせてやるよ」と言って、肉屋で3個入りのコロッケを買ってきて1つだけ半分に切り、1個半ずつにする。そして丼にご飯をよそい、千切りキャベツとコロッケを乗せてコロッケ丼を2つ作るのだ。最後に冷蔵庫を開けて卵を取ろうとすると、卵が1つしか無いことに気づき「あっ……」となるのだが、「特別だぞー」と言いながらその1つしかない卵を彼女の丼にだけかけて出してあげるのである。僕は「これがうめーんだよ」とガツガツとコロッケ丼を食べる。そんな僕を横目に、彼女も一口食べ「……あ、うまい」と言うのである。
中学の頃の同級生何人かと飲んでいると「今月営業ノルマきつくてさー」「今年中に会社から独立しようと思ってんだよ」など、みんな仕事の話に花を咲かせる。すると唐突に「最近どうなの?」と僕に話が振られ、僕は口ごもりながら「まぁぼちぼち……」と曖昧な返事を返すのだ。
次の日の昼過ぎにスーパーで買い物をして帰る途中、河川敷で野球をしている小学生のボールがこっちに転がってくる。僕は「兄ちゃんこっちこっちー!」と呼ぶ小学生の方にボールを投げ返し、その流れで小学生に混ざって本気で野球をするのだ。日も暮れてきて、夕方「兄ちゃんまたなー」と小学生たちは散り散りに帰っていく。僕は土手でひとりスーパーの袋を片手に、ぼんやり空を見ながら「就職かー」と呟く。
そんなある日、僕が家でテレビゲームをやっている横で、それを見ていた彼女が急に「ねぇ」と話しかけてくる。僕がゲームをやりながら「ん?」と聞くと、彼女は「子供できた」と言うのだ。ゲームをする手を止め、やっていたシューティングゲームは敵の攻撃を受け「バーン!」という効果音と共に画面に『GAME OVER』と表示される。そして僕は彼女の方を向き「そっか、じゃー結婚するか」と言うのである。
結婚を決めた僕は運送会社に就職し、彼女と一緒に住むことになる。こうして僕の一人暮らしは終わりを迎えるのである。
これが僕が10代の頃に思い描いていた一人暮らしだ。想像にしては夢がない。憧れていたわけではないのだが、こうなるんだろうなぁ、という予感がしていた。
今の一人暮らしはあの頃の想像とは全く違うけれど、決して悪くはなさそうだ。だが、今でもたまにこうやって、昔思い描いていた暮らしをしばらく想像してみるのである。
暗闇ボクシングの真相

ここ何年も運動という運動をしていない。高校生までずっとサッカーをやっていたので、やめて10年以上経つ今でも、その頃の筋肉や運動神経の貯金が残っている気がしていた。しかし現実はそんな貯金などとうの昔に使い果たし、オケラのくせに態度だけは金持ち気取りの没落貴族と化していたのだ。
筋肉が衰えたため首や腰に負担がかかり頻繁に痛くなることが続いていたので、一度病院へ行ってみると、やはり「定期的な運動をした方がいい」ということらしい。この「定期的な運動」というのは意外と難しい。
よくあるマラソンやウォーキングといった自発的な運動は、誰の監視下にも置かれずにやるのが基本なので、確固たる継続の意志を持っているか、それ以外に何もやることがない限りは続かない。スポーツジムに入会してトレーニング器具で定期的に運動をするというのも同様の理由でかなり難しい。そうなると、どこかのスポーツ教室のように監視する教官がいて、定期的に行かないと気まずい、という
先日、友達との会話の流れでこの話題になった。僕が「何か運動してる?」と聞くと、その友達は「やってるよ。暗闇ボクシング」と言った。
暗闇ボクシング? 全く聞いたことがない。なんだその狂気を含んだ響きは。呪われた一族に伝わる暗殺術かなにかだろうか。
その時、僕が
暗闇の中でボクシング? どういうことだ。対戦相手が見えないじゃないか。音や気配だけで相手を察知してパンチするのか。続けていれば五感は研ぎ澄まされそうだが。
しかし対戦相手の気配を感じてパンチしたなら良いものの、もしレフリーを殴ってしまっていては大変だ。そのまま気付かずレフリーをノックアウトしてしまった場合、反則負けになるのだろうか。暗闇でボクシングをやらせておいて、それで反則負けにさせられてはたまらない。
そう考えると、もしかしたらレフリーだけは暗視スコープのようなものをつけているのかもしれない。レフリーだけが暗闇の中でも見えているリングで、2人のボクサーが戦っている。奇天烈な格闘技だ。
観客はどうだ。携帯電話の明かりで照らすこともできないので、恐らくリング上のボクサーは見えない。シューズがキュッと擦れる音や、たまーに当たるパンチの音で楽しむのだろうか。それはもはやボクシングの試合を観に行き過ぎて、普通のボクシングの試合に飽きている人向けじゃないのか。セコンドの丹下段平も「打ってる? 打ってるのか? ジョー」と言うことだろう。
解説者の仕事も難しく、音だけを聞いての実況も容易ではない。しかも、会場が暗闇なので映像は映せず、ラジオのようなもので音声だけの中継になるのだろう。昔かよ。暗闇の中でボクシングをすることにおいての疑問は尽きない。
するとさらに友達は「サンドバッグをさ、暗闇の中で殴るのがいいんだよ」と言う。そうか、ボクシングジムに通うと言っても健康のために通っている人は、トレーニングを中心に行うことも多い。試合などはしないのだ。
それにしても暗闇の中でサンドバッグを見失ったりはしないのだろうか。というか、ボクシングジムのどこからが暗闇なのだろうか。それによってはサンドバッグまで辿り着けない可能性がある。サンドバッグのありそうな場所まで手探りで歩いてみて、とりあえずこの辺りかな? と思う場所を殴ってみるのか。サンドバッグの場所を見つけることに慣れるまで何日もかかりそうだ。
しかし実際に行ってみたら、ジムの受け付けからすでに暗闇の可能性もある。まず「すいませーん」と言ってみて「こちらへどうぞー」というような声のする方向が受け付けのカウンターだろう。そこで入会したいという旨を伝えれば、入会書を渡されるはずだ。暗闇の中で入会書を書くのは至難の業だが、とりあえず適当な場所に名前と電話番号と入会の動機などを書いて提出すれば、ジムの人もどこに何を書いたかは見えないはずなので問題なさそうだ。
だが、入会金を支払う時が厄介で「入会金、ン千円になります」と言われて払っても、払ったお札が何円札なのかがわからない。「一万円からお願いします」と言って一万円札を渡しても「これ、本当に一万円札ですか〜? 千円札なんじゃないんですか〜?」と疑われることだろう。暗闇受け付けでの金銭トラブルは必至である。暗闇ボクシングを始めるまでの道のりは長いのだ。
そもそも、なぜボクシングを暗闇の中でやるのだろう。暗闇の中にいると視界が無い分、見えるものに気を取られず、集中して自分と向き合えるということなのだろうか。
そんなストイックな精神でボクシングをやっているのなら、暗闇ボクシングの試合に出ろよ。なんで自分を高めておいて練習止まりなんだよ。ストイックなのか意識が低いのか、どっちなんだよ。
そんなことを思ったので、友達に「なんでわざわざ暗闇でボクシングやんの?」と聞いてみた。すると友達は「暗闇の中だと周りが気にならないから、集中して自分と向き合えるんだよ」と言った。
暗闇ボクシングの試合に出ろよ。お前ならできるよ。構えたミットのど真ん中に寸分
「暗闇って言っても薄暗い程度で、クラブみたいにライトアップされたジムで音楽かけながら、リズムに合わせてサンドバッグに打ち込むんだよ」
おいおいおい、とんだパーリーピーポーじゃねぇか。さっきまでの、自分と向き合って肉体と精神を高めていたストイックなお前はどうしたんだよ。まるで真逆の人間になっちまったじゃねぇか。
僕は幻滅した。清楚で純朴そうな、メガネをかけていて地味だけど顔は整っているクラスの女子が、プライベートでチャラついた一軍男子たちと遊んでいるのを見かけたような気分だ。
聞くところによると、暗闇ボクシングとは新手のエクササイズのようで、
不意に得た興味を一瞬で削がれることがある。僕は友達に暗闇ボクシングを一緒にやってみないかと誘われたが、断った。
運動はしようと思っている。もし僕の想像の方の暗闇ボクシングを見つけたら入会するかもしれない。