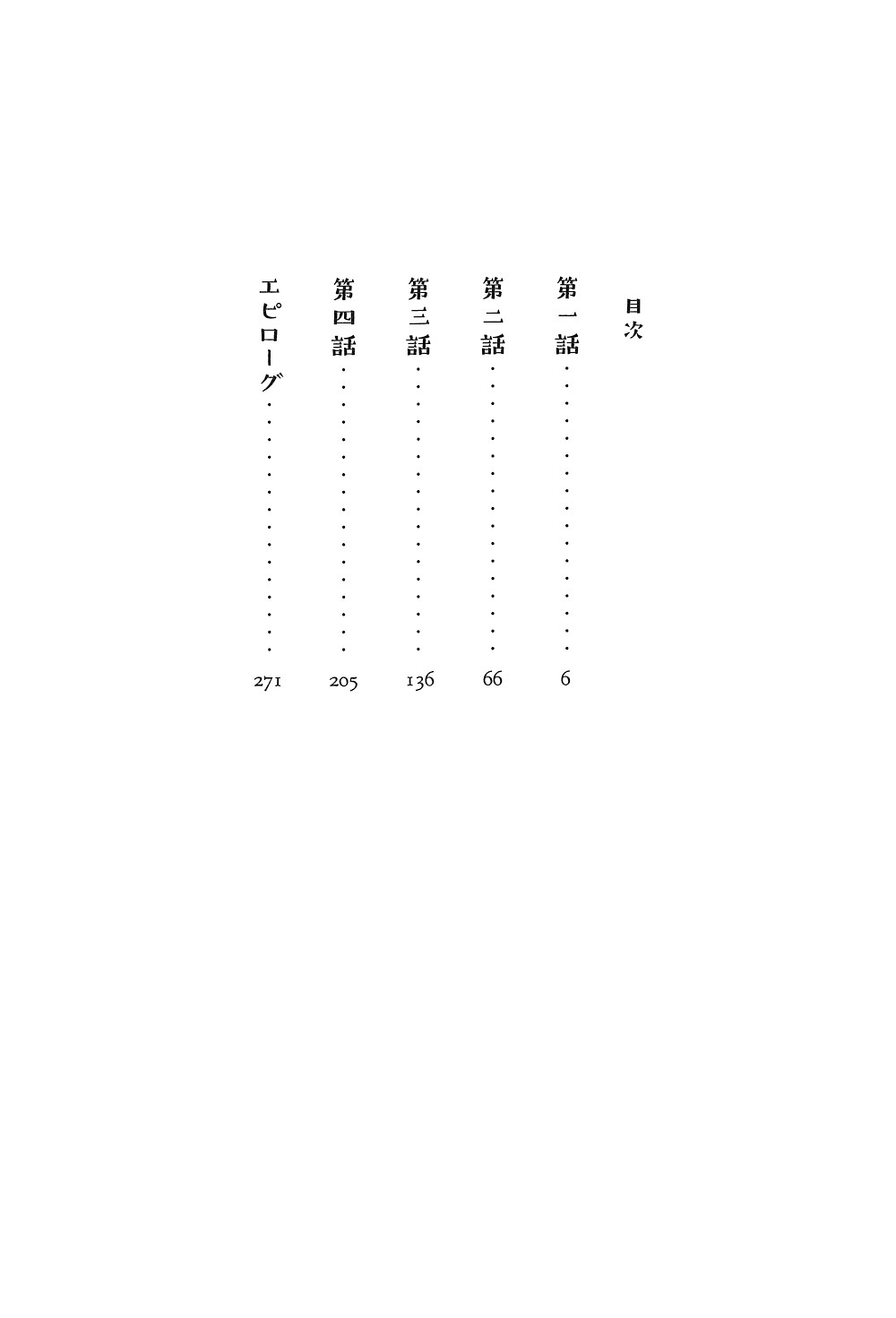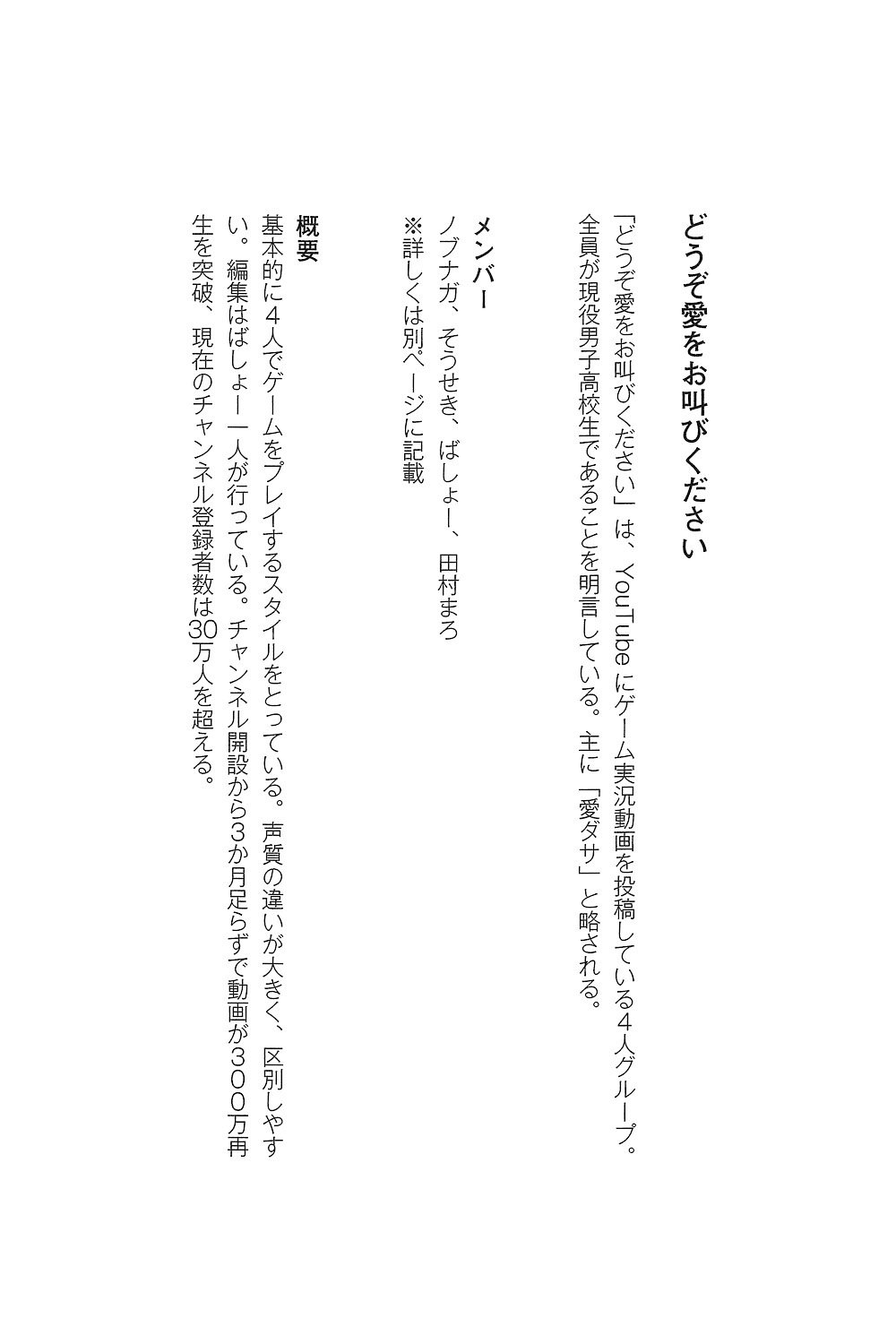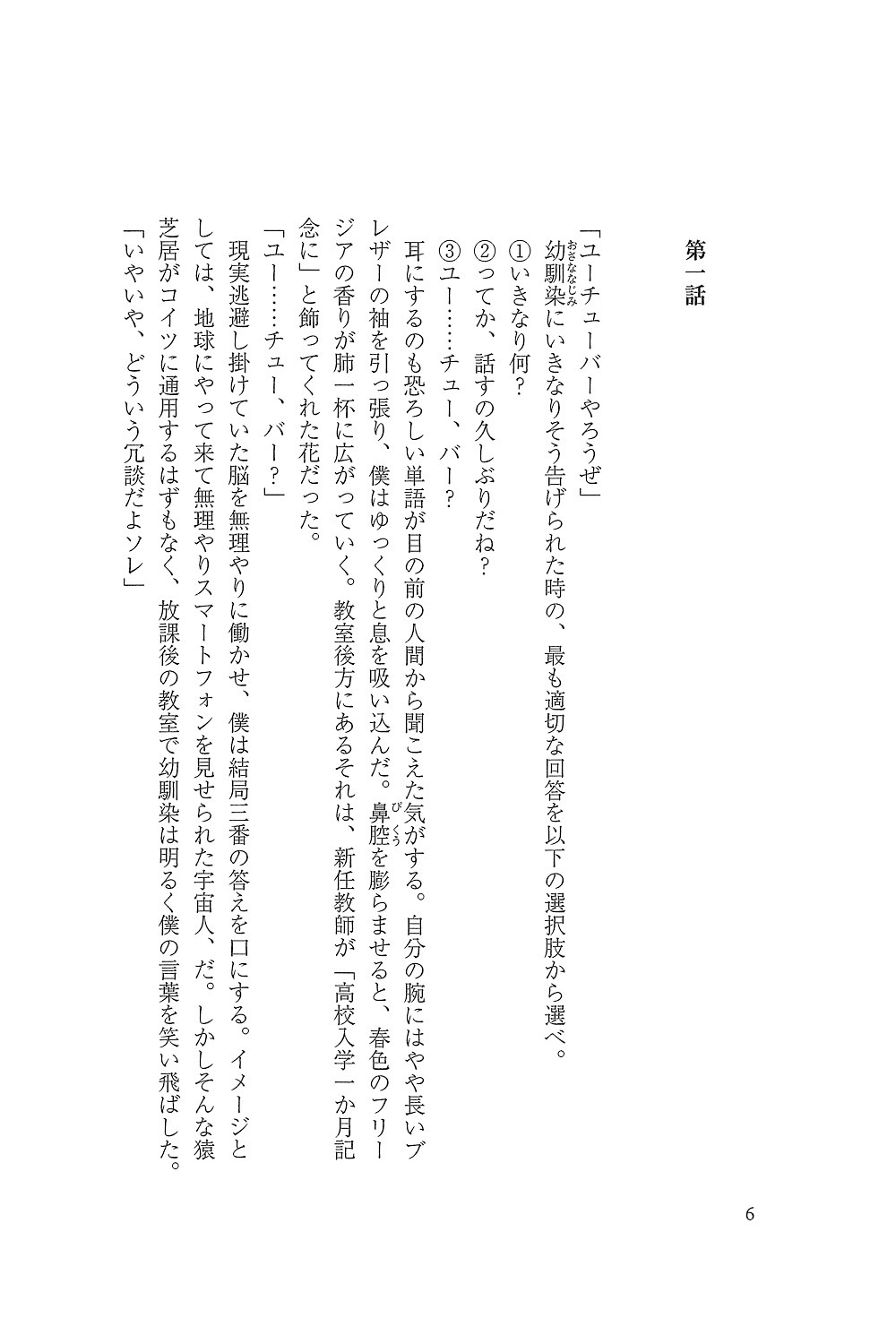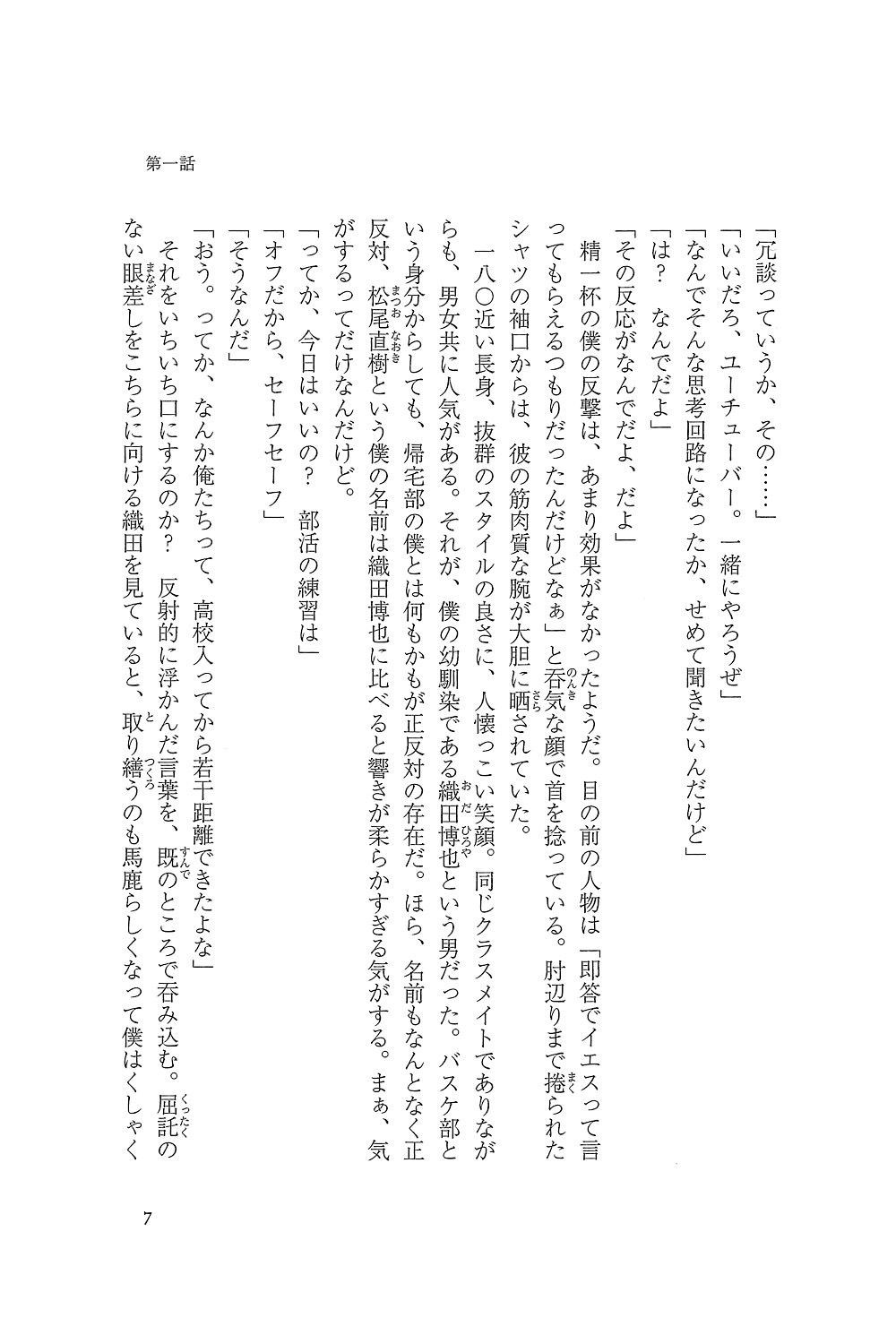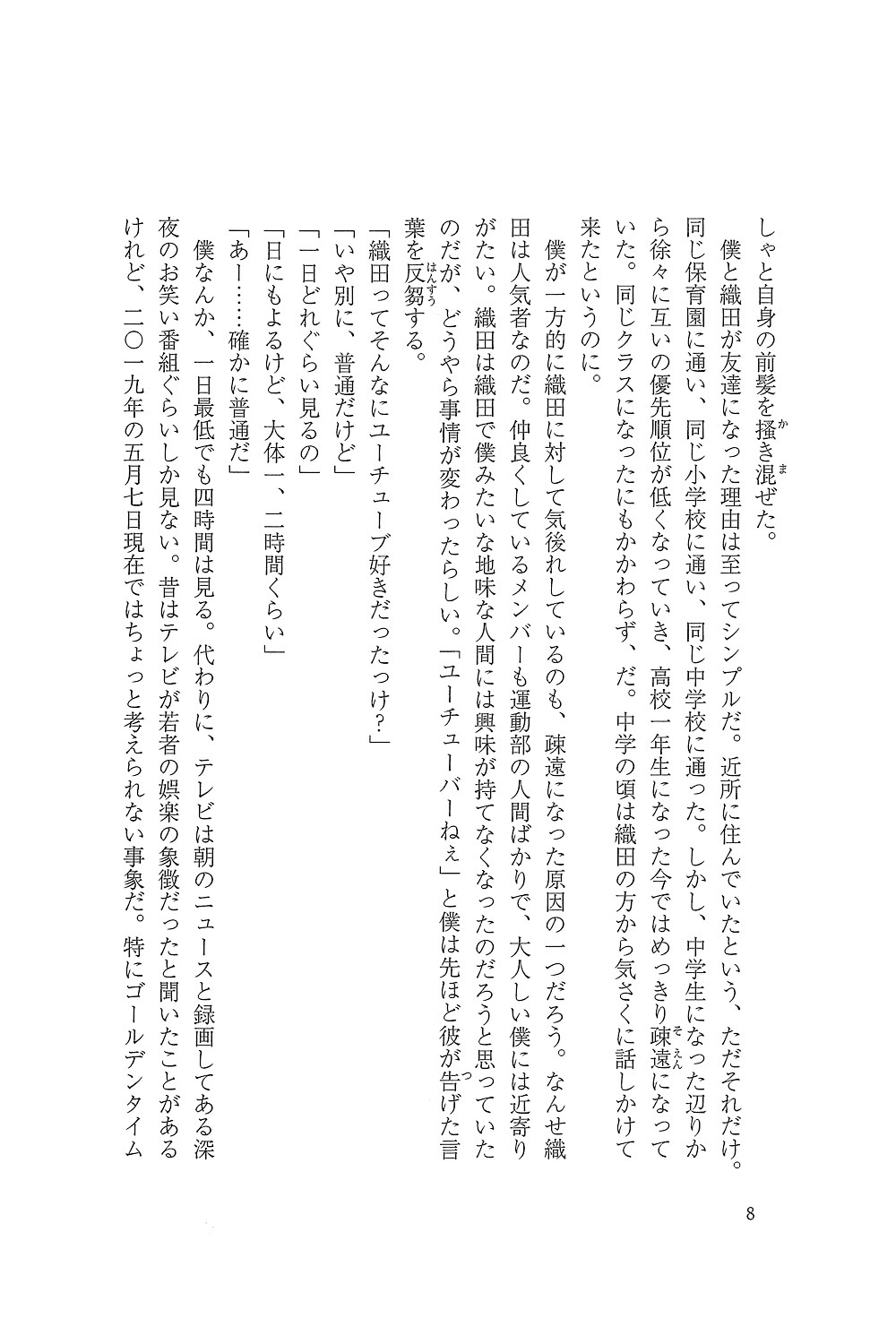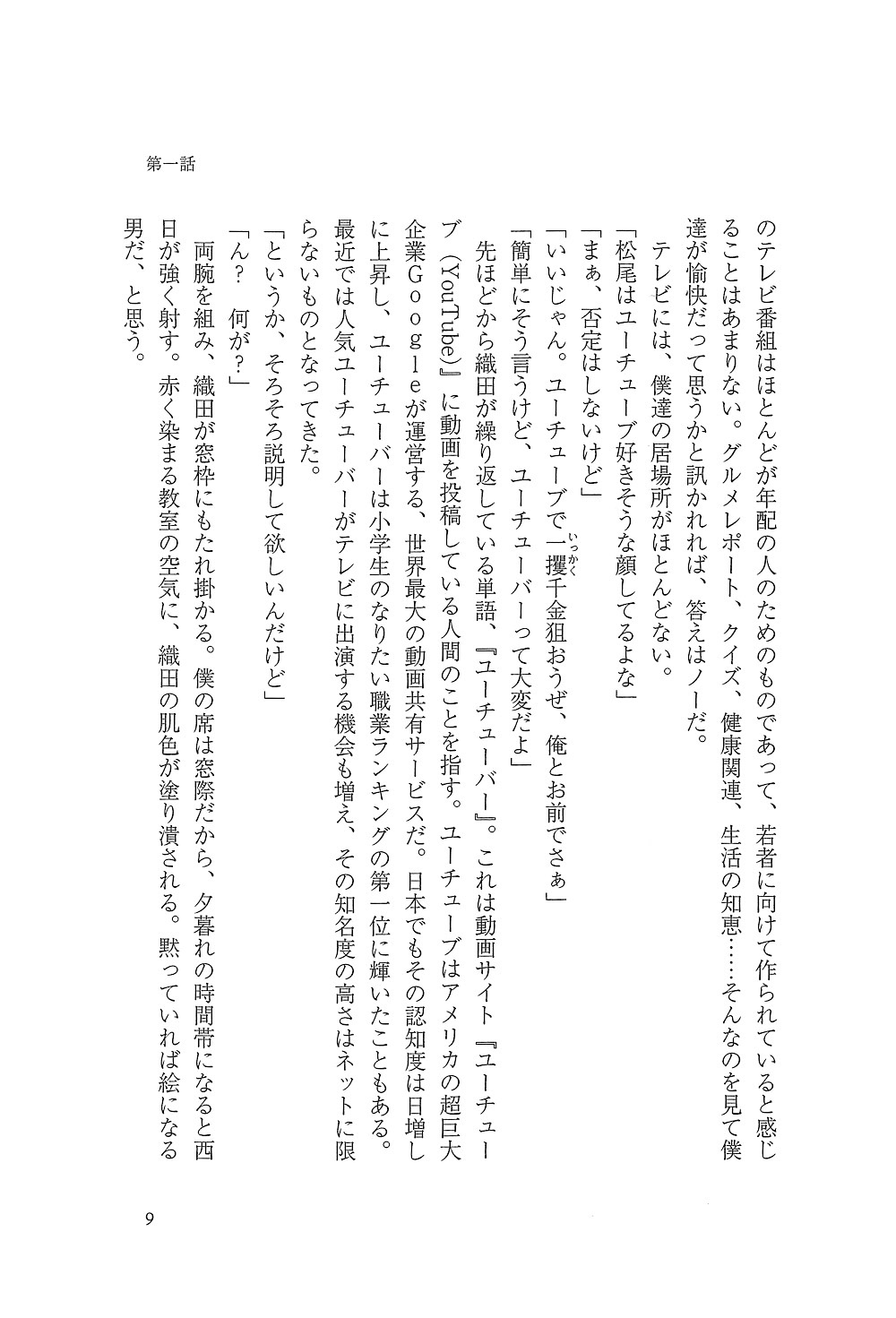どうぞ愛をお叫びください
「どうぞ愛をお叫びください」は、YouTubeにゲーム実況動画を投稿している4人グループ。全員が現役男子高校生であることを明言している。主に「愛ダサ」と略される。
メンバー
ノブナガ、そうせき、ばしょー、田村まろ
※詳しくは別ページに記載
概要
基本的に4人でゲームをプレイするスタイルをとっている。声質の違いが大きく、区別しやすい。編集はばしょー一人が行っている。チャンネル開設から3か月足らずで動画が300万再生を突破、現在のチャンネル登録者数は30万人を超える。
第一話
「ユーチューバーやろうぜ」
(1)いきなり何?
(2)ってか、話すの久しぶりだね?
(3)ユー……チュー、バー?
耳にするのも恐ろしい単語が目の前の人間から聞こえた気がする。自分の腕にはやや長いブレザーの袖を引っ張り、僕はゆっくりと息を吸い込んだ。
「ユー……チュー、バー?」
現実逃避し掛けていた脳を無理やりに働かせ、僕は結局三番の答えを口にする。イメージとしては、地球にやって来て無理やりスマートフォンを見せられた宇宙人、だ。しかしそんな猿芝居がコイツに通用するはずもなく、放課後の教室で幼馴染は明るく僕の言葉を笑い飛ばした。
「いやいや、どういう冗談だよソレ」
「冗談っていうか、その……」
「いいだろ、ユーチューバー。一緒にやろうぜ」
「なんでそんな思考回路になったか、せめて聞きたいんだけど」
「は? なんでだよ」
「その反応がなんでだよ、だよ」
精一杯の僕の反撃は、あまり効果がなかったようだ。目の前の人物は「即答でイエスって言ってもらえるつもりだったんだけどなぁ」と
一八〇近い長身、抜群のスタイルの良さに、人懐っこい笑顔。同じクラスメイトでありながらも、男女共に人気がある。それが、僕の幼馴染である
「ってか、今日はいいの? 部活の練習は」
「オフだから、セーフセーフ」
「そうなんだ」
「おう。ってか、なんか俺たちって、高校入ってから若干距離できたよな」
それをいちいち口にするのか? 反射的に浮かんだ言葉を、
僕と織田が友達になった理由は至ってシンプルだ。近所に住んでいたという、ただそれだけ。同じ保育園に通い、同じ小学校に通い、同じ中学校に通った。しかし、中学生になった辺りから徐々に互いの優先順位が低くなっていき、高校一年生になった今ではめっきり
僕が一方的に織田に対して気後れしているのも、疎遠になった原因の一つだろう。なんせ織田は人気者なのだ。仲良くしているメンバーも運動部の人間ばかりで、大人しい僕には近寄りがたい。織田は織田で僕みたいな地味な人間には興味が持てなくなったのだろうと思っていたのだが、どうやら事情が変わったらしい。「ユーチューバーねぇ」と僕は先ほど彼が
「織田ってそんなにユーチューブ好きだったっけ?」
「いや別に、普通だけど」
「一日どれぐらい見るの」
「日にもよるけど、大体一、二時間くらい」
「あー……確かに普通だ」
僕なんか、一日最低でも四時間は見る。代わりに、テレビは朝のニュースと録画してある深夜のお笑い番組ぐらいしか見ない。昔はテレビが若者の娯楽の象徴だったと聞いたことがあるけれど、二〇一九年の五月七日現在ではちょっと考えられない事象だ。特にゴールデンタイムのテレビ番組はほとんどが年配の人のためのものであって、若者に向けて作られていると感じることはあまりない。グルメレポート、クイズ、健康関連、生活の知恵……そんなのを見て僕達が愉快だって思うかと訊かれれば、答えはノーだ。
テレビには、僕達の居場所がほとんどない。
「松尾はユーチューブ好きそうな顔してるよな」
「まぁ、否定はしないけど」
「いいじゃん。ユーチューブで
「簡単にそう言うけど、ユーチューバーって大変だよ」
先ほどから織田が繰り返している単語、『ユーチューバー』。これは動画サイト『ユーチューブ(YouTube)』に動画を投稿している人間のことを指す。ユーチューブはアメリカの超巨大企業Googleが運営する、世界最大の動画共有サービスだ。日本でもその認知度は日増しに上昇し、ユーチューバーは小学生のなりたい職業ランキングの第一位に輝いたこともある。最近では人気ユーチューバーがテレビに出演する機会も増え、その知名度の高さはネットに限らないものとなってきた。
「というか、そろそろ説明して欲しいんだけど」
「ん? 何が?」
両腕を組み、織田が窓枠にもたれ掛かる。僕の席は窓際だから、夕暮れの時間帯になると西日が強く射す。赤く染まる教室の空気に、織田の肌色が塗り潰される。黙っていれば絵になる男だ、と思う。
「織田がユーチューバーになりたいって言うのは、まぁ、百歩
「それはほら、お前が軽音楽部の動画を作ったって
本間というのはクラスメイトの本間
「ほらこれ」と織田は何でもないことのようにスマートフォンをこちらへ見せてくる。アカウントは高校の軽音楽部のもので、入部希望者に向けた動画がアップされている。画面いっぱいに広がった映像は、見覚えがありすぎるものだった。
十秒ほどのオープニング映像の後、少人数用のスタジオが映し出される。その中央に置かれたパイプ椅子に座っているのは、軽音楽部の部長だ。彼はオーバーに手を動かしながら、カメラに向かって話し続けている。男の
『と、いうわけで、今日は新入生へ我が軽音楽部を紹介したいと思います! 世の中の高校生たちは皆軽音楽部に興味があるんじゃない? ってか、ない奴なんていないでしょ。軽音楽部に入ったら良いことしかない! 男も女も良い奴ばっかり! あ、楽器の貸し出しはやってないから楽器は自分で用意してもらうことになるから! それと──』
動画はまだ五分ほどあったが、織田はそこで停止させた。画面の中では部長が口を半開きにしたまま硬直している。
「いやー、良い動画だよな」
織田はしみじみと
「本当にこれを見て僕に声を掛けたの?」
「おう!」
「この動画、とにかく見やすい! ぶっちゃけ軽音部の部長の話してる内容とか全然興味ないんだけど、それでもスルスルーっと見れた。それってやっぱ松尾の編集がデカイと思うんだよね。例えばここ」
織田が画面下にあるシークバーを動かす。動画が巻き戻され、三十秒辺りから再生される。
『ってか、ない奴なんていないでしょ。軽音楽部に入ったら良いことしかない! 男も女も良い奴ばっかり!』
再放送される部長の台詞。何の変哲もないワンシーンを一時停止し、織田は「ここ!」と声を張り上げた。
「こいつが一言喋る
「まぁ、カットはしてるけど」
「ほらー、やっぱり。気付いた俺すげー!」
「あ、そこで自分を褒めるんだ」
「冗談だって。こんな編集できる松尾がすげーよ。俺にはこんなの無理だもん」
「そ、そんなことないと思うけど」
大体、こんな編集はユーチューブではよくあるテクニックだ。
ネット動画は基本的にテレビに比べてテンポが速い。喋り方も、
今回の場合なら、部長の台詞と台詞の間を全て一秒から二秒ほどカットしている。これにより、中だるみした印象を視聴者に与えない。
「軽音楽部の動画を手伝うくらいなら、俺とユーチューバーになってもよくね?」
「いや、どういう理屈なのソレ。大体、今回はたまたま手伝ったってだけだし。僕の趣味の動画作りに協力してくれるって本間さんが言ってくれたから、そのお礼で軽音楽部に協力したって流れで……」
「趣味ってアレか? PV作り」
「はいぃ?」
心臓が止まるかと思った。なんで織田がPVのことを知ってるんだ。動揺が顔に出ていたのか、織田が「いや、本間から聞いてさ」と言い訳するみたいに早口で捲し立てた。
「もしかして、あの動画見たの?」
「見たいって言ったら本間が送ってくれた、データで」
「本間さん、あの動画見せちゃってるの?」
「普通に周りの奴らに自慢してたよ。俺も保存したし。あ、これこれ」
織田が再生した二分足らずの短い動画には、一人の少女が映っている。本間さんだ。校舎裏に立つ彼女が手にしているのは、A4サイズのスケッチブックだった。『たっくんへ』と可愛らしい丸文字で書かれている。流れるBGMにはうっすらと歌手の声が入っていた。僕の好きな曲だ。
『嫌いって言ってごめんなさい。素直になれなかったけど、本当はたっくんのことが大好きです! これからもずっとたっくんと恋人でいたいです!』
ローカルニュースのワンコーナーで流れそうな、なんともほっこりした映像だった。
「……」
「……」
僕は織田を見て、織田は僕を見た。二人の間に、ほっこりと呼ぶにはやや生暖かい沈黙が落ちる。流れる空気の穏やかさに、僕の顔はじわじわと熱を持ち始めた。
「なんでそこで黙るの」
「いや、これのどこがPVなんだろって考えてた。本間は可愛く撮ってもらったって喜んでたけどよ、さっきの動画と違ってなんかのんびりしてる動画だよな。ただただ本間が自分の彼氏に向かって叫んでるだけだし。退屈というか、つまんねーというか。さっきの軽音楽部の紹介動画はそんな風に思わなかったけど」
「いやいや、これは敢えて間を大事にしてる動画だし、さっきの動画と違って不特定多数の人間に見せるつもりで作ってないし」
「ちなみにこの動画のタイトルは?」
「……『どうぞ愛をお叫びください』」
「ふへっ」
「笑うなって」
「笑ってねーよ」
織田の指が、スマホ画面をなぞる。本間さんが照れながら話しているシーンだ。
『初めてたっくんが話しかけてくれた時、私、心臓がどきどきして死ぬかと思いました。たっくん、私に言ったよね。“付き合ってくれないか”って。本当は部活の買い出しの話だったのに、私ってば告白だと勘違いしちゃって──』
「本間が『松尾くんのPV作りに協力したの』って言ってコレ見せてきたから、なんかイメージと違ってさぁ。コレ、見ちゃまずいやつだった?」
「別に、まずくはないし、本間さんにもお礼のつもりでデータ送ったけど。でも本当に誰かに見せるとは思ってなくて」
「ここまで作り込んでて、誰にも見せるつもりがないってことはないだろ。テロップまで入れてるのに?」
「それは別にいいでしょ。本題じゃない」
「それもそうか」
反論すると、織田はあっさりと引き下がった。スマホを胸ポケットに入れ、織田は仕切り直すように大きく息を吐いた。顔を下げ、少しの沈黙の後再び上げる。
「じゃ、組むか」
「いやいや、なんでそうなったの」
「いいだろ。俺の周りに松尾以上に動画作りの才能あるやついないし」
「そもそも僕以外で動画作ってる人間を知らないの間違いでしょ」
「そんなことねーって。俺はお前のこと天才だって思ってる」
「そんなわけないでしょ」
「謙遜すんなって。あと、松尾だったら元々仲いいし、方向性の違いで解散することも無さそうだし」
「……」
「真面目に口説いてんだから、そろそろ折れてくれよ。俺、組むならお前以外考えられないんだって。な、俺ら、ガキの頃から友達だろ?」
なんて都合の良い口だろう。この一か月間、友達面なんてほとんどしなかった癖に。文句だとか断る理由なんてものは、いくらでも見つけることが出来た。「目立つの嫌いだから」とか「動画作りは自分一人でやりたい趣味だから」とか。なのに、ポロリと口から飛び出したのは、
「まぁ、織田がそこまで言うならやってもいいけど」
「マジで!」
机を両手で叩き、織田は思い切りこちらへ身を乗り出した。
「その代わり、やるからには本気でやってもらうから」
「おうおう、松尾が乗り気で何よりだ。早速作戦会議と行こうぜ」
「作戦会議って、どこで?」
僕の問いかけに、織田は平然と答えた。
「そりゃ、松尾ん
僕は、
「懐かしー、何年ぶりだよ」
マンションの一角、4LDKの僕の家に織田が足繁く通っていたのは、小学生の頃の話だ。玄関でスニーカーを脱ぎ、織田はきちんと両端を揃えて置いた。軽薄そうな容姿とは裏腹に、織田は意外とこういうところはきちんとしている。
「五年とか六年とか、それくらいじゃない?」
「マジか。そりゃ色々と小さく見えるわ」
「狭い家で悪かったね──あ、待った」
僕の自室のドアノブに手を掛けた織田を、慌てて制する。「ん?」と織田は
「悪いけど、入るならリビングで」
「お前の部屋じゃねーの?」
「人が入る前提の状態じゃないから」
「散らかってるって?」
「散らかってると言うか、心構えのない状態で他人に部屋を見られたくない」
「出たー、松尾の完璧主義。エロいもんでも隠してんのか?」
ケラケラと笑う織田に、僕の眉間に自然と
「ま、とにかく入って」
「はいはい、リビングな」
灯りを
「お前ん家のリビング、こんなんだっけ?」
織田がキョロキョロと室内を見回す。僕が中学を卒業したタイミングで模様替えをしたから、彼の記憶の中の姿からは随分と様変わりしていることだろう。
「そりゃ変わるよ、何年経ってると思ってるの」
「ふーん」
織田はソファーに浅く腰掛けると、くわっと大きく
「何飲む?」
「牛乳」
「いま麦茶しかない」
「一択なのに何で聞いたんだよ」
「一応、コミュニケーションのつもり」
「じゃあオレ、麦茶ノミタイ」
「お
冷蔵庫から麦茶を出し、二人分をグラスに注ぐ。二人掛けソファーは織田が占領しているから、仕方なく僕は一人掛けのソファーに座った。テーブルにトレイを置き、並べたコースターの上にグラスを置く。織田はそれを
「でさぁ、早速ユーチューバーの話なんだけど、松尾的に何したい?」
「言い出しっぺは織田なんだから、まずは織田のビジョンからだろ」
「それがさぁ、何もないんだよなぁ」
「はあ?」
思わず顔をしかめた僕に、織田は悪びれた様子もなくその長い足を組み直した。
「そもそも織田はなんでユーチューバーになろうと思ったの」
「それはアレだよ、なんかカッコイイし楽しそうじゃん」
なんとも
「俺さ、とりあえず松尾と一緒に何かやりたいって思って」
「なんで急に僕にこだわり始めたの」
「理由なんてないけどさ。なんとなくだよ、なんとなく」
へらりと、織田が笑う。答えるつもりはないということか、
僕は深々と
「織田のスタンスはよく分かった。織田が、ユーチューバーで成功するってことをかなりナメてるってことも」
「ナメてねーって。ヒカキンとかマジスゲーって思ってるもん」
「ユーチューバー目指してる癖にヒカキンさんを凄くないなんて言う奴がいたら、はったおした方が良いと思うよ」
昨今の人気ユーチューバーへの眼差しは、芸能人に対するそれに近いのかもしれない。ラジオからテレビへ、テレビからネットへ。新たな情報媒体が登場すると、そこに相
「まず僕と織田が決めるべきなのは、どのジャンルにするか、だよ」
「ジャンルって?」
そこから始めるのか、と僕は大きく溜息を吐いた。
「織田はさぁ、テレビに出てる人って聞いたらどんな人を思い浮かべる?」
「んー、俳優とか芸人とか。あとはスポーツ選手?」
「他にもたくさんいるよね。ニュースを読むアナウンサー、批評をする評論家、気象予報士。料理のコーナーだと料理家が出るし、音楽家もいる。歌手とか、演奏家。あとはタレントだってそうだね」
「それが?」
「ユーチューブも、単なる枠に過ぎないって話だよ。テレビと一緒で、ただの媒体に過ぎない。ほら、一時期テレビで迷惑ユーチューバーがたくさん取り上げられてただろう? あとは、テレビの人たちがこぞってユーチューバーを馬鹿にしてた時期もあった」
だが、どんな媒体にだってそのリスクはつきものだ。別にユーチューブに限ったことではなく、テレビでも、雑誌でも、日常生活でも、なんでもそう。安易に注目を集めようとする人間は過激な言動に頼りがちだ。
「ユーチューバーっていうのは、もはや一くくりにして語れるものじゃない。そんなのは、若手芸人がテレビの深夜番組で無茶してるのを見て、最近の若者は品がないって眉を
一息に言葉を吐き、そこで僕は織田がニヤニヤしながらこちらを眺めていることに気が付いた。「なんだよ」と唇を
「オタクはそういうの強いよな。好きなものに強い」
「オタクで悪かったな」
「褒めてるんだよ。やっぱ、ユーチューバーやるなら松尾とやるのが正解だ」
そう言って、織田がグラスの中の麦茶を
「とにかく、まずはユーチューバーにどういうジャンルがあるかってのを説明する。多分、織田は自分の好きなユーチューバーの動画以外見てないだろ?」
「うん、全然見てない」
即答された答えに、いっそ清々しさを覚える。ユーチューブにアカウント登録すると、視聴環境を色々とカスタマイズできる。その中でも最も重要なのが、『登録チャンネル』の欄だ。
動画投稿者は、それぞれチャンネルを持っている。これは誰でも簡単に設定することができ、視聴者はこのチャンネルを登録することで投稿者の動画更新にすぐ気付くことが出来る。勿論、視聴者は登録していないチャンネルの動画を見ることも可能だ。
ユーチューブには
軽音部の動画がいい例だ。再生回数二桁、こんなのは別に珍しいことではない。
「一番メジャーなのは多分、実写バラエティー系だと思う。大掛かりな企画だったり、実験動画だったり。メントスコーラドッキリやスライム風呂なんかは一時期みんなやってたね。あとは無人島でリアルサバイバル生活とか、何百人も集めて鬼ごっこみたいなテレビの後追い企画とか。若者には一番人気のジャンルかもしれない」
「まぁ、想像しやすいな。オレが見てるのもそういうやつ」
「こういう動画で大変なのは、やっぱり企画を立てるところだろうね。あと、実際にやる手間もかかる。豪遊系の実験企画は僕らみたいな学生には難しい」
ユーチューバーとは、結局何をする人間なのか。考えた末、僕は『一人テレビ屋』だと結論付けた。動画を企画する、撮影する、タレントとなる、編集する、宣伝する。それらを全て自分達でやるのがユーチューバーという職業だ。学生の片手間に簡単にできるようなものじゃない。
「人気ユーチューバーってタレント力タイプと企画力タイプで別れると思うんだよね。ユーチューブの強みは、テレビと違って興味のないものを見なくて済むことだと思う。例えば、僕がある若手芸人を好きだとするでしょ? で、その芸人をテレビで見たいと思っても、一時間の番組で三言くらいしか喋らないかもしれない。でも、ユーチューブだったら百パーセントの確率でその芸人だけを見られる。好きな相手だけに時間を注ぐことができる」
「好きなものだけを見られるってのはそうだよな。テレビはいろんな人間に向けて作ってっからじいさんばあさん向けとか若者向けとか混在した作りになってるけど、ユーチューブは特定の層に直接届くってイメージがある」
「商品紹介やハウツー系っていうのも人気ジャンルだね。商品紹介はその名の通り商品を紹介する動画、ハウツー系は生活に役立つ知恵の紹介って感じ。料理やメイクみたいな。大食いやペットみたいな、誰かの生活の延長系の動画も需要がある。音楽や映像作品、所謂クリエイティブ系も多いね。あとはパチスロや釣りみたいな、その人の趣味に特化している動画もウケてる。延々と車の映像を流したり、焚火の映像を流したり。ニッチ過ぎてテレビだとありえない企画だけど、意外と需要があるんだよね。他は教育系かな。英会話とか、歴史とか、勉強とか。塾さながらの講義が無料で見れたりする」
「そこらへんはオレらには無理だろ」
「だね。僕もそう思う。専門知識が必要な分野だ。トレンドを追っかけてる動画もあるけど……これはまぁ、ユーチューブ版ワイドショーって感じだね。世相を切るとか、過激な発言で
「じゃ、松尾が好きなジャンルは?」
問われ、僕は一度口ごもった。自身の両手の人さし指の腹を
「ゲーム実況」
答えを聞くや
「だと思った!」
「なんだよその反応」
「だってお前、昔からゲーム好きじゃん」
「そりゃまぁ、好きだけど」
ゲーム実況とは読んで字の
ゲーム実況というジャンルの発展に一役買ったのが、お笑いコンビ『よゐこ』の有野晋哉だ。二〇〇三年に彼が番組内で有野課長としてゲームをプレイするという企画が始まり、これが大ヒット。多くのネットユーザーに影響を与えた。
今や有名ゲーム実況者ともなるとその人気は
「けど、実際問題、一番現実的な選択肢だと思うんだ。なんせ、ユーチューバーって今や
人間の数には限りがあり、人間の持つ時間にも限りがある。視聴者は既にお気に入りのユーチューバーを見付けており、彼らが投稿する動画を消費するのに忙しい。その結果、ユーチューバーの人気上位層はほとんど固定化されている。
「芸能人みたいに元々知名度がある場合は例外だけど、
「なんか消去法みたいな考え方だな」
「消去法じゃなくて現実的に考えてるんだよ。あと、実況やるなら条件がある。まず、二人ではやらない」
「はぁ?」
先ほどまでの姿勢から一転し、織田が前のめりになってこちらを見た。
「やる気になったんじゃなかったのかよ」
「やる気はあるけど、二人ではやらない。ゲーム実況するなら四人がいい。そういうポリシーなんだ」
「どういうポリシーだよ」
「四人の方がキャッチーだし、ターゲット層も広くなるだろ? 四人の内の誰かを好きになれば、視聴者は追いかけてくれるんだから」
もっといえば、昔のパーティーゲームの定員は四人だ。ゲームでユニットを組むのに一番キリが良い数字だろう。
「そういうもんなのか?」
「そういうもんなの」
「まぁ、分かったよ。で、他の条件は?」
「正体がバレないようにすること。クラスメイトとかに僕達の動画を見せない」
これはシンプルに、僕の
「まぁ、匿名ってのは賛成だな。炎上した時に顔バレしてたら厄介だし」
「そもそもゲーム実況者って、顔出ししてない人も多いからね」
僕はソファーから立ち上がると、菓子箱からポテトチップスを取り出した。テレビラックの横に置かれた箱には、間食用のお菓子が常備されている。
「ほら、コンソメパンチ。織田、好きだろ」
「オレの為にわざわざ用意してくれたわけ?」
「まさか。父さんが一か月前に買って来てくれて、そのまま放置してたんだ。ほら、僕はうすしお派だから」
「相変わらずだなぁ」
「織田もね」
テーブルの上に置かれたポテトチップスの袋を手に取り、織田はバリバリと豪快な音を立てながら破り開けた。その内の一枚を
「そういえばさ、松尾と
思い切り噴き出した。ゴホゴホと咳き込む僕を尻目に、織田は何枚もまとめてポテトチップスを口へと放り込んでいた。
「なんで、今、桜田さんの話になったの」
桜田
織田が何故か嬉しそうに自身の膝を叩く。
「その反応ってことは、やっぱり付き合ってないんだな。いやー、残念残念」
「桜田さんとはそういう関係じゃないから」
「そういう関係ねぇ。クラスメイトの本間さんにはあんなに愛を叫ばせてたのに」
「言い方」
茶化され、僕は軽く眉根を寄せた。織田がへらりと口元を
「最初に聞いた時からずっと思ってたんだけどさ、本間さんの動画のBGMの歌って、桜田の声じゃね?」
「黙秘します」
「いやいや、バレバレだから。そうなってくると、お前が作ってるPVってのは桜田の歌に対してのものじゃないか?」
こういうところで織田は鋭い。前髪をいじりながら、僕は小さく首を縦に振った。否定し続けて
「ああいう風に誰かが愛について語る動画を何本か撮って、それを繋げてPV風にまとめたいと思ってたんだよ。本当、アレは自己満足な動画制作だけど」
「カーッ、すげえ創作意欲。まぁ、どんなPVセンスだよって思わなくもないけど」
「うるさいなぁ。出来上がりを見てもない癖に」
「いつ出来上がるんだよ」
「それは……あと三本くらいは動画を撮らないとなんとも。
「松尾って、昔からそういう芸術センスはないからなぁ」
「いいんだよ、ネットにアップするつもりはないし。あの動画に関しては他人に見せる用のセンスを使うつもりもない」
「ふーん?」
織田が
ソファーに伸びる自身の足を交差させ、ふくらはぎを締め付ける。なんでもないような顔をして、僕はさりげなく話題を変えた。
「僕より織田の方はどうなの、彼女とは」
「お? 聞くか?
わざわざ左手を広げ、織田は薬指に
正直、織田の恋愛事情なんざどうでもいいが、出来ることなら円満な関係を続けて欲しいと思う。なんせ中学時代、僕と桜田さんはこの件でさんざん苦労させられたのだから。
「──でさあ、
「あ、ごめん。聞いてなかった」
「聞けよ!」
オーバーなリアクションをする織田に、自然と口元が
「嬉しいよ、こうやって松尾と前みたいに喋れて」
「え。何、突然」
「高校に入ってから、なんとなく距離出来たじゃん」
ポテトチップスの
「それは、織田が話しかけてこないからだろ」
恥を忍んで発した台詞に、織田はぽかんと口を開けた。見事な
「もしかしてそんな理由? 俺、松尾に避けられてるなって思ってたんだけど」
「はぁ? 僕のどこが」
「だってお前、俺が友達といたら露骨に目線外すし、挙動不審になるし」
「それは織田の友達が怖いからだよ!」
「怖くないだろ、クラスメイトだぞ」
「織田みたいな派手メンには分かんないんだよ。あの威圧感が」
「あー、松尾って昔からビビりだもんな」
「そういう問題じゃない。絶対にそういう問題じゃないから」
「二回も言わなくても」
「とにかく! 先に話しかけるのは織田の役目だろ、昔から」
「うわぁ、めんどくさい彼女みたいなこと言ってるよ。引くわー」
「めんどくさくない!」
「ハイハイ」
降参したように、織田が両手を上げる。まだまだ言い足りないことはあったが、良しとしてやることとする。僕はソファーにもたれ掛かると、足先までを軽く伸ばした。
「それで、話は戻るけど、僕は四人で実況をやりたい」
「あー、ユーチューバーの話」
「織田的に、誘いたい奴はいるの?」
僕の問いに、織田は考え込むように自身の
「一人、何かと便利な奴がいる」
「ゲーム実況? 別にいいけど」
そうあっさりと提案に応じた男の顔を見て、本当に織田は僕の気持ちをこれっぽっちも分かっていないと痛感した。
織田にユーチューバーをやろうと誘われた翌日の昼休み。オタク友達グループでまったりと昼食を摂っていた僕を、無理やりに連行したのが織田だった。友人から「カツアゲか?」「喧嘩か?」と冗談半分本気半分の言葉を投げかけられ、僕はただ「多分大丈夫」と曖昧に答えることしか出来なかった。なんせ、僕自身も何が起こっているのかよく分かっていなかったから。
僕が強制的に連れて来られたのは、人の少ない第二体育館。その中では、数人のバスケ部員がボールを投げて遊んでいた。うちのバスケ部はそこそこの強豪で、バスケ部の為にこの学校を選んだ奴も何人かいるらしい。ただ、規模が大きいのが玉に
「なあ、
開口一番、織田が告げた言葉がそれだった。そして、先ほどの反応に戻る。友人からの突然の誘いに、坂上は頭に疑問符を付けた表情で、それでもあっさりと頷いた。
「ゲーム実況? 別にいいけど」
「やったぜ」
ガッツポーズする織田の
彼もまた、織田と同じように僕のクラスメイトだ。
──いや、怖いって! と僕は思った。織田が普段つるんでいる友人の中でも、坂上は『僕的近付きたくない人間ランキング』で堂々の一位に輝く人間だ。喋ったことはおろか、目が合ったことすらない。髪型もなんだか威圧的だし、私服のセンスも凄そうだし。
「織田、織田」
僕は織田のブレザーの袖を引っ張ると、体育館の出入り口から少し離れた場所へと誘導した。「坂上、ちょっと待ってて」と織田は
高校一年生男子の平均をやや下回る身長の僕からすると、織田の顔も坂上の顔も随分と高い位置にあると言わざるを得ない。僕が小声で話そうとすると、織田は気を遣ってか、少し
「三人目って、もしかして坂上君?」
「そうだけど」
「あのさ、坂上君には事前に事情を説明したの? ほら、僕がいることとか」
「いや、全く」
「だったらさ、向こうとしてもなんでここに僕がいるんだろって思ってるよね? ってか、僕と坂上君って、色々と真逆すぎるよね? 仲良くなれると思う?」
「なれるなれる。坂上、良い奴だもん」
そりゃ織田にはね! と、僕は思わず叫びそうになった。坂上といえば、掃除時間中に机を運びながら「動線に立つなよ」と僕の友達に凄んだり、体育の時間中に体調を崩した僕の友達に「さっさと保健室に行け」と怒鳴ったりした、あのおっかない坂上だ。とにかく声がでかくて怖い。
「松尾はさ、初めから線を引き過ぎなんだって」
織田がポンと肩を軽く叩く。そうだろうか。線を引いているのは、ナメられまいと威圧感を振りまいている坂上たちの方だと思うのだけれど。
「あんま坂上待たせても悪いしさ、ほら、戻るぞ」
「坂上君を誘うのは決定事項なの?」
「おう!」
わあ、なんて
「ごめんごめん、坂上。待たせた」
「いや、それは良いけどよ……」
坂上の視線は、織田に引きずられるようにして連れて来られた僕へと注がれている。坂上の元へ意気揚々と戻った織田と、その隣で青汁を呑み干した後みたいな顔をしている僕は、
「さっきのゲーム実況ってさぁ、そこにいる奴……えっと、名前なんだっけ」
「ま、松尾です。松尾直樹です」
坂上と話していると、自然と身体が縮こまる。というか、名前くらい覚えておけよ。クラスメイトだろ。なんて文句は、当然ながら脳内に
「あー、そうだった。松尾な、松尾」
「名前忘れてやんなよ」
織田の指摘に、坂上は手刀を切るような動きをした。
「悪い悪い。それで、松尾も一緒にやるってことだよな? ここにお前が連れて来てるってことはさ」
「そうそう。松尾さ、パソコンスゲー詳しいの」
そんなことはない。僕はパソコンに詳しいのではなく、編集にちょっと詳しいのだ! なんて反論も、勿論出来ない。僕はどうしてこうも意気地なしなのか。
「へー」
坂上は太い両腕を組み、僕を見下ろした。蛇に睨まれた蛙のように、僕はその場で硬直する。彼は値踏みするように僕の顔を凝視した後、織田へと視線の先を変えた。気安い口調で、彼は織田へと話しかける。
「で、ユニット名とかどうすんの?」
僕は思った。コイツ、やる気だ!
作戦会議の場所は、自然と僕の家と決まっていた。親がおらず、騒いでも長居しても怒られない。そういう点で、僕の家は拠点にするに相応しい場所だった。
「まーたリビングかよ」
「事前に来るって言ってくれたら僕も用意したって」
「どうせ野郎の部屋なんだから、汚くたって気にしないって」
「汚いかどうかが問題じゃなくて、完璧じゃないのが問題なの」
「ハイハイ」
僕と織田が会話している様子を、リビングのソファーに座った坂上が物珍しげに眺めている。コルク製のコースターの上に、僕は麦茶の入ったグラスを三人分並べた。
早々に坂上が一人用ソファーに座ったせいで、僕と織田は二人掛けのソファーに隣り合って座る
「で、これが松尾の作った動画?」
スマートフォンを横向きにして、坂上がユーチューブの動画を再生している。「そうそう」とうすしお味のポテトチップスを開封しながら、織田がおざなりに答える。先ほどコンビニで買ったものだ。
「へー、軽音部ってこんな紹介動画も作ってたんだな。すげぇ見やすい」
「そ、そうかな」
僕の語尾が今にも消えそうなのは、タメ口で話していいものか未だに確信が持てないせいだ。今のところ坂上が怒っている様子はないが、内心でどう思われているかまでは分からない。
「松尾と織田って、どういう関係なワケ?」
「幼馴染なんだよ、家が近所でさ」
答えたのは織田だった。答えを取られた僕は、手持無沙汰を誤魔化そうとポテトチップスを口に運んだ。
「へぇ、どうりで仲いいわけだ。教室では隠してたのか? 入学してから織田が松尾と仲良くしてるところ、見たことないけど」
「隠してたんじゃねーって。ただ、ちょっとした行き違いがあってさ」
「ま、別にどうでもいいけどな。織田の交友関係とか」
「いや、ちょっとは興味持てよ」
織田が坂上の肩を叩き、二人はゲラゲラと大きな声で笑った。今のどこに笑う要素があったのだろうか。彼らには独特の空気感があり、互いに分かりあっていることがありありと伝わってきた。ここは僕の家だと言うのに、一人だけアウェーな気分だ。
「それで、松尾は織田の
唐突に話題を振られ、僕は
「ゲーム実況者なぁ……。俺もユーチューブはよく見るけど、実況グループ作るなら三人より四人がいいと思うぜ」
「あ、それは僕もそう思ってるんだ」
織田よりも坂上の方が、ユーチューバーには詳しそうだ。彼の意見が自分と同じだったことに、ちょっとだけほっとする。
「だよな? パーティーゲームするなら基本は四人だし。残り一人のあてはあるのか?」
「僕は全然。そういうのは織田の担当だし」
「俺? 俺は坂上以外、ピンとくる奴がいない」
「ピンと来なくても、数合わせでテキトーに呼ぶのはダメなのかよ。バスケ部の連中とかさ」
「ダメに決まってんだろ。遊びじゃねーんだぞ」
坂上の提案を、織田は即座に切り捨てた。遊びじゃないんだ……と、僕はコッソリと織田の横顔を盗み見る。普段はふざけてばかりの彼の目は珍しく真剣だった。
「とにかく、俺はメンバー選びに妥協はしない」
「お前口だけは達者だよなぁ」と坂上が溜息を吐いている。
「でも、妥協しない方が良いって意見には僕も賛成だな」
「松尾の友達ってのはどうだ? ほら、言ってみれば俺は織田の友達だし、松尾の友達誘えばちょうどいいんじゃね?」
「却下。松尾の友達には華が足りない」
失礼な、と怒らないのはそれが事実だと身に染みて理解しているからだ。僕も僕の友達も、とにかく地味であることは間違いない。だが、これだけは主張しておく。こういう地味な人間が地味に頑張っているからこそ、世の中は成立しているんだぞ。
「まぁでも確かに、地味な奴二人はグループ的に良くないかもな」と言ったのは坂上だ。「だろ?」と織田が得意げに続ける。
「少し考えてみろよ。アイドルでも芸人でも、キャラには役割ってもんがある。グループにはバランスが大事なんだ。で、そう考えるとここにいる三人はなかなか良いバランスだと思う」
そう言って、織田は親指の先を自分の顔へと突き付けた。
「俺がカッコイイ担当で、松尾が可愛い担当。で、坂上が面白担当」
「俺だってカッコイイ担当だろ」と即座に坂上が突っ込みを入れている。可愛い担当と言われ、僕は
「で、この三人に加えるとしたら、どういう人材が必要か。俺なりに考えたわけよ」
「それで?」
僕が続きを促すと、織田は勿体付けた態度で自身の顎を軽く擦った。
「飛び道具だな」
「抽象的だね、随分と」
「分かりやすく言うと、ぶっ飛んだ奴。オレらの常識を超えて、面白いことが出来るヤツ」
織田は簡単にそう言ってのけるが、かなり無茶な注文だ。ソファーの上で背中を丸め、僕はこれまでの自分の交友関係を残らず思い返す。一番ぶっ飛んでいると思うのは小学生時代にポケットでカタツムリを飼っていた東田君だが、織田が言いたいのはそういう人材のことではあるまい。
「あー、俺、一人だけ心当たりあるわ」
坂上が手を挙げる。「心当たりって?」と織田が食い気味に尋ねた。
「いや、知り合いとかじゃないんだけど、前に軽音部のライブ行った時に色んな意味でスゲー人がいたから、その人とかどうかと思って」
「軽音部、いいね。そいつを第一候補にしよう。次の軽音ライブ、三人で見に行くぞ」
「えー」
無意識のうちに、不満が口から漏れた。二人から一斉に視線を向けられ、僕は慌てて口を
興奮した人間に囲まれると、理性を保っている自分だけが取り残されたように感じてしまう。
「松尾はうるさいのが苦手なのか?」
「苦手っていうか、得意ではないかなぁ」
「坂上、松尾の言うことを気にし過ぎるな。コイツは昔から苦手なもんばっかだから、一々気にしてたらやってけないぞ」
「言い掛かりじゃない?」
「小学校の修学旅行でお化け屋敷に行きたくないって一時間ぐずってただろ」
「いつの話だよ」
確かに、織田の言葉は間違ってない。だが、それは僕が暗いところとホラーが苦手なのが原因であって、それを理由に苦手なものばかりだと結論付けられても困る。
「ふうん、松尾はオバケ苦手なのか。B級ホラー映画が好きそうな顔してるのにな」
「あ、ゾンビは大丈夫」
「どういう基準なんだ」と坂上が顔をしかめる。「そんなことより、活動名考えようぜ!」と織田が強引に僕らの会話に割り込んだ。
「活動名?」
「本名でネット活動するわけにはいかないだろ? 顔出ししないとはいえ、名前がバレるのはリスクがありすぎる。……松尾、なんか書くものあるか?」
「メモで良ければ」
父親が職場で貰って来た粗品のメモ帳は、意外と使い勝手が良くて重宝している。筆箱に入っていたペンを取り出し、僕はぐるぐるとペン先を軽く走らせた。綺麗にインクが出るのを確認し、一枚目を破り捨てる。何かを作る時、僕は万全を期して取り組むことにしている。
「テキトーに出していこうぜ、数打ちゃ当たるだろ」
織田はそう言うが、名前なんて簡単に思いつくものじゃない。小説家志望ならペンネームを、ハガキ職人ならラジオネームを持っているのが普通なのかもしれないが、
「ヒロ君ってのはどうだ? ほら、織田博也だしよぉ」
「自己紹介の度に自分のことヒロ君って呼ぶの嫌だわ、幼稚園児か」
「じゃあシンプルにヒロとか」
「絶対もういるだろ、そんな名前」
「
「じゃあお前は坂上明彦でアキ君か?」
「なんかしっくりこねーな。俺、アキって
「顔は見えねーからどうでもいいだろ」
「いやいや、気になるだろ。俺もお前も」
坂上と織田の会話を聞き流しながら、僕は思考をそのままメモに書きつける。カッコいい名前といえば、トランプなんてどうだろう。ハート、ダイヤ、エース、スペード。いや、これは安直すぎるかもしれない。じゃあ、キング、ジャック、エース、ジョーカー……これだとスパイ映画のコードネームみたいだ。
「さすがにジョーカーは中二病過ぎるだろ」
横から織田にメモを覗き込まれ、顔中が熱くなる。恥ずかしさで人間が死ぬなら、僕は今この瞬間に昇天している。
「ヒロ君よりはマシだって。松尾、
フォローしてくれる坂上の優しさが、かえって僕を傷付ける。ネーミングセンスがないことは自分でも最初から分かっているさ。黙り込んだ僕の背中を、励ますように織田が叩く。
「こういう名前って、気取らない方がいいんじゃね? ほら、おでんとかアジフライとか」
「なんで
それからいくつか候補を出し合ったが、結局ピンとくるものは一つもなかった。ぐだぐだと続いた実りの無い会議は、「今日はもう解散だな」という織田の台詞で締めくくられた。
「じゃ、俺、今日は彼女と約束あっから」
そう言って颯爽と自転車で走り去った織田の背中を張り倒したくなったのは、僕だけではないだろう。時刻は十九時、外は既に暗かった。オートロックの入り口を通り、二人きりとなった僕と坂上は気まずさを隠さないままに互いの顔を見合った。こうしてまじまじと見ると、坂上の首は太い。がっしりとした肩幅といい、日に焼けた肌といい、僕とは歩んできた人生が違うのは明らかだった。
「あー……えっと、坂上君、駅まで送っていくよ」
「いいのか? 道分かんなかったから助かる」
社交辞令のつもりだったのだが、坂上は素直に提案を受け入れた。スマホを使えば道ぐらいすぐに分かるだろうに。
「あ、うん。じゃあ、えっと……こっち」
「おう」
僕が歩き出すと、坂上はすぐ隣に並んだ。友達らしい距離感覚ではあるが、織田がいないと何を話していいか分からない。友達の友達は、単なる知り合いだ。
「あー……松尾って、何部?」
沈黙に耐えかねたように、坂上が話題を切り出した。僕は頬を掻き、ぎこちなく答える。
「帰宅部だよ。中学の時は放送部だったんだけど」
「へえ。放送部って、体育祭とかのアナウンスしてる?」
「そう。他にも色々とやることがあって。それで動画の編集をし始めて」
「すげーよなー。そういう、クリエイティブな趣味っての? 俺だってよくユーチューブ見るけど、だからって動画作ってみようとは思わねーし。ってかさー、松尾って普段ゲームとかすんの? 俺も結構やるんだけどさ、オーバーウォッチとかフォートナイトとか」
「そうなんだ、僕もたまにやるよ」
「マジで? じゃあ、今度一緒にやろうぜ。え、松尾って普段どういうゲームすんの? ハード何持ってる? バスケ部の奴らって、ゲームと言えばモンハン・スマブラって感じでさぁ。織田とか、他にやるゲームっつったらスマホゲーだけじゃねーの」
ゲームの話になった途端、坂上は饒舌になった。クラスメイトの意外な一面を見付け、僕はちょっとだけ親近感を抱く。
「僕はゲームならなんでもやるかな。基本的に、最新型のハードは全部揃えてるし。でも、最近はパソコンゲーが多いかも。シミュレーションゲームが好きなんだ、海外製の」
「へぇー、どんな?」
「civilizationとかcities:skylinesとかstellarisとか」
「どれもやったことねぇ。あー、でも俺、あれはやってみたいと思ってるんだ。HoI」
「Hearts of Iron、面白いよね。あれは時間泥棒だよ」
「松尾、マジでなんでもやってんだな。ゲーム」
「なんでもじゃないよ、興味があるものだけ」
「はー、どっからそんな金湧いて来るんだ? 実はバイトしてる?」
言われた言葉の意味が理解できなくて、僕は反射的に足を止めた。複雑に電線が絡み合った頭上で、飛行機の光がチカチカと瞬いている。延々と続く住宅街はどの庭も綺麗に手入れされ、家の前には複数の高級車が並んでいる。でも、僕がそれらを不思議に思ったことはない。生まれてからずっと、僕にとってこの光景が日常だからだ。
「坂上君、バイトしてるの?」
「週二でラーメン屋のシフト入ってる。ゲームも服も、小遣いじゃ足りないしな」
僕の家は昔から小遣い制だ。月に三万円ずつ渡され、現金で足りない分はクレジットカードを使うように言われている。バイトをするくらいなら勉強しろ、というのが母親の主張だ。実際のところ、空いた時間はゲームに費やされてオシマイなのだけれど。
「ラーメン屋か、大変そうだね」
「部活やってなきゃ、もっとシフト入れんだけどなぁ。正直、バスケとかやる気ないし、いつ辞めてもいいんだけどさぁ」
「やる気ないのにバスケ部に入ったの?」
「勧誘されたんだよ、背が高いから。でも俺、ボール使うセンスが壊滅的でさ。先輩の頭に思いっ切り当ててブチぎれられたり」
「あー……それは大変そう」
ボールを当てられた先輩が。ブレザーに包まれた坂上の腕は、僕の太腿くらい太い。きっと凄まじい速度だっただろう。
「ユーチューブでスゲー人気出ねぇかな。そしたらバイト辞められるのに」
「ユーチューブで収益化するのは大変だよ、一円を生み出す壁が高い。すぐに千円稼ぎたいならバイトの方が絶対効率的だと思う」
「だよなー。俺もそう思うわ」
坂上はクツクツと喉奥を鳴らすように笑った。坂上の方が、織田よりもユーチューブの仕組みについては詳しそうだ。
ユーチューバーが収益を得る方法はいくつかあるが、その中でメインとなるのが広告収入、スーパーチャット、チャンネルメンバーシップだ。広告収入は読んで字のごとく、動画につけた広告によって生まれる収益だ。動画の再生回数によって収入が変化するのだが、動画再生数などの基準をクリアしないと動画投稿者は収入を得ることができない。再生数二桁の軽音部の紹介動画の場合、生まれる利益はゼロだ。
スーパーチャットは配信中に視聴者が配信者に直接お金を支払うことのできる仕組みだ。配信の特徴はテレビの生放送と同じく、リアルタイムであることだ。編集済みの動画とはまた違った魅力が生まれる。
そして、チャンネルメンバーシップ。これを最も分かりやすく説明すると、
他にも企業案件やイベント開催など収益を得る方法はあるのだが、それらが可能なのは人気ユーチューバーくらいだ。僕らがあれこれ考えるのは、まさしく絵に描いた餅というやつである。
「それにしても、織田はなんでユーチューバーやろうなんて思ったのかね」
「あ、坂上君、ここを右」
真っ直ぐに歩き続けようとした坂上の腕を、僕は遠慮がちに叩いた。坂上は怒らないどころか、気にする素振りすら見せなかった。
「松尾はどう思う?」
「え、何が」
「織田だよ、織田。なんでユーチューブやろうと思ったんだろ」
「織田は昔からそういうところあるから、考えても意味はなさそう。思い付きだけで動くというか」
「ふーん。じゃ、逆に松尾はなんで動画を作ってるんだ?」
「それは軽音部の人に頼まれたからで、」
「そうじゃなくてよ。こう、趣味の動画とか。自分の為に動画を作ろうと思う瞬間ってどういう時なんだろうって思って。俺にはない感覚だからさ」
動かそうとした唇が固まったのは、
恥ずかしさと痛々しさ、そこに微かに混じる甘酸っぱさ。今からたった一年前、中学三年生の僕には人生で初めて仲の良い女友達ができた。それが、桜田さんだった。
桜田さんはクラスで目立たない存在だった。特定の女子生徒とだけ仲が良く、それ以外の人間とはほとんど喋らない。人見知りというよりは、人と群れることを極端に嫌っているように僕は感じていた。両目の上で切り揃えられた重い前髪、一番上まできっちりと
僕たちが初めて喋ることとなったきっかけは、桜田さんのミスだった。放課後、放送部の活動を終えた僕が教室に戻ると、彼女の机の上にノートが開きっぱなしのまま置かれていた。僕はなんとなく、本当に、ただなんとなくそのノートを覗き込んだ。罫線の引かれた大学ノートには、やたらと角ばった文字で詩が書きつけられていた。
「どうぞ愛をお叫びください」
ピカピカの天秤の皿の上で 君の好きが死んでいる
努力と才能と何もかもが 反対側に乗っている
天秤はぐらぐら揺れていて なのにきみは知らないふり
本当は好きなんでしょう 自分を信じたいんでしょう
将来をダメにしたくないって言い訳するのは簡単で
傷だらけの腕を隠してきみは大人になろうとしている
夢に手を伸ばす気持ちを『愛』と呼ぶんじゃないんですか
みすぼらしい好きを捨てることがきみにとっての愛ですか
どうぞ愛をお叫びください
いいじゃん いい加減だって
きみが『好き』っていうんなら めでたしめでたしを望まないで
いいじゃん 全部無駄だって
きみが『好き』っていったことが はじまりはじまりの合図なんだ
洗練されていない、荒削りの言葉の羅列。だけど、それがいいと思った。他の詩が気になってページを
「し、しんでやる!」
「えぇ?」
一体何がどうしてそうなったのか。僕が考えている間にも、桜田さんの顔はどんどん赤くなっていった。乱れた前髪の隙間から、珍しく彼女の眉毛が見えている。
「えっと……素敵な詩だね」
とりあえず素直な感想を口にすると、桜田さんは勢いよく僕の両肩を掴んだ。手に込められた力に心臓がドキドキしたけれど、もしかしなくともこのドキドキの原因は恋愛感情ではなく恐怖のせいだった。怒った女子って、とても怖い。
「なんで勝手に見るの。人がトイレ行ってる間にコソコソと」
「いや、勝手に見たというか、目に入ったというか」
「あー、死にたい。恥ずかしい。終わりだ、人生が終わった……」
「なんで? あ、もしかしてこの詩、桜田さんが書いたとか?」
「それ以上言ったら殺す」
睨みつけられ、僕はコクコクと必死に首を縦に振った。桜田さんが何故取り乱しているかは分からないが、この詩の作者であることは間違いないようだ。
桜田さんは僕から手を離すと、まるで当たり前みたいな態度で席へと座った。ノートを机の中に押し込み、背筋を正し──そしていきなり自分の
「……ぅ……」
「え?」
何かを言われたことだけは分かったが、声が小さすぎて聞き取れなかった。耳に手を当てて顔を寄せると、桜田さんは勢いよく顔を上げた。
「だから、どうだったかって聞いてんの!」
だからもなにも、最初から聞き取れていない。額から変な汗が噴き出るのを感じながらも、僕は慎重に言葉を選んだ。
「いいって思ったよ。すごくいいって思った」
「お世辞?」
「いや、本当に」
告げたのは本心だった。僕にとって詩なんてものは、教科書や小難しい本に載っているとても遠い存在だったから。だから、こんな風に身近な人間が詩を作っていること自体に驚いた。凄いと思った。
僕の言葉に、桜田さんは「うあー」と言いながら自身の前髪を激しく掻き回した。思わず一歩後ずさった僕に向かって、桜田さんは
「あれ、詩じゃなくて歌詞なんですけど」
「そ、そうなんだ」
「一応、曲もあったりするんですけど。最初だけ」
「へ、へぇ」
「聞きたいよね?」
「ア、ハイ」
態度は威圧的だが、それが緊張の裏返しであることには薄々勘付いていた。僕は正面の椅子を引くと、桜田さんと向かい合うようにして座る。桜田さんは自分の喉を擦り、「あ、あー」と短く声を出した。なんだか自暴自棄になっているようにも見える。
「じゃ、いきます」
「どうぞ」
互いに見つめ合っていると、こちらにまで緊張が伝わってくる。汗の浮かぶ手の平を、僕はブレザーに押し付けた。
「どうぞ愛をお叫びください
いいじゃん いい加減だって
きみが『好き』っていうんなら めでたしめでたしを望まないで」
普段よりも力強い声。伸びやかに響くアルト。唇が
胸の奥から沸き上がったのは、純粋な感動だ。クラスメイトというひいき目を抜きにしても、彼女の歌声には力があった。
誰かが新しいものを作る瞬間って、きっと奇跡みたいなパワーがある。
僕も何かを作りたい。僕も何かを与えたい。君みたいに! そんな激しい衝動が、僕の中へと
気付けば僕は立ち上がり、桜田さんに歩み寄っていた。
「僕、桜田さんの歌が好きだ」
「あっそ」
そっぽを向いたまま、桜田さんはまたガシガシと髪を掻き回した。
「桜田さんの曲に動画をつけたい」
「勝手にすれば」と彼女は唸るように言った。髪を掻きむしるあの動作が、恥ずかしさを誤魔化す時の癖だと気付いたのは、それから数か月後のことだった。
あの後だ、僕が本格的に動画編集の勉強に取り組むようになったのは。それまでは部活で必要になった時だけ教科書から知識をつまみ食いして編集を行っていたのだけれど、きちんと技術を身に着けたいと考えるようになった。テレビ番組の編集に着目するようになり、テロップの出し方なども気にし始めた。中学校を卒業する頃には皆に動画編集の腕前を認められるようになり、卒業パーティーのムービー制作の編集を行ったりもした。
桜田さんとは、卒業式以来一度も言葉を交わしていない。彼女は別の学校に進学したし、以前のように学校で偶然会う機会も無くなった。
連絡先は互いに知っていた。なのに彼女からメッセージが届かないことこそが、僕達の今の関係を表している。
僕から連絡する勇気がないのは、最後に喧嘩した時の彼女の顔が忘れられないからだ。
「僕が本気で動画を作ろうと思うきっかけになった人がいるんだけど……なんというか、僕にも胸を張れる何かが欲しかったんだ。肩を並べたかった。それで勉強を始めたら楽しくなって、それでまぁ、今に至るって感じかな」
結局、僕が坂上に説明したのは、記憶の
「そうやってやりたいことに向かって努力できるヤツってマジで尊敬するわ」
「いや、僕なんて全然だよ。編集技術もまだまだだし」
「まだまだってことは、これから上達していくつもりってことだろ? やっぱスゲーよ」
そう言って、坂上は僕の背中を叩いた。貧弱な僕の身体には大きすぎる衝撃だったが、痛いとは言いたくなくて、僕は咳き込みそうになったのを我慢した。
「織田の友達っつって松尾が出て来たのはマジでビビったけど、でも、今日一緒に過ごして納得だったわ。お前、良い奴だな」
「いやいや、こちらこそ坂上君を誤解してた」
「どんな誤解してたんだよ」
「んー……悪そうな奴は大体友達、みたいな人だと思ってた」
恐る恐る言った台詞に、坂上は大きな笑い声を上げた。
「もしそんな奴だったら、織田は俺のこと絶対松尾に紹介してないって」
「そうかな」
「織田は頭いいからな。いや、成績は悪いんだけど、地頭っつーの? 何をしたら自分がやりたいことが上手くいくかってのを嗅ぎ分けるセンスが半端ないんだよ。だからアイツがユーチューバーをやるっつって俺ら二人を会わせた時点で、ある程度気が合うって読めてたんだと思う」
「僕ら、気が合ってた?」
自身の鼻先を指さす僕に、坂上はキョトンと目を丸くした。その口が豪快に開かれ、またしても笑い声が響く。
「いや、めちゃくちゃ合ってんだろ! ゲームの話盛り上がってたよな?」
「盛り上がってたんだけど、僕だけ楽しいのかなってちょっと心配してたから」
「松尾っていつもそんなめんどくせーこと考えてんの? 友達なんだから、もっと気楽にいこうぜ。呼び方もさ、坂上でいいって。呼び捨てで」
あの坂上を呼び捨てにする日がくるなんて、想像すらしていなかった。実は心の中で文句ばかり言っていたことは、墓場まで持って行こう。
赤くなった頬に、自身の手の甲を押し付ける。じっとこちらを見つめる坂上は、明らかに僕の呼び掛けを待っていた。
「じゃ、じゃあ、坂上」
「おう!」
ニカッと歯を見せて笑う坂上の姿があまりに眩しかったものだから、僕は思わず両目を
軽音部のライブは、その翌週の木曜日に行われた。音楽室は吹奏楽部の部室となっているので、軽音部の活動は専ら部室でもあるスタジオで行われる。五十人という部員数に対して部室が狭すぎると不満の声が上がっているが、空き教室がないため改善される見込みはなさそうだ。
テーブルを三つ横に並べただけの受付では、クラスメイトの本間さんが観客に名前を書かせていた。軽音ライブは月に一度のペースで行われるのだが、ライブの度に全バンドが発表するわけではないらしい。
織田と坂上を廊下の端で待たせ、僕は一人で受付を済ませることにした。
「いらっしゃい、松尾君。ライブ来てくれたんだね」
「うん、ちょっと興味があって。あ、三人で」
「男子三名ね。今日はゲスト以外全組一年生バンドなんだけど、どのバンド目当てで来たの?」
本間さんが差し出したアンケート用紙には、バンド名が書かれていた。どうやらこれで各バンドの集客力を調査しているようだ。
□ ヒルダケ
□ black sunder
□ でこぽん
□ イカすスーツ専門店
□ BADSINGS
□ ゲスト 健康法師
右から順に、ヨルシカ、back number、あいみょん、ヤバイTシャツ屋さん、RADWIMPSのコピーバンドらしい。名前の時点で学生の
本間さんは教えてくれなかったが、最後のゲストは米津玄師のパロディーだろうか。
「今日はなんとなく来たんだ」
「じゃあ、七番目の『ノリで来た』ってとこにチェック付けて」
本間さんの指示に素直に従い、僕はチェックボックスに書き込んだ。今日出演するバンドはどれも結成したばかりで、人気差がほとんどないらしい。今日の客は友達を応援しに来た一年生か、新しい顔ぶれを見に来た軽音部ファン、或いはゲスト扱いの健康法師のファンであるようだ。健康法師は二年生部員なのだが、集客が不安だった部長が無理やり今日のライブに
「それにしても珍しい組み合わせだね。織田君と坂上君と松尾君って」
「まぁ、色々あって」
「松尾君と並ぶと、なんか番犬みたいだね。あの二人」
手を口元に添え、本間さんがクスクスと笑った。あの
「それじゃ、ライブを楽しんで」
本間さんに見送られ、僕達はスタジオへと入室した。スタジオは既に薄暗く、僕は誰かの足をうっかり踏みつけないことに全神経を集中させた。坂上と織田は慣れたもので、早々に端のスペースを確保してる。
「松尾、俺らの前で見たら? 後ろだったら見えなくね?」
「お前、背が低いもんなぁ」
織田と坂上にそう言われて、僕は渋々二人の前に立つことになった。言っておくが、僕の身長が低いのではない。この二人の背が高いのだ。
「ってか、本間さんって結構可愛いよな」と坂上が言った。「俺の彼女には負けるけどな」と織田が無駄に張り合っている。コイツは隙あらば
「でも本間さんには彼氏いるみたいだからね。誰かは知らないけど」
PV用の動画の中で本間さんが愛を叫んでいた相手のことだ。坂上が大きく溜息を吐く。
「はー、俺も彼女欲しいわ」
「坂上は恋人いないの?」
「いねーわ。松尾だって童貞だろ?」
「どっ、えっ」
そういう会話は得意じゃない。しどろもどろになった僕を腕で制し、織田が胸ポケットから何かを取り出すような動作をした。
「はい、イエローカード。セクハラは事務所NGです」
「いや、普通の会話だろ」
「セクハラする側はいつもそう言うのよねー、これだから男子は!」
「なんでお前が女子側なんだよ」
坂上が織田の肩を叩き、二人はゲラゲラと笑った。この二人のノリには時折ついていけない。
「松尾も坂上に変なこと言われたらちゃんと怒っていいからな」
織田に言われ、僕は肩を
それからしばらくして、軽音ライブが始まった。バンド一組当たり、持ち時間は二十分。明らかに場慣れしている生徒からMC中に六回噛んだ生徒まで、パフォーマンスのクオリティーにはかなりの差があった。アンプがけたたましく叫び、ドラムの振動がダイレクトに肌を揺らす。
軽音部のライブに来ると、うるさいと心地よいの境目はどこにあるのだろうと考えてしまう。あまりの大音量に耳を塞ぎたい時もあれば、激しいリズムに身を任せたくなる時もある。魅力を感じる音楽とそうでない音楽に、何か違いはあるのだろうか。
マイクを掴む女子学生が、叫ぶように歌っている。観客からは歓声が上がっているが、僕はどうにも手放しで称賛することができなかった。脳裏にちらつくのは、桜田さんの歌声だった。
「では、スペシャルゲスト、健康法師!」
部長のMCで最後に登場したのは、これまでのバンドとは明らかに毛色の違う男だった。まず、一人だ。ほっそりとした長身に、乱雑に後ろに
きゃー、と聞こえた黄色い歓声は入り口付近に立つ女子生徒からだった。その中には、本間さんも混じっていた。
「アイツだよ」
肘で僕の腕を小突き、坂上が言った。
「アイツが例のスゲー奴」
確かに色々な意味で凄い。振り返ると、織田は
健康法師はマイクを掴むと、「えー、どうも」と短く声を発した。その声の低さに驚く。大人の男という表現が似合う、圧倒的な美声だった。
「それじゃ、歌います」
そう言って、彼はエレキギターの弦を弾いた。何が始まるんだとドキドキしていると、何故かドラムがリズムを刻む音が聞こえた。ドラムには誰も座っていないのに。
「おお、大勢揃って来たな。さあさあずーとこっちへ
アップテンポの曲に乗って紡がれる、
健康法師の語りはさらに熱を増し、彼はついにはギターを手放した。それでも音楽は鳴り続けている。どうやらエアギターだったらしい。
「ほんとうに笑わねえか? じゃ言うけど、じつは、おれの怖いのは、
そこまで聞いて、ようやく分かった。落語だ。有名な『饅頭こわい』の一節だ。
話の流れが分かって聞くと、早口の内容も聞き取れる。話が進むにつれて曲も盛り上がっていく。マイクを掴む彼の手にも力が入っているのが分かる。音楽の盛り上がりと共に加速する語りを終え、彼は言った。
「へへへ、あとは、お茶がこわい」
曲が終わった瞬間、その口元がふと綻ぶ。観客席からまたしても黄色い歓声が上がった。理解できないのにすごい。それが、僕の素直な感想だった。
健康法師が披露したのは、結局その一曲だけだった。
全メンバーの演奏が終わり、その日のライブはお開きとなった。「ありがとうございました!」という部長の声に、皆が拍手で応じている。肩を叩かれ振り返ると、織田が親指を立てていた。
「アイツ誘うわ」
だろうね、と僕は苦笑した。さっきの男は、織田の求める飛び道具像にピッタリだったから。
「俺、声掛けて来るから」
即断即決。織田の行動は早かった。僕と坂上をスタジオに残し、一人で控え室に向かって行った。
「やっぱ気に入ったかー」と言う坂上は、他人事みたいな顔をしていた。
「ついていかなくていいと思う?」
「いいだろ、アイツ交渉上手いし」
「さっきの人、仲間になってくれるかな」
「ま、半々ってとこじゃね? なんか、誰かとつるまなそうな雰囲気もあるし」
そうこうしているうちに、肩を落とした織田がスタジオへと戻って来た。報告を聞かずとも結果は明らかだった。
「断られたんだね」
僕の言葉に、織田は「残念ながら」と溜息を吐いた。
「じゃ、第二候補を探す?」
「いや、俺は絶対アイツがいい」
「でたよ。織田の石頭」
坂上がこめかみを押さえる。
「織田的にはどれぐらい勝率の見込みがあるの?」
「手応え的には十五パーセント」
「それ絶対盛ってるだろ」
あはは、と乾いた笑いは自然に途切れ、男三人は頭を抱えた。そもそも、友達同士ですらユーチューバーをやるのはハードルが高い。ましてや見も知らぬ後輩から声を掛けられて、話に乗ってくるはずがない。
「三人共、今日の演奏はどうだった?」
うんうんとスタジオ隅で唸っているクラスメイトを
「松尾君はどのバンドが一番好きだった?」
「やっぱ、最後の人が一番インパクトあったかなぁ。健康法師」
「本当? 良かった」
僕の言葉に、本間さんの目が輝きだした。先ほども歓声を上げていたから、彼のファンなのかもしれない。
「先輩、松尾君に会いたいって言ってたの。直接感想伝えてあげて」
「え? なんで松尾に?」と織田が口を挟んでくる。
「それは秘密。松尾君、私が先輩のところまで案内するから一緒に来てくれない?」
急展開に戸惑いながらも、僕は首を縦に振った。女子にお願いされると断れない性格なのだ。
「じゃ、坂上君と織田君、松尾君のことちょっと借りるね」
見送る織田の口が、パクパクと動く。う・ま・く・や・れ・よ、と言っているようだが、勝手に期待しないで欲しい。こっちは織田の半分くらいしかコミュニケーション能力がないというのに。
僕が本間さんに連れて来られたのは、ついさっき織田が訪れたであろう控え室だった。先ほどステージに立っていた一年生部員たちがはしゃいでいる中、健康法師は一人、パイプ椅子の上で
「
この人、夏目って名前なのか。いや、健康法師が本名でないことは分かっていたけれど、なんとなく普通の名前であることに違和感がある。真ん中で分けた黒髪が、綺麗な顔の
「あー、もう撤収の時間?」
目を
「そうじゃなくて、松尾君です。ほら、前に紹介するって言ってた」
本間さんの言葉に、夏目の両目が見る見るうちに見開かれた。「君かー」と勢いよく立ち上がる夏目に、僕は一歩分後ろへ下がった。
「あ、ど、どうも」
「軽音のライブ、聞きに来てくれたんだね。ありがとー」
「あぁ、いえ。全然。冷やかしみたいなもんなんで」
「松尾君、健康法師の演奏が一番良かったって言ってましたよ」
余計なことを口走った僕を、本間さんがすかさずフォローしてくれる。「照れるなー」と夏目が
このまま世間話をしていても
「あの、夏目さん、ちょっとお願いがあるんですけど」
「お願いって?」
「えっと……僕らと一緒にユーチューバーやってくれませんか?」
「いいよー」
「ユーチューバーって言ってもゲーム実況っていうジャンルで、先輩が想像するものと少し違うかもしれな──え、今なんて言いました?」
あまりに気の抜けた返事だったせいで、聞き流してしまった。目を白黒させる僕に、夏目はへラリと力の抜けた笑みを見せた。
「だから、いいよって」
「でも、さっき織田が頼んだ時はダメだったって……」
「あー、織田ってさっき来たあの背の高い奴? 俺、自分より背が高い奴って嫌いなんだよね」
嘘だろ、そんな理由だったのか。唖然としている僕を見て、夏目が「冗談冗談」と掴みどころのない声で言った。
「本当はチームプレイとか面倒ごととか嫌いなんだけど、松尾君の頼みなら仕方ないかなーって」
「ほ、ほんとですか? というかなんで? 僕、夏目さんと接点なかったと思うんですけど」
「いやいや、接点大アリだよ。あ、自己紹介してなかったね。俺、夏目
「あ、僕、松尾直樹です。あの、一年生です。帰宅部で、部活とか入ってないんですけど」
「知ってる知ってる。松尾君、この前ウチの部の映像編集手伝ってくれたでしょ?」
もしかして、軽音部の動画編集を手伝ったことが理由なのか。情けは人の為ならずということわざは本当なのかもしれない。人助けの大切さをしみじみと噛み締めている僕の心を読んだように、「いや、あの件は別にどうでもいいんだけどさー」と夏目はあっさりと言ってのけた。
「君のおかげで俺と佳代、別れずに済んだから。喧嘩してたんだけど、あの動画見て仲直りしたんだよー」
「オレとカヨ?」
佳代、というのはもしや本間佳代さんのことだろうか。僕は夏目の隣に立つクラスメイトの顔を見た。彼女は恥ずかしそうに自身の頬を押さえている。
たっくん……喧嘩……本間さんの彼氏……夏目拓光……。情報のピースが一つに繋がる。動揺を隠せないまま、僕は二人を交互に指さした。
「もしかしてお二人、付き合ってらっしゃる?」
「えへ、そうなんだ」
答えたのは本間さんだった。「部活ではあんまり大っぴらにしないようにしてるんだけどね」とはにかみながら続ける彼女の表情を、僕はカメラ越しに見たことがある。
夏目は僕の肩に手を置くと、顔を覗き込むようにこちらを見下ろした。織田よりも少し背が低い、多分、身長は一七五センチといったところか。坂上の手と違い、夏目の手はほっそりとして綺麗だ。
彼の両目がニッコリと細められる。軽薄さと
「松尾君さ、才能あるよ」
「いやいやそんな」
「俺、あの動画見て凄いなって思ったもん。佳代、すっごい可愛いかったよねー」
彼氏の直球の褒め言葉に、本間さんが顔を真っ赤にしている。イチャつくなら二人でやってくれよ、と僕はこっそりと思った。
恋人への愛は、どうぞ本人にお伝えください。