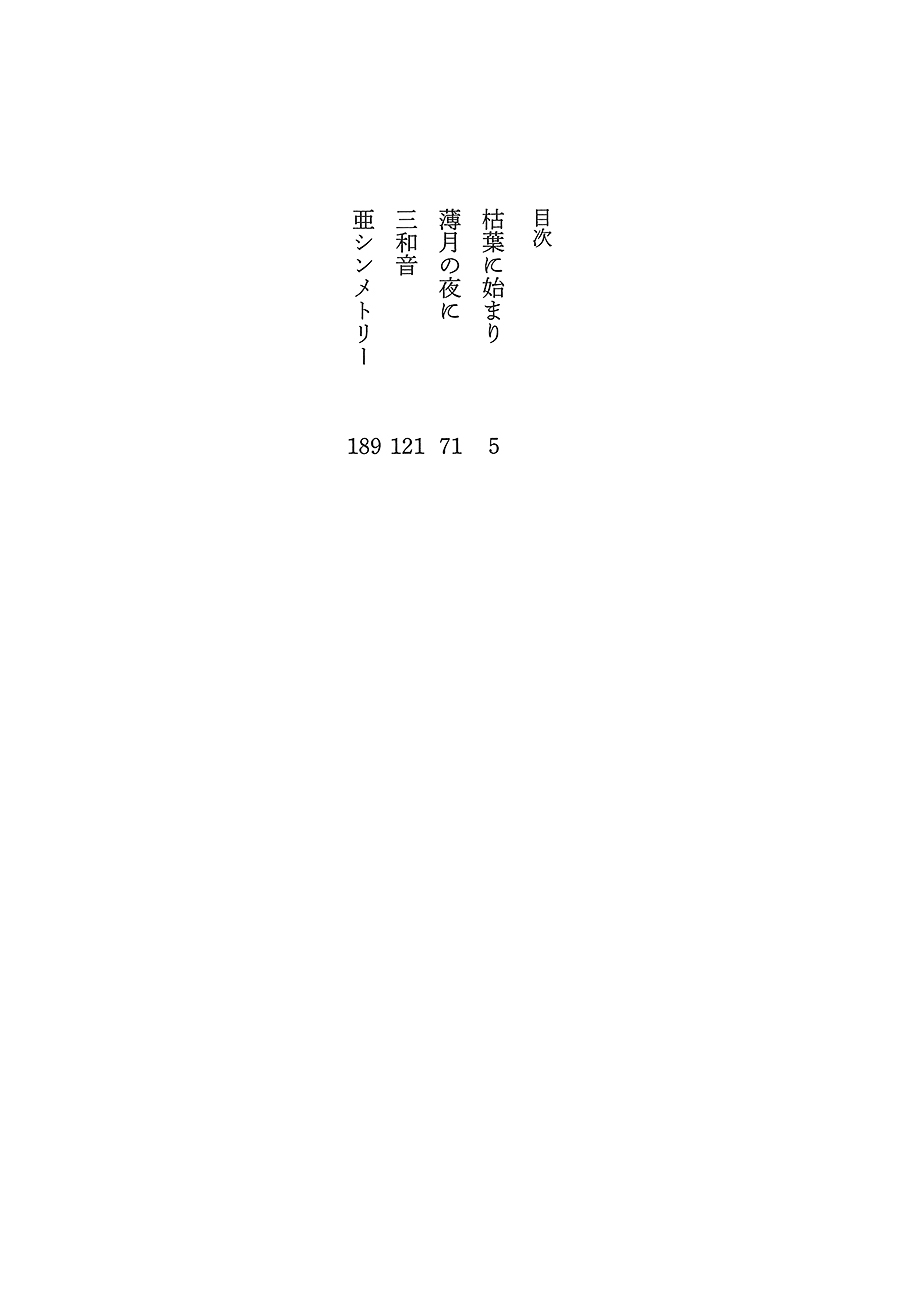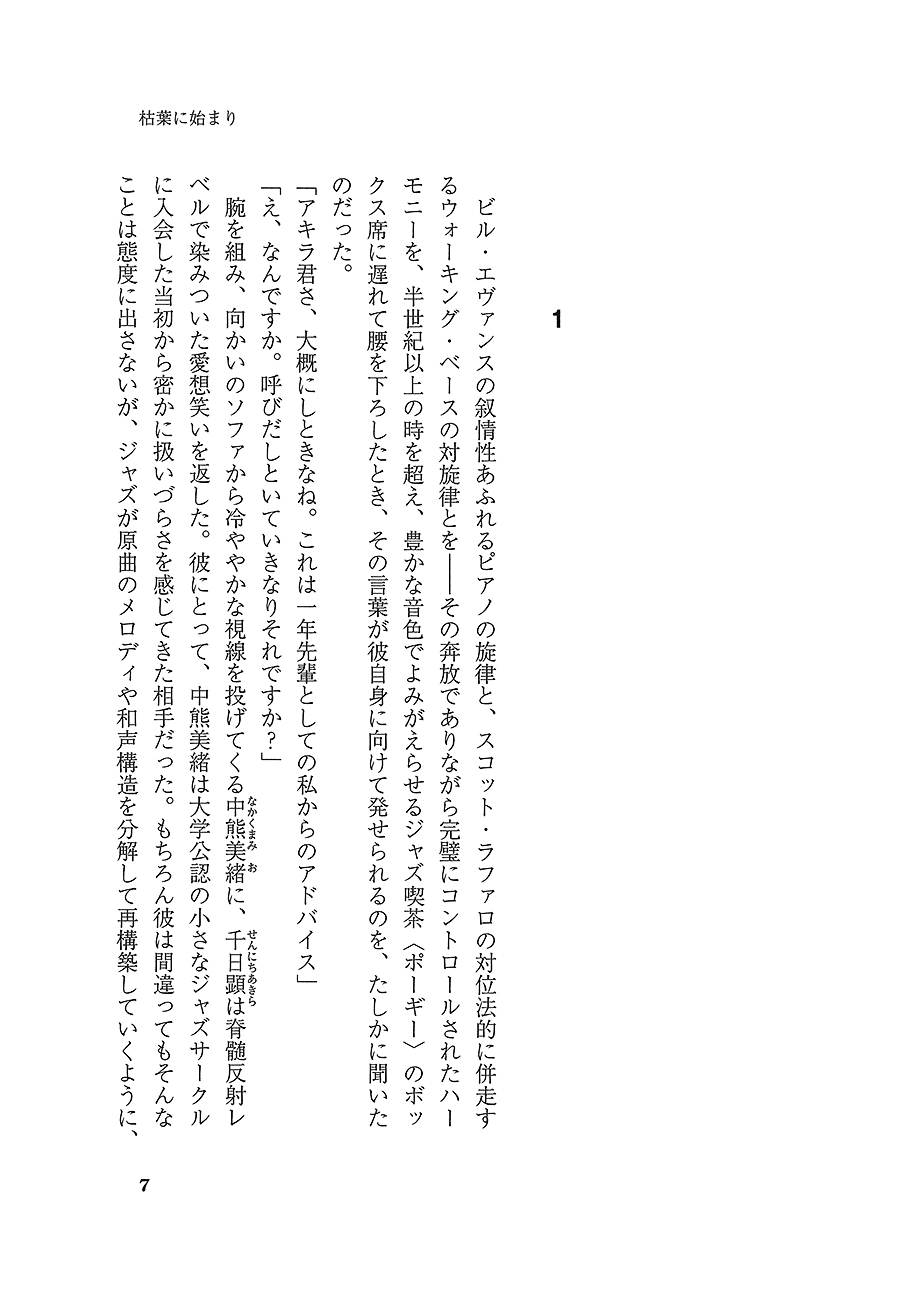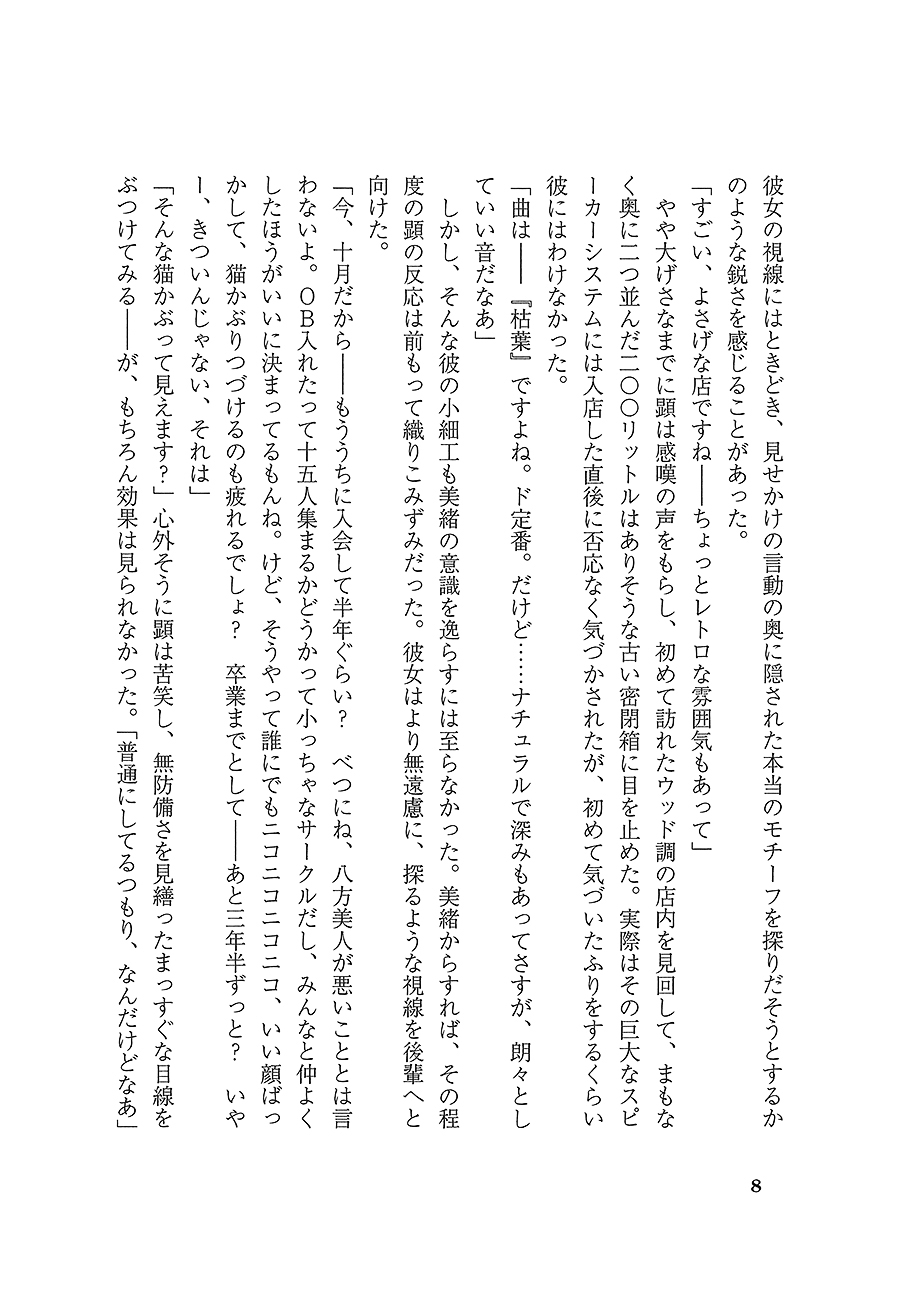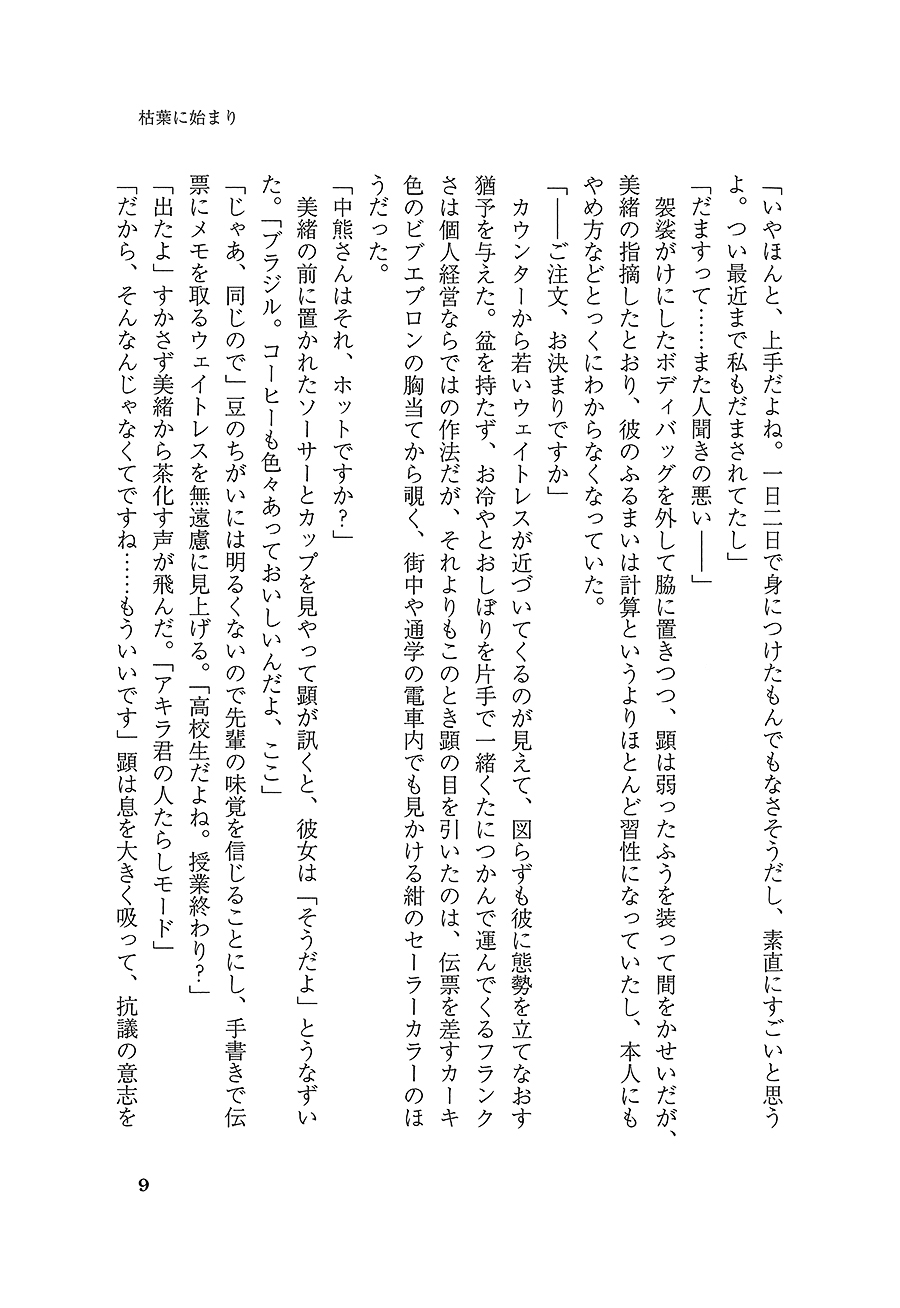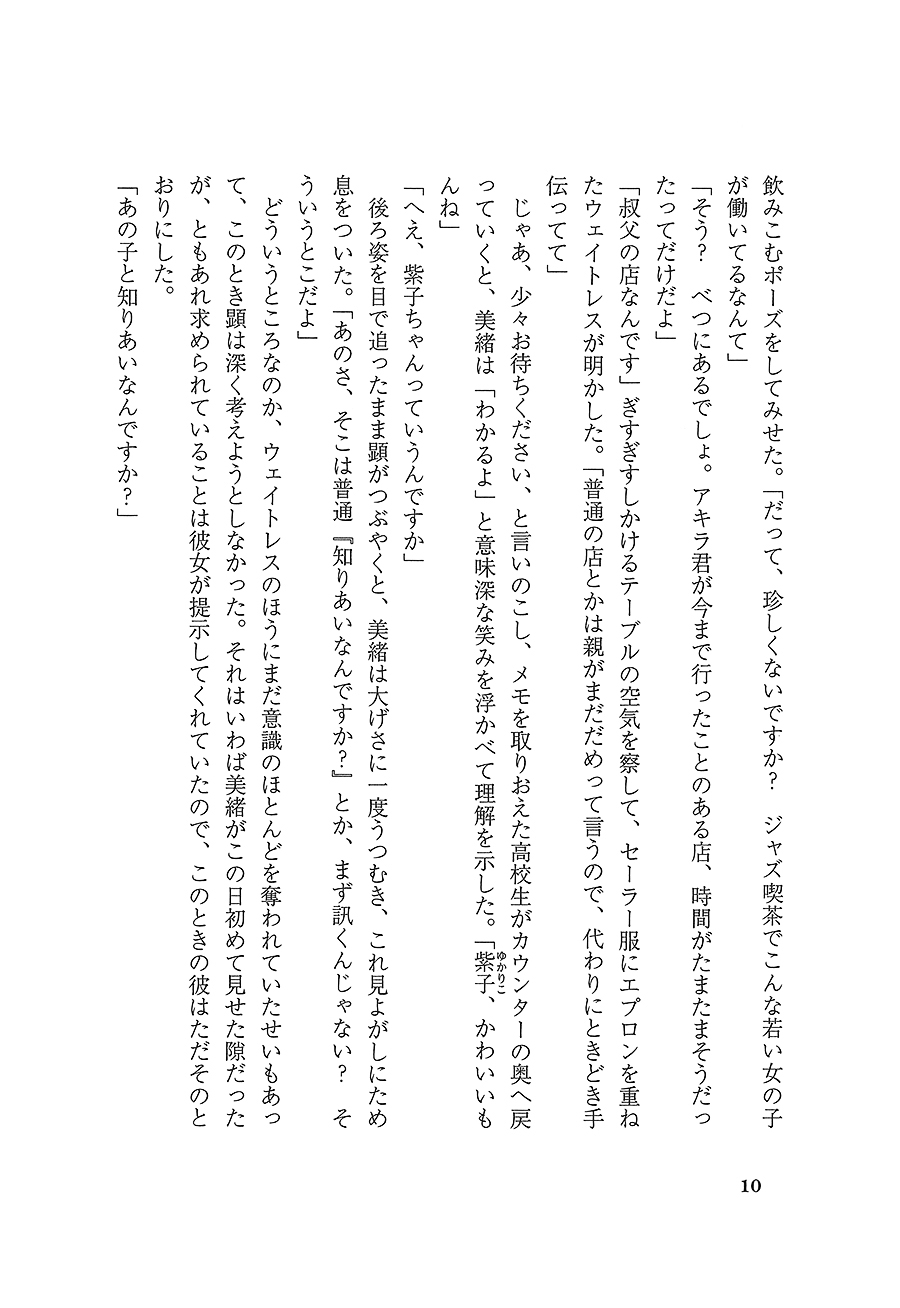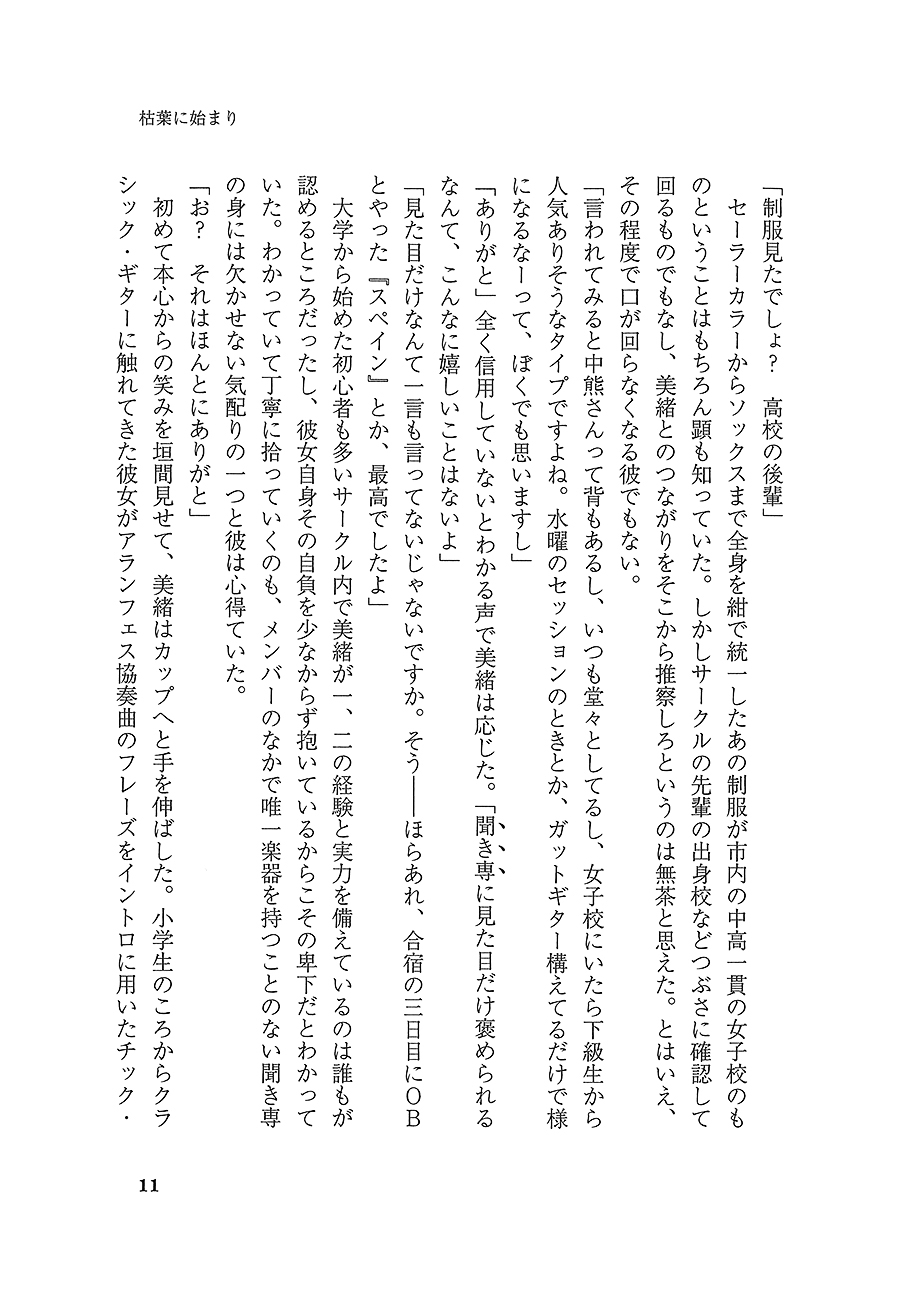枯葉に始まり
1
ビル・エヴァンスの叙情性あふれるピアノの旋律と、スコット・ラファロの対位法的に併走するウォーキング・ベースの対旋律とを――その奔放でありながら完璧にコントロールされたハーモニーを、半世紀以上の時を超え、豊かな音色でよみがえらせるジャズ喫茶〈ポーギー〉のボックス席に遅れて腰を下ろしたとき、その言葉が彼自身に向けて発せられるのを、たしかに聞いたのだった。
「アキラ君さ、大概にしときなね。これは一年先輩としての私からのアドバイス」
「え、なんですか。呼びだしといていきなりそれですか?」
腕を組み、向かいのソファから冷ややかな視線を投げてくる中熊美緒に、千日顕は脊髄反射レベルで染みついた愛想笑いを返した。彼にとって、中熊美緒は大学公認の小さなジャズサークルに入会した当初から密かに扱いづらさを感じてきた相手だった。もちろん彼は間違ってもそんなことは態度に出さないが、ジャズが原曲のメロディや和声構造を分解して再構築していくように、彼女の視線にはときどき、見せかけの言動の奥に隠された本当のモチーフを探りだそうとするかのような鋭さを感じることがあった。
「すごい、よさげな店ですね――ちょっとレトロな雰囲気もあって」
やや大げさなまでに顕は感嘆の声をもらし、初めて訪れたウッド調の店内を見回して、まもなく奥に二つ並んだ二〇〇リットルはありそうな古い密閉箱に目を止めた。実際はその巨大なスピーカーシステムには入店した直後に否応なく気づかされたが、初めて気づいたふりをするくらい彼にはわけなかった。
「曲は――『枯葉』ですよね。ド定番。だけど……ナチュラルで深みもあってさすが、朗々としていい音だなあ」
しかし、そんな彼の小細工も美緒の意識を逸らすには至らなかった。美緒からすれば、その程度の顕の反応は前もって織りこみずみだった。彼女はより無遠慮に、探るような視線を後輩へと向けた。
「今、十月だから――もううちに入会して半年ぐらい? べつにね、八方美人が悪いこととは言わないよ。OB入れたって十五人集まるかどうかって小っちゃなサークルだし、みんなと仲よくしたほうがいいに決まってるもんね。けど、そうやって誰にでもニコニコニコニコ、いい顔ばっかして、猫かぶりつづけるのも疲れるでしょ? 卒業までとして――あと三年半ずっと? いやー、きついんじゃない、それは」
「そんな猫かぶって見えます?」心外そうに顕は苦笑し、無防備さを見繕ったまっすぐな目線をぶつけてみる――が、もちろん効果は見られなかった。「普通にしてるつもり、なんだけどなあ」
「いやほんと、上手だよね。一日二日で身につけたもんでもなさそうだし、素直にすごいと思うよ。つい最近まで私もだまされてたし」
「だますって……また人聞きの悪い――」
袈裟がけにしたボディバッグを外して脇に置きつつ、顕は弱ったふうを装って間をかせいだが、美緒の指摘したとおり、彼のふるまいは計算というよりほとんど習性になっていたし、本人にもやめ方などとっくにわからなくなっていた。
「――ご注文、お決まりですか」
カウンターから若いウェイトレスが近づいてくるのが見えて、図らずも彼に態勢を立てなおす猶予を与えた。盆を持たず、お冷やとおしぼりを片手で一緒くたにつかんで運んでくるフランクさは個人経営ならではの作法だが、それよりもこのとき顕の目を引いたのは、伝票を差すカーキ色のビブエプロンの胸当てから覗く、街中や通学の電車内でも見かける紺のセーラーカラーのほうだった。
「中熊さんはそれ、ホットですか?」
美緒の前に置かれたソーサーとカップを見やって顕が訊くと、彼女は「そうだよ」とうなずいた。「ブラジル。コーヒーも色々あっておいしいんだよ、ここ」
「じゃあ、同じので」豆のちがいには明るくないので先輩の味覚を信じることにし、手書きで伝票にメモを取るウェイトレスを無遠慮に見上げる。「高校生だよね。授業終わり?」
「出たよ」すかさず美緒から茶化す声が飛んだ。「アキラ君の人たらしモード」
「だから、そんなんじゃなくてですね……もういいです」顕は息を大きく吸って、抗議の意志を飲みこむポーズをしてみせた。「だって、珍しくないですか? ジャズ喫茶でこんな若い女の子が働いてるなんて」
「そう? べつにあるでしょ。アキラ君が今まで行ったことのある店、時間がたまたまそうだったってだけだよ」
「叔父の店なんです」ぎすぎすしかけるテーブルの空気を察して、セーラー服にエプロンを重ねたウェイトレスが明かした。「普通の店とかは親がまだだめって言うので、代わりにときどき手伝ってて」
じゃあ、少々お待ちください、と言いのこし、メモを取りおえた高校生がカウンターの奥へ戻っていくと、美緒は「わかるよ」と意味深な笑みを浮かべて理解を示した。「紫子、かわいいもんね」
「へえ、紫子ちゃんっていうんですか」
後ろ姿を目で追ったまま顕がつぶやくと、美緒は大げさに一度うつむき、これ見よがしにため息をついた。「あのさ、そこは普通『知りあいなんですか?』とか、まず訊くんじゃない? そういうとこだよ」
どういうところなのか、ウェイトレスのほうにまだ意識のほとんどを奪われていたせいもあって、このとき顕は深く考えようとしなかった。それはいわば美緒がこの日初めて見せた隙だったが、ともあれ求められていることは彼女が提示してくれていたので、このときの彼はただそのとおりにした。
「あの子と知りあいなんですか?」
「制服見たでしょ? 高校の後輩」
セーラーカラーからソックスまで全身を紺で統一したあの制服が市内の中高一貫の女子校のものということはもちろん顕も知っていた。しかしサークルの先輩の出身校などつぶさに確認して回るものでもなし、美緒とのつながりをそこから推察しろというのは無茶と思えた。とはいえ、その程度で口が回らなくなる彼でもない。
「言われてみると中熊さんって背もあるし、いつも堂々としてるし、女子校にいたら下級生から人気ありそうなタイプですよね。水曜のセッションのときとか、ガットギター構えてるだけで様になるなーって、ぼくでも思いますし」
「ありがと」全く信用していないとわかる声で美緒は応じた。「聞き専に見た目だけ褒められるなんて、こんなに嬉しいことはないよ」
「見た目だけなんて一言も言ってないじゃないですか。そう――ほらあれ、合宿の三日目にOBとやった『スペイン』とか、最高でしたよ」
大学から始めた初心者も多いサークル内で美緒が一、二の経験と実力を備えているのは誰もが認めるところだったし、彼女自身その自負を少なからず抱いているからこその卑下だとわかっていた。わかっていて丁寧に拾っていくのも、メンバーのなかで唯一楽器を持つことのない聞き専の身には欠かせない気配りの一つと彼は心得ていた。
「お? それはほんとにありがと」
初めて本心からの笑みを垣間見せて、美緒はカップへと手を伸ばした。小学生のころからクラシック・ギターに触れてきた彼女がアランフェス協奏曲のフレーズをイントロに用いたチック・コリアの『スペイン』をきっかけにジャズに興味を持った、というのは新歓の自己紹介で自ら語っていたことだ。
「あと一つ、訂正しとくけど」コーヒーを一口飲み下したあと、美緒は言った。「下級生に人気ありそうってアキラ君、さっき言ってたけど、そんなことないから。自分で言うのも口幅ったいんだけど、私、同級生や上級生にも人気あったから」
「さすが――」
「まあでも、そんなことはどうでもよくて」と後輩の口が回る前にさえぎって、彼女は首を振った。「わかってても、いつの間にか本題からどんどん話逸らされちゃうんだから、ほんと上手だよね」
「え、ぼくのせいなんです? だって、そもそも今日なんで呼ばれたのかも、まだ――」
「しっ。一旦黙る。それ以上しゃべらない。いい?」
ぴんと立てた美緒の人さし指に操られるように、顕が向かいの席で背筋をしゃんと伸ばし、従順さを過剰にアピールする顔で口元を引きむすぶと、彼女は束の間げんなりした表情を浮かべた。が、すぐに気を取りなおして言った。
「わかってこうやって見てると、けっこう面白いもんだね。セッション日のスタジオでも、勉強会で集まったときも、誰に対しても当たり障りなく、楽しく愛想よく、場を乱さず、ほどよく持ちあげてほどよく本音をさらして――そういう全部が実は、ここから奥は誰にも踏みこませたくないってラインがはっきり引いてあるのを気取られないためのカモフラージュになってるって感じ?」
「いや、あの……訊かれても困るんですけど」
「ほんと、感心してるんだよ。十八やそこらでそこまで身につくもんなの?」
「えっと、今日はつまり、そのお説教のために呼びだされた……っていう?」
「お説教? なんでよ」美緒は心底意外そうな表情で応じたが、内心では顕が想定どおりの反応を見せてくれることに満足していた。「そんなこと私、一言も言ってないよね? すごいと思う、面白いもんだねって言ってるんだよ。一応先輩として、大概にしときなよって、親切心でアドバイスはしたけど。アキラ君がそうしたいなら好きに続ければいいし」
ではなぜ呼びだされたのか、いやそもそも美緒の指摘が真実を言いあてているともまだ認めていないし、などと顕はすばやく思いをめぐらせた。が、目の前に座るこの先輩にはそんな心の動きさえ捕捉されている気がしてどうにも居心地が悪いのだった。
「べつにね、みんなの前でばらすつもりもないし」顕を安心させてやるために、美緒はボックス席の低いソファの背に片肘を載せ、リラックスした声音でつけ加えた。「ただ、一度そういうの取っぱらったアキラ君と、腹割って話してみたいなと思ってたんだよ」
「え、なんですか。告白ですか?」
貞操を守ろうとする乙女よろしく両肩を抱いて、顕はすかさず冗談めかしたが、そうしてストックのなかから取りだしたパターンで対応できることに彼が安堵していることすら見透かしている美緒は「だから、そういうのをね――」と口にしかけ、しかし続く言葉はため息の底に沈んでいった。「いいや。言い出しっぺなんだし、まず私から腹を割ってみせろってもんだよね」
「割らなくていいですよ」
「最初にはっきりさせとくけど」面倒を避けようとする顕の声を無視し、美緒は通達した。「私がアキラ君に告白する、なんてことは絶対ないから。なんでかっていうとね、基本的に私もアキラ君と同じ考えだから」
「ぼくと?」意図を汲みかねて顕は訊きかえした。「というと……え、どういう?」
「だってアキラ君、同じサークルとか、クラスでもバイト仲間でもいいけど、そういう小っちゃなコミュニティのなかで誰かとカップルになるなんて、絶対に考えられないって思ってるでしょ?」
動揺が顔に出そうになるのをとっさに抑えつけて、顕は「そんなことないですよ」と、かろうじて心外さを取りつくろうことに成功した。「誰がそんなこと言ってるんです?」
しかし美緒はにやにやと笑みを浮かべるばかりで答えなかった。種を明かせば、先月の夏季休暇中にあった京都でのサークル合宿の三日目、酒の入ったOBに絡まれて顕がぽろっとこぼした本音をたまたま立ち聞きしただけなのだが、こういうものは可能なかぎりもったいぶるのが美緒の楽しみ方だった。回りくどいもの、遠大な仕掛けを好む彼女の性質は幼少時から培われてきたもので、教育番組の影響を受けて中学生時代には自室の大部分を占領するルーブ・ゴールドバーグ・マシン――いわゆるピタゴラ装置の制作に夢中になっていた時期もあった。
「じゃあ、たとえばよ」と、直立するポールに巻きついた振り子が解放され、一見隔絶された別ルートのビー玉を計算どおりに弾く瞬間を見逃すまいとするように、期待に満ちた笑みを浮かべて彼女は投げかけた。「森本と可児ちゃんのこと、アキラ君はどう思ってる?」
「森本と……可児ちゃんですか?」
二人は顕と同じ一年生で、サークル入会後ほどなくしてつきあいはじめており、自主練習日はもちろん、セッション練習でも先輩やOBからの指示がないかぎりは決まって一緒に演奏していた。
「どうって――」
「正直にね」
美緒に釘を刺され、それでも顕はすでに出かかっていた「楽しそうでいいと思いますよ」をあえて口にすることで、そのあとの言葉を選ぶ時間を作りだした。「演奏は……まあ、森本は全くのドラム初心者だし、可児ちゃんは可児ちゃんでちょっと、ピアノ経験があるのを過信しすぎてる感じはありますよね。彼女にしたらリードしたいっていうか、森本にいいとこ見せたい気持ちが強いんでしょうけど、雰囲気でごまかしすぎっていうか……典型的な脱力奏法だから、四月と比べてもほとんどミスタッチ減ってないですし」
「なるほど」と美緒は納得したように何度もうなずいた。「ほどよい本音だね。的確でいて実にほどよい本音だ」
「あんまりこういうこと、ほんとは言いたくないんですよ」少しでも美緒の同情を買えれば、と期待して顕はぼやいた。聞き専でいるかぎりジャズの本当の魅力は半分も理解できない、という奏者上位の空気は彼らのサークル内の一部にも根強くある。「本人たちや、ほかの人にも言っちゃだめですよ」
しかし美緒は「どうしようかなー」とかすかにあごを反らせ、新たに手中に収めたカードを弄んだ。「話の流れ上、そんなこと訊いてるんじゃないって絶対わかってるくせに、またはぐらかされちゃったしな」
とはいえ、そろそろ頃合いでもあるな、と彼女は判断した。
「あーあ」と、美緒はこれ見よがしのぼやき声をもらした。「合宿のバーベキューのあとみたいに、『ああいう、その場その場で現地調達していける人たちってすごいですね』ってセリフ、アキラ君の口からもう一回聞きたかったんだけどなあ」
このときにはさすがに、顕もすべてを理解した。その言葉を口にしたことを彼ははっきり覚えていたし、それは彼が未成年で、あの合宿三日目の夜も黒ウーロン茶と特保コーラしか飲んでいなかったからだし、執拗に恋愛話をふっかけてきたOBはずいぶん酒が入って正体があやしくなっていたからこそ油断して口にした本音だった。
「みんな花火とかやってたし、周りに誰もいないと思ってた? だめだよ、車乗るときと嫌み言う前は、ちゃんと指さし確認しなきゃ」
「聞いてたんですか……あれ」哀れみを誘うべく顕は声を絞りだした。「いや……あれはですね、あのくらい言わないと、いつまでも解放してくれそうになかったんですよ。思った以上に強い言い方にはなっちゃいましたけど、べつにあの二人のことそこまで――」
「人の恋路をつかまえて現地調達って、ひかえめに言ってすごい言い草だよね」美緒は空恐ろしさを表すようにあごを引いてみせた。「とっさの皮肉にしたって、普段から思ってなきゃそうそう出てこないでしょ」
「だからそれは、その……言葉のあやというか」
「言葉のあやで『軍隊とか、刑務所なんかの機会的同性愛も、現地調達も、本質的には大して変わりませんよね』なんて表現、出てくるかね?」
そこまで聞かれていたとなれば、もはやどんな言い逃れも無意味だった。「後出しはひどいですよ」と彼は空しく抗議した。
「アキラ君がいつまでも正直に言わないからでしょ」
「べつに、全部が全部そうだって言ってるんじゃないですよ。べつに可児ちゃんたちを恋愛ごっこだとも言ってないですし」方針転換せざるを得なくなって、顕は弁明を試みた。「ただ、あくまで一般論として、そこになんの疑問も抱かずに突き進める人たちがうらやましいなって話で」
「『飼育ケースに入れられた実験用マウスみたいに』?」
「それはぼく言ってませんよね?」
顕が冷静にあらためると、美緒は「くそ」と舌打ちをしてかすかに口角を上げた。「かからなかったか」
「何陥れようとしてるんですか」警戒と不服を強くにじませた声をもらし、そのあと、これまでの言動から導かれる事実を指摘した。「っていうか今の、中熊さんの本音ってことですよね」
「そうだよ」と美緒は臆面もなく認めた。「ああいう子らを少なからず冷めて見てるっていうのはさ、突きつめれば、根っこのとこではそう思ってるってことでしょ。きれい事でごまかしたってしょうがないじゃんね」
すごい言い草はどっちなんだか、と口には出さず顕は内心で毒づいた。実験用マウスと比べたら、現地調達など皮肉として手ぬるくすら思えてくる。
「ただ、私はアキラ君みたいに普段から可児ちゃんたちを茶化したり、うらやましがってみせたりしてないし、そういう意味でアキラ君のほうが断トツ罪深いってのは少しも変わらないんだけどね」
自身の潔白さと顕に対しての優位性については揺るがないことを美緒が明確にすると、反論する気も失せた顕は「もうそれでいいです」と白旗を上げた。
「わかればよろしい」顕の神妙な態度に満足した美緒はボックス席のなかでじっくり背筋を伸ばし、二人の新たなパワーバランスにふさわしい高慢な笑みを浮かべた。「で」と居丈高に、有無を言わさぬ強さで彼女は申しわたした。「ここからが本題なんだけど」
もはや疲れの色を隠す義理も感じられなくなって、顕は「まだ本題じゃなかったんですか」と嘆息まじりにぼやいた。
2
「これ、見てくれる」
美緒は脇に置いた自身のバッグからクリアファイルを引きだすと、顕から見える位置まで持ちあげてみせた。中にはA4サイズの用紙が数枚挟まっている。
「高校の後輩からね、ちょっと相談されてるんだけど」明らかに無気力な目をした顕を気にもとめず、美緒は話を進めた。「新聞部で使ってるパソコンから最近、誰かが見つけたテキストらしいんだけど、書かれてる当時のこと知ってる人、もういなくてね。しかも内容がいまいち理解できないって、後輩の子らのあいだでちょっと話題らしいんだよ」
「中熊さん、高校時代は新聞部だったんです?」
仕方なく話につきあっている体のまま顕が訊くと、美緒は「全然」と首を振った。「軽音にはときどき顔出してたけど、基本帰宅部。高校入ってからは、ジャズバーとかで素人参加OKのセッションがあると連れてってもらったりしてたから、そっち優先」
そういえば以前にそんなことを聞いた気もするな、と顕が納得するあいだに、美緒はクリアファイルから当該テキストが横書きで印刷された用紙を取りだした。
「で、この内容がさ、美術部であった事件――っていうか、トラブルのことをね、何日かたって新聞部が取材したものらしいんだけど。たしかに読むと、なんだか妙なんだよね。それでアキラ君にも知恵を借りれたらなって思って」
「なんでまたぼくに?」
「私も聞きたいです、それ」同調する声は芳ばしい香りをテーブルへと運んできた紫子のものだった。「お待たせしました。ブラジルです」
豆本来の味を活かす中煎りのコーヒーを客に提供し、ウェイトレスとしての最低限の役割を果たすと、紫子は美緒に向きなおった。
「やっぱりその話だったんですね」それとなく恨めしさをこめた声で言った。「私は、ドロシー先輩に解いてほしかったのに」
「その呼び方やめてって、いつも言ってるよね」美緒はげんなりした顔でぼやき、そのあとあらためて紫子を見上げた。「頼れる頭数は多いほうがいいでしょ?」
「それは……そう、かもですけど」
「中熊さんに相談した後輩って、紫子ちゃんのことなんです?」
俄然前のめりになって顕が訊くと、美緒は紫子から目を離さないまま「まあね」とそっけなく応じた。「ほら、給仕がすんだらウェイトレスはさっさと持ち場に戻る」
ところが、紫子は先輩の促しに応じるどころか、丸い盆を胸に抱えたまま美緒が座るソファの端にちょこんと腰を下ろした。
「おおい。座っちゃったよこの子」
「今、ほかにお客いないですし」呆れ声をもらす美緒に悪びれることなく言い放って、そのあと紫子は「お邪魔ですか?」と、それまでに見せていた営業用の顔とは別の引き出しから屈託のない笑顔を取りだして顕に伺いを立てた。
それが実際には計算された作り笑顔であることは百も承知で、顕の損得勘定は瞬時に彼女と共同戦線を張るほうに利を見出した。美緒にとってどうやら望ましい展開ではないらしい、という以外に理由を探す必要すら感じなかった。
「ドロシー先輩っていうのは?」と顕は了承の言葉に代えて、テーブルに身を乗りだし紫子に尋ねた。「なんでドロシー?」
「紫子だけなんだよ、私のこと未だにそんなふうに呼ぶの。それより――」
「あ、今は紫子ちゃんに訊いてるので」本題へと軌道修正を図る美緒をさえぎって、先ほどの仕返しとばかり口元に人さし指を立てた。「ドロシー先輩は。お口チャックで」
「おま……」横書きの印刷物を持つ指先に一瞬力が入ったあと、美緒は意識して体から力を抜くとソファに背中を預け、強がり半分に二度うなずいた。「いい感じに本性出てきたんじゃん」
「ビリー・ティプトンってアーティスト、アキラさんは知ってますか?」早く説明したくて仕方ないふうを装って、紫子は顕の目を自身へと向けるべく問いかけた。「アメリカの昔のジャズミュージシャンで、楽器は主にピアノ、あとサックス――」
「たしか、男装で音楽活動してた人じゃなかったっけ?」雑誌かテレビか、あるいはネットで触れた知識だったかも定かでないまま、顕がかすかな記憶を引っぱりだすと、紫子が嬉々としてうんうん、とうなずいたので彼は気を良くした。「そのころは性別間の職業格差がひどくて、女性だとミュージシャンの仕事がもらえなかったから、とか――」
ミュージシャンとしてだけではなく、私生活でも従兄弟などごく一部の人間以外には女性であることを隠したまま、出会った女性たちと複数回家庭を持ち、養子に迎えた三人の息子たちにも潰瘍性の出血による死を迎えるまで男性だと信じさせていたことで死後ジャズファンの枠を越えて話題になった――顕が承知しているのはその程度の略歴だけだった。日本ではビリー・ティプトンのアルバムは発売されていないから、聞き専の顕からすれば、エピソードがいくら魅力的だろうと話の種としては飛び道具の域を出ない。
「私も、叔父さんから教えてもらっただけなんですけど」と笑顔のまま紫子は断った。「叔父さんに誘われて、母と一緒に見にいったジャズバーでたまたま、先輩がセッションに参加してて」気遣うように、反応を楽しむようにちらりと横の先輩を見やる。「それを見た叔父さんが、若きビリー・ティプトンがいるぞ――って」
暗い色の細身のパンツに白の開襟シャツを合わせた美緒が白い照明を浴び、ギターを巧みに操る姿を脳裏にありありと思いうかべると、紫子は初めて目にしたその日の感銘と興奮を何度でも反芻できるのだった。ジャズバーのセッションに大人に混じって参加する同年代の女の子がいるなんて、ましてそれが同じ学園に通う二年先輩だなんて、唯一許されるアルバイト先という以外ジャズに大した興味も抱いていなかった彼女には想像もしないことだった。
「ビリー・ティプトンのビリーは、父親のウィリアムからとってて」と、紫子は目を輝かせて説明した。「本当のファーストネームはドロシーなんです」
本名までは知らなかった顕は「それでドロシー先輩」と納得してうなずいたが、そのあいだにも、にやにやと笑みがこぼれるのを抑えきれなかった。
「べつに私は男装してたつもりもないし」と、美緒は先んじて弁明した。「楽器だってちがうのに、紫子の叔父さんも失礼な話だよね」
「いいじゃないですか。かっこいいですよ男装のギタリスト」ひるまず顕は言って、たたみかけるように満面の笑みでくりかえした。「かっこいいですよ男装のギタリスト」
「腹立つわこいつ」
「そうですよ。失礼じゃないですか」
顕の態度をいさめようと、そうして美緒の隣で力む紫子も美緒からするとやはり的が外れていて、援護射撃の名目で背後から貫かれている気分になるのだった。
「本当にドロシー先輩、文句なしにかっこいいんですから」
3
「で、今度こそ本題」
顕がコーヒーにようやく口をつけ、紫子が抱えていた盆を膝に置くと、美緒はA4用紙の端をテーブルでそろえつつ言った。巨大な密閉箱から流れるモノラル録音の『枯葉』は幾度目かのリピートによって冒頭へと戻っていた。
「ていうか、あんたもまだ戻らないわけね」
本格的に隣に居座る構えの後輩を見やってぼやく美緒に、紫子は「もちろん」と返し、事後承認を求めるようにちらっと顕に目を移した。
「頭数は多いほうがいいって中熊さん、自分で言ったじゃないですか」
顕が望まれるままの役割を果たすと、紫子は再び作り笑顔を返し、顕もまんざらでもない顔でほほ笑みかえした。それを見て美緒はちくりと刺しておきたくなった。
「現地調達がどうこうって理屈こねてたけど、アキラ君ってもしかして女の子とつきあったことないの?」差しだしかけていたA4用紙を顕の手が届かない位置まで引っこめて、美緒は邪推した。「紫子がかわいいのはわかるけど、いくらなんでもちょろすぎるんじゃない?」
「ありますよ。失礼だなあ」
片手をついてテーブルに乗りだし、美緒の手からやや強引に用紙を受けとりながら、小学生のときだけど、と顕は心のなかでつけ足した。言葉足らずは彼にとって嘘のうちにも入らないが、当時の顛末がトラウマとなって今日の自分が形成されているという、逃れようのない事実に体じゅうの神経が音もなくさざ波立つ感覚があった。
二人にそうと悟られないために、「美術部のトラブルって言ってましたけど、これ、ジャズとなんか関係あるんですか?」とさりげないふうを装って、受けとった用紙に目を落としつつ顕は訊いた。
紫子がジャズでつながる美緒に相談し、美緒がジャズ研の後輩に持ちかけた点について尋ねたつもりだった。しかし、紫子と顔を見合わせたあと、美緒から返ってきたのは「美術とか音楽とか、ジャズとか、表現を垣根で区切って考えたがるようじゃ、アキラ君もまだまだだね」というはぐらかしだった。「無粋だよ無粋」
「アンリ・マティスっていう画家、知ってますか? あそこの壁に飾ってある、切り紙絵の作者なんですけど」
もちろんあれはレプリカですけど、と補足しつつ背後を指さす紫子に促されて、ふりかえった先に、青と黒のシンプルな色彩が目を引く切り紙絵を収めた大きな額が飾られていた。躍るように大胆にかたどられた黒い人影の左胸に、罪の刻印のような不穏な赤がぽつんと小さくあしらわれている。
「あの切り紙絵、『イカルス』ってタイトルなんですけど、『ジャズ』っていう挿絵本に収録されてるんですよ」紫子は流れるようによどみなく説明したが、それは美緒に協力を仰いだ際にも同じ説明をしたからだった。「はさみで色をダイレクトに切りだせる切り紙には、ジャズの即興性と通じるものがあるとかで」
「わかった? 表現っていうのは常に、ジャンルを超えて影響しあってるの」
紫子からの受け売りであることを棚に上げて高説を垂れる美緒に、紫子も叔父からつい最近仕入れた知識にすぎないことを棚に上げて満足げにうなずき、顕はこの二人に丸腰で立ちむかったところで時間の無駄という現実だけを受けいれて再び手元に目を落とした。
「とにかく、これを読めばいいんですね?」
「読んでもらったらわかるけど、ちょびっとだけね、ジャズにも通じるモチーフが出てくるんだよ」美緒は一転して励ますような声音で言い聞かせ、そのあと最低限の信頼関係はキープしておこうと本音の一部を明かした。「まあでも、正直ジャズとか関係なしに、アキラ君の知恵を借りれればなって、ほんとに思ったんだよ。八方美人って、頭の回転よっぽど良くないと無理なんでしょ?」
やはりばかにされているとしか受けとめられずに、顕はあからさまに眉をひそめた。「聞いたことないですけど。そんな理屈」
「アキラさんは八方美人なんですか?」
「八方どころか、もう十六方だろうが三十二方だろうが、全方位・全天候型の愛想ふりまきマシーンだよ」
「えー」美緒の適当な誇張を真に受けて、紫子はもう少し顕から距離をとっておこうとするようにソファの端で身じろぎした。「それはちょっと――引く、かも」
「あの」放っておくとどこまで好き勝手言いだすかわからない気配を察して、顕は折り目一つないA4用紙の上端をぱたぱた振りかざし、恨みがましい声で不平を述べた。「これ読みたいんで、少し静かにしてくれます?」
「ああ、ごめんごめん」
美緒が乾いた声で笑って謝ると、紫子も「冗談ですよ」と、美緒と同じ温度の笑顔と軽い言葉一つで前言を取りつくろった。「引いてないです」
「それ、たぶん音声データか、テープからの書きおこしだと思うんだよ」と、本題へ戻って美緒は説明した。「なんだけど、だいぶ古い話なのか、それ以外に資料らしい資料がPCにも、ほかの活動記録にも見つからないらしいんだよね」
顕はまだ冒頭の数行に目を走らせた程度だったが、たしかにこのテキストが音声を書きおこしたものであることに疑いはなさそうだ、という印象を持った。PC上のテキストデータがいつ作成されたものかは、紫子に頼めばあるいは確認できるかもしれない。しかし元になった音声の録音日時がわからないままでは、そのトラブルとやらが発生した年代を特定するにはたしかに不十分だろうと思えた。
「取材だけして、当時も記事にはしなかったのかもって、クラスの新聞部の子が言ってました」紫子が少しだけかしこまった固い声音で補足した。「部の伝統的にもあんまり、ドロドロした記事を載せる習慣はないみたいですし」
「とにかく、いっぺん最後まで読んでみてよ」と美緒は促した。「詳しい話はそれから」
それを邪魔していたのはそっちなんだけど、と顕は思ったが、思うだけにとどめて「わかりました」と応えると、もういちどカップに口をつけて、そのあとようやく腰を据え、じっくりテキストに目を通しはじめた。
それからしばらくのあいだ、二人も向かいの席で静かにしていた。が、ものの一分とたたないうちに紫子が「あれ?」と声をあげ、美緒の顔を見た。「あのプリント、私が渡したやつと別ですか? たしか、四つ折りにしてた気が――」
紫子の観察力に内心どきりとしながら、美緒は「よく気づいたね」と苦笑した。「紫子にもらったあと、家でコーヒーこぼしちゃってさ。人に見せるのに――しかも、この店に持ってくるってときに、インスタントのやっすい色と香りが染みついたやつはさすがに……ね?」
決して広くない自室でギターケースから愛用のギターを取りだし、いつものようにポリッシュを染みこませたクロスでボディを拭こうとしたとき、テーブルに置いていた保温マグにネックを引っかけて倒してしまったあとの顛末を美緒は身ぶりを交え、最前までの配慮などどこへやら臨場感たっぷりに再現しはじめた。が、そのころにはすでに、顕の意識は年代不明のトラブルを取材する見ず知らずの高校生の――あるいは音声からテキストへ書きおこした生徒の――視点と一つになっていた。
彼にとってやや意外だったのは、テキストのなかで取材に応じている人物が、トラブルの当事者でも目撃者でもなく、被害を受けたとされる女子生徒の父親らしいという点だった。
〈ヤー、はい、ありがとうございます。……いえいえ、とんでもない。こっちこそ、最初にお礼を言わせてほしいです。アリサ――娘のことでわざわざ、こんなところまで来てもらって、とても嬉しいと思います。ウン? 今ですか? 残念、まだ母親のところです。少し時間がたったから、だいぶ落ちついた感じと聞いてます。だけど……ウーン……まだ絵のことになると……。
アー、そうですね。すぐ始めても? じゃあ、まず……どうしますか。父親の私から見たアリサのことからでも?
彼女の絵を一度でも見てもらえば、そのままと思います。筆のタッチと一緒で、昔から彼女、とてもデリケートな――センシティブな子です。こっちだと、あの背のおかげもあってほら、歩いてるだけできっと目立ってしまうでしょ。私たち親の都合で、傷つきやすいあの子に辛い気持ちをたくさんさせてしまったんだと思います。そのことを彼女に謝りたい気持ちで今、ここがいっぱいです。
そう、小さいときからとにかく、絵を描くのが好きな子だったですね。本当に間違いなく、絵に愛されていた。クレヨンとスケッチブックだけあれば、いつまでも絵を描いてました。目に見えたもの全部、絵にしないと気がすまないという感じで……だからこそ今の彼女を見るの、とても辛いです。
一つ、言わせてください。私たち誰も、今度のこと長引かせたいと思ってません。十七か十八――彼女たちの年齢だったら、よくあること……たしかに少し、やりすぎたんだと思います。だけど誰だって同じような、はっと思いついて、あっ、なんかイタズラしたいぞって気持ちになること、あると思います。ただ……できたら、ずっと同じクラブでアリサのこと見てたなら、それに耐えられない子だとわかってほしかった。それが残念です。
彼女を弱い子だと、私も、彼女の母親も思ってないです。ただ少し無防備というのかな、まだ心の守り方を知らないだけ――無防備でいられる強さ、人を疑わない強さがある子だというふうに思います。傷つくことを受けいれることをできる子です。
そういうセンシティビティこそ、あの子の持って生まれたギフトと思います。だから去年、あの『春の日』も県の代表作品に選ばれたんじゃないかな……『春の日』を観たことが? アー、残念。この国の春、私も大好きです。その春の、のんびりとした暖かさと明るさ、小さな命のブレスをですね、センシティブな水彩の色使いとタッチで――アー、ごめんなさい。今日の話と関係なかったですね。
いえ、アリサは先生や――クラブの顧問ですね――あと、クラブの子たちに訊いてもらえばわかると思います。代表に選ばれたからといって彼女、鼻を高くしたり、周りに自慢するような子じゃないです。このときも本人より、親の私たちのほうがいっぱい喜びました。それでも……たぶん、ジェラシーをこう、メラメラメラ――っていうふうに感じる子が、同じクラブのなかにいたんじゃないかな。悲しいことだけど……仕方がないです。
このあいだ同じふうに家に来て、会ったとき、アリサは言ってました。「間違いなく彼女たち、許されないことをしたんだけど、みんな未来があるし、あまり大げさなことにしたくない」と。それまで同じ気持ちだったはずの私たち、そのときさすがに怒りました。少しね。だってアリサより――傷ついた私たちの娘より、その子たちのほうが優先みたいなニュアンスに聞こえたら、あなたほっとけますか。
ごめんなさい。そうですね、少し落ちつきましょう……リラックス、リラックス……ウン? そう、彼女たち、たしか小田という先輩の女の子、それに蟹江という先輩の女の子のことですね――すいません、彼女たちを呼び捨てにすること、どうか許してほしいです。まだ今、そこまでの余裕の気持ちになれないです。それに思いだしてみても、あのイタズラのことを聞くまで、アリサから彼女たちの名前を聞いたこと、なかったんじゃないかなと思います。どのくらいのつきあいだったのか……今もアリサ、話そうとしないからわからないです。
最初におかしいと気づいたとき、アリサ、クラブ活動をやらずに、学校を終わるとすぐ帰ってくるようになりました。今年もコンテスト近かったですから、少し前からあの『枯れた葉』の制作に集中していたはずでした。ときどき写真を撮って、私たちにも途中のできあがりを見せてくれてました。でもあのときだけ、もう完成したのかなと訊いても、どうしてか答えてくれない。見るからに元気がないのも心配と思いました。
アリサは先生に話してくれたの、庄司さんという女の子でした(?)。そうじゃなかったら今も私たち、何も知らなかったかもしれない。そう思うととても恐ろしいです。
庄司さんも最初、そのことを忘れていたんだらしいですね。彼女もクラブの一年先輩だけど、それまであまりつきあいがなくて、用があるときだけ話すし、友達じゃないと聞きました。
もしあのイタズラがなくて、『枯れた葉』を最後まで完成させていたら……とても素晴らしい作品になったと思います。今だって私、あの絵をとても魅力的と思います。紅葉から日にちをたって、今にも落ちてしまいそうに垂れさがった一枚のカエデの葉と、これから厳しい冬に向かう細い枝――その二つを、まるでお互いをねぎらうような構図で、とってもセンチメンタルに、厳しさと優しさの眼差しで捉えた作品でした。冬の前の冷たい空気の感じと、くすんだ赤とオレンジのまだらな葉が光に透けて、葉脈だけがまだ赤々と燃えているコントラストがですね、まるで命あるすべてのものへの賛歌のようなのです。親バカと笑ってくれていいです。でも、どこまでも穏やかな『春の日』より、はるかに美しくて、愛らしいとあなたも言うでしょう。観たら、きっとね。
正々堂々、真正面から勝負したら、音をあげるのは明らかは確か。だから彼女たち、ずるい方法を使いました。芸術と向きあう全員を――つまり彼女たち自身の、それまでの努力まで全部を冒涜する方法を……。
私、絵についてそんなに詳しくないです。でも、もし油絵だったら、アリサのパレットにこっそり、同じように血を混ぜたとしても、誰も気づかなかったかもしれない。でも彼女の得意の絵、水彩画でした。アリサだったら、次の日に見たとき、きっと乾いた色のほんの少しのちがいに気づいたんじゃないかな。もしかしたら、塗る前から、いつもと混ざり方のちがいに不思議を感じてたかもしれない。自分の手で作品を台無しにさせられた彼女の気持ち、考えると本当に辛いです。
優しい子だから、アリサ、一人で抱えて誰にもそのこと話さなかった。ただ、様子おかしいと気づいたの、私たちだけじゃありませんでした。悪いことをして、神様に見逃してもらえるなんて思わないほうがいいです。
言ったとおり、アリサも無防備なところあります。だけど、クラブの時間に作業して、パレットをそのままにしてちょっと部屋を出るくらい、きっと誰でもやります。聞いたらその日、美術室を出てすぐの廊下でたまたま庄司さんとすれちがって、一言とか二言、言葉を交わしたんだそうですね。ずっと絵のこと考えていて、どんなことを言われたか覚えてないようですが。
庄司さんの話だと、そのとき「いいの?」とアリサに確認したらしいです。でもアリサから返ってきたの、興味なさそうな生返事だった。だから少しムッとしただけで、会話、それで終わってしまいました。絵に集中しているときのアリサを思ったら、とてもそのシーン簡単に想像できるし、お互いあまり印象に残らなかったとしても当然と思います。
でもしばらくたってから、もしかしたらと思えてきたんだそうです。そのときの庄司さん、美術室の閉まったスライディングドアの小さな窓から、部屋の中を見てました。そのことアリサもわかってたけど、あのとおり慎重さが仇になって、彼女が何を見てるかまで確かめられなかった。だけど、あとになって庄司さんがあの日、アリサがいない隙に穏やかに描かれた葉の前でコソコソしていたことを思いだしたのです。
そこでアリサは先生に相談して、本人に確かめてもらったら、アリサのパレットに血を混ぜたことを白状したんだそうですね。それより前からアリサにそういう噂、ときどき流れていたらしいです。絵の完成のためなら、自分の血を使って色を作るクレイジーな子だと。アリサの絵、長く観ると祟られる呪いの絵だそうです。とんでもない話です。一番たくさん観てきた私たち、こんなにピンピンしてるのにね。
え、私……ですか? そんな怖い顔を? 本当に? すみません。でもたぶん、あなた正しいです。きっと私、今も心のどこかで今回のことを許せてない……。
心が狭い人間と思いますか。でも私のなかの、このおどろおどろしい先輩への気持ち、とてもまだなかったことにできません。だけど……そうですね。あなたが私の目をまっすぐ見て、そう言うんだったら――がんばって忘れると約束します。前に進むのにきっかけって大事です。今日をそれにしなければいけないと私、思ってます。
今、一番アリサを気にして連絡をくれるの、庄司さんです。だから私たち、彼女にとても感謝してます。悲しみや心の傷を嘘にできなくても、よくないことのあとにもこういう小さな実りがあること、忘れたくないです。
私が知ってる話、これで全部と思います。約束を守って、アリサのところに直接聞きにいかないでもらえること、本当にお願いします。
次にアリサが絵を描くとき、きっと今までよりもっと素敵な作品を生んでくれる。私たちそう信じてます。強く、強く――はい、そう言ってもらえると私たちも、とても嬉しいです。
もうすぐ暗くなります。どうぞ帰り、お気をつけてください。いえ、こちらこそ、どうもありがとうございました。〉
「――なるほど」
最後まで目を通したあと、二人に気づかれないようしばらく考えをめぐらせる時間を置いてから、顕は口を開いた。
「ちょっと……面白いですね。まだ少し、感想がうまくまとまらない感じですけど」
「でしょ」と、美緒は手応えを感じて身を乗りだした。「わかる」
「何があったのか、核心部分はまあ、はっきりしてますよね。アリサって子の絵の才能か態度を疎んで、彼女のパレットに血を混ぜる悪質なイタズラがあった――そのせいで彼女は絵を描くのをやめてしまっていて、父親はそんな娘の様子に心を痛めている、と。だけど、それ以外の部分で何個か引っかかるというか、気になるところがありますよね……書きおこしの精度の問題、なのかな……」
手元の用紙を見つめたまま、半ば独り言のように要点を再確認していく顕の思考を妨げないように、美緒と紫子は口を挟まずにいた。顕はそんな二人の配慮にも、美緒の思惑にまんまと乗せられて集中力を発揮しだしたことに彼女たちがこっそり目配せしあって、声もなく笑っていることにも気づかなかった。
「これ、書きこんじゃっても?」
ようやく顔を上げてテキストを指さし、顕がお伺いを立てると、美緒は「どうぞどうぞ」と快諾した。「あげるから自由に使っちゃっていいよ。そのかわり、責任持ってちゃんと持って帰ること」
ペン貸そうか、という美緒の厚意を辞退し、自身のかばんから青の水性ボールペンを取りだすと、顕は再び手元に意識を戻して気になるポイントにチェックを入れていった。
テキストの体裁自体にも気になるところはあった。取材時の音声データをそのまま書きおこしたにしてはずいぶん短い気がするし、取材側の発言がすべてカットされているところを見ても、録音方法に不手際でもあったか、そうでなくても二次加工済みの要約原稿と考えるほうが自然と思える。いずれにしろ高校生の素人仕事である以上、当時の正確な事情や意図を推しはかるのは難しそうだった。
「とりあえず……このくらいですかね」
数分後、顕は一段落つけてペンを置いた。その声には幾ばくかの手応えとともに、保留印を押したようないぶかしみがくすぶっていた。
「何かわかった?」
「えっ、そうなんですか?」
純粋な興味から訊く美緒と、見くびりからくる驚きを隠さない紫子に、顕は「わかったっていうか……推測できることならいくつか」と慎重な姿勢をくずさず言った。「ていうか、たぶん二人ももう、わかってる程度のことばっかになると思いますけど」
「そうなんですか?」
くるっと美緒のほうへ向きなおって、期待の眼差しを浴びせる紫子を美緒は煙たそうに手で追いはらった。
「わざわざ来てもらって、せっかく読んでくれたんだから」と諭して、そのあと顕のほうを見て促した。「とにかく、まずはアキラ君の考えを聞かせてよ」
「ここ、中熊さんのおごり――ってことでいいですよね?」カップの取っ手を軽く持ちあげて確認したあと、顕はテーブルの中央に受けとったテキストを広げた。「まず――中熊さんも、紫子ちゃんも気づいてると思いますけど、大前提としてこれ、取材を受けてるこの父親ですけど、たぶん外国の人ですよね」
「まあ、だろうね」と美緒はすんなりうなずいた。「厳密に言うなら、日本語が母語じゃない環境で育った人、かな。それなりに流暢にしゃべれてるっぽいし、滞在歴はそこそこ長そうだけど」
「結婚相手が日本人で、子どもが生まれたあと日本に移住とかってパターンじゃないですか? 親の都合でアリサに苦労させたって、たしかどっかで言ってたような」
紫子の推測は確たる根拠があるわけでもなかったが、否定できる材料もまたなかった。美緒の言う流暢さについては、編集の手がどのくらい加わっているかにもよってくるとはいえ、ひとまずそこは問題ではないだろう、と顕は考えていた。
「このテキストが妙な感じするのって、たぶん、悪さしてるのはその、日本語ネイティブじゃない人ってとこが半分くらいあると思います」と彼は端的に感触を告げた。「あとの半分は、やっぱり、音声を書きおこしたテキストってところがミソなのかなと」
逆さまのテキストを覗きこみつつ、美緒はふんふん、とうなずいた。「それで?」
「最初に読んでみて、一番違和感が残るのってやっぱり、イタズラの犯人が結局誰だったのかってところですよね。普通に読んでいくと小田と蟹江って先輩の名前が出てきて、当然この二人がやったんだろうと思うんですけど……後半になると、庄司さんって別の先輩がアリサのいない隙にコソコソしてたとか、先生が確かめたら白状したとか出てくる」
「そうなんだよ。しかもそのあとまた、庄司さんに感謝してる――とか出てくるし」
「最初はいい先輩な感じでお父さんも話してましたもんね」
飲みこみよく素直な反応を見せる二人に顕は知らず知らず気をよくし、「あくまでここに書かれてることだけから読みとるって前提でいきますね」と、それまでより自信を深めた声音で続けた。「それで、まず気になったのがここです」
「どれ――〈そこでアリサは先生に相談して、本人に確かめてもらったら、アリサのパレットに血を混ぜたことを白状したんだそうですね。〉……これがどう気になったの?」
指さした一文を逆さまの位置から器用に音読する美緒に、顕はさらに段落を遡って、傍線を引いておいた別の一文を指し示した。「少し前のここ、見てください。〈優しい子だから、アリサ、一人で抱えて誰にもそのこと話さなかった。〉――ここでは、アリサは誰にも話さなかったと言ってるんです」
「あー……たしかにそうだね」
「この時点では誰にもってことなんじゃ?」紫子が指摘した。「庄司さんのコソコソとかを思いだしたのはそのあとっぽいですし」
「そうとも読めるけど――アリサの様子がおかしいって気づいたのは、両親だけじゃなかったとも、このすぐあとに言ってるんだよね。それってやっぱり庄司さんのことだろうし、それにほら、もっと前のここにも、やっぱり庄司さんが先生に話したと書いてある」
こちらも予めボールペンで印をつけておいた〈アリサは先生に話してくれたの、庄司さんという女の子でした(?)。〉と書かれた一文を顕は提示した。
「この文はたしかに……よくわからないですよね」紫子は二方向からの視線をきっちりと意識した、やや芝居がかった難しい顔でつぶやいた。「最後のこのカッコハテナも、これを書きおこした新聞部の子も意味がわかってないってことですよね」
「〈アリサは〉じゃなくて、もしかして〈アリサのこと〉みたいな意味で言いたかったんじゃない? 私らだってその場で考えながらしゃべってるとさ、途中で文の組み立てが変わっちゃって、それでもその場ではなんとなーく伝わっちゃうんだけど、文字にしたらきっとメチャクチャだろうなってこと、あるじゃん。ましてや外人さんなわけだし」
美緒の推測ももっともではあった。が、顕の考えていることはちがった。
「その〈アリサは〉がポイントだと思うんです」と、彼は力強く言った。「今見てもらった三ヵ所のうち、二つの文に〈アリサは〉っていう言葉が出てきてますけど……実はその二回を含めても、〈アリサは〉って文字列は全体で四回しか出てこないんです。しかもそのうち三回は、すぐ下に〈先生〉がくっついてる」
「そうなの?」
「数えたんですか?」
顕は二人の声にまとめて一度だけうなずいた。「これだけアリサの名前は出てきてるのに、〈アリサは〉の形はその四回だけ――もっと言うとですね、この父親の話し方の癖としか言いようがないですけど、気をつけて読んでみると助詞の〈は〉自体、ほとんど使ってないんですよね」
「はへえ。よく気づくね、いっぺん読んだだけでそんなとこまで」感心した様子で美緒は顕の顔を見た。「やっぱり、私の見込んだとおりだったんじゃない?」
「それはどうかわかりませんけど」と顕はそっけなく受けながした。「問題はそれが何を意味するのか、です」
「何を意味するんですか?」
「〈アリサ〉と〈先生〉のあいだに挟まってる〈は〉は、助詞の〈は〉じゃないんじゃないかってこと」と顕はそれまでより優しい声音で、紫子に向かって説明した。「で、助詞じゃないってことは、つまりこの〈は〉は、音のとおり〈わ〉ってことになる――わ行の〈わ〉ね」
「〈わ〉?」用紙の余白に顕がボールペンで〈わ〉と書きこむうちにも、紫子は彼の考えを汲みとって「あっ」と声をあげた。「アリサワ先生か!」
「そういうこと」と、いくらか気分が良くなっていることを自覚しつつ顕はうなずいた。「父親の言う〈アリサは〉は先生の名前だった――そう仮定すると、だいぶ読みやすくなるというか、全体的にも筋が通ってくるよね」
「〈アリサワ先生に話してくれたの、庄司さんという女の子でした〉……〈そこでアリサワ先生に相談して、本人に確かめてもらったら、アリサのパレットに血を混ぜたことを白状したんだそうですね〉――たしかに、このほうが断然意味がわかりやすいですね。これならカッコハテナも必要ないです」
「普通なら聞きまちがったりしないんだろうけど、何せ娘がアリサだし、父親のイントネーションも相当だったんじゃないかな」補足したあと、顕は残り二つの〈アリサは〉の箇所もペン先で向かいの二人に指し示した。「ここと、それからこっちも、アリサワ先生と読みかえると、それまでより腑に落ちます。こっちの一回だけ、顧問の発言への怒りがこもってるってことなのか、呼び捨てになってますけど」
〈アリサは先生や――クラブの顧問ですね――あと、クラブの子たちに訊いてもらえばわかると思います。〉の箇所と、〈アリサは言ってました。「間違いなく彼女たち、許されないことをしたんだけど、みんな未来があるし、あまり大げさなことにしたくない」と。〉の箇所をやや時間をかけて、行きつ戻りつしながら確認したあと、美緒と紫子は呼吸を合わせたかのように同時に顔を上げた。
「そうなるとやっぱり、先生にイタズラのことを相談したのは庄司さん、ということになるわけね?」と美緒が確認した。「イタズラを白状したのは小田と蟹江の二人――でも、ここには庄司さんがコソコソしてたって」
〈だけど、あとになって庄司さんがあの日、アリサがいない隙に穏やかに描かれた葉の前でコソコソしていたことを思いだしたのです。〉の一文を、ギター奏者らしい固い指先で示す美緒の顔は疑問をぶつけているというより、基礎課題を順調にクリアした塾生に応用問題を提示する講師のようだった。
「その前に――ていうか、そこを解決するためにも、まずこっちから片づけていいですか」
美緒の左手で隠れている直前の一文を、やや強引に割りこむようにして顕が指さすと、二人の指が触れたとたん、美緒はぱっと手を引っこめた。「ああ、ごめん。続けて」と、彼女は胸の前で左手をかばいつつ、ばつが悪そうに苦笑した。「昨日、練習してたら指の皮はがれちゃったんだよね」
「えっ、大丈夫なんですか?」
「いいから」心配する紫子をぞんざいに退けて、二人と視線を合わせずにすむように、美緒は顕が指さす先を覗きこんだ。「で、どこって?――〈そのことアリサもわかってたけど、あのとおり慎重さが仇になって、彼女が何を見てるかまで確かめられなかった。〉――ここがどうしたの?」
「イタズラがあった日の庄司さんとアリサのやりとりですけど、まとめると、二人は美術室前の廊下ですれちがって、そのとき庄司さんは閉まったドアの小窓から美術室の中を見て、『いいの?』ってアリサに確認してるんですよね。でもアリサはこのとき、彼女が何を見てそう訊いてるのか確かめられなかった。だから〈興味なさそうな生返事〉をして、それで終わってしまった」
「うん。だから、それがどう――」
「アリサは絵に集中しているとそうなるって、この父親言ってますよね。そこ以外にも、娘には無防備なところがあると何度か出てきます。だとしたら、この〈あのとおり慎重さが仇になって〉という言い方、ちょっと妙な気がしませんか?」
「たしかに」先に反応したのは紫子だった。「どのとおりだよって感じですね」
「そう。で、どのとおりなのか、もういっぺん頭から探してみたんだけど」顕はテキストの一枚目を正面に持ってくると、二人から読みやすいように上下をひっくりかえして冒頭近くの一文をペン先で示した。「これじゃないかなって」
〈こっちだと、あの背のおかげもあってほら、歩いてるだけできっと目立ってしまうでしょ。〉
「歩いてるだけで目立つって、たぶんアリサは周りの子より、頭一つくらいは背が高かったんじゃないかな」と、顕は途中から美緒へも目を向けつつ推測した。「まあ低くても目立つっちゃ目立つでしょうけど……どっちにしてもですね、その〈背のおかげ〉でこのときも、庄司さんとはドアの小窓から見える美術室の中の景色がちがった――そう考えるといいんじゃないかと」
「ははあ……アリサの性格が慎重だからじゃなくて、庄司さんとの身長差が仇になって、何を見てるのか確かめられなかったってわけね」美緒は覗きこんだ姿勢のまま、納得を表すようにわずかにあごを反らした。「それはまあわかったとして、それでもまだ、そのあとの〈庄司さんがあの日、アリサがいない隙に――〉のとこは解決しないんじゃない?」
「そうでもないです」と余裕をにじませるゆったりとした声音で言って、顕は問題の一文を含む段落を丸ごとペンで囲ってみせた。「この段落の辺りって、ところどころ主語が曖昧じゃないですか。一行目の〈でもしばらくたってから、もしかしたらと思えてきた〉のはアリサなのか、それとも庄司さんなのか。次の段落が例の〈そこでアリサは先生に相談して――〉で始まるもんだから、余計にややこしかったんですけど……こっちはもう解決してますよね」
「アリサワ先生に相談したのは庄司さん、でしたね」紫子が律儀におさらいした。「ってことは――」しかしそれ以上考えるつもりはないらしく、あっさり手放した。「どういうことですか?」
「〈もしかしたらと思えてきた〉から〈先生に相談し〉た――話の流れを汲むと、そうなるよね」美緒が思案する面持ちでつぶやいた。「つまり主語はどっちも庄司さん……ってことは、〈庄司さんがあの日、アリサがいない隙に――〉のところも?」
「そういう前提で考えてみるべきだと思います」と顕はうなずいた。「そうしたら、あとはさっきの〈慎重さ〉と同じ間違いを探せば終わりです」
「同じ間違い?」
「はい」と顕はくりかえしうなずいたが、ここへきて美緒による誘導が彼の考える結論へ向かってあまりに心地よく作用することに違和感を覚えて慎重さを取り戻した。保留していたいぶかしみが再び首をもたげるのを感じた。「――中熊さん、さすがにもうわかって言ってますよね?」
顕の指摘に、美緒は「何?」とけげんな声で応じた。「なんでそうなるの」
「ちがうならいいんですけど」と彼は断った。「ただ、わかってるんだったら、紫子ちゃんだって先輩から説明してもらえたほうがいいんじゃないかって思って」
顕からの思わぬ援護に、紫子もそれはもちろんそう、と言わんばかりの期待の眼差しを美緒に向けうんうんと力強くうなずいた。が、仮に顕の推測どおりだったとしても美緒が素直に認めるとは思えず、現実に彼女は後輩からの決めつけに困って眉をひそめるポーズを決めこむばかりだった。ほんの束の間、顕と紫子は諦めを共有する視線を交わし、しぶしぶテキストへと目を戻した。
「――〈だけど、あとになって庄司さんがあの日、アリサがいない隙に穏やかに描かれた葉の前でコソコソしていたことを思いだしたのです。〉」と、減退する気力をふりしぼって顕は読みあげた。「この一文、主語の問題を横に置いといたとしても、ほかにも明らかにおかしいとこありますよね」
「どこ?」
「あくまでそのスタンスなんですね?」しらじらしくテキストを覗きこむ美緒にせめてもの嫌みを浴びせて、顕はペン先で該当箇所をなぞった。「もちろん、この〈穏やかに描かれた葉の前でコソコソ――〉のところですよ」
「たしかに……なんか、持ってまわったような言い方ではあるよね。要はアリサが描いてた絵の前で、ってことでしょ?」
「父親によると、その絵のタイトルは『枯れた葉』でしたよね」あえて断片的な情報を小出しにして、美緒の隣で全く同じポーズで覗きこんでいる紫子へと目を移す。「もうわからない?」
「へ? あ、私ですか?」
回答を求められるとは全く想定していなかった紫子は急いで首を振った。自分で答えを導くつもりはないという点では、紫子も美緒とスタンスは同じだった。
「私は全然」紫子は他力本願丸出しの笑顔を投げかけた。「自分でわかるんだったら、こうやってドロシー先輩に頼ったりしてないじゃないですか」
その先輩がつい先ほど顕に適用したロジックからいけば、作り笑顔や愛想を状況に応じてあざとく使いこなす紫子の身のこなしも彼女のスペックの高さを示唆しているのでは、と彼は思ったが、あえて指摘はしなかった。容姿を抜きにしても、美緒よりも数段わかりやすいという点ですでに彼はある種の共感と好感を紫子に抱いていた。
「小田や蟹江が、『枯れた葉』の前でコソコソしてたんですよ」と、顕は半ばやっつけ気分で二人に結論を伝えた。「そのことを〈あとになって庄司さんが〉〈思いだした〉んです。庄司さんが絵の前でコソコソしてたのを、アリサが思いだしたわけじゃないんです」
「待って何、どういうこと? そんないっぺんにわーって言われても――」
顕が〈穏やかに描〉を二重線で消し、〈小田や蟹江が〉と書きこむうちにも、二人から「おおっ」という示しあわせたかのような感嘆の声があがった。
「〈あとになって庄司さんがあの日、アリサがいない隙に小田や蟹江が『枯れた葉』の前でコソコソしていたことを思いだしたのです〉――完璧ですね!」人さし指でなぞりつつ、確かめていくうちに紫子の声は上ずっていった。「え、すっご、やばくないですか?」
左の袖をつかんでぐいぐい顔を近づけてくる紫子を「わかったから落ちつけ」とたしなめて、しかしそうする美緒も顔がほころぶのを自覚していた。「けどまあ、ほんとお見事だわ、まじめな話。ここまであっさり答えが出るとはね、まさか思ってなかったもん」
「アリサの絵、テキストの中で『春の日』と『枯れた葉』が出てきますけど、〈どこまでも穏やか〉に描かれてるのは『春の日』のほうなんですよね。それでここも、なんか違和感があるなーって、思っただけですよ」
「へー、うん? あー、そうでしたっけ?」興奮の余韻は残しつつも、やはり他力本願丸出しの声で言って、紫子はテーブルの用紙に手を伸ばした。「見ていいですか?」ペンを持つ手を顕が浮かせると、用紙を手元に引きよせてすばやく向きをそろえ、横組のテキストに指先と目をすべらせる。「〈どこまでも穏やかな『春の日』より、はるかに美しくて〉――ほんとだ。たしかに書いてますね。なるほど……はあ、なるほど」
「じゃあ、一応これで全部、解決ってことでOK?」一人でしきりにうなずいている紫子を尻目に、美緒は顕に確認した。「ドアの小窓から美術室の中を見たとき、小田と蟹江がアリサの絵の前でコソコソしてたことを、庄司さんがあとで思いだした――ほかにはまだ、なんか気になるとこある?」
わずかに逡巡したあと、顕は「ぼくのほうは特に」と答えた。今や一刻も早くこの先輩からの目的不明の依頼を片づけてしまいたかった。
「紫子はどう? 何かアキラ君に訊いときたいことある?」
「……アキラさんに?」まだテキストの上を泳いでいた目を上げて、紫子は心ここにあらずといった面持ちで淡泊に首を振った。「私はべつに」
「元はといえばあんたが持ちかけた相談でしょうが」と美緒は呆れぎみに諭した。「それならそれで、なんか言うことあるでしょ」
「え? あ……そっか。そうでした」紫子はテキストを手放すと、最初におしぼりを運んできたときと同じよそ行きの笑みを顕へ向けた。「わざわざ先輩のために今日は、ありがとうございました。最初は正直、えっ、誰? って思いましたけど、結果とっても助かっちゃいました。色々と」
「紫子ちゃんが喜んでくれたなら、来たかいあったかな。コーヒーもおいしかったし」顕は顕でひるむことなく笑顔で応じ、好機と捉えて「ここには決まった曜日で入ってるの?」と滑らかに言葉を継いだ。「土日は?」
「んーと、色々ですよ」紫子は作り笑顔を微塵も曇らせることなく返した。「叔父さんたちの都合次第だし、曜日も特に決まってないんです」
「決まってても教えるわけないじゃんね」美緒が横槍を入れたが、顕にとってはそれも想定のうちだった。「やめなよ、みっともない。紫子目当ての常連おじさんじゃあるまいし」
「セッション日とか、予定が合いそうな日あったらいつでも見にきたらって、誘おうと思っただけですよ」と顕は用意しておいた口実を展開した。「〈常時見学歓迎〉って、サークル紹介にもいつも載せてるじゃないですか」
「あのね、そんなのは在学生向けの勧誘文句に決まってるでしょ。部外者の、しかも高校生が自由に出入りしていいって話じゃないの」
「そうでしたか? 在学生限定なんて、大学のホームページのサークル紹介にも、ツイッターのプロフィールにも、そんな断り入れてないですよね」
顕の言うとおり、実際にはOBなんかはかなり気ままに出入りしているし、顧問からはジャズ研のないほかの大学の学生が実質的なメンバーとして活動に参加していた時期もあると美緒も聞いていた。
「まあ、たとえば受験生として、志望校を見学に来ました――って体なら、問題ないかもだけど」と、それでもあえて限定的に美緒は認めた。「仮にそんなで見学に来たって、紫子も肩身狭い思いするだけじゃんね」
「そこはぼくとか、頼れるドロシー先輩がみんなに紹介するなり、フォローしてあげればよくないです? それこそジャズのウェルカム精神で」
「紫子はどうなの」一向に辞退の意向を表さない紫子に目を向け、美緒は問いただした。「来たいの?」
志望校の見学という体なら、という部分にこめた意味を念押しする美緒の鋭い眼差しには気づきつつ、紫子は挑むような心持ちで「すごい楽しそう」と、一旦は前向きな声で応じてみせた。「――なんですけど、やっぱり遠慮しておきます。先輩や、みなさんの活動の邪魔したくないですから」
「全然、そんなの気にすることないのに」顕は聞き専の気楽さで無責任に保証し、しかしそれ以上は深追いせずに「でも、そっか」と本人の判断を受けいれた。「残念」
「すいません」とにこやかに謝って、そのあと膝に置いていた盆を手に紫子は腰を上げた。
いいかげん仕事しないと怒られちゃうので、と二人に言いのこし、紫子はようやく外国製のリカーボトルを並べたカウンターの奥へと戻っていった。
「中熊さんが変な圧かけるから」
紫子の後ろ姿を見送ったあと、顕は視線を美緒へとすべらせて不満をもらし、美緒は呆れたようにうつむくことでその視線を遮断した。
「そんなに紫子のこと気にいった?」
「そうですね」と、コーヒーを口に運んでその冷たさに眉をしかめながら、顕はすんなり認めた。普段から本心を覗かれないために予防的に愛想をふりまく顕とちがって、紫子が自在に出し入れするそれは常に自身のごく近視眼的な利益のために使われることが、それゆえのわかりやすさが彼の目には清々しくさえ映ったし、同類亜種の邂逅にも似た不思議な親近感を生んでいるのだった。「かわいいですし」
テーブルに残されたテキストを拾いあげながら、美緒は「あ、そ」と、自身のカップにわずかに残るコーヒーよりも冷ややかにつぶやいた。
4
「――そうだ。もう一つ、アキラ君の考えを聞いときたかったんだよね」
各テーブルの清掃や備品の補充をして回るために紫子が再びフロアへ出てきたタイミングを見計らって、手にしたテキストから顔を上げ、美緒が言った。
「まだ何かあるんですか」
せっかくだしもういちど紫子の顔を見てから帰ろうかな、などと悠長に構えていた隙を突かれたかっこうの顕はいかにも面倒そうなため息で応じた。
顕の態度など今さら意に介するわけもなく、「この、アリサがパレットに血を混ぜられたことに気づいたあとなんだけどさ」と美緒はかまわずに続けた。「彼女、なんでそのことを誰にも言わなかったんだと思う?」
「なんで――優しい子だからって、たしか父親が言ってませんでしたっけ」
「それは父親の勝手な印象で、そう決めつけてるだけでしょ。本当のアリサの気持ちはちがったかもしれないじゃん」
「そりゃまあ、そうですけど……じゃあ、中熊さんはなんだったと思うんです?」
おそらくそうして欲しいのだろうと踏んで水を向けると、美緒からは「現地調達だよ」という自信に満ちた答えが返ってきた。「刑務所とか、軍隊だけじゃなくて、女子校もその手のエピソードなら各世代、噂レベルから当事者公認まで事欠かない空間だからね」
「えっと……よくわからないんですけど。つまり?」
「だから、小田か蟹江と、アリサとのあいだにさ、一方通行か双方向だったかは知らないけど、もし以前にそういう感情の行き来があったんだとしたら――そのこじれがこんな悪質なイタズラにつながったんだとしたら、アリサはきっと親にはもちろん、誰にも相談できなかっただろうなって話」
女子校の実状については知る術のない顕は「はい、先生」と、テーブルに載せた手のひらだけで小さく挙手をした。「少なくとも自分が悪いわけじゃないんだったら、堂々としてればいいんじゃ?」
「わかってないね。わかってないよ、アキラ君」美緒はいかにも訳知りという渋面になって肩をすくめた。「たとえアリサに一ミリもその気がなくて、袖にしたほうだったとしてもね、学校っていう閉じた空間で、そういう噂話の中心に据えられて平然としてられる神経の子じゃなさそうじゃん。イタズラが発覚したあとは絵描くのも、学校行くのもやめちゃってるみたいだし」
「タイプ的にはまあ、そうかもしれないですけど。でもそれ、あくまで中熊さんの想像なんですよね?」
「何が言いたいかっていうとね」と、美緒は一方的に結論へと進んだ。「要するに、やっぱり現地調達なんてろくなことにならないよね、ってこと」
その声は顕にはもちろん、アンリ・マティスの切り絵のそばにあるテーブルでアクリル製のホルダーに爪楊枝を補充していた紫子の耳にもはっきりと届いた。
「なんか……ヤな言い方」それまでは作業を優先して二人の会話を聞きながしていたが、耐えかねて手を止めると紫子はふりかえった。「そういう一括りにして乱暴に決めつける感じ、私は嫌いです」
「客の話にいちいち首を突っこんでこないの」一応はたしなめたあと、美緒は少しも動じることなく「現地調達のこと?」と紫子にあらためた。「私はかなり的確な表現だと思うけど。でもまあ、出典はアキラ君だから、文句があるなら窓口はこっち」
「ちょっと乱暴すぎると思います」
美緒に促されるまま顕へと矛先を向ける紫子に「もちろん、全部が全部ってわけじゃないよ」と、強引に首をひねった不自然な体勢になりながら、顕は自分でもよくわからない弁解を口走った。「なかにはほら、本物だってあると思うし……いや、本物ってなんだってなったら、なんだろうね。ちょっとうまく言えないんだけど」
「きちんと説明もできないそういう曖昧な感覚とか、ごく個人的な価値観にそうやって無神経に強い言葉を当てはめるの、無責任だと思います」となおも収まらずに紫子は言い募った。「アキラさんは軽い気持ちで言ってるのかもですけど、茶化されるほうの身にも――」
「ごめんなさい」
早々に白旗を掲げ、顕は素直に謝った。紫子と対立するつもりもメリットもなかった。
「まあまあ――紫子もね、ちょっと落ちつきなって」いけしゃあしゃあとなだめ役に回って、美緒が場を取りもった。「アキラ君もよくないけどさ、紫子の頭ん中もたぶん、女子校のことだけ想定して言ってるでしょ。べつにアキラ君、そういう意味でその言葉使ってないからね。あくまで環境ごとに流されて場当たり的に恋愛スイッチが入っちゃってそのことになんの疑問も抱かない人たちをついつい冷めた目で見てしまうオレ、的なやつだから」
「いや、うん……なんだろ。間違ってないですけど言い方……」
「つまり、場当たり的に入ったスイッチには一つも『本物』はないって、やっぱり決めつけてるってことですか?」
美緒の助け船に乗ったものか迷って哀れを誘う風情の顕に、紫子はいっそうむっとして追及の手を伸ばした。胸にくすぶる不満の何割かは本来、美緒に向けるべきものだった。それをわかっていて、ぶつけやすい的に甘えていることも紫子は自覚していた。
「いや、だからね、そんなことは一言も――」
「いやあ、そりゃあそうでしょ」
弁解を試みる顕の声に、断定する美緒の声がぴたりと追走した。紫子の言葉が顕を反射板にして、自身へも向けられていることに美緒は気づいていた。
「そりゃそうでしょ」と、顕の戸惑う目線を平然と受けとめて美緒はくりかえした。「私もそこは、完全にアキラ君に同意」
「いやいやいや」顕は慌てて首を振った。「勝手に一緒にしないでくださいよ」
「なんでよ? そこアキラ君が妥協しちゃだめでしょ」美緒はやや過剰なまでに目をむいて顕に迫った。「中、高と私、そこそこもてたって話、さっきしたよね。つまりそういう、恋愛ごっこに舞いあがっちゃう子たちをね、私は身をもって、見て知ってるわけ。手が届く範囲で適応しちゃう子が出てくるのも、べつに悪いとは言わないし、仕方ないことだとも思うよ。でも、そういうのをいたずらに生みだすような環境っていうのは、やっぱりさ、歪なんじゃないかなって思うわけ。そのときはカップル成立してても、大抵は片っぽが卒業したりで、環境が変わると終わっちゃうらしいし」
「大抵ってことは、なかにはそうじゃないカップルもいるってことですよね?」
顕の指摘に、美緒は「まあ、そうだろうね」と認めた。「ただ、それは今問題にしてる『場当たり的な関係』じゃなかったってことでしょ」
そんなふうにすっぱりと線引きできるものだろうか、と直感的に顕はいぶかった。「それって結果論で、スイッチが入ったときは場当たり的だったってカップルだって――」
「あのさ」心外だという顔で美緒はさえぎり、眉をひそめた。「さっきから何、アキラ君はどっちの味方なの」
どっちの味方も何も、顕からすれば何事にも例外はあるでしょう、というシンプルな立ち位置を表明しているにすぎず、彼女がなぜそんなにもむきになって否定したがるのか理解できなかった。
「なかには『本物』もあると思いますよ」と、その定義はひとまずおくとして、顕はあえて断言した。「自分で言っといてなんですけど、現地調達をそんな潔癖さで全部否定してたら、行きつく先って少女漫画みたいに運命的な出会いを夢見る乙女しか残らなくないです? 中熊さんってこう見えてあれですか、本気で白馬の王子さまとか、遅刻しそうな朝に曲がり角でぶつかったのが噂の転校生で――みたいな出会いを待ってるんですか?」
「おお……おう」美緒はのどで低く唸りながら、めまいを催したように大げさに背もたれへとのけぞった。「まさか……提唱者に下からハシゴ外されるとはね」
「中熊さんが勝手に持ちだして、勝手に登りだしたんですよ」
はああ、と美緒は深いため息をもらした。そのあと、興が醒めた面持ちで「なーんか、がっかりだわ」とぼやくと、手元に目線を落とし「じゃあもう、この話はおしまい」と唐突に打ちきった。「はい。お開き」
自ら話題を振っておいて、戦況が不利と見るや一方的に無効試合を宣言するのは上級生の横暴というものではないか、と顕は思った。が、それでこの先輩の前から解放されるのなら利用しない手はないだろうという打算のほうがこのときは勝った。
「そうですか」とだけ言って、テーブルのペンをしまうと顕は腰を上げた。「じゃあ、そろそろぼくは行きますね」
「はい、また練習日ね」美緒はうつむいたまま淡泊な声で応じ、しかしそのまま顕がボックス席から出るのを視界の端で捉えると顔を上げた。「待った。忘れ物」
手にしたテキストを美緒が差しだすと、顕はあからさまな迷惑顔で応じた。「いや、べつにいりませんけど」
「だめ。ちゃんと持って帰るって、あげたとき約束したよね」
「約束っていうか……わかりました。持って帰ればいいんですね?」
コーヒー代と思えば安いものか、と納得させて顕は手を伸ばした。が、その見えすいた魂胆に思い至らない美緒ではなかった。
「私は、人からもらったものは食べ物以外、最低十年は捨てないって決めてるけど」用紙の端をつかむ指に力をこめたまま、彼女は先回りして告げた。「人として」
「十年!」あまりにばかげた年月の提示に顕は辟易し、何より用済みのテキストを押しつけられる意味が一ミリもわからなかったが、この場だけでも受けいれる態度を表明しないかぎりはテーブルごしに用紙を引っぱりあう不毛な綱引きは終わりそうになかった。「努力はし……てみないこともないです」
「まあいいでしょう」鼻を鳴らしつつうなずいて、ようやく美緒は用紙を手放した。そのあと、唐突にかしこまったと思うと「今日はありがとね」と、穏やかな口ぶりになって告げた。「初めて上っ面魔人じゃない本当のアキラ君が見れた気がして、楽しかったよ」
何か気の利いた返しの一つでも浴びせないことには帰るに帰れないぞ、という顕なりの意地が働いて、それが「ひどいなあ。なんですか上っ面魔人って」と、大学入学以降も半年のあいだ保ってきたまさにその仮面を瞬時に装着しなおしてみせるという芸当につながった。「でも、中熊さんのそういう歯に衣着せないとこが、キレッキレのギタープレーにもきっと活きてるんですよね。如実に。如の実に。実の如く」美緒が眉をひそめるのもかまわず、笑みをキープして「それじゃ」と小さく頭を下げる。「お疲れさまです」
「――もっとさ、思ってることは顔にも口にも、正直に出していいんだよ」
一切のからかう調子は消え、呆れるでも、親切心の押し売りでもなく、先輩風を吹かすでもなく、ただ指が覚えているから爪弾いたアルペジオの音色のように、なんの他意も飾り気も感じさせない声だった。思わず、顕は踏みだしかけていた足を止めた。美緒が知っているはずはなかった。それでも、その声が、美緒の思惑とはおよそ無関係に、顕にとって最も聞きたくない声を、記憶のなかの、今なお当時のままの鋭さで彼ののど元へと突きつけられている小学生の声を連れてきた。
正直なら何言ってもいいわけじゃないんだからねっ!
「聞き専だからって、いらない気をつかってるのか知らないけどさ」と、動きの止まった顕に向けて美緒は続けた。「色々コソコソ言うやつもいるんだろうけど、音楽なんて聞き手あってなんぼだし、そんな了見の狭い奏者側の言い分なんて所詮そのレベルってことで、気にしなきゃいいんだよ。プロでそんなこと言う人、聞いたことないしね」
美緒の声は顕の耳にも届いていた。が、それでも今や彼のなかでまざまざとよみがえり、仮面の内側で苦々しく反響する遠い声をかき消すまでには至らなかった。小学生間の手加減を知らない、集団に守られた優位性を盾にして冷たく放たれる攻撃的な言葉の数々。当時の顕からすると、なぜ当事者でもない彼女たちがそんなふうに怒りをぶつけてくるのか理解できず、ただただ戸惑うばかりだった。
同じクラスの女の子の「ヤじゃなかったら」という言葉を真に受けたことが、真に受けてあまり深く考えずにその申し出を承諾したことが、残り一年半の小学校生活を決定づけるとは、当時の幼い頭では想像もつかなかったし、実際のところ、そのことで自身を責める気持ちには顕は今もなれずにいた。友達への体裁も強く意識した見栄えのいい恋愛ごっこを望む彼女からの要求は日増しに膨れあがって、次第に――わりとすぐに――疎ましく感じるようになったのも無理からぬことだった、というのが彼のなかの一貫した評価だった。だからといって、一つひとつの要求に「めんどくさい」や「それぐらい一人で行けばいいじゃん」と返すのと同じような気安さで、「ヤじゃなかったらって言ったから、まあいいかって思っただけで、べつに最初から好きじゃないし」と口にしたことになんの罪もないとはさすがに思っていないが。
「もし聞き手に、曲とか、演奏の出来不出来に口出しする権利がないんだったらさ」顕が記憶の声に捕らわれているとも知らず、美緒はさらに持論を開陳した。「料理食べて、味のことあれこれ言っていいのも料理人だけってことになっちゃうじゃんね」
意識の片隅で、顕は美緒の声をかろうじて拾いつづけていた。が、自身の目線が美緒に向けられたままであることは、このとき、彼は全く意識していなかった。その目に映っていたのは、クラスの半数あまりから疎外されたまますごした寒々しい最終学年の教室だった。隙間風に吹かれたように、やがて、彼は小さく背筋を震わせた。そのことが、美緒に自分本位の手応えを与える結果になった。
「お、今落ちかけたな、ん?」低い背もたれに肘をつき、より深く覗きこむように顕の顔を見上げて、美緒はからかいの笑みを浮かべた。「そっかそっか。べつにいいんだもんね? アキラ君は現地調達肯定派なんだし」
突拍子もないその指摘を一蹴する必要性によって、皮肉にも顕の意識は現在へと引きもどされた。「何言ってんですか」と、彼は冷淡につぶやいた。「そんなわけないでしょ」
本当に、これっぽっちも、そんなわけはなかった。が、あまり躍起になって否定するのも美緒をいっそう調子づかせる結果になるとわかっていた。それに――奇しくもこのときが、暖色の電球に照らされた白い頬に憎たらしいほどの自信を貼りつけたこの先輩をもしもふりむかせられたなら、彼女の潔癖なまでの現地調達否定こそ運命論じみた現実逃避の産物にすぎなかったと証明できるのではないかという、顕自身が培ってきた品性に照らせば嗜虐的で低俗な企みに属する誘惑が芽ばえるのを初めて自覚した瞬間でもあった。
もちろん、彼はその誘惑を即座に打ち消した。傾きかけた日を浴びて白く光るすりガラスのドアへと向かいながら、やや離れたテーブルの前にいる紫子に――彼にとってわかりやすく、だからこそ好感を持てて、純粋な欲求からまずは友好的な関係を構築したいと思える一つ下の女の子に「ごちそうさま」と気安く声をかけることで、その目的は容易に達せられた。「今度また、ほかの曲も聞きにくるね」
「あ、はい。叔父さんに言っときます」と紫子は応じた。そのわかりやすさに顕は深い安堵を覚えた。
ありがとうございましたー、という平坦な声に送りだされて、ビル・エヴァンス・トリオの歴史的名演で満たされた防音空間を抜けだし、車や人々の行き交う雑踏へと自ら溶けこんでいくときには、彼はいつもと変わらない精神状態をすっかり取り戻していた。
5
「残念でしたね」
入り口のドアが閉まり、往来の喧騒から切りとられた叔父こだわりの音響空間が再び完成するのを待ってから、紫子は天井付近にぼんやり目線をやっている美緒に声をかけた。
「そんなわけない、らしいですよ」
「んー」と、美緒は気のない生返事で応じた。「なんだっけ」
「すっとぼけですか」
台拭きを握る両手にこっそり力をこめて、紫子は聞こえないよう小声でこぼした――つもりだったが、美緒は聞き逃さなかった。「なんか言った? そこのウェイトレスさん」
「――いえ。なんでも」
紫子は小さく首をすくめて、それきり近くのテーブルの補充作業に戻った。酒の提供を始める一時間前までに、カウンター席と各テーブルの補充作業を終えて上がるのが出勤した日の紫子のルーティンだった。それは雇用者としての叔父と紫子のあいだの最優先の約束事であり、紫子の両親が叔父に提示した絶対条件でもあった。
「片づけちゃっていいですか?」
あとは美緒が座るテーブルを残すのみとなって、紙ナプキンや爪楊枝といった補充品セットと台拭きをカウンターに残し、まずは顕のカップだけでも、と思って声をかけると、スマートフォンをいじる手元を見たままの美緒から「全部片づけちゃってどうぞ」と許可が下りた。
二組のカップを紫子が通路側へ引きよせるあいだも、美緒は目的もなくただ時間を潰しているふうだった。「ひょっとして、上がるの待っててくれる感じです?」と淡い期待をこめて、紫子は訊いてみた。「だったら、ちょっと早めに――」
「今、話していいなら、それでもいいけど?」と美緒は物問いたげに目線を上げて、そのままちらっとカウンターのほうを見やった。「叔父さん、奥にいるんでしょ?」
「います……けど」紫子は気構えつつうなずいた。「べつに大丈夫ですよ、それは。よっぽど大声じゃなかったら、音楽もあるし、奥にいると内容まではほとんど聞きとれないですから」
「そう」と言って、美緒はスマートフォンをテーブルに置いた。そのあと、居住まいを正すと紫子に向きなおった。「じゃあ今、ここで訊くけど。これで満足だった?」
ソーサーにかけていた指を放し、紫子は紫子で「満足?」と、客であり先輩でもある美緒へ挑む目でくりかえした。「そういうこと言うんだ」
「あれの解読、してほしかったんでしょ?」
「先輩に解いてほしかったんです、私は」
紫子はすねるポーズで口をとがらせ、恨めしい声をもらした。紫子の希望は百も承知で、美緒が今日の形をとったことも頭ではわかっていた。それでも、顕の手前ためこんだあれこれが今になってのどへと押しあがってくるのを止められなかった。
「先輩って」と、紫子は不満もあらわに言った。「いっつも一人で、勝手に決めちゃいますもんね」
「自分のことは自分で決めてるだけ」紫子の苦情がどこから地続きのものか、美緒は正確に理解していたが、今さらその程度では動じなかった。「それにね、私が解いてないなんて、一言も言ってないでしょ」
美緒の得意げな声色にひるんだわけでも、その報告が意外だったわけでもなかったが、紫子は反応できず黙りこんだ。だから余計にたちが悪いんでしょう、という内心の声さえ美緒には見透かされているにちがいなかった。
それでもまだ、と紫子は自身に言い聞かせた。勝ち筋はまだ、かろうじて残っている。
美緒は顕にテキストを差しだしたときと同じ動作で別のクリアファイルから新たに数枚の用紙を取りだし、テーブルに扇状に広げた。
「そもそも創作でしょ、これ。たぶん紫子の」
手に取るまでもなく、それは最初に相談を持ちかけたとき、紫子が美緒に手渡したテキストで間違いなかった。「どうしてそう思うんですか?」とだけ紫子は訊いた。
「どうしてもなにも、できすぎてるでしょ。ネタ元になった出来事やデータはあったのかもしれないけど、どう考えてもアキラ君が謎解きした部分なんかはできすぎ」
「できすぎってだけじゃ――」
「できすぎの上に、ありえないんだよね」美緒は余裕ぶったくだけた口調になって、広げた用紙から二枚目を抜きとった。「ここ――〈アリサは先生〉のとこが〈アリサワ先生〉なんだとしたらよ、音声からこのテキストを書きおこした誰かさんって、美術部の顧問がアリサワ先生だった時期を知らない世代の子ってことになるよね。父親のイントネーションがいくら変だったにしても、さすがに知ってたら、その可能性に気づかないなんておかしいもんね。そのくせに当時の生徒――小田と蟹江、それに庄司さんのことは迷わず漢字で表記してる。蟹江はまあ、ほかになさそうだしいいとしても、オダには織物のほうの織田もあるし、ショウジも東海林の可能性だってあるのに、なんでこの子は全員の漢字表記を知ってたんだろうね?」
「思いこみ……とか?」紫子は悪あがきを試みた。「そのへん適当に決めつけちゃう子だったんですね、きっと。なんせ高校生のやることですし」
「それか、表音文字で〈オダ〉と〈カニエ〉だと〈穏やかに描かれた――〉のとこがすぐばれちゃうかもって不安になった、とかね?」冷ややかな目つきで美緒は指摘し、紫子の無反応に自信を深めてテキストへと目を戻した。「どっちにしても、アリサワ先生って美術部の顧問が今までにいたか、学校に確認すれば創作かどうかはすぐはっきりするでしょ」
ビブエプロンの肩紐を直す仕草でわずかな時間をかせいだあと、紫子は「そこまでわかっちゃってるなら、ごまかしてもしょうがないですね」と、引き際を見誤らずに観念した。
「アキラ君もわかってたよ、たぶん。紫子を疑ってたかは知らないけど」
「そっか」と淡泊な声をもらし、紫子はスカートがしわにならないように両手で押さえながら顕が座っていた側のソファの端にするりと体をすべりこませた。「全部、お見通しですか」
「なんでまた座るの?」
「あーあ。何もかもお見通しか」嘆息しつつ紫子はくりかえした。「まいったなあ」
「まいったなあ、じゃなくて」
「だってだって、これでもう終わりってことじゃないですか」紫子は家族を除けば美緒の前でしか見せない甘えた声と態度になって、テーブルの下で足をばたつかせた。「ちがいます?」
そうして油断を誘いながらも、美緒からテーブルのテキストへと目線をさりげなく移す紫子の意図を、美緒はきっちり把握していたし、彼女なりの責任感のためにこうして店に残っていたのだった。
「何を言わせたいかはわかるけど」と、非情に徹して美緒は言った。「紫子もいいかげん、自分のことは自分で決めれるようになってかないとね」
美緒のその苦言に、紫子はなんの反応も示さなかった。ただ美緒がテキストから最後の一枚を抜きだすのを強ばった表情で見ていた。
〈あなたが私の目をまっすぐ見て、そう言うんだったら――がんばって忘れると約束します。〉
書きおこしテキストの終盤に現れるその段落を読みかえしながら、美緒はふっと、記憶のなかの確かなきらめきの残光をすくいとるような笑みを浮かべた。ここへきて初めて美緒がその顔を見せたことが、何より残酷な現実を紫子に突きつけるかっこうになった。
「前に進むきっかけにするんでしょ」まっすぐ紫子の目を見据えて、美緒はこの回りくどいやり口への感心と激励まじりの優しい声で言い聞かせた。「大丈夫。がんばるまでもなくね、たぶんすぐ忘れちゃうから。それは全然悪いことじゃないからね」
最後の望みも絶たれていたとわかって、紫子は体じゅうの熱という熱が急速に失われていくのを感じた。どうしてなのかが、ずっと――今このときでさえ、紫子にはわからなかった。身勝手で、都合よく先輩風を吹かせるところがずっと嫌いだった。そうして正にその年長者然とした眼差しが、紫子の胸に刻まれる一つ目の墓標になった。あの震えるような、息がつまる季節に共有した時間は今度こそ二重の封がされて、タイムカプセルの中で長い眠りにつく思い出になってしまった。
「あー、もうっ」受けとめきれないとわかっている喪失感から一時的に身をかわすために、紫子はあえてあっけらかんとした声で嘆いてみせた。「謎解きのほうに目がいってれば、ここだけはばれないと思ったんだけどなー。だめだったかあ」
「そういう狙いだったの? むしろ私が最初に気づいたの、こっちなんだけど」美緒は苦笑しつつ再びその段落に、〈おどろおどろしい先輩への気持ち、とてもまだなかったことにできません。〉という一文に目を落とした。「紫子がよこすテキストに〈どろしい先輩〉なんて書いてあったら、私が気づかないわけないでしょ。てか逆に、先にそこに気づいたから、全体がどんな仕掛けになってるかも見当がついたんだし」
そういう意味では、二人の関係など知るべくもない顕があの短時間でこのテキストを読みといてみせたことには美緒も素直に感嘆したし、たどるべき本筋をきちんと用意していた紫子の律儀さにも――一念からくる周到さの産物とはいえ――同じく感心させられたものだった。もちろん、だからといって紫子の望みに応じるつもりがないことに変わりはなかったが。
「どーしてもだめ……ですか」
「だーめ。もう一年半前から言ってる」
未練がましく、しかしこれまでよりいくらかフランクに、すねた声音で食いさがる紫子を突っぱねて、美緒は広がった用紙を両手でまとめるとテーブルにトントンやって端をそろえた。女子校のすべてがそうではないと頭でわかっていても、少なくとも彼女の周りには絶えずつきまとったもの――友情か恋か、それらのあいだでぼんやり輪郭をとる何かかにかかわらず、重く、そのくせ脆い、自重に耐えられない鉄の鎖で縛りあうような人間関係から距離を置くために、高校までと無関係の共学へ進んだことは紫子も承知していることだった。
「――わかりました。約束は約束……だもんね」
丸めた背を力なく背もたれへと預けて、紫子は潔く引き下がった。こんなに長いあいだ引きずっておいて本来なら潔いも何もないが、ともあれこれ以上はいくら冗談めかしたところでみじめになるばかりだろうし、自らしかけた責任としてみっともなく取り乱す姿だけはさらすまいと決めていた。
「それはそうと」と、強がり任せに気持ちを切りかえて、紫子は美緒がクリアファイルに戻そうとしているテキストを目顔で指し示した。「それも、捨てずに持っててもらえるんですよね?」
意味を飲みこめず、美緒は手を止めた。「何?」
「十年でしたっけ。たしか」美緒が眉をひそめる様子にいくらか溜飲を下げて、紫子はわずかに目を眇めた。「私があげたやつですもんね、それ」
顕に強いた方便が自身にはねかえってきたことを悟って、美緒はかったるさを隠そうともせずに表情をゆがめた。「あのね――」
「何、企んでるんです?」
言いのがれる隙を与えず追及する声に、美緒は「企むとか、そんなんじゃなくてね」とごく軽い受け答え一つでかわそうとした。手にしている数枚の用紙のどこにもコーヒーをこぼした染みなど見当たらないことが、紫子の確信を深めているとはこのとき、うかつにも気づかずにいた。
「――〈音をあげるのは明らかは確か。〉」
眇めた目をいっそう細めて、紫子が本来知るはずのないその一節をそらんじてみせたとき、美緒はその日最大の動揺を一滴たりとも表情へもらすことなく受けとめきる必要があった。それは最初に紫子から渡された――今この場に残っているテキストには存在しない一節だった。
美緒のほほ笑ましい無反応にくすくすと声もなく笑ったあと、紫子は同じ一節をイントネーションだけを変えて「音をあげるのは顕か私か」と、ささやくようにくりかえした。
顕に持ちかえらせたテキストに紫子が触れる機会が一度だけあったことを、美緒は苦々しく思いおこした。多少の違和感を覚えられていたとしても、あのわずかな時間でそこまで読みとられる可能性は低いだろうと甘く見た自分を呪わずにいられなかった。
「アリサの絵、私が先輩に渡したやつだと『枯れた葉』と『春の一日』ですもんね。なのにアキラさんが『春の日』って言うから、ん? って思って。そしたら」
「そうだっけ?」と、とぼけとおす方針をすばやく固めて、美緒は首を傾げた。「ちょっとよく言ってることがわかんないけど」
すると、紫子は信じられないという顔で目を見張った。「はあ、まじですか先輩」と腹の底から呆れて、それでもすぐ、優位さからのみ生じる類いのくだけた笑顔に戻った。「だって、あんなに私、〈アリサは〉以外で助詞の〈は〉を使わないようにって、さんざん気をつけたのに。ここだけであっさり二回も使われちゃって、そのせいで先輩のやつだと、余計に難易度上がってたんじゃないです? それでも解いたあの人は……まあ、ほんのちょっと、どうでもいいけどちょっとだけ、すごいのかもですけど」
紫子が今さら何を主張しようと、美緒が改竄を加えたテキストは顕がすでに持ちかえっていた。それだけが美緒に残された強みだった。自ら土俵を割りさえしなければ、紫子の指摘が二人のあいだで確認された事実とはならないことだけが。
「で?」と身を乗りだし、紫子は再び問いかけた。「何を企んでるんですか?」
ここへきて二人は真正面から視線をぶつけあった。追いつめる紫子の圧力と、二年先輩という不変の圧力とが拮抗して生じた束の間の沈黙を、エヴァンスとラファロの奔放なアドリブが、今では古典となった五十年以上も前のこもった柔らかい音色が、天才たちが生きた過去からの見守りの眼差しのように吹きぬけていった。
「ルーブ・ゴールドバーグ・マシン――みたいなものかもね」やがて、明らかな煙に巻く意図をもって美緒は言った。「言ってみたら」
「ルーブ――何、え? マシン? それはどういう?」
中学時代までの趣味については聞かせていない紫子の反応を平然と黙殺し、美緒は「それよりさ」と小さく嘆息したあと、巨大な密閉箱のほうをあごでくいと示した。「いつまで同じ曲ばっか客に聞かせてんの、この店は?」
話を逸らされまいと構えていたつもりだったが、そのクレームには紫子も思わず「ええっ」と素直な不満の声をもらした。「だって、リピートでかけとけって、あの人が来る前に先輩がリクエスト――」
紫子の抗議は諦めとともに尻つぼみになって、最後まで続かなかった。結局、いつもそうなのだった。はぐらかすと決めたら美緒はどこまでもはぐらかすし、これ以上食いさがったところでルーブなんとかマシンも、『春の日』への改変も、そこにどんな意味があるのかも明かされることはないのだろう。少なくとも当分は。それだけは紫子にもわかった。それを惚れた弱みと、自分がたやすく受けいれてしまえることも。
「そもそも『枯葉』って私、あんま好きじゃないんだよね。ぶっちゃけると」紫子の心情にいちいち配慮していてはきりがないと知っている美緒は一方的に続けて、胸焼けでも起こしたように顔をしかめてみせた。「ジャズの題材としてどうこうじゃなくて、元のシャンソンの世界観っていうか、歌詞がどうにもね」
「……じゃあかけろなんて、べつに言わなきゃいいのに」
八つ当たり半分にぼやきつつ、それでも要望を受けたスタッフの務めとして紫子はテーブルに両手をつくと立ちあがった。顕を迎えるための演出なのか、遠回しのヒントの一環だったのか知らないが、なんにしろ顕のためとわかった時点で、その片棒を担がされていたというだけで紫子からすれば気に食わなくて当然だった。
「それに、私はけっこう、歌詞もいいと思いましたけど」と、オーディオのリモコンがあるカウンターへ歩いていきながら紫子は意見した。叔父の許可なく触っていいボタンは厳密に決められていた。「哀愁が漂ってて、案外よくなかったですか?」
若いころに愛しあった恋人たちがそれぞれに年月を重ねて再会するも、二つの人生は再び重なることなく、幸せな日々の思い出や後悔は吹きだまる枯葉とともに北風が忘却の夜へと運び去ってしまう、というシンプルかつ余情たっぷりの大人のバラードは、紫子たちの年代が普段親しんでいる音楽とは全く趣がちがっていて新鮮だった。日本語の訳詞によるレコードも戦後いくつか発売されていて、今回のために下調べするなか、紫子もインターネット上ではあったがそれらの音源やフランス語の原曲を一通り耳にしていた。
「年寄りの自己憐憫ソングがダメってわけじゃないけど」と美緒は言った。「私らが共感するような歌じゃないでしょ」
別れを惜しむぐらいなら別れなければよかったし、そうできなかったのならつまり結ばれるべき相手ではなかったのだから惜しむ必要もない、というのが美緒の恋愛に対する構え方だった。一時の熱情に任せて燃えつきておいて、あのころが一番輝いていたと思い出を慈しむ晩年をすごしたければ勝手にしたらいいが、人生が落葉を迎えるときにこそ最良のパートナーとともにあることを美緒は理想としているし、そのための歩みを若い時分から重ねていくべきだと考えていた。人生とは遠大なその歩みの途上に自ずと立ちあらわれる悲喜こもごもであるべきだと。
「ほかのお客さんがいるときはそういうこと、思っても言っちゃダメですよ」
カウンターの裏に回って、リモコンを手に取りつつ紫子が注文をつけると、美緒からはすぐさま「言うわけないでしょ」と答えが返ってきた。「人のこと好き嫌いと善し悪しを混同するバカみたいに言わないでくれる」
「善し悪しだとしてもですよ」とたしなめて、紫子は『枯葉』のリピート再生を停止させた。
善し悪しなら美緒はけんかをふっかけかねない、などと本気で危惧したわけではもちろんなかった。しかし、このとき――ピアノ・トリオの演奏が途切れ、防音材に囲まれた店内を厳かなまでの無音が支配した瞬間に、自身の心に未体験の反転が起こるのを、たしかに紫子は感じたのだった。
美緒は何事も理性のコントロール下に置くことにこだわりすぎるきらいがあった。そばで見てきた経験から、紫子はそう感じていた。音楽も、接続する社会とのコミュニケーションにしても、恋愛でさえも――卒業して環境が変わると大抵のカップルは終わる、と美緒は顕に説明した。まるで他人事のように。一方的に終わらせた張本人だなんてことはおくびにも出さずに。身勝手で、都合よく先輩風を吹かせるところがずっと嫌いだった。だけど、と今、紫子は不可思議な手応えとともに理解しかけていた。美緒は何よりもそれを――あるいは無意識のうちに存在を予感して――恐れているのではないか。理性のコントロールを外れたところに眠っているかもしれない自身の未知の一面を。それが解き放たれたあと、自分がどう変わってしまうのかを。
「水、おかわりもらえる?」
美緒が空のコップを持つ手をぞんざいに揺らし、紫子に催促した。紫子はリモコンを元の場所へ戻すと新しいコップを取り、製氷機の貯氷庫を開けて氷を入れた。
もしそうだとしたら、とピッチャーの水を注ぎいれながら紫子は考えていた。美緒が顕に目をつけたというのはどういうことなのか? 紫子と距離を置こうとしたのは?
紫子が『枯葉』の歌詞に共感したのは、一時は愛しあうも別れた恋人たち、という人物設定に、一年半ものあいだ消化できずにいる未練を安易に投影してのことだった。やはり先輩の言うとおりかもしれない、とここへ至って、紫子はその態度をあらためた。憐憫に浸るにはたしかに、私たちはまだ若すぎる。
「〈落ちはてて過ぎた日の色あせた恋のうた〉」
中原淳一による訳詞の印象的な一節をこっそり、胸の奥の貯氷庫に眠らせるように小さくつぶやくと、紫子はコップを片手にフロアへ戻っていった。春まではまだ半年ある。交わしたばかりの約束に、どんな曲解を持ちこめば一度は破り捨てる覚悟まで決めた入学願書を提出する名分が立つか、屁理屈をひねりだす時間はたっぷりあった。