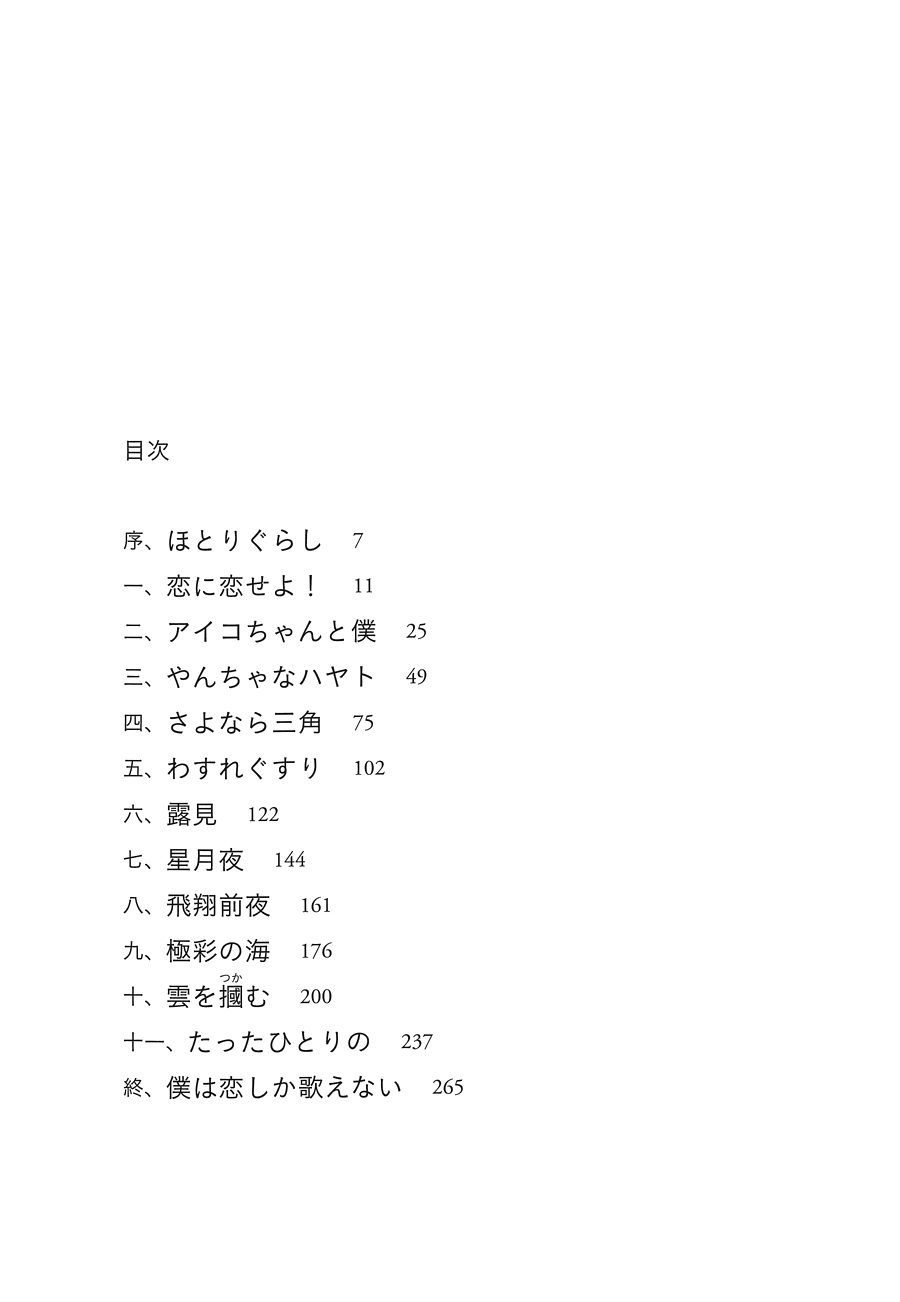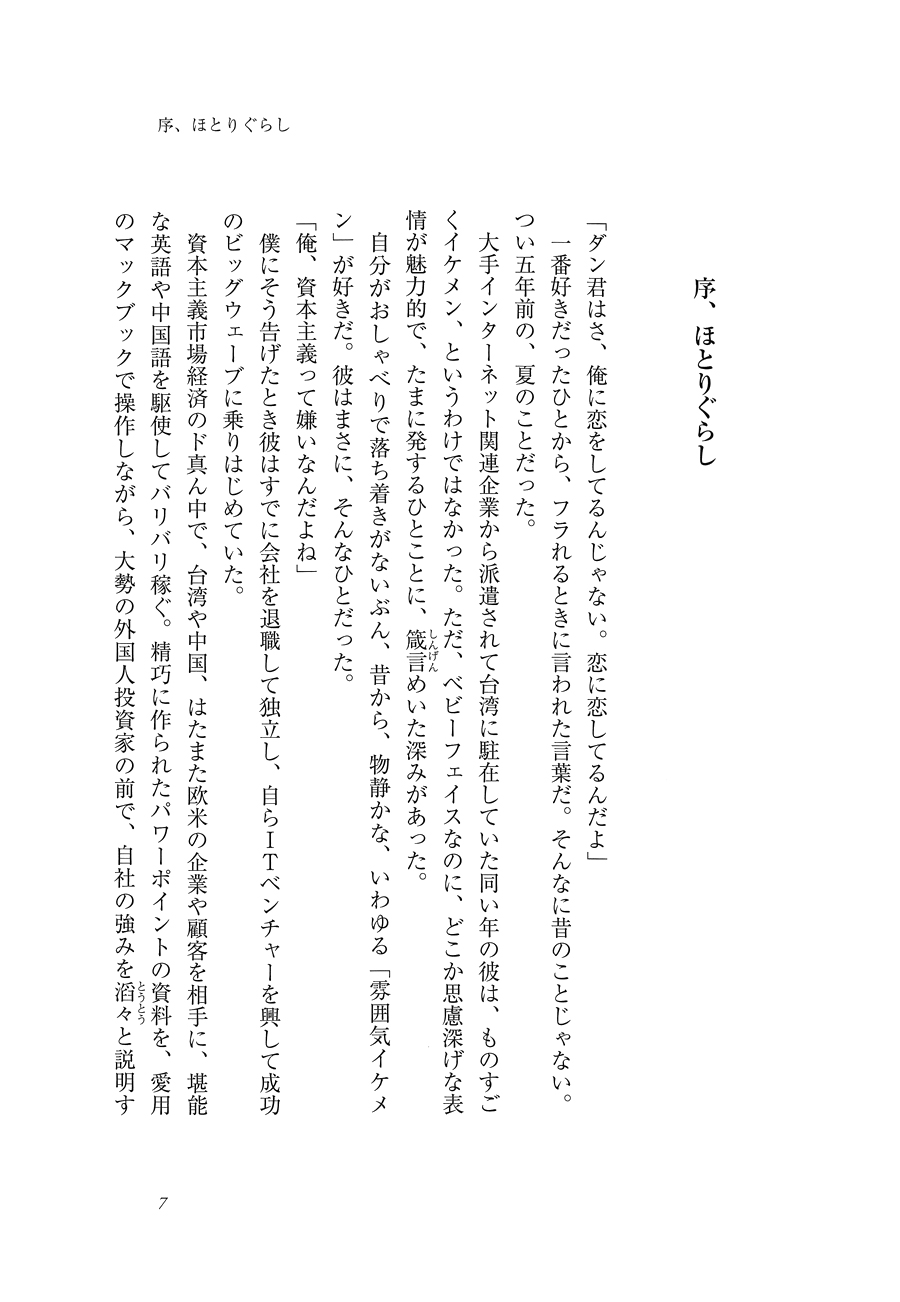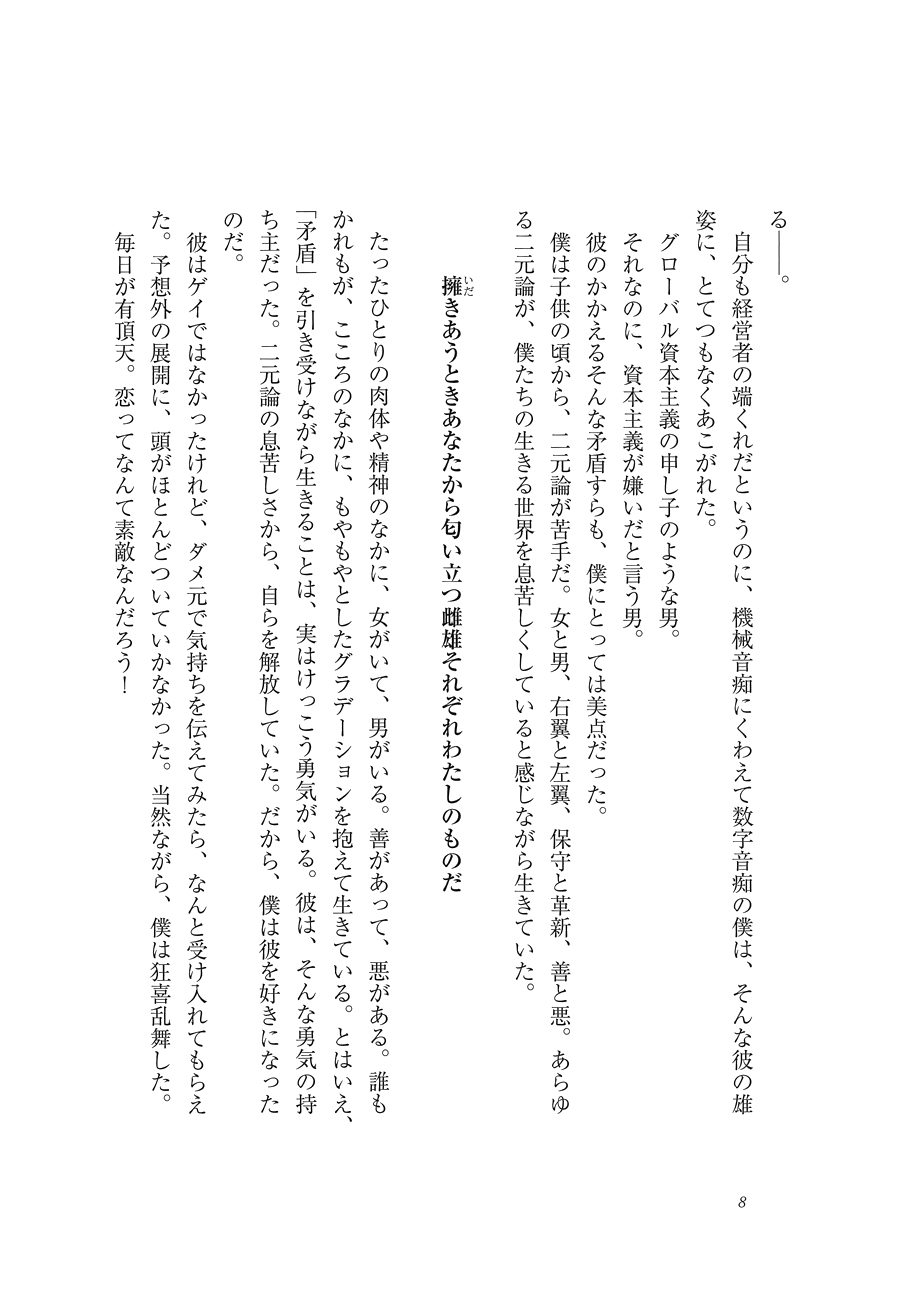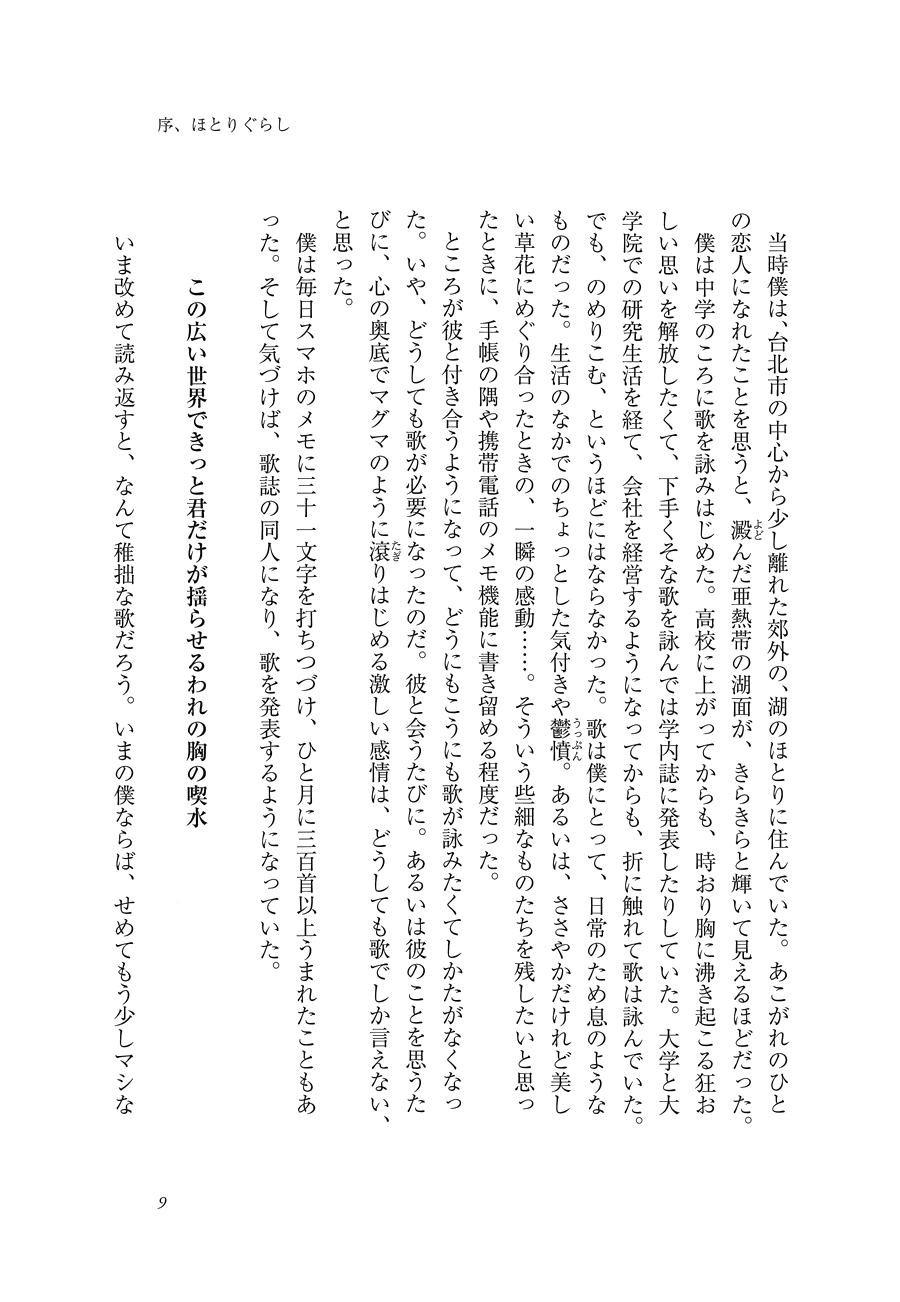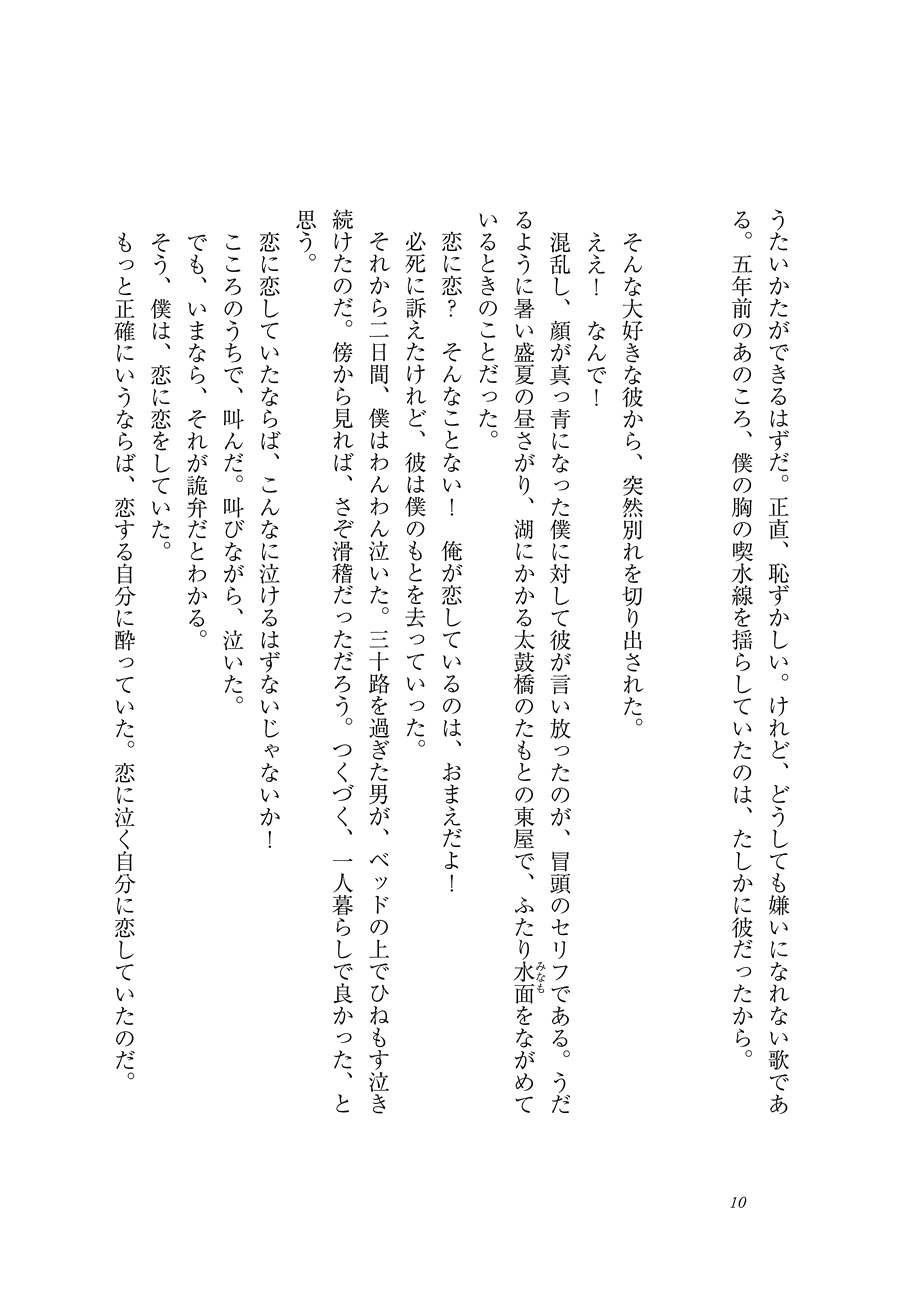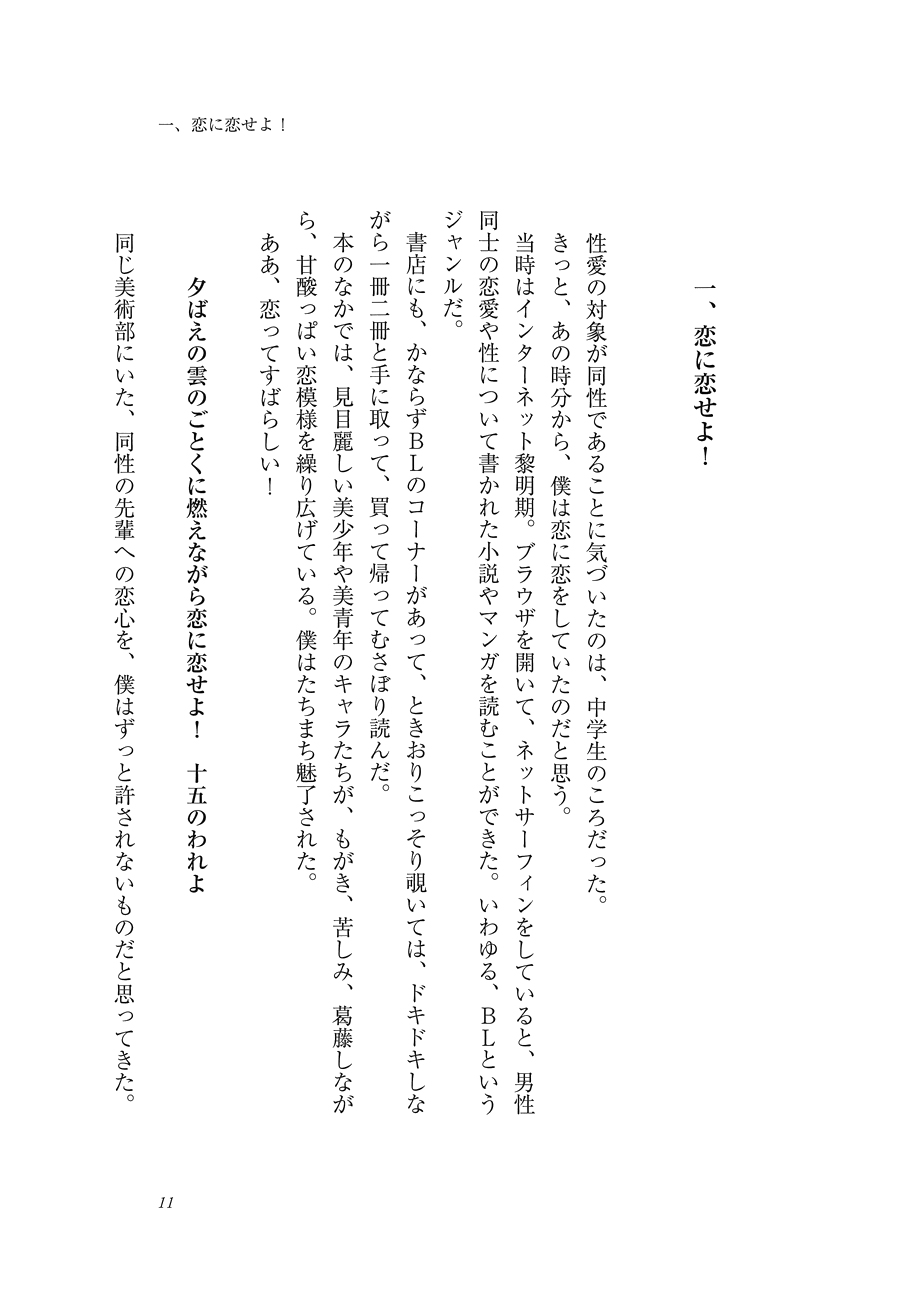一、恋に恋せよ!
性愛の対象が同性であることに気づいたのは、中学生のころだった。
きっと、あの時分から、僕は恋に恋をしていたのだと思う。
当時はインターネット黎明期。ブラウザを開いて、ネットサーフィンをしていると、男性同士の恋愛や性について書かれた小説やマンガを読むことができた。いわゆる、BLというジャンルだ。
書店にも、かならずBLのコーナーがあって、ときおりこっそり覗いては、ドキドキしながら一冊二冊と手に取って、買って帰ってむさぼり読んだ。
本のなかでは、見目麗しい美少年や美青年のキャラたちが、もがき、苦しみ、葛藤しながら、甘酸っぱい恋模様を繰り広げている。僕はたちまち魅了された。
ああ、恋ってすばらしい!
夕ばえの雲のごとくに燃えながら恋に恋せよ! 十五のわれよ
同じ美術部にいた、同性の先輩への恋心を、僕はずっと許されないものだと思ってきた。テレビのバラエティ番組では、グロテスクなゲイのキャラを演じるお笑い芸人が、「ホモ」をネタにして笑いを取っていた。
ところが、BLマンガや小説のなかでは、あたりまえのように男同士で恋愛をしている。異性愛者だったはずの主人公が、あれよあれよと同性と恋に落ち、紆余曲折はありつつも、当然のように結ばれる。
思春期の未熟なこころは、夢と現実の境目を、たやすく見誤ってしまいがちだ。僕は、BLの世界と、現実の世界の区別が、徐々につかなくなっていった。
夏休み、合宿で先輩と同室になった。信州の山荘の狭い部屋でふたりきり、というシチュエーションの非日常感もあいまって、僕は完全に現実を見失っていた。
「俺、先輩のことが好き」
夜、お風呂から帰ってきた先輩が、ベッドに寝転がり携帯用ゲーム機を取り出してゲームをし始めたとき、僕は思わず気持ちを吐露してしまった。
先輩が、目を見開く。
「俺もだよ。俺もずっと、おまえのことが気になってたんだ。嬉しいよ」
先輩は、僕の座るベッドへとやって来て、やさしく抱きしめてくれた……なんてことには、もちろんならなかった。
先輩が、やさしいひとで良かった。
彼はただ、「そっか。ありがとう。でも、俺は気持ちに応えられない」と、なんでもないことのように言ってのち、黙々とゲームを再開した。
僕は、はじめて失恋を知ったのだった。
ところが、失恋の経験は、僕をさらなるファンタジストへと育んでゆく。
現実の世界で負った傷を、ファンタジーの世界で癒やす。いわゆる「二次元」にハマるひとの心理は、だいたい同じなのでは、と思う。自宅の勉強机のひきだしに、教室の机の奥深くに、BL本がどんどん増えていった。
先輩に失恋したのちも、同級生に気になる子ができたりした。とはいえはじめての失恋で、夢と現実の別を思い知ったばかりの僕は、もう二度と同じあやまちは繰り返すまい、と思っていた。たとえ学校で誰かを好きになったとしても、かならず胸のうちにとどめること。同性愛者であることなんて、絶対に知られてはいけない。
辛くなったら、本屋に行けばいい。BLマンガや小説をひもとけば、そこには僕を癒やしてくれる、きゅんきゅんするような恋が、あふれているんだから。
ところが僕がファンタジーの世界に閉じこもり続けるのを許してくれるほど、中学校は甘い場所ではなかった。都心の共学校ということもあり、同級生たちはどこかませていて、三年生ともなれば、話題は恋のことばかり。
ダンって、女に興味なさそうだよね。
うん、わかるー。あ、ひょっとしてホモなんじゃない?
あはは、あいつならあり得るわ!
……。
廊下や教室の隅のさざめきは、当然僕の耳にも入ってくる。
やばい、やばい。僕も女の子に恋をしなくては。普通の恋を、しなくては。だけどどうしたらいいんだろう。
まぼろしの恋のはなしのさざめきに上唇が黒ずんでゆく
「普通の恋」へのプレッシャーが、日々強まってゆく。
ところがどう頑張ってみても、女の子との恋愛が想像できない。あの先輩の、やさしい横顔を思い出すと、胸がどうしようもなく苦しくなるのに、クラスで一番かわいい、と男子たちが騒いでいるレナちゃんの顔を思い浮かべても、僕のこころは波立たなかった。
嘘も、たくさんついた。
好きなタイプの話になれば、流行りの女優やグラドルの名前を、したり顔で出してみたりした。レナちゃんの名前も、申し訳ないけれど、何度か使わせてもらった。そのたびに、こころのなかの大事な部分が、じわじわ溶かされてゆくような心地がした。
悩み多き日々のなかで、ちょっとした事件が起きた。
当時はいまのようにジェンダーの平等が叫ばれる時代ではなかったから、僕の通っていた学校では、あたりまえのように「女子は家庭科、男子は技術」というカリキュラムが組まれていた。
男子が技術室で万力や
僕の学校の男女比は、約3対2だったので、「技術・家庭科」の時間には、通常四十人以上がいる教室に、十数人の女子が残るのみとなる。授業を効率的に進めるために、家庭科のとき女子は、教室の前方に集まって座るように指示される。
つまり、普段は別のひとが使っている席に座ることになるのだ。
あの日も、僕が技術室でベニヤ板と格闘しているあいだ、教室では家庭科の授業がおこなわれていた。僕の席に座ったのは、同じ附属の小学校から進学してきた、比較的仲のいい女の子。
どういうわけか知らないけれど、彼女はその日にかぎって、僕の机のなかを漁ってみたらしい。するとびっくり! 男同士の、キワドいイラストが表紙のマンガや文庫本が、どっさりと見つかった。
ちなみに僕の学校には、いわゆる「校則」がなかった。マンガや雑誌の持ち込みも禁止されてはいなかったし、制服すら、着ても着なくても自由だった。だから、机のなかにBLマンガを隠しておいたとしても、学校の規則に違反しているわけではない。
しかしこのとき、僕の机のなかには、もっとヤバいものが入っていた。
自分で書いた、「BL小説もどき」である。
「先生、オサノ君の机からなんかすごいもの出てきちゃった……」
家庭科の授業で僕の机に座った女の子は、あろうことか、思春期の僕の妄想が書き連ねられたノートを、先生に渡してしまったのだった。
しかも、悪いことに、僕が「ノート」に書いていた「小説もどき」は、何人かのイケメンな同級生をネタにしていた。
メデューサのようにはだかり
オサノ君、ちょっと……。声をひそめた先生に呼ばれた。
技術の授業で、不得手な木工作業を終えたばかりの僕は、へとへとに疲れていた。
なんだよ、めんどくせえな。
ぼやきながらも、根がビビリな僕は、言われるがまま先生について中庭にいった。この時点で僕は、先生が出席簿の下に、例の「ノート」を隠し持っていることに、気づいていない。
たぶん、五月か六月だったと思う。立ちはだかる先生の頭上に、抜けるような青空がひろがっていたのを、覚えているから。
「あのね、あなたを責めているわけじゃないの」
ここまで言われても、僕はまだ状況をいまいち把握できていなかった。
なんのこと?
きっと、僕は
「思春期だからね、色々あるのはわかるの。でもね、こんなものを書いていたら、あなたはまわりからとんでもない色眼鏡で見られてしまうのよ。わたしは、それが心配なの」
そこから先は、記憶があいまいだ。でも、「血の気が引く」というのは、こういう感じのことを言うんだなあ、と、遠のく意識のなかで思ったことが忘れられない。
教室に戻ると、何人かの女子が、僕の顔を見てひそひそと話をしているのが目についた。いや、ほんとうは僕のことなんか、話していなかったのかもしれない。でも、先生に「ノート」を突きつけられたあの瞬間から、僕はクラスの全員が、僕をわらっている気がするようになった。
色眼鏡。
先生は言った。でも、色眼鏡ってなんだよ。
聞き慣れない言葉を頭のなかで
それでも、「恋」にあこがれる気持ちは高まるばかり。
同級生たちは、彼女や彼氏とデートをしたり、セックスをしたりしていた。
ある日、クラスの女子生徒たちが、教室の隅に集まって、さめざめと泣くひとりの女の子を慰めていた。なんでも風のうわさでは、卒業して附属の高校に進学した先輩と付き合っていたけれど、のっぴきならない事情で別れることになったらしい。
……いいなあ。
泣いている子には申し訳ないけれど、そう思った。別れ話ですら、別れる相手のいない僕には羨ましかった。
僕だって、そういう恋がしてみたい。クラスの男子や先輩と、甘酸っぱい恋がしたかったのだ。
ドキドキしながら、好きだ、と伝える。
すると彼も、おまえが好きだと言ってくれた。
わたしは、身を震わせた――。
恐れと期待がないまぜになった、高鳴る胸を抱えながら、親に隠れてこっそり一夜を共にした。
ところが若い身空では、いかんともしがたい事情がうまれて、やがて別れが訪れた。
打ちひしがれて泣いていると、クラスの子たちが心配して、慰めにきてくれた。
だいじょうぶ、もっといいひと見つかるよ。
ひどいよね、こんなかわいい子を捨てるなんてさあ!
きっと相手が後悔するよ――
こんな感じの一連のながれが、僕にとっての「恋のイメージ」だった。青春とは、こういう切ないものがたりの上に、成り立つものにちがいない。そう信じていた。
恋に彩られた青春への渇愛は、募ってゆくばかりだった。
そのころインターネット上には、ゲイのひとたちのための出会い系掲示板が、ちらほらと見られるようになっていた。
〈一七五センチ、六十キロ、十五歳の中三です。髪は長めの茶髪で今風です! あまり年上過ぎないひとで、会える方いたら、よろしくおねがいします。同年代くらいだと嬉しいです〉
学校での「普通の恋」をあきらめた僕は、インターネットという文明の利器を活用して、恋をしてみようと思い立った。
児童ポルノ禁止法が施行され、青少年健全育成条例なども厳しくなった今日からしてみれば、われながらなかなかリスキーなことをしていたものだ、と背筋が寒くなる。良くも悪くも、ユルい時代だったのだ。
当時は携帯もまだそんなに普及していなくて、やっと「ナンバー・ディスプレイ」(かけてきた相手がわかる、という機能。いまではあたりまえだが、当時としては画期的だった)が普及しはじめたくらいだった。
写メなんてもちろんないから、出会い系で連絡を取って会うことになった相手の容貌は、実際に会うまでわからない。
待ち合わせ前日の夜、相手からパソコンにメールが届く。
〈明日は楽しみにしているよ! 四時にモヤイ像の前で待ってます! 俺は、赤いライダースジャケットに、普通のジーンズ
こんな感じで服装やヘアスタイルについて書いてあって、電話番号が付されている。携帯がなかったころよりはだいぶマシだったのだろうけれど、それでもスマホがある現代に比べたら、会うのはけっこう大変だった。
約束の時間に、あえて少し遅れるように、待ち合わせ場所に向かう。こちらの服装やヘアスタイルも相手に伝えてあるから、先に着いてしまうと、すぐに見つけられてしまう。
「……もしもし? もう着いてますか?」
渋谷駅に着いて、モヤイ像の近くの壁の裏から、小声で相手に電話をかける。
「うん、いまモヤイ像の前にいるよ。そっちは?」
「すみません、あと五分くらいで着けると思います!」
電話をしながらこっそり様子を窺っていると、メールに書かれていたのとは似ても似つかない容貌の男が、携帯電話片手に、真っ赤なライダース姿でモヤイ像の前でそわそわしている。
え、あれはムリ! ハタチだって言ってたのに、絶対三十は超えてるだろ……
電話を切った僕は、すぐに相手を着信拒否して、渋谷駅から逃げ去ってゆく――。
こんなロクでもないことを、しょっちゅうやっていた。
当時、僕と連絡を取ってくれていた男性の皆さん、ごめんなさい。
どうしても恋がしてみたくて、恋人を持ってみたくて、こんな「遊び」を繰り返していた。そしてついに、ひとりのひとと実際に会ってみたのだった。
相手は十九歳の、商船大学生。メールでやりとりしていても、やさしく頼りがいがある感じで、けっこう馬があった。
なにより、情報に具体性があった。嘘をついたり、年齢を詐称している様子が見られない。
待ち合わせ場所は、いつもの渋谷、モヤイ像前。僕は初めて、相手よりも先に着いていた。
午後四時半。
あらわれたひとは、想像したほどイケメンではなかったけれど、それまで連絡を取ってきたひとに比べれば、かなりいい感じ。それに、彼はちゃんと十九歳の見た目だった。
ファッキンだったかミスドだったかは思い出せないけれど、ふたりでお茶を飲みながら話をした。その後、しごく自然とラブホに向かう流れになった。いや、自然と言ったら嘘になる。僕はとにかく、セックスをしてみたかったのだ。BLマンガや小説で描かれているような、イケメンとの甘くてとろけるようなセックスを。だから、あれは僕が誘ったのだと思う。
しつこいようだが、当時はとにかくいまよりも、なにもかもがユルかった。身分証での年齢確認など、された覚えがない。タスポなんかもなかったから、街なかの自動販売機で、中坊があっさり煙草を買うことのできた時代である。
ましてや僕の学校は、制服がない。そして僕の身長は、一七五センチ。顔立ちも大人びていたから、ラブホには何の問題もなく入ることができた。
〈ご休憩・二時間〉終えてもう全部わかったような顔して駅へ
はじめてのセックスは、ただ痛くて、つらいだけだった。
そもそも何の知識もないのだ。それは相手も同じだったけれど。
ベッドに敷かれたシーツの赤が、いつまでもまなうらから消えてくれなかった。
痛いのは、身体だけではなかった。
「いけないこと」をしてしまった罪悪感で、胸が痛かった。
ひょっとしたらこれは、先輩への恋心よりも、もっとずっと「いけないこと」だったのではないか。母にバレたらどうしよう。ひきだしの奥のBLマンガや小説が見つかってしまうよりも、はるかに、失望させ、傷つけるかもしれない――。
幼少期に両親が離婚していて、母子家庭で育った僕は、とにかく母にすべてが露見するのが怖かった。母に失望され、母から見放されるのが、怖くて怖くてしかたがなかった。
胸が、悲鳴をあげていた。
なにより、はじめての性行為は、僕が思っていたのと「なにか」ちがった。
恋が、うまれなかったのだ。
BLマンガだったなら、コトが済んだあとに彼がやさしく僕を抱きしめ、「愛してる」とか「かわいいよ」だとか囁いてくれるはずなのに。そんな甘い時間は、一秒もなかった。
BLマンガや小説で、幸せに結ばれるふたりは、かならず「自然」に出会っていた。同級生だったり、あるいは、街のパン屋でばったり出会ったり。
インターネットを介した出会いは、まったく自然じゃなかった。作為的な出会いの果てに、BLみたいな恋はなかった。
虚無と失望、そして恐怖が渦巻く胸の激しい痛みに耐えながら、僕は渋谷駅へと走った。
まだ恋を知らざる胸を、ししむらを、成長痛が引き裂いてゆく
どうすればいいんだろう。どうすれば、自然に出会って、自然に恋ができるのだろう。どんな相手と一緒になれば、母や家族みんなが僕の恋を祝福してくれるのだろう。
乗車率百五十パーセントの車内で、僕は必死にイケメンを探した。もしここで、誰かと目が合ったなら、きっと僕たちは恋に落ちるんだ。
「君、かわいいね」
かっこいいお兄さんが、僕を
「俺も、ずっとさっきから気になってました……」
顔を赤らめて答える僕に、お兄さんはやさしく微笑みかけて、そっと携帯番号を書いたメモを渡してくれる――
中学生の妄想は、とどまるところを知らない。
もちろん、そんなかっこいいお兄さんは、新玉川線の車内には、いなかった。
僕は叫び出したかった。
恋がしたい! 僕は、恋がしたいんです!
あの日のこころの叫びの余韻が、いまも胸に残っている。