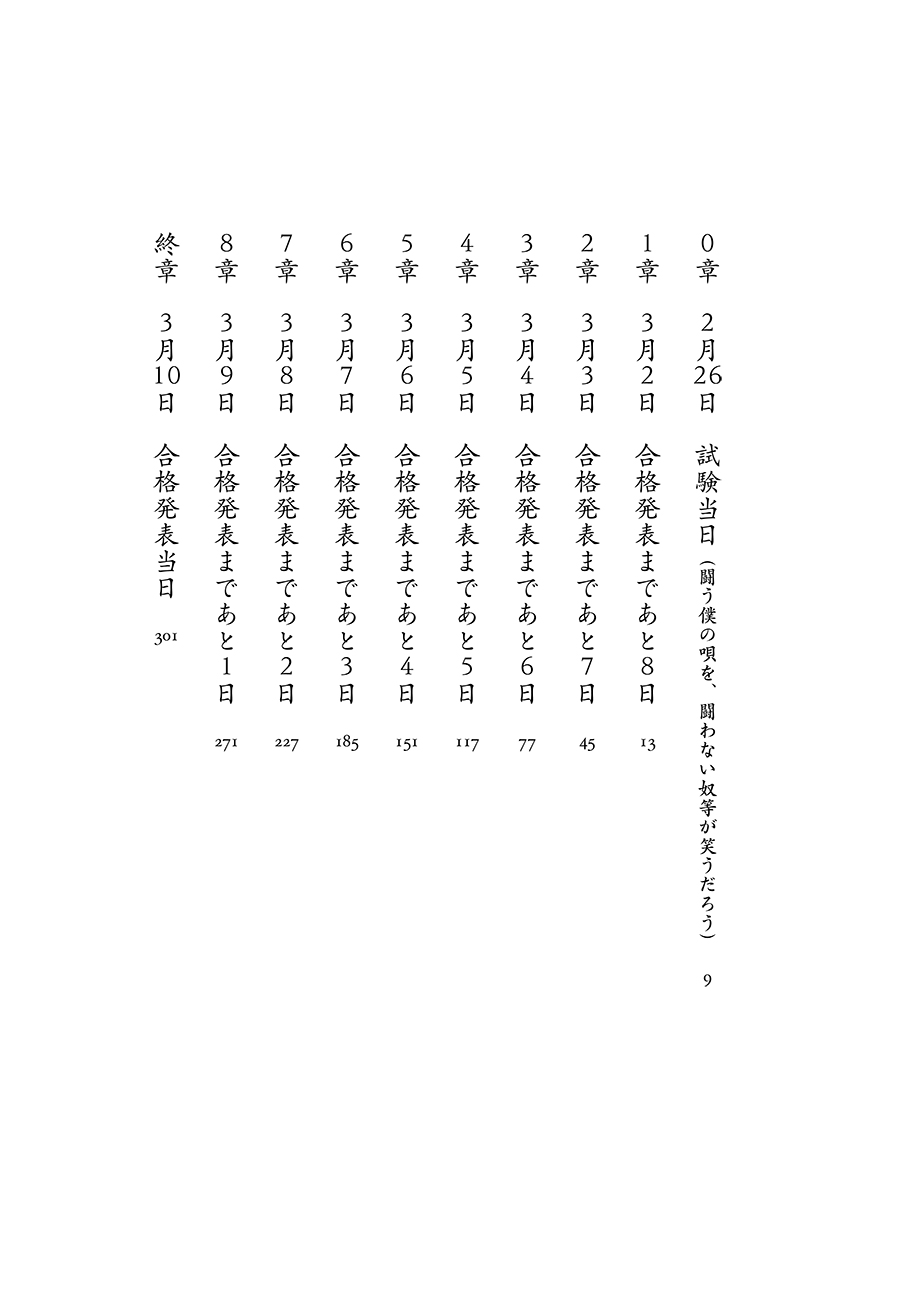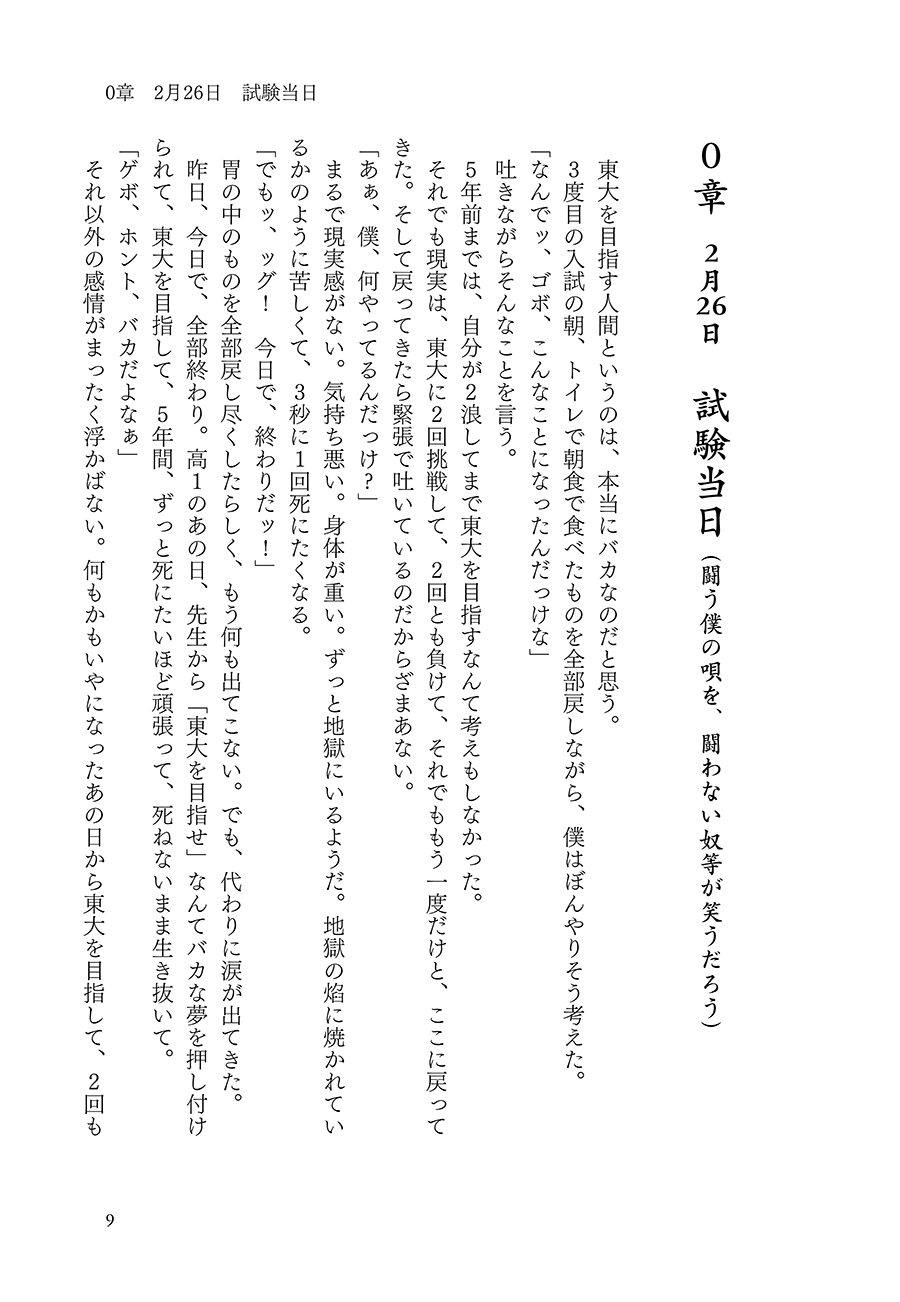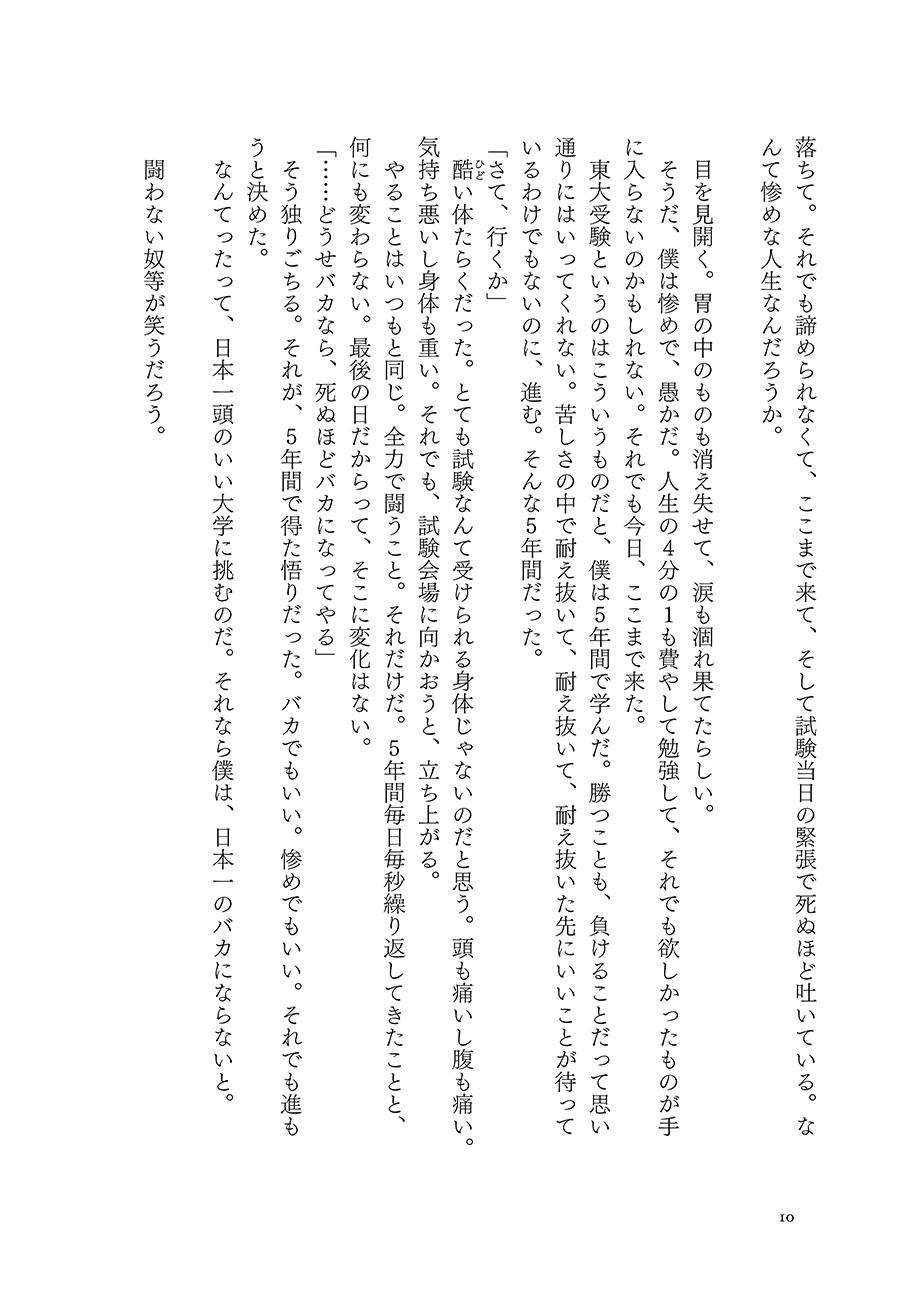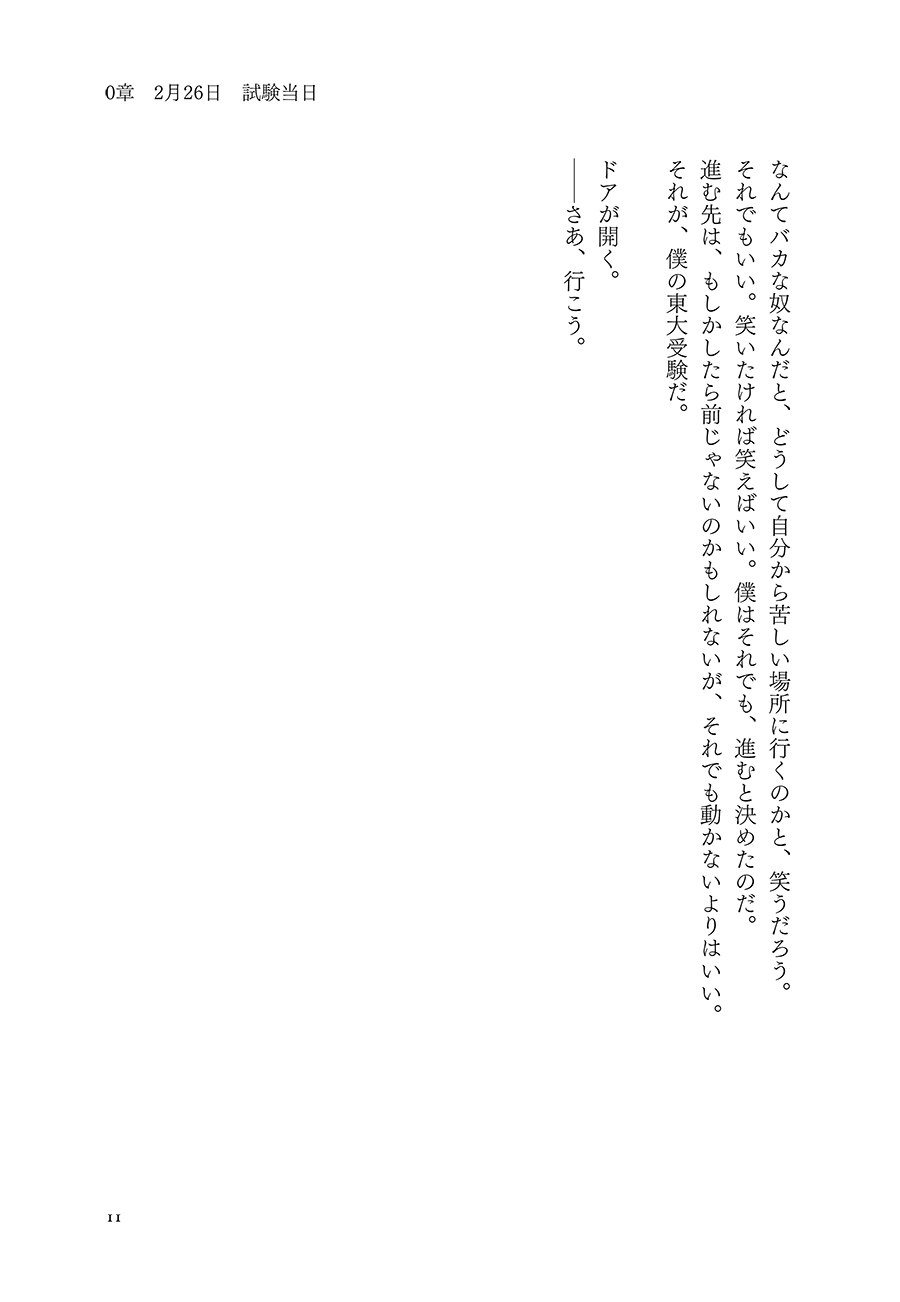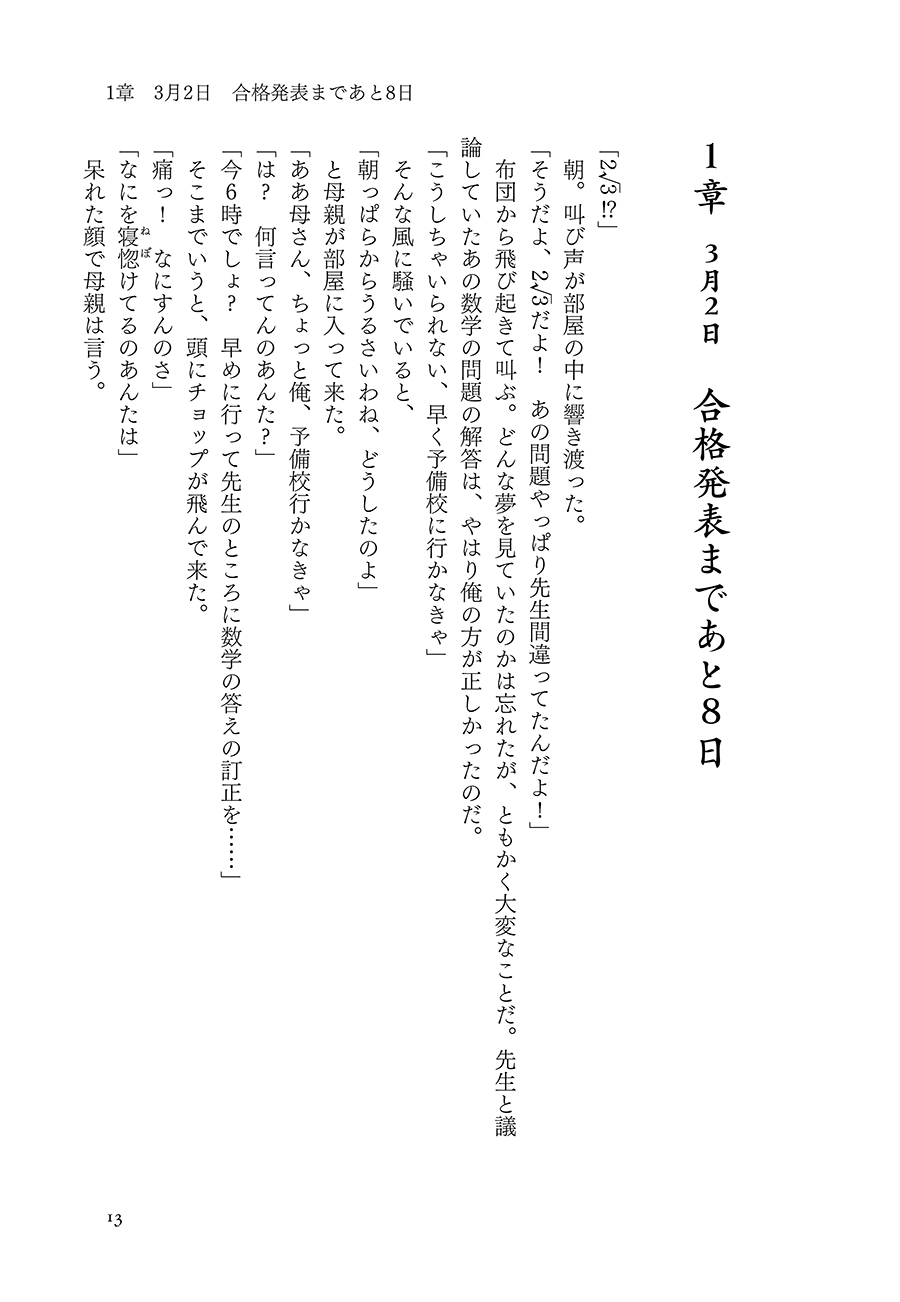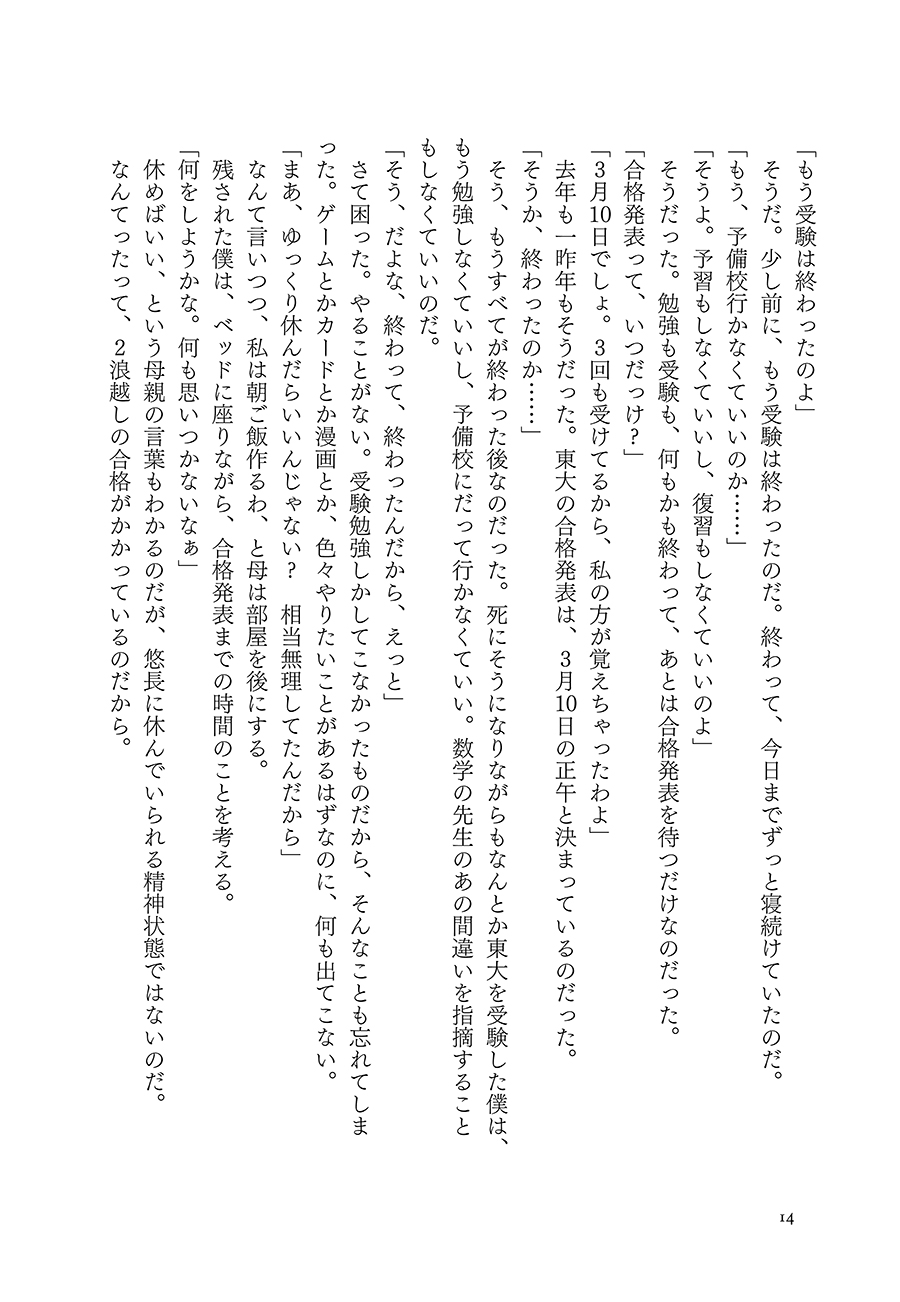1章 3月2日 合格発表まであと8日
「2√3!?」
朝。叫び声が部屋の中に響き渡った。
「そうだよ、2√3だよ! あの問題やっぱり先生間違ってたんだよ!」
布団から飛び起きて叫ぶ。どんな夢を見ていたのかは忘れたが、ともかく大変なことだ。先生と議論していたあの数学の問題の解答は、やはり俺の方が正しかったのだ。
「こうしちゃいられない、早く予備校に行かなきゃ」
そんな風に騒いでいると、
「朝っぱらからうるさいわね、どうしたのよ」
と母親が部屋に入って来た。
「ああ母さん、ちょっと俺、予備校行かなきゃ」
「は? 何言ってんのあんた?」
「今6時でしょ? 早めに行って先生のところに数学の答えの訂正を……」
そこまでいうと、頭にチョップが飛んで来た。
「痛っ! なにすんのさ」
「なにを寝惚けてるのあんたは」
呆れた顔で母親は言う。
「もう受験は終わったのよ」
そうだ。少し前に、もう受験は終わったのだ。終わって、今日までずっと寝続けていたのだ。
「もう、予備校行かなくていいのか……」
「そうよ。予習もしなくていいし、復習もしなくていいのよ」
そうだった。勉強も受験も、何もかも終わって、あとは合格発表を待つだけなのだった。
「合格発表って、いつだっけ?」
「3月10日でしょ。3回も受けてるから、私の方が覚えちゃったわよ」
去年も一昨年もそうだった。東大の合格発表は、3月10日の正午と決まっているのだった。
「そうか、終わったのか……」
そう、もうすべてが終わった後なのだった。死にそうになりながらもなんとか東大を受験した僕は、もう勉強しなくていいし、予備校にだって行かなくていい。数学の先生のあの間違いを指摘することもしなくていいのだ。
「そう、だよな、終わって、終わったんだから、えっと」
さて困った。やることがない。受験勉強しかしてこなかったものだから、そんなことも忘れてしまった。ゲームとかカードとか漫画とか、色々やりたいことがあるはずなのに、何も出てこない。
「まあ、ゆっくり休んだらいいんじゃない? 相当無理してたんだから」
なんて言いつつ、私は朝ご飯作るわ、と母は部屋を後にする。
残された僕は、ベッドに座りながら、合格発表までの時間のことを考える。
「何をしようかな。何も思いつかないなぁ」
休めばいい、という母親の言葉もわかるのだが、悠長に休んでいられる精神状態ではないのだ。
なんてったって、2浪越しの合格がかかっているのだから。
今年こそはと意気込んで挑戦した東大受験。すべてを出し切って、緊張で当日吐きながらも、懸命に闘った結果が、8日後には出るのだ。合格できたかどうか気になって気になって仕方がないのだ。いくら合否を気にしても、結果が変わるわけでもないのだから、いっそ一思いに結果を伝えてくれればいいのに。合格なのか不合格なのかわからない状況で10日間も待たされる、というのは生殺しもいいところだ。
去年までは、それでもやることを強いて探して、予備校の解答速報を見て「ああこの問題が合ってた」「あの問題の答えは間違えてた」と言いながら、合格か不合格かを考え続けて、ずっと悶々としていた。
「それは今年はやめよう。心臓によくないし、結局そんなことを考えても合格か不合格かなんてわからないんだから」
過去2回は、ずっとぐるぐる考えた末に、不合格だった。
「人事を尽くして天命を待つ、だ。3日前にすべてを出し切ったんだから、合格か不合格かは気にしないようにしよう」
誰もいない部屋で、僕は独りごちた。
「だけどあんたも出世したわよねー」
ウチは父が単身赴任で、基本的に家には母と僕しかいない。そして母親も午後から仕事に行くことが多いので、夕食は基本的に僕1人だ。しかし朝食は母が作ってくれて、2人で食べる。
ご飯。納豆。魚。味噌汁。お茶。そんな普通の和食を食べながら、母はふいに思い出したようにそう言ったのだった。
「出世、したかな? いや、出世はしてないと思うんだけど」
僕がそう言うと、母はあっさり、
「まあそうよね。浪人生なんてニートみたいなもんだし」
返す言葉もない。そりゃ、別に学校に通うわけでもなくただ勉強している期間なんて、ニートみたいなものだと自分でも思う。でも流石にその物言いはないんじゃないだろうか。
「それでもあんた、東大に3回も挑戦できたんだから。一時期じゃ考えられなかったわよ」
3回。そう、僕は2浪なので、現役合格者の3倍受験したわけだ。
「挑戦だけなら誰でもできるでしょ。それに、2回不合格になったわけだし」
と、ついマイナスな答えをしてしまう。僕は基本的にいつもマイナス思考だ。褒められると否定したくなるし、プラスのことを言われると必ずマイナスで返してしまう。
「まあそうだけど、でもあんた、東大よ? 東大。日本のトップの大学に挑めるなんて」
母は言う。ちなみに母は地方の出で、大学は地元の短大。父と結婚して東京に出てきたために、東大というのは母にとっては漠然と「すごいところ」というイメージなのだろう。
「まあ、受かってるかわからないけどな」
僕はそう口にしたが、合否がまた気になり出して、なんとなく辛くなる。そんな僕の様子など意に介さず、母はこんなことを言い出した。
「だってあんた、ずっと学校でビリだったでしょ?」
そう、今でこそ東大を目指してはいるが(いや、まあ目指しているだけなのだが)、僕はずっと学校で一番頭が悪い人間だった。入学時の偏差値が50の中高一貫校で、偏差値35を下回る学年ビリ。それが僕だった。
「私忘れないからね、中学2年生の時の三者面談」
それは思い出したくないエピソードトップ3に入るイベント。中学2年生の時、教育に熱心な数学の先生が担任だったのだが、そこで見事にずっとビリの成績だったのだ。
「ちゃんと勉強してりゃ、こんな成績にはならんだろう」
学年ビリの成績表を叩きつけ、先生はそう言い放った。
「見ろ、英語なんて100点満点中5点だぞ! ちょっとでも勉強してりゃ、最悪赤点だけは回避できたはずだ」
英語5点、数学15点、国語18点、理科10点、社会14点。赤点どころの騒ぎじゃない、酷い点数のオンパレードだった。
「このままだと、高校進学どころか、進級だってできませんよ」
母親の方を一瞥し、先生は冷たく言い放つ。母も僕も、すっかり萎縮してしまった。
「なあ、西岡。教えてくれよ。なんで勉強しないんだ?」
先生の声は3人しかいない教室に冷たく響き渡った。声はそんなに大きくないはずなのに、その声は僕の心に突き刺さった。
「この質問、前回の面談でも聞いたよな。んで、『これからはやります』って言ったじゃねえか。なのにこの成績だろ? なんで勉強しないんだ?」
今思うと、先生も参っていたのだと思う。なぜ勉強しないのか、僕自身もわからない。ほんの少しでもやれば、必ず赤点だけは回避できるような試験で勉強しない理由がわからない。
「なあ、答えてくれよ、西岡」
先生のその声は、本当に「わからない」から質問している、そんな声色だった。
それに対して、僕はずっと隠しておくはずだった思いを、本音を、ぶちまけることにしたのだった。
「先生、僕、勉強してます。ちゃんと勉強してるけど、成績が上がらないんです」
「いやぁ……あれはないわよ。あんなこと言ったら、先生キレるの当たり前でしょ」
母親が言う。
そう、事実として、僕の「勉強してます」発言の後、先生はブチギレたのだった。
曰く、「それはポーズを取ってるだけだろう」。
曰く、「努力していれば結果が出なくてもいいと思ってるだろう」。
曰く、「お前の根性が曲がってる」。
曰く、「勉強していると本気で思っているなら、一からやり直せ」。
勉強してないと自覚しているのならまだいいが、それすら自覚していないということに、先生は怒り狂ったのだった。
「30分の予定だった三者面談が3時間になったのよね。それでその後の面談の親御さんから苦情が入って、『まだ話し足りないから明日も来い』って言われるし」
そう言えばそうだった。あの時、自分は2日連続で3時間ずつ、面談したのだった。
「あの時先生が『お母さんも来てください』って言うから、仕事休むことになって」
「流石に私も『あなたのお子さんはバカだ』と6時間も聞くのは辛いものがあったわ」
そりゃ、そうだよなぁ、と思う。
こういうのは、6年経っても恥ずかしい記憶として残り続けていくものだなと思う。
成功なんてすぐに忘れてしまうけれど、失敗して恥をかいたり、あるいは他人に迷惑をかけたことというのは心の深いところに刺さったまま残り続けてしまうものだ。
「まあでも、何が言いたいのかというと─」
母親が仕切り直してまとめに入る。色々話した上でまとめに入る、これがこの人の口癖なのだ。
「よくもまあ、あんなところから東大を目指して2浪もしたわよね。こう言ったら酷いかもだけど、あんたホントバカだったじゃない? だって万年学年ビリで、『なんで勉強しないんだ?』って言ったら『勉強してる』だもの。バカでしょ」
いや、確かにバカなのだが、母親から弄られると流石に心に来るものがある。
息子が凹んだ様子に気付いたのか、母親はからかうような口調をやめ、真面目なトーンでこう言った。
「そんなバカだったのに、よく頑張ったなってことよ」
確かにそうだ。僕は救いようのないバカだったし、キッカケがなかったらここまで走って来ていないだろう。
「そんなあんたが、師匠に会って、ここまで来れたわけでしょ。東大に受かってるかどうかは知らないけど、あんた本当に師匠に感謝しなさいよ」
師匠。久々にその言葉を聞いた気がする。
「そりゃ感謝してるよ。師匠がいなかったら、東大に3回も挑戦しようなんて思わなかった」
師匠。どん底だった僕を変えてくれた人。東大を目指すキッカケをくれた人。
「あんたどうせ、今日、暇なんでしょ? 会いに行ってきたら」
母親はそんな風に言った。暇だと決めつけるなよと思ったが、しかし確かに暇だったので、何も反論できなかった。
メールを送ると、すぐに師匠から「いいよ、いつものカフェに10時で」と返信が来た。
「いつものカフェ」というのは、僕と師匠が会う時によく使っていた、学校の近くのカフェだ。朝ご飯を食べた後、電車に乗って向かう。
高校時代は毎朝7時台の通勤通学ラッシュの電車に揺られていた。9時台となると電車は空いていて、今日は簡単に座席に座れてしまった。
ふう、と息を吐く。ここから学校まではそこそこ時間がかかる。何をしようかと考えたが、何も思いつかなかった。ずっと1分1秒を惜しんで勉強していたが、もう、そんなに勉強する必要もない。「勉強」という心の大部分を占めていた容量が一気に消えているのを自覚する。
(ま、そのかわり、合格か不合格かが死ぬほど気になるのがこの時期なんだけどね)
「大学受験」というのは、受験生にとって一つのゴールだ。小学1年生から高校3年生まで勉強してきたことのすべてを紙の試験にぶつけられる最後にして最大のチャンス。「学歴」という、人生において重要な肩書きになるであろうものを得るための唯一の機会。そしてそのために全力を注いできた受験生にとって、合格発表は天国と地獄を分ける人生のビッグイベントだ。だからだろうか。受験生はこの時期、それまでの人生を走馬灯のように思い出すという。
合格と不合格のせめぎ合いの中で、生きているとも死んでいるとも言えない時間の中で、受験生1人1人が自分の人生を振り返るのだ。
(そうだな、せっかくだし今回は、自分の人生を振り返ることに時間を使おうかな)
僕はこれまで、走り続けてきて、振り返る時間がなかった。さっき母から言われて初めて、「あの頃から比べたら、遠くに来たものだな」と気付いたくらいだ。
(「師匠に感謝しなさいよ」、か)
そういえば母のあの言葉は、本当によくわかる。僕の人生は、あの人に会うまで、どん底と呼ぶに相応しいものだったのだ。
小学生の時から頭が悪くて、成績は常にドベだった。一生懸命勉強してるつもりなのに先生からは「勉強してない」と怒られるし、中高一貫の学校で高校への進学が危ぶまれるほど成績が悪かった。
運動神経もゼロに等しく、個人競技なら負けるだけだが、チームスポーツとなると仲間の足を引っ張るだけだった。野球では一度もバットに球が当たったことがないし、守備につけば自分のポジションにボールが飛んでくるたびに点数を取られてしまった。サッカーではボールに触れることすらできない。
勉強もダメ。スポーツもダメ。他に誇れるものなど何もない。頑張っても、「人並み」にすらなれない。それどころか周りの人の足を引っ張って、「お前のせいだ」と責められて、いじめられて。僕はずっと、そんな人生を送っていたのだった。
同級生からいじめられるたびに、先生から怒られるたびに、「どうしてお前はそんなにダメなんだ」と責められている気がした。何も達成できないのも、いじめられるのも、他の誰のせいでもなく、僕のせいだと気付かされた。それをバネに頑張ろうとするけれど、それでもまったく結果が出ず、いつしかすべてを諦めていた。
世の中に絶望していた……なんて大それたものではない。ただ、自分が嫌いになったのだ。
それが、決定的になったのが、あの「勉強してます」を否定された三者面談だった。
あの時も僕は、何も変えられないし、頑張っても無駄なのだと再確認した。
3時間×2回の時間の中で、嫌というほど、自分が嫌いになったのだった。
そんな暗い思考をしている乗客がいることなどお構いなしに、電車は走る。もう1駅行けば、高校の最寄り駅に辿り着く。
(でも、「勉強してる」っていう勘違いを正してくれたのも、師匠だったな)
僕は師匠の言葉を思い出す。あれは確か、中学3年生の頃だっただろうか。
「『勉強してる』。それは嘘じゃないだろうな」
師匠は言った。「ちゃんと机に向かって、ちゃんとペンを持って、宿題も真面目にやろうと努力している。お前は確かに、ちゃんと勉強しているんだろう」
多くの大人が「ふざけんな!」と怒るようなことを言っても、師匠だけは冷静に話を聞いてくれた。
「じゃあなんでお前の成績は上がらないのか。それは別に、お前の頭が悪いからでも、お前の根性が曲がっているからでもない。お前に『意思』がないからだ」
「意思、ですか?」
「『先生が言うからやる』、『親が怒るからやる』、『周りの子がやるからやる』、お前が勉強する理由はどれも、『自分の意思』がない」
「それ、僕だけですか? 自発的に勉強しない人なんて、僕以外にもたくさんいるでしょ」
「ああ、もちろん。だけど大抵の場合は、『赤点を取りたくない』とか『先生や親から怒られたくない』とか、後ろ向きでも何か『自分の意思』がどこかに存在する。だが、お前には『自分の意思』がない。前向きな理由も後ろ向きな理由もない。怒られたくないとも思ってないし、赤点を回避したいとも思ってない。完全に受け身で、自分から何かが欲しいという意思がない」
僕は言葉に詰まった。
「意思があれば、『どうやって赤点を回避するか』と考え始める。勉強したくないなら、『いかに効率的に成績を上げるか』を考え始める。でもお前は、先生や親が言うから机に向かうポーズをしているだけ。自分から何も摑もうとしていない。それじゃ成績は上がらないさ」
確かにそうだった。僕は、先生が言うから勉強して、母親が言うから勉強して、ただそれだけのことをしているだけだった。
本当なら、「高校に入学できるくらいの成績を上げなければならない」とか「将来のことを考えて勉強しなければならない」とか、色々自分で考えて行動しなければならないところを、僕は全部放棄していたのだった。
「お前の意思はどこにある? 西岡壱誠」
師匠は僕の名前を呼んだ。
「お前は一体何がしたい? あるいは、何をしたくない? それがない状態で勉強しても、お前はずっと今のままだ」
僕は、一体何をしたいんだろう?
「それを聞かせてくれよ。俺は別にお前にどうなって欲しいわけでもない。成績を上げて欲しいとも、立派な人間になって欲しいとも思っていない。お前が好きなように生きればいい」
続きは本書でお楽しみください。