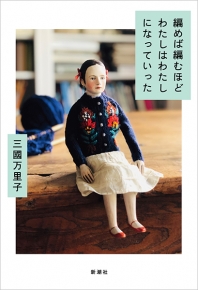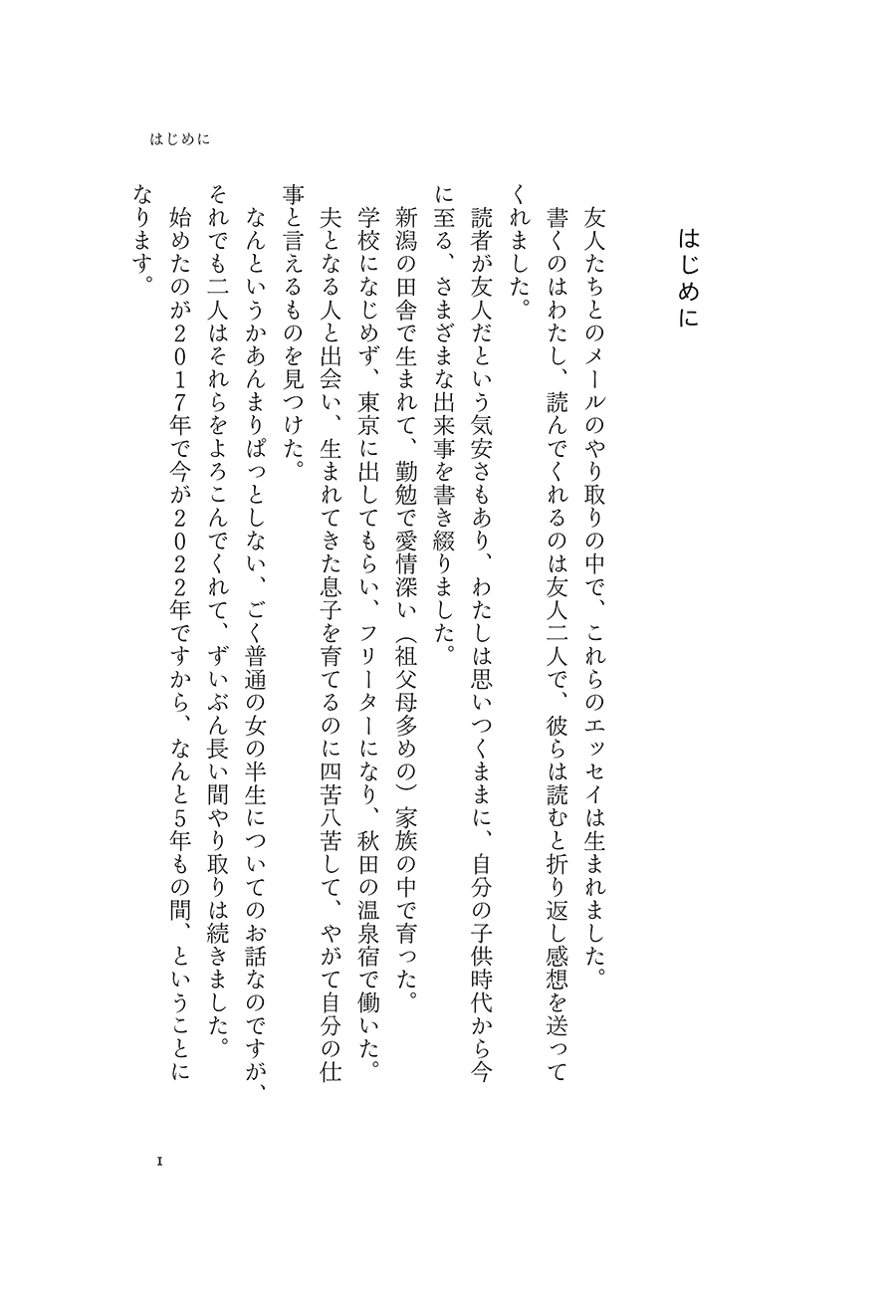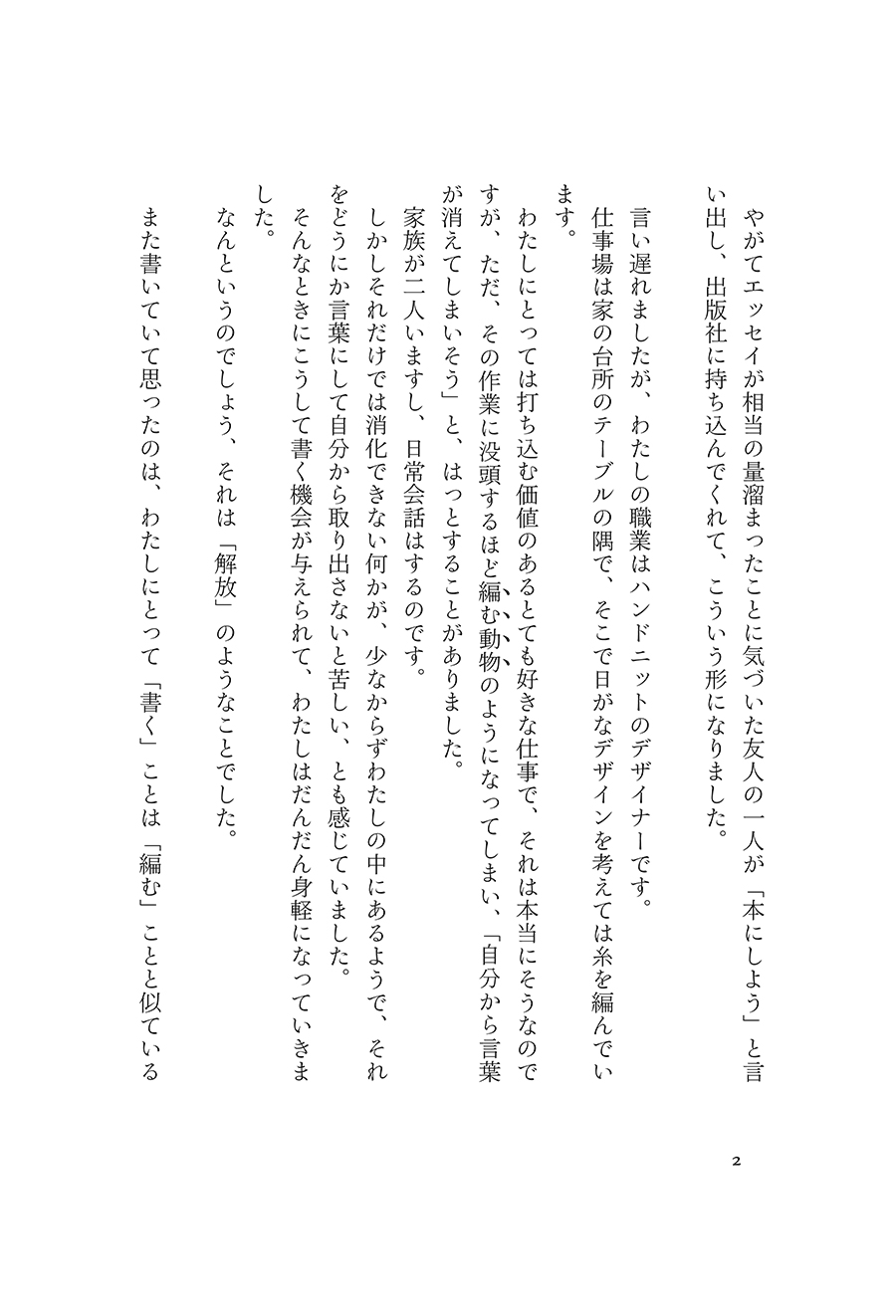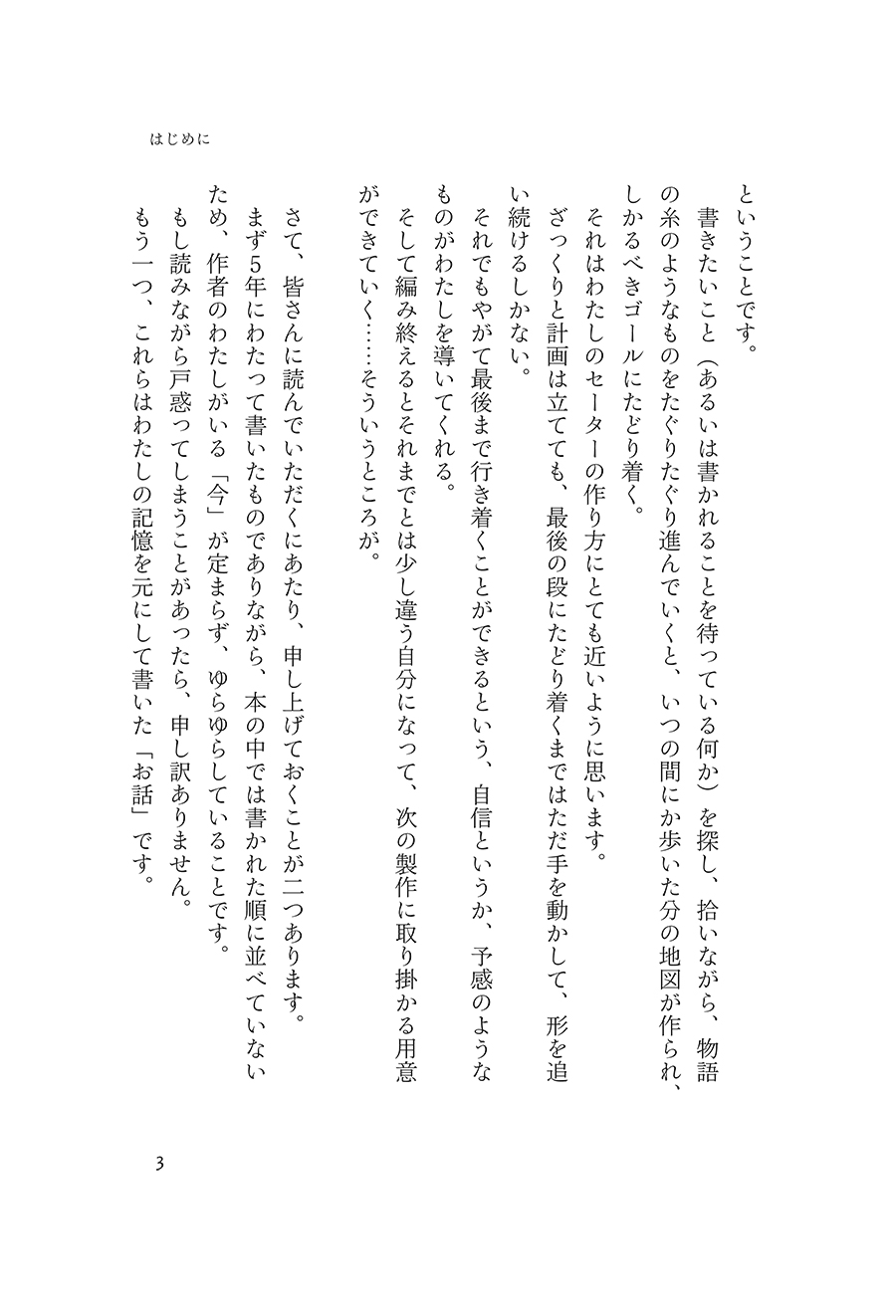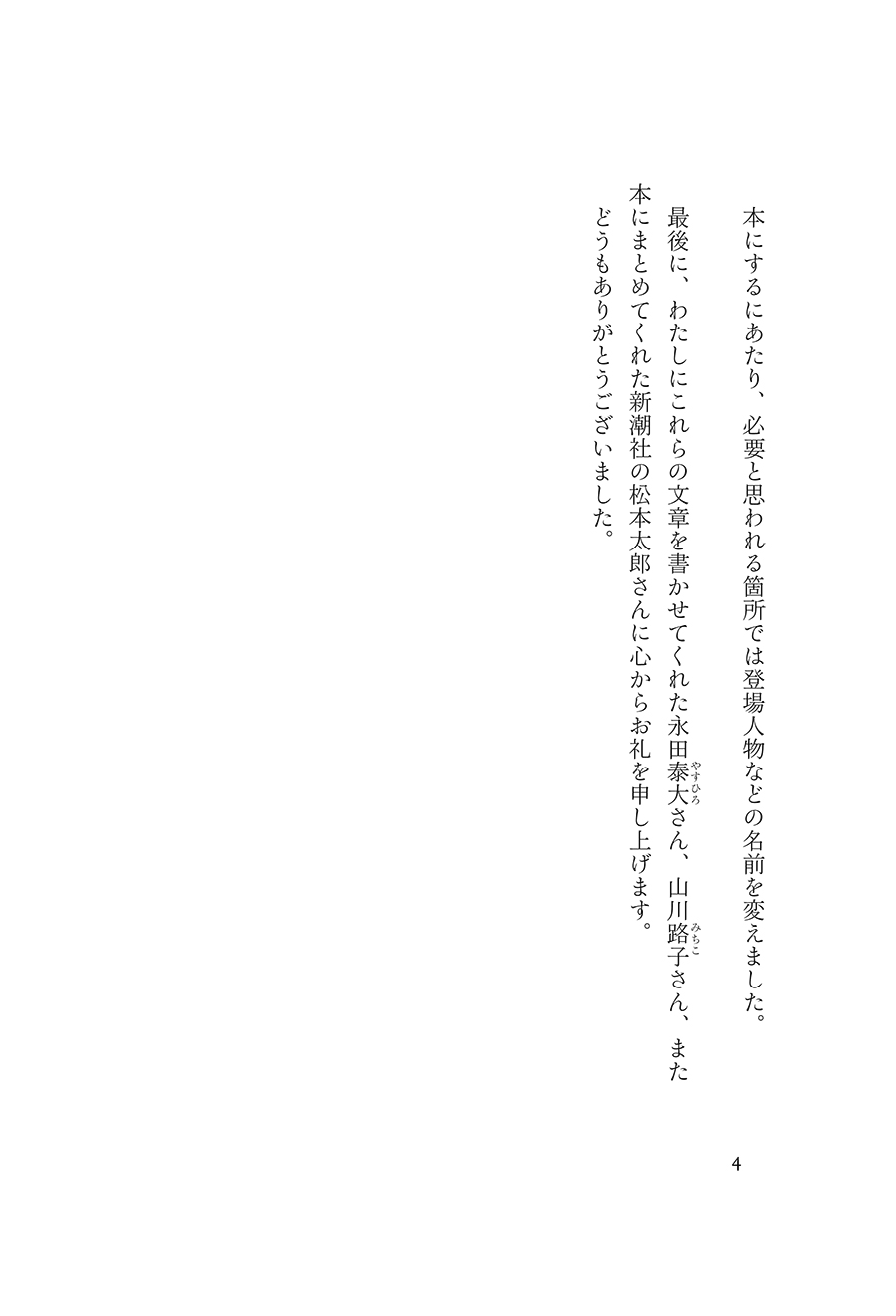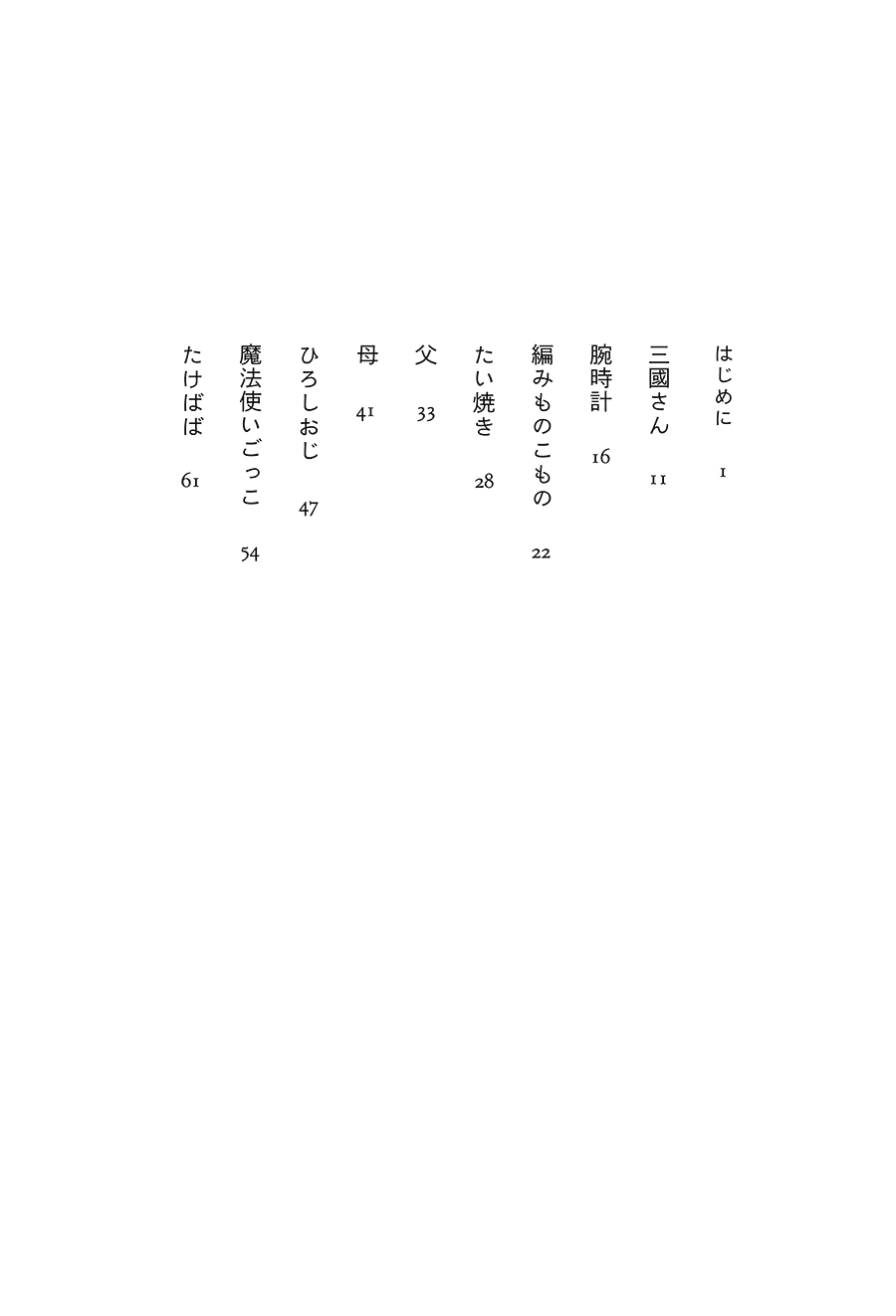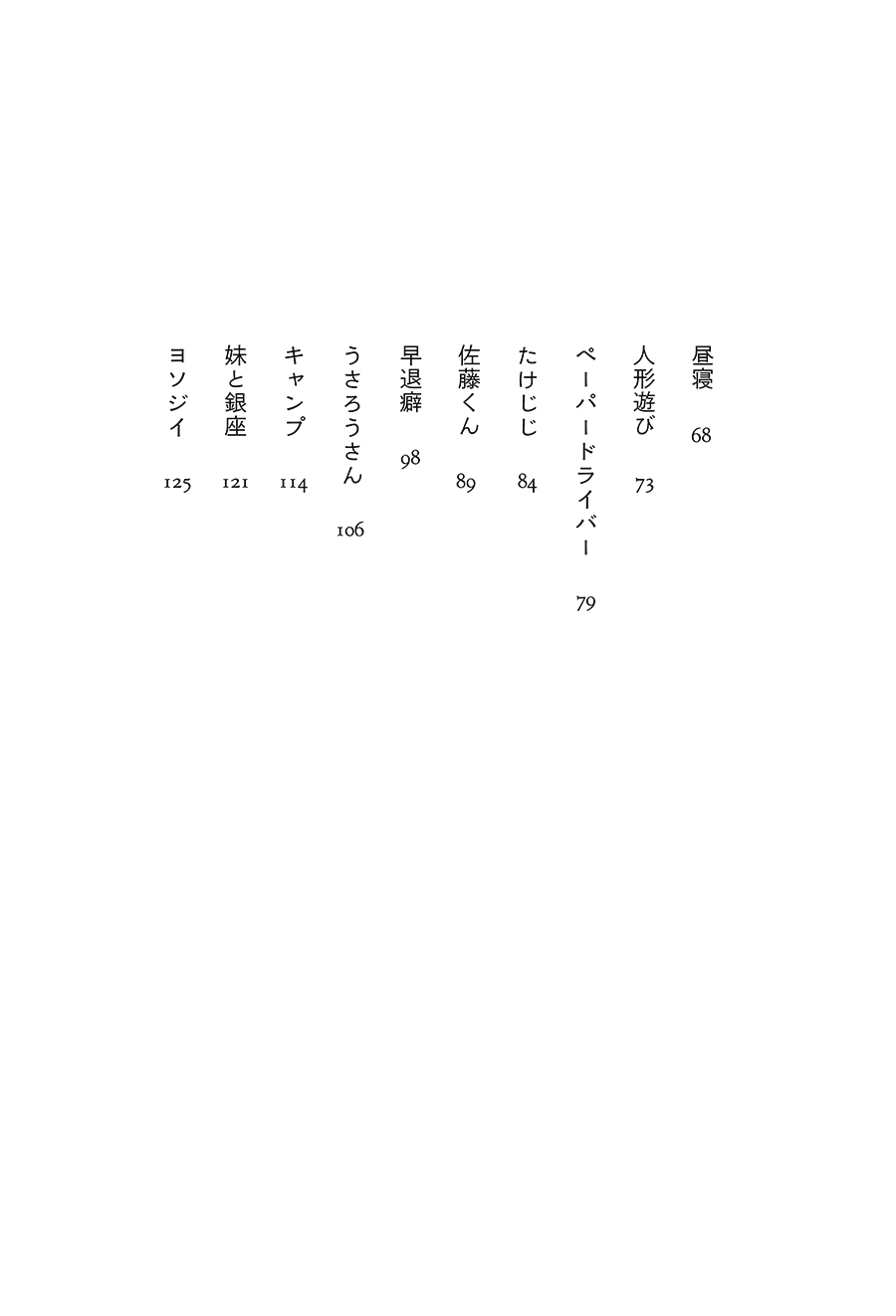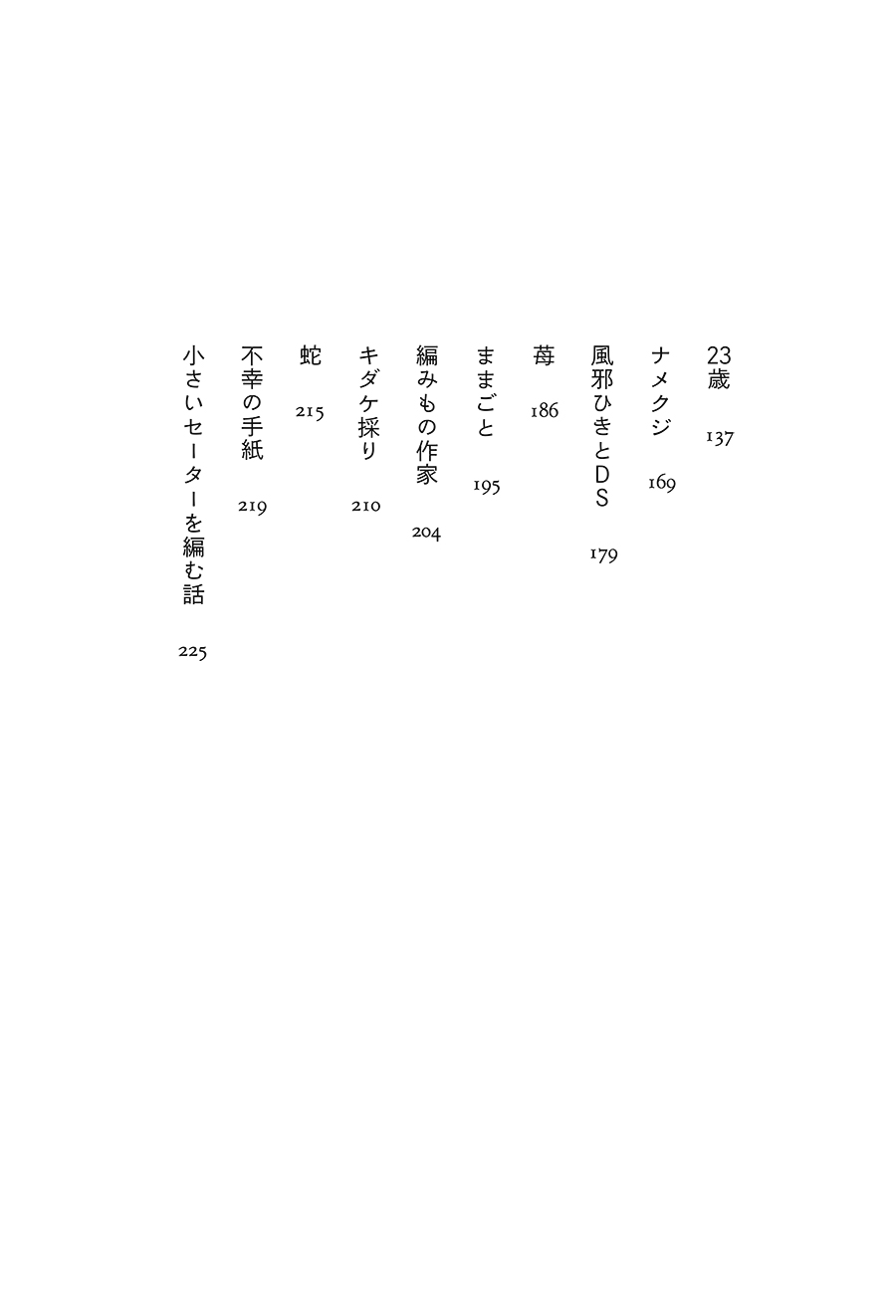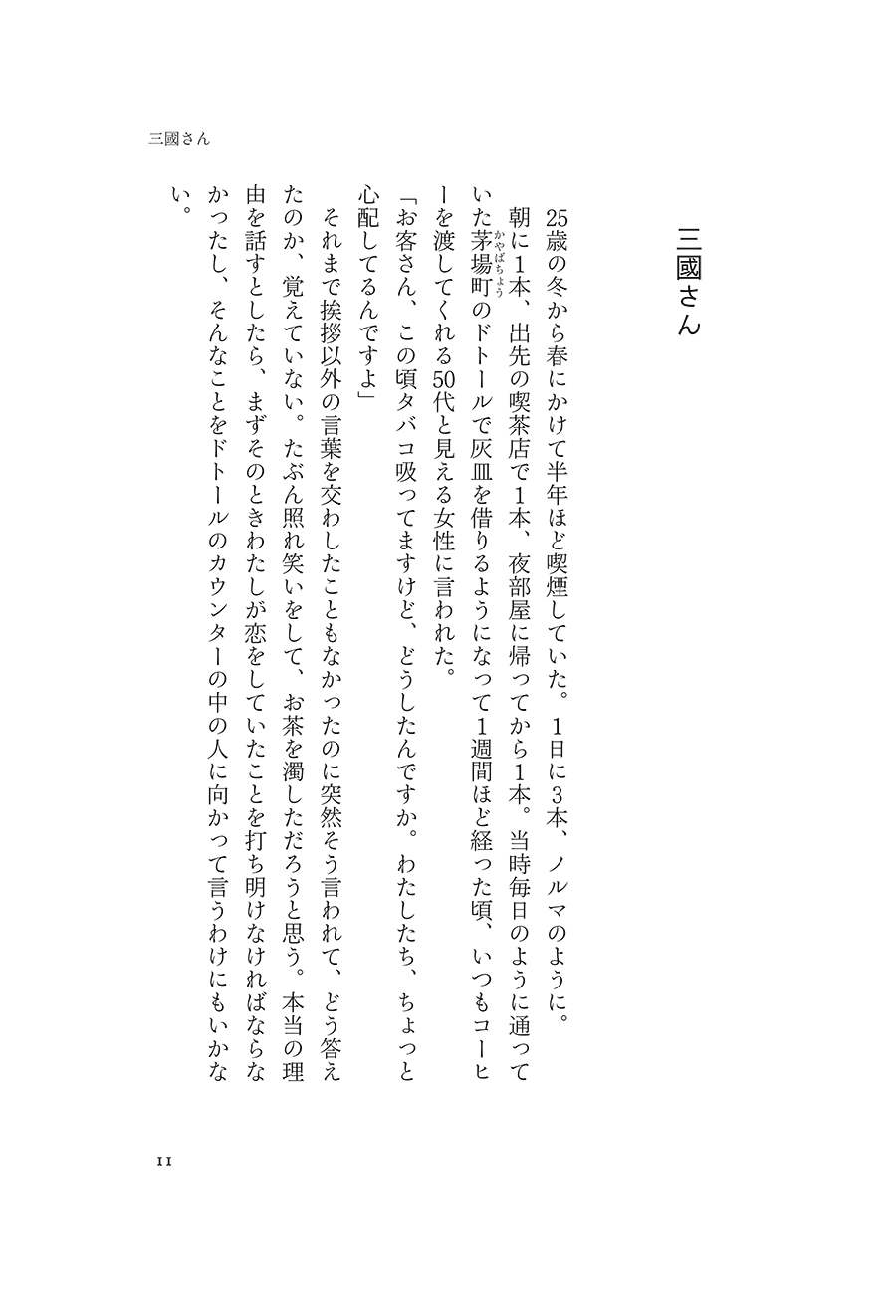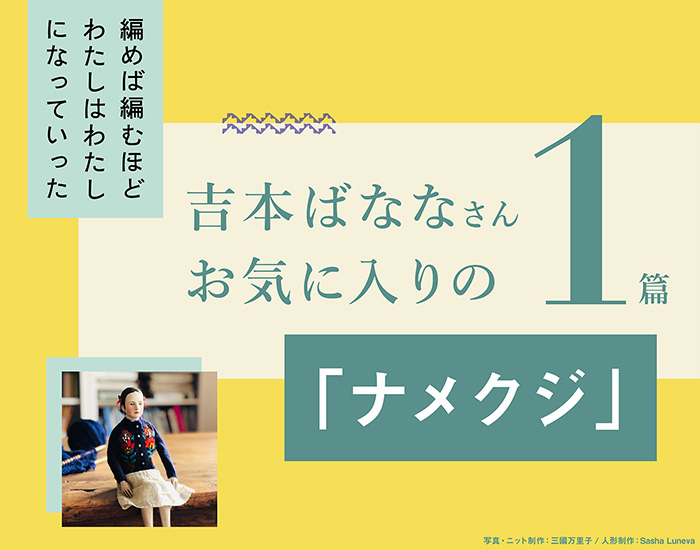
ナメクジ
我が家でいちばん遅く夕食をとるのは大学生の息子だ。
11時近くに帰ってきてまずシャワーを浴び、パジャマ姿で自分の味噌汁を温め、和室のちゃぶ台に用意されたおかずと、帰宅時間に炊き上がるように炊飯器にセットされたご飯を食べる。食べ終わるとゆっくり食休みをし、夜中の1時過ぎ頃、茶碗を洗ってから自室に引き上げる。
わたしはうとうと布団の中で水と食器の立てる音を聞く。寝床がキッチンのテーブルと本棚の狭い隙間に敷いてあり、チャポチャポというその音を聞きながら眠るのがうれしい。音が止むのに気づくことはほとんどなく、いつの間にか眠り込んでいる。
そういえば昨日はわたしが炊飯器のタイマーのセットを忘れ、息子が帰ってから急遽、鍋でご飯を炊いた。時間がかかった分お腹が空いたということもあるのだろう、
「うまいです、鍋で炊いたご飯」
と息子はお代わりしながら真顔で報告した。
茶碗を洗いながらも、息子は上機嫌で布団の中のわたしに向かって喋り続ける。
「鍋炊きご飯、ああ鍋炊きご飯、鍋炊きご飯……自由律俳句です」
とかなんとか。馬鹿だね、今時ご飯くらいでこんなに喜ぶなんて。わたしは適当に相槌を打ちながら、息子がキッチンを去る前に眠りに落ちた。
今朝目覚めてふと思い出したのは「ナメクジ」のことだ。
そういえばこのマンションに越してからもうずっと、ナメクジを見ていない。ここは1階なのに、どこにも隙間がないからだね。鉄筋コンクリートってすごいもんだ。
春日部で住んでいたのは掘っ立て小屋のような隙間だらけの一軒家で、あったかい時期はやたらナメクジが出た。どこからやってくるのかわからないけれど、風呂場やキッチンの床に1匹、2匹と現れたと思うと、そのうち茶の間の畳の上までキラキラした足跡を残しながら這っているのを見つけてギョッとする。ナメクジってなんであんなにかわいくないんだろう? カタツムリは、かわいい。ああして背中に丸い貝殻みたいのを載せれば、全然違うのに。
夫はナメクジを目の敵にした。見つけるとすぐ割り箸を持ってきてつまみ上げ、水洗トイレに捨てて流す。まだ3歳の息子はそれを見て、嘆いた。かわいそうだ、助けたいというのだ。とはいえ息子は臆病で、自分でナメクジに触ろうとはしない。仕方なしに、わたしがティッシュペーパー越しにそれをそっと持ち上げ、玄関の外の紫陽花の葉にのせると、一部始終を見届けた息子は納得顔で家に戻った。
その日からナメクジを救出する日々が始まった。
日がな家にいる息子とわたしにとって、それはちょうどいいイベントにもなった。ナメクジを見つけると息子はわたしに「いた!」と報告する。はいはい、とわたしがティッシュを掴んで教えられた場所に向かう。
昨日は1匹助けた。今日は2匹。
わたしはそのうちにもうティッシュを必要としなくなり、指先でそっとつまみ上げるコツも会得した。触った後は念入りに手を洗った。ネバネバが結構強烈なのだ。強くてデリケートな粘膜でできた、固体と液体の間のような生き物だった。
いっぱい助けたよねえ。
何匹くらいかな?
最初の救出からふた月ほどたったある日、息子と玄関の外にしゃがみながら、顔を見合わせて考え込んだ。何十匹もだよねえ……。ふとある思いつきがわたしの口からこぼれた。
「あのさ、せいちゃん知ってる? ナメクジのじょうおうさまのこと」
「知らない」
「ナメクジをさ、いっぱい助けたじゃん、せいちゃんとお母さんで」
「うん」
「50匹くらいだと思うんだよ、今までのを合わせると」
「うん」
「それでさ……。99匹助けるじゃん、いつかは」
「うん」
「100匹目を助けた時に、じょうおうさまが現れるんだよ、ナメクジの」
「ええ!?」
息子はぴょんと立ち上がる。
「じょうおうさまが!?」
「そう。ナメクジのじょうおうさまが来て、言うの。『わたしの国のナメクジたちをよくぞ助けてくれました。お礼に魔法でせいちゃんの願いをなんでも叶えてあげます』って」
「おー!」
息子は有無もなく、わたしのうそ話を信じた。次の日からは、ナメクジの救助に弾みがついた。見つけると一目散に、息子はわたしの元に飛んでくる。助けると、昨日までの数に今日の分を足し算する。
じょうおうさまに何をお願いしようか。ナメクジを葉っぱの上に置きながら、わたしたちは話し合った。乗り物が好きな息子は「新幹線の700系に乗りたい」と言った。また次の日には「ミニカーのガシャポンで、持っていないのを出してもらう」と。いいねえ。すごくいいね。わたしは心の中にナメクジの女王の姿を描き、息子に説明した。
「普通のナメクジよりちょっとだけ大きいんだよ。堂々と立派でね、つやつやしてる。頭には冠を載せているの。透き通った光でできた虹色の、小さい冠」
側で聞いていた夫は鼻で笑った。なんのこっちゃ、ついてけねえ。
しかし息子とわたしの遊びを禁じはしなかった。息子がいない時には相変わらず、せっせとナメクジをトイレに流していたが。
ナメクジの女王は降臨したか?
しなかった。少なくとも息子もわたしもその姿を見ていない。
その年の晩秋、ナメクジの姿がめっきり少なくなった頃、息子が幼稚園に入園し、ナメクジを助ける遊びそのものがいつの間にか消えたからだ。春でなく秋に入園したのにはわけがあった。
息子はその年の春には言葉をまだうまく話せなかった。
うまく、というのは、「人にわかるような発音で」ということだ。息子の言葉には子音が抜けていた。使うのは「あいうえお」という母音と「ん」だけ。たとえば息子はわたしのことを「おあーあん」と呼び、ナメクジの女王さまのことは「あえういおおうおうああ」と発音した。これが理由で市の保育園入園の審査に引っかかり、入園の時期が遅れたのだった。
発音のことをおいても、息子が「話す」に至るまでには色々とあった。時間をさらに遡る。1歳を過ぎ、ふつう赤ん坊が「パパ」「ママ」「まんま」といった短い言葉を言い始める時期に、息子が発した音は「あーあー」くらいだった。そのかわり、口から出る音に文字が対応していることはわかっていて、「あいうえお」が一文字ずつ印刷してある積み木を並べて言葉を作り、わたしたちに言いたいことを伝えた。
「くるま」
「こはん(ご飯)」
「みふい(ミッフィー)」などなど。
その頃、夕方になると息子を抱き上げて、よく散歩した。
見晴らしの良い道路に出ると、彼はぐるっと頭をめぐらし、小さい人差し指を薄水色の空に突きつける。わたしはその指先をたどり、月が出たことを知る。
「お月さま出たね」
息子はうれしいらしく、体を上下に揺する。
さらにまた、息子は人差し指を空の違う方向に向ける。その先には明るく灯った点がある。金星を見つけたのだ。
「お星さまも出たね」
息子は激しく体を上下に揺らす。
言葉の代わりに、息子はこんなふうに気持ちを伝えた。
やがて息子は赤ん坊から幼児になったが、しばらくの間は、泣いたり笑ったりということ以外で意味のある音を口から出すことはなかった。ジェスチャーと「あいうえお」の積み木でだいたいの用は足せた。それでもわたしは時々途方にくれるような気持ちになった。
何を考えてるんだろうね。知りたいなあ。
切ないような思いで息子を眺めた。
知りたい。
きっとこの子の頭の中では毎日毎日、いろんなことが起きてるんだろうに。
変化が訪れたのは3歳になる頃だった。
ある日、部屋で遊んでいる息子が、歌うような抑揚で何か言っている。
「あん、あん、あん〜」振り向くとテレビに「アンパンマン」が映っていた。うろたえた。この現場を一緒に見てくれる証人が欲しかった。とはいえ家にはわたしと息子の二人きりしかいない。わたしは幻かもしれない「あん、あん、あん」をこの世に定着させなければ、と、息子に駆け寄って確認した。
せいちゃん、言えたね、アンパンマンだよね。
息子は上機嫌で「あん、あん、あん〜〜」と、繰り返した。
それから息子のボキャブラリーは日毎に増え、ほぼ同時に言葉と言葉を組み立ててしゃべるようになった。なぜか「母音だけ」でしゃべるので、よその人にはなかなか伝わらないが、それでもわたしは息子から出る言葉が聞けることが、心からうれしかった。
おかしなことに、いざ話し始めると、息子のおしゃべりはどこか書き言葉のようだった。言葉を話すための「足し」になるかもしれない、くらいの気持ちで毎日絵本を読んで聞かせていたのが、思わぬ形で影響したのかもしれない。おそらくあのナメクジの話も、それらの絵本を読むうちにわたしの中で育った物語だったのだろうという気がする。
二人でナメクジを逃がしていたのはこの頃だった。
4歳の誕生日を過ぎて数ヶ月経つと、息子の発音には少しずつ「子音」が足されていった。さらに、息子の未発達な言葉を受け入れてくれる幼稚園を見つけて入園し、その生活に馴染む頃には、いっぱしに口の達者な子供になり、少し前に発音に難があったことも、いつの間にか家族の間の笑い話の一つになった。
そんなことを思い出しながら、さっき、大学に行く支度をしている息子に聞いてみた。
「ナメクジの女王のこと、覚えてる?」
「ええと、あれでしょ、あの100匹助けたら……ってやつ」
「そう。よく覚えてたね」
「うん」
小さい頃の出来事はたいがい忘れてしまっている息子にしては珍しいことだ。どんなふうにそれが彼の中に残っているのか、もっと聞いてみようかとも思ったが、言葉にしてしまうと息子の中の記憶が変形してしまう気がして、やめた。わたしは話題を変えた。
「今日の君の弁当なんだけど、緑の野菜がなくてさ。全体に茶色くてすまん」
息子はテーブルに用意された地味な肉じゃが弁当に目をやり、アメリカ人のように肩をすくめて「マーベラス」とつぶやいた。そして蓋をしてバッグにしまうと、学校に向かった。
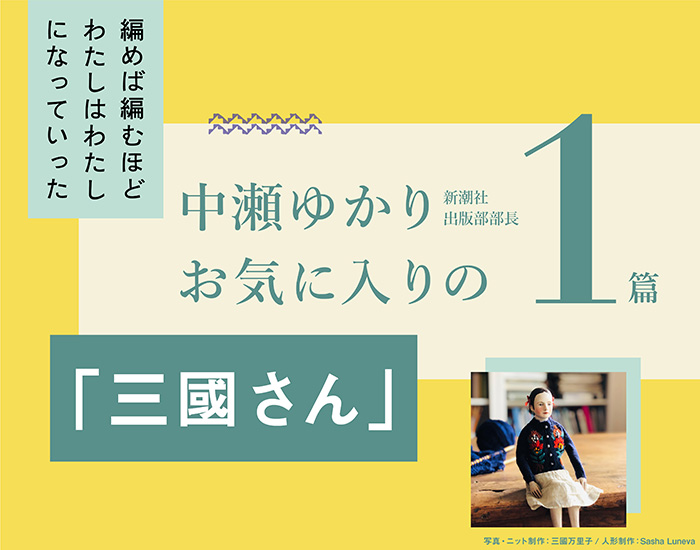
三國さん
25歳の冬から春にかけて半年ほど喫煙していた。1日に3本、ノルマのように。
朝に1本、出先の喫茶店で1本、夜部屋に帰ってから1本。当時毎日のように通っていた
「お客さん、この頃タバコ吸ってますけど、どうしたんですか。わたしたち、ちょっと心配してるんですよ」
それまで挨拶以外の言葉を交わしたこともなかったのに突然そう言われて、どう答えたのか、覚えていない。たぶん照れ笑いをして、お茶を濁しただろうと思う。本当の理由を話すとしたら、まずその時わたしが恋をしていたことを打ち明けなければならなかったし、そんなことをドトールのカウンターの中の人に向かって言うわけにもいかなかった。
それにしても、喫煙できる場所としてある喫茶店でタバコを吸ったからといって心配されるなんて、わたしはよほどタバコというものが似合わなかったのだろうと思う。
実を言うと、わたし自身大してその味が好きというわけではなかった。だとしたら、なぜわたしはタバコを吸うことになったのか。発端は、好きになった人が、ひどくむっつりした男だということにあった。その人とはアルバイト先が一緒だった。
会えるのは朝、挨拶するときだけで、「おはようございます」とこちらから声をかけると、目線を合わせずに「……ます」とボソボソッと答える。少し勇気を出して「雨が降りそうですね」と話しかけても一瞬空を見上げて、無言でそっぽを向いてしまう。
なんでそんな人のことを自分は好きになったのか。その理由を腑分けするように明快に説明できたとしたら、それはきっと恋ではないと思う。その人のことを、わたしはほとんど何も知らなかった。名前は三國さんというらしい。クラシック音楽をやっている人らしい。アルバイト仲間から聞き出せたのはそれくらいで、教えてくれた仲間にしてもあの人はよくわからないよ、ということだった。なんかちょっとこわいよね、無口だし、と。
それでも毎朝挨拶するうちにわかったことがあった。
三國さんの胸のポケットにはいつもタバコとライターが入っている。どんな味がするんだろう。なんていう銘柄だろう。
知りたい。
でもあの人に「タバコは何吸ってるんですか」なんて、聞けるだろうか。だめだめ、無理だ。だってこないだ「今日これから晴れるでしょうかね」って声をかけたら、「知らない」って言われた。「知らない」だよ? 「晴れそうだね」とか、せめて「どうかな」とかでもなくて。
別のときには、「きのう三國さんが夢に出てきたんですよ」って、すごい勇気を出して言ったのに、ボソッと「そりゃあよかった」って。
ひどい。
わたしに興味がないとしても、言い方ってものがあると思う。わたしはすでに傷だらけだ。できればもう痛い目に遭わずにタバコの銘柄が知りたい。そこでわたしは一計を案じ、行動に移した。まず朝、コンビニに行き、レジの上に並ぶすべてのタバコを1箱ずつ買った。20〜30箱はあったと思う。次に、仕事場で三國さんを見つけると、その大きく膨らんだレジ袋を差し出し、
「好きなの一つあげます、タバコを吸う人達みんなにあげてるの。クリスマスだから」
そう一息に言って、彼の動向を見守った。彼は案外素直にありがとうと言い、パッケージを一つつまみあげた。
キャスター・マイルドの5mg。
わたしは確認するとその場を立ち去り、休憩室に行って、たむろしていた仕事仲間に残りのタバコを全部あげてしまった。
その日の帰り、コンビニで、改めてキャスター・マイルド1箱と、ライターを1本買った。自分の部屋で、台所のシンクに向かって1本火をつけてみる。
吸って、口から入ってくるのが煙だけ、というのはおかしな感覚だった。
こんなものが好きなのか、三國さん。
煙はわたしの肺から血管に入って、全身をめぐる。これは、体に悪いんだろうな。でも三國さんの体に入ってるのと、同じ毒だ。そう考えるとうれしい。
わたしはいま少し三國さんになろうとしている。
そういうわけで、わたしはそれから自分の中の三國さんを確認するように、律儀に日に3本、タバコを吸うようになったのだ。
行きがかり上、タバコをやめた理由も手短かに書いておく。一人の男性を知りたくて、さらにはその人自身に「なりたくて」始めたタバコだったが、その必要がなくなったのだ。半年後、わたしは三國さんと結婚した。もう目を開ければそこに彼はいたし、わたしは「単なる自分自身」としてあることの安らかさを再び見い出して、いつのまにかタバコを吸う習慣を忘れていったのだった。
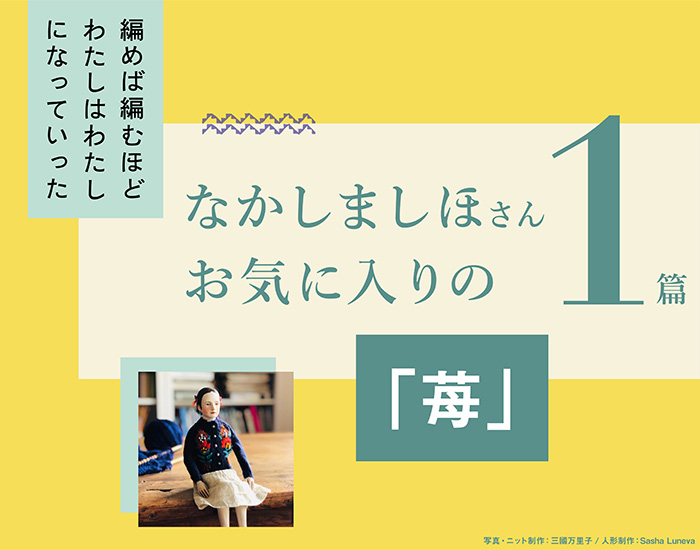
苺
その二つ年下の女の子に出会ったのは、わたしが小学4年の春だった。
もう名前を思い出せないから、仮にさっちゃんと呼ぶ。
さっちゃんとはその春の間、放課後に時々遊んだ。どういう経緯で知り合ったのかもはっきりしない。わたしたちが通っていたのは1学年20人前後のこぢんまりした小学校ではあったが、学年も登校班も違う子供と親しくなるなんてことはふだんのわたしにはまずないことだった。考えられる可能性としては、おそらく、いつも一緒に遊ぶ友達のうちの誰かにその子の家に連れて行かれたのが始まりだろうと思う。
その子とわたしには一つ共通点があった。わたしたちはそれぞれに「転校生」だった。
わたしはさっちゃんと出会う2年前に、父方の祖父母の家から母方の祖父母の家に、会社員をしていた父、母、一つ年下の妹と越してきていた。母が婚家の仕事を手伝ううちに体をこわしてしまい、その療養のために、隣村にある母の実家に4人で居候することになったのだ。元いた学校と、転校先の学校はほんの5、6キロしか離れていなかったが、転校先の方が、よりいなかで、農家が多かった。
元いた地区が、勤め人の家や商家が比較的多いことに比べて、母の実家のあたりは大体どのうちも畑か田んぼをやっていた。郵便局に勤める
学校帰りに畑中を突っ切って家に向かうと、たいていどこかの畝の中に、うずくまるようにして草むしりをする祖母がいた。彼女はわたしを見つけるとわざと素っ頓狂な声で言う。
「あらリボンちゃん、おかえりなの?」
わたしはうなずく。
わたしはもちろん「リボンちゃん」ではない。
祖母はわたしのことが好きだからそう呼ぶのだと、わたしは知っていた。彼女は妹のことも同じく「リボンちゃん」と呼んでいた。妹もわたしと同様に、祖母に可愛がられていた。
祖母の家族への愛は畑という形で表された。
彼女は農協で手に入る最も良い苗を選び、最善と信じる肥料を施した。深く耕し、畝を形良く整え、作物に応じてマルチ(畝の覆い)を張った。彼女はベストを尽くした。わたしたち家族に可能な限りおいしい作物を食べさせることが祖母の何よりの張り合いであることをわたしたちは知っていた。
その畑で穫れるものでわたしが一番楽しみにしていたのは、5月に熟す苺だった。
祖母の作る苺をどう言えばいいだろう。姿形からして、絵に描いたような苺とはかけ離れている。
川の上流の石ころのようにごつごつと不揃いで、大きさもビー玉くらいの小さいものから子供のこぶし大まで、様々だった。そして素晴らしく、いい香りがした。まるで苺が安心して深々と呼吸しているようだった。
どれも甘かったが、時々なにこれ、というくらいに凝縮した、天国みたいな味のが混じっていた。
おいしく食べるのにいちばん大事なのは、洗ったりしないことだ。
もちろん冷蔵庫にも入れない。
日光に温まっているのを、摘みながら食べる。
祖母は農薬を使わなかったから、蟻がかじった跡もあり、時には実の中に蟻が混じっていることもある。
間違ってそれを噛んでしまい訴えると、母は笑って「抵抗力がつくよ」と言った。父は「調味料」と言った。それでわたしはもう砂だろうが蟻だろうが、あまり気にしなくなった。
苺を摘むのはわたしの権利だった。
ここの家の子だから、好きなだけ食べていい。
わたしが食べると、おばあちゃんもよろこぶ。
こうしてわたしはその季節の間、学校帰りにはランドセルを背負ったまま苺畑にしゃがみ込み、満足するまで食べてから、家に戻るようになった。
ある日さっちゃんと帰り道で一緒になった。
わたしは自分の家を教えるついでに、苺畑にさっちゃんを招いた。
毎日ここで苺を食べてから、家に帰るんだ。
さっちゃんは、いいなあ、と言った。
さっちゃんのうちに苺畑はないらしい。
あまり考えるまでもなく、わたしは言った。
それならさ、さっちゃんも好きな時にここに来て食べていいよ。
さっちゃんはうれしそうだった。
いいの、ほんとに?
いいよ、わたしの友達だから。
ここで言っておくと、わたしは誰にでもそんなことを言うわけではない。
さらには、わたしはさっちゃんのことが他の子より特別に好きなわけでもなかった。ただ、彼女にはわたしが知っている匂いがした。転校生という生き物が発する匂い。
それはさっちゃんの、周りを窺うような、ぎこちない物腰から立ち上っていた。さっちゃんを陰で「うそつき」と呼ぶ女の子もいた。だからまりこちゃんも気をつけたほうがいいよ、騙されないように。へえ、わかった、とわたしは機械的に返事した。
そして2年前に自分が転校してきた時、周りの子供に対していくつかの嘘をついたことを思い出した。
わたしは前いた学校では、全然友達がいなかったの。
だからこっちの学校に越してきて、やっと友達ができそうでうれしい。
たとえばそんな嘘だった。
他愛のない、害のないものではあった。
それは新しい場所で自分を作っていくために、演じながら半ば無意識についた嘘だった。
しかし、口から出した後で、嘘は自覚されて、異物として心の中に残る。わたしは次第に無垢ではなくなった。言い訳になるが、その頃わたしは味方を作ることが必要だった。
急務だった、と言ってもいい。
新しいクラスに二人、わたしをターゲットに意地悪をする女の子たちがいて、ある日買ったばかりの消しゴムが消えたと思ったら、次の日に真っ黒になって床に転がっていたりした。そんな経験は初めてだった。
混乱した。怖かった。
担任の先生は、何かというとすぐ怒り出すおばあさんで、頼る気持ちにはならなかった。それでも他の子供たちはこだわりなく無頓着で、休み時間や放課後に遊ぶうちに友達が何人かできた。それはわたしが努力して勝ち得たものだった。
全員でなくてもいい、数人で十分。
そうこうするうちにいつしか水のpHが変わるように少しずつ子供達の意識が調整されて、クラスが「わたしの存在込み」の場所になっていった。嘘もつかずにのうのうと暮らしていけるのならば、それに越したことはない。でもさっちゃんはこないだ越してきたばっかりで、きっとわたしと同じような苦労をしているのだろう。
「同族」のよしみといえばいいのか、なんというか、そういうわけでわたしは祖母の苺畑をさっちゃんと分け合おうと思ったのだ。
苺は春の
口に含めば、さっちゃんは苺になる。
甘く、やわらかく、いい匂いになる。
世界に溶け込んで、その瞬間からもうずっと、ここに居ていいんだ。
さっちゃんを苺畑に招いた2日後の夕方、台所にいる母に「まりちゃん、ちょっと」と呼ばれた。母の隣には祖母がいた。
「おばあちゃんが今日、畑で苺を食べてる女の子を見つけたんだって。それで『あんたどこの子だね?』って聞いたら、こないだまりちゃんが連れてきた、あの引越してきた子だって。その子、『まりこちゃんが好きな時に苺を食べていいって言ったから食べてるんだ』って言ったって。そうなの?」
わたしは頷いた。
母と祖母は顔を見合わせた。
わたしは「それ」が何かまずいことだという可能性を、その時まで考えていなかった。
「だめだった?」
祖母はわたしを見てきっぱり言った。
「いい。まりちゃんがそう約束したんなら、いいよ」
その後さっちゃんとは数回遊び、やがて自然と疎遠になった。
わたしはその2年後にまた引越しをして、再度新しい場所に自分を慣らそうと試みた。しかしその時、12歳になっていたわたしは、うまく自分を「演じる」ことができなかった。
自意識が強くなる時期に入りかけていたせいかもしれない。
ここは、この舞台は、どういう「設定」のもとに動いているのだろう?
そんなことを意識しすぎて、人前でぎくしゃくするようになった。
人との距離をどう取ればいいかわからない。
自分の皮膚が薄く薄くなったような感覚だった。
何に触れても痛い。
その春にも苺は相変わらずおいしかったに違いないが、わたしの心はいつもヒリヒリとして、この世の良いものを、そのままの姿で受け入れることができなくなってしまった。
「おばさんになったら、もっと鈍感になって、生きることが簡単になるかな。でもそうしたら、生きてるって言えるかな。そうして鈍感になってまで生きる意味なんて、あるかな」
わたしは子供部屋で日記に書いた。
その答えを言おうとして、わたしが今、ここにいる。
鈍感になったか、ということについては、まあそうだね、と言っておく。
生きやすくなったか、という問いへの答えも同じ。
そしてありがたいことに、それでも生きる意味があるか、という問いに対してわたしは「うん」と言うことができる。その理由は、ひとことでは言えない。
生きてみないとわからないことばかりだったし、知らないことを知ることによって強くなった。それを鈍感と呼ぶなら呼んでもいい。
でもそのおかげで今は人としっかり関わりたいと思えるし、ヒリヒリを押さえ込んで、意志の力で少しは周りの状況を変えていける。だからわたしはこれからも生きて、世界の中に入っていきたいと思う。というようなことは、言えるかもしれない。
不思議なことに、仕事を始めてから仲良くなる人たちは、転校を経験してきた人たちが多いよ。なんでだろうね。もう転校生の匂いなんて、わたしたちの体から消えてしまったはずだけど。