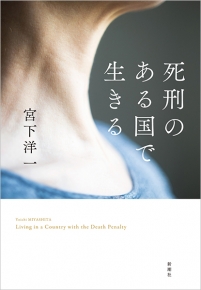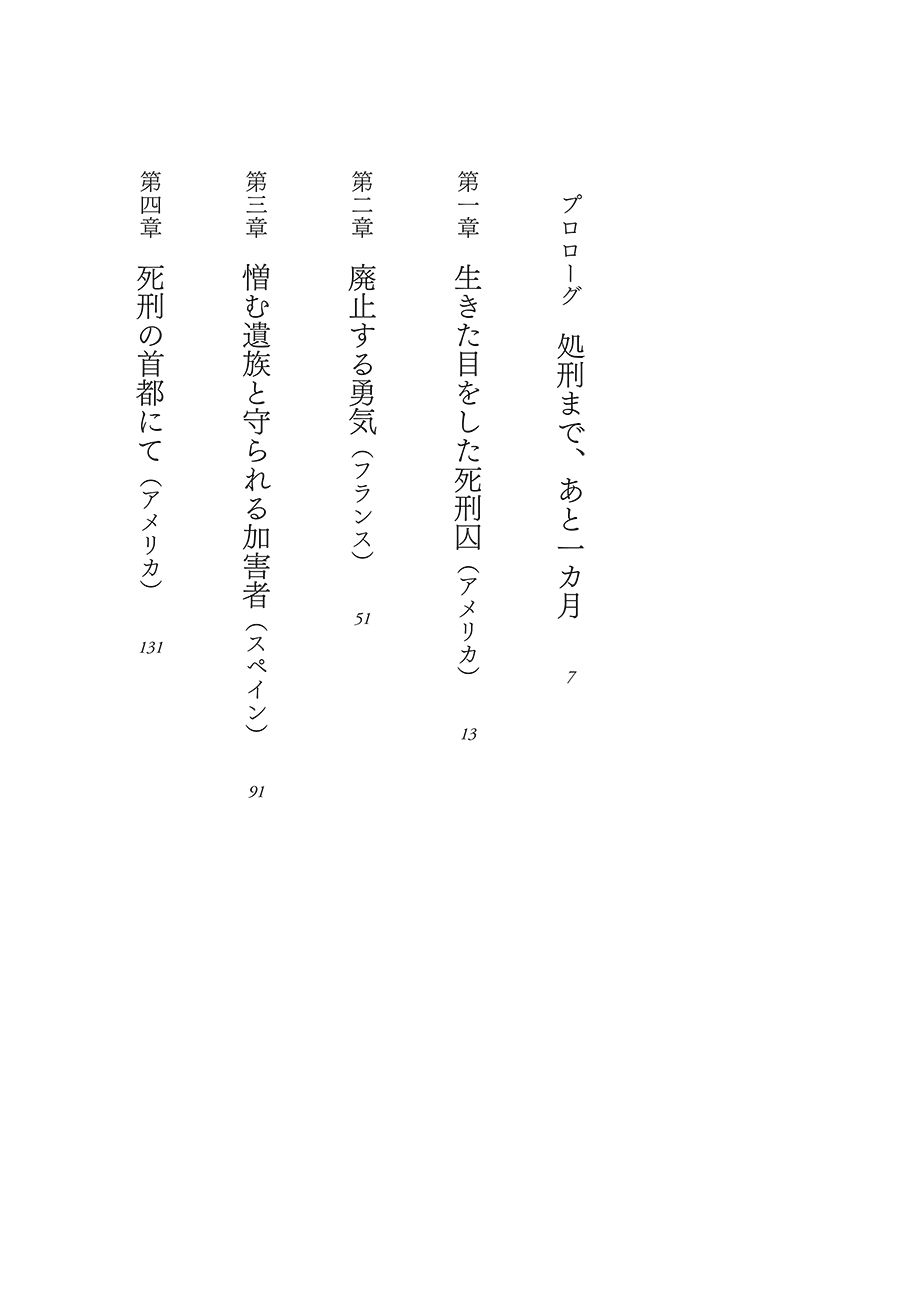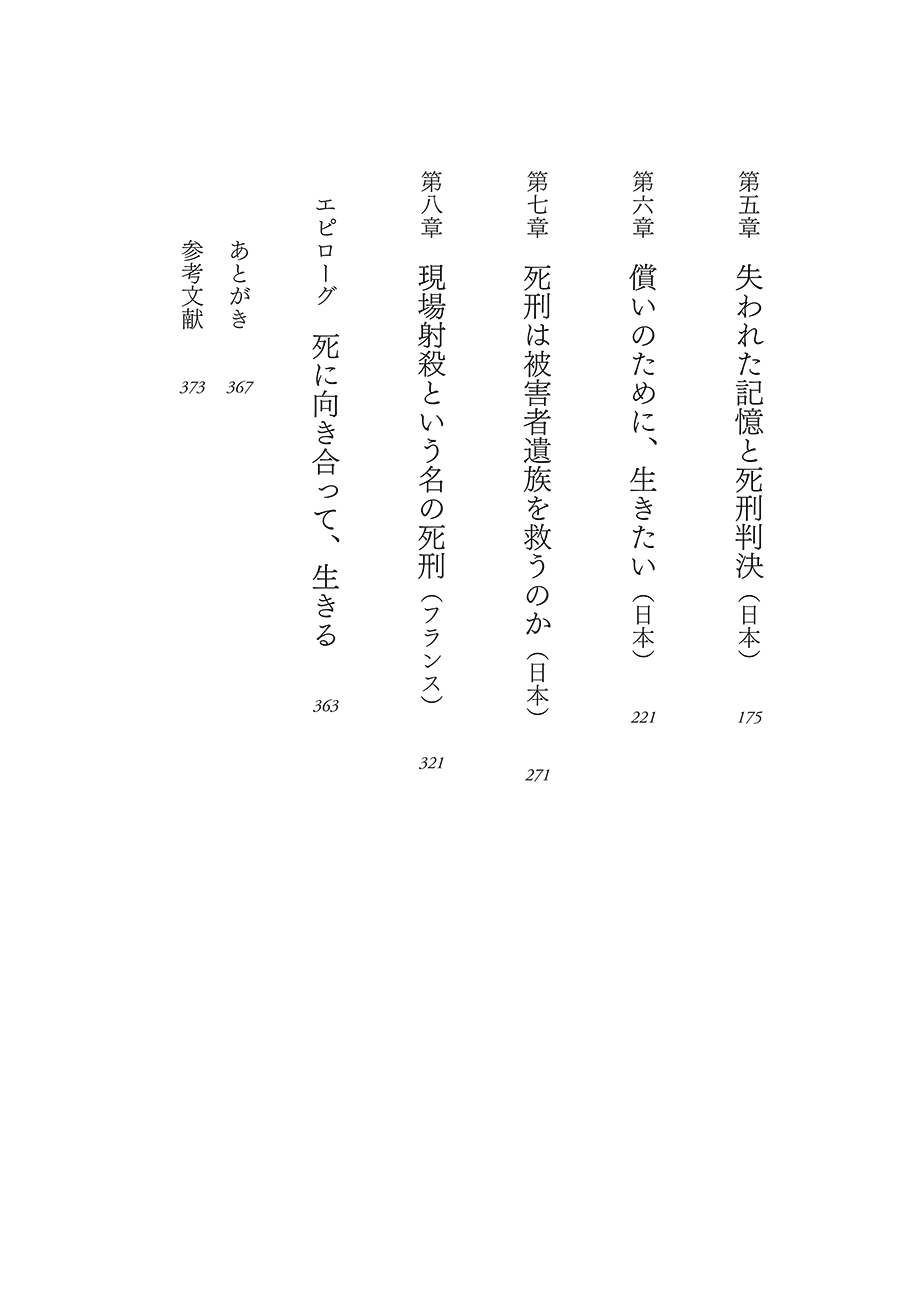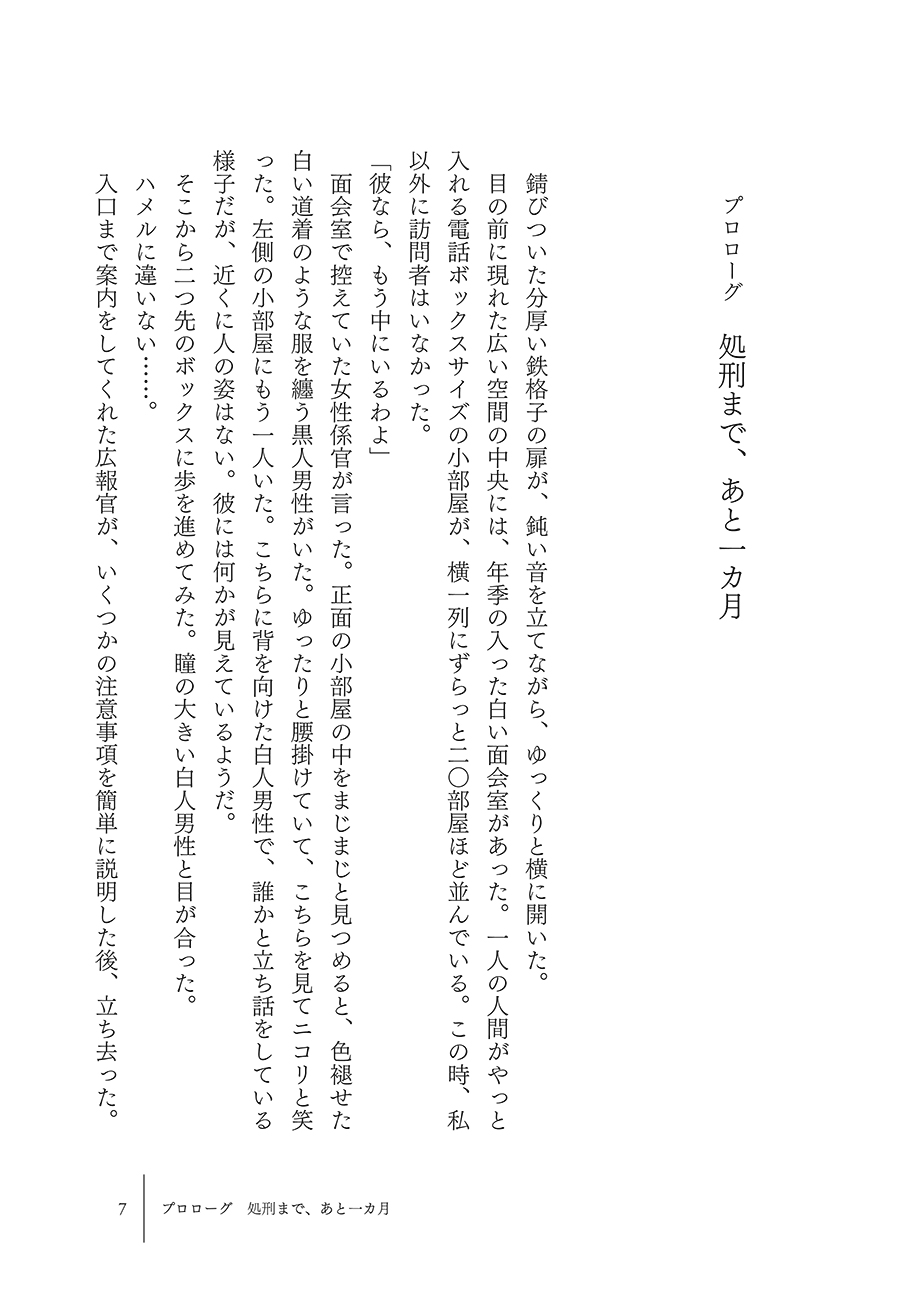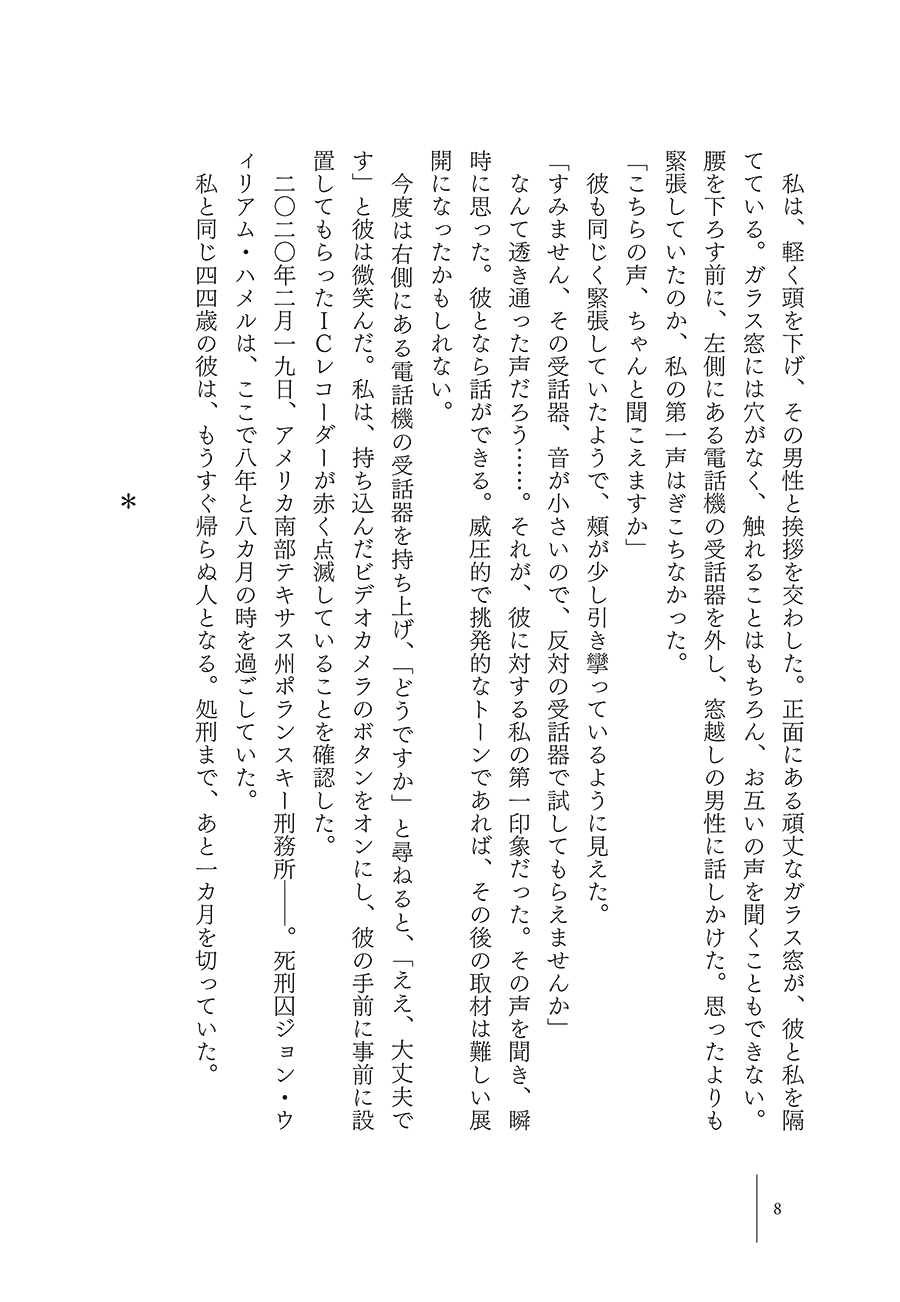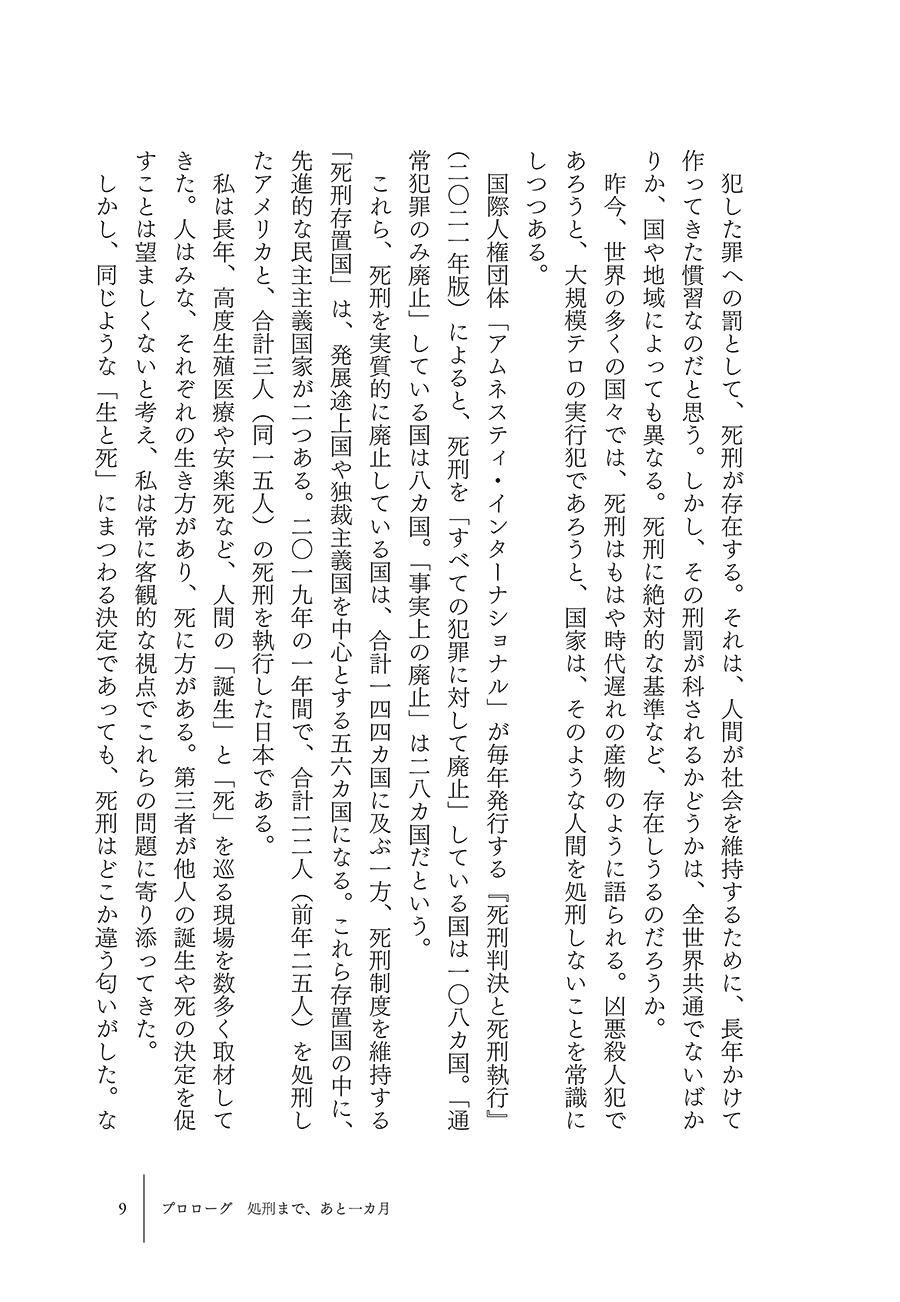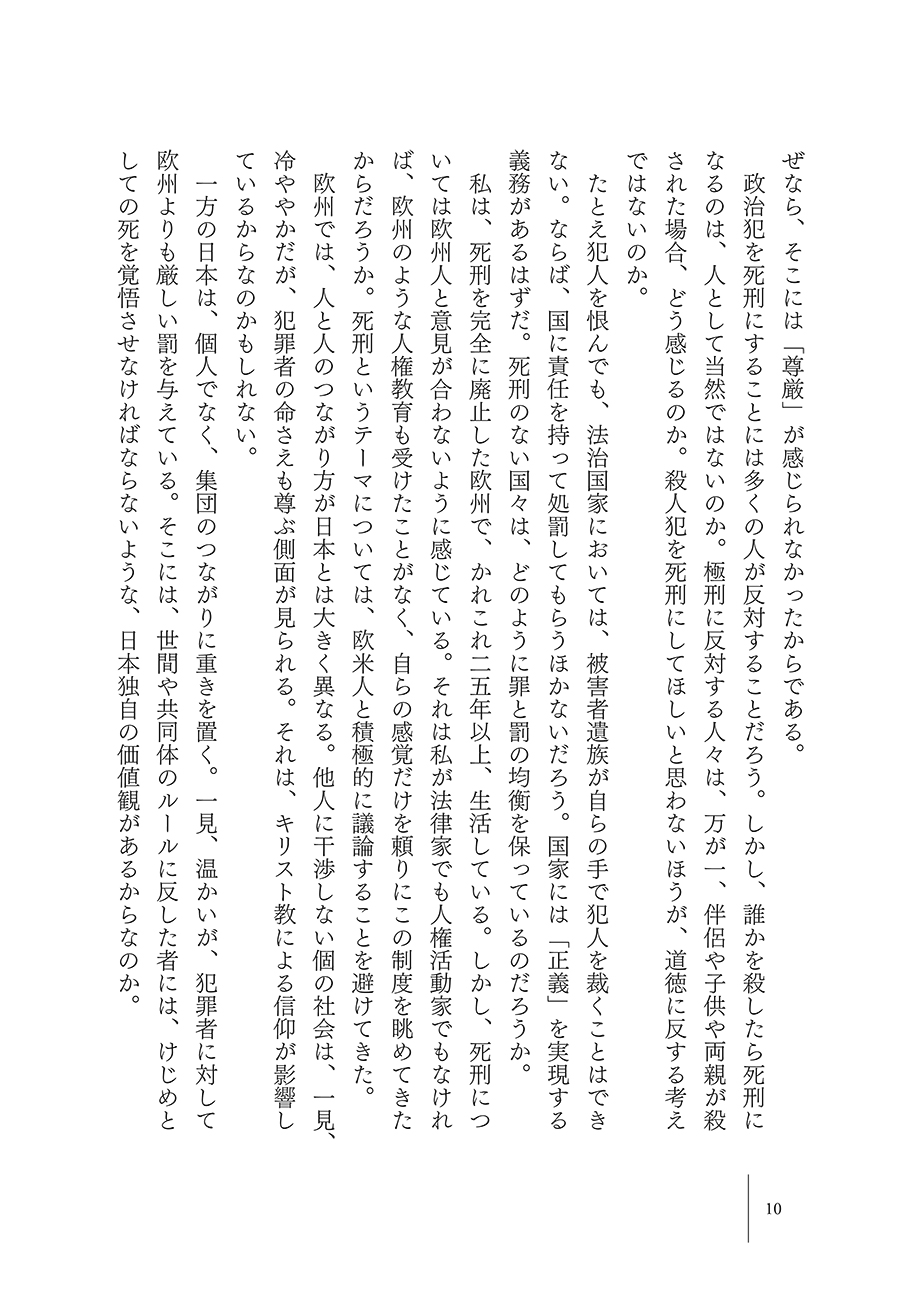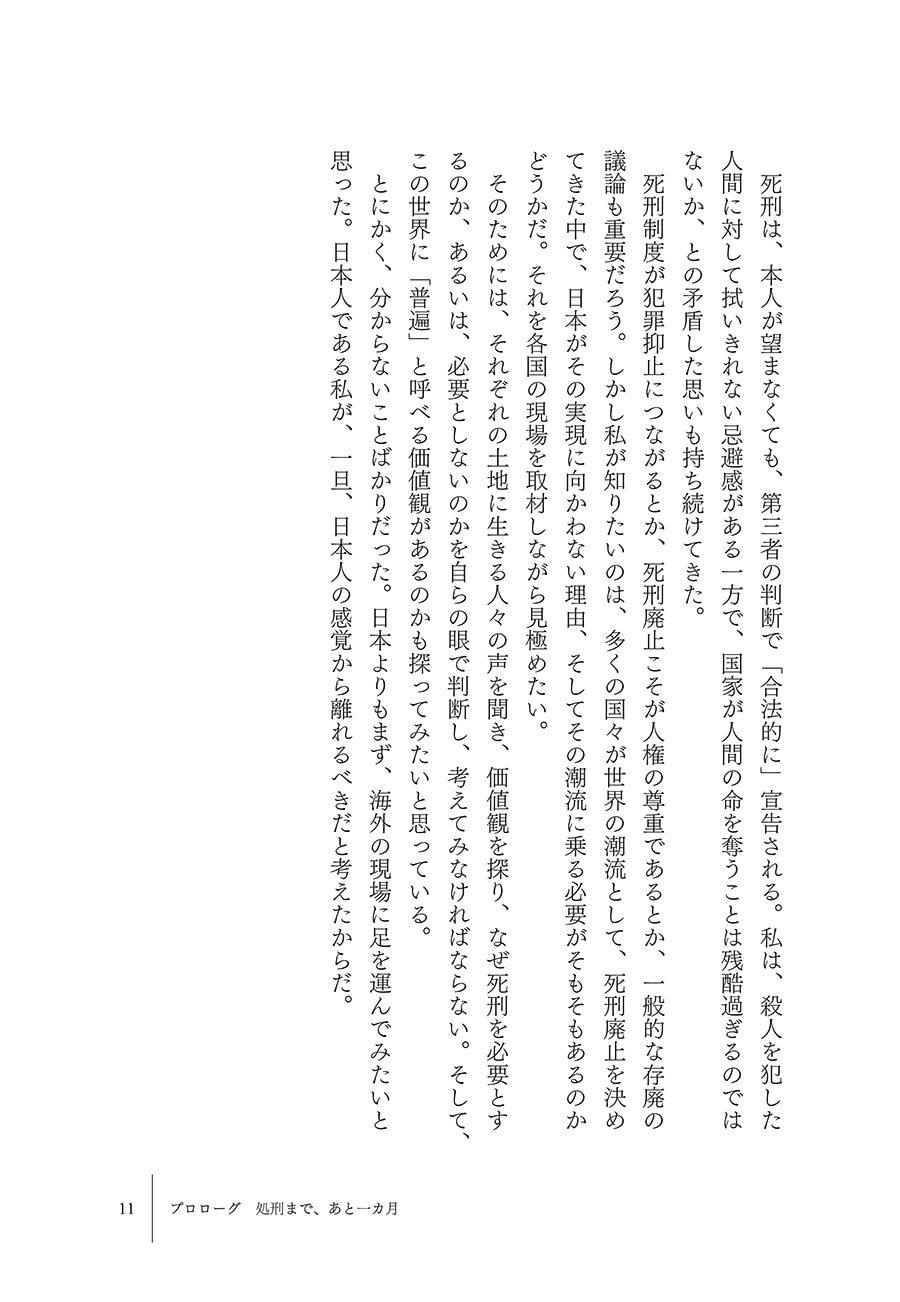プロローグ 処刑まで、あと一カ月
錆びついた分厚い鉄格子の扉が、鈍い音を立てながら、ゆっくりと横に開いた。
目の前に現れた広い空間の中央には、年季の入った白い面会室があった。一人の人間がやっと入れる電話ボックスサイズの小部屋が、横一列にずらっと二〇部屋ほど並んでいる。この時、私以外に訪問者はいなかった。
「彼なら、もう中にいるわよ」
面会室で控えていた女性係官が言った。正面の小部屋の中をまじまじと見つめると、色褪せた白い道着のような服を纏う黒人男性がいた。ゆったりと腰掛けていて、こちらを見てニコリと笑った。左側の小部屋にもう一人いた。こちらに背を向けた白人男性で、誰かと立ち話をしている様子だが、近くに人の姿はない。彼には何かが見えているようだ。
そこから二つ先のボックスに歩を進めてみた。瞳の大きい白人男性と目が合った。
ハメルに違いない……。
入口まで案内をしてくれた広報官が、いくつかの注意事項を簡単に説明した後、立ち去った。
私は、軽く頭を下げ、その男性と挨拶を交わした。正面にある頑丈なガラス窓が、彼と私を隔てている。ガラス窓には穴がなく、触れることはもちろん、お互いの声を聞くこともできない。腰を下ろす前に、左側にある電話機の受話器を外し、窓越しの男性に話しかけた。思ったよりも緊張していたのか、私の第一声はぎこちなかった。
「こちらの声、ちゃんと聞こえますか」
彼も同じく緊張していたようで、頬が少し引き攣っているように見えた。
「すみません、その受話器、音が小さいので、反対の受話器で試してもらえませんか」
なんて透き通った声だろう……。それが、彼に対する私の第一印象だった。その声を聞き、瞬時に思った。彼となら話ができる。威圧的で挑発的なトーンであれば、その後の取材は難しい展開になったかもしれない。
今度は右側にある電話機の受話器を持ち上げ、「どうですか」と尋ねると、「ええ、大丈夫です」と彼は微笑んだ。私は、持ち込んだビデオカメラのボタンをオンにし、彼の手前に事前に設置してもらったICレコーダーが赤く点滅していることを確認した。
二〇二〇年二月一九日、アメリカ南部テキサス州ポランスキー刑務所──。死刑囚ジョン・ウィリアム・ハメルは、ここで八年と八カ月の時を過ごしていた。
私と同じ四四歳の彼は、もうすぐ帰らぬ人となる。処刑まで、あと一カ月を切っていた。
*
犯した罪への罰として、死刑が存在する。それは、人間が社会を維持するために、長年かけて作ってきた慣習なのだと思う。しかし、その刑罰が科されるかどうかは、全世界共通でないばかりか、国や地域によっても異なる。死刑に絶対的な基準など、存在しうるのだろうか。
昨今、世界の多くの国々では、死刑はもはや時代遅れの産物のように語られる。凶悪殺人犯であろうと、大規模テロの実行犯であろうと、国家は、そのような人間を処刑しないことを常識にしつつある。
国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル」が毎年発行する『死刑判決と死刑執行』(二〇二一年版)によると、死刑を「すべての犯罪に対して廃止」している国は一〇八カ国。「通常犯罪のみ廃止」している国は八カ国。「事実上の廃止」は二八カ国だという。
これら、死刑を実質的に廃止している国は、合計一四四カ国に及ぶ一方、死刑制度を維持する「死刑存置国」は、発展途上国や独裁主義国を中心とする五六カ国になる。これら存置国の中に、先進的な民主主義国家が二つある。二〇一九年の一年間で、合計二二人(前年二五人)を処刑したアメリカと、合計三人(同一五人)の死刑を執行した日本である。
私は長年、高度生殖医療や安楽死など、人間の「誕生」と「死」を巡る現場を数多く取材してきた。人はみな、それぞれの生き方があり、死に方がある。第三者が他人の誕生や死の決定を促すことは望ましくないと考え、私は常に客観的な視点でこれらの問題に寄り添ってきた。
しかし、同じような「生と死」にまつわる決定であっても、死刑はどこか違う匂いがした。なぜなら、そこには「尊厳」が感じられなかったからである。
政治犯を死刑にすることには多くの人が反対することだろう。しかし、誰かを殺したら死刑になるのは、人として当然ではないのか。極刑に反対する人々は、万が一、伴侶や子供や両親が殺された場合、どう感じるのか。殺人犯を死刑にしてほしいと思わないほうが、道徳に反する考えではないのか。
たとえ犯人を恨んでも、法治国家においては、被害者遺族が自らの手で犯人を裁くことはできない。ならば、国に責任を持って処罰してもらうほかないだろう。国家には「正義」を実現する義務があるはずだ。死刑のない国々は、どのように罪と罰の均衡を保っているのだろうか。
私は、死刑を完全に廃止した欧州で、かれこれ二五年以上、生活している。しかし、死刑については欧州人と意見が合わないように感じている。それは私が法律家でも人権活動家でもなければ、欧州のような人権教育も受けたことがなく、自らの感覚だけを頼りにこの制度を眺めてきたからだろうか。死刑というテーマについては、欧米人と積極的に議論することを避けてきた。
欧州では、人と人のつながり方が日本とは大きく異なる。他人に干渉しない個の社会は、一見、冷ややかだが、犯罪者の命さえも尊ぶ側面が見られる。それは、キリスト教による信仰が影響しているからなのかもしれない。
一方の日本は、個人でなく、集団のつながりに重きを置く。一見、温かいが、犯罪者に対して欧州よりも厳しい罰を与えている。そこには、世間や共同体のルールに反した者には、けじめとしての死を覚悟させなければならないような、日本独自の価値観があるからなのか。
死刑は、本人が望まなくても、第三者の判断で「合法的に」宣告される。私は、殺人を犯した人間に対して拭いきれない忌避感がある一方で、国家が人間の命を奪うことは残酷過ぎるのではないか、との矛盾した思いも持ち続けてきた。
死刑制度が犯罪抑止につながるとか、死刑廃止こそが人権の尊重であるとか、一般的な存廃の議論も重要だろう。しかし私が知りたいのは、多くの国々が世界の潮流として、死刑廃止を決めてきた中で、日本がその実現に向かわない理由、そしてその潮流に乗る必要がそもそもあるのかどうかだ。それを各国の現場を取材しながら見極めたい。
そのためには、それぞれの土地に生きる人々の声を聞き、価値観を探り、なぜ死刑を必要とするのか、あるいは、必要としないのかを自らの眼で判断し、考えてみなければならない。そして、この世界に「普遍」と呼べる価値観があるのかも探ってみたいと思っている。
とにかく、分からないことばかりだった。日本よりもまず、海外の現場に足を運んでみたいと思った。日本人である私が、一旦、日本人の感覚から離れるべきだと考えたからだ。
第一章 生きた目をした死刑囚
先進的な民主主義国家において、死刑制度を維持し、死刑囚が二〇〇〇人を超えるアメリカ合衆国。中でも、執行数が他州と比較できないほど多い、人口約二九〇〇万人の南部テキサス州を訪れることにした。
ネットで調べると、同州の刑事司法省(Texas Department of Criminal Justice、通称:TDCJ)の公式ホームページが検索のトップに現れてくる。連邦制のアメリカは、連邦とは別にそれぞれの州が立法・行政・司法機関を持つが、死刑も同様に「連邦」と「州」の二つのレベルに分かれている。
連邦の死刑については一九七二年から停止されていたが、一九八八年、連邦最高裁が再開を認めた。それ以降、死刑が執行されたのは、二〇〇三年三月のジョージ・W・ブッシュ政権下での三件のみ。しかし、トランプ大統領政権下の二〇二〇年七月、一七年ぶりとなる死刑が執行され、わずか一人の大統領の下で合計一三件執行された。
その他はすべて、州による死刑になる。テキサス州刑事司法省のホームページを詳しく見てみた。
刑法犯を検索できる「オンラインサーチ」があった。受刑者の氏名、テキサス州刑事司法省から与えられた「#」で始まる受刑者番号、連邦政府のデータベースとなる受刑者番号(SID)、性別、人種などを入力すると、刑法犯の情報が出てくる。
さらに、そこには「死刑囚監房(Death Row)」と書かれた項目がある。この中にある「死刑囚」の文字をクリックすると、彼ら全員の一覧表が現れてくる。横一列に死刑確定囚の受刑者番号、刑法犯情報、姓、名、生年月日、性別、人種、死刑確定日、出身郡、犯行日が表示されている。それが縦に二〇九列、つまり二〇九人(二〇二〇年三月六日更新)が並んでいた。
驚いたのは、「死刑執行予定日」という項目も記されていることだ。アメリカでは、死刑判決から一定の年数が経つと、死刑囚に、いつ死刑場に送られるのかが知らされる。とはいえ、順番はばらばらで、判決が下された者から順番に執行されるわけではない。だいたい月に二人の死刑が、このテキサス州では行なわれているようだった。
もうひとつ、目を引いたのは、「刑法犯情報」をクリックすると、囚人服を着た死刑囚の顔写真が表示され、その下には、身長、体重、髪の色や目の色から、以前の職業、前科、事件の概要、共犯者、犠牲者の人種と性と五つの情報が掲載されていることだ。ここまで詳しい情報があると、生々しくて身の毛がよだつほどだ。
だが、こうした情報が公開されているおかげで、私は、どのような人物に当たり、どのような取材計画を立てるべきかを前もって準備することができた。
死刑執行が目前に迫っている死刑囚に会い、彼らの肉声を拾うこと。「予告された死」を前にした人間は、何にすがり、何を求め、何に苦しむのか。もしくは苦しまないのか。これらの話を本人の口から聞くことは、死刑の本質を知る上で、何よりも貴重な体験だと思えた。
そして、彼らの死刑に立ち合い、最期の一呼吸を見届けることで、私が何を感じ、考えるのかを知りたいという思いもあった。すると、面会すべき死刑囚の顔がネット上に現れてきた。
死刑囚──ジョン・ウィリアム・ハメル(#999567)
死刑囚──トレイシー・ビーティー(#999484)
両者ともに殺人犯で、死刑執行日が二〇二〇年三月中旬に予定されていた。この二人に会うために、スペイン北東部バルセロナの仕事場にいた私は、二月中の取材を遂行しようと思った。だが、そもそも死刑囚に会って話をすることなど、そう簡単にできるものなのだろうか……。
二〇一九年一二月二九日、テキサス州刑事司法省のジェレミー・ディーセル広報部長に連絡を取ってみることにした。出発点でつまずいてはならないと思い、最初のメールは時間をかけて丁寧に作成した。しかし、五文字にも満たない冷ややかな返事しか返ってこなかった。
彼は、あまり長い文章を好まないのかもしれない。そこで、今度はシンプルな内容でメールを送り直すと、年明けの一月六日、次のような返信が来た。
〈よろしければ、いつでも電話をください。しかし、手続きは非常にありきたりなものです。我々にインタビューの申請をしていただき、受刑者が同意すれば、それをセッティングすることになります〉
早速、広報部長に電話した。彼の下で働くロバート・ハースト広報官が、受話器を取った。部長は多忙を極めているため、手続きは彼が引き継ぐという話になった。希望する取材内容と取材意図を書き、一月二二日、パスポートのコピーと一緒に申請書を送った。
一月二四日午前零時、就寝前に返事が来た。ハースト広報官は「同意」という文字をメッセージの中に太字で記入し、取材申請が通ったことを私に報告した。アメリカとスペインの時差を考えると、意外とすんなりと死刑囚の同意をもらい、取材許可を得ることができたものだと思った。
二月一四日、バルセロナ空港から、まずは経由地のフロリダ州マイアミに向けて出発した。
あなたが会う人たちは死刑支持者
マイアミの空港には、マスクを付けたアジア人の団体旅行客が集まっていた。中国・武漢で起きている「新型コロナウイルス」の感染を警戒していることは間違いない。だが、彼ら以外に感染予防策を講じている人は見当たらない。私も、マスクは大袈裟だと思っていた。
国内線に乗り継ぎ、テキサス州最大の都市ヒューストンに到着する頃には、日付は二月一五日に変わろうとしていた。この日は、空港近くのホテルに一泊することにした。入り口を抜けると、アメリカの懐かしい匂いが漂ってきた。バニラコーヒーなのかシナモンガムなのかよく分からない、ヨーロッパや日本のホテルにはない、この独特な甘い匂いがアメリカに来たことを実感させる。
翌日、気温は摂氏一九度と二月にしては暖かかった。空は一面が曇っていた。空港で予約済みのレンタカーを借りた。ピックアップトラックに乗りたかったが、そんな資金はない。日産のセダンにした。道路には、欧州と比較できない超大型トラックやピックアップトラックばかりが走っていて、借りた車がミニカーに見えた。
正午、このアメリカ取材で、案内人となってくれる女性に会い、昼食を共にすることになっていた。指定された「テキサス牛が
「英語とスペイン語、どちらが得意かしら」
白シャツと黒デニムのオテロは、まずそう尋ねてきた。
「スペイン語ですけれど、アメリカに来たので英語で話しましょう」
オテロは、ステーキを頼み、私には「このアンガス牛がいいわよ」と勧めてきたので、その通りにした。彼女は、陽気なわけでも素っ気ないわけでもなく、ただ淡々と話す女性だった。
「この国の死刑問題は、教育格差と奴隷の歴史が大きく関係していると思うのよ」
そう話した後、前年にアメリカ全土を揺るがしたテキサス州の黒人死刑囚の話題を持ち出した。死刑執行が五日後に迫る中、女優キム・カーダシアンや歌手リアーナといった著名人が、彼の無罪を大々的に主張した。国全体で死刑反対の声が湧き上がった。テキサス州最高裁判所は、刑事控訴審からの延期勧告を受け入れた。不当な人種差別裁判の典型で、それが当然の社会だった同州でも、状況が徐々に変化してきている例だという。
「以前は、あまり見られなかったことよ。世間の声や圧力が、裁判の行方を覆す要因になってきたということかしら」
彼女は、異なる国や州を転々とし、エリート街道を歩んできたこともあってか、テキサスの司法、または、アメリカという国の司法を第三者的な視点で捉えることができる人のようだ。広い視野を持つ彼女からは、死刑が時代遅れなものに見えているようだった。
「あなたがこれから会う人たちはみな、死刑があって当然だと思っているかもしれないわ。この州の人々は、保守的で原理主義者が多く、一般的に彼らは死刑を支持します。たとえ刑務所長でも、物事を理解していないわけではないけれど、世界で起きていることに無関心であったり、単純に人種差別主義者であったり……。私にはよく分からないわ」
私はテキサス州で死刑を取材するにあたり、キーパーソンが誰なのかを、知っておきたかった。
「今から言う人たちの名前をメモしてください。私からも連絡をしておくので、滞在中に会ってみたらどうかしら」
彼女はテキサス州最高裁判所の元女性裁判官、死刑廃止団体の代表、それに冤罪を勝ち取った元死刑囚の名前と連絡先などを読み上げた。彼女の死刑に対するスタンスは、反対派に属する。私の考えも探ってきたが、まだ取材を始めたばかりで明確になっておらず、彼女に興味を持ってもらえる返事はできなかった。
会計をしている間、彼女は先に車に行って待っていると言った。慌ただしい食事だった。アンガス牛は、普段、ヨーロッパや日本で食べる牛肉とは違う、癖になりそうな味だった。ドアを開けると高音のロック音楽と客の大声から解放され、だだっ広い静かな駐車場に出た。白い四輪駆動車の前に立つオテロが、黒い塊を差し出した。
「これ、とても良い本よ。滞在中に参考にしてください。もし気に入ったら、事務所にはコピーがあると思うので、あなたの帰国前に渡すわ。すごく高いから買ってはダメよ」
これでもう一度、彼女に会うきっかけが作れた。オテロは、年季の入った黒いカバーの『デス・ペナルティー(死刑)第三版』を手渡した。分厚く、重さ四キロはある一〇〇〇ページ弱の学術本だった。
《中略》

ハメルとの出会い
二月一九日の午前一一時半、私は約束の時間よりも三〇分早く、テキサス州南東部ポーク郡のリビングストンにあるポランスキー刑務所に到着した。早めに到着したのは、少し緊張していたせいかもしれない。
この日はテキサス州に来てから、もっとも激しい雨が降っていた。二日前までの生暖かい空気は消え、気温は摂氏六度まで下がっていた。悪天候のせいで、美しいはずのリビングストン湖も茶色く濁って見えた。車からの視界も悪く、ただただ殺風景で、周辺にはレストランもスーパーも見当たらない。とにかく目の前にある一本道に車を走らせた。
しばらくすると、低層の大きな建物が目に飛び込んできた。有刺鉄線が張り巡らされているため、見誤りようがない。ポランスキー刑務所だった。ベージュの雨雲とくすんだ建物全体の色が同化していて、刑務所がより大きく見えた。ここの敷地は一九一ヘクタールで、東京ドーム約四一個分に当たる広さを持つ。
この刑務所は、州内の死刑囚全員を収監しているが、死刑そのものを行なっている施設ではない。処刑自体は、ここから約七〇キロ離れた「死刑の首都」と呼ばれるハンツビル刑務所で執行されている。テキサス州刑事司法省の本部も同刑務所の向かいに置かれている。
検問をパスすると、駐車し、エンジンを切った。メールで指示されていた通り、ノート、ペン、ICレコーダー、ビデオカメラ、デジタルカメラだけをバッグから出し、残りはすべてトランクに入れた。コートを着て、刑務所の看板が壁にかかった正面玄関に向かった。そこには、空港の手荷物検査と同じ機械があり、男性と女性の係官が、暇そうに世間話をしていた。
用件を告げると男性係官が「ハースト広報官を呼んできます」と言って、傘もささずに外に出た。数分後に体の大きな男性が、傘をさしながら、重そうな足取りでゆっくりと近づいてきた。
「ロバートです。はじめまして」
メールの文章や電話越しの大きな声から想像していた人物とは違い、優しそうな目をした男性だった。年齢は私と同じか、少し若いくらいだろうか。体調がすぐれず、車内で仮眠をとっていたのだと言った。
刑務所の中に入るためには、荷物検査の後にIDチェックがある。登録を終えると、赤いプラスチックの訪問者カードが渡された。頑丈な自動ドアが開いた。抜けるとそこは、有刺鉄線に囲われた外庭だった。正面にはもう一つの扉があり、ここが実際の刑務所の入り口になる。中に入る前に、ハースト広報官が遠くに見える建物を指差した。
「あれが二〇〇人あまりの死刑囚が収監されている監房です。われわれに近い側にあるこちらの建物は、一般の受刑者専用で、約二〇〇〇人が収容されています」
一般の受刑者たちは、二人一組の雑居房で生活をしているが、死刑囚はそれぞれ独房を割り当てられている。理由はいろいろあるが、「受刑者同士の闘争や殺し合いを避けること」が最大の理由だという。軽く発せられた言葉だったが、迫力があった。
ポランスキー刑務所では、二〇一九年末、立て続けに殺人事件が発生し、受刑者二人の命が奪われていた。それはテキサス州刑事司法省にとって、脱獄の次に厄介な問題だが、数年に一度は起きてしまう惨事のようだ。
この情報を知るだけで、刑務所内の荒々しさが伝わってくる。そんな刑務所の中に私はいて、翌月に死刑が執行される男性と、いよいよ面会することになる。
受刑者が手がけた手工芸品や絵画作品が置かれた廊下を通り抜け、面会室の手前にある受付に辿り着いた。そこで訪問者カードを職員に示すと、錆びた分厚い緑色の鉄格子の扉が鈍い音を立てて開いた。
静寂な面会室が広がっていた。ハースト広報官は、すでに待機していた女性係官と会話を始めた。死刑囚へのメディアインタビューが許される週に一度の水曜日だというのに、私以外、メディア関係者は一人もいなかった。真っ白の小部屋が並ぶ面会室の中には、三人の死刑囚がいることが察せられた。私の質問を嗅ぎ取った係官は、顎を前に突き出して言った。
「彼なら、もう中にいるわよ」
二人の死刑囚を横目に、数歩先に進んでみる。向けられた視線からハメルだと分かった。しかし想像していた死刑囚とは、顔つきが異なった。彼の顔は何度もネット上で検索し、頭に焼き付けてあった。そのおかげで、すぐに判別できたが、事件当時の写真の面影は残っていなかった。
髪が薄くなったとか、太ったとかいう単純な外見の変化によるものもあるだろうが、私が想像していたような殺人者の雰囲気が彼にはなかった。そう感じたのは、パソコン上で眺めていた写真とは懸け離れた「純朴な目」のせいだったのかもしれない。
受刑者が純朴でないと断定しているような言い方に聞こえたとすれば、そうかもしれない。私の中にもそのような固定観念があった。だからこそ、ハメルを見たときのギャップに驚いてしまったのだろう。
ハースト広報官が受話器を取り、ハメルに向かって、私が誰で、どこから来た人間なのかを説明した。すでに提供済みの情報だが、確認のためだという。さらに、いくつかの注意事項も伝えていた。
「まず、この刑務所のセキュリティーについては話さないこと。次に、インタビューの間に居心地が悪くなったり、会話を止めたくなったりしたら、係官に知らせること。あとは、礼儀正しく振る舞うことだ。質問があるか」
ガラスの反対側で、同じく受話器を持つハメルは広報官の目を見つめ、頷きながら「OK」とか「イエス」と「ノー」だけを繰り返していた。まだ言葉を交わす前だが、彼がとても真面目な男性に見えた。もっと横柄に対応するのかと思っていたが、それも私の勝手な想像だったのだろう。
実は、この日の朝八時半、ハースト広報官から「URGENT(緊急)」と書かれたメールが突然、届いた。
〈トレイシー・ビーティー(#999484)が取材を拒否すると言っている。それでもあなたは、ポランスキー刑務所に来ますか?〉
取材予定だったもう一人の死刑囚がドタキャンすると言うのだ。このような事態は当然起こりうると予測していた。私は、精神的に混乱状態の死刑囚がほとんどで、取材に応じるほうが稀だろうと思っていたからだ。だから、テキサス州に着いてからずっと、取材がどう転ぶのか分からないという不安で一杯だった。
一連の約束事を聞き終えたハメルが、横に立つ私のほうを見た。広報官が「さあ、今から一時間、好きに話をしてくれ。奥で待っている」と言って、すばやくその場を去った。
受話器の音声を確認した後、プラスチック製の椅子に座り、腕時計の針に目を落とした。見ず知らずの人間、しかも死刑囚の男性と、一時間も会話を続けられるのか、正直、心配だった。
視線を上げると、ハメルがこちらからの問いかけを待っているように見えた。
「こんにちは。体調はどうですか」
そう挨拶しながら、今まで経験してきた取材とは異なる、妙な胸のざわつきを感じていた。
ハメルの体は思ったよりも大きかった。ボックスの中は窮屈に違いない。いや、長い刑務所生活で、窮屈という感覚など、とうの昔に忘れてしまっただろうか。
「背中の痛みと(小腸や大腸などの消化管に問題のある)クローン病を患っていますが、薬は飲んでいません。でも、大丈夫です。健康だと思いますね」
死刑執行日が一カ月後に迫っているにもかかわらず、取材に応じた理由は何だったのか。まずは素朴な疑問を投げてみることにした。私なら、自暴自棄になって外部との接触など意味がないと考えてしまうだろうし、まともな精神状態を保てないはずだ。
「なぜ、私のリクエストに応じたのですか」
ハメルは、目を逸らさず、ずっとこちらを見つめている。
「応じてもいい時だと思ったのです。死刑の執行日が近づいていますから」
意表を突く答えだった。死刑の日が迫っているからこそ、応じるというのだ。肉声が一般人に届くことに「
「いいんです。それによって、少しでも誰かの役に立てれば、それでいいんです」
とても冷静で、落ち着いた声だった。彼の視線は、ずっと私の目元に注がれている。だが、受話器を握る彼の手が、わずかに震えているのが見えた。