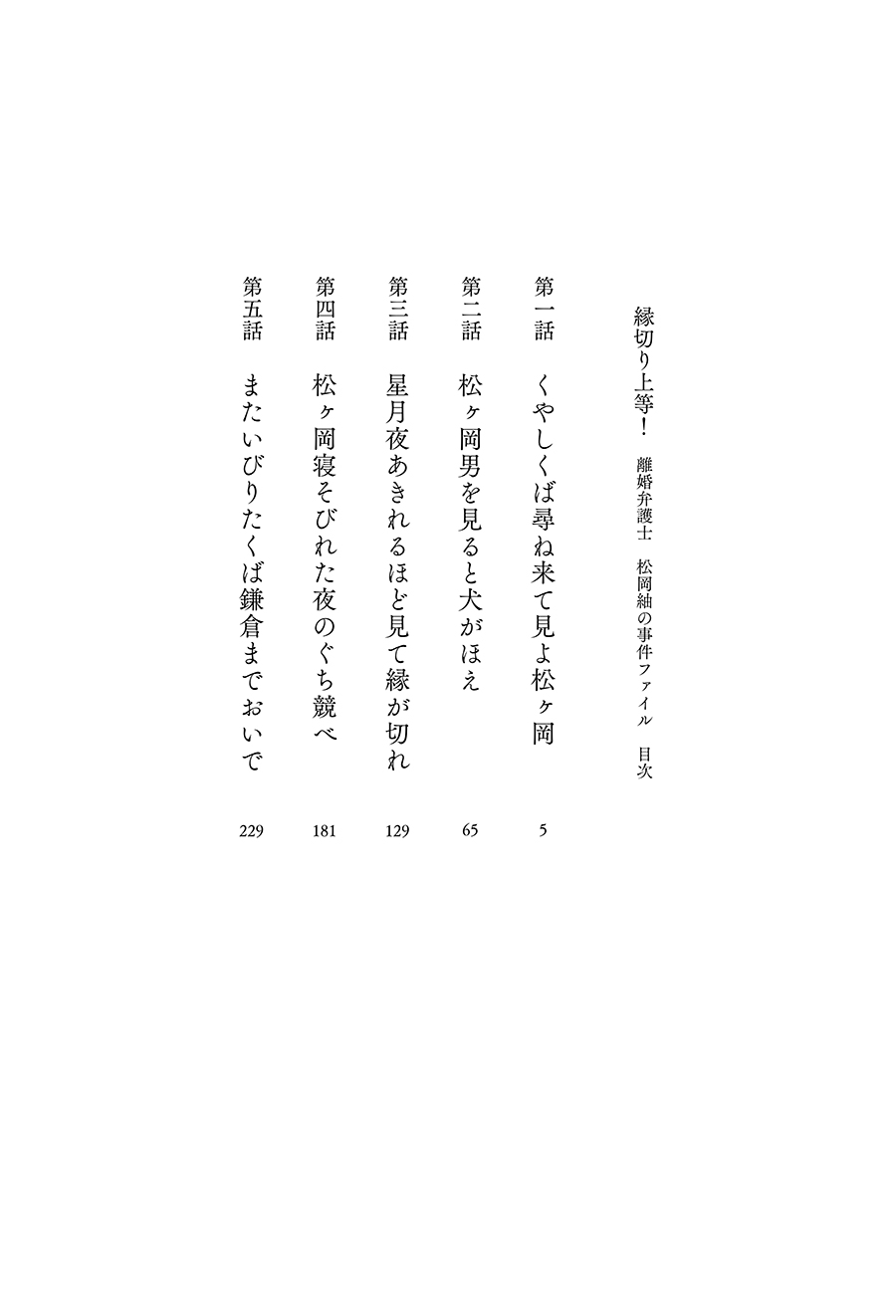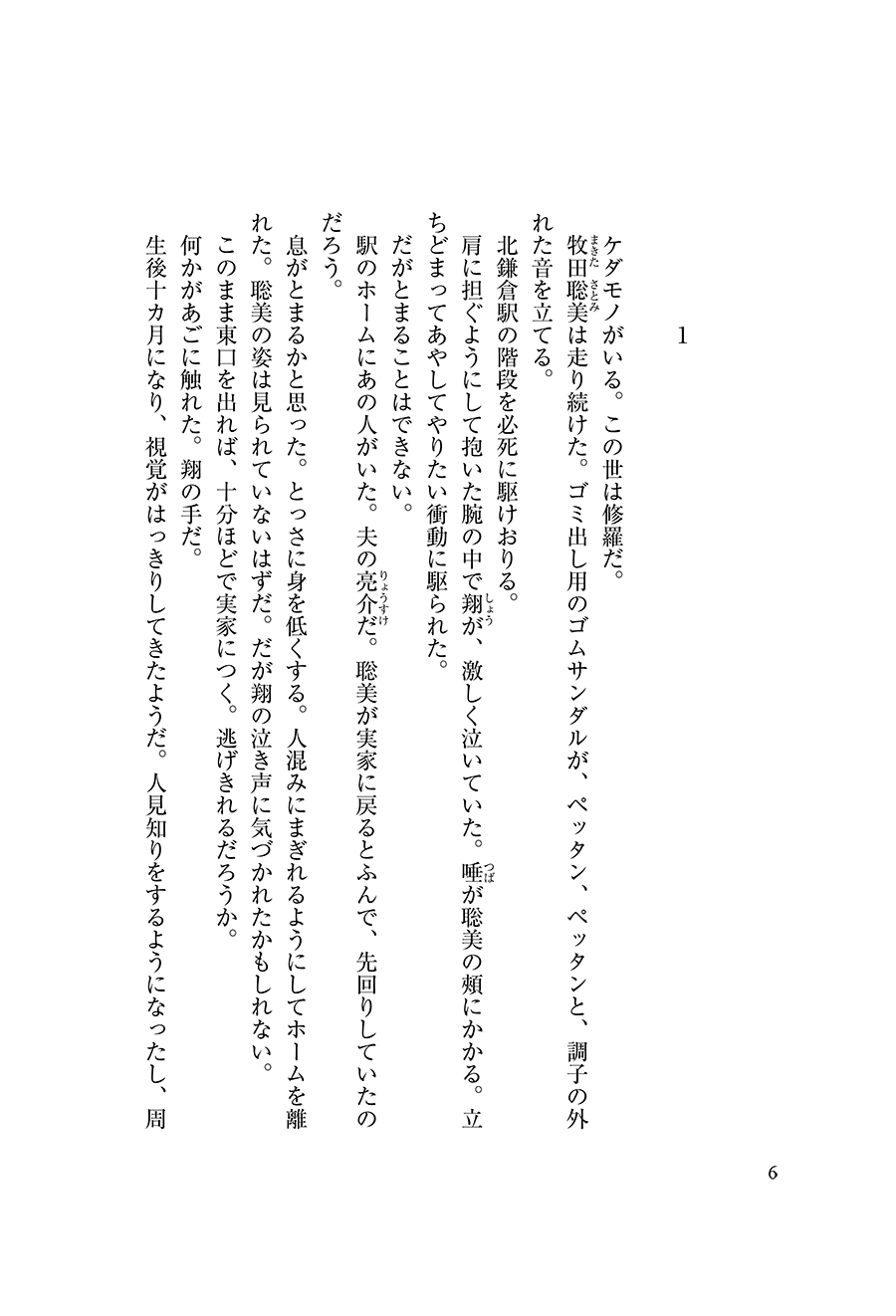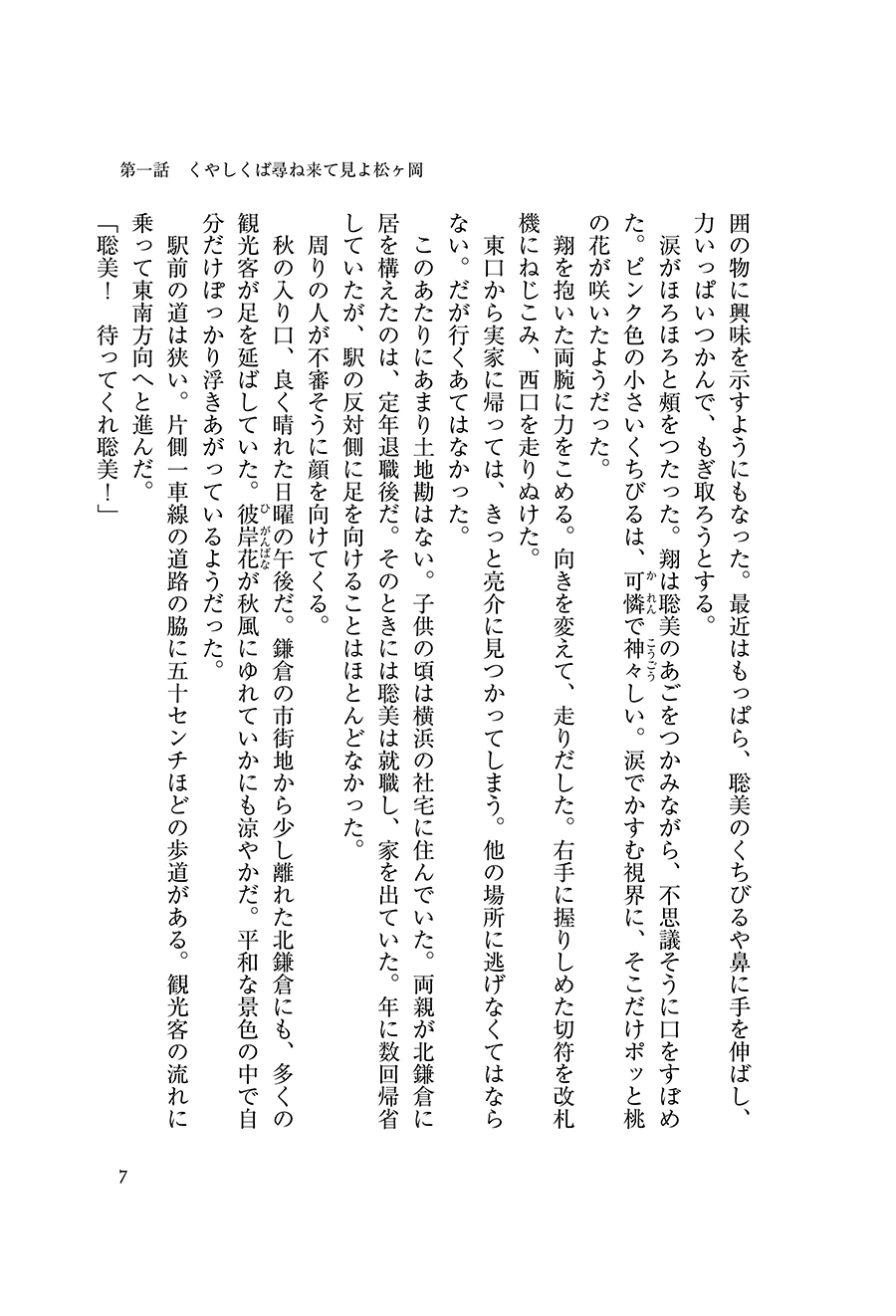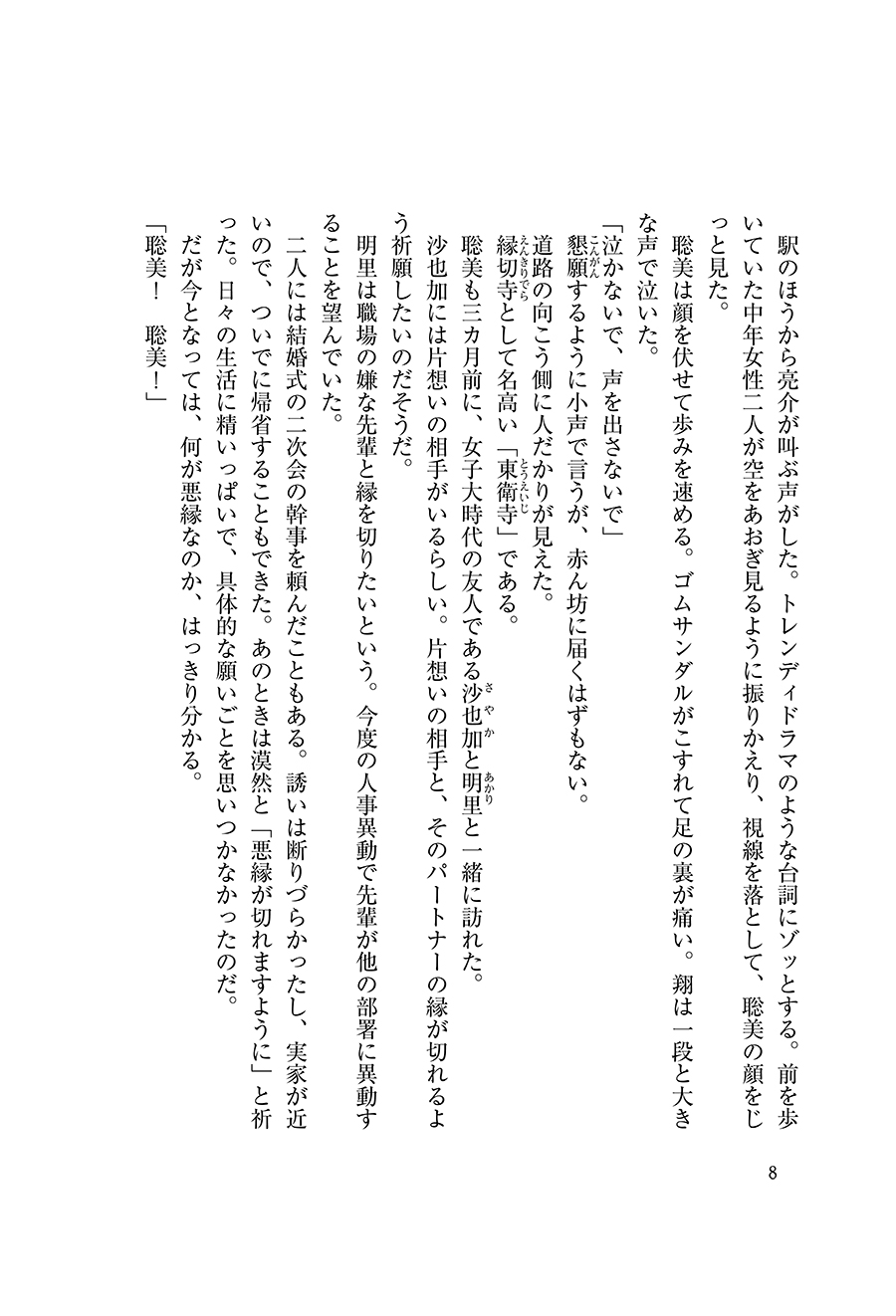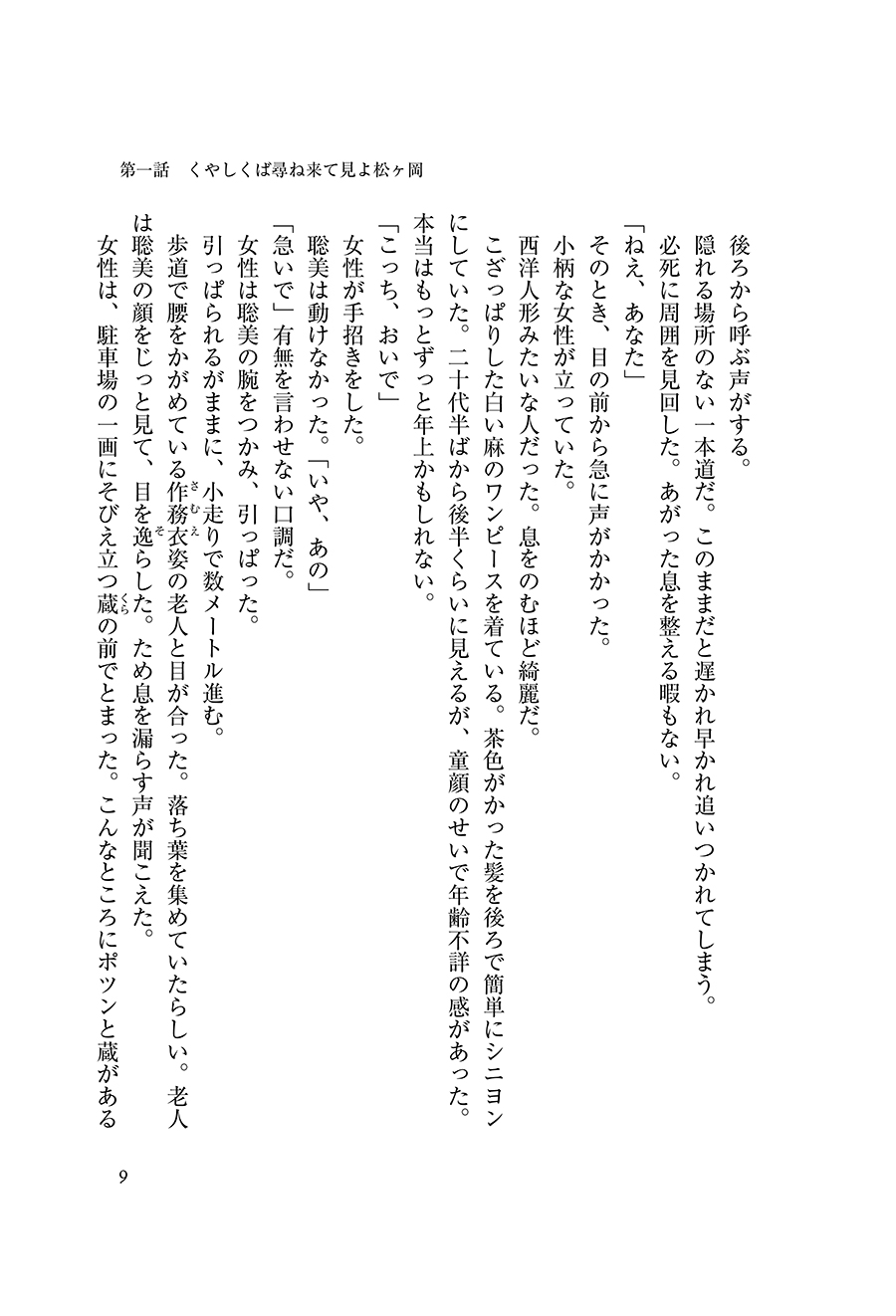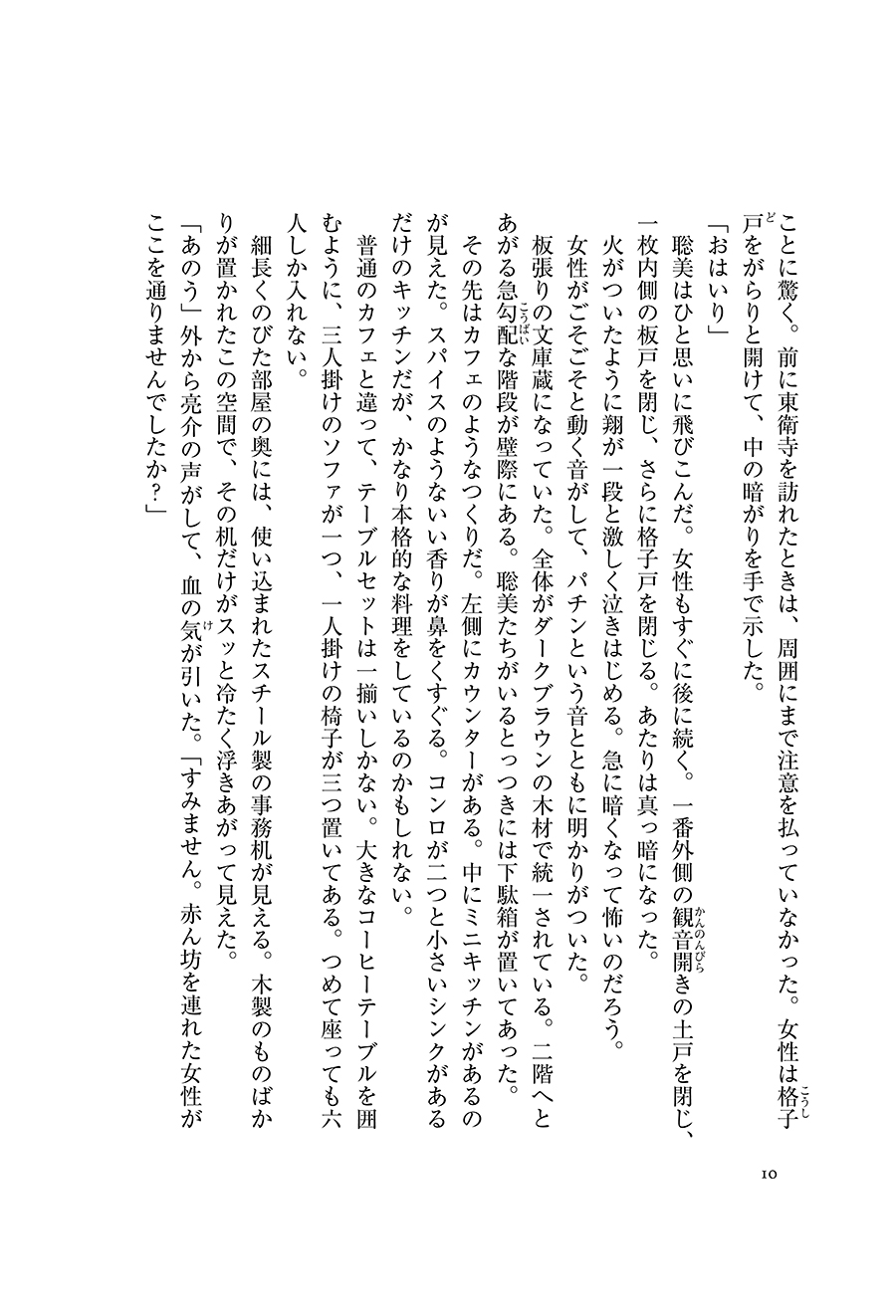第一話 くやしくば尋ね来て見よ松ヶ岡
1
ケダモノがいる。この世は修羅だ。
北鎌倉駅の階段を必死に駆けおりる。
肩に担ぐようにして抱いた腕の中で
だがとまることはできない。
駅のホームにあの人がいた。夫の
息がとまるかと思った。とっさに身を低くする。人混みにまぎれるようにしてホームを離れた。聡美の姿は見られていないはずだ。だが翔の泣き声に気づかれたかもしれない。
このまま東口を出れば、十分ほどで実家につく。逃げきれるだろうか。
何かがあごに触れた。翔の手だ。
生後十カ月になり、視覚がはっきりしてきたようだ。人見知りをするようになったし、周囲の物に興味を示すようにもなった。最近はもっぱら、聡美のくちびるや鼻に手を伸ばし、力いっぱいつかんで、もぎ取ろうとする。
涙がほろほろと頰をつたった。翔は聡美のあごをつかみながら、不思議そうに口をすぼめた。ピンク色の小さいくちびるは、
翔を抱いた両腕に力をこめる。向きを変えて、走りだした。右手に握りしめた切符を改札機にねじこみ、西口を走りぬけた。
東口から実家に帰っては、きっと亮介に見つかってしまう。他の場所に逃げなくてはならない。だが行くあてはなかった。
このあたりにあまり土地勘はない。子供の頃は横浜の社宅に住んでいた。両親が北鎌倉に居を構えたのは、定年退職後だ。そのときには聡美は就職し、家を出ていた。年に数回帰省していたが、駅の反対側に足を向けることはほとんどなかった。
周りの人が不審そうに顔を向けてくる。
秋の入り口、良く晴れた日曜の午後だ。鎌倉の市街地から少し離れた北鎌倉にも、多くの観光客が足を延ばしていた。
駅前の道は狭い。片側一車線の道路の脇に五十センチほどの歩道がある。観光客の流れに乗って東南方向へと進んだ。
「聡美! 待ってくれ聡美!」
駅のほうから亮介が叫ぶ声がした。トレンディドラマのような台詞にゾッとする。前を歩いていた中年女性二人が空をあおぎ見るように振りかえり、視線を落として、聡美の顔をじっと見た。
聡美は顔を伏せて歩みを速める。ゴムサンダルがこすれて足の裏が痛い。翔は一段と大きな声で泣いた。
「泣かないで、声を出さないで」
道路の向こう側に人だかりが見えた。
聡美も三カ月前に、女子大時代の友人である
沙也加には片想いの相手がいるらしい。片想いの相手と、そのパートナーの縁が切れるよう祈願したいのだそうだ。
明里は職場の嫌な先輩と縁を切りたいという。今度の人事異動で先輩が他の部署に異動することを望んでいた。
二人には結婚式の二次会の幹事を頼んだこともある。誘いは断りづらかったし、実家が近いので、ついでに帰省することもできた。あのときは漠然と「悪縁が切れますように」と祈った。日々の生活に精いっぱいで、具体的な願いごとを思いつかなかったのだ。
だが今となっては、何が悪縁なのか、はっきり分かる。
「聡美! 聡美!」
後ろから呼ぶ声がする。
隠れる場所のない一本道だ。このままだと遅かれ早かれ追いつかれてしまう。
必死に周囲を見回した。あがった息を整える暇もない。
「ねえ、あなた」
そのとき、目の前から急に声がかかった。
小柄な女性が立っていた。
西洋人形みたいな人だった。息をのむほど綺麗だ。
こざっぱりした白い麻のワンピースを着ている。茶色がかった髪を後ろで簡単にシニヨンにしていた。二十代半ばから後半くらいに見えるが、童顔のせいで年齢不詳の感があった。本当はもっとずっと年上かもしれない。
「こっち、おいで」
女性が手招きをした。
聡美は動けなかった。「いや、あの」
「急いで」有無を言わせない口調だ。
女性は聡美の腕をつかみ、引っぱった。
引っぱられるがままに、小走りで数メートル進む。
歩道で腰をかがめている
女性は、駐車場の一画にそびえ立つ
「おはいり」
聡美はひと思いに飛びこんだ。女性もすぐに後に続く。一番外側の
火がついたように翔が泣きはじめる。急に暗くなって怖いのだろう。
女性がごそごそと動く音がして、パチンという音とともに明かりがついた。
板張りの文庫蔵になっていた。全体がダークブラウンの木材で統一されている。二階へとあがる急
その先はカフェのようなつくりだ。左側にカウンターがある。中にミニキッチンがあるのが見えた。スパイスのようないい香りが鼻をくすぐる。コンロが二つと小さいシンクがあるだけのキッチンだが、かなり本格的な料理をしているのかもしれない。
普通のカフェと違って、テーブルセットは一揃いしかない。大きなコーヒーテーブルを囲むように、三人掛けのソファが一つ、一人掛けの椅子が三つ置いてある。つめて座っても六人しか入れない。
細長くのびた部屋の奥には、使い込まれたスチール製の事務机が見える。木製のものばかりが置かれたこの空間で、その机だけがスッと冷たく浮きあがって見えた。
「あのう」外から亮介の声がして、血の
「ええっ? 何だって?」
誰かが大声で訊きかえした。声色から、高齢の男性のように思えた。先ほど道ですれ違った作務衣姿の老人だろう。
心臓をきゅっとつかまれるような緊張が走った。老人と聡美は目が合った。顔を見られたように思う。赤ん坊を連れていたことも見ているはずだ。
翔は泣き続けている。
「赤ん坊を連れた女性を見ませんでしたか? 小柄で、三十歳くらいで、髪を後ろで一つ結びにした地味な女です」
地味な女、という言葉が胸に刺さった。
亮介は「聡美の
「赤ん坊を連れた女だあ?」
自分の心臓が高鳴る音が聞こえる。
「お兄さんね、ここをどこだと思ってるんだい? 東衛寺の
「あの、だから、赤ん坊を連れた女性を見かけませんでしたか? 泣き声も聞こえますよね?」
亮介がいらだっている。
「赤ん坊を連れた女性なんて、ここらには沢山いる。いちいち覚えてないね」
老人の答えにほっと胸をなでおろした。
亮介の舌打ちが聞こえてくるようだった。思い通りにならないと、すぐに機嫌を
足音が蔵の前を通りすぎる。遠ざかっていくのを、息を止めるようにして待った。
「大丈夫?」
女性が靴を脱ぎながら振りかえった。
気づかわしげというよりは、どこか浮ついた口調だ。この状況を楽しんでいるようにも見えた。
「あがっていきなよ。お茶いれるよ」
「いいんですか?」
「うんうん、大丈夫だよ。こういうことは、よく、あるからね」
女性は振りかえりもせず、カウンターの中に入っていった。
今外に出ると、亮介と鉢合わせるかもしれない。一時的にでもかくまってもらえると都合がいい。
「それでは、お言葉に甘えて……」
聡美は控えめに言ったが、女性の耳に入ったかは分からない。
周囲に視線をめぐらす。蔵の天井は民家よりやや低い。米や作物ではなく、
お洒落なカフェに改装されたような跡があるが、事務机がある奥のほうの空間は、オフィス風に改装されている。結果として、ごちゃっとした古い住宅風の空間に仕上がっていた。
窓はぴったりと閉じられ、外の光は一切入ってこない。扉のほうを振りかえると、そこもしっかり閉じられている。
カウンターから女性が首を出した。きょろきょろする聡美を見て笑った。
「大丈夫だよ。窓は鉄扉、鉄格子、障子戸の三重になってる。出入口の扉も三重。外には防犯カメラも設置してある。外壁は
「えっと、何の話を……」
「あなた、旦那から逃げてきたんでしょ?」
女性が小首をかしげた。それだけの動きなのに、とんでもなく可愛らしい。同性の聡美ですらドキッとしてしまう。
「まっ、そのへんに、座りなよ」
女性はカウンター前のソファを指さした。
聡美はおずおずと腰かける。深呼吸をした。久しぶりに息をした気分だった。翔は泣きつかれたのか、うとうとと眠り始めている。静かにソファに寝かせた。
息を整えていると、まもなく女性がお盆を持ってカウンターから出てきた。
「ほうじ茶と、お
ニコニコしながら、コーヒーテーブルに茶器を並べていく。
「ほらほら、どうぞ」
勧められるままに、ほうじ茶に口をつける。温かな苦みに、ほっと気持ちがほぐれた。喉が渇いていたことに今さら気づいた。身体じゅうに水分が染みわたっていく。
お茶請け昆布は、カラリと
「これ、美味しいですね。どこのですか?」
思わず尋ねると、女性は得意げに笑った。
「これねー、私が作ったの!
つられて笑いそうになったとき、外の扉をドンドンッと叩く音がした。
ぎょっとして身を固くする。
「おーい、
外から、先ほどの老人の声がした。
女性は立ちあがり、扉へ歩みよった。
「お父さん、もう外は大丈夫なの?」
「大丈夫。さっきの男はどこかに行った」
女性が三重に閉められた扉を一つずつ開けていく。
作務衣姿の老人が顔を出した。サンタクロースのような、いかにも
外で作業していたせいか、頰はりんごのように赤くなっている。
「ああ、いらっしゃい」目尻に深い
靴を脱いで蔵に入るとすぐ、コーヒーテーブルの上をのぞきこんだ。
「あっ、お茶請け昆布だな。俺も食べたい」
「はいはい」
と言いながら、女性はカウンターの中に入っていった。
「それで、どんなご相談なんですか?」老人が穏やかな口調で言った。
「相談?」困惑して見つめかえす。
「あんた、依頼人じゃないのか?」
女性はカウンターの中から顔だけ出した。「困っているみたいだから、かくまっただけだよ」
老人のぶんのほうじ茶とお茶請け昆布を出すと、パタパタッと階段をのぼり、すぐにまたおりてきた。
片手に名刺入れを持っている。クリームがかった卵色で、小さなリボンがついた可愛らしいものだ。名刺を取りだし、聡美の前に置いた。
『
「私は松岡と言います。紬先生って呼ぶ人が多いかな。弁護士をしていて、ここは私の事務所なんですよ」
今日の夕飯はカレーライスなんですよ、というような何気ない口調だった。聡美は紬先生の顔をまじまじと見た。つるりと均整のとれた顔を見ていると、アナウンサーだとか、女優だとか言われても信じてしまう。
聡美はこれまで、本物の弁護士を見たことがなかった。ドラマで出てくる女性弁護士は、肩で風を切って歩くスーツ姿の女性ばかりだ。
こんなにふんわりとした雰囲気の人が弁護士をしているなんて想像がつかなかった。
「弁護士の先生なんですか?」
「そうなんですよ」紬先生は
玄太郎と呼ばれた老人が軽く頭をさげた。
「父はすぐ向かいの、東衛寺で住職をしていたんです。今は住職を引退して、この事務所を手伝ってもらっています」
「お二人は親子、なんですね」
二人の顔を見比べる。言われてみれば、すっきりとした鼻筋や丸い目が似ている。
「紬先生と呼んでらっしゃったから、てっきり他人だとばかり」
「呆れちゃうでしょ?」紬先生が苦笑した。「うちの父は本当に親馬鹿で、私が弁護士になったことに舞いあがって、『紬先生』と呼んでくるんですよ」
「親馬鹿で何が悪い!」玄太郎が言いきった。「うちの娘が弁護士先生になったんだ」
紬先生は、縁切寺で名高い東衛寺の末娘だという。兄が二人いる。長男が住職を継ぎ、次男は県外で就職した。
紬先生は法科大学院を卒業して、三度目の挑戦で司法試験に合格した。
「こいつは昔からのんびり屋で、浪人中ものほほんとすごしていたんです。見ている周りのほうがやきもきしましたよ」
浪人中も玄太郎が生活の面倒を見ていたし、晴れて弁護士になった今でも実家に住まわせているという。末娘には大甘の様子だ。
玄太郎が語るあいだ、紬先生は「またはじまった」と言わんばかりに顔をしかめていた。だが照れも否定もしない。
「目の前に縁切寺があるでしょう。離婚専門の法律事務所を開くには、ここはちょうどいい立地なんですよ。離婚したい人がこのあたりに沢山やってきますからね。この蔵は父が所有していますが、もともとはカフェが入っていたんです。私が独立を考えていた時期にカフェが閉じることになったので、事務所として使わせてもらうことにしました」
玄太郎は目を細めてうなずいた。
聡美にとっては、別世界の住人たちのようだった。周囲の愛情を一身に受けて、紬先生には余裕と自信がただよっていた。
聡美自身、家庭環境には恵まれているほうだ。地方銀行勤務の真面目な父と、専業主婦の母との間に生まれた一人娘だ。高校までは横浜で育ち、東京の女子大を出してもらった。
恵まれているはずなのに、聡美の中はふにゃふにゃと生焼けで、確固たるものがなかった。
ため息をついて、湯飲みに視線を落とした。
2
聡美は女子大を出て、大手電機メーカーの子会社に就職した。
秘書業務からはじまり、総務全般の業務を担うようになる。
夫となる牧田亮介に出会ったのは、入社五年目で、仕事がだんだん楽しくなってきた頃だ。亮介は、本社に出入りしている税理士だった。数カ月に一度、子会社にも顔を出す。書類整理を手伝っているうちに会話を交わすようになり、食事に誘われた。
社交的で決断力のある亮介はまぶしかった。大人しくて自信のない聡美にとっては、自分にないピースを亮介が埋めてくれるような安心感があった。
亮介は年収が高く、上昇志向も強かった。デートでのエスコートも完璧だったし、見た目も悪くない。ただ、一緒にいるとき、急に不機嫌になることがたまにあった。だがそれは、仕事が忙しくて疲れているせいだろうと思っていた。
聡美の二十九歳の誕生日のとき、亮介がプロポーズしてきた。聡美は照れながら「お願いします」と返した。これを逃したら、もう結婚できないような気がした。横浜の大きな式場で、友人たちがうらやむ豪勢な結婚式をあげた。
結婚してすぐ聡美の妊娠が発覚した。歯車が狂い始めたのはその頃だ。聡美は特につわりがひどいほうだった。吐き気で仕事も家事も満足にできない。亮介は怒った。自分では家事を一切しないくせに、家の中が整っていないと我慢ならないようだった。
迷った末に、聡美は仕事を辞めることにした。後ろ髪を引かれる気持ちはあった。給与は安かったが、職場の同僚たちとは良好な関係だったし、仕事も楽しかった。だが自分にとって大切なのは、亮介とお腹の中の子供だと思った。仕事と家庭の両方を追いもとめるのは欲張りなのかもしれない。両方とも中途半端になるのは嫌だった。
仕事を辞めたいと亮介に伝えると、亮介は薄く笑った。
「女はいいよな。すぐに逃げられて」
聡美は何と答えていいのか分からなかった。逃げているつもりはなかった。身を切る決断をしたつもりでいた。
「違うの。家のことをきちんとしたくて――」
「仕事をしていないなら、家のことはきちんとしてね」
亮介は大げさにため息をついた。
税理士だからか、お金の使い道にも口うるさかった。聡美は毎月、一円単位で家計簿をつけて亮介の前で収支報告をしなければならなかった。計算が合わないと、ねちねちと責められる。
もらっている生活費も十分ではなかった。もう少し生活費をくれないかと頼んだこともある。「お前は金を
大きな腹を抱えて、遠くの激安スーパーまで行った。投げ込みチラシを熟読して、特売日はもちろん逃さない。通信費を抑えるために格安スマートフォンに買い替えた。
だが今思うと、妊娠中はまだ平和だった。本当に苦しくなったのは翔が生まれてからだ。
翔は予定日より三週間以上早く生まれた。
それまで痛みは全くなかったのに、ある日の朝、急にじわじわと腰痛がはじまった。亮介に話そうかとも思ったが、迷っているうちに亮介は仕事へ行ってしまった。腰痛はだんだんと強くなった。午後九時を回っても、亮介は帰ってこなかった。十時をすぎて「後輩と飲んで帰る」とメッセージがきた。聡美は腰の痛みを訴えたが、「明日病院に行ってみたら」と返信があっただけだ。
腰痛で一睡もできなかった。午前二時、はうようにしてトイレに行ったら、少量の出血があった。恐ろしくなって病院に電話すると「今から来てくれ」という。
一人で立つことはできなかった。雨傘を二本使って、松葉杖のように体重をのせながらなんとか外に出る。タクシーをつかまえて自力で病院に向かった。
やっとの思いで分娩室に入ると、あとは早かった。ものの三時間ほどで生まれた。生まれたばかりの翔を腕に抱いたとき、意外なことに感激や喜びは込みあげなかった。ただホッとした。一人でやり切った。思えば、聡美の人生で一番達成感を味わったのは、このときだったかもしれない。
午前六時頃、病室でスマートフォンを見ると亮介からメッセージが入っていた。「なんで家にいないの? 男でもできたの?笑」とある。脱力した。病院からは亮介にも連絡がいっているはずだ。留守番電話を確認していないのだろうか。気持ちがすうっと引いていくのを感じた。
しばらくすると聡美の両親が駆けつけた。亮介がやってきたのは、昼前になってからだった。その日は土曜日だった。これが平日だったら、亮介は来なかったかもしれない。
翔が生まれてからの記憶はとびとびだ。
夜泣きが激しい子だった。翔が泣きはじめると、亮介は迷惑そうに顔をしかめ、ブランケットを持ってリビングルームのソファへと移動する。
北鎌倉の両親を頼ろうかとも思った。だが、父は
帰宅したときに夕食ができていないと亮介は不機嫌になる。けれども亮介の帰宅時間は日によって違うし、連絡なしに外で食事をとってくることもある。限られた食費を考えると、つくった料理を無駄にするわけにはいかない。翌日の昼間、聡美が残飯を食べた。人と話すこともない。声の出し方すら忘れていく。
休日はさらにみじめだった。亮介は昼すぎまで寝て、食事をとるとソファでダラダラしていた。聡美だけが
翔が泣いていても亮介はお構いなしだ。それが一番こたえた。我が子が泣いているのに放っておけるなんて、どういう神経をしているのだろう。そう思ってイライラしていると、ふと、まだ亮介に期待している自分がいたのかと驚く。
亮介に手伝いを頼んだこともある。だが亮介は、「じゃあお前は、俺の仕事を手伝ってくれるわけ?」と言った。
「別に
対等な関係で役割分担をしているだけなのか。それならどうして、亮介はいつも偉そうで、聡美は亮介の機嫌をうかがってばかりいるのか。
「でも……」聡美が口を開くと、亮介はぎろりとにらんだ。
「私もたまには休みたくて」
ぜいたくは言わないから、せめてぐっすりと眠りたかった。最後に三時間以上まとめて寝たのはいつだったか分からない。
「俺は忙しい仕事をやりくりして、なんとか休日を作ってる。お前ももうちょっと、頭使って工夫したらどうなの?」
翔が生まれてからも、亮介から渡される生活費は変わらなかった。亮介の生活も変わっていない。休日に友人たちとゴルフに出かけることもあるし、飲みに行くこともある。それらはいずれも「俺が工夫して
それでも聡美はめげなかった。仕事だと割りきって、毎日働くつもりで家事や育児をこなそうと試みた。同僚もいないし、ボーナスもない。孤独な仕事だ。平気な日と、涙がとまらない日があった。だが、なんとか日々、踏んばっていたのだ。
限界が近いことは自分でも分かっていた。
昨日のことだ。
土曜日の昼さがり、亮介はリビングルームのソファで横になっていた。ビールを飲み、テレビを見ながらくつろいでいる。片手でしきりにスマートフォンをいじっていた。夜間や休日に仕事のメールを返していることもある。聡美はあまり気にしていなかった。
しばらくすると、亮介は寝入ってしまった。スマートフォンを握った腕がソファからにょきっと飛びだしていた。力がゆるんだのか、亮介の手からスマートフォンが落ちた。ゴトッと音がしたが、亮介は起きない。よほど仕事で疲れているのだろうと思った。最近は常に帰りが遅かった。
近寄って、落ちたスマートフォンを拾う。
中を見るつもりはなかった。ただ、目に入った。
茶色と黄色で配色されたアプリ、カカオトークが開かれていた。
トーク画面に名前は一つしかない。「S♡Aya」である。
名前の横に③と表示されていた。未読メッセージが三件きているということだ。最後に送られたメッセージには「今日もあのフレンチだよね? 楽しみ!」と記されている。
手が震えた。
とっさにスマートフォンを伏せて、元の落下位置に戻した。
深呼吸をしながら、寝室へ移動する。ベビーベッドで寝ている翔の寝顔を見つめた。
亮介は浮気をしている。
LINEでやり取りをすると、妻にバレやすい。だから最近は、浮気相手とカカオトークでやり取りをするらしい。女性誌のコラムで読んだことがある。
そうと気づくと、亮介の怪しい言動はいくつも思いあたった。
土日でも夕方から出かけることはざらにあった。友人と飲むと聞いていたが、亮介の友人を紹介されたことはない。
平日の帰りも遅い。週に一度ほどは朝帰りがあった。
聡美は翔の世話に必死で、亮介の話を
S♡Ayaという名前が頭の中でぐるぐると回った。亮介の話の中で、よく「杉山さん」という人物が登場する。同じチームに所属する女性税理士で、亮介の後輩にあたるらしい。とても優秀で、産後一カ月で仕事に復帰し、バリバリと働いているという。Sは杉山のSなのではないか。
杉山あや。
口の中だけでつぶやくように言ってみた。なんとなく、華やかな女性の姿が浮かんだ。地味顔の聡美とは正反対のタイプの女だ。
夕方、亮介は平気な顔で出かけて行った。とめたり、問いただしたりできなかった。気が動転して、どう対処していいか分からない。普段より入念にトイレの掃除をしたり、風呂のカビをとったりする作業に没入した。身体はくたくたのはずなのに、不思議と疲れは感じなかった。亮介は夜遅くに酔っ払って帰ってきた。
自分の中で何かがプチンと切れたのは、翌日、つまり今日のお昼だった。
亮介と向かい合ってガパオライスを食べていた。正確には、ガパオライスを食べていたのは亮介だけだ。聡美は翔に離乳食を食べさせるのにかかりきりで、自分の食事どころではなかった。
テーブルの上で亮介のスマートフォンが震えた。画面は伏せられていた。杉山からの連絡ではないかと思った。
亮介はスプーンを皿のふちに置いて、スマートフォンに手を伸ばそうとした。だが動きが雑だった。スプーンが皿の上で跳ねて、床に落ちた。亮介は構わずスマートフォンを手にとり、いじりはじめた。
聡美は何も言わず、翔へ離乳食を与え続けた。しばらくして亮介が口を開いた。
「ねえ、スプーン」
その言葉を聞いて、聡美の身体は急に震えはじめた。自分でも訳が分からなかった。涙が一気にあふれ出した。
亮介は、落としたスプーンを拾えと言っている。新しいスプーンを用意しろと言っている。それも聡美の仕事だと。
やっと自分の気持ちに気づいた。聡美は怒っていたのだ。今までは自分の怒りにすら目を向けていなかった。直視するのは恐ろしかった。
聡美は翔を抱いて立ちあがった。離乳食で汚れた翔の口をさっとふく。何も言わずに玄関へと向かった。
「えっ? 何?」
ワンテンポ遅れて、亮介が追ってきた。
聡美は焦った。ゴミ出し用のゴムサンダルをつっかけ、下駄箱の上においてある集金用の小銭入れをつかみ、家を飛びだした。
追ってくる亮介を振りはらうように走り続けた。電車に駆け込む。亮介を振り切れたようだった。スマートフォンすら家に置いてきた。行くあてはなかったが、足は自然と実家のある北鎌倉に向かっていた。幸い電車で一本、四十分ほどの距離である。
電車の窓に映った自分の姿を見てあぜんとした。ジーンズにくたくたのネルシャツを着ている。すっぴんで髪もぼさぼさだ。「生活に疲れたおばさん」というのが、ぴったりな言葉だった。まだ三十一歳になったばかりだ。独身で働いている元同級生たちは、しゃきっとしている。どこで道を間違えたのだろう。
だが、自分がみじめだとは思わなかった。腕の中にある小さい命だけが聡美の誇りだった。翔を立派に育ててみせる。
電車の揺れが心地よいらしく、翔はエヘヘと笑った。笑った顔は亮介そっくりだった。
今はこんなにかわいいこの子も、歳を重ねると亮介のような男になるのかと想像して、背筋が寒くなった。亮介のそばにいてはならないと、強く思った。
電車が鎌倉方面に近づくにつれ、聡美の決心は徐々に固まっていった。
3
「先生、私、離婚したいんです」
聡美の口から言葉がもれた。
ほうじ茶をすすっていた紬先生は顔をあげた。
「さっき追いかけてきた、あの旦那さんと?」
「そうです。私、精一杯頑張ってきたつもりです。我慢もしてきた。だけど、私が我慢し続けるのは、この子のために良くないんじゃないかと思うようになりました」
ソファで眠る翔に視線を落とした。紬先生もつられて翔を見る。「可愛いね」と小さくつぶやき、口元にえくぼを浮かべた。
「明日にも離婚届をもらってきて、夫に突きつけてやります。あの人はどうせ子供に興味がない。親権でもめることもないでしょう。さっさと離婚届に記入して、もう、明日か明後日には役所に出す。私は実家に戻って就職活動をする。新しい生活をはじめるんです」
すらすらと言葉が出てきた。
頭のどこかで無意識に考えていたことなのかもしれない。
「あっ、それは、ちょっと」紬先生が身を乗りだした。両手をパーのかたちにして、こちらに向けている。「ちょっと待って。まだ離婚しないほうがいいかもしれない」焦ったように早口で言った。
「えっ、なんでですか?」言葉に不快感がにじんだ。
せっかくの決意表明に、冷や水を浴びせられたような気がしたのだ。
「そうですよ。お嬢さん」玄太郎が口を開いた。「寺法でも、足かけ三年、丸二年は寺に滞在することでやっと離婚が――」
「お父さんは黙ってて」
紬先生がぴしゃりと言った。玄太郎はすねたように口をとがらせ、カウンターの奥へ引っこんだ。
「まず確認したいんだけど、旦那さんと離婚について話し合ったことはあるの?」
「ないです」
「喧嘩したりは?」
「ほとんどないです。私が何か言っても、すぐに言いくるめられてしまって、喧嘩になりませんから」
「どうして離婚したいと思ったんだっけ?」
「夫は家事や育児に非協力的で、態度も高圧的なんです」
言葉にすると
「あっ、あと、浮気してると思います」
「浮気ね」
口調は落ち着いているが、紬先生の目が一瞬、光ったような気がした。
「いつ浮気に気づいた?」
「昨日です」
聡美は言葉を選びながら、浮気を見つけた経緯を説明した。家を飛びだしたところまで一気に話す。数秒の沈黙の後、紬先生はやっと口を開いた。
「じゃあ、旦那さんに、浮気のことは尋ねてないのね?」
「尋ねてません。私が家を飛び出したから、浮気がバレたと思っているかもしれませんが」
「うんうん、そっかそっか」
紬先生はふっと口元をゆるめて微笑んだ。「パートナーの浮気に気づいたとき、すぐに問い詰めない。これ、離婚を有利に進めるための鉄則だよ。つらいだろうけど、ぐっとこらえて相手を泳がせたほうがいい。あなたもよく耐えたね」
まっすぐ向けられた目には、初夏の海のようにゆったりと暖かくて、明るくて、それでいて何か楽しいことが始まるかのような期待感が浮かんでいる。
「もう大丈夫だよ。これまでよく頑張ったよ」
その言葉を聞いて、
いつの間にか、聡美の頰を涙がつたっていた。今日何度目の涙か分からない。
「お父さーん、
紬先生が後ろへ首をねじった。
「はいはい」玄太郎の声が返ってくる。
「さっき、まだ離婚しないほうがいいかもって言ったじゃん。それには訳があって。そもそも離婚って、どうやったらできると思う?」
聡美は戸惑いながら答えた。「えっと、離婚届を出す?」
「そう。それが一番簡単な方法ね。離婚について二人で合意ができているとき。合意にもとづいて離婚届を出せばいい。じゃあ、一人は離婚したいけど、もう片方は離婚したくないときは?」
「裁判になるんでしたっけ?」
「もめにもめたらね。まずは離婚について合意できないか、交渉してみることが多いかな。交渉が無理そうなら、家庭裁判所に『調停』を申し立てる。男性一人、女性一人の調停委員が中心となって、双方で話し合いをするの。調停で話がつかない場合だけ、裁判官の判断をあおぐことになる。離婚件数全体からすると、調停で離婚するのが八%くらい、その先までもめるのが三%ちょっとくらいね」
八%や三%というのが、高いのか低いのかピンとこなかった。だが無視できない数字だ。離婚した人のうち、九人に一人は、裁判所のお世話になっているのだから。
「離婚までに結構時間がかかるんじゃないですか?」
紬先生は渋い顔でうなずいた。
「調停が半年から一年。裁判も一年ちょっとかかることが多い。両方するなら、離婚まで二年くらい覚悟しといたほうがいいよ」
二年もかけて離婚する人たちがいる。それほどの情熱で片方が別れたいというのなら、別れさせてやったほうがいいのではないかと思えた。そんなに別れたいのに離婚できないのなら、そもそも結婚って何なのだろう。
「じゃあ次の問題」
紬先生は人さし指を立てて見せた。
「一方は離婚したい。他方は離婚したくない。裁判で争うことになった場合、裁判官は何を見て、離婚させるかを決めるでしょうか?」
「どれだけ相手がひどいことをしたかとか、どれだけ夫婦仲が冷めきっているかとか、そういう事情を見るんじゃないんですかね」
言いながら、奇妙な気持ちに襲われた。
公衆の面前で夫婦仲について語るなんて変だ。大の大人が集まってそんなことをしているのかと思うと、
「うんうん、そんな感じ。意外と知られていないのだけど。裁判では、法定の離婚事由がないと離婚できないのよ」
紬先生はA4サイズの黄色いメモパッドを取り出すと、スワロフスキーのついたピンク色のボールペンで文字を書きつけた。書道を習っていたのか、達筆でとめはねが利いている。
『① 配偶者の不貞行為
② 配偶者からの悪意の遺棄
③ 三年以上の生死不明
④ 回復の見込みのない強度の精神病
⑤ その他、婚姻を継続し難い重大事由』
メモパッドを聡美に向けて見せた。
「このうちどれかが必要ということ。あなたの場合は、旦那さんの浮気があったのよね。それだと①の『配偶者の不貞行為』があるということになる。証拠をしっかり集めておけば、裁判になっても離婚できる可能性が高いですよ。浮気の証拠は集めてあるの?」
「いえ。メッセージを見ただけです」
食事の約束を確認している内容だった。もしかすると食事をしていただけで、浮気に至っていないかもしれない。だが、まちがいなく浮気しているように思えた。ただの直感だが、当たっているような気がする。
「証拠は集めたほうがいいよ。疑っていることに気づかれたら、旦那側は証拠を消し始めるかもしれない。浮気について問い詰めていない今だからこそ、貴重な証拠を集められる」
「でも、裁判にならなきゃいいんでしょう? 正直、あの人とこれ以上、話し合いとかしたくないんです。さっさと離婚届に記入してもらって、出してしまいたい。不倫の慰謝料って、大した額はもらえないと聞きました。お金のことはあきらめて、新しい生活を始めたい気持ちが強いです」
紬先生は首を横に振った。
「お子さんがいるでしょう。一、二年の我慢で、今後二十年が変わってくるのよ。これまでも我慢されてきただろうけど、今が一番の我慢のしどころなんだよ」
「今後二十年、ですか?」
「まず不倫の証拠を押さえる。そのうえで旦那さんと交渉。離婚すること、子供の親権はこちらに渡してもらうこと、慰謝料の額について取り決める。さらに、財産分与の内容と、養育費の支払いについても一緒に決めてしまいましょう。不倫の証拠があれば、旦那さん側は強く出られない。財産分与や養育費みたいな、額の大きい部分についても有利な条件でまとめることができるかもしれない。実際は交渉してみないことには、どうなるか分からないけどね」
紬先生はフフッと愉快そうに笑った。
玄太郎が、お盆に新しいほうじ茶と黒糖羊羹を載せてきた。
ゆっくり甘味を味わうなんていつぶりだろう。強烈な甘さに、あごが痛くなるくらいだった。口の中に残る甘い余韻を楽しみながら、ほうじ茶をすすった。心がほぐれていく。
「お嬢さん、
聡美は首を横に振った。
「東衛寺の山号は松岡山という。『まつがおか』と言えば、縁切寺、駆込寺で名高い東衛寺のことをさす。今も昔も、女性の立場は弱い。縁切寺に駆け込んできた女性たちにまつわる川柳が沢山残ってるんだよ」
玄太郎は紬先生のメモパッドを手元に引きよせて、文字をさらさらと書いた。元住職だけあって、玄太郎も達筆だ。
「声に出して、読んでみてごらん」
聡美はメモパッドを手にとり、おそるおそる口を開く。
「くやしくば、尋ね来て見よ、松ヶ岡?」
玄太郎は満足そうにうなずいた。
「江戸時代の人が
玄太郎によると、「くやしくば……」の言い回しには、本歌があるらしい。「恋しくば尋ね来てみよ
時はさらにさかのぼり、平安時代。心優しい青年が、狐を
このエピソードは江戸時代、歌舞伎の演目にもなって人気だった。そこから引っ張ってきて、「くやしくば……」の川柳を詠んだらしい。
「松岡法律事務所に駆け込んできたあんたはラッキーだ。紬先生はこう見えて、なかなかしたたかだからね。きっとあんたの力になってくれるはずだ」
紬先生はホホホと澄ました顔で笑った。
「お父さん、だからこのかたは依頼人じゃないって。なりゆきで助けちゃっただけだし、相談料をとるわけにはいかないんだよ」
「先生に弁護をお願いしたら、いくらくらいかかるんでしょうか?」
紬先生は意外そうに眉尻をあげた。宙でこつんと目が合う。
「着手金で三十万円。慰謝料みたいに、旦那さんから財産的利益を受け取る場合は、別途成功報酬をもらうけど」
聡美は深呼吸をした。三十万円は決して安くない額だ。貯金から出せないこともないが、数カ月分の生活費だと思うと苦しい。
すぐには決断できなかった。
「あと、証拠集めをうちの探偵に頼むなら、その費用も別途かかるよ。調査の範囲にもよるけど、十数万円から三十万円くらいかかることが多いかなあ」
「探偵、ですか?」
唐突な単語に目を丸くした。探偵といえば、ドラマやミステリー小説で出てくる「名探偵」のイメージが強い。
「離婚の証拠集めはプロに頼んだほうが確実だからね。法律事務所によっては探偵事務所と提携していることもあるよ。うちは離婚専門だから、専属の探偵を一人置いてるの」
と言って、部屋の奥に置かれた事務机のほうを振りかえった。
「普段はあそこに探偵の
「先生の机かと思ってました」
「私の
どういうわけか、そんな紬先生を見て、玄太郎は深いため息をついた。
聡美は隣で眠る翔に視線を落とした。
亮介の
翔が生まれた日のことを思い出した。一人で翔を産んだ。その事実を胸のうちで
膝の上で
戦わなくちゃいけないときだと思った。今後の二十年が変わるという紬先生の言葉が胸に重くのしかかっていた。今ここで頑張るか頑張らないかで、翔を大学まで行かせてやれるかが変わってくる。けれども、いきなり探偵や弁護士に頼む覚悟はなかった。
「私、浮気の証拠、自分で集めてみます」
絞り出すように言った。一呼吸おいて顔をあげる。
「先生の名刺、もらっていっていいですか」
「もちろん。何かあったらどうぞ。こうやって離婚を考えはじめたくらいのときに相談してもらえるのがベストだけど、養育費の取り決めは離婚後もできるから。あとからやっぱりどうにかしてほしいって依頼もウェルカムですよ」
紬先生は聡美の反応を予期していたように、微笑みながらゆっくりうなずいた。
「浮気の証拠って、肉体関係があることが分かるものだよ。だから、仲が良さそうな日常会話のメールだけだと不十分だからね」
紬先生が言うには、二人でホテルに出入りしている写真や、肉体関係を認めるやり取りのメールや録音データなどがあれば一番だという。ホテルの領収書なども証拠になることがある。
アドバイスを聞きもらすまいと必死だった。
一方、紬先生は最初からずっと、一貫して余裕のある態度だった。勝手な話だが、それがちょっと鼻についた。安全なところから、あれこれ言われているような感じがしたのだ。
親切にもかくまってくれた。アドバイスもくれた。だがそれらの行為は、圧倒的に恵まれた人からの
身分制があり、尼がいて、仏を信じていた時代ならそれでも良かった。しかし人はみな平等だと教わって育った現代人にとって、施しは屈辱だった。
「失礼ですが、先生はご結婚されたことはありますか?」
意地悪な気持ちで訊いた。「失礼ですが」とつければ許されるものではない。本当に失礼な質問だ。
紬先生は顔色ひとつ変えず、きっぱりと答えた。
「ないですよ。今後も結婚の予定はありません」
ふんわりとした雰囲気なのに、この質問に答える瞬間だけ、紬先生の目に強い光が
聡美はたじろいだ。二人の間にぴりっとした緊張感が走る。
だが同時に、しめしめという気持ちが胸の中にわいてきた。美人で家族に恵まれ、弁護士という立派な仕事についている。完全無欠に見える紬先生にも、欠点があるのかもしれない。
紬先生みたいな人に、聡美の気持ちが分かるとは思えない。いじけた気持ち半分、
「結婚したことのない人に、離婚したい人の気持ちが分かるんですか?」
「分かりますよ」
紬先生は即答した。口元には不敵な笑みが浮かんでいる。聡美からの質問を面白がっているようにも見えた。
「私ね、結婚って意味不明だと思う。だから結婚をやめる人の手伝いなら、進んでやるのよ。みんな結婚、やめちゃえーって思ってるから。縁切り上等! 人の縁を切るのは楽しいのよお。ふふっ」
おかしくてたまらないとでもいうように、紬先生は口元に手をあてて笑った。あざとい仕草も美人がやるとサマになる。
横で玄太郎が再びため息をついた。
――紬先生はこう見えて、なかなかしたたかだからね。
シミひとつない紬先生の横顔をながめながら、玄太郎の言葉を思い出していた。
4
聡美は翔を抱いて家に戻った。
「睡眠不足が続いていて、余裕がなかったの。パニックになって、家を飛び出しちゃった。本当にごめんなさい」
いじらしく謝った。浮気に勘づいたわけではないと、亮介に信じ込ませる必要があった。
亮介は不機嫌を隠さず「信じられない」と言った。「これが会社だったら」とか「母親としての自覚が」とか、ネチネチと言い
何を言われても、聡美は一向に構わなかった。表面上は、亮介の機嫌を直そうとオロオロするふりをした。
家を出た聡美を、亮介が追ってきたのは意外だった。聡美のことなど放置するだろうと思っていた。だがそんなことで心を許してはいけない。亮介は外面がよく
亮介がどこまで勘づいているかは分からない。だが聡美の家出以降、スマートフォンを肌身離さず持ち歩くようになった。風呂に入るときすら脱衣所に持ちこんでいる。これでは浮気の存在を認めているようなものだ。
スマートフォンをこっそり持ちだすことはできるかもしれないが、パスコードが分からなかった。先日偶然中を見たときに、聡美の顔認証でもロック解除できるよう設定しておけばよかったと後悔した。
こっそり鞄の中や、財布の中も漁った。領収書の類は出てこなかった。お金にマメな人だから、領収書はどこかにまとめて整理していそうだ。だがそれは家ではなく、きっと会社に置いてある。
機会をうかがいながら、二週間ほど経った。ここ最近は、亮介の口から杉山の話が出なくなった。以前は何かにつけて、聡美と比べて杉山を褒めることがあった。浮気がバレたかもと肝を冷やして、話題にしなくなったのかもしれない。
今までにもまして、亮介が不機嫌な日が増えた。出した料理に口をつけずに自室に戻ってしまったり、風呂の温度が熱すぎるというだけで怒鳴ったりした。聡美はぐっとこらえて、その度に謝った。
証拠さえ集めれば、この生活を終えられる。それだけが希望だった。「杉山あや」「税理士」などと検索して、情報を探していた。何人かの税理士がヒットしたものの、亮介と接点がありそうな者はいなかった。
少しずつ秋が深まって、涼しい日も増えてきた。焦りだけがじりじりと募る。
突破口になったのは、リンクトインというビジネス特化型SNSだった。実名顔出しで、所属会社や経歴を公開している人も多い。他業種他業界の人とつながるのに便利で、転職の際にもよく使われている。
亮介が所属している会社の名前で検索すると、何名ものスタッフが出てきた。目を皿のようにして女性を探す。
杉山という女がいた。「ジュニアアナリスト」という肩書になっている。ライトグレーのスーツ、白いカットソーを着て、堂々と写真に写っている。理知的な印象の人だった。
名前は「杉山文子」となっている。「あや」ではなく「あやこ」だったのかと腑に落ちた。同じ会社に「杉山」姓の者はこの人しかいなかった。
すぐにフェイスブックを開く。「杉山文子」と検索して、本人らしいアカウントを見つけた。リンクトインに登録されている顔写真と同じ写真が登録されていた。
トップページでは、ビジネスニュースがいくつか引用されている。プライベートな写真などは一枚もあがっていない。
万事休すだった。聡美からダイレクトメッセージを送ってみることも考えた。だが、不倫相手の妻から突然連絡が来たら、杉山も当然警戒する。すぐ亮介に連絡を入れるはずだ。それでは逆効果だ。
ふと、思いついた。
震える指先でスマートフォンを操作する。フェイスブックを一度ログアウトして、IDのところに亮介の電話番号を入れる。亮介の誕生日は七月二十八日だ。パスワードの欄に、ryosuke728とか、ryo728などと適当に打ち込んだ。何通りか試しているうちにヒットした。
新しい機器からのログインだから、亮介のスマートフォンに通知がいっているかもしれない。でも構うものか。亮介は四六時中スマートフォンを見ているわけではない。気づかれないうちに、中をのぞいておこうと思った。
すぐメッセージボックスを開く。「杉山文子」とのやり取りがあった。
深呼吸をして、おそるおそる中を見る。短文のメッセージが連なっていた。一番古いメッセージは、二週間前、聡美が家出した直後だ。
会社のメールだと何だし、こっちで連絡するわ。
という一文で始まり、待ち合わせ場所や日時をすり合わせる内容が続く。会社帰りに何度か会っているようだった。
二人で会ったであろう日時の後にも、やり取りを交わしている。
今日はありがと。
別にいいけど、奥さん泣かせてひどい。笑
でも、もう女としては終わってるし。
子育て頑張ってるんでしょ。
あいつ頭悪いから、息子も馬鹿になりそうで怖い(笑)
でも牧田さんに似るよりはいいんじゃん?笑
ひどっ! 俺に似たほうが良いだろ。
息がとまるかと思った。画面に映る文字列をじっと見つめる。翔は亮介に似てほしくないと願っていた。亮介は亮介で、翔が聡美に似ることを嫌がっている。
なんだ、私たち、嫌い同士なんだ。
腹の中にすとんと納得するものがあった。お互いに嫌いだから、お互いを大事にできない。当然の成り行きだった。
それなら私たちは、どうして結婚したのだろう。互いの中に幻想を見ていたのだろうか。
不思議と亮介に対して腹は立たなかった。
二週間ほど前、聡美が家出したことで、亮介は焦っただろう。浮気に勘づかれたかもしれないと思ったのだ。それで亮介はカカオトークを使うのをやめた。会社のメールでやり取りするわけにもいかず、フェイスブックのメッセージ機能を使うことにしたのだろう。
冷めた目で「杉山文子」という名前を見つめた。
聡美よりもずっと親しげに亮介とやり取りしている。亮介を茶化すような文面から、二人の対等な関係性がうかがわれた。聡美は冗談を言って亮介をからかったことなどなかった。
亮介によると、杉山は子供を産んで一カ月で職場復帰したのだそうだ。服装や化粧もきちんとしているらしい。スーパーウーマンだから、亮介のような男にも対等に物を言えるのだろうか。
杉山と自分を比べるとみじめだった。いい大学を出て、資格をとって、バリバリ働いている。結婚もして、子供も産んで……。
ふと紬先生のことを思いだす。あの人だって美人で、弁護士資格を持っている。
世の中にはどうしてこんなに、すごい人が多いのだろう。聡美が聡美なりに頑張ったところで、自信の持ちようがない。
杉山や紬先生みたいな人たちは、聡美を見下しているに違いない。そう思うと、
寝室から、翔の泣き声が聞こえた。目が覚めて、近くに聡美がいないことに気づいたのだろう。たった一人で病院に駆け込んで、翔を産んだ日のことを思いだす。
翔のことを考えているときだけ、強くいられた。
私の宝物、絶対に守る。
深呼吸をひとつすると、杉山と亮介のメッセージのスクリーンショットをとりはじめた。
十月最後の土曜日、亮介は何も言わずに家を出た。
行き先は分かっていた。渋谷にあるセルリアンタワー東急ホテルのラウンジだ。杉山とのメッセージから、待ち合わせの場所や時刻も把握していた。
亮介を見送って十分ほど待った。
ブラウンを基調とした開放感のあるラウンジで、聡美は明らかに浮いていた。
これでも、汚れのないチノパンと白いブラウスを着てきた。だがパンパンに荷物の詰まったマザーズリュックは場違いに映っただろう。周囲には商談をしているビジネスマンやお見合いをしているらしき男女が多い。
亮介は窓際の明るい席に通されていた。周辺の席は埋まっている。聡美は隅のほうの狭い二人掛けに案内された。亮介と多少距離がある。二人の会話は聞こえないだろう。だがこちらの
すらりとした女性が亮介の前に座った。
あれ、と思った。
女性は片手に赤ん坊を抱いていた。ブランドものの大きなトートバッグを肩からさげている。聡美のリュックと比べると値段は
店員を呼ぶのに、女性が横を向いた。やはり杉山だった。写真で見るよりもずっときれいだった。あごのラインがシャープで肌にたるみがない。モダンな
不倫相手に会うのに、赤ん坊を連れてくるなんてこと、あるだろうか。そもそも、子供を産んだばかりなのに不倫する神経が分からない。そんな人がどういう行動をとるかなんて、分かるはずがない。
スマートフォンを取りだして、カメラを向ける。二人の顔が分かるよう精一杯ズームして、写真をとる。気配を察したかのように、杉山がこちらを振りかえった。面食らったが、そのまま写真を数枚とった。写真を確認すると、杉山の顔がはっきり写っている。
千六百円もするオレンジジュースは、全く喉を通らなかった。
二人は何かをしきりに話し合っている。聡美はすぐにお会計ができるよう、現金を用意した。二人がラウンジを出たら後を追うつもりでいた。ホテルの部屋に入っていく様子を押さえられれば、またとない証拠になる。
だが、三十分ほど経った頃に、亮介だけが席を立った。伝票を荒っぽくつかむと、一人でラウンジの出口へ歩き出した。
後を追うか迷った。用意した現金をつかんで、立ちあがろうとする。だが慌てたせいで、小銭を床にじゃらじゃらとこぼしてしまう。それに反応して、翔が「あーっ、あー」と声を出しはじめた。やばいと思った。身をかがめて、急いで小銭を集める。
顔をあげると、すぐ目の前に、杉山が立っていた。片腕に赤ん坊を抱いている。可愛らしいひよこ柄のチュニックとレギンスを着せている。女の子だ。
「あなた、牧田さんの奥さんですよね?」
堂々とした口調で杉山が言った。
「えっ、あっ、はい」
たじろぎながら、聡美は答えた。
「ここ、いいですか」
杉山は聡美の正面の空席を指さした。聡美は黙ってうなずく。
心を落ち着かせようと思った。聡美は何も悪くない。悪いのは、不倫をしている杉山のほうだ。こうやって正面きって攻めてこられても、聡美としては何も問題ないはずだ。
「牧田さんの不倫のこと、気づいてるんですね」
「あ、あなたね」聡美は声を絞りだした。
何を言えばいいか分からない。だが黙っているのはしゃくだった。
「自分も子供がいるのに、人の家庭をめちゃくちゃにして、何とも思わないんですか」
口から出た言葉は、昼ドラみたいに陳腐だった。
「私は、私だったら、そんなこと、できません。どういう神経してるんですか」
杉山は面食らったように、目を見開いた。
「えっ?」
「えっ、じゃないですよ。白々しい」
「何か勘違いされていませんか?」
「勘違い?」
「そう」杉山は赤ん坊を抱きなおした。
「私は牧田さんから個人的な相談を受けていただけです。こんな小さい赤ちゃんがいて、仕事もあって、不倫なんてしてる暇ないですよ」
あぜんとして、杉山を見つめかえす。
きっちり塗られたファンデーションの下から、青黒いクマが見えた。目も赤く充血している。赤ん坊を抱く手の指には、
この人も母親なんだと急に実感した。
ベビーシッターや家事代行サービスを利用して、なんとか職場に復帰している。男たちからは
「個人的な相談って、何のことですか?」
杉山がため息をついた。ほうれい線がくっきりと刻まれた。
「二週間ちょっと前に、奥さん、家出されたんでしょう。それでどうしようっていう相談というか、愚痴というか、そういうものを聞かされていました。しょうもない話ですよ。自分が浮気していたんだから、奥さんに逃げられても自業自得じゃないですか? 会社の先輩だから律儀に対応していますけど、正直うんざりしていたんです。誰か女の人によしよしって慰めて欲しいだけに見えましたから」
すみません、と言いそうになって口をつぐむ。亮介がしでかしたことについて、聡美が謝るのは筋違いな気がした。
「フェイスブックでやり取りをされていましたよね?」
「ああ、あれを見て、奥さんは今日、こちらにいらしたんですか」杉山は片手で器用に赤ん坊を揺らしながら言った。「会社のメールでやり取りするのも変でしょう。かといって、牧田さんと個人的にLINEを交換するのも誤解を呼びかねません。ビジネス目的で使っているフェイスブックのアカウントでやり取りしていたんです」
「そうだったんですか……」
一旦そうは言ったものの、杉山の話をどこまで信じていいか分からなかった。浮気相手の妻から責められて、作り話をしているだけかもしれない。
「でも、カカオトークでもやり取りされてましたよね」
聡美はスマートフォンを取り出し、メモ帳に「S♡Aya」と打って示した。
「トーク画面にこの名前が表示されていました。これって、あなたのことですよね?」
杉山はスマートフォンをのぞき込み、眉間にしわを寄せた。
「えっ? 何これ?」
しきりに首をかしげている。
数秒して、合点がいったというように顔をあげた。
「あーそっか、そういうことか。私、スギヤマ・アヤコじゃないですよ。文の子と書いて、『フミコ』と読むんです。響きが可愛い『アヤコ』にどうしてしなかったのかと親を責めたこともあります。名前の通り、可愛げのない、頭でっかちな女に育ちました」
自虐するような笑みを浮かべた。
聡美はじっと杉山の顔を見た。こんな美人でも、自分のことを「可愛げがない」と思って悩むことがあるのだろうか。確かにシャープで冷たい印象がある。可愛いというよりは綺麗な人だ。ないものねだりだと思ったが、同時に、杉山に親近感を覚えた。
「第三者の私が口出しするのも変ですが、もし覚悟があるなら、探偵を使ってちゃんと不倫の証拠を集めたほうがいいですよ」
杉山は気づかわしげに聡美を見た。
「お子さんが小さいのに浮気してるなんて最低でしょ。他人事ながら私も腹が立ってきて、牧田さんにやんわり注意していたんですよ。今日も説教してやろうと思っていたんです。休日にわざわざ子連れでやって来たのもそのためです。でも彼は慰めてほしいだけですから、プイッと機嫌を損ねて、どっかに行っちゃいましたけどね」
亮介は浮気のことをとがめられ、杉山に腹を立てていた。だから家で、杉山の話題が出なくなったのかもしれない。
聡美はとっさにその場でスマートフォンを開く。スクリーンショットで保存していたフェイスブックのやり取りを見返す。
別にいいけど、奥さん泣かせてひどい。笑
子育て頑張ってるんでしょ。
でも牧田さんに似るよりはいいんじゃん?笑
杉山のメッセージはどれも聡美をかばっている。「笑」という文字がついているせいで、小馬鹿にされたような印象を抱いていた。だがこれは、茶化して伝えることで、先輩である亮介を怒らせないようにしていたのだろう。
「主人の不倫相手って、あなたじゃないなら、誰なんですか?」
聡美が尋ねると、杉山は再び、深いため息をついた。目を伏せて、数度まばたきをする。口にするか迷っているように見えた。
杉山は深呼吸をして、口を開いた。
「沙也加さんって人。あなたの大学時代の友人でしょ。結婚式の二次会の幹事をしてもらったときに知り合って、そのときからズルズル続いているみたいよ」
5
それから年末まで、あっという間だった。
聡美は松岡法律事務所を再び訪れ、正式に離婚事件を依頼した。
紬先生は「おっけい、おっけい。お任せあれー」と笑って請けおった。
すぐに法テラスに電話をして、二人で出かけた。民事法律
「あれ、どっちだったっけ?」
横浜駅を出てすぐ紬先生は周囲をきょろきょろと見回した。自信満々に「こっちだ」と歩きだしては、「あ、失礼しました。こっちでした」と方向を変える。
もしかしてこの人、ものすごい方向音痴なのか?
不安が込みあげてきた。こんな人に弁護を任せて大丈夫なのだろうか。とりあえず聡美がスマートフォンの地図アプリを見ながら道案内をした。
「法テラスって、よく行かれてるんじゃないんですか?」
やんわり指摘してみると、
「月イチくらいで行ってるんだけど。横浜駅が難しすぎるんだよ。出口が沢山あってさあ」
あっけらかんと返された。
話を聞くに、紬先生は完全なインドア派で、仕事以外ではほとんど外出しないという。移動に慣れていないから迷う。迷って疲れるからもう外に出たくなくなる。負のループにはまっているように見えるのだが、本人はあくまで「おうちが一番だからねえ」とのんびり話している。
法テラスでの手続き自体は簡単だった。いくつかの条件をクリアすれば、弁護士費用を立て替えてもらえる。月五千円の分割払いにしてもらえるらしい。書類を提出して、短い面接を行うだけだった。
二度目の打合せでは、探偵の出雲
出雲は野良犬のような、ちょっと崩れたイケメンだ。事務所一階奥の事務机に腰かけ、背を丸めている。
飲酒や喫煙をやめて、規則正しい生活を送れば、王子様のように見違えるはずだ。だが本人は、自分の見た目に一向に構っていないようだ。
「ちょっと小汚いくらいが、尾行に向いてるんですよ」
言い訳のように低い声で言った。
働きぶりはよかった。杉山から追加でもらった情報に基づいて、亮介と沙也加の密会日を割りだした。自宅から亮介を尾行し、ラブホテルに入っていく瞬間の写真をとってきた。自分では決して集められなかった強力な証拠だ。プロに依頼してよかったとしみじみ感じた。
十五万円ほどの代金がかかったが、仕方ない。弁護士費用のほうを分割払いにしていたから、探偵費用は一括で払えた。
亮介の不倫相手が沙也加だったことに、聡美は少なからずショックを受けていた。夫と友人から、同時に裏切られていたことになる。亮介がカカオトークでやり取りしていた相手は、「S♡Aya」だった。ハートマークを外して読むと「サヤ」となる。
沙也加に付き合って、東衛寺を訪れたことが思い出された。片想いの相手と、そのパートナーの縁が切れるよう祈願したいと言っていた。
あれは亮介と聡美の間の縁を切ろうとしていたのだ。だからこそ聡美を誘って、一緒に
だが悔いはなかった。あんな男、沙也加にくれてやる。
不倫の件がなくても、遅かれ早かれ、亮介との関係は煮詰まっていただろう。むしろ不倫が発覚したのは良いきっかけだった。
必要な証拠をすべて揃えたところで、聡美は家を出た。荷物は密かに少しずつ、実家に送っていた。
両親に事情を説明したとき、母は絶句していた。だが父はぼそりと「帰ってこい」と言ってくれた。それだけで十分に心強かった。
翔を連れて実家に戻った途端、亮介は慌てた。だが反撃する暇も与えず、紬先生が亮介を呼びだした。
不貞の証拠は押さえてあること、聡美は離婚を希望していること、翔の親権は聡美がとること、翔の大学卒業まで一定の養育費を払う必要があること、婚姻期間中に亮介が稼いだ財産の半分は聡美のものであること。
紬先生は淡々と説明した。
亮介は大人しく聞いていた。見栄っ張りな人だ。誰かの前で取り乱したり、暴言を吐いたりしない。同席した聡美をじっと、
「僕のほうでも弁護士を立てます」
宣言通り、数日のうちに亮介の代理人から連絡が入った。代理人同士でやり取りして、聡美の要求を八割がた飲むような条件で合意に至った。
年の瀬が迫った十二月中旬、亮介と聡美、それぞれの代理人が連れ立って公証役場に行った。取り決めた内容を公正証書にしておくためだ。
養育費の支払い約束を公正証書にしておけば、万が一、養育費が支払われない場合にも強制執行をかけることができる。亮介の給料のうち一部を差し押さえて、聡美が受け取ることができるのだ。
紬先生に依頼していなかったらこれほどまでにきっちりと養育費の取り決めを交わせなかっただろう。弁護士報酬はかかるものの、気苦労を一部肩がわりしてもらえたのはありがたかった。
公正証書をつくった後、亮介から離婚届を受け取った。すぐに署名をして、出してしまうつもりだった。
離婚届を持って役所に向かい、記入台の前に立つ。
いざ自分の名前を書こうとすると、手が震えた。
私、本当に離婚するんだ。そう思うと足がすくんだ。
自分がバツイチになるなんて幼い頃は想像もしなかった。そういう人たちがいるのは知っていたが、自分の身に降りかかってくるとは思っていなかった。
ひと思いに離婚届に記入して窓口に提出した。窓口担当の女性は一瞬にやりとしたが、すぐに真顔に戻って「受領しました」と、ことさら事務的に言った。
やっとすべてが終わり、すべてが始まる。
年が明けて、一月二日。
聡美は翔と一緒に、東衛寺を訪れた。
人の流れに身を任せて
小銭入れから五円玉を取りだして、ふと手をとめた。もう縁づくのはこりごりだ。そっと五円玉を戻す。
親子ともども健康に暮らせますように。新しい生活が軌道に乗りますように。就職先が決まりますように。
これまでの人生で一番熱心に祈ったかもしれない。賽銭箱から離れて外に出ると、門の前で玄太郎と行きあった。ゴム手袋をはめて大きなゴミ袋を持っている。門前で
「あけましておめでとうございます」
聡美が頭をさげると、玄太郎は破顔した。
「ああ、牧田さん。じゃなくって、今は
玄太郎は聡美の旧姓を口にした。
「事務所に寄ってやってください。紬先生は年末年始も関係なく、仕事に追われているみたいです。小山田さんの顔を見たら喜ぶと思います」
玄太郎とその場で別れて、松岡法律事務所に向かった。
弁護士は年末年始も働くのか。大変だなあと他人事ながらに思った。そういえば亮介も年末年始に忙しくしていることがあった。今となってはそれが本当に仕事だったのか分からないが。
道沿いの
事務所について、玄関口で扉を叩く。反応がない。
「おはようございます」
と声をかけてみるがやはり返事はない。
扉に手をかけると、鍵がかかっていなかった。おそるおそる顔だけ中に突っこむ。一階には誰もいなかった。
突然、ガシャンッと二階から物音がした。何か重いものが落ちて割れたような音だ。ガタガタ、ドンと大きな音が続く。翔が驚いて、腕の中で泣きはじめた。
聡美はとっさに靴を脱ぎ、壁際の階段をあがった。紬先生が過労で倒れたのかもしれないと思った。
階段をあがってすぐのところに、高さ一メートルくらいの金属製の
机の周りはひどい有り様だった。机上には書類が山積みになっている。書類の合間をぬうようにマグカップが五つ並んでいた。片付けずに放置しているものらしい。壁際に並んだ本棚から、いくつかのファイルが落ちて散乱していた。そのすぐ近くに紬先生が尻もちをついていた。
「先生、大丈夫ですか」
慌てて柵を開け、駆けよった。
「ああ、牧田さん。じゃなくって、小山田さんか」
紬先生が顔をあげた。聡美がさしだした片腕をとって、よろよろと立ちあがる。ウールのスカートがタイツのはき口に巻き込まれて、めくれあがっている。
「先生、スカート!」
聡美が慌てて指摘する。
紬先生は「ああ」とスカートを引っ張って、形を戻した。
「どうも、あけましておめでとう」
何事もなかったように紬先生が笑いかけてきた。聡美も戸惑いながら挨拶を返す。
書類の山の隙間から、猫が二匹ひょっこりと顔を出し、聡美をまじまじと見つめた。
一匹は鼻先に黒い模様の入った白黒模様、もう一匹は尻尾が短く折れ曲がった茶トラ柄だ。
「あら、知らない人がいるのにトメ吉とハネ太が出てくるなんて珍しい」
紬先生はかがんで、両手で二匹を抱きあげた。
白黒の猫を前に出して「こっちがトメ吉。女の子」、茶トラの猫を前に出して「で、こっちがハネ太。男の子」
名前が分かるのか、ハネ太は元気よく「にゅあー」と鳴いた。
「可愛い名前ですね」
「でしょー?」ハネ太は紬先生の腕の中で喉を鳴らしている。
白黒のトメ吉は抱っこが嫌いらしく、腕から勢いよく飛びだして、一メートルほど離れたところで毛づくろいをはじめた。
「私、寺の娘じゃん? 小さい頃から書道をしてて、
ハネ太をなでつけながら、のんびりと言う。
翔は猫を近くで見るのは初めてだ。聡美に抱きつきながら、首だけ回して不思議そうにハネ太を見つめていた。
「寺の娘、そうか。そうですよね」
紬先生は縁切寺で育った。離婚したくて願掛けにくる人たちを小さい頃から沢山見ているだろう。だからこそ、「結婚って意味不明」と思うし、自分自身も結婚しないと宣言してしまうのかもしれない。
聡美の思案顔に気づいたのか、
「あはは、写経ってジジ臭いか? 料理も趣味だし、猫飼いさんのYou Tubeを見るのも好きだよ。って、聞いてないか」
と、のんきに続ける。
弁護士という仕事があって、写経と料理が趣味で、可愛い猫を飼って、猫飼いさんのYou Tubeを見て……と、おひとり様の生活も充実している。だから積極的に結婚したいと思わないのだろう。
「いや、というか先生、この部屋、どうなってるんですか?」
聡美は部屋を見渡した。大きな机が一つ、簡単な事務机が二つあるが、どれも物で埋まっている。書類は半分ほど整理されているが、それ以外は出しっぱなしになっている。
「どうって、ここは私の執務室だけど」
「執務室、こんなに散らかっていて、仕事できるんですか?」
「えっ。できるけど」
紬先生は不快そうに口をとがらせる。耳の痛い指摘だったのかもしれない。
「夏までは事務員さんがいたんですよ。でも旦那さんの転勤で引っ越してしまって。それ以来、お父さんと出雲君にも手伝ってもらっているけど、まあ、この有り様というか……私ってどうも整理整頓が苦手で。顔が整いすぎているせいかな」
紬先生は首をかしげながら、本気なのかジョークなのか分からない一言を付け加えた。
反応に困り、あはは、と笑って流すしかない。
「事務員さん、募集しないんですか?」
「募集、してますよ。でもね、誰でもいいってわけじゃないんですよ。契約書とか
あれっ、もしかして。
ふいに浮かんだ考えに、胸が高鳴った。
いや、さすがにそんなに都合よくいくわけがない。頭の中で打ち消してから、もう一度考える。
契約書を整理する仕事ならしたことがあった。経理部の仕事も手伝っていた。秘書業務も経験がある。実家は北鎌倉駅の反対側だ。事務所まで徒歩で十五分、自転車だと十分以内の距離に住んでいる。
自分以上に適任の者はいない気がした。
先ほどの初詣で、就職先が決まりますようにと願ったばかりだった。こんなにタイミングのよい話があるだろうか。
奮発して百円玉をお賽銭箱に入れたのがよかったのだろうか。
迷っているだけではダメだ。勇気をふりしぼって、ええいままよと口を開いた。
「あの、先生。事務員募集、私じゃだめですか?」
紬先生はどんぐり眼をさらに丸くして、聡美を見つめかえした。
畳みかけるように、聡美は自分がいかに適任かを説明した。
書類周りの仕事もできるし、事務所の掃除もできる。方向音痴の紬先生のガイドだって、やろうと思えばできると請けあった。
紬先生はハネ太を抱きながら、神妙な顔で聞いていた。
「小山田さんの案件はもう終わったから、弁護士
そこで言葉を詰まらせた。
ハネ太がぐるぐると喉を鳴らす音が事務所に響く。
「でも、この仕事は、小山田さんにとっては辛いかもしれないよ。離婚の傷もまだ癒えていないでしょう。他人事とはいえ、沢山離婚事件を見るなんて、自分の傷をえぐるようなものだよ。相手方から嫌がらせを受けることも多いしさ」
紬先生の言うことはよく分かった。
聡美も、離婚に至る経緯を思い出して、気分が
だが落ち込んでいる暇はなかった。とにかく働いて、翔と暮らしていかなくてはならない。月に一度、亮介と翔は面会交流することになっている。きちんと育っていることを亮介に見せつけてやりたかった。
亮介には散々傷つけられた。聡美と翔が二人で幸せに暮らしていくことが、一番の復讐になる気がした。聡美なりの意地だった。
「私はここに駆け込んで、やっとあの人と戦うことができた」発する声はかすれている。だがするすると言葉は出てきた。
「これからも戦うし、負けるわけにはいかないんです」
何と、誰と戦っているのか。自分でも
「事務員といっても内勤だけじゃないよ。出雲君の仕事の手伝いで、場所取りや尾行をしてもらうこともあるし、何かと大変だよ?」
紬先生が保険をかけるように言ってくる。その目には戸惑いの色が浮かんでいた。そりゃそうだろうと思う。数カ月前、弁護士と依頼人という関係で知り合ったばかりだ。上司・部下となると勝手も違うだろう。
「大丈夫です。先生、雇ってください。きちんと働いて、自立して、あの人に言ってやるんです。くやしくば尋ね来て見よ松ヶ岡、って」
紬先生と目が合った。
数秒の沈黙ののち、紬先生の目元がふっとゆるんだ。
「お父さんの昔話、説教臭くて嫌なんだけどなあ」
頭をかきながら、聡美に笑いかけた。
「とりあえず、まずはこの部屋の掃除をお願いしようかな。物を整理する暇がなくって、散乱してるんだよ」
なぜか自慢げに言った。
聡美は執務室を見渡した。骨が折れそうだ。けれども、胸の内にわきたつ気持ちがあった。久しぶりに外で働けるのが嬉しかった。
「よろしくお願いします」聡美は頭をさげた。
身体の揺れに反応して、翔がはしゃぎ声をあげた。聡美は腕の中のぬくもりを感じながら、翔を優しく抱きしめた。