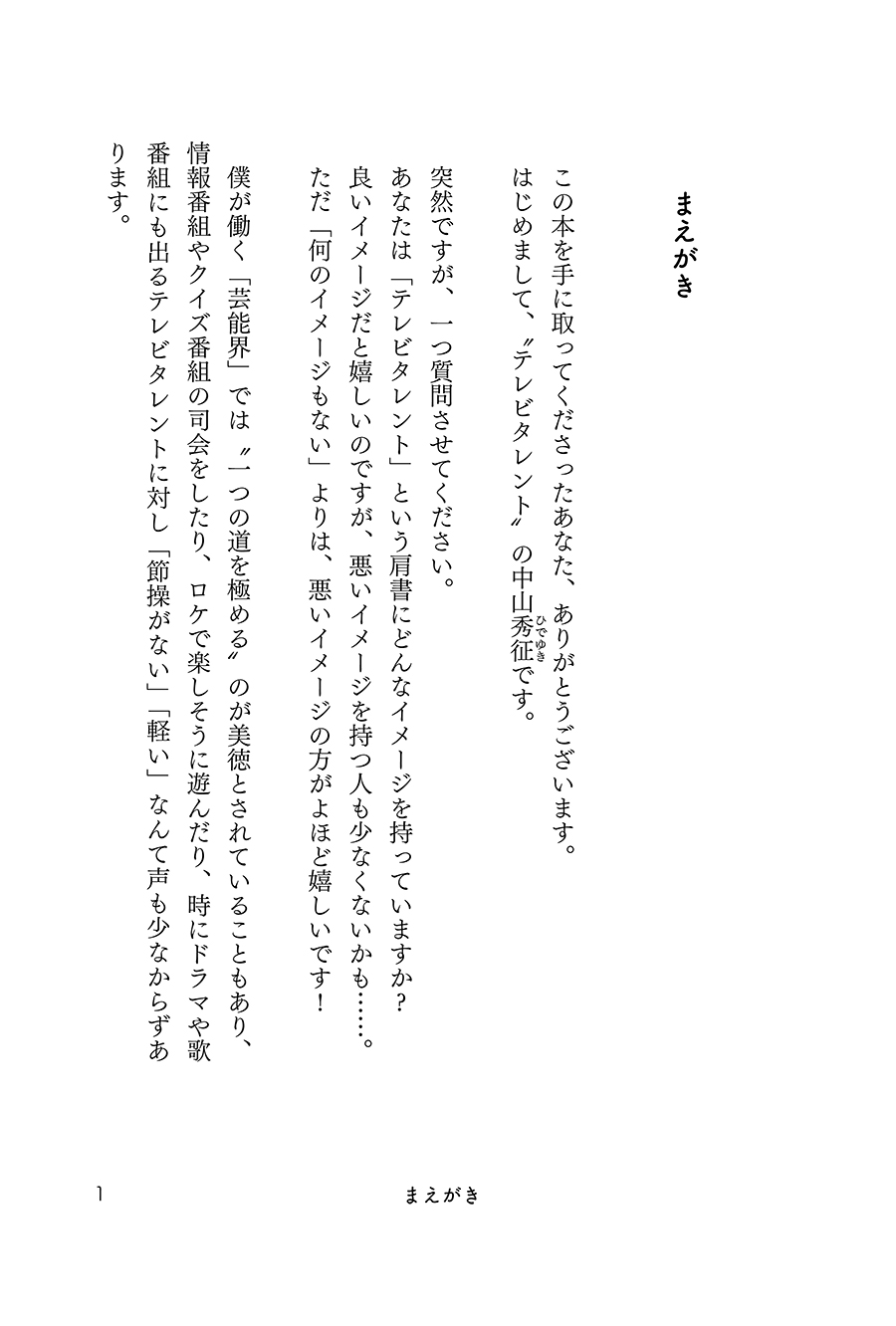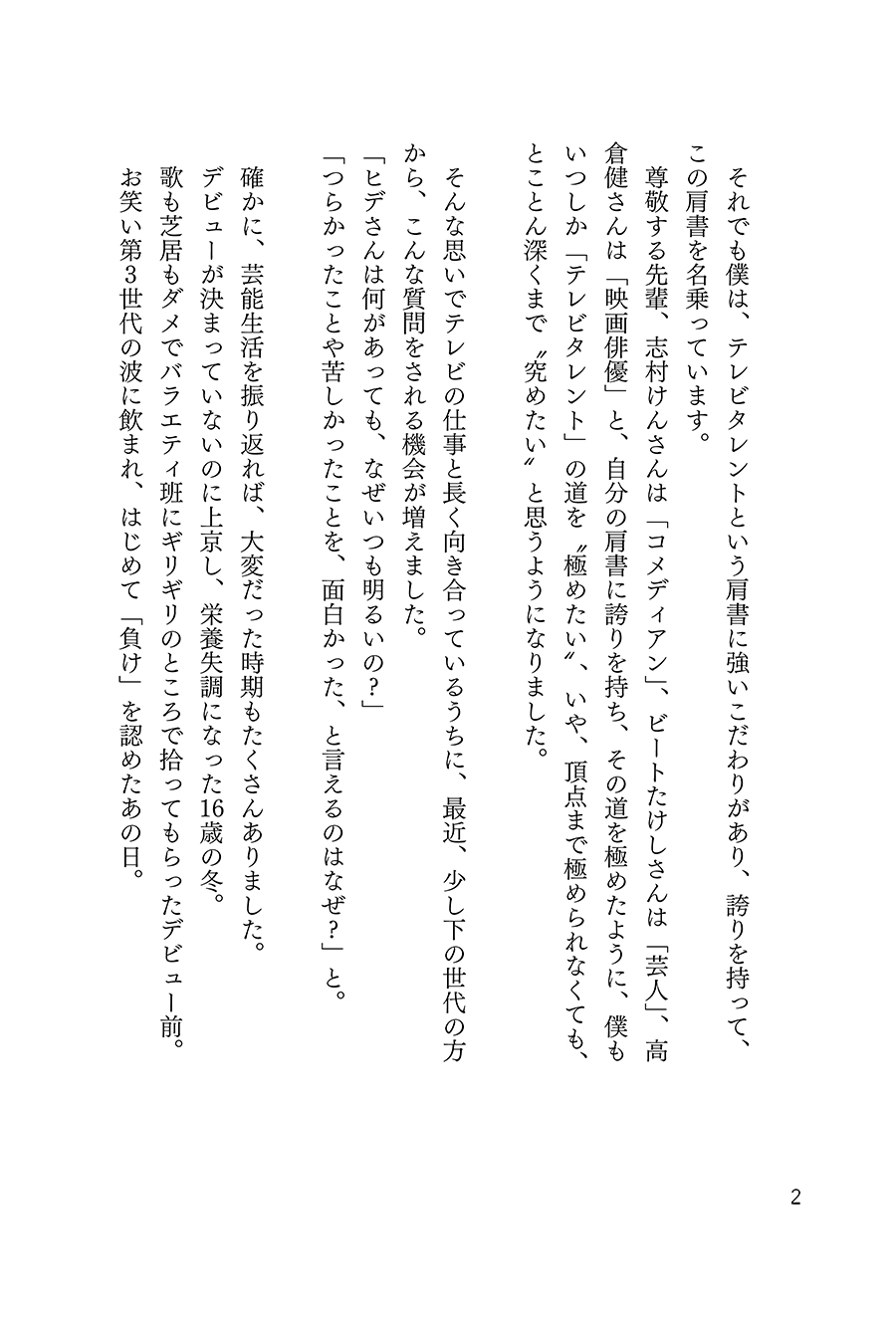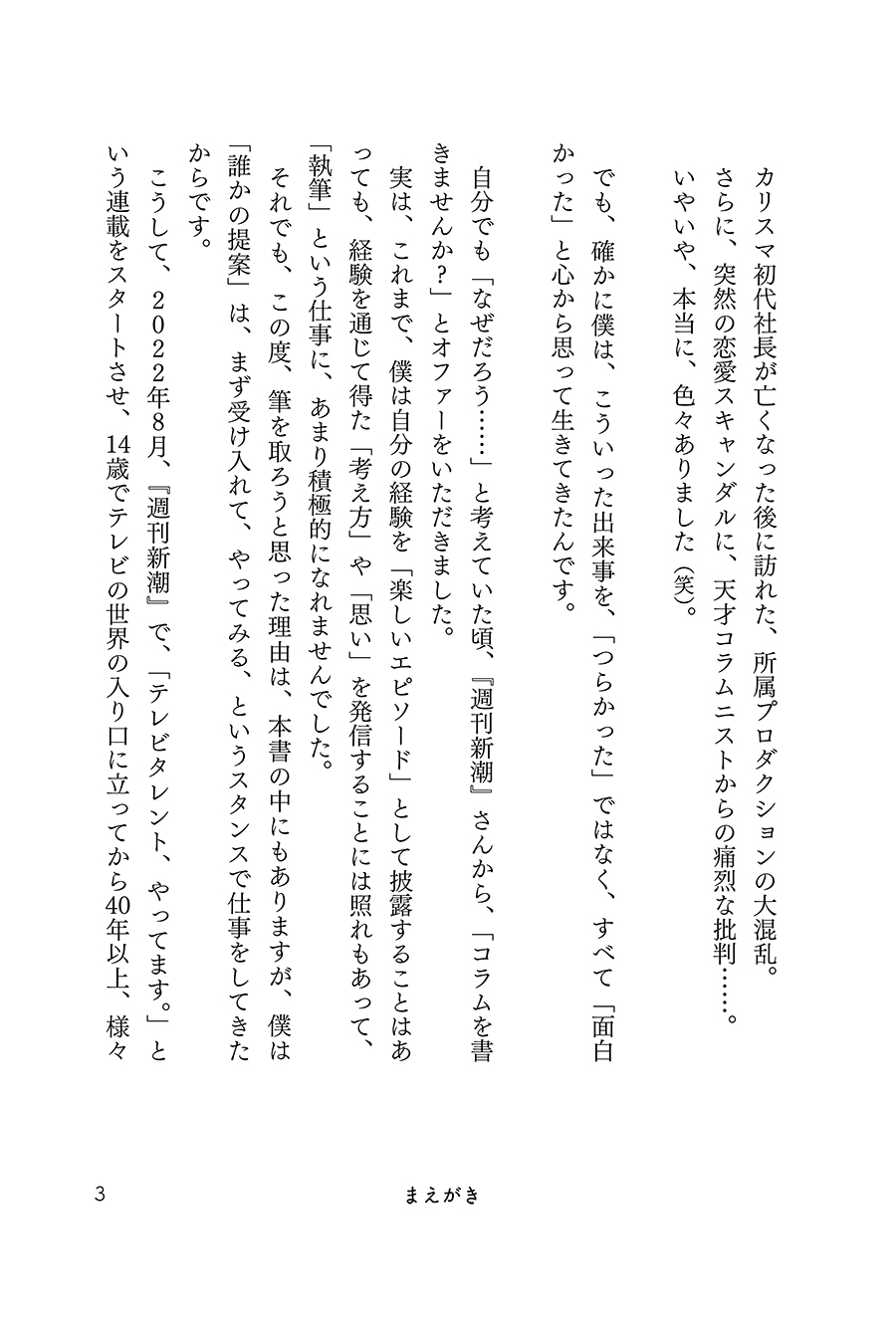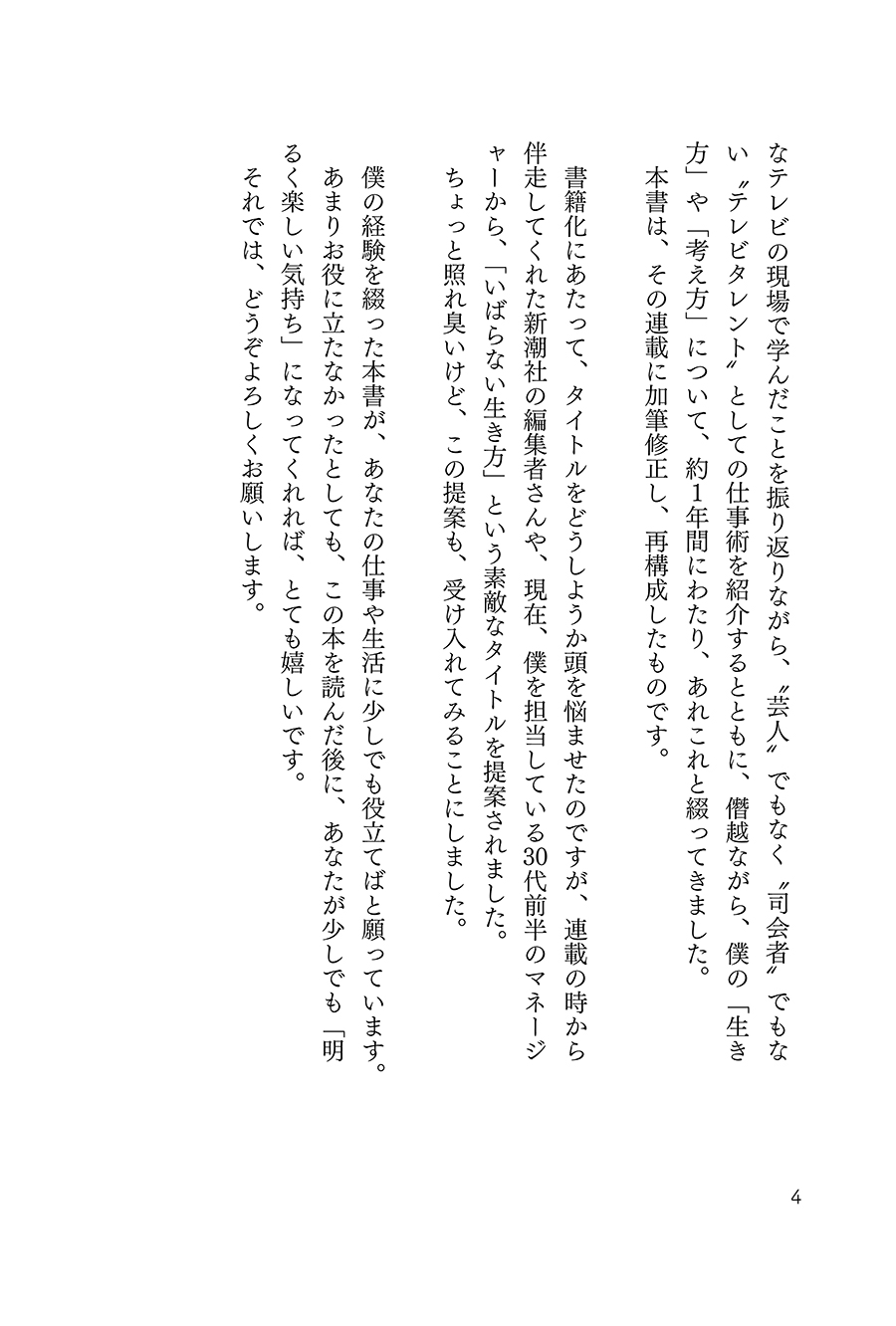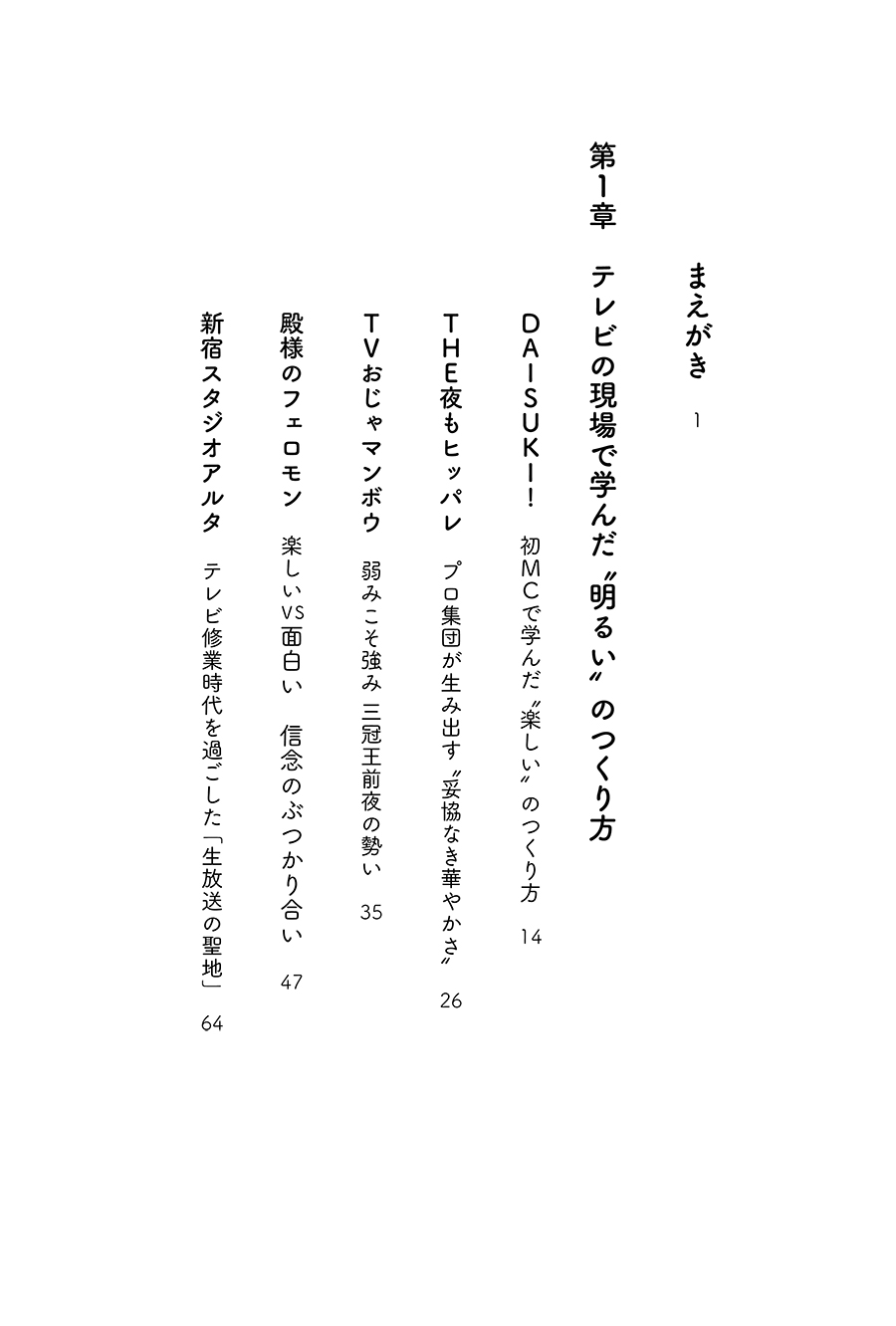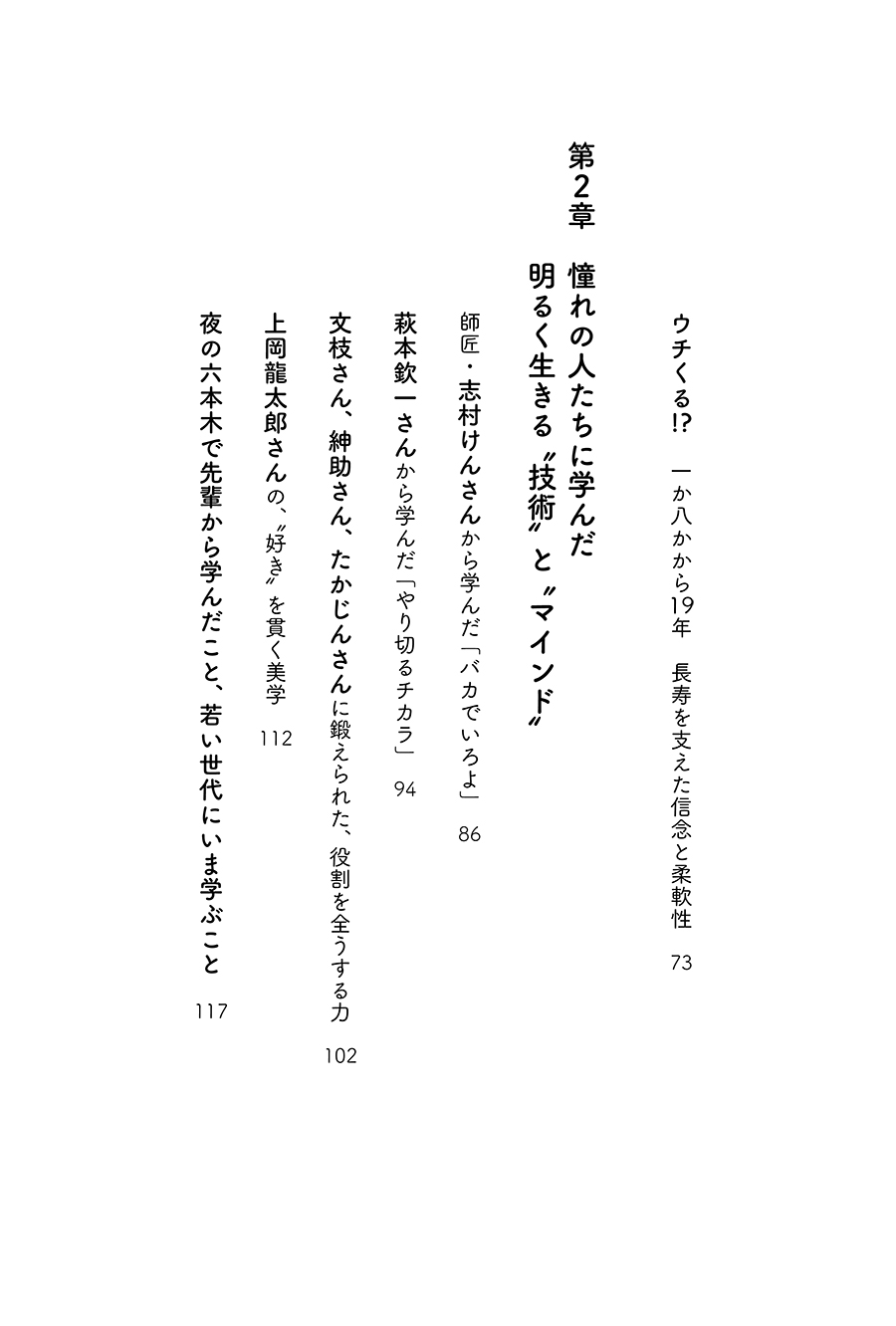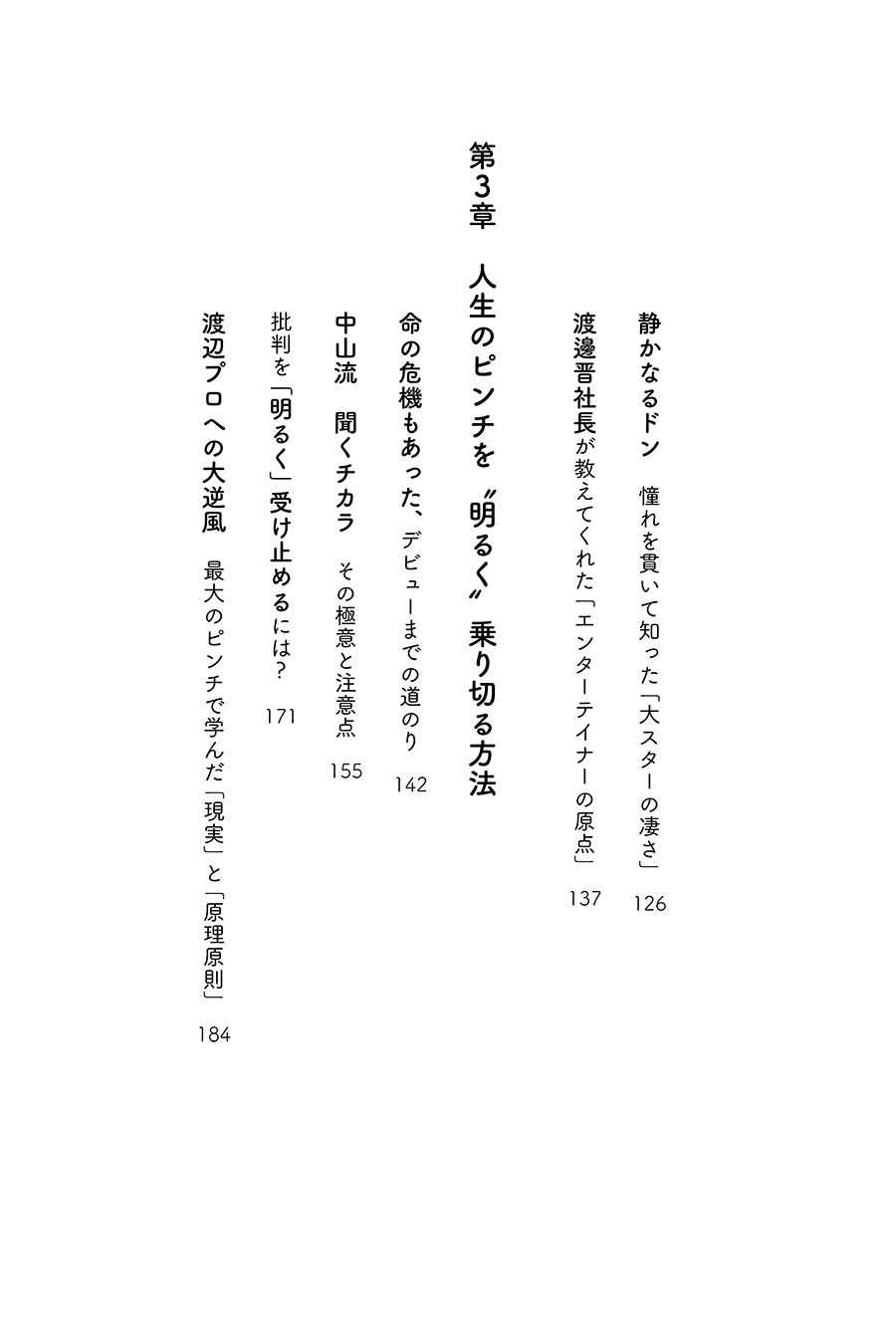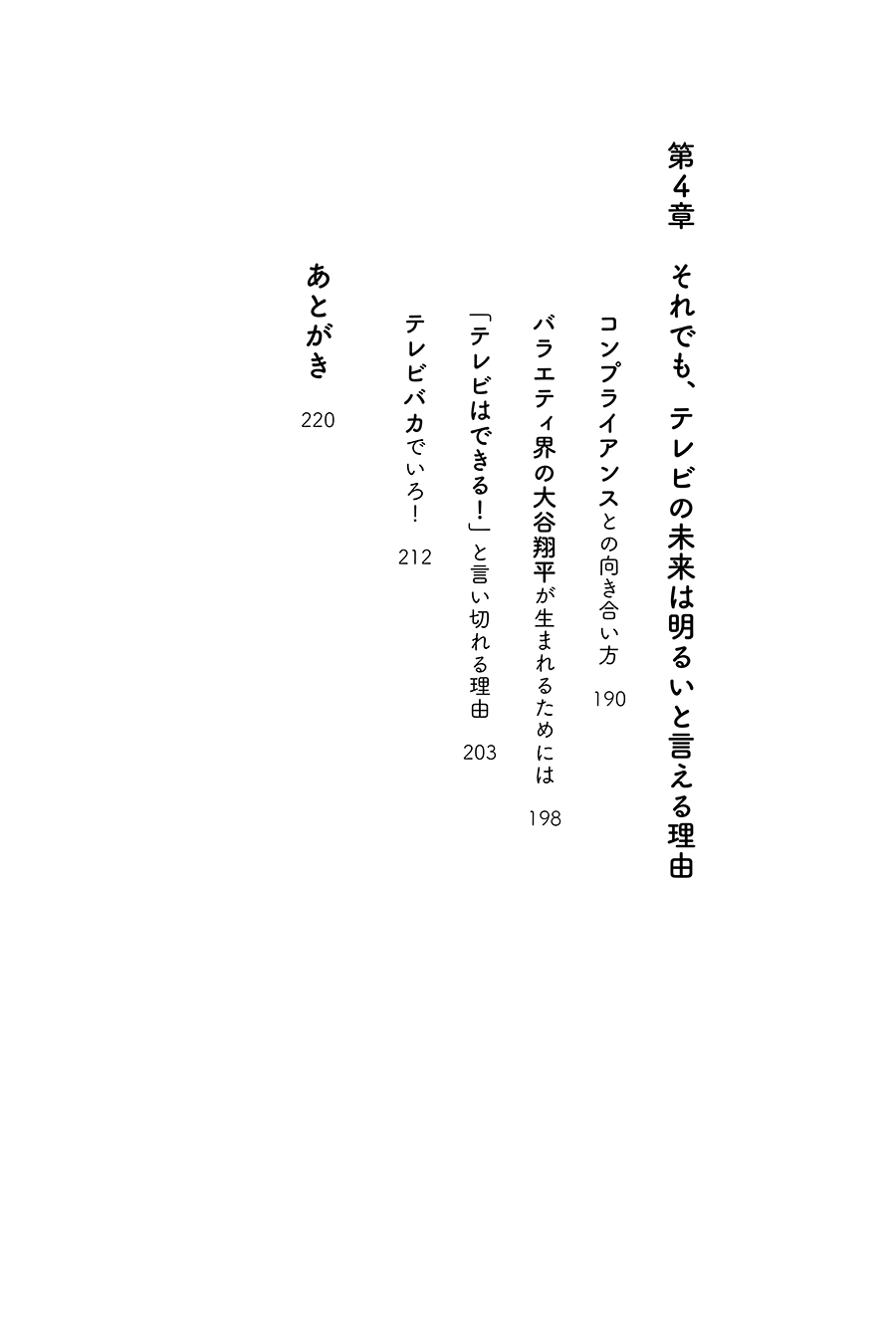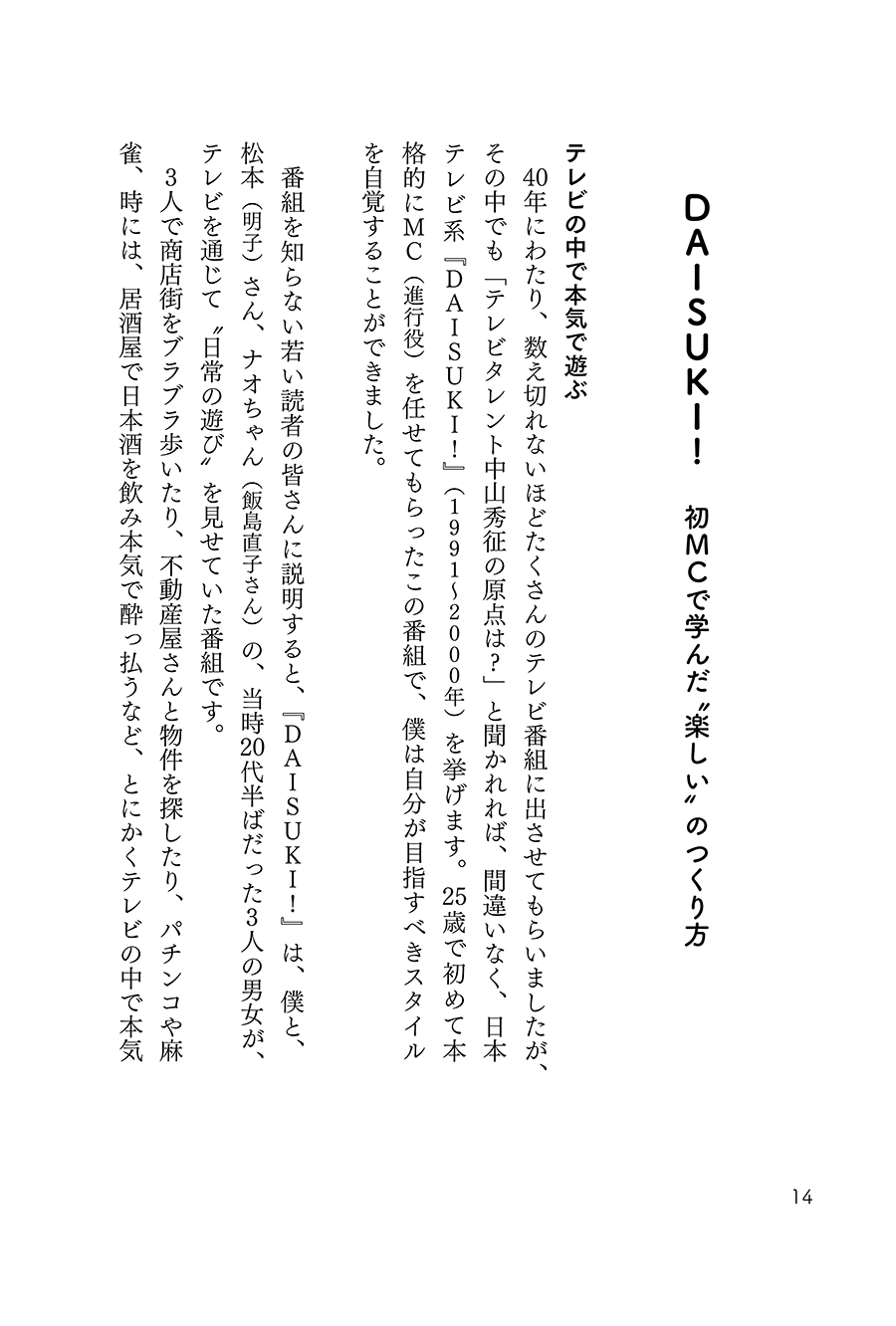まえがき
この本を手に取ってくれたあなた、ありがとうございます。
はじめまして、“テレビタレント”の中山秀征です。
突然ですが、1つ質問させてください。
あなたは「テレビタレント」という肩書にどんなイメージを持っていますか?
良いイメージだと嬉しいのですが、悪いイメージを持つ人も少なくないかも……。
ただ「何のイメージもない」よりは、悪いイメージの方がよほど嬉しいです!
僕が働く「芸能界」では“道を極める”が美徳とされていることもあり、情報番組やクイズ番組の司会をしたり、ロケで楽しそうに遊んだり、時にドラマや歌番組にも出るテレビタレントに対し「節操がない」「軽い」なんて声も少なからずあります。
それでも僕は、テレビタレントという肩書に強いこだわりを持ち、誇りを持って、この肩書を名乗っています。
尊敬する先輩、志村けんさんは「コメディアン」、ビートたけしさんは「芸人」、高倉健さんは「映画俳優」と、自分の肩書に誇りを持ち、その道を極めたように、僕もいつしか「テレビタレント」の道を“極めたい”、いや、頂点まで極められなくても、とことん深くまで“究めたい”と思うようになりました。
そんな思いでテレビの仕事と長く向き合っているうちに、最近、少し下の世代の方から、こんな質問をされる機会が増えました。
「ヒデさんは何があっても、なぜいつも明るいの?」
「辛かったことや苦しかったことを、おもしろかった、と言えるのはなぜ?」と。
確かに、芸能生活を振り返れば、大変だった時期もたくさんありました。
デビューが決まっていないのに上京し、栄養失調になった16歳の冬。
歌も芝居もダメでバラエティ班にギリギリのところで拾ってもらったデビュー前。
お笑い第三世代の波に飲まれ、はじめて「負け」を認めたあの日。
カリスマ先代社長が亡くなった後に訪れた、所属プロダクションの大混乱。
さらに、突然の恋愛スキャンダルに、天才コラムニストからの痛烈な批判……。
いやいや、本当に、色々ありました(笑)。
でも、確かに僕は、こういった出来事を、「つらかった」ではなく、すべて「面白かった」と心から思って生きてきたんです。
今から10年ぐらい前のことです。
私のマネージャーを20年近く勤めてくれている大川内くんから、「芸能界で学んだことや経験したこと、結婚して家庭ができて子育てに奮闘していることなどを執筆しませんか」と話がありました。
でもその時には「俺がやって来たことは特別じゃない、普通のことだから」と断りました。照れはもちろん、まだ何も成し遂げていないし……という迷いが正直ありました。
すると彼は、「いつも僕たちに話してくれてることは、芸能の世界ではない、テレビを見て下さっている方たちの生活や人生にも、きっと何かの参考になるんじゃないかと僕は思っています。何より、聞いていて面白い、元気が出る話ばかりですから……!」と言いました。「面白い」「元気が出る」、この言葉がずっと心のどこかにひっかかっていて……。
月日は流れ、2年前頃、週刊新潮さんから、「コラムを書きませんか?」とオファーをいただきました。
このオファーを聞いた瞬間、自分の経験を「楽しいエピソード」としてだけでなく、その経験を通じて得た「考え方」や「思い」を発信してみようかなと、自然にスッと思えたんです。50代も半ばを過ぎ、以前よりも少し「大人」になったのかもしれません。
筆を取ろうと思った理由は他にもあって、本書の中にもありますが、僕は「誰かの提案」は、まず受け入れて、やってみる、というスタンスで仕事をしてきたから。
ちょっと時間は経ったけど、こうして、2022年8月、週刊新潮で、「テレビタレント、やってます。」という連載をスタートさせ、14歳でテレビの世界の入り口に立ってから40年以上、様々なテレビの現場で学んだことを振り返りながら、“芸人”でもなく“司会者”でもない“テレビタレント”としての仕事術を紹介するとともに、僭越ながら、僕の「生き方」や「考え方」について、約1年間にわたり、あれこれと綴ってきました。
本書は、その連載に加筆修正し、再構成したものです。
書籍化にあたって、タイトルをどうしようか頭を悩ませたのですが、連載の時から伴走してくれた新潮社の担当者さんや、僕を担当している30代前半のマネージャーから、「いばらない生き方」という素敵なタイトルを提案されました。
ちょっと照れ臭いけど、この提案も、受け入れてみることにしました。
僕の経験を綴った本書が、あなたの仕事や生活に少しでも役立てばと願っています。
あまりお役に立たなかったとしても、この本を読んだ後に、あなたが少しでも「明るく楽しい気持ち」になってくれれば、とても嬉しいです。
それでは、どうぞよろしくお願いします。
第1章
テレビの現場で学んだ“明るい”のつくり方
DAISUKI! 初MCで学んだ“楽しい”のつくり方
テレビの中で本気で遊ぶ
40年に渡り、数え切れないほどたくさんのテレビ番組に出させてもらいましたが、その中でも「テレビタレント中山秀征の原点は?」と聞かれれば、間違いなく、日本テレビ系『DAISUKI!』(1991年〜2000年)を挙げます。25歳で初めて本格的にMC(進行役)を任せてもらったこの番組で、僕は自分が目指すべきスタイルを自覚することができました。
番組を知らない若い読者の皆さんに説明すると、『DAISUKI!』は、僕と、松本(明子)さん、ナオちゃん(飯島直子さん)の、当時20代半ばだった3人の男女が、テレビを通じて“日常の遊び”を見せていた番組です。3人で商店街をブラブラ歩いたり、不動産屋さんと物件を探したり、パチンコや麻雀、時には、居酒屋で日本酒を飲み本気で酔っ払うなど、とにかくテレビの中で本気で遊んでいました。今なら「それって、普通のテレビ番組じゃない?」と感じる方も少なくないかもしれません。
でも、放送が始まった1991年は、まだまだテレビを観る人も、テレビの中の人たちも、「バラエティはスタジオを中心に作り込むモノ」という常識が強く残っていた時代でした。
それにもかかわらず、毎週オールロケで“遊び”を見せるバラエティは新鮮だったのか、「土曜の夜に肩の力を抜いて観られる」と支持され、深夜番組としては異例ともいえる高視聴率(最高14・7%)を獲得したこともありました。
ただ、「バラエティはかくあるべし」という方々からは「あんなのテレビじゃない」と辛辣なご意見も……。特にMCの僕は「テレビで遊んでいるだけ」「芸がない」などとバッシングも受け、コラムニストのナンシー関さんからは「生ぬるいバラエティ番組」の「象徴的存在」なんて書かれたりもしました。
そんな、「中山秀征はテレビの中で何やら楽しそうに遊んでいるタレント」というのは、好き嫌いにかかわらず、僕を知ってくれている方々の多くが僕に対して抱いているイメージではないでしょうか。
そんなイメージ、言い換えれば、僕のスタイルが生まれた番組が『DAISUKI!』。それも、意図しない「ハプニング」から生まれたものでした。
MCの役割は「空気」を伝える?
初回ロケを迎えるにあたり、僕は「番組のキーパーソンは飯島さんだ」と考えていました。というのも、実は僕は、番組スタートから約1年半後に、2代目MCとして途中参加した追加メンバーでした。レギュラーの2人と早く打ち解けた雰囲気を出さなければと、始まる前から少し焦っていました。
もっとも、松本さんは同じ事務所の先輩で10年来の信頼関係があるし、普段通りで大丈夫だろう、という安心感がありました。問題は、初対面の飯島直子さん。彼女と番組内で上手く絡むためには……。それまで見てきた先輩MCの方々のテクニックを振り返りながら、あれこれ策を練っていたのです。
しかし、長く考えていた“あれこれ”は、初回のロケで、あっさり覆されました。それも、想像をはるかに超える良い方向に。
初回のロケ地は若者の街・渋谷。当時流行していたバスケの「3on3」にチャレンジしました。
試合が始まり、僕がシュートを決めた直後、なんと、ナオちゃんから突然ハグされたのです。当時は同世代の女優さんからハグされるなんてなかった時代ですから、ただただ驚いてしまって……(笑)。
「これはテレビ。何かコメントしなきゃ」と焦った次の瞬間、経験したことのない雰囲気を感じました。目の前のナオちゃんは満面の笑み、松本さんも周りにいるスタッフも、とにかく楽しそうに笑っている。ロケ現場全体が、何かこう、キラキラした楽しい空気に包まれていたのです。
「もしかして、この“楽しい空気”を伝えるのが、僕の役割なのでは……?」
まだぼんやりしていた、MCという仕事の輪郭が少しだけクッキリした気がしました。
それは、カメラに向かって「僕のこの発言、この行動を撮ってください」と主張して“見せる”のではなく、「楽しんでいる僕たちを、どうぞどこからでも撮ってください!」と“見てもらう”イメージ。ゴールが決まれば、3人で喜びを分かち合い、決められれば3人で地団太を踏んで悔しがる。感情を爆発させ全力で楽しむことを意識したロケは想像以上に大盛り上がりしたのです。
そしてロケが終わった時は、僕だけではなく、松本さんもナオちゃんも、スタッフのみんなの表情にも、「この番組は行ける!」という確信が生まれているように見えました。
「今、テレビの中で起きていることは、こんなに楽しい!」
明るく楽しい空気を伝えることが、僕に向いているMCスタイルなのかもしれない。初回ロケをキッカケに、タレントとして大きな一歩を踏み出せました。
そして、楽しい空気を作り、その空気を伝えるための具体的な手段も、このあと僕は、『DAISUKI!』を通じて、多く学んでいくのです。
テレビで「日常」を感じさせるワザ
誰もが経験する“日常の遊び”をテレビにした、当時としては斬新な番組。
これが、多くの人が語ってきた『DAISUKI!』評でしょう。ただ、僕なりにもう少し深掘りさせてもらうと、この番組の凄さは、テレビなのに“日常”を感じさせる、その技術や演出にあったと思います。
そもそも、日常生活にテレビカメラが入ったら、それは非日常です。ドキュメンタリー番組だって、カメラが回ったら、取材対象者は少し演技もするし……。撮られることが仕事のタレントは、なおさら“演じてしまう”もの。ところが、「DAISUKI!」のスタッフは“演じさせない”演出が抜群に上手かった。
たとえば、番組の代名詞ともいえる“街歩きロケ”では、出演者を後ろから映す「バックショット」を多用していました。背中って、どうしても隙が出るし、カメラを意識していないから自然と素に近いトークになるんです。
そして、もう一つ、大きな効果があって……。実は、このバックショット多用の演出は「視聴者に4人目の出演者になって欲しい」という考えのもと、演出陣が知恵を振り絞って生み出した“発明”とも言えるものでした。
僕、松本さん、ナオちゃんと同じ目線で街の景色を見たり、会話を背中越しに聞いたりすることで、テレビを観ている人も、僕らと一緒に街を歩いているような気持ちになれる。平成初期のテレビで、VR映像のような“参加型”を意識していたそうです。背中越しに街歩きをするシーンは、その後、街ブラ系番組の「定番の
他にも、「説明ナレーションを入れない」「テロップでコメントのフォローをしない」など、日常の雰囲気を身近に感じてもらうため、あえて“引き算をする”細かな工夫も施されていました。
僕自身はというと、番組内のトークでは常に日常感を意識していました。
例えば、ナオちゃんに大物歌手との熱愛報道があった時のこと。観ている人は、絶対にその話を聞きたい(もちろん僕も松本さんも!)。そんな時、『DAISUKI!』のトークはどんな感じになるかと言えば……。
まず、僕が「あぁ、夏休みだね〜ナオちゃん。こんな時のBGMは?」と軽く振りを入れます。するとナオちゃんは「ん〜。サザンかなぁ」なんてトボけてくれる。肝心なことを言葉にしていなくても、ナオちゃんの表情や声のトーンで「噂の彼とは、うまくいってるな」という雰囲気は伝わります。伝わったら、それ以上は踏み込まない。膨らまさない。わかる人にはわかるし、わからない人にも楽しそうな雰囲気は香ってくるもので……。
ポイントは「香る」で止めておくこと。実際の日常会話だって、実は細かい言葉よりも雰囲気で、相手の伝えたいことを感じとることが多かったりしませんか? こんな風に、『DAISUKI!』では、トークでも“日常の香り”を大切にしていました。
今なら、番組を観ながらSNSで「ナオちゃん、うまくいっているんだね」とか、「中山、今の結構攻めたな〜」とか実況しながら、“香り”の解釈を共有できます。何気ない会話の考察もできて、当時以上に番組を楽しめそうです。ただ、当時はX(ツイッター)もインスタもなかった時代。観ている人ひとりひとりが、それぞれの解釈で“香り”を楽しむしかありませんでした。
でもだからこそ、「4人目の出演者」としてじっくり番組に入り込み、僕ら3人が感じていた「楽しい空気」を深く共有できたのかもしれません。
当たらないと言われた「男1・女2」の組み合わせ
2022年、BS日テレで22年ぶりに『DAISUKI!』の復活特番が放送され、その後も、不定期ながら特番として何度か放送されています。松本さん、ナオちゃんとのロケは、どれだけ久しぶりでも、故郷に帰ってきたような安心感があります。
2人との出会いは「運命的」としか言えないのですが、実は90年代初めのテレビ業界では、男1人&女2人の組み合わせは「当たらない」と言われていました。
理由はハッキリと分からないのですが、いわゆるジェンダーバイアス(性別役割による固定観念)かと。意図していなくても、男性が女性を従えているような構図に見えてしまったのかもしれません。
ところが『DAISUKI!』での3人の「構図」は全く違いました。
ナオちゃんは、釣りのロケで「私、釣りって嫌〜い」「つまんない」とか平気で言っちゃう人。テレビの常識は「つまらなくても、一生懸命やるのがプロ」だけど、日常ならこんな状況はある。日常感を大切にする『DAISUKI!』なら、こんな正直すぎる発言もアリなんです。
そして、一方の松本さんは、爆弾発言をフォローするでもなく、マイペースに釣りを始めちゃう。「ナオちゃん釣り嫌いって……。え? 松本さ〜ん?」と、2人に翻弄されっぱなしの中山。自分を“曲げない”ナオちゃんと、自分が面白いと思った方に“曲がって行く”松本さんとの間で、3人は常に「1-2」「2-1」、時には「1-1-1」の関係になりました。仲はいいけれど、全員が同じ方向を向いている状態はめったにないんです。
当時20代だった男女3人が腕を組んで歩いていても、変にベタベタした感じに見えなかったのは、一緒にいるのに同じ方を向かない「3人の構図」にもあったと思います。もっとも、腕を組んでいたのは、松本さんの視力が悪く、危険防止のために人の腕をつかむ癖があった、という理由もありますが……。
「ネガティブな浪費」ではなく「ポジティブな無駄」
そんな、この3人ならではの構図をじっくり楽しんでもらうため、『DAISUKI!』の収録には、「たくさん撮って、なるべく編集しない」という不思議なルールがありました。普通は、長い時間カメラを回していろんなシーンを撮影したら、その中から、面白い瞬間、瞬間を切り取ってつなげ、1本のVTRに仕上げていきます。それが『DAISUKI!』の場合、妥協せずに何時間もカメラを回したうえで、実際のオンエアでは、日常感のある「面白い流れ」の部分を、あまり編集せずたっぷりと使います。
だから、オープニングからの20分をほぼ編集しないで流すこともありましたし、キャンプロケの回では、「スープの味付け濃くない?」「逆に薄くない?」のやり取りで放送時間のほとんどを占めたことも……。「日常感のある面白い流れを丸ごと見せたい!」。出演者もスタッフもその思いは一致していました。
コスパやタイパが重視される今では、『DAISUKI!』のロケは無駄が多いと言われたかもしれません。ただ、「生産性」という点で見れば、決して低いわけではなかった。編集はなるべくしない、台本にはロケ地までの地図など情報のみ、過剰な事前準備をしない……など、あらゆる無駄を省いて、お金と時間と労力を「当日の収録」に一気に注いでいた感覚です。
“日常の楽しさを見せる”という番組の目的がしっかりと共有できていたからこそ、ロケ当日は、全員、粘りに粘るという、一点に集中できたわけです。とはいえ、室内スキー場のロケで、11時間もカメラを回したときは、スタッフから「もう勘弁してくれ」と悲鳴が上がっていましたが……(笑)。
今振り返ってみると、無駄は無駄でも、目的無く労力を使う「浪費」ではなく、明確な目的に向けて、労力を使ってはいたが、その使い方が過剰だった。つまり「ポジティブな無駄でもあったのかな」と考えています。『DAISUKI!』ならではの“日常の楽しさ”の裏には、間違いなく、この「ポジティブな無駄」があったことは確かだと思います。
この「ポジティブな無駄」は、僕のテレビタレント人生のもう一つの原点ともいえる番組でも徹底されていました。
【『DAISUKI!』で学んだ、明るく生きるヒント】
- 「楽しませる」ではなく「みんな一緒に楽しむ」
- 引き算の演出で「日常」を香らせ「空気」を共有する
- 楽しい人間関係は「一緒にいるけど同じ方向を向かない」
- 一点集中の「ポジティブな無駄」は目的共有があってこそ