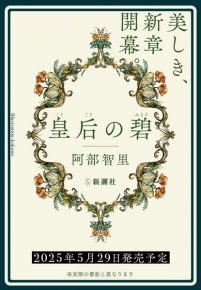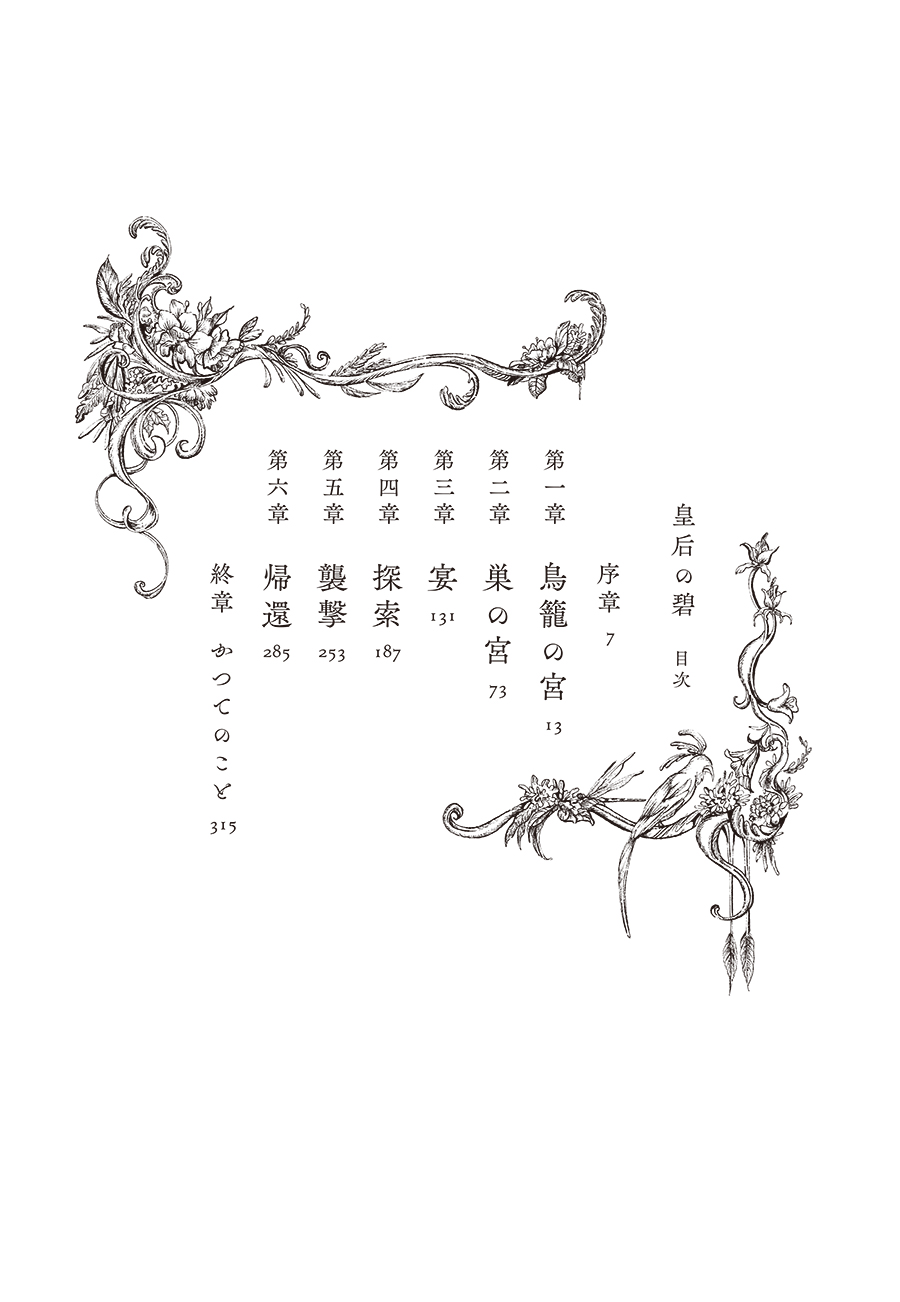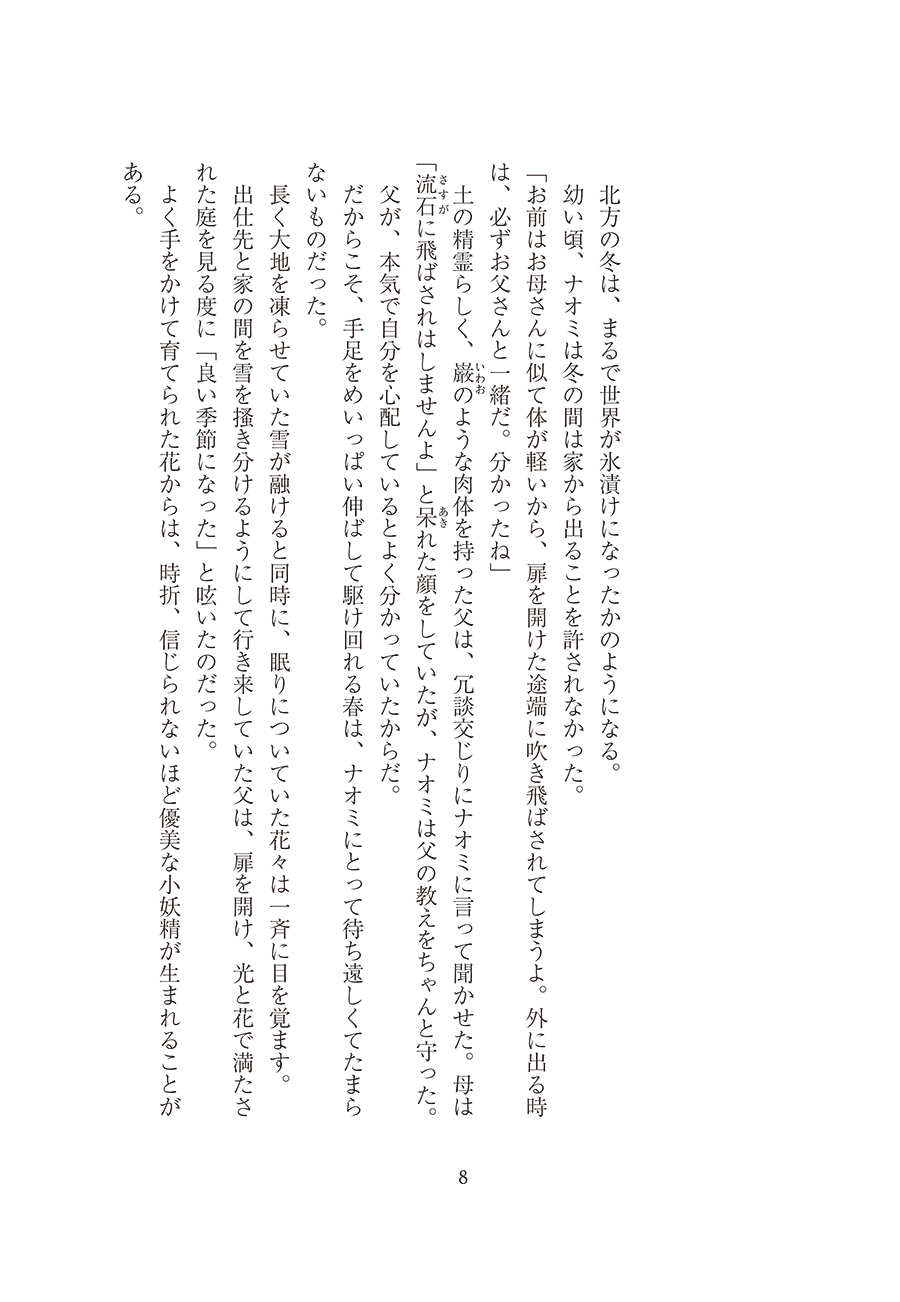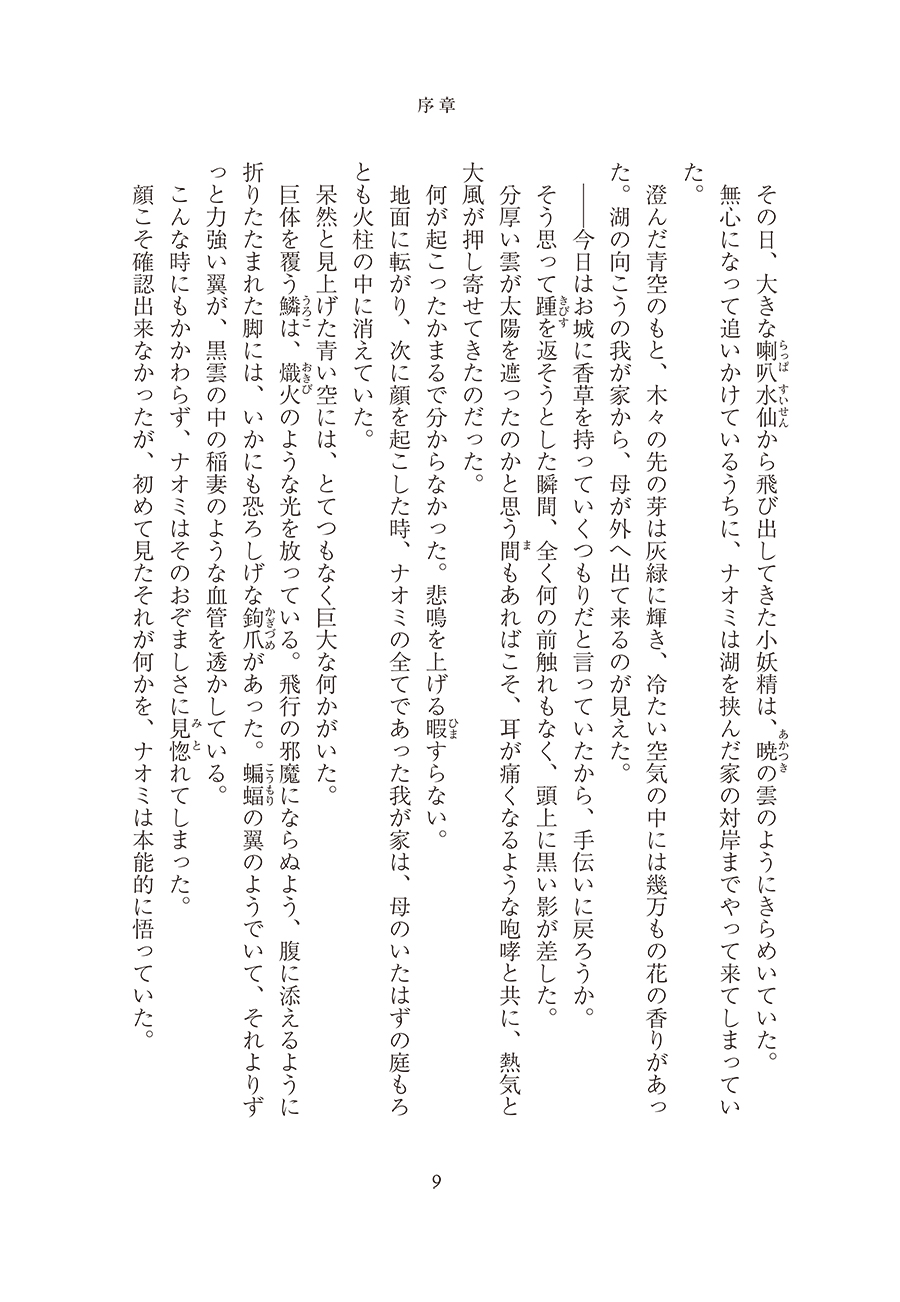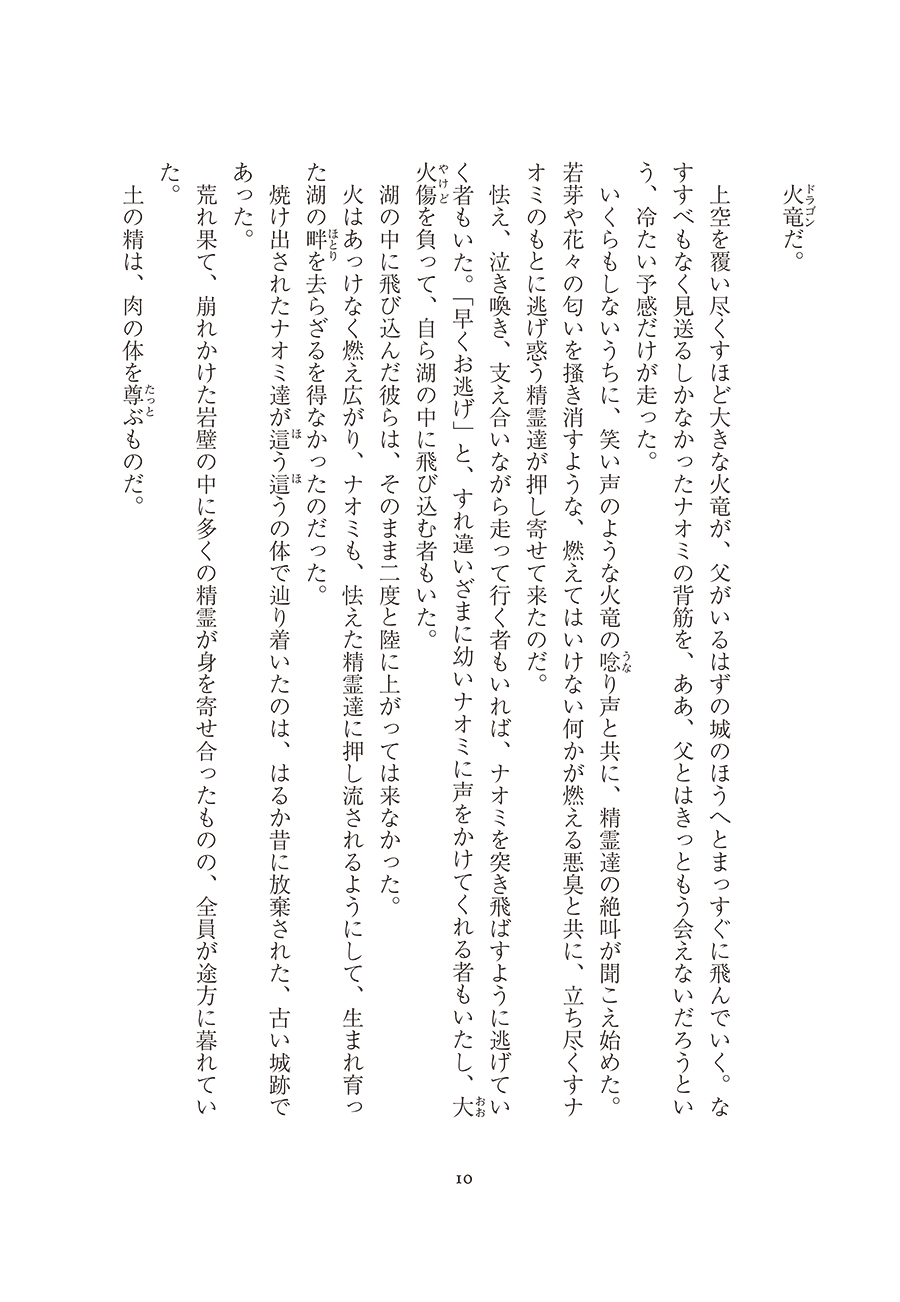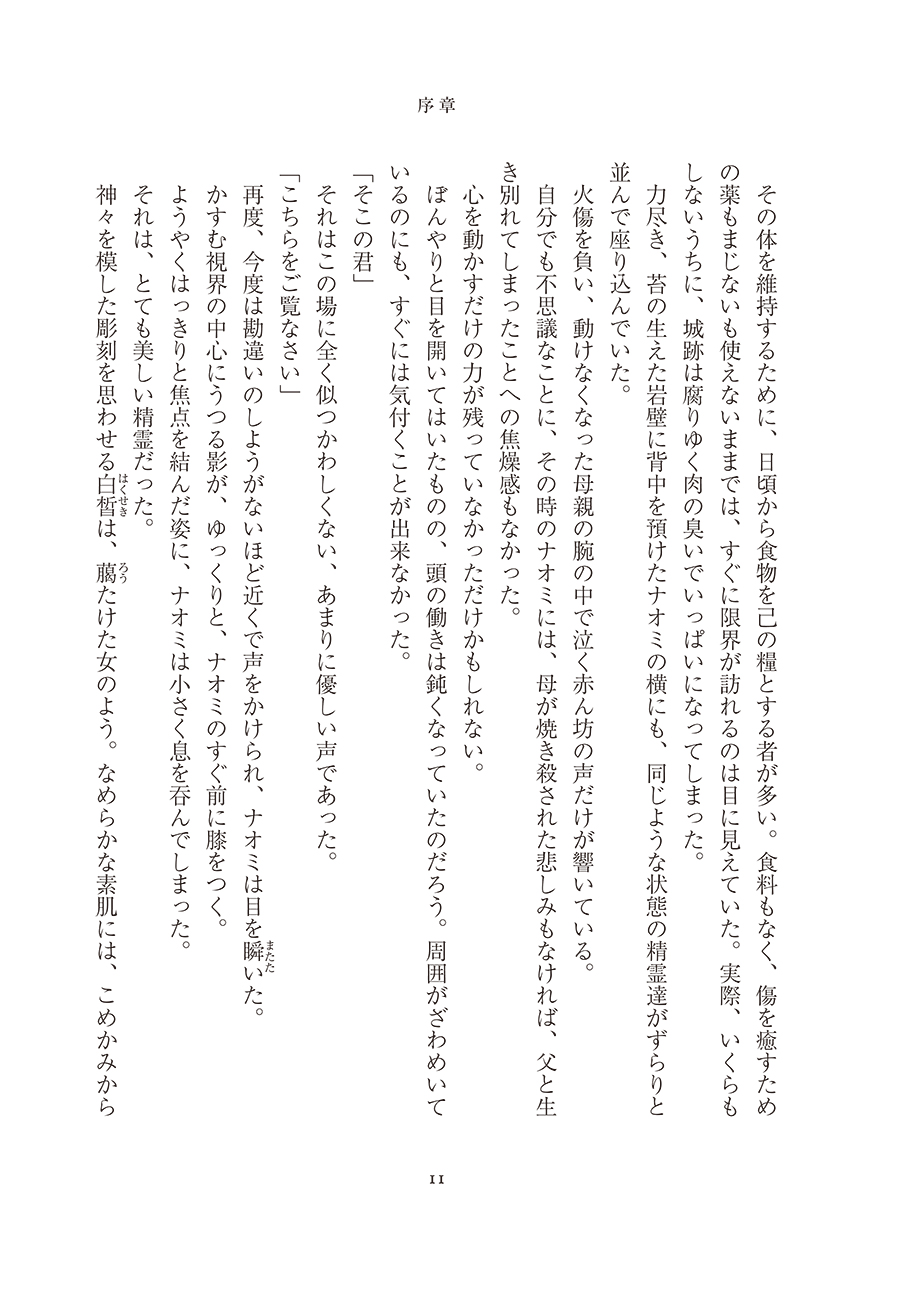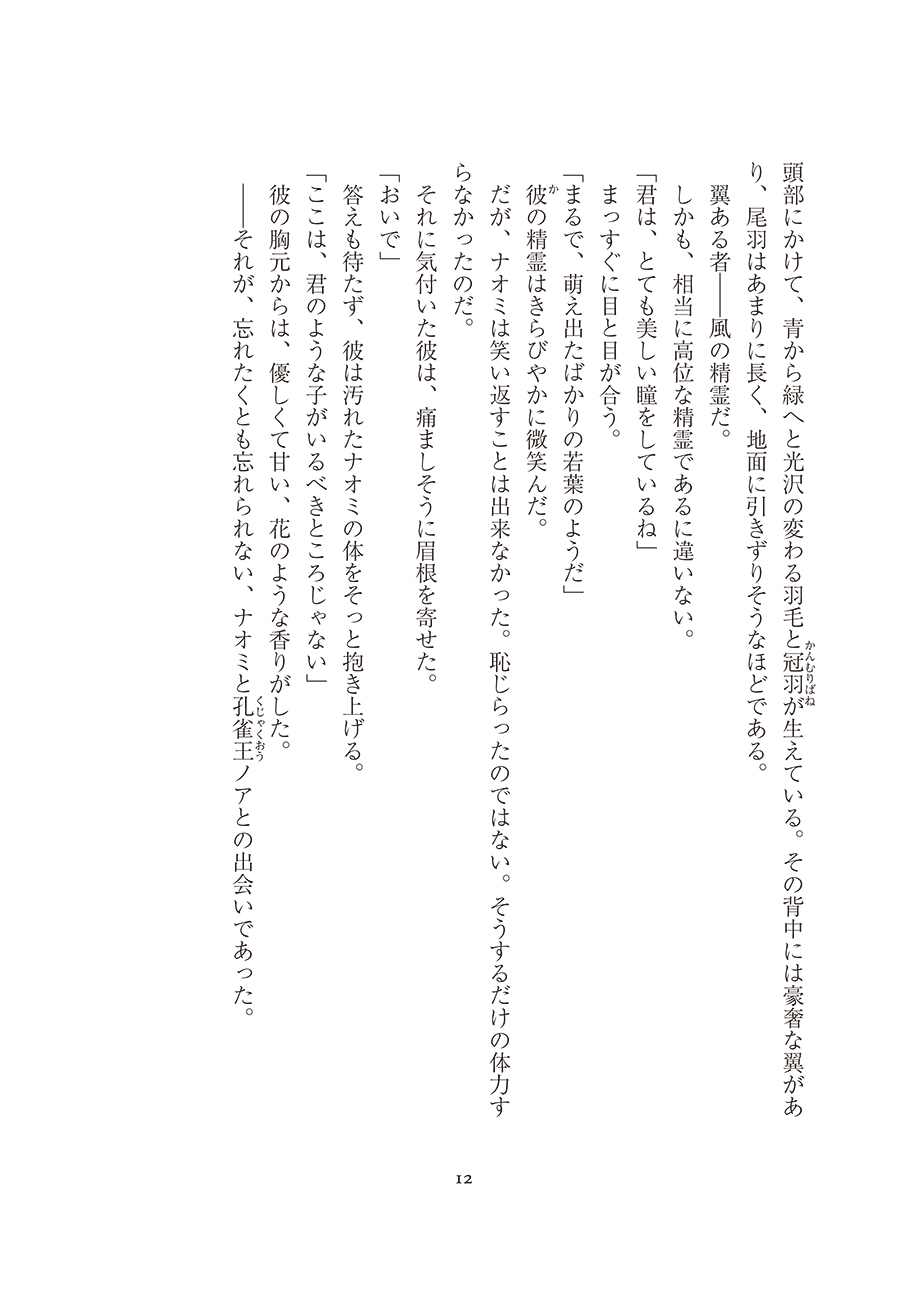序 章
北方の冬は、まるで世界が氷漬けになったかのようになる。
幼い頃、ナオミは冬の間は家から出ることを許されなかった。
「お前はお母さんに似て体が軽いから、扉を開けた途端に吹き飛ばされてしまうよ。外に出る時は、必ずお父さんと一緒だ。分かったね」
土の精霊らしく、巌のような肉体を持った父は、冗談交じりにナオミに言って聞かせた。母は「流石に飛ばされはしませんよ」と呆れた顔をしていたが、ナオミは父の教えをちゃんと守った。
父が、本気で自分を心配しているとよく分かっていたからだ。
だからこそ、手足をめいっぱい伸ばして駆け回れる春は、ナオミにとって待ち遠しくてたまらないものだった。
長く大地を凍らせていた雪が融けると同時に、眠りについていた花々は一斉に目を覚ます。
出仕先と家の間を雪を搔き分けるようにして行き来していた父は、扉を開け、光と花で満たされた庭を見る度に「良い季節になった」と呟いたのだった。
よく手をかけて育てられた花からは、時折、信じられないほど優美な小妖精が生まれることがある。
その日、大きな喇叭水仙から飛び出してきた小妖精は、暁の雲のようにきらめいていた。
無心になって追いかけているうちに、ナオミは湖を挟んだ家の対岸までやって来てしまっていた。
澄んだ青空のもと、木々の先の芽は灰緑に輝き、冷たい空気の中には幾万もの花の香りがあった。湖の向こうの我が家から、母が外へ出て来るのが見えた。
──今日はお城に香草を持っていくつもりだと言っていたから、手伝いに戻ろうか。
そう思って踵を返そうとした瞬間、全く何の前触れもなく、頭上に黒い影が差した。
分厚い雲が太陽を遮ったのかと思う間もあればこそ、耳が痛くなるような咆哮と共に、熱気と大風が押し寄せてきたのだった。
何が起こったかまるで分からなかった。悲鳴を上げる暇すらない。
地面に転がり、次に顔を起こした時、ナオミの全てであった我が家は、母のいたはずの庭もろとも火柱の中に消えていた。
呆然と見上げた青い空には、とてつもなく巨大な何かがいた。
巨体を覆う鱗は、熾火のような光を放っている。飛行の邪魔にならぬよう、腹に添えるように折りたたまれた脚には、いかにも恐ろしげな鉤爪があった。蝙蝠の翼のようでいて、それよりずっと力強い翼が、黒雲の中の稲妻のような血管を透かしている。
こんな時にもかかわらず、ナオミはそのおぞましさに見惚れてしまった。
顔こそ確認出来なかったが、初めて見たそれが何かを、ナオミは本能的に悟っていた。
火竜だ。
上空を覆い尽くすほど大きな火竜が、父がいるはずの城のほうへとまっすぐに飛んでいく。なすすべもなく見送るしかなかったナオミの背筋を、ああ、父とはきっともう会えないだろうという、冷たい予感だけが走った。
いくらもしないうちに、笑い声のような火竜の唸り声と共に、精霊達の絶叫が聞こえ始めた。若芽や花々の匂いを搔き消すような、燃えてはいけない何かが燃える悪臭と共に、立ち尽くすナオミのもとに逃げ惑う精霊達が押し寄せて来たのだ。
怯え、泣き喚き、支え合いながら走って行く者もいれば、ナオミを突き飛ばすように逃げていく者もいた。「早くお逃げ」と、すれ違いざまに幼いナオミに声をかけてくれる者もいたし、大火傷を負って、自ら湖の中に飛び込む者もいた。
湖の中に飛び込んだ彼らは、そのまま二度と陸に上がっては来なかった。
火はあっけなく燃え広がり、ナオミも、怯えた精霊達に押し流されるようにして、生まれ育った湖の畔を去らざるを得なかったのだった。
焼け出されたナオミ達が這う這うの体で辿り着いたのは、はるか昔に放棄された、古い城跡であった。
荒れ果て、崩れかけた岩壁の中に多くの精霊が身を寄せ合ったものの、全員が途方に暮れていた。
土の精は、肉の体を尊ぶものだ。
その体を維持するために、日頃から食物を己の糧とする者が多い。食料もなく、傷を癒すための薬もまじないも使えないままでは、すぐに限界が訪れるのは目に見えていた。実際、いくらもしないうちに、城跡は腐りゆく肉の臭いでいっぱいになってしまった。
力尽き、苔の生えた岩壁に背中を預けたナオミの横にも、同じような状態の精霊達がずらりと並んで座り込んでいた。
火傷を負い、動けなくなった母親の腕の中で泣く赤ん坊の声だけが響いている。
自分でも不思議なことに、その時のナオミには、母が焼き殺された悲しみもなければ、父と生き別れてしまったことへの焦燥感もなかった。
心を動かすだけの力が残っていなかっただけかもしれない。
ぼんやりと目を開いてはいたものの、頭の働きは鈍くなっていたのだろう。周囲がざわめいているのにも、すぐには気付くことが出来なかった。
「そこの君」
それはこの場に全く似つかわしくない、あまりに優しい声であった。
「こちらをご覧なさい」
再度、今度は勘違いのしようがないほど近くで声をかけられ、ナオミは目を瞬いた。
かすむ視界の中心にうつる影が、ゆっくりと、ナオミのすぐ前に膝をつく。
ようやくはっきりと焦点を結んだ姿に、ナオミは小さく息を呑んでしまった。
それは、とても美しい精霊だった。
神々を模した彫刻を思わせる白皙は、﨟たけた女のよう。なめらかな素肌には、こめかみから頭部にかけて、青から緑へと光沢の変わる羽毛と冠羽が生えている。その背中には豪奢な翼があり、尾羽はあまりに長く、地面に引きずりそうなほどである。
翼ある者──風の精霊だ。
しかも、相当に高位な精霊であるに違いない。
「君は、とても美しい瞳をしているね」
まっすぐに目と目が合う。
「まるで、萌え出たばかりの若葉のようだ」
彼の精霊はきらびやかに微笑んだ。
だが、ナオミは笑い返すことは出来なかった。恥じらったのではない。そうするだけの体力すらなかったのだ。
それに気付いた彼は、痛ましそうに眉根を寄せた。
「おいで」
答えも待たず、彼は汚れたナオミの体をそっと抱き上げる。
「ここは、君のような子がいるべきところじゃない」
彼の胸元からは、優しくて甘い、花のような香りがした。
──それが、忘れたくとも忘れられない、ナオミと孔雀王ノアとの出会いであった。
第一章 鳥籠の宮
『風送り』の儀式は、風の強い日を待って行われる。
灰色の雲は分厚いが、その流れは速く、形を変えては地上に光の筋を落としている。
天上にかかる梯子のような光に照らし出されたのは、雨上がりの鮮やかな緑の丘と、丘の上に設けられた舞台であった。
青金石で出来た舞台は、完璧な円形をしている。
青地に金粉が散らばっているかのような石面は滑らかに磨き上げられ、十二宮の神々の姿が金線によって浮かび上がっていた。
舞台の周辺には、大勢の風の精霊が集まっている。
その背中に見事な翼を持つ、鳥の一族である。居並ぶ者はみな悄然と項垂れており、中には、涙をこぼしている者の姿もあった。
翼を持っていないのはこの場でたった一匹、ナオミだけだ。
目の前に居並ぶ立派な翼の隙間から、ナオミはそっと舞台を覗き見た。
そこには、二羽の高貴な風の精霊が向かい合っている。
一羽は、孔雀王ノア。
ナオミが女官として仕えるべき主君であり、不遜な表現が許されるならば、かつて自分を拾ってくれたという一点において、養父とも言うべき存在である。
重厚な衣は、金の摺り模様が豪奢に入った白だ。水晶と月長石で出来た王冠には真っ青な髪が映り込み、幻想的な色目を作り出していた。
そしてもう一羽は、雌の白孔雀の精──ノアの妻、アビゲイルである。
たおやかな肢体にまとうのは肌を透かすほどに薄い衣のみであり、王の伴侶という身分にふさわしい装飾の数々は全て取り払われている。
純白の翼と、同じ色の艶やかな長髪を風になびかせた彼女は、その身を飾るものがほとんどないにもかかわらず、恐ろしいほどに美しかった。
「それでは王さま。これにてお別れにございます」
穏やかに告げられた孔雀王は、「アビゲイル」と、堪えきれなくなったように妻の名を呼んだ。
「やはり、考え直してはもらえぬか」
「まあ、王さま……」
この期に及んで何をおっしゃるのかと言わんばかりの妻に、孔雀王は頑是ない子どものように首を振る。
「やはり、納得がいかぬ。そなたはこんなにも美しいというのに」
「まだ、美しいからこそでございます」
アビゲイルはやわらかく、しかしきっぱりと断言した。
「創造手は我々を創りたもうた時、ただ『美しくあれ』とお命じになりました。今、我が身を奉れば、きっと星の座に迎え入れて頂けるでしょう。でも、ほら……」
アビゲイルが差し伸べた白い二の腕の内側には、針の先で突いたような、ほんの小さな黒子があった。
馬鹿な、と動揺も露わに叫び、孔雀王は黒子を衆目から隠すように妻の腕をつかんだ。
「こんな小さな黒子ひとつで、貴女の美しさが損なわれるものか!」
「いいえ、王さま。駄目なのです」
なおも納得のいかぬ様子の夫に、ふと、アビゲイルの瞳に諦念が宿る。
「恐れ多くもわたくしは、イリスさまに嫉心を抱いてしまったので」
思わぬ名前に、ナオミは目を見開いた。
それまで固唾を呑んで主君たるつがいを見守っていた周囲の精霊達も、たまらずに小さく翼を揺らす。
──イリスは、孔雀王の最初の妻の名だ。
孔雀王は呆気に取られた様子で黙り込み、何故だ、と苦しい声を上げたのは、それから随分と経ってからのことであった。
「何度も言ったではないか。私は貴女を一番に愛していると。イリスは、すでに私の妻ではない」
しかし、アビゲイルはその言葉に顔を歪めた。
「王さまのお言葉に噓がないのは存じております。でもわたくしは、とうとう子をなすことが出来ませんでした」
「アビゲイル!」
気色ばむ孔雀王に、今度はアビゲイルのほうが聞き分けのない子どものようになって言う。
「王さまが、本心ではお子がなくとも良いとお考えなのは存じております。でも、ずっとずっとわたくしは王さまのお子が欲しかったのです。そうすれば、イリスさまにひとつでも勝れるものが得られるのではないかと期待して──そんな己の浅ましさに、疲れ果ててしまいました」
そう告げた声はいかにも苦しげで、今にも消え入りそうだった。
「出来れば、この思いはあなたさまに申し上げぬまま、お暇しとうございました……」
しんと静まり返った舞台の上を、雨の匂いを含んだ風が抜けていく。
緑の艶を帯びた孔雀王の青い髪がなびき、アビゲイルの頼りない肩口を撫でた。
「酷いお方だ。そんな風に言われては、私は私の無力を呪うほかにないではないか」
のろのろと顔を上げた孔雀王は、傍から見ても明らかな葛藤を経て、言葉を継いだ。
「……暇を許す」
孔雀王の許しを得て、アビゲイルは安堵したように微笑んだ。
「ありがたく存じます」
名残り惜しげな夫の手からするりと逃れ、アビゲイルは舞台の中央に立った。
そんな妻を苦渋に満ちた面持ちで見つめながら、孔雀王はようよう口を開く。
「我が最愛の妻、アビゲイルの要素に告ぐ」
孔雀王の命令を受け、アビゲイルの体の周囲に、金の粉のような光が舞い上がった。
「アビゲイルとこの私、孔雀王ノアとの間に交わしたつがいの契約よ、ここに出でよ」
孔雀王の声が形になったかのように、光の粒は一瞬にして姿を変えた。
細い一本の線の形に集まった光は大きく波打ち、アビゲイルの周囲を取り巻きながら、花のような紋様を描いていく。
そのうちいくつかは、金の透かし細工の装飾品のようにアビゲイルの額と首、手足を彩った。
これほど高位の精霊の契約紋を見ることは滅多にない。
その細やかさ、複雑さと美しさに、ナオミは密かに見惚れてしまった。
アビゲイルは、自身を飾り、周囲を取り巻く光の紋様を見ながら、歌うように言う。
「かつて、わたくし白孔雀のアビゲイルは、孔雀王ノアの求めに喜んで応じ、その妻としての務めを果たすと誓いました。しかし今、それは叶わなくなりました。力及ばず、悲しく、心より申し訳なく思いますが、どうかお暇をお許し下さい」
これに、孔雀王は震える声で応じる。
「白孔雀のアビゲイルは、私の求めによく応え、その役目をまっとうした。永劫、アビゲイルは我が妻であるが、その身を元素に還すことを許そう」
金色の光は淡く色を変え、紋様がほどけて消えていく。
己の体に巻き付く紋様が全て消えたのを見て取り、アビゲイルはまるで体が軽くなったことを喜ぶかのように翼を広げた。
「──貴女の旅路に、幸多からんことを」
別れの言葉に次いで孔雀王の形の良い唇から漏れ出したのは、美しく賢い妻を褒め讃え、その行く末を寿ぐ歌であった。
王の歌声に応じて、周囲の精霊達も歌い出す。
雲雀の精の高らかな声、小夜啼鳥の精の軽快な声が合わさり、歌声がひとつの大きな旋律となって天に届くや、雲が割れた。
ひときわ清冽な光が、舞台の上へと降り注ぐ。
光の中で、アビゲイルは穏やかに笑った。
王に対し、最後に一歩足を引き、胸に手を当ててお辞儀をしてみせると、アビゲイルはゆっくりと空を見上げる。
天上に向けて羽ばたいた瞬間、翼の端が光の中に崩れ始めた。
しゃりしゃりと、雪を搔き崩すような音を立てて、アビゲイルの翼が、頰が、髪が、その手足が光の中へと溶けていく。
光の粒が、風に乗って渦を巻いている。
かつてアビゲイルであった風の元素を空に送り届けるため、翼を持つ者達は次々と大空に飛び立った。歌いながら、鳥の精達が縦横無尽に空をめぐり、手にした色帯を翻す。
その翼で起こった風に乗って、光の粒が大気の中へと拡散していった。
光の痕跡がすっかり消えてなくなるまで、孔雀王は、妻が消えた空をずっと見送っていたのだった。
***
気付くと、地上には孔雀王と、飛べないナオミだけが取り残されていた。
「私は、そんなにイリスに心を残しているように見えたか?」
王は、風の精達が舞い続ける天空を見つめながら、しかし明確にこちらに向かって声をかけてきた。
「恐れながら、王さま……」
何と答えるべきかと悩みながら口を開くと、「いや、すまぬ」と先を制される。
「そなたに訊いても詮無いことを言ったな。忘れてくれ」
ナオミがそれ以上答える間もなく、宙を舞っていた鳥の一族が、ぞくぞくと舞台へと戻って来た。たちまちのうちに、孔雀王は近習やら衛兵やらに囲まれて、ナオミと言葉を交わすような雰囲気ではなくなってしまう。
若い女官達も地上に降りてきたので、自分も同じ場所に並ぼうと踵を返しかけ、不意に「ナオミ」と王から名前を呼ばれた。
「はい」
即座に応じれば、孔雀王とナオミの間に立っていた鳥の一族の者は困惑の面持ちで、あるいは心得た風にその場から退く。
まっすぐに視線が通る形になったナオミに、力なく王は笑いかけた。
「城に戻ったら、一度顔を見せなさい」
周囲の者が驚く気配がしたが、ナオミは狼狽えることなく片膝をつき、「承知しました」と礼をした。そのまま、孔雀王の乗った輿と、お付きの一行が宮殿に戻っていくのを待って、ようやく立ち上がった時だった。
「土蜘蛛のくせに……」
敵意を隠さない、苦々しい声に振り返る。
そこでナオミを睨みつけていたのは、先頃、共に見習いから女官に上がったばかりの同輩である白鳩の精だった。
──土蜘蛛とは、土の精霊の蔑称である。
ナオミはまたかと思っただけだったが、これに顔色を変えた者がいた。
「エステル、あなた、どうしてそんなことを言うの!」
食ってかかったのは、ナオミと仲の良い、白鳥の精のサラである。
「サラ、いいから」
サラは、風の精霊の中に一匹紛れ込んだナオミに対しても分け隔てなく接してくれる、ナオミにとってほぼ唯一の友であった。
「ちっとも良くないわ、ナオミ。こういう時は、すぐ怒らなきゃ」
ナオミの代わりに憤慨するサラに、エステルは鼻を鳴らす。
「土蜘蛛に土蜘蛛と言って何が悪いの。地を這うことしか出来ない者が、王さまの御前に上がるなんて間違っているわ」
馬鹿なことを、とサラは眉根を寄せる。
「その言葉は、ナオミを大切になさっている王さまのお考えに異を唱えるということよ。あなた、王さまに歯向かおうと言うの?」
サラに反撃を喰らったエステルが、さらに言い返そうと口を開きかけた時だ。
「神聖な風送りの舞台で、お前達は何をしているのです!」
厳しくも聞き慣れた怒声に、若い女官達は一斉に身を竦ませる。
割って入ってきたのは、女官頭のアダである。
耳木菟の精であり、額に特徴的な飾り羽を持つアダは、若くは見えるが百年もの間、孔雀王に仕えてきた高位の精霊である。少し前まで、ナオミたち女官見習いの教育係を務めていたのだ。灰色の髪は上品で、顔立ちはいかにも怜悧に整っているが、今まで一度も笑ったことがないかのようにいつも険しい表情をしている。
実際、アダは高位の精霊とは思えないほど怒りっぽいので、女官見習い達からは恐れられつつも、ある種の親しみを持って慕われていた。
死にかけていた上、風の精霊のしきたりなどほとんど知らなかったナオミを、一端の女官になるまで厳しくも温かく教育してくれたのはアダである。
「こんな所でぐずぐずしていないで、さっさと城に戻りなさい!」
アダの一喝を受けて、エステルも慌てた様子で飛び立った。
直接絡んでくるわけでもなく、かと言ってサラに同調するでもなく、ほのかな戸惑いや嫉妬を滲ませてこちらを遠巻きにしていた他の女官達も、アダに追い立てられるようにして次々に舞い上がっていく。
結局、ナオミの隣にはサラだけが残った。
「エステルったら、どうしてあんなに意地悪なのかしらね……」
サラは呆れたように呟き、気遣わしげにナオミを見やった。
「ナオミ、あんなの気にしては駄目よ」
「私なら平気」
エステルのあれはいつものことだ。
敵意を隠さない分、分かりやすくて可愛らしいとも言える。
「宮殿まで、一緒に帰りましょう」
「そこまで気を遣わなくて大丈夫よ」
翼のある者達は飛んで帰れるが、ナオミはここから歩いて鳥籠の宮に戻らなければならないのだ。
「それより、先に行って沐浴の準備をしておいて。寄り道せずに、なるべく早く戻るから」
サラは何か言いたそうにしていたが、問答無用にナオミがその背中を押すと、大人しく白い翼を広げた。
「じゃあ、準備して待っているわね」
「うん。お願い」
さ、行って、と再び背中を押すと、サラは走り出す。
丘を滑るように駆け下り、力強く羽ばたいた両の翼に風をつかむと、すうっと体が浮き上がる。サラの向かう先には、黒い岩肌を露出した峻険な山々を背にして、鉄と硝子で出来た宮殿の丸屋根が輝いていた。
曇天から差し込む光線の最中を飛んでいくサラの後ろ姿を見送ると、ナオミは一度伸びをして、宮殿に向かって歩き出した。
雲の流れは速い。きっと、夜には晴れることだろう。
***
ナオミが孔雀王ノアに拾われてから、すでに五年の月日が経っていた。
孔雀王がナオミを連れ帰り、今やナオミ自身の棲み処となっている宮殿は、その見た目と用途から『鳥籠の宮』と呼ばれている。
棲んでいるのは、いずれもその背に立派な翼を持つ、鳥の一族ばかりだ。
背中に翼も翅もない──つまりは、風の精霊としての特徴を何も持たないナオミは、鳥籠の宮において明らかに異質な存在であった。
ナオミの出身地である北方には、多くの土の精霊が存在している。
一口に土の精霊と言っても、木を片手で引き抜くような大柄な種族も、穴熊の巣に入って行けるような小柄な種族もあった。木の家を建てて村を形成する者や、金銀宝石を得るために岩山を掘り、その跡地を整えて棲み処にする者などもいる。
彼らの特性として共通しているのは、いずれも大地に根差した暮らしを営み、器用に動く手足を持ち、何かを作ることを得意としているという点である。
土の精霊は、この世界を作った創造手の姿に最も似ているとも伝えられており、そのことを何よりの誇りとしていた。風の精霊のように飛べず、水の精霊のように泳げず、火の精霊のように姿を変えることも出来ない代わりに、価値あるものを生み出す力を持っているのだ。
精霊の多くは宝石の輝きを自身の構成要素として好むが、産出された石を、宝石と呼ばれるまでに輝かせる技術を持つのは、土の精霊のみである。そして、美しい宝石を使った宝物はまじないの器としても機能する。
守りのまじないの器となった宝は、持ち主を守るように働く。
癒しのまじないの器となった宝は、持ち主の怪我や病を治すように働く。
憎しみのまじないの器となった宝は、持ち主に不幸をもたらすように働く。
そんな土の精霊の作った宝を、契約によって手に入れようとするのが風の精霊であり、謀略によって奪い取ろうとするのが、火竜などに代表される火の精霊なのであった。
火の精霊は、土の精霊や風の精霊からは、憎悪を以って『火の化生』とも呼ばれる。
まじないによって結ばれた、精霊の契約は絶対だ。
火の化生は、土の精霊が使えない、あらゆるまじないを操ることが出来るため、しばしばその力を対価にした契約を持ちかけてくる。しかし、契約がうまくいくことは滅多になく、契約の穴を狡賢く狙ってくるから、絶対に耳を貸してはいけないのだと伝えられていた。
土の精霊の子どもは物心つく頃になると、欲を出して火の化生と契約をして痛い目に遭った先祖の話を飽きるほどに聞かされる。ナオミも、竈や明かり取りの蠟燭など、少しでも火の気がある所であれば奴らは姿を現すから、もし火蜥蜴を見つけたら、言葉を交わす前に水をかけろと教えられて育った。
それなのにあの日、城の内部にいた誰かが、禁忌を犯したのだ。
火竜はたやすく城に侵入し、そこに蓄えられていた宝を全て奪い取ってしまった。
そうして焼け出されたナオミ達は、知らないうちに、風の精霊の多く棲む東方との境界に近付いていたのだ。
北方の土の精との交易を受け持つ孔雀王は、焼け出された土の精霊の様子を見にやって来て、そこでナオミを拾ったのである。
孔雀王は、土の精霊達を出来るだけ助けようとした。他の城に報せを送り、北の地に戻れるように手配をし、鳥籠の宮のわずかな食料を惜しみなく分け与えた。
しかし、逃げて来た者の全てを助けることは出来なかった。
風の精霊は、もともと食事をあまり必要としない。大勢の土の精霊を養えるような備蓄は、鳥籠の宮にはもとよりなかったのだ。
孔雀王が、多くの女官の中でも特にナオミを気にかけてくれているのは、そのことを今でも気にしているせいもあるのだろう。
***
鳥籠の宮の正面門扉は鉄で出来ている。
見た目にもいかにも重々しいが、その形は見事なアーチを描き、青銅の百合によって優美に飾られている。猛禽の翼を持つ衛兵達に軽く挨拶をしてから中に入ると、雪花石膏の広間がナオミを出迎えた。
アビゲイルを悼んで宴席が設けられているのか、いたるところで音楽が奏でられている。最上部まで吹き抜けの広間には硝子の天井から外の光が入り、日が傾き始めたこの時間でも明るかった。
中央の吹き抜けを囲むように部屋が幾層にも重なっており、上層には孔雀王とその妻が、下層には彼らに仕える女官や衛兵達が棲むようになっている。
基本的に、高位の精霊は上部に棲み、低位の精霊は、低位であればあるほど居室も下へ追いやられる形だ。きっと翼のある者にとっては高い所ほど居心地が良いのだろうが、ナオミは大地に足を着けることで己の要素を満たしているから、下層のほうが好ましい。
見習いから女官になったばかりの今はまだいいが、長く仕えているうちに引っ越すように言われるのは分かっていて、先々を考えるとなんとも悩ましかった。
城の最下部には、背後の山から引いて来た水場が備わっている。
山の石を切り出して造られた水路で足を洗ってから、ナオミは地下の沐浴場へと急いだ。
「おかえりなさい」
螺旋階段を下りていくと、体を拭くための布と、真新しい女官の衣を大切そうに抱えたサラが待ち構えていた。
「待たせたわね」
「全然待ってないわ。行きましょう」
水晶のビーズがあしらわれた飾り帯を解き、その下の麻の腰紐を外す。簡素な生成りの衣を脱ぎ捨ててから、共に洗い場へと入った。
蠟燭の火しか光源のない洗い場は薄暗い。
天井に近いところには、下半身が魚の姿をしている水の精霊を模した彫刻がある。水の精霊が傾けている水瓶から、地面の熱で少しだけ温まった水がこちらに向けて注がれるのだ。
「水の精って、本当にあんな姿をしているのかしら……」
両手で羽繕いをしていたサラが、彫刻を見上げて呟いた。
「どうしたの、急に」
「だって私、水の精なんて見たことがないもの」
「ここじゃ見たことのある精霊のほうが少ないでしょうね」
風の精霊と土の精霊は、宝を狙う火の精霊に対抗する目的で手を組む場合が多い。その点、水の精霊の多くは水中に棲んでいるので、火の精霊の脅威には縁遠い。
鳥籠の宮の住民にとって、何とかして契約をしようと迫ってくる火の精霊以上に、水の精霊は得体の知れない存在なのだった。
「今度から、私達も宴の席に呼ばれることになるでしょう? もし今後、水の精がお客さまとして宴にいらしたとして、その姿に驚いてしまったら失礼になるわ」
ナオミは「この子ったらなんて真面目なのかしら」と呆れてしまったが、正式な女官になることを真剣に捉えているサラの姿は好ましかったので、結局は何も言わなかった。
洗い場から出て体の水気を拭いた後、真新しい女官服を身に纏う。
濡れた髪のまま、若い女官にあてがわれた大部屋に戻ると、他の女官達の姿はほとんど見えなかった。せっかくなので、普段は取り合いになる大鏡の前に陣取り、サラに髪を整えてもらう。
「ナオミって、とっても綺麗な目をしているわよね」
鏡越しにこちらを見つめながら、しみじみとサラが言う。
「サラは、いつも褒めてくれるから好きよ」
ナオミの虹彩は明るい黄緑色をしている。鳥の一族では、あまり見かけない色である。
サラや孔雀王は素敵だと褒めてくれるのだが、他の者からは珍しがられたり、不気味がられたりする場合がほとんどだ。多少なりとも見目が良ければ、この変わった瞳の色も魅力として映ったかもしれないが、ナオミはやや三白眼気味な上に、口角が下がっているので、普通にしていても不機嫌に見えてしまうことが多かった。誤解されたくなければ意識して口端を持ち上げるようにと、ここに来たばかりの頃からアダには何度も注意されているほどだ。
「ナオミは、正式に王さまのお召しを受けるのかしら……」
真顔でぽつりと呟かれ、ナオミは思わず噴き出した。
「それはないわよ!」
建前上、この城において、つがいのない女官は全て孔雀王の女ということになっている。
その唯一の例外が、おそらくは自分だ。
「知っているでしょう? 王さまは美しい風の精霊のお子をもうけなければならないのだもの。まざりものを作るような真似はなさらないわ」
違う属性の精霊がつがうことは不可能ではないが、要素が喧嘩して子は出来にくいし、出来たとしてもどっちつかずの無能が生まれる場合がほとんどだ。
サラは、ナオミの言葉に自分が傷ついたような顔をした。
「だって、王さまが自ら手元に引き取ることを決めた精霊はナオミだけなのよ。これまで何度もお話し相手にあなたを呼んでいるし……お気に入りなのは間違いないのよ」
そう真剣に語るサラは、清らかな内面がそのまま体に表れたかのような姿をしている。
純白の髪はゆるやかに波打ち、ぱっちりとした目は実直そうな澄んだ褐色をしている。頰は明るい薔薇色で、両の翼は白鳥の全き白。
晴れの日に飛ぶ姿は、神々しいほどである。
確かに、いくつかの理由があってナオミは孔雀王に気に入られている。だが、いつか孔雀王のお召しを受けるとしたら、それは自分ではなくサラであり、サラの言う「お気に入り」がいかに的外れなものであるかを、ナオミは誰よりもよく分かっていたのだった。
支度をすっかり整えた後、ナオミはサラと別れ、王のもとへと向かった。
最上階へと繋がる、吹き抜けを利用した螺旋階段は見栄えの良さが優先で、小柄なナオミが使うにはあまりに一段一段が大きい。難儀しながら階段を上り、ようやく目的の場所に着く頃には、すっかり日が暮れてしまっていた。
謁見の間は、吹き抜けを囲むように、床の中心に穴が開いた円形をしている。
敷物に織り込まれた銀糸は怪しくきらめき、惜しげなく切子の燈台に火が点され、部屋いっぱいに星をちりばめたようである。開放が可能な壁面と天井は鉄と硝子製で、城の周囲がよく見渡せた。
昼間の予想は当たったようで、夜空に雲はなく、美しい満月が顔を覗かせている。黒岩山の峰を背にする位置には、月光と部屋の明かりを受け、蛋白石を贅沢にあしらった玉座が淡い虹色に輝いていた。
王の私室は、その奥だ。
取次ぎを頼むまでもなく、部屋の前には衛兵の他に、アダが腕を組んでこちらを待ち構えていた。
「遅いですよ、ナオミ!」
いつもの調子で怒られて、慌てて礼をする。
「申し訳ございません」
「早くこちらへ」
速足のアダの後ろについて、垂れ下がる薄布を掻き分けるようにして辿り着いた王の居室では、部屋の主がすでにくつろいだ姿となっていた。
「よく来たね」
王の最も私的な空間であるそこには、ナオミにはさっぱり意味の分からない契約紋を書き散らした羊皮紙が散らばったままとなっている。側仕え達が仕事をおろそかにしたわけではなく、散らかした彼自身がそうするように命じているのだ。
「あの後、他の子とちょっと揉めたらしいね」
疲れ切った顔をしているが、それでも少年のような口調でからかってきた王に、ナオミはあえて軽口を返すことにした。
「王さまが私を気にかけて下さっているおかげで、エステルに嫌味を言われました」
「それはすまない」
大して悪いと思っている風もなく、しかし王は少しだけ笑ってくれた。
「さて……。ナオミを呼んだのはね、今度の宴について相談しておきたかったからなんだ」
笑いをおさめ、すみやかに本題に入った孔雀王は、異様なほどに静かな表情に変わった。
「私はアビゲイルを止められなかった。こうなっては、新たな妻の選定のため、蜻蛉帝がここにやって来るだろう」
──蜻蛉帝、シリウス。
風の精霊全てを束ねる、げに恐ろしき皇帝陛下の御名である。
ナオミが生まれるよりもはるか昔、鳥の一族と蟲の一族の間で、大きな戦があったという。勝ったのは蟲の一族であり、その長であった蜻蛉の精の王は、以来、皇帝としてこの東方の地に君臨している。
蜻蛉帝は残酷で、なおかつ美しいものが大好きなことで有名であった。
欲しいものを手に入れるためならば、どんな暴挙も厭わない。支配した端から宝物を奪い、美しい娘を召し上げ、しかし気に入らなければすぐに殺してしまうという。
本来であれば、敗北した時点で孔雀王は元素に還されるはずであったが、そうはならなかった。あろうことか蜻蛉帝は、孔雀王とその妻イリスの美しい見目を気に入り、殺すのが惜しいと言い出したからだ。
結果、イリスは蜻蛉帝に献上され、孔雀王はより美しい鳥の子をもうけることを条件に、この鳥籠の宮で生きていくことを許されたのである。
そのためにふさわしい母体として、蜻蛉帝はアビゲイルを選んだのだ。
しかし、アビゲイルは孔雀王の子を生むことが出来なかった。彼女が元素に還ったという報せが届けば、新たな雌を選ぶため、再び蜻蛉帝がこの鳥籠の宮にやって来るのは間違いない。
「恐らく、あの方は楽しい宴席を満喫して、私の妻にふさわしいと思う者を選び、そのまま帰って下さるはずだ」
そう語る孔雀王はナオミに対してというよりも、自分自身に言い聞かせているようだった。
「でも、蜻蛉帝が、女官の誰かをお召しになる可能性も捨て切れない」
かつてイリスにそうしたように、という孔雀王の声なき声が聞こえた気がした。
「アダには、若い女官達に事前に心構えを説いてもらうつもりだ。しかし実際に蜻蛉帝を前にしたら、頭では分かっていたとしても、平静ではいられなくなる子もいるだろう。正直、私だってあの方を前にすると体が震えてしまうくらいだからね」
冗談めかして言いつつも、孔雀王の笑みは笑みの形になっていなかった。
「女官になったばかりのナオミにこんなことをお願いするのもおかしいのだけれど、新入り達をよく見てあげてくれ。何か起こりそうな時は、すぐにアダに伝えて欲しい」
アダには怒られると思って平静を装う者も、同じ新入り相手には気が緩むだろうから、と。
「かしこまりました」
ナオミの即答に、孔雀王は満足気に頷いた。
孔雀王が、ナオミを重用する理由はここにある。
白孔雀のアビゲイルが妻としての役目を辞した今、翼のある女達は、誰もが次の孔雀王の妻に選ばれる可能性を持っている。もとからその風潮はあったものの、アビゲイルが暇を願い出たという報せが走ってからというもの、鳥籠の宮には雄雌特有の、独特な緊張感がそこかしこに感じられるようになっていた。
そんな中で、ナオミは孔雀王の美しさには心より感嘆しつつも、万が一にも己が選ばれることはないと分かっていた。
なぜなら、自分は『土蜘蛛』だからだ。
エステルは正しい。
他の多くの者が思っても口にしないだけで、鳥籠の宮において明らかにナオミは異質であり、その異質さを誰よりも理解しているのもまた、ナオミ自身なのだった。
ナオミは天地がひっくり返っても、自分が孔雀王の妻に選ばれないことを理解しており、ナオミが己の境遇を冷徹に見極めていることを、王もまたよく承知していたのだった。
ナオミが正式に女官となった日、孔雀王はこう言った。
「翼がない以上、踊り手は務まらないだろうが、それを補って余りあるほどに君は聡明だ。だから将来、ナオミにはアダの補佐役になって欲しいんだ。一歩引いたところからよく皆の様子を見て、私に報告をしておくれ」
一羽でも生き生きと新入りいびりに精を出すアダが、本当に補佐を欲しているかどうかは怪しいものだったが、孔雀王がナオミに何を望んでいるのかは理解した。
以来、女官や女官見習いの娘達が裏でどういう噂をし、どういった振る舞いをしているか、ナオミは何一つ隠さず孔雀王に報告している。
嫉妬するエステルに辛く当たられてもナオミが平然としていられるのは、エステルが永遠に妻に選ばれないことを、ナオミだけが知っているからだ。我ながら性格が悪いと思うのだが、自分に意地悪をすればするほど、エステルは自身の望みから遠ざかっているのだから、何を言われてもおかしいだけなのである。
アダは、身分を弁えず孔雀王と親しく会話するナオミには苦い顔をしていたが、王を取り巻く状況を鑑みて、やむを得ないと諦めている節があった。
王の横で、礼儀正しくそっぽを向いていたアダを見て孔雀王が言う。
「ナオミはいつも冷静で頼もしいね。若い頃のアダみたいだ」
あんまりな言いぐさに、ナオミは思わず目を剝いた。アダもつられたようにこちらを見て、意図せず顔を見合わせる形となる。
「失礼ですが、王さま。わたくしはナオミほど不愛想ではありませんでしたよ」
不本意そうに口を挟んだアダに、孔雀王は「ほら!」とアダとナオミを交互に指さした。
「今の顔なんか、そっくりだ」
一瞬反駁しようとして、しかしむっと口を閉ざしたアダに、孔雀王は今度こそ声を上げて笑ったのだった。
***
風送りの儀からいくらもしないうちに、蜻蛉帝による、新たな孔雀王の妻の選定が行われることに決まった。
孔雀王の予想通りである。
告知があってからというもの、その宴のための準備は、鳥籠の宮を挙げて進められた。
妻の候補と目される高級女官は歌や踊りの稽古に打ち込み、すでに夫のある古株の女官達は、宴の支度に奔走する。蟲の一族の要素の足しになるかは分からないが、味を楽しんでもらうために甘いものをあれこれと取り寄せ、葡萄酒も数を取り揃える。
ナオミのような、まだ出来ることの少ない新任の女官達は、宴に使う道具の準備に駆り出された。
明らかに自分達よりも古い椀や鉢を磨きながら噂するのは、当然、蜻蛉帝シリウスのことである。
「蜻蛉帝って、どんな姿をしているのかしら」
「お母さまに聞いたけれど、正門のてっぺんに頭をこすってしまうくらい大きいらしいわ」
「それじゃ、謁見の間にも入れないじゃない!」
「あなた、きっとからかわれたのよ」
アダに見つかって叱られないよう、小声で言い合う年若い女官達は、餌を欲しがる雛のようだ。
彼女達の多くは、この城に勤める女官と衛兵のつがいの間に出来た鳥の一族だ。一見すると楽しそうだが、妙にはしゃいだ風であるのは、みんなが緊張しているからだろう。
鳥籠の宮は、もともとは東に棲む風の精霊と、北に棲む土の精霊が交易をおこなうための拠点として築かれた宮殿である。
現在も、孔雀王は鳥籠の宮の主として、蜻蛉帝から北方の土の精霊との交渉を一手に任されている。王の妻も含め、宮殿において王に仕える女達は、宴の席で客分をもてなすのが重要な役割となっているのだ。
客分は夫のある女に手を出すことは許されていないので、つがいのいない若い女官を守るため、対外的に女官は全て王の女であるという形を採っている。
だが、蜻蛉帝の前では、そんな決まりなどまるで意味を持たない。
宴席では、ナオミ達若い女官は客の給仕に回ることになっているが、より重要な相手のもとにより優秀な者が行かされる決まりになっている。優秀であると認められたい反面、恐ろしい蜻蛉帝に近付きたくはない、というのがみんなの正直な気持ちなのだった。
「私のお父さまは百年前に蜻蛉帝と戦ったのだけれど、本当に化け物みたいだったって言っていたわ」
「昔は、綺麗な女の子をみんな召し上げて、でも飽きるとすぐに殺してしまっていたって」
「やだ、こわい」
「でも万が一、蜻蛉帝からお召しがあったら断れないわ……」
半泣きになった少女の言葉に、しんと会話が途切れたと思った瞬間、「馬鹿馬鹿しい!」と強い声が上がった。
「自分が選ばれるに違いないと思っているなんて、思い上がりも甚だしいこと」
つんと唇を尖らせて言うのは、エステルだ。馬鹿にされた少女が、顔を真っ赤にして言い返す。
「そういう意味じゃないわよ!」
「そういう意味でしょう。それに、私だったら喜んでお召しを受けるわ」
エステルが、若い女官の中でも特に孔雀王に惚れ込んでいるのは周知の事実である。ナオミはどういう風の吹き回しかと怪訝に思ったが、エステルは大真面目に続けた。
「だって、そうすれば、王さまのお役に立てるかもしれないのよ」
──イリスさまみたいに。
神妙な顔で告げられた言葉に、その場にいた者は全員黙り込んだ。
イリスを召し上げたいと蜻蛉帝が言い出した時、あまりに無体な要求に、孔雀王は怒り狂ったという。しかし、孔雀王を宥め、これを機に戦いを終わらせるための契約を持ちかけるように進言したのは、他でもないイリス自身であったと伝わっている。
イリスが、自身を蜻蛉帝に捧げることで孔雀王の命を守ったのは間違いない。
孔雀王自身が何と言おうとも、その心を一番に占めているのはイリスであろうことは想像に難くなく、この事実こそがアビゲイルの要素を摩耗させたものの正体なのだと思われた。
「ナオミはどう思っているの?」
急にサラから声をかけられ、ナオミはたじろいだ。周囲の視線が、自然と自分に向く。新任女官の優劣は判然としないが、王の「お気に入り」であるナオミが給仕役につくのは間違いないと思われているのだ。
「さあね。そうなってみてから考えるわ。もし本当にお召しがあったらお断りなんて出来っこないし、今ここでいくら悩んでも時間の無駄だもの。私はただ、鳥籠の宮の女官としての務めを果たすだけよ」
淡々と答えれば、仲間達は拍子抜けしたような顔になり、次第にそれもそうかという雰囲気に落ち着いていった。
器を磨く手の動きだけは止めないまま、ナオミは澄ました顔のエステルをちらりと見る。ナオミは孔雀王に恋心を抱いていないので、エステルの熱っぽい健気さを前にすると、少しばかり怯んでしまう部分があった。
いつか自分にもそういう相手が出来るのだろうかとふと浮かび、この鳥籠の宮で暮らしている限り、それはないかとすぐに思い直す。
土蜘蛛と呼ばれる自分を良いと言ってくれる風の精霊がいるとも思えないし、女官を続ける限り、外部からやってきた土の精霊とどうこうなれるわけもない。苦楽を共にできる伴侶の存在に憧れがないわけではないが、今更、鳥籠の宮を出て土の精霊達と交わろうとしたところで、自分が歓迎されないことは容易に想像がつく。
ならば、アダにならって独り身のまま、可愛い女官達を育てる立場になるというのも決して悪くはないと思えるのだった。
***
いよいよ蜻蛉帝到来の朝がやってきた。
普段、外壁の白と鉄の黒で構成されている鳥籠の宮は、蜻蛉帝の歓迎のために華やかに彩られた。
広大な吹き抜けに面した壁面には孔雀王の飾り羽を象った幕が張られ、数日前から集められた花々が、回廊を埋め尽くすようにして瑞々しく咲き誇っている。
女官達は純白の薄衣の上に特別な時だけ身に着けることを許された色帯を巻き、兵士達の鎧は、近付けば顔が映り込むまでピカピカに磨き上げられていた。
鳥籠の宮の住民が全ての支度を整えて、息を殺すようにして待ち構える中、南の空に黒い影がさした。
鳥籠の宮の周辺は、晴れの日が少ない。
今日も今日とて雨の匂いのする曇天の中、分厚い雲をこじ開けるようにして蟲の軍団が姿を現した。
黒い影が見えてから、こちらに降り立つまではあっと言う間であった。
先鋒を切って透明な翅の動きを止めたのは、槍を持った蜂の精の一団だ。
全身金色に輝く鎧をまとい、その鎧には黒々とした縞模様が入っている。おおまかな体の形は鳥の一族と共通しているのに、顔だけは虫そのものだったのでナオミはぎょっとしたが、よくよく見れば、蜂の頭を模した兜を被っているようだ。
口元がわずかに開いており、唇と顎の一部が少しだけ覗いているが、表情どころか性別さえも分からない。地面に降り立った瞬間から、道を作るように整列するその動きは、舞の一種なのかと思ってしまうほどにきびきびしていて隙がなかった。
そうして、蜂の精達が作った道の真ん中に、とてつもなく大きな蜻蛉が舞い降りた。
あまりに力が強く、もし翅で叩かれでもしたら大怪我をしてしまうので、万が一見かけたとしても絶対に刺激してはいけないと伝わる大蜻蛉の化け物──千丈蜻蜓だ。
ナオミも目にするのは初めての怪物を悠々と乗りこなしているのは、その乗り手としてふさわしい大きさの精霊だった。
ナオミの想像も及ばぬような宝玉で身を飾り立てた大男こそ、悪名高き蜻蛉帝シリウスである。
噂にあった、「門扉に入れないほど」の背丈ではなかったが、そう形容したくなるのも納得の巨躯である。地面に立った瞬間、風の精霊にあるまじき重量感のある足音が響いたほどだ。
あえてそのように装飾のされた靴なのか、それとも彼自身の足なのか判然としなかったが、地面を踏みしめる金属の靴には、禍々しい鉤爪が見える。
その身に纏うのは、配下の蜂の精のものとよく似ているが、より豪華な装飾のされた黒い鎧だ。背丈に見合う長さの透き通った翅は、まるで水晶で出来たナイフのように鋭く両脇に突き出ている。鎧のいたるところに惜しみなく黄金と金剛石があしらわれ、蜻蛉の頭を模した兜の複眼部分には、特別巨大な青玉が二つも嵌っていた。
だが、巨大な宝石よりも目を引いたのは、鎧の上からかけられた首飾りであった。
あまりに鮮やかな、大きな緑の宝玉が五つも連なっている。
そのうち一つは見るからに極上の緑柱玉だと分かったが、他は何という名前の石なのかも分からない。新緑を思わせる石、橙色の星が中に散っている石、目の冴えるような水色を帯びた、淡い緑の石もある。きらびやかなそれらの中でも特に目を引いたのは、中央に配置された石だった。
この色を何にたとえたらよいのだろう。
他のどの石よりも深く澄みきった緑の宝玉は、曇天の中でも不思議と輝きを失わず、持ち主の首元で自ら発光しているかのようだ。
随分長いこと見惚れていたような気がしたが、実際ナオミが目を奪われたのは、蜻蛉帝が降り立ち、歩き出すまでのわずか数瞬である。
その歩みに従い、蜂の精が行く手に道を作るように槍を高く掲げる。
蜻蛉帝が近付くのに合わせ、鳥籠の宮の住民も敬意を示して足を一歩引き、礼儀正しく視線を落としていく。ナオミも如才なくそれに倣ったが、蜻蛉帝がこちらに近付いてくるにつれ、鎧の擦れるガチガチという音が、まるで猛獣が威嚇のために牙を鳴らしているかのように聞こえた。
「ノアよ! 息災にしていたか」
門扉の前で待ち構えていた孔雀王に、蜻蛉帝のほうから声をかける。
口調こそ親し気であったが、その声は低く、雷鳴か大きな獣の唸り声のようだ。
ナオミが顔は動かさないまま、目だけを動かして様子を窺うと、ちょうど蜻蛉帝は自らの兜を脱ぎ捨てたところであった。
うねる黒髪がまとわりついた頰には、わずかに瑠璃色の斑紋が浮いて見える。
肌は鋼のような光沢を持っており、鼻梁は高く、唇は薄い。
こうして華奢な孔雀王と並び立つと、同じ属性の精霊とはとても思えないほどに猛々しい印象であるが、顔のつくり自体は、風の精霊の特徴が強く出て、彫りが深く優美ですらあった。
だが、化物でなくて良かったと安堵するには、その眼差しはあまりにも冷ややかだ。
「はい。陛下こそ、ご健勝そうで何よりでございます」
そつなく挨拶を返す孔雀王を見下ろす蜻蛉帝の表情には、全く温かみが感じられない。大きな鷲がネズミの尻尾を捕まえて、さあどこから食ってやろうかと吟味しているかのようだった。
蜻蛉帝は酷薄に微笑む。
「しかし、せっかく良い雌を選んでやったというのに、子をもうけることも出来ないまま逃げられるとは情けないことだ。そなたに甲斐性がないのではないか?」
一瞬、孔雀王が蜻蛉帝を睨みでもするのではないかとナオミは危ぶんだが、彼は従順に頭を垂れるのみであった。
「私が不甲斐ないばかりに、陛下にはご足労頂いてしまい、大変面目なく存じます」
挑発に乗らなかった孔雀王に、蜻蛉帝は面白くなさそうに鼻を鳴らす。
そのまま、蜻蛉帝は蜂の兵の担ぐ輿に乗り替え、宴会の支度を終えた最上階まで、自らの翅を一切使わずに運ばれていった。
今日は、妻の候補である踊り手以外の者が吹き抜けを飛ぶことは禁じられている。出迎え役だったナオミ達は、皇帝と王を追って螺旋階段を上らなければならなかった。
苦労して上まで辿り行くと、こちらで待機していた女官らによって、すでに宴は始まっていた。
竪琴の音色と甘やかな歌声が、空間いっぱいに響き渡っている。
硝子の天井にかけられたまじないで増幅された光が虹色に降り注ぐ中、薄衣の衣装をまとった高級女官達が、翼を広げて舞い踊る。
上座に目をやれば、いつも孔雀王の玉座のあるところには、鳥籠の宮にはあまりそぐわない、豪奢な玉座が据えられていた。
黄金の台座に緑玉髄の装飾がほどこされたそれに、悠々と腰を下ろしているのは蜻蛉帝だ。歓待する側の孔雀王は、その隣の幾分控えめな装飾の座具におさまっている。
新たな妻の品定めに来ているはずなのに、極上の美貌を誇る女が歌い、見事に竪琴を奏でようとも、次々と着飾った女が飛び出し、いかにすばらしい舞を披露しようとも、蜻蛉帝はそちらにはちらりと目をやるだけで、後は孔雀王のほうばかり見つめている。
孔雀王は顔こそ笑っているが、内心穏やかではないだろう。
そうこうしているうちに曲が終盤に差し掛かり、踊り手と給仕係が、それぞれの控えと入れ替わる頃合いが近付いてきた。
予想通り、ナオミは銀の大甕から葡萄酒を蜻蛉帝と孔雀王に供する役目を与えられた。相方となったのは、こちらも大方の予想通り、サラである。
隣を窺うと、取手の片割れを持つサラの手は震えていた。
「サラ?」
小声で名前を呼ぶと、サラは我に返ったように目を瞬く。
「大丈夫よ。しっかりお務めを果たしてみせるわ」
にっこりと笑う表情には陰りは見えなかったが、考えるよりも先に口が動いた。
「場所を替わるわ」
今の立ち位置だと、サラが蜻蛉帝の相手を務めることになる。なんとなく、このままサラを出て行かせるのは良くないような気がした。
ナオミの言葉を聞いたサラは、彼女には珍しく唇を尖らせた。
「見くびらないで。私だってちゃんと出来るわよ」
「そうじゃない。先に名前を呼ばれたのは私でしょう。女官の序列に従うなら、私が蜻蛉帝のお相手にならなきゃ」
「でも──」
「アダさま」
なおも食い下がろうとするサラを押し留め、ナオミはせかせかと女官達の間を見て回っていた女官頭を呼び止めた。
「この期に及んで、何事ですか!」
不備があったのかと顔色を変えてすっ飛んできたアダに、ナオミは自分とサラを交互に指さす。
「今日、最初に名前を呼ばれたのは私でした。蜻蛉帝のお相手を務めるべきは私ですよね?」
一瞬、年若い目の前の女官二匹と上座を見比べたアダは、全く迷わずに頷いた。
「その通りです。今の位置のほうが間違っていますね。序列はちゃんと守るように」
ね、とナオミは小さく微笑むと、なおも逡巡するサラと無理やり場所を入れ替わる。
「なんか、あなたに悪いわ……」
ぽつりと呟くサラに、「何を言っているの」とナオミは笑う。
「あなたの気持ちどうこうではなく、これは序列の問題よ。最優秀の座は渡さないわ」
「まあ」
エステルあたりが聞けば嫌な顔をしただろうが、ナオミの気遣いはしっかりサラに伝わったようだ。サラは緊張がほどけたように微笑むと、曲が終わり、控えていた階段から謁見の間に上がる間際、「ありがとう」と小さく囁いたのだった。
ナオミ達がしずしずと進むうちに、次の曲が始まった。
先ほどよりもずっと速い曲調だ。
竪琴がかき鳴らされ、燕の翼を持つ女達が鋭く旋回し、長い薄衣がひゅるひゅると弧を描く。
蜻蛉帝と孔雀王の中間となる位置に酒甕を下ろすと、おそらくは蜻蛉帝の使っている香なのだろう、眩暈がしそうなほどの強い麝香が匂った。
サラには強がって見せたが、ナオミだって蜻蛉帝は恐ろしい。
孔雀王と談笑する蜻蛉帝はこちらを一顧だにしなかったが、そのほうが助かるというものだ。
長い銀杓を使って己の掌に数滴酒を垂らし、毒がないことを示すため、全てを舐めて飲み込む。汚れた手を帯に挟んだ手巾で軽く拭いてから、改めて杓で酒を汲み、蜻蛉帝の金の椀に注ごうとした時だった。
「変わった毛色の者がいるな」
低くおどろおどろしい声が響くのとほぼ同時に、手首を強くつかまれる。
先ほどよりも強く麝香が匂い立ち、あまりの驚きに、心臓が動きを止めたような心地がした。
「こちらを見よ」
従わなければと思ったからではなく、まるでこの声自体がまじないであるかのように、自然とナオミの顔が上がる。
ぶつかりそうなほどの近距離で、目と目が合った。
間近にした蜻蛉帝の瞳は、最高級の青玉もかくやという鮮やかな青をしている。
そこに浮かんでいるのは、先ほどまでの踊り手を見やった時の無関心な目とも、孔雀王に対する嗜虐的な目とも明らかに違う、好奇心の光だった。
「翼のない者が、どうしてこんなところにいる?」
珍しい生き物に純粋に興味を覚えたような、ナオミの目や肌の色を検分するような眼差しを認めた途端、すとんと腹の底が据わった。
ナオミは、確かに鳥籠の宮において土蜘蛛と蔑まれることもしばしばであるし、自分でも異質な存在であることは誰よりも理解しているつもりだ。
だが、それを恥ずかしいと思ったことは一度もない。
「棲み処を火竜に奪われて死にかけていたところを、孔雀王に拾って頂きました」
答えた声は、我ながら呆れるほどに落ち着き払って聞こえた。
「なるほど」
ナオミが動揺を見せなかったことを面白がってか、蜻蛉帝は両眼をゆっくりと細める。
「ここは、高慢な風の精ばかりだろう。土蜘蛛などと蔑まれて、さぞや嫌な思いをしているのであろうな?」
「いいえ」
大変よくして頂いておりますと、にっこりと微笑んで返すと、蜻蛉帝は急に大声を上げた。
「なんと気の強い娘だ!」
一瞬、怒声かと思ったほどの声量であったが、それは銅鑼のように、あるいは雷のように響く笑い声だった。
いつの間にか、音楽は止まっていた。
蜻蛉帝が笑うのを止めると、花のひとひらが落ちても聞こえそうなほどの沈黙が謁見の間を支配した。
今や、この場にいる全員が、蜻蛉帝と自分に注目している。
「そなた、名は何という?」
蜻蛉帝の一言に、大勢が息を呑む音がひとつになって聞こえた。
──名を訊かれるのは、お召しの合図だ。
これに応じて名を明かせば、ナオミは蜻蛉帝のお召しを受け容れたことになる。
一瞬、うっかり助けを求めるように、蜻蛉帝の隣に座る孔雀王を見てしまった。
孔雀王は目を見開き、真っ青な顔をしている。
だが、止めてはくれない。そんな権限は、そもそも彼にはないのだ。
ナオミは、出来る限り自然な素振りに見えますようにと祈りながら、視線をもとに戻した。
蜻蛉帝の瞳は相変わらずギラギラと輝き、こちらを射抜くようだ。
ほんの数日前、自分は言った。もし本当にお召しがあったら、お断りなんて出来っこない、と。
喜んでいる顔に見えるよう、意識してきゅっと口端を吊り上げる。
「わたくしの名は、ナオミと申します」
これで、今宵の蜻蛉帝の相手が決まった。
続きは本書でお楽しみください。