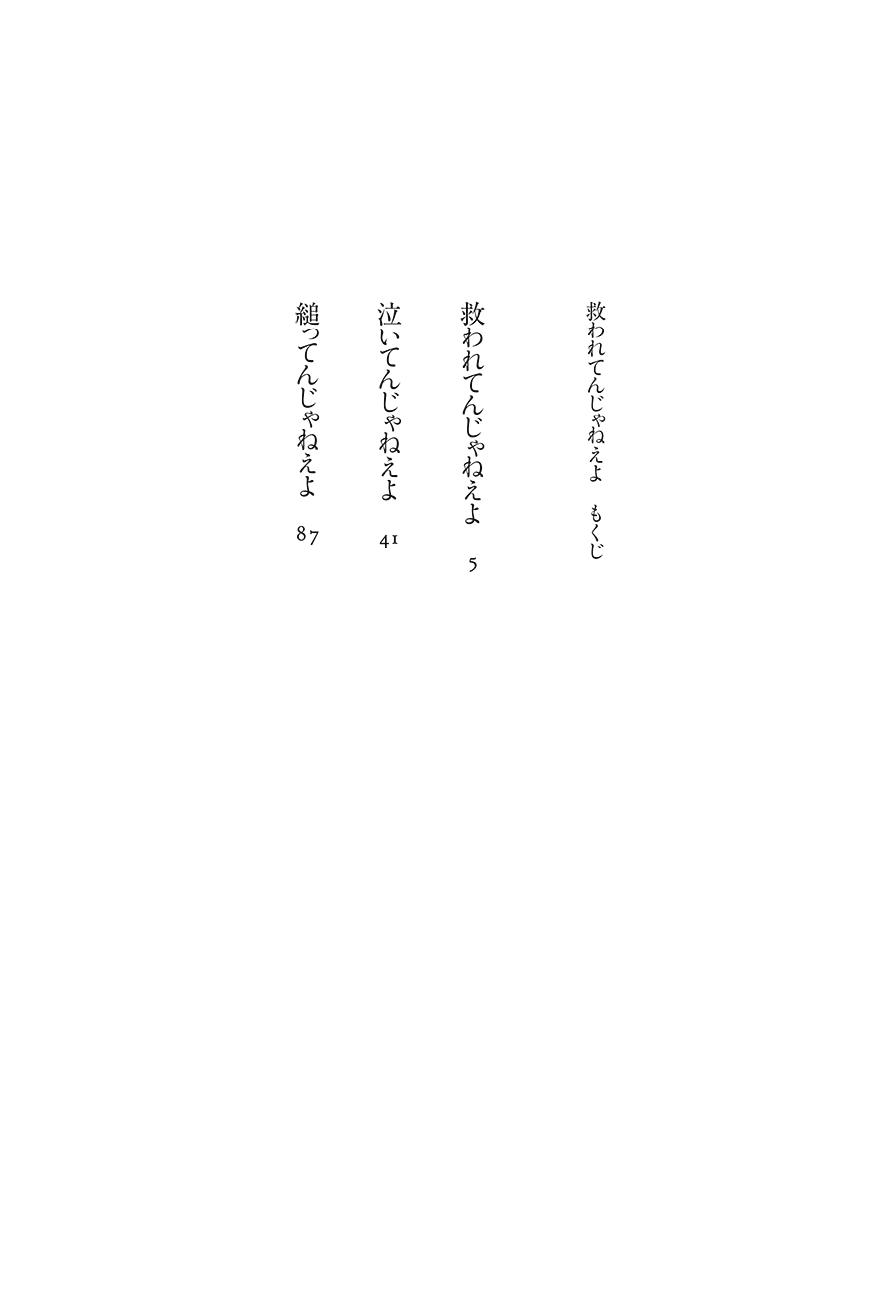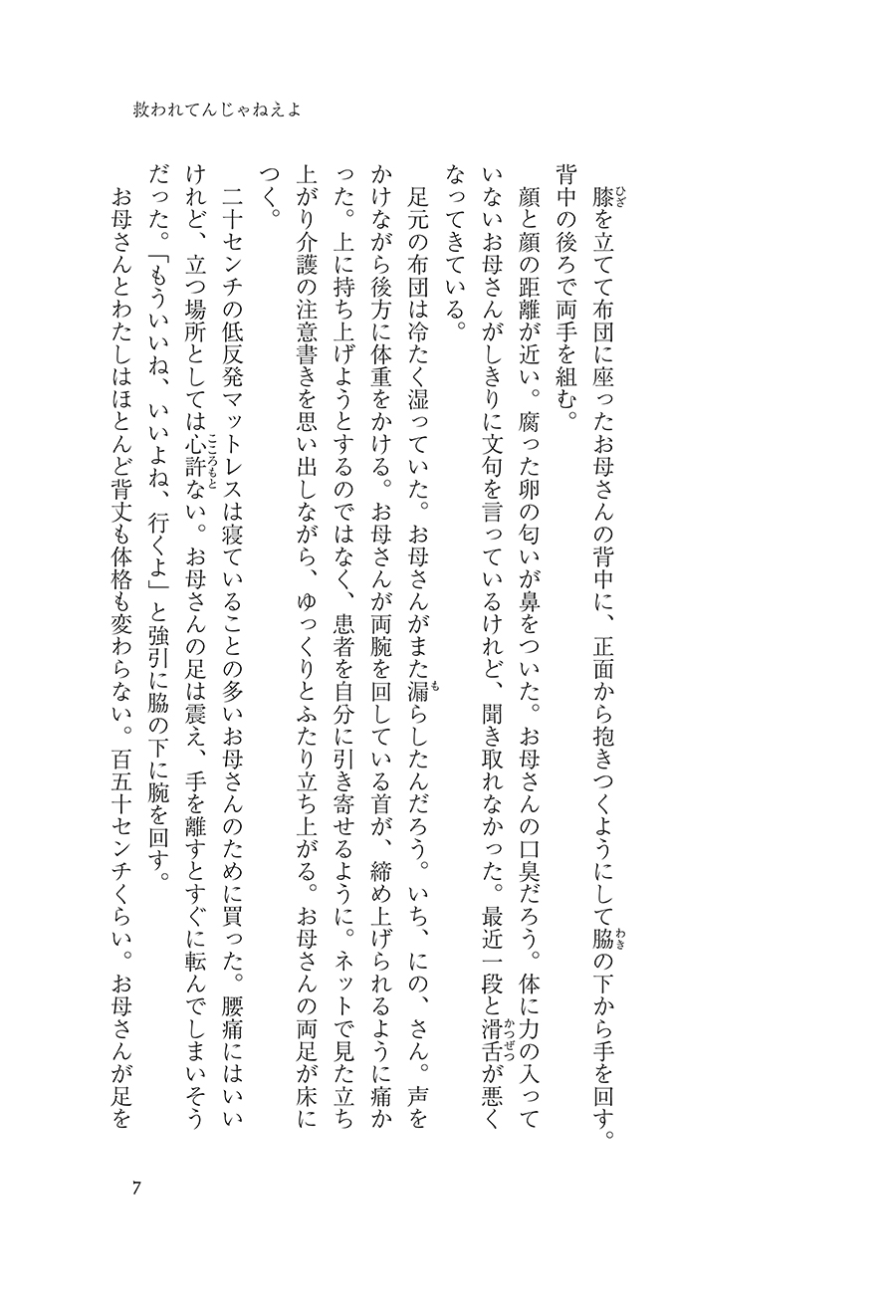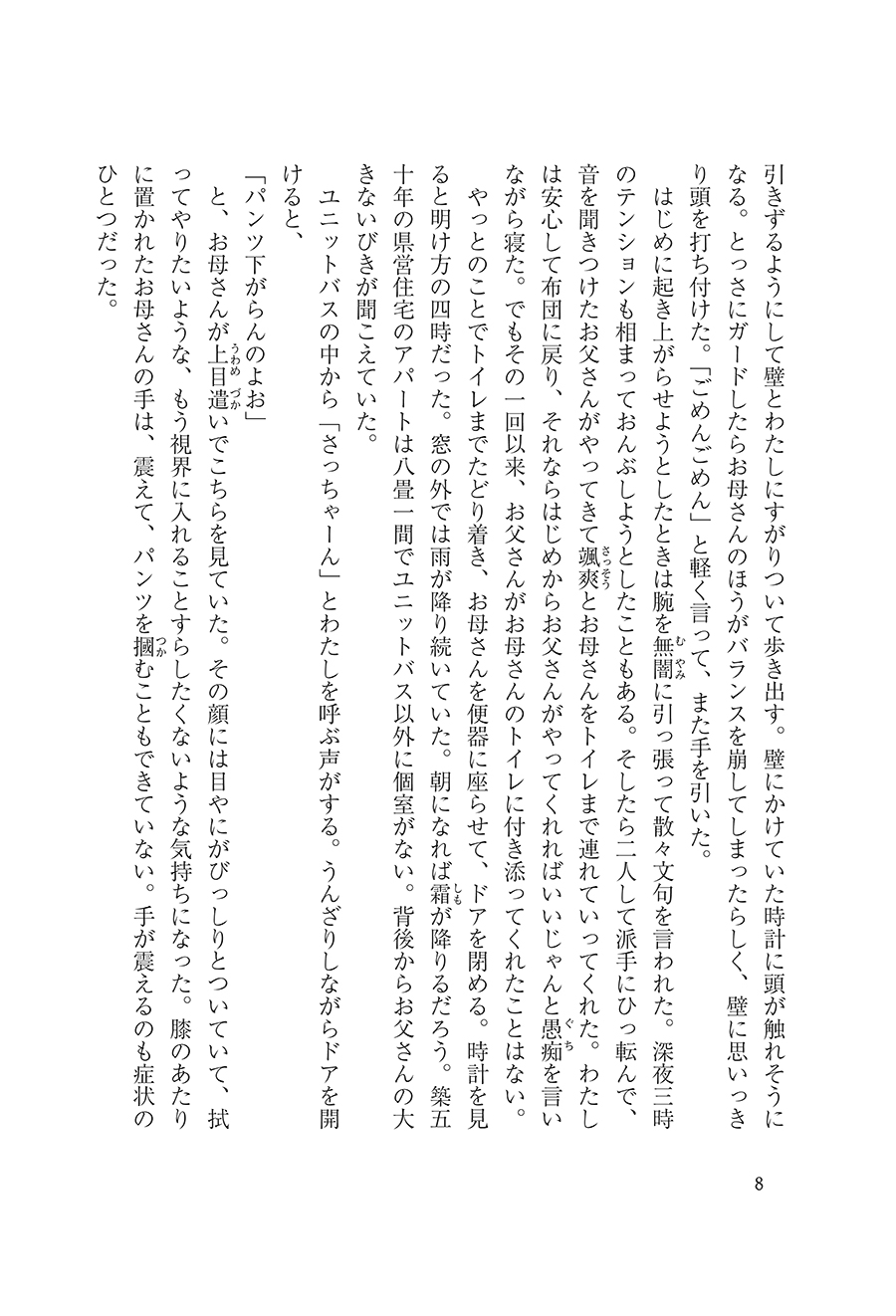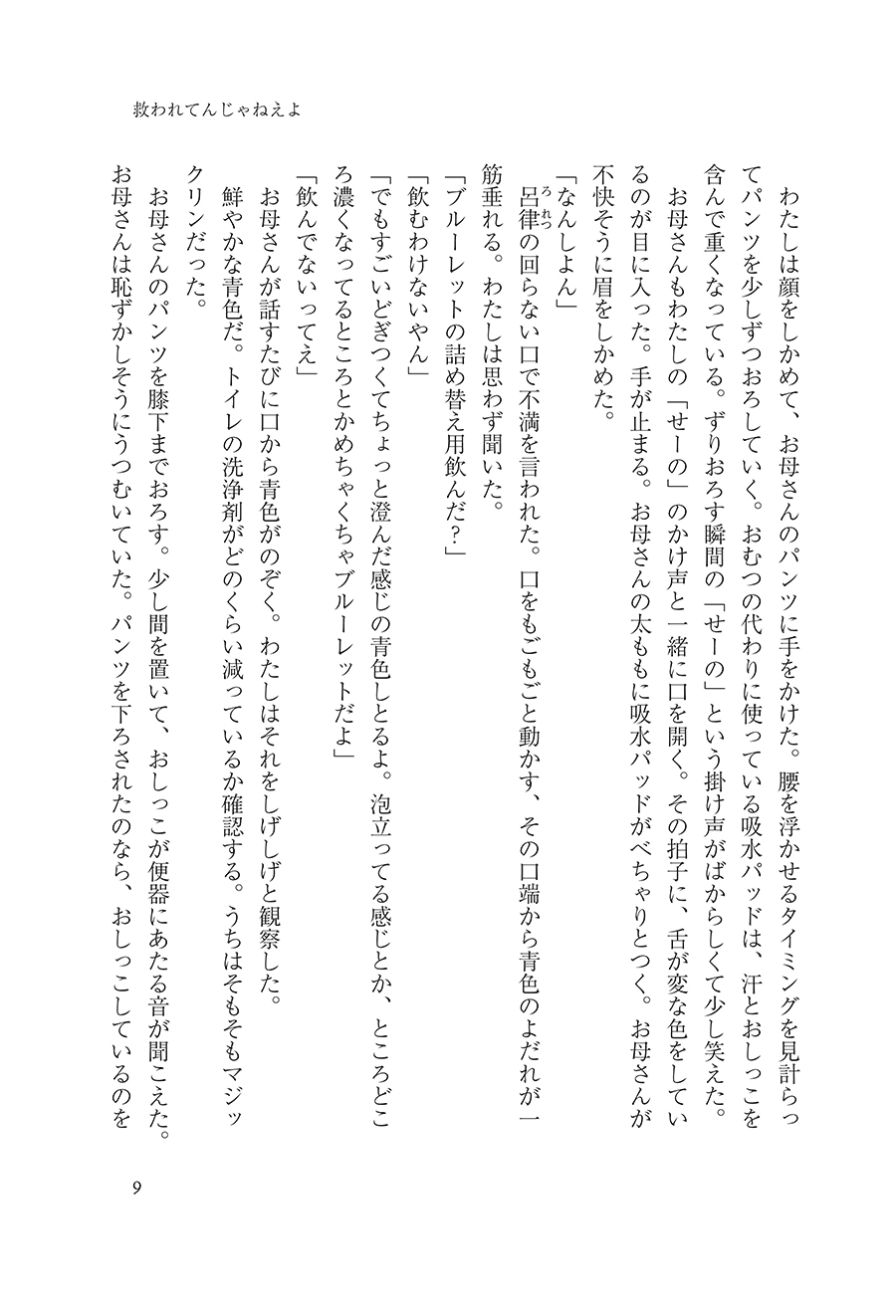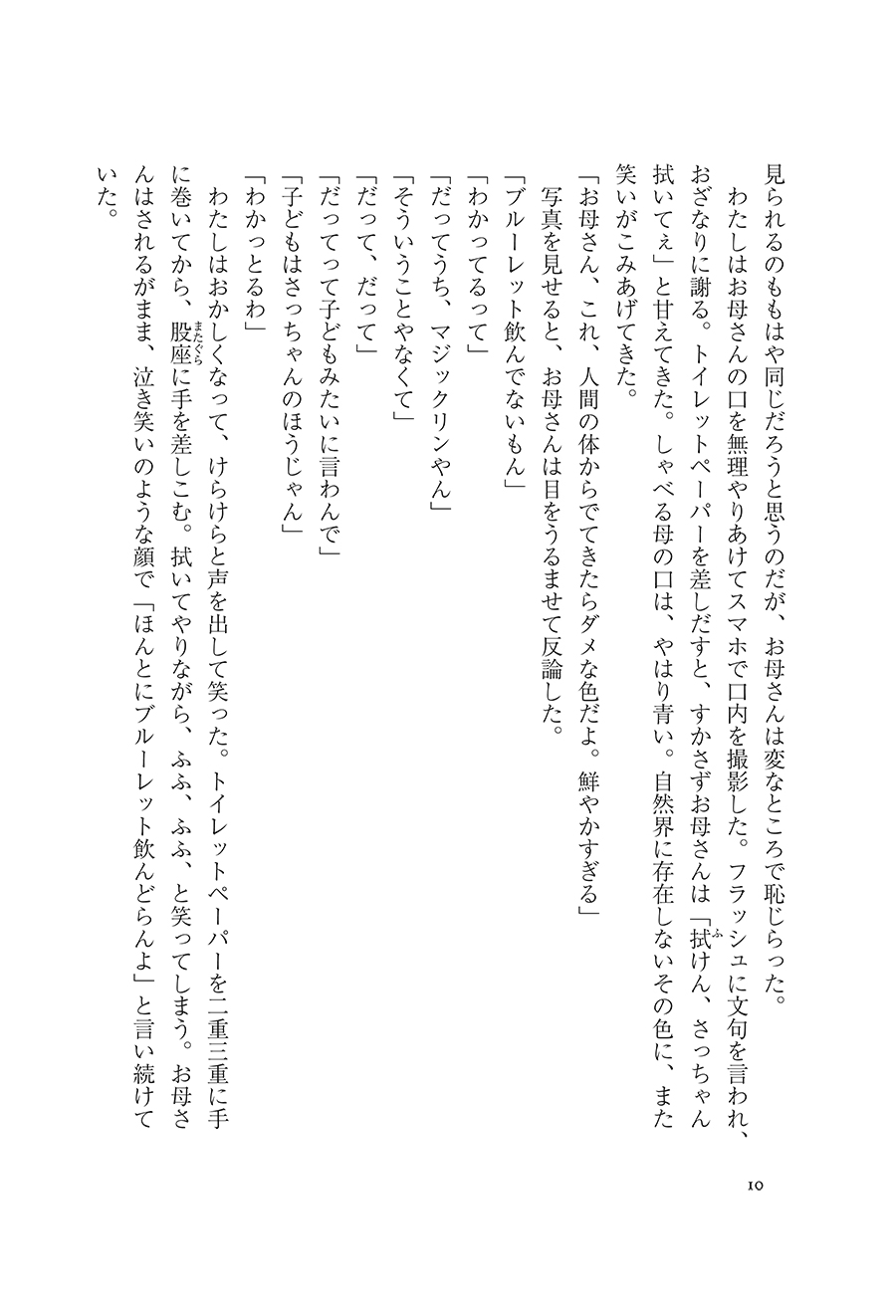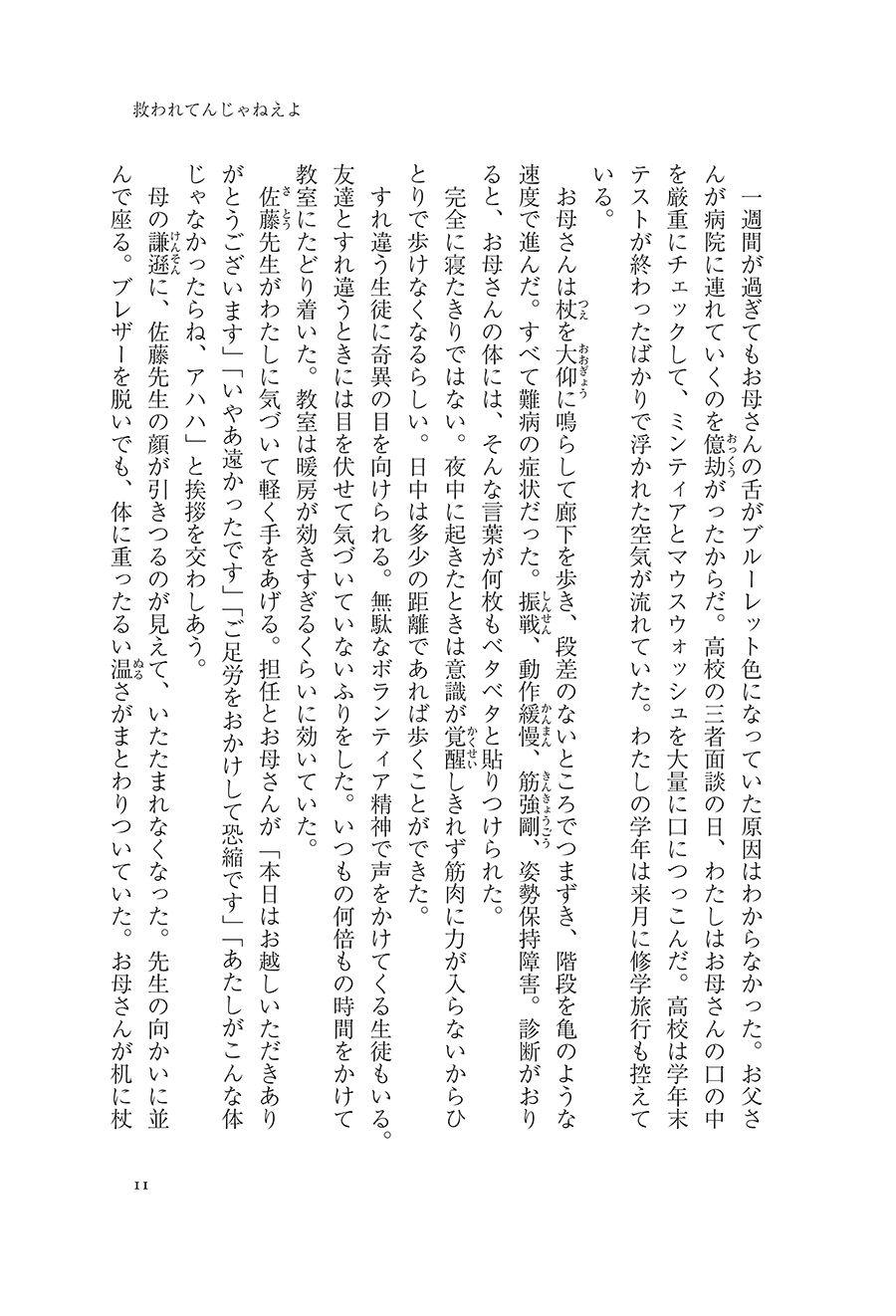救われてんじゃねえよ
顔と顔の距離が近い。腐った卵の匂いが鼻をついた。お母さんの口臭だろう。体に力の入っていないお母さんがしきりに文句を言っているけれど、聞き取れなかった。最近一段と
足元の布団は冷たく湿っていた。お母さんがまた
二十センチの低反発マットレスは寝ていることの多いお母さんのために買った。腰痛にはいいけれど、立つ場所としては
お母さんとわたしはほとんど背丈も体格も変わらない。百五十センチくらい。お母さんが足を引きずるようにして壁とわたしにすがりついて歩き出す。壁にかけていた時計に頭が触れそうになる。とっさにガードしたらお母さんのほうがバランスを崩してしまったらしく、壁に思いっきり頭を打ち付けた。「ごめんごめん」と軽く言って、また手を引いた。
はじめに起き上がらせようとしたときは腕を
やっとのことでトイレまでたどり着き、お母さんを便器に座らせて、ドアを閉める。時計を見ると明け方の四時だった。窓の外では雨が降り続いていた。朝になれば
ユニットバスの中から「さっちゃーん」とわたしを呼ぶ声がする。うんざりしながらドアを開けると、
「パンツ下がらんのよお」
と、お母さんが
わたしは顔をしかめて、お母さんのパンツに手をかけた。腰を浮かせるタイミングを見計らってパンツを少しずつおろしていく。おむつの代わりに使っている吸水パッドは、汗とおしっこを含んで重くなっている。ずりおろす瞬間の「せーの」という掛け声がばからしくて少し笑えた。
お母さんもわたしの「せーの」のかけ声と一緒に口を開く。その拍子に、舌が変な色をしているのが目に入った。手が止まる。お母さんの太ももに吸水パッドがべちゃりとつく。お母さんが不快そうに眉をしかめた。
「なんしよん」
「ブルーレットの詰め替え用飲んだ?」
「飲むわけないやん」
「でもすごいどぎつくてちょっと澄んだ感じの青色しとるよ。泡立ってる感じとか、ところどころ濃くなってるところとかめちゃくちゃブルーレットだよ」
「飲んでないってえ」
お母さんが話すたびに口から青色がのぞく。わたしはそれをしげしげと観察した。
鮮やかな青色だ。トイレの洗浄剤がどのくらい減っているか確認する。うちはそもそもマジックリンだった。
お母さんのパンツを膝下までおろす。少し間を置いて、おしっこが便器にあたる音が聞こえた。お母さんは恥ずかしそうにうつむいていた。パンツを下ろされたのなら、おしっこしているのを見られるのももはや同じだろうと思うのだが、お母さんは変なところで恥じらった。
わたしはお母さんの口を無理やりあけてスマホで口内を撮影した。フラッシュに文句を言われ、おざなりに謝る。トイレットペーパーを差しだすと、すかさずお母さんは「
「お母さん、これ、人間の体からでてきたらダメな色だよ。鮮やかすぎる」
写真を見せると、お母さんは目をうるませて反論した。
「ブルーレット飲んでないもん」
「わかってるって」
「だってうち、マジックリンやん」
「そういうことやなくて」
「だって、だって」
「だってって子どもみたいに言わんで」
「子どもはさっちゃんのほうじゃん」
「わかっとるわ」
わたしはおかしくなって、けらけらと声を出して笑った。トイレットペーパーを二重三重に手に巻いてから、
一週間が過ぎてもお母さんの舌がブルーレット色になっていた原因はわからなかった。お父さんが病院に連れていくのを
お母さんは
完全に寝たきりではない。夜中に起きたときは意識が
すれ違う生徒に奇異の目を向けられる。無駄なボランティア精神で声をかけてくる生徒もいる。友達とすれ違うときには目を伏せて気づいていないふりをした。いつもの何倍もの時間をかけて教室にたどり着いた。教室は暖房が効きすぎるくらいに効いていた。
母の
佐藤先生がわたしの成績表を机に広げ、今年一年の学校生活について振り返りをはじめる。お母さんは成績表をのぞきこみ、「あら
「お母さんから見てご家庭での
佐藤先生が尋ねる。お母さんは待ってましたとばかりに話しはじめる。
「さっちゃんにはあたしの介護も家事もやってもらってて、負担やろうなあって心配しとったんです。それまで家ではなんにもしない子だったから。あたし、薬が効くまでは歩くことひとつできんけん」
お母さんが机の縁にひっかけていた杖に触れる。
「不自由させて気の毒かなあって。あたしの障害年金がおりたら、助かるとですけど」
「おうちでもお手伝いをたくさんされていて素晴らしいですね。学校でも清掃の時間など真面目に取り組んでいただいていまして」
佐藤先生がいつもよりワントーン低い声でほめ言葉を紡いでいく。真面目。優しい。そんな誰にでもあてはまるような言葉たち。お母さんはそれをうれしそうに聞いている。
「沙智さんは、卒業後の進路はどうしたいと考えてますか?」
「……いまは考えてません」
考えるのが億劫で、つき放すように言ったわたしの返答も、佐藤先生はめいっぱい好意的に解釈してくれた。そうですね、いまはおうちでのお悩みも多いでしょうし、少しずつ解決していって、三年生になったら進路も本格的に考えていきましょう。先生の穏やかな声は、上滑りして、うまく耳に届いてこなかった。
少しずつ解決と大人は言うけど、じゃあ、だれが解決してくれるっていうんだろう? 薬が効く。障害年金が出る。解決の道は明確だ。道は明確なのに、薬がいつから効くのかも、障害年金がいつから受給できるのかも、わたしにはわからないし、だれも教えてくれない。
わたしが顔をうつむかせたとき、カランカランと金属音が鳴った。視線を向けると、お母さんの杖が床に倒れている。お母さんがあわてて拾おうとして、転びそうになるのが見えた。
「あ、大丈夫ですよ、お母さん」
佐藤先生が言って、急いで拾ってくれた。お母さんの顔は紅潮している。わたしもきっと顔が赤くなっている。お母さんが緩慢に姿勢を戻す。トレーナーの首元に青いしみがあった。
教室を出ると
「さっちゃん、どうだった?」眉を下げて聞かれる。
「別に普通だよ」
「あーさっちゃんは怒られないよねえ、あたしバカだからなあ」
彼女はそう言いながら前髪を一房ずつ整える。綺麗に整えられた眉がちらちらと見えた。
わたしは成績がいいわけじゃない。わたしが怒られないのはわたしが優等生だからじゃないってことを、この子はわかっている。特別扱いされてるもんね、と目だけで訴えてくる。その目がするっとわたしのお母さんを見つめる。いやな予感がした。猛烈に。優子の口が開く。ああ、と小さな
「さっちゃんとこはおばあちゃんなんだあ」
わざとらしいくらいに目を細めて、彼女は言った。わたしは傷つくよりも先に、煩わしく思った。
わたしが難病の母親を介護していることを知らないクラスメイトはいない。佐藤先生が朝のホームルームで我が家の事情を話して、手助けしてやってくれと宣言したから。優子のお母さんが慌てた様子で「こら、失礼でしょ」と優子の肩を叩いた。
目を伏せる。お母さんを見つめる。お母さんは白髪の混ざった短髪で化粧っ気がない。しわもたくさんあって杖をついていて腰は曲がっている。着替えが上手くできなくて、部屋着のベージュのスウェット上下を着ている。手は震えている。うつむいてわたしとも目を合わせない。自分の指を握りしめる。指先は冷たいのに、体は火照っていた。
「お母さんだよ」
ぼそりと、ずいぶん遅れて返事をしてから、お母さんの腕をつかんだ。脇の下と
小さいころに見た夢の中で、お父さんを本気で殴ったことがある。
お父さんはいまの何倍も強大な存在だった。その夢で、わたしはそれが夢なのか現実なのか曖昧なまま、体を起こして隣を見るとお父さんとお母さんが同じ布団にいた。うちには八畳の部屋が一部屋しかない。そこに布団を三枚敷いて寝ていた。夢の中で目を覚ましたわたしはお父さんがお母さんにのしかかっている光景を目にして、あっと思う。お母さんが殴られる、と直感的に感じる。お母さんは確か「痛い、痛い」と言っていて、なにか暴力的な行為が行われているみたいだと、夢の中の幼いわたしは察する。わたしが飛び起きてお父さんの背中を必死に殴ると、お父さんはあわててわたしに布団をひっかぶせ、「寝とれ!」と怒鳴る。怒られたことに驚いたわたしはかぶせられた布団にくるまったまま、また眠りに落ちる。
そのことを思い出すたび不思議に思っていた。当時小学生にもなっていなかったわたしがそんな夢を見るなんて。いま考えると、あれは現実だったのだろう。
わたしはお父さんとお母さんのセックスの声を聞くたび、それを思い出す。
「痛い、痛い」
お母さんのか細い声が背後で聞こえる。その声はあの記憶にそっくりだ。わたしが現実に沿って記憶を書き換えたのか、お母さんの声が変わっていないのか。
二人の息遣いと
一週間くらい前、わたしが必死にお母さんを立ちあがらせてトイレまで連れて行ったとき、お父さんがトイレでAVを見ていた。スマホの小さい画面を食い入るように見ていたお父さんの姿は一週間たったいまでも目に焼きついている。そのAVからは女性のアンアンした声が聞こえていた。わざとらしいやつ。反して、お母さんは決してそんな声をあげない。常に声を押し殺している。押し殺してくれないとこちらも困るけど、苦しそうな声を聞いていると心配にもなる。
はやく終わらないかなと目を固く閉じた。お母さんの姿を、思い浮かべたくもないのに思い浮かべてしまう。おしめを変えるような恰好で、ふたりが向き合っていると思うと変な感じがした。
さらによくわからないのは、セックスの頻度が最近増えているということだった。
昨日、排泄介助をしていると言ったら佐藤先生におおげさなくらい同情された。心配でもなく労わりでもなく同情。わたしは不幸自慢スカウターで言えば結構戦闘力高めなんだと思う。お母さんも対外的に見れば不幸自慢スカウターカンストだ。難病で、娘に介護されていて、もともと体が弱くて。今後薬が効く保証もない。障害年金を受給できるのは申請から四、五か月後らしい。年金があったらヘルパーも雇えるし、施設にも入れる。薬が効いたら五年くらいは日常生活にまったく問題はなくなる。いまはその狭間にいた。
お母さんにとっては、きっといまが一番、闘病記で注目されるシーンだ。だれに話しても「辛いよねがんばって」って言ってもらえる。ソーシャルワーカーとかいう職業の人に言ったら「受給までに時間がかかることは社会的弱者にとって問題です」って記事でも書いてくれるんじゃないかな。
「足」とお父さんの声がする。お母さんがぼんやりした声で「え?」と応じる。
「右足、上げて」
「こっち?」
「ちがう、おれから見て右」
「こう?」
「そう、ちがう、左は降ろさんでいい」
「どっち?」
「どっちも上げろって」
隣で振動が大きくなる。その揺れを感じていると、セックスってお父さんとお母さんなりのボケなんじゃないかなと思えてきた。お母さんは明らかに難病になってからセックスに応じる回数が増えた。なんでかは、わからない。
もういっそ、ぜんぶに意味があったらいい。お母さんがお父さんとセックスするのは自分の病気の辛さを紛らわせるためだとか、病気の自分を見捨ててほしくないからだとか。理由があったらいい。しかしどう考えたって、そんな大層な理由なんかなく、お父さんとお母さんはセックスしている。娘の隣で。ちょっと頻度が増えている。心なしか激しくなっている。
トイレでAVを見ていたときのお父さんはすごく必死に
人には
振動がやんだ。するっと布団を抜け出す。酒の匂いにまじって、青臭いような匂いがする。お父さんとお母さんのほうは見ない。ユニットバスに入って扉を閉める。トイレと風呂が一緒くたになっているから、トイレのほうの床も水浸しになっていた。便器にうんこ座りをして、スマホを取りだす。
スマホでSNSのアカウントを開いて、「眠れない泣」と
*
朝六時三十分のアラームで起きて、となりを見るとお母さんがいなかった。一晩起こされなかったからか、体が軽かった。
伸びをして振り返ると、八畳の一角にある、台所ともいえない狭いキッチンスペースにお母さんが立っていた。キッチンの脇にある小さな窓から、朝日が差しこんでいた。わたしは布団に座って毛布にくるまったまま、お母さんの背中を
お母さんが溶かした卵にスプーン山盛りの砂糖を入れる。料理するお母さんを見たのは半年ぶりだった。首元には、もう青いしみはついていない。よれたスウェットに
「あ、起きたん? 机だしといてくれる」
お母さんが振り返って言う。ワンルームのわが家にはダイニングテーブルなんてものはない。食事のときはいつも、折り畳みテーブルを出していた。
「お母さん」
思わず声をかけた。起きられたんやとか、元気になったんとか、言葉が浮かんだ。口から出てきたのは違う音だった。
「卵、だし巻きがいい」
「ええ? もう砂糖入れたよ」
「どうせお父さんが食べるでしょ、わたしの卵だし巻きにして」
わたしのわがままに、お母さんは「めんどくさ」とぼやきつつ、白だしの瓶を取りだしてくれた。年中閉め切っているカーテンを開けると、太陽が燦々と照っていた。光が目に
その日以来、お母さんの調子はぐんぐんとよくなっていった。一週間ほど前に薬を変えてみたら、それが体に合って、症状が急激に緩和されたらしい。もう日常生活に支障はなくなると思いますと主治医の太鼓判つきだ。お母さんの痰が青くなっていた原因もわかった。主治医に定期診察で相談したところ「着色の錠剤を飲んだときに嚥下できなくて、着色剤が溶けだしたんでしょう」と三秒で返答がきたらしい。
そしてお母さんの症状が薬でほとんど治まったころ、障害年金の受給が決まった。
受給決定の発表はわが家の折り畳みテーブルを囲んで行われた。お父さんがもったいぶって年金証書をテーブルに置く。わたしとお母さんは大げさに拍手をした。やった、やったと声に出してみたり手を握り合ってみたり、年金証書を三人でのぞきこんであほみたいな喜び方をした。
月十万円。証書の支給額の欄にはその数字が書かれていた。わが家のひと月の世帯収入の半額だ。お父さんは年金事務所に通った苦労を恩着せがましく語った。わたしとお母さんは「やっと解放されるわ」と憎まれ口をたたいたり、「使い込んだらだめやで」と冗談を言ったりした。薬が効いて。障害年金が出て。解決の道がぱあっと開けた気がした。こんなに簡単なことだったのかと呆気なくなるくらいだった。三人とも終始浮かれていた。
年金の振り込みがあったのはその三週間後だった。冬の底にひびが入りはじめていた。
「お母さんさあ、このご飯何日目? ちゃんと冷蔵庫いれたん?」
「もう覚えとらんけど、冬やし腐らん腐らん」
「いやもう
「老眼やもん」
そんな問答をするのは五回目だった。お母さんはいつも「あたしばっかり悪者にして。空が青いのもポストが赤いのもあたしのせいね」と泣くか、「そんなに言うなら食べんでよか!」と逆ギレするかのどちらかだった。今日は泣かれた。ベリーショートで皮膚炎がひどい赤い顔で泣かれると、本当に子どもをいじめているような気持ちになる。泣きまねではなく本気で涙を流すのだから体を張っていた。
お母さんが床に伏せって家事できなかった期間は、わたしが代わりをしていた。炊事、洗濯、掃除。お父さんは仕事ばかりで手伝うそぶりさえみせなかったから、自然と母の役割はわたしに移ってきた。
お母さんは病気のあいだわたしに感謝しつつも「あたしの苦労のわかったやろ」なんてにやついていたけど、わたしのほうがよっぽど勤勉な主婦だった。お母さんという人はそもそも主婦に向かない人なのだ。お母さんが病気になる前のうちの献立には週三でインスタントラーメンが組み込まれていたし、洗濯は二日に一回、掃除は月に一度していれば偉いほうだった。なによりお母さんには衛生観念がなかった。
「空がこんなに青いのも、電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのもみんなあたしが悪いのよ。ぜーんぶお母さんのせい。空がこんなに青いのも、電信柱が高いのも……」
語呂よく泣くお母さんをほっぽって、
お母さんがあまりにしつこいので「うるさい」と怒鳴った。お母さんは、親に叱られた子どもみたいに縮こまって枕を濡らしながらまだ「ポストが赤いのも……」と唱えつづけている。ぴんぽーんとチャイムが鳴る。出るとお父さんだった。
お父さんは一週間前に家の
お父さんは手に提げていた紙袋を布団に放った。わが家では布団は基本的に敷きっぱなしである。お母さんには見向きもせずテレビの電源を入れる。バラエティ番組が流れだす。わたしはお父さんの近くに寄っていって「これなに?」と聞いた。紙袋にはビックカメラのロゴがプリントされていた。いやな予感がした。
「なん買ってきたん?」
開けようとすると、手で邪魔された。開封してはいけないらしい。
「カメラ」
お父さんから返ってきたのは、端的な答えだった。カメラにしては袋が大きい。絶対に問いつめなければいけない、と直感が働いた。お父さんが仕事用の
「わたしも最近カメラ興味あるんだよねーなに買ったん? 大きい袋やん、ほかの部品も買った感じ?」
「お、興味あるん」
お父さんはスーツのまま袋を開けはじめた。中身も厳重に箱にしまわれている。その側面には本体の写真がプリントされている。
「デジタル一眼レフのズームレンズセット。望遠レンズ三百ミリで画角も探してたのにぴったりだったから、買っちゃった。三脚も持ち運びしやすいやつがあるって店員さんに言われて。仕事でカメラ使うやろ、ちょうどいいし買っとこうち思うて」
一眼レフに望遠レンズに三脚! 買っちゃったじゃねえよ! とパンチするお気持ちだったが、仕事用と聞いて安心した。
「あ、仕事用ってことは経費で落ちるんや。焦った」
「いやこれは私用でも使うから自腹」
「は?」
わたしとお母さんの声が重なる。お母さんが、がばっと起き上がってこちらにやってきた。普段からは考えられない俊敏な動きだった。
「私用で写真撮ることなんてないやろ、絶対ないやろ。いくら? いくらしたん?」
問い詰めたのはわたしだった。お母さんはこういうときにお父さんに強く出られない。お父さんがテレビとわたしたちを交互に見て、煙草を吸う。わたしはテレビを消した。
「あ、なんすっとか!」とリモコンを取りあげられる。テレビがつけられる。芸人の声が部屋に響く。いくらだったのかともう一度問いつめると、お父さんはテレビに目をやったままふーっと煙を吐いた。
「十万」
またしても端的な答えだった。じゅうまん。思わずオウム返しする。障害年金の月の支給額だ。仕事で広報に関わるようになってきちんとした撮影をしなきゃいけないとか、趣味の一つももっていないと人間としてよくないとか言い訳が聞こえる。仕事なら経費で買ってほしいし、年収三百万に届いてから文化的な生活を求めてほしい。
「そいはあたしのお金やん!」
お母さんが枕を握りしめて叫んだ。その枕には茶色いよだれのシミと青い点々がまだらにある。お父さんはぶすくれた顔でテレビを見つづけていた。普段は低俗だとバカにしているくせに。また泣き出して、しゃくりあげるお母さんの声と、芸人の笑い声だけが部屋に響いていた。
どうせすぐ飽きて使いもしないカメラにそんな大金使うなんて。うちが貧乏で苦労してるって知っているくせに。お母さんの十万円が決まったとたんにこれだ。
そんなふうに、言うべき文句はたくさんあった。でも体は固まってしまっていた。どこか予定調和のような、わたしはこの展開を予想していたような気持ちがあった。
ホームルームでわが家は「お母さんの介護で大変なおうち」だと紹介された。問題はお母さんの難病だけってことにされた。そうじゃなかった。お母さんもお父さんももともと問題のある人だった。病気のあいだは忘れていられたそのことを、思い出した。お父さんはテレビの芸人から目を離さなかった。ちっとも笑えなかった。
翌日、夜九時を過ぎてもお母さんが家に帰ってこなかった。
近所のスーパーに買い物に行くとでかけて、五時間が経っていた。スーパーまでは徒歩二十分の距離だ。お父さんは家にご飯が用意されていないことに腹を立ててひとりで外食に行ってしまい、わたしだけでお母さんを探しに行くことになった。アパートの自転車置き場をのぞいてみると、わたしの自転車がなくなっていた。お母さんが乗っていったのだろうか。
スーパーまでの道を歩き出す。途中のコンビニまでの道には点々と街灯がある。街灯には虫の死骸がこびりついていた。子どものころ空き地だった場所は新興住宅地になっている。小さな神社を通り過ぎて、信号を渡った場所にはラブホテルがあった。最寄りのスーパーまではあと一キロほどだ。ラブホテルはよく聞くお城みたいな外観じゃなかった。灰色と薄ピンクの武骨な建物で、あちこちにひびが入っている。サービスタイムの
利用案内の看板が信号機の陰に隠れるようにあった。十八歳未満のご利用はご遠慮いただいています。その看板の下に、お母さんはいた。傍らに自転車が横倒しになっているのが見えた。たったいま倒れたかのような横座りでお母さんは泣いていた。
「なにしてんの」
息が白く凍る。しゃがみこむ。お母さんが倒れているのは道路わきの芝生の上だった。人工的な芝生には霜が降りている。着古したスウェットがじっとりと濡れているのが見えた。お母さんが泣きまねをする。まねなのか本当に泣いているのかは、判断がつかなかった。
「起き上がれんくなったあ」
両手をのばしてくる。わたしはその手を、しっかりとつかんだ。お母さんの手には泥がついていて、ひどく冷たかった。黄色のジャンパーの裾が茶色く汚れている。スウェットの膝の部分には血がにじんでいた。助け起こそうとするが、手を引っ張るだけでは立ち上がれない。介助をしていたときのように、脇の下から背中に腕を回した。
「お母さん、治ったんじゃないの」
「治ってない、薬で症状が抑えられてるだけ」
「それ治ってるやん」
「ちがうって、この病気は死ぬまでつきあう病気なの」
「症状がないんでしょ? 治ってるやん」
「でも今日転んだし」
「お母さん病気じゃなくてもこけるやん」
「病気やもん、病気やから転んだんやもん」
お母さんの足はずっと震えている。もうそれが寒さのせいなのか病気のせいなのか、わたしにはわからない。
お母さんは病気になる前から、持病があるわけでもないのに毎週病院に行っていた。清掃のパートで動作が遅いと毎回怒られると愚痴って、しばしば泣いた。頭痛と
抱き合うようにして立ち上がらせる。お母さんが事情を説明しはじめるけれど、ぜんぶが耳をすり抜けていった。自転車は置いていくことにした。肩を組むようにして歩き出す。ラブホテルのピンクのライトが煌々と灯っていた。
お父さん、この姿を撮ってくれないかなと、ふいに思った。飽き性なお父さんの性格を考えると、十万円のカメラが今後役に立つ機会はそう多くないだろうし。
「月十万あったらさあ、わたしも修学旅行いけてさあ、お母さんも施設入れるんよな」
障害年金がでたら、と夢想していたことだった。治っていないのなら入る選択もあるはずだ。お母さんは「施設は絶対入らんからね」と意固地になった。
「入ってよ」
「入らん」
「入れや」
「やだ」
「なんで」
「さっちゃんがおらんやん。ほかの人におしっこ拭かれるなんてやだ」
「わたしも拭きたくないって」
「やだやだやだ。一生さっちゃんに拭いてもらうんだもん」
「垂れ流しとけ」
ラブホテルからカップルが出てきて、わたしたちを避けるようにして追い越していった。お母さんがわたしの腕を強くつかむ。
わたしは心底、お母さんの体の重さに打ちのめされていた。
*
その日は、修学旅行の振り替えで午後は休みになり、昼に下校できた。
修学旅行は来週に迫っていたけれど、積立金を払っていないわたしは行けない。お母さんにそれとなくお願いしてみたこともあったけれど、「夜、さっちゃんがいないと起き上がれるか不安だから行かないで」とグズられて終わった。クラスの浮かれた雰囲気になじめないまま、わたしは半ドンの日もそそくさと帰路についた。
お母さんに、おむつ代わりの吸水パッドを買ってきてと頼まれていた。お母さんは転んだ日以来、極端に動きたがらなくなった。医者にリハビリとして歩きなさいと言われても散歩すらしない。かと思えば「少しは歩かないと体力落ちるから」と夜中に突然アパートの廊下を往復しはじめることもあった。階段を使わないタイプのダイエッターと同じだ。
ドラッグストアで吸水パッドを黒いビニール袋に入れて渡される。店を出た。比較的暖かい日だった。春が近づいている。透き通った光に目を細めたとき、自転車置き場の隣の喫煙スペースで煙草を吸う男性と目が合った。
「うわっ」
思わず声がでた。相手もこちらに気づく。カッターシャツにジャージを羽織った男性。佐藤先生だった。ついてない。うちの高校では登下校時の買い物が禁止されているのだ。コンビニも飲食店もドラッグストアもダメ。理由はよく知らない。探り合うような空気が流れる。
「煙草バレたら教頭に嫌味言われるからさ、黙っててくれない?」
先に口を開いたのは佐藤先生だった。その意外な言葉に、わたしは急いで首を縦に振った。
佐藤先生が眉間にしわを寄せて、斜め上を向く。ふーっと吐き出す。人が煙草を吸っている姿を見るのは好きだった。お父さんの煙草は許せないけど他人なら許せる。
「共犯な」
佐藤先生が口の前に人差し指を立てるのを見て、見逃してくれるらしい、と安堵した。自転車の籠にスクールバッグをいれる。教科書や資料集が詰まったバッグは重い。鍵をさしてそのまま帰ろうとしたら、声をかけられた。
「修学旅行、積立金がなくても行けるかもしれないんだ」
わたしはグラついた自転車を持て余して、スタンドは立てたまま、サドルにまたがった。自転車にはお母さんが転んだときの泥がまだついている。佐藤先生のほうを見た。彼はわたしの顔を見ていた。
「あまりお金がない生徒のために、三月末まで
スタンドを立てたまま自転車を漕いだ。車輪の回る音がする。電気を起こすときにやるやつだ。この自転車はどこにもつながっていないから、非生産的な行為だった。先生が、停められているバイクによりかかった。
「修学旅行のことも、しょうがないってすんなり納得しちゃっただろ。もっと相談していいんだよ。
「先生に相談してもなんにも変わんないですよね?」
ブレーキを握る。古い自転車は
「……たしかにおれは実際に介助を手伝うとかはできない。でも例えば進学先の大学に配慮してもらえるように言うとか、国の補助制度を調べてみるとかはできる。いまは介護する子どもに対する支援団体もあるし、スクールカウンセラーの先生ともう一回話してもいい。もっと大人に頼っていいんだよ。諦めないでほしい」
いまにも手を握ってきそうなくらいの熱弁だった。佐藤先生はわたしの担任になってすぐ、親の衛生観念がおかしいこととか、お昼ご飯を買うお金をもらえないとか、わたしの困りごとを察知して声をかけてくれた。スクールカウンセラーにつないでもらったこともあるし、奨学金を紹介してもらったこともある。真面目な先生だ。
結局、カウンセリングは今年に入ってスクールカウンセラーが非常勤の人に代わって行かなくなった。奨学金は「借金だ、恥ずかしい、おれが苦労させていると思われるじゃないか」の三拍子でお父さんに許してもらえなかった。なにも解決しなかったじゃないかと佐藤先生を責めたいわけじゃない。佐藤先生のやさしさは本当だって、わかっている。でも。
わたしは佐藤先生に笑いかけた。
「お母さんの病気、治ったんです」
タイヤをゆるく回して、ブレーキを握る。甲高い音がする。悲鳴みたいな音。
「いや、難病やから、死ぬまでつきあっていくことに変わりはないんですけど、薬が効いて日常生活に支障がなくなったんです。病院の先生は働くこともできますって言うくらい。もう、介護も家事もしなくていい。障害年金ももらえるから、いままでみたいな貧乏もせんでいい、ってなったんです。すごいじゃないですか。ぜんぶ解決ハッピーエンドじゃないですか」
でもね、先生。そうつないだ言葉が自分で思っていたよりも湿っぽく響いて、わたしはちょっと動揺しながら続ける。
「わたし、なんでやろ。いまのがずっと、苦しいんです」
お母さんは先週もひとりで出かけて転んで怪我をつくってわたしにそれを見せびらかした。わざとじゃないかと思うくらい、ずるむけの傷だった。腕と足には青あざがいくつもついていた。大人になるほど人間は怪我をしないんだと思っていたのに。大きい
昨晩、お母さんはわたしが勉強している横で「話そうよお」と子どもっぽく口をとがらせて、何時間も何時間もお父さんやわたしの悪口を言った。お父さんと結婚しなければ。わたしを産まなければ。お父さんの散財癖がなければ。お母さんの口から出てくるのはわたしがこの十七年間ずっと聞かされ続けていたことだった。お母さんは家計簿をぐるぐる塗りつぶしていた。ボールペンで。家計簿は真っ黒なページばかりだった。わたしはそれを見るたびに胸が苦しくなった。ごめんと謝ると、あんたが謝ったってどうしようもなかやろ、とお母さんは馬鹿にするみたいに言った。
「修学旅行は行けません。うち、貧乏やもん」
わたしはブレーキから手を放して隣を見た。佐藤先生は再びバイクにもたれかかってわたしを見ていた。薄い笑顔だった。口角が上がって、目が細くなって。佐藤先生はたぶん自分が笑ってるってことに気づいていない。
去年の担任の先生もスクールカウンセラーの先生も、笑っていた。薄い、安心していいんだよみたいな微笑み。辛いってこぼしたとき、人はなぜか、たいていこの表情をする。
佐藤先生はたぶんたくさん勉強してくれた。助けようとしてくれた。安心して。辛かったでしょ。話していいんだよ。大人を頼って。そんな言葉をたくさんかけてくれた。でも、この人は親の代わりに修学旅行のお金を出してくれるわけじゃない。うちに来て、母のおしっこを拭いてくれるわけじゃない。話して楽になるなら、こんなにややこしくはなっていなかった。
佐藤先生は黙ったままだった。わたしは自転車のスタンドを倒して、ベルをりんと一回鳴らした。バッグの位置を調整して、転ばないようにこぎだす。自転車はタイヤがパンクしている。
「さっちゃん、あのね、あのね、今日一人で病院行ってねえ」
お母さんの背中はわたしの背中よりちょっと広い。お母さんが話しだしてもわたしは返事をしなかった。
時計は夜の十時を指していた。修学旅行の当日。みんなは沖縄で枕投げでもしている時間帯だった。お父さんはまだ帰ってきておらず、わたしは外食して帰ってきたばかりだ。帰宅すると、お母さんがうたた寝して起き上がれないと布団でもがいていて、トイレに行きたいというので介助をするハメになった。完治したわけじゃないから、たまに介護をしなければいけないことがあった。
背中合わせのままお母さんとわたしで腕を組みあう。体育のときにやった立ち上がり方だった。せーの、と声をかけてわたしが必死に立ち上がらせようとするのに、お母さんは声をそろえようともしなかった。
お母さんは唐突に言った。
「
はあ? と声が出たのか、嘘やんとツッコんだのか。どちらかわからないと思ったけど、どちらもしていなかった。脱力して言葉が出てこなかった。
腫瘍は良性か悪性かまだわからないんやけどね、これから入院して検査する必要があってね。悪性やったら手術せんといけんらしい。怖かあ。お母さんの全然怖いと思っていなさそうな声が耳を抜けていく。
「ほら、あの転んだやつも病気の症状やったんよ。脳腫瘍があると、歩けなくなったり片方の手足が
勝ち誇ったような声だった。気づいたら胸を押さえていた。体を貫くみたいに痛みがあった。背中にあるお母さんの重さ。目の前がゆっくりと暗くなっていくような感覚があった。なんでやねんって明るくツッコめたらいいんだってわかっていた。難病の次は脳腫瘍かいって。お前なんで嬉しそうに言ってんねんって。コントみたいに。できなかった。気が塞いでいく。息が浅くなる。
なにも考えたくなくて、とりあえずお母さんを立ち上がらせようと、背中に体重をかけた。人という文字は人と人とが支え合ってできているのですの形だ。全然立ちあがれない。お母さんの踏んばる力が弱すぎるらしかった。支え合うって、片方だけがなんとかしようとしてもできないものだ。
後ろから抱えあげることにした。後ろから手を脇の下に差しこんで持ち上げると、猫がだらっと伸びるみたいに、お母さんもだらっと伸びた。人体はときどき液体みたいな動きをする。お母さんが膝を立てようともがいているあいだに腕が重さに耐えきれなくなった。べしょっとふたりとも潰れる。
「ちょっと! 支えとってよ!」お母さんに文句を言われる。
「支えてるって。お母さんこそちゃんと立って」
「立てないもん。トイレ漏れる」
「漏れるのはトイレじゃなくてうんこやろ」
「下品なこと言わないの。おしっこ!」
「どっちでもいいし」
「さっちゃん、はやくー」
「もうひとりで行ってよ……」
お母さんがひとりで立ってトイレに行けるなら、わたしもお母さんもこんなに苦労はしていない。そうわかっていても、イライラが抑えられなかった。発病報告がまだ頭に残っていた。
次は正面から試す。正座から前傾姿勢、四つん這いになって立ちあがる方法。のろまな動きだが四つん這いになるところまではいけた。声をかけながら片方ずつ足を布団につける。壁に手をついてもらって、壁を伝うように立ち上がらせる。十分ほどかけてようやく立ち上がったころには、冬なのに汗みずくになっていた。お母さんの肩を横から支える。
「壁から手ぇ離して。大丈夫? 行くよ」
声をかけながら一歩踏み出した。魚の腐ったような匂いがして、思わず顔を逸らす。口が臭い。お母さんは
顔を逸らした拍子に支える手の力が緩んで、一歩目でお母さんがバランスを崩した。もう片方の手をのばす。届かない。支えようとした腕が体重を支え切れない。肩を組む体勢のまま、わたしもお母さんも、仰向けに倒れこんだ。
お母さんは目覚まし時計でしたたかに頭を打ったようだ。狭いワンルームで二人が倒れたものだから、
一目見て、あっ、と気づく。家族に隠していた、わたしのBL本たちをいれた段ボールだった。焦って、お母さんにバレるまえにどかそうとするが、健康器具が重くて動けない。
「もれ、もれる」
段ボールの下から、呂律の回らない声がした。お母さんが動いた拍子にBL本たちが段ボールからどさどさとでてくる。半裸の男同士が絡み合っている表紙が見えて、わたしは絶望で目の前が真っ暗になっていく感覚がした。床に倒れたまま、急に虚無になる。蓄積された「しんどい」がぜんぶ降りかかってきて、退いてくれない。意味もなく泣いてしまいそうになった。
そのとき、布団の上に放置されていたリモコンにBL本の一冊が当たったらしく、パッとテレビがついた。頭が痛くなるくらい大きい音が頭上から降ってきて、とっさに耳を塞ぐ。お母さんがリモコンに手を伸ばすのが見えた。届かない。顔をあげる。隣でお母さんもテレビのほうを見たのが、なんとなくわかった。
小島よしおが『でもそんなの関係ねえ!』と海パン一丁で叫んでいた。
ブワッ、と。その瞬間に起こった感情はどうにも表現できない。小島よしおの声だけが流れる部屋でお母さんと目を合わせた。目やにだらけの目。一瞬の沈黙。体の力が抜けた。笑いが出てきた。口が知らぬうちに大きく開いている。体の内側からでてくる笑いを抑えきれない。肩が震える。テレビの中の観客の笑い声よりも大きい声が出てくる。
隣を見るとお母さんも笑っていた。最近は病気で表情の乏しいお母さんしか見たことがなかった。ああ、こういう笑い方もする人だった、と思う。あははと腹の底から声が出ていた。笑い声の合間に「もれ、もれた」という言葉が挟まる。アンモニア臭が部屋に充満する。段ボールの下から湯気が立ち上るのが見える。わたしの布団にもおしっこが沁みてくる。
『でもそんなの関係ねえ!』
健康器具の下敷きになったまま、また笑う。笑い上戸の酒飲みになったみたいに、すべての事象に笑った。わたしのBL本たちがお母さんのおしっこでふやけている。
『はい、オッパッピー!』
顔をあげる。テレビ画面の明るさにめまいがする。夜のバラエティ。一発屋傑作選。小島よしおでいまこんなに本気で笑ってるの、きっと、わたしたちだけだ。
ピンポーンと玄関チャイムが鳴った。さっちゃーんと叫ぶ声がする。お父さんの声だった。まだ鍵は見つかっていないらしい。健康器具を無理やり体からどける。足が
「さっちゃん、カメラ買うてきた!」
勢いこんで言われる。手にはビックカメラの紙袋があった。
「こないだ怒ってたから。二人のぶんも同じやつ買ってきたんよ」
わたしは立ち尽くしたまま、体の力が抜けていくのを感じた。玄関の壁によりかかり、ずるずると座り込む。お父さんがわたしに袋を押しつけて部屋にあがる。受け取った袋はどっしりと重い。中をのぞきこむと十万のカメラのセットが入っていた。お父さんのカメラと合わせて合計二十万。ははは。
お父さんが部屋を見て、「はあ? なんこれ」と
「リモコン壊れた」
お母さんは布団にリモコンをぶつけながらこちらを振り向いた。そして、お父さんを目に映したその瞬間に、
「あ、おかえり! 今日病院行ってね、脳腫瘍が見つかったの!」
と満面の笑みで言った。隣でお父さんが「はあ?」とバカでかい声を出す。
「ほらあ、あたしがおかしかったんじゃないでしょ」
続けられたお母さんの言葉に、わたしは今度こそぶっと吹きだしてしまった。
「嬉しそうに言うな」
「また病気なったんか」
わたしとお父さんが同時にツッコむ。
「まず心配してよ」
お母さんがむくれて言った。ふ、ふ、と同時に息を漏らして、三人で声を立てて笑った。窓の外がぱあっと一瞬明るくなった。テールランプの赤が窓を照らして、すぐに消える。
お父さんは部屋でなにが起こったのかを聞きたがったけど、先にお母さんをどうにかしてと押しつけた。お父さんが軽々とお母さんを抱えあげてユニットバスに連れていく。車の走行音がまだ聞こえている。襖は破れ、部屋には段ボールと健康器具とBL本が散らばっていた。テレビの音量は上がったままだ。お母さんの布団には漏らしたシミが広がっている。青い点がいくつか散っていた。鮮やかな色。ブルーレット詰め替え用の液を散らしたみたい。
わたしは部屋の入り口でそれを眺めた。ふふ。小さく漏らす。服が乱暴に洗濯機に入れられたときのボタンがぶつかる音が聞こえる。
「さっちゃんが寝てから、ね」
薄い壁越しに、お母さんが甘えた声を出すのが聞こえた。
「いま」
「あとで」
「いまがよか」
「聞こえるからダメだって」
風呂場での会話に聞き耳を立てていると、テレビがCMに切り替わった。
林修が『いつやるか? 今でしょ!』とドヤ顔で言う。
奇跡じゃん! とわたしは思わず爆笑した。両親に聞こえないよう、自分の布団にもぐって毛布を二枚ひっかぶった。布団の中で笑いを必死にこらえる。なんでこんな小さなミラクルにちょっと救われたような気になっているのか、自分でもわからない。現実はなにも変わっていない。でも、この笑いだけは、手放しちゃいけないとわかっていた。
真っ暗な視界の中で、あの青い点がまだ鮮やかだ。肉体が壁にぶつかるような音がする。制止の声はもう聞こえてこない。笑いの波はまだ収まっていない。テレビはもう次の番組に移り変わっている。だれかの笑い声が聞こえる。