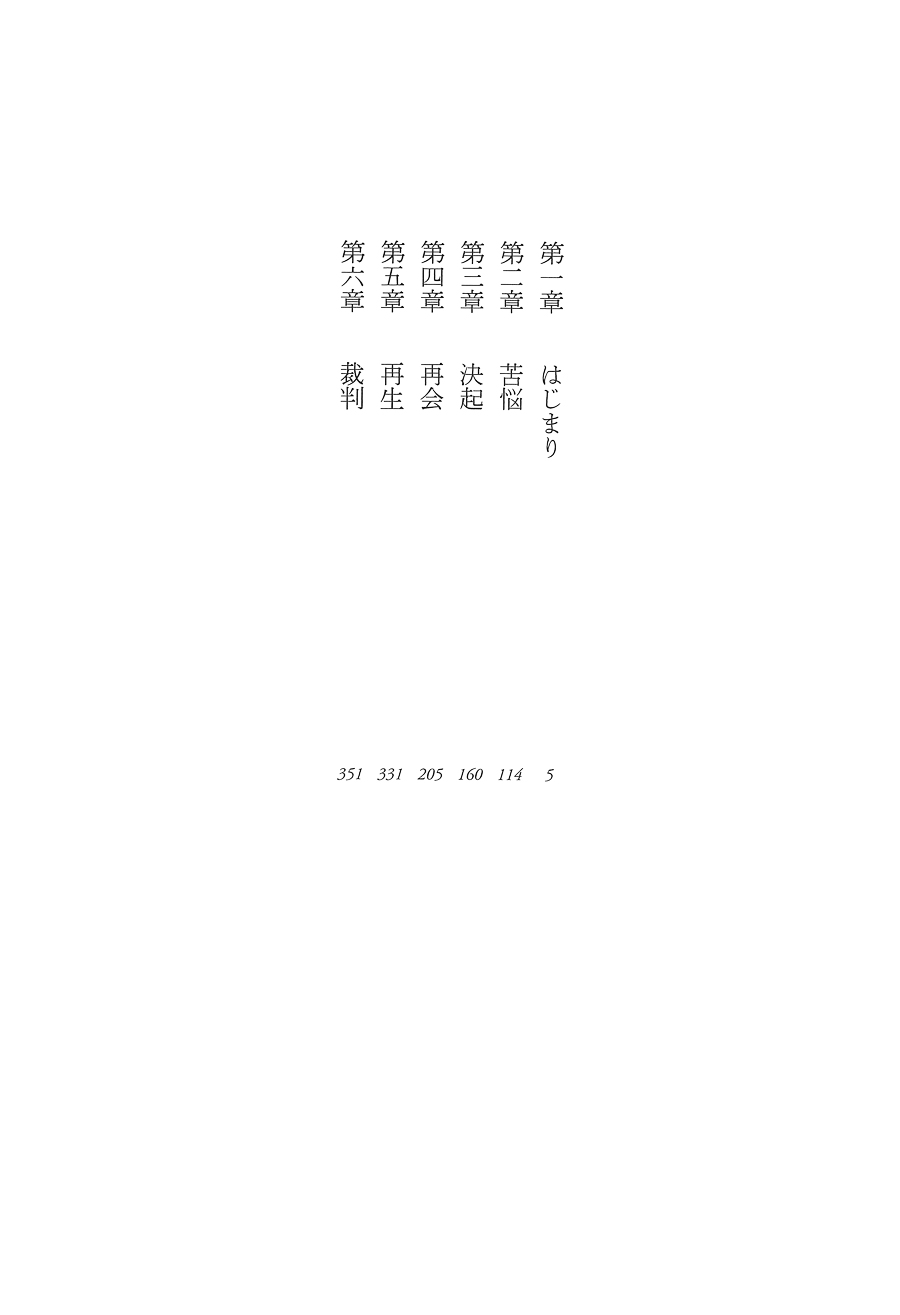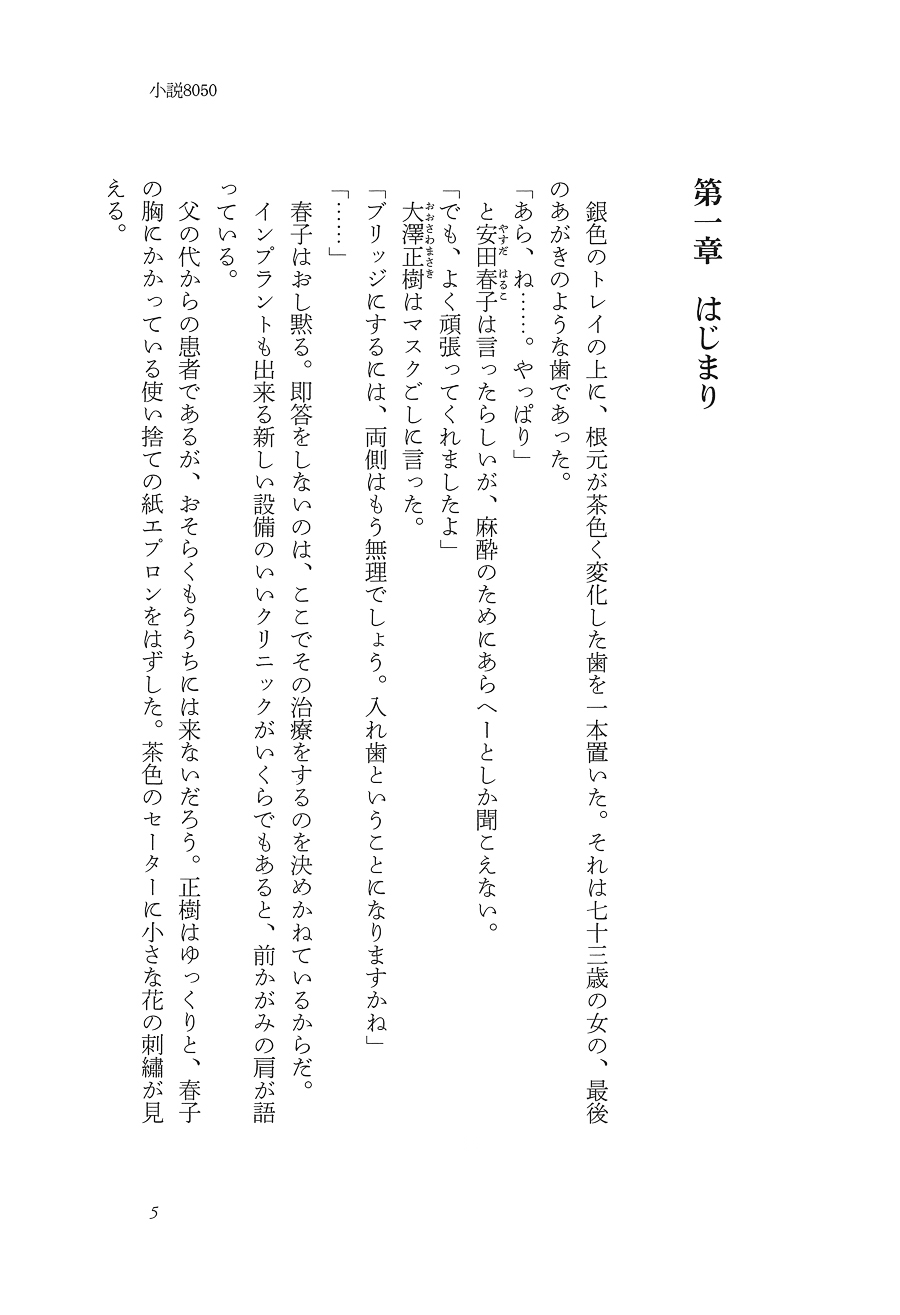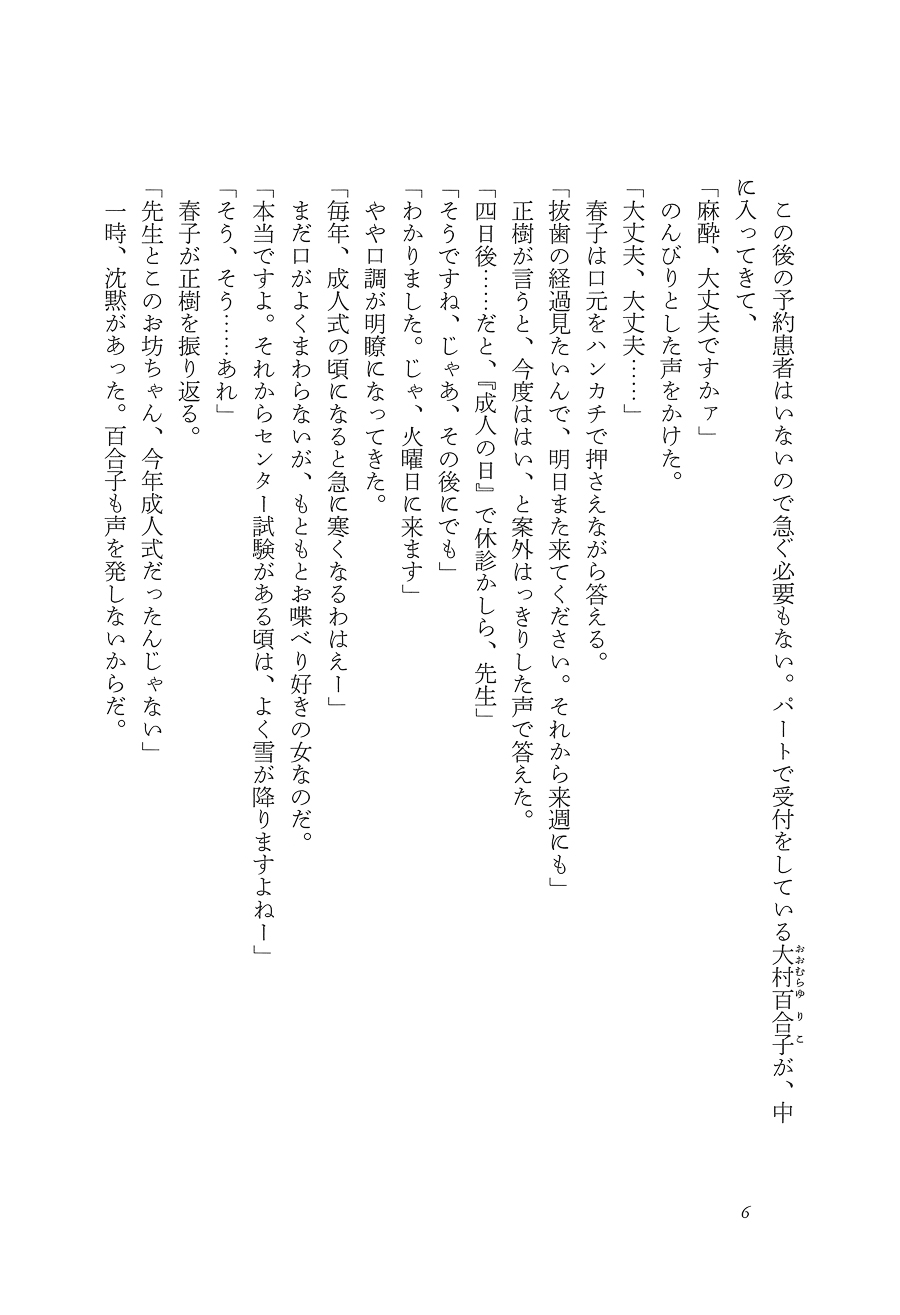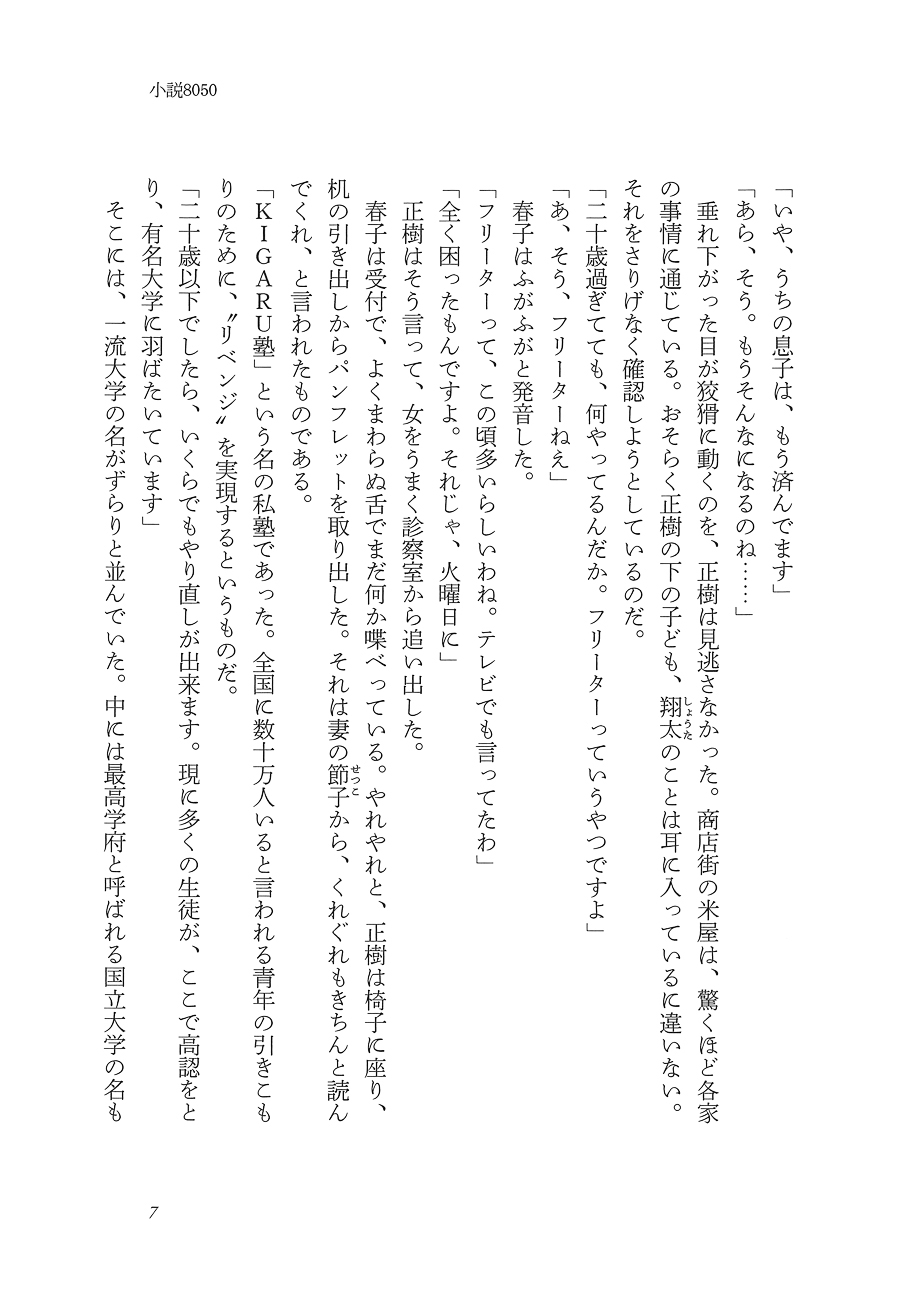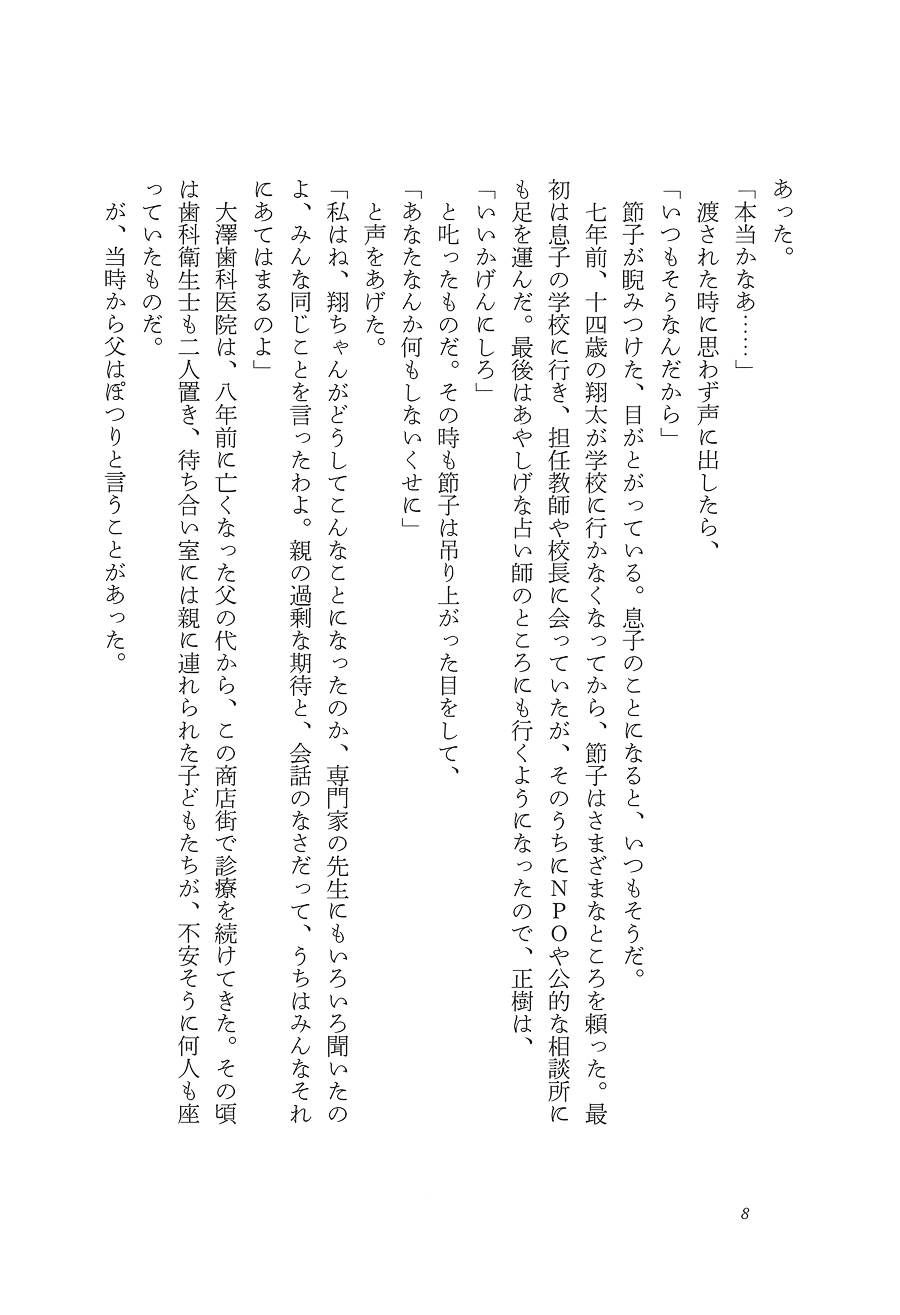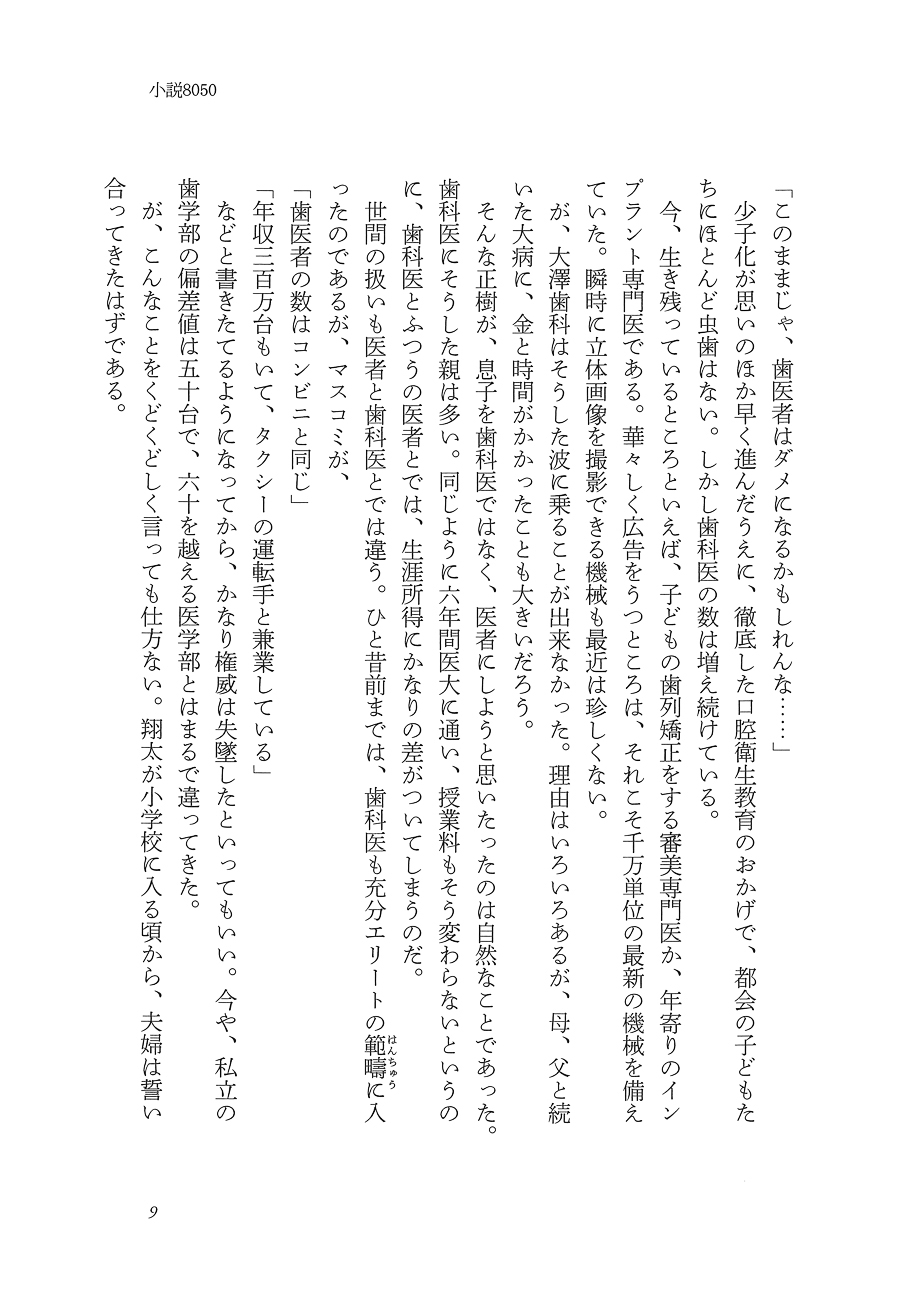第一章 はじまり
銀色のトレイの上に、根元が茶色く変化した歯を一本置いた。それは七十三歳の女の、最後のあがきのような歯であった。
「あら、ね……。やっぱり」
と
「でも、よく頑張ってくれましたよ」
「ブリッジにするには、両側はもう無理でしょう。入れ歯ということになりますかね」
「……」
春子はおし黙る。即答をしないのは、ここでその治療をするのを決めかねているからだ。
インプラントも出来る新しい設備のいいクリニックがいくらでもあると、前かがみの肩が語っている。
父の代からの患者であるが、おそらくもううちには来ないだろう。正樹はゆっくりと、春子の胸にかかっている使い捨ての紙エプロンをはずした。茶色のセーターに小さな花の刺繍が見える。
この後の予約患者はいないので急ぐ必要もない。パートで受付をしている
「麻酔、大丈夫ですかァ」
のんびりとした声をかけた。
「大丈夫、大丈夫……」
春子は口元をハンカチで押さえながら答える。
「抜歯の経過見たいんで、明日また来てください。それから来週にも」
正樹が言うと、今度ははい、と案外はっきりした声で答えた。
「四日後……だと、『成人の日』で休診かしら、先生」
「そうですね、じゃあ、その後にでも」
「わかりました。じゃ、火曜日に来ます」
やや口調が明瞭になってきた。
「毎年、成人式の頃になると急に寒くなるわはえー」
まだ口がよくまわらないが、もともとお喋べり好きの女なのだ。
「本当ですよ。それからセンター試験がある頃は、よく雪が降りますよねー」
「そう、そう……あれ」
春子が正樹を振り返る。
「先生とこのお坊ちゃん、今年成人式だったんじゃない」
一時、沈黙があった。百合子も声を発しないからだ。
「いや、うちの息子は、もう済んでます」
「あら、そう。もうそんなになるのね……」
垂れ下がった目が狡猾に動くのを、正樹は見逃さなかった。商店街の米屋は、驚くほど各家の事情に通じている。おそらく正樹の下の子ども、
「二十歳過ぎてても、何やってるんだか。フリーターっていうやつですよ」
「あ、そう、フリーターねえ」
春子はふがふがと発音した。
「フリーターって、この頃多いらしいわね。テレビでも言ってたわ」
「全く困ったもんですよ。それじゃ、火曜日に」
正樹はそう言って、女をうまく診察室から追い出した。
春子は受付で、よくまわらぬ舌でまだ何か喋べっている。やれやれと、正樹は椅子に座り、机の引き出しからパンフレットを取り出した。それは妻の
「KIGARU塾」という名の私塾であった。全国に数十万人いると言われる青年の引きこもりのために、“リベンジ”を実現するというものだ。
「二十歳以下でしたら、いくらでもやり直しが出来ます。現に多くの生徒が、ここで高認をとり、有名大学に羽ばたいています」
そこには、一流大学の名がずらりと並んでいた。中には最高学府と呼ばれる国立大学の名もあった。
「本当かなあ……」
渡された時に思わず声に出したら、
「いつもそうなんだから」
節子が睨みつけた、目がとがっている。息子のことになると、いつもそうだ。
七年前、十四歳の翔太が学校に行かなくなってから、節子はさまざまなところを頼った。最初は息子の学校に行き、担任教師や校長に会っていたが、そのうちにNPOや公的な相談所にも足を運んだ。最後はあやしげな占い師のところにも行くようになったので、正樹は、
「いいかげんにしろ」
と叱ったものだ。その時も節子は吊り上がった目をして、
「あなたなんか何もしないくせに」
と声をあげた。
「私はね、翔ちゃんがどうしてこんなことになったのか、専門家の先生にもいろいろ聞いたのよ、みんな同じことを言ったわよ。親の過剰な期待と、会話のなさだって、うちはみんなそれにあてはまるのよ」
大澤歯科医院は、八年前に亡くなった父の代から、この商店街で診療を続けてきた。その頃は歯科衛生士も二人置き、待ち合い室には親に連れられた子どもたちが、不安そうに何人も座っていたものだ。
が、当時から父はぽつりと言うことがあった。
「このままじゃ、歯医者はダメになるかもしれんな……」
少子化が思いのほか早く進んだうえに、徹底した口腔衛生教育のおかげで、都会の子どもたちにほとんど虫歯はない。しかし歯科医の数は増え続けている。
今、生き残っているところといえば、子どもの歯列矯正をする審美専門医か、年寄りのインプラント専門医である。華々しく広告をうつところは、それこそ千万単位の最新の機械を備えていた。瞬時に立体画像を撮影できる機械も最近は珍しくない。
が、大澤歯科はそうした波に乗ることが出来なかった。理由はいろいろあるが、母、父と続いた大病に、金と時間がかかったことも大きいだろう。
そんな正樹が、息子を歯科医ではなく、医者にしようと思いたったのは自然なことであった。歯科医にそうした親は多い。同じように六年間医大に通い、授業料もそう変わらないというのに、歯科医とふつうの医者とでは、生涯所得にかなりの差がついてしまうのだ。
世間の扱いも医者と歯科医とでは違う。ひと昔前までは、歯科医も充分エリートの
「歯医者の数はコンビニと同じ」
「年収三百万台もいて、タクシーの運転手と兼業している」
などと書きたてるようになってから、かなり権威は失墜したといってもいい。今や、私立の歯学部の偏差値は五十台で、六十を越える医学部とはまるで違ってきた。
が、こんなことをくどくどしく言っても仕方ない。翔太が小学校に入る頃から、夫婦は誓い合ってきたはずである。
「この子は医者にしよう。歯学部ではなく医学部に入れよう」
幸いなことに父の代からの蓄えで、診療所を兼ねたこの家とは別に、投資用のマンションをひと部屋、優良な株と定期預金は持っていた。定期の方はかなりさみしいことになっていたが、整理すれば、私立の医学部に行かせるのもそうむずかしいことはないというのが、夫婦の出した結論であった。
その頃翔太よりも五つ齢上の
「この年から努力するというのは大切なことなんだ。努力はクセになるからな」
と正樹は言い、翔太にも中学受験を勧めた。
「でも男の子なんだから、中学までは公立でいいんじゃないかしら。翔ちゃんは友だちと別れるの嫌がっているし」
と抗う妻を馬鹿と叱った。
「男の子だからこそ中高一貫校に入れなきゃ駄目なんだ。中学で気づいても遅い。名門と言われるところは、高校から入るのは至難の業だ。ほとんどとっていない」
妻に自分で集めてきたパンフレットを見せる。確かに最近、中高一貫校は、高校からの募集を減らしていた。
「由依もそうだが、いい学校で出会う友だちは一生の友だちだ。地元の公立の子どもたちとはレベルが違うんだ」
そういう正樹も私立の中高一貫を出ていたが、母校に息子を入れるつもりはまるでない。昔は新御三家の次ぐらいにランクされていた学校であったが、経営陣のごたごたと私鉄乗り入れで劇的に偏差値を落としていた。私鉄開通と偏差値とは驚くほどかかわりがあり、駅が出来た代わりにその地区の子どもたちが都心をめざすようになったと、当時ある週刊誌が書きたてたものだ。
だからこそ昔からの、名の通った学校、鉄道などに影響されない学校をめざさなければいけないと正樹は説いた。
「医者になるんだったら、十歳から始めるんだ。そのくらいから始めてちょうどいいんだ」
いつしか正樹の気迫は妻にも伝わり、節子も息子の受験に協力するようになった。いや、協力などという生やさしい言葉ではない。そもそも中学受験は母親が中心となり、子どもに徹底的に尽くす。
節子は本当によくやっていた。夕方になると夕食の他に弁当をつくり塾に届けた。雨の日も雪の日もだ。コンビニ弁当など絶対に食べさせない。自転車で届けるが、時々は正樹が車で送ってやった。
冬の寒い日、塾から出てきた妻にこう声をかけたものだ。
「親のこういう苦労を子どもはちゃんと見ているさ。いつか本当に有難かったって思うはずだよ」
やがて受験が始まった。夫婦は近くの神社に詣でて、正樹は一ヶ月酒を断った。そしてめでたく翔太は、第二志望の中高一貫校に合格した。それは夫妻にさらに新しい、はるかに大きな苦労を課すこととなったのである。

それは突然起こった。
中学二年生の夏休みが終わった時、翔太は、
「もう学校に行きたくない」
と言い出したのである。最初は夏の疲れだと思っていた。
「明日になれば、ケロッとして行くんじゃないの」
とのんびりと構えていた節子であったが、それが一週間となり、十日となった頃には本気で焦り始めた。正樹たちは、さっそく学校に出向く。そこで担任や校長と話し合った結論は、この学校にはいじめはない、というものであった。どうしてそんなことを言いきれるか、と質問する妻に、年に四回ほどのアンケート調査をする上に、相談室とカウンセラーを置き、生徒はいつでもそこに行けるようになっているというのだ。
「あの担任、まるでなってない。少しも親身になってくれない。っていうか、他人ごとみたいに喋べる」
節子は怒り、正樹とともに翔太と同じ小学校から進学した友人の家を訪ねたのだ。が、彼はクラスが違うのでよくわからないと答えた。
「僕よりも、仲のいい友人に聞いたらどうですか」
と言われ、節子は言葉に詰まった。翔太は家に中学の友人を連れてくることもなかったし、日曜日に誰かと遊ぶ約束をしたこともなかったのだ。
正樹は妻と共に、あらたまって息子に問うた。
「学校にはこのまま行かないつもりなのか」
その時、翔太ははっきりと答えた。
「もうあんなところに二度と行きたくない」
「翔ちゃん、あんた、いじめられたの? ひどいことされたの?」
妻の質問に、翔太は奥歯を喰いしばっている。その顔はまだ幼なく、正樹は公園で息子が姉に鉄棒の順番をとられた時の顔を思い出した。
「いったい誰がやったの? どんなことをされたの?」
と節子は金切り声をあげたが、もう翔太は何も答えなかった。
「とにかく、もう二度と、あいつらのいるところに行きたくはない」
「あいつら、って誰なの? 言いなさい。はっきり言うのよ!」
という母親の声は無視して、翔太は立ち上がった。
「とにかく僕は行かないよ。ママがもし――」
そこで言葉を区切った。
「もし僕を無理やり行かそうとするなら、僕はママを許さない。本当だよ」
あの時、節子は口をぽかんと開け、わなわなと体を震わせていたが、すぐに気が変わるだろうと、正樹はかなりタカをくくっていたところがある。それは息子をまだ幼ない者としてとらえてしまったからだ。
子どもにとって学校は絶対的なところだ。学校に行かなければ、子どもは世界を失なってしまう……。そう息子のことを考えていた自分は、なんと無知だったのだろうかと、正樹は後悔している。
七年前も、“引きこもり”はとうに社会問題になっていたではないか。それなのに自分は心の中で、うちは違う、と考えていたのである。
それからいろんなことがあった。夫婦二人で、叱責し、懇願し、
「とにかく学校に行って
と頭を下げたこともあった。

その後、妻は妻なりにいろいろな事を考えたのである。正樹が翔太を連れて子どものメンタルを専門にしている、精神科医のところに話を聞きに行った。都の相談窓口も訪れ、カウンセラーという人物がうちにやってきたこともある。ちょうど中学卒業時で、彼は通信制や単位制の高校を勧めてくれた。
「いちばんつらいのはお子さんなんですよ」
彼は言ったものだ。
「何とかして、この状況から逃れたいともがいているはずです。ほんの少しのきっかけで、立ち直る例はいくらでもあります」
そうよ、そうよと、つぶやく節子はあの頃、何冊もの本を読んでいた。妻がいちばん感動したのは、十年にわたる引きこもりの青年が、一人の教師と出会ったことで、新しい人生をつかむというものだ。青年は努力して高卒認定試験に合格した後、獣医をめざして大学に入学した。
「いくつになってもリベンジは出来ます」
という言葉と共に、さわやかな風貌の青年の写真があった。それは節子がこうあってほしいと望む未来の息子の姿であった。
「こういう人はいくらでもいるのよ。そう、いくらでもね。うちの翔ちゃんだって、やり直すことが出来るのよ」
正樹は否定しなかった。そう信じることが妻の唯一の希望であることがわかっていたからだ。
しかし十五歳の翔太は、高校受験にまるで興味を示さなかったのである。それどころか、昼夜を逆転させた生活を始めるようになった。夜の十二時過ぎ、家族が寝静まった頃起きてくる。そして冷蔵庫の中から麦茶や牛乳を出して飲み、節子のつくっておいた食事をむしゃむしゃ食べる。風呂に入る、洗濯をする、そしてまた自分の部屋に戻り、パソコンであれこれ見たり、ゲームをする。家族が起き出す頃には息を潜め、トイレに行く時以外はまず出てこない。昼過ぎに節子が、簡単な食べ物をのせた盆を置いておく。それを食べて夕方眠りにつくらしい。つくらしいというのは、部屋の中での生活を家族の誰もが把握していないからだ。
「お前はいつからネズミになったんだ!」
最初はあまりのことに、正樹は息子を殴ったこともある。力ずくで部屋からひき出そうとしたことも一度や二度ではない。そのたびに節子は泣いて止めた。その妻に向かって、
「お前の育て方がいけないんだ。まともな人間に育てられなかったお前がいけない」
と怒鳴ったことは、今では悔いている。
その後で、節子が心療内科に通い出したと聞いたからだ。
「このままだと、ママ壊れちゃうよ。それでもいいの」
と由依は冷たく言いはなった。由依は中高一貫の女子校を出た後、現役で早稲田の政経に入った。この優秀な娘の存在は、どれほど夫婦の救いになっていただろうか。しかし今回、この由依が大澤家に大きな変革を求めたのである。

妻の節子が、診察室のドアを開けた。
「
坂本家は、この大澤歯科医院からツーブロック先にある、四十坪の土地に立つ木造の二階家だ。
小さな商店街と住宅地が隣り合わせにあるこの界隈は、山の手とはいえないが、昔は中程度の勤め人が住んでいた。世田谷の一等地と比べると、ここいらはほどほどの地価だったと年寄りは言う。
このところ、高齢化が進み、いくつかの空き家が出来た。商店街の空き家は、すぐに牛丼のチェーン店や、スマホショップになる。住宅の方は、大きなうちはマンションに変わり、小さなうちは駐車場になるか、そのまま古びていく。
「あのうちは、残された奥さんが施設に入ったのよ、それであのままになっているのよ」
節子から聞いたことがある。死亡すれば、誰かが相続するなど動きがあるが、生きていればそれも出来ない。九十歳、百歳になり、たとえ家のことは忘れていても、法律上は所有者なのだ。
坂本家はそうした家の一軒であった。夫の方はとうに亡くなり、妻の方がひとり息子と暮らしていた。正樹はこの妻の方の、入れ歯をつくったことがある。あれが十年前であった。姿が見えなくなったと思ったら施設に入ったと聞いたのが数年前、そして昨年は亡くなったという知らせが届いた。葬儀は近くの斎場で行なわれ、節子が焼香をしてきた。
「喪主は息子さんだったけど、結婚も就職もしていないんだって。ひとりでいたわ」
節子はこういうところに、とてもよく気のつく女だ。
「親戚も少なくて、とても寂しいお葬式だったわね」
「仕方ないさ、都会の葬式なんてそんなもんだよ」
「やっぱり、おじいちゃん、おばあちゃんのお葬式って、孫がちょろちょろしていて、こらっ、なんて怒られて、にぎやかなのがいいわよねー」
節子は栃木の出身である。正樹は妻の身内の、幾つかの葬式を思い出した。確かに近所の人たちに加え、小学生や幼児の孫が行儀悪くあちこち走りまわっていた。が、あれは確かにいい光景であった。新しい生命体はキラキラと光輝やいていて、死んでいったものの命を引き継いでいくのを、はっきりと見たような気がした。
「私たちも、あんな寂しいお葬式になるのかもしれないわね……」
と節子がつぶやいた。自分たちのうちのどちらかが死に、どちらかが老いさらばえた時に、結婚もせず仕事にもついていない翔太が喪主の席に座っている光景は、あまりにもリアルな想像であった。正樹はぞっと背筋が寒くなった。
「まあ、そんな先のことは考えないことだな。翔太はともかく、由依はまともな結婚をするはずだよ」
「そうね、そうだといいんだけど……」
妻がうかない顔をしたのは、この頃既に娘の相談を受けていたからに違いない。
そして今年の正月、久しぶりに帰ってきた娘から、結婚を考えている人がいると打ち明けられた、と妻は言った。
「それはよかったじゃないか」
正樹は単純に喜んだ。節子は美人の部類に入るが、由依は親のひいき目で見ても、中の中といったところだろう。翔太が母親そっくりの、端整で、涼し気な顔なのに比べ、娘は父親に似ている。多少エラが張っているのを、神経質過ぎるほど気にしていた。早稲田を卒業する時、アナウンサー試験をはなから諦めたのも、この顎の形が原因だと半ば本気で正樹を責めたことがある。
「まあ、いろいろあったけど、由依もやっとおさまるところにおさまるわけだ」
節子は由依の相手について、ぽつりぽつりと語り始めた。東京出身で、父親はさる商社の執行役員をしている。母方の祖父は長年参議院議員を務めた人物だという。
「家柄はわかったが、本人はどうなんだ」
「写真見せてもらったけど、まあ、感じのいいふつうの男の子、
「同じ会社のちゃんとした青年なら、何の問題もないじゃないか」
「問題があるのはこちらでしょう」
何もわかってないとばかりに、節子は声を荒らげた。
「由依は言ったわ。彼はひとりっ子だから、きっとうちのことをいろいろ調べるはずだ。もし引きこもりの弟がいるってわかったら、相手のうちに引かれてしまうって」
「馬鹿馬鹿しい!」
正樹も思わず荒い声を出す。
「今どき引きこもりなんて、珍しいことでもないだろう。翔太は別に犯罪をおかしたわけじゃない。ちょっとした人生の休憩をとっているだけなんだ」
それは自分自身に何度も繰り返した慰撫の言葉である。
「由依も姉だったら、もっと弟のことを思いやってやるのが本当だろう。胸を張って堂々と言えばいいじゃないか」
「そんなに簡単にいくはずがないじゃないの」
節子は正樹を睨むように見た。それとそっくりの二重瞼の目を持つ息子のことを思った。もう何年もきちんと正面から彼を見ていない。
「由依はちゃんと育って就職もしてくれて、だからちゃんとかまってやらなかった。翔ちゃんのことだけにかまけていて、私は本当に可哀想なことをしたと思ってるの。由依は今だからって打ち明けてくれたわ。大学生の時に、友だちをうちに連れてこれなくて、本当につらい思いをしたって。もし引きこもりの弟を見られたらどうしようって、そのことばっかり考えていたって」
「堂々としていればいいんだ、堂々と」
「そういうことが出来ないんですよ、年頃の女の子だから。だけどね、由依にもやっといい人が見つかって、結婚したいって言ってるんですよ。だから私は、なんとか由依の思いをかなえてあげたいんですよ」
なんと節子は泣いていた。そしてとり出したのが、例の「KIGARU塾」のパンフレットなのである。ぱらぱらとめくってみる。これによるとまずカウンセリングがあり、場合によっては精神科医も紹介してくれる。その後に学業復帰のプログラムが組まれる仕組みだ。
引きこもりのために、今や多くの高校が手をさし伸べてくれている、とプログラムには書いてあった。私立高校、通信制高校、単位制高校、そしてアーティストをめざす高校。目標を決め、決して焦らずに、進んでいくことが大切だ。そのために、生徒には個別のアドバイザーがつき、丁寧につき合っていく。この塾から、大学進学を果した生徒もとても多いという。進学先の大学名がずらりと並んでいた。
「この塾でまず知ってほしいのは、人生はやり直せるということです。若いあなた方には、いくらでもそれが出来るということ」
パンフレットの最初のページには、その文字があった。そして楽し気に談笑する数人の若者がいる。モデルだろうか、それとも本物の塾生なのだろうか、こんな風に顔をさらしても大丈夫なほど、彼らは自信をつけたということか。
「ちゃんとこれを読んでほしいの。とにかくこれは最後のチャンスなのよ」
節子はおごそかに宣言した。
「由依からくれぐれも頼まれているのよ。引きこもりだと、相手のうちに言えないけど、浪人中で塾に通ってます、そう言いたいんですって」

パトカーが来たので、近所の者たちが坂本家の前に集まってきた。何事かと、正樹と節子も外に出た。パトカーの他にも、トラックや軽ワゴン車が停まっており、黒いバンから、スーツを着た男が降りてきた。その後ろを二人の警官と十人ほどの男たちがついていく。
「そのうちはずっと空き家ですよ」
誰かが声をかけた。
「坂本のおばあちゃんも亡くなったし、息子さんの姿も、もう何ヶ月も見かけないけどなぁ、いったい何があったんですか」
「空き家荒しかな」
警官も男たちも何も答えない。門扉を開けて中に入っていく。ブロック塀の内側の庭は荒れていた。枯れた梅の木の下に、茶色の雑草がはびこっている。使いふるしたバケツやホースが、玄関の前に投げ出されていた。
「坂本さん、坂本さん」
スーツを着た男が大声をあげた。あたりはしんとする。
「何度もご連絡しましたが、返事をいただけませんでした、私は東京地裁の執行官です。民事執行法に基づき、これより強制執行に入ります。この家は坂本
物見高い近所の者たちもしんとしてしまった。近くでまさかこんなことが行なわれようとは想像もしなかったのだ。
「坂本さん、坂本さん、ドアを開けてください。中にいることはわかっているんですよ」
もう一人のスーツ姿の男が言う。襟には弁護士バッジが光っていた。
「だから、いないんだってば」
さっきの男が言った。正樹が目をこらすと、布団屋の隠居であった。
「もう何ヶ月もここには人がいないんだよ」
「だけどさ」
「私、このあいだ真夜中に、コンビニで息子さん見ちゃった。だから確かに住んでることは住んでるのよ」
まさかと布団屋は言い、それきり押し黙る。パトカーと野次馬にひかれて、男子高校生が四人近寄ってきた。面白そうじゃんとスマホで写し始めた。
「プライバシーにかかわることだから、撮影は禁止です」
若い警官がおしとどめた。
「坂本さん、坂本さん」
男はインターフォンを押しながら呼び続けるが、全く気配がない。代わりに作業服姿の男が工具箱を手に進み出る。
「おっ、ドラマで見たのと同じじゃん」
高校生が興奮した声を出す。男が鍵穴に何度も工具を差しては回しを繰り返すと、解錠されたのか、振り返って執行官と称した男に頷いた。
「坂本さん、入ります」
警官たちを先頭に、スーツ姿の二人が中に入った。
「死んでんじゃね?」
と高校生。
「中に腐乱死体ってよくあるじゃん」
大人たちは黙ってなりゆきを見守っていた。昨年まで、坂本昌子は生きていて、数年前までここで庭仕事をしていたことを思い出す。曲がった腰で草とりをしていた姿を、町内の者たちはよく見ていたものだ。しかし息子の姿は見かけなかった。
やがてドアが開いた。大家の代理人らしいスーツ姿の弁護士につき添われて出てきたのは、肥満したジャージ姿の男であった。何ヶ月も床屋に行っていないのか、髪が耳の下まで伸びていた。
おとなしくしているのが、かえって不気味だった。
「坂本さんとこの息子さんじゃないの!」
感にたえぬ、という風に女の声がした。
「まるっきり変わっちゃったけど。ずっと引きこもりだったのね」
女が声をあげる。布団屋に向かって話しかけた。
「8050っていうやつだね。年とった親の年金めあてに、引きこもりの子どもがべったりくっついているというやつ」
二人の警官はさっさとパトカーに乗ると立ち去った。事件性がないと判断したのだろう。ジャージ姿の男は弁護士、執行官とともに、到着したタクシーに乗り込む。別段嫌がっている風にも見えない。“きょとん”という表現がぴったりだ。それは長い冬眠を突然邪魔された熊のように見えた。自分の親が死んだら、なすすべもなく、ひたすら閉じこもっていた中年男。生きていく訓練がまるでされていない男は、これからどうするのか。
家に戻るまで、節子はひと言も発しなかった。予約の患者がいないので、正樹はそのまま二階の自宅にあがる。ダイニングテーブルの前に、節子は放心したように座った。正樹は確信した。あの光景にいちばん衝撃を受けたのは、自分たち夫婦だったのだ。
やがて節子が口を開いた。
「あれって、うちの三十年後の姿なのよね……」
「考え過ぎだろう、翔太がこのまま年をとるはずがない」
「いいえ、そうなるわよ。そうならないって、誰が保証してくれるのっ」
「ちょっと落ち着け、あのうちは特殊なんだ、息子をちゃんと社会人にしなかったからああなるんだ」
「うちも同じじゃないの。うちだって、うちだって……。ねえ、あのパンフレット、あなたに渡したわよね」
「下の診察室にある」
すぐさま階段をおりていく。そしてパンフレットを手に持って戻ってきた。
「あなたも来て。お願い」
医院は三階建てで居住部分は二つのフロアになる。かつて両親も同居していたため、余裕あるスペースになっていた。三階の由依の部屋は、今は納戸のようになっていて、その奥が翔太の部屋になる。息子が真夜中、自由に過ごせるのもこの広さのためだ。節子はそのドアをどんどんと叩いた。
「翔ちゃん、翔ちゃん、ちょっと開けて頂戴」
しばらくして、
「なんだよ」
内側からドアが開いた。そこに息子がいた。はっきりと姿を見たのは何ヶ月ぶりだろうか、ある時から極力見ないようにしてきた。全力で本気で向き合った時もあったのだ。それを言いわけにして、ずっと目をそらしてきたのは事実だ。
「いったい何なんだよー」
思いきり不機嫌な声を出す息子が、それほど肥満もせず、髪も長くないことに正樹は安堵した。ちらっと部屋の中が見える。洗濯ものが干され、机の上でパソコンが、ピコピコ音をたてながら光っていた。
「どうしても今、話をしたいのよ、大至急よ」
「るせえなぁ……」
翔太はしんからかったるそうな声を出した。声は外見よりもはるかに変わっていた。はきはきとした長いフレーズを最後に聞いたのは、変声期のまっただ中だったかもしれない。
「ママはね、翔ちゃんにどうしても話したいことがあるのよ」
「何だよ、ここで言ってくれよ」
「いいえ、じっくり話したいのよ、ちょっとリビングまで来て」
節子はいつのまにか、翔太の手をつかんでいた。その気迫に押されてか、のろのろと歩き出した。そうきつくはないが、体臭がぷんとにおった。一日おきに風呂に入っていると節子は言ったものだが、二十歳の青年が一日中部屋に閉じこもっていれば、体からさまざまな臭いが発されるのはあたり前だろう。
翔太は気だるそうにソファに腰をおろし、脚を組んだ。息子の素直さが意外だった。涙が出てきそうになる。節子も同じだったらしく、
「翔ちゃんの好きな、ミルクティ

はしゃいだ声をあげた。
「いらね。それより早く話して」
正樹は思いきって声をかける。
「お前、ちゃんと食べてるのか」
「まあね」
「床屋も行ってるらしいな」
それには答えない。節子は月々のものを渡していた。それで時々小さな買物をしたりするようだ。以前カウンセラーという人物と話をした時、それが出来れば希望は充分あると教えてくれた。
「翔ちゃん、これを見て」
節子はパンフレットを広げた。最初のページで、あの写真と言葉があるはずだった。
「人生はやり直せるということです」
なんだよ、これ。翔太は低い声で呟いた。
「このパンフレットを見て。それからこれからのことを真剣に考えてほしいの」
「ふざけんじゃねーよ」
右脚が動いたかと思うと、テーブルを蹴っていた。茶碗が大きく動き、液体がこぼれた。
「ババア、ふざけんじゃねえ」
息子の発した声を、正樹は夢の中のことのように聞いた。
ふざけんじゃねー! 翔太は何度も吠えながら両手をざざーっと左に動かす。茶碗に急須、ティッシュペーパーの箱が音をたてて床に落ちていく。
しまい忘れた醤油差しが最後に落ちて、黒い飛沫をあたりに飛ばす。
ふざけんな! 今度は足を使った。テーブルを倒そうとしたがうまくいかず、椅子を次々と蹴る。木製の椅子は、醤油差しよりもはるかに大きな音をたてた。
「クソババア、二度とそんなこと言うな!」
翔太は節子を睨みつけた。目が赤くなっている。
「そんなことをもう一度言ってみろ。お前をぶっ殺すからな」
それから正樹の方を振り返る。
「お前もだぞ」
廊下をわざと足音高く行く。そしてバタンとドアが閉まる。
気がつくと、節子が泣いている。片づけもせず、両手で顔を覆い、静かに泣いている。
「どうして……どうしてこんなことに……」
今までおとなしく引きこもっていた息子の、突然の暴力であった。何が起きたのかよくわからないのは正樹も同じだった。
「あいつは、突然の変化に耐えられないんだろう」
先ほどちらっと見た、部屋の中を思い出した。洗濯ものは干してあるものの、案外片づいていた。そしてずっと音をはなっていたパソコンの画面。きっとあれでゲームをしていたに違いない。
暖房の効いた部屋で、ぬくぬくと無為なときを過ごしている息子を、本当に情けないと思う。
「お前が甘やかしたんだ」
と言いかけ、
「俺たちが」
と変えた。これ以上の
「もう小遣いはやるな。飯をつくってやることもない」
「そういうわけにはいかないでしょう……」
「いや、それがあいつのためだ」
まだ子どもなのだと思う。このところ正樹たちは、息子に対して無視する作戦をとっていた。無視はするが、手はかけてやっていた。妻は真夜中に起きてくる息子のために、余分につくっておいたものを冷蔵庫やテーブルの上に置いていた。
食べ物と冷暖房、そしてパソコンという娯楽を与えたために、彼は長い時間、あの部屋に籠城したのだ。そう、それはまさしく籠城であった。そこで息子はたった一人の城主だ。何不自由なく、誰からも命じられることなく、気ままに暮らしていた。そこに突然の親からの命令だったので、息子は逆上したのだ。
正樹はこのように冷静に分析した。するとここから解決の道筋が見えるような気がしてくる。
「もう甘やかすな」
妻ではなく、自分に言い聞かせる。
「あの子にも親離れしてもらわなくてはならない。それから俺たちも子離れしなくちゃいけないんだ」

「もう私たちも覚悟を決める時なのよ」
母の言葉に由依が大きく頷いた。節子が連絡したのであろう。日曜日の午後、娘は久しぶりに現れたのである。手には和菓子の箱を持っていて、この娘も随分やわらかくなったと正樹は思う。
大学生の頃は、冷ややかな、取りつく島もない娘であった。ひたすら勉強することによって、自分の固い殻をつくり上げようとしているかに見えた。それでも母親とはあれこれ睦まじくしていて、一緒に買物にも出かけたりしていた。二人で仲よく喋べっているところに正樹が入っていくと、ぴたっと口を閉じる。
が、年頃の娘というのはこんなものだろうと思っていたし、友人たちからもそう聞いていた。
娘と一緒にゴルフに行く、などという話を聞くと、信じられなかった。
今、こうして目の前にいると、軽くウェイブした髪といい、ピンク色の口紅といい、美しく明るい娘になったと思う。好きな男がいると、こうも違うものだろうか。
口元が綺麗なのは、中学校の時に歯列矯正をしてやったからだ。三年間、歯をワイヤーで締めるのは、少女にとってつらいことだ。この頃都会の子どもは、たいてい矯正するが、それでもからかわれたりする。しかも矯正中、由依は眼鏡をかけていた。コンタクトにすればいいと思ったのだが、
「ブスになる時は思いきりブスになるんだって」
と節子から聞いても意味がよくわからなかった。まあ女子校だからこそ、そんなことが出来たのだろう。
持ってきた和菓子を食べながら、由依はぽつりぽつりと自分の話をした。つきあっている男から、そろそろ挨拶に行きたいと言われたそうだ。
「私はもうちょっと待って、って言ってるの」
由依は目を伏せた。この後の言葉を言っていいか悪いか、考えあぐねているようであった。
「だって翔太のこと、わかっちゃうじゃないの」
「何も言ってないの」
「うーん、ビミョウに伝えてるかなー」
小さなため息をついた。
「ずうっと医大めざして浪人中だって言ってる。それでかなりめげてるって。彼はね、よくある話だね、って言って気にしてないけど」
「引きこもりだって、ちゃんと言えばいいじゃないか」
「イヤよ」
プイと横を向く。矯正のおかげで、形のいいプロフィールだ、気にしていたエラの張りもかなり改善されている。
「弟が引きこもりだなんて、私、絶対に言いたくない」
「おかしなことを言うな。引きこもりなんて、今、日本全国に百万人だかいるんだぞ。医大浪人生なんかよりも、ずっとよくある話だろ」
「あのね、世間にはよくある話かもしれないけど、自分がそのよくある話に関係するのって絶対にイヤ」
「まあ、由依ちゃん、そんなきつい言い方しなくても」
「ママは今回は黙ってて。私は、ママからメールもらって、ああ、やっとこの時が来たって思った。この時が」
「この時」を二度繰り返した。
「今、ちゃんと決断しなきゃ、翔太はこのまま廃人になってしまう」
「ハイジンって何だ?」
「ハイジンはハイジンよ。人として終った人。私ね、仕事柄、相続のごちゃごちゃいっぱい見てるの。今ね、いちばん問題になってるのが、廃人のきょうだいよ。親の財産を整理しようにも、どうしようもないの。ねえ、お父さん、はっきりと聞くけど、老後をどう考えてるの。まだ五十代だけどそろそろ考え始めてるよね」
娘の職種は何だったろうかと、正樹は思い出そうとする。損保会社で企画部とか言っていなかったか。そこはこんな口のきき方をするのか。
「お前の世話にはならんから安心しろ」
むっとして言った。
「うちはもう跡継ぎはいないし、適当な時になったらここは閉める。そして家を売った金で、母さんと施設に入る。負担はかけない。安心しろ」
「ほらね、それですっきりすると思ってる。翔太のことなんかまるで考えていない」
「考えてるさ。その時はお前とあいつにいくらかの金を渡すつもりだ。それで何とかしてくれるだろう」
「何とかならないから、こんなに社会問題になってるんじゃないの」
由依はピンク色の唇を思いきりゆがめた。
「ほら、8050よ。知ってるでしょ。親が八十歳になっても、子どもは五十歳でパラサイトしている。引きこもりのまま中年になっているのよ。おっそろしい話よね。親の年金をあてにして生きてる。たいていが男よ。五十になっても、就職も結婚も出来ない、小汚ないさえない初老のオヤジになってくのよ」
こんなに口がまわる娘だったかと、正樹は
「たいていが男よ。どうしてかわかる? 親が甘やかして育てるからよ。今の世の中、女の方がずっと厳しく育てられてるわよね。女だからちゃんと勉強しなさい。一人で生きていける人になりなさいってね。ううん、私、責めてるわけじゃないわよ。私は、おかげでちゃんとした大学出て、いい会社入れたんだもの。私はね、ちゃんと上澄みの人生をおくりたいと思ってた。今だったらね、私はね、歯医者のお嬢さんで、早稲田出ている。あちらのおうちだって文句ないわよ。いいお嬢さんとおつき合いさせていただいて、って、あちらのお母さんも喜んでた。だけど翔太がいたら、私、どうなるの。たちまち下の方にいっちゃうのよ。わかる?」
正樹は信じられないもののように、娘の饒舌を聞いていた。この論理が正しいのか、正しくないのかまるでわからない。ただひどく不愉快なのは確かだ。
「お前は、弟がいると下に落ちていくと言うのか」
「そりゃ、そうよ。お父さん、引きこもりなんかありきたりだ、よくあることだって言うけど、そうやって自分を慰めてるのよ、甘いわ。だけど、いくら世間に多いことだからって、こういうことはアクシデントなの。災難なの。災難は災難としてちゃんと対処しなきゃいけない、っていうのが私の考えだわ」
「お前は……」
やっと息をついた。
「弟のことを災難だなんて言うのか。そんな冷たいことがよく言えたもんだな」
「冷たいも何も、こういうことは冷静に考えようよ、お父さん」
その“お父さん”という言葉は、“お客さん”と同じ響きを持っていた。
「今だから言うけどね。いいえ、ママには話してるけど、翔太のことで、私がどれだけイヤな思いをしたと思ってんの。大学生の時も、一度もうちに友だち連れてこられなかったわよ。一度なんか、あいつと道で出くわして、本当にびっくりした。引きこもりって、自分じゃ気づかないかもしれないけど、ふつうの人とまるで違ってるのよ。えっ、お父さんたち気づかない? 陽にあたってないから肌が白くて、ぶよぶよしている。太ってなくても体に締まりがなくてぶよぶよしているの。歩き方もヘン。たまにコンビニ行くぐらいでちゃんと歩いてないから、ヒョコヒョコしてる。何よりも目つきが不気味なのよ。本当、ちゃんとまわりを見ていないって感じ。一緒に歩いてた子が、なんかキモい、って私に言った。その子、親友だと思ってたから、私は正直に言ったわよ。私の弟で引きこもってるって。そうしたら、彼女、ヒッキーかぁーって……」
そこでひと息ついた。
「へえ、ヒッキーかって。あのね、その言葉聞いたら、私はちょっと安心したの、軽い愛称って気持ち明るくしてくれるのね。そうしたら、その子、何て言ったと思う? でも、将来ヤバいかも。幼女に何かしそうだねって……私、それを聞いて……」
泣くまいとして唇を噛んだ。
「もうダメだと思ったの。私の将来、翔太にやられちゃうかもって」
節子がたまらず声をあげる。
「何てこと言うのかしら。その友だちがおかしいのよ。偏見に満ちていて失礼なのよ。全く……」
「だけどママ、翔太の性生活まで知ってるわけじゃないでしょう」
「そ、そんな」
「翔太だって、健康な二十歳の男の子なら、マスターベーションだけで満足しないことだってあるかもしれない。私は本当に怖いの。あいつが何か犯罪やらかしたらどうしようかって……」
「性生活とか、マスターベーションとか、くだらないことを言うのはよせ」
正樹は怒鳴った。そうでもしなければこの場の空気に耐えられそうもなかった。
「お父さん……」
節子はママで、正樹はお父さんだ。昔はパパと呼んでいたような気もするが。
「だけど大切なことよ、お父さん。私たちは爆弾を抱えているようなものじゃないの」
「爆弾……」
節子がつぶやく。
「そうよ、このあいだ引きこもりの男の通り魔事件があって、同じことをやるんじゃないかって心配したどっかの元事務次官が、自分の引きこもりの息子を殺しちゃったじゃないの。私、あのニュースにぞっとした。翔太のことを思って」
正樹は黙る。本当にそのとおりだ。あの殺人事件を知って、冷静でいられた引きこもりを持つ家族は誰もいまい。
「私ね、今まで好きな男の人が出来ても、翔太のこと、この人どう思うかなって考えて、いつも引いちゃった。つまりそれだけの相手だったかなあ、って今では思います」
だけど、と身を正した。
「今度のことだけはちゃんとしたいんです。結婚したい相手がやっと現れたんです」
わかった、わかったと正樹は言った。
「翔太のことが障害になるなら、父さんがあちらの方とちゃんと話す。わかって欲しいってちゃんと話す。それでいいだろう。それでわからないような男と家族なら、お前と結婚する価値のない相手だ」
「ほら、すぐそういう風にいくんだから」
由依は叫んだ。
「もうキレイごとはやめて、ちゃんと話しましょうよ。私はそのために来たんだから」
そして床に置いたトートバッグから、どさりとパンフレットを取り出した。それは節子が口にした「KIGARU塾」のものであった。
「ママから聞いて、私もここのこと、いろいろ調べさせてもらった。最近、いいことばっか言って、お金ばっかりとるところがあるけど、ここはちゃんとしてるわ。ほら、この
さらに二冊本を取り出した。
『引きこもりこそ日本を変える』
『引きこもりの僕が塾をつくった』
その帯には、流行りのデザイン髭で顔半分をおおった男が微笑む写真があった。
「お父さん、ママ、ここだったら信用してもいいんじゃない」
付箋をつけたページを差し出した。そこにはこう書かれていた。
「引きこもって苦しんでいた時、僕はいつも物語のようなことを考えていました。ある日、僕を変えてくれる何かが起こることを夢みていました。が、それは物語でもなく、ごくふつうのきっかけでした。信頼出来る人が現れ、もう一度やり直せと言ってくれたんです」
でも、と読み終った節子が言う。
「もう何度も私たちはきっかけを与え続けてきたわ。カウンセラーにも相談して、うちに来てもらったこともある」
「だからここ読んで」
もう一箇所、付箋をつけたページがあった。
「“その時”がいつ来るか、誰にもわかりません。僕の場合は、親が必死になっていた十六、十七の時ではなく、二十三歳の時でした。“その時”は必ず来ます。それを見極め、行動するのが最後のチャンスなのです」
由依は本をバタンと閉じた。
「聞いたら、荒療治を始めてるんですって? そうよ、それがいいと思う。お父さんもママも翔太を甘やかし過ぎてたんだわ。こんないいとこ、出ていくはずがないわ。ねえ、最後のチャンスよ。私も協力するわ。翔太を、絶対にここに行かすのよ。それでこの石井氏に彼を変えてもらいましょうよ」
帯の男をもう一度見る。綺麗な歯並びだ。引きこもりの間はどうしていたんだろう。
帯のコピーにはこう書かれていた。
「自ら引きこもりを体験したからこその真実の教え!」
文字は赤く染めてある。
「まずはお電話ください。専門スタッフがじっくりとお話しさせていただきます」
KIGARU塾のパンフレットのはじめに、フリーダイヤルの数字が並んでいた。それは、正樹がかつてすがったいくつかの組織を思い出させた。
「息子さんはちょっとした迷路に入っているだけなんですよ」
あるNPOの男は言ったものだ。
「小さなきっかけでも、その迷路から出ることは出来るんです。それを手助けするのが私たちの役目です」
小太りのあの誠実そうな男は、いまどうしているのだろうか。何度かうちに来て説得をしてくれたのであるが、息子はついに心を開かなかった。
翔太は吐き捨てるように言ったものだ。
「人の大事な時間を奪いやがって」
若い女性もいた。この時は翔太は部屋から出てこようともしなかった。彼女はドアの前に立ち、根気強く翔太に話しかけた。
「あのね、私も翔太君と同じなの。中学一年の時に学校に行くのがイヤになってね、それから全部合わせても一ヶ月も行ってない。私は翔太君の気持ちよくわかると思うんだ。だから、ちょっとだけ出てこない? 少しだけ話をしてみない?」
後で翔太は怒りを込めてこう言った。
「あんな芝居じみた気持ち悪い声、ゲロしたくなった」
その後、どれだけ多くのことがあっただろう。希望が芽ばえかけて、ことごとく徒労に終ったのだ。
「これが最後のチャンスだと思うの」
由依は何度も同じ言葉を繰り返す。
「ママもお父さんも、あの子を甘やかしてきたのよ。私ね、いつも思ってた。どうしてドアを蹴破って入っていって、いい加減にしろ、働け。それがイヤなら出ていけーって言わないんだろうって」
同じことを正樹は、かつて実の妹の
「どうして進学しないならせめて働け、って言わないの。どうしてうちから追い出さないの」
そしてつけ加える。
「うちの娘が同じことしたら、私なら出てけーって蹴とばしてやるわ」
引きこもりと縁のない子どもを持つ親は、必ずこう言うのだ。私ならもっと強気に出る、子どもをそんなに甘やかしたりしないと。
しかしいったいどんな親が、いきなり子どもを外に追いやることが出来るだろうか。もう頼る人がいないからといって、一人発奮して日雇いにでも行くと思っているのか。親に捨てられたことに絶望して、自殺するかもしれないのだ。その前に犯罪に巻き込まれる可能性もある。
だいいちそんな強い人間に育てなかったことは、親がいちばん知っている。外で死なれることを怖れて、ずっとうちの中で好きにさせてきたのだ。そして息子は二十歳になった。
肉親である娘も、叔母と同じことを口にする。
「どうしてもっと強く出ないのよ」
今その言葉には切実感がある。なぜなら自分の幸福がかかっているのだ。
引きこもりの家族など、今どき珍しくない。結婚するつもりの相手に、そんなことまで隠すのか、という正樹の言葉に、由依はこのように反論した。昔から弁のたつ娘なのだ。
「もちろん私は、いつかは話すつもりなのよ。だけどね、努力している、改善しようとしている、って姿勢は見せたいと思ってる。だってそうでしょう。あちらのご両親に、今までどうしてたの、随分長い間ほっておいたのね、という印象を持たれるのは嫌なのよ。どこのうちだってマイナスはあるわ。だけどね、そのマイナスをほったらかしにしているうちって、やっぱり軽蔑されると思うの」
だからこそこのKIGARU塾なのだ。ここは驚くべき就学復帰率を誇る。カウンセラーがマンツーマンでついて、きめ細かい指導をするというのだ。引きこもりの若者に意欲を持たせ、その意欲をうまく向学心へとつなげるのだという。
大学だけではない。アート系の専門学校に進学する者も多いとパンフレットにはある。引きこもっている間に興味を持った、ゲームやアニメの世界に進むらしい。
が、費用の高さに正樹は驚く。五十万、七十万、百万コースとわかれているのは、どのくらい長く、いくつ講座を受けるかで決まるのだ。
翔太が引きこもり始めた七年前、いや五年前にだってこんなものはなかった。もっと素朴といおうか、手づくり感があった。今、引きこもり支援は、確かにビジネス化してシステマティックになっている。引きこもりは商売になるのだ。しかしそれは悪いことではない。立ち直りの方法が明確に多様化してきたからではないかと、いつもどおり前向きに考えようとしている自分に気づく。
「とにかく見学に行ってみるか」
「お父さんだけじゃダメよ。翔太を連れていかなきゃ」
「それが出来れば苦労しないよ」
「いつもそうじゃないの。お父さんかママが行って、ここがいい、ここに通わせようと思っても、本人が頑として行かなきゃ何にもならないじゃないの」
ここ見てと、パンフレットを指さす。
「ほらね、まず第一段階として、説得、お迎え、っていうのがあるの。これって自信がないとやらないと思う。プロの仕事として、確実にやる、って気持ちがあるからよ」
このコースは三万円とある。つまり本人を塾に連れていくのに、これだけかかるということだ。
「しかし、ある日、突然、というわけにはいかないだろう」
「だから、こっち側もいろいろ考えなきゃ。私はこの際だから、将来のことをちゃんと話すのもアリだと思う」
「そんなことしたら、あの子はキーッとなると思う」
節子が顔をしかめた。
「とにかく変わったことをされるのが大嫌いなのよ。このあいだ珍しくあの子が出かけたから、私は窓を開けて軽く掃除をしたのよ。そうしたら怒ること、怒ること、勝手にこんなことするなーって大騒ぎよ」
「だからママ、息子が怒ったからって、いちいちおびえてちゃダメなのよ」
そういう口調は妹にそっくりだった。
――お兄さん、ダメよ、どうして息子にビシっとしないの? どうして息子にそんなに気を使うのよ。
気を使わなければ、息子の機嫌をとっていなければ、とても同じ家の中で暮らせないのだ。そして引きこもりの場合、機嫌をとるというのは、出来るだけ無視をして、いないものとして扱うことなのである。まともに向き合っていたら、とても自分の精神がもたない。いつか息子が何かに気づき、目ざめた時に、自分の持っているエネルギーをぶっつければいい。そうありもしないことを考えて、ずっと問題を先のばしにしているうちに、時間はたっていった。
しかしもうそれは限界にきていると由依は断言した。
「いい、お父さん。翔太ももう二十歳よ。子どもの時と違って、そろそろ焦り出しているはずよ。だってこのままだと“廃人”になるもの」
また「廃人」という言葉を聞いた。それは妻と見た、家から強制退去させられる坂本家の息子の姿と重なる。
だらしなく太った体、伸びた髪、ぼんやりとした表情……。
二十年後か三十年後、古びた大澤歯科医院から引き出される翔太の姿が見えるようであった。

正樹はこの七年間、見て見ぬふりをしてきた。出来るだけ視界の中に入れまいとしたうえに、何か目撃したとしても、それについて深く考えまいとしてきたのだ。
たとえばダイニングテーブルに向かうと、その上に残飯を見ることがある。いつもなら先に起きた節子がすばやく片づけるのであるが、何かの拍子にそれを目にすることもある。
そして風呂。正樹には朝風呂の習慣がなかったからかち合うことはない。それでも洗面所に残る湯気のにおいや、散らかったタオルを見るたびに、不快さがこみ上げてくる。この薄気味悪さは、味わった者でないとわからないだろう。
「お前はいつからネズミになったんだ!」
と怒鳴ったことがあるが、そんな生やさしいものではない。
以前、見知らぬ他人が勝手に住みついていた家がニュースになったことがある。ひとり暮らしの中年の男が、留守の間に冷蔵庫の中の食品が減ったり、部屋のものが動いていることを不審に思い、隠しカメラを仕掛けておいた。そこに写っていたのは、天袋に潜む女の姿である。女は家主が出かけたとたん、下に降りて自由に動きまわるのだ。
正樹は心底ぞおーっとした。息子の引きこもりが始まって四年めくらいの頃である。自分の寝ている間に、誰かが勝手に動きまわっているのは、大層気味が悪い。たとえそれが自分の息子でもだ。もし意志の疎通があったら、決してそんな感情は持たなかっただろう。
正樹にとって、部屋から出ない息子は、天袋に隠れている他人と同じなのである。
夜中に目がさめると、物音が聞こえることがあった。テレビの音、冷蔵庫を閉める音。食べものを温めているらしく、においを感じることもある。
「あれでも気を使って、出来るだけ音をたてないようにしているのよ」
節子は
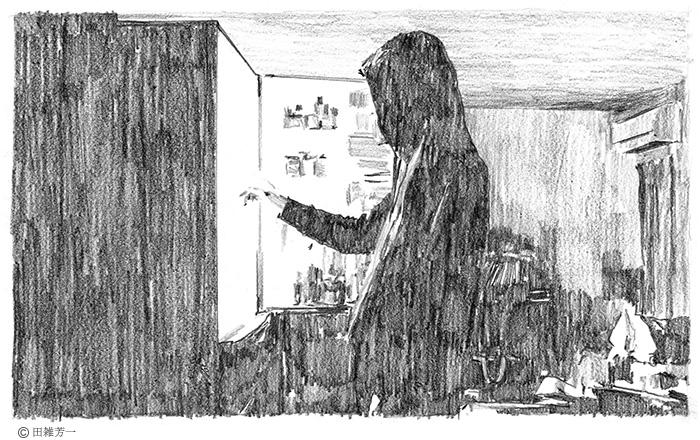
その日夫婦はしめし合わせて、居間のソファに座っていた。テレビも消し、あかりもスタンドだけにした。
「もうそろそろ来るんじゃないの」
節子がつぶやく。十二時過ぎに夫婦が眠りにつくと、約一時間後に翔太は部屋から出てくるというのだ。
その言葉どおり、廊下をひたひたと歩いてくる音がする。そして蛍光灯のスイッチが押される……。
「あっ!」
翔太は驚きの声をあげた。それはそうだろう。誰もいないと思っていた居間のソファに両親が座っていたのだ。
「チッ、脅かすなよー。いったい何なんだよー」
きびすを返そうとした、そのグレイのニットの後ろ姿は、完全に大人の男であった。
「まあ、座りなさい。ちょっと話がある」
「このあいだもそう言って、話をしたばっかじゃん」
「あの時よりも、もっと重要な話なんだ。そこに座りなさい」
「翔ちゃん、座って……」
節子がすがるように言った。
「その間に、お夕飯をチンしてあげるわ。ええと、今日は鍋だったから火にかけるわね」
「もう、いらないよー」
「いらないって、あなた、夕ご飯食べに来たんでしょう」
翔太は黙って、両親のいるソファの方ではなく、ダイニングテーブルの前に腰をおろす。節子がいそいそと夕飯を並べる。今夜は鶏のつくね鍋であったが、テーブルにコンロを持ち込むことはなく、キッチンの火で温めた。
その他に菜の花にカツオ節をかけたもの、里芋の煮物を翔太は
それを眺めながら、正樹はかすかに安堵した。息子の食事のマナーがさほど悪くなかったからだ。これについては、節子が口うるさく言っていたからだ。
――これならば、まだ何とかなるかもしれない――
そうだ、坂本家の息子のようになる前に、ことは急がなくてはならない。
食事が終っても、翔太はダイニングテーブルの前にいる。両親のいるソファには座ろうとしない。
「まあ、いい。ここで話そう」
翔太は頷きもしない。
「お父さんたちもこの間聞いたんだけど、由依が今度結婚するそうだ」
唇の端がかすかに上がった。祝福ではなく、フンという皮肉に見えた。
「これで二人の子どものうち一人が、完全に独立するわけだ。これを機に、父さんたちも将来のことを考えなきゃならない」
何日も前から考えていた言葉を、注意深く続けていく。
「お前は知らないだろうが、町中のこんな小さな歯医者は、年々さびれるばっかりだ。うちにやってくる患者さんは、日に十人がいいところだ。もうこれではとてもやっていけない。おじいちゃんの代からの医院だし、あと十年は頑張るつもりだったけど、そろそろつらくなってきた」
これは半分は脅しだ、息子の出方次第では、あと十年はやるつもりである。近所の年寄りを相手にしていれば、何とか食べていけるだろう。
「由依は結婚に向けて、まとまった金を欲しがっている。すぐにマンションを買いたいそうだ。その気持ちもわかるから、この際はっきりと、うちの財産の額を教えて由依に生前贈与してやるつもりだ」
「このうち、売るのかよ……」
ようやく反応を示した。おお、いいぞと思った。脅しが少しずつ効き始めているのだ。
「いや、この家を売って施設に入るには、俺たちはまだ若過ぎる。だけど医院は近いうちに閉じるかもしれない。だからここできっちりと、お金のこともちゃんとしよう、っていうことだ」
そして正樹は、定期預金の通帳と、証券会社からの報告書を取り出した。
「これがこの家を除いた、うちの全財産だ。小さいマンションもあるが、あれはたいしたことはない。おじいちゃんとおばあちゃんの介護のことがあったから、かなり減らしてしまった。だけど結構あるぞ。そう悪くはない。ほら、見てみないか」
翔太は微動だにしない。
「ここから一千万を由依に渡すつもりだ。お前にもやる。だからこの金を使って、もう一回人生をやり直してみないか。そのためにはこういうのもある」
KIGARU塾のパンフレットをかざした。
「お前がOK出してくれれば、ここの塾の人が、三日後にやってくる。そしてお前をこの塾に連れていってくれるはずだ。うちからも通えるが、お父さんは寮に入った方がいいと思う。下は十二歳、上は三十五歳までが埼玉県で暮らしているそうだ。何の制約もない。個室で毎日自分の好きなことをして暮らしていってもいいんだ。お前がうちの中でしてるのと同じことを、ちょっと違う場所でするだけなんだよ。そう悪い話じゃないだろう」
「マジかよ……」
うなるような声をあげた。
「あのインラン女が結婚するからって、どうしてオレがヤなめにあわなきゃいけないんだよ」
「インラン女って……」
節子の声が震えている。
「アンタら、何も知らないだろうけど、大学生の頃、アンタらの留守に男をひっぱり込んでたことがあるぜ。昼間っからヒイヒイ声あげて、みっともないったらないぜ」
「まさか……」
「勤めるようになって、このうち出ていったら、すぐにその男と暮らしてんだぜ。バッカだよなー。しかもあの女、あの頃フェイスブックやってて、いろいろバラしてやんの。しかもゆるくて、オレもすぐに入れたフェイスブックに、二人で出かけたところを載せてさ、今の彼氏に見られたらどうするつもりなんだろ。笑っちゃうよなー。あの女のせいで、どうしてオレが追い出されなきゃいけないんだよ。えー!!」